
0
熱を、教えて。
「あー…えーっと、修司さん」
「なんだい?」
「俺は、修司さんのこと受け止めるから、え、っとその」
「ゆっくり決めて構わないんだよ?」
「いや、大丈夫。だって、修司さんは俺のこと傷つけないでしょ?」
修司は目を瞬かせて、吉乃の言葉に大きく頷いた。当然だ。愛しい子を傷つけてまでセックスなんぞしたいと思わない。しかし、男同士にはどうしてもリスクが伴う。「俺、修司さんの熱を知りたい」と言い募る吉乃に、修司は溜め息を吐いた。
「分かった。もう少し勉強してくるから、今度の土日でもいいかい?」
「…え、えぇ、あ、うん?」
「君自身が言ったように、俺は吉乃くんのことを傷つけてまでシたいわけじゃないからね。今日は違うことしよう」
そういってベッドに押し倒してくる修司を、今度は吉乃が目を瞬かせる番だった。そっと服の裾から節くれた指が入って来る。ひんやりとしていて、身体が跳ねた。
▼
吉乃が通っていた大学の教授である修司と付き合いを始めたのは、吉乃が大学を卒業してからだった。‘偶然’を装って、修司が通うバーに行って、声を掛けたのがきっかけで。二十ほどの年の差があることを負い目にか、なかなか手を出して来ない修司に怒ったのが、前戯の始まり。
前戯ばかりで、いつになったら本番になるのかと言ったのが冒頭――先週のこと。
「…ん、」
ぬるりと自身の陰茎が修司の口の中に収められたのを見て、吉乃は慌てて両の手で口を押えた。じゃないと、咄嗟に静止の言葉が出てしまう。この人は『やめて』と言うと本当に手を止めるのだ。いや、違うそうじゃなくて、本心からじゃなくて、咄嗟に出た『やめて』という言葉にも手を止める。かつて、何度もそれでイタイ目を見た。イきたいのに、なかなかイかせてもらえないもどかしさいに、吉乃は口を塞ぐことで回避するようになっていた。
「…ふぁ」
手を止めたあとは、ナニをどうしてほしいか説明を要求してくる。どんな羞恥プレイだ。自身を傷つけまいという故の行動だと分かっているけれど、それはそれで恥ずかしくて。
「ひもちいい?」
「そ、そこで喋んなぁ」
「そうかい?気持ち良さそうだねぇ」
口から出された自身の陰茎をれろりと舐め上げ、先っぽをクルクルと親指で弄られる。同じ男なのだ、気持ちいいところなんて大体同じだと思う。つまり、そういうこと。この人の自慰もそういった方法でしているのかも、と思ったら堪らなくなった。
「ンっ」
「いつでもイッていいからね、吉乃くん」
下腹部を占領する修司の目尻は下がり、その目には探究心やら欲やら色々なものが孕んでいた。探求心の色が見えるのは、いかにも修司らしくて。己を欲の高みまで連れて行くだけに、囁かれるように吐精を促す修司の節くれだった指が幹を擦る。舌先が先端の過敏な部分を嬲り、全体を指で擦り上げられ――「んんっぁ…くぅ、」、目の前がスパークして、腰が勝手に何度も震える。
「気持ちよかったかい?」
「修司さ、」
吐き出した精をとろりとまるで見せつけるかのように、ティッシュに吐き出す修司の姿に吉乃は目眩がした気がした。
「声を出してくれないから、あまり気持ち良くないのかと思ったけど安心したよ」
「…だ、だって萎えるでしょこんな、男の声だし」
「萎える?どうして?恋人の可愛い姿を見て萎える男がどこに居るんだい?」
修司は吉乃の手を取って、自身の下腹部へあてる。下着越しに昂ったソコがびくりと跳ねたことに、吉乃も一緒になって跳ね上がった。待って。でかくね?
「そんな驚いた顔をしないで。大丈夫、ゆっくり拡げていけば入るらしいから」
「…らしいって、え?ほんとにこれ、俺ン中入る?ほんとに?」
「慣らせば入るって言ってたし、痛かったらちゃんと止めるからね」
「誰が言ってたんだよ…」
「その筋の人、かな」
「どの筋だ…」
吉乃は恐る恐るその下着越しに感じる熱に触れる。堅くなって、先端部分は下着の色が変わっていた。グレーだからよくわかる。そのことに、修司も気付いたのか照れくさそうに笑った。
「俺は君の声をもっと聞きたい」
「ひぅ」
「いつからか、君は声を出さなくなったけど。俺は吉乃くんの声を聞きたいってこと覚えておいてね」
うつ伏せになって、尻を高く上げている体勢はどうにも恥ずかしくて。吉乃は、修司の匂いが染み付いた枕を抱き締めながら、腰を震わせた。思わず出そうになる声を噛み殺して、ぐちゅぐちゅという耳障りな水音を聞き流す。修司が優しく臀部を撫でてくるのが更に羞恥を煽った。
「ン、」
「大丈夫かい?」
「う、ん」
大丈夫だから、何も言わないでほしい。ここに至るまでに、どれほどリスクや云々を語られたと思っている。例え、修司のソレが予想よりも大きくても、吉乃は負ける気はなかった。吉乃とて、無知で挑んでいるわけではないのだ。
「ふぅ、ぁ」
前立腺をほっそりとした指が掠めていく。思わず声が溢れた。奥に進もうとしていたであろう指が戻ってくる。トン、とその膨らみを指がタップする。「ひぅ、」枕を抱き締める手に力がこもった。
「気持ちいい?」
だから、聞かないで欲しい。とろりと吉乃自身の陰茎からカウパーが溢れているのを見て、察してほしい。嬌声になる前の、母音だけが吉乃の小さな口から出る。
「あぅ、あ、あッ」
「初めての子はあまり気持ちよくなれないって書いていたけど、吉乃くんは賢いねえ。ちゃんと気持ちいいんだねえ」
耳元で囁かれる修司の声に熱が孕んでいるのを、吉乃は確かに感じた。吉乃の背中と修司の上半身が擦れ合う。修司の体温も、高揚していた。しっかりと、己の身体で欲を感じてくれている。その歓びといったらーー!
「ひんっ」
「良い子、良い子だよ、吉乃くん。今ね、指何本か分かる?」
「わか、っ、わかんないぃ」
「三本入ってるんだよ。しっかり、咥えてくれてる」
「あ、ン、い、言わなくて良いって、ばぁ!」
「でも、喋ってる方が気が紛れるでしょ?」
どこの誰情報だ、それは。喋るたびに、腹に力が篭って修司の指を締め付けてしまう。そこに苦しさがないものだから、困ったもので。吉乃は枕に喘ぎ声を吸収してもらうべく、更に力を込めて枕を抱きしめた。
そうしているうちに前立腺を甚振っていた指が、ようやく拡張作業へと戻っていく。が、代わりに身体を横に向けられた。「ひぃぁぁあっ」予備動作なしで何てことをしてくれるのだ。一緒になって修司とベッドに横たわり、衝撃で後孔を締め上げる。
「お、締まった。気持ち良かったかい?本当は後ろから挿れるのが楽らしいんだけどね、」
「ま、まだ入らないぃ」
「うん、そうだね。もう少しかな。代わりに、こっちも触らせて」
修司の空いた左手が吉乃の胸に触れた。小さく主張する吉乃の乳首をくるりと指先で転がす。時折、つまんで、弾いて。そして引っ張って。それを繰り返されながら「ヒッ」ぐぷりと指がナカで回され、前立腺をかすめた。その両方の衝撃といったら。吉乃は腰を何度もくねらせた。ガクガクと前後する腰が言うことを聞かない。
「吉乃くん?」
「イッ、イッたから、指止めてぇぇぇええ!」
「え?」
ふわりと修司の匂いが動く。身体を起こして、吉乃の正面を見たらしかった。吉乃の陰茎から溢れ流れていく白濁したソレに、腹に収まっていた指の動きも止まる。
「本当に、今ので達したのかい?」
「…んっぅ」
未だ震える腰は言うことを聞きそうになく、びくんびくんと震えている。吉乃は修司の言葉に何度もうなづく。
「も、入る、入るから」
「ーー痛かったら、ちゃんと言うんだよ?」
「ん」
手早く着けられたスキン越しに感じる修司の熱に、吉乃は身体を大きく跳ねさせた。いざとなると恐怖心がある。あるけれど、今からするのは、ちゃんと愛されている、愛を感じる行為だ。修司は絶対に吉乃を傷付けない。そっと枕から手を離して、身体を正面に向ける。
吉乃が動いたことで、修司は目を見開いて「正面は、負担が大きいそうだから」と吉乃の腰に手を入れて、後ろ向きに変えようとしてくる。気遣いもありがたいが、そこまで気を使われなくたって吉乃とて柔ではないのだ。
「いいっ、前からシよ。修司さんを、正面から感じたい」
「…ッ、吉乃くん、君って子は本当に…」
腰の下に入った手が抜かれて、正面から掴んでくる。文系と言いつつ、大きな手のひらが労るように吉乃の腹を一度撫でた。これから、修司と繋がるのだ。吉乃は、修司の首に手を伸ばす。
「おねがい、絶対に、離さないで」
「もちろん。やっと君を手に入れたんだから、何があっても手放すことはしないよ」
宛てがわれる熱に、吉乃は息を詰めた。
「ひぅん゛ん゛」
「…っはぁ、」
「しゅ、しゅうじさ、んぁ」
ゆっくりと入り込んでくる灼熱のようなそれ。吉乃は修司の背中に爪を立てて、潜り込んでくる修司の熱に耐えた。じっくりねっとりと時間をかけて解されたソコに痛みは無い。ただただ、熱かった。
ふーっ、ふーっ。
荒く早い吉乃の呼吸音が反響する。
「吉乃くん、大丈夫だからゆっくり息して。そんなに早い呼吸だとツラいだろう」
「ん、だいじょうぶだから、ひといきに」
ひくりと吉乃の薄い腹が動く。あぁ、今ここまで入ってんのか。吉乃は自分の腹に触れた。もう少しで全てを収めることが叶うのだ。その仕草に修司は何を思ったのだろう、ゆっくりと腰を引いた。くぽんと音ともに修司の陰茎が抜けていく。
「ひっぅ、な、なんでぇ?」
「苦しいのかと…」
「く、るしいとかじゃなくて」
「うん」
「…もう少しで、全部入ると思ったから」
修司は目を瞬かせ、天を仰いぐ。吉乃には悪いが仕切り直しになる。しかし、だ。俺の可愛い子がこんなにも可愛いなんて。誰が想像しただろう。いや、誰かが想像しただけで腸が煮えくり返るだろうが。
「それは、ごめんね…?」
修司は再び後孔に自信を宛てがい、またゆっくりと腰を押し進めた。「あ゛ぁ゛っ」張り詰めた亀頭が肉壁を割って押し入ってくる。吉乃は、身を屈めて首筋に顔を埋めてくる修司の首にしがみついた。痛みは、ない。
「レイく、」
「あきざねさ、あぁんッ」
ぱちゅんと奥まで入り込み、修司のふわりとした陰毛の感触を尻たぶに感じた。入った。やっと。
「ん、吉乃くん大丈夫かい?」
「ふぁ」
返事ができない。圧迫感と直に感じる熱に得とも言えない感情が吉乃の心境を占めていたから。
「良い子だね、全部入ったよ」
「んっ、ん、」
修司の言葉に何度もうなづいて。それから、緩やかに腰を動かし始めた修司に、吉乃は腰を浮かせてくねらせる。控えめな艶やかな声が修司の耳に届く。
控えめなのが吉乃らしいが、もう少し声を出して欲しいとも思う。言ったところで吉乃は出さないだろうが。そこも、いじらしくて愛らしいのだ。
「ふ…ぁあ、、」
「もう少し、早くしても?」
「んっ、だか、ら聞かなくてもッ」
吉乃の言葉に、修司の腰を動かすスピードが上がる。耳を塞ぎたくなるほどの粘着質を伴った水音が部屋に響き渡る。
よしの。修司の囁きじみた喘ぎ混じりの呼び名に、吉乃は中が大きく収縮したのが分かった。普段は教鞭を摂る真面目な男が、今自分でしっかりと感じている。その事実が、吉乃を悦ばせた。
「……んくっ」
「イキそうだね、中が収縮して、っぐ」
グィっと腰を大きくグラインドさせて、吉乃の前立腺を狙い始めた修司に吉乃は必死にその男の背にしがみついた。爪が立つ痛みがあれど修司は気にせず、腰を振り、吉乃の腹につきそうなほど反り勃った陰茎を握る。「くぁっ」いきなりの動作に、吉乃は甲高い悲鳴をあげた。
「こっちも、可愛がってあげた方がイキ易いだろう」
「…いっ、いらないぃぃ」
「……ほら、もういいからイキなさい」
上下に擦られる吉乃の陰茎が、こぷりとカウパーに混じり白濁を吐き始めた。中が定期的に締まり始め震えるのを、修司は奥歯をかみ締めて耐える。先に達するのは年上のプライドで避けたかった。
「…っぁぁああ゛あ゛」
びくん。大きく吉乃の身体が跳ねる。中が締まり、陰茎から精液が吐き出された。その締りを追いかけるように、修司が腰を振る。「んぃぃっ」吉乃の悲鳴じみた喘ぎ声が聞こえようとも。
「すまない、腰が止まらない」
「ふぁ、ひぃ……あぁぁん」
喘ぐだけの吉乃と、吉乃の片足を担ぎ上げて腰を振る修司。まるで獣のまぐわいみたいだな、と吉乃の意志の片隅が思うのを最後に、腹の奥が一瞬熱くなったのと同時に意識がトんだ。
「……ぐっ、……ふー、吉乃くん?吉乃くん!?」
目尻を赤くして気を失っている吉乃の頬をぺちぺち叩く修司は、手を額に当てて大きく溜め息を吐いた。年甲斐もなくやり過ぎてしまった。俺は、盛った猿か。
吉乃の中から自身を引き抜いて、修司はスキンの口を縛った。サイドチェストからティッシュを出して、吉乃の身体を簡単に拭いてやる。スキンとまとめてゴミ箱に放り込み、比較的汚れが少ない端に吉乃を避けた。ローションをこれでもかと使ったから、ベッドの一部がパリパリと乾いていて洗濯が思いやられる。
「起きてから風呂でいいか、」
ひとりごちて、修司は下着を履き吉乃を抱き込むように横たわった。起きたらシーツも洗わなければな。吉乃のうなじに鼻を擦りあてながら、起きたあとのタスクを思い浮かべ、修司もゆっくりと眠りに落ちた。
君がバーに来るように仕向けて、ちゃんと罠にかかってくれた。目を掛けて来た子を手に入れた瞬間は、修司にとって忘れられない思い出だ。




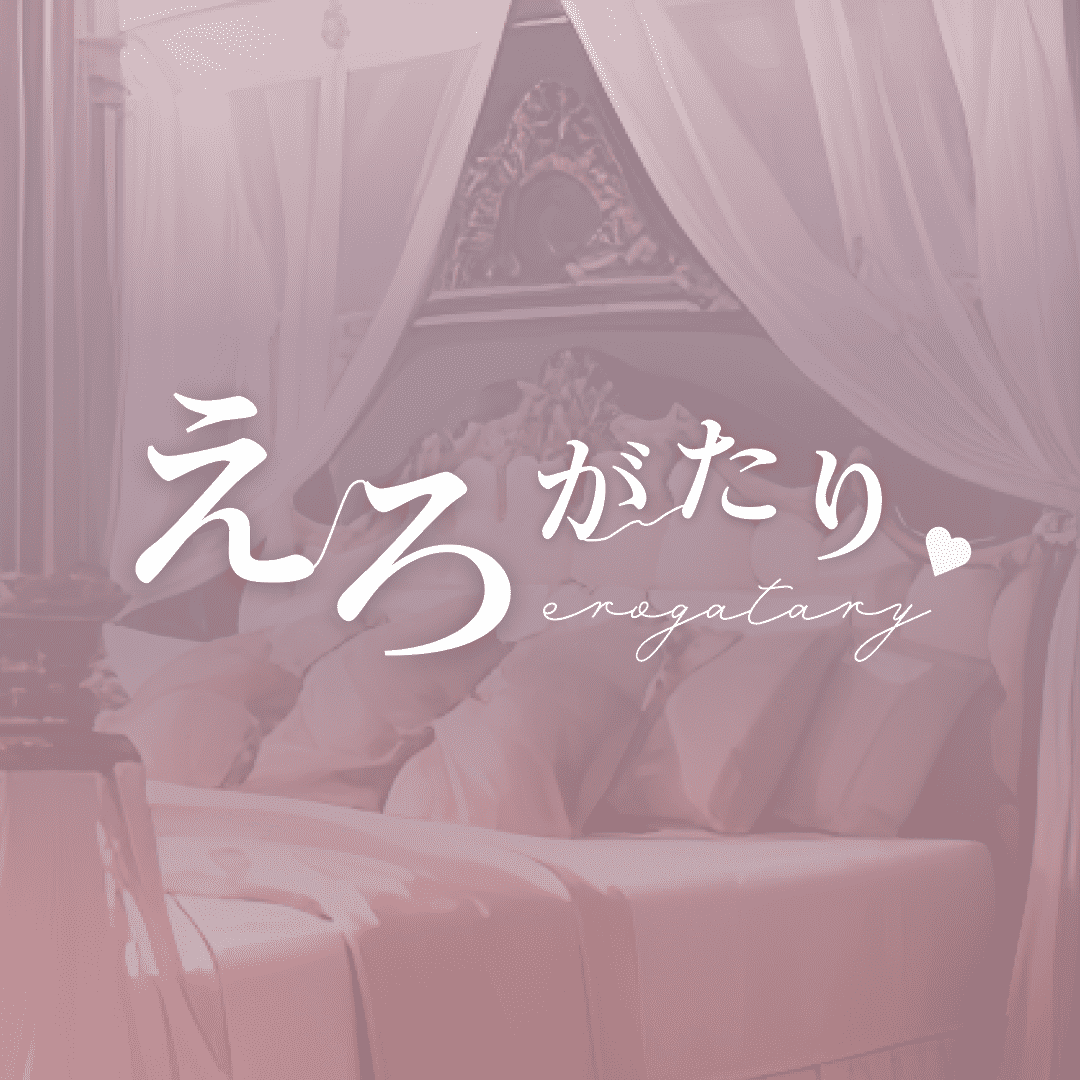




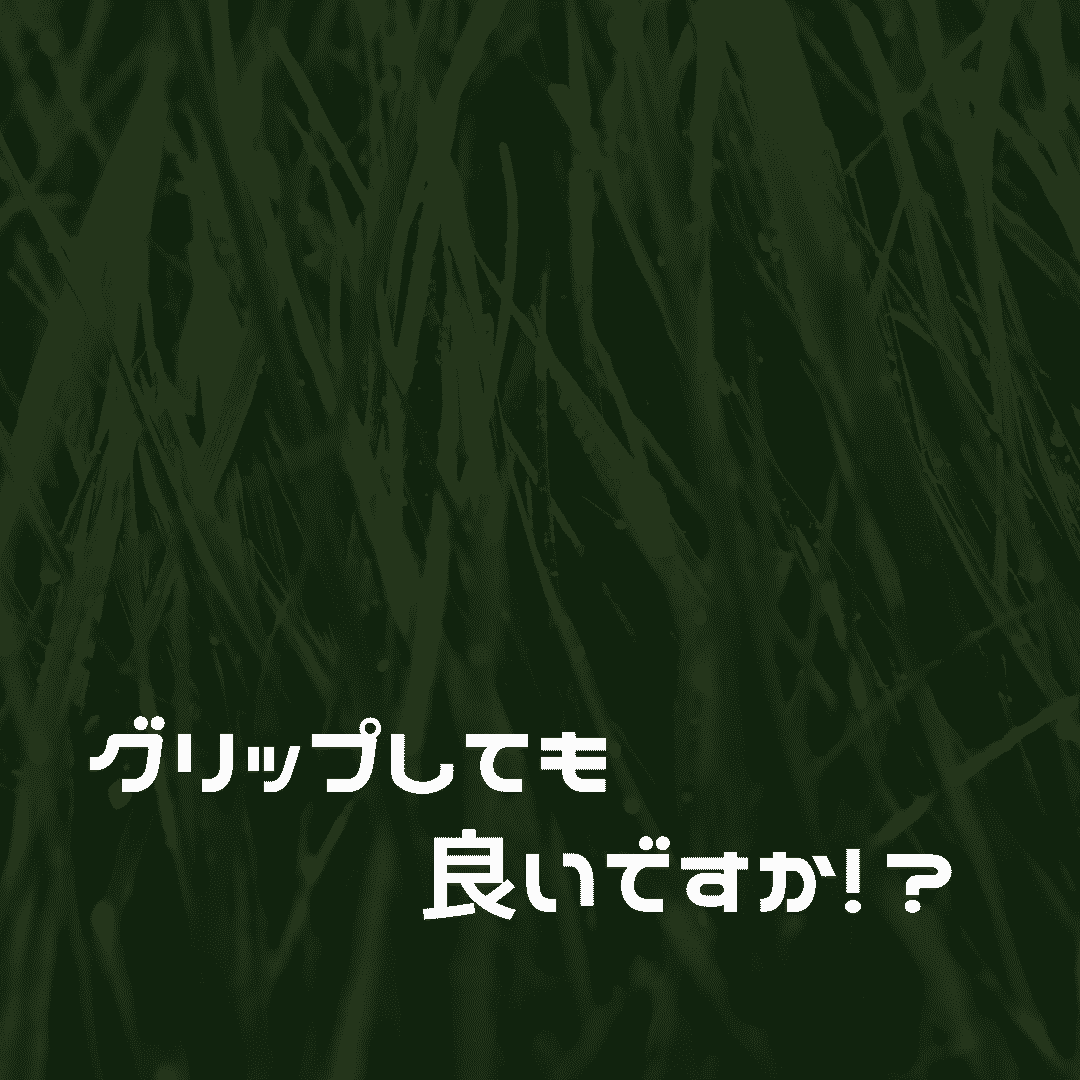

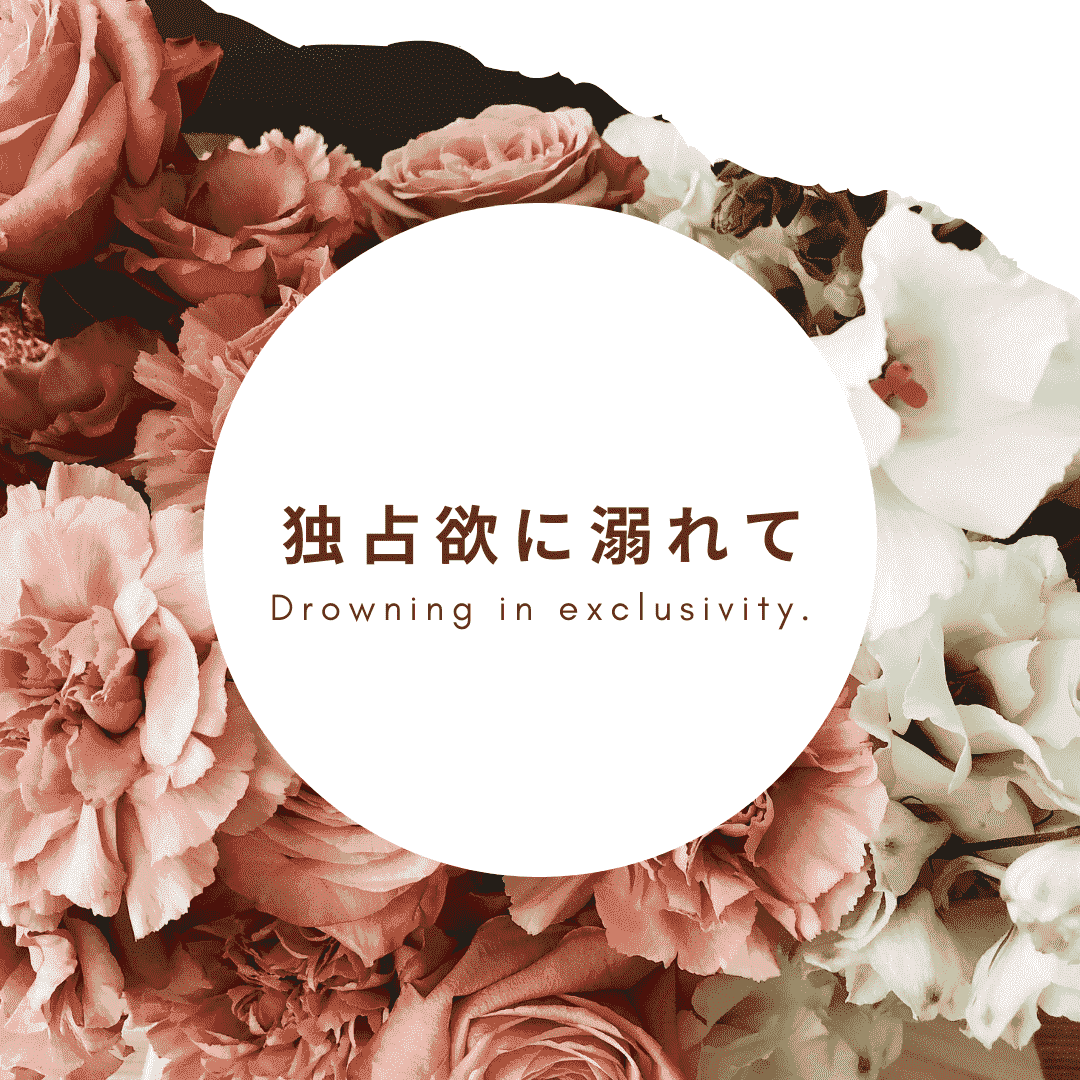
コメント