
0
2
BL
セックスしないと出られない部屋【☀×🌟の場合】
目の前に鍵のかかった扉と、無駄にでかい長方形のプラスチック看板がある。鍵のかかった扉は押しても引いても開きそうにない。扉の上部に掲げられた看板には、次のように文字が刻まれていた。
セックスしないと出られない部屋。
死んだ目でもう何度も看板を読み直している俺の横では、猫毛の赤メッシュがトレードマークの友人が眠っている。混沌とはこの場のことを言うのかもしれない。
「どこだここ……」
セックスしないと出られない部屋である。嫌というほど現実を主張してくる看板に瞳を虚ろにせざるを経ない。取り敢えず、横で眠っている脚長男を起こさなければならない。話はそれからだ。
結論、俺こと蒼雅花梨と、その友人の幻中真冬は、謎に包まれた個室の中に閉じ込められていた。
「駄目だな。俺のも圏外になってる」
スマホで電波の有無を確認していた真冬が、眉をひそめてため息をついた。この情報化社会でまさかの圏外とは、ここは山奥かどこかなのだろうか?考えれば考えるほど、ストレス性の胃痛が止まらない。
「せめて怜斗さんか翔太あたりに連絡が付けばな……」
「やっぱ、俺達自身で出る方法探すしかないか……?」
流石の真冬ーーーこう見えても彼はかなりの頭脳派だーーーも、なんの手がかりもない密室だと手詰まりだ。部屋の中には意識を失っていた俺たちが寝かされていたベッドと、見るからに怪しい引き出し付きのクローゼットがある。あとは施錠のされた扉があるのみで、それ以外は何もない。床も壁も真っ白で、下手な病室よりも殺風景だ。
もう一度、扉の上に設置された看板の文字に視線を滑らせる。セックスしないと出られない部屋。なんだそれは。国の少子高齢化対策にしては乱暴だ。いや、というか例えそうだったとしても、俺たちは男だ。なおさら訳がわからない。
「……。花梨、大丈夫か?顔色めっちゃ悪いぞ」
「え!?あ、ああ、大丈夫。俺も何か探すべきだよな、ごめん」
「いいよ、しんどいなら座ってろって。こんな状況に置かれたら無理ねえよ」
慌てて立ち上がろうとしたところを、真冬によって再び座らされる。そして俺のすぐ隣に腰掛けて、疲れを発散させるように身体を上に伸ばした。
「にしても、マジでわけわかんねーなこの部屋。どこの同人誌の世界だよ」
俺にとってはそもそもそんな概念が存在すること自体信じられないのだが、同人誌界隈ではお決まりらしい。しまった、こんな時のために同人誌を読んでちゃんと勉強しとくんだった……って、こんなの予想できるかっつーの!
本能的な現実逃避から、無意味な自問自答を頭の中で何度も繰り返す。するとまた葛藤が顔に出ていたのか、真冬がこちらをじっと見てきていたので、慌てて冷静を装った。
「な、なんにしても、もうちょっと何かないか探してみるしかないな」
「ま、そうだなー……。いかにも怪しいのはあのクローゼットだけど」
真冬がチラ、と目線をよこしたのは、入室直後から明らかに異質な雰囲気を放っているクローゼットだ。見た目はただのクローゼットだが、何が出てくるかわかったもんじゃない。開けるには地味に勇気が必要だ。
ここは自分が先陣を切るべきだと内心覚悟を固めて立ち上がろうとすると、真冬の方が先に立ち上がった。そのまま黙ってクローゼットの方へと歩みを進め、扉に手をかけたので、俺は慌ててその背中を追った。俺より断然落ち着いた様子の真冬が振り返る。
「座ってていいのに」
「任せっきりにするわけにいかないだろ」
こんな時こそ協力第一だ。一人じゃ無理でも、二人ならできるなんてこともある。第一、真冬にばかり面倒事を押し付けてはいられない。俺だって当事者だ。
「くく、かわいーな、お前は」
「はぁ?なんだよいきなり……」
窮地に陥っているはずなのに、真冬はなんだか余裕そうだ。
真冬が俺の方を見て笑いながら、クローゼットの扉を開ける。はてさて何が飛び出してくるかと身構えたがーーーー中から出てきたのは、水の入ったペットボトル2本のみだった。
「……え?」
てっきり化け物か何かでも飛び出してくると思っていた俺は、間抜けな声をあげて呆然とした。しかしどこからどう見ても、ただのペットボトルに入った水だ。同じく眼をぱちくりさせた真冬が、その無色透明な容器を手に取る。
「なんだこれ。水?」
「水……だな。多分……」
何とも拍子抜けな答えだ。真冬がひととおりペットボトル全体を確認して、恐る恐るキャップを開けようとする。俺はそれに驚いて、思わず口を挟んだ。
「飲むのか?」
「んー、まあ……。飲んでみねえとなんの液体なのか分かんねえしな」
「き、気をつけろよ。何か入れられてるかもしんねえし……、あ、なんなら俺が飲むよ」
見たところ何の変哲もない水だが、油断はできない。こんな部屋にある水だし、何か変なものが入れられているかもしれない。
真冬もそれをわかっているはずなのに、その余裕そうな表情は崩れない。
「何か入れられてるって、例えば?」
「え、そりゃあお前……。良くないものとか」
「良くないものってのは?」
「え゙、うーん……。その、なんか……変な薬とか……」
「変な薬?例えばどういう効果の?」
やけにぐいぐい質問して来て困惑する。真冬の楽しそうに眼を細める姿はどう考えてもからかっていて、俺はおい、と咎める声をあげる。思った通り反応を楽しんでいたらしく、真冬はニヤニヤしながら、ごめんってと一言返した。
「大丈夫だよ、変な感じしたらすぐ吐き出すって。飲んでみねえことには分かんねえからな」
「う、ほんとだろうな……。面白がって飲んだりするなよ」
「それに、何かあってもお前なら助けてくれるだろ?」
さも当然のことかのように、真冬はそう言い切ってみせる。これまた結構なご要望だ。……まあ、俺にできることはなんでもする。当然だ。
「わ、分かったよ。気をつけろよ」
不安そうな俺を安心させるみたいに、真冬が笑ってみせる。そしてボトルのキャップを捻り、迷うことなく飲み口に唇をつけた。
ボトルの中の謎の液体がひとくち分、豪快に口の中に注がれる。その思った以上の量に俺は若干焦った。試飲にしては大胆すぎじゃないか? 真冬は平然とした表情で、口の中をもごもごさせている。やがて分厚い喉仏が上下して、その液体を飲み下した。俺は一切変わらない真冬の表情を凝視する。
「ど、どうだ?」
「んー、なんかやけに甘えな……。やっぱただの水じゃねえかも」
「え゙っ」
嫌な予感が的中してしまったかもしれない。全身の血の気が引くのを感じる。やっぱり俺が飲んでいれば良かった。真冬に何かあったらどうしよう。
「そんな顔すんなって!ひとまずなんともねえから。痛いとことか、変なとことかも全然ねえし」
「で、でも……」
「大丈夫だって!でも、これはもう飲まない方がいいかもな。共倒れになったら流石に洒落になんねえし」
片倒れでも、俺にとっては十分洒落にならない。考えれば考えるほど、嫌な結末ばかりが頭に浮かんでくる。この状況を打破するためには、やはりこの部屋から出る手がかりを探すのが先決だ。
「と、とりあえず、出る方法を探さなねえと……。ま、真冬は座って待ってろよ!何があるか分かんねえし!」
「なんだよ、心配症だな〜。俺、もしかして結構愛されてる?」
「ばっ、からかうなよ!」
不意打ちで地味に恥ずかしいことを指摘され、ばっと頬に微量の熱が溜まる。咄嗟に目元を腕で隠して、顔を反らした。真冬の表情は見ていなかったが、すぐになんだか物憂げなため息が聞こえてきて、俺は視線をもとに戻した。何故か真冬も目元を手で覆い隠している。
「……。なんだよ」
「いや……。たまんねえなあと思って」
「はぁ?なんだよそれ……。取り敢えず、ベッドで座って待ってろよ。俺はもう少し、扉の付近に何かないか見てみる」
「じゃ、俺はついでにベッドの方に何かないか見てみるわ」
十分身体を張ってくれたのだから、素直に休んでくれていていいのに。人のことは言えないが、相変わらず根が頑固だ。
そうして俺と真冬は、目の前のクローゼットの扉を一旦閉めた。このペットボトルの液体が、波乱を呼ぶとも知らずに。
各々で捜索を開始して数十分。俺はベッドの方を見ると言った真冬のほうがやけに静かなのに気がついて、慌てて捜索を中止した。少し距離のあるベッドの方に駆け寄ってみると、両頬を真っ赤にした真冬がベッドに沈んでいた。ふぅふぅと息を乱す様子は明らかにただ事じゃなくて、血の気が引く。
「真冬!」
慌てて真冬の額に手のひらを当ててみると、それなりに熱い。発熱しているのだろうか。なんにしても早くここを出て、解熱剤を飲ませるか、病院に連れて行くかしたほうがいい。
何かこの熱を冷ませるものがないか探そうと、その場から離れようとする。しかし熱くなった額から離れた手首を、同じぐらい熱い片手に掴まれて、俺は驚いた。とんでもない力だった。
「……。花梨……?」
名を呼ぶ声は少し浮ついていて、瞳も虚ろだ。なんとか定まった瞳の焦点が徐々に俺を捉え、真冬は握っていた俺の手首をゆっくり放した。
「大丈夫か!?」
「ん、だいじょぶだいじょぶ……。って言いてえとこだけど、こりゃやっぱ、さっきの水になんか盛られてたな」
勇気が裏目に出ちったな、と苦笑いする真冬。その頬には汗が浮かんでいて、なんだか苦しそうだ。
どうしよう。やっぱり、無理にでも止めるべきだった。早く、部屋から出る方法を探さなくてはならない。慌てぶりが顔に出ていたのか、真冬が上半身を起こして、俺の頭を撫でる。
「そんな顔すんなって。多分、命に別状はねえよ」
「そ、そうなのか?なんで分かんだよ?」
「んー……ほら、ここってセックスしないと出られない部屋だろ?多分、そういう気分になるもん盛られただけだと思う」
真冬はそう言うと、自分の下腹部の方に目線を下ろす。俺もそれにつられてし目線を移動させて、そこにあったものにかっと両頬が熱くなった。真冬の股間が、ジーパン越しに膨れ上がっている。それはその……、つまり、そういうことだ。
「わ……っ、だ、大丈夫なのか!?」
「そりゃきつくねえと言えば嘘になるけど……、ま、ほっとけば収まるだろ。薬も流石に時間には勝てねえよ」
どうやら真冬は、このまま時間経過であさまるのを待つつもりだ。しかしそれは、耐久や拷問に近いそれではないだろうか。
何か俺にしてやれることはないのだろうか。そりゃ出口が見つけられるならそれに越したことはないが、今の所どん詰まりだ。悶々と思考を巡らせるが、碌な案が出てこない。いやーーー案自体はあるが、それは俺にとっても真冬にとっても、とんでもなく負荷がかかる案だ。
「ま、真冬」
「うん?どした」
張り切って声が裏返りかける俺に、真冬が怪訝そうな表情を浮かべる。嗚呼これで却下されて今後の関係に亀裂が入ったら如何しよう、いやしかし、ここから出られなければ今後もクソもない……。頭の中を飛び交う言葉たちを整理整頓して、俺は流れに任せてその提案を口にした。
「セックス、しねえ?」
「は?」
真冬が今日イチの勢いで目を見開く。数秒の沈黙が流れる。その沈黙に胸が苦しくなったが、俺はそのまま勢いでゴリ押しした。
「だ、だって!セックスしなきゃ出られねえなら、逆にセックスすれば出られるんだぞ?」
「……。本気で言ってんのか?」
その思った以上に低いトーンの声に、柄にもなく背筋が凍った。しかし押し負けるわけにはいかない。
「だって、お前そんなに苦しそうなのに、放っとけねえよ……。そりゃ、俺となんて、したくねえかもしんねえけどさ」
「あー、違う違う。俺が怒ってんのはそっちじゃなくて」
真冬にこんな顔をされるのはいつぶりだろう。怒っているし、呆れてもいる。そんな顔だ。
「お前、もっと自分を大切にしろよ。気遣ってくれんのはありがてえけどさ。その提案はたしかにてっとり早えけど、負荷もかかるし失うものも色々大きいだろ。ちゃんと分かってるか?」
「わ……分かってるよ!分かってていってんだ!」
真冬は若干きょどっている俺の言葉を信じられないのか、ギャグ漫画みたいなジト目でこちらを威圧してくる。如何すれば信じてもらえるだろうーーーーそこで、ふと思い出した。クローゼットの奥に隠されている、現状の元となったもののことを。
俺は慌ててベッドから立ち上がり、クローゼットの方へ駆け寄る。予想外だったのか真冬の方は少しの間静かになっていたが、俺がクローゼットの扉を開けたのを見て、察したらしい。花梨、と咎めるような声が飛んできた。
真冬がこちらにたどり着く前にペットボトルを手に取って、キャップを開ける。そのまま飲み口に口をつけて、液体を口の中に流し込んだ。
「馬鹿ッ、やめろ花梨!」
真冬が慌てて止めに来たが、その頃にはとっくにひとくち飲み下していた。真冬の静止を無視してもうひとくち飲わやみ干す。
「分かった、わかったから!そんぐらいにしとけ!」
真冬の顔は相変わらず赤くて、息も切れていたが、それでもわざわざこちらまで駆け寄ってきた。俺はなんとなく振り返りにくくて、クローゼットの方を向いたまま扉を閉める。すると細長くも逞しい腕に後ろから身体を抱き寄せられて、突然の抱擁に心臓がいつもより大きく収縮した。突然縮まった距離に身体が強張る。
「ほんとに、いいんだな?やっても……」
ぎゅうと腕に込められた力が強くて一瞬動揺するが、意思に変わりはない。真冬の体温の高さを感じながら頷くと、真冬は観念したように息をついた。
「言っとくけど、俺はお前が好きだから……。この機会も思う存分、利用するからな」
真冬が俺を好きだという事実は、知っていた。聞かされていて、一度断っていた。
「好きだ、花梨……。こんな形だけど、この気持ちには何の偽りもない。これからお前を抱くのは嫌々じゃないってこと、ちゃんと知っといてくれよ」
「ま、真冬……」
いつもより格段に真剣な声のトーンに、緊張の鼓動が止まらない。細長い指先で顎を持ち上げられ、視線と視線がぶつかりあった。
「嫌だったら、ちゃんと突き放せよ」
そう言うと真冬は、壊れ物に触るみたいに慎重な手つきで、俺の顔に自分の顔を寄せる。長い睫毛が俺の瞼に当たって、唇が重なり合った。あ、これキスされる、と気がついたときには、もう唇同士がくっついていた。そういえば、真冬に初めて告白されたときも、こんな風にキスをされたーーーーそんなどうでもいい思考の最中。
突然膝裏に真冬の腕が回って、そのまま姫抱きされた。予想外のアクションに思わず間抜けな声を上げてしまう。
「うわぁっ!?」
「取り敢えずベッドな。立ったままやるなんて論外だから」
これでも高身長で抱っこしにくい部類の自覚があるのだが、真冬はそんなのお構いなしだ。軽々と抱っこされてしまった俺は、あっという間にベッドまで運ばれ、降ろされた。
隣に座った真冬は余裕がなさそうなのに、手つきは依然として優しいものだった。愛おしむように髪の毛に指を通されて、もう一度キスをされる。すぐに前に出た舌先に、唇をつんつんとノックされる。恐る恐る空洞を作ると、その間からぬるりと舌が入り込んできた。
「んッ!うぅ……っ、ん」
「は、……ふ……」
ファーストとセカンドは事故みたいなもので済ませているとはいえ、舌を入れられるのは流石に初めてだ。どうすればいいか若干戸惑うと、それを察知したのか真冬の方から、舌を絡め取ってきた。ぬりゅぬりゅと唾液が混ざり合う感覚に、脳が浮つく。
「ぅ……ふぁ……っ」
何もかもが未知の領域だ。この状況も、友人とのディープキスも。
真冬の舌に自分の舌をぎゅ〜っと絡めとられる感覚で、なんだか脳が痺れる。気のせいか身体の内側も熱くなってきた。さっき飲んだ謎の液体の効果が出てきたのかもしれない。
「ぷぁ……っ、はぁ……」
「ん……、なんか、めっちゃ顔赤いな。さっきの水の効果出てきた?」
「わ、かんね……。なんか、身体熱い」
なんだかお腹の奥あたりから、ぽっぽと熱が発生している感覚がある。ついでに、頭も若干ふわふわする。今の所、やはりあの水は完全に危ない薬である。やっぱり、二口は飲みすぎたかもしれない。
「……、駄目だ。エロすぎる」
「え?」
「いや、なんでもねーよ」
真冬が辛抱たまらないというように唇を噛むので、俺は自分が今一体どんな顔をしているのか気になった。もしかしたら、だらしない顔をしているかもしれない。真冬もこういうところは笑わずに我慢してくるのだから、なんだか複雑だ。
「どこか触ったら駄目とか、逆に触ってほしいとことかあるか?」
「いや、特にねーかな……。どうやってすすめるのがいいのかいまいちよく分かんねえし。任せる」
なんだか投げやりっぽくなってしまったが、本当によく分からないのだ。すると真冬はんー、と軽く唸りながら考えて、俺の上半身のシャツに手をかけた。首元のネクタイを解いて、次にボタンを外していく。
「……、胸、やっぱ触んのか?」
「んー?うん。そりゃ触るだろ、つーか俺が触りてえ」
「ッお、おう、そうか……」
突然ダイレクトな願望をぶつけられて、恥ずかしさで頬が熱くなる。そんな俺を見て、真冬はなんだか楽しそうに、その口に微笑みを漂わせていた。
真冬が近くにあったナイトデスクからローションの容器を取り出して、中身を掌に広げた。露わになった平たい胸を撫でながら、俺の耳朶に唇を落とす。
「んっ……」
外の冷気に晒された俺の胸を、真冬の手のひらが優しく触る。微妙に膨らんだ肉の部分を揉みながら、形のいい親指と人差し指が、両側の乳頭を軽くこすりあげた。
「んっんん……っ、んっ」
「大丈夫?痛くねえ?」
「ん、大丈夫……」
擦るのと同時にきゅっきゅうっと先をつまみ上げられる。耳元で囁かれるのと同時にやられると背筋がぞわぞわして、なんか、変な感じだ。
こすっこすこす……しこしこしこ……
「ぁっんっ……、まふゆ、それ、なんかへん……」
「変?どんな感じだ?」
「胸、ピリピリする……なんか腹の奥もむず痒い」
「…………」
真冬があまりにも神妙な面持ちで俺を見るため、何か変なことを言ったかと一瞬不安になる。しかし嘘は言っていないのである。
こすっこす……くりっくり、くにゅっ
先程より強い力で乳首を捻られて、ピリッとした電流が胸元から腰へと走る。
「ぁっあん……」
全く本意ではない変な声が止まらない。これはほんとに自分の声だろうか。気のせいか下腹部も熱い。
真冬が俺の首筋を撫でながら、大丈夫、と安心させるように囁く。
「それが、気持ちいいってことだぜ。さっきの薬で、感度良くなってんのかもな」
きゅむ、きゅむっ……きゅう〜〜っ
「ひぁっんぉ……♡うそ、ちくび、きもちいい……っ」
「は、なんか、いけないこと教えてるみたいで興奮すんな……。もっと触るから、ちゃんとこの感覚覚えよーな」
軽く引っ張り上げられた乳首が、今度は乳頭を押す形で潰される。ぐりぐりと乳輪の中で先端が擦れて、下半身がビクつくどころか、下腹部で汁が漏れる感覚すらあった。信じられない。
くりゅっくりゅ……くに、くにくに……
「はっん……♡あっぁあ……♡んぅ……♡」
「は、可愛い……。お前、そんな声出すんだな」
「ゃっ、きくなバカ、あっ、んぉ♡」
「なんでだよ。すっげえ可愛いぜ?」
ぎゅっぎゅ〜〜っ、ぎゅっ!
摘まれ引っ張り上げられた乳首が、段々濃い色を帯びて膨れ上がっていく。
乳首で感じている事実もそれで変な声を出している事実も、全てが恥ずかしい。違う、違う違う、これは薬のせいだ、と何度も頭の中で言い聞かせる。
「はっ、はぁ……♡あっ、んッ!?」
やがて両胸を弄っていた方の手がするりと下に落ち、やんわりたちあがってしまっている俺の屹立をズボン越しに擦った。びくんと分かりやすく腰が揺れてしまう。
「ん、勃ってるな……。ちんこ、自分で触ったことあるか?」
ぶんぶんと首を横に振る。それを見た真冬は少し息を整えてから、優しく俺の屹立の裏側部分を撫であげる。
「ふぁ……♡んっ」
「ここは、基本胸より気持ちよくなれるからな……。ちゃんと触り方、覚えとくんだぞ」
「あっぁ♡かりかり、だめ……っ♡」
爪先で掻くように触られて、くすぐったさに身をよじる。若干荒い手つきで制服のベルトに手がかけられた。あ、あ、と羞恥で顔面が煮立っている間に、下着ごとズボンがずり降ろされて、俺の屹立がご開帳だ。真冬がぱちぱちと瞳を瞬かせながら、それをガン見する。
「へえ。思ったよりちっちゃくて可愛いな」
「お、ま……っ!言っていいことと悪いことがあるだろ!?」
「なんだよ。褒めてんだぜ?」
くくっと真冬が笑う。ちんこが小さいことのどこが褒め言葉なのか、さっぱり分からない。にゅちゅ、とローションを纏った細長い指が、俺の屹立の胴体の部分を包み込む。
にゅちゅっ、にゅちゅっ、にゅちゅっ
粘性の液体の音を立てて、ゆっくり上下運動が始まった。腰がじんわりとした甘い刺激に包まれる。たら、とみっともなく唇の端から唾液が垂れた。
「あっあぁあん……♡らめぇえ……♡ぬちゅぬちゅ、きもちいいのぉ……ッ♡♡んぁあん……ッ♡」
「ッ、素直でよろしい……」
ぬっちゅぬっちゅ、にちゅっぬちゅ、ぬちゃぬちゃぬちゃ……
快楽に蕩ける意識の隅で、真冬の余裕のなさそうな息遣いが聞こえる。その吐息の熱さにつられて目線を下腹部から上に上げると、熱情がこもりにこもった眼差しが、俺の身体を刺した。釘付けにされたみたいに、その橙の眼を見つめてしまう。真冬も少しの間黙って俺の顔を見つめて、何を思ったのかは分からないが、また唇を重ねてきた。
「んっ……♡ふ、うぅ♡んっんっんっんっ♡んうぅっ♡」
「は、ん……っ」
ぬちっぬちぬち、くりゅ、くりゅくりゅ……っ
亀頭を指の腹で押しつぶされ、陰嚢を軽く揉みしだかれる。急所を触られることへの本能的な恐怖よりも、むず痒い快感のほうが上回って、困惑の感情が抑えられない。
ぐりゅっぐりゅぐりゅ!くにゅくにゅくにゅ!
亀頭と鈴口をそれぞれ同時に押されて、喉が勝手にあられもない声を絞り出す。
「ひッぐぅ゙ゔ〜〜〜………ッ!♡♡まって、きちゃッ、♡んぁっあんっ♡なんかきちゃうッ!♡だめっ、あっあっあっあぁあ゙っ!♡♡」
「は、花梨、可愛いな。すっげー可愛い……。イきそうなのか?いいぜ、このままイけよ」
じゅぽじゅぽじゅぽっ!にちゅにちゅにちゅにちゅにちゅっ!
「ひゃあぁああん゙っ!♡♡りゃめぇええっ!♡」
射精を促す強烈な動きに、びくんと身体が弓矢のようにしなる。汚れるからと真冬の身体を突き放す暇もなく、俺は真冬の手の中に精を吐き出した。
ぴゅるるっ!ぴゅっぴゅう〜〜〜っ!
「ぁ゙ッ、あんん……ッ♡♡で、でてりゅうぅう…………ッ♡♡あぁあああ………♡♡」
「はぁ、は………、初めてなのに、ちゃんと気持ちよくなれて偉いな」
真冬が俺の額にキスを落として、嬉しそうに笑う。子供扱いすんなと言いたい。言いたいのに、快楽の余韻で脳が痺れて、息を整えるのにも一苦労な有り様だ。
「……さて、気持ちいいのに慣れてもらったところで。ここからが佳境だな」
刺激に浮かされた頭でも、それがなんのことを言っているかはすぐに分かった。ドキ、と緊張で心臓が高鳴る。
「どうする?抵抗あるなら、自分でやってもいいと思うけど」
「い、いや……。むしろ、触ってもらったほうがありがたいな……。自分でできる自信がねえ」
「………触ってもらったほうがいいって言い方なんかエロいな」
「おい」
まだうまく力の入らない手で真冬の胸板をぺちっと叩くと、真冬は意地悪な笑顔で、冗談だよと俺の頭を撫でる。ただでさえ普段から近い距離がさらに近づいて、なんだかそわそわする。
「痛かったらちゃんと言うんだぞ。手とか上げて」
「っはは、歯医者かよ」
くだらない内容なのに、それがなんだかとても安心して、くすくす笑ってしまう。実際、安心させるためにいったんだろうな、となんとなく感じた。
真冬が新しくローションの容器から中身を取り出す。俺がベッドの上に寝転がると、真冬が俺の足を持ち上げて間に座るので、その体制の恥ずかしさにまた顔が熱くなった。なんだかお腹の奥が疼く。
少しの間、天井を見つめたまま大人しくしていると、やがて後孔をローションのひんやり冷たい感触が襲った。
「は、ん……ッ」
いくら薬で感度が高まっているとはいえ、そこはあまりにも未知の領域だった。細長い指が何度か穴の縁をなぞり、ゆっくりと中央に指を突き立てる。
「うぁッ、は、ぁ……ッ!」
スローで侵入してくる指先に、がく、と腰が浮く。痛みと強烈な異物感に、脚の爪先が伸びた。
「大丈夫か?あんま痛いなら、こっちに意識向けろよ」
「っ、ぁっあ♡ん……っ♡」
痛みを薄めるためか、真冬が先程達したばかりの陰茎をにゅぷにゅぷと触る。痺れにも近いビリビリした刺激に、若干気が紛れる。
「はっ、は……ッ中、うごぃ、て、あぁ……っ!」
「っ、ごめん、ごめんな……。もうちょっと進めれば、多分、アレがあるはず……」
真冬は悪くない。そう言ってやりたいが、異物感に言葉が持って行かれて、まともなことを言えない。
真冬は何かを探すような手つきで、俺の中を弄っている。やがて異物感に慣れてきた頃、真冬の指がある一点をずりっと擦り上げ、俺はそこから走った刃のような刺激にがくんっと腰を揺らした。
「ひゃあっ!?♡」
その声は今までの痛みに耐える声とは違う、甘やかなものだった。今のは本当に自分が出した声か?恐る恐る真冬の方を見てみると、少しの間目を丸くしていたが、やがてそれは意地悪な笑顔へと変わっていった。さっと血の気が引く。
「ぁ、まってッあ゙っあぁ゙っ!?♡」
こりゅ、こりゅこりゅっ
たった今判明したその急所を、ぐりぐりと指の腹で押し潰される。擦られ押された神経から刺激が走り、体が痙攣する。
がくっがくっ、がくっ!
「ふぁ゙あッ!?♡♡な、に……っ?あッだめっあっあっ!♡あ、あぁああ゙ん゙……っ!♡」
ぐりっぐりっとリズミカルに内側を抉られるたび、性感帯を直接殴られているかのような快楽が走る。真冬が鼠径部に唇を落として、笑った。
「大丈夫、ここ、多分前立腺だぜ。男の人が中で一番気持ちよくなれる、大事な場所」
「じぇ、んりつしぇん……っ♡しゅごしゅぎ……っだめぇ……っ」
「へぇ、やっぱりここって気持ちいいんだな」
関心の声を上げながら、真冬はぎゅ〜っと俺の両足を抱き締める。そして再度、中の腸壁と前立腺を強くこすり上げた。
ずりゅずりゅっ、にぢゅゔうっ!
「んぉおおおっ!?♡♡ だ、だめっていって、あぁ゙っお゙っ♡お♡お゙ぉ♡お゙ぉっ、あ゙ぁ〜〜〜ッッ!♡♡」
「すっげ、指食い千切られそう……」
こりゅっこりゅ、こりゅんこりゅんと引きずり回される前立腺の刺激に、俺はもう恥も外聞もなく喚き散らしてしまっている。目の前で急所を弄りまくる男に引かれてはいないかと度々頭によぎるが、確かめる余裕などあるはずもない。
「ほら、こっちも擦ってやるから、もっかいイっとけ」
「あぇっ!?ひゃあっ!♡んんぅううう〜〜〜〜ッッ!♡♡」
ちゅこっ、ちゅこちゅこちゅこちゅこ!
「ぁイっく♡いっく♡いくっいくっ!♡ぁッあ゙ぁあ〜〜〜〜……ッッ♡♡」
腹に刻まれる快感は全身をめぐり、それが脳にぶちまけられたとき、下顎が天井を向いた。いつの間にやら上を向いていた屹立からぴゅ〜っと白濁の液体が吹き出した。真冬がぺろりと舌なめずりしたのが見えた。
「っはは、絶景……」
「はぁっ、はぁ………っ♡はぁ……っ♡ぁ〜っだめ、まだ、いってるぅう……っ♡♡」
「ほら、花梨……。まだ一本目だぜ?」
興奮したように息を詰めた真冬の声がする。まだ一本目。これで一本目?これで二本になって、三本になって、最後は……?
きゅうっ、きゅうん……っ
「……?なんか、中しまった?」
「へっいや、別に……ッ」
しまった、思考に伴って身体が勝手に反応してしまった。なんにもない様子を装いたいのに、顔が勝手に熱で燃え上がってしまう。真冬がニヤッと瞳を細めて笑い、俺の内股に唇を落とした。
「分かりやすいな、お前は」
「う、うるせえっ」
いちいち言動が気障なので、無駄なドキマギしてしまう。後孔の縁に2本目の指がかけられ、先が中に侵入してくる。尻穴を広げられる感覚に背筋がぞわっとしたのもつかの間、3本目の指先も一緒に中にはいってくる感覚があって、また情けない声が口から飛び出る。
「いぁっ、はっ、あ……っ!あっあんっ♡あっ♡」
強烈な異物感と前立腺がかすれる刺激を同時に味わい、息が切れる。やがて根本まで飲み込まれた3本の指は、ゆっくり前後運動を始めた。
ぬっちゅ、ぬっちゅ、にゅっぽ、にゅっぽ、にゅっぽ……っ
「はっあッあん……ッ♡あっああ……っ♡ま、まふゆ、それ……っ♡なんかへん……っ♡」
「ん、気持ちいいか?」
「わ、かんない、けどっ♡たぶん、きもち、いぃ……っ♡♡」
大分薄まった痛みと苦しさの向こうから、ぞわぞわと内をくすぐるような初めてのむず痒さを感じた。自分も知らない自分を暴かれているようで、なんだか怖さがある。
「んあっあっあ……っ♡なか、ぬちゅぬちゅ……っ♡でたり、はいったり……っ♡んぁっ、んぅううう……っ♡」
「ッ、は、くそ……駄目だ……っ」
意識の片隅で、真冬が低い声で喉を鳴らしたのが聞こえた。中に挿入された指はそのままに、ガチャガチャと金属がこすれる音がする。やがて聞こえた布擦れの音と鼻をかすめた雄の匂いに、真冬が自分の屹立を取り出したのだと分かった。
にゅちゅ、にゅちゅ、にゅちゅ……っ
しゅこっしゅこしゅこしゅこっ!にちゅにちゅにちゅにちゅッ!
後孔を弄る音とは別で聞こえる摩擦音は、俺の屹立を触っていたときとは段違いに激しかった。随分手加減されていたのだと、今更知る。
「ん゙っ、ぐ……っ♡」
それは首輪をつけられ拘束されている、獣のような声だった。もしかして、相当我慢させてしまっているのだろうか。無理はしないでほしいが、でもこれで獣が解き放されたら、自分はどうされてしまうのか全く予想がつかない。
そうこうして刺激に身悶えているうちに、動いていた指が一度止まり、引き抜かれる。そして上から俺の顔をのぞき込んだ真冬の顔は、始めた当初の余裕のある笑顔はなくなっていた。頬は赤く蒸気し、橙の瞳は熱情に煮え立っている。
「も……、いいか?」
それでも声色は、優しいものだった。全てはこの部屋から出るためーーーそしてここまできてしまった。今更断る理由はどこにもない。俺はなるべく真冬に遠慮して欲しくなくて、今できる限りの笑顔で返事をした。
「いいよ」
*
全く誰のどういう策略なのか知らないが、それにしても質の悪すぎる悪戯ーーーそれで済まされていいのかわからないほど手の込んだ悪戯だがーーーだ。
ベッドの上に前が開いたシャツ一枚で寝転がる花梨の姿に、俺は内心情緒がめちゃくちゃだ。ひとりでいるときに何度も思い浮かべた情景が目の前にーーーー不本意なことに存在してーーーー人間性を試されている気すらした。
「も……、いいか?」
大好きな人の淫らな姿に、理性がじりじり焼ける音がする。焼け残った理性はもう残り少ない。どこまで耐えられるかは、時間の問題かもしれない。
花梨の肌に触れている部位が熱い。花梨がどんな返事をするか、彼の性格を考えればすぐ分かるはずなのに、異様なほどに心臓の鼓動が大きく聞こえた。
「いいよ」
花梨は俺の方を見て、まるでこちらを安心させるかのように、くしゃと笑ってみせる。目尻に溜まった涙とその笑顔の健気な組み合わせに胸を打たれて、俺はするべきことを忘れて、一瞬その笑顔に魅入った。
こういうとき、どんな顔をすればいいのだろう。どんな声で、言葉で、話をしたらいいのだろう。こんなことは誰も教えてくれなかった。
先程自分で射精させたはずの俺の陰茎は、もう普通に再度立ち上がっている。我ながら正直すぎる身体だが、俺だって20歳の健全な男だ。しかも相手は自身が片想い中の少年である。
すぐそばのナイトデスクの引き出しを漁って、中からコンドームを引っ張りだす。まさかこの歳でーーーしかも未成年の想い人を相手にーーー使うことになるとは思わなかった。
「痛かったら止めるから、ちゃんと言えよ」
「ん、だいじょぶ……。ここまで来たらもう逃げねえよ」
台詞は男前だが、その表情にはやはり不安が残っている。当然だ。俺が花梨の立場だったとしてもそうなるだろう。とにかく俺にできるのは、なるべく彼に負荷がかからないようにすることだけだ。
上から覆いかぶさる体制で、花梨の顔の横に手を置く。している行為は淫らなのに、ベッドの上で静かに次の行程を待つ花梨の姿は、誰よりも愛らしく純真に思えた。薄く膜を貼った綺麗な瞳に心臓の鼓動が早まって、わざとらしく戯けた態度を取ってしまう。
「怖かったら抱きついててもいいぞ」
跳ね除けられる前提の冗談だったし、実際からかいの意味も含まれていた。しかし花梨は、予想外にもその冗談を咎めることはせず、俺の首元に腕を回す。えっ、と声が出そうになった。
「……じゃあ、甘える」
すり、と肩に目元を擦り寄せられ、ただでさえ早い鼓動がさらに加速する。漫画だったら、ずっきゅーんだかどっきゅーんだか、そんな感じの効果音が出ていたことだろう。
ローションと体液で光るピンク色の蕾に、自分の先端を押し当てる。びくんと花梨の身体が揺れた。
にゅる、にゅるっ……にゅちにゅち……っ
「あっあぁ……ッは、はいっ、て……っ!」
「ッ、花梨、しっかり深呼吸しろよ……」
勢い余って中を傷つけないように、ゆっくりゆっくり腰を押し進める。挿入する過程で前立腺が潰れるのか、花梨があっと甘い声をあげて腰を浮かせた。
「ッんぁああっ!♡♡ぅ゙あっ♡じぇっじぇんりつせんっ!つぶれゔぅうっ!♡」
「は、ぁぐっ、めっちゃしまる……ッ!」
思ったより中の締め上げはキツく、少し気を抜くと持って行かれそうだ。しかし、我慢できないほどでもない。
にゅくっ、にゅぷぷぅうう……っみちみちぃ……っ
押し進めた屹立はやがて行き止まりにたどり着き、とちゅん、と花梨のお腹の方から音がした。
本当に、入った。若干きついのはきついが、柔らかいひだに包まれ吸い付かれる感触が気持ちいい。何より、自分の大好きな人と繋がれているという事実が大きな興奮材料となっていた。
花梨は挿れられた衝撃が大きいのか、顎を仰け反らせて体を痙攣させている。
「ほら、花梨……。入ったぜ」
「ぁ、っ♡はぁ、ふぅ……っ♡にゃか、おっきぃい……っ♡♡みちみち、あちゅい……っ♡」
熱く張り詰めた下腹部を見て喘ぎを漏らす姿は、小さい子猫のようだ。今この人をこんな風に喘がせているのが自分だと思うと、背筋がぞくぞくした。
はっ、はっと大きく息をする花梨の頭を撫でながら、ベッドと真反対の方向にある扉に目を向ける。鍵が空いた様子はなく、それらしき音もしない。ある程度動かなければカウントされないのかもしれない。
「少しずつ、動くからな……っ」
「っ、ん、ぅんっ」
ぱちゅっ……ぱちゅっ……ぬちゅっ……
自分の両手と花梨の両手を絡めながら、入れた腰を上げて、もう一度入れ直す。腸壁を擦られる強い刺激に、花梨が俺の背中にぎゅっと縋りついた。俺もその背中を抱き返し、強く肌を密着させた状態で、ゆっくり腰をふる。
ぱんっ……ぱんっ……とちゅっ……とちゅっ……
「はッあぁあ……ッ♡ゆっくり、ぬちゅぬちゅ……っ♡まふゆのおっきいの、なかでうごいて、ッぉん、んん〜〜〜〜……ッ♡」
「はっ、ッ、花梨、花梨……」
部屋から出なきゃいけないから仕方なく、と言いつつ、俺はもうすっかり行為に夢中になってしまっている。ぴるぴる震えながら俺の屹立を受け入れている花梨に、愛しい感情が止まらない。半空きでちろりと舌が見えている口に、自分の唇を押し付ける。
「ん……っ!♡んむっ、ぅ、♡ん♡ん♡んぅっ♡」
「ん、ふ……っ」
湿った柔らかい唇を甘噛みし、舌先で口内の至るところをなぞり上げると、中がきゅうっと締まる。興奮してくれている。こんな形で初めてを迎えて、不本意なはずなのに、どうしようもないほど先を期待してしまう。
とんっ、とんっと奥を叩くようにして腰を入れると、花梨の身体がその度小刻みに震える。
とちゅんっ……とちゅっ、とちゅっ、とちゅっ……
「あっあんっ♡♡おく、おくしびれうっ♡あっぁ、あっだめっ♡んぉっ♡んぅうっ♡」
「ん、奥、気持ちいいか?」
「きもちぃ♡きもちいぃのだめ……っ♡♡へんになっちゃう、からぁっ♡んんっ♡」
「なにそれ、めっちゃエロ……。怖い?初めてだもんな、そりゃ怖いか」
まあ、こんなことを言っている自分も実際は初めてなのだが。せっかくならどろどろに甘やかしてやりたいところだが、焼け残った理性はもう残り少ない。優しくしてやれる余裕は到底なかった。
ぱんっぱんっぱんっぱんっ!ずんっずんっずんっずんっ!
「んぉっ♡おっおっおっ!♡♡つよい♡まふゆっ♡それつよっ♡♡い、いくっ、だめっいっちゃうぅっ!♡」
ぴゅっ!ぴゅるっ!ぴゅるるる……っ
腰を入れるスピードを早めると、花梨の身体ががくっがくっと大きく揺れて、屹立が弱々しく射精した。どの角度でどんな風に見ても愛しい。もっとたくさん気持ち良くなってほしい。もっと一緒に気持ちよくなりたい。
ばちゅっばちゅっばちゅっ!どちゅっどちゅっどちゅっ!
「ぉ゙あ゙ッ♡らめっ♡いったばっかにゃのにっどぢゅどぢゅっ♡♡ぅお♡お、おぉおっ♡おぉっ♡♡」
「はっぐ、ぅ゙……っ」
いった直後でただでさえ締まっていた中が、追撃で更に締め上げを強くする。もうちょっとだけこのままでいたかったが、そろそろ限界だ。
「ぁ゙、花梨、俺もそろそろいきそう……っ」
「っん、ぅん♡いい、よ、出して、まふゆ……っ出して、ぁんっ!♡あんあんあ゙ん゙っ!♡♡」
それは射精寸前の男にとって、シンプルだがとんでもない殺し文句だった。自然と腰を打ち付けるスピードが上がり、腹の奥から精子がぐんぐんあがってくる。あー、くそ、俺にもっと忍耐があれば、楽しみも長くなったのにーーーーもう思考回路は完全に、本来の目的から逸脱してしまっている。
「あー、イくっイくっ♡」
ぱんぱんぱんぱんぱんぱんっ!どちゅどちゅどちゅどちゅどちゅっ!
「ひぁ゙あ゙あ゙ッ!!♡♡いっぐぅうううううっ!!♡♡♡」
大きく痙攣する花梨の体が離れてしまわないように、しっかり抱きしめて、奥に腰を打ち付ける。
どびゅうううっ!びゅるっびゅるびゅる、びゅううう〜〜〜………っ!
ほぼ同じぐらいのタイミングで絶頂した花梨の締め上げに、俺は花梨の中で勢い良く射精した。
「ぁっでてる、でてるぅ……っ♡♡なか、びくびくしてるぅう……っ♡」
「っ、はいはい、俺、ちゃんとゴムしたからな……」
涙目で喘ぐ花梨の頭をなでて、俺は中から自分の陰茎を引き抜いた。
そうして、ようやく扉の鍵が開く音がしたのだった。
*
事が済み、扉の鍵が空いたあと。最初はなかったはずなのになぜか部屋に出現していたバスルームで、俺と真冬は身体の洗浄を済ませた。
結論から言うと、鍵の開いた扉の先は、都外にある謎のカフェだった。二人で部屋を出たあと、あの謎の部屋に続く扉は跡形もなく綺麗さっぱり消え去っていた。何もかもが非日常すぎた。こちらは友人とセックスしたという事実の受け入れすら手こずっているというのに。
取りあえず都内にあるそれぞれの家に帰るため、俺と真冬は二人で電車に揺られていた。時間帯は夕方でそこそこ人がいたが、奇跡的に座席の確保もできた。
珍しくぼーっと窓の外を眺めている真冬の横顔を、隣から黙って盗み見る。切れ長の美しい瞳は太陽の光を受けて、宝石のように輝いている。赤のメッシュが入った茶色い猫毛は、思わず触って確かめてみたくなるほど丁寧に手入れされている。横顔はそこらの一級芸術品と同等か、それ以上に美麗でシャープな形だ。
セックス、してしまった。行為が終わって時間がたてばたつほど、隣にいるただの友人だったはずの男を意識してしまう。そして同時に、これで関係性に大きな亀裂がもたらされないかという不安も大きくなっていった。もう会いたくないといわれてしまったらどうしよう。それは、かなりショックだ。
「花梨?……どうかしたか?」
気が付けば、自分もぼーっとして、しかも真冬のことをガン見してしまっていた。きょとんとした顔でこちらを見る真冬に、慌てて顔の前で手を振って、なんでもないと取り繕う。真冬は少し頬を染めて、春の訪れを予期するかのような暖かさをもって笑う。
「はは、顔赤くなってんぞ」
「なっ…お、お前だって!」
「えっ、マジか?こりゃ夕日のせいだ」
「今どき少女漫画でもそんな表現使わないぞ…」
「なんだよ、俺たちの好きな漫画にもあっただろ?」
すっかり調子よく笑みを浮かべる真冬は、先ほど窓の外を眺めていた時と比べると、何かに安心しているようにも見えた。もしかして、真冬も俺と同じことを考えていたのだろうか。そうだとすれば、今後の関係性は言うほど心配する必要はないかもしれない。
「なあ、花梨」
「……なんだよ、真冬」
窓の外の夕日に照らされながら、互いの視線が交差する。真冬が宝物に触れるみたいな優しい手つきで、俺の頬に手を添えた。その手の熱い体温に、少しだけ鼓動が早まる。
「俺、お前のこと諦めねえから。翔太にも怜斗さんにも渡さねえ」
いや、渡すとか渡さないとか、そもそも関心のない俺に恋愛なんてできっこない。そう言い返そうとした直後、真冬がいる方の俺の上頬に、体温が走った。真冬の細い毛先が間歩らに少し触れた。
「ま、元々諦める気なんてなかったけどな。今日ので更に覚悟決まったから、決意表明」
「……。か、勝手にしろ!」
真冬が初心だなあと茶化すように笑う。キスされた部分が思った以上に熱を持って、俺はひどく動揺した。そっぽを向かれているというのに、しばらくの間、真冬はこちらを見て微笑み続けていた。
終









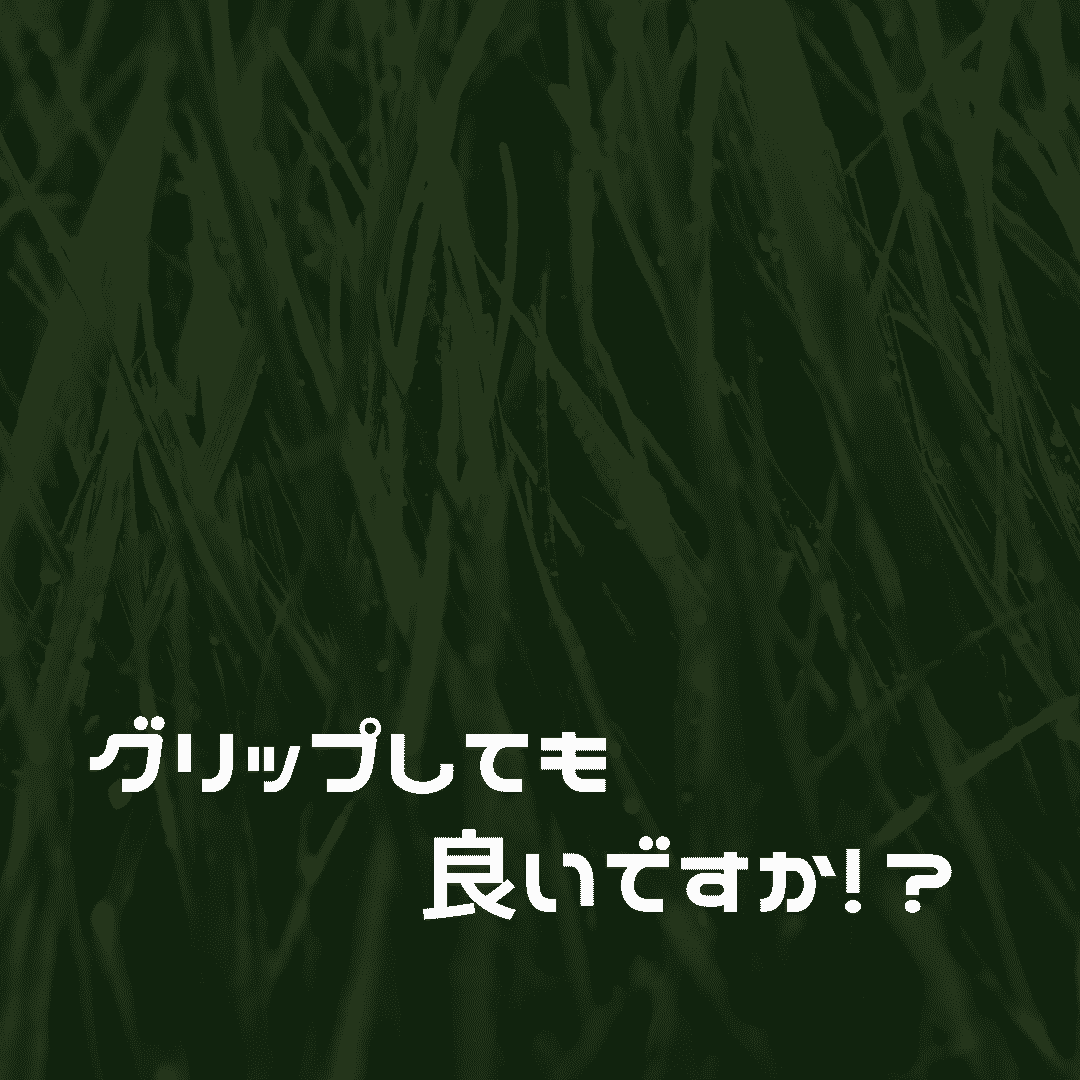

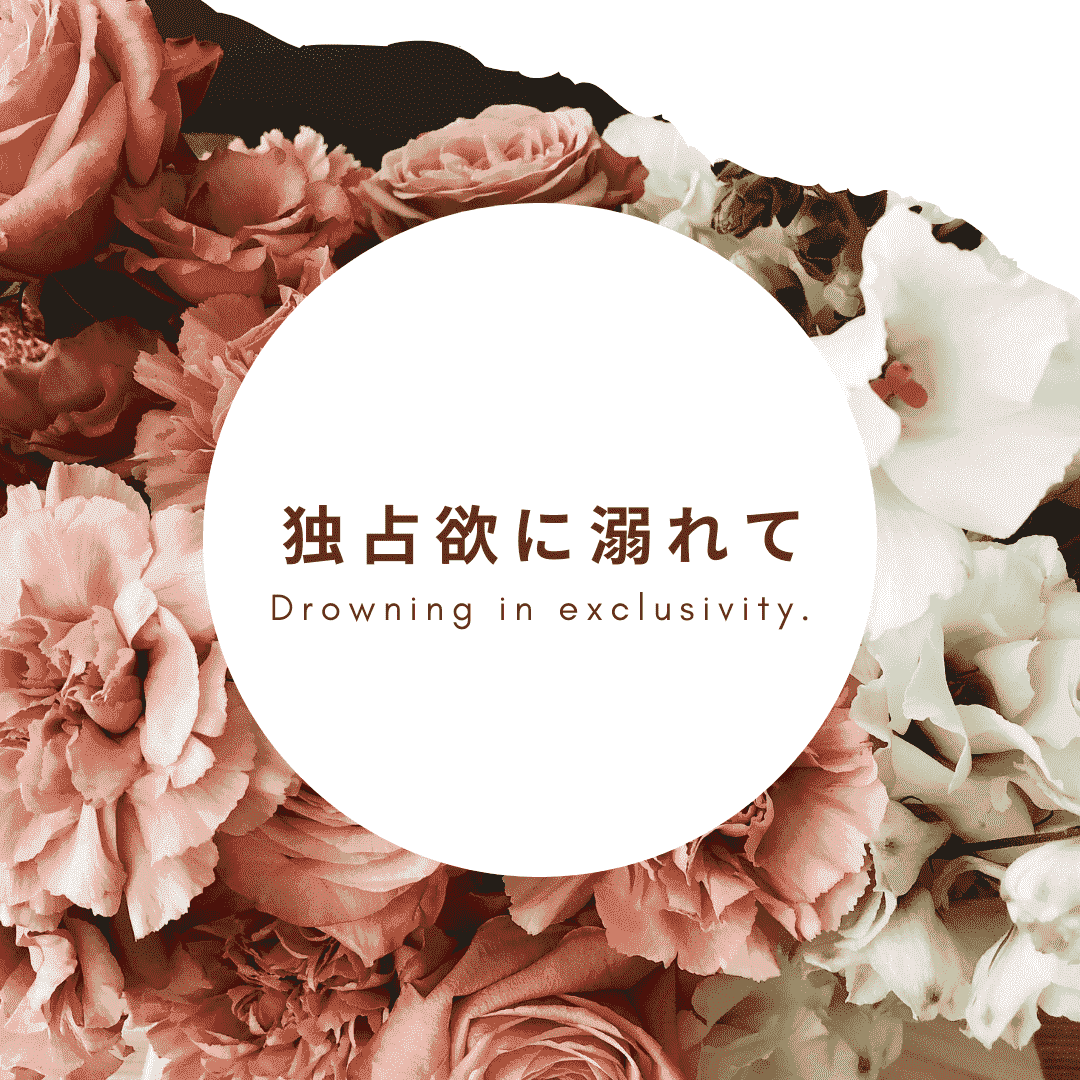
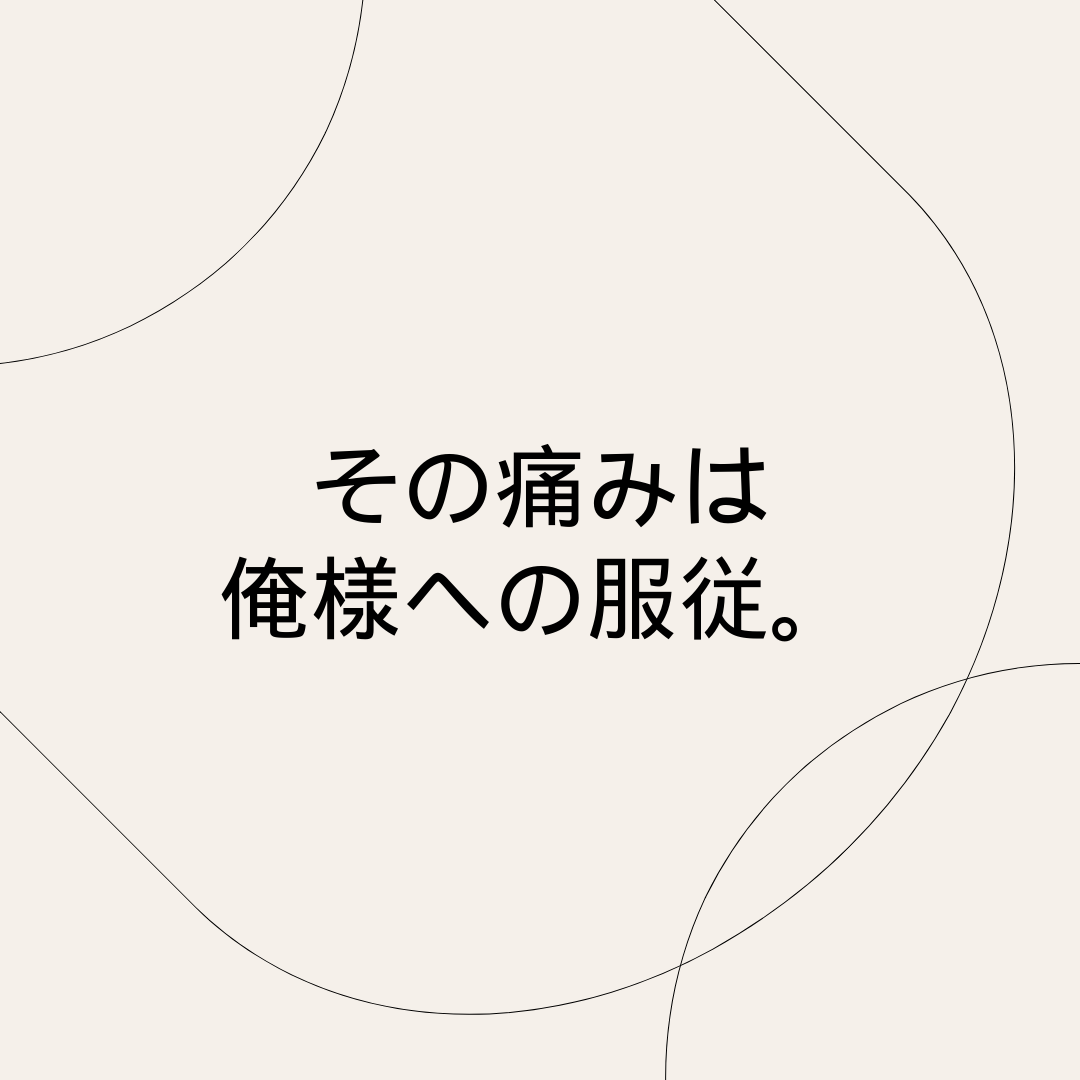
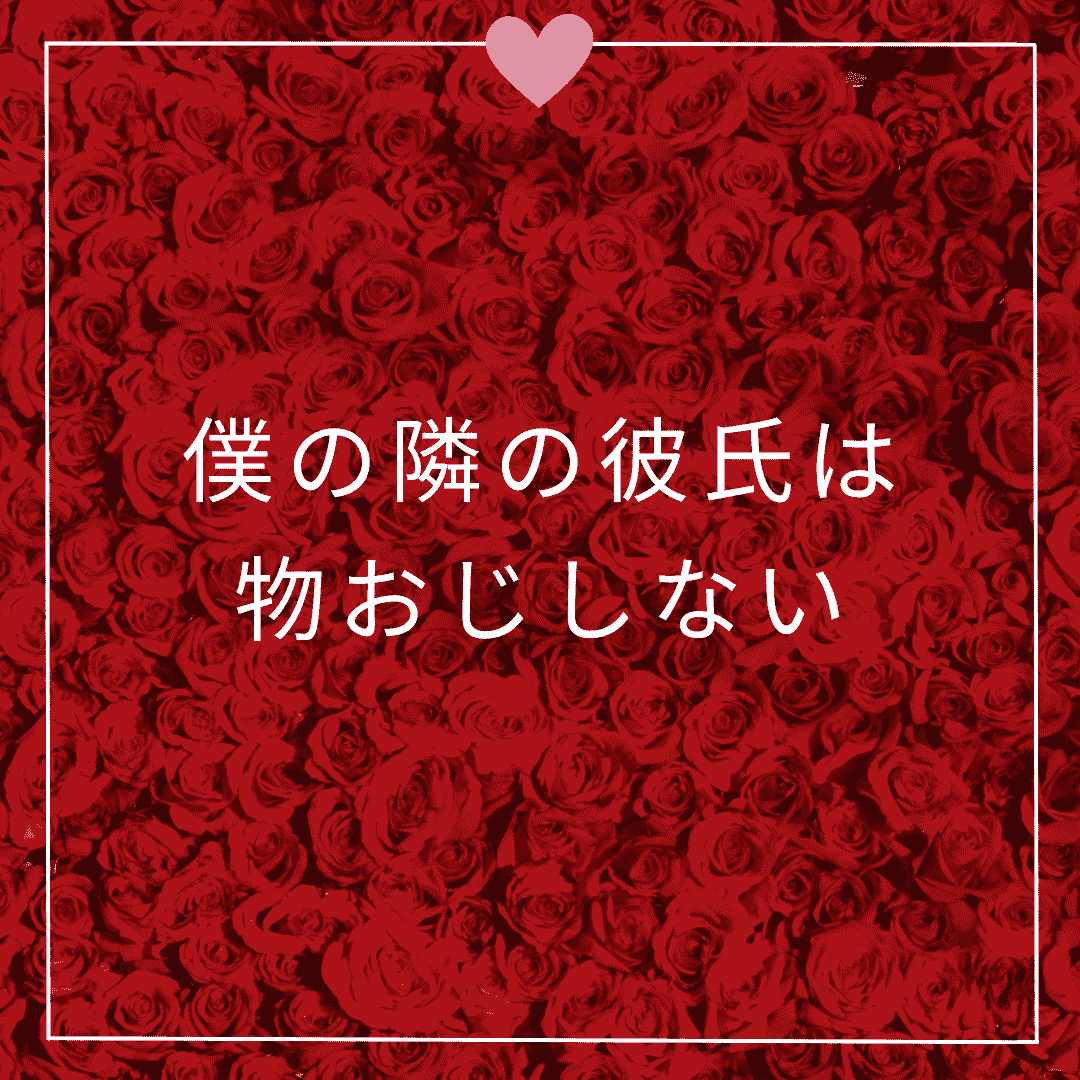
コメント