
0
再会
ぷしゅう、と音を立てながら電車のドアが開く。深まった秋の空気が流れ込んできて、思わず顔が突っ張った。
変わらない。
古ぼけた小さな駅舎も、ざらついたコンクリートも。
戻ってきた故郷は、何も変わっていなかった。
1
「前原さん、まだ頼んだ仕事終わってないの?」
「あ、はい……すいません」
「もう3年目なんだよ?いつまで新人気分でいるの」
「すいません……」
悪態をついた課長はそのまま去っていく。今日は比較的に機嫌がいいみたいで、文句はそれだけで済んだ。だけど、私の仕事は終わりそうにない。
入社3年目。
普通の人間なら、そろそろ後輩の指導を担当するころなのだろうけど、私にその役割が回ってくることはない。容量の悪い私にとって、自分の仕事だって満足にこなせるものじゃないからだ。
20時まで残業してやっと家に帰る。
お風呂に入って化粧を落として、ベッドに横たわるころにはすでに24時を回っている。
スマホに来るのは何かのお知らせばかり。友達も恋人もいない。
ふと、スマホのカメラを起動して自分の顔を映してみる。疲れ切った死んだ目の女が映っただけだ。
田舎から上京してきて就職したはいいものの、都会にもなじめず、会社にもなじめず、一人で毎晩涙をこらえている。
「何でこんなことになったんだろ」
ふとつぶやいた言葉を反芻する。
これなら、わざわざ上京する必要なんてなかった。
「最後に、お母さんのご飯食べたいな」
死ぬ前に?何で死ぬ必要があるんだろう?
人間には天啓がやってくる。
私にとって、この瞬間がそうだった。
2
翌日には会社に退職願を出していた。
2週間後に退職すると告げて、消化していなかった有休を残りに充てる。課長はすごく嫌な顔をしたのだけど、もうそんなことはどうでもいい。
アパートを引き払って帰省する準備を整え、私は新幹線に飛び乗った。
「急に帰ってくるって言うからびっくりしちゃった。こっちで暮らすの?」
「……うん、都会はあんまり合わなかったみたいで」
「そうなの。大変だったわね」
「……うん」
車で迎えに来てくれた母はよくしゃべった。これまでろくに連絡も取っていなかった娘が帰ってきたのだから積もる話があるのは当然だと思う。
「そういえば、栄太君いたじゃない?アンタがよく遊んでた」
「川原栄太?」
「そう!その栄太君!」
「どうかしたの?」
「栄太君も帰ってきてるのよ!立派になっちゃってもう!」
川原栄太は、幼馴染と言ってもいい存在だ。
私と違って活動的なタイプで、運動はできるけど勉強は不得意。ガキ大将といったほうが正確かもしれない。中学に入るころからかかわらなくなっていたのだけど……どうやら地元を飛び出していたらしい。
「今何してるの?」
「それがね!こっちで会社おこしていろいろやってるみたいなのよ!すごいわねぇ~!」
「いや、栄太じゃなくてお母さんのほうが」
「あら」
実家は何も変わっていなかった。
最後に見たときから、時間が止まっているかのように変わらない。
私の部屋も、少し埃っぽいだけで何も変わっていなかった。
数年ぶりにベッドに転がると、自然に瞼が下りてくる。
「仕事、探さないと」
つぶやくと嫌なことを思いだしそうになる。
3
再会は唐突だった。
「なつき?戻ってきてたんだ!」
「え?」
手続きのためにやってきていた就職相談所。
順番待ちをしていると、声をかけられた。
日に焼けた体格のいい男性で、スーツを着ていてもその舌の肉体が引き締まっているだろうことは想像に難くない。
はっきり言って、私の知り合いにこんな人間はいなかったような気がする。
「すいません、どちらさまでしょうか」
「わかんない?俺だよ、栄太だよ。川原栄太」
「えい……た?」
人間はこうも変わるものなのか。
目つきが悪くていまひとつパッとしなかった少年が、10年しないうちにさわやかな青年になっていた。欠点だった睨むような目つきも、今では自信に裏打ちされた鋭さになっている。
「いやー、まさかこんな場所で会うなんてな!偶然ってやつ?」
「偶然だと思う……思わせて」
「LINE教えてくれよ!飲みに行こう!」
「あの……ちょっと……」
周囲の視線が気になる。
というか、栄太の声が大きい。なんでこんなに響く声が出せるんだろう。
「わかった……教えるから」
「ありがとう!」
あれよあれよという間に、私の連絡先には栄太の名前が追加された。
その夜、早速お誘いがあった。
4
「いい店でしょ?実は俺の店だったり」
「栄太の店?どういうこと?」
「経営してるのは別だけど、この物件のオーナーが俺なの。今日は店休日だから、使わせてもらってんだよ」
「へ、へぇ……」
なんでも、栄太はここ数年必死にお金をためていたらしい。
肉体労働をはじめとして、投資もやったり、経済を学んだり、とにかく資金を作っていたそうだ。そうして、まとまったお金を手にした彼は、故郷に戻って会社をいくつかおこした。
こういうバーだったり、スポーツ体験だったり、不動産だったり。仕事を覚えることもできずに、逃げかえってきた私とは全く対照的だ。自分が情けなくなってきて、涙がこぼれそうになる。
「ま、飲もうよ」
「……うん」
お酒もつまみも栄太が作ってくれた。
粗暴なだけだった幼馴染が、いつの間にかいっぱしの大人になっている。その一方で、私の精神性は高校時代から変わっていない。人が恐ろしくて何もできない……子供のまま。
「実は、なつきのことが好きだだったんだ」
「そうなんだ……え?」
唐突に、あまりにも唐突に栄太がそんなことを言い出した。
グラスに落とした視線をあげると、その先には栄太の顔がある。
日に焼けた、男の顔が。
「中学のころから疎遠になっちゃって、そこからうまくいかなかったけど。いろいろとやったんだよ」
「そう、そうなんだ」
「……今でも、好きだ」
「……」
私は答えることができない。
何を答えたらいいのだろう。
釣り合わない?突然すぎる?意識なんてしていなかった?
迷っているうちに、キスをされた。
アルコールを含んだキスは、生臭さと薬品が最初にやってくる。だけど、そのあとにお互いの体温が伝わってきた。燃えているように熱い。
「なつき、好きだ。何年もかかったけど、運命なんだと思う」
「えい、た……?」
栄太の瞳を見ていると何も言えなくなる。
鋭さを増した瞳は、私の心を見透かしているようだ。
5
「シャワー、浴びてくるから」
「わかった。待ってる」
流されるままにタクシーに乗り、そのままホテルに来てしまった。
心臓がさっきからうるさいぐらいに鳴っている。このまま一線を超える?栄太と?そんなことしても大丈夫?だけど、結局のところそのために私は故郷に戻ってきたんじゃ……ああ、ダメだ。アルコールと興奮で訳が分からなくなってる。
頭を冷やそうと思って冷水のシャワーを浴びた。
思っていたよりも水は冷たかった。
私の体を男の手が撫でまわす。
大きくてごつごつした手は、触れるたびに電気が走るみたいに感じる。
「敏感なんだ」
「その……初めてだから、わかんない」
「大丈夫、怖くないから」
私はもう全裸になっている。
全身を人前にさらけ出すのは躊躇したのだけど、いざやってみるとそこまででもない。問題だったのは、自分の感覚が鋭くなりすぎていることだ。
「あぅ!」
「大丈夫、感じるのは悪いことじゃないから」
乳首を愛撫されて思わず声が出た。
自分の中に知らない感覚が生まれていくのがわかる。呼吸が浅くなって、体温が上昇するのがわかる。じんわりと自分の中の欲望が膨らんでいく。
栄太が欲しい。
「けっこう胸、大きくなってたんだな」
「……きらい?」
「大好きだよ」
「あんっ!」
乳首に栄太が吸いついて、そのまま吸い上げてくる。
喉の奥から甘えた声が漏れて、栄太の頭を抱きしめる。それでも力が緩むことはない。
「そ、そこ……あっ!」
私が声を漏らすと、弱点を見つけたように攻めてくる。
しばらくの間、私はその快感に浸り続けた。
「あ……やだ」
「こんなに濡れてるのに?」
目の前に来た指は、てらてらと粘液で光っていた。
「恥ずかしい……恥ずかしいよ」
「大丈夫、なつきはきれいだよ」
「あっ、ゆび……だめ……!」
反射的に出た拒否の言葉は見透かされていたようで、栄太の指は敏感になっているクリトリスや膣中を愛撫していく。出し入れされる指が卑猥な音を立てて、その音が私の頭を貫く。
「いやっ、だめっ、いやっ!」
「大丈夫、そのまま受け入れて」
「これっ……これなにっ?なにっ 」
」
「『イク』って言ってみて」
「言えない……そんなこと……ああっ!」
指の動きが激しくなった。
腹筋に力が入る。自慰で感じる感覚だけど、その何倍も強い。自分の中に大きな波が生まれていく。
「言ってごらん」
「イクっ!イクっ!いくぅぅ!」
耳元でささやかれてその通りに口が動く。もう、自分の中に生まれた快感に逆らうことができない。全身に力が入って、息もできなくなる。
「イクいくいくいくいくぅぅぅぅっ!」
嵐のようなオーガズムの中で、私は忘我の境地にいた。
口を閉じることができなくて、そこから舌がこぼれる。
体はびくびくと痙攣していて、言うことを聞いてくれない。
なのに、私の口は動く
「栄太がぁ……栄太が欲しいの」
きっと、私の顔はとろけ切っていたことだろう。
6
目を覚ました時、見慣れない場所だったからドキッとした。
だけどすぐに、昨日泊まったホテルだと思い出す。
「すごかった……なぁ」
すでに快楽の余韻は去っている。
だけど、下半身には名残のような痛みが残っていた。
隣で眠っている栄太に気付くと、その頬に触れてみる。
満足そうな彼の顔を見て、私はもうひと眠りすることにした。
そもそも、今日はしばらく歩けそうにないし。





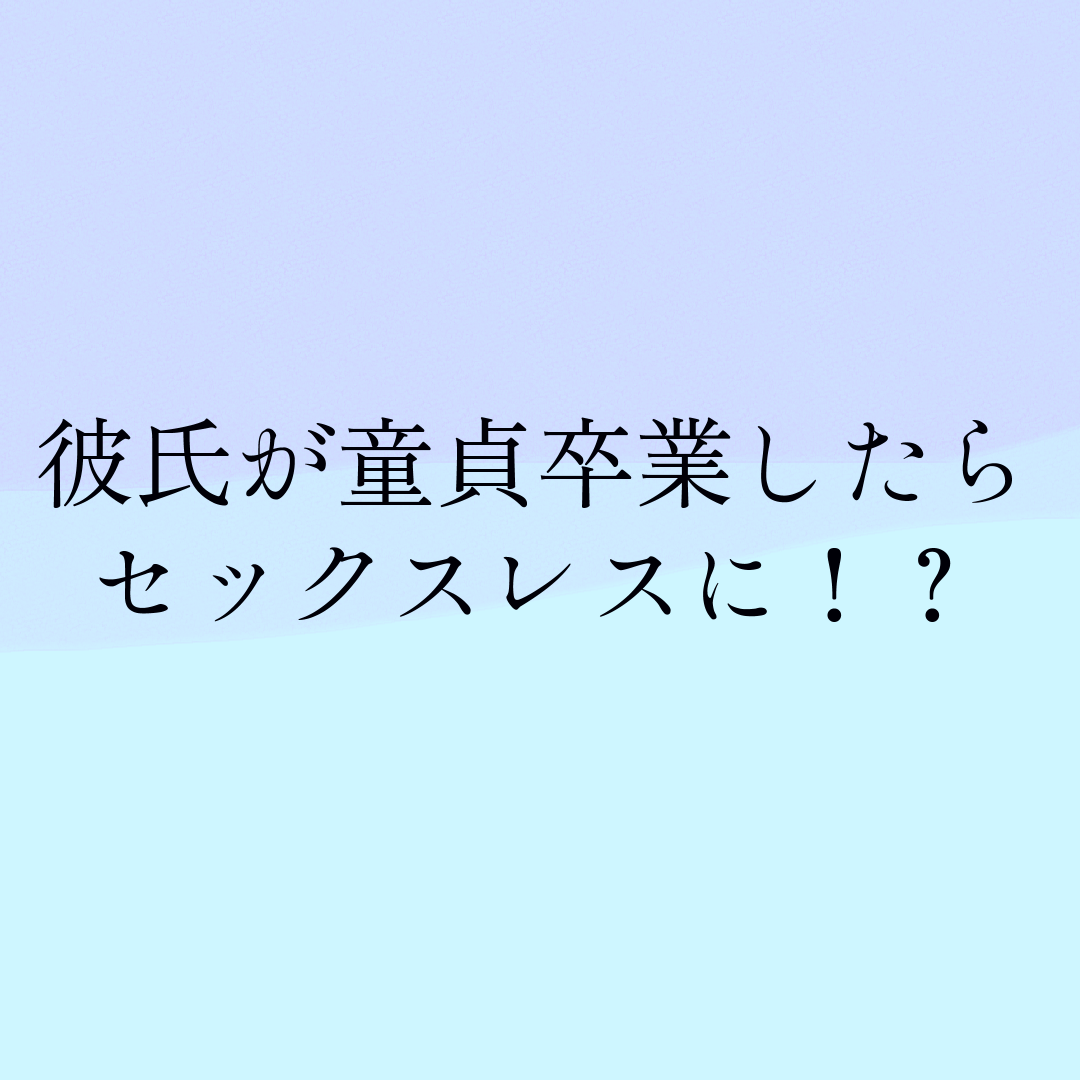







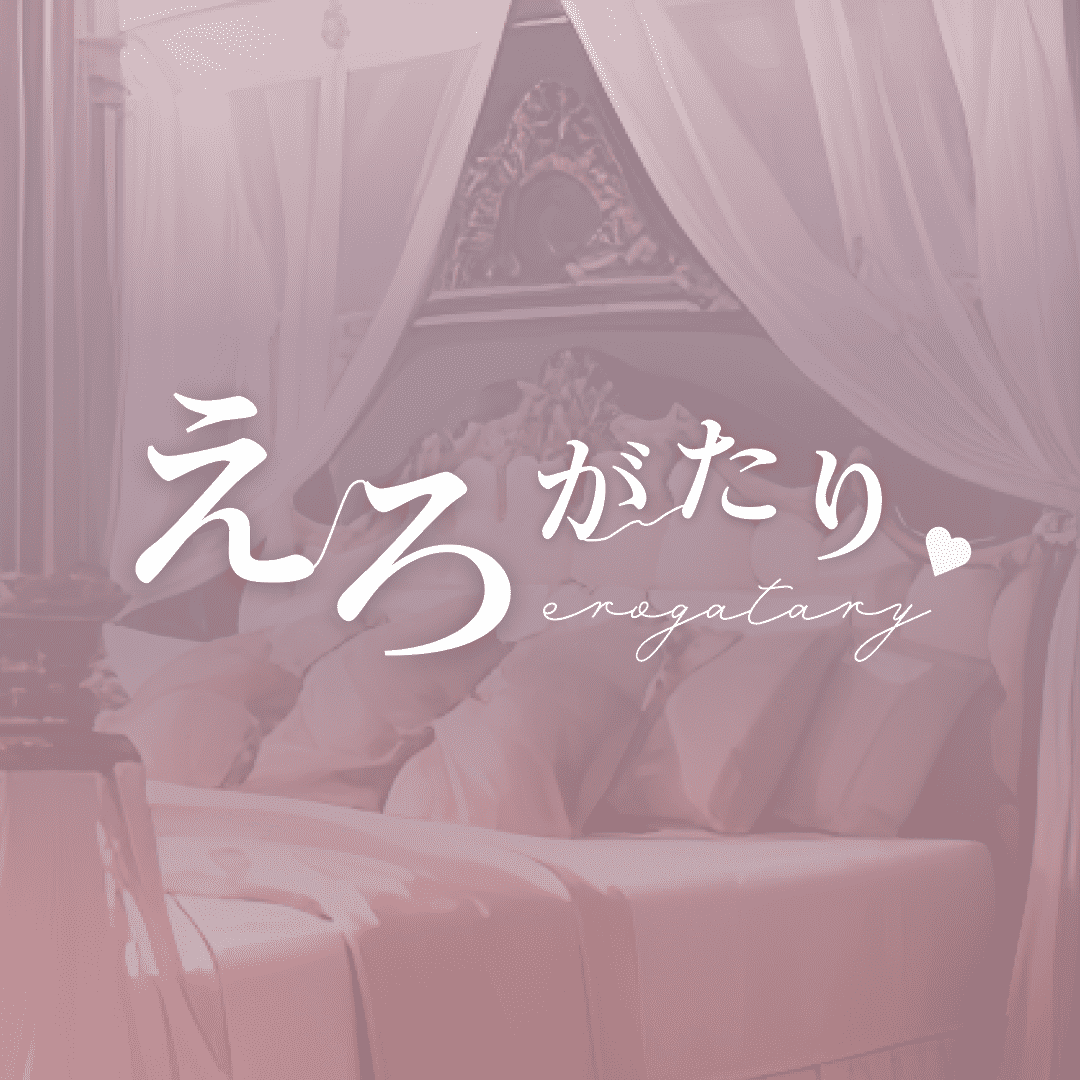
コメント