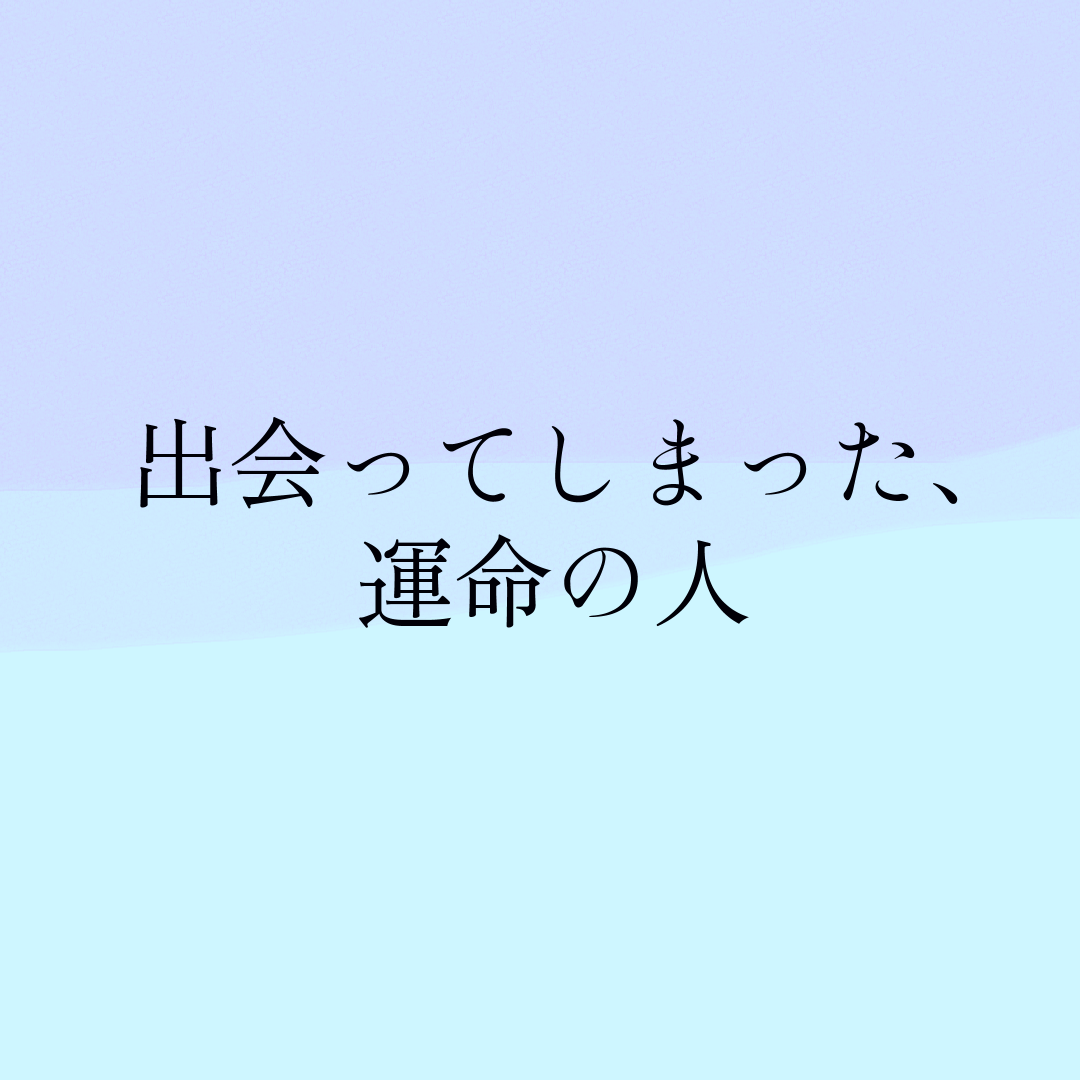
0
出会ってしまった、運命の人
「こんにちは」
「あら、正岡さん」
俺は正岡雄二。介護施設にあるベッドの開発者だ。
今日は点検日だったので、さまざまな介護施設に足を運び、ひとつひとつ丁寧にベッドをチェックした。
忙しい中で、俺を知っている入居している方々が声をかけてくる。話し相手に困っているのか、俺を見付けると手を振って会話をし続けるのだ。挨拶程度で止めたいけれど、なかなか断れずにズルズルと行ってしまう。
「柚木さん」
俺が聞き相手になっていたおばあちゃんの名前が呼ばれる。聞いたことのない凛とした声の人だ。
俺が振り向くと、そこには170センチメートルほどの身長の女性がいた。
顔はキリリとして、涼しげな目元が印象的で、唇は薄い。全体的にきつい印象を与える人だ。声と見た目から、性格も同じそうで近寄りがたい。
「あら、ルミちゃん」
柚木のおばあちゃんはそんな彼女にもニコニコと笑顔を向けている。
俺は混乱した。もしかして、俺の認識が間違っているだけでこの女性はいい人なのでは。「お仕事の邪魔したらダメでしょう」
子供の言い聞かせるように、優しい声音で言うルミと呼ばれた女性は、こちらへ頭を下げた。
「すみませんでした。お喋りが大好きで……その?」
そこでお互いに初めてだったことを思い出して、俺は挨拶をした。
「正岡と言います。施設のベッドの保守点検をしてます」
「ああ! 今日来るって言っていましたね。私は大塚です。よろしくお願いします、正岡さん」
ニコリと彼女が笑った。涼しげな目元が細められ、そこだけ青春の風が吹いているように華やかで暑かった。
「どうしたんです? 顔が真っ赤ですよ」
彼女の熱が俺に伝わったのだろう。俺の体温はグンと上昇して、汗が噴き出した。
「あはは。じゃあ、こちらの点検は終わりましたので。では……」
俺は逃げるように去った。取り残された彼女の方を振り向くと、小さく手を振って見送っていた。
俺は会社に帰って今日の報告書を書く。
とある施設になったとき、彼女のいる施設だと思い出し、想いを馳せる。
久しぶりだった、あんな感覚。思春期で女子の透けたブラジャーを見て以来の体の熱さだった。
俺は独身だ。彼女はどうなんだろう。
彼女の名前と働いている場所、職業以外、何もわかっていない。今日知り合ったのだから、当然と言えば当然だが。
俺は目を瞑り彼女の姿を思い描く。スリムな体だったな。握ったら折れてしまいそうだ。胸がないのも逆に彼女っぽくていい。脱いだら実は着痩せするタイプだったりして。
「正岡」
ポンと肩を叩かれ現実世界に帰ってきた。後ろを見たら課長がいた。
「仕事終わったなら帰れよ」
「うっす」
俺は書類を提出し、家に帰った。
次の日、会社の電話が鳴った。事務員が取り次いたのは課長だった。
何か嫌な予感がする。
「はい。はい。すぐ行きます」
「どうしたんです?」
柚木のおばあちゃんがベッドから転落したらしい。柵はしてあったのだが、柵を外したとのことだ。ベッドに異常がないかすぐに見て欲しいという。
俺が駆け付けると、柚木のおばあちゃんが腰を摩って椅子に座っていた。隣にはルミさんがいた。俺は目だけで挨拶したら、彼女は軽く頭を下げる。
「柚木さん、大丈夫?」
俺は屈んで柚木さんと目線を合わせた。
「ごめんなさいねえ」
「腰を打ったのですが、それ以外は大丈夫とお医者さんが」
ルミさんが説明をしてくれた。
「では、ベッドを見ますね」
彼女に案内されて、柚木さんの部屋に入った。
俺が点検をしている間、彼女はじっと見ていた。あの目で見られるのが凄く緊張する。俺はたらりと汗を垂らした。
「冷房、もう少し温度下げましょうか?」
「ああ、いえ。これはそういうものでは」
彼女が近づいてきて、ハンカチを俺の額に当てた。ふわりと漂うフローラルな香り。俺の鼓動がドクンと高鳴る。
彼女の顔が近くにある。彼女は無防備に俺に笑顔を向けている。俺はドキドキドキドキと心臓が速くなるのを感じた。
「あ、あの……」
「夫もそうですけど、男性って汗っかきなんですね」
俺の手が止まった。
夫? 彼女は既婚者? 頭がパニックになった。
「大変。もっと汗が出てきて……やっぱり冷房を下げた方が」
「あっ、えっと、え、あのっ、大丈夫です!」
「本当ですか?」
首を激しく縦に振った。彼女は俺に心配の目を向けている。
「……終わりました」
工具を置き、ベッドに異常がないことと、もう一度点検をした旨を伝えた。
ルミさんはほっと安心したように出ていき、施設長を呼んできた。俺は報告書をその場で渡し、辞去した。
肩を落として帰ってきた俺を見て、課長はなんだという顔をした。
「正岡。どうした辛気臭い顔して。フラれたか? 施設のおばあちゃんに! がはは」
「うー……」
疲れて、机に伏せる。そして、ルミさんのことを思い出す。
人生で初めてフられた。
俺以外帰ってしまった後、車が駐車場に入ってくるのが見えた。誰か忘れ物でもしたのだろうか。
扉がコンコンコンと叩かれた。社員ならすぐに入ってくるはずだが、その気配がない。
「どなたです?」
声をかけ、扉を開けたら、そこにはルミさんがいた。
「どうして……」
「これが忘れ物でありまして」
差し出されたのは俺の工具だった。確かに施設で使ったままにしてしまったような。
「ありがとうございます。あの、中で麦茶でも飲みませんか?」
「いいんですか?」
「ええ、こんな狭い場所ですが、どうぞ」
彼女を中に入れたのは半分下心を持ってのことだ。彼女は気づいているのだろうか。
ルミさんは落ち着いた様子で、冷たい麦茶を飲んでいる。こくりこくりと喉が動くのが艶めかしい。
麦茶が唇の端についたのか、ペロリと赤い舌が液体を舐める。なんて色気だ。くらくらする。
「あついですか?」
「え?」
俺は急いで額に手を当て、汗の確認をした。しかし、おでこはサラサラだ。
「ふふ、顔が真っ赤」
彼女の様子が妖しい。俺はごくりと唾を飲み込んだ。
「ほら、あついんでしょう?」
彼女に言われると確かに体が熱い。彼女が「あつい」と発する度に「確かにそうかも」と思う自分がいて、体も反応する。
彼女が徐々に近づいてくる。息がかかるほど彼女の顔が近づく。背の高い彼女は背伸びをしないでも、俺の顔をじっくりと見ることができるのだ。
「ねえ、正岡さん」
彼女の清涼な息が鼻に当たって、大きく吸い込むと、今度は逆に熱い息を彼女に吐き出す。
「あつい……」
彼女の手が俺の息子に触れた。
「え、ちょっと、」
流石に焦る俺は彼女の手を取った。折れてしまいそうなほど細い腕。俺は急いで腕を放した。
「すみません!」
「いいの。ここと同じく元気な人ですね」
自分の下を見たら、三角印のテントを張っていた。彼女はそのトップを撫でるように触れた。
「うっ」
ソコを俺以外が触れることは風俗に行った一年前きりだ。俺のムスコがビンビンと手に反応する。
「くっ、やめてくれ……本気で」
「戻れなくなると?」
彼女は楽しそうに笑った。
「いいじゃないですか。私も溜まってて」
顔を近づけてきて、舌を入れてきた。ぬるりとした感触は彼女には似合わないと思い、舌を拒絶した。しかし、蛇のように絡みついてくる舌に段々とその気になってくる。
ちゅっぷりゅぱ。
リップ音と舌を絡める音が夜の会社に響き渡る。そうだ、ここは会社だ。
「駄目。意識逸らしちゃ」
彼女はまた、俺のソコに手を持っていき一撫ですると、作業着のファスナーを下ろした。
プルンと現れる俺のムスコ。コイツはとても素直に彼女に従っている。
「入れて欲しいの」
「でも、ルミさんはまだ体の準備が……」
「もう準備万端」
彼女はパンツを下ろし、ショーツ姿になる。俺の手を取って、彼女の秘密の花園へと誘う。
くちゅ。
水音がした。はっきりと彼女は濡れていますと言っているかのように。
彼女が壁に手をついて、こちらを見る。肉の薄いお尻がこちらを向いている。そして、しどしどに濡れたもう用をなしていないショーツも。
俺はゆっくりと花に近づき、ショーツをずらした。そこにはくぷりと愛液を噴き出す蜜唾があった。上手そうな濃いピンク色をしていて、今か今かとオレを待っている。
「入れますよ」
「ええ」
ズッ。
「あっ」
「ふっ」
彼女がのけ反り、俺は彼女の呼吸に合わせて、奥へ奥へと入れていった。彼女のナカはとろとろで締め付けが良い。上等と言えた。
「ねえ、もっと動いてぇ……」
彼女は乱れると、媚びた声を出せるのかとまた新たな彼女を発見した。
「お望み通り」
俺は彼女の細い腰を両手で持つと、パンッパンと腰を打ち付けた。
「ふっ、あんっ! はあん!」
彼女が額に汗を浮かべながら喘ぐ。俺はふっふっと鼻息を荒くして、一心不乱に腰を動かした。
「イ、イっちゃううううう」
「これで最後だ!」
パンッ!
強くグリと押し込み、彼女のナカが震える。
「あああああああああ!」
体をガクガクとさせ、イった彼女はどんな彼女よりも美しかった。
「大丈夫ですか?」
俺のはまだパンパンに起立したままだったが、彼女の体の方が心配だった。
「ええ。それよりも正岡さんの方が……」
「コレは一人で処理しますので」
「いいえ、私が始めたことです。奉仕させてください」
俺は天にも上がるような心地で彼女の施しを受けた。
「何故、今日は俺とシてくれたんですか?」
「それは内緒です」
冷たい麦茶を飲みながら、彼女は笑った。そして、飲み終えると、丁寧にグラスを洗って帰って行った。
次の点検日にあの施設へ行ったらもうルミさんはいなかった。
「あの、ルミさんってどうされたんですか?」
「ルミさん? ああ、彼女ね。彼女は夫の転勤でついて行っちゃったわ」
ルミは柚木のおばあちゃんの猫の名前らしい。本名ではなかったのか。名字を名乗ったような気がしたが、ルミで覚えていた俺は彼女の名前を一切知らないまま関係が終わった。
その夜は酒に弱いのに、酒をたらふく飲んだ。翌日、二日酔いで初めて欠勤をした。
完





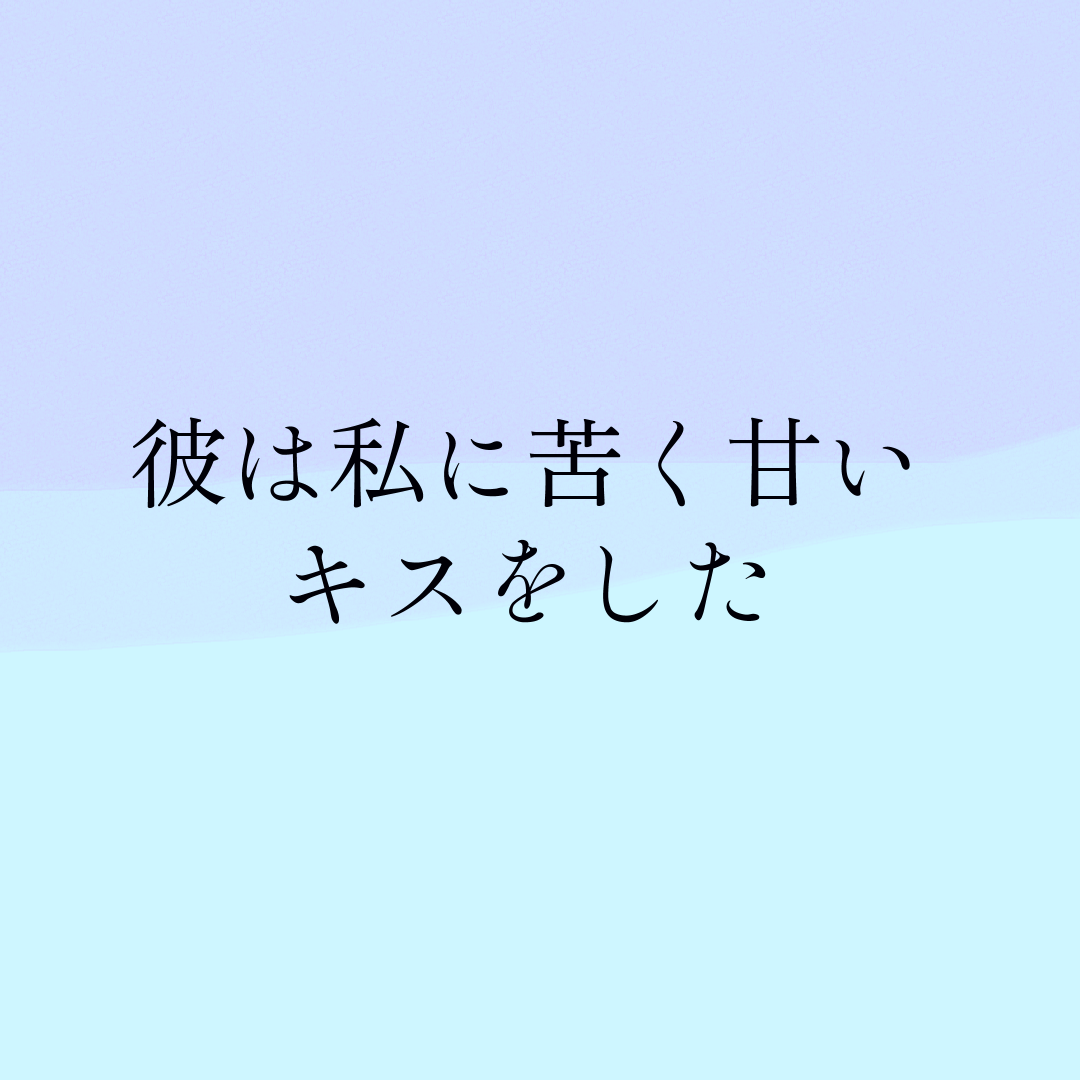
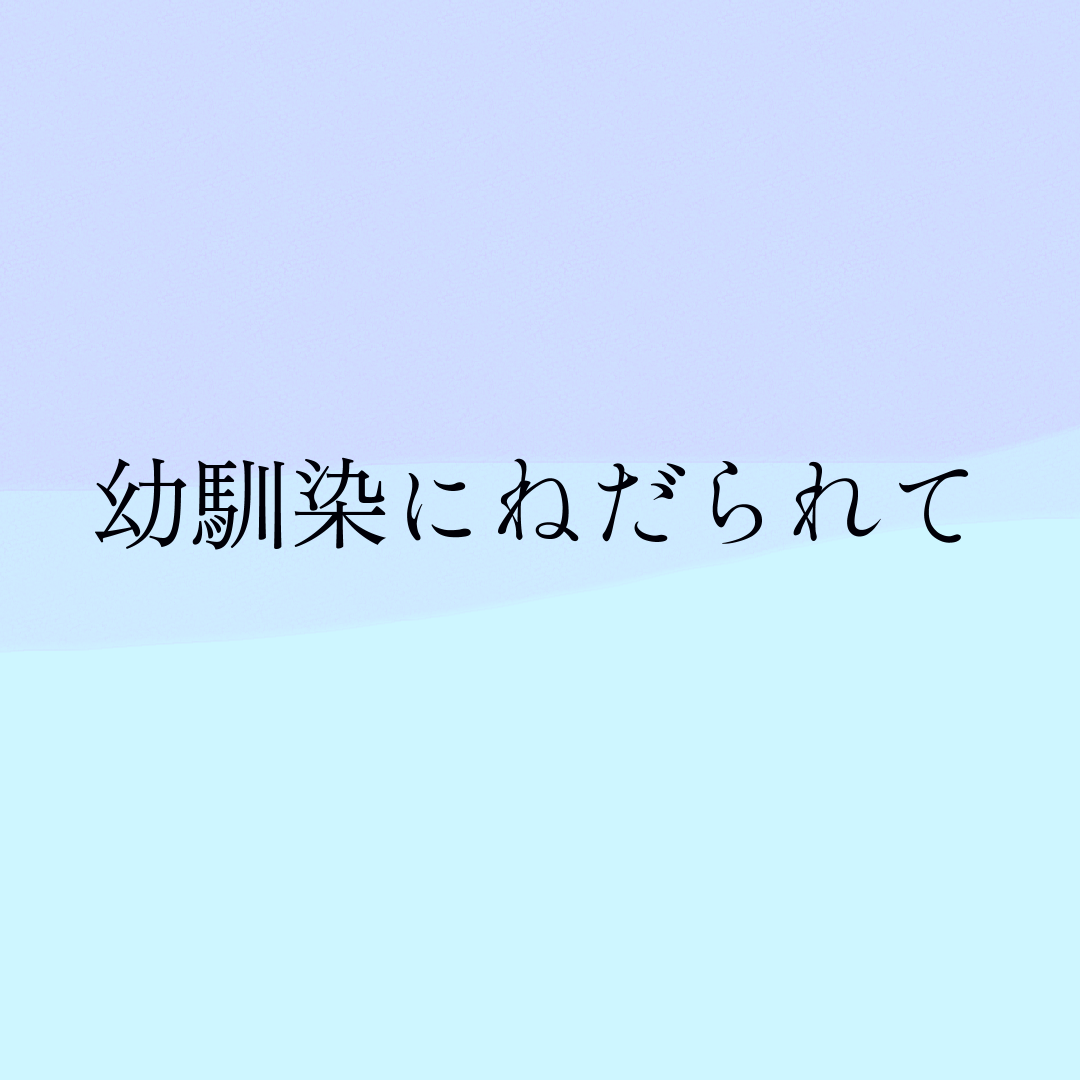
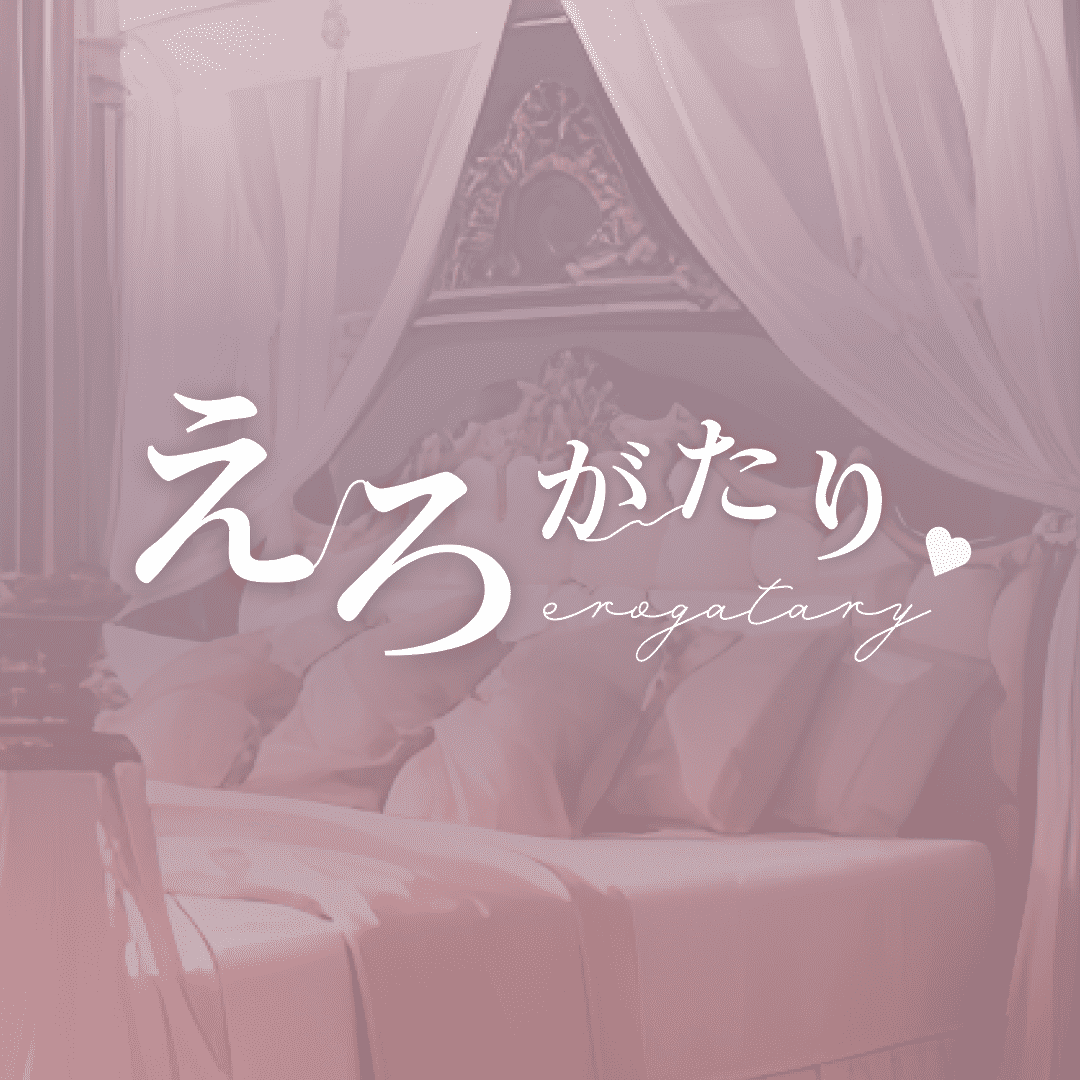
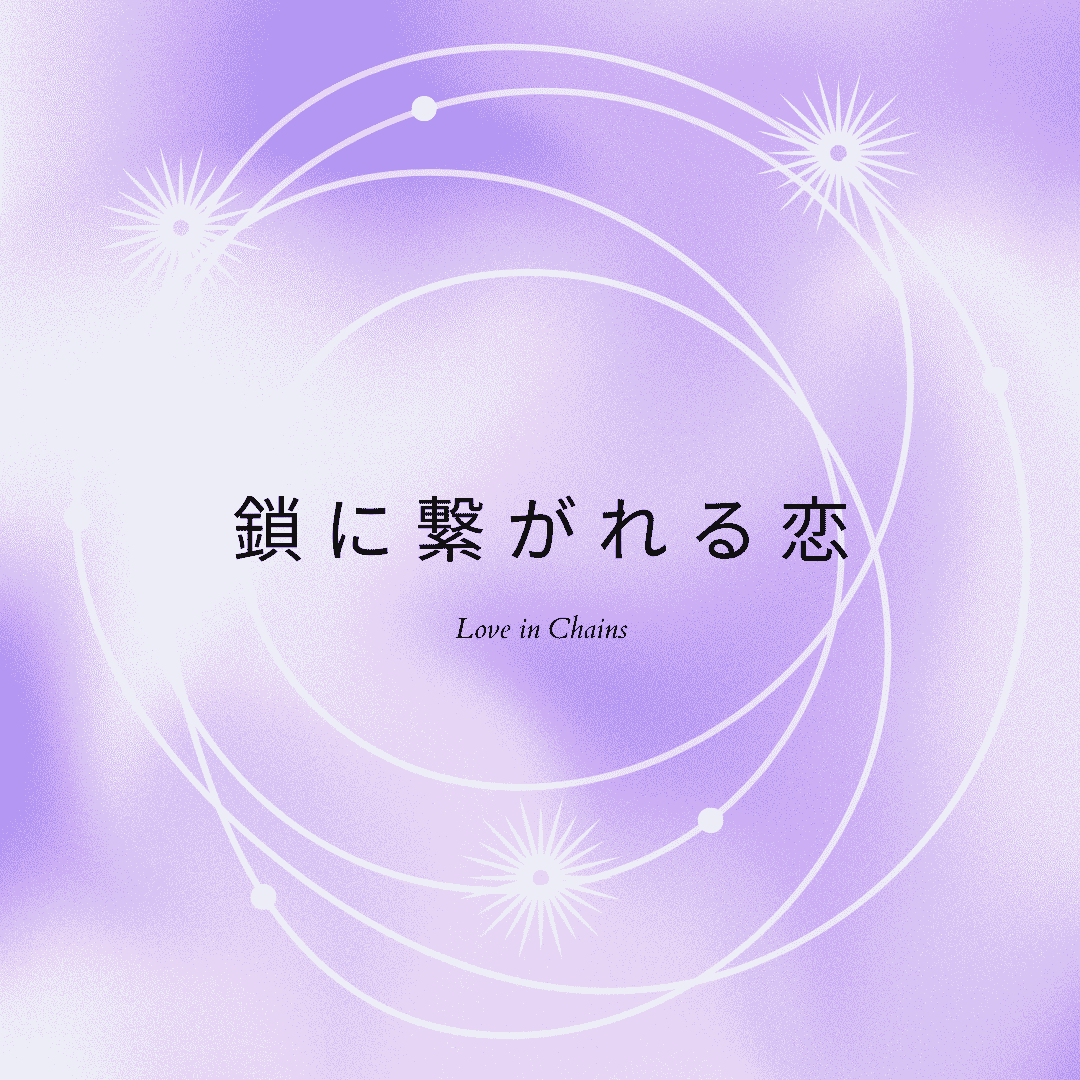




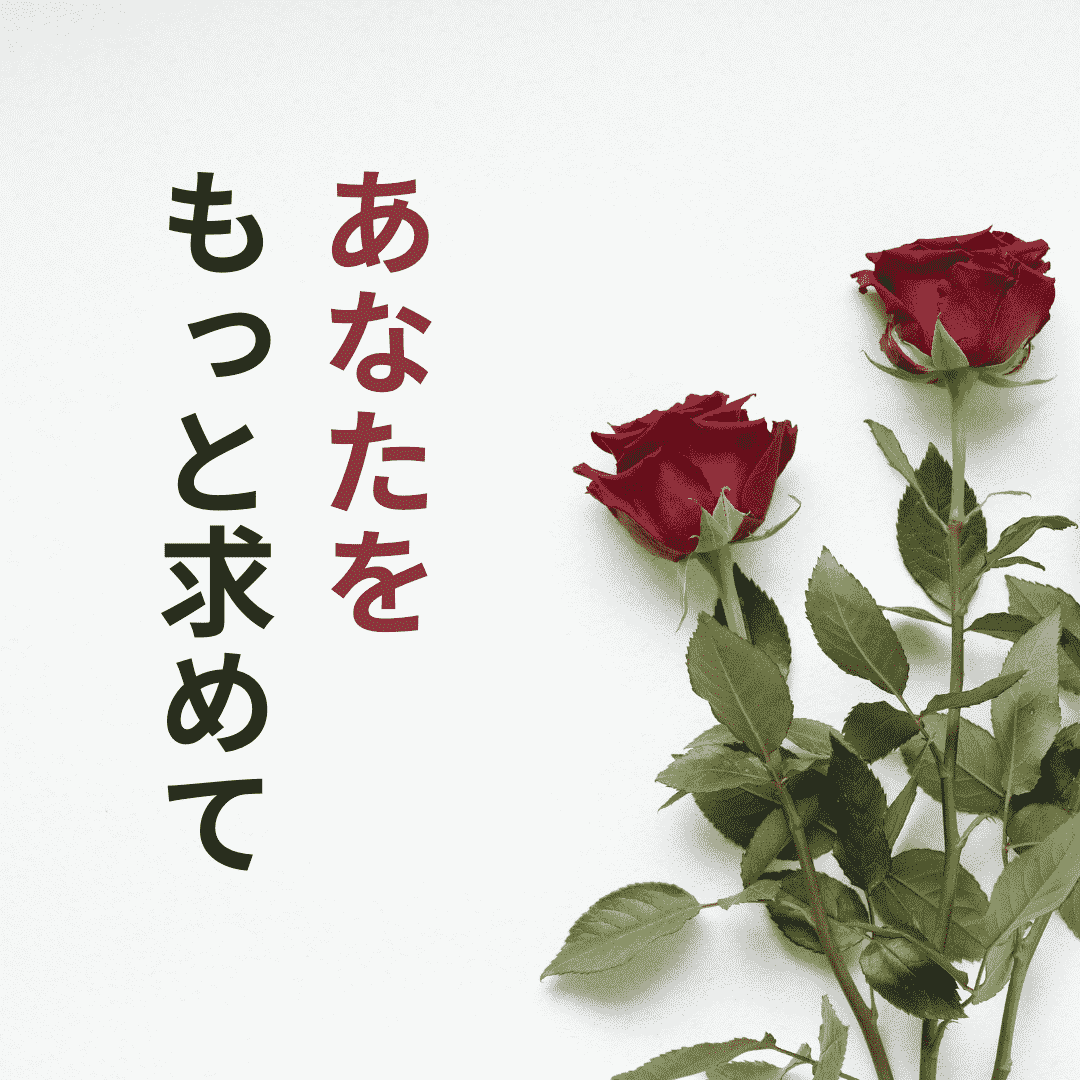

コメント