
0
綻び
私は真田 紗季(さなだ さき)。
夫の克弥(かつや)と結婚して10年。
残念ながら子供はいない。
二人ともそのことに関しては納得して生活している。
これはほんとに可能性の話だけど、原因はおそらく—克弥にある。
だって私は一度検査を受けているから。
結果は『問題ない』というものだった。
克弥は
『そんなもの検査する必要ない。授かりものなんだから…』
と言って検査していない。
だから私ももう子供はあきらめている。
ただ義実家からの私への風当たりは強い。
克弥はいたって普通の会社員で、妊活に関して理解がないだけで私たちの夫婦仲は悪いわけではなかった。
家事も手伝ってくれるし私の外出も特に咎めたりしない。
交友関係にもパートにも口を出すことはなく、とても穏やかな夫との生活に不満はなかった。
その代わり義実家からの”孫要請”に対して盾になってくれることもなく、『我関せず』というスタンス。
さらに30代も後半に差し掛かり結婚生活も長くなってきて、マンネリというか女として愛されているかどうかは少し疑問に感じることが多いのも否めない。
「ただいま」
「あ、おかえりなさい」
「ほら、手紙入ってたぞ」
仕事から帰ってきた克弥がテーブルに私宛のはがきを置く。
『同窓会のお知らせ』
そう書かれた往復はがきだった。
「同窓会かぁ」
懐かしい友達の顔が浮かぶ。
高校の同窓会は何年ぶりだろう?
仲のいい子たちとは個人的に会ったりするけど、全員集まる同窓会は久しぶりかも。
「同窓会?」
部屋着に着替えた克弥がテーブルにつきながら尋ねてくる。
「うん 高校の」
「へぇ」
「久しぶりだし行ってみようかなぁ?」
「いいんじゃない?行っておいでよ」
ビールを開けてテレビをつけながらそう返す克弥。
賛成してくれてはいる。
克弥の態度は何となく気に入らないけど反対されないんだし、人の同窓会なんて興味ないのもわかる。
もやもやした気持ちを抑えて
「うん。じゃ行くことにしよ」
とテレビを見て笑っている克弥に笑顔を向けて言った。
ベットに入ると克弥が話しかけてきた。
「同窓会いつ?」
「来月の末だよ」
「そう」
「地元に戻るから泊りになるけどいい?」
「いいんじゃない。ホテルに泊まるの?」
私の両親は高齢者向けマンションを購入して老後を謳歌している。
事実上実家はない。
「そうだね、ビジネスホテルが近くにあるからそこに泊まろうかな?」
「そっか、もしのご両親のとこ行くようならよろしく言っといてね」
めったに会いに行かないけど、きちんとうちの親のことも気にかけてくれてる。
よくできた旦那なんだけどなぁ。
すぐに寝息が聞こえてくる。
あぁこの人と最後にシタのっていつだっけ?
結婚しているからもちろん行為はこの人としかしていない。
だとしたら私—。この人がしてくれなかったら女として求められることってないのかな?
そんな漠然とした不安が押し寄せてくる。
そんな不安を消すように頭を振って私も目を閉じた。
特に他意はない。
でも何となく同窓会までに少しでも見た目を磨きたいとういうのは女の性(さが)だと思う。
昔誰かが言っていた。
『同窓会—。男は女に見られることを意識して、女は女と張り合うために磨きをかける』
確かにその通りかも。
何となく少しでも友達より若く見られたいしきれいでいたい。
それは男子の目が気になるというより、”女の見栄”なんだろう。
克弥は『40手前になると同窓会で気になるのは“役職”だ』と言っていた。
30代後半の私たちは男女ともに同窓会はステータスの披露の場になるのは仕方ないのかもしれない。
そう思いながら念入りにスキンケアして着ていく服を選ぶのだった。
「じゃ 行ってくるね」
同窓会当日の朝。
私は克弥に見送られてマンションを出た。
新幹線に乗って1時間半。
駅に着くととりあえずホテルにチェックイン。
部屋に入って荷物を置いた瞬間携帯が鳴る。
『もしもし紗季?もう着いた?』
「奈々子。着いたよ」
親友の奈々子だ。
奈々子とはちょくちょくあっている。
彼女は実家に泊まるらしい。
誘われたけど奈々子のお兄さん夫婦も同居しているということなのでご遠慮させていただいた。
『まだ時間あるからそっち行っていい?』
やっぱりいづらいのかな?(笑)
「いいよ、狭いけどおいでよ」
電話を切って10分もしないうちに奈々子は部屋にやってきた。
「久しぶり。って言っても2か月ぶりか」
「だね」
相変わらず派手な感じなのに全く嫌味じゃない奈々子の若さがうらやましい。
小学生の子供が2人もいるとは思えないスタイルとパワフルさに毎度圧倒される。
「まだ着替えてないの?」
「うん。今着いたばっかだから」
いくつになっても同級生と会うとその当時に戻れるのは不思議。
すぐに旦那やパート先、義実家のことも全部忘れてしまう。
「あ、そう言えば」
しばらく話が盛り上がったところで奈々子が思い出したように言う。
「三木くんくるらしいよ」
三木君…。
その名前に私の心臓が少し騒ぐ。
三木 尚樹(みき なおき)。
私は彼と高校時代付き合っていた。
若かった私たちは遠距離恋愛には耐えきれず、卒業してから徐々に溝が広がり別れを選ぶことになった。
「私はお似合いだと思ったのになぁ」
「もう昔の話よ。三木君だってもうお父さんじゃない」
そう言って笑い飛ばす。
「うーんそうなんだけど…」
奈々子にしては珍しく歯切れが悪い。
彼は父親の知り合いかなんかのお嬢さんと見合いして結婚したと聞いている。
今までタイミングが合わなくて同窓会でもあったことがない。
興味はある。
どんな大人になったんだろう。
「お互いもういいおじさんおばさんだしね」
自分に言い聞かせるようにそう呟く。
「紗季は全然変わらないじゃん」
「そう?ありがとう。でも奈々子のそのパワフルさもずっと変わらないよね」
お互いに笑いあう。
「三木君もこの前ちょっと会ったけど、あんまり変わってなかったよ」
奈々子の言葉にどうしても心がざわついてしまう。
とても真摯で優しくて、それでいてひっぱってくれる強さもあって…。
制服の彼の姿が浮かぶ。
「まぁ今日会ったら話せるかもね」
「もう!」
ちょっといたずらに笑う奈々子にこの気持ちのざわめきを知られないように私は笑った。
「ななこぉーさき―久しぶりー」
同窓会の会場につくと懐かしい面々に次々声をかけられた。
地元を離れている私たちは積もる話もたくさんある。
立食形式だけどどれもおいしい食事は、友達と食べるというエッセンスもあってついつい箸が進んでしまう。
「よう」
奈々子と食事を楽しんでいたら突然声をかけられて驚く。
「…!三木君」
私より先に奈々子が声を出す。
「相変わらずお前らよく食うなぁ」
そう言って優しい笑顔を見せる三木君に思わず目を奪われてしまう。
「違うよ!私達が食べてるときに限って三木君が見てるってだけ」
奈々子が反撃。
「え?そうなの?」
なんて楽しそうに笑う三木君は本当に高校生のままのように思えた。
「紗季…。元気だった?」
「う…うん。み、三木君も元気?」
彼の変わらないまなざしに返事がぎこちなくなってしまう。
「うん」
短い会話だけで少し—、ほんとにわずかな時間見つめあった。
「おうっ。紗季ちゃんじゃん!マジ久しぶり」
すぐに三木君の友達の洋治君が私に話しかけてきて我に返される。
しばらく4人で話していたのに、奈々子と洋治君はいつの間にかみんなの中心に連れていかれている。
「あいつら変わんねぇな」
そんな奈々子たちを、私と三木君は少し離れたところからほほえましく見つめてしまう。
「そうだね。あの二人の周りっていつも騒がしかったよね」
「紗季も全然変わってないよ」
まっすぐ見つめられてドキッとする。
「ど、どういう意味?大人になれてないってこと?」
わざと怒ったふりをする。
「はは…。違うよあの時のまま…。」
そう言って目を細めて私を見る。
「もう、私はおばさんだよ」
照れ隠しに笑って見せる。
「それ言ったら俺もおじさんだな」
「ううん!三木君は…」
歳を重ねてさらに素敵に見える。
世間でいうところの”イケおじ”だろう。
そう思ったけど言えるはずもなく、
「立派なお父さんなんじゃない?」
そう付け加えた。
「はは…お父さんか…」
なぜか三木君はさみしそうに視線を落とした。
「紗季、三木君ビンゴやるってぇ」
私たちの沈黙の間に奈々子の声が響いた。
「いいねぇ。俺こういうの強いんだよな」
「ビンゴ強いってなんだよ!」
三木君の発言に誰かが突っ込む。
そしてみんなに笑いが起きる。
「行こう紗季」
そう言って私の肩にそっと手を添えた三木君。
変わらない感覚。忘れられない感触に何か止められない衝動が沸き上がってしまう。
少し近づいた三木君からあのころと変わらないやわらかい香りがした。
いけないいけない。
私たちはもうお互いの人生を歩んでいる。
そう言い聞かせてみんなの輪に混ざった。
二次会、三次会を終えたころにはみんな高校生に戻っていた。
でもそろそろ魔法がとける時間。
それぞれ別れを告げてまた次回を約束する。
「じゃあまた連絡するね」
奈々子と別れて私もホテルに向かう。
「紗季!」
ふいに呼び止められて振り向くと
「三木君…」
彼が走って私に向かってきた。
「はぁはぁ、この年で走るのしんど」
と言って笑う。
「大丈夫?どうしたの?」
そう言って彼の肩に手を置く。
するとその手をがしっ!と握られて、
「少し話したいんだ。いい?」
とても真剣な顔でそう言ってきた。
「…う、うん」
圧倒されてうなずいてしまう。
すると三木君は顔をほころばせた。
どうやら同じビジホに泊まっているらしい。
そう分かって三木君の部屋にお邪魔することになった。
コンビニでお酒とソフトドリンクなんかを買って彼の部屋に向かう。
よくよく考えたら、既婚男性の部屋に既婚女性が行くなんてありえないのに、お酒のせいで麻痺してたのかそれとも高校生に完全に戻ってしまっていたのか…。
部屋に入ってからも、『○○君はだいぶおじさんだった』とか『○○さんは別人になってた』
とか同級生の話題で盛り上がった。
しばらくすると三木君が真顔で聞いてきた。
「そう言えば紗季は子供は?」
「…うちは…いないし、、もう…」
「あ、なんかごめん」
「いいの。三木君ちはお子さんいくつ?」
空気を壊したくなくて明るく聞いてみる。
「小6の男の子だよ」
「へぇじゃあすぐ中学生だね」
「うん」
「三木君奥さんもきれいな人だって聞いたよ。お子さんもイケメンかな?」
と笑ったのに、三木君は沈んだ表情をしている。
「三木君…?」
「ごめん…」
「…」
三木君はうつむいていた顔をあげて私を悲しそうな瞳で見た。
つぎの瞬間—
「!!」
ギュっと三木君に抱きしめられる。
「み、三木君!?」
「ごめん、ちょっとだけ…」
そう言われてそのまま三木君の背中にそっと手を回してみた。
「あぁ、紗季の感触…紗季のにおい…。落ち着くなぁ」
「…何かあったの?」
「…いや」
そう言ってほほ笑む三木君の顔はとても悲痛な感じだった。
「紗季は…」
「ん?」
「紗季は今…幸せ?」
絞り出したようにそう聞かれて胸がズキンとなる。
幸せかと聞かれたらそれはそうだろう。
子供はいないけど夫婦間に大きな問題はないしパートも楽しい。
お金にも困ってないし友だちもいる。
でも…欲を言えばいろいろ不満はある。
女としての幸せって考えたらどうなのかはわからない。
「ごめん、変なこと聞いて」
何も答えられない私に三木君は謝って私から離れた。
しばらくの沈黙…。
「…俺おやじの仕事関係の人と結婚したんだ」
突然三木君がポツリと語りだす。
「こんな時代にさ会社同士のつながりを強くするためって」
ふっと笑う。
「実際俺らの結婚のおかげでこの業界でうちの会社も嫁の家の会社も勝ち上がってこれたんだけど、嫁は好きな奴いたみたいでなんかかわいそうだなって…」
まるでドラマか映画みたいな話にちょっと驚いてしまう。
「だから嫁も大事にしたし、子供だってむちゃくちゃかわいくて…」
「そうなんだ…」
「でもなんか最近わかんなくなってきちゃって…」
三木君は頭を抱える。
「子供がかわいいことは変わらないんだけど、俺と嫁の関係はうまく言えないけどお互い演じてるっていうか…」
三木君の声が震えてる。
「若かった時は俺も嫁もそれしかなかったのかもしれないけど、今の俺は嫁と嫁が好きなやつを引きはがしてまで俺と結婚すべきだったのか?もっとほかにいい方法があったんじゃないか?嫁はほんとに幸せなのか?いろいろ考えてぐちゃぐちゃで…」
私は思わず三木君に寄り添ってしまう。
「そんなときいつも思い出すんだ。紗季のこと」
「三木君…」
「それはきれいな思い出だからかもしれない、そう思って今回同窓会に出てみた。
そんで紗季に会ったら思ったんだ。俺…紗季のことが今でも…」
いけない!
それ以上言わせたらいけない。
そう思ったらとっさに—。
「!!」
三木君の唇を自分のでふさいでいた。
「…紗季…」
唇が離れた瞬間三木君が驚いた顔でこっちを見ているのがわかった。
「…あ、ご、ごめん…なさい」
そう言ったけどそれは遅かった。
ガバっ!
次の瞬間三木君に押し倒された。
「み、三木君!」
「紗季!ごめん俺」
そう言いながら私に馬乗りになって急(せ)くように自分の服を脱ぎ始めた。
高校時代には見たことのない服の下にある三木君の胸板に、頭とは裏腹に気持ちは高鳴っているのがわかる。
「紗季も…」
自分の服を脱ぎ去るとすぐに私のシャツのボタンに手をかける。
どうしよう。
いい年して恥ずかしくなる。
旦那の前に付き合った人もいる。
確かにその時も旦那の時も初めてはやっぱり恥ずかしかったし緊張した。
でもそんなんじゃない。
もっともっとなんか違う気持ちが沸き上がってくる。
三木君とはずっとプラトニックな関係だったから?
でも私は何となく思う。
私はずっとずっと三木君とこうなりたかった。
他の誰でもない。
三木君を求めていたんだ。
そんなことを考えているうちに私の肌は三木君の視線の前にさらされていた。
「なんか、すげー興奮する」
三木君は下着一枚になった私を見て本当に初めてセックスするような高校生の表情をしていた。
「う、うれしい」
「え?」
「三木君が私を見てその…興奮してくれて…」
言ってしまってから恥ずかしくて顔が熱くなる。
「きれいだよ」
そう言ってから三木君は私にキスをしてくれた。
なんとも官能的でとろけそうな感覚に簡単に堕ちてしまう。
見た目から言ったらきっと克弥のほうが世間一般のイケメンだし、高身長で筋肉もついているのかもしれない。
でも間違いなく私の体は三木君とのほうがいい反応をしている。
その理由はわからない。
この背徳的な行為に興奮しているのか?
それとも高校生に戻っている感覚に興奮しているのか?
ううん。どっちでもない。
私は確実に目の前にいる三木君に吸い寄せられている。
運命さえ感じている。
「あっ…」
下着越しに胸に軽く触れられただけで下腹部がじわっと熱くなる。
「ヤバ、俺こんな反応したの初めてかも」
そう言って自分の下半身を私に押し付けてくる三木君。
確かに恐ろしいほど張り詰めて熱くなっているのがわかる。
すぐにズボンを脱いでパンツも脱ぎ去る。
そこに現れたソレに息をのむ。
私の表情を見て三木君はおかしそうに笑って
「俺のそんなおおきい?」
と聞いてくる。
「もう!そんなこと聞かないでよ!」
「ふふ…ごめん。でも紗季に合わせてゆっくりするから」
その言葉に『あぁやっぱりするんだ』と実感して私の下着がじわっと濡れてしまう。
「あぁ紗季の胸やわらかい」
堪能するようにゆっくりとふくらみをさすったり揉んだりしている。
可愛い。
こんな三木君初めて見た。
「私も触っていい?」
自分でも驚くほど積極的になってしまう。
三木君も一瞬驚いたけどすぐにうなずいてくれる。
「うっ!」
さするたびに切なげな声をもらす三木君。
たまらない。
こんなふうにセックスを楽しんだのって初めて…。
高校生の頃は三木君とこんなこと…想像できなかったな。
「紗季…すごい濡れてる」
私の秘部に手を伸ばして三木君が嬉しそうに笑顔を見せる。
ぴちゃ…。
彼の指にもてあそばれて私のソコはどんどん蜜をあふれさせているのがわかる。
「あ…ん。三木君きもちぃ」
「俺も…たまんない」
私に背中を向けてゴムを装着する。
そしてそのまま自然と三木君は私の下着をはぎ取って蜜口に彼自身をあてがう。
「挿入(い)れるよ」
コクっとうなずくとゆっくりと私の中に三木君が割り入ってくる。
「はぁっ…。あ…」
彼の形を鮮明に感じる。
一瞬克弥の顔と会ったこともない三木君の奥さんのことが脳裏をよぎる。
でも最奥に突き付けられた猛りに全部吹っ飛んでしまう。
「はぁ…。紗季の中最高」
深くため息をついてぐっと腰を押し付けて三木君がつぶやく。
「ずっと入っていたい」
「バカ」
「でもほんとに動くのもったいない」
うれしいけど私の腰はうずいてしまう。
みっともないほどにあふれさせる蜜に負けないほど三木君のモノは膨張してくる。
じれったくなった私はぎゅっと三木君に抱き着いてそのまま三木君を組み敷く。
思ったよりも簡単に反転した三木君の体を見下ろして彼の胸に手を当てる。
「さ、紗季!」
下になってちょっと焦っている三木君。
ちょっと意地悪な気持ちになってしまう。
「私は三木君をもっと味わいたいの」
そういうと腰をゆっくりグラインドさせる。
大胆な自分にも驚くけどそれよりも三木君との相性の良さに酔いしれてしまう。
私の中を余すことなく埋め尽くして、さらにドクンドクンと脈打って私を刺激する。
「あぁぁ…。あん」
「紗季…紗季」
私の動きに答えるように彼の腰も動いて、その手は私の胸をわしづかみにしている。
恍惚の表情を浮かべる三木君に私の気持ちも満たされていく。
しばらくすると突然、三木君が下から腰を突き上げて突いてきた。
「あぁあぁん!いや三木君!」
「紗季声押さえて」
「ん。うん」
そうだここはビジホ。
となりに聞こえてしまう。
「もし隣の部屋が男だったら、紗季の声聞かせたくない」
こんなふうに言われたらあそこがきゅんとしてしまう。
「あ、きゅってなった」
「いやん…。」
「紗季マジでよすぎ」
上半身を起こして私の乳房にしゃぶりつきながら夢中で腰をふっている三木君。
彼の頭を抱きしめて腰を両足でホールドする。
「あん。三木君もっと…。もっと欲しい」
「俺ももっともっと一つになりたい」
セックスなんて…と思っていたけど間違ってた。
女として扱われたいと思ってたけど、そうじゃなくて女として本能で求めた先にこの快楽があるんだ。
「紗季…。紗季以外の誰を抱いたとしてもこんな気持ちにならない」
三木君も同じように感じているみたいでうれしい。
「あぁもうきちゃう。体の奥からなんかきちゃう」
「いいよ。一緒に…一緒にいこう」
終わりたくないけどこの波にのまれたい。
そう思いながらも私たちはきつく抱きしめあってキスをして、そのあと壊れそうなほどまじりあって—果てた。
「紗季…俺は…」
そう言いかけた三木君の唇を今度は人差し指で制する。
「また連絡する。三木君も何かあったら連絡ちょうだい」
離れがたい思いを振り切って一度だけ熱く抱きしめあった後自分の部屋へ戻る。
私は知ってしまった。
知らなければよかったかもしれないこと。
お互いの夫婦の小さな綻びが私たちを引き合わせて、もうつくろえない綻びへと絡まってしまったことも…。






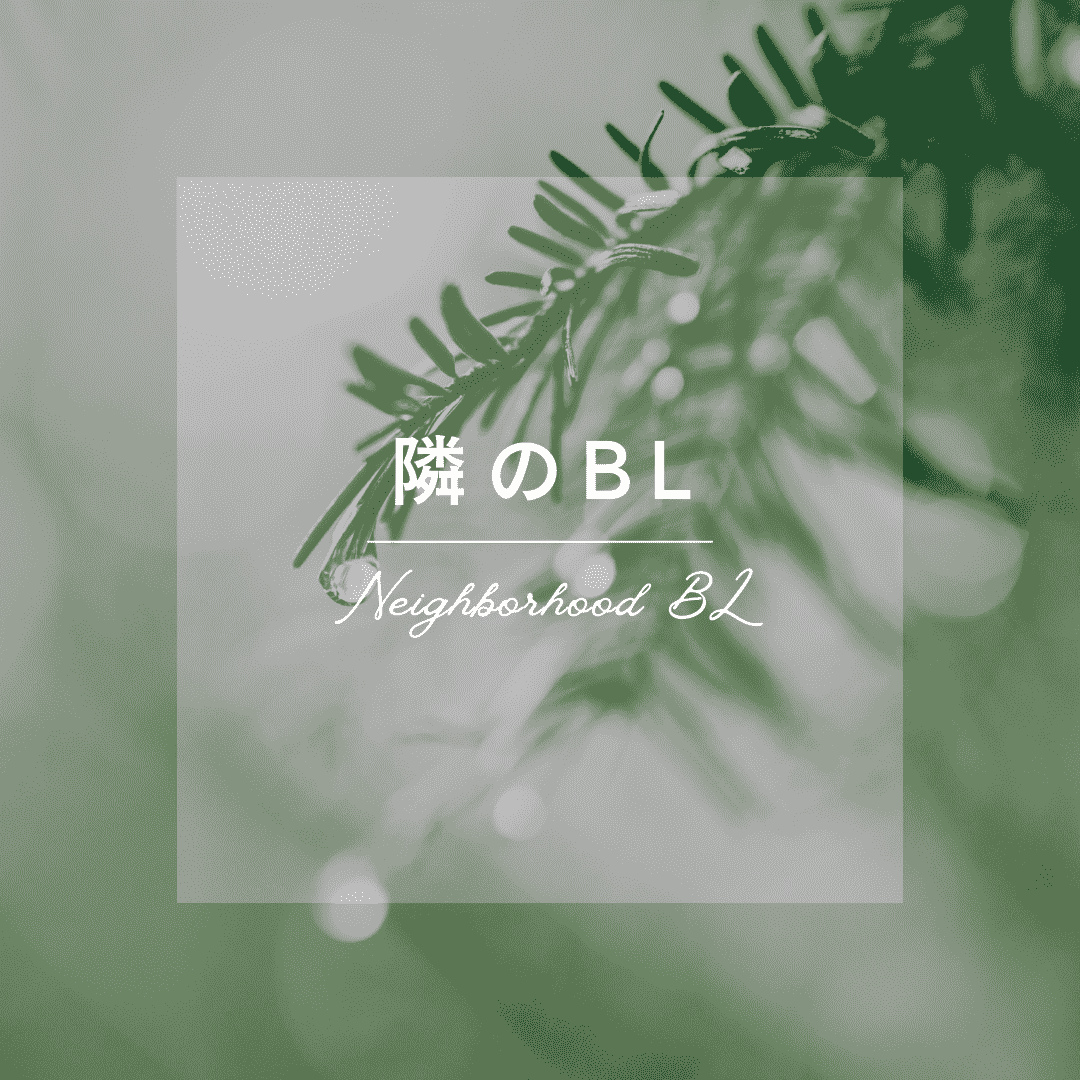
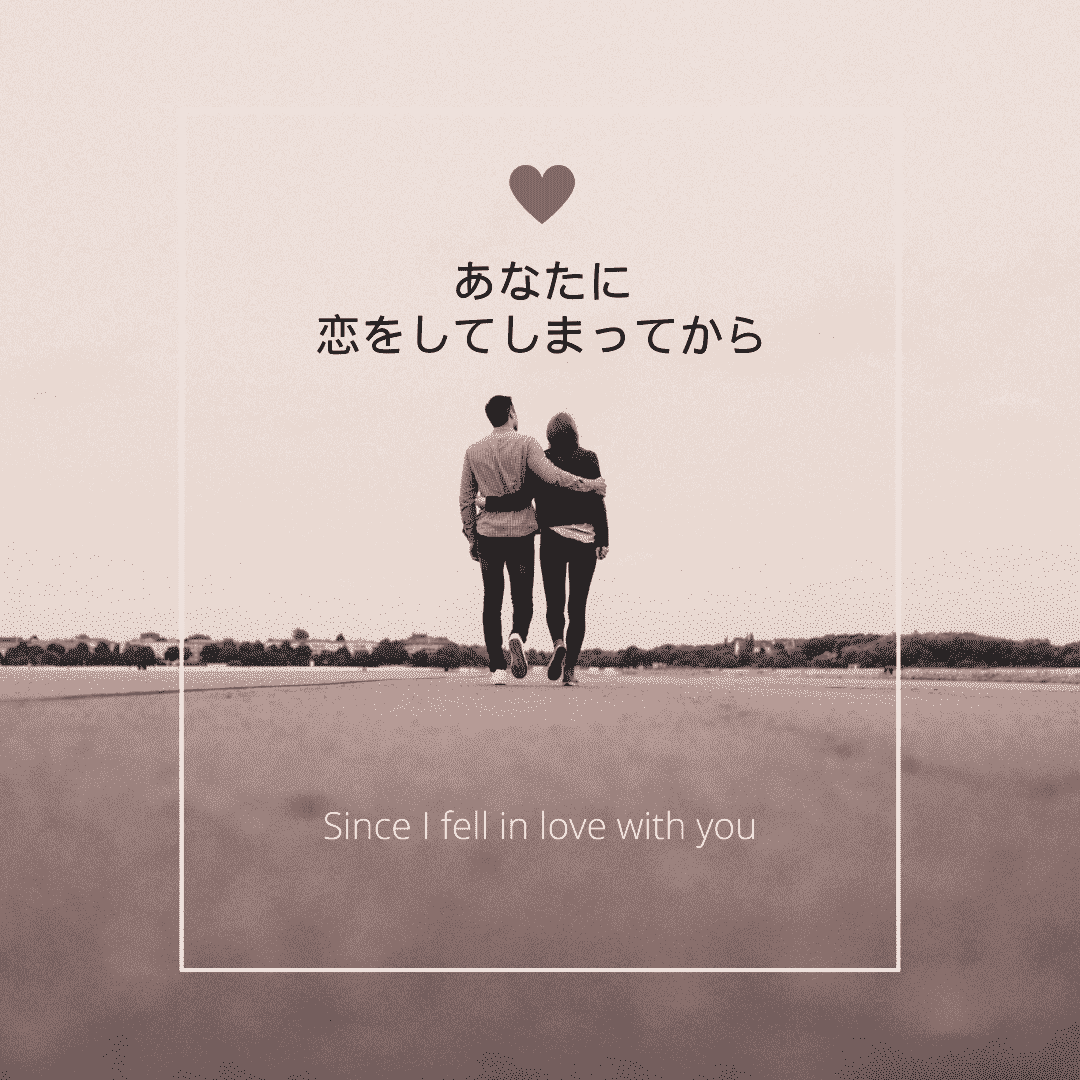

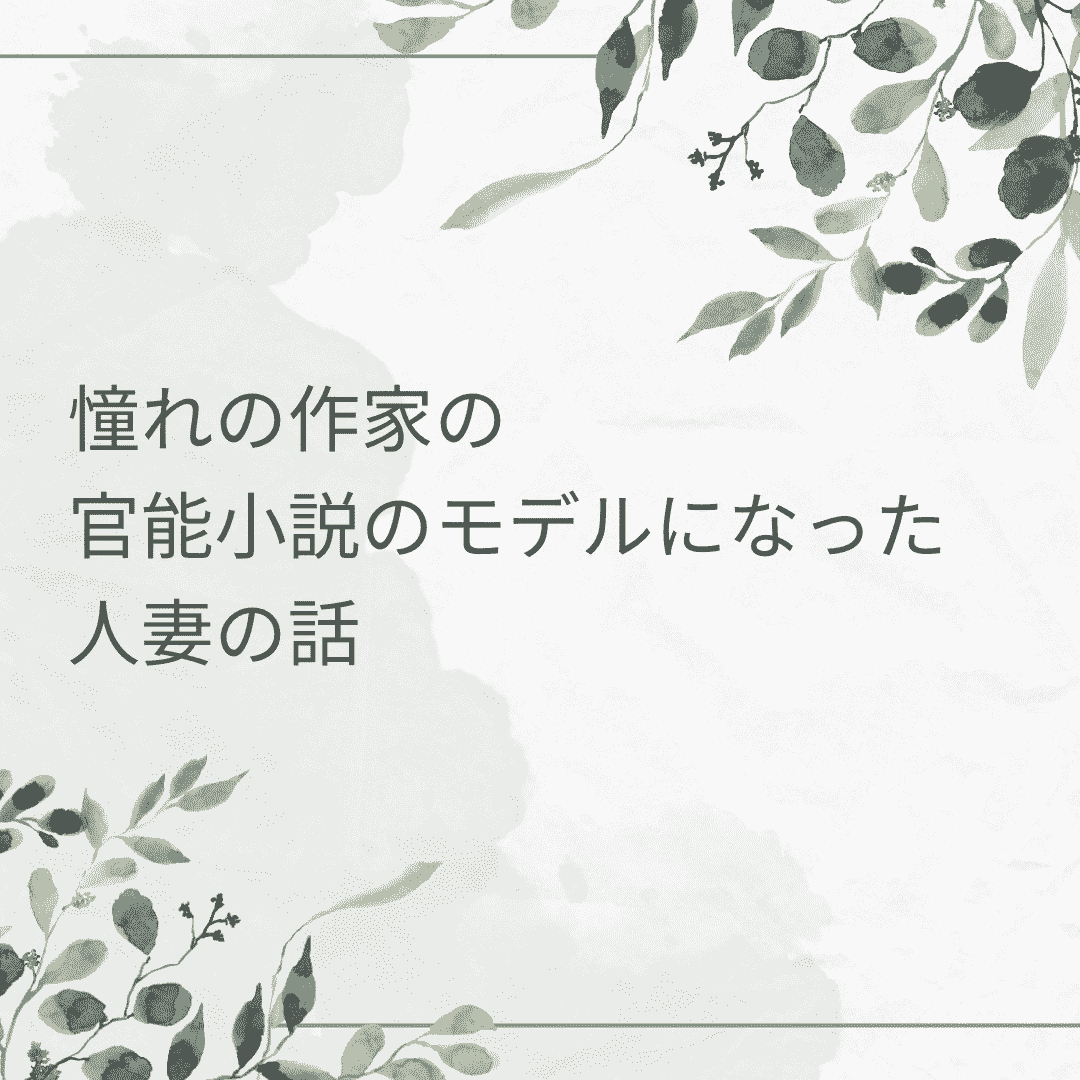


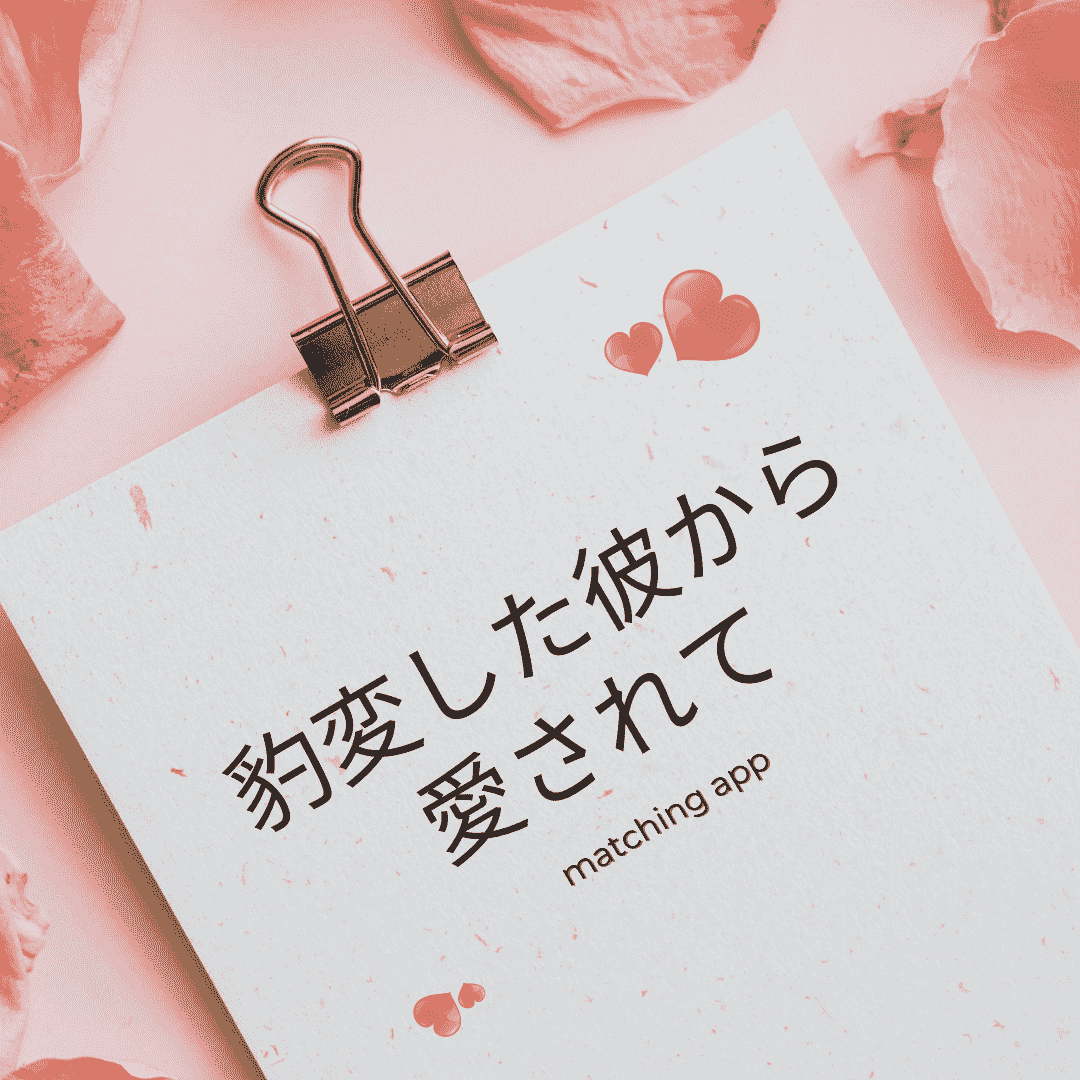

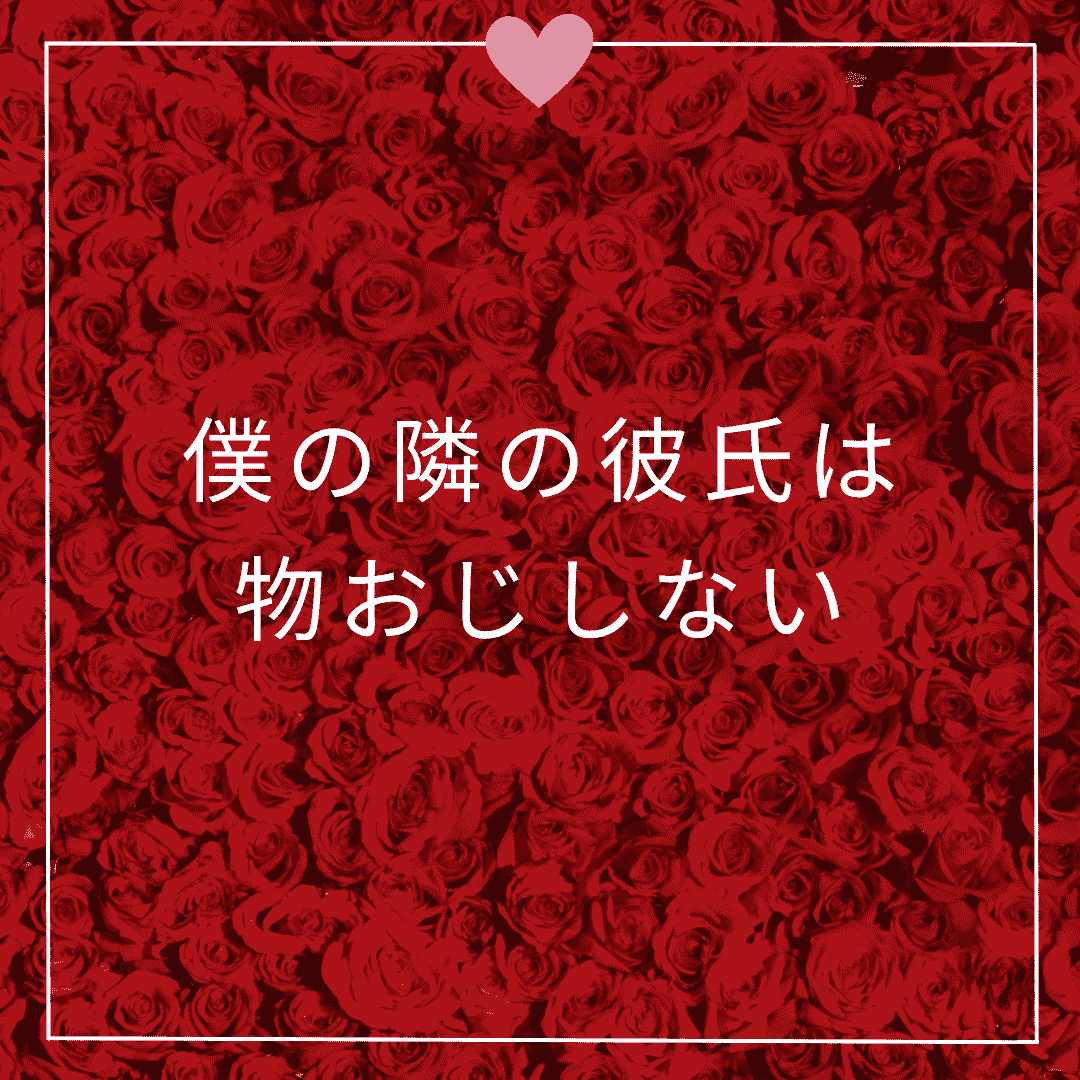
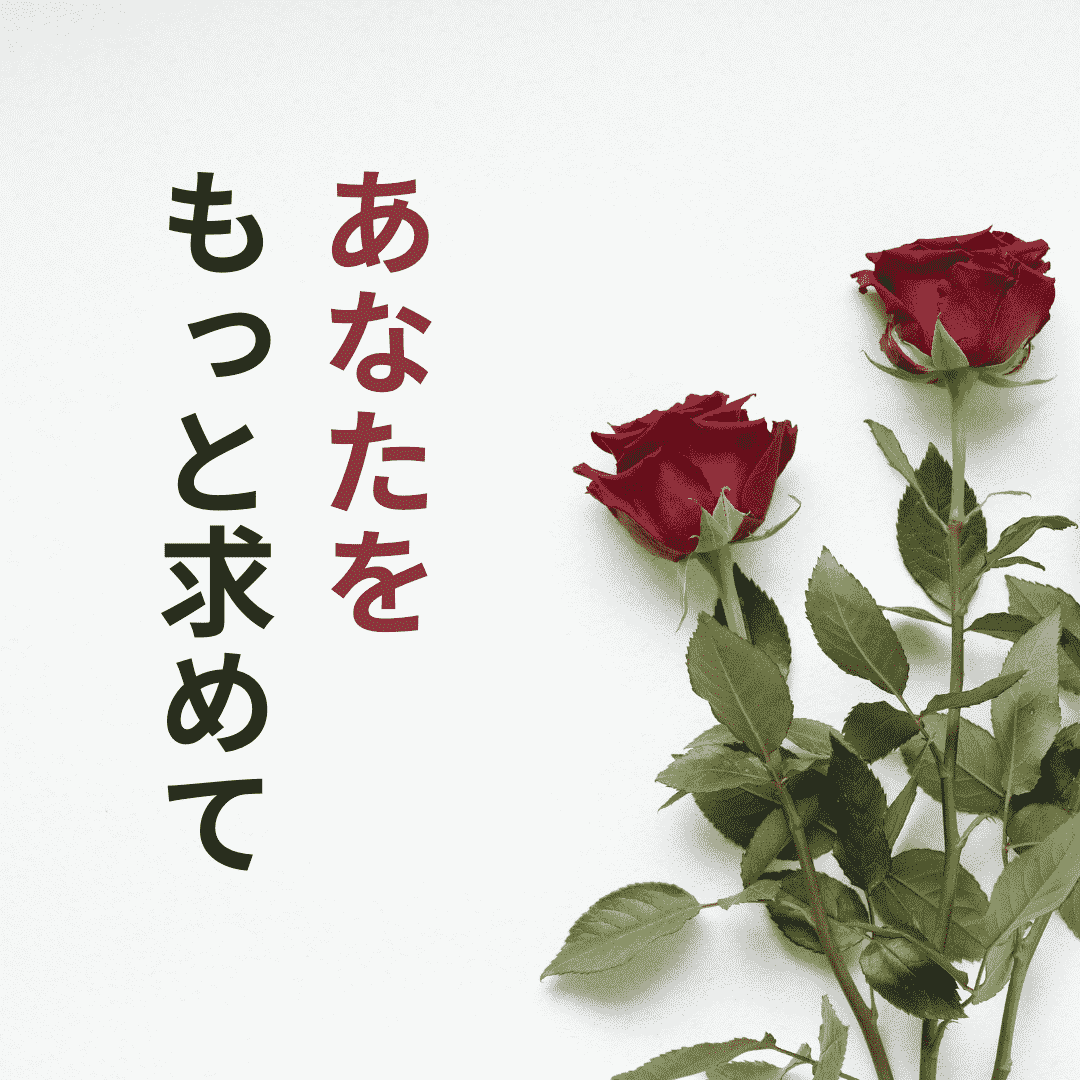





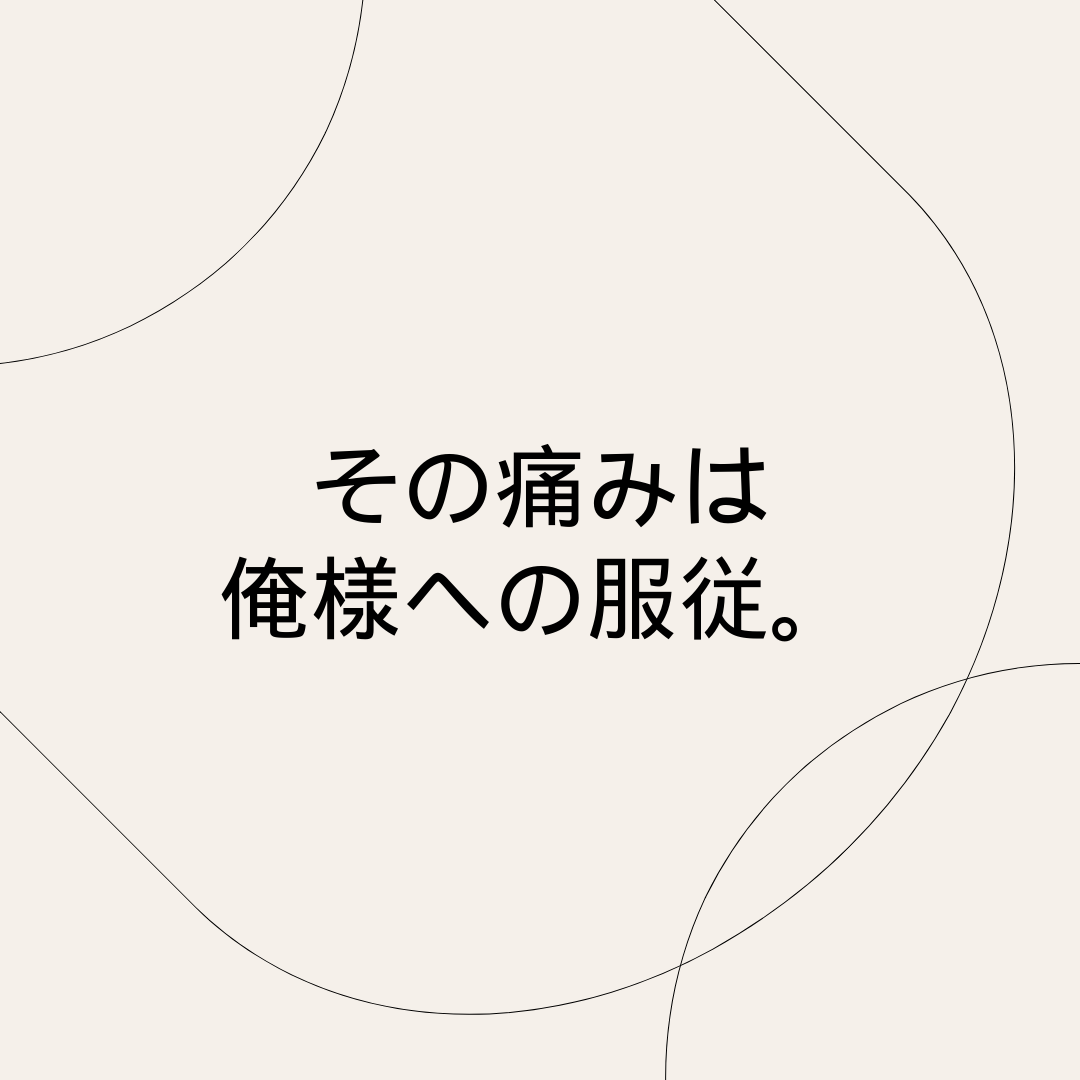
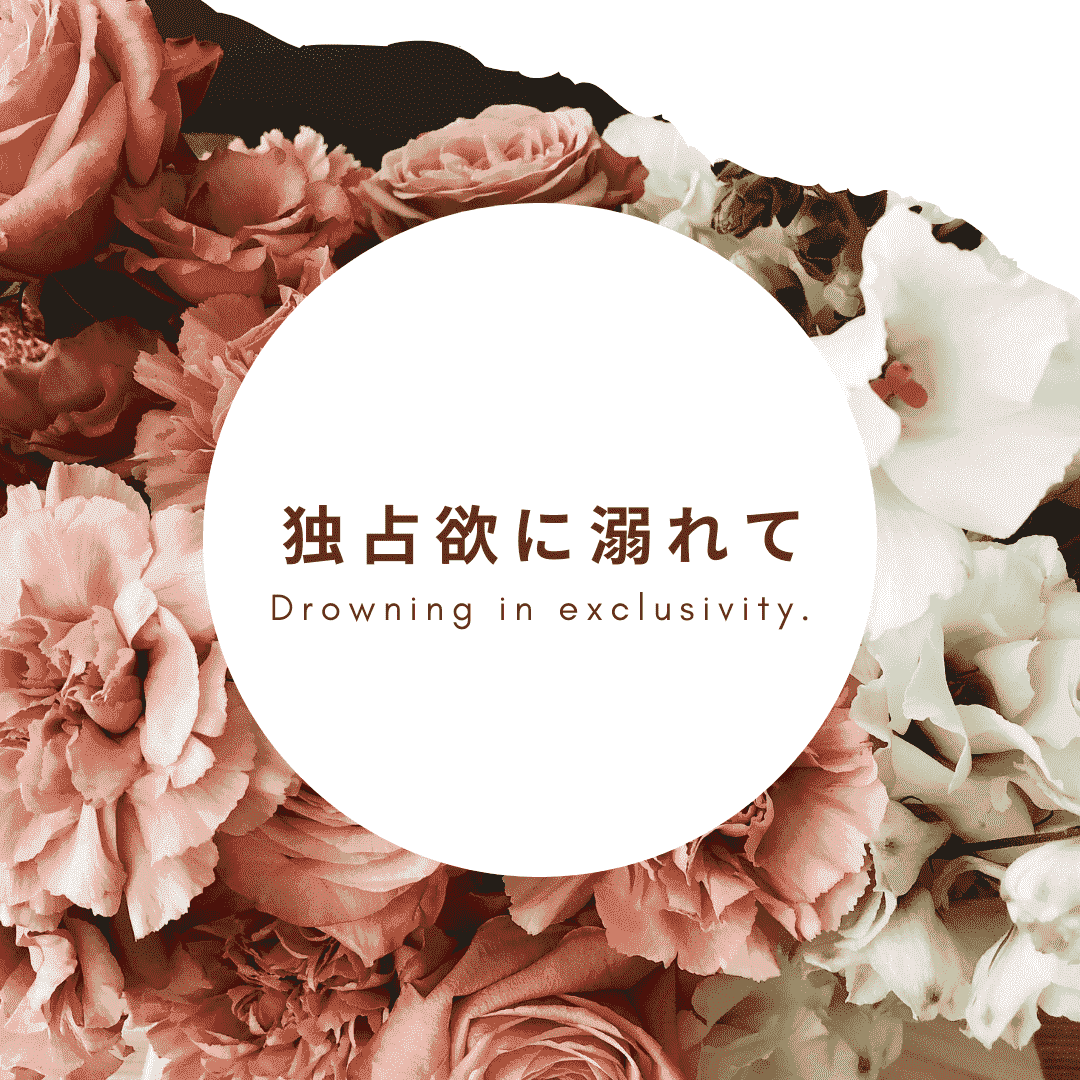
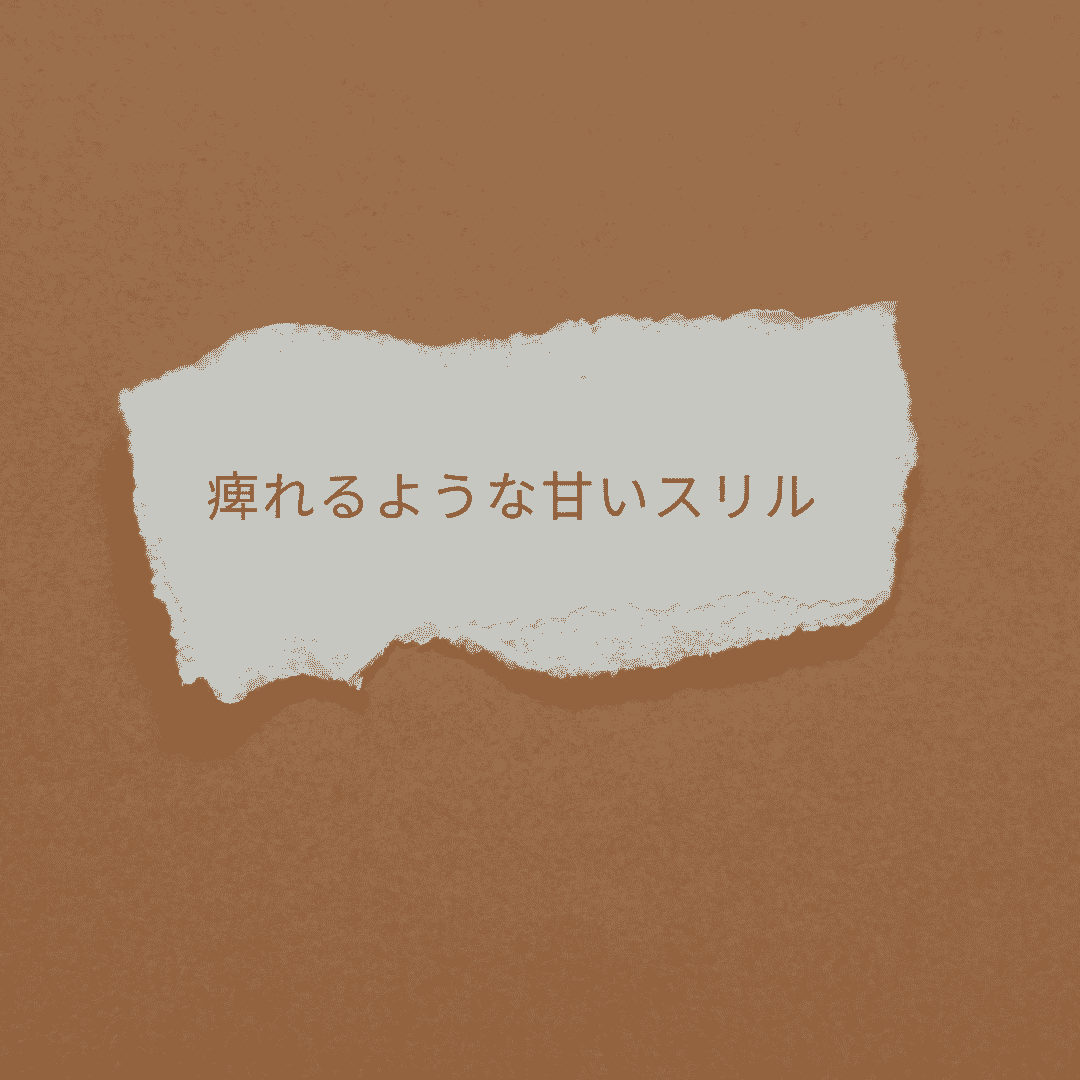


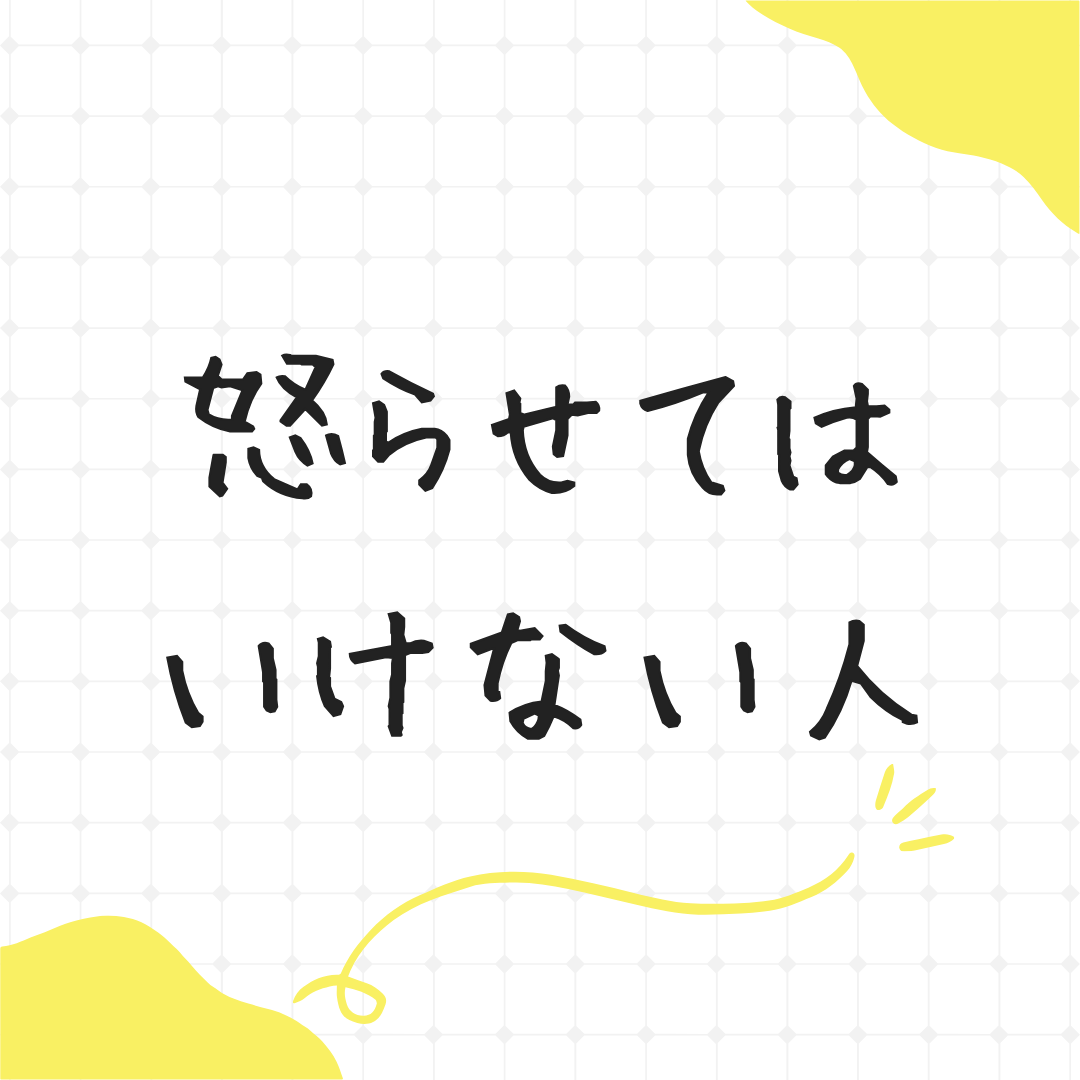

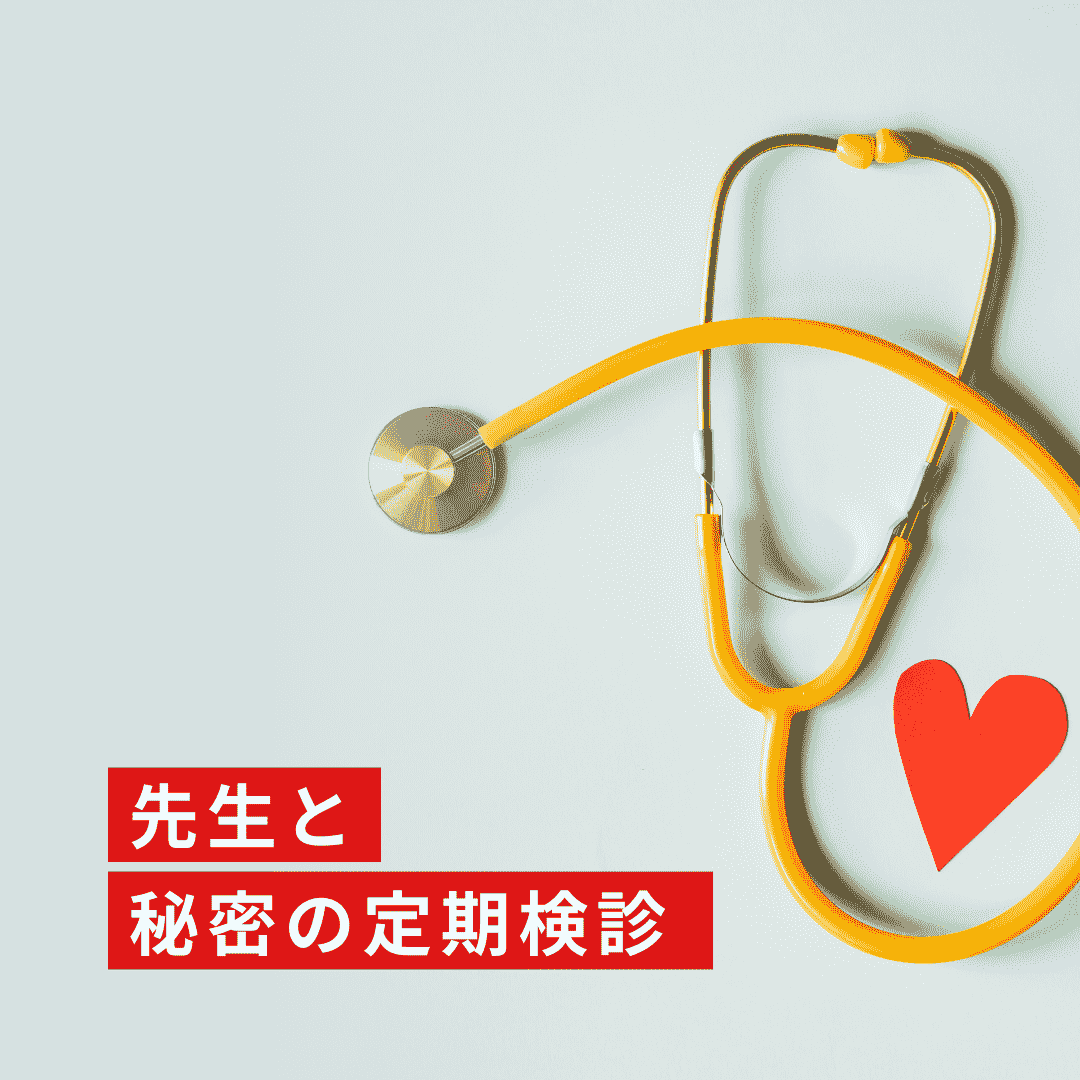
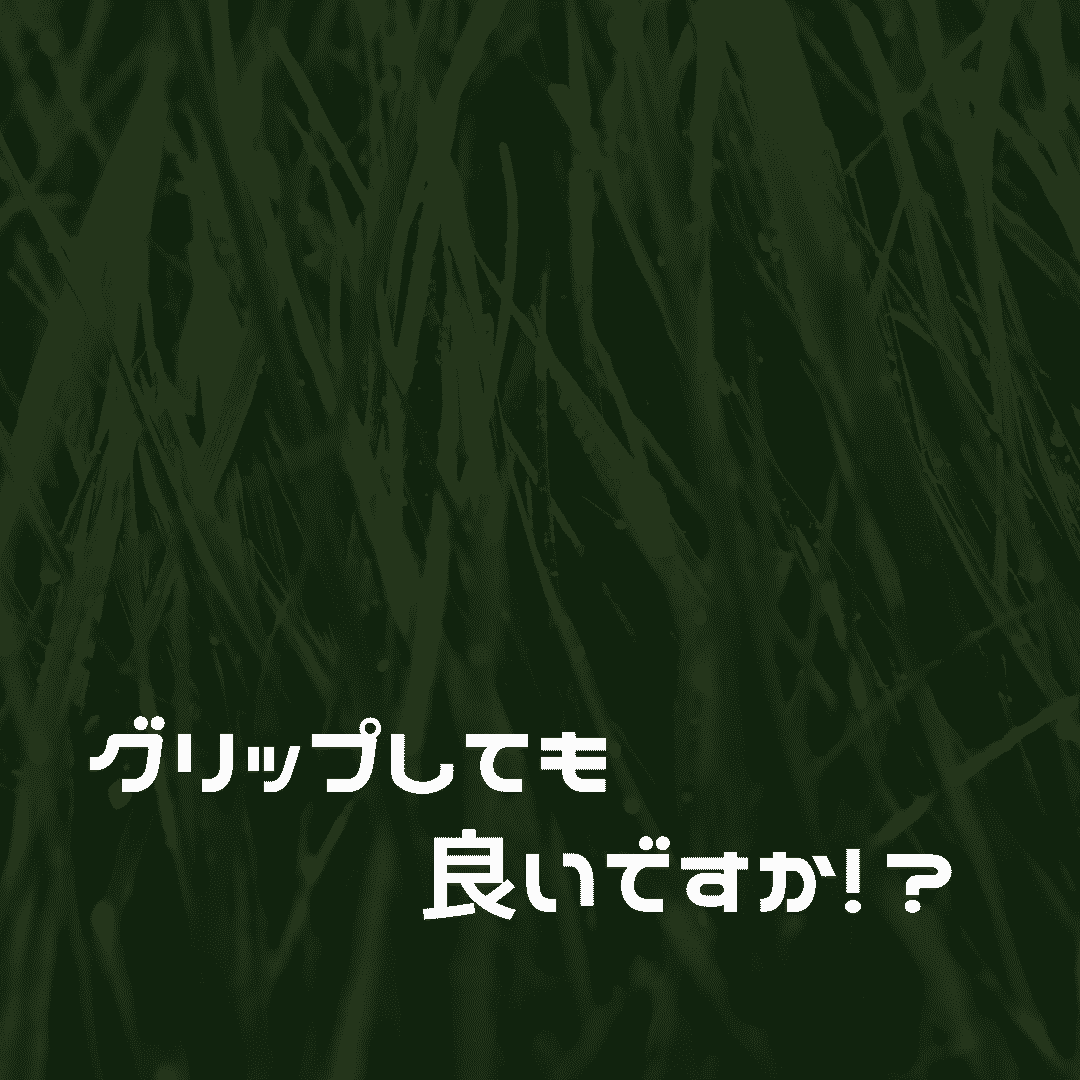
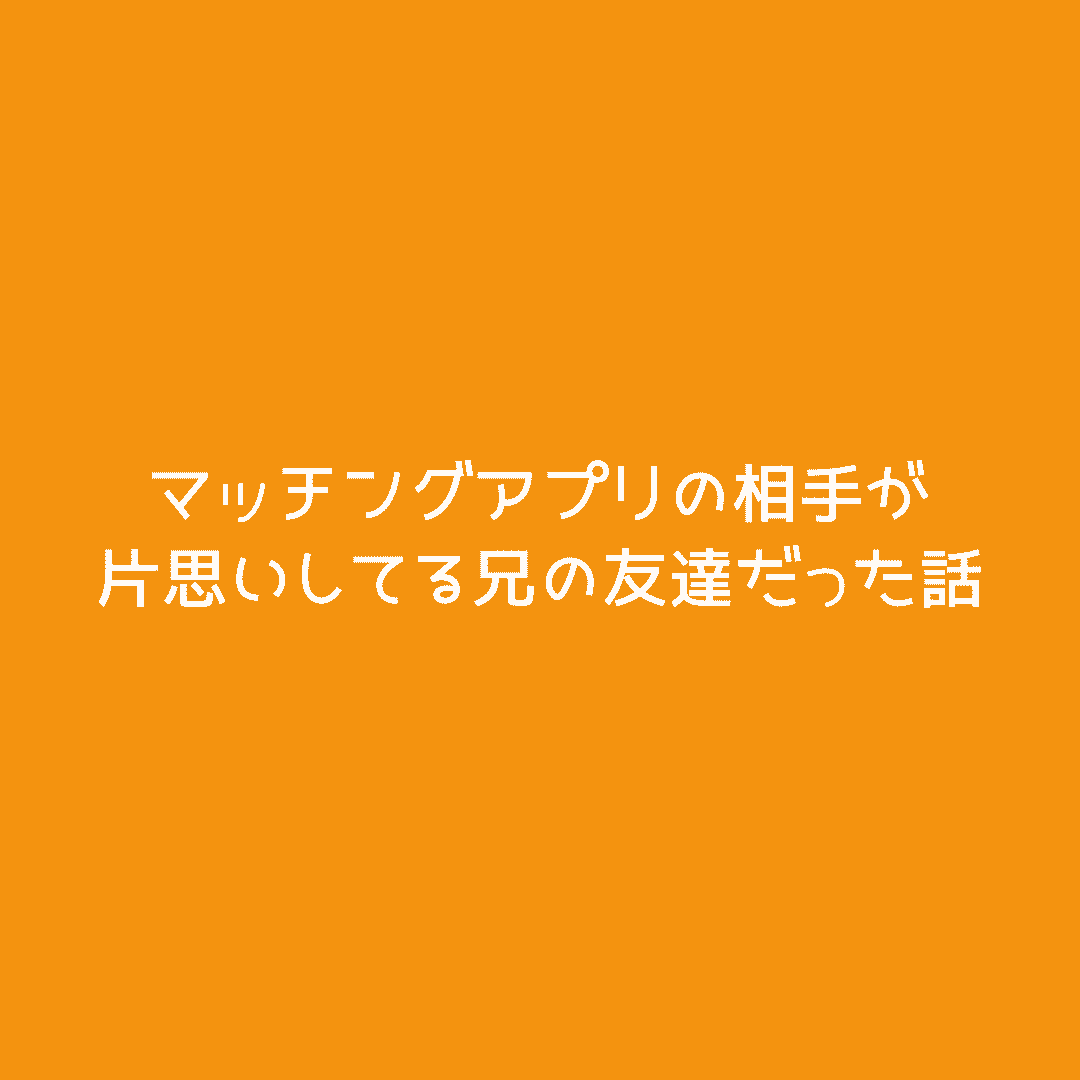
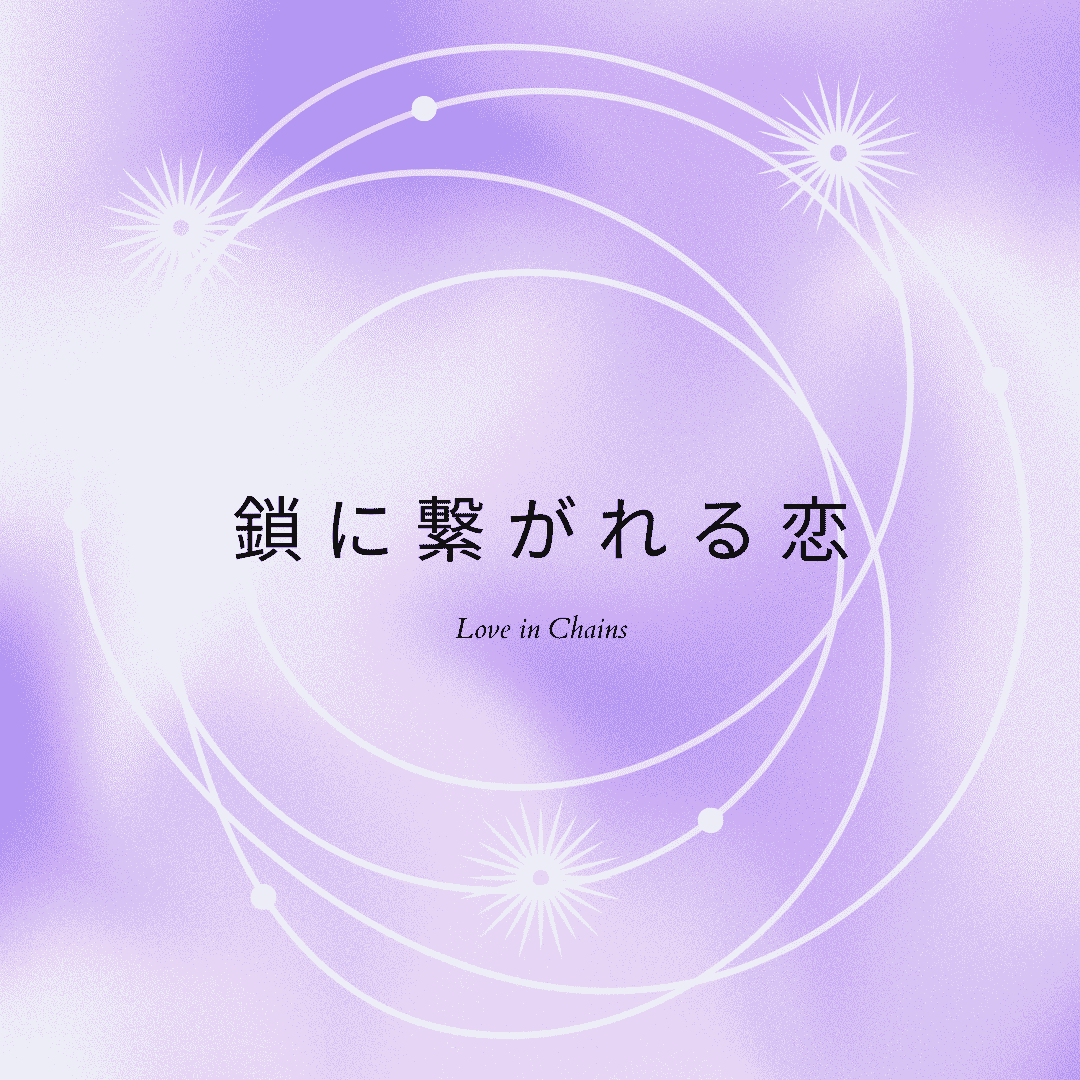


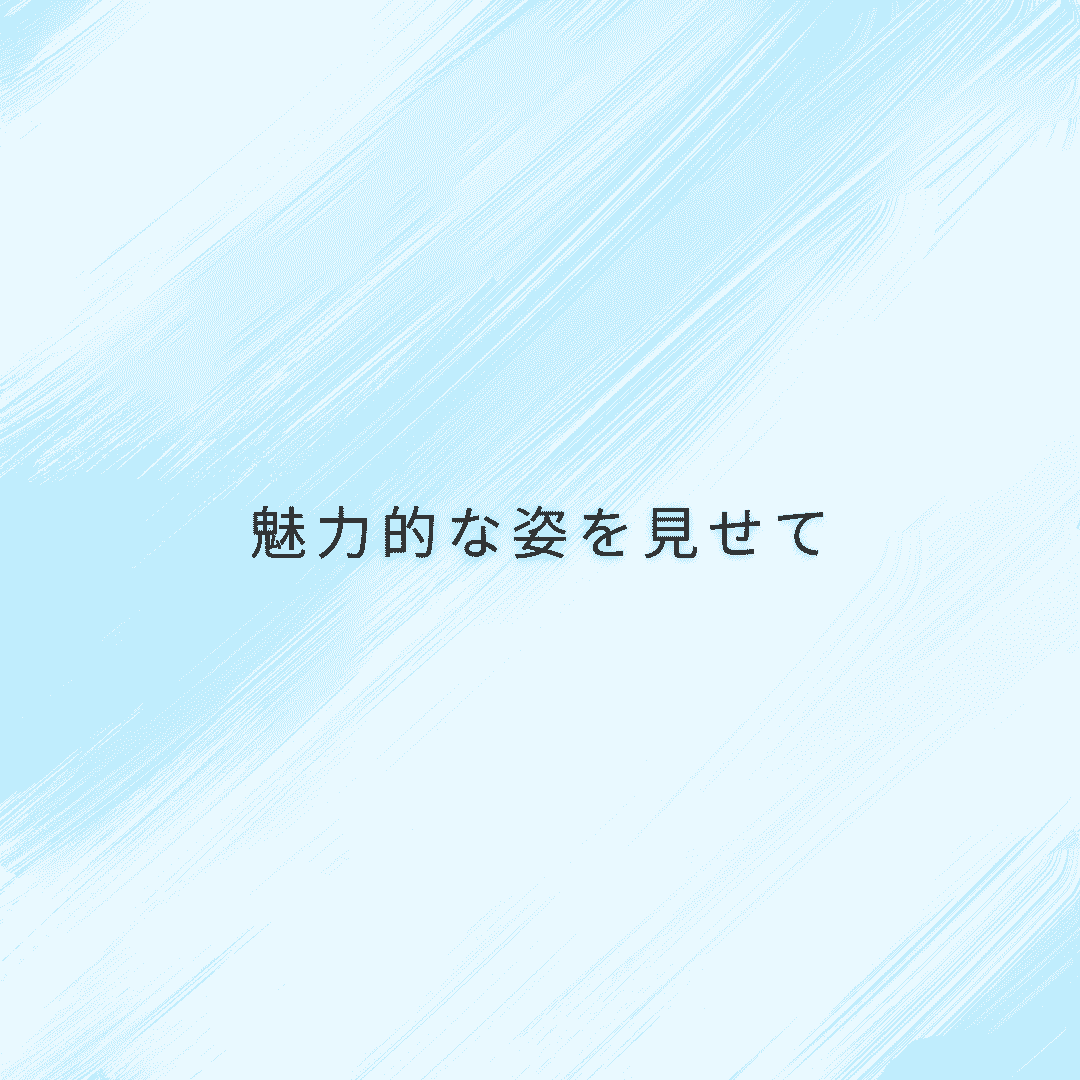
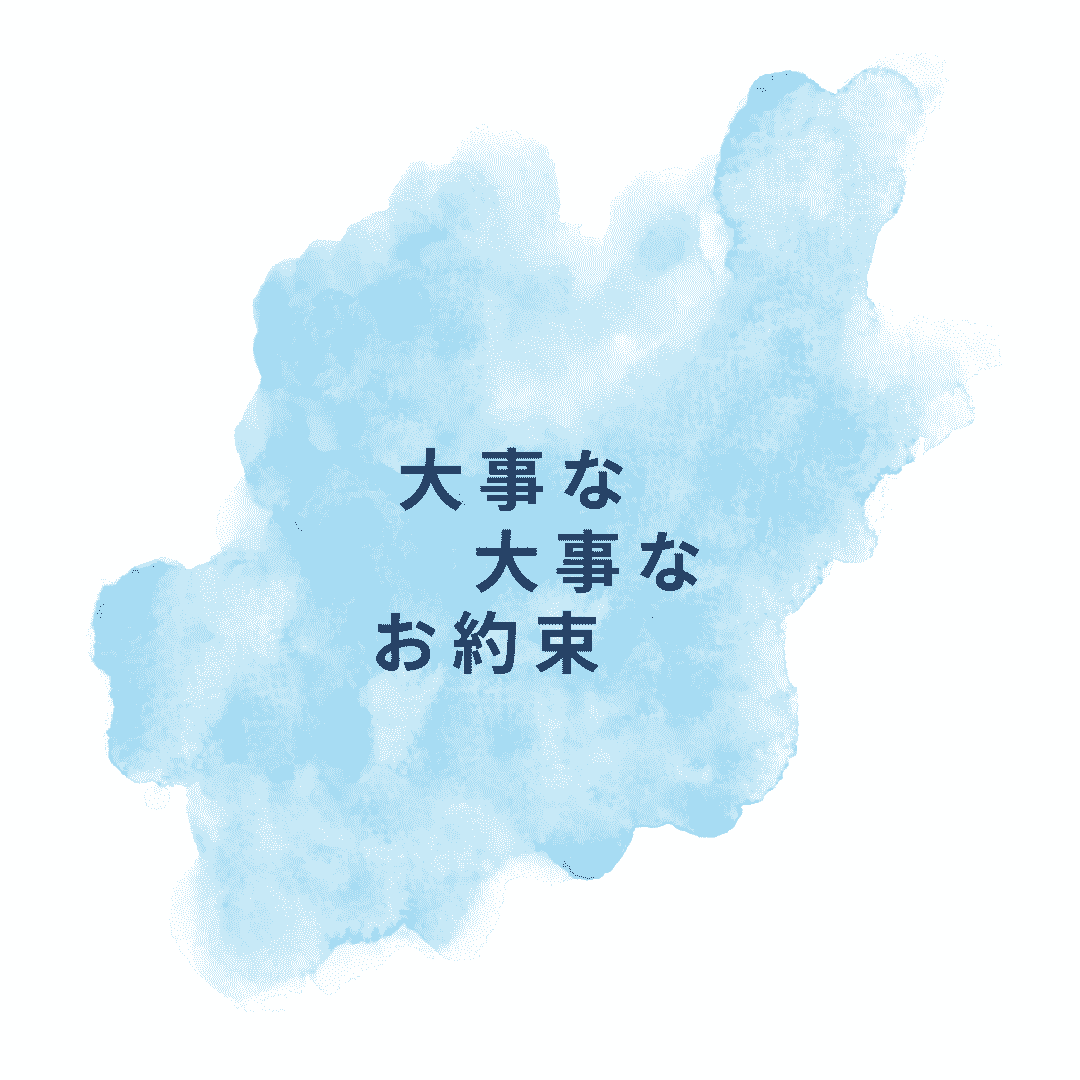


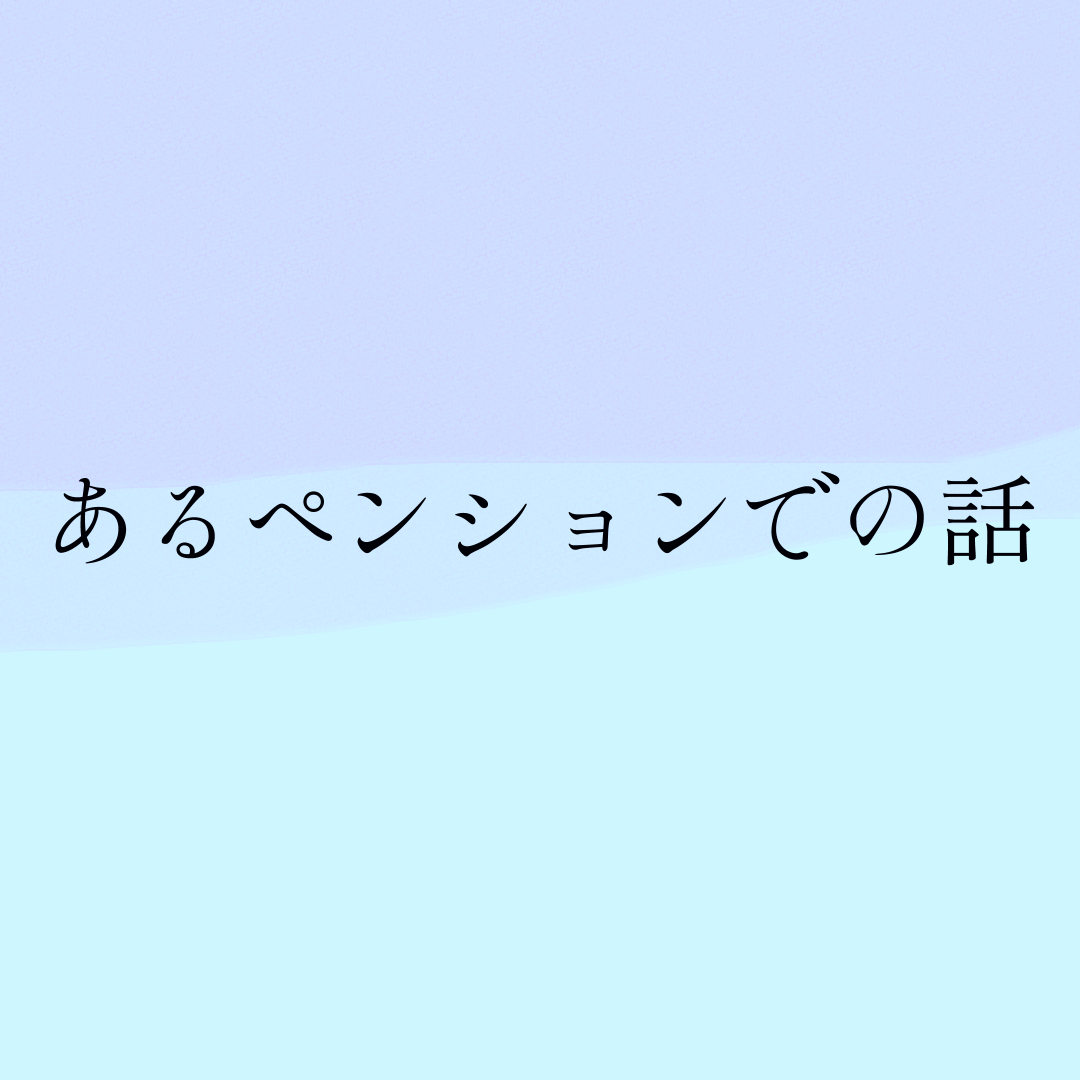
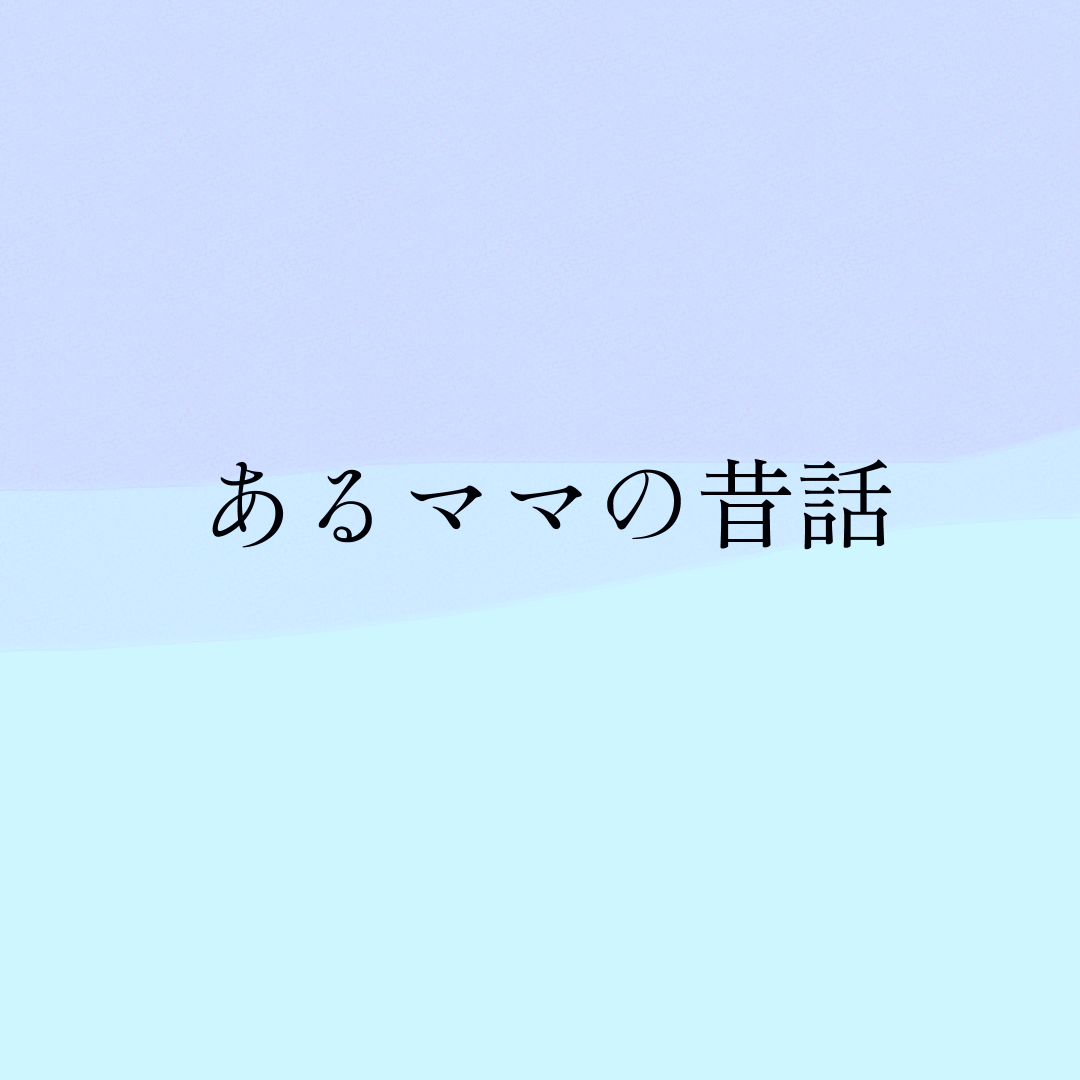
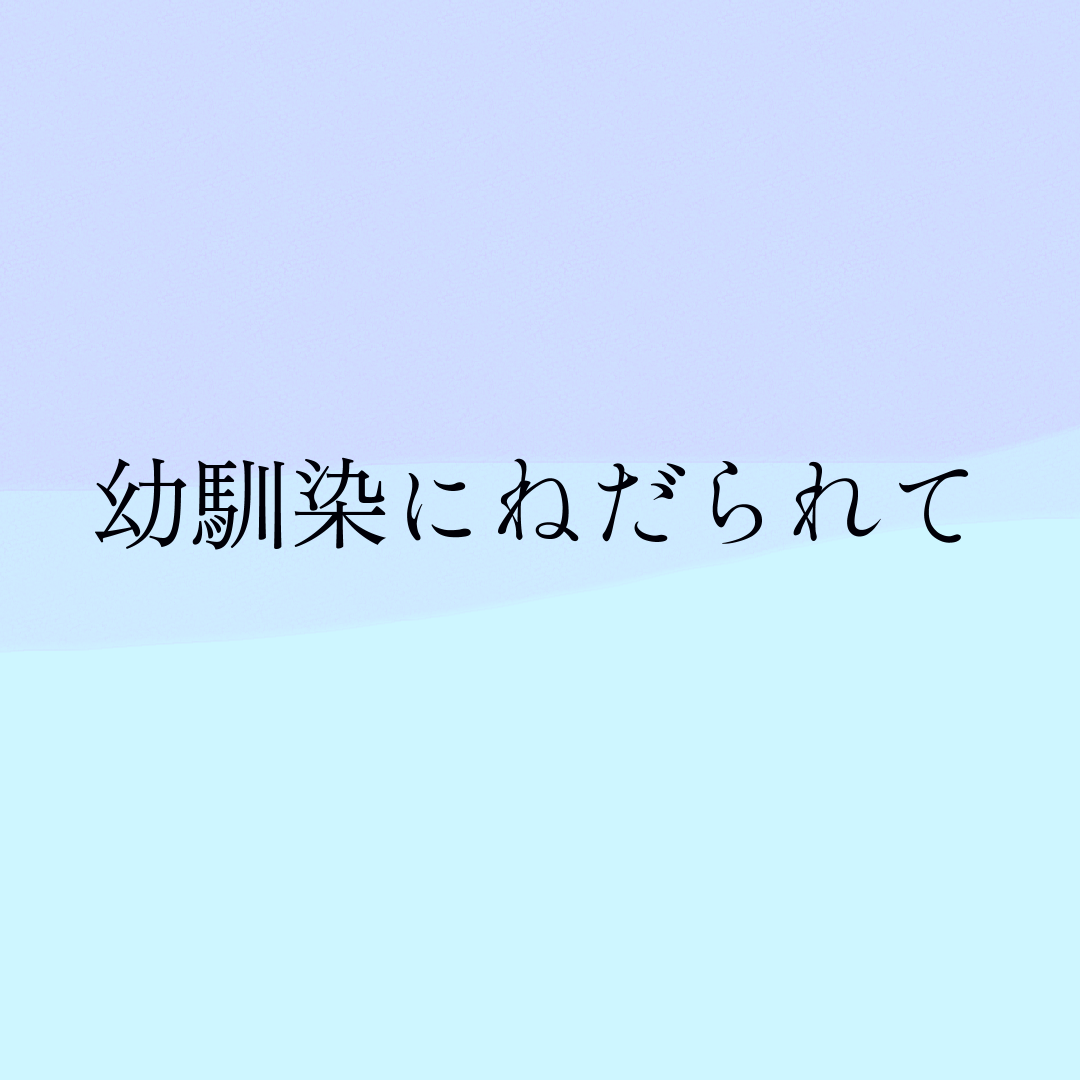
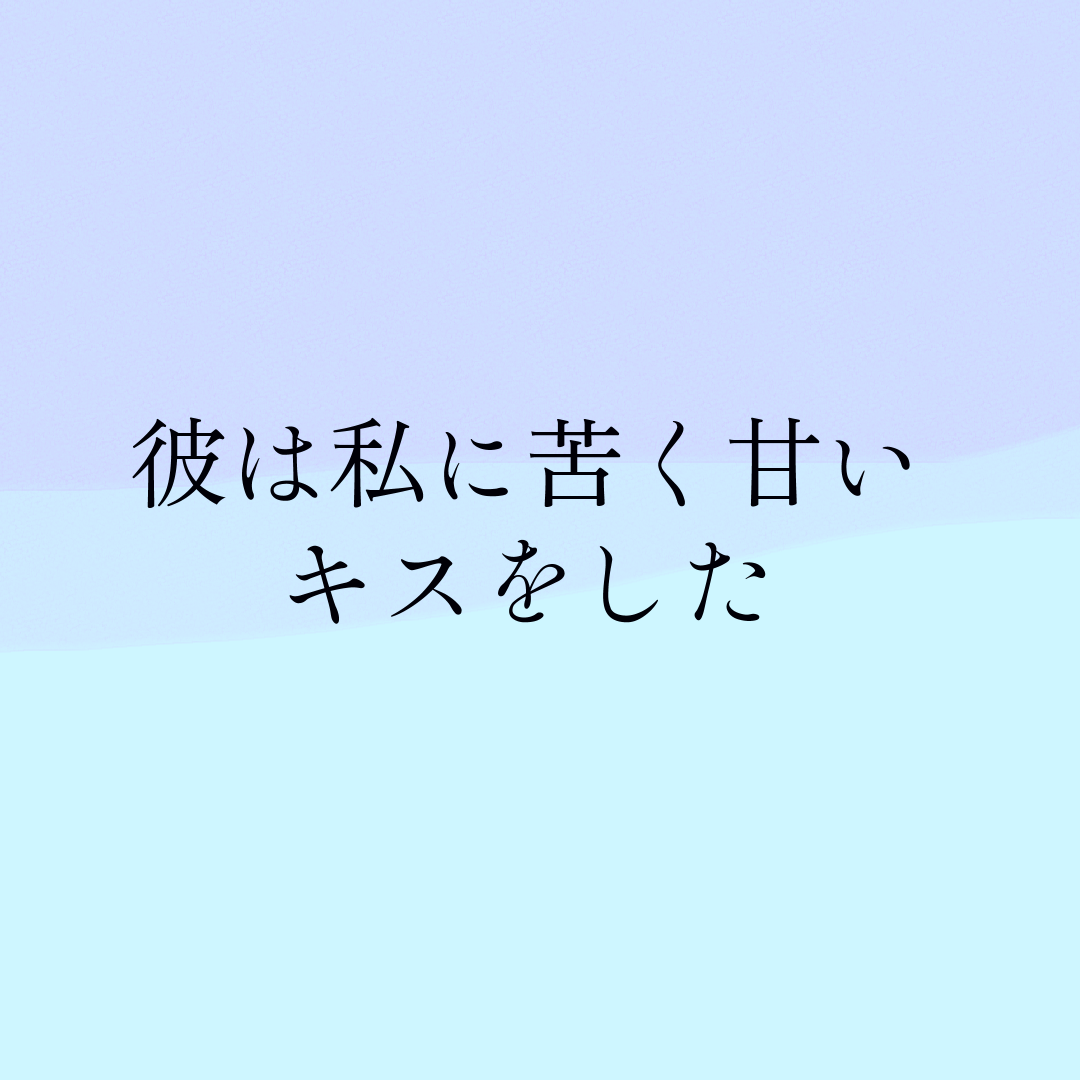
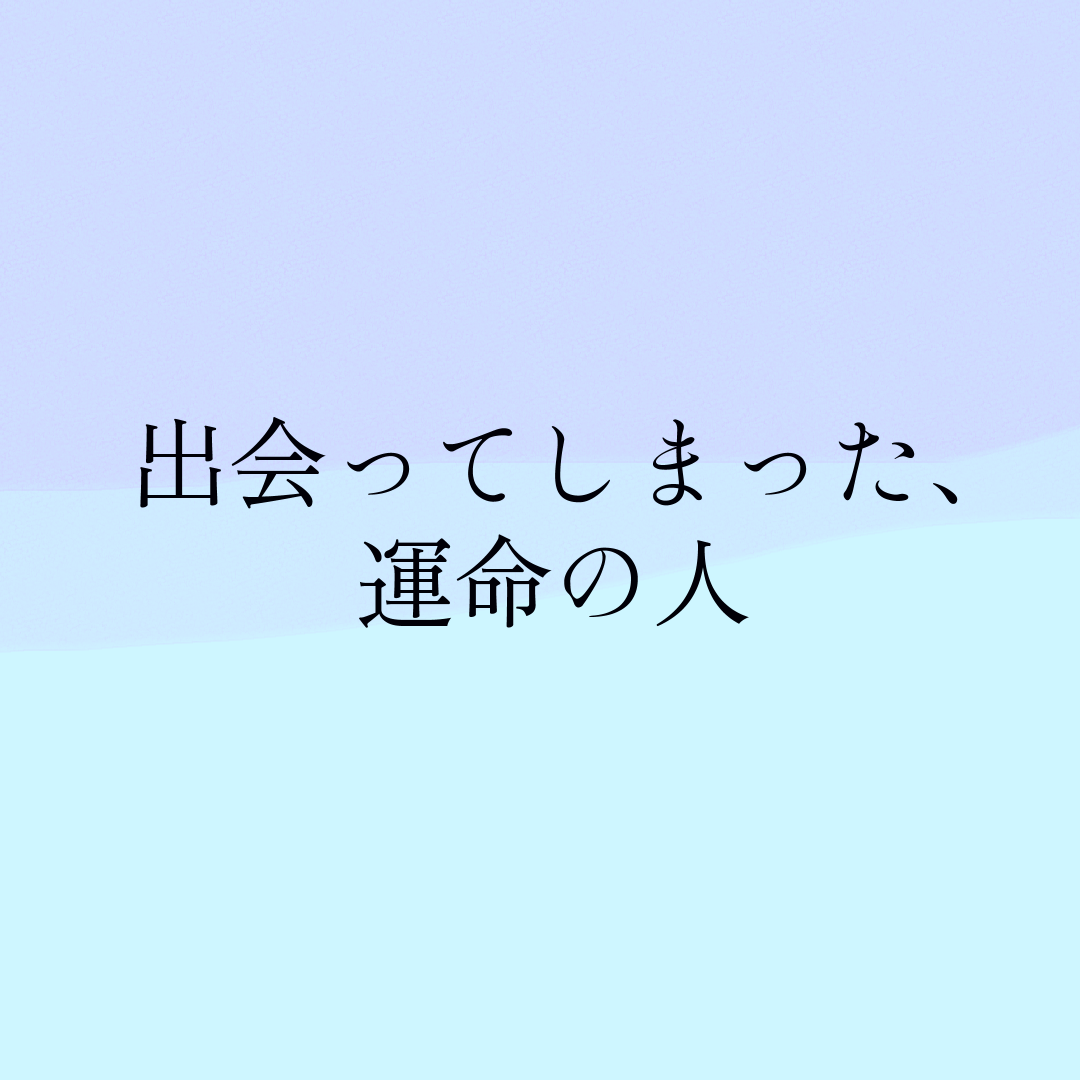
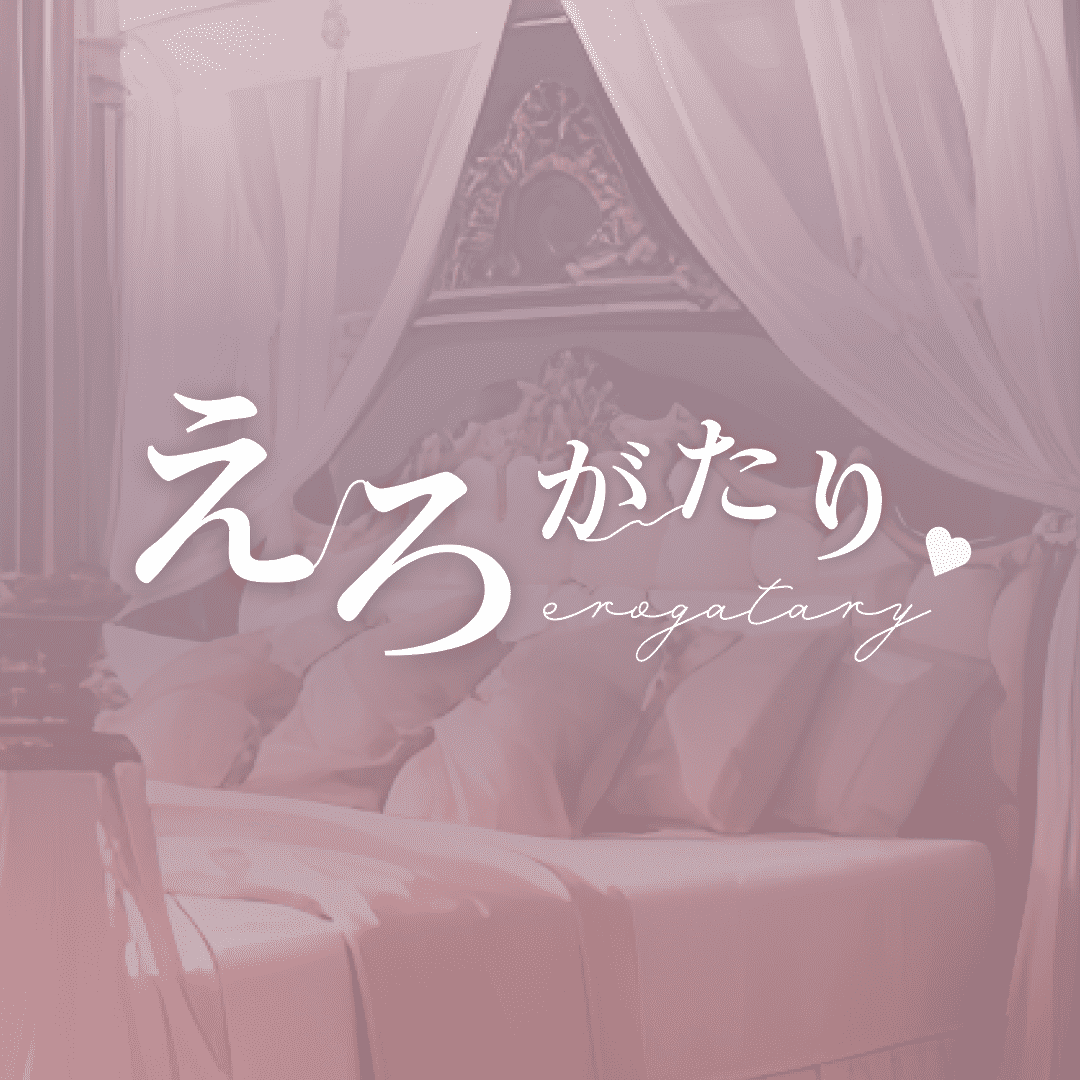
コメント