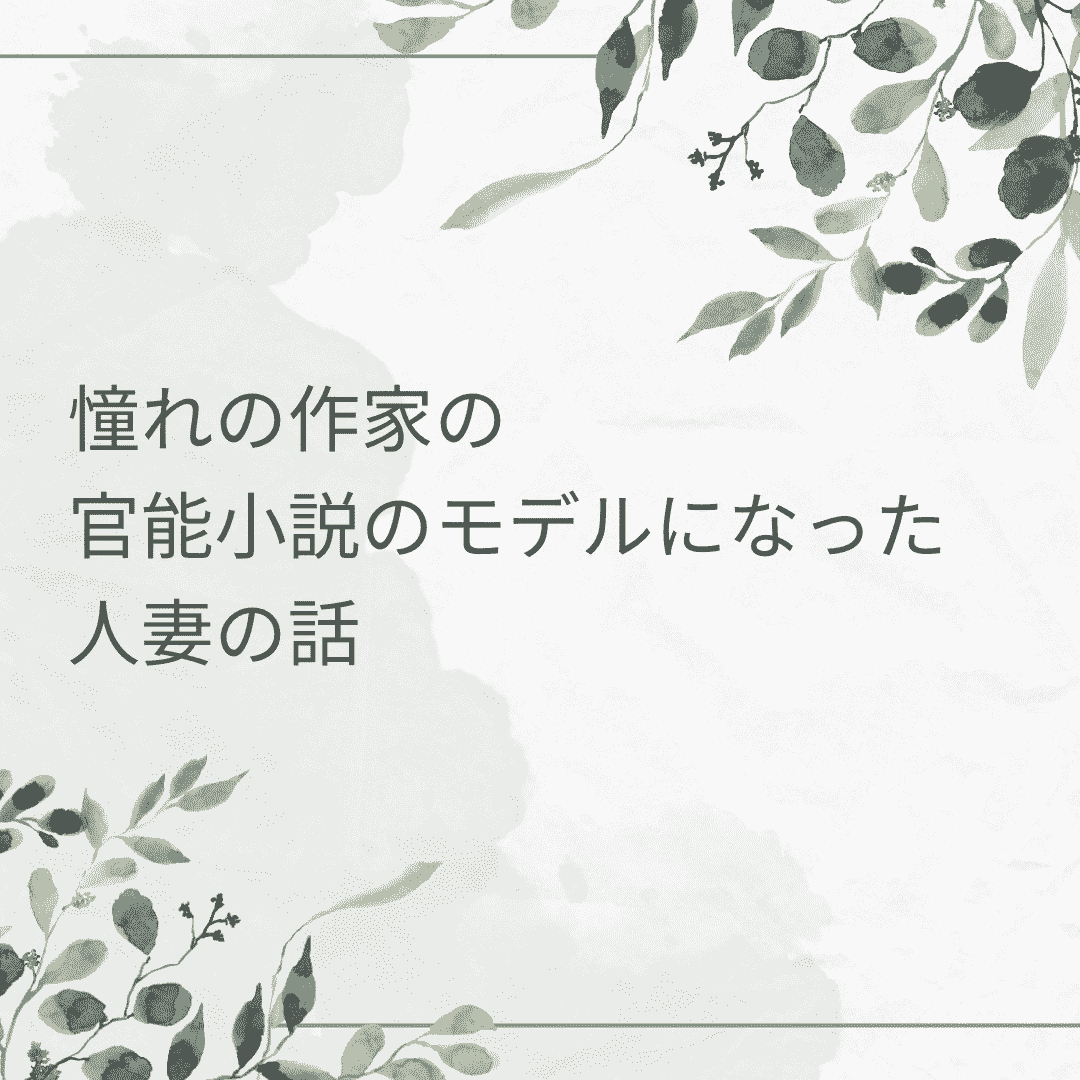
0
憧れの作家の官能小説のモデルになった人妻の話
「こんにちは」
「あ、こんにちは」
お隣さんはいつも家にいる。
買い物の時間が一緒みたいで玄関先でよく会う。
あごひげなんかはやしちゃって、目にかかるくらいのちょっともっさりしたノーブルヘアで、何考えてるかわからない雰囲気の男(ひと)。
でもどことなく漂う色気のある大人の男性に見える。
ニート?
ううん、よく見ると時計やお財布はちょっと名の知れたブランド品だ。
それに時折誰かたずねてきているみたいだし…。
私は瀬戸 麻美(せと あさみ)。
26歳の専業主婦だ。
2年前に大学の同級生だった瀬戸 貴男(せと たかお)と結婚してこのマンションに越してきた。
貴男とは大学から仲のいい間柄だったから情熱的な恋愛っていうわけではなかったけど、一緒にいると安心できるおだやかな関係。
貴男の収入だけで夫婦二人の生活は安定している。
だから貴男の希望で結婚を機に専業主婦になった。
旦那とのおだやかな日々。
悠々自適な生活。
周りからもうらやまれる環境だろう。
友だちにも言われる。
『生活にも気持ちにもゆとりがあってうらやましいぃ!』
確かにそう。
私だって好きな人と何の問題もない生活はほんとに幸せだって思ってた。
貴男のために家事をして家を守る。
もちろん女としても自分なりに身なりにも気を遣っていた。
“結婚したら女捨ててる”なんて思われないように。
でも、人の気持ちってどうにもならない。
半年ほど前から私はそれを実感している。
貴男の残業が増えて休日も土日のうちどちらかは1人で外出する。
持ち物のセンスが変わったり身なりに気を遣って流行に敏感になった。
気付いてしまえばテンプレ通りの兆候。
そう、貴男には私じゃない女がいる。
たった2年。
でも交際期間を交えたら6年。
それだけの期間があれば男の人は1人の女に飽きてしまうんだろうか?
それとも私に貴男を振り向かせておくだけの魅力がなかっただけなのかな?
きっと貴男は知ってしまったんだろう。
刺激や情熱のある恋というものを…。
私たちにはそういう激情はなかったから。
「はぁ」
専業主婦の私には彼に不倫の事実をたたきつけるような勇気はなく、ただただ悶々と日々を過ごしている。
そんな私がふとしたきっかけではまったのが恋愛小説。
その深みにはまって最終的にたどり着いたのが『官能小説』と呼ばれるジャンルのモノだった。
“官能小説ってなんだかいやらしくて背徳的な読み物”って思ってた。
確かにエッチなシーンは多い。
けれど燃え上がるような恋愛経験の少ない私にはとても魅力的に見えたし、今まで感じたことのないときめきを私にくれた。
昼下がりのちょっとした休憩時間に、私はお気に入りの作家さんの小説を携帯でスクロールする。
『モリノ マリオ』。
私のお気に入りの作家さんだ。
彼の小説の好きなところは『臨場感』。
読んでいるだけで体が熱くなってくる。
それだけじゃない。
10代のころのような甘酸っぱくてキュンキュンするストーリーに私は沼っている。
小説の中の女性は信じられないくらい激しく求められ乱れ溺れていく。
ヒロインのように感じたい。
そう思うと自然に私の手は自分の胸のふくらみに手を当ててしまう。
誰かに触られてると想像しながら手を動かす。
そのまま手を下に這わせて下着の中に手を入れる。
「あ…」
私の秘部は自分でもびっくりするくらい濡れていた。
ぴちゃ。
卑猥な音が一人きりの静かな部屋に響く。
その羞恥心が私をさらにみだれさせる。
指を一本だけ中に入れてみる。
『中すごいよ』
小説の中の少年の声が脳内に響く。
もっと—。もっと—。
私は自分のいいところを指で探す。
「あっ!」
すぐに探り当ててそこを執拗に責める。
「あぁ…あぁ…んんっ!」
自分で自分を慰めながら一気に昇りつめた。
脱力しながら指を抜き取る。
指を伝ってトロッと蜜があふれる。
「…!」
そのままベランダに目をやると—。
やだ!ベランダの窓があいてる!
今更遅いけどあわてて窓を閉める。
そして冷静に考える。
大丈夫。
そんなに大きな声出してないしここの窓が開いていてもお隣の窓が開いてなければ聞こえていないはず。
そう考えて、気持ちを落ち着ける。
ふぅ。
今日も貴男の帰りが遅い。
ベランダに出て手すりにもたれて星空を眺める。
もしかしたら今頃貴男は私じゃない誰かと会っているのかな?
そんなことを考えていると、不覚にも視界がにじむ。
ガタンっ!
となりのベランダからの音にびくっとなる。
思わずそちらに目を向けると”ヒョコ”っと隣の住人が顔をのぞかせた。
「あ、こんばんわ」
「あ、ど、どうも」
普通に挨拶されてあわてて挨拶を返す。
彼はエナジードリンクの缶を片手に持ってベランダの手すりに腕をかけた。
何となく気まずい空気感を彼は気にしていないようだけど、私は耐えられなくなって軽く会釈して部屋に戻った。
ベランダの窓を閉めて呼吸を整える。
昼間のことが気になる。
でもあの様子だと聞かれてないよね?
それにしても—。
きれいな横顔だったな。
それに指も長くてきれい。
一瞬でそこまで観察してしまった自分がちょっとおかしくなる。
それからまた何日も何事もなく過ぎていく。
お隣さんともたまに会うけど、いつもと変わらないことに安心する。
貴男も相変わらず…。
嬉しそうにスマホを眺めている。
私の視線に気づくとあわてたように画面をゲームに変えたりして…。
「はぁ、ちょっと買いすぎたかなぁ」
ある日の買い物で特売のために少し量が多くなってしまった。
一袋には収まったもののペットボトルなど重さもそこそこだ。
マンションのエントランスでエレベーターのボタンを押してバッグレストに荷物を置いて少し腕を休める。
「こんにちは」
ふと後ろから声をかけられて振り向くとお隣さんがいた。
「こ、こんにちは」
ちらっと私の荷物を見る。
「今日は荷物多いですね」
普段しない会話に心拍数があがってしまう。
「あ、はいちょっと買いすぎちゃって…」
そう言って曖昧に笑って見せた。
エレベーターが近づいたので荷物を持ち上げようとする。
「もちますよ」
突然そう言って荷物に手を伸ばしてくる。
「え…でも…」
「大丈夫です」
タイミングよくエレベーターが到着して扉が開く。
「さ、行きましょう」
そう言って彼は私をエレベーターの中に促す。
そして私たちの部屋の階のボタンを押す。
「あ、ありがとうございます」
「いえ…」
沈黙のまま静かにエレベーターは上昇する。
「きれいな髪ですね」
「…!」
「あ、ごめんなさい。僕くせ毛なのでその黒髪がうらやましくてつい」
「あ、えっと…」
「あ!あの気持ち悪いこと言ってしまって申し訳ない」
ポン♪
またまたタイミングよくエレベーターが居住階につく。
「どうぞ」
ドアを抑えて私を降ろしてくれる。
なんだかドキドキするな。
久しぶりにこんなに女子扱いされて…。
私たちの部屋の前まで荷物を運んでくれるお隣さん。
「あの、ありがとうございました。助かりました」
「いいえ、じゃまた」
そう言って彼は自分の部屋に帰っていった。
部屋に入って荷物を出そうとして気付く。
あれ?これって…。
袋の中に小さなボールペンが入っていた。
さっき荷物を受け取るときに彼が荷物を少し持ち上げたのを思い出す。
少しひっかけた気がするから穴が開いてないか確認したと言っていた。
その時に彼の胸ポケットに刺さってたのが入っちゃったのかな?
そう思って急いでお隣のチャイムを鳴らす。
ピンポーン。
「はーい」
そう言って顔を出した彼はもうスウェットに着替えていた。
「あ、あのさっきはありがとうございました。そ、それでこれ…」
ボールペンを差し出す。
「あ。これ僕のです」
「あ、やっぱり」
「あぁ、さっき買い物袋に入っちゃったんですね。申し訳ない」
そうやって照れ笑いする彼の背後が気になってしまう。
こぎれいにされた部屋の中心にPCが置かれている。
ちらっと見える本棚にはたくさんの本が見える。
「あ、僕在宅で仕事してて…。ずっと家にいるしあやしいですよね?」
「あ、えっと…」
「はは…。いや奥さんわかりやすいですね」
「ご、ごめんなさい!」
「いやいやいんです。実際あやしい仕事してるんで」
「え?」
「良かったらあがってください」
玄関で立たされたままの私に優しく微笑みかける。
「あ、こんな男の部屋に上がるなんて嫌ですよね…」
「い、いえお邪魔したいです」
思わず好奇心が勝ってしまう。
だって気になってたんだもん。
この人の仕事とか昼間何してるのかとか…。
「ぷはは…。どうぞ」
おかしそうに笑った彼にちょっと恥ずかしくなってしまったけど、促されるままに部屋に上がらせてもらう。
「うわ」
本とUSBがたくさん。
「ぼく、小説家なんです」
「え?」
「しかも、官能小説」
「…!」
驚きのあまり視線を落とす。
そこにはPCの横に置かれた原稿が見える。
『シエスタ—快感—・・モリノ マリオ』
…。嘘
表紙に書かれたその作者の名前に心臓が早くなっていく。
原稿から彼に視線を移すと、はにかんだように笑っている。
「…部屋に入ったこと後悔してますよね?」
いや、なんていえばいいの?
大好きな作家さんがこんなそばに住んでいたなんて…。
でも、あんなエッチな話を作り出している人が目の前にいる。
これって結構危険な状況では…。
そんな考えがグルグルして動けない。
そんな私に一歩近づくマリオさん。
「この話」
マリオさんは『シエスタ』の原稿を指差す。
「瀬戸さんがモデルなんだ」
そうにっこり微笑む。
「え?」
あまりのカミングアウトに戸惑う。
「ずっと気になってたんです、素敵な人だなって。でも人妻じゃないですか?だからせめてぼくの作品の中で乱れてほしくて」
思わず視線を泳がせてた。
「そしたら少し前に聞いちゃったんです」
申し訳なさそうに瞳を伏せたマリオさん。
「ちょっと行き詰ってベランダでエナドリ飲んでたらその…、瀬戸さんのちょっと色っぽい声」
!!!
嘘!
あの日のアレ。
聞かれてたんだ。
恥ずかしくて顔が熱くなる。
「ごめんなさい。でもあれって…あの時間ってご主人いないだろうし、瀬戸さんの声しか聞こえなかったし、もしかしてって思って」
1人でシテたって知られてしまってるんだ。
「…えっと…あの」
「僕こういう仕事してるんで想像力働いちゃうんです」
うろたえる私にかまわずマリオさんはしゃべり続ける。
「もしかして旦那さんとはそういうことしてないんじゃないかって。いやしてもらってないんじゃないかって」
図星だ。
「しかもここ半年ぐらい瀬戸さん浮かない顔してることが多いから、もしかして旦那さんは…」
そこでマリオさんは言葉を切った。
気付かれている。
旦那に浮気されて昼間に一人で自分を慰めているみじめな主婦。
膝から崩れ落ちて顔を覆う。
そんな羞恥心いっぱいの私に反してマリオさんはこう言った。
「そしたら僕の妄想は膨らんでとまらなくなって…」
気付けば私のすぐ隣にマリオさんが寄り添っていた。
「いいにおい」
そう言って髪の毛を触る。
「『彼女は旦那を思い出しながら自分のアソコをさすってみる。きっと今頃本物の旦那の指はほかの女を楽しませている。そう分かっていても彼女は遠い昔旦那がしてくれていたように自分のアソコに自分の指を這わせる』ねぇどう?」
そう言いながら私の肩をそっと抱くマリオさん。
“いけないこと”そんなことはわかっている。
でも彼の長身な体に包まれたら知らなかった気持ちが体の中心からあふれてくる。
「ねぇどうやって感じるの?最後に旦那としたのいつ?」
マリオさんの吐息が首筋を這いあがってくる。
不精なようできちんと整えられたあごひげがうなじを刺激する。
「『もっと…もっと奥にいきたい…。彼女は泣きながら快感を探すように神経を集中させた』こんなふうに思った?」
マリオさんの作品の朗読はまるで私の心の中を見ているように核心をついてくる。
「僕は、もっと知りたい。瀬戸さんのこと」
唇が触れるか触れないかの距離でささやかれる。
私の体はもう我慢できなかった。
「…麻美」
「え?」
「麻美です…。そう呼んで…」
貴男と同じ名字で呼ばれるのは耐えられなかった。
それは罪悪感なのか、それとも私を一人の女として見て欲しかったからなのかは判らない。
「ふっ…。了解“麻美”」
マリオさんはおだやかな笑顔でそう言ってゆっくり自分の唇を私のに重ねた。
あぁ、なんてやわらかいんだろう。
優しくて暖かい。
「麻美の唇はプルンとしてて僕のに吸い付いてくるみたい」
私はその余韻に浸ってしまう。
するともう一度唇が重ねられる。
気持ちいい。
キスだけでこんなにも。
何度か唇を重ねた後、その隙間から生暖かさを感じる。
「口開けて」
何度か彼の舌で唇をノックされた後そう言われる。
いわれるままにうっすら口をあける。
ぬるっ。
その瞬間に無遠慮にマリオさんの舌が私の口内に滑り込んで歯列をなぞった。
そしてすぐに私の舌を絡めとる。
「ん、ふ」
「人妻のくせに、そんな生娘(きむすめ)みたいな反応して。僕をもてあそんでるの?」
フルフルと首を横に振る。
だってキスだけでこんなに翻弄されてるのは私の方だもん。
しばらく私とのキスを堪能した後にマリオさんは私を抱きしめた。
「僕は官能小説家だからここまでで終わりにしてもこの先の行為は小説の中の麻美にすることができる」
私を抱きしめたまま彼は続ける。
「そう思ってたしそうするのが一番だって思ってる。けど—」
抱きしめる力が少し強くなる。
「やめないで」
私は彼の言葉を待たずにそう告げる。
「いいの?後悔しない?」
私は彼の腕の中でこくりとうなずく。
「もっと私のこと知ってほしい。マリオさんのことも…知りたい」
そう言った瞬間背中が床に張り付けられる。
「僕って結構過激な小説書いてるんだよ」
「知ってる」
「え?」
「私、あなたのファンなんで」
そう言ってくすっと笑うと、マリオさんも微笑んでくれた。
「あっ!」
ほほ笑んだ後いきなり私はシャツのボタンを引き裂いた。
パンパンパン!
はじけ飛んだボタンが部屋の中を縦横無尽に飛び散った。
まるで彼の小説を読んでいるかのような光景に胸が躍ってしまう。
そのおだやかな見た目からは想像できないほど荒々しく急かすように私の胸やおなかや見えてるところ全部に何度も唇をおとしていく。
「あぁ、想像より豊満だね」
そう言って長くてきれいな指で私の体を撫でまわす。
「しかもやわらかい」
満足そうにそういう。
「こっちも確かめさせて」
そう言いながら私のスカートをまくり上げる。
ぴちゃ。
下着の上から彼の指が触れた瞬間私の下半身は卑猥な水音を立てた。
「…!」
恥ずかしさに顔をそむけてしまう。
「すごいね。かわいいよ」
私の恥ずかしさとは裏腹にマリオさんは嬉しそうに満足そうに言った。
「あぁ、僕の指まで熱くなるくらいの蜜があふれてる」
そう言って濡れてしまった彼の指を眺める。
「もったいないな。直接触るね」
いうより早く下着をはぎ取る。
「あん!」
触れられただけで電流がはしったみたい。
「僕のが早くほしいのかな?すごくひくひくして誘ってるよ」
こんなに言葉にされながらセックスしたことないから恥ずかしくて仕方ない。
「ねぇ一つ分かったよ。麻美は恥ずかしいって思うと感じちゃうんだね」
確かに、羞恥心が快感に変わっている気がする。
「Mなのかな?これは楽しみだなぁ」
そんなことを言うマリオさんの変態的なまなざしにも反応してしまう体が恨めしい。
「麻美も僕のこと知りたい?」
どんなことを意味しているのかも分からずとりあえずうなずく。
「そっか」
マリオさんは私から少し離れるとスウェットのズボンと下着を脱ぐ。
「ほら見て」
目の前にマリオさんの猛りが差し出される。
「まだちょっと足りないかな」
草食系の奥にある肉食の瞳の輝きにたじろいでしまう。
「もう少し大きくなったら麻美の中に入れるよ。ほらどうしたら大きくなるかな?」
そんなことを言われてどうしていいかわからずおそるおそる触ってみる。
「ふふ。くすぐったい。そんなんじゃだめだよ」
「…」
「僕の小説ではね麻美は欲求不満で目の前のチンポにむしゃぶりつくんだよ」
「!」
そんな。
それをしろっていうの?
「恥ずかしがらなくて大丈夫。ここには僕と麻美しかいないから」
そう言ってずいっと私の顔の前にモノを突き出す。
ゴクっと唾をのむ。
「ほら、欲しいんでしょ?僕のチンポだよ」
マリオさんの言葉は不思議だ。
マリオさんに言われると本当に私はこのチンポが欲しくてずっとずっと飢えていたように感じてしまう。
私は目の前のソレを掴んで口の中にほおばった。
「うっうっ」
マリオさんが声をもらす。
私の口の中でマリオさんは質量を増していく。
その何とも言えない充足感。
私は夢中でむさぼる。
「あっいいよ麻美。もう」
苦悶の表情でマリオさんは私を彼のモノから引き離す。
マリオさんのモノと私の口の間に私の唾液が糸を引く。
「今度は麻美の中でかわいがって」
まだ放心状態でされるがままに足を開かれてひだを開かれる。
とろ。
ただそれだけの行為に私の蜜口はよだれを垂らす。
「今あげるからね」
マリオさんは私の目を見てそう告げて、最大限に大きくなったモノをゆっくりと私の中に沈めていく。
「んん…」
ぬるぬるとゆっくり私は彼のモノを受け入れていく。
限りなく密着していく二人の体に満足感から安堵の吐息がもれる。
「はぁ…」
「ん?気持ちいいの?」
うんうんと首を縦に振る。
「僕も…すごく…いい」
マリオさんは私の中を味わうようにゆっくりと腰を動かしている。
たまらないほどねっとりと私の中を絡めとっていく。
「麻美は1人でこの体を慰めていたんだね。もったいないなぁ」
「いや…恥ずかしいからそんなこと言わないで」
「あんな声聞いたら僕はずっとたまらなかったんだ。いっぱい味わうよ」
「まり…お …さん」
覆いかぶさってきた彼の背中に跡がつくほど爪を立てて抱きしめた。
「あぁすごい、締まる」
苦しそうなマリオさん。
少しずつ動きが早くなる。
「一緒に…。一緒にイキたいよぉ」
「いいよ、もうイキそう?」
そんな些細な優しさに、同じ年の貴男にはない年上の余裕を感じて身をゆだねてしまう。
「うん、あぁ。もう来ちゃう」
秘部と秘部を激しくぶつけあってこすりつけるようにグラインドさせる。
「あぁ、マリオ!」
「麻美!」
「「あぁぁぁぁ!」」
二人の絶頂を告げるように私の蜜口からしぶきが飛び散る。
床に横たわっていた私はゆっくり体を起こす。
「…麻美。帰るの?」
「うん」
「そっか、洋服どうしよう?」
あぁそうだ、ボタンはじけちゃったんだ。
「これ着てって」
そう言ってさっきまでマリオさんがきていたTシャツを渡される。
無地のグレーのTシャツ。
これなら貴男も気付かない。
そう思ってそでを通す。
あ、マリオさんの香り…。
思わず笑みがもれる。
「どうしたの?嬉しそう」
「ううん、なんでもないです」
下着とスカートをはいて立ち上がる。
マリオさんも体を起こして壁にもたれかかった。
彼の前にしゃがんで、
「実は私携帯小説にはまってて、モリノマリオのファンなんです」
改めてそう告げる。
彼の目が大きく見開かれた。
でもすぐににっこり笑って
「マジか…。嬉しいけどはずいな…」
と言った。
「ねぇ、また私をモデルに書いてくれますか?」
「こちらこそ、実践込みでよろしくお願いしたいよ」
そう言って私の髪をなでる。
私たちは一度唇を重ねた。
そして私はまた専業主婦“瀬戸 麻美”に戻って、何もなかったかのように部屋に戻る。
今夜もまた貴男の帰りは遅いようだ。






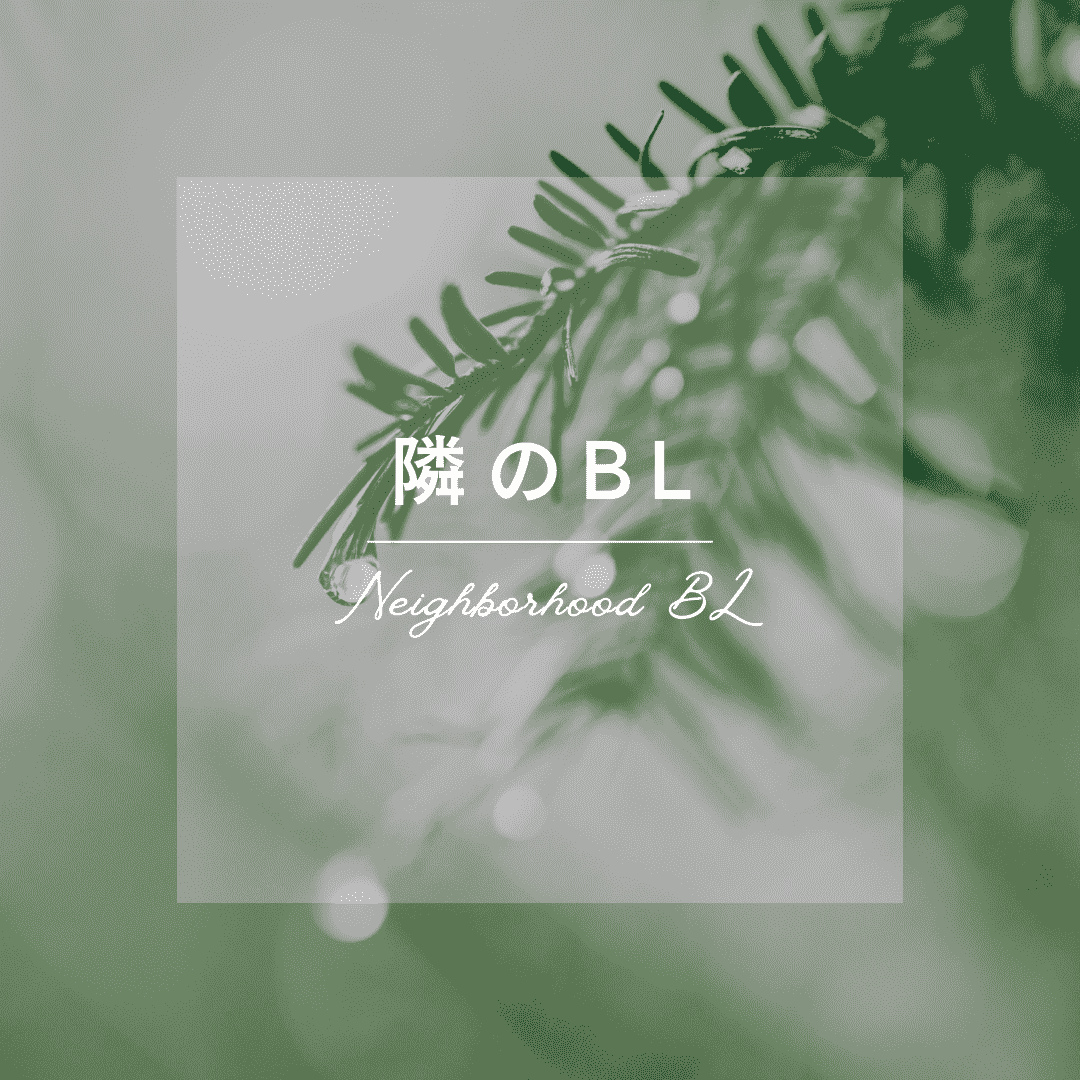
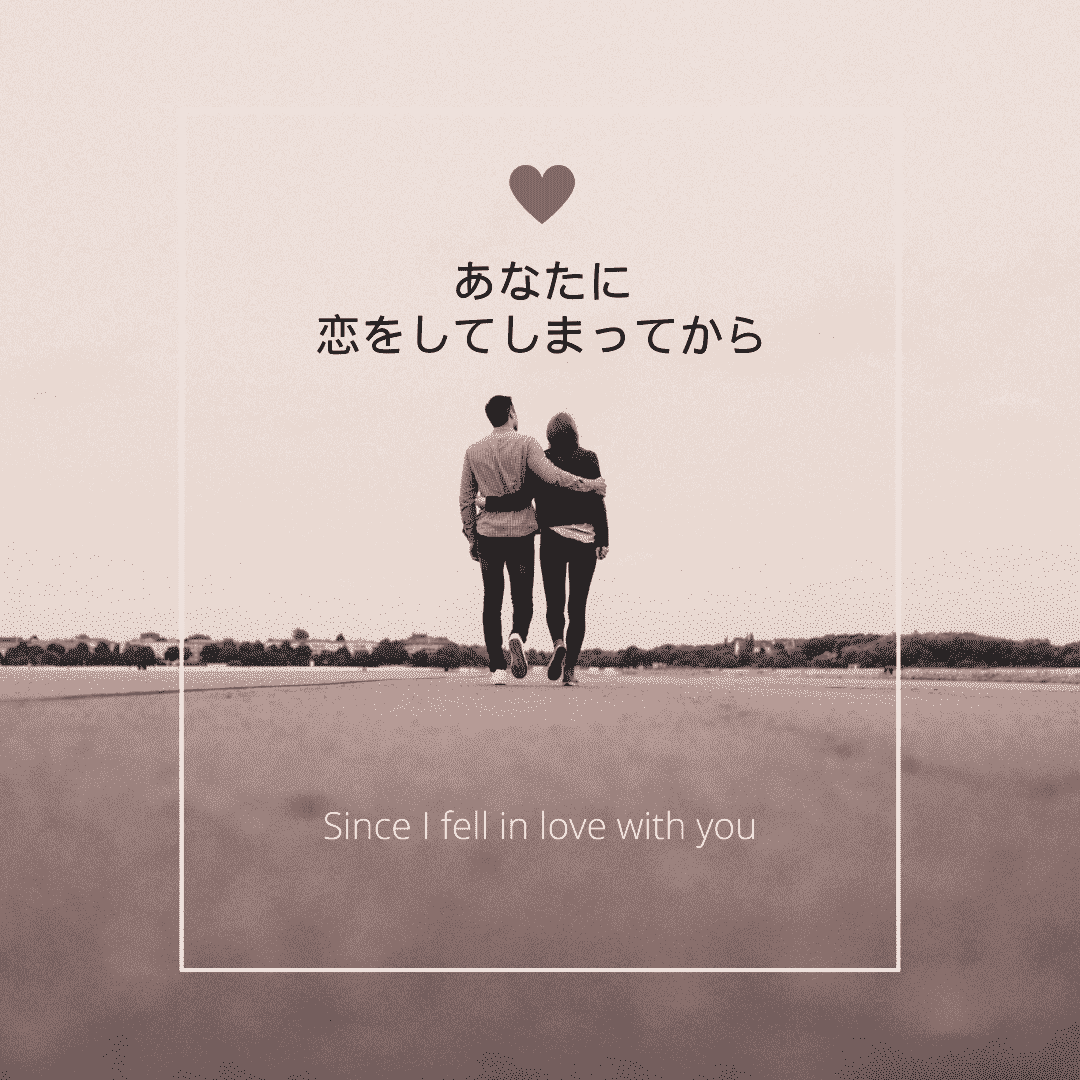



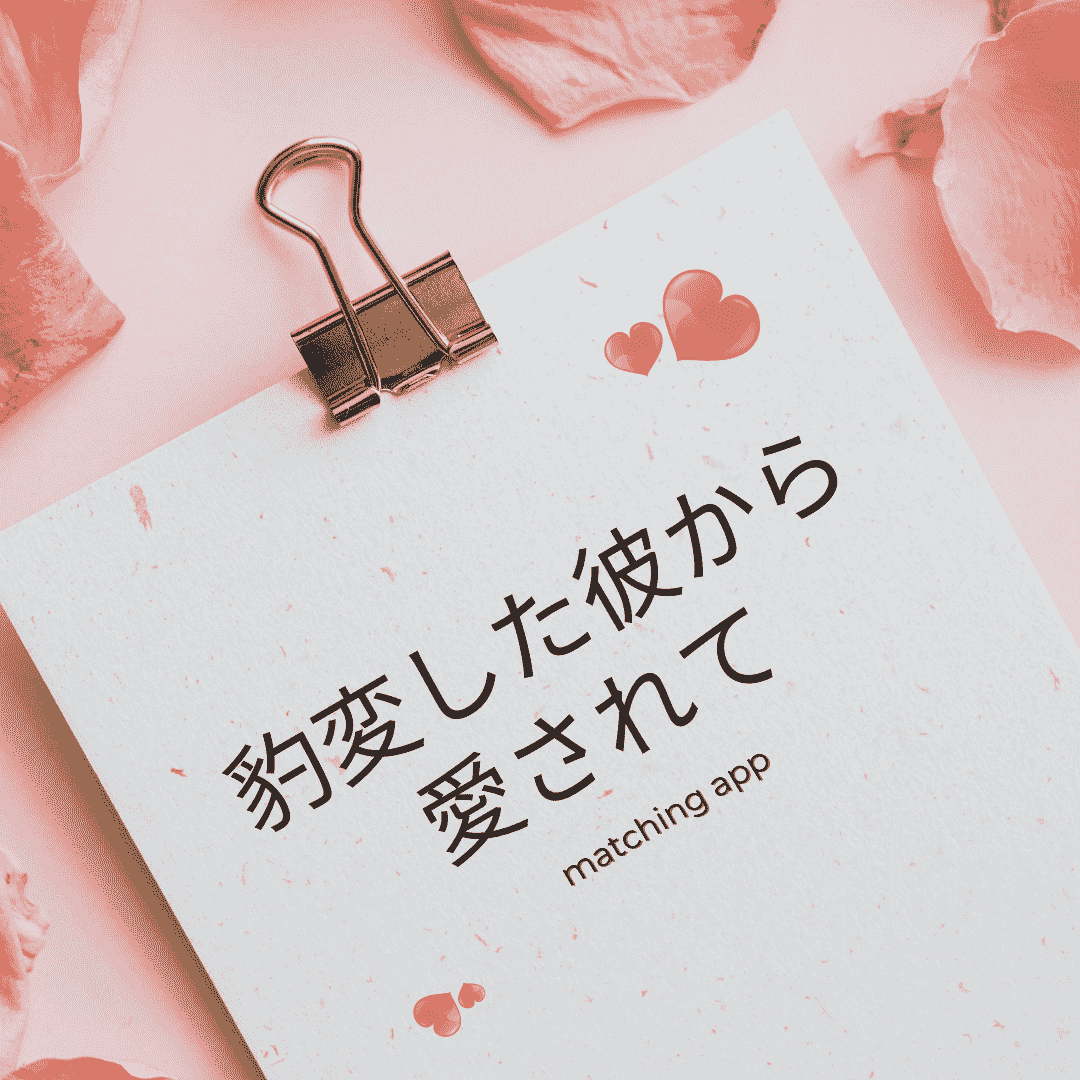

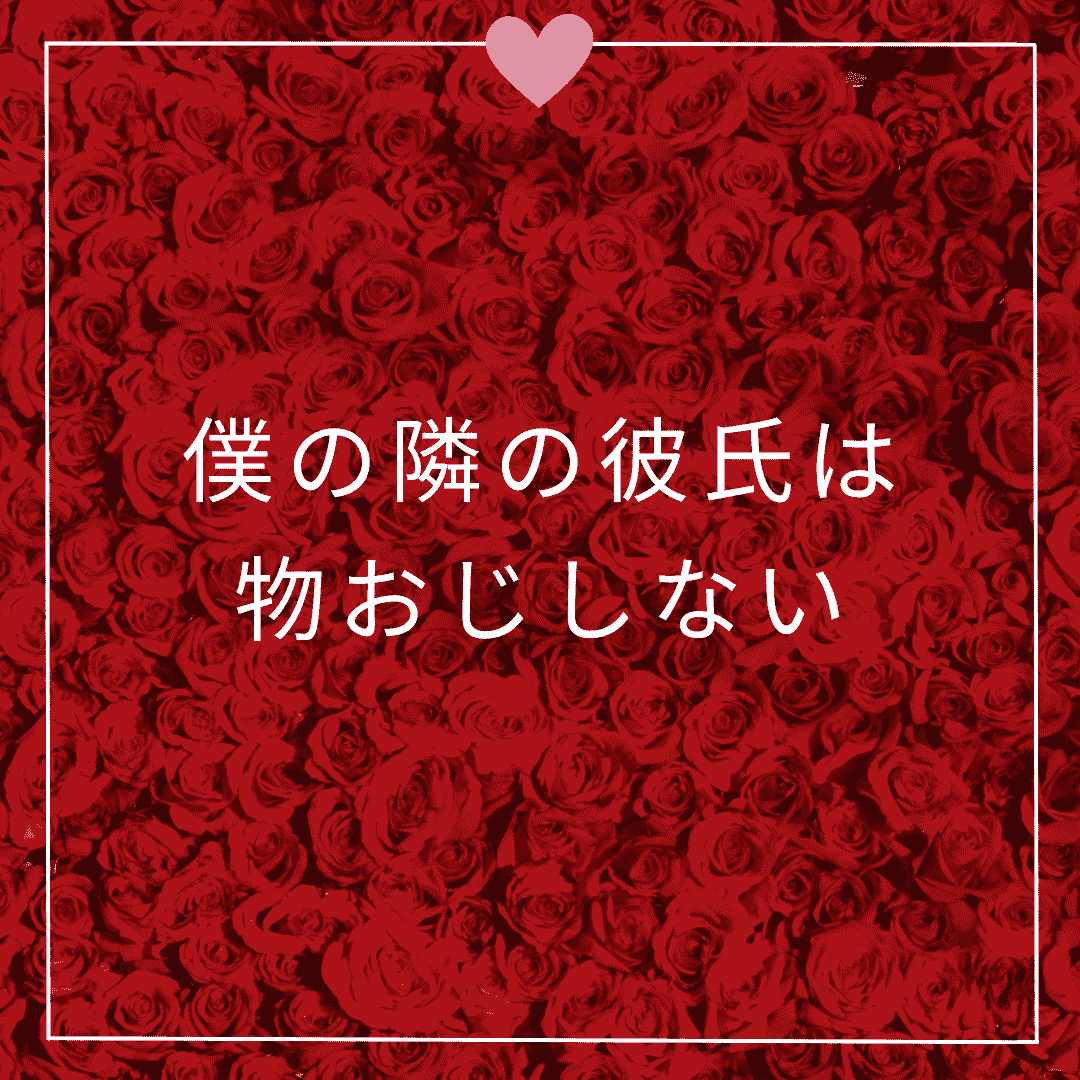
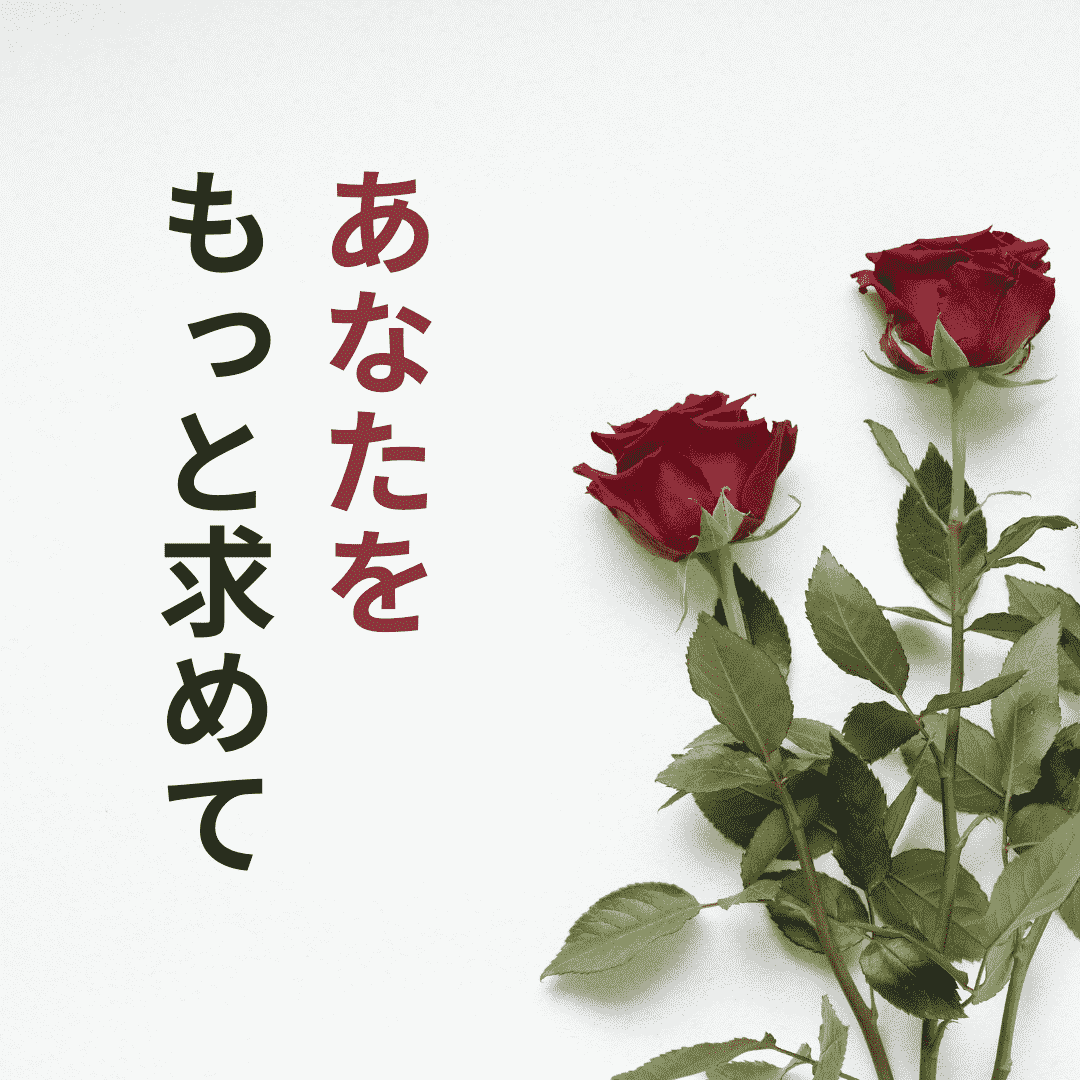





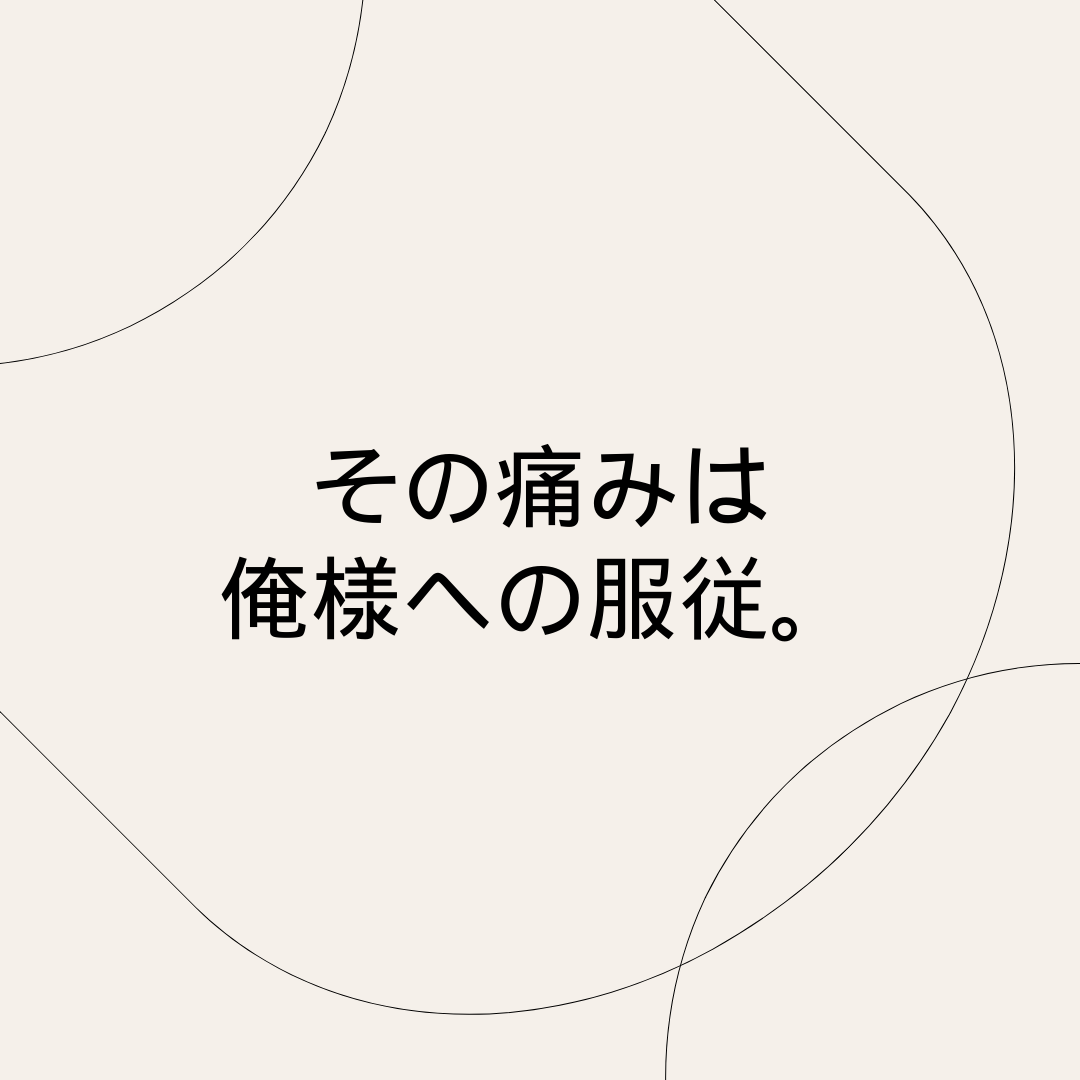

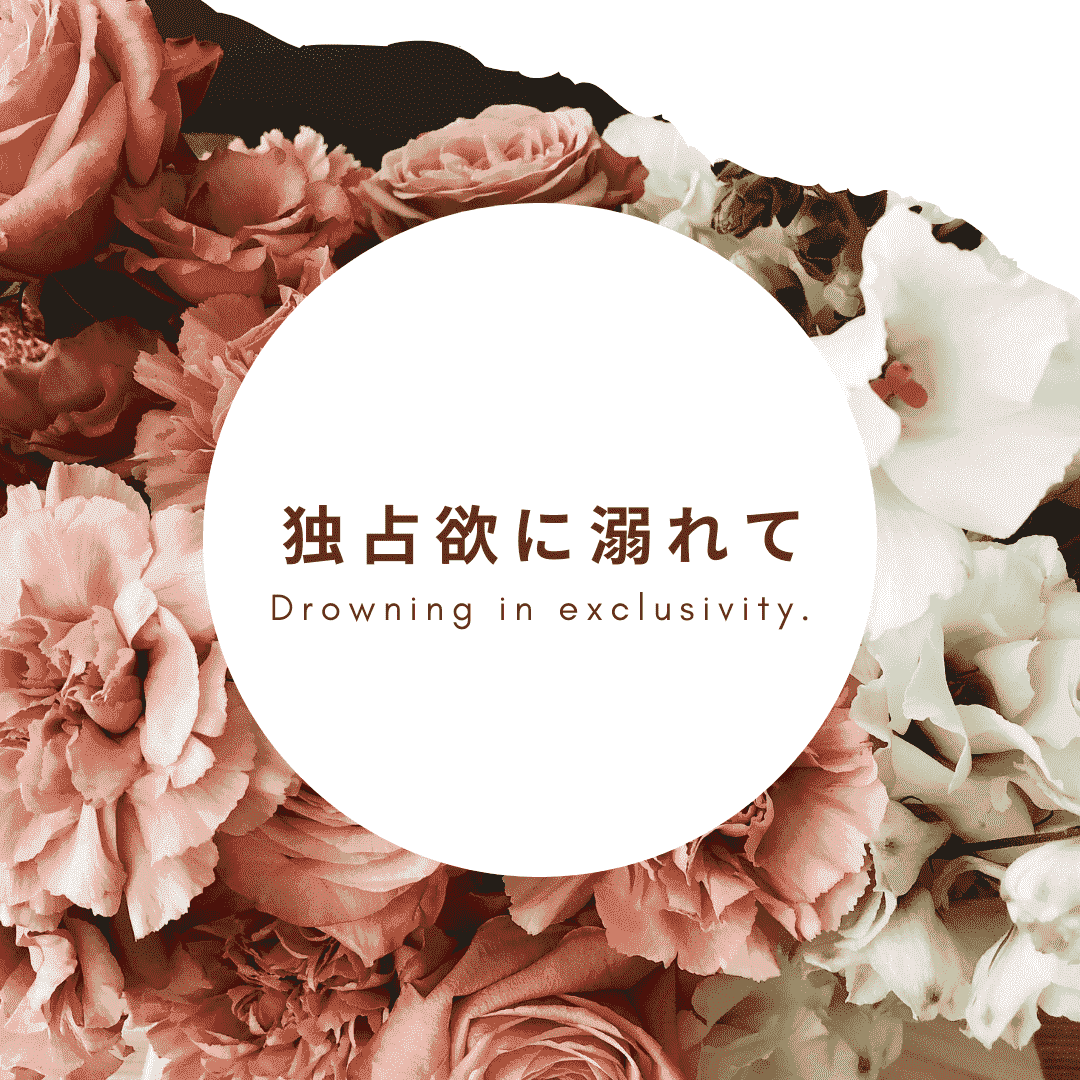
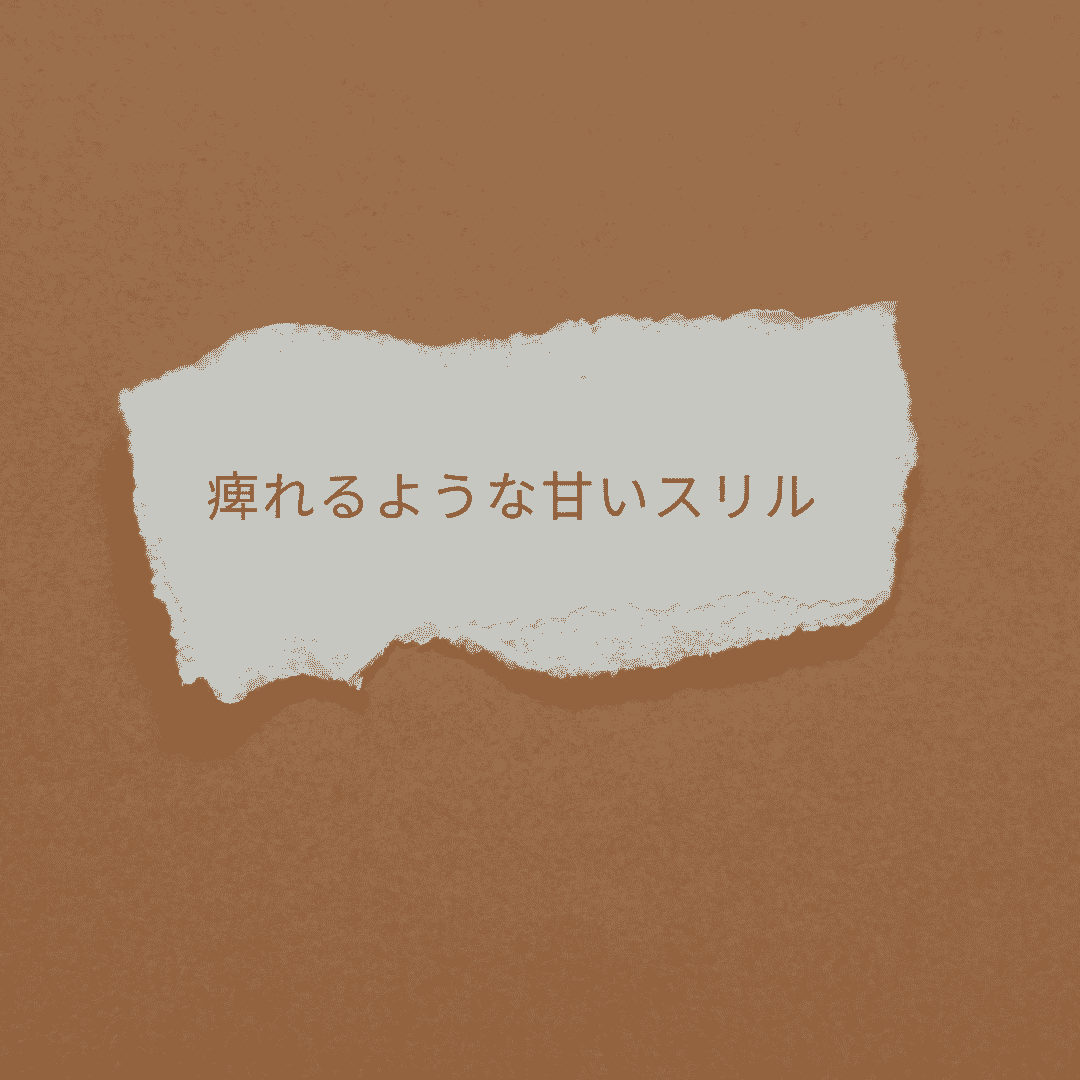


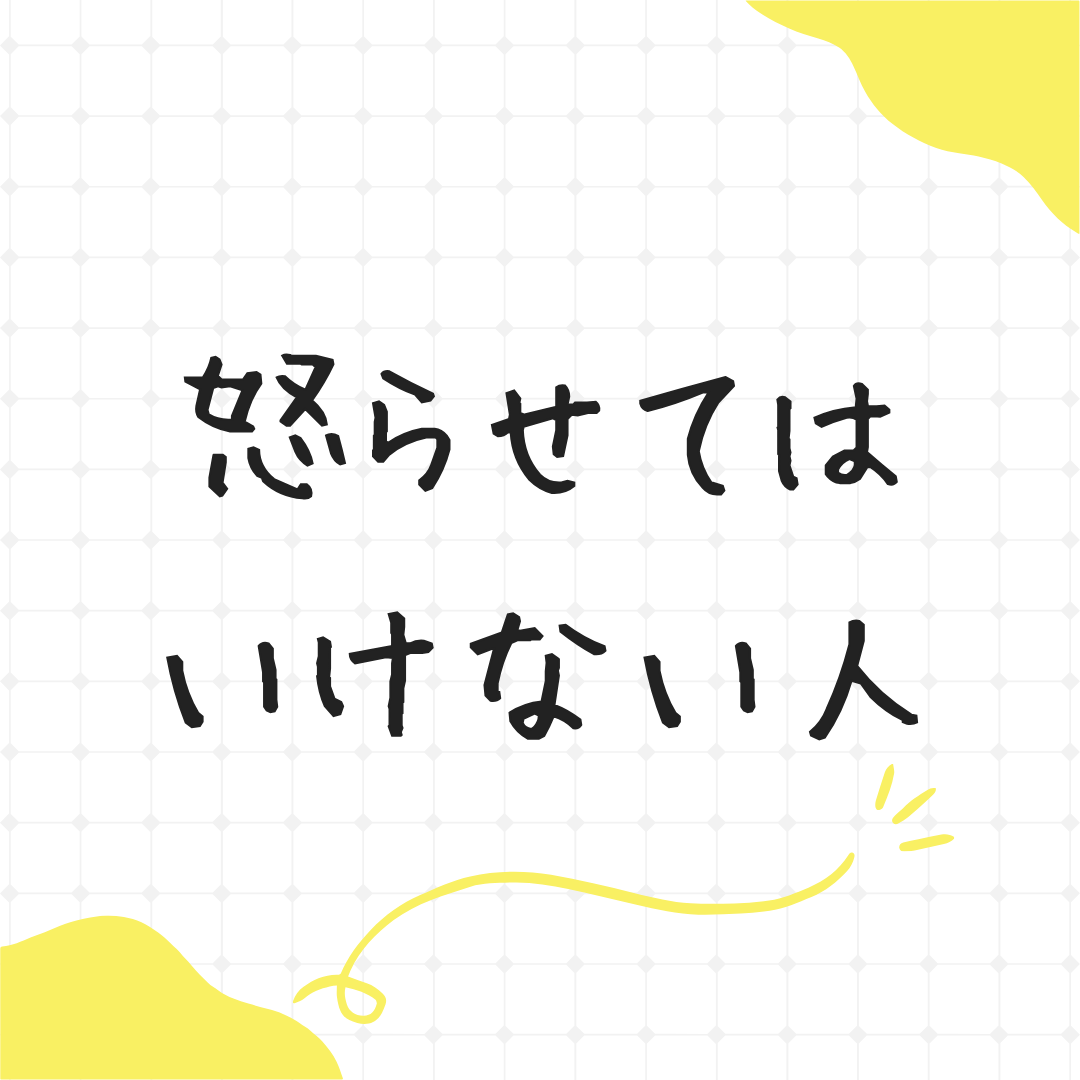

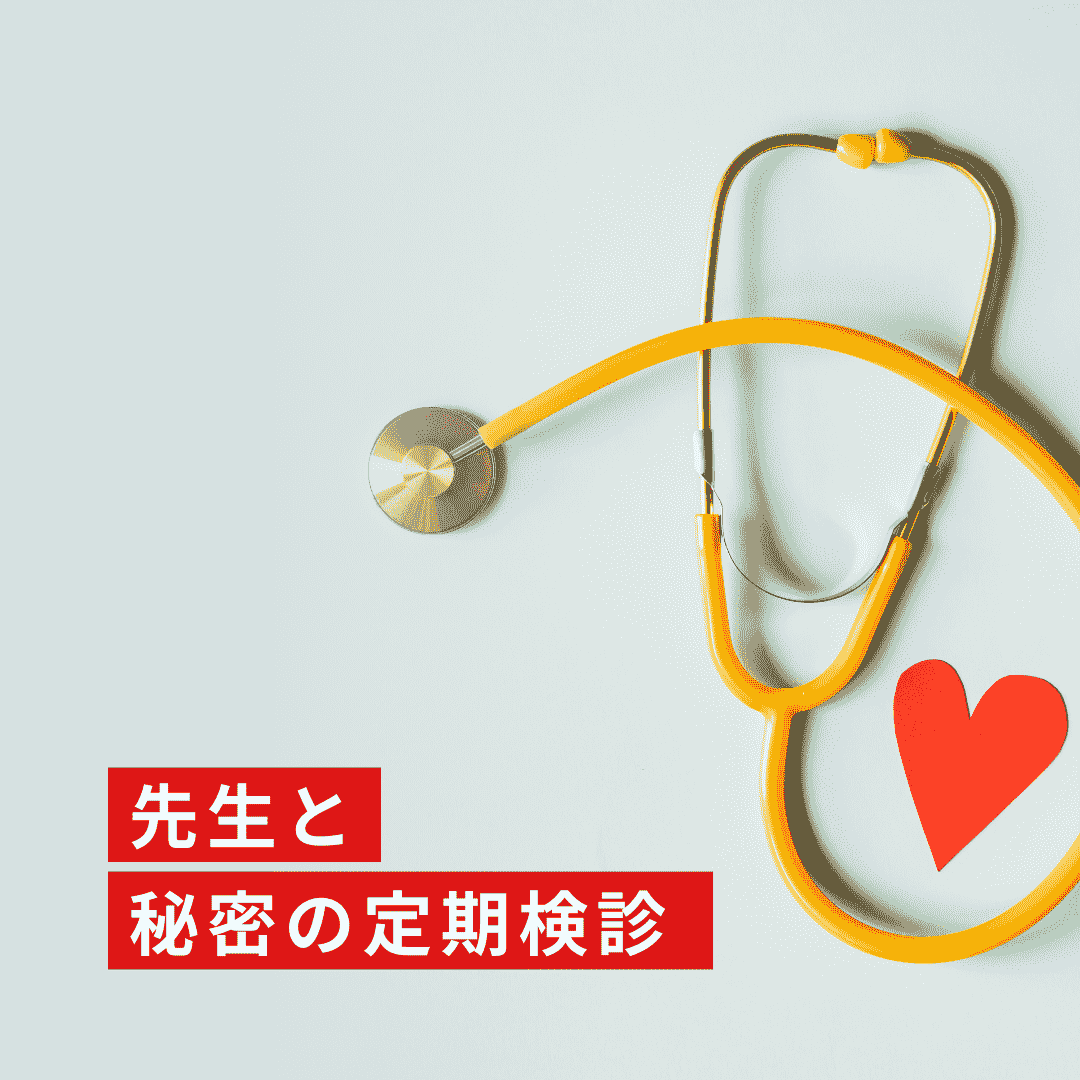
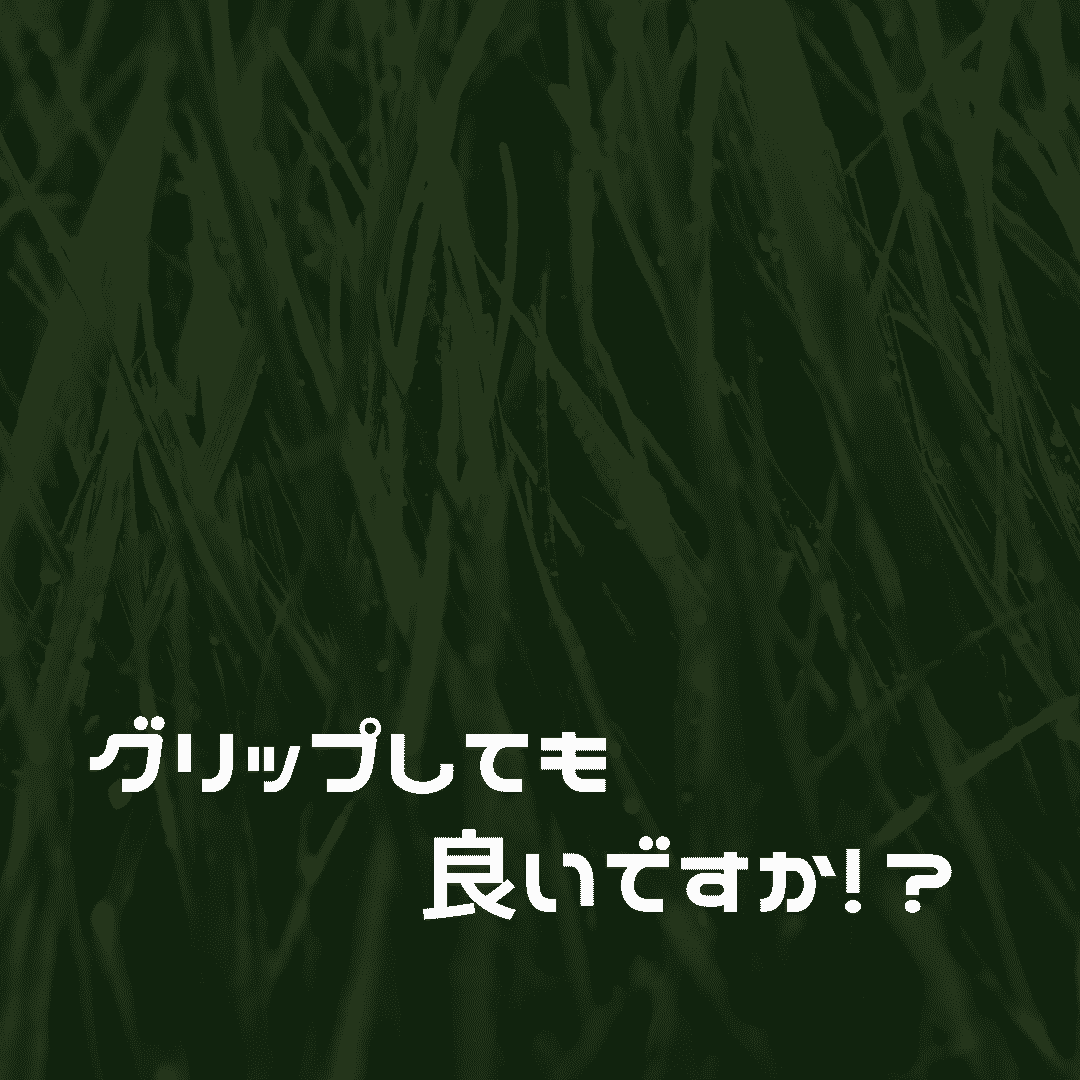
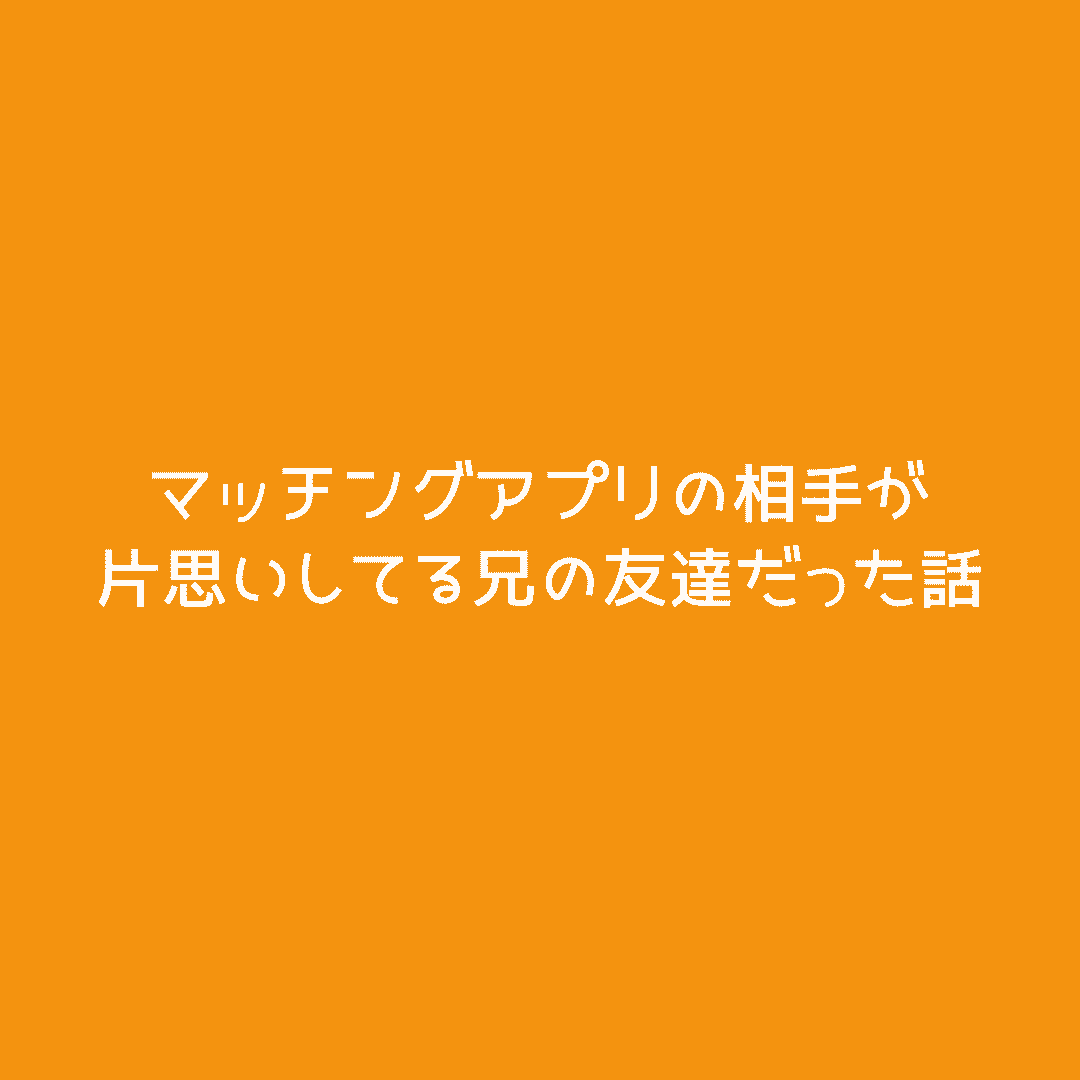
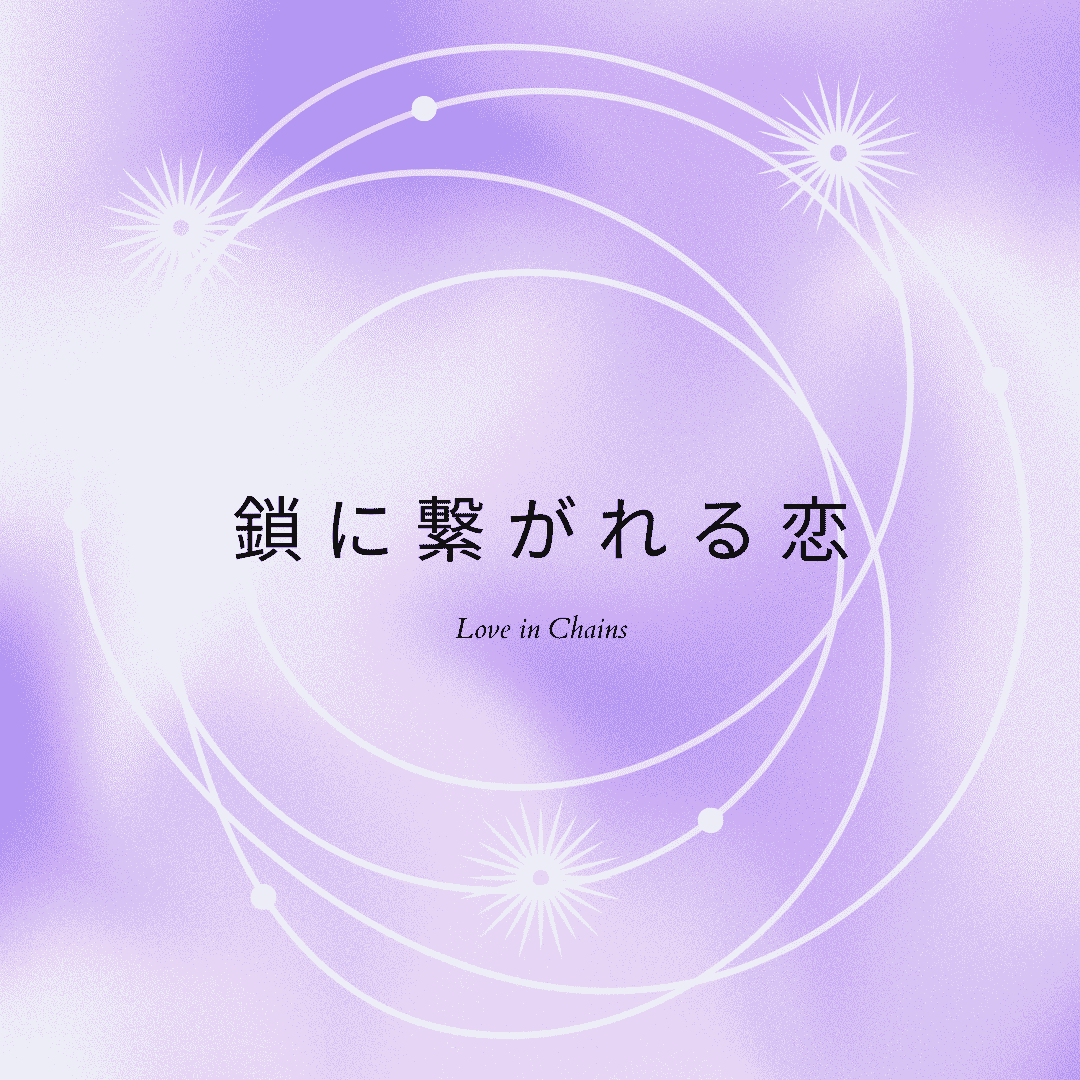


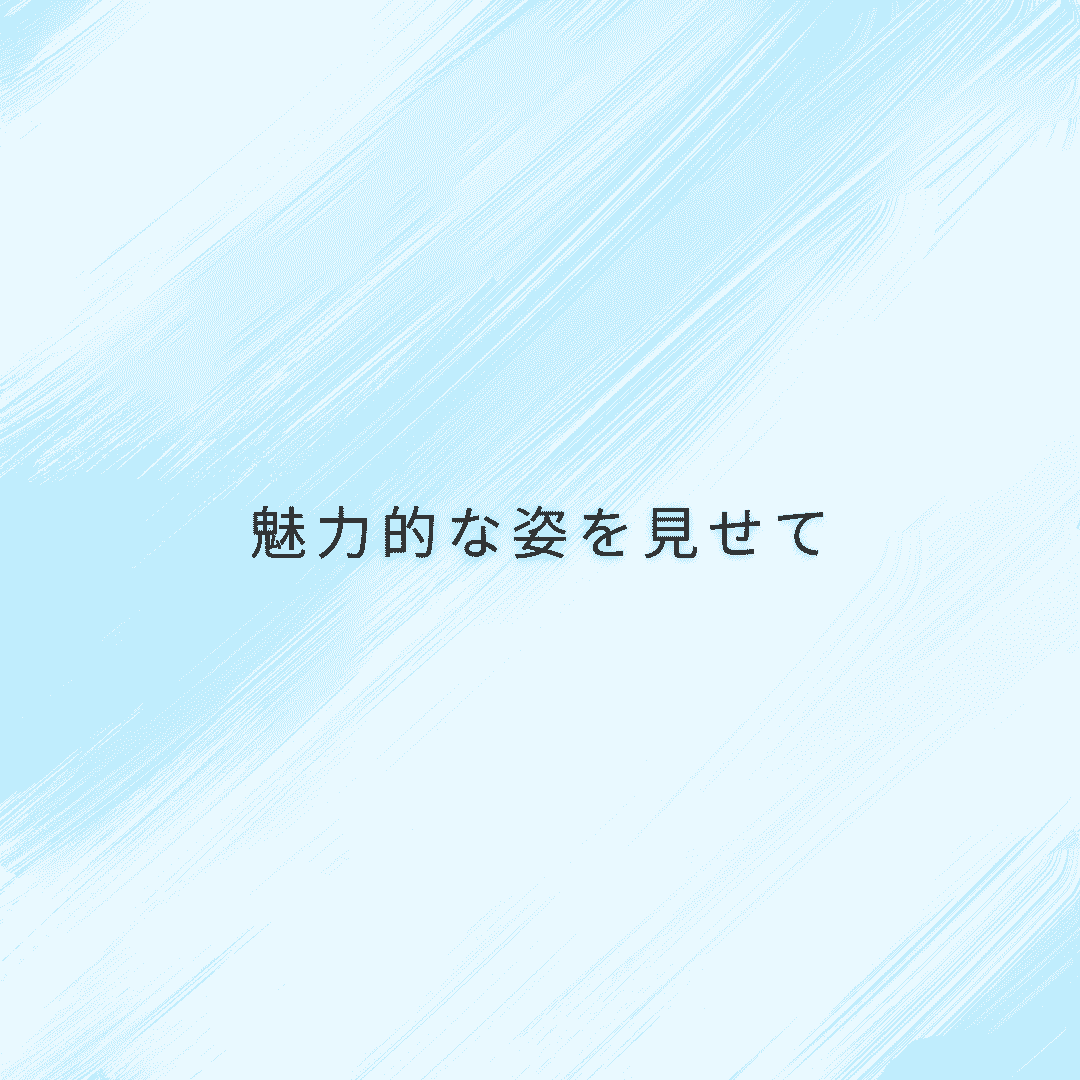
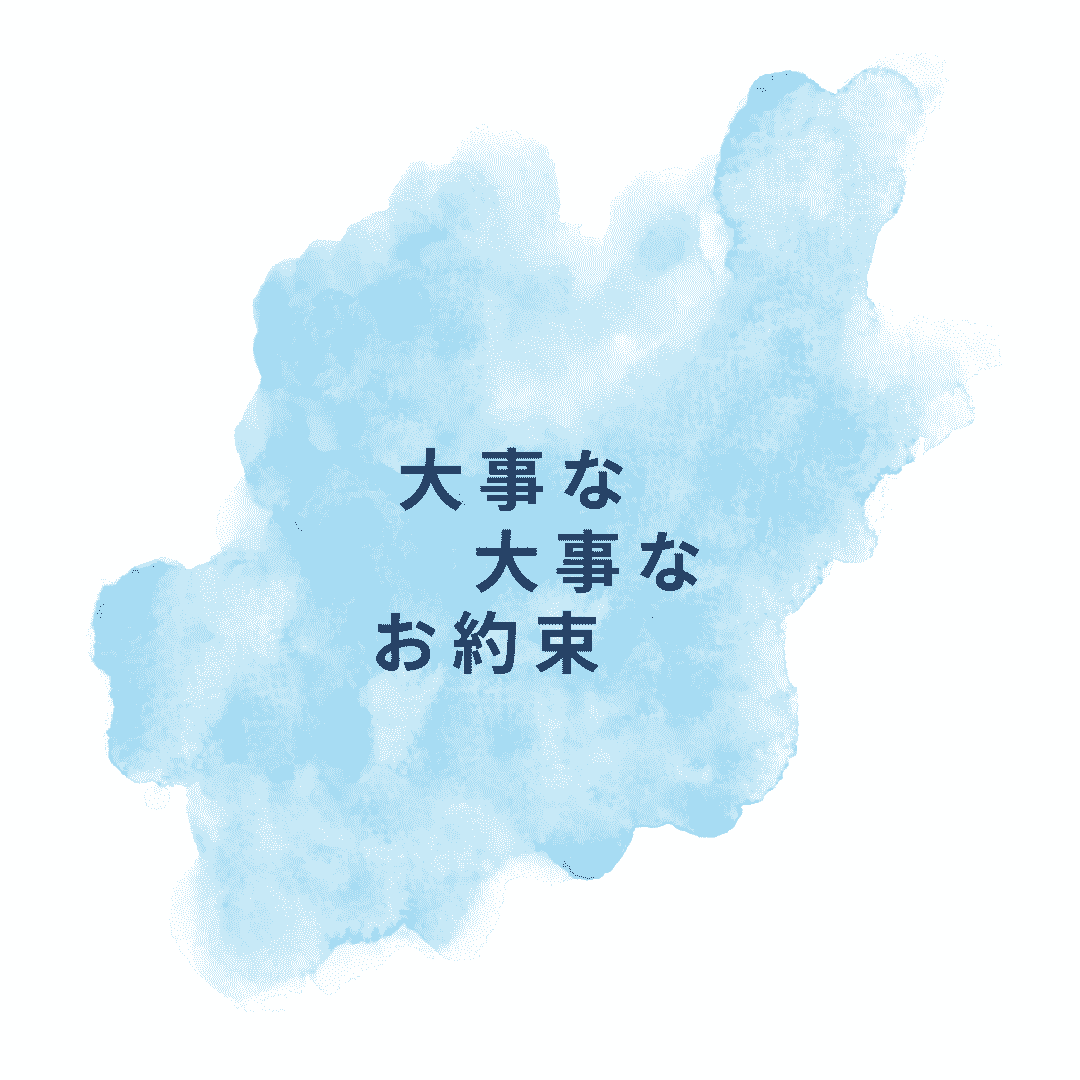


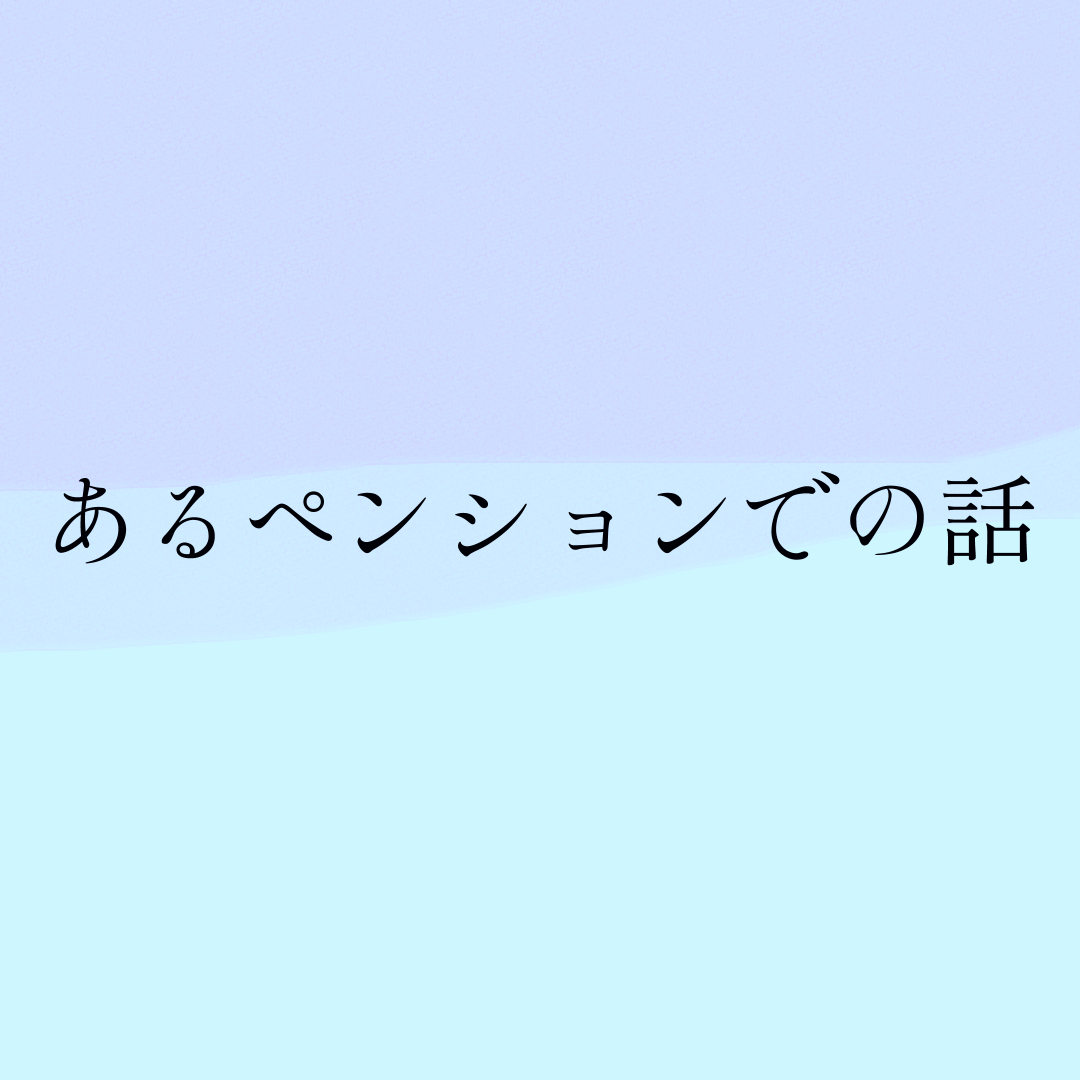
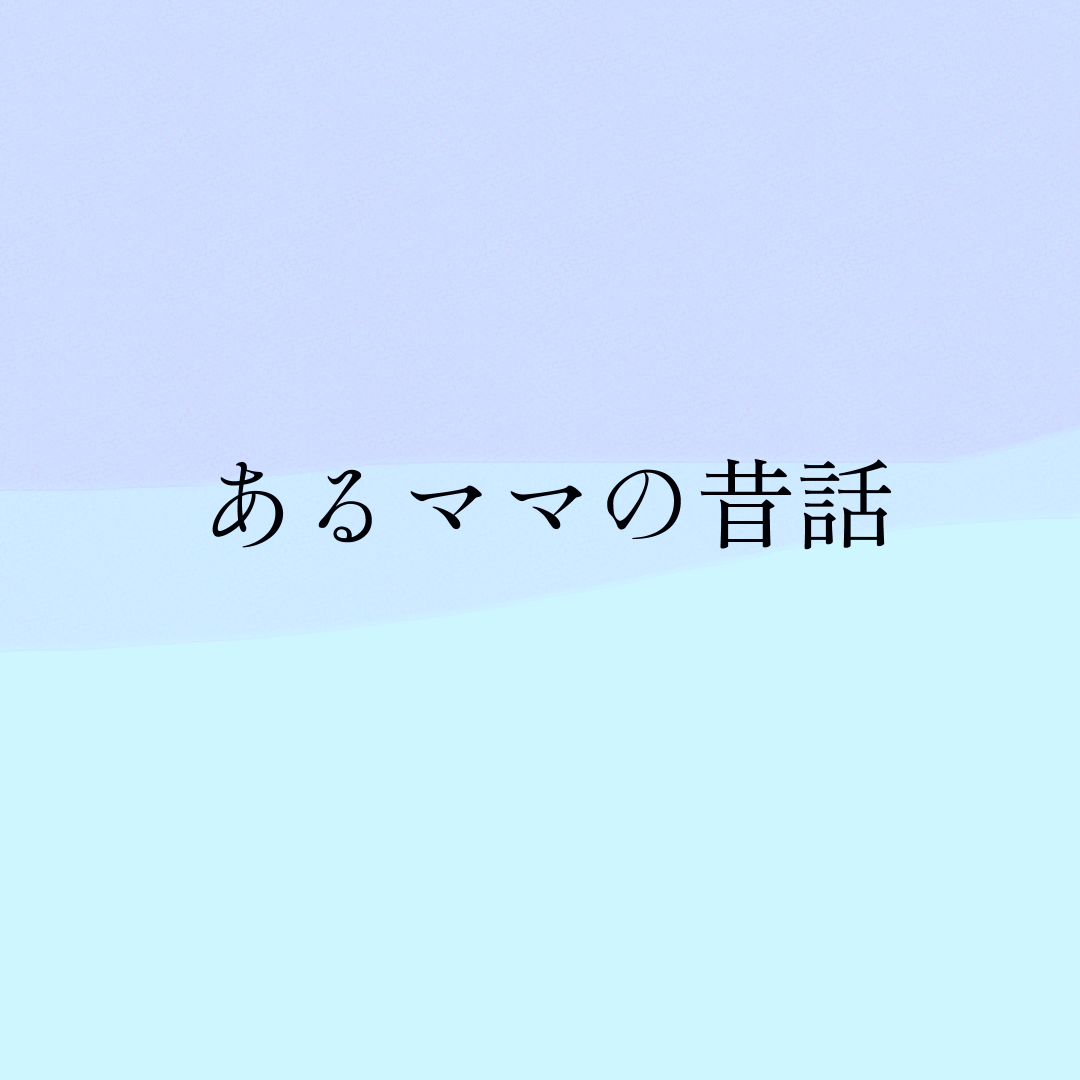
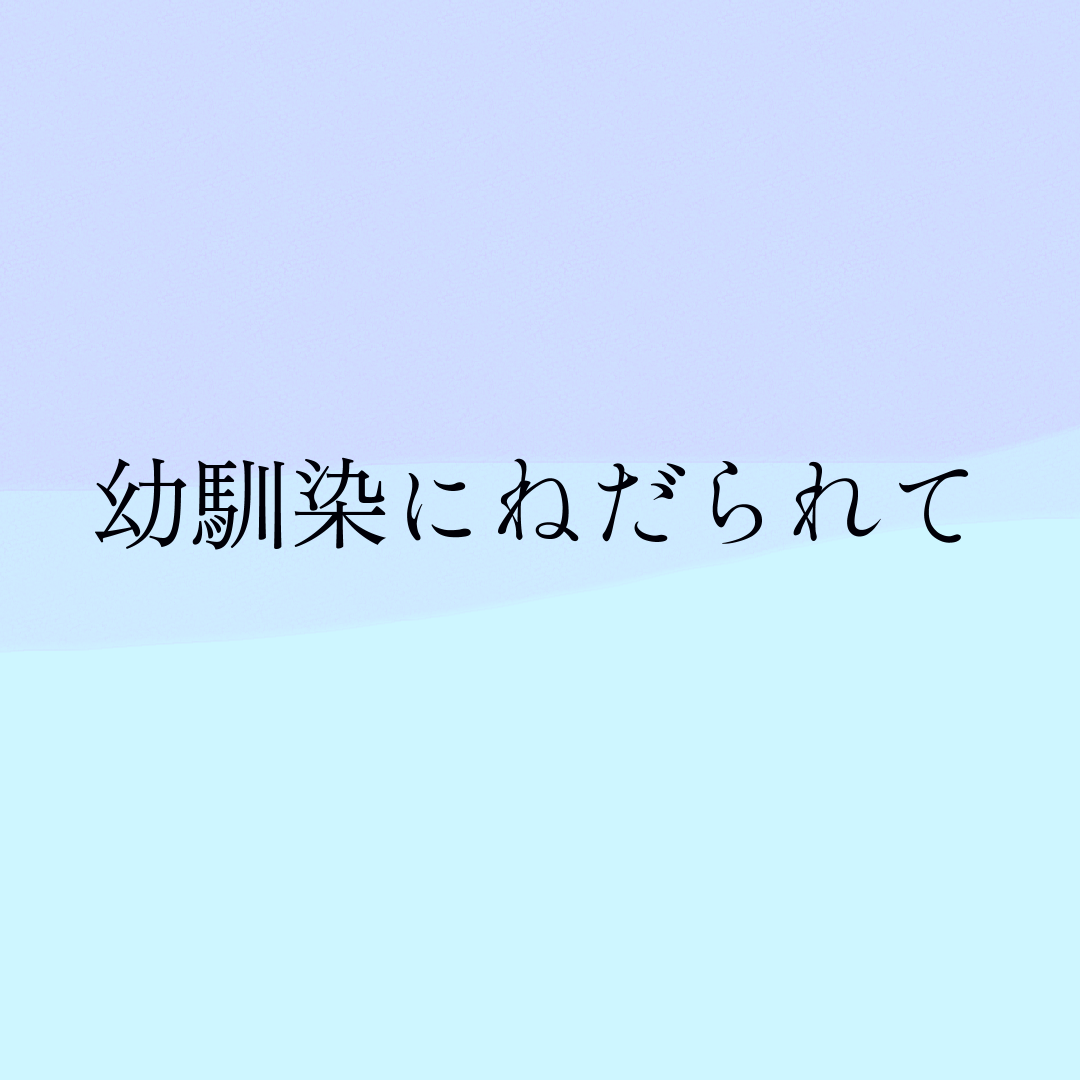
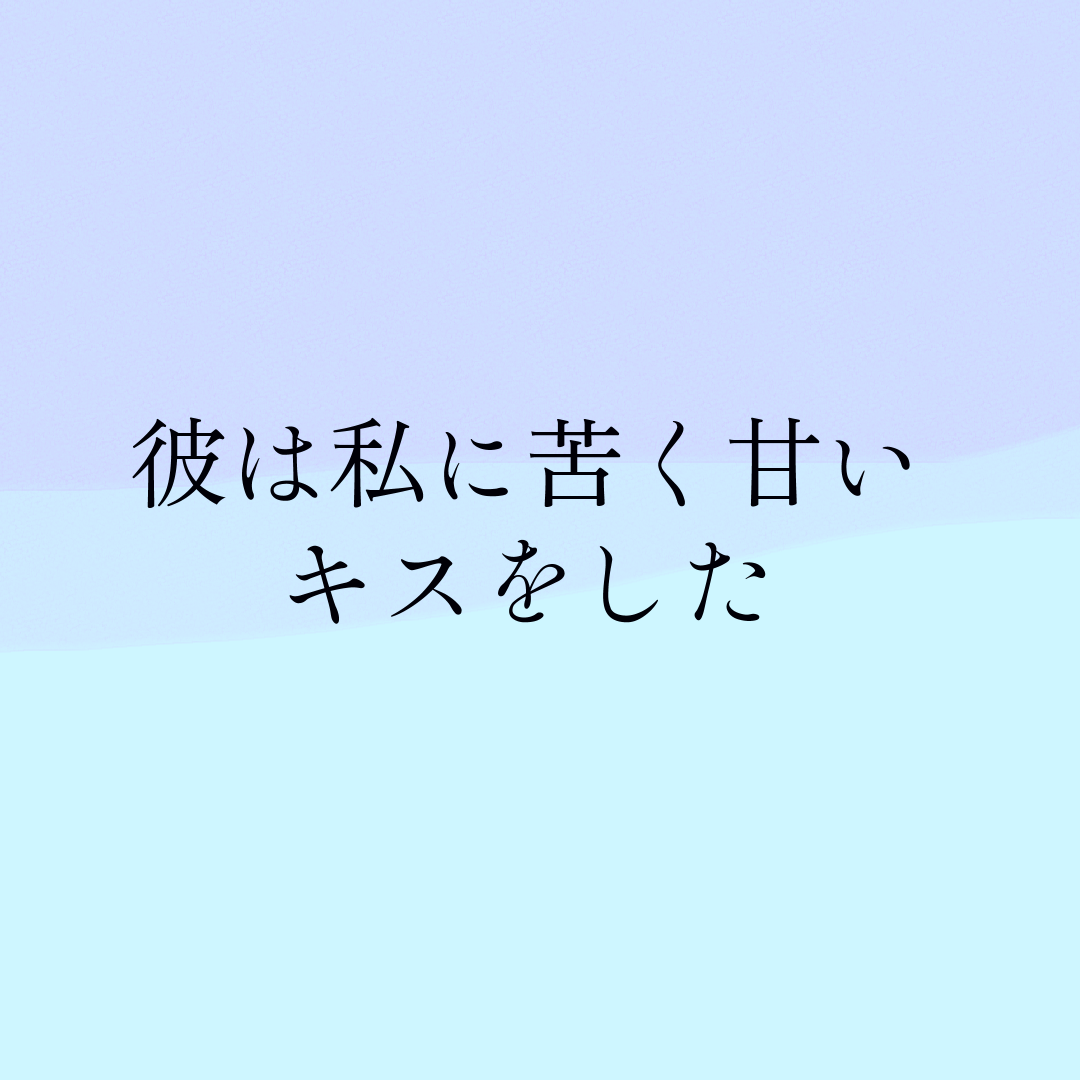
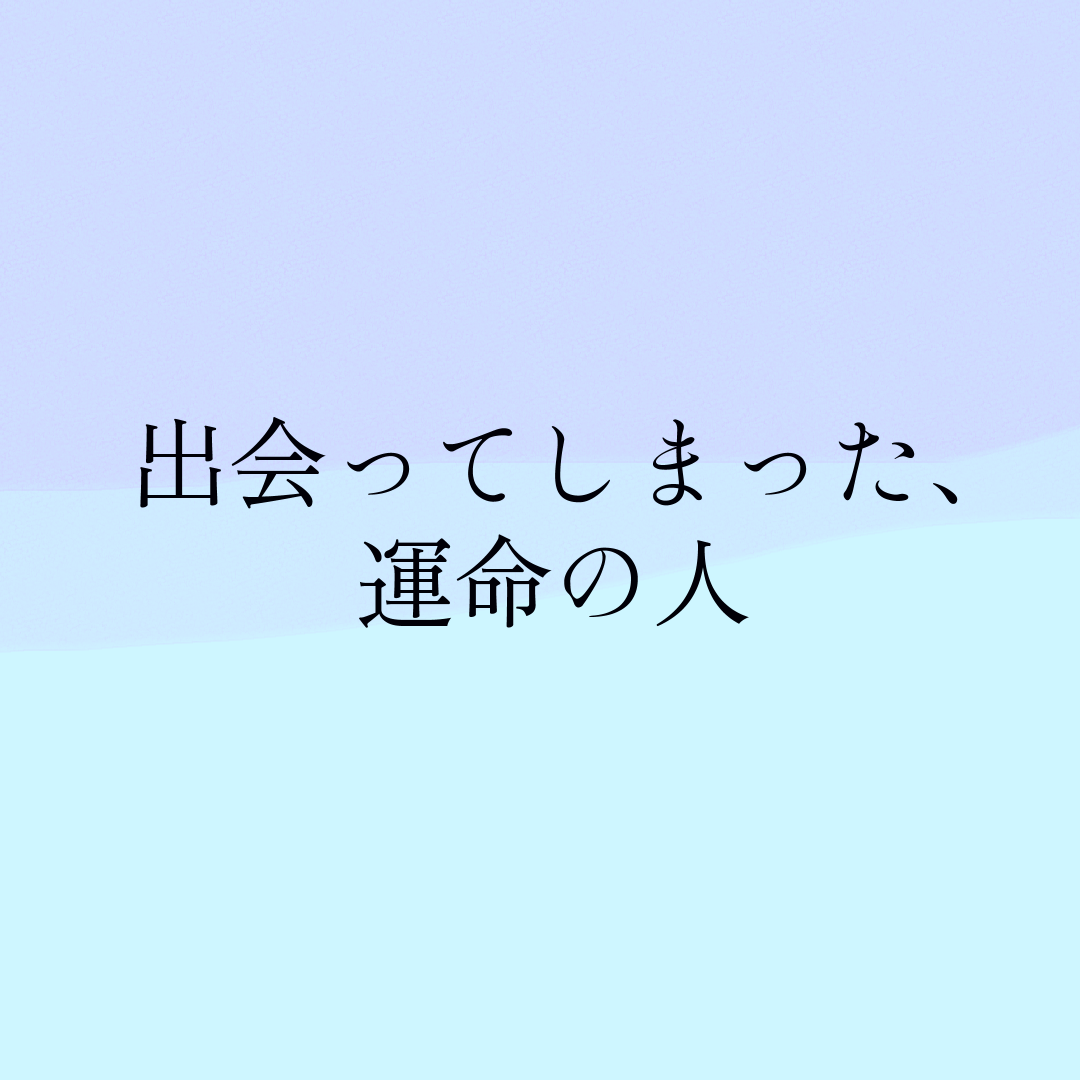
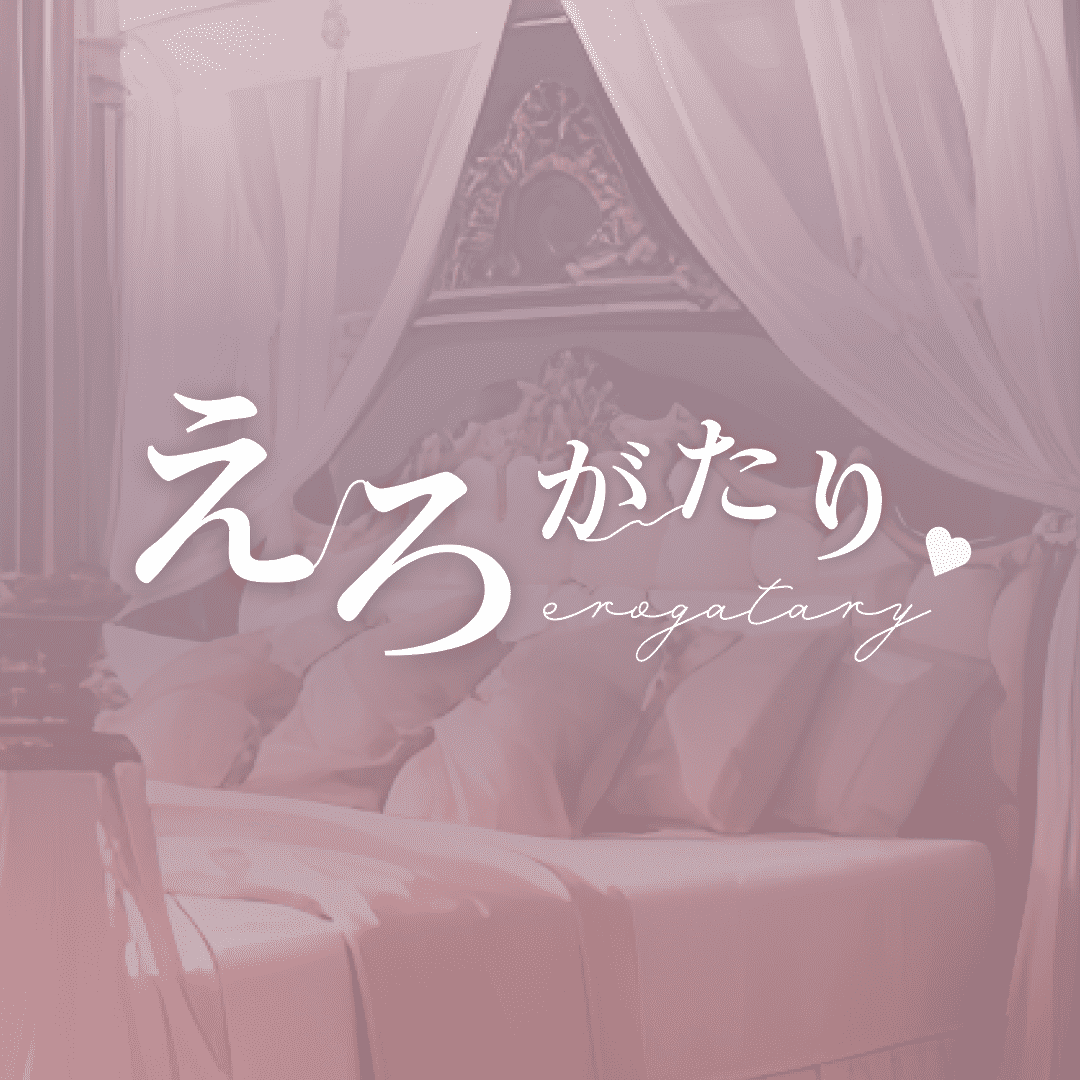
コメント