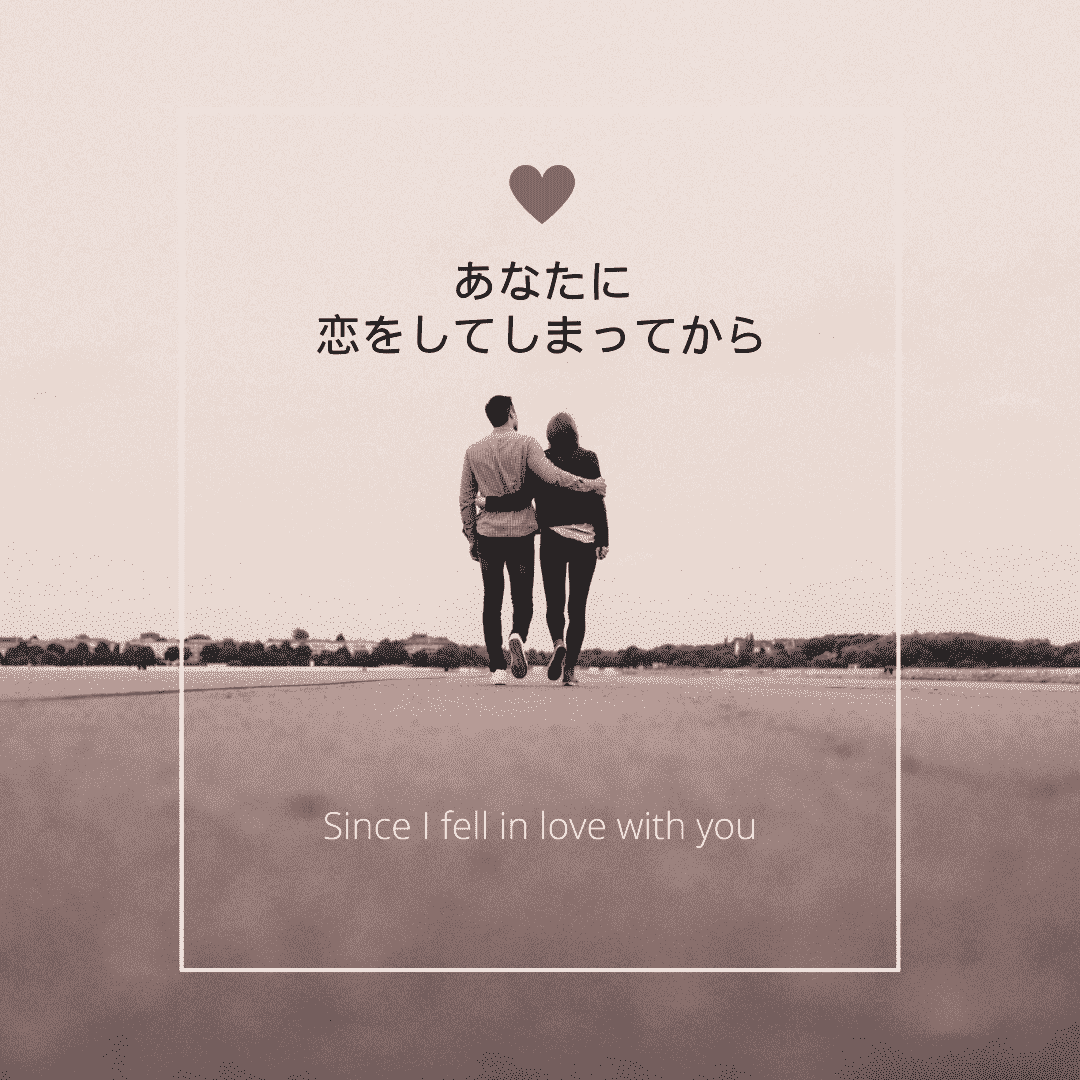
0
あなたに恋をしてしまってから
「おい、そろそろ閉まるぞ」
パシャパシャと水面を叩かれ、思わず顔を上げた。
水面から身を乗り出して、プールサイドに上がって、ゴーグルを外した。
小さくため息を吐いて、私を見つめてきた彼の横を通り過ぎようとした所で腕を掴まれた。
「なんで無視するんだ?今日はやけに俺のことを無視するじゃないか」
彼の腕を振り解こうとするが、男の力に女の私が勝てるはずもなく、目一杯腕を振りあげようとしてもそれすら簡単に止められた。
勘の良い彼だからこそ、気づかれたくなかったし、気づいて欲しくなかった。
「別に…無視なんかしてないわよ。私帰るんだから早く離して」
「ほら、機嫌悪いだろ。なんだよセフレには話せないってか?」
彼の言葉に顔に熱が集中して、すぐに周囲を見渡した。
こんな公然の場所で、彼は一体何を口走っているのか。
慌てた私の姿を見て、彼は面白い玩具を見つけた子供のように、また「セフレだからか」と先程よりも声を上げて言い始めた。
流石に周囲に何か聞かれても困ると、急いで空いていた手で彼の口元を抑えた。
むぐぐと、声を出せずにいる彼だったが、彼が私の手のひらを舐めたことで、すぐに終わってしまった。
「何するのよ!舐めるなんて!」
「お前の体舐めまわしたことあるんだから今更だろ?」
勢いよく口元から手を離して、汚いものを見るように手のひらを睨んだ。
確かにセフレだったが、それは少し前までのことだ。
それは彼が結婚する前の話で、世帯を持ってからは、一切体を重ねたことも、こうやって会って話すことも絶っていた。
「それになんでアンタがここにいるの?もう大会には出てないんだから、別にここに来る理由はないでしょ」
「それもそうだが、俺は誰かの為に大会には顔を出しているぜ?意地っ張りで、恋人にも振られて、大会でも賞を逃した奴の為にな」
腰に手を当てて、さも当然かのように自慢げに語り出した彼にいつものように、何かを言う気力などなかった。
全てが本当のことなのだから。
一世一代の大会に備えて準備を進めてきたのに、前日に結婚を考えていた同棲相手に振られ、その挙句。
いつもなら出来ていたはずの種目を失敗して、盛大に大恥をかいたのだ。
しかもそれを目の前の彼に見られていたということが、最悪なことだった。
恋人のことはきっとコーチ辺りが彼にペラペラと話でもしたのだろう。
小さくため息を吐き、彼を強く睨みつけてトンッと強く胸を押した。
「だったらなに?笑いに来たの?セフレだったアンタにそんな資格ないわよね?早く家に帰りなさいよ、可愛い奥さんが家で待ってるんだから」
そう強気に吐き捨てて、腕を振り解こうとした所で、グンと腕を引かれ、そのまま更衣室に連れ込まれた。
周囲には私と彼しかおらず、何を言っても誰も私達を気にする人はいない。
離して、やめて、と非難しても、彼が手を離すことはなく、寧ろそれ以上に強く腕を引かれる。
ガチャンと鍵を締める音が聞こえてきて、すかさず何をするのかと抗議をするも、彼は顔を俯かせながら小さく呟いた。
「そうだな、少し前までは可愛い奥さんもいたよ。だけど今はもういない。アイツは別の男の元に行ったよ」
そう言って小さくため息を吐いた彼は左手を見せてきた。
既にそこにあった物はなくなっており、あれだけ自慢げに見せてきたはずの指輪はどこにもなかった。
あんなに喜んで結婚したはずなのに、まさかもう別れてしまったなんて。
同情してしまいそうになったが、私も恋人を失った身として慰める言葉が見つからなかった。
彼の言葉に顔を俯かせていると、両頬を掴まれてグッと上に持ち上げられた。
きっとブサイクな顔をしているのに、彼はどこか愛おしげに私を見てきて、そのまま唇が重なった。
今度は両頬を優しく包み込んできて、力の入っていなかった唇は、いとも簡単に彼の舌によってこじ開けられた。
そんな気分じゃないはずなのに、ねっとりと咥内を犯されてしまえば、体は簡単に熱を帯びる。
久しぶりに感じた彼とのキスは心地良くて、目を細めてうっとりと思わず感じ入ってしまう。
歯列や上顎、下顎などをコリコリと舌先で擦られ、ゾクゾクとした甘い疼きが下腹部に感じ始める。
彼の腕を掴んで抵抗しようとしても、徐々に力の抜けていく手では、もっととせがんでいるような形になってしまう。
「ん、ぶッ、んんぅッ、う、ぅ、ぅんッ…」
声を出そうとしても、息ごと彼に飲み込まれてしまい、上手く声が出せなくなった。
大きな口が一瞬だけ離れても、すぐに私の唇と重なり、今度は逃げていた私の舌を捕まえられた。
根元から先端に掛けて畝ねるように、吸い上げられて、ビクンと体が跳ね上がった。
ぢゅうっと強弱を付けて、舌を吸い上げられてしまえば、徐々に体に力が入らなくなっていく。
カクンと膝から崩れ落ちるように、ちゅぱっと唇が離れた時。
グンッと彼の逞しい腕に支えられたことで、倒れることはなかったが力の抜けてしまった足では思うように立っていられなかった。
久しぶりの感覚に、はひはひと過呼吸じみた呼吸を吐きながら彼の胸板に額を押し付けた。
「そんなに気持ち良かったか?ツンケンしない方がお前は可愛いぜ。顔だって美人なんだからさ」
からかうように言ってくる彼に、反応をすることも、皮肉を言うこともできずに、ただ呼吸を整えようとするが、それすらも脈打つ心臓を抑えることで手一杯だった。
しっかりと支えられる腰と、先程よりも更に密着する腰に、彼の火照る熱が伝わってきて、キュンっと甘い痺れが下腹部を駆け抜けた。
着替えてもいないし、水着のままだと隠すことも出来ず、ジュワッと膣内から溢れ出した愛液が太ももを伝い落ちていくのを感じた。
彼の胸板に顔を押し付けて、小さく熱い吐息を吐き出す。
「…アンタとは、久しぶりなんだから、感じちゃうのは…仕方ないでしょ…」
恥ずかしさ以上に、二年ぶりの彼とのキスをもっとしたいと思う自分がいたのだ。
乱暴だけど、しっかりと私を気持ちよくしてくれようとしてくれる優しさ。
お互いに大会も忙しかったあの頃は、恋人を作る余裕もなくて、それでも体だけは誰かを求めてしまった。
あの時、セフレと関係を続けようか悩んでいると相談されたあの日。
私は彼にセフレとして立候補したのだ。
チャンスだと思った。
友人でもないただの同業者。
それだけの関係で終わらせたくなくて、私達はあの日にセフレ関係となったのだ。
今までのセフレは気まぐれで私を呼び出したりしたのに、彼はまるで恋人のように私のことを抱いてくれた。
優しさを持って、痛くないかと聞いてくれたり、どこか一緒に出掛けないかと誘ってくれたり。
それが嬉しくて、自分の思いを胸にしまい込んだまま、彼との関係は数年続いた。
しかし所詮はセフレだ。
彼の一番にはなれないし、彼の隣にいる人は既に決まっていた。
結婚の話を聞いてからは、潔く彼の前から姿を消した。
連絡先も全て削除して、彼との関係は完璧に絶った。
同業者だったこともあって、何度も顔を合わせてどうして連絡先を消したのかと詰め寄られたこともあった。
しかし、自分の思いだけでそれ以上彼を振り回したくなかったのだ。
理由も言わないで、結婚する彼を心から祝福して、私も新しい恋に走った二年前。
それが今では彼にも見捨てられ、大会でも成績を収めることができずに崖っぷち。
けれど、そんな私の心の寂しさを埋めてくれるのはやはり彼しかいないのだ。
ゴクッと息を飲む音が聞こえてきて、腰を支えていた彼の腕が、ゴソゴソと股間を弄り、ボロンッとあの頃と変わらない、太さと長さを保ち、天高くそそり立った陰茎を取り出した。
は、と頭上から熱い吐息を吐くのが聞こえて、私の水着を少しずらし、ズリズリと膣の割れ目と太ももの間を太い陰茎が往復し始めた。
太ももを締めてと、耳元で囁かれ、キュッと足を少し閉じると身震いをするように、彼の体が僅かに震えた。
太ももの間を行き来する陰茎の感触に、小さく息を吐いて、ゆっくりと下に視線を落とした。
赤黒くて血管の浮き出た陰茎は、禍々しくもあり扇情的で、思わずうっとりと見つめてしまう。
早くそれを中に入れて欲しい。
そう望んで口に出せばきっと、イタズラを覚えた子供のように口元をニヤつかせてすぐに入れてくれないかもしれない。
徐々に腰を振り乱す速度が上がり、ゆっくりと彼を見上げるように見つめると、額に汗を滲ませて、熱い吐息を吐き出す彼と視線が交わる。
「は、ッんッ…ぅ…でそう…?」
「ッ、あ…いきそ…」
彼の胸板に手を添えて、汗ばむ彼の小麦肌に唇を押し付けて、チュウッと軽く吸い付いた。
そして彼の体がビクビクと激しく震えた瞬間に、噴き出すように精液がビュルッと吐き出され、太ももの間を白濁とした液体が伝い落ちた。
ふうふう、と荒い息遣いをしたのも束の間で、彼の手が私の片足を持ち上げて、出したはずなのに萎えることのない陰茎を、濡れそぼった膣内に挿れてきた。
「ひ、んんッ、うぅッ、!」
強烈な衝撃が体に走り、ゴリゴリと深い所を突き上げられて、堪えきれない快感が体を駆け抜けていく。
持ち上げられた太ももからは、吐き出された精液が滴り落ちていて、顔に熱が集まってしまう。
グポグポと最奥を突き上げられる度に、ガクガクと足が震え、きゅうきゅうと強く膣内を締め付けた。
耐えきれない快感の波が押し寄せてきて、熱い吐息を深く吐き出して、彼の首に縋るように弱々しく腕を回した。
「んひッぃ、ッあぁ…んあぁッ!ひ、ぐぅッ、あぁッ!」
「は…ッ、ぁ…久しぶりの中…最高…こんなに締め付けてきて…可愛い…」
何度も深々と奥ばかりを突き上げられて、粘着質な音がお互いの間から響いていた。
彼が腰を打ち付ける度に、お互いの下腹部の間から白濁とした液体がひっきりなしに糸を引いているのが見えて、自分がどれだけ感じているのかを見せつけられているような気分になる。
肉ひだを割り開くように、浅い所から深い所まで突き上げられて、ひぐと情けない喘ぎ声を漏らして、ビクンと背を仰け反らせて達した。
それでも最奥ばかりを突き上げてくる陰茎の速度は止まらず、ガクガクと揺さぶられる度に陰茎がコリッと何度も子宮口を突き上げてきた。
ちゅぽちゅぽとまるで子宮口とキスをするように、先端が時折優しく子宮口の手前で速度を落とす。
そしてすぐに浅い所まで一気に引き抜かれ、深々とまた突き上げられるを繰り返す。
訳も分からない強い快感が体を駆け抜けていき、何度も強く中を締め付けてしまう。
「んぐぅぅッ、や、あぁッ、んあッ、あぁッ、ぁッ!」
「…ッ、やっぱりお前と、のセックスが一番好き…それに…お前と一緒に、ん…ッ、いる方が…俺好き…ッなんだ…」
耳元で囁かれた言葉に、ゾクゾクとした快感が駆け抜けていき、ビクンと体を痙攣させて二度目の絶頂を迎えた。
はくはくと必死に呼吸をするも、膣内でビクビクと痙攣しだした陰茎と、歯を食いしばり顔を顰めた彼を見つめた瞬間。
ビュビュッと勢いよく中に吐き出された精液に、体を激しく痙攣させて三度目の絶頂を迎えた。
激しい突き上げが緩やかなものに変わり、名残惜しく膣内がヒク付き始める。
物足りなくて、もっと彼と繋がっていたくて、自らゆったりと腰を揺らし、彼の耳元で甘く囁いた。
「んひッ…ッうぅん…ッ、わ、たしも…すきぃッ…」
答えを聞いた彼は、嬉しそうに目を細めて笑みを浮かべてから、今度は私の体を持ち上げて、甘いキスをしながら衝動を再開するのだった。






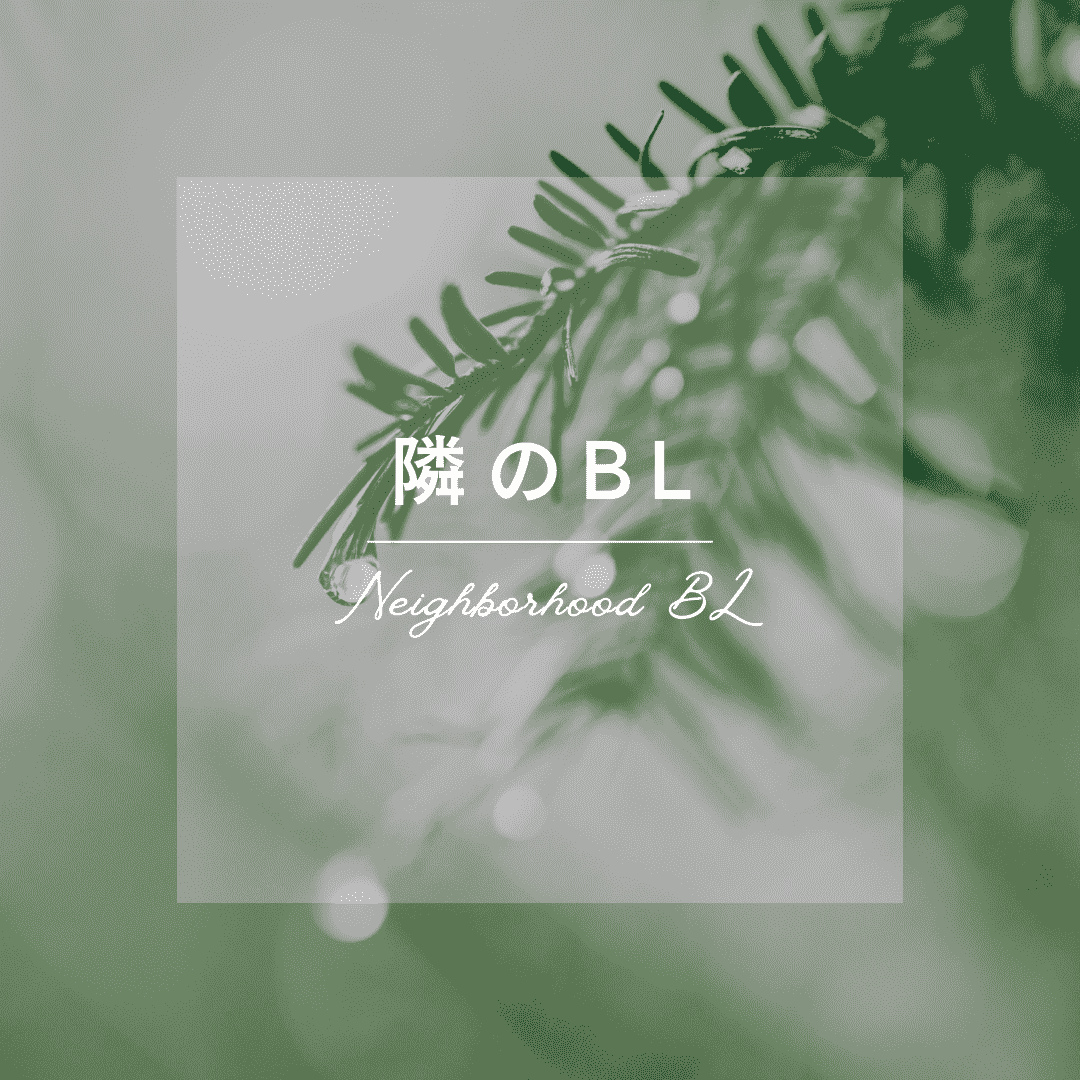

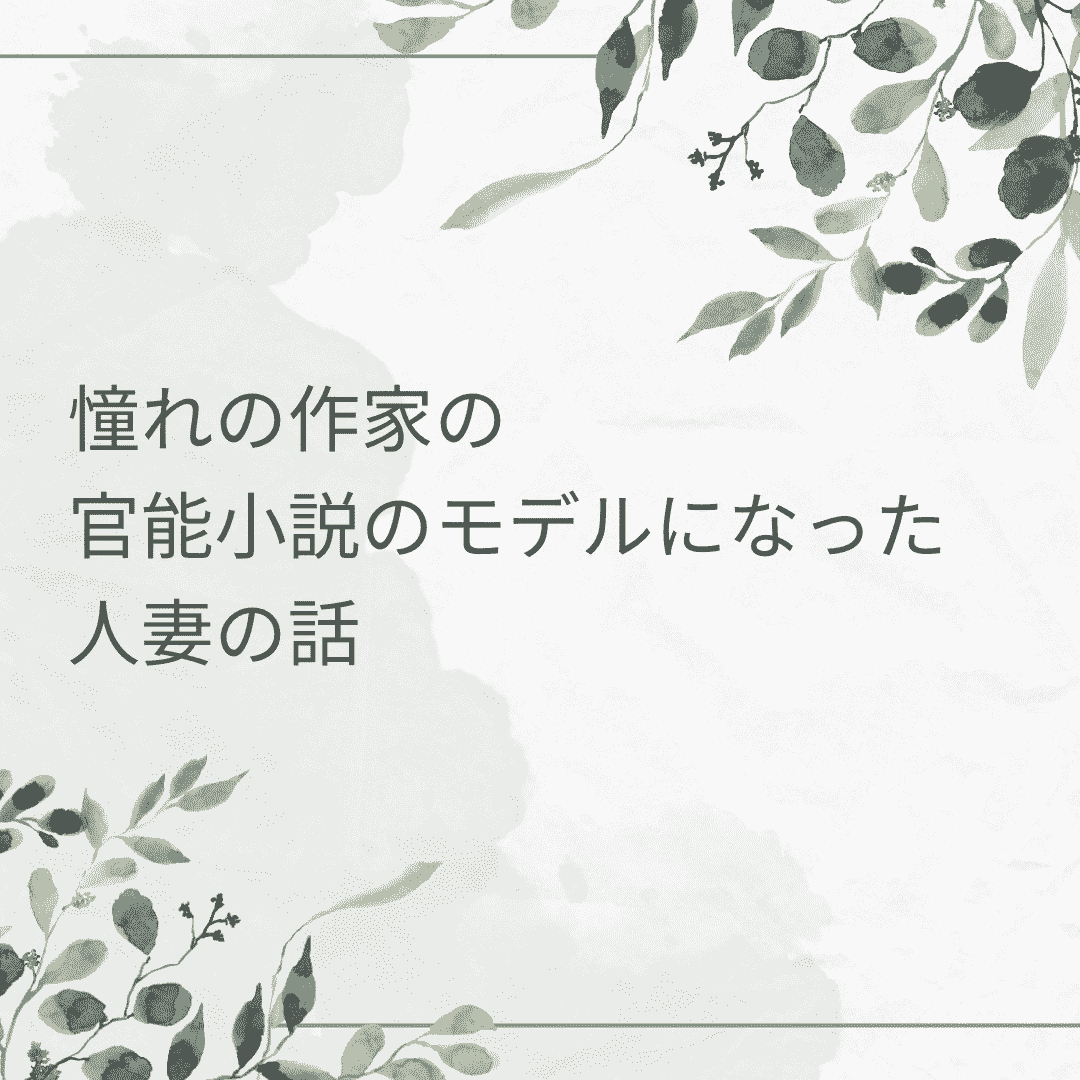


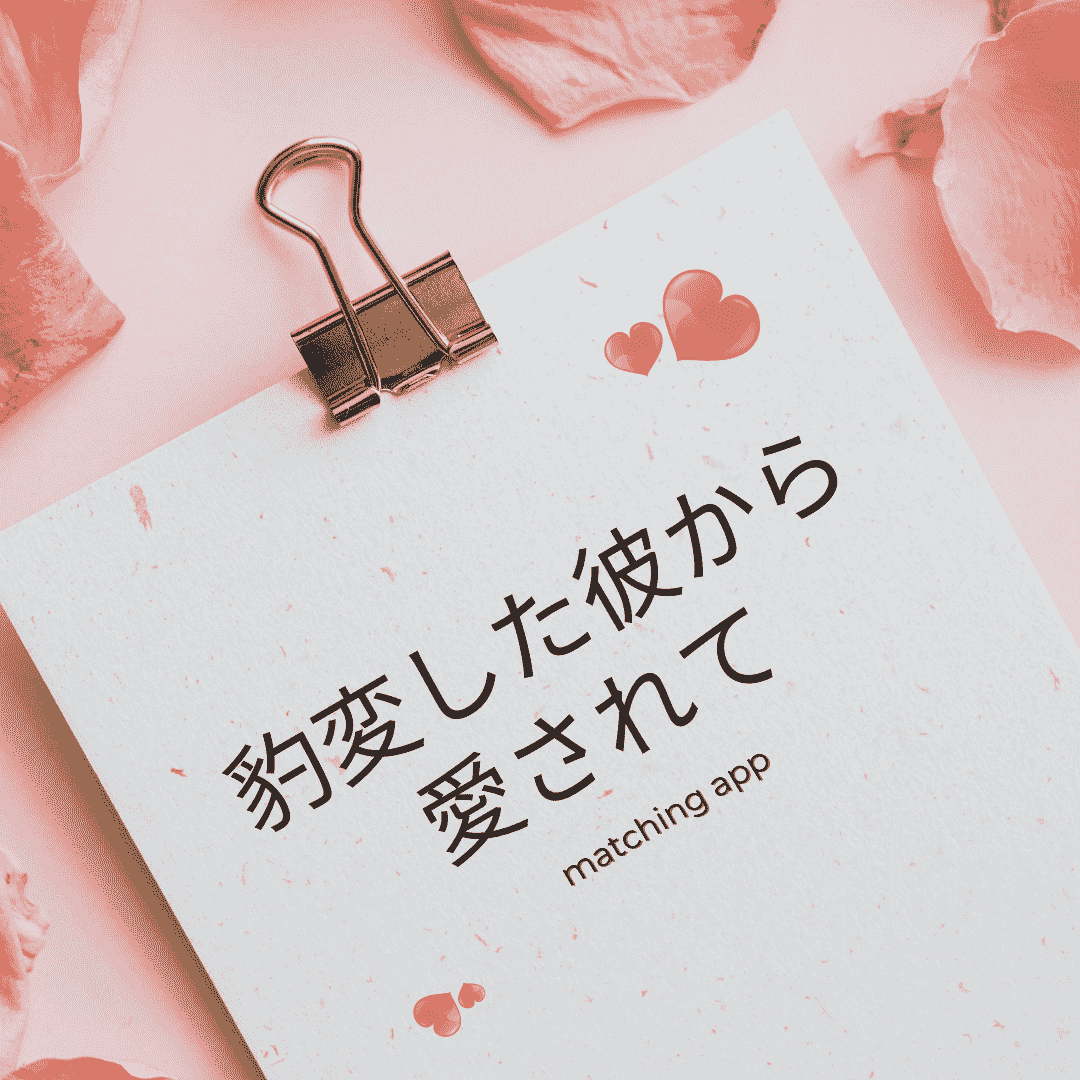

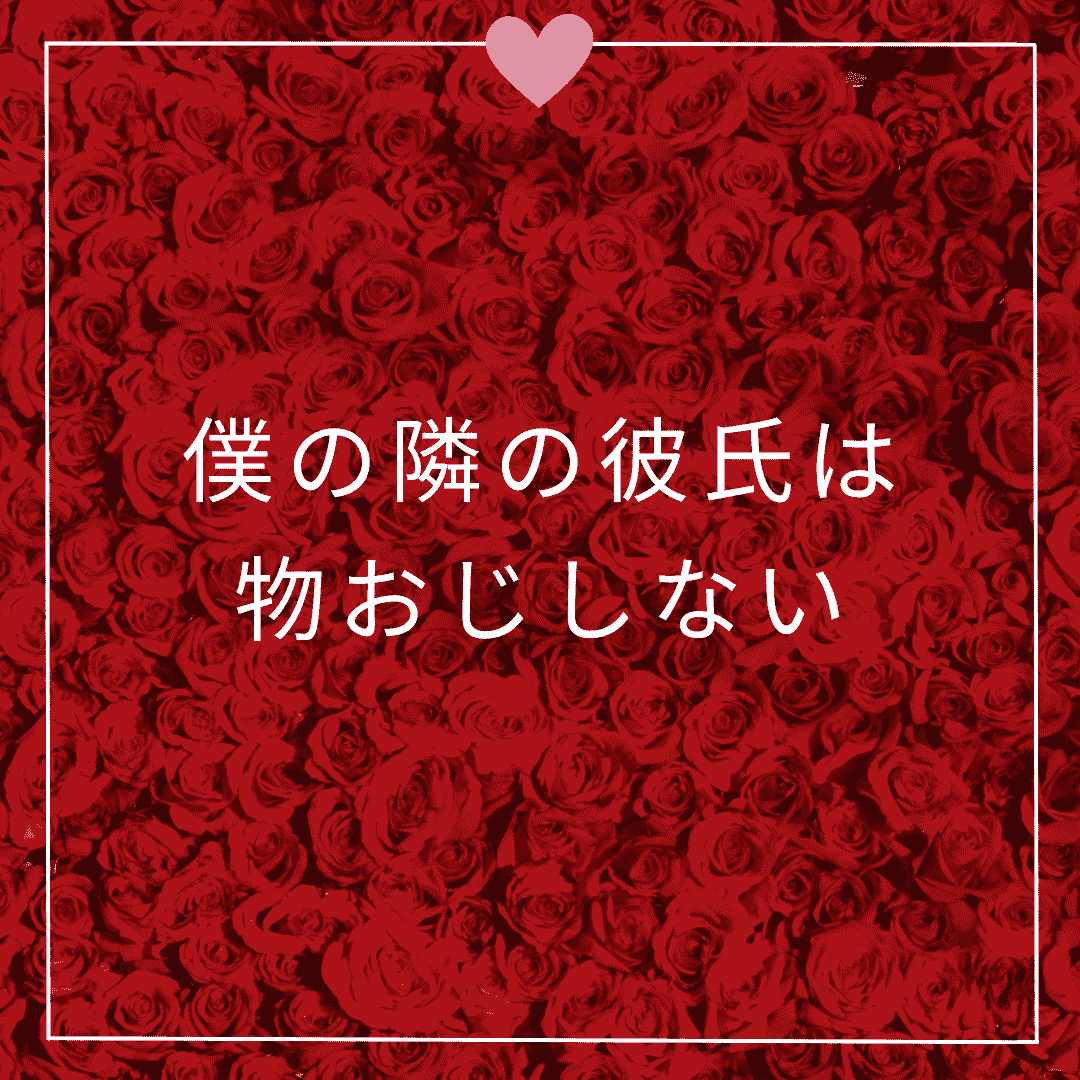
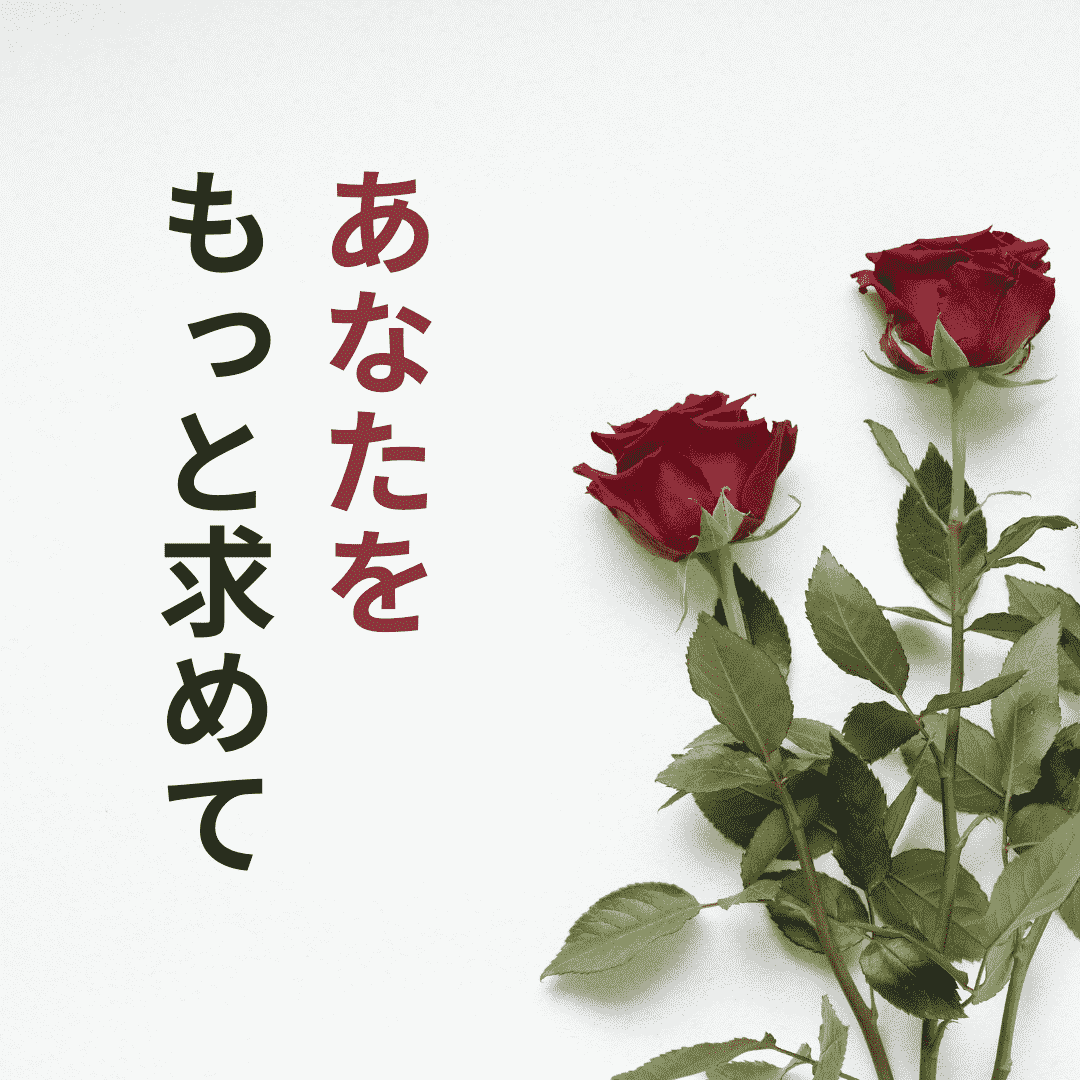





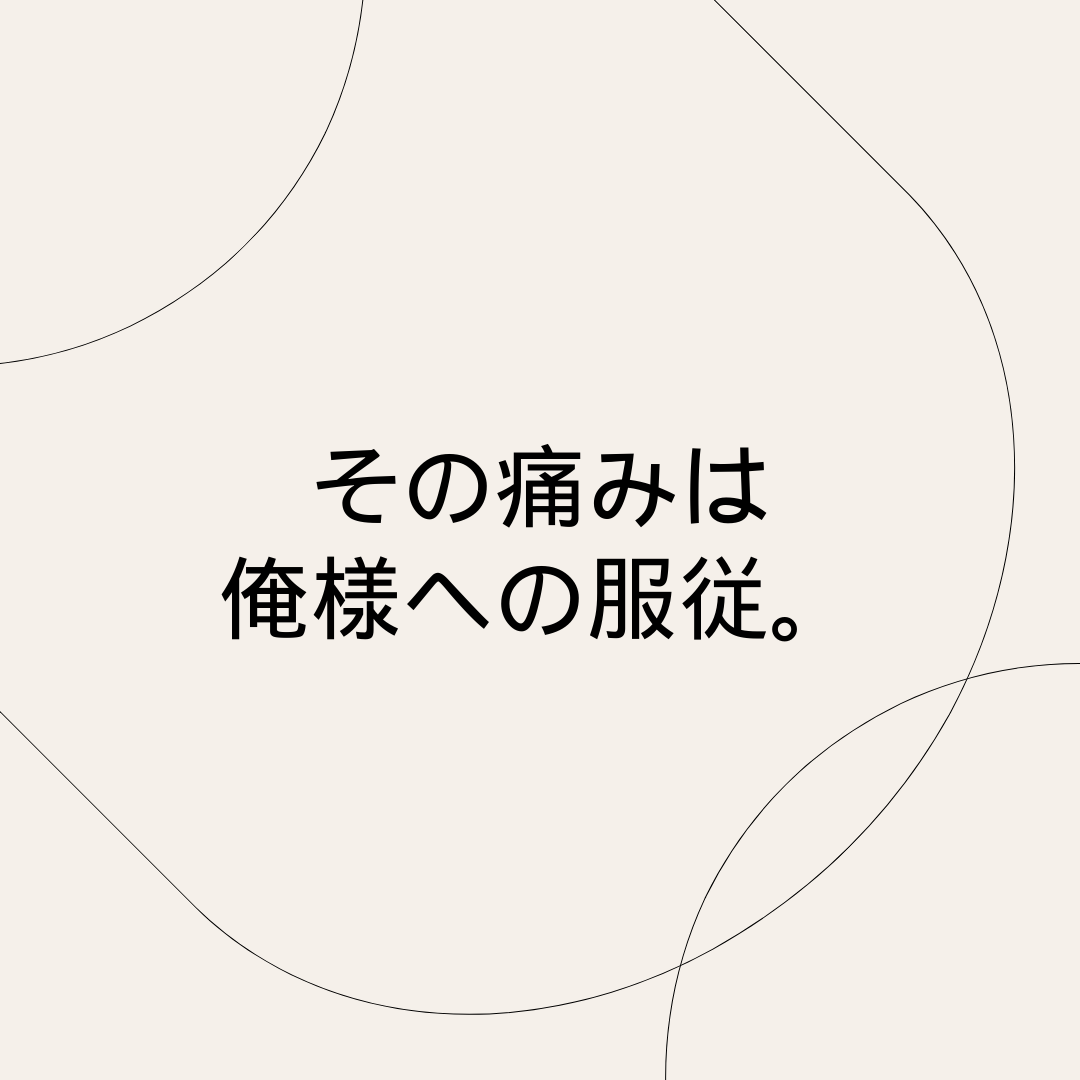

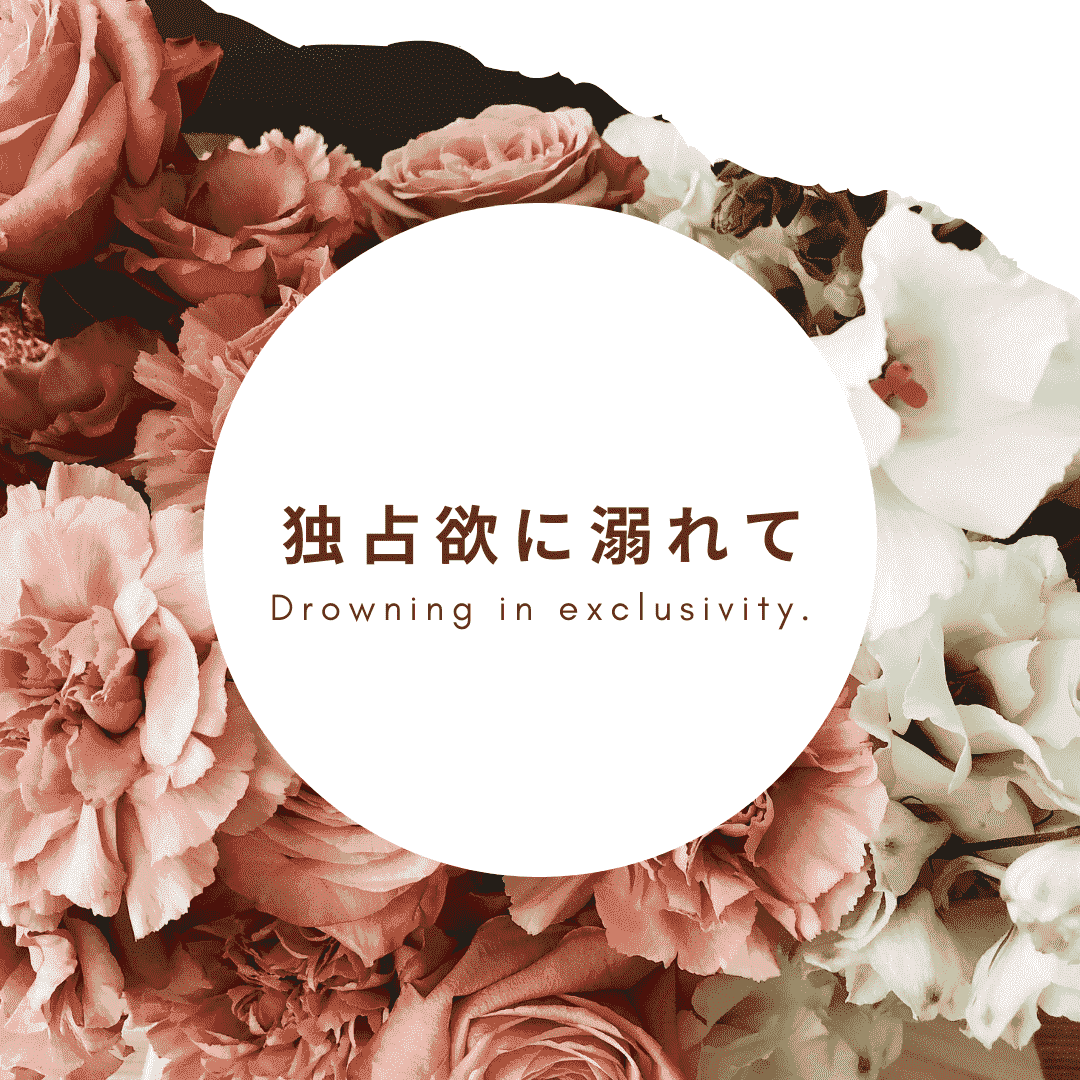
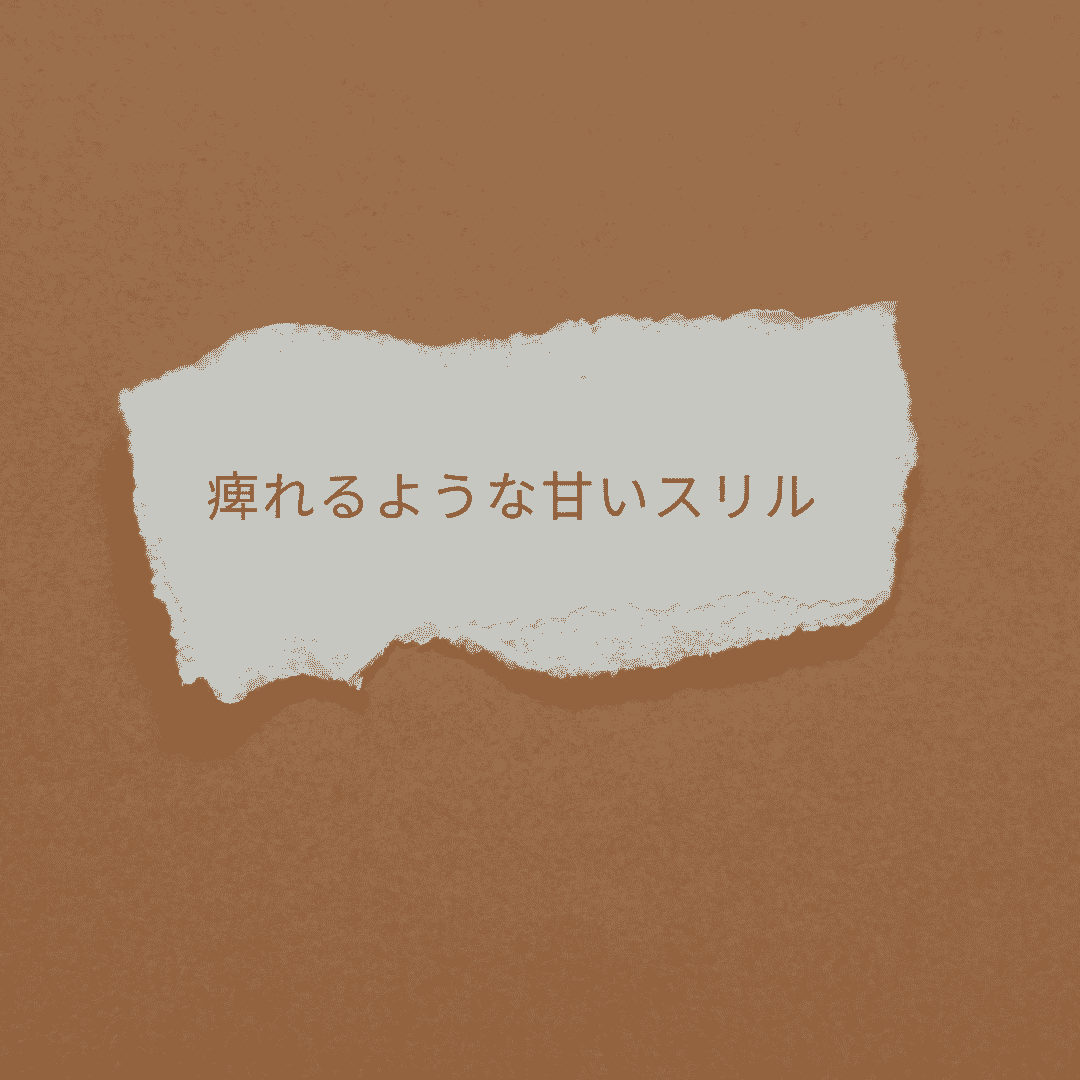


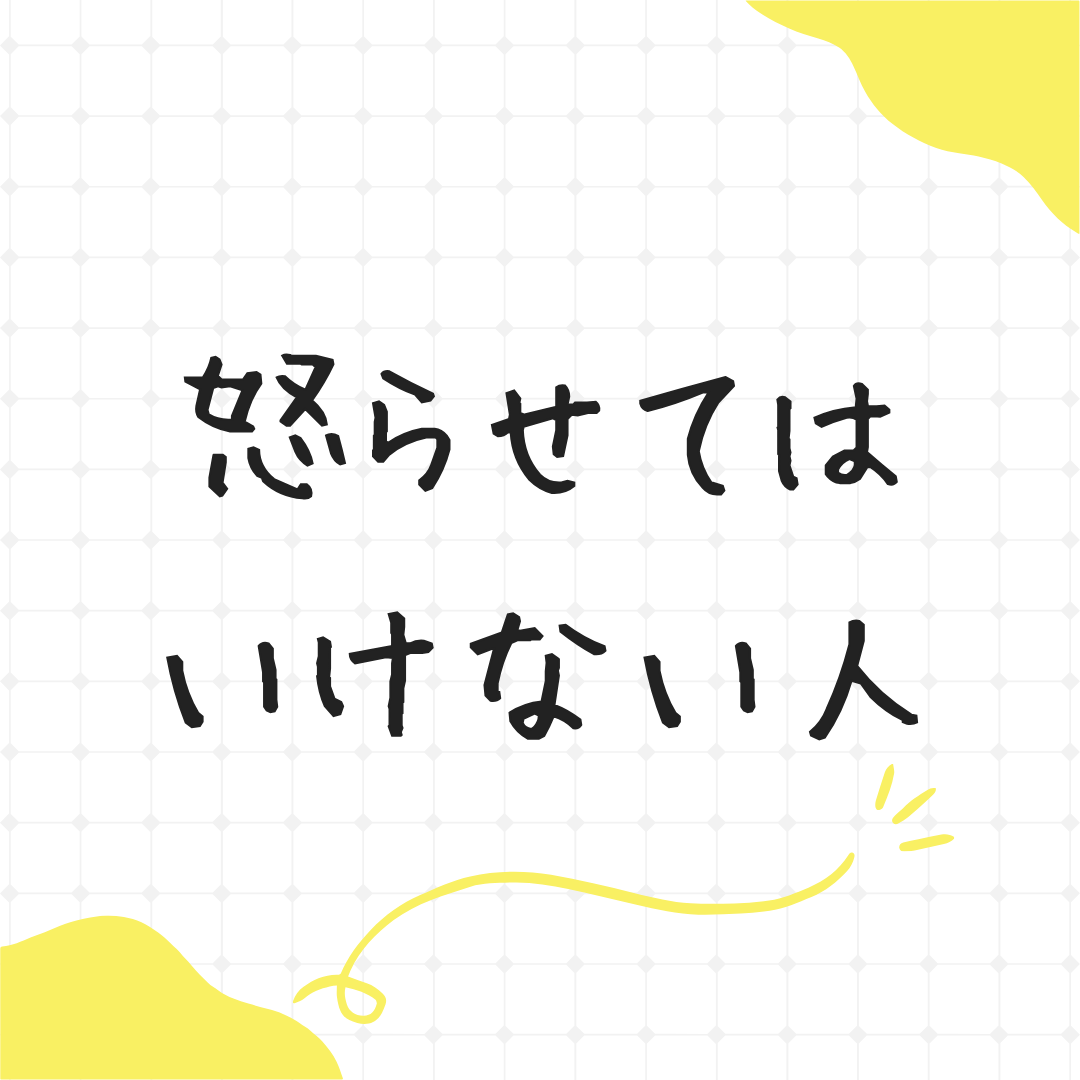

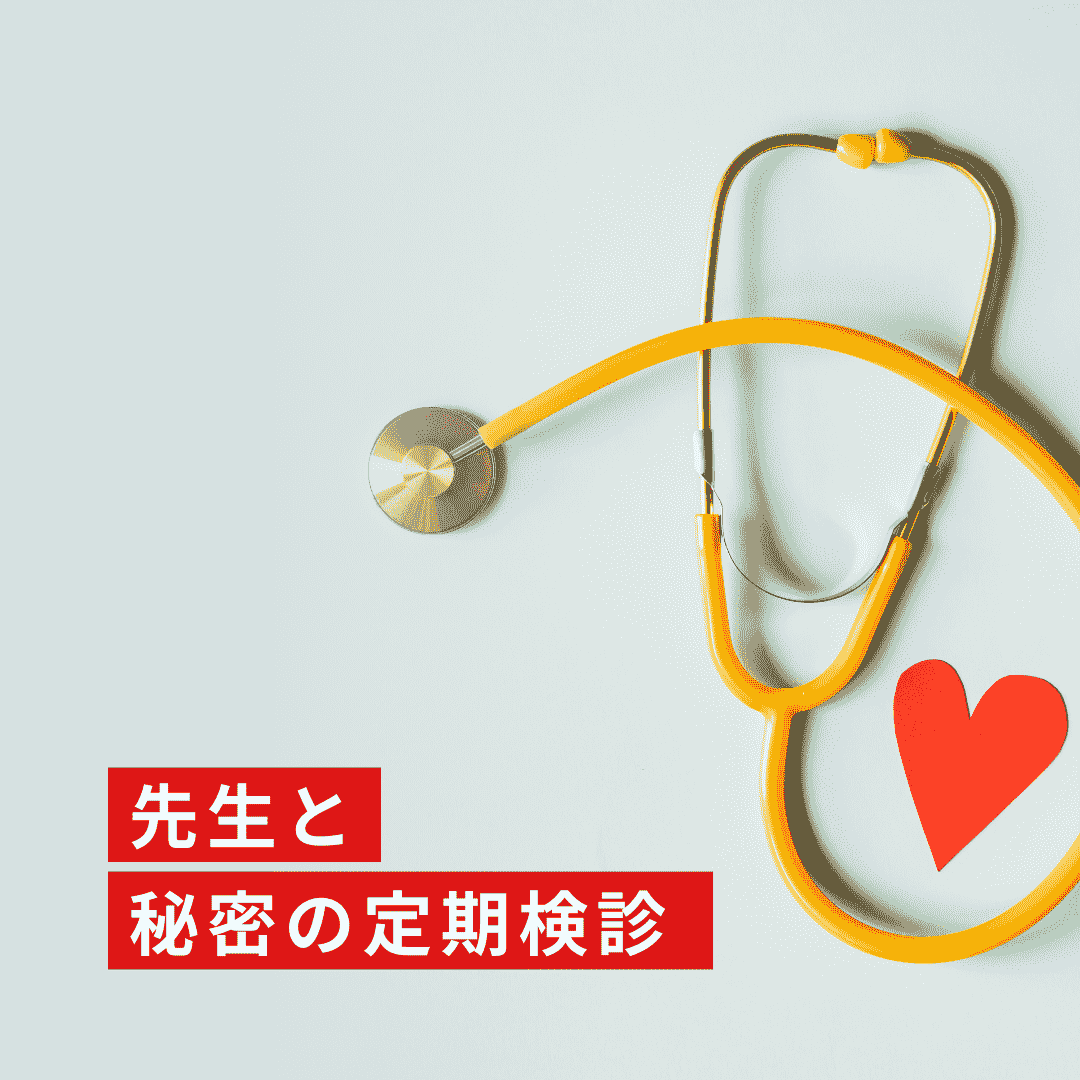
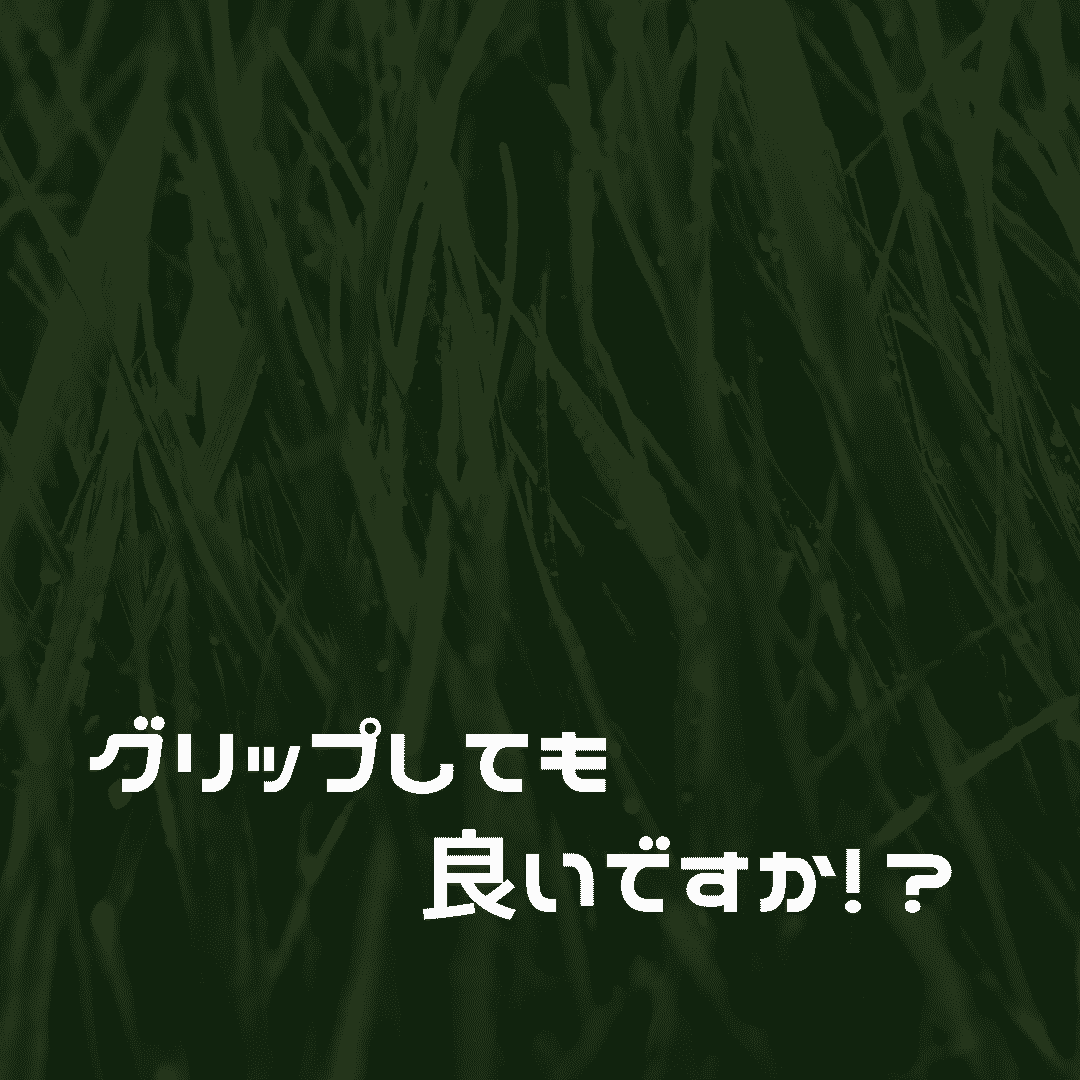
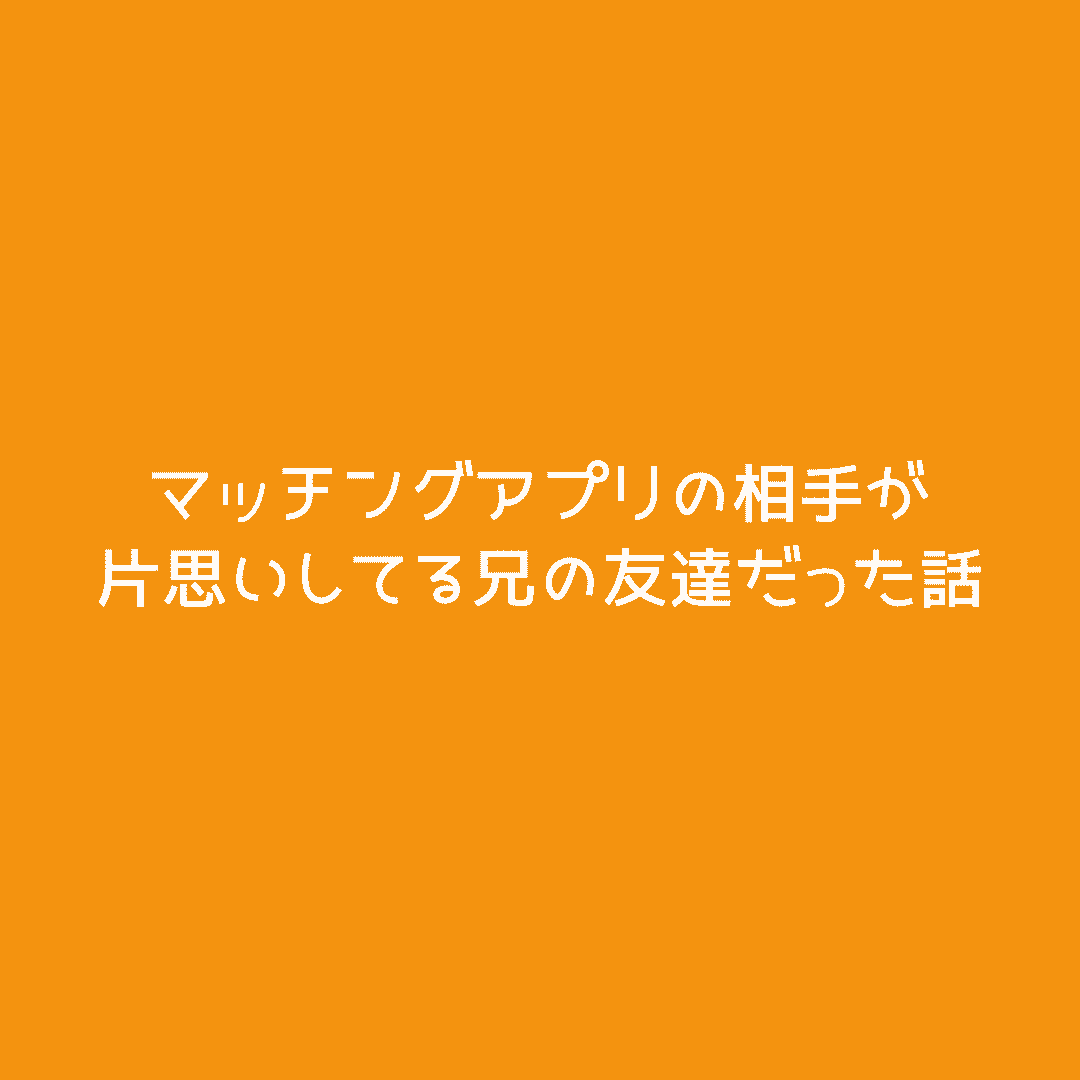
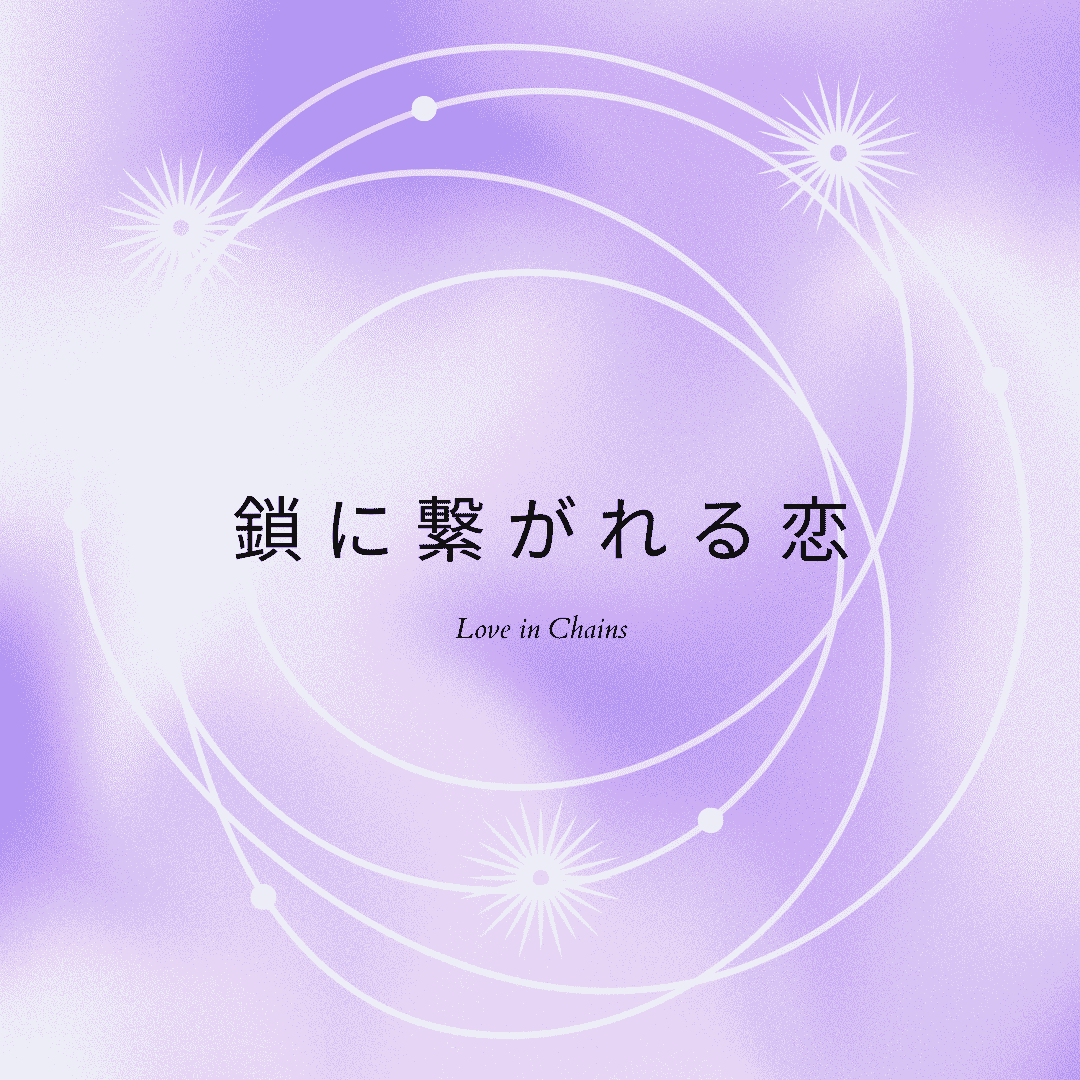


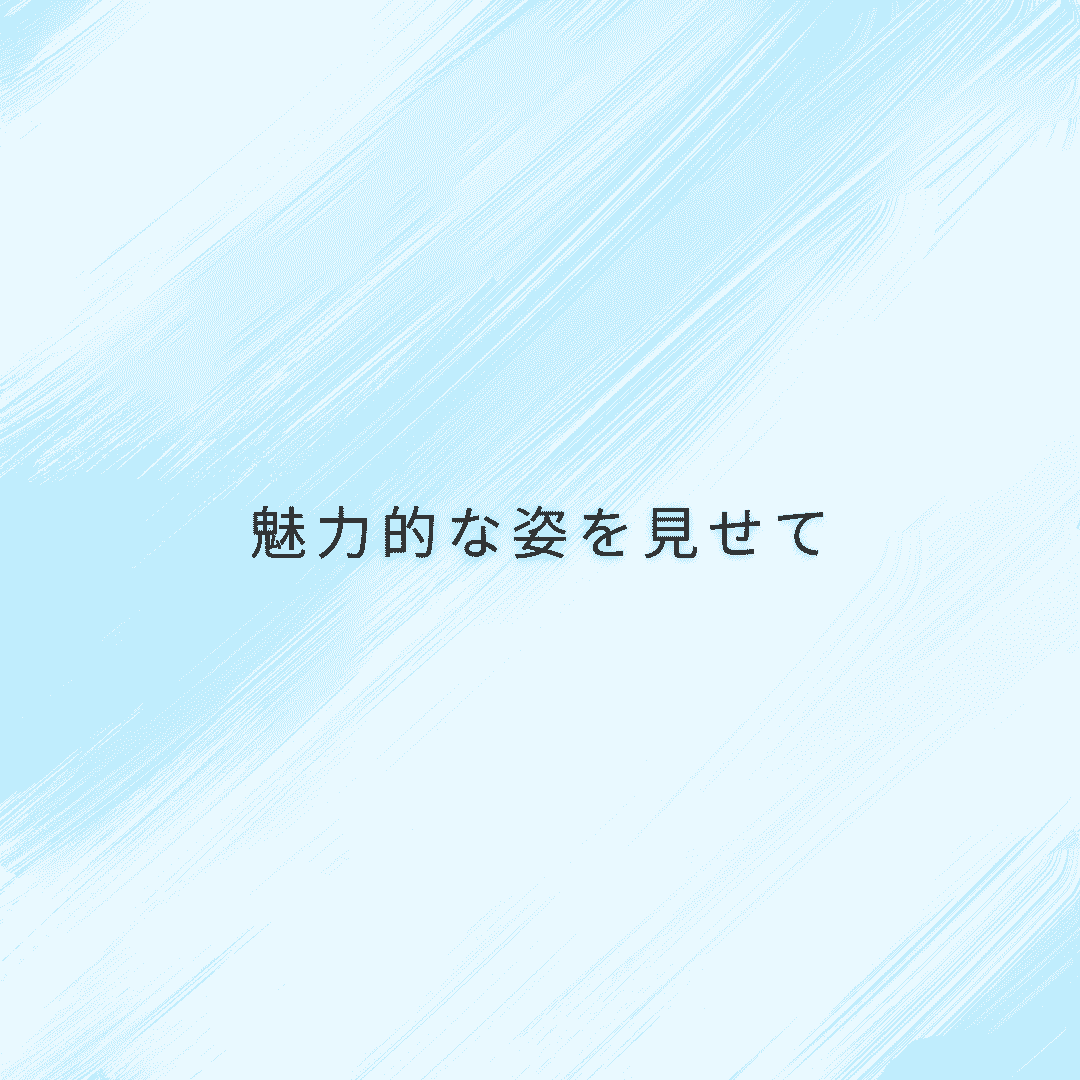
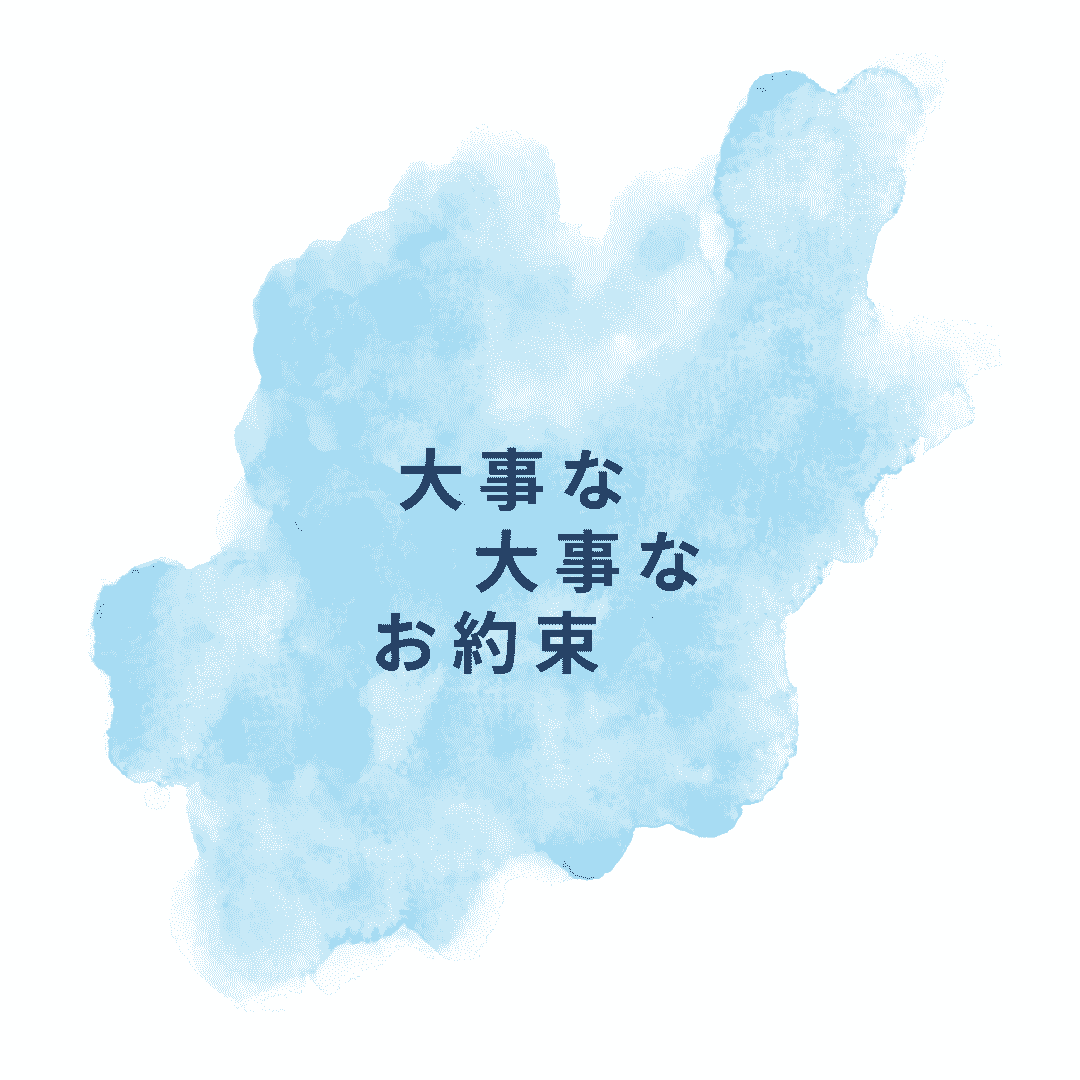



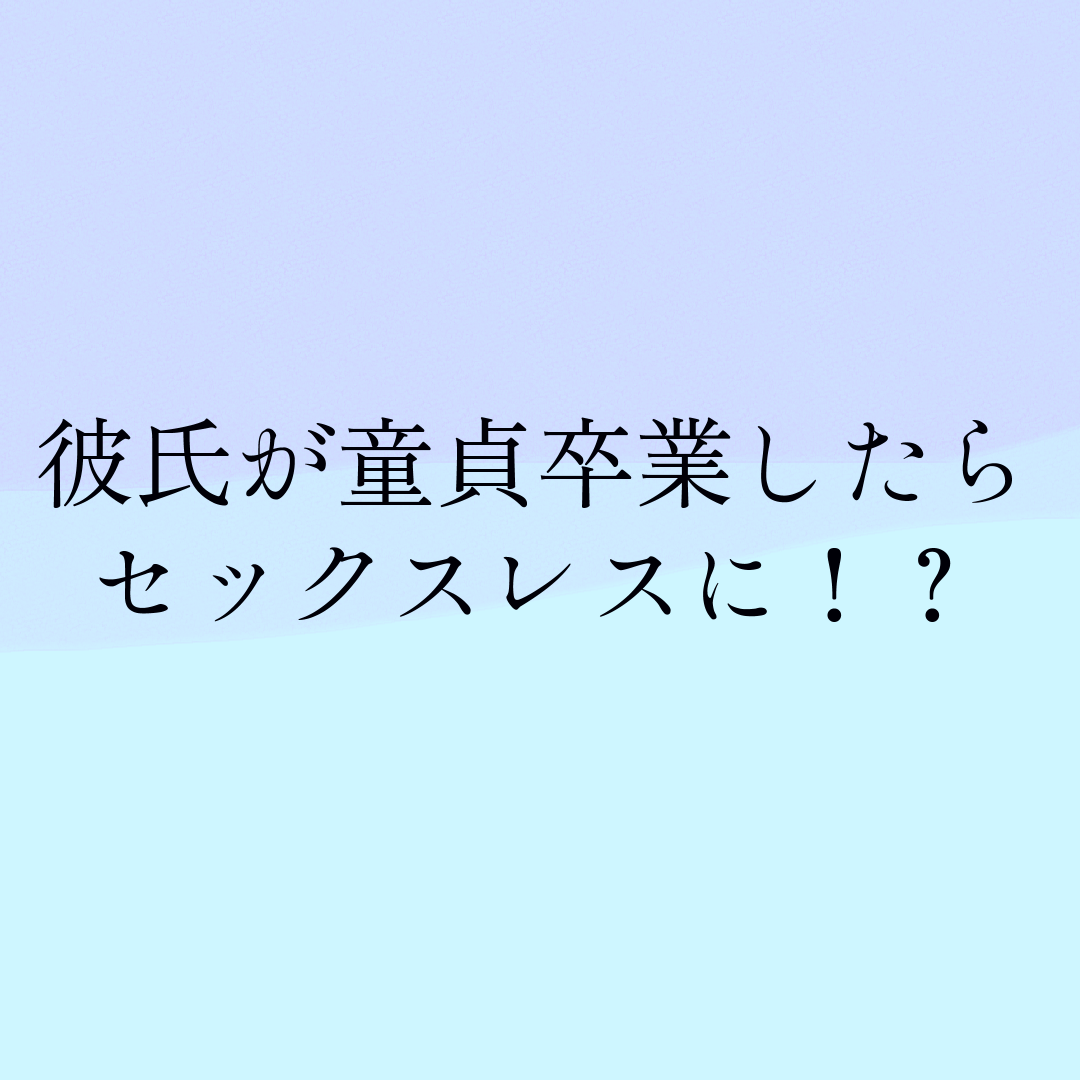








コメント