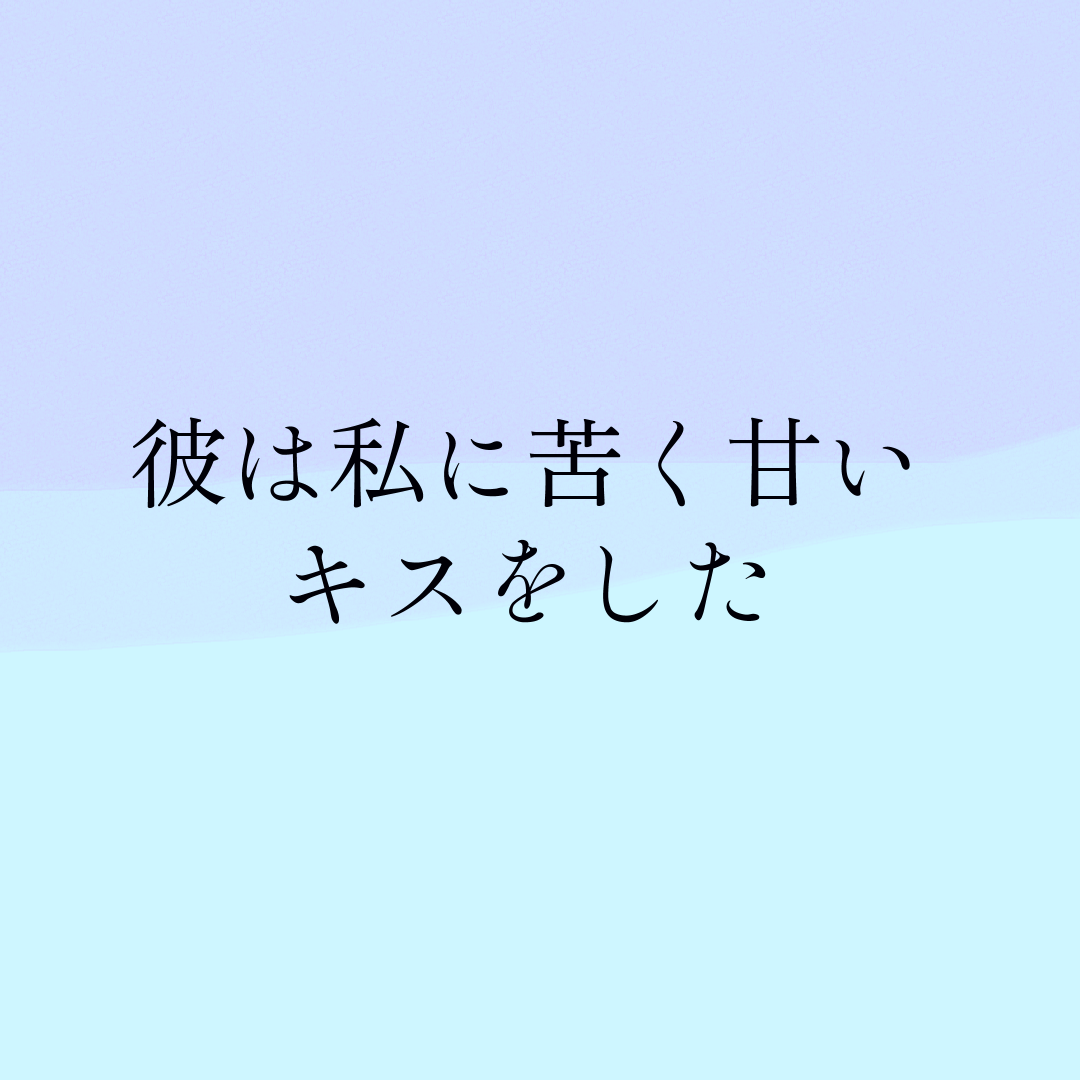
0
彼は私に苦く甘いキスをした
「奈央ちゃん、結婚するんだって?」
夫の昴が新聞を読みながら私に聞いてきた。
奈央とは私の1つ上の姉だ。私は真央と名付けられ、双子のように仲睦まじく生きてきた。
職場で出会った夫と私が結婚したときに、寂しそうな目をしていた姉を思い出す。
「先越されちゃったな」
私はそれから、一人暮らしをする姉の元へ通うようになった。妹が先に結婚をした引け目を感じていたのかもしれない。結婚と姉の口から出たとき、思わず抱き着いて喜んでしまった。しかし、私は「結婚する」とは聞いたけれども、相手を知らなかった。
「奈央ちゃんのところ行ってくるね」
「ああ、結婚式がいつだか聞いておいてくれ」
私と夫は非常に淡白な関係だ。夫婦とはそういうものなのだろうか。新婚のときから、ラブラブという言葉は存在せず、夫婦の営みに関しても、お互いしたかったらする。しかし、夫と一緒にいて不自由を感じたことがないので、相性はいいのだろうと思った。
今日は姉の引越し前日だ。それで、私が手伝いに行く訳である。
「奈央ちゃん」
「ああ、真央」
部屋を覗くと、段ボールだらけになっていた。あらかた終わっているらしく、私の役目は食器を段ボールに入れることになった。
「ただいま」
背後で声がした。とても懐かしい気持ちになる声。声を聞いただけで夏の暑い盛りを思い出した。
振り向くと、そこには祐介がいた。高校生のときの1つ下の後輩。髪を金髪に染めていて、ピアスをしている。昔の純朴な少年とはまるで変っていた。しかし、声は確かに祐介だ。見た目も金髪を黒くしたら祐介だ。10年ぶりの再会に私は困ったような顔をしていることだろう。
「真央セン」
懐かしい響きだ。そう呼ぶのは祐介だけだ。
途端に意識が10年前にさかのぼる。
「真央セン、好きな人いないの?」
「うん」
「なんだ。僕も眼中になしかー」
「それって」
夏の暑い中、コンビニの前でアイスを食べていたら、いきなりそんな話題を振られた。私は驚いて祐介の顔を見る。
「あのさ。30まで結婚できなかったら、僕としない?」
「何それ。面白そうじゃん」
私は本気にしてなかった。
アイスを半分こしたことも、自転車を二人乗りしたことも、水道を壊して水浴びしたことも、全て祐介との思い出だ。それを10年の間で忘れてしまっていた。
「あれ、もしかして2人って知り合い?」
「うん、高校が同じ」
祐介が姉の質問にそう答えた。祐介は姉に私とのことを話してなかった。しかし、苗字とそっくりな顔から、奈央が私の姉であることは察していただろう。
何故、言わなかったのだろう。
「あ! もしかして、真央の秘密の友達?」
祐介のことを姉に話したことがある。名前など、詳しいことは避けて。だから、姉は祐介を私の〝秘密の友達〟と呼んでいる。
まさか、姉の結婚相手が祐介とは……。
ぼーっとしている私に姉が心配そうに顔を覗いてくる。
「あ、ごめんごめん。食器終わったよ」
手だけはきちんと動いていた。
その後、引越し準備のお礼ということで、焼肉に連れて行ってくれた。
白い煙が立ち上る中で、私は黙々と肉を焼いている。二人は酒をがばがばと飲んでいる。その飲みっぷりに私ははあと深いため息を吐いた。
私と奈央の違いは様々あるけれども、お酒の強さは対極的である。下戸の私とザルの奈央。私はちびちびウーロン茶を飲んで、二人のために肉を焼いているのだ。
「少しお手洗い」
「俺も」
私が立ち上がると、祐介も立ち上がった。奈央はタッチパネルでお酒を追加注文している。
周りに人がいるけれども、やっと祐介と二人きりになれた。
「なんで、奈央と結婚するの?」
「それは真央センが結婚しちゃったから」
「私のせいだと言うの?」
喧嘩腰になるなと私を宥める祐介。だから、似ている姉をターゲットにしたのか。疑問が湧く。
「本当に奈央ちゃんのこと好きなわけ?」
「結婚するくらいだからな」
トイレの前ということもあって、人が来る。その度に私たちは口を噤んだ。
「それで、祐介はなんで私が結婚したこと知ってるわけ?」
「真央センに会いたくなって捜し回っていたら、その、旦那さんと歩いているのが見えて」
私は一応、それで納得した。
「ちょっとトイレ長くない?」
奈央が私たちの様子を見に来た。
「ごめんごめん。並んでて」
私は謝りながら、また肉を焼きに席に戻った。
「はー、飲んだ。食った」
奈央を家に送り届け、コンビニに入った。祐介がアイスが食べたいと言うのだ。まだアイスの時期には早かったが、コンビニのアイスコーナーは今日も冷えていた。
「あー、ないのか。残念」
「何が?」
「あの日、二人で食べたアイス」
奇妙な約束をした日に食べていたアイスは確か廃番になっていたはずだ。もう一生手に入らないもの。私は少し感傷的になる。
「真央センさ。なんで結婚したの?」
「相性が合ったから」
「それは気持ちの面? 体の方?」
いきなりそんなことを聞くので、私はアイスのコーナーを挟んで向こう側にいる祐介の顔を見る。くしゃと歪ませて、泣きそうである。
その顔で、私はあの日の約束は本気だったことを悟った。
「祐介……」
「ごめん。アイスこれでいいや」
氷菓子を持ってレジへ向かった。私もアイスコーヒーの容器をレジに持って行こうとしたら、氷がだいぶ溶けていた。
コンビニの駐車場で飲むアイスコーヒーは氷が溶けていたせいで薄い。祐介は震えながら氷菓子を食べている。
「なんで、この季節にゴリゴリ君買ったのよ」
「あのアイスに一番近かったから」
もし、あのアイスがあったら、私も半分もらうことになり、震えていたかもしれないのか。
「なあ、真央セン」
「何?」
祐介は私にキスをした。コーヒーの苦みとソーダ味アイスの甘みが合わさって、微妙な味がした。
ちゅっと軽いリップ音を立てて、彼の顔が離れた。
「これで終わり」
勝手な人だ。キスひとつで満足するとは。というより、勝手に奪っておいて自己完結しないで欲しい。
「祐介」
「何?」
私は祐介の手から氷菓子をひったくると齧った。しかし、齧り方がまずかったのか、棒についているはずの残りのアイスはべしゃと地面に落ちた。
「ぷっ」
「あははははは」
近所迷惑も考えず、私たちは腹を抱えて笑った。コーヒーはさらに薄くなった。
家に帰ったら電気が消えている。夫を起こさないようにそーっと入る。
すると、寝室から女の声がするではないか。しかも、普通ではない。これは、女が悦ぶときに出す声だ。
私は速くなる鼓動を抑えながら、寝室の扉をわずかに開け中を見る。
そこには裸で夫と交わる奈央がいた。
夫のペニス(口に出すのも嫌だが)を奈央がじゅぽじゅぽっと咥えながら頭を前後に動かしている。
二人は全くの裸であり、夫のソコはビンビンと立ち上がっている。
もしかして、夫は相手が私だと思って、奈央を抱いている?
「奈央ちゃん」
一瞬浮かんだ考えは吹き飛ばされた。奈央だとハッキリ認識して交わっているのだ。
「昴さん、私にチンポちょうだい」
姉の下品な言葉に耳を塞ぎたくなる。
私たち夫婦のセックスは淡々と進むので、そんな言葉を使ったことがない。
「仕方ないな、淫乱奈央ちゃんは」
夫は奈央の頭を撫で、奈央を四つん這いにさせた。姉は腰を振って夫のソレを待っている。
「早く入れてぇ……」
「まあまあ、焦らすのも乙なものだよ」
ソレを奈央の割れ目に擦り付けている。これも私とシたことがないことだ。
「いくぞ!」
くぷりと水音がしたような気がした。夫のペニスが姉のナカに入ったのだ。
「あん! いいわぁ、昴さんのチンポ」
「まだまだよくなってもらわなくちゃな」
パンパンと部屋に響く腰を打ち付ける音。そして、姉の嬌声。
「あっ、あっ、あの子ったら、あん! 私の婚約者とキスしてたのよお」
「それはいけないな」
二人のこの関係はいつからなんだ。今日からか。それとも前から?
先ほどのコンビニでの一幕を見られているということは、奈央が何かを買いにコンビニに行ったことになる。
「んあっ!」
姉の高い嬌声で思考から現実に戻された。
もしかして、これは私への復讐? 嫉妬なんて可愛いものじゃない。
私はそっと扉を閉めて外へ飛び出した。
「祐介!」
「こんな夜中に出歩いてたら危ないぞ」
私は祐介の胸に飛び込んだ。勢いが良すぎて、祐介がふらつく。しかし、足を踏ん張ってくれたおかげで転ぶことは免れた。
「どうした?」
私はどうしたらいいか分からず、とりあえず祐介に連絡をした。連絡先は焼き肉屋で交換していた。
「祐介」
「何?」
「今日、祐介の家に泊めて」
ごくりと祐介が唾を飲み込んだ気配がした。





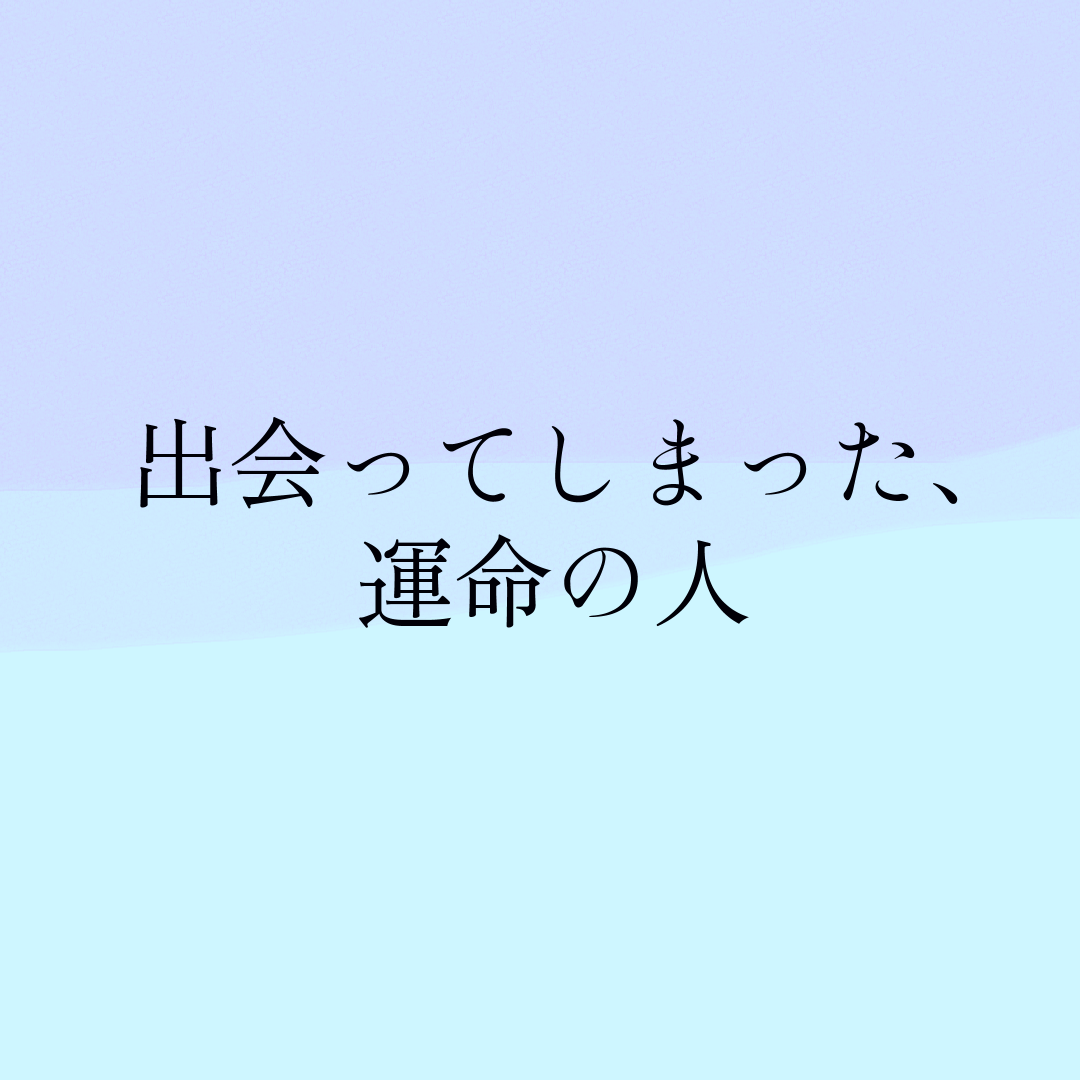
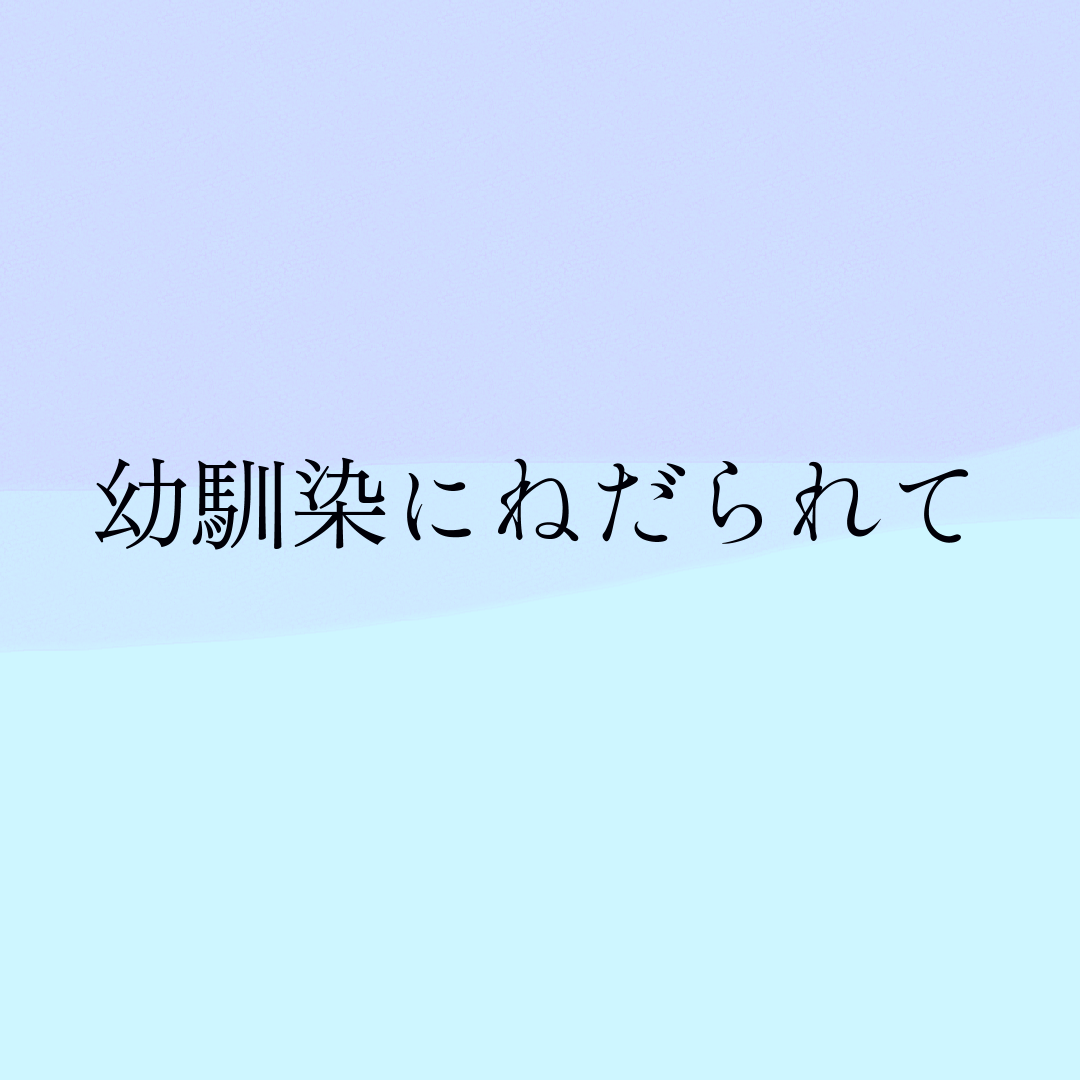
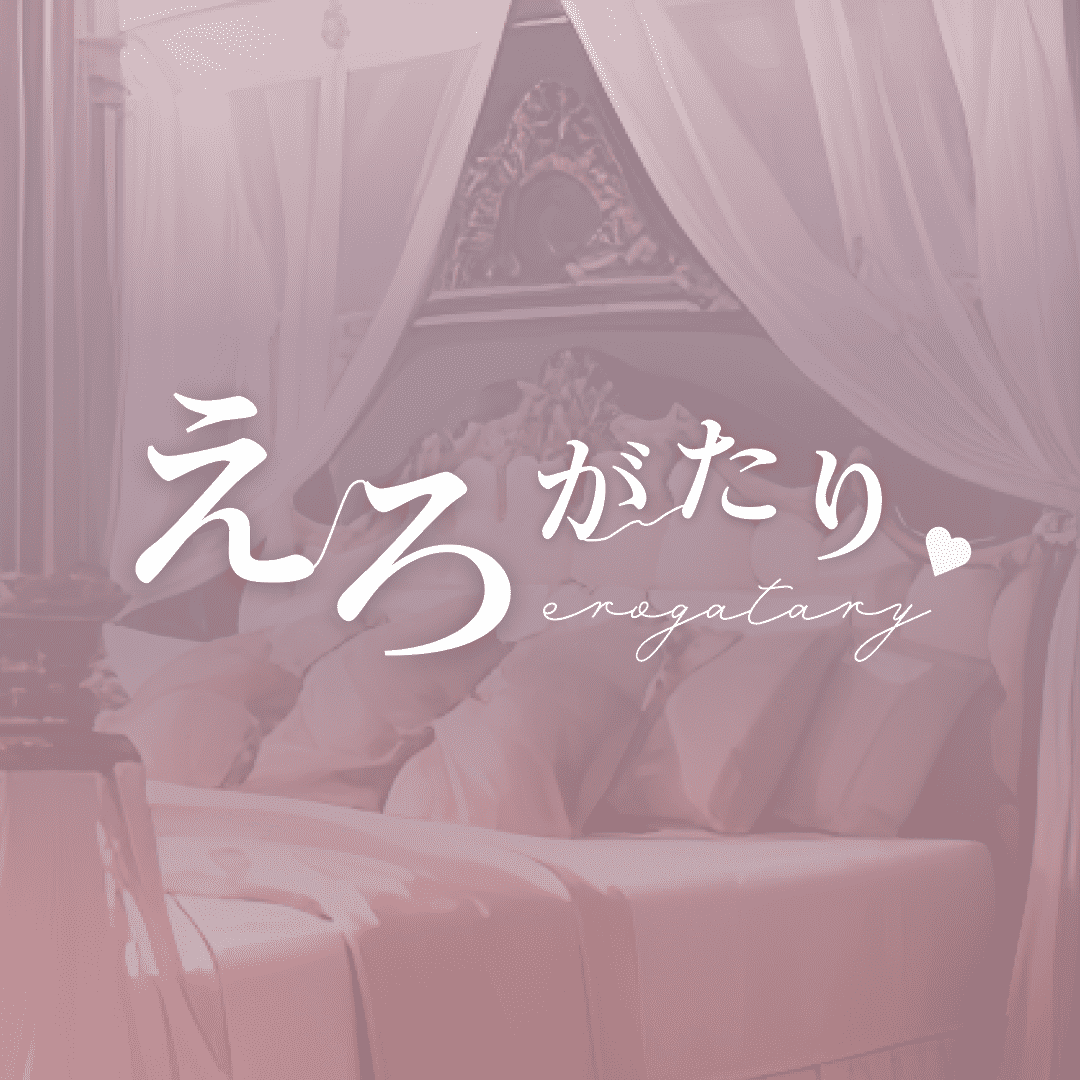
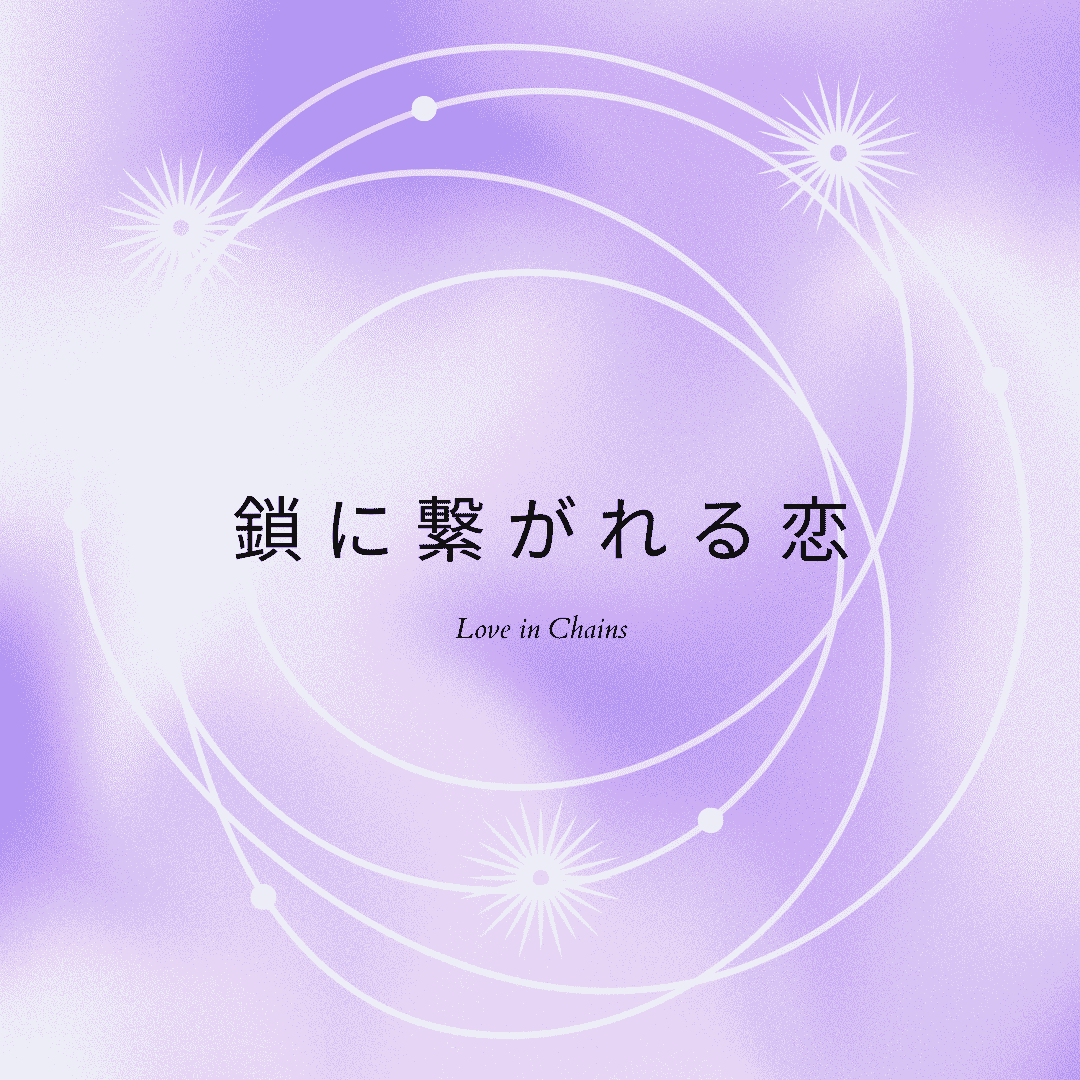




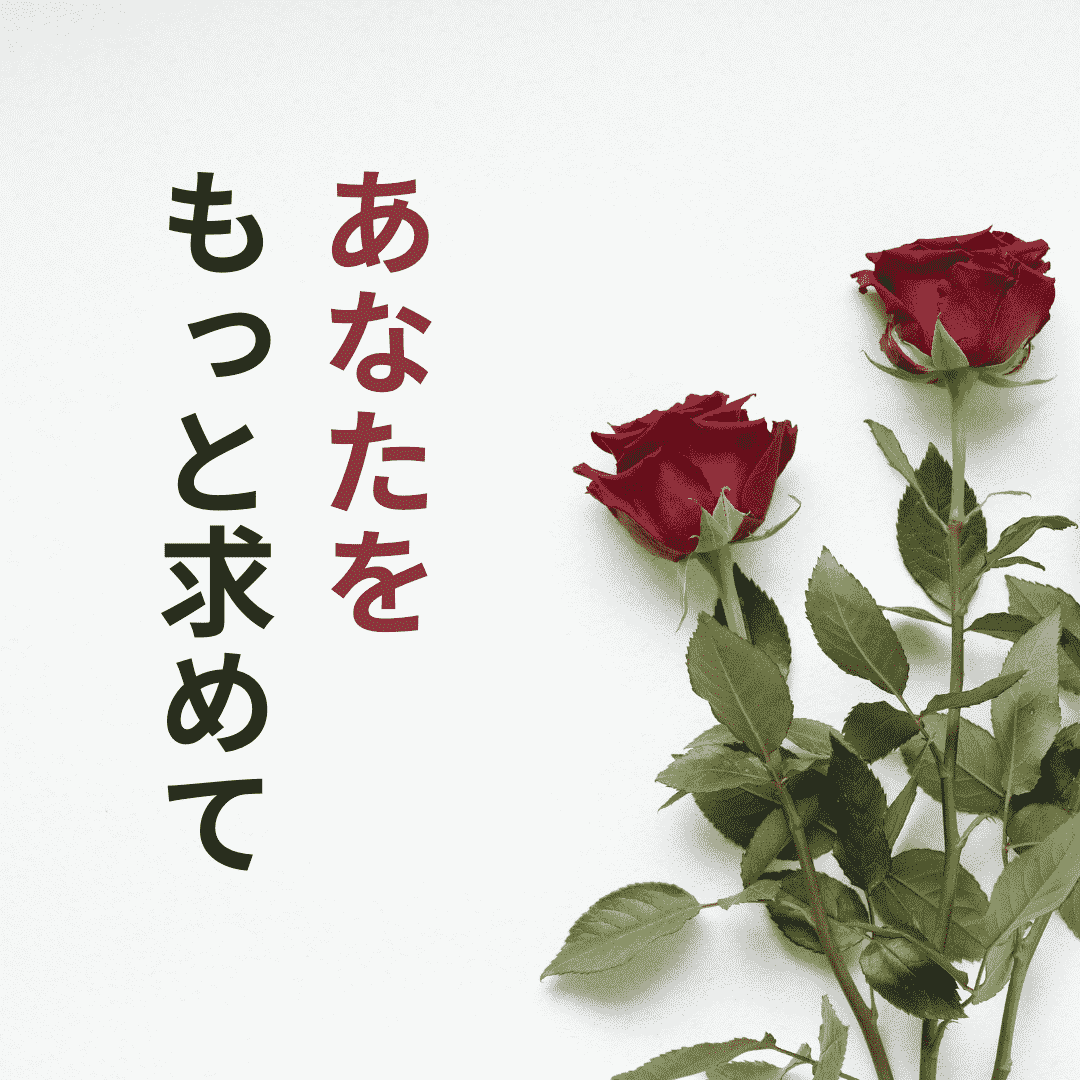

コメント