
0
真夏の夜に二人ですること
「何、また振られでもした?」
私をバカにするような視線を向ける彼の足目掛けて、砂を蹴り上げた。
既に帰る支度をしていたのか、ビーチサンダルに掛かった砂に不満げな顔をして何をするんだと文句を言ってきた。
毎日毎日飽きもせずに、嫌味たらしく私に話し掛けて来るものだ。
しかし、実際は彼の言葉は少し的を得ていた。
それが余計に腹立たしく思えて、唇を尖らせながら拗ねるようにサーフボードを車に積み込んだ。
モヤモヤとした気持ちのまま、ここにいたって何も始まらない。
今日はササッと食べれる物を用意して、夏らしく冷やし中華でも準備して、この鬱憤を晴らそう。
そう静かに心に決めて、海水を洗う為にシャワールームへと向かおうとした時に、強く腕を掴まれた。
私の腕を強く掴む彼を不満げに見つめる。
「…何よ、さっきまで私のこと馬鹿にしてた癖に」
「別に馬鹿になんてしてない。ただ波に乗ってる時でも楽しそうじゃないなって思っただけだ」
彼の言葉に思わず下を向いてしまった。
何も言い返す気力も湧かなくて、小さくため息ばかりが漏れてしまう。
自分の左手を見て、確かに一ヶ月前までは薬指にはめられていた指輪の存在を思い出す。
毎日見る度に胸が弾んで、仕事中にそれが目に付くだけで顔が緩んだ程嬉しかった。
挙式だって一緒に決めようと話して、雑誌やウエディングプランナーと話す時は最高な気分だった。
けれど、それがたったの半年で壊れてしまったのだ。
ただ一緒にお気に入りの映画を見て、これから待っている挙式について二人で話し合っていた時。
掛けたはずの鍵を開けて、家の中に泣きながら入って来たのは、彼の部下の女だった。
泣き腫らした目で家の中に入って来たかと思えば、妊娠検査薬を彼に見せて結婚してくれなんて叫んだ。
あの時程、辛い思いをしたことはない。
たった一度だけ体を重ねただけだと、言い訳を並べる彼にさよならを言った。
結婚も決まって、籍もこれから入れるって時に、彼の浮気はどうしようもない悲しみだった。
頼りになる上司で私の憧れでもあった彼と交際して、数年の歳月が流れてやっと夫婦になれると浮き足立っていた矢先にあれだ。
指輪は既にゴミ箱に投げ捨てて、彼のことを全て忘れる為に久しぶりにサーフィンも始めた。
ウエディングドレスを着る為に肌を焼かないようにと、大好きだったサーフィンすら我慢していたのに。
苛立ちと悲しみが毎日続いて、サーフィンをしてもそれが晴れることはなかった。
楽しいはずのサーフィンさえも辛くて、どうしたらいいのか分からなかった。
「茶化しならやめてくれる?今最高に気分が悪いの」
「そんなつれないこと言うなって。これでも愛を育んだ仲だろ?」
何を今更言っているのか。
彼とは遠くの昔に終わっているし、今は彼と関わりがあるのは、サーフィンだけだ。
けれどたまに、彼と一緒にいた時の方が楽しかったと思ってしまう。
あの時はお互いの趣味がサーフィンだったこともあって、毎日のように仕事終わりに海にやってきては、時間を忘れて楽しんだものだ。
彼は独身が好きなのだと言っていたのに、あっさりと私を選んでくれて、彼と過ごす時間は何よりかけがえのないものだった。
けれど私が婚約者に恋をしてしまったせいで、別れることになった。
その時も咎めることも責めることもしてこなかった。
ただ一言幸せになればそれで良いと言った。
その言葉を聞いて、私も彼の幸せを心底願っていた。
あっさりと関係は解消され、彼も何度か恋人を作っては別れてを繰り返していたらしい。
だが今はもう独身生活を謳歌して、不特定多数の女性と関係を持つだけになったという話だけを聞いた。
人のことを気遣ってくれる優しさがあるからこそ、彼には女性が寄ってくるのかもしれない。
小さくため息を吐いて、困ったように私を見つめる彼の方を見た。
そして彼に左手を見せた。
一瞬目が見開かれたが、すぐにいつもの彼の表情に戻り、私の腕を引き寄せてきた。
「そうか、なら今は独り身ってことなんだな?」
「だから何よ。馬鹿にするならすれば?結婚するのって浮かれていた私のことを」
「馬鹿にするもんか。お前と別れてから俺が特定の相手を持たない理由が分かるか?」
長い前髪を後ろに流して、小さくため息を吐いたかと思えば、開けていた車の中に押し倒された。
危うくサーフボードに当たりそうになり、抗議の目を彼に向けるも、いつもの表情とは違ってどこか真剣な目に見える。
「…何よ、慰めてくれるの?」
「慰めて欲しいって言うなら慰めてやるぜ?俺の厚い胸板でな」
「…本当馬鹿よね」
懐かしいやり取りに、私をからかうのが彼なりの優しさなのだと知る。
昔もそうだった。
暗い雰囲気が嫌いで、いつも人を笑わせてくれたりからかっては笑顔にさせてくれる。
人気もなく人通りも少ない海辺には、私達の車だけが止まっている。
結局誰かの人肌を求めてしまっていたのかもしれない。
彼の首に腕を回して、ゆっくりと引き寄せた。
私の気持ちに気づいたのか、口端を上げて嬉しそうに笑みを見せた彼は、すぐに首筋に軽いキスをして、鎖骨や胸にキスをした。
お互いにまだ海水の匂いがして、さっきまで早く家に帰ろうとさえしていたのに。
私をジッと見つめる目には、先程の茶化すような色はなく、熱を孕んでいた。
「…ん…ッ、うぅ…」
「ホント、昔と同じで胸とか弱いよな。それに吸い付きたくなるような肌も俺好み」
「うる、さい…ッ…ひ、ぅ…ッ!」
胸の谷間や鎖骨などに軽いキスをしていたのが、突然水着の上から胸に貪り付かれて、鼻に掛かるような甘ったるい声が漏れた。
ぢゅるっと胸の先端を甘く吸い付かれ、時折舌で弄ぶように、少しずつ天を向き始めた乳首をコリッと弄られる。
たったそれだけのことなのに、体は簡単に快感を拾い上げて、ビクッと体が震えた。
それでも彼の舌が止まる様子はなく、それどころか胸を下から鷲掴みにされ、水着をずらして直に舐められた。
熱過ぎる咥内は、ねっとりした唾液で溢れていて、それが余計に乳首に纏わり付いて火傷しそうだった。
「ひ、ッ、うぅッ…あつ、ッ…」
コリコリと乳首を弄られる感触に、身を捩って顔を逸らした。
体に熱がこもるような気がして、堪えきれずに熱い吐息を吐き出した。
長い前髪を何度も掻き上げて、無我夢中で乳首を吸い上げる彼を見つめて、ふと垂れる前髪を耳に掛けてあげる。
すると一瞬目を丸くし、すぐに目を細めて嬉しそうに笑みを浮かべて、強く乳首をぢゅるっと吸い上げられた。
突然の強い刺激に体が大きく震えて、背を仰け反らせてしまい、余計に彼に胸を突き出す形となってしまう。
ぢゅるるっと何度も執拗に乳首だけを吸い上げられる。
「あ、うぅんッ!ん、んッあぁ!」
「んッ…は…可愛い声だな。昔と変わらない。やっぱりお前が一番可愛い声してる」
トロッと唾液を纏わせた唇が乳首から離れていき、うっとりと私を見つめる彼に、顔に熱が集中した。
恥ずかしさと、もし誰か来たらという不安が押し寄せて、思わず目を強く閉じた。
はは、と楽しそうに笑う声が聞こえた瞬間、グリッと強く乳首を摘まれて、大きく背を仰け反らせて、腰をビクビクと痙攣させて達してしまった。
目をパチパチと瞬きして、自分に何が起きたか理解できないまま、快感の走る体にじわりと涙が溢れた。
何が起こったか分からないまま、膣内はヒクヒクと収縮して、トロリと愛液が滲み出した。
声を上げる間もなく自分は達したのだと気付き、一気に顔が熱くなる。
「恥ずかしがるなって。すっごく可愛い。そんなに感じてくれたなんてな」
一人で頷きながら嬉しそうに笑みを見せて、優しく私の腰の下に手を入れて、水着をスルリと脱がせていくのをぼんやり見つめることしかできなかった。
涙を流す私の頬を撫でながら、額や頬に軽いキスをしながら、愛液の溢れる膣をスリッと上下に擦る。
甘い痺れが体中を駆け抜けて、先程の達した余韻が抜けないままビクビクと震えてしまう。
どこを触られても敏感に反応してしまい、それが余計に恥ずかしくて、膣を擦る彼の腕を弱々しく掴んで首を横に振った。
「や、ぁッ、や、だッ…ぁッ、んぅッ…はず、かしい…」
「何言ってるんだよ。お前の恥ずかしい部分なんて全部見たって。どこにホクロがあるとか、何個あるかだって俺は分かるぜ?」
からかうように私を見つめる彼の目に、不安感がなくなっていく。
昔と変わらない彼の愛撫に体が敏感に反応して、元婚約者とのセックスのことなんて頭のどこにもなかった。
ただ彼との思い出だけが頭を埋め尽くして、早く次をして欲しいと、期待の眼差しで彼を見つめてしまう。
辺りは薄暗くなり、彼の後ろからは夕日が沈むのが見え隠れしている。
ぼんやりと周囲を見つめながら、彼の手を掴んで膣の入口に導いた。
目を大きく見開いて、喉が上下するのが見えた。
「ほんと…お誘い上手だな」
小さく耳元で囁かれ、熱い吐息を吐いて、彼が私の上に覆い被さってきたのを見つめていた時。
ゴリッと膣内に硬い何かが押し入って来る感覚があった。
「あ、ぁぁぁ、ッ、んあぁッ!」
肉ひだを割って入ってくる太い陰茎は、何度もビクビクと震えながら、肉壁を押し上げて奥まで入ってくる。
痙攣する腰を止めることが出来なくて、彼の頭を抱き抱えるようにしがみつくと、鎖骨や胸に何度も吸い付かれ、仰け反って甘い喘ぎ声を零す。
グニグニと奥まで突き進んでくる陰茎に、快感が体を駆け抜けていく。
やっと子宮口まで辿り着いた所で、彼が深い息を吐いて、唇に軽いキスをしてきた。
「は…ッ…痛かったら言えよ?」
困ったように笑うも、額に滲む汗や眉を潜める表情を見て、彼も限界が近いのだと知る。
がっしりと強く腰を両手で掴まれ、ガクガクと突き上げられる膣内に、何度も体が痙攣してしまう。
久しぶりのセックスの感覚が堪らなくて、飲み込めない唾液が口端から溢れてしまう。
何度も垂れてくる前髪がやけに色っぽくて、子宮口ばかりを突き上げてくる彼に、縋るように彼の両頬を手で包み込んで引き寄せた。
唾液で濡れる唇を何度も何度も重ねながら、火傷しそうな程熱い舌を絡めていく。
「んぶッ…ひ、ぅッ!んんッ…あぁッ!だぇッ…だめ、ぇッ!も、ぉッ…いっちゃッ、いくぅッ…!」
きゅうっと強く膣内が痙攣し、激しく腰を震わせて中を突き上げられる快感に達してしまった。
体を仰け反らせて、過呼吸じみた呼吸をしながら余韻に使っていると、今までよりも早く膣内を突き上げられて、ひぐっと情けない悲鳴が漏れた。
グンッと強く腰を引き寄せられて、子宮口が更に強く押し上げられる。
「ッ、ひッ、ぐッうぅぅん!」
強烈な快感が体を駆け抜けていき、きゅうっと強く質量の増した陰茎を締め付けると、彼の顔も険しくなり、唇を噛み締めている。
「は、ぁッ…でる…ッ!」
グッと強く目を瞑る彼が、よりいっそう強く陰茎を子宮口に打ち付けた瞬間。
びゅる、びゅるっと勢いよく精液が吐き出された。
飲み込むことも、浸透していくこともない精液が膣内から溢れ出し、ドプドプと止めどなく流れ出してきた。
精液が逆流する感触さえも、快感となった体を襲い、唇を噛み締めてビクンと体を震わせて達した。
お互いに荒い呼吸音と、時折聞こえてくる波の音に酔いしれながら、彼の顔をジッと見つめた。
「…俺の彼女になってくれるなら…ここもっと沢山満たしてあげるけど、どうする?」
すりっと軽く下腹部を撫でられる。
いつもの茶化すような顔に戻り、そんな顔をされても愛しさが込み上がり、軽いキスを唇にして締まりのない顔をしながら笑みを浮かべた。
私の行動に目を大きく見開いて、驚きを隠せない彼を見つめながら、ゆったりと腰を動かしそれが答えだと示した。
それに応えるように再開された腰の突き上げに、外が真っ暗だろうとお構い無しに、久しぶりのお互いの熱を確かめ合うのだった。














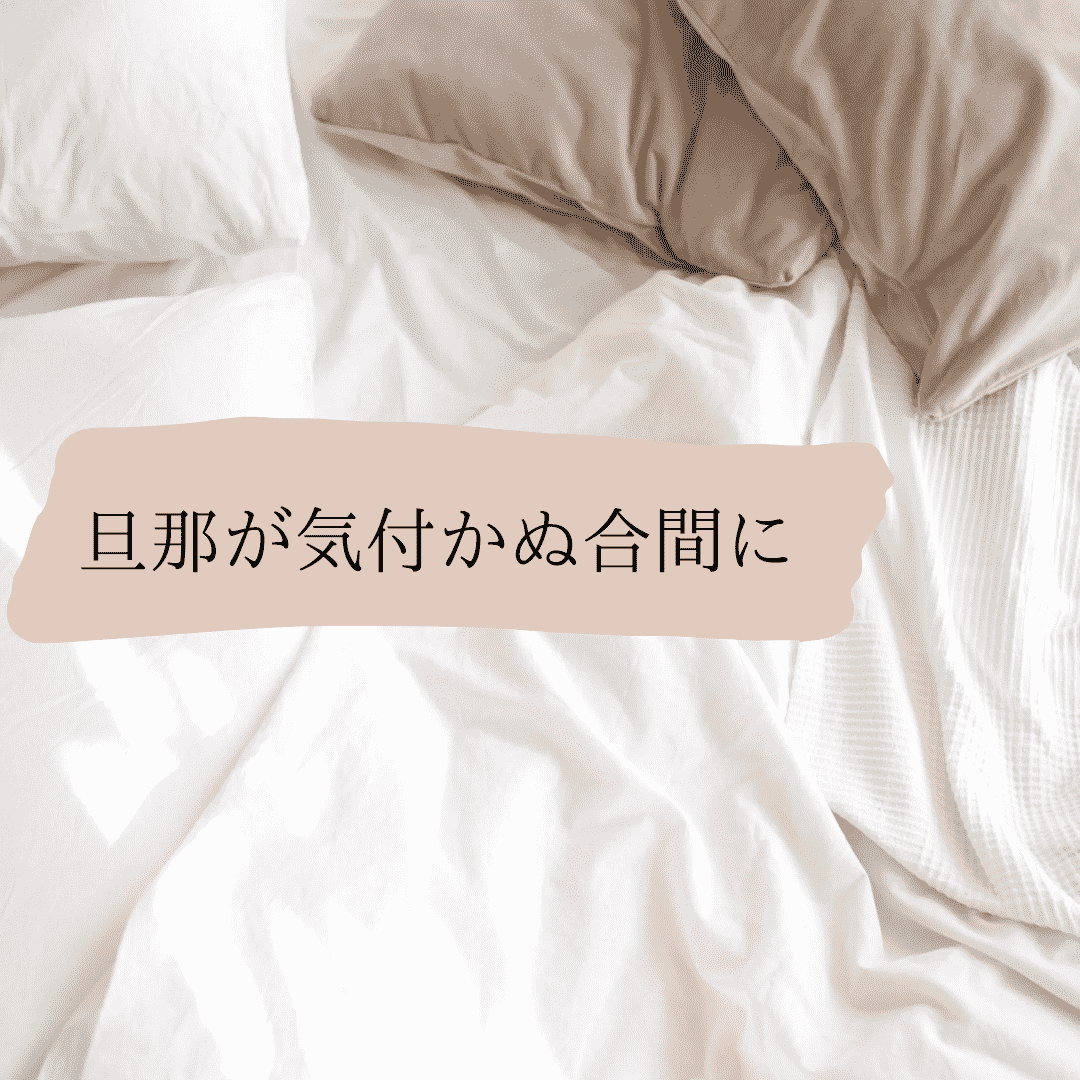
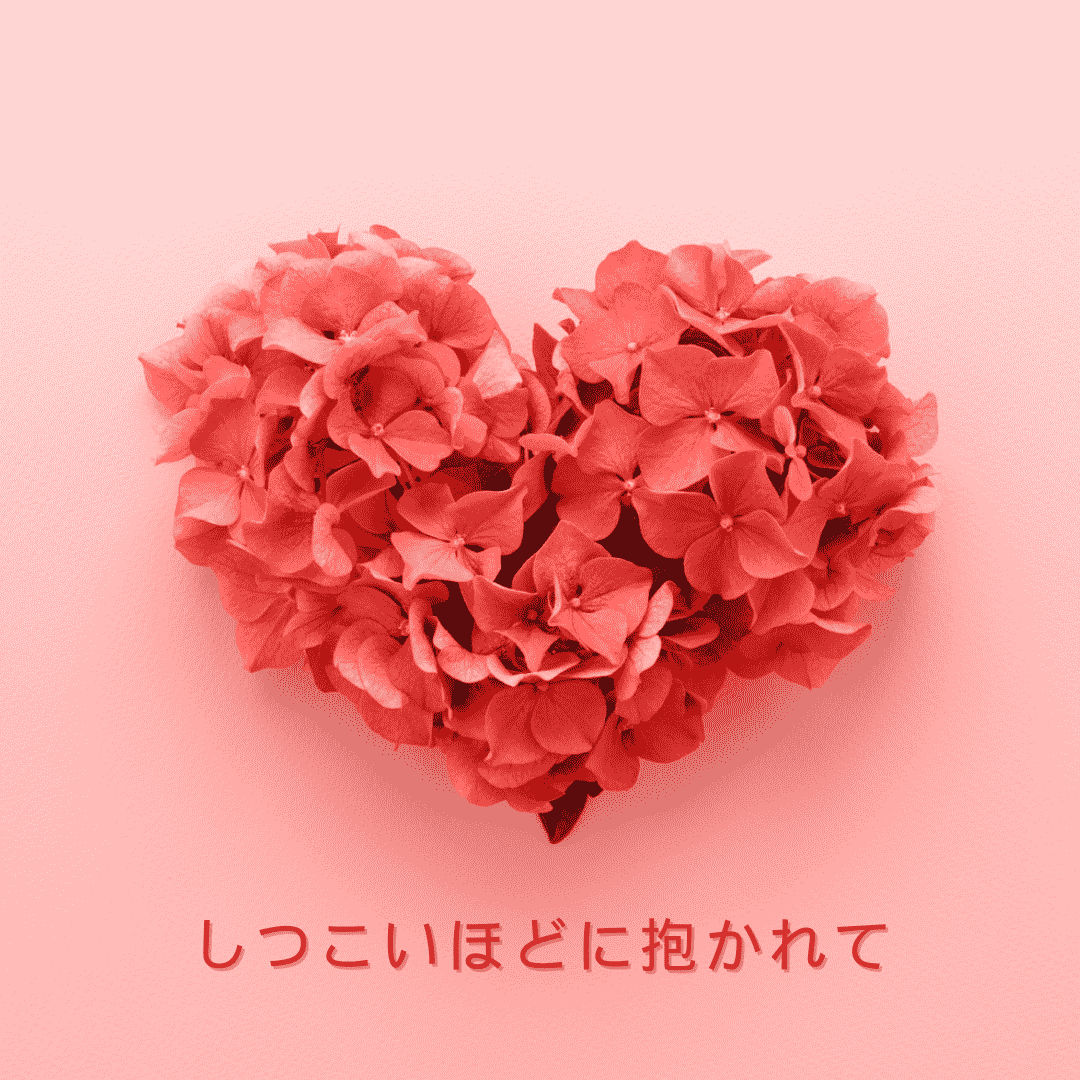

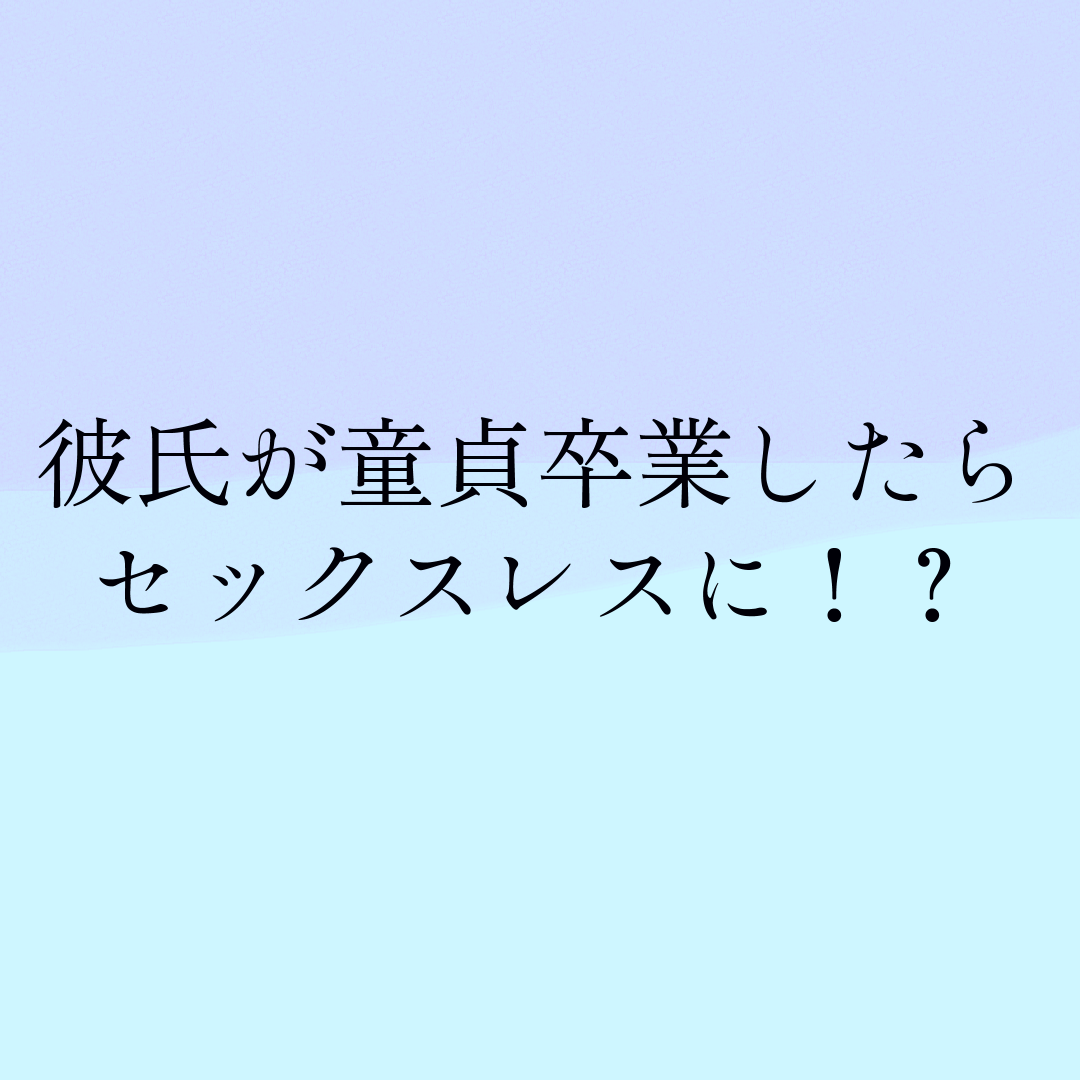








コメント