
0
メン×メン
(まただ……でも今日は絶対マズいやつだ……)
宇津木隆美は深呼吸を何度か繰り返す。そして、意を決して視線を下に向けた。
するとそこには、想像とピッタリ一致する、毛深い中年の手が、自分の太ももに這わされているのが見えた。
「うっ……」
思わず漏れてしまう声に反応するかのように、耳元でブフッと鼻息が漏れる。
「き、気付いちゃったかな……お、おじさん、君みたいに可愛い子と毎日こうやって……身体が密着してるとね……ほ、本当に、本当に……」
言葉が途切れる度に、長く熱い息が耳元にかかり、背中に悪寒が走った。
「あ、あのっ……」
きつく言い返そうと思って出した声は、蚊の鳴くような大きさしか出ない。
隆美はギュッと瞳をつぶった。と同時に、明るいあの声がバスの車内にこだました。
「あっれー?隆美じゃん!おはよー!!」
「し、白石くん!?」
変態行為を働く中年と隆美の間に割って入るような形で、白石が隆美の肩を組んでくる。
「ちっ……な、なんだよ……」
中年は白石の登場に舌打ちをして見せるものの、そのままそそくさと反対側を向き、何事もなかったかのようにつり革を掴んだ。
「お、おはよう。白石くんもこのバスだったんだ?」
「んー今日はたまたまな。昨日チャリがパンクしちゃってさー。朝練に間に合わないから仕方なく。隆美は?お前部活ないだろ?」
「僕は、ちょっと自習のために……」
「へー-まっじめー!」
カーブするバスの動きに合わせて、白石が隆美に寄りかかってくる。制汗剤だろうか。爽やかな柑橘の香りが隆美の鼻腔をくすぐった。
ブロロロ……と去っていくバスを、二人並んで見送る。
すると、白石は歩き始め、口を開いた。
「なぁ、さっき襲われてただろ?」
「えっ?」
驚いて振り返ると、制服のポケットに手を突っ込みながら、いつものあの飄々とした笑みを浮かべる白石の姿が、視界いっぱいに入る。
「いつもなの?アレ。」
「あ、え……あ、と。なんか数か月前から……でも、あそこまで、直接触られたのは……初めてかも。」
「お前、なんだかんだ気弱そうな感じするもんな。」
「あ、うん。ごめん。」
通学カバンを胸に抱きかかえ、隆美はなんどか頭を下げた。
「隙アリアリって感じで。」
「うん、そうだね、気を付ける……」
「やられても大きい声出せねーだろ。」
「うん、ごめん。」
「そしたら逆にこっちからヤってるとこ見せつけたらいーんじゃね?」
「うん、そうだ……ってええ??」
白石の突飛な発言に、隆美が頓狂な声をあげる。
「あーいうオッサンはさ、コソコソ隠れてでしかやれねーんだよ。だったら逆にこっちから見せてやればいいんじゃね?」
「え、ど、どうやって……?」
色々と疑問は浮かぶのだが、まず最初に隆美の口からこぼれた疑問はそれだった。
「俺に任せろって。」
そう言って白石は隆美に近寄ると、頬に手を触れながら静かに微笑んだ。
***
「ほ、本当に大丈夫?」
翌朝、二人はいつも隆美が使う停留所で、バスが来るのを待っていた。
「大丈夫だって、俺に任せろ。」
「うん、ありがとう。ごめんね、白石くんにこんなことさせて……」
「気にすんなよ。」
「でも、どうして?僕にそこまで……」
純粋な隆美の質問に、白石は少し間を置いたあと、静かに口を開き……かけたところでタイミングよくバスが到着した。
「まぁ、気にするなよ。」
「え?あ、うん……わかった。」
白石は、何かほかに言いかけていたような気もしたが、バスの音にかき消され、隆美の耳には届かず、仕方なく彼の後を追ってバスに乗り込んだ。
いつも通りの混雑。ステップをあがった所、運転手からも座席に座る人間からも死角になるところに、今日もあの中年は立っていた。
隆美の姿を確認すると、あからさまに、いやらしい笑みを浮かべて見せる。
「っ……」
昨日のあの感触を思い出し、隆美は一度軽く身震いする。
「心配すんな。シミュレーション通りやるぞ」
ポンと白石に肩を叩かれ、緊張がほぐれる。
「うん、わかった。」
意を決して頷くと白石と隆美は、丁度中年の視界に入るギリギリの所で立ち止まる。
『バス、動きます。おつかまりください。』
運転手のアナウンスと共にバスが動きだし、慣性の法則にしたがって、乗客の身体が一様に揺れる。隆美は白石にバックハグされる形で、窓に身体を押し付けた。
「隆美、いいか?」
「うん。」
コクリと頷く隆美に、白石は満足そうに微笑みかけると、そのまま中年に見せつけるように、ゆっくりと隆美の身体に両腕を絡ませた。
「っ……ぁ」
昨日と同じ柑橘の匂いが鼻腔をくすぐる。マスクをしていても感じるその香りに、隆美は思わず声が漏れた。
「抑え気味にな。」
そう耳打ちされた隆美は、静かに頷いた。すると、その返事を合図に、白石の腕が静かに隆美の下半身に這わされた。
「っっ!!」
ビクンと自然に身体が跳ね、肩にかけていた鞄を、ズルリと足元へ落としてしまった。
近くに立っていたOLが、その音に一度だけこちらを見たが、すぐに視線をスマホに戻した。
(あ、危ない……気持ちよくなってどうするんだ)
せっかく協力してくれているのに、と隆美は気持ちを入れなおすように、深く深呼吸する。
「大丈夫、力抜いて。」
そう静かな声音で囁かれただけで、隆美は脱力してしまった。その隙を見逃さず、白石は隆美の足を抱え上げるようにその間に腕を伸ばし、ゆっくりと一度スラックス越しに、隆美の股間を撫で上げた。
「ぅ……んぅ」
たった一度撫でられただけなのに、自分でもわかるぐらいに、隆美のペニスは怒張を始める。ジュン…と滅多にこぼれない愛液が、下着に染みるのも感じた。
「ふふ、もう甘勃ちしてる。朝抜かなかったの?」
「そん……な、しないよ……」
「なんで?すっげーキモチイイのに?」
相変わらず耳元で囁かれ、隆美はどんどん息があがってしまう。白石は、バスの動きに合わせて、不自然にならないように、器用に幾度も、隆美に股間を撫で上げた。
「っぁ……ん、あ…はぁっ……」
バスの窓ガラスに吹きかけるように、熱く甘い吐息がもれ、隆美の周りだけが曇る。
「隆美の可愛いな。直接触っていい?」
「へ?……え、あっ!ぁんっ!」
間髪入れず、白石は器用にフロント部分を開けると、流れるように隆美の下着の中に手を突っ込む。直にペニスを握られ、隆美は一瞬甲高い声を漏らすが、車内アナウンスにうまくかき消され誰も気付いていないようだ。
「めっちゃピンクじゃん、もしかして、まだ使ったことないの?」
「ふぇ?あ……ぁ…っ、んぅ、な……ぃ」
「へぇーそうなんだぁー。」
白石は含みを持たせた声でそう囁くと、更に手の動きを早めた。
クチュクチュと卑猥な水音が聞こえてくるが、周りの誰もが、自分達の醜態に気付いていないようで、幻聴かと思うほどだった。そして、息を深く吐き、与えられ続けている快楽を追い始めたのだ。
「あ……ぁ……んっ、ぅ…んんっ!」
「ねぇ、隆美。知ってる?男でもさぁ、女みたいに気持ちよくなれんだよ。」
「うっ……うっん、……えぇ?」
刺激を受けながら意識を飛ばしかけていた隆美は、白石の言葉に彼の方を振り返る、と丁度あの中年と目があった。
「!!」
ビクン!と羞恥に身体を震わせるが、白石はそんな隆美には気付かず、それまでペニスを掴んでいた手を、彼の臀部の方へ回し、その秘部へと指を這わせた。
「ふあっ…!」
今まで触れる機会などなかった箇所を触られ、思わず下肢の力が抜けて、そのままガクンとバスの壁に凭れ掛かった。
「……大丈夫ですか?」
寄りかかった際にバタン!と大きな音を立ててしまったため、隣に立っていた先ほどのOLが隆美に声をかけた。
「大丈夫ですよ、ちょっとバランス崩しただけみたいです。」
コクコクと頷くだけの隆美に変わって、白石が人当たりの良い声で返事を返した。その言葉に安心したのか、OLはまたスマホに集中し始めた。
「隆美、あんまり大きい声だしたら、聞こえちゃうだろ?」
「ごめ……でも、あのオジサンが。」
「あぁ、あいつ?あいつなら最初から俺たちのことカメラで撮ってるよ。」
「えっ!うそ……あンっ!!」
「あーあ、せっかく出せそうだったのに、ちょっと小さくなっちゃったね。ごめんね、ちゃんと出させてあげるから。」
あまりの羞恥に少しだけ首を傾げた隆美のペニスを、白石はまた丁寧に扱き出したのだ。
「気持ちよくなっておきな。」
「ん……ぅ」
そこまでやる必要が本当にあるのか、と隆美の最後の理性が叫んだ気がしたが、今はもう、どうでも良い。白石がくれる快楽の方が、何倍も良かったのだ。
「んっ、んっ……んんぅ!」
攻め立てられ、腰のあたりに熱が集まり、数少ない経験から吐精が近いことを悟る。
「し、白石くん……でちゃ…」
「いいよ。俺の手の中に出していいから。」
「だ、ダメだよ……んっ、ぁあ……あっ、あっ」
必死に唇をかんで声を我慢しようとするが、それでも口の端から、淫らな声が漏れてしまう。
「隆美、噛んで。」
白石は短くそういうと、マスクの端から自分の指を突っ込み、隆美に咥えさせた。
「ふぐっ……」
慌てて吐き出そうとするが、グッと下歯に指をかけられ、うまく吐き出せない。それよりもそのまま歯列を指でなぞられ、また別の快楽が生まれてきたのだ。
(あ…ダメ、出ちゃう……)
ブルッと一度大きく身体を震わせると、それに呼応するように、白石のペニスに添えられた手の動きが早くなる。
「んっ、んっ……んんんっ!!」
隆美のペニスが限界を訴え、白石の手のひらの吐精しようとした矢先、
キキーーッ
と大きくバスが急停車した。
「んぅ……」
その勢いで隆美と白井は重なるように壁に押し付けられ、隆美の精は白石の手ではなく、自身の下着の中に思い切り吐き出された。
『急停車失礼したしました。出発します。次は高校前ー高校前ーお降りの方はボタンを押してください』
何事もなかったかのように流れる運転手のアナウンスに、隆美は肩で息をしながら、そのまま深く深呼吸する。
「隆美、平気?」
気付けばいつのまに綺麗にしたのか、涼しい顔をした白石が、優しく自分の頭を撫でてきた。
「し、白石くん……」
「今日はこのままサボろっか。色々汚れちゃったし……それに…」
白石はそこで言葉を区切ると、いたずらっぽく笑って、隆美の耳に耳打ちした。
「隆美、すっごいエッチな顔してるから、学校行ったら大変だよ?」
「へっ?」
そう言って、隆美は恥ずかしさのあまり、慌てて窓ガラスの方を向いた。うっすらとうつる自分の顔は、誰が見てもわかるほど、蕩けていた。
「俺、一緒にいるからさ。」
ポンポンと頭を優しく撫でられ、隆美の胸はキュウと締め付けられた。
「うぅ……ごめん、白石くん。ありがとう。」
『高校前ー高校前ーお降りの方前から順番にどうぞー』
タイミングよくバス停に着くと、二人は連れだって降りていく。
「隆美、俺ヤボ用があるから、ちょっと反対のベンチに座ってな。このまま帰ろう。俺ん家の方が近いから、シャワー浴びて一緒にゆっくりしようぜ。」
「わかった。」
おぼつかない足取りで、横断歩道を渡る隆美をニコニコと見送ると、白石は急に表情を変えて、振り返る。
「ありがとな、オッサン。協力してくれて。」
目の前には、隆美に痴漢行為を働いていた中年が、いやらしい笑みを浮かべて立っていた。
「や、約束通りにしたからな!ほ、ほら動画も!」
そう言いながら差し出すスマホを、白石は無言でひったくる。
「おー、いいじゃん。最高。やっぱり頼んで正解だったわ。」
「こ、これで警察には……」
満足そうに笑う白石に、中年はすがるようなまなざしを向けた。
「さーな。次、隆美を狙うような真似したら。どうなるかわかってんな?」
「触れって指示したのはそっちだろう!私はずっと密着して見ているだけだった!」
ムキになる中年に白石は、ハハッと笑うとまた表情を無にして、中年の胸倉をつかむ。
「見るのも罪だっつってんだろ。いいか。金輪際近づくな。」
そう言い放つと、白石はそのまま中年を放り投げた。
中年は、ヒイッと短い叫び声を残し、そのまま後ずさりしながら去っていった。
「チッ……まぁいいか。これで俺は晴れて隆美の救世主になったわけだし。」
パンパンと手を叩くと、そのまま白石も踵を返し、歩き出した。
「しらいしくーん!バスくるよー!」
道路の反対側から自分を呼ぶ隆美の声に、白石は大きく手を振る。
「いじらしいなぁ、これから何されるかわかってんのかねぇ。」
ニヤリと笑いながらそう呟くと、白石は、小走りで、隆美の待っているバス停へと向かっていった。








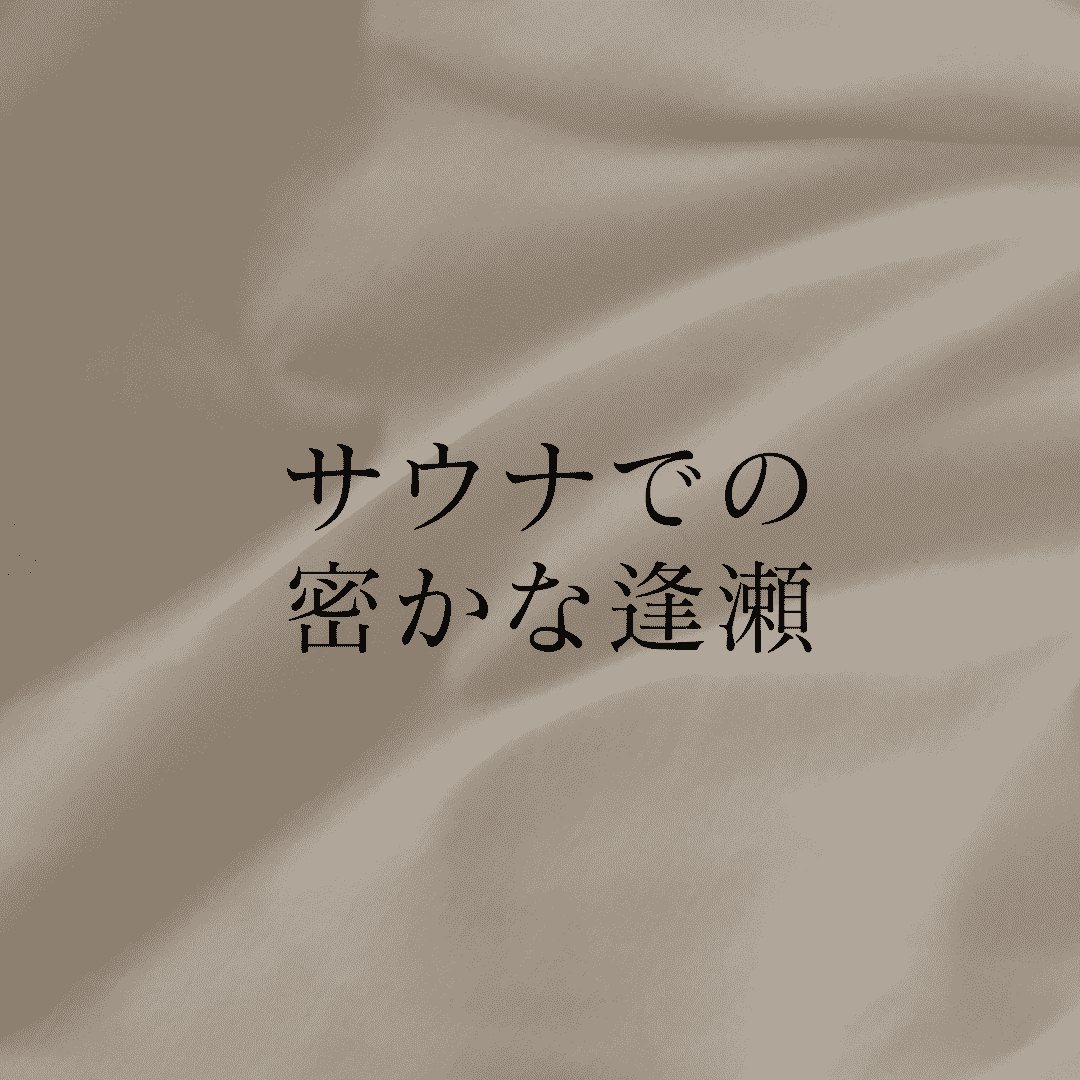
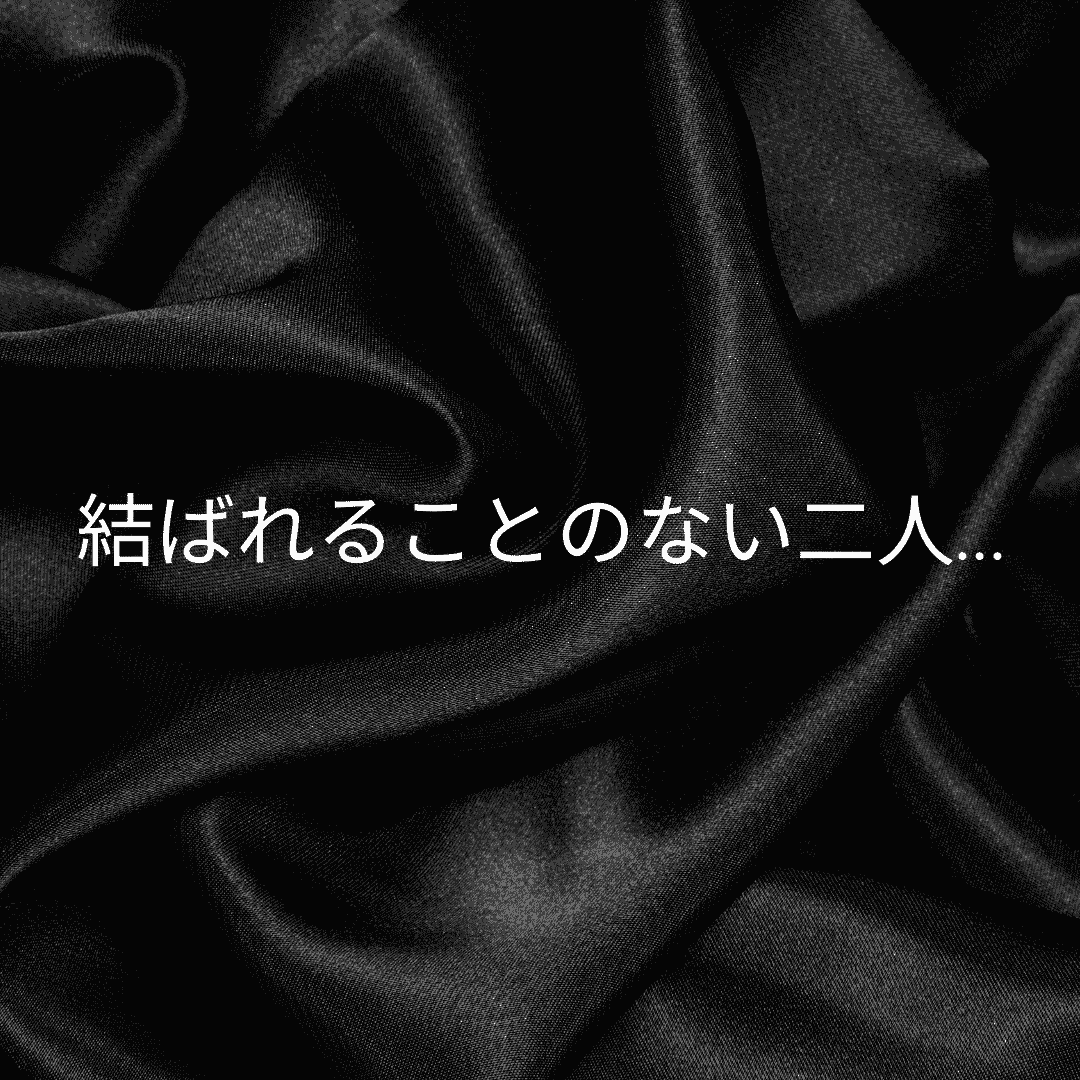




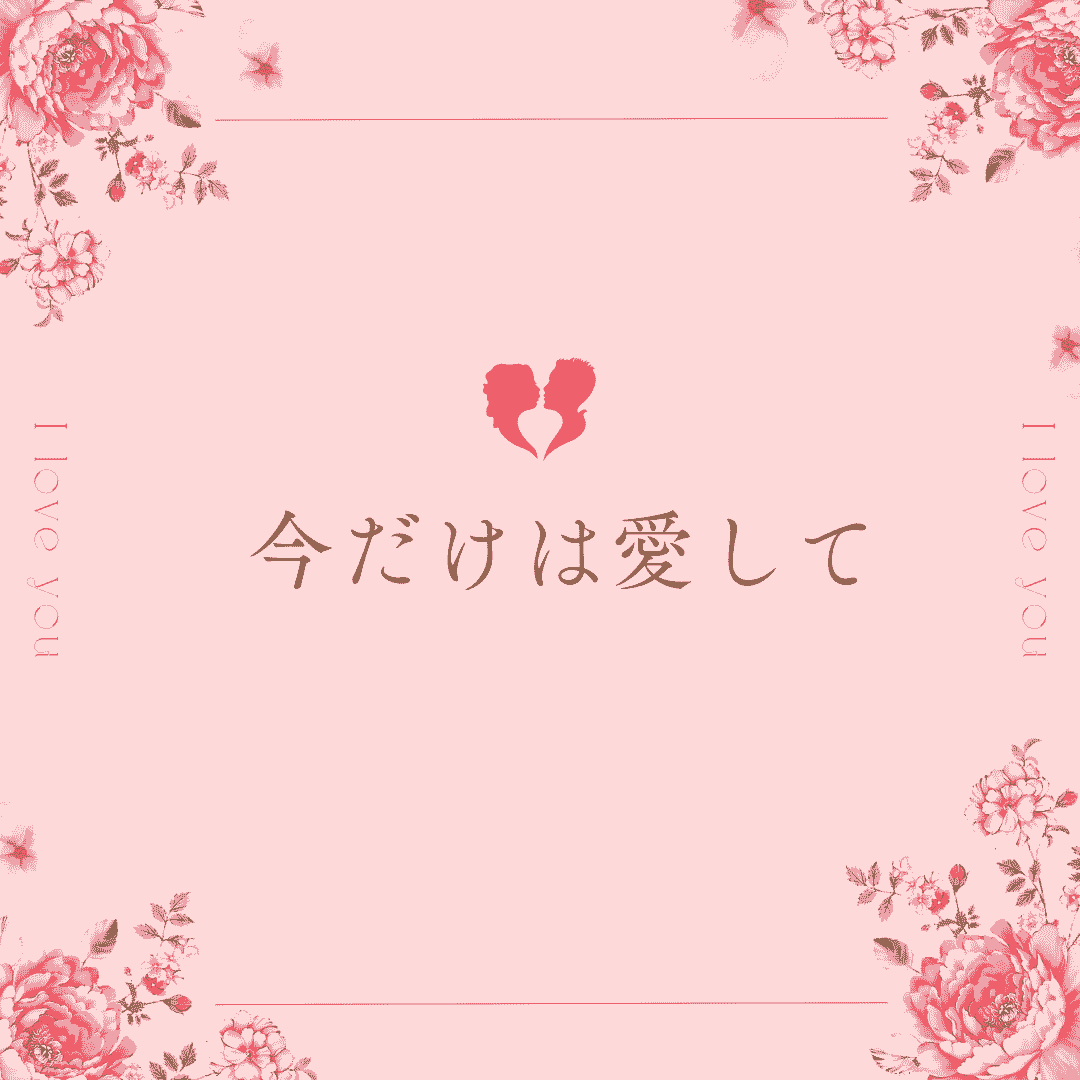

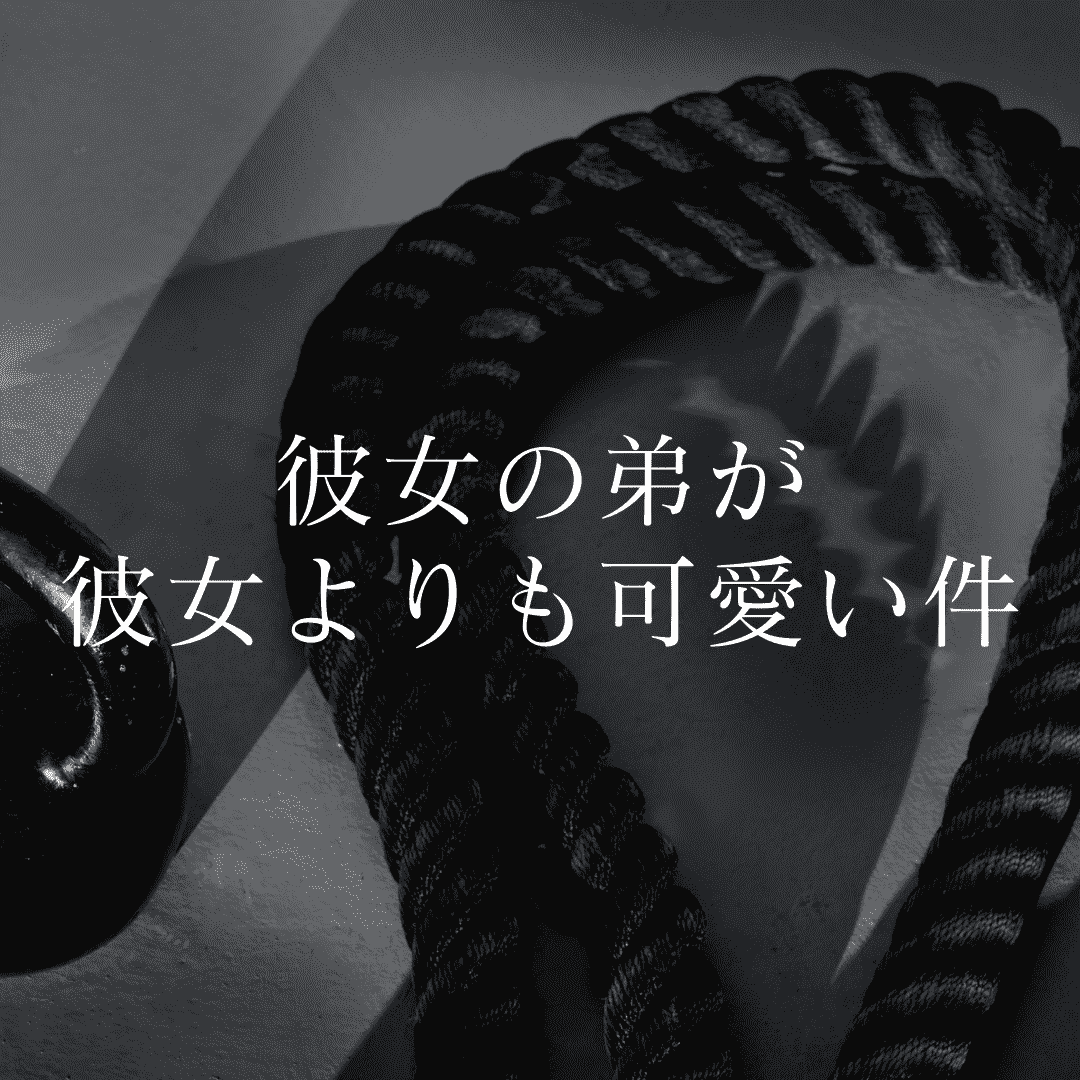




.png)








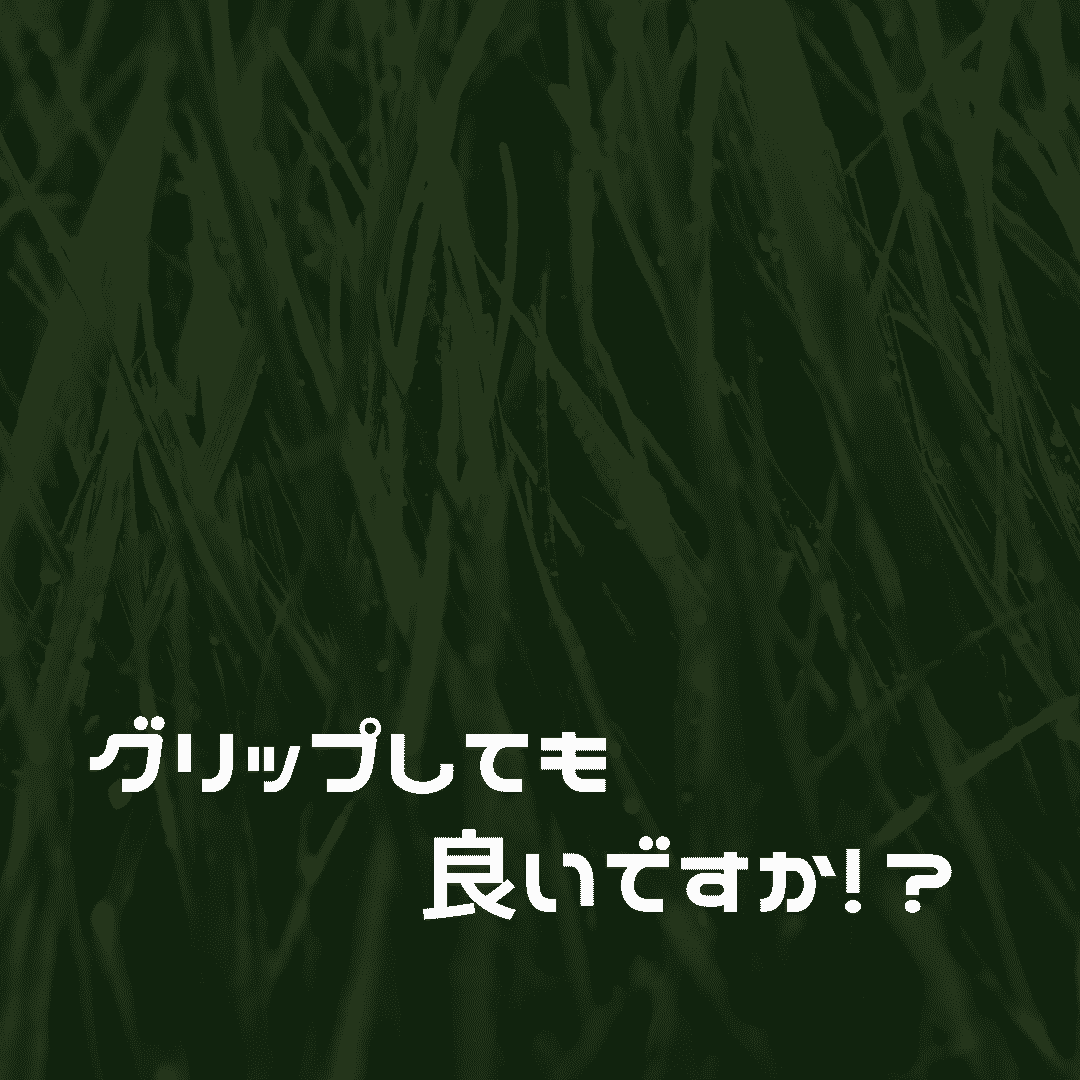

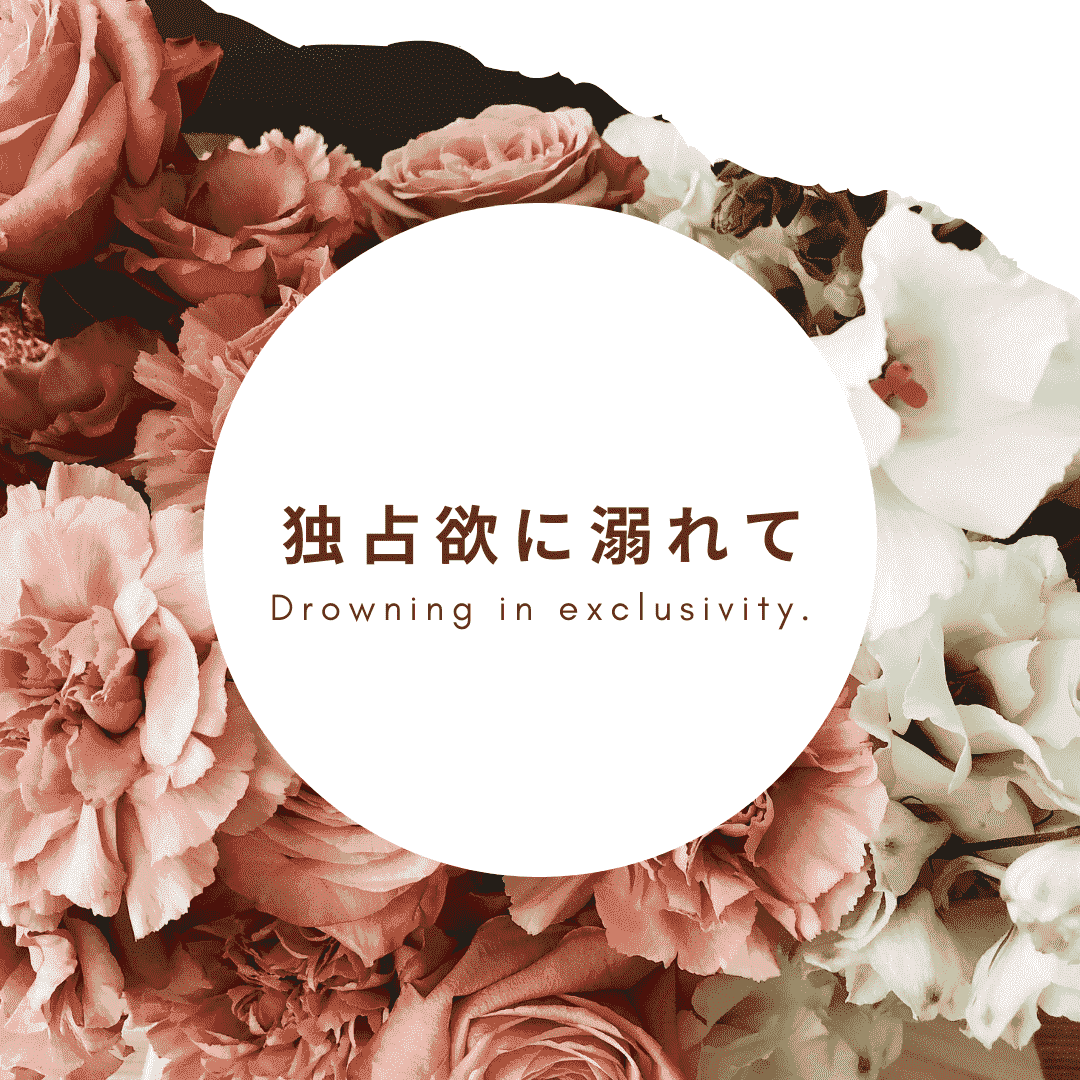
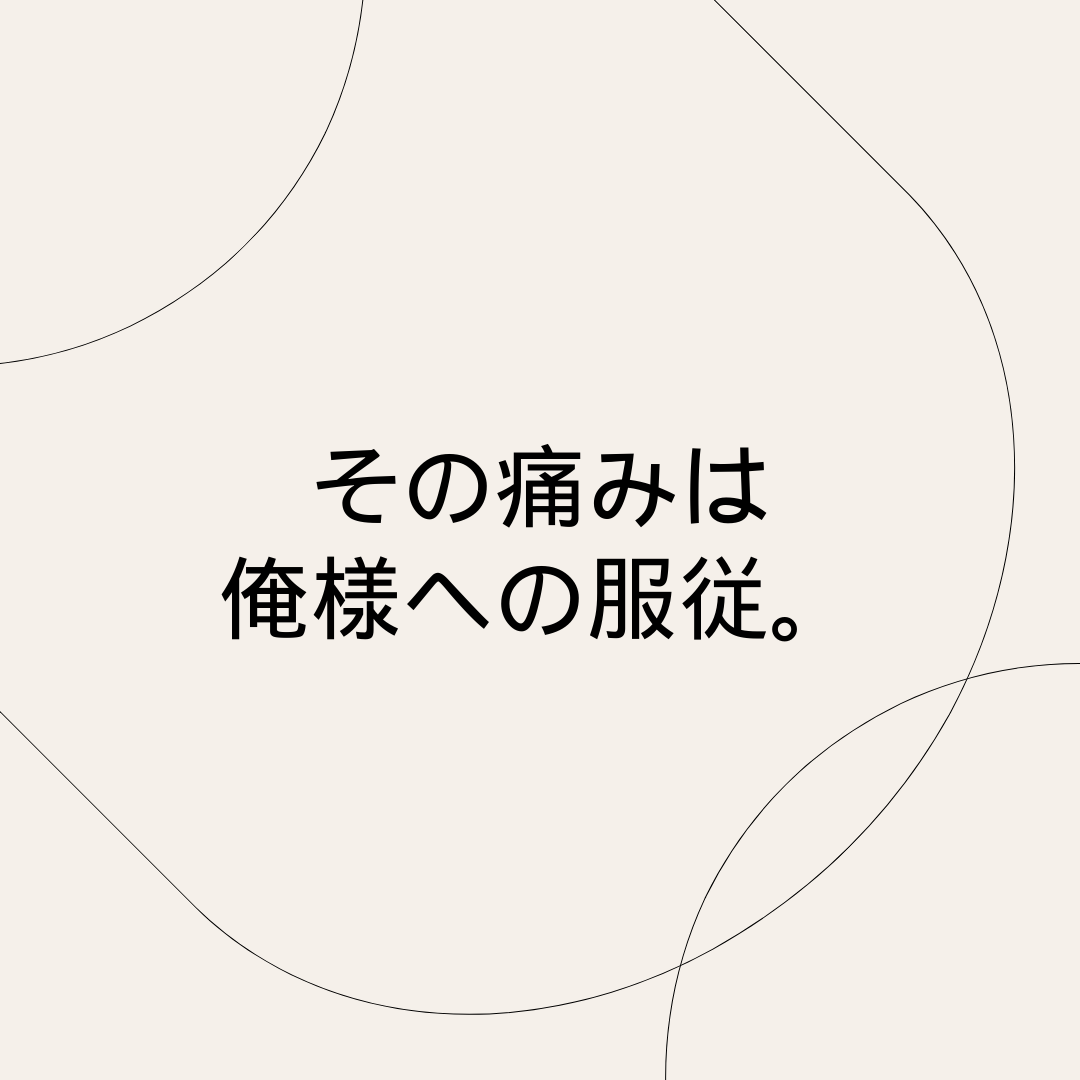
コメント