
0
絶対に手を出さないと誓ったはずが
コロナ禍が終了して通勤地獄が復活した。
和美は溜息をつきながら、今朝も超満員の通勤電車に乗る。
(在宅勤務の時は良かったな……)
(仕事が終わったら、郁夫とはすぐにできたし。)
「す、すごい人だな。」一緒に乗ってくれている郁夫がうめく。
再び、超満員電車に乗る羽目になった和美は、痴漢対策として、ボーイフレンドの郁夫にいつも一緒に電車に乗って貰っている。たまたま、勤めている会社の最寄り駅が同じということもあって。
(ま、郁夫と一緒なら痴漢にあうこともないと思うし。)
そう思っていた。その時までは…。
スマホが振動してメール着信を告げたため、私はポケットからスマホを取り出そうとした。
その時、電車が揺れて、スマホを落としてしまう。
(あ……!)
足元に落ちたと思うのだが、満員電車の中、確認できない。身体をすこしずつずり下げて、スマホを拾おうとこころみる。
向かい合わせの郁夫に押し付けられた胸がひしゃげたままの状態で、ずりずりと郁夫の身体をなぞりながら、身体をずり下げていく。やっと床にまで手が届いたが、巨大な胸のせいで下がまったく見えない。
(ど、どこかな?)
郁夫の股間に胸を押し当てたままで、手で床をあちこち探ってみる。
左右に身体を動かすたび、柔らかい胸が、郁夫の股間をむにむにと刺激してしまっている。
(あ、あった)
やっとスマホを見つけた私は、ゆっくりと立ち上がる。
今度はふたつのふくらみが、先ほどとは逆方向に下から上へと郁夫の身体を撫で上げた。
ようやく元の姿勢に戻った私は、メールを確認しようと郁夫に背を向けてスマホを覗き込んだ。
(あれ?)
なんだかうなじが涼しく感じる。少し経って、それが、後ろにいる郁夫の鼻息のせいだということに気づいた。同時にお尻のあたりを誰かが触っているのに気づいた。
(え、ちょ、ちょっと、痴漢?)
それが郁夫の手だと気づくのには、さほど時間はかからなかった。大胆にもスカートの上部の隙間から手を差し入れ、パンティの中に手を差し入れて来ている。
(あっ、ん、んんっ)
よく知っている指が、割れ目の後ろから入り込んでくる。入り込んだと思ったら、上下左右にかき回し始めたのだ。
(んぅうっ、い、いっちゃう…ん、ん、んん!)
満員電車の中で周りに聞かれないよう、私は声を抑えるのに必死だった。
「もう、今朝はどうしてあんなことをしたの?」
帰宅した郁夫に対して詰問する。二人は同棲中なのである。
「あんなことをされて、興奮するなっていうのは無理だよ。」
「これでこすられたら、男はみんな勃起するって。」
私の胸を両手で持ち上げながら、郁夫は反論した。
「ボディガードに痴漢されていちゃ、話にならないじゃない?」
「捕まったらどうするのよ?」
「その時はプレイだといえばいいじゃないか?」
(もう。郁夫ったら。)
私は恥ずかしさで顔が火照るのを感じながら「電車の中では手を出さないで!絶対によ!」と郁夫に向かって、言い放った。
「自信ないけどなあ。こいつがいるんだから!」
私のおっぱいを両手でお手玉の様に弄びながら、郁夫は訴えてきた。
「でも。事前に充分シテおけば、大丈夫かも?」
「……え?」
私はあっという間に押し倒され、Tシャツを脱がされてしまった。飛び出した二つのふくらみに郁夫はむしゃぶりつく。
「あっ、…はあぁん…んんっ」
いきなり襲われた驚きのあとに、快感が怒涛のように押し寄せてくる。
「今日はずっと我慢していたんだぞ。こいつのせいで。」
私のおっぱいを揉みしだきながら、そう呟く。次にスカートとパンティもあっという間に取られてしまった。濡れ始めている私のアソコに肉棒を突き立てると、
「和美のおっぱいは男にとっては凶器なんだぞ。」
「あんっ…し、仕方ないじゃない。」
「電車に乗っている男どもは、どんな眼差しでお前を見つめていると思う?」
「俺がボディガードにならなかったら、あっという間に痴漢されて犯されるぞ!」
「だ、だから郁夫が守ってよ!」
(妬いているのね)と嬉しくなった私は、そう叫んだ。
「今朝、本当はこうしたかったんだ。」
郁夫は背中に回した私の両手を左手でおさえると、後ろから突き立てて来た。右手は背後から胸を揉みしだき続けている。
「っんあ!あっあんっあん!」
両手の自由が利かない状態で前かがみになりながら、郁夫の肉棒で、リズミカルに突き上げられる。
(あ、朝こんなだったら、座席に座っている人に私の感じている顔をみられちゃってたわ。)
でも、それもいいかもと思い出すと、愛液がどんどん溢れ出して来るのを感じた。それを食い止めようと、両脚を閉じようとする。そうすると、アソコが肉棒をぎゅっと締め上げるのだ。
「うう、締まって、気持ちいい。もう、出そうだ。」
「んぅっ、んっ、あっ、い、…いく!」
郁夫の熱いほとばしりを受けて、私は絶頂に達した。
「き、今日も相変わらずぎゅうぎゅう詰めね。」
目の前の郁夫に、そうつぶやいた。
「まあ、仕方ないか」
「しかし、何とかして欲しいよな。」
昨夜プレイしたせいか、今日は手をだしてこない。夏の前とはいえ、満員電車の中は蒸す様な暑さになっている。昨日のプレイのことを思い返すと、上気してしまい余計に暑くなってくる。
(暑いな。前にいるのは郁夫だし、少しくらいなら服をはだけてもいいかな。)
そう思って私はブラウスの第1ボタンを外した。大きな胸の間で蒸れた空気が開放され、少し涼しくなる。
(あ~、涼しい)
襟を少しぱたぱたさせながら仰ぐ。胸元からはブラと、その隙間から乳首がほんの少し顔をのぞかせている。私は、自分の胸元をじっと見つめる郁夫の視線に気が付いた。電車が揺れて、二人の密着度がさらに増していく。
(え、ま、まさか)
何か固いものが太もものあたりにあたると思ったら、それは勃起した郁夫の逸物であった。
(昨日、ちゃんと抜いたはずなのに…)
はっきり感じられる固い逸物は、電車の振動と人混みの圧力で、私の股間を着衣の上から押し続けている。そのうち、電車の揺れで、私の股間が逸物をはさみこむ形になってしまった。固い逸物が敏感な蕾を、着衣の上から摩擦し続ける。
(あ、気持ち、いい!)
昨日に引き続き、私は今朝も感じてしまっていたのだ。
「て、手は出していないだろ?」
帰宅してから私に責められた郁夫は、そう言い訳をする。
「じゃ、足ならいいってわけ?」
真っ赤になりながら、私はそう怒鳴った。
「だから、仕方ないんだって。」
自分の股間を指し示しながら
「こいつには悪気はないんだから。」
「どうも、抜き方が足りなかったみたいね?」
むんずと彼の逸物をつかむと、私はそういって、微笑んだ。
「いうことを聞かない悪い子にはおしおきをしないとね。」
「え、一体、どうするの?」
ギクリとして郁夫が尋ねる。
「こうするのよ。」
私は彼の下半身を裸にすると、自分もワイシャツを脱ぎ捨てた。ぶるんと飛び出したおっぱいで郁夫の逸物をいきなりはさみこむと、もみしだきながら吸いたてる。
「あっ…き、気持ちいいよ。」
「もっと、しぼりださなきゃね。」
「……うっ」
郁夫が射精した。飛び出した精液を飲み下しながら、なおもペニスを吸い続けてみる。
「イって直ぐは、やめてくれ!」
下半身を震わせながら郁夫は訴えるが、私は無視して舐め続けた。しばらくすると、また元の状態に復活する。
「今度は、こっちね。」
彼のモノを自分の中に導こうと、私は自分から彼にまたがった。
「あっ、んあっ、あっ…いぃ…!」
彼の上で腰を激しく回しながら、動き続ける。
おっぱいも私の動きに合わせて、ぶるんぶるんと揺れ動いている。
「あ、いく、いっちゃう…」
絶頂に達した私と共に、彼も再び、樹液を私の中に放つのだった。
「はあ、はあ、もう出ないよ。」
出し終えたあと、彼は荒く息をしながらそうつぶやく。逸物も勢いを失ってしなびたままだ。
「ねえ、私、そんなに魅力がないかな?」
郁夫の目の前に横座りになり、そう尋ねる。
閉じた両脚の後ろの方からは、女陰がちらりと見え、さっきの精液がぷくぷくと溢れ出している。私は、自分の右側のおっぱいをもちあげ、乳首を舐めながら、妖しい視線を郁夫に向けた。その淫猥な光景に、郁夫の股間は、急激に元気を取り戻し始める。
「……もっとできるね。」
舌なめずりして、私は彼のモノを自分の中に導くため身を乗り出した。
(さすがに昨日はやりすぎちゃったかな?)
今朝、前に立っている郁夫の顔には生気がない。目がうつろな状態である。
(ごめんね。)
私は心のなかで謝りながら、満員電車の業苦に耐えていた。昨夜はあれから2回、郁夫と身体を重ねた。最後は勃起しなくなってしまったため、口で吸い続けながら、生気をしぼりつくした感じだった。しぼりつくされた郁夫とはうらはらに、和美の方は、元気はつらつとした状態だった。
満員電車が途中駅で停車し、乗客の入れ替えがおこり、新しい乗客が入ってきた。一人、ダンディな叔父様が二人の横に立つ。
(あ、いい匂い)
叔父様からは香水のいい匂いがする。匂いからするとフランフランの香水のようだ。
(いい匂い、え、何なのこれ)
身体の芯の辺りがかっかと熱くなり始めるのを、私は感じた。なぜか頭がぼおっとしてくる。そして、秘芯からは、愛液が湧き出し始めた。
(わ、私、発情しちゃってる。)
両脚をきつく閉じて愛液が溢れるのを食い止めようとするが、すでに内腿を濡らし始めている。うなじや胸元から、甘くいやらしい匂いが立ち上る。はあ、はあと荒い息をしながら、郁夫の顔を見上げ、彼のポケットに手を突っ込むと、彼の逸物をぎゅっとにぎり締めた。
(か、和美、お前、おかしいぞ)
たじろぎながらそうささやく彼の声が、和美には聞こえた気がした。
夢を見ているような気持ちの中で、私はあの、手を出さないという誓いは撤回しようと心に決めた。
どうも、満員電車内でのプレイは、癖になりそうである。





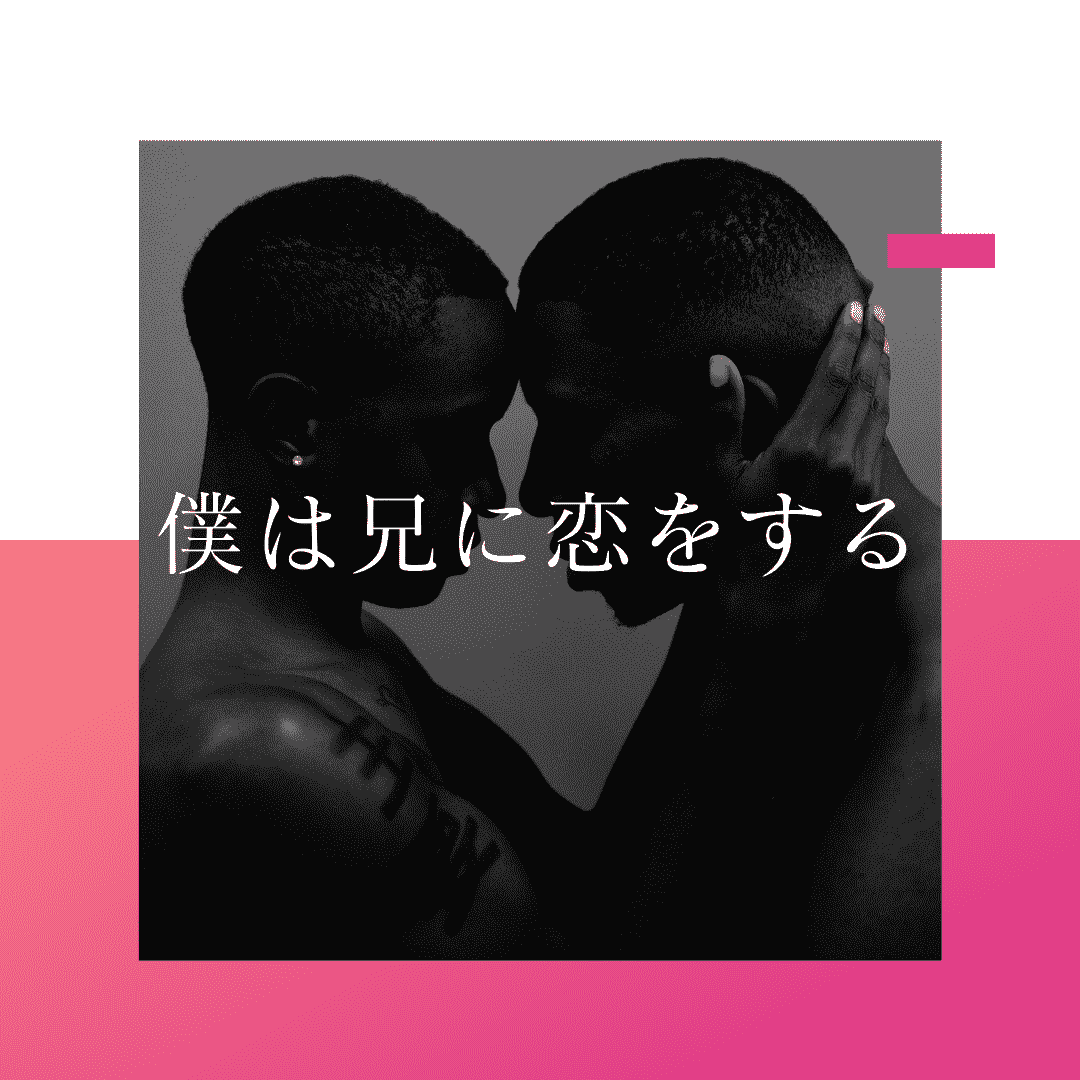


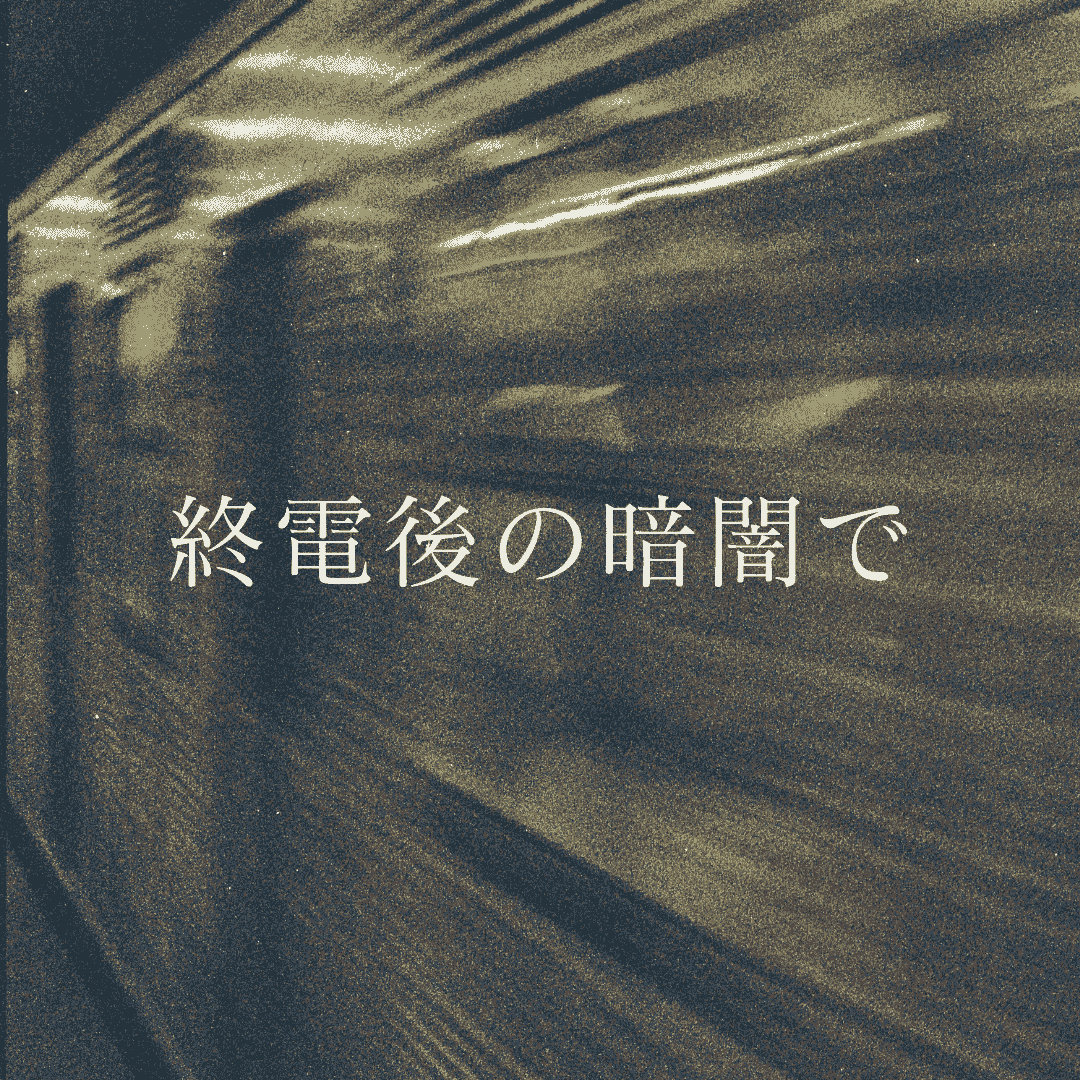
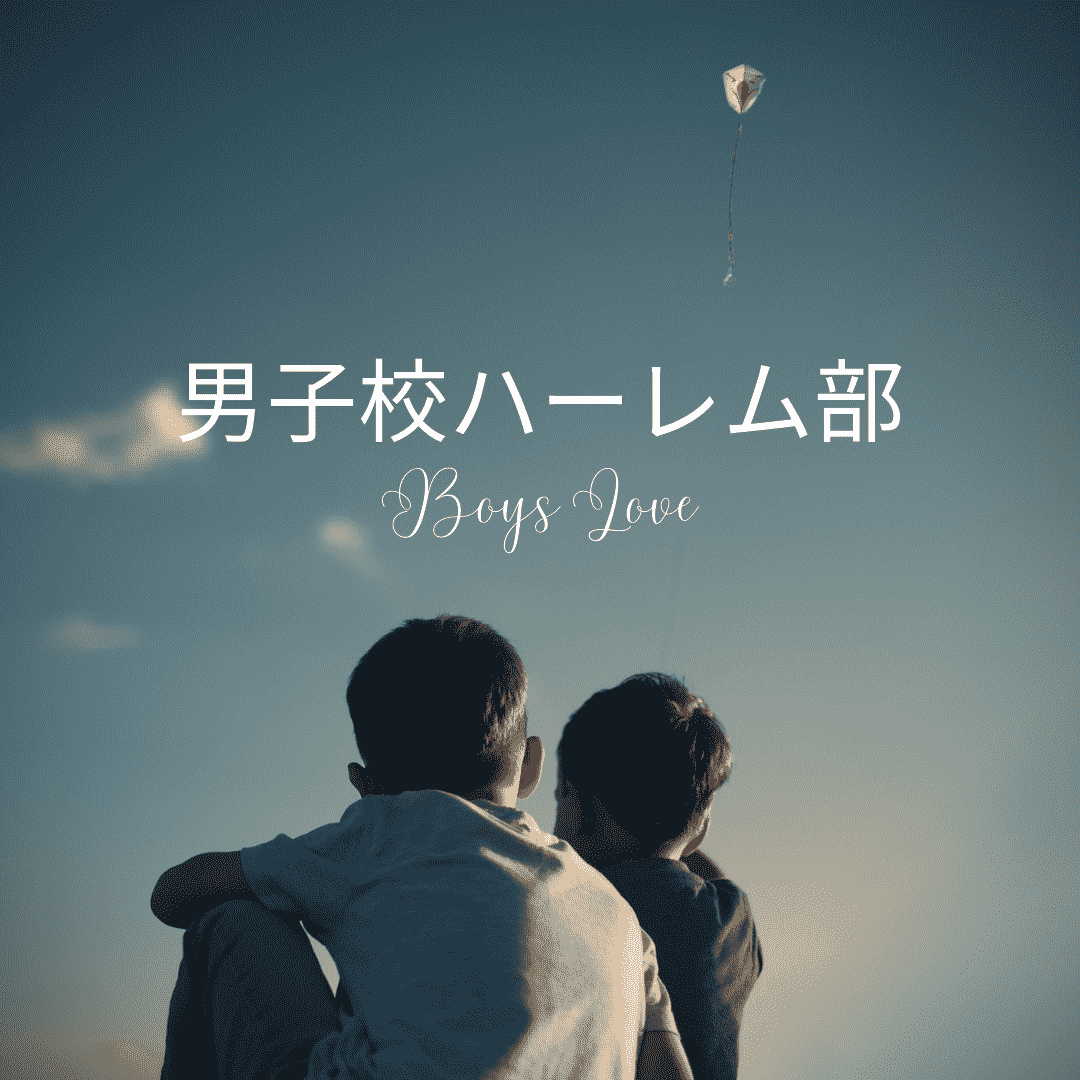
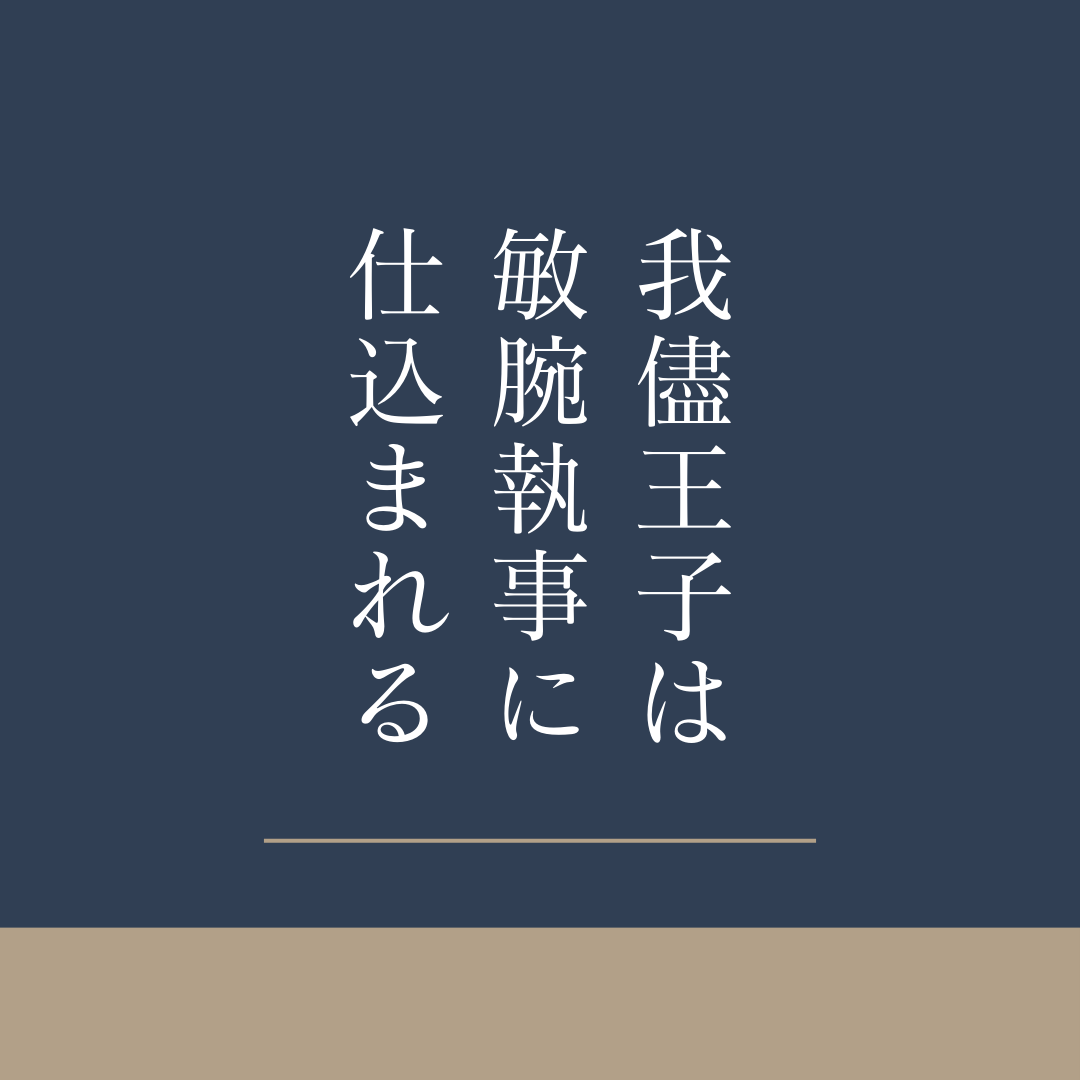

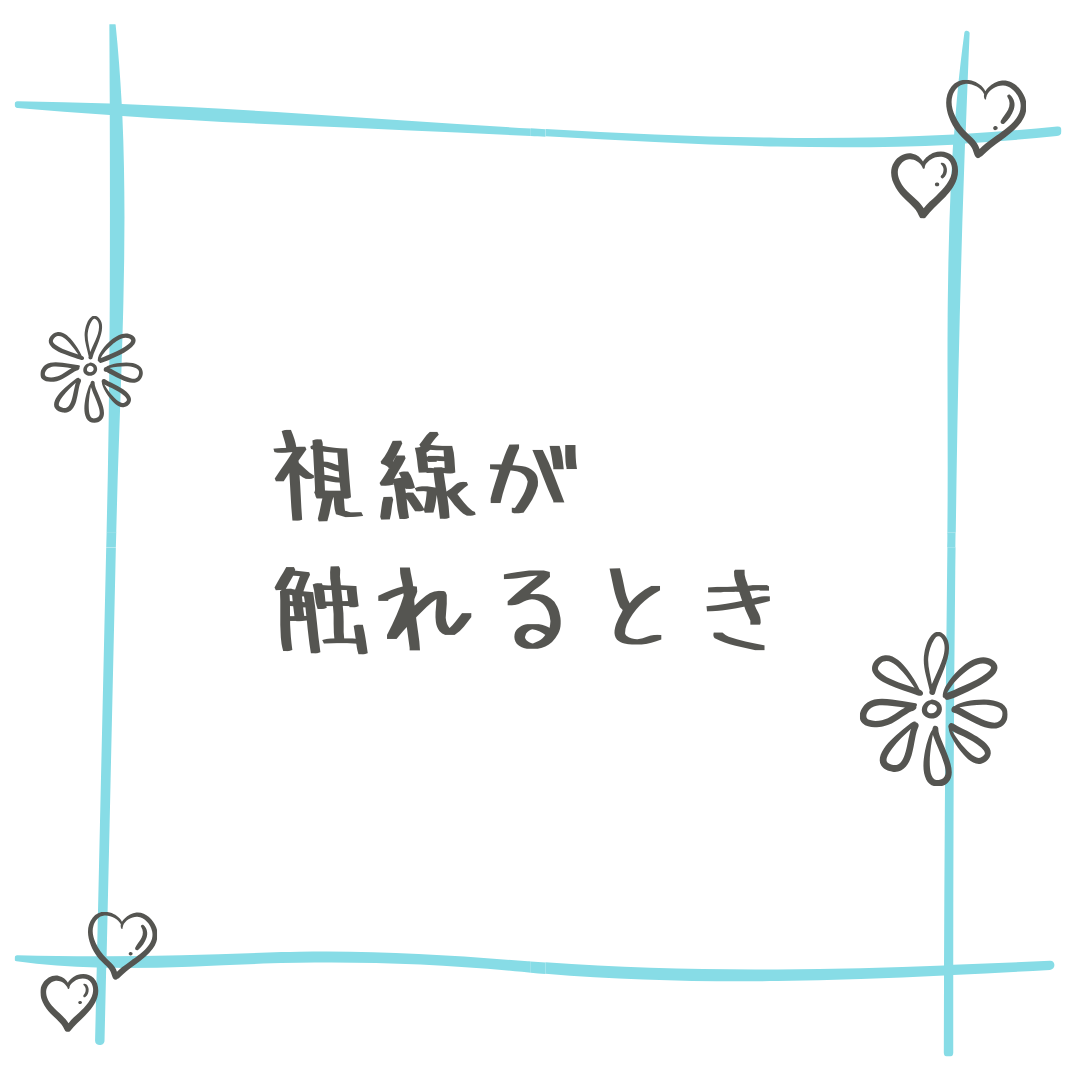



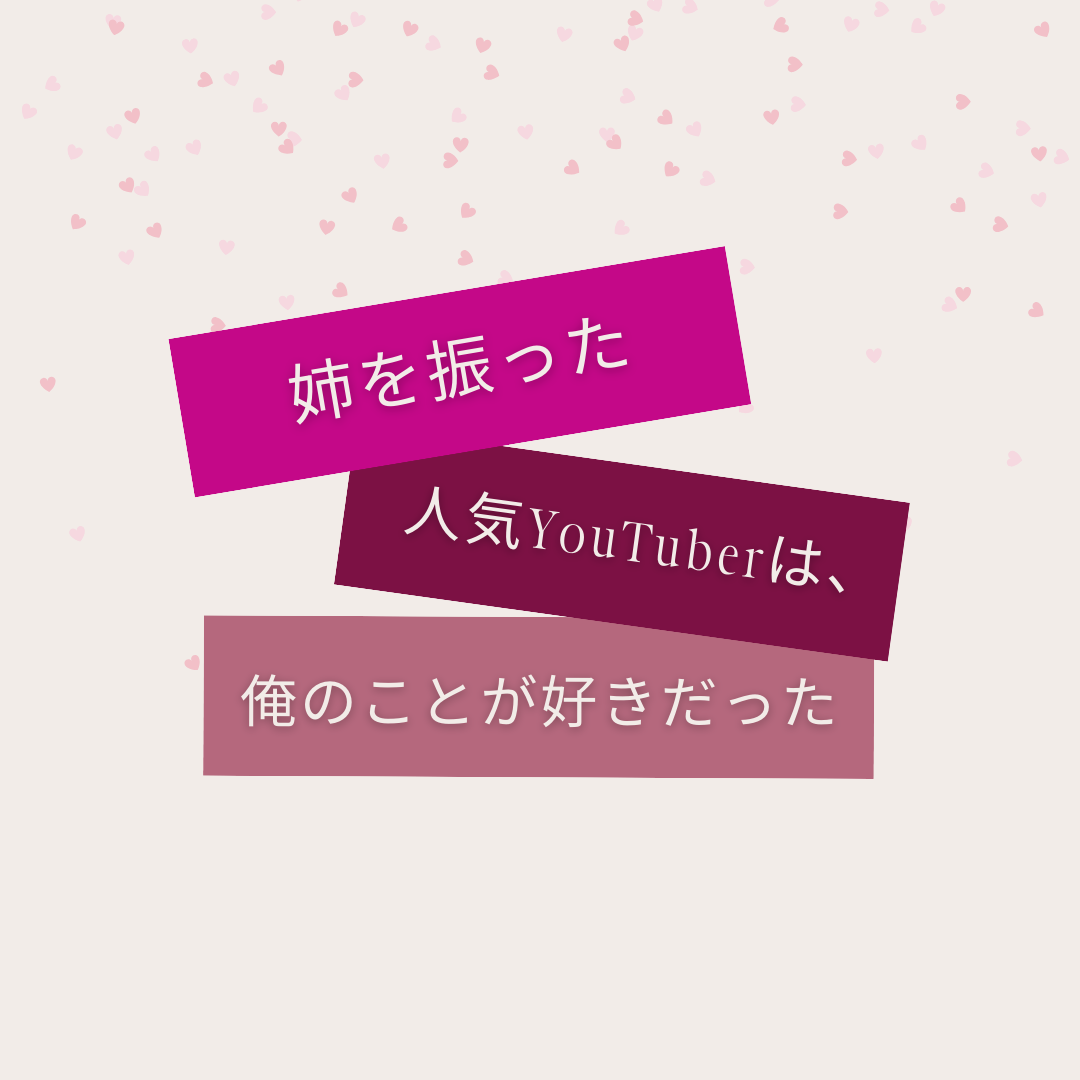









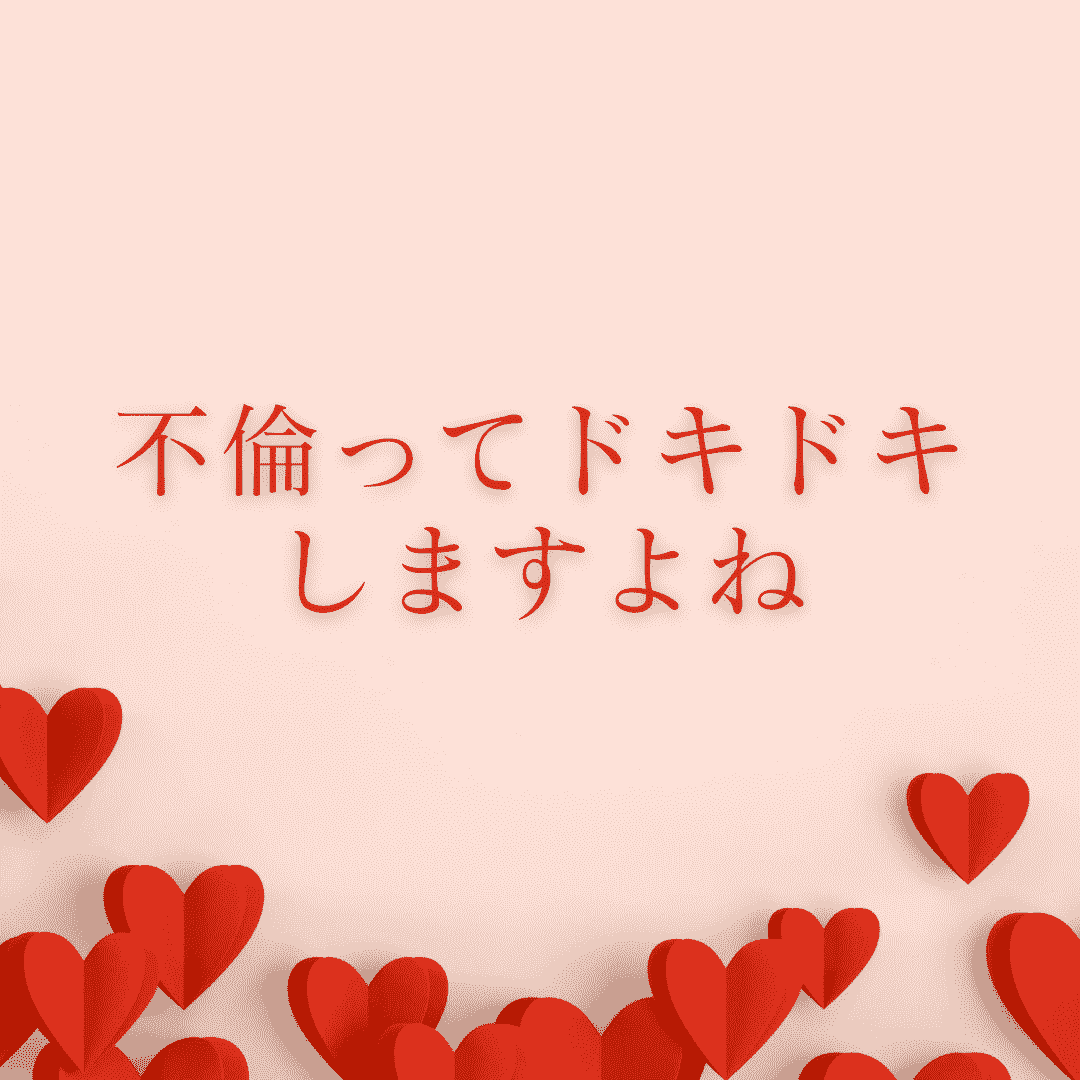




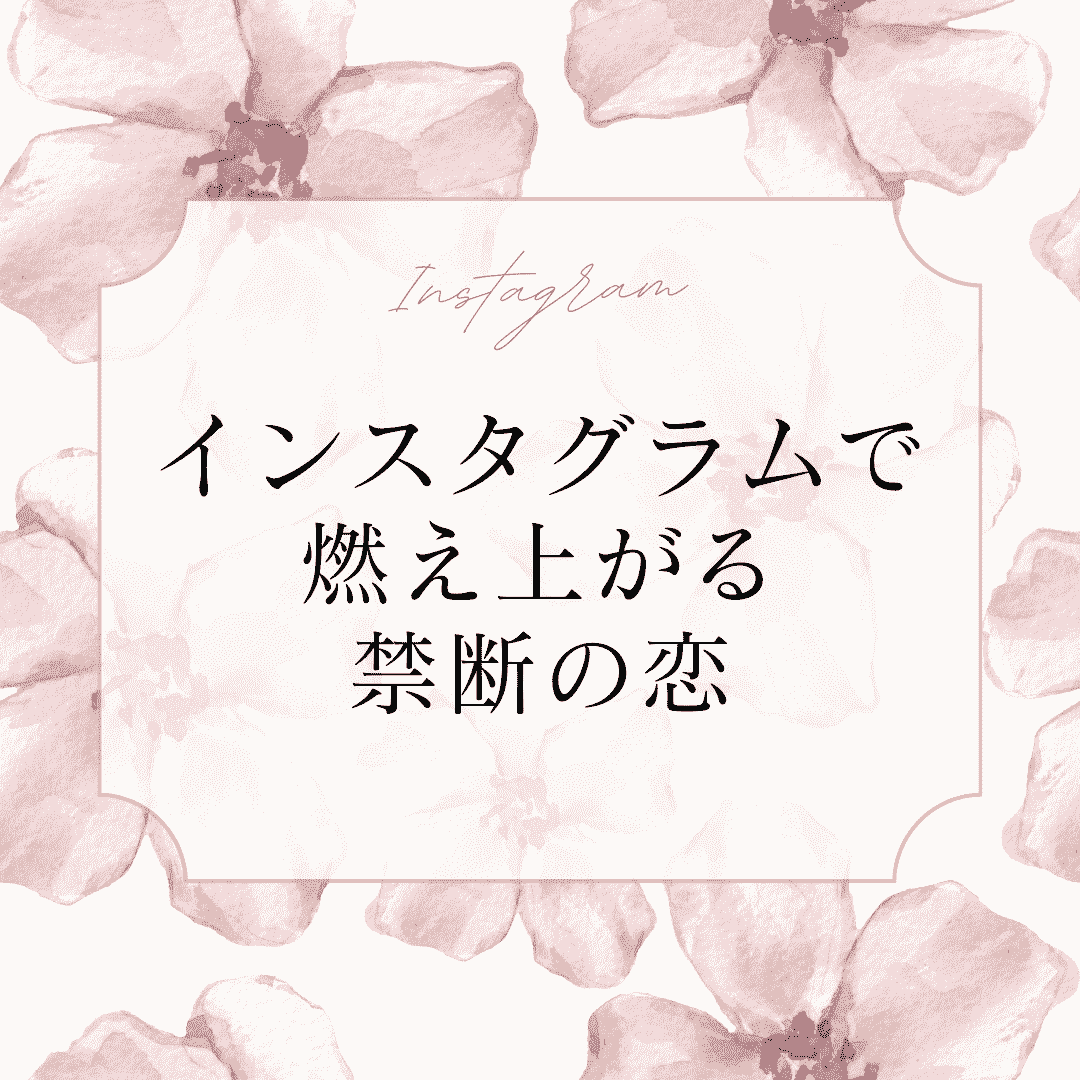

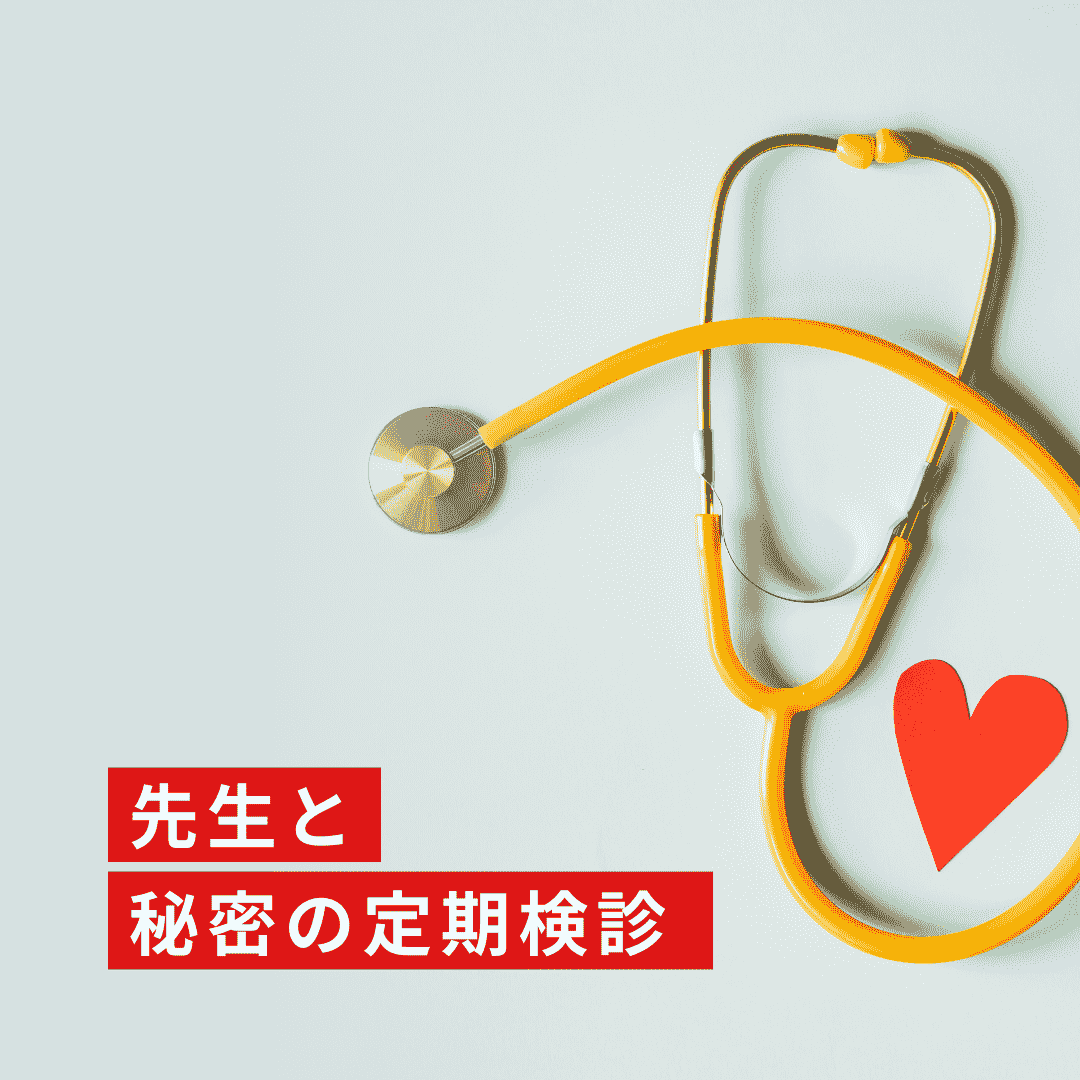


コメント