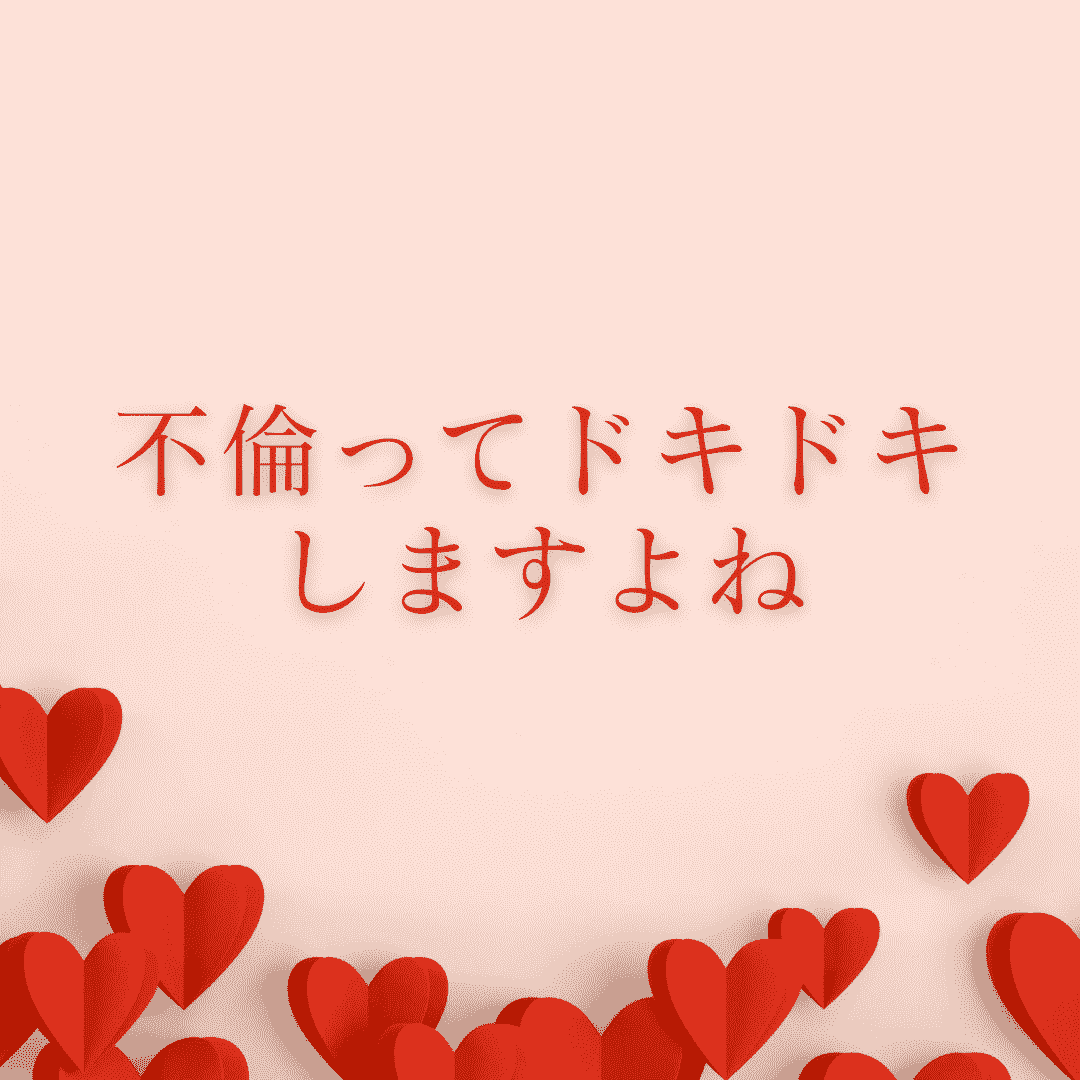
0
不倫ってドキドキしますよね
私の名前は鈴木百合。好奇心旺盛な二十八歳。私は結婚をしていて、幸せな日々を送っている。
旦那とは中学からの付き合いで、二十五歳という区切りのときに、プロポーズされた。私はモテる方ではないので、最初で最後のチャンスだと思って、オッケーしたのだ。
でも、付き合いが長すぎた。旦那といると、安心感はあるけれども、幸せだとは思わない。多分、お互いの仕事が忙しく、接する時間が短いからだろう。
今日もパンを口の中に詰めるようにして食べて、家を出た。片付けは旦那がしてくれる。
仕事はファッションブランドの広報を担当している。あまり大きな会社ではないので、社員数は少ない。今のところ、広報課の課長と私と、バイトの琴美ちゃんのみだ。この3人で回すと言っても、課長は管理が主な業務だし、バイトの子はライティングがメインなので、私が業務のほとんどをこなすことになっていた。だから、毎日残業が酷く、何度か課長に泣きついたこともある。
「もっと人を増やして欲しいです。」
課長は私の目の下のクマを見ると、「そうねえ。」と呟いて自分のネイルを見た。美しい深い赤色のネイル。私には爪にまで気を配っている余裕はない。だから、その綺麗な爪が、憎らしいほどだった。
いつも通りに出社をすると、まだ私しかいなかった。私は昨日やり残していた業務に早速取り組み始める。
一体何分経ったのだろうか。昨日の分がやっと終わり、私は解放された気分になった。いや、これから本当の業務時間が始まるのだけれど。
「あの。」
「はい!」
いきなり背後から声をかけられて、私は思わず飛び上がった。聞こえた声は男の人だ。この部門には男性がいないから、他の部署の人だろうか。
振り返ると、背がすらりと高い男性が立っている。昔読んだことのある人気雑誌の亮平君に似ていて、細い薄めの顔が爽やかさを増している。熊みたいな旦那と正反対の男性だった。
私は思わずその容姿にキュンとときめいてしまった。
亮平君のファンもこんな感じでときめいたのだろうか。
だが、彼はニコリともせず、
「おはようございます。広報課に異動となりました平坂です。」
と、自己紹介を始めた。
せっかく爽やかな顔をしているのだから、口元だけでも笑えばいいのに…と私は少しむっとしたが、広報課の先輩として、胸を張った。
「鈴木です。よろしくお願いします。」
椅子から立ち上がり、握手をするために右手を差し出した。平坂は一瞬戸惑ったが、私の手を取ってくれた。筋張った硬い手が、私の手を優しく包み込む。私はその心地よい力加減に、おや?と思った。だってこんな仏頂面なのに、相手への絶妙な加減ができるのだ。きっと本当は優しい性格なのだろうか。この握手からそんなことを考えた。
課長が出社すると、改めて彼を紹介してくれた。営業にいたが、どうやら、課長が無理やり引っ張ってきたらしい。
「営業成績は良かったらしいのに、いいんですか? 連れてきちゃって。」
彼に聞こえないように課長に耳打ちした。
「あら、人が欲しいって言ってたのはあなたじゃない。」
…私のせいにされた。
ということで、平坂は私の部下となったのだ。
「このワンピースなんですけど、素材が柔らかいから、もう少し動きのある写真の方が良くないですか?」
「確かに。その方がわくわく感が伝わっていいわね。」
彼は非常に有能だった。営業にいたからか、相手が本当に欲しいと思うようなものを提案してくる。そして何より、今まで私が受け持っていた業務を分担することができるようになり、残業が減ったのでとても助かった。
「平坂君って手綺麗だよね。」
「なんですか。セクハラですか。」
業務がひと息ついたので、コーヒーブレイクをしている時だった。平坂が異動してきて一カ月ほど経った頃、業務を常に二人で行っているからか、私と彼の距離は、初めての頃よりぐっと縮まっていた。もちろん上司と部下という意味で。
「セクハラじゃないよ。純粋に褒めてるの。」
でも、私の脳内では彼の長く綺麗な指で愛撫されたら、どれだけ気持ちいいのだろうかと、セクハラまがいなことを考えてしまっていた。旦那の指は太く毛も生えていて、挿入するときにイイところまで届かないことが多いのだ。
(平坂君の指なら……)
唾を飲む代わりにコーヒーを喉に流し込んだ。
平坂は無表情で、そんな私を見ている。
そういえば、まだ平坂の笑顔を見たことがない。私の中の好奇心が湧き上がるのを感じた。平坂の笑顔が見たい。面白い話はいくつかストックがある。その中の何が彼にハマるだろうか。
うんうん、と唸っていると、彼が私の顔を覗き込んできた。その近さに私はびっくりした。旦那でさえこんなに接近するのはキスするときくらいだ。私はぎゅっと目を瞑る。すると、息が当たってきた。彼のプライベートゾーンってこんなに狭かったっけ? 私は混乱し、息を殺すことしかできなかった。お昼にペペロンチーノを食べたけど、口臭大丈夫かな?
彼はしばらくしてスイと顔を離した。
「先輩って、綺麗な肌してますよね。」
「え?」
「すげー柔らかそうで触れたくなるっていうか。」
彼は顔を染めながら、ボソボソとつぶやいた。
そんな平坂を初めて見たので、照れてしまい、自分のスキンケアについて早口で説明するハメになった。その間、彼は頷きながら私の話を熱心に聞いてくれていた。
「田舎でゴスロリの撮影!? 何年前の映画ですか。」
「上が斬新なアイディアだ! って言ってきたのよ。」
「何も斬新じゃありませんけど!」
そんなやり取りが私と課長の間であり、私と平坂は、よく晴れた東北へ放り出されることとなった。課長はついてこなかった。会社でしかできない仕事が溜まっているから、とのことだ。だから、私と彼の二人が出張に選ばれることとなった。
撮影は順調だったが、広報としてこれが正解なのかを考えた。
「ねえ、どう思う?」
「どうって……上命令なら仕方ないんじゃないすか?」
周りを見回すと、畑や田んぼばかりの風景。景色だけは綺麗だった。臭いは近くに牛小屋があるせいか最悪だったが。
撮影が終わると、皆、車に乗り駅方面に帰る。彼からは普段嗅ぐことがない彼自身の匂いがした。それは決して不快な臭いではなく、心地よいと感じる匂いだった。一方の私は…、と気になり、平坂の方を見る。
彼の顔は珍しく余裕のない顔をしている。
どうしたのだろう。私はそんなに臭いのか…なんて申し訳ない気持ちになり、窓側に身を寄せた。
この町の主要な駅に着き、解散となった。
しかし、そこであるハプニングが発生した。
「あれ、傘がない。」
衣装の傘がないのだ。あれは自社で作成したもので、今のところあの一本しか作られていない。
「現場に置いてきたのかも。」
「じゃあ、取りに戻りますか?」
私が困っていると、平坂がさらりと言った。現場はここから車で一時間だ。もう夕暮れである。
「今からだとタクシーで行っても日が暮れちゃうわ。」
「泊まればいいじゃないすか。どうせ経費で落ちるでしょ。」
「そうね。じゃあ、平坂君、先に帰って。」
「夜になるかもしれないのに、女性一人を行かせるわけにはいかないでしょう。」
…私は悩んだ。二人で取りに行っても、どうせ傘一本のことだ。そんなに人数はいらない。
「俺、運転できますよ。見てくださいよ、この駅。タクシーなんて一台もないじゃないすか。」
平坂からの提案に、私は同意せざるを得なかった。仕方なく平坂と同じ車で現場へと向かった。傘を探し出すのにかなりの時間を要し、結局見つかったのが民家だった。
「疲れた。」
「もう電車諦めて泊まるしかないすね。」
付近を見るとネオンがパチパチと弾け光る古びたホテルを見つけた。私たちは仕方ないと顔を見合わせて、そこに入った。
「二部屋ください。」
「二部屋?」
ホテルの従業員がじろりとこちらをねめる。
「二部屋で。」
鍵をぽいと投げてきた。私たちは足早にそこを立ち去った。
「じゃあ、俺こっちなんで。」
隣の部屋に平坂が消えて行った。私も部屋に入る。
辺りを見回す。剥げた壁紙。電気をつけているのに薄暗い部屋。天井を見ると、人の顔のようなシミがあり、はっきり言って怖かった。
今晩だけと自分に言い聞かせ、シャワーを浴びる。お風呂場もあまり言葉にしたくないものだったが我慢した。
***
……真夜中になっても寝られない。ホテル全体がミシミシと音を立てているのだ。こんなところで寝られる訳がない。私は段々と、この建物が崩壊するのでは…と本気で思い始め、怖くなった。
するりと布団から抜け出すと、平坂の部屋をノックする。もう寝ているだろうか。
「なんすか。」
彼はどうやらまだ起きていたようだった。私の姿を見て、彼は眉を顰める。どこかおかしいところでもあったのだろうか。それでも彼は私を部屋に入れてくれた。
「それで?」
「なんか怖くて。」
「子供っすか。」
「そんなんじゃないわよ。」
私はぷいと顔を背けた。そんな彼は、備え付けの電気ケトルで湯を沸かしている。
彼の手に目がいった。やはり綺麗な指だ。今日の日焼けで真っ赤になっているが、それでも彼の手の骨の出っ張りや、スラリとした指や、美しく切り揃えられた爪が私の好奇心をかき立てる。
もし、この指で私を――。
「なあ。」
いきなり彼は私の前に立ちはだかり、顎を持ち上げた。
「俺の部屋にそんな格好で来て、欲情した顔をこっちに向けてるってなんなの。」
彼の言っていることが、まったく分からなかった。そんな私を察したのか、彼の指が顎から喉へ伝っていく。ぞくぞくとした感覚が私を襲う。微妙な力加減なので、喉がヒクヒクと動いてしまう。そして、彼の指は私の胸元をトントンと叩いた。
「こんな露出の高い服着て誘ってんの?」
確かに胸の谷間が見える部屋着を着ている。彼の角度からだとどこまで見えているのだろう。
彼は私の目の前に指を突き出した。美しい指を間近で見て、餌を目の前にした犬のように息を荒くしてしまった。
「ふーん、これをナカに挿れて欲しいんだな?」
そういいながら平坂が笑った。その笑みはとてもサディスティックな歪んだ笑みで、爽やかさの欠片もなかった。
「あんた、既婚者なのに、いい度胸してんじゃねえか。」
「そうね。不倫って…なんだかドキドキする。」
「普通そうだろ。」
何を言っているんだか、と冷たい視線が私に向かってくる。好奇心が爆発している私はそんな視線でさえ興奮材料になる。
「一回でいい。その指で私を。」
「最後まで言わなくても、センパイのお望み通りにしますよ。」
私は自ら部屋着を脱ぎ、彼の前で肌を晒した。
「やっぱり、あんたは肌が綺麗だな。」
つーっと肩を指で撫で、胸の頂きを摘まんだ。強い力で摘ままれると思ったが、気持ちいい力加減だ。私はいつかの握手を思い出した。
彼も興奮して乗ってきたのか、行為が大胆になってくる。絶妙に触れるか触れないかのフェザータッチを披露すると、下へと指を運んだ。
ようやく彼の指が手に入ると、じっとその時を待った。
しかし、彼の指は太ももへ流れて行った。
私が そんな……と絶望をしていると、彼はまた笑った。分かってやっているのだ。
私はそんなサディストな面の彼も魅力的に見えて、好きになった。私はこの人のことを本気で好きなのだろうか。
ようやく私の入口に彼の指があてがわれたときの幸福と言ったら。こんな幸せをしばらく感じたことがなかった。うっとりと彼の指を咥え込んで堪能する。奥底から性なる欲望が湧きたち、私の蜜壺はトロトロと汁を吐き続けた。
彼も私のナカをぐるりと掻きまわし、反応を見て楽しんでいる。こんなに楽しいセックスがあったなんて…。
そして、とうとう彼の長い指が私の奥のよく感じる部分に当たった。
「あっ!」
大きく反応すると、彼は楽しそうにそこを攻め立てた。
「あっ、そこ! そこ、が、ィい!」
私と彼はその後、指以外でも繋がった。
「はっはっ、ヤバい。はっ……あんたの匂い最高。」
彼は汗ばむ私の匂いに高まって、精を放った。
***
翌朝、ホテルの受付へ行くと、昨日見た従業員がいた。
「結局、一部屋で良かったようですな。」
余計なことを言って、私たちを送り出した。
「なんかすっきりしたわ。」
「そんなに溜まってたんすか。」
彼は砕けた敬語に戻っていた。昨日のSな笑みを浮かべる彼は、どこへ行ったのやら。また無表情だった。
「会社に戻ったら、きちんと二部屋分、請求するわよ。」
「でも、さっき一部屋分しか領収書貰ってないすよ。」
「嘘!?」
私たちは急いでホテルに戻った。





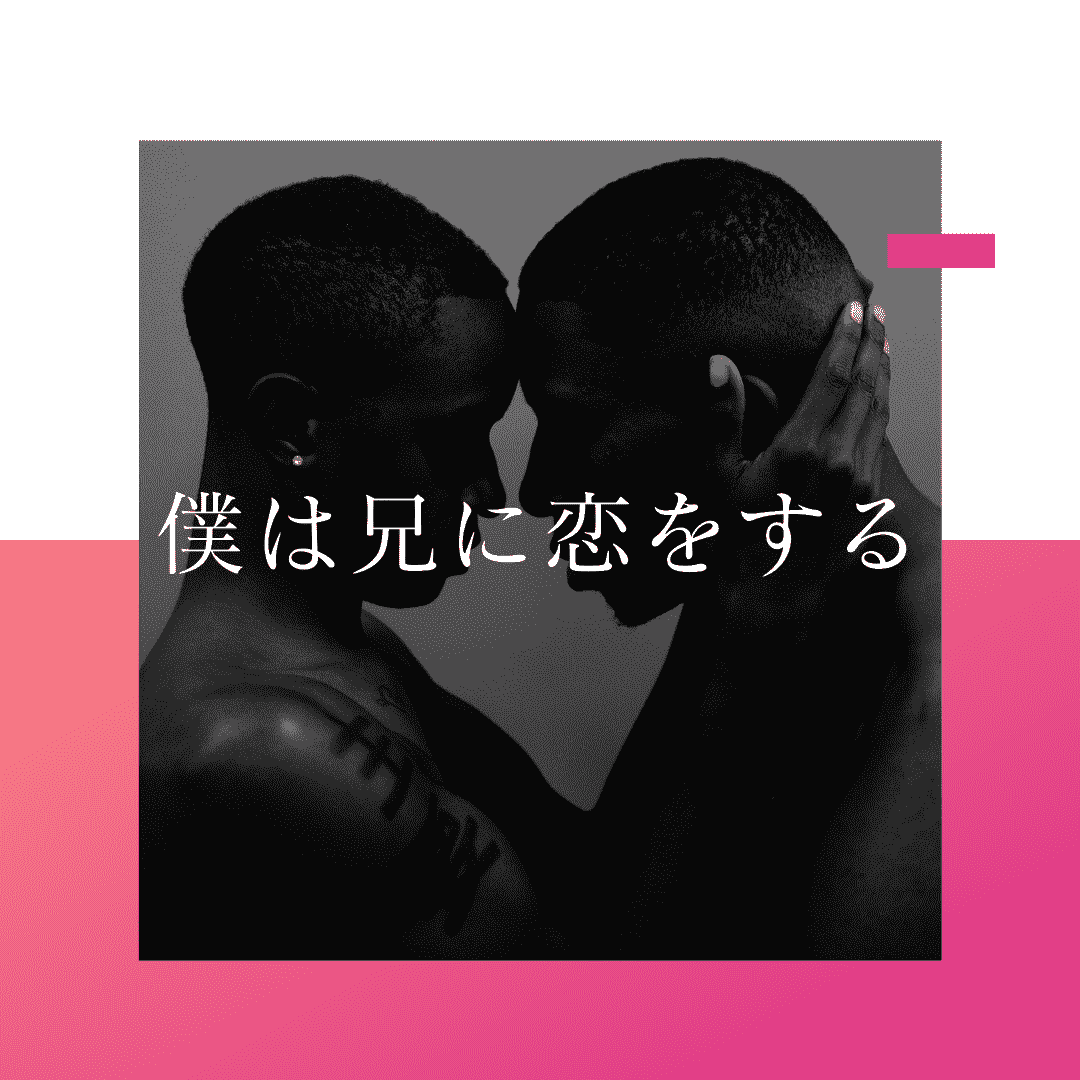



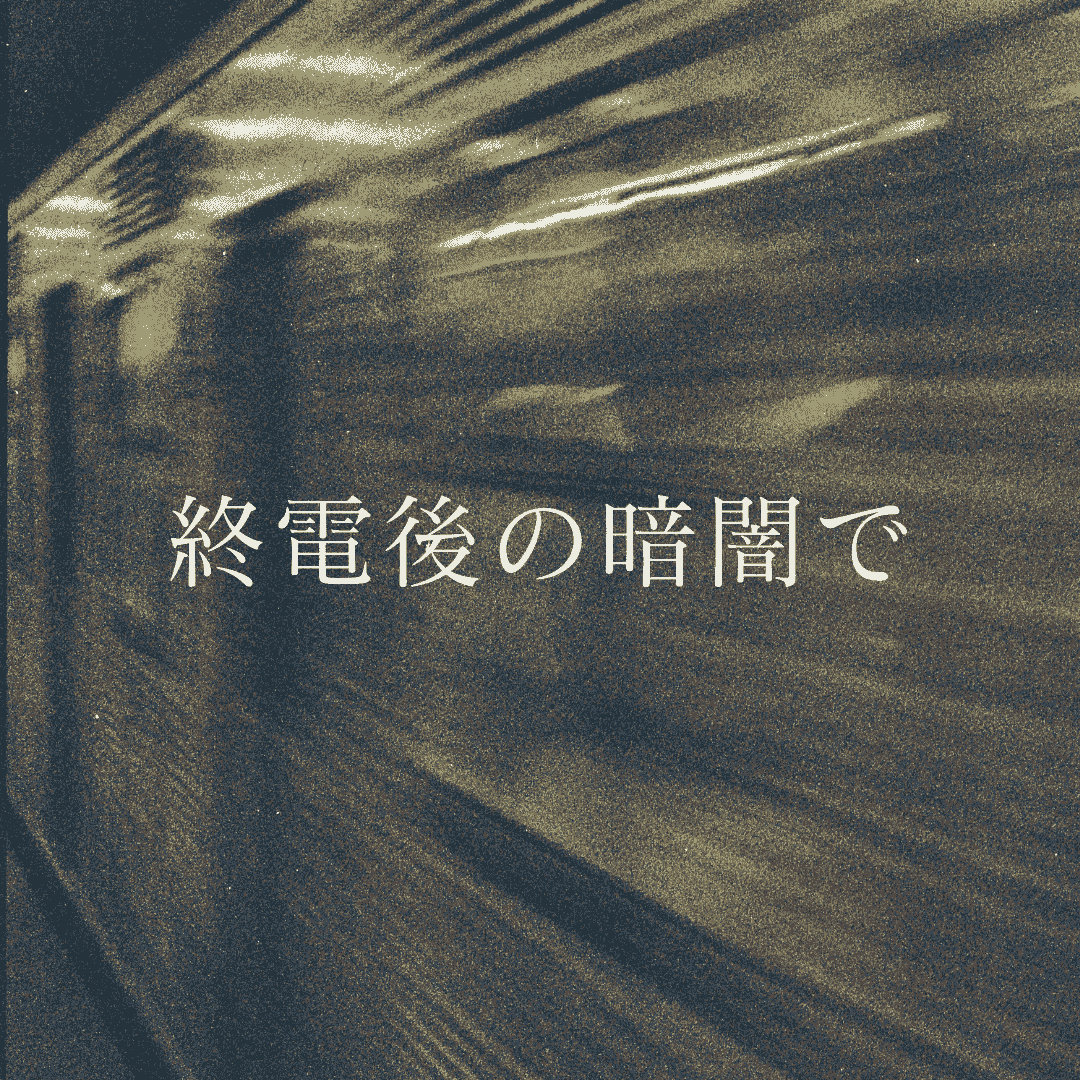
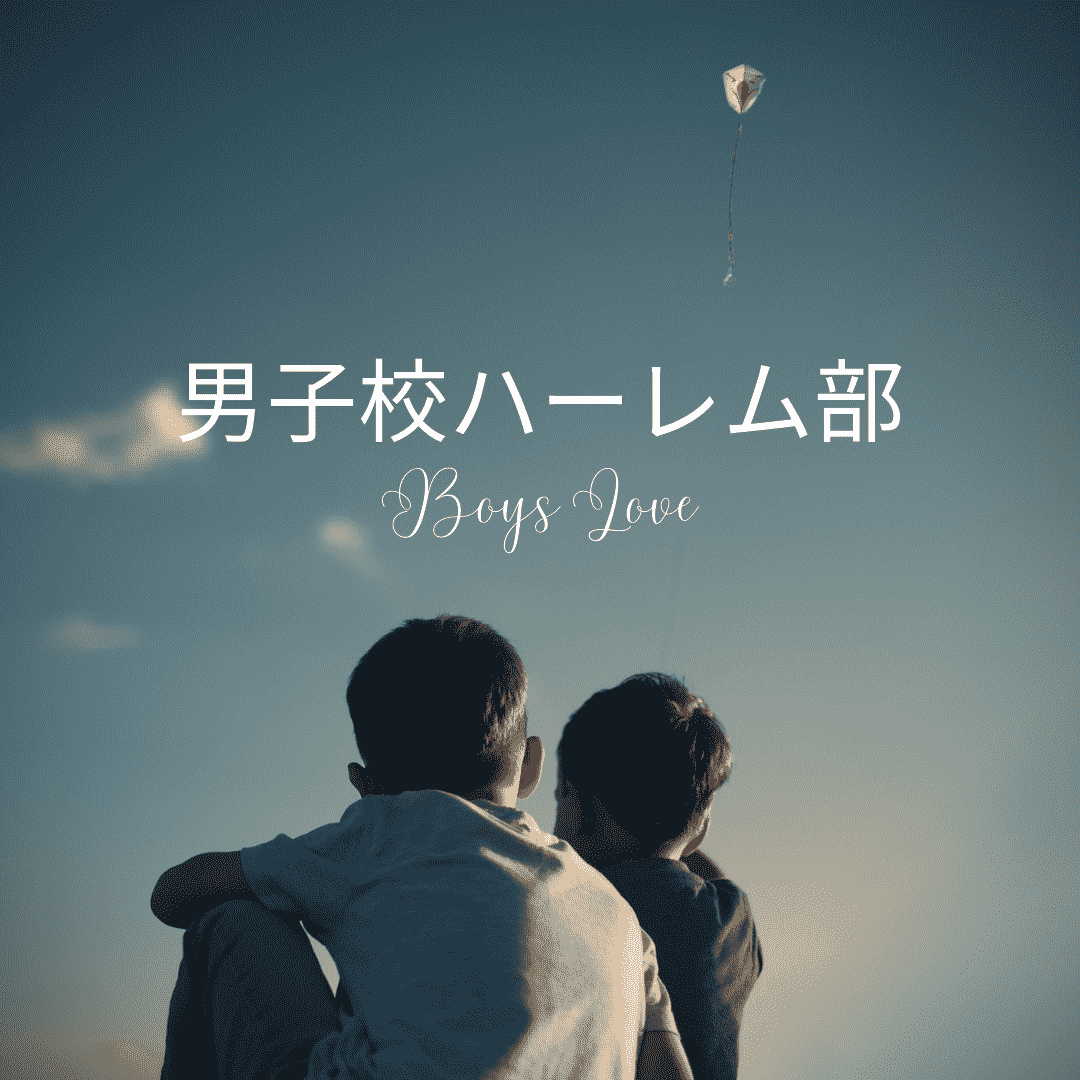
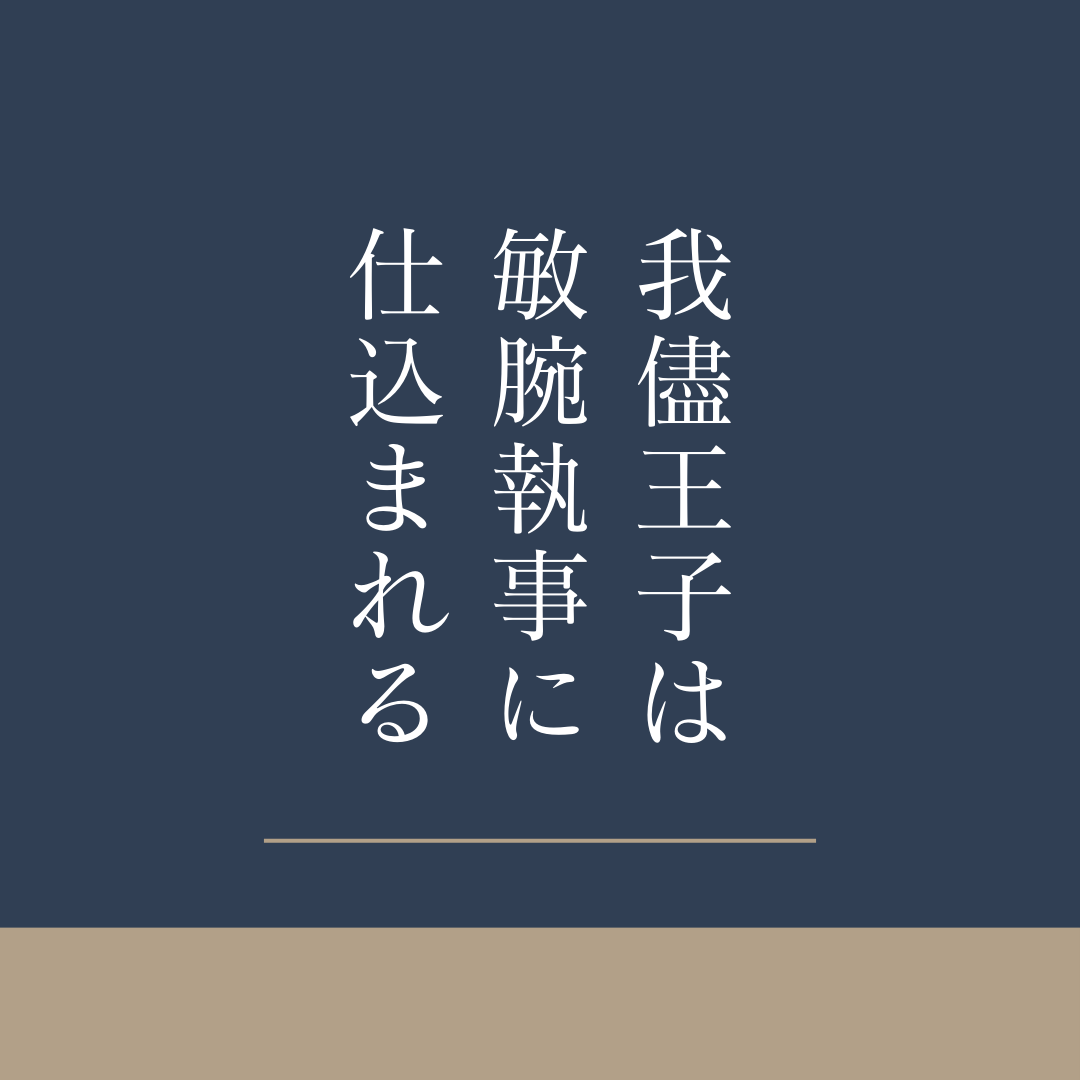

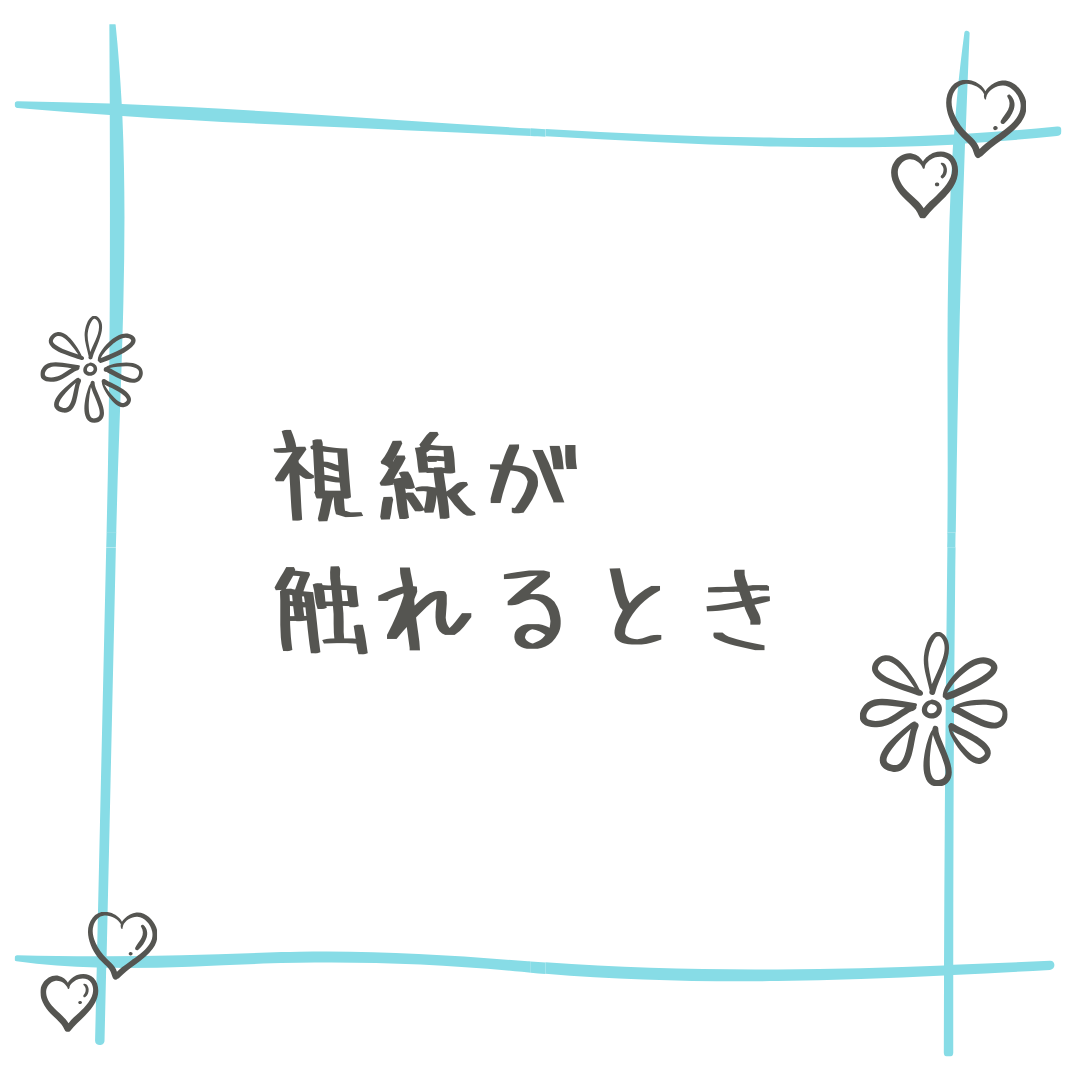



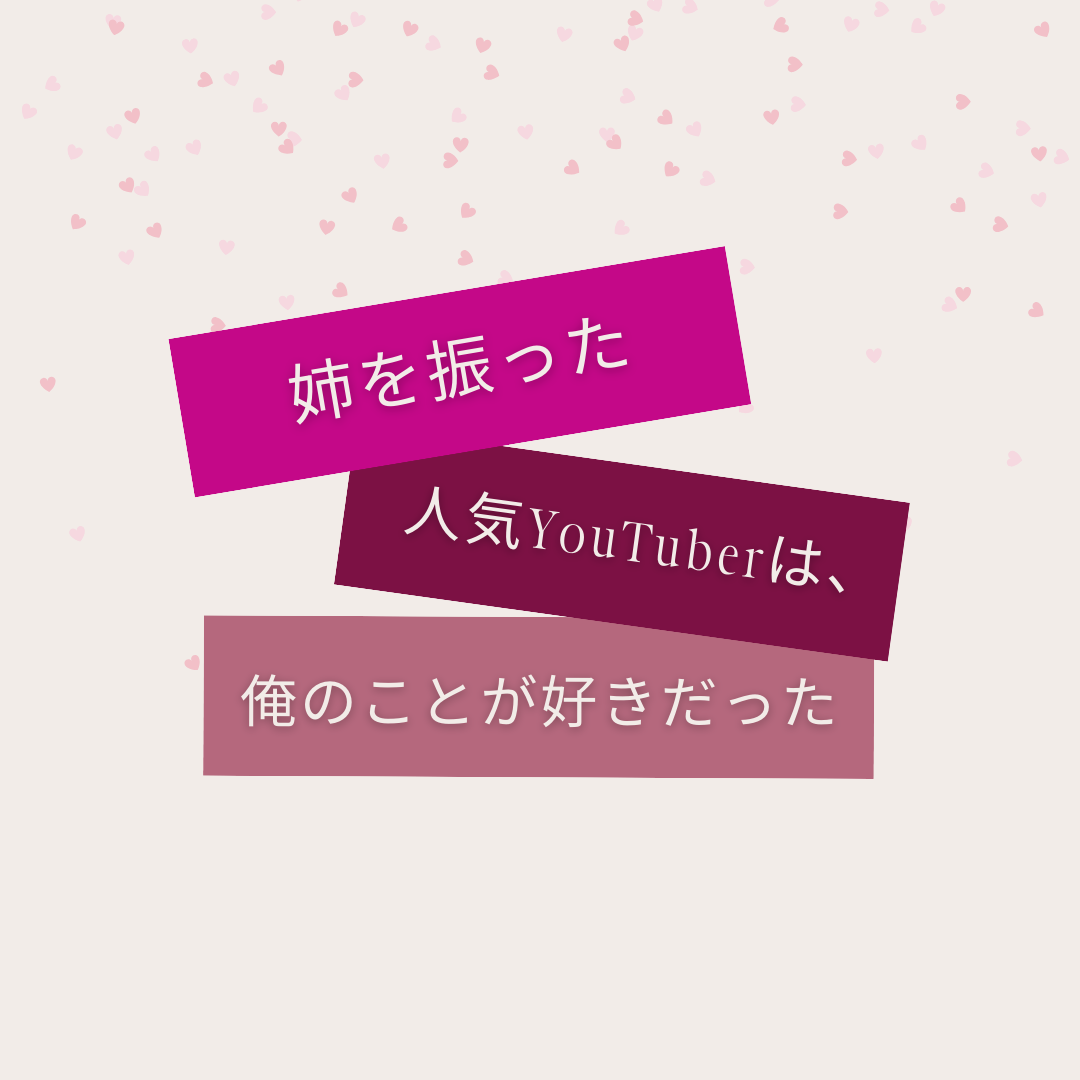













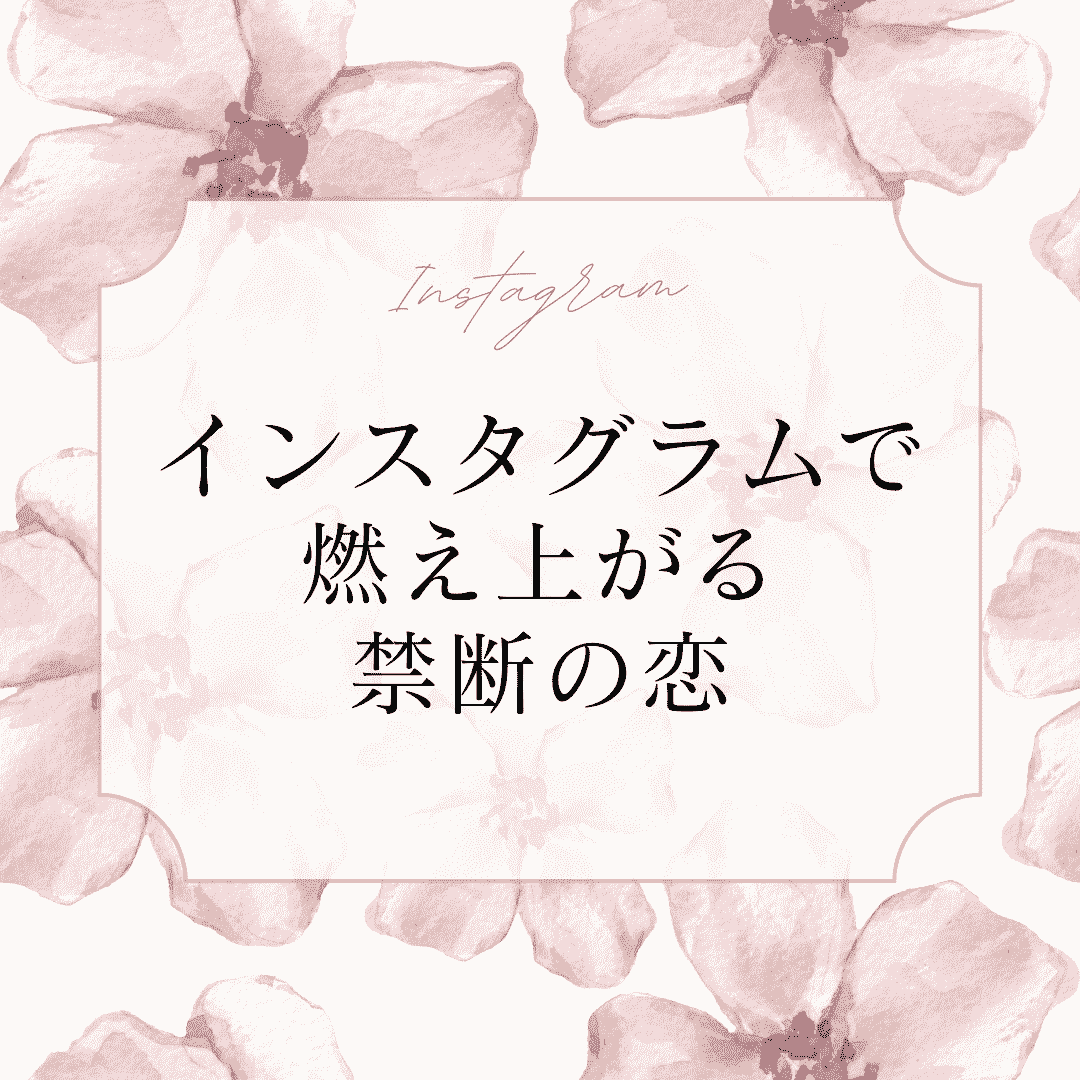
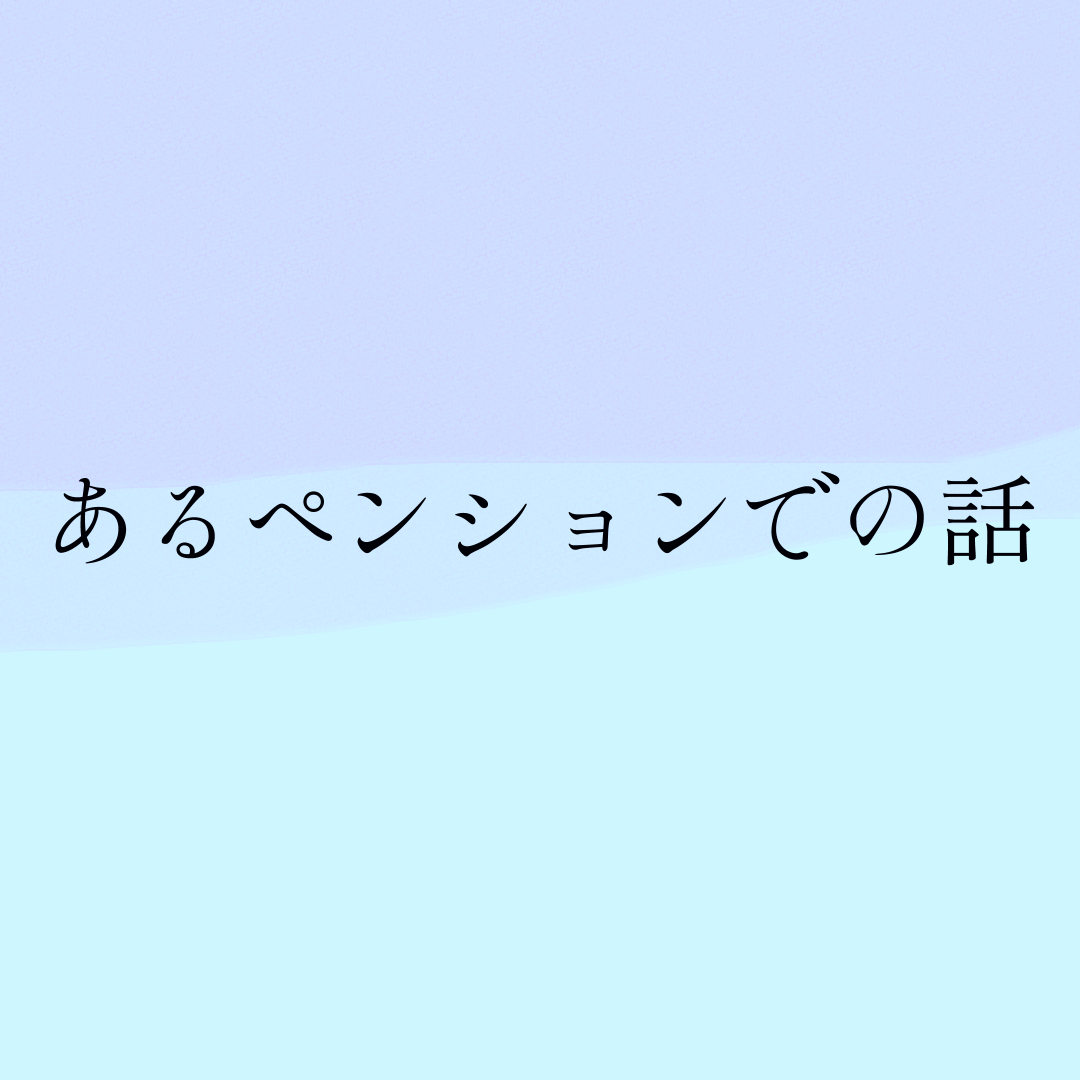
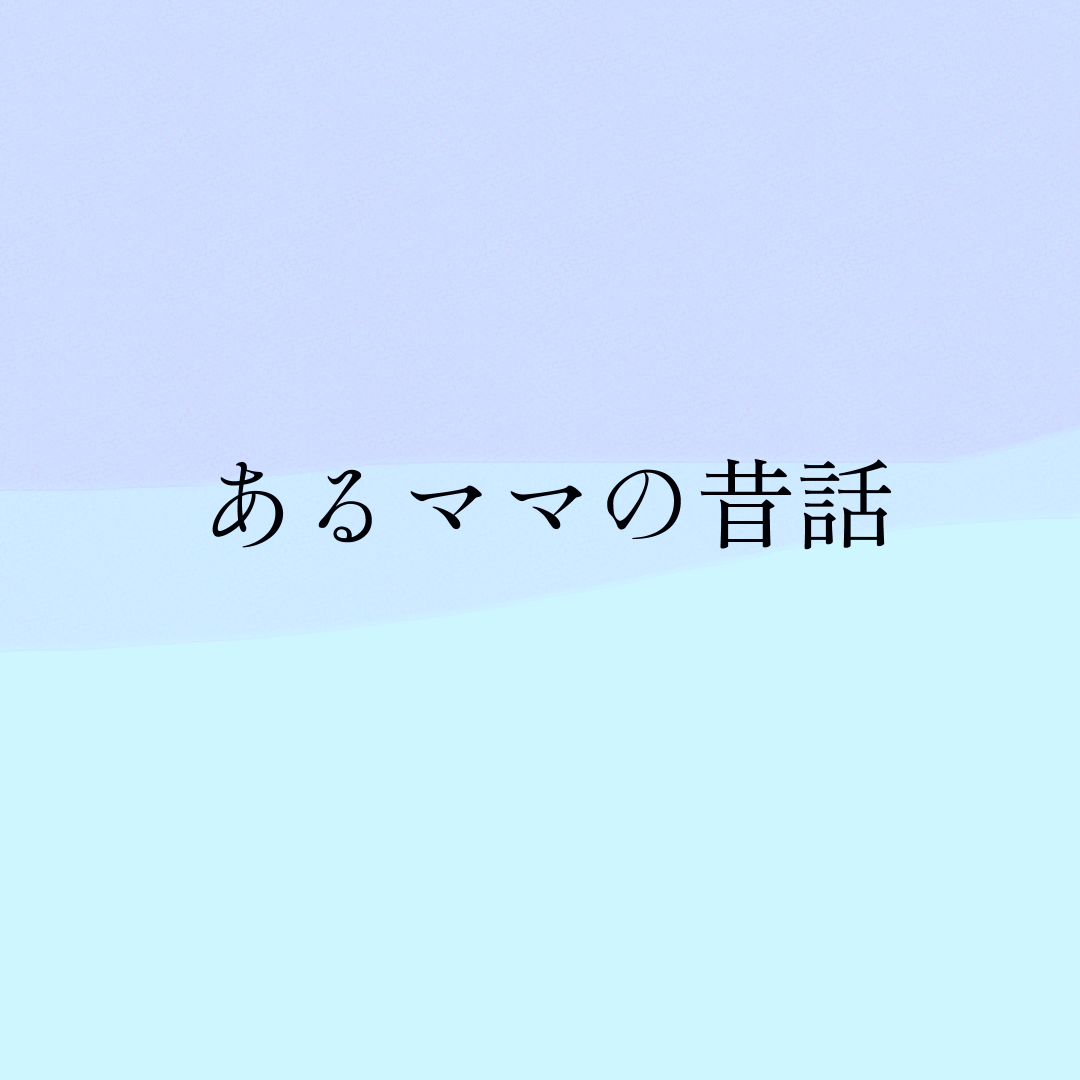
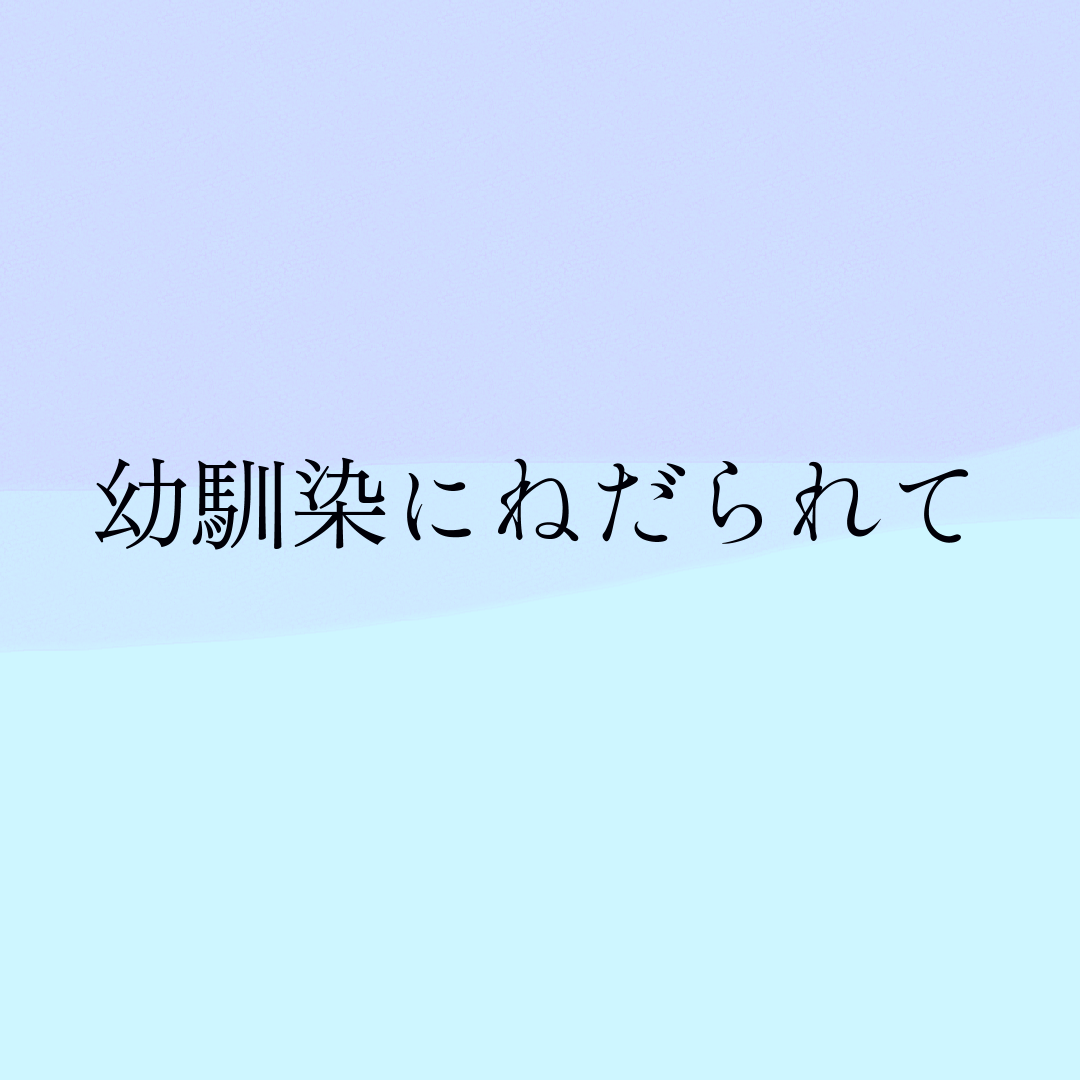
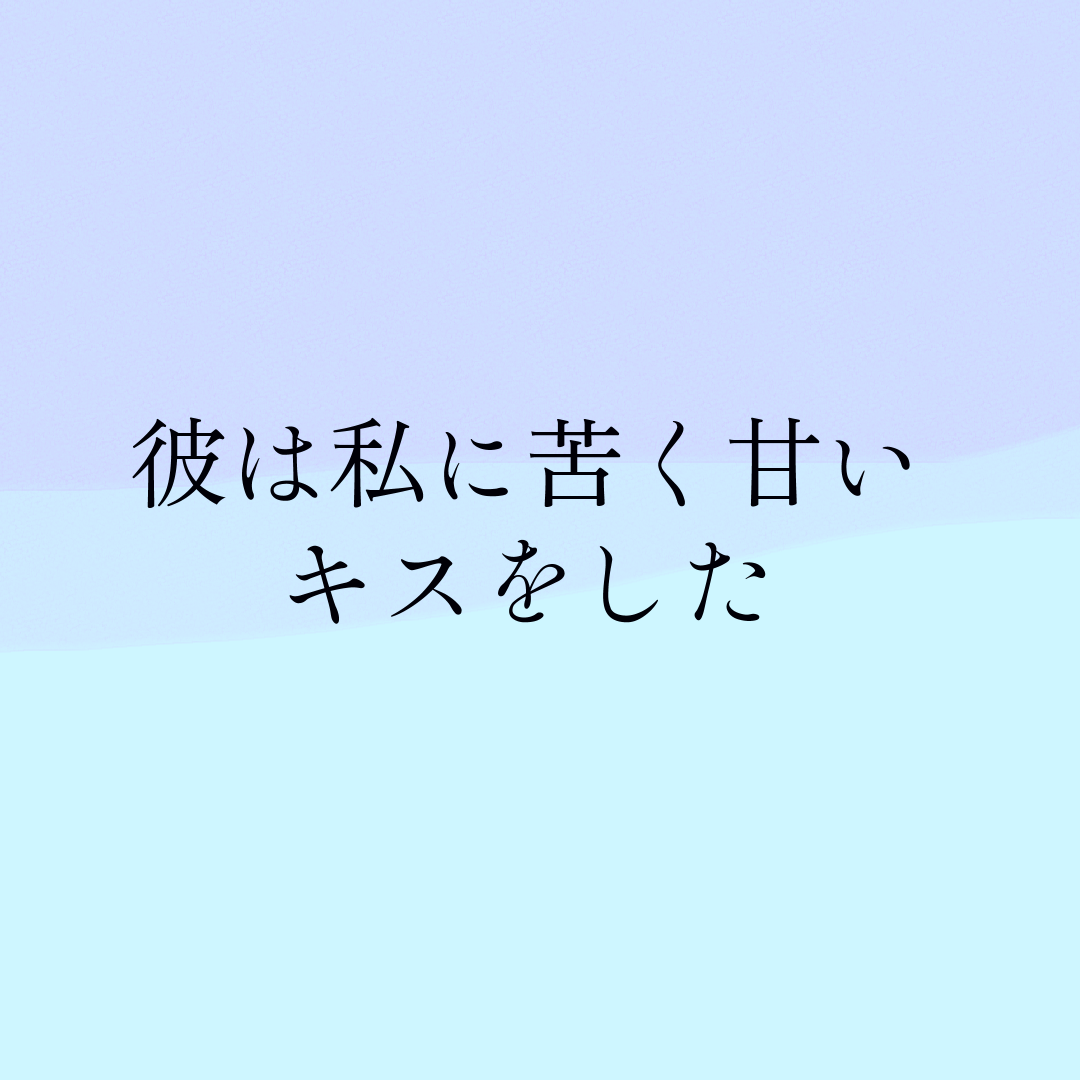
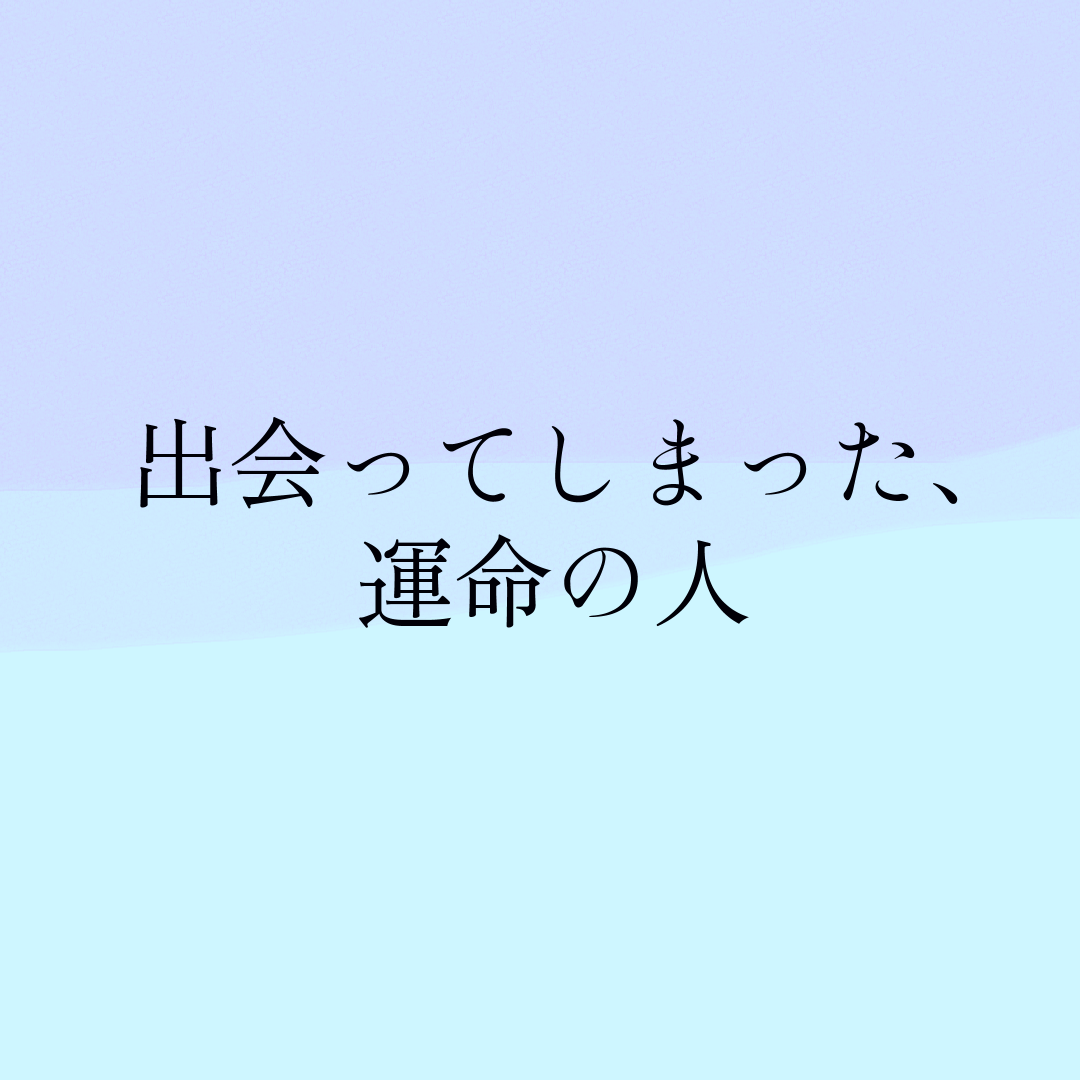
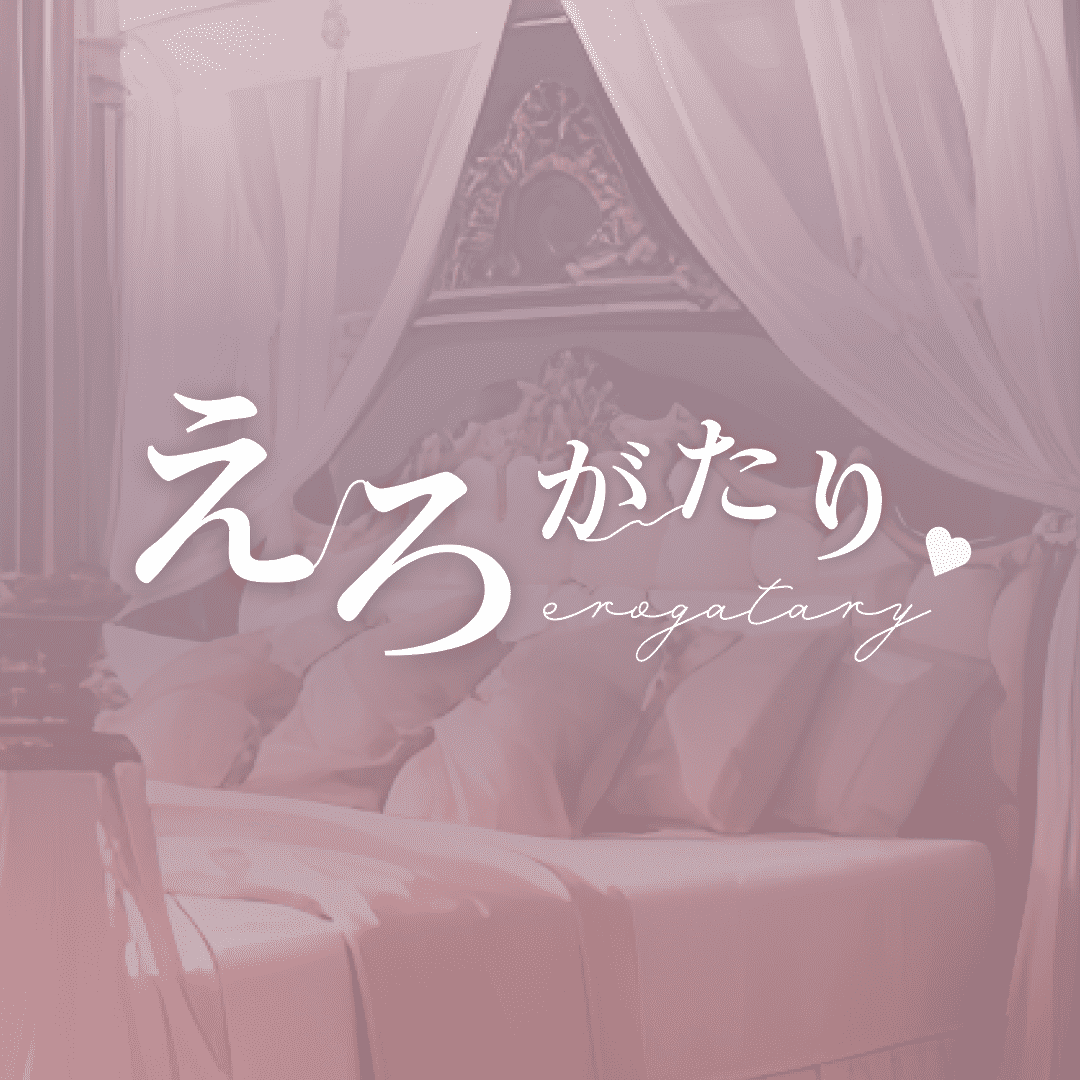
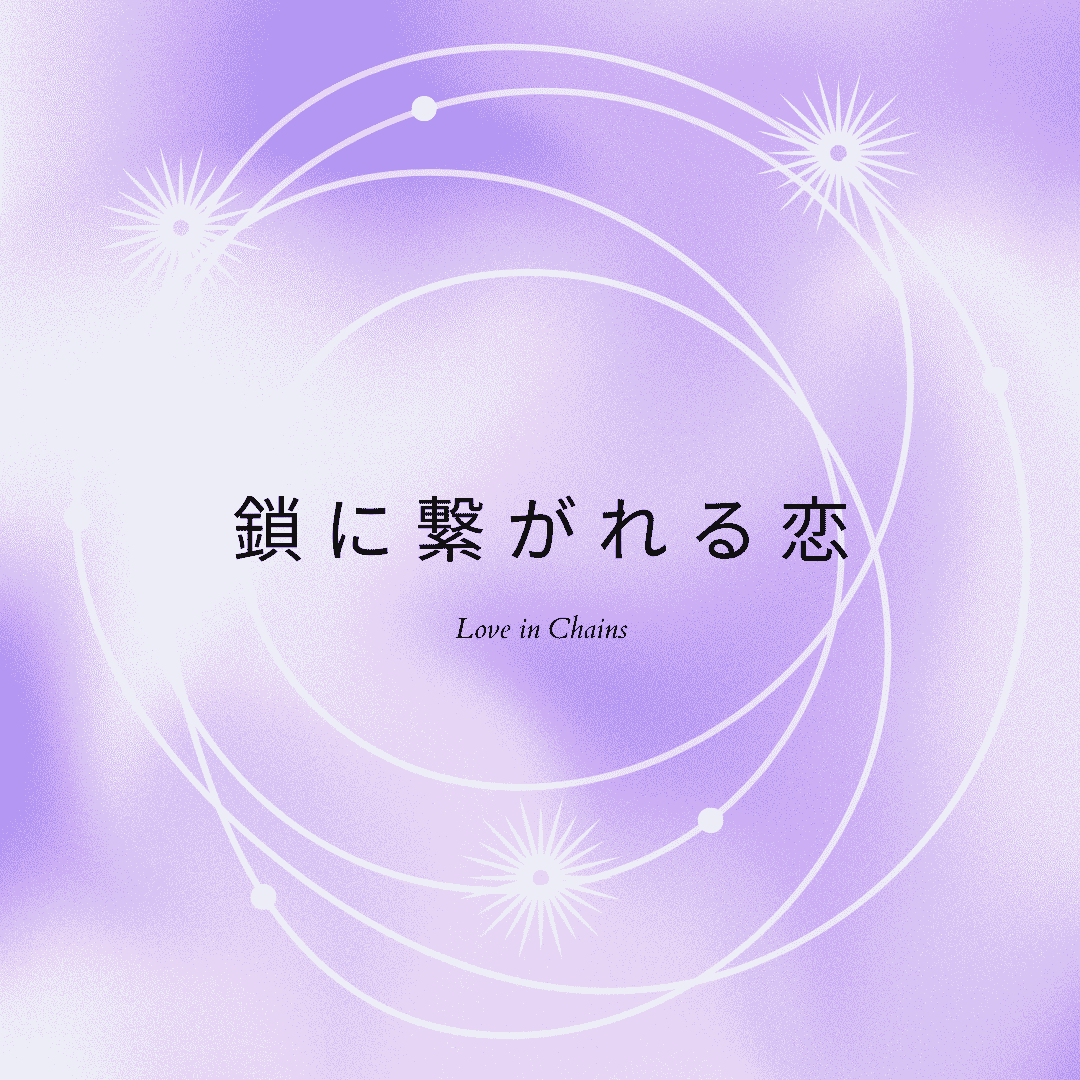



コメント