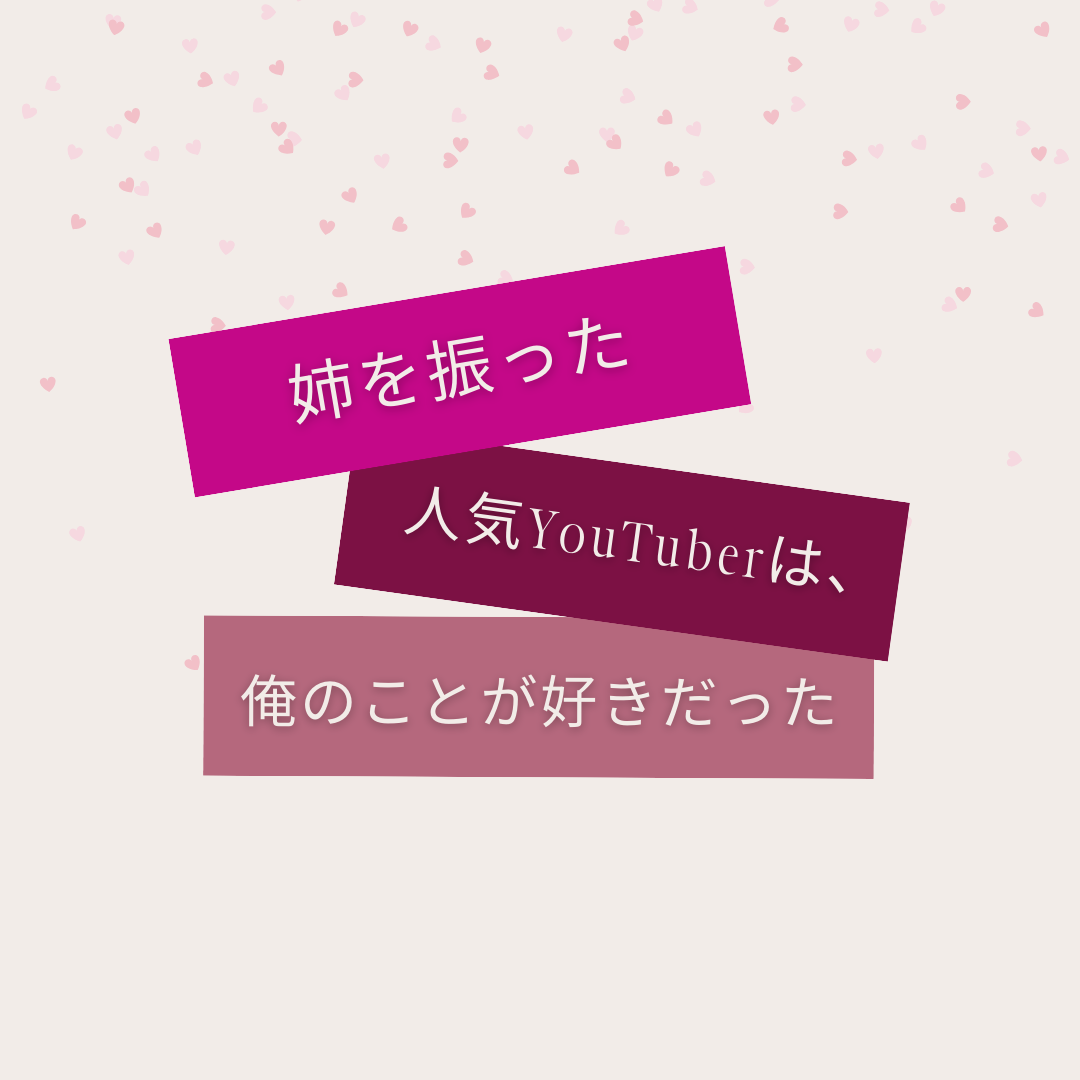
0
姉を振った人気YouTuberは、俺のことが好きだった
「ミハルンの動画見たー?」
「超人気歌手のaisと新曲コラボとか凄すぎ。夢あるよね~。」
高校3年生の女子たちが盛り上がる話題の中心は、だいたいYouTuber。俺のクラスでよく名前が上がるのは、ミハルンこと屋下ミハルだ。
ミハルンチャンネルは、つい最近登録者数50万人を突破した大人気のYouTubeチャンネル。歌ってみたやオリジナル楽曲の制作、雑談がメインのチャンネルで、その甘い顔面と声優顔負けのイケボを武器に、どんどん登録者を増やしているそうだ。
「マナトはYouTubeとか見ないの?」
ぼーっと窓の向こうの景色を見ていると、動画の話で盛り上がっていた隣の席の女子に、話しかけられた。
「たまには見るかな。」
「てかここで流しちゃおー! みんな聞いてー!」
そう言って隣の席の女子は動画を再生し始めた。アップテンポなイントロが流れ始める。この曲、確か1ヶ月前とかに聞いたな。やっと公開になったんだ。
だなんて、ここでは口が裂けても言えない。
ー
「おかえりマナト!」
「ただいま。自分の家みたいなくつろぎかたしてますね?」
「お前のねーちゃん出てったんだからさー部屋あいてんじゃん。毎日きたっていいだろ。そのうち家買ってやるから。」
「そんな服買うみたいなテンションで言われても。」
「どのあたりがいい? 駅近の分譲マンションとかいいよなー」
「勝手に話進めないでくださいって。」
授業が終わり帰宅すると、さっき教室で大音量で流れていた声に出迎えられた。茶色の癖っ毛に聞き取りやすい声、にこにこと人懐っこい犬みたいな顔のこの男こそ、ミハルンチャンネルの屋下ミハルだ。
ミハルさんと出会ったのはちょうど半年前。つい最近まで一緒に住んでいた姉が、この家に連れてきて、紹介してくれたのだ。
「友達のミハルくん! マナトってYouTubeとか詳しいっけ。」
いやそこまで、と答えると、姉はその場でラインで動画のURLを送ってきた。2人が何やら隣の部屋で話し込んでいる間、俺は自室のベッドの上で、送られてきたURLを開いた。さっき家に入ってきた男が画面の中で元気よく話している。てかミハルってどんな漢字を書くんだ? そんなことを考えながら見ていたら、いつの間にか動画は終わっていた。
それからミハルは、定期的に家に遊びにくるようになった。人気YouTuberがこんなにふらふらと遊んでいていいのかわからないが、いつも高そうなお菓子を持ってきてくれるから、そこだけは感謝している。俺が甘党だと知られてからは、持ってきてくれる量が増えた。
当たり前のようにミハルさんと姉が付き合っているものだと思い込んでいたある日、姉が泣いて帰ってきた。ミハルさんに振られた、とだけ言い、1週間も経たぬうちに、傷を癒すために、女友達とルームシェアするからと家から出て行った。その次の日、なぜかミハルさんが家にきた。
「なにしにきたんですか?」
持ってきてくれた期間限定のフルーツゼリーを食べながら聞くと、ミハルさんは耳を疑うようなことを言ってきた。
「俺さ、マナトくんのねーちゃんじゃなくてマナトくんが好きなんだよね。」
「はあ?」
「もうさ、どタイプ。マナトくん猫ちゃんみたいな顔してるし、声可愛いし。」
「姉は?」
「友達の紹介で知り合って、最初のうちはあー好きかもって思ってたんだけどさー、マナトくんの画像見せてもらってびっくりしたよね。俺こっちの方が好きだわって。そりゃ家にも通っちゃうよね。」
「じゃあ最初からそう言ってくれればいいのに。」
「タイミングとかわかんなくてさ。ねーちゃんに振ってごめんって言っといて。」
「なんて適当な……」
そんなこんなでその日のうちに、俺は処女喪失してしまった。初めての男同士のセックスだったから、相性がいいかどうかとかわかんなかった。けど、気持ちよかったから、そのまま付き合うことにした。俺もだいぶ適当な男かもしれない。
「今日もまたヤりにきたんですか?」
「まあねえ。ほら、チャロフの新作チョコ。」
「うわー!……って、まじで餌付けみたい。」
「いいじゃん。ほら、チョコ食べた口でちゅーしようよー」
ミハルが箱を開けて、チョコを1つ出してくれた。それをあーんしてもらって、口の中で溶かしていく。溶け切るうちにミハルが口付けてきて、強引に舌をねじ込んできた。ブラックコーヒー味のするミハルの唾液と混ざって、カフェモカみたいな味になっていく。いいな、一緒に料理してるみたいな気分。ミハルが家にきてやることといえば、セックスばかりだ。でも毎日動画配信頑張ってるわけだし、これが癒しになってるのならいいかも、なんて思っている。
「ふぁ……っ」
「キスしただけで気持ち良くなっちゃった?」
唇を離し、ごくっとカフェモカみたいな味の唾液を飲み込む。ミハルの一部を身体に取り込めた気分。これも悪くない。舌が性感帯なこともバレてるけど、もういいや。おいしいなら、なんだっていい。
「はいマナトくん服脱ごうねえ。」
「んぅ。」
両手を無理やり上げさせられ、徐々に制服を脱がされていく。前に1回着たままヤったらシャツに自分の精液ついたから、それからは絶対脱がせてくれるようになったのだ。2人とも裸になり、ベッドに移動した。
「チョコ美味しかった?」
「おいしかった、です。」
「よかったーまた買ってくるからねえ。」
ちゅ、と音を立ててもう一度口付けられ、それから乳輪のあたりを指の先の方だけで優しくなぞられる。こういったフェザータッチが好きなことまで覚えてるの、高額スパチャ投げてくれる視聴者を覚えているみたいな感覚と、同じなのかな。フェザータッチが好きなマナトさん、みたいな。
「何考えてんの、他所ごと?」
「んうっ!」
集中していないのがバレて、強めに乳首を摘まれ、また変な声が漏れてしまった。ミハルはこの声のこと、かわいいって言ってくれるから、我慢せずに出すことにしてるのだ。
「かわいいねえ。乳首弱くなっちゃったの、俺のせいだもんねえ。」
「ん……吸っちゃ、や。」
「やじゃないでしょ。」
「ぁああッ」
今度はかりって甘噛みされた。フェザータッチ以外の攻められ方をすると、さらに甘ったるい声が出てしまう。俺の声を聞いたミハルは嬉しそうに笑い、太ももの間に顔を埋めてくる。若干硬くなっている俺のちんこを、溶けかけのアイスを吸う時のように、舐め始めた。
「ん……うっ、ん……」
ミハルの口の中で、俺のちんこがむくむくと膨らんでいく。根元まで丁寧に唾液を塗し、根元の方を手で、先端は口でどんどん刺激されていく。
「はぅ……っ、きも、ち……っ」
「ひもひい?」
「ぁああ、そこでっ、だめッ」
もそもそとちんこを咥えたまま言葉を話され、くすぐったさよりも気持ちよさが勝ってしまうのも、なんだか悔しい。先端を舌でちろちろと舐められていただけだったのが、一気に喉奥まで咥え込まれる。
「あが……ッ!」
あまりの刺激の強さにぎゅっと目を瞑ると、視界が遮断されたことで、さらにその刺激がダイレクトに伝わってしまう。がくがくと腰が揺れ、ミハルの喉奥を何度も突いた。俺の我慢汁とミハルの唾液が混ざり、さらに滑りが強くなっていく…。もう何も考えられなくなりそう…とその時。
「あ……っ、まって、出ちゃ。」
「いいよ。」
再び、咥えたまま喋られ、ちんこを握っている手がさっきよりも強く速くなっていく。ぴきぴきと血管が強く浮き出る感覚の後、ミハルの喉奥に吐精した。
「……っ、また、飲むんですね。」
ごく、っとわざとらしく飲み込むところまで、見せつけてくる。相変わらずだ。
「マナトくんの精子飲むとさー、なんか、声良くなる気がすんだよね。」
「元々声いいじゃないですか。」
「まあね。じゃ、俺も気持ちよくなっちゃおうかな。」
ミハルが持ってきたゼリーを、直接俺の穴のあたりにぶっかけられ、ぐちゅぐちゅとそこをほぐされていく。人差し指も追加され、2本の指がスムーズに動くようになって、すぐに抜かれる。こんなにも手早いのに、全く痛くない。ミハルに身体を熟知されているのが、よくわかった。これをするの、もう何回目なんだろう。
「入れるね。」
さっきよりも優しい声で言われ、ゴムがついたちんこが挿入されていくのを感じ、ゆっくりと息を吐き出す。根元まで入ると、すぐに抱きしめて、そこにちんこが馴染むまで待ってくれているのだ。
「……ミハルさん、こういうところだけ優しいですよね。」
「だけって失礼な。だってマナトのこと、傷つけたくないし。」
「やっぱり優しい。好き。」
「素直なマナトかわいい。俺も大好き。」
鼻のてっぺんにキスされ、ミハルはマナトの腰を掴み、ゆっくりと動き始める。もうどこを押したら気持ちいいか全部バレてるから、俺はただ力を抜いて、その気持ちよさを享受しているだけでいいのだ。
「ぁあんっ、ん……あっ、そこッ」
「マナトの好きなところ、ちゃんと全部覚えてるから。」
「あぅっ、きも、ちっ、あっ中でっ、中でイっちゃ……っ!」
「何回でもイっていいからね。」
「ぁああッ、イくッ!」
あたたかい声に包まれ、細かい中イキを繰り返す。イくたびにちんこの出し入れは速くなっていき、俺のなかでさらに硬く膨らんでいく。
「ミハルさん、も……っ」
「マナト……ミハルって呼んで。」
「……っ、ミハル、ミハルっ……ぁあっ。またイくッ!」
名前を呼んだ直後に、なかが喜んでるみたいに痙攣した。その衝撃でミハルの腰の動きがゆっくりになり、達したのがわかった。
「名前……破壊力やべえわ。」
ゴムの口を結びながら、ミハルが興奮した声で、そう言った。俺も呼び捨てで呼んだ瞬間、とんでもない快感に包まれたから、気持ちはわからなくもない。
「これからさ、普通にミハルって呼んでいいよ。なんならタメで話してくれていいし。」
「うーん、考えときます。」
「なんでだよ!」
「なんか、セックス中だけの特別な呼び名、って感じしていいな……って、」
「やっぱりマナト世界一可愛い!」
ゴムをゴミ箱に投げ捨てたミハルが、まだベッドから動けない俺に、飛びついてきた。
「そういえば推薦で大学決まってるよな。大学生になったらカップルチャンネルやっちゃう?」
「またまたー俺そんな顔も声も良くないし。」
「何言ってんだよすぐ登録者数100万人超えるって!」
「んー、じゃあそれまでには一緒に住まないとですね。」
「よっしゃ、家買ってくるわ。」
「またそれっすか。」
大きめの声で笑うと、つられてミハルも笑った。こうやって、全部曝け出せるのはミハルだけだ。これからもこうやって、笑い合えますように。





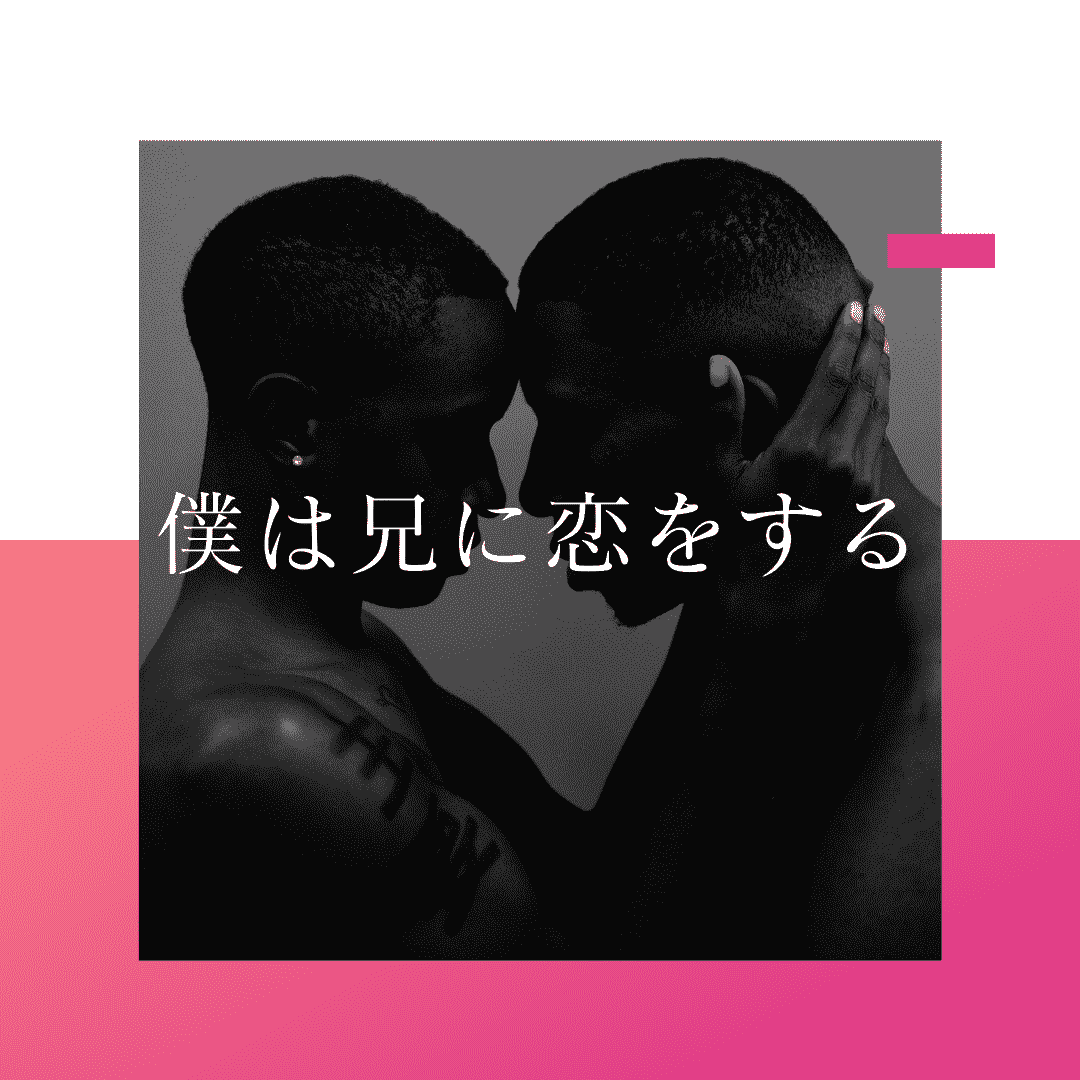



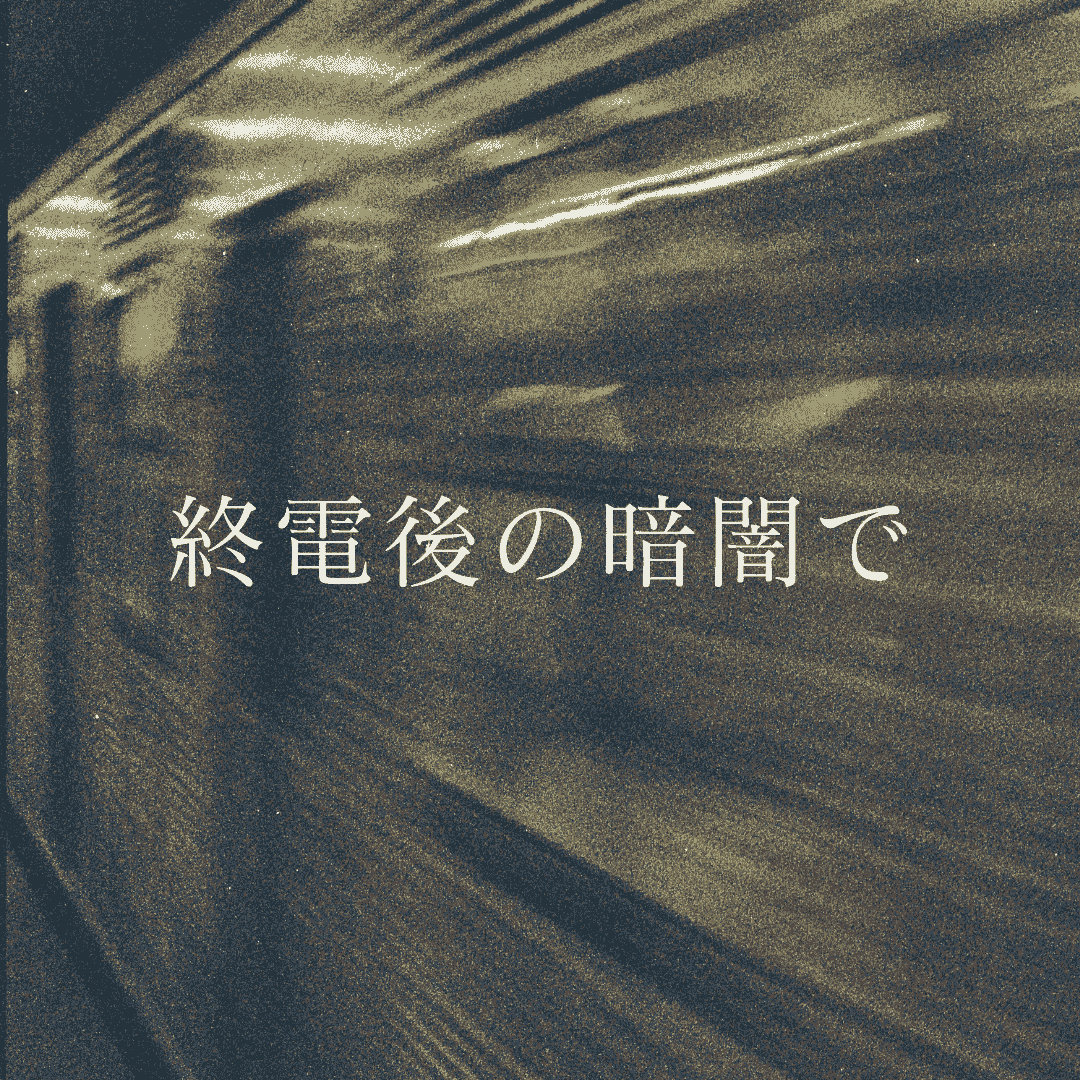
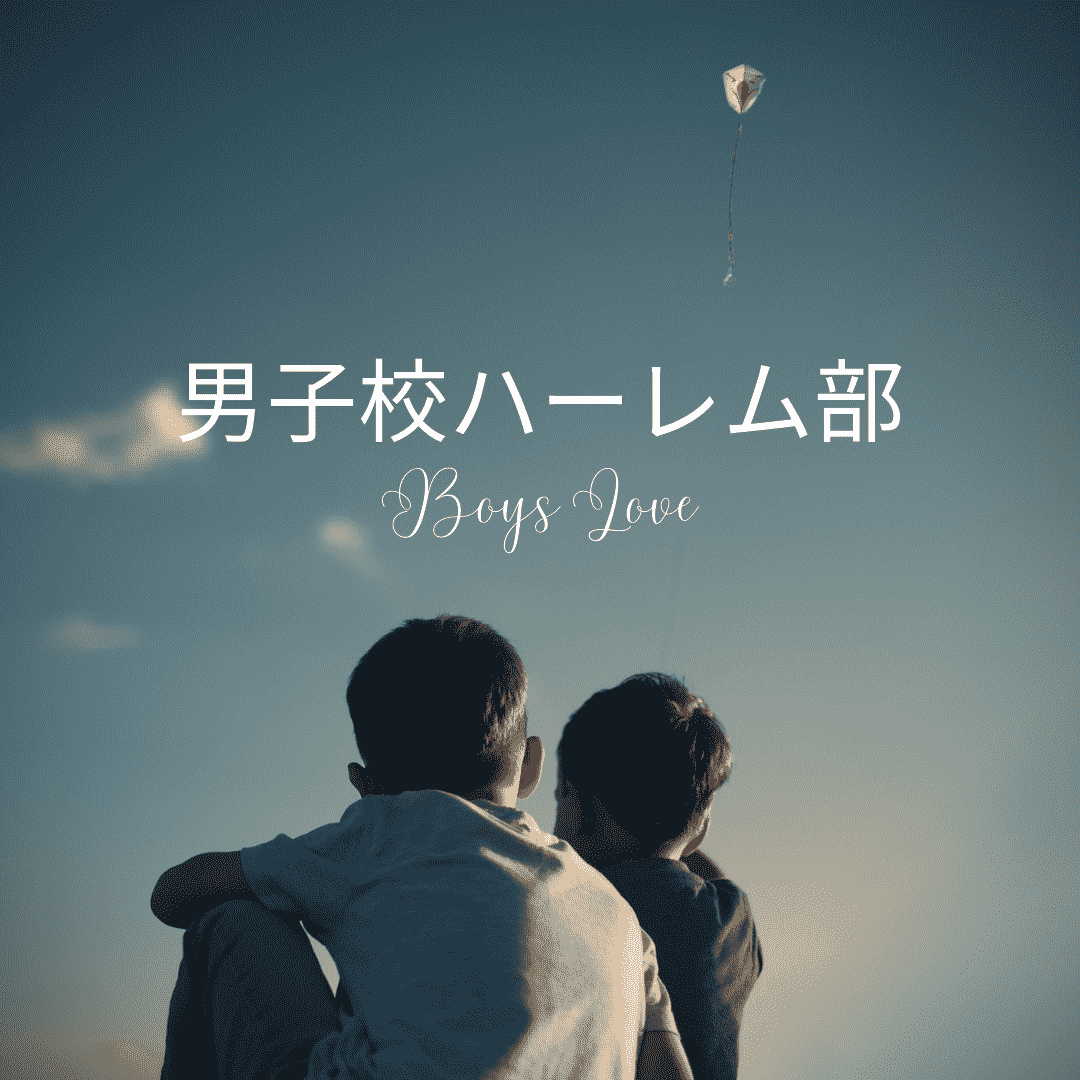
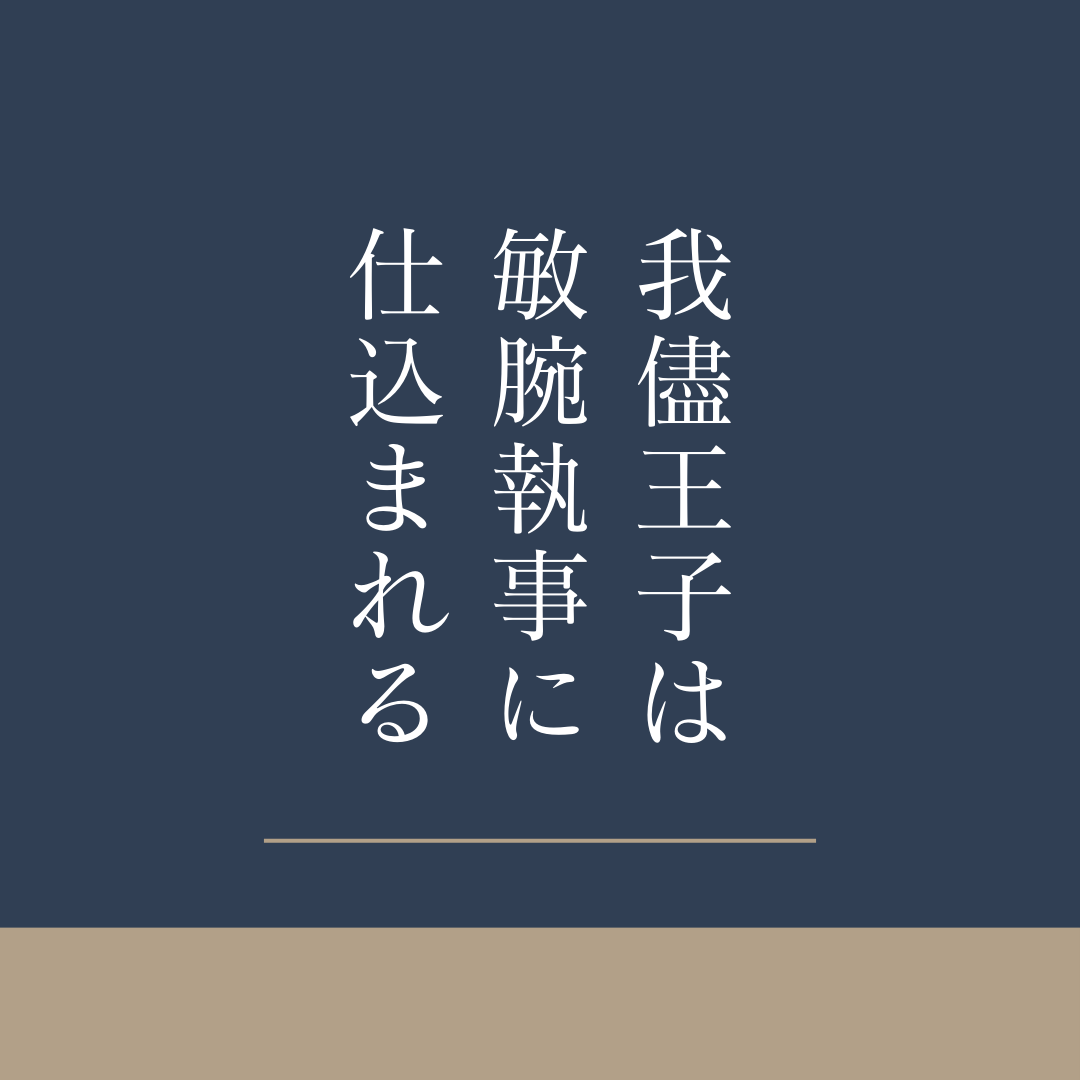

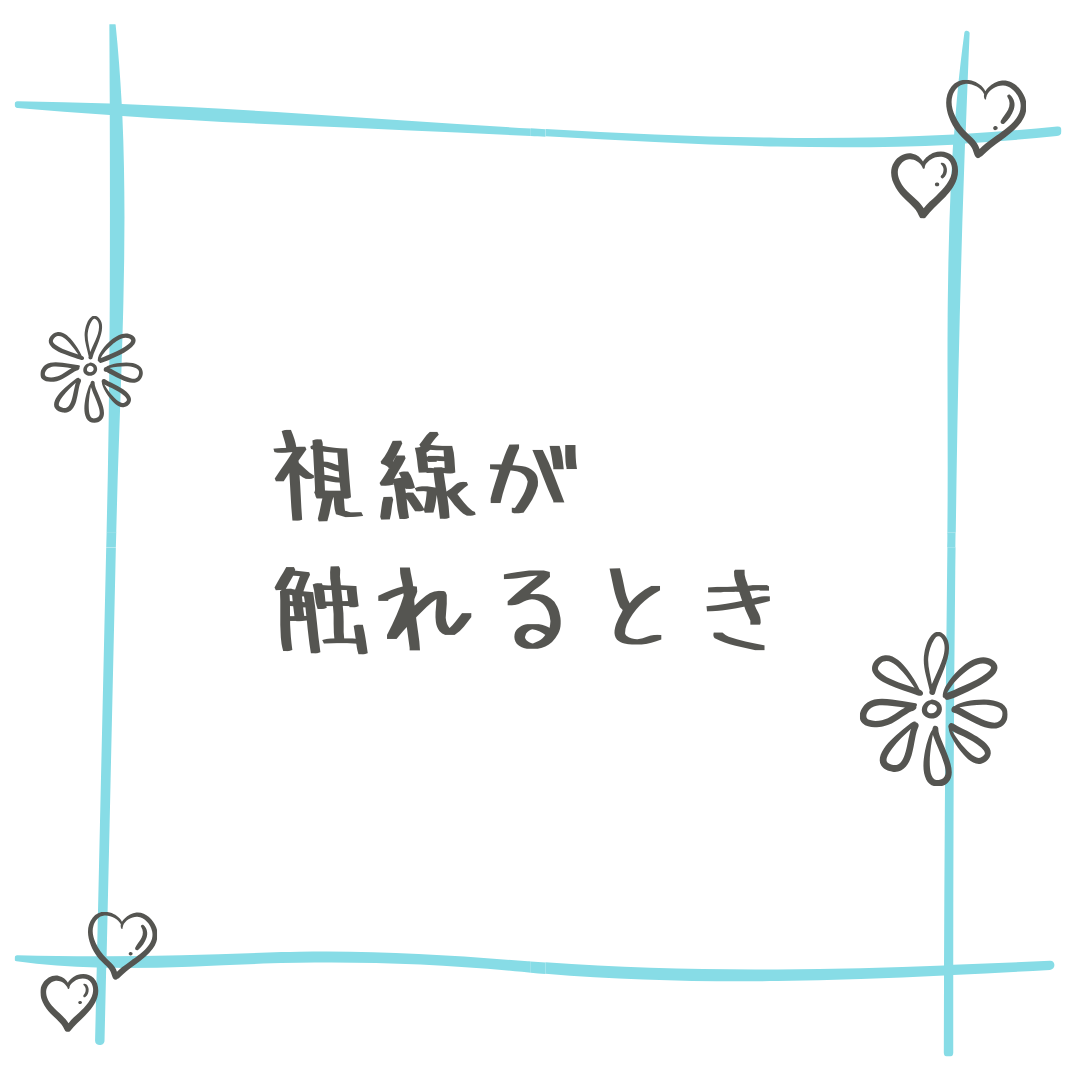












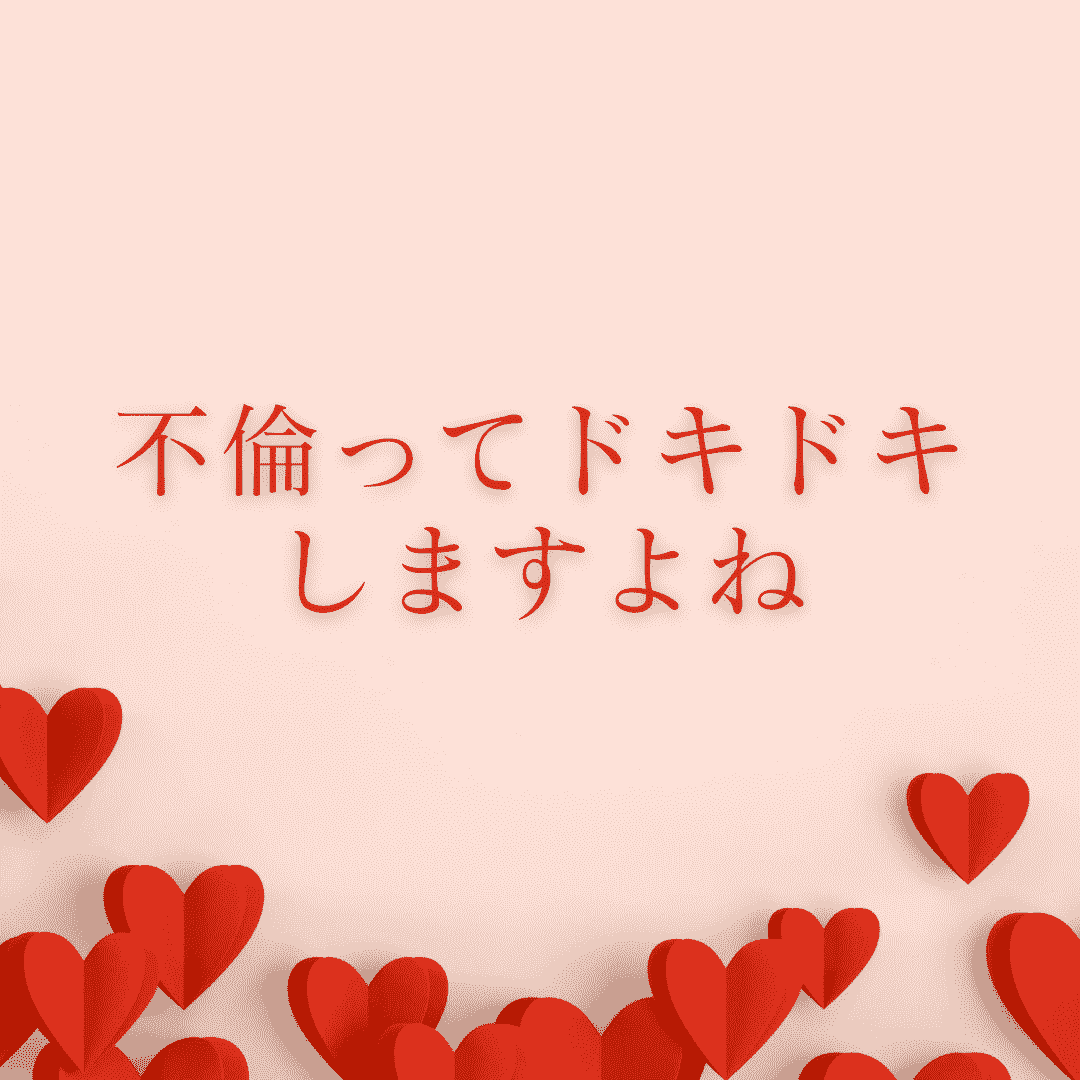




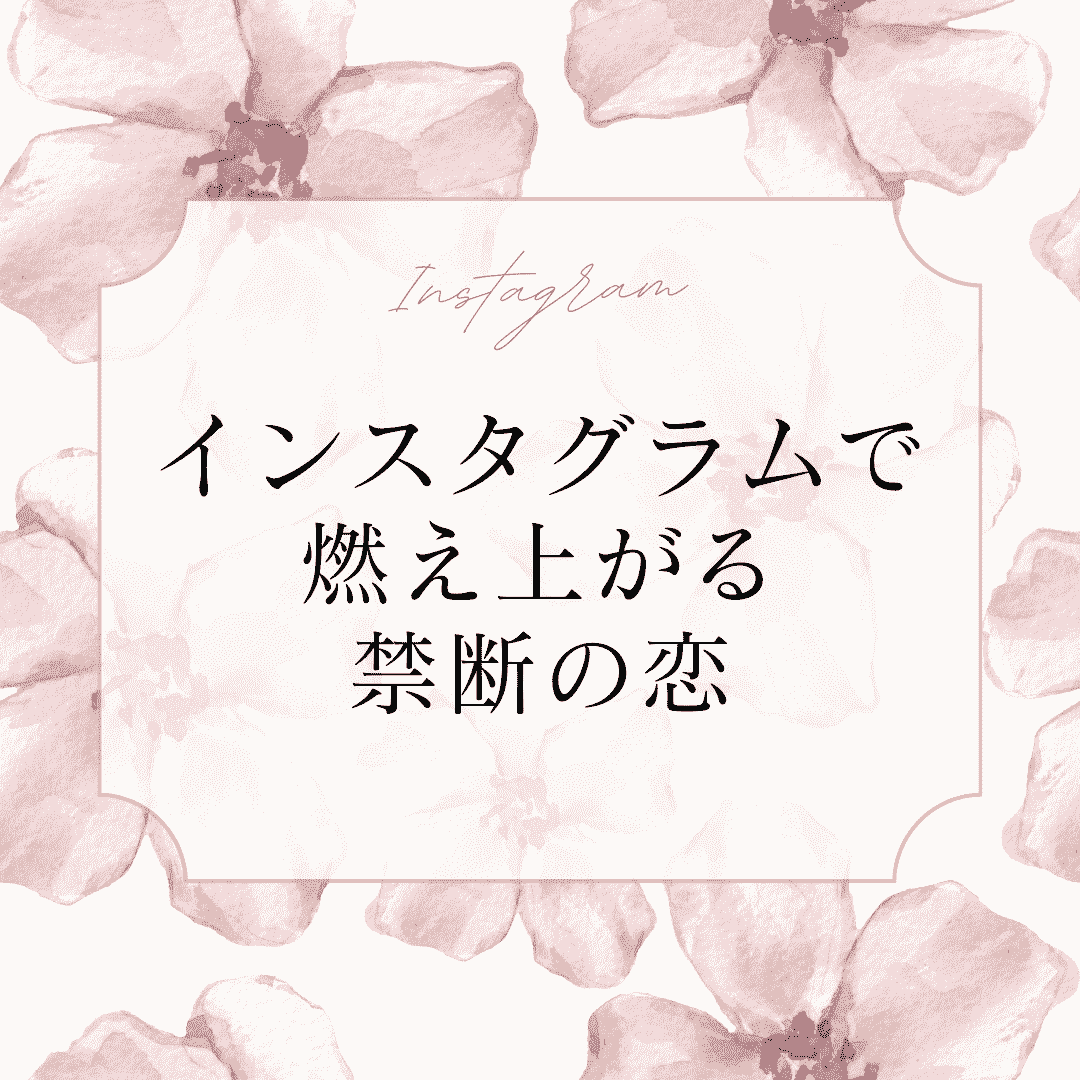






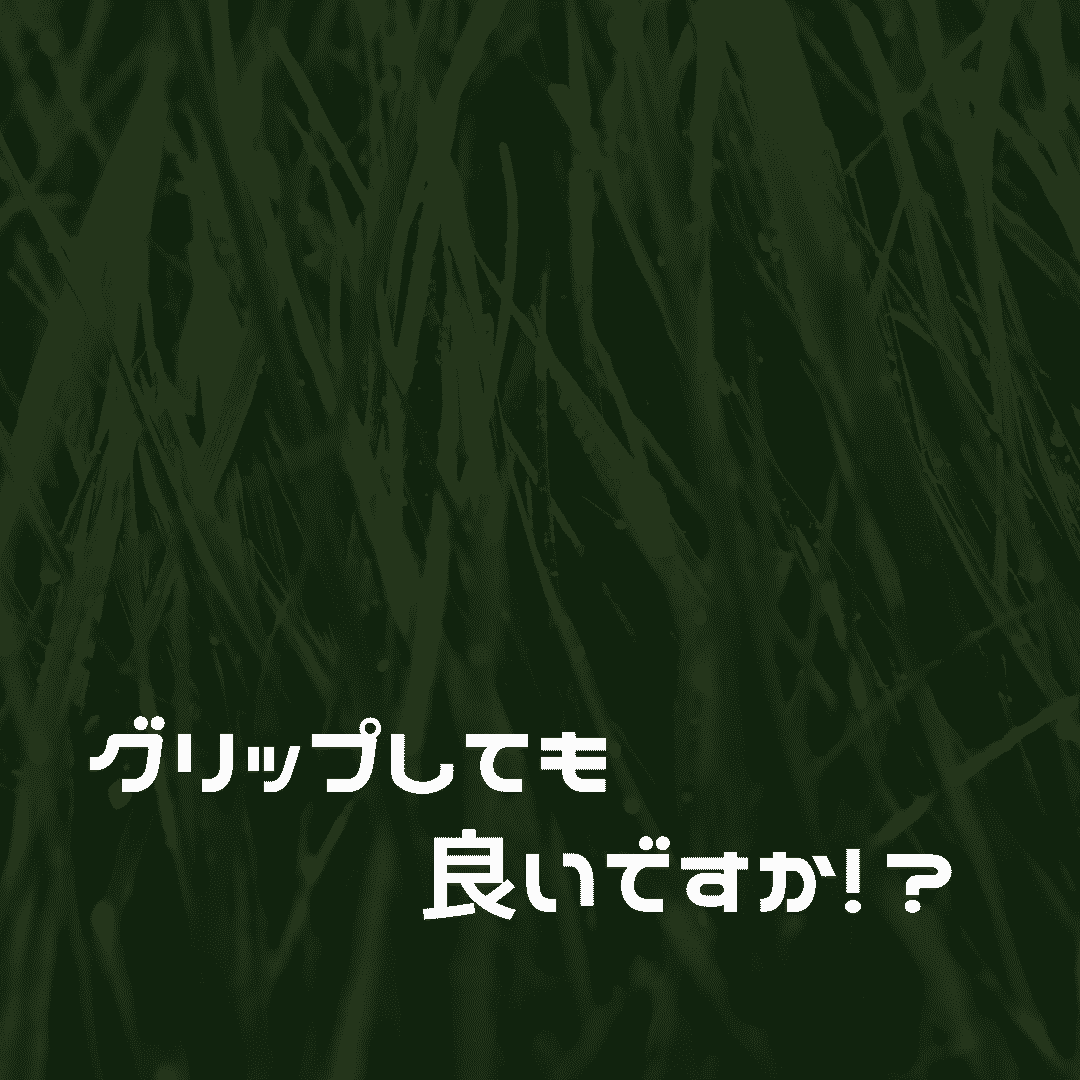

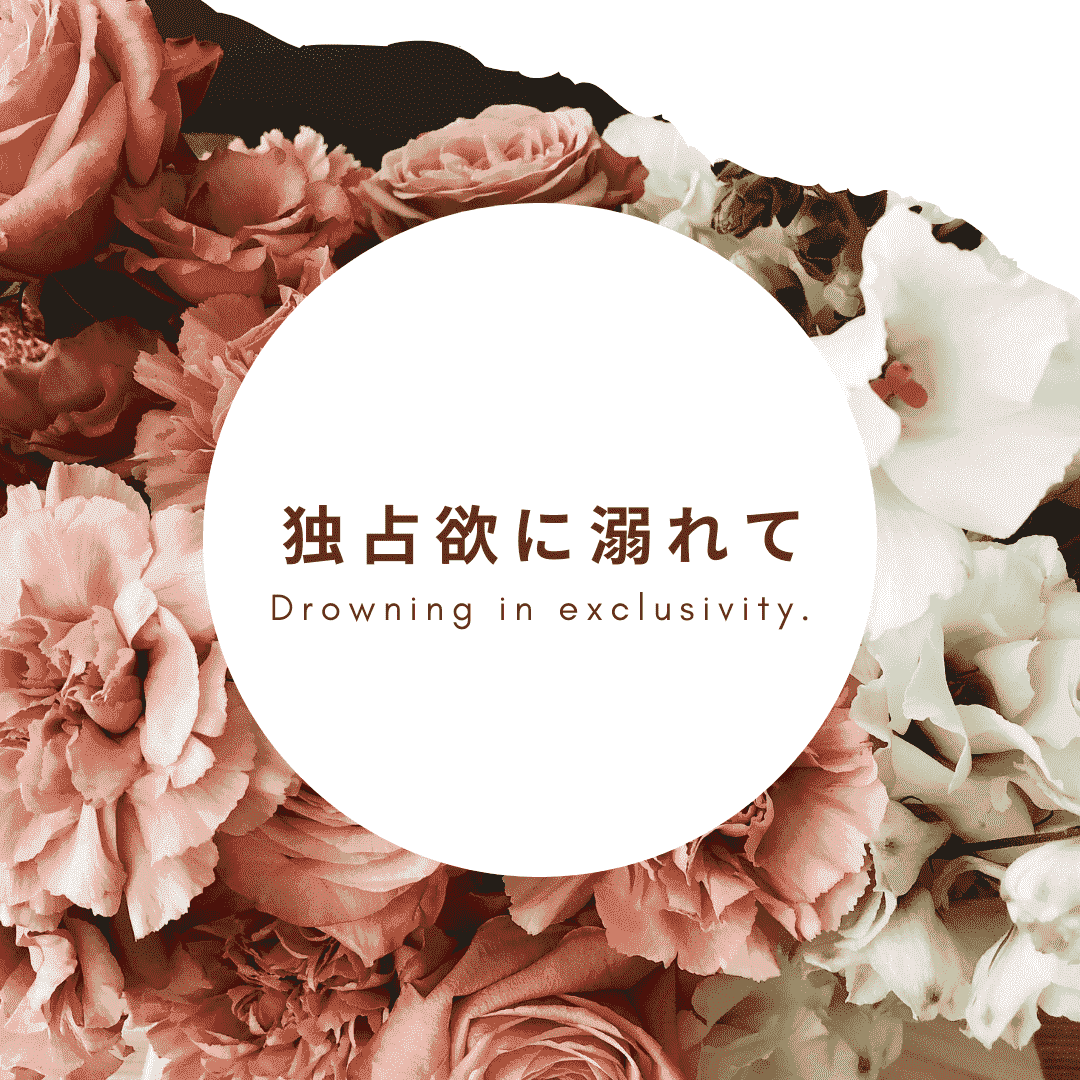
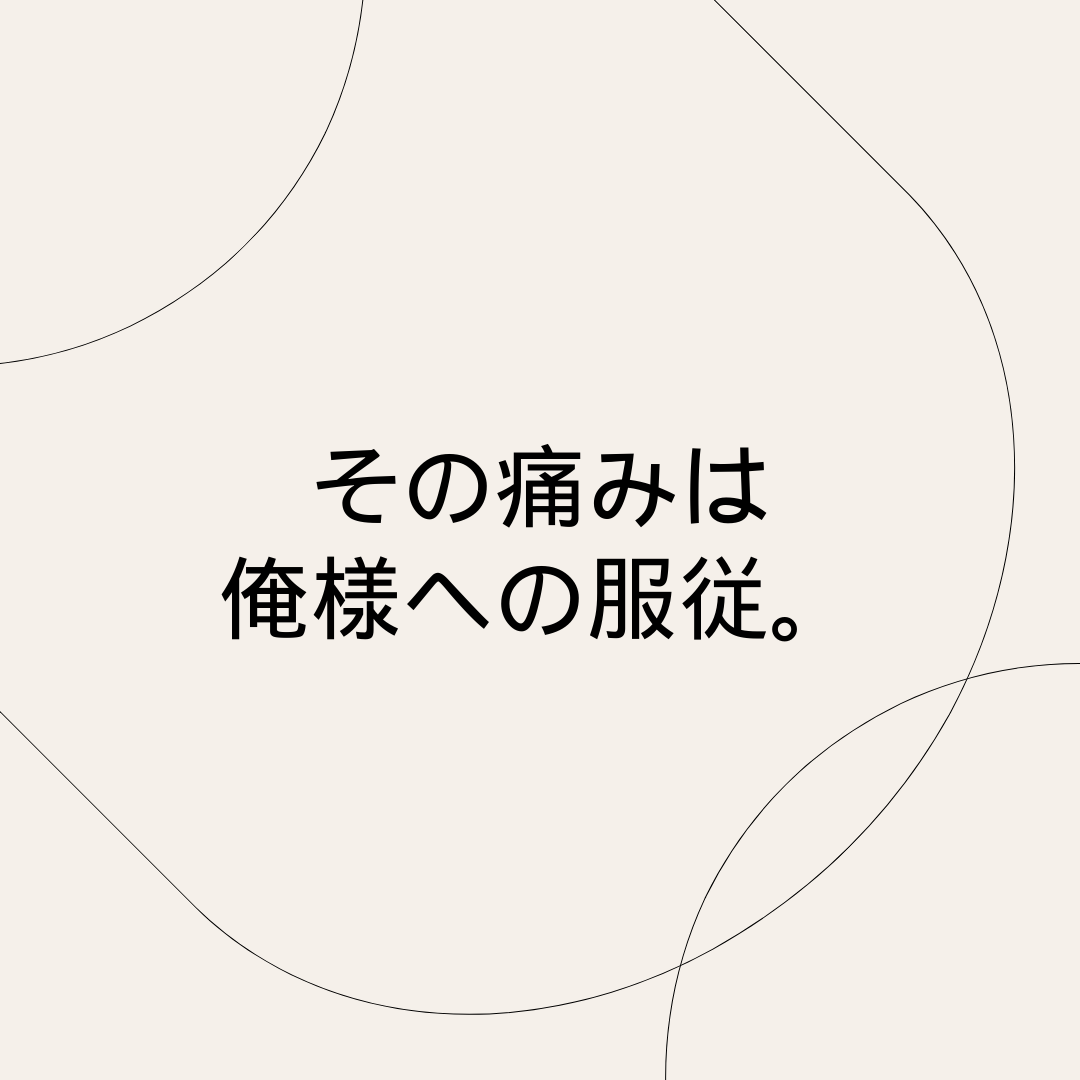
コメント