
0
深夜病棟、癒しの君
カラカラとカートを押しながら、山内リクは、消灯前の検温のために病棟の廊下を小走りに駆け抜ける。夜勤の入りは、いつも戦場だ。
「あー!リクー!明日サッカーしようぜ!」
「こら!みっちゃん!もう寝る時間だろー!それに病院はサッカー禁止って何度言えばわかるんだよー!だーめ!治ったらな!」
「あら、リクちゃん!今日夜勤だったの?ちょっと後で寄ってよ!お見舞いの果物持っていって!」
「ごめんね、トメさん。嬉しいけど、それは貰えないからご家族に持って帰ってもらって。」
ひとたび廊下に出ればあちこちから声がかかり、都度笑顔で返事をしながら、次の担当患者の病室へ向かう。
「えーっと、残りは個室だけか……今日は個室で使ってるのは……お、一番奥の丹波さんだけか!」
意外に早く終わりそうだ、とリクはそのままの勢いでカートを押していく。
「こんばんはー丹波さん。就寝前のバイタルチェックさせてください!」
静かに個室の引き戸を開くと、ベッドサイドの読書灯だけつけて、静かに本のページを捲っていた丹波が顔を上げて、リクに手を振った。
その姿に、リクの胸の奥がトクンと跳ねる。悟られないようにリクはすぐに視線をそらすと、そのまま後ろ手に扉を締めた。
「やあ、山内くん。お疲れ様。相変わらず君は人気者だね。」
「えっ?そうですか?」
リクはカートを押しながら丹波のベッドサイドへ向かうと、丹波に体温計を渡し、そのまま差し出された腕に血圧計を巻いた。
「ここまで君を慕う人たちの声が聞こえてきたよ。」
「あー子供たちですか?すみません、痛みがなくなるとみんなもう元気が有り余ってしまうようで……」
「ふふ、いいんだよ。ああいう元気な声というもの良い栄養剤になる。」
そういいながら丹波は、それまで読んでいた本をパタンと閉じると、サイドチェストの上に載せた。
「そう言って頂けるとありがたいです。体温計も大丈夫ですか?」
「あぁ、問題ないと思うが一応確認してもらえるか?」
そういいながら、丹波はリクの手に押し付けるように体温計を持たせると、そのままスルッと撫でるような形で手を滑らせた。肌ざわりの良いその手のひらに、リクはカッと頬が熱くなる。
「うん、問題なさそうです。いよいよ丹波さんも明日で退院ですもんね。僕が最後の日の夜勤で嬉しいです!また何かあったらいつでも呼んでください。」
取り繕うように早口でそういうと手早く血圧計を片づける。
「ありがとう。君には色々とお世話になったね。あとでお礼をさせてくれ。」
ゆっくりと布団にもぐりこみながら丹波はそう言って、静かにリクを見上げた。
「そんな!お気になさらず!では、失礼します!」
丹波の言葉に笑顔で返事をすると、リクは彼の病室を後にした。
「明日かぁー。そっかぁー。」
患者が元気になって退院していくことは、この上なく喜ばしいことに違いない。しかし……
(いや、そもそも患者さんに、そういうよこしまな気持ちを抱く俺がいけない!)
ぴしゃりと自分に言い聞かせ、リクはそのままナースステーションへと戻っていった。
自分がそういうマイノリティの側にいると認識したのと、看護師を目指し始めたのは同時期だったように思う。特定のパートナーはいないが、今は仕事が楽しいし、それで十分と思っていたのに……
そんなことを考えながら、リクはトボトボと廊下を歩いていく。
「ま、最初から叶わない想いだ!明日の朝元気に挨拶して別れよう!」
日の目を見ない想いは、これが初めてではない。良い出会いだった、とリクは無理やり自分に言い聞かせ、ステーションの椅子に腰かけると、勢いよくカルテを書き始めた。
「山内ー!休憩おさきー!」
ナースステーションでカルテをまとめていると、先輩が間延びした声で仮眠室から戻ってきた。
「お疲れっす!特になんもなかったです。」
パソコンを操作し、ログアウトしてから、リクは傍においてあったペットボトルとピッチを持って、椅子から立ち上がった。
「急搬は?」
「今のとこ外科はないそうです。」
「おっけー、ゆっくりしてきなー!」
「あざっす!」
先輩と院内ピッチを交換し、リクは給湯室へ向かう。買い置きしてあるカップ麺にお湯を注ぎ、冷蔵庫に入れておいたおにぎりとヨーグルトを取り出し、それらを抱えて仮眠室へ向かった。
一息に食事を食べ終えると、リクはあちこちテレビのチャンネルを変えながら、ヨーグルトをのんびり食べ進める。
「明日の明け、何しよっかなー。買い出しして、車のオイル交換と……」
ピピピピ!
ボーッとテレビを眺めながら呟いていると、突然テーブルの上のピッチが鳴り響いた。
「あれ?先輩忙しいのかな?」
画面を見れば、丹波の病室からのコールだ。滅多に鳴らないコールに慌ててリクは立ち上がり、ナースシューズを履いた。
「はい、丹波さん、どうされましたー?」
ガラガラと仮眠室の扉をあけ、ナースステーションを小走りで通り抜ける。
『……』
しかし丹波からの返事はなく、ゴソゴソと衣擦れのような音が聞こえるだけだ。
「丹波さん?」
『……ぅ、……あ』
すると少し離れたところからうめき声のようなものが聞こえた。
「えっ?」
リクの顔色が一瞬にして曇り、大慌てで丹波の居室へと向かう。
(急変?いや、ありえない。持病もなくて今回はただの骨折で……)
あらゆる最悪の想定がリクの頭をよぎる。
(今日の当直は誰だったか?いやこの場合はまず先輩に……)
頭の中でパニックを起こしながら、リクは病室の前で立ち止まり、即座に扉を開く。
「だいじょ……えっ?」
「あっ……うぅ、はぁ……あぁ…」
勢いよく開かれた扉に気付かないのか、丹波はリクに背を向ける形で、小刻みに身体を震わせている。
「あぁ……やまっ、うちくん……あぁ、はぁはぁ……ああっ!」
(えっ、もしかして……いや、もしかしなくても??ていうか、今僕の名前……)
予想外の自慰行為を盗み見てしまい、リクは慌てて踵をかえそうとするが、思うように身体が動かない。長いことこの仕事をしていると、こういう場面に出くわすことは珍しくない。いつもならそっと何も見なかったことにして、気付かれないように立ち去るのだが……
「あぁ……うっ、あっ……はっ、あ……出るっ……うっ」
普段の温厚な彼からは想像もつかないワイルドな息遣いに、あろうことか自身の身体が反応してしまう。
(バカっ、俺はなんてこと……)
ビクビクッと幾度か身体を跳ねらせ、欲を吐き出したのか、丹波の背中が大きく弛緩する。
(マズい、ばれるっ……!)
慌てて病室を後にしようと身体を動かした瞬間、出入口の傍に設置してある洗面台に手があたり、かけてあったプラスチック製のコップが勢いよく落ちた。
カラーン!!
勢いよく落ちる音に、丹波が上体を起こし振り返る。
「やまうち…くん?」
そして動揺を隠しきれない声で、リクの名を呼んだ。
「あ、ご、ごめんなさい!ナースコールが鳴って、それで……す、すみません!」
慌てて居住まいをただし頭を下げるリクに、丹波はいつもの様に優しい声音で返す。
「いや、すまない。こちらこそ……そうか、耽っている最中にうっかり押してしまったのかな、お恥ずかしいかぎりだ。忘れてくれ。」
「そんな、全然!その、僕……」
どう返事をしようか考えながら彼の方を向くと、やや視線が下に向けられた丹波の姿が目に入った。
「君……」
「え?……うわあっ!」
丹波の視線を辿ってリク自身も目線を下に向けると、スクラブの上からでもハッキリとわかるほどに怒張した、自分のペニスが見えた。
「ごごごめんなさい!」
「いや、あやまることないよ。フフ……なぁ、よかったら、こちらにおいで。」
気持ちよくしてあげるから。と続けられ、リクはふらふらと引き寄せられるように、丹波の元へ向かってしまった。
「たんばさ……ん」
優しく手を引かれ、ぽすっとベッドサイドに腰掛ける。
「休憩終わるまであとどれぐらいだい?」
顎を掬われながらそう問われ、最後にわずか残った理性で、必死に計算する。
「あと、さんじゅっぷんくらい……」
「あぁ、十分だね。素晴らしい」
丹波は嬉しそうに呟くと、そのままリクの唇に齧りついた。
「あっ……た、んばさ…うっ、ぁ…も、……ああっ!」
スクラブの上下をはだけさせられ、リクは丹波に馬なりになる形で、彼から与えられる快楽にだらしなく声をあげてしまう。
「可愛いね、夢のようだよ……」
「っぅ……んぁっ!また…でちゃ…」
胸の突起を丁寧に舐め上げられながら、リクは丁寧に自身のペニスを撫で上げ、またブルブルと身震いする。
「あぁ、構わないよ。もう一度出したら、ココも私を迎えてくれそうだ。」
そういいながら、丹波はリクの秘部に深く埋めた指を軽く動かした。
「んあっ!!あぁ……そ、そこ…アツい…」
「私の指を美味しそうに咥えてくるよ。君、本当に初めてかい?」
丹波の問いかけに、リクは余裕なくコクコクと首を縦に振る。
「最高だ。可愛いね山内くん……」
「いや……」
はぁはぁと荒い呼吸の合間に、リクは今度は短く首を振る。
「ん?どこか痛い?」
「なまえ……名前で呼んでください。リクって…」
しどろもどろになりながら、可愛らしいお願いをしてみせるリクに、丹波は一瞬大きく目を瞠る。そしてニコリと一度笑うと、そのままリクに深く口づけた。
「あぁ、もちろんだよ。リク。」
そして耳元でそう囁くと、リクはあっけなく丹波の手中に吐精した。
「そろそろ休憩時間も終わってしまうからね。挿れるよ……」
吐き出したばかりのリクの精を、丹波は器用に秘部に塗りこんだ。
「うんっ…んぁ」
丹波の指の動きに合わせるように、自然と腰が動いてしまう。
「可愛いね、リク。さぁ、ゆっくりと息を吸って。」
丹波に優しく背中をさすられ、リクは深く息を吸う。と同時に、丹波の熱く滾ったペニスがリクの中へと侵入してきた。
「ひあああっ!!」
ギュウと丹波にしがみつき、リクは弓なりに身体をしならせ嬌声をあげる。
「ッ……はぁ、最高だ。君のナカが僕にしがみついて離してくれないよ。」
「あっ……やぁ、そんな……言わないで…」
重力に従うように腰を鎮めると、更に快楽が深くなりリクは及び腰になる。
「ほら、奥までちゃんと挿れないと気持ちよくなれないよ。」
しかし、そんなリクの動きを丹波はすぐに見抜き、グッと彼の腰を掴み自分の方へ引き寄せた。
「ああっ!!あっ……ふかっ…んぁっ、あっ」
「本当はもっと楽しみたいんだけど。もうすぐ君は、みんなの看護師さんに戻らないといけないからね……ごめんね。」
そういうと丹波は、下から突き上げるようにリクの最奥に腰を打ち付けたのだ。
「あっ!んあっ!!た、んばさっ……ああっ!も、あんっ!ああっ!」
「っく……あぁ、気持ちいいね、リク」
丹波に優しく撫でられたリクは、だらしなく淫らな声をあげながら、緩く頷いた。
「ん、きもち…ぃい……僕、また……いっちゃ…」
「あぁ、流石に若いからすぐに復活するね。」
先ほど吐精したばかりだというのに、リク自身はダラダラと愛液を垂らしながら、ゆるく勃ち上がっている。丹波は優しく微笑みながら自身の律動と合わせ、優しくリク自身も扱う。
「んあっ、あっ……たんばさ…」
「マコトだよ。」
「ふえっ?」
「マコトだ。呼んでくれ。」
そうだ、マコトさんだ。と頭の片隅で思う。
「んあっ、マコトさ、きもちい、きもちぃ……よぉ、いっちゃうぅ…」
「あぁ、僕もだよ、一緒にな…」
グチュグチュと卑猥な水音が大きくなるにつれ、リクの解放も近づく。
「あっ、ああっ……イっ……あああっ!!」
「……っく」
奥に熱い熱を感じながら、リクは眼下で優しく微笑む丹波と、そのまま流れるように唇を重ねた。
***
「リクー!またなー!」
「こらっ!リクさんでしょ!もうっ!…すみません、お世話になりました。」
母親に無理やりお辞儀させられながらも笑顔で手を振る患者に、リクも目いっぱいの笑顔で手を振る。
「はーい!もう怪我しないようにねー!」
「そろそろみんなの看護師さんの時間は終わりかな?」
「!!」
背中に聞こえた声にリクは驚いて振り返る。
「マコトさん!」
「迎えにきたよ。もう上がりだろう?一緒に帰ろう。今からは僕だけの癒しの君になってくれ。」
「ちょ、待ってください!すぐ着替えてきますから!」
人目を憚らず腰を抱いてくる丹波を制止しながら、リクは小走りに病棟へと戻っていく。
その横顔には、丹波以外誰も知らない癒しの笑顔で、満ち溢れていた。





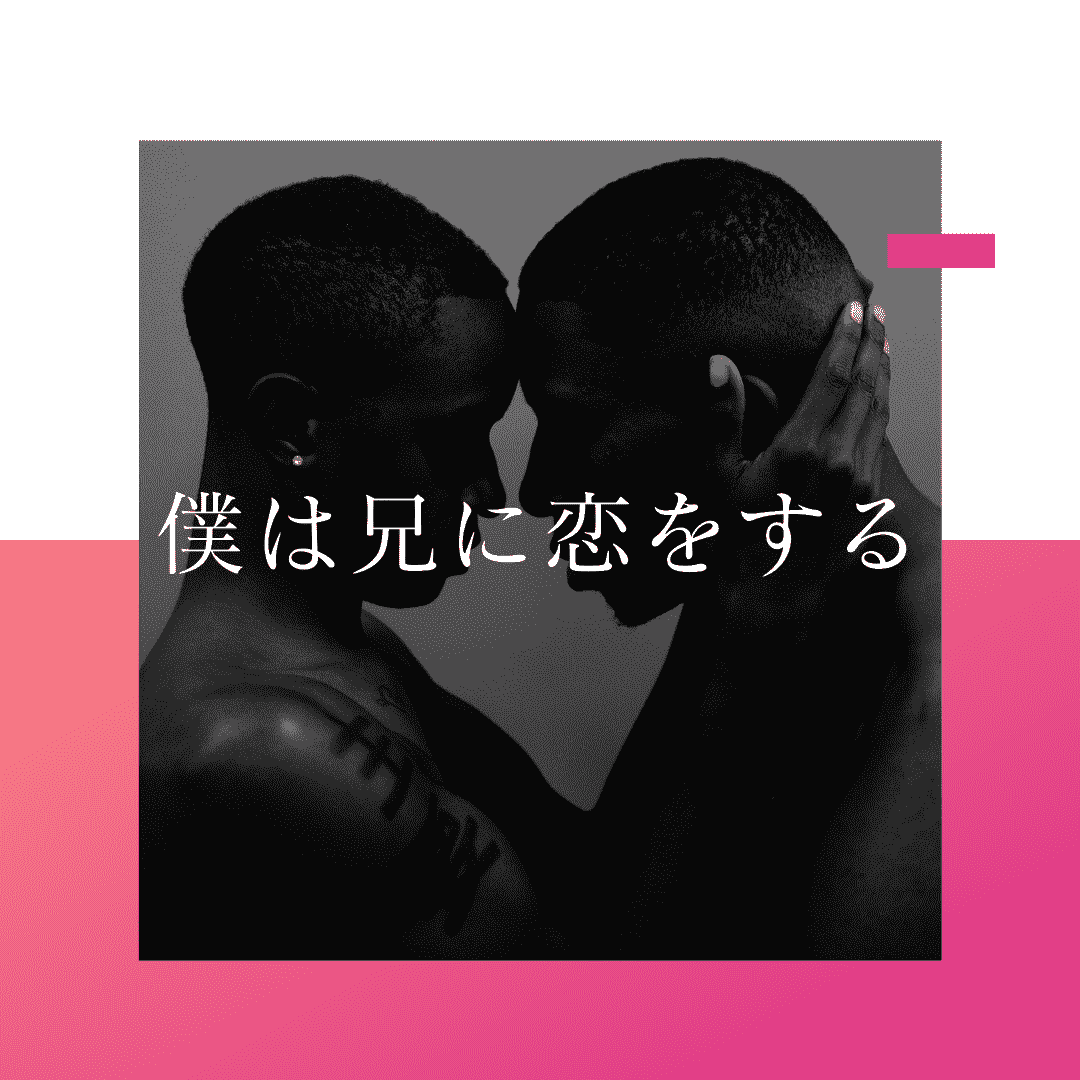



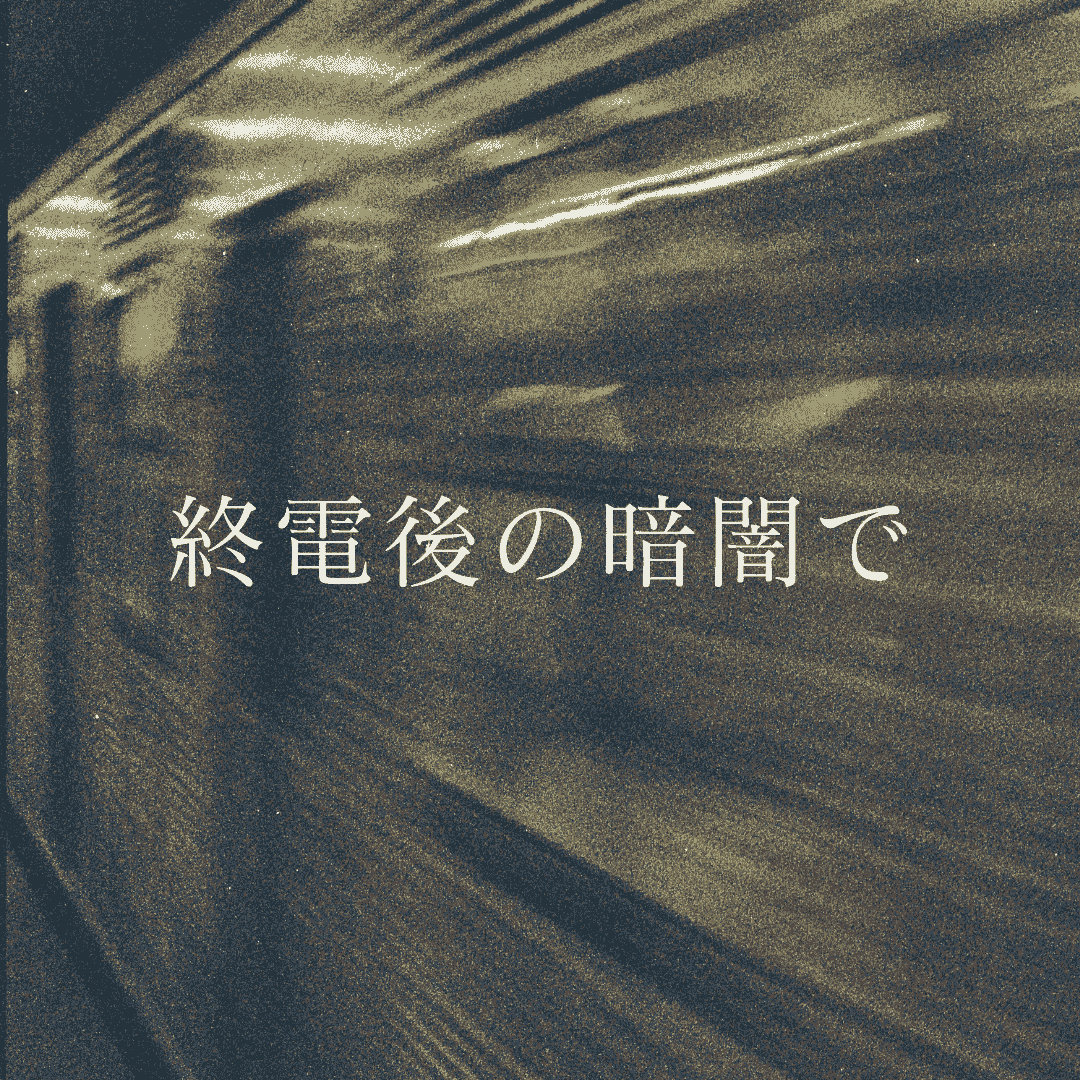
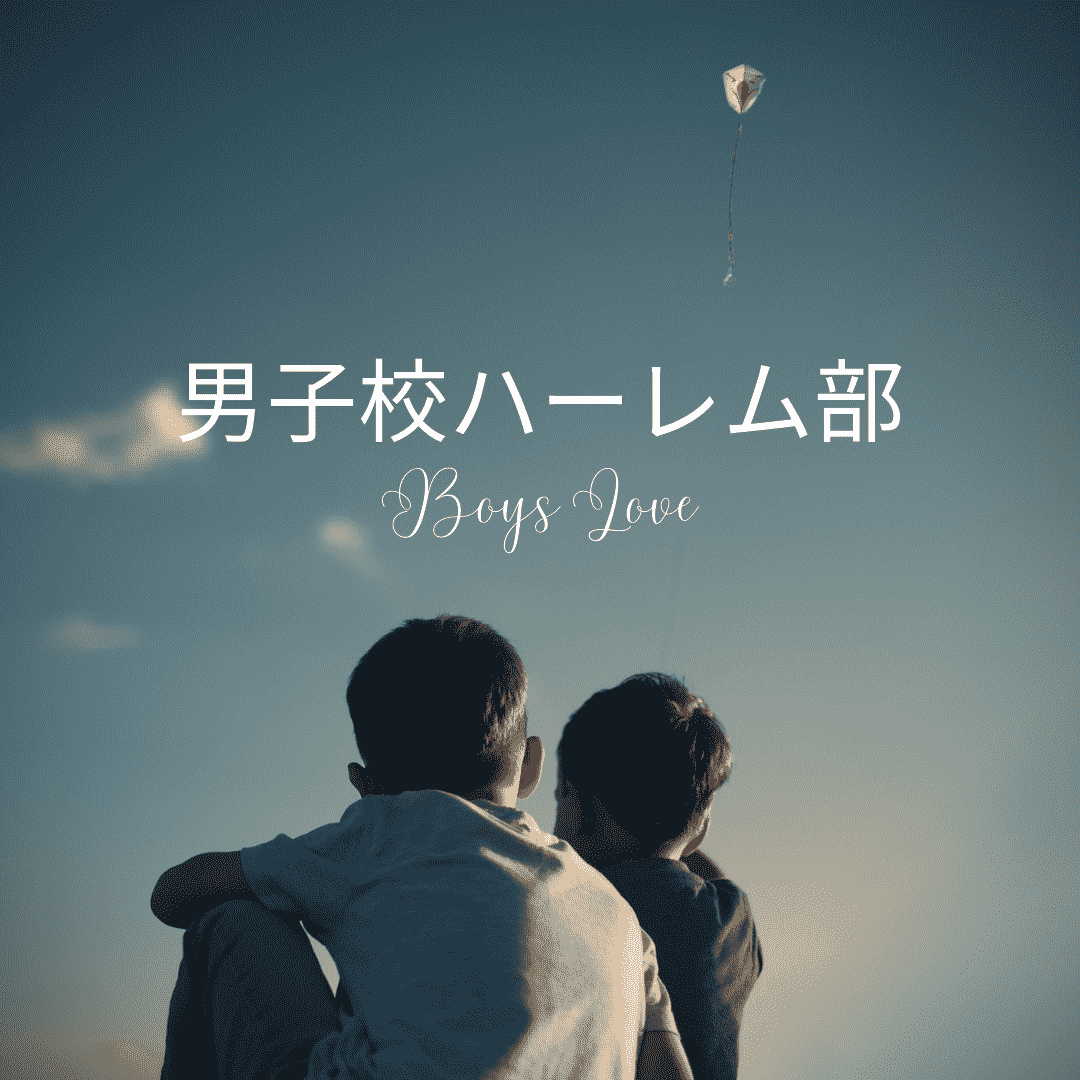
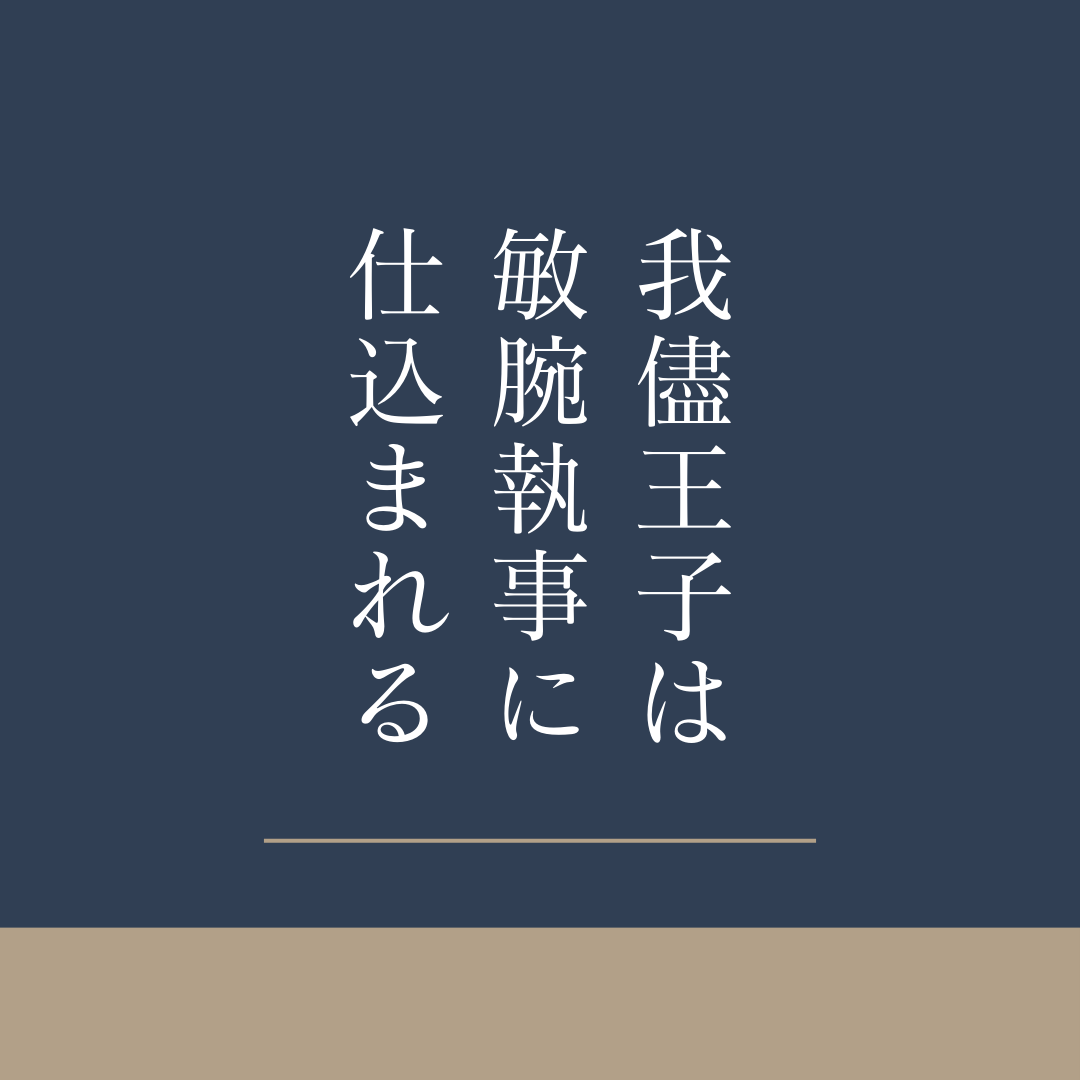

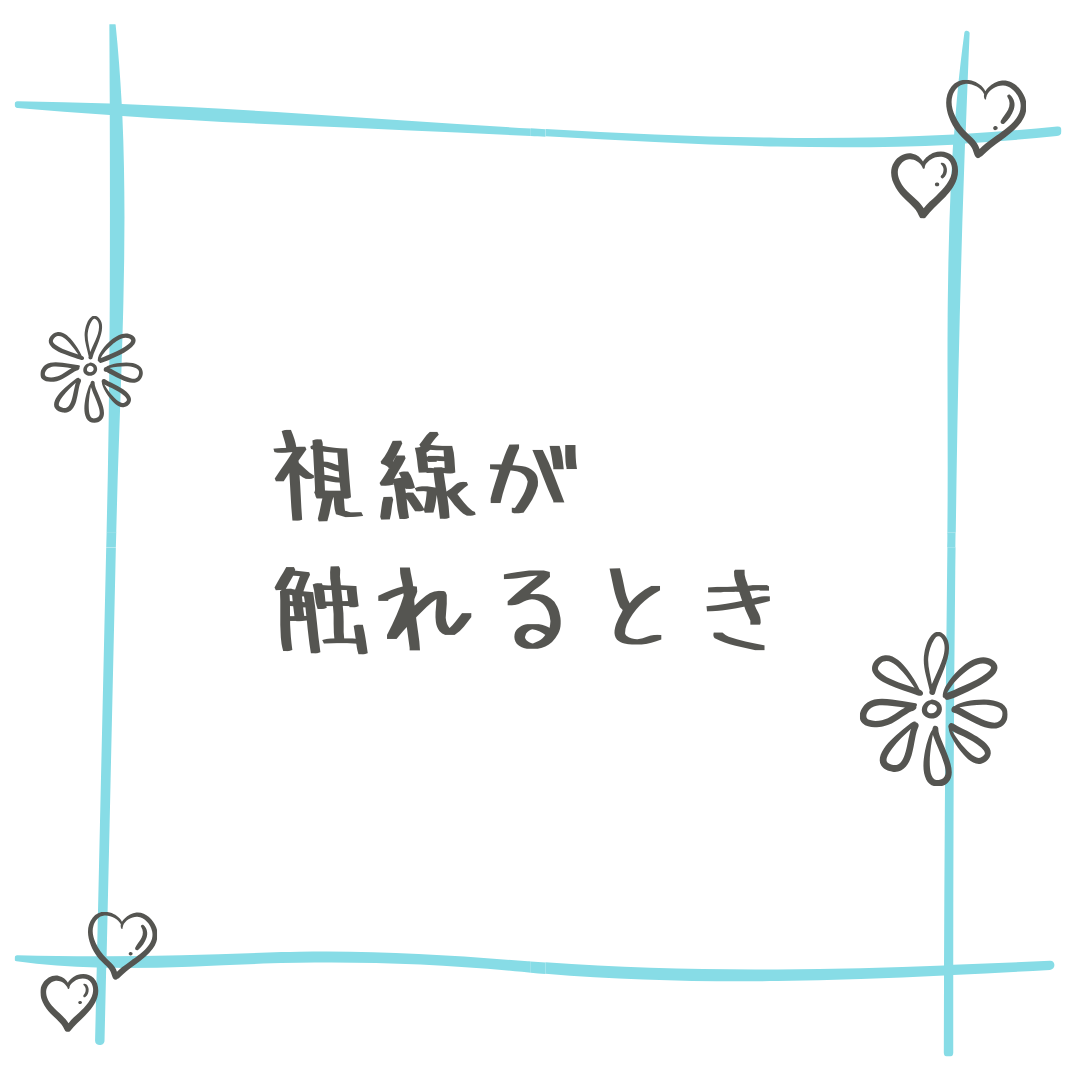



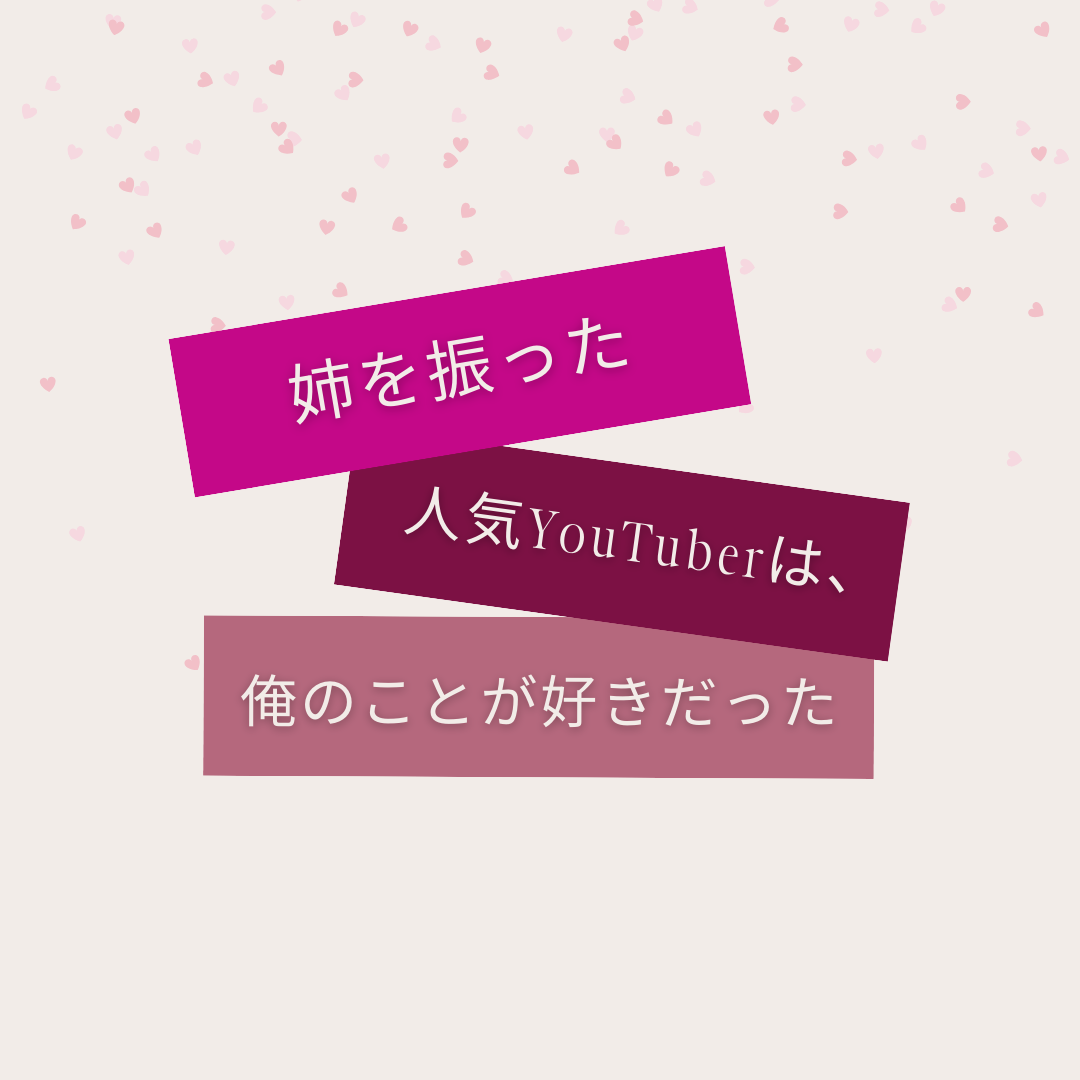








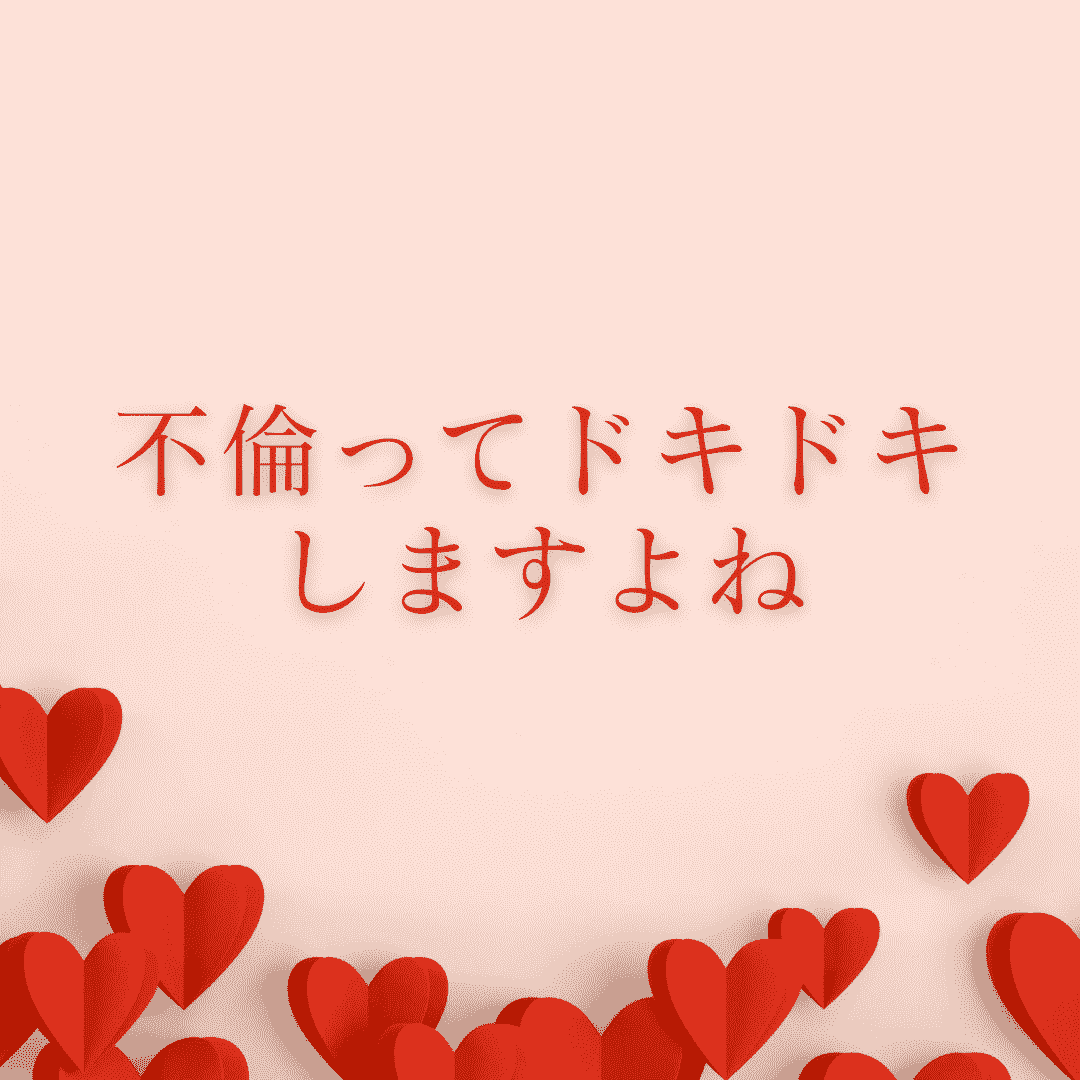




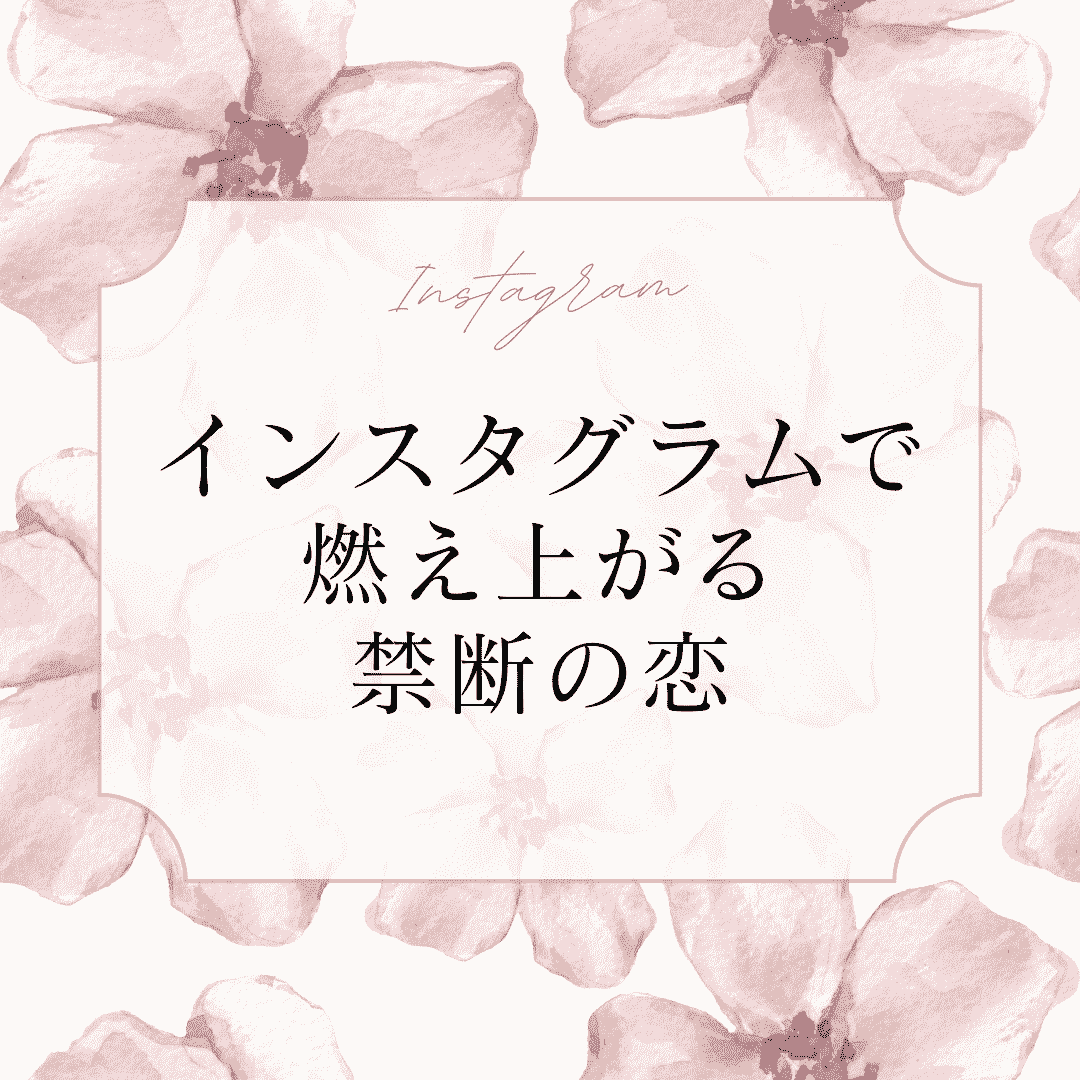






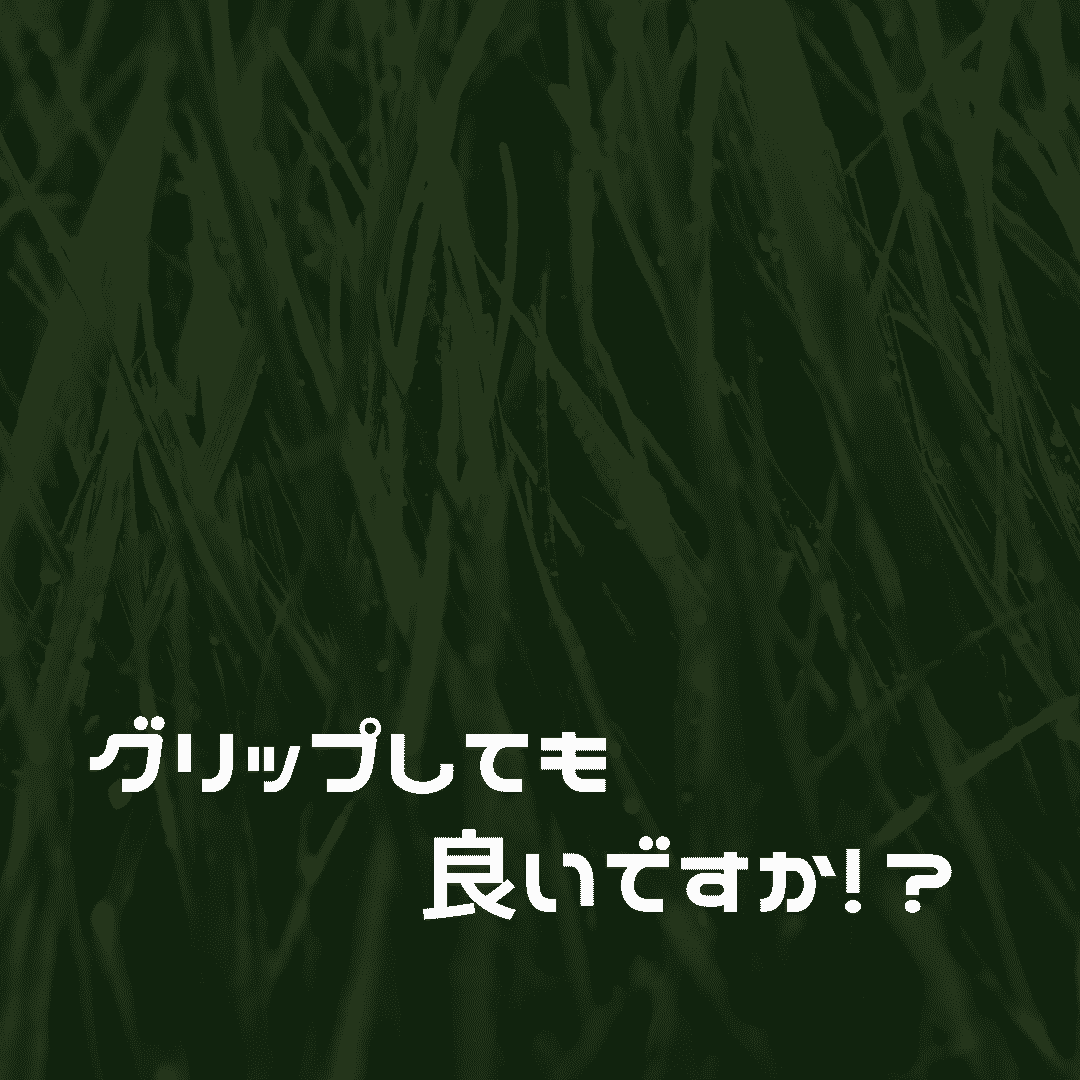

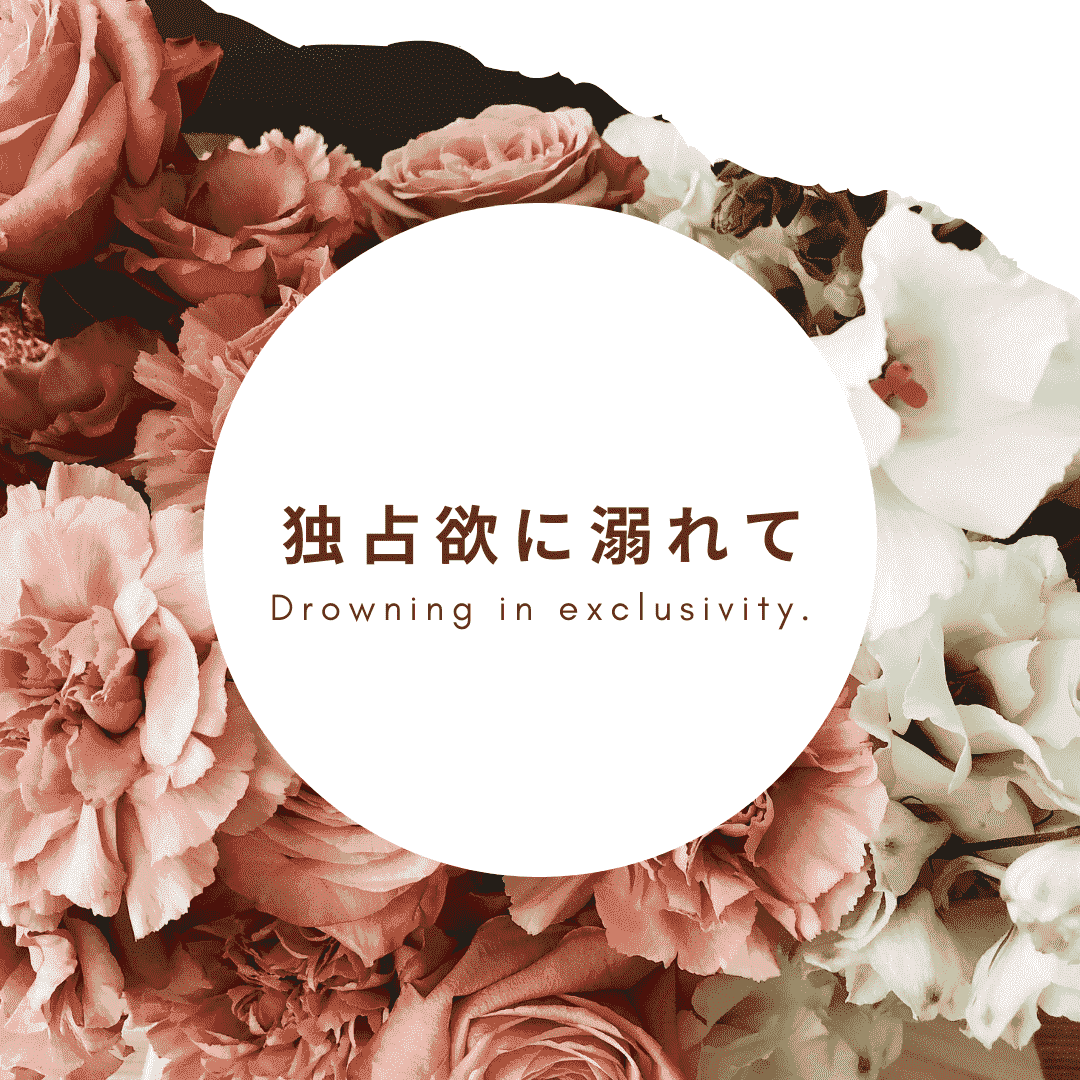
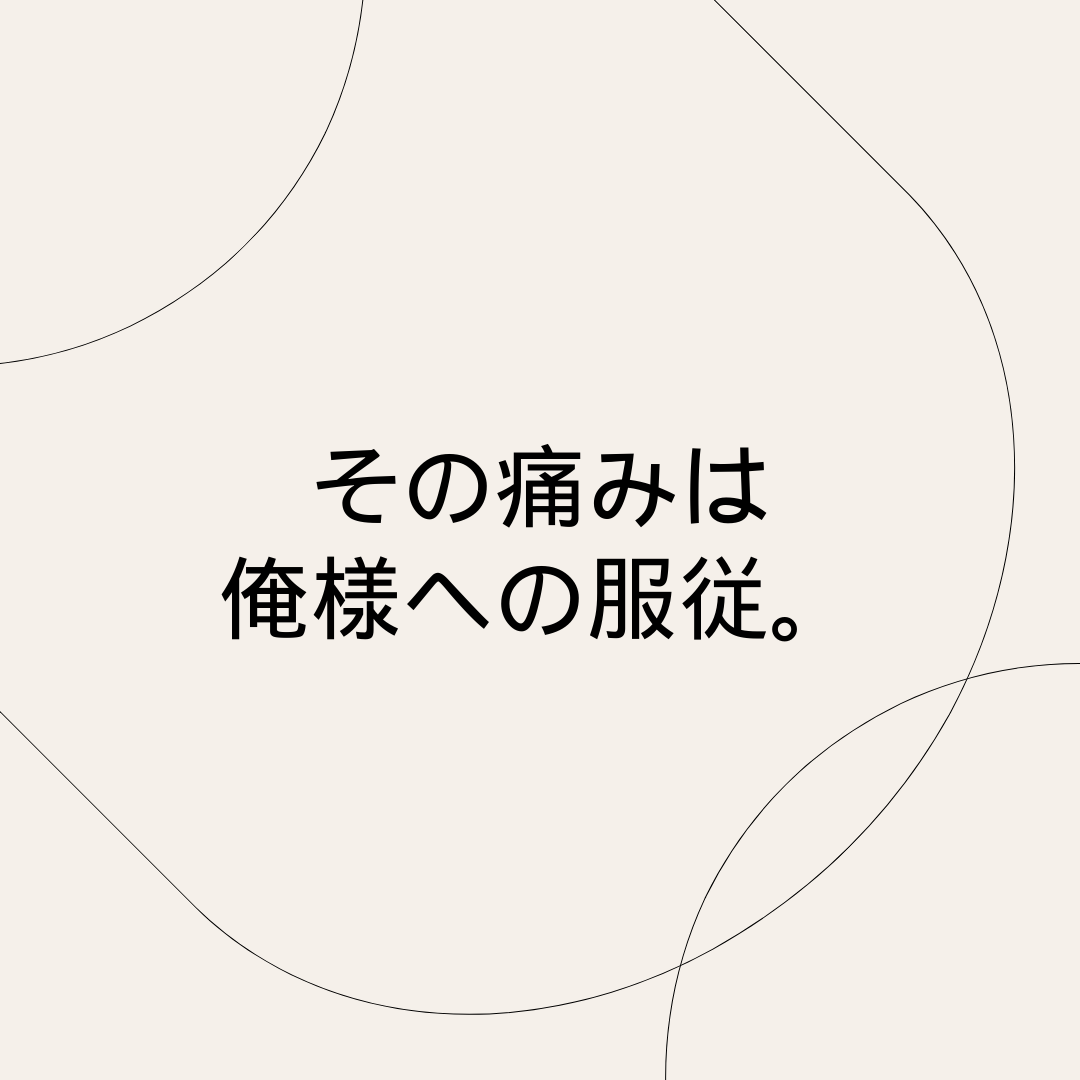
コメント