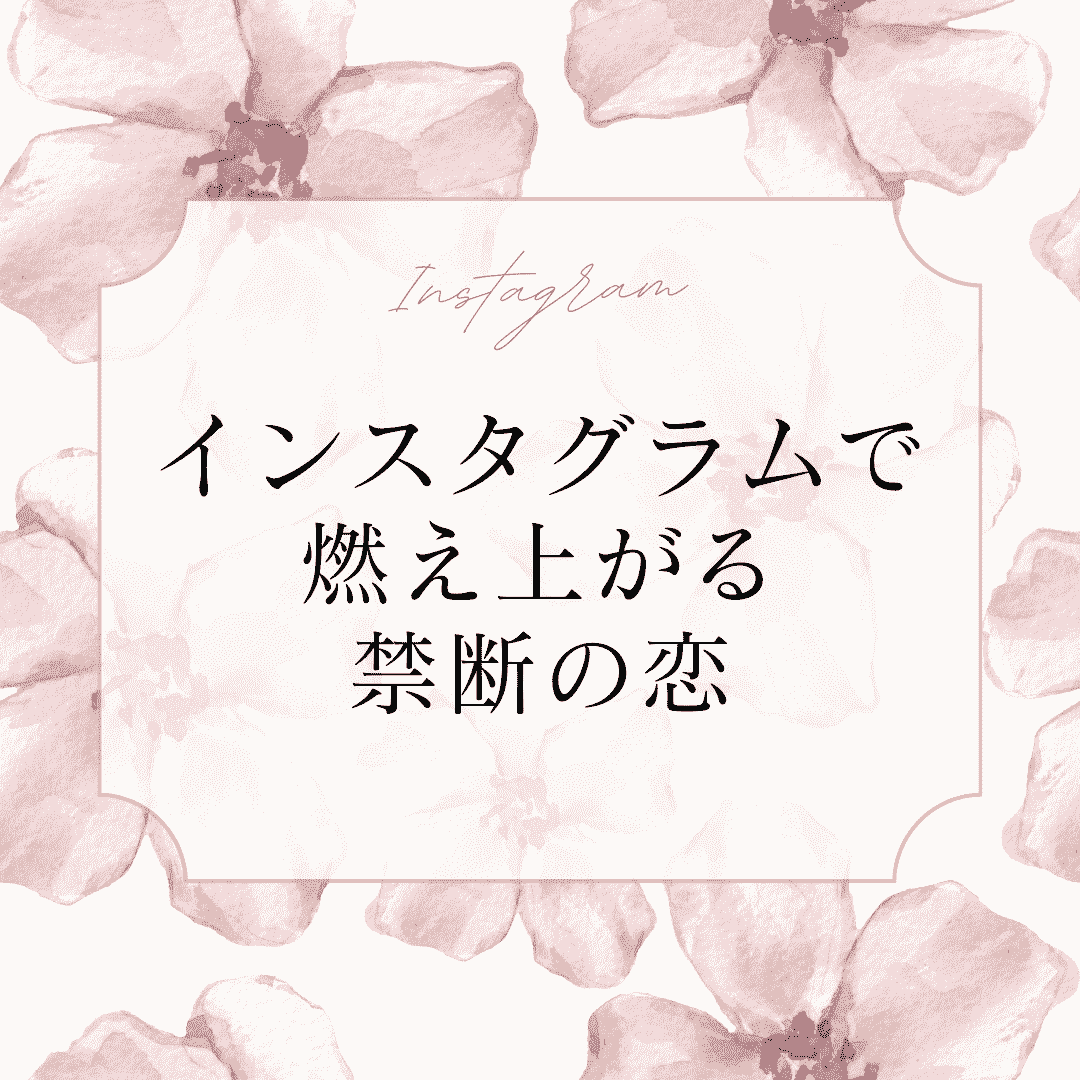
0
インスタグラムで燃え上がる禁断の恋
気になっている人がいる。
その人はインスタグラムに自撮りを載せている人で、私と同じ女性だ。
家族写真や、ホストクラブに通っている写真もたくさん載せている。
幸せな家庭とホスト狂いの様子が想像できなくて、不思議な気持ちにさせられる。
「イトウせんせーい!」
「ナカニシさん、おはようございます」
そんな彼女は私の働く保育園に子どもを通わせている、立派なお母さんだ。
「ほら、マーくんもおはようございますして!」
「おはよぉございましゅ。」
「マーくんおはよう!今日もよろしくね〜!」
「……」
「ナカニシさん?どうしました?」
「ふふ、ほんとイトウ先生は子どもが好きなんだなぁって……」
あなたは夜明けまでホストと遊んでましたよね? なんて聞けるわけがない。
その一言を言ってしまったら、すべてが終わるような気がして。必死に我慢をして子どもたちの相手をすることに専念しようとする。
没頭したらそんな雑念はどこかにいって、子どもたちの世話に集中できる。
自分の持ち合わせている集中力に感謝しつつ、他の子たちや彼女から預かっているマーくんの面倒をみて、日々の業務に追われていたらすっかり夜遅くなってしまう。
こうやって私の一日は終わっていくんだ…としみじみしていると、今日はやけにマーくんのお迎えが遅いことに気がついた。
「マーくん、ママまだこないね。」
「うん……」
マーくんは物静かで、普段からあまり自己主張はしない子だけれど、今日は違った。
「ママ、たぶんおにいさんたちに会いにいってるのかも。」
「えっ?」
この子は親がホストクラブに通っていることを知っているのか?
「せんせいみたいな人がママだったらよかったのに。」
「マーくん……ママはお家のお仕事が忙しいのかもよ?」
「ちがうよ、ママ、ずっと夜はいないんだもん。」
切なげに語るマーくんは、嘘をついているようには見えなかった。
だからこそ業務の一環として、マーくんの母親であるナカニシさんに聞き正さないといけないと思った。
「おまたせしました…」
「マーくん、パパが来たよ。」
「……」
ナカニシさんではなく、ナカニシさんの夫が来てしまった。
しかし、業務の一環として、聞くべきことは聞かないといけない。
「あの、ナカニシさん……」
「ああ知ってます、ナツミのことだろう……すみません、迷惑をかけて……」
「いえ、その……私どもは平気なのですが、マーくんが心配で……」
なにより優先すべきなのは子どもの心のケア、それを心配して声をかけると的外れな返事が返ってきた。
「ナツミはああ見えて不誠実な女なんだ……君ならわかるだろう?」
「ちょっ、やめてください……!」
「パパ?」
「ああ、マサトごめんよ……先生、この後空いてますよね?」
「……私生活のことは答えかねます。」
「せんせい?」
「……空いてますが。」
「なら家に来てくださいよ、歓迎しますよ……マサト、いいだろう?先生が家に来てくれるぞ」
「うん!」
半ば強制的に、自宅訪問が決まってしまった。
その後残りの業務を終わらせて、他の先生たちに挨拶をしてから園を出ると、ナカニシさんが門の前で待っていた。
「待ってたよ、イトウ先生。」
「は、はい……」
「マサトは家で寝てるよ、ほら早く行こうか。」
肩を抱かれたまま車に乗せられて、不信感を募らせながら、そのままナカニシさんの家に向かう。しんと静まり返った小さなアパートに到着したが、マーくんは家にはいなかった。
「あの、マーくんは……」
「実家に預けてる、ここは私の事務所代わりに使わせてもらってるアパートだよ。」
「……帰ります。」
「帰るのかい?業務時間外に既婚者の家にホイホイついてきた先生が?」
「……私は、ただ……」
にやりと笑ったナカニシさんの夫は、私を玄関の床に押し倒すと、ぐりっと勃起したモノを太ももに押し付けてきた。
「ひ、っ……!!」
「イイんだろ?素直になった方がお互いのためだぞ。」
どうしてこんなことになったのか困惑していると、ナカニシさんの夫は「インスタグラム」と言ってきた。
「君は妻のインスタグラムをフォローしているよね?……私のもフォローして連絡を取り合おう。」
「い、嫌です!離してください!」
「子どもの容態変化とかのやり合いついでに、セックスのお願いをするだけだよ、悪いことではないだろ?」
「悪いことです!」
「……分かってるんだぞ、君……イトウさん最近シてないから性欲が溜まっているだろ。」
「……っ」
確かにここ最近は業務に追われていて、そういったこととはご無沙汰ではあるけど…。なんでそんなことを把握されているんだ?!
「イトウさんのインスタグラムはフォローしているからね、業務の忙しさからムラムラしてることまで丸わかりだよ。」
……これは過去一番ぞっとした出来事かもしれない。
まさか軽い気持ちで投稿したものを見られて、こうやって現実で窮地に追いやられるとは思いもしなかった。
「妻はホストクラブ通い、夫はそのしわ寄せで仕事漬け……マサトが可哀想だから実家に連れ帰っているけど、人恋しい夜もあるんだよ。」
だからといって、身近な保育士に手を出すのはどうかと思う。
抵抗しようにも力ではかなわず、されるがままに受け入れることしかできなかった。
悔しいがこれが現実だ……女の私には、男の力に勝つことができなかった。
そのままパンティを脱がされて、気持ちとは裏腹に肉欲的な期待でぐじゅぐじゅと濡れた割れ目をなぞられ、糸を引いている様子を見せつけられる。
その濡れた秘部を割り開くように、指で広げられてとろりと垂れる母蜜の様子を口頭で告げられた。
「どれだけ期待してるんだ。」
意地悪のような言葉にも必死に耐える。
……これが終わったら、開放されると信じて。
「……ふぅ。」
ナカニシさんの夫の、がちがちに勃起した男のモノを出され、あまりの大きさに驚いてしまった。
「ナツミ……妻は大きすぎて痛いと言うから、マサトを授かれたのは奇跡だ。」
そう言うナカニシさんの夫はコンドームを器用に付けて割れ目を往復するようになぞり、じれったさから手で上下に揺れるそれを掴んで膣口まで導くと、笑ってずぷん! と一気に最奥まで貫いてきた。
「かひゅっ……!」
「ああ、イイ……」
再生した処女膜を突き破るような痛みとともに、熱がダイレクトに当たって、じんわりとお腹の中が熱くなる。
そこからは、遠慮のない抽挿を繰り返されて、口からは母音しか出てこない…。
「あ、ぁ、あぅ、あ〜……!!」
「は、っく……いい締め付け具合、だっ……!」
ぐちゅん、ぐちゅんと膣内をかき回す水音が恥ずかしくて、必死に冷静になろうとしてみたけれど、無理だった。
漏れる声に悲しいくらい気持ちいいのに抗えない自分の弱さが悔しくて、気持ちよくて頭がばかになりそうだ。
「っあぁあっ!ぅう……!!」
どくんどくんとコンドーム越しに、ナカニシさんの夫が精液を吐き出したのがわかる。
その勢いから結構な量を出していて、溜まっていたのもわかってしまって、胸がきゅうきゅうと疼く。
「あの。」
「……なにかな?」
「…………もう一回、シませんか?」
**
軽快な通知の音と共に、じゅわりとパンティが湿るのがわかる。
あれから数回、ナカニシさんの夫とは連絡を取り合っていて、その都度セックスをしていた。
だから、通知の音だけで反射的にパンティを湿らせてしまうような淫乱が誕生してしまったのだ。
約束の時間にナカニシさんの夫と合流して、いつも通りアパートに連れていかれるまでは一連の流れだった。唯一違ったことと言えば、ナカニシさんがアパートの部屋の中にいたことだろうか。
「ナカニシさん……!?」
「イトウ先生、来てたんですね。」
冷や汗が止まらない、だって、私とナカニシさんの夫は……。
「全部最初から知ってましたよ、イトウ先生が彼に何回も抱かれて、パンティをこんなに濡らしたメスの顔をするようになるまで……」
ナカニシさんは、すべてを知っていた。
知った上で、こんなお遊びみたいなものを許してくれていたんだ。
「勘違いしないで、私……先生のその顔が見たくて許してたんだから。」
イトウ先生のメスの顔を、うちの子にも見せてあげたいなぁ、なんてとんでもないことを言い出した時には、汗がぶわっと吹き出して、それだけはやめてくださいと土下座をして懇願した。
それでもにっこりと笑ったナカニシさんはスマートフォンから手を離さず、ナカニシさんの夫はいそいそと私の服を脱がせようとしてくる。
「ほら、イトウ先生の女の顔を撮らせてもらうから……早く脱がせて。」
「わかってるよ、ちょっと待ってくれ。」
「や、めてください……!!」
「人の男に手を出したイトウ先生に拒否権はありませんよ?」
なにが「人の男に手を出した」だ、あんな状況で始まった関係に、下心もなにもないはずだ。
**
「ぅ、ん……!」
「ああすごい、ずっぽり入ってる……身体の相性はいいのね。」
「っああ、イイ具合だ。」
「ふ、ぐぅぅっ……!!」
ぐちゅぐちゅと内側をいつも通りかき回されて、声が漏れてしまう。
声を漏らしてしまうと、ナカニシさんにからかわれてしまう…。頑張って我慢しようとするが、ナカニシさんの夫の責めが強くなるから、結果的に声が出てしまうのだ。
スマートフォンのカメラレンズを、こっちに向かって手を振ってくるナカニシさんには、全く悪気がなさそうで、余計に辛くなる。
「いい顔してるわよ!。もっとこっちに視線ちょうだい!」
無邪気なナカニシさんのハメ撮りレターは私のスマートフォンにも送られてきていて、逃げ場はないと実感した。
……軽快な通知音が聞こえてきて、冷や汗とパンティの湿り気が気になる。
あれから何度か、ナカニシさんとナカニシさんの夫と、インスタグラムのダイレクトメッセージでやりとりをしている。
最初は怯えていたのに、今ではすっかり撮影会にハマってしまっていて、いけないことだとわかっているのに拒否できない自分がいた。
「あ、イトウ先生〜!」
……だって、私はナカニシさんのことが大好きだから。





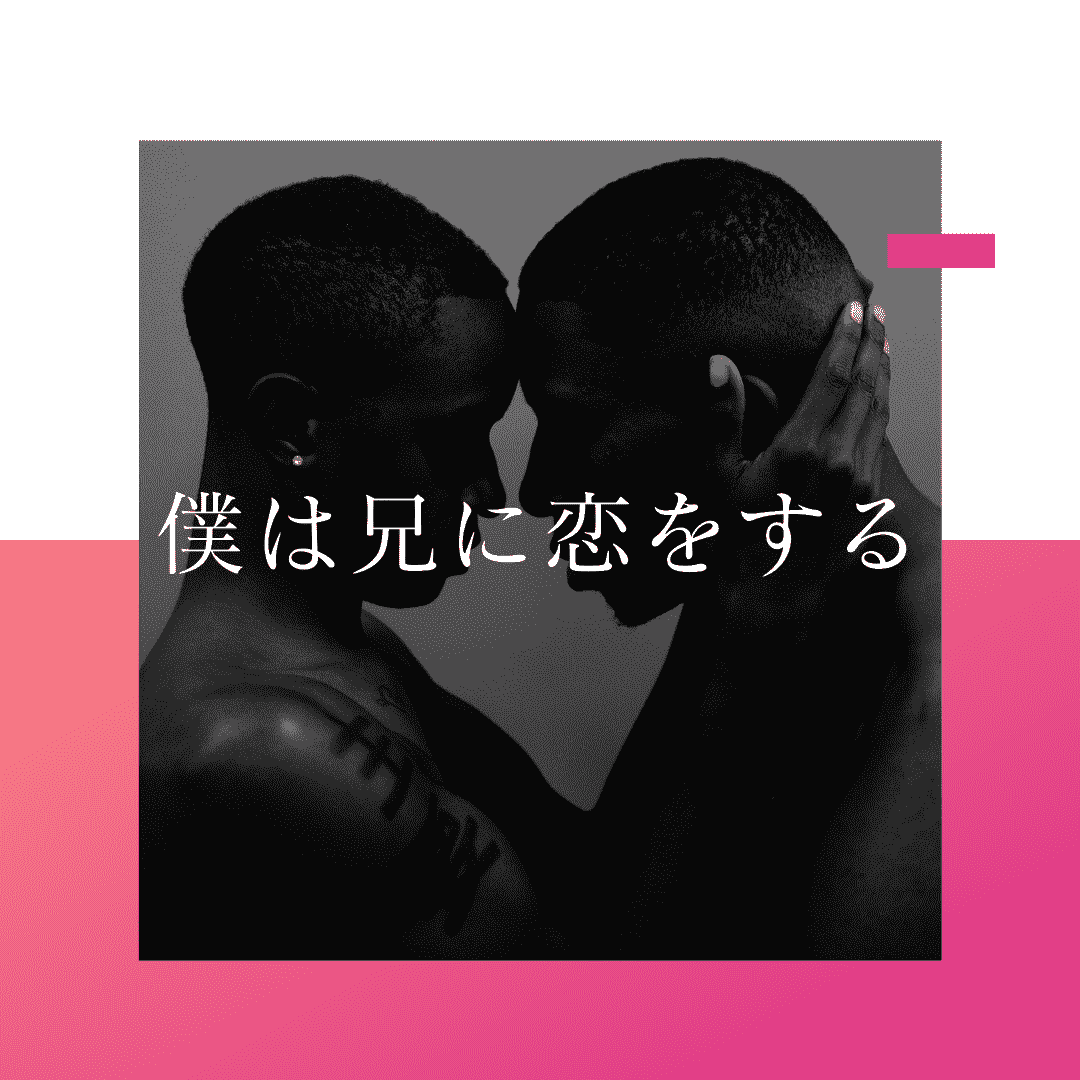



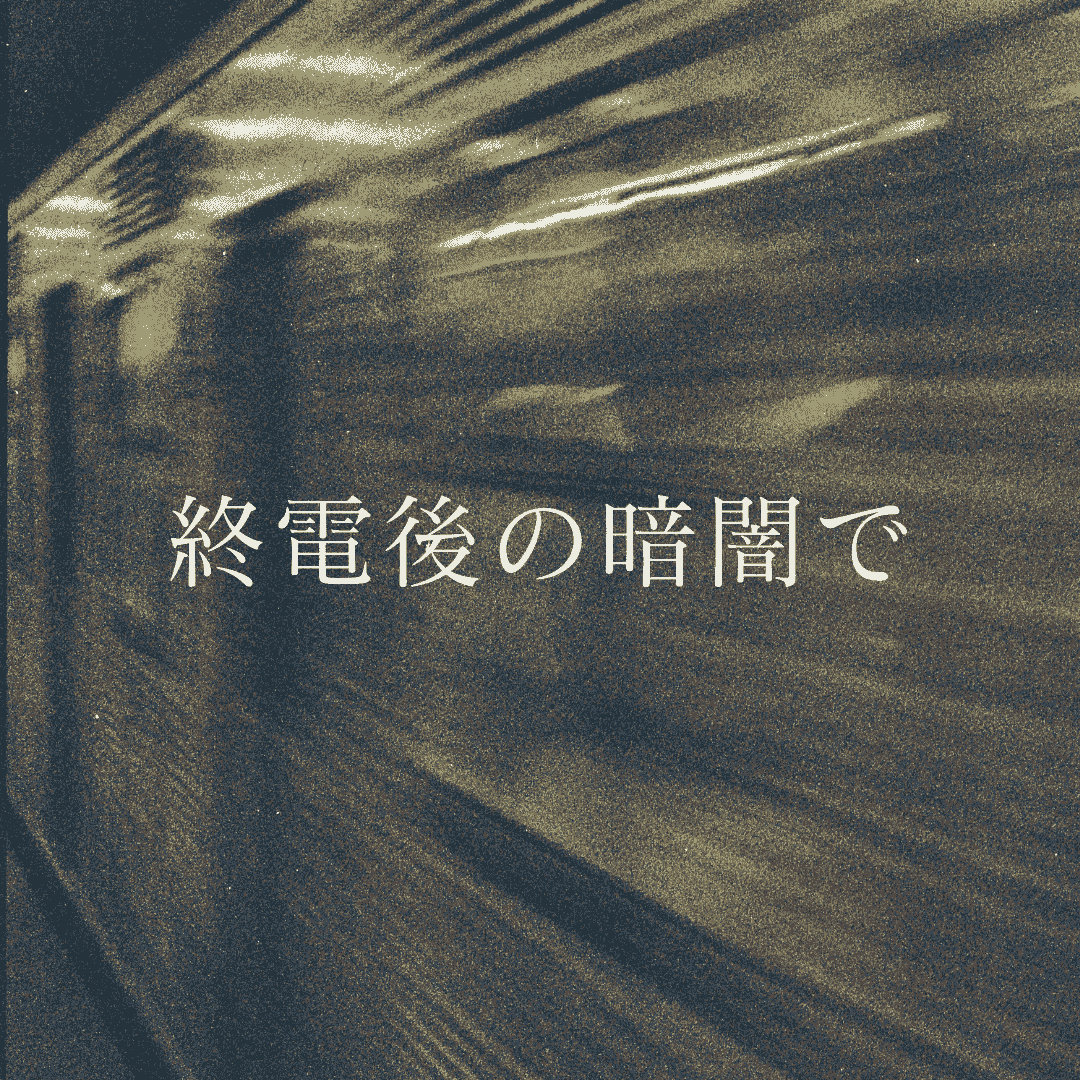
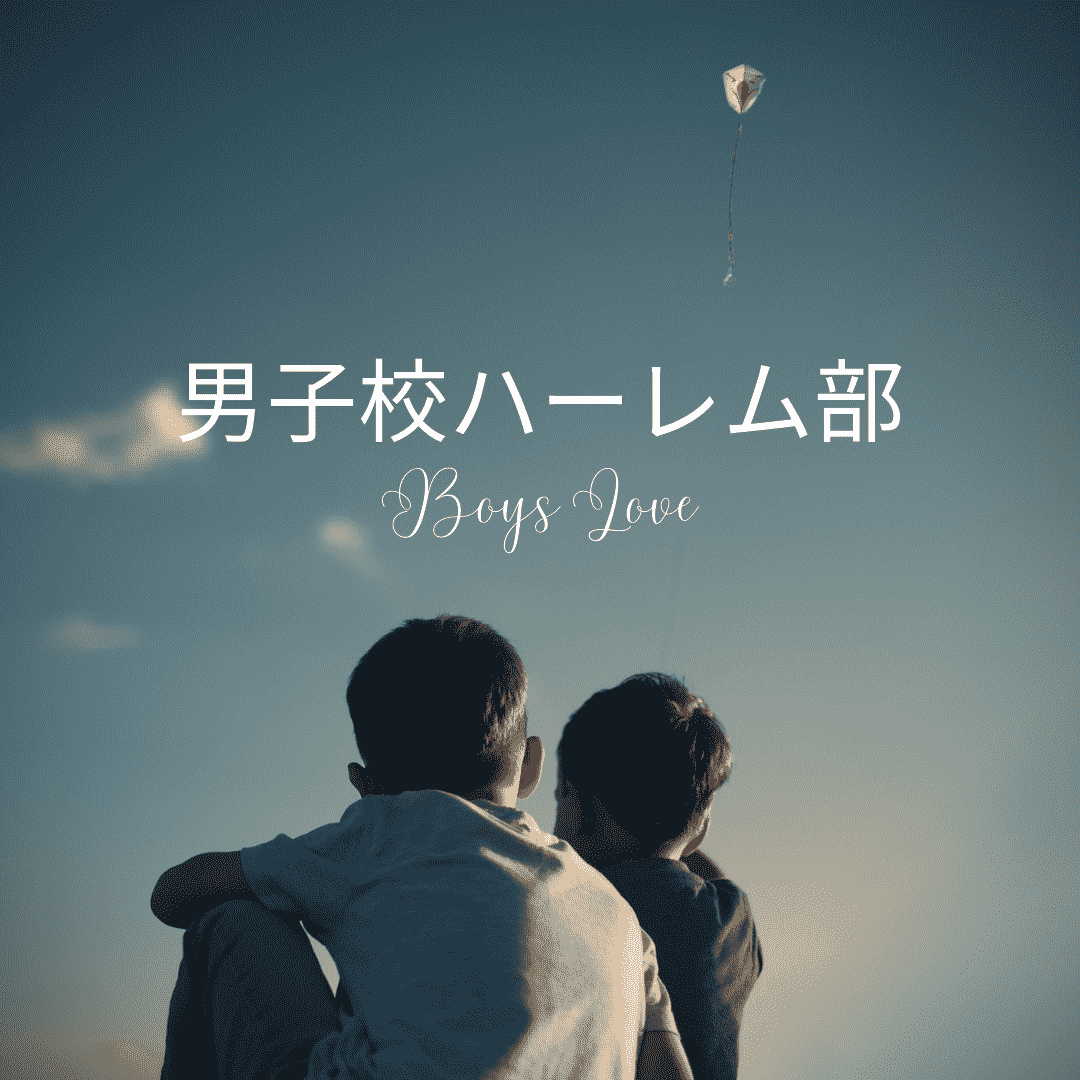
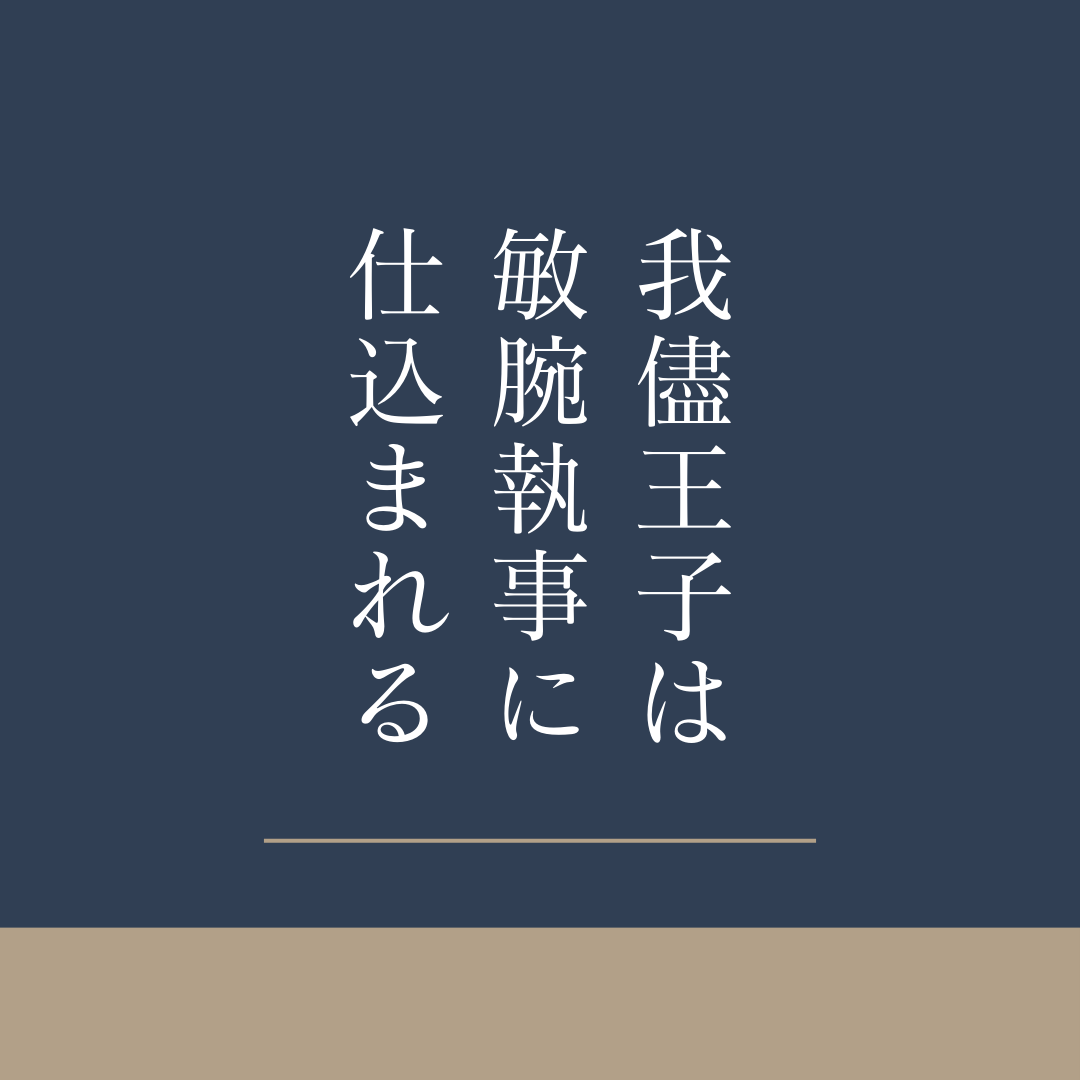

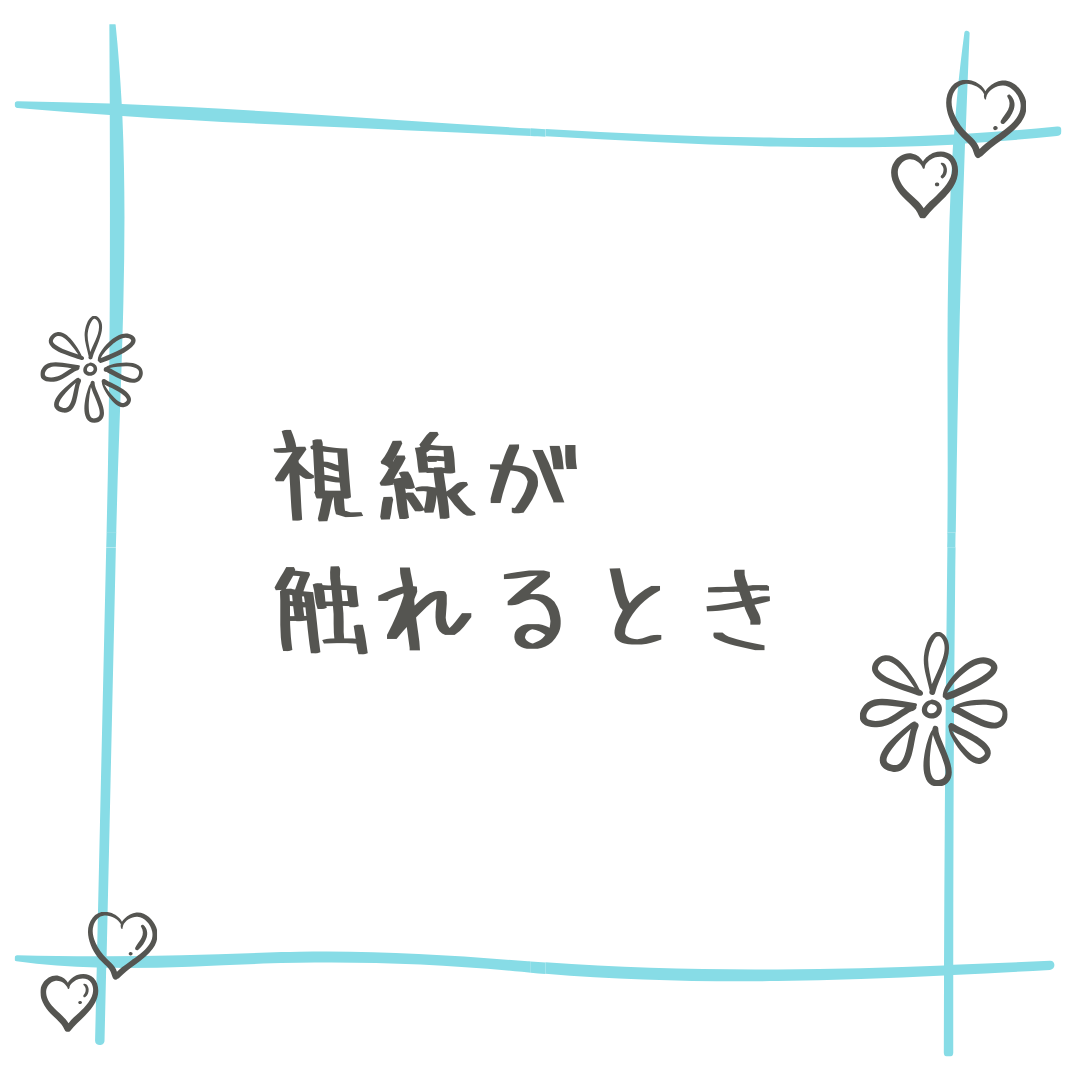



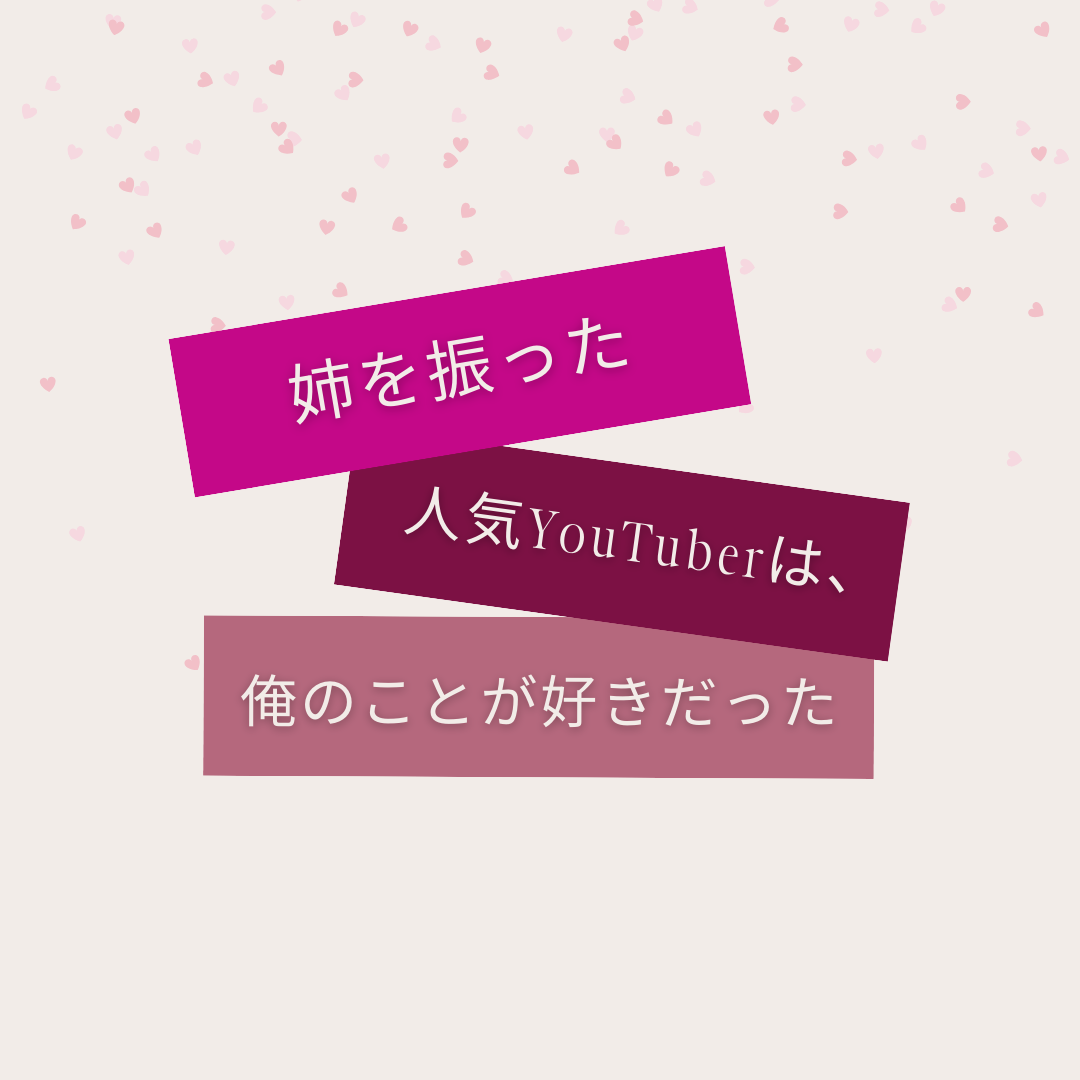









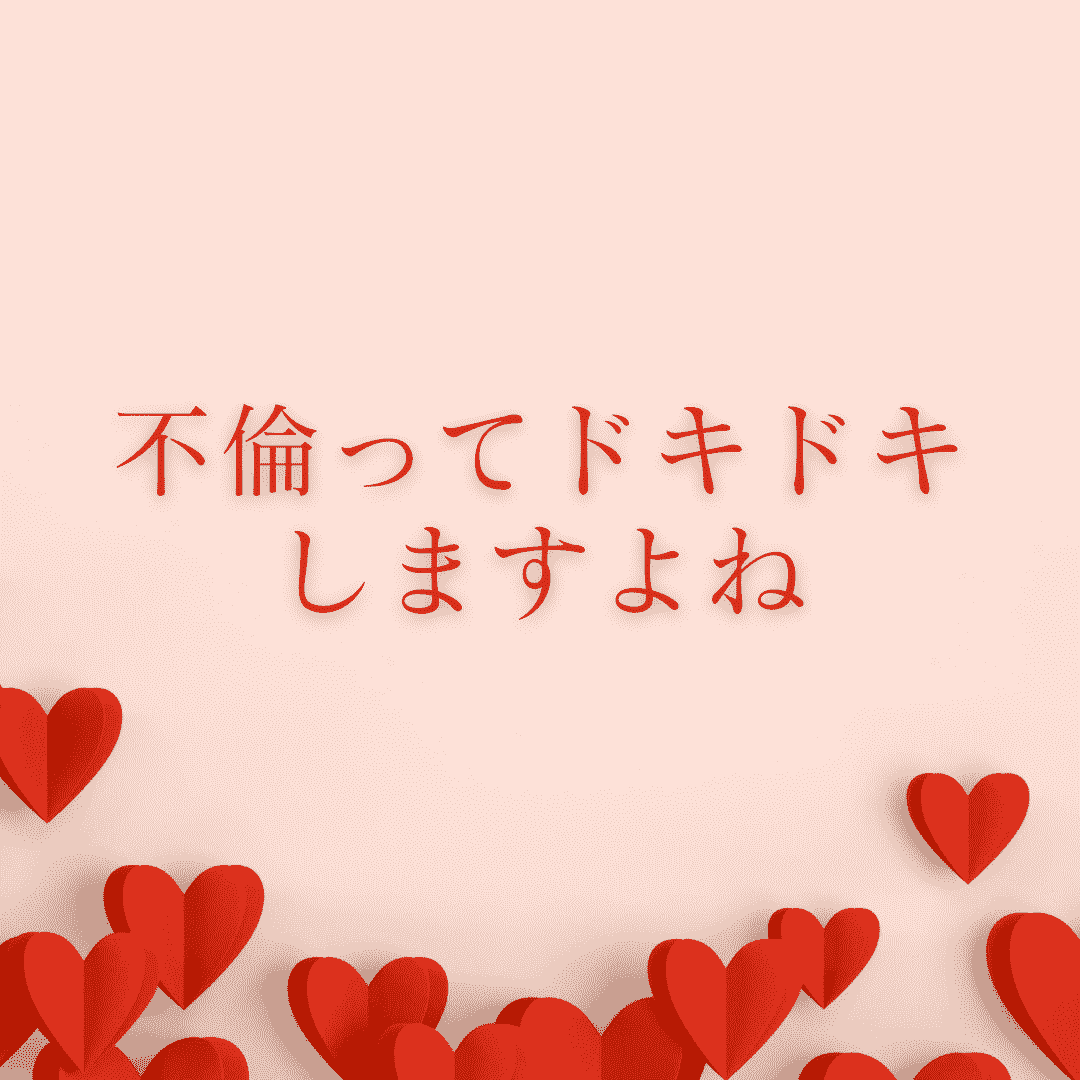




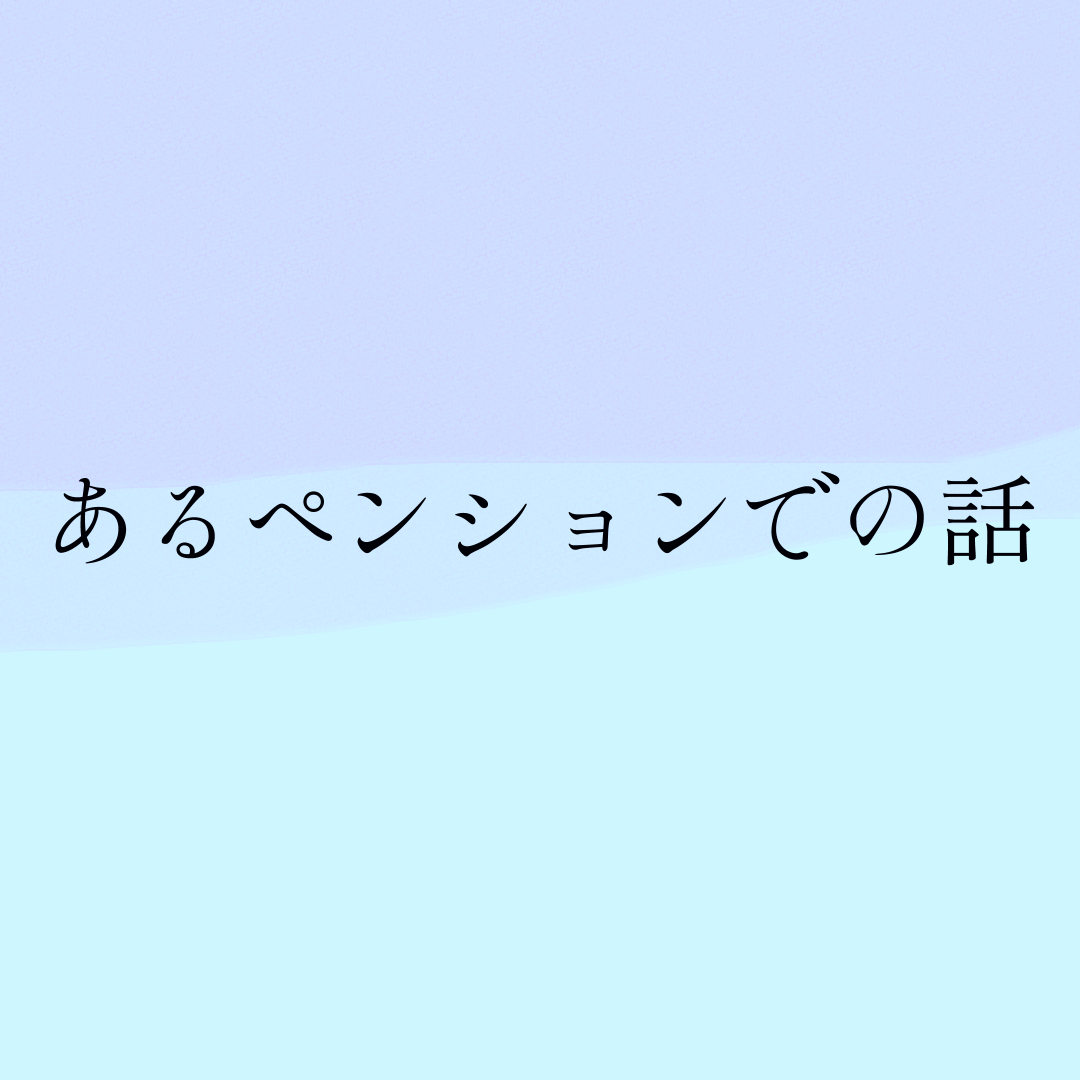
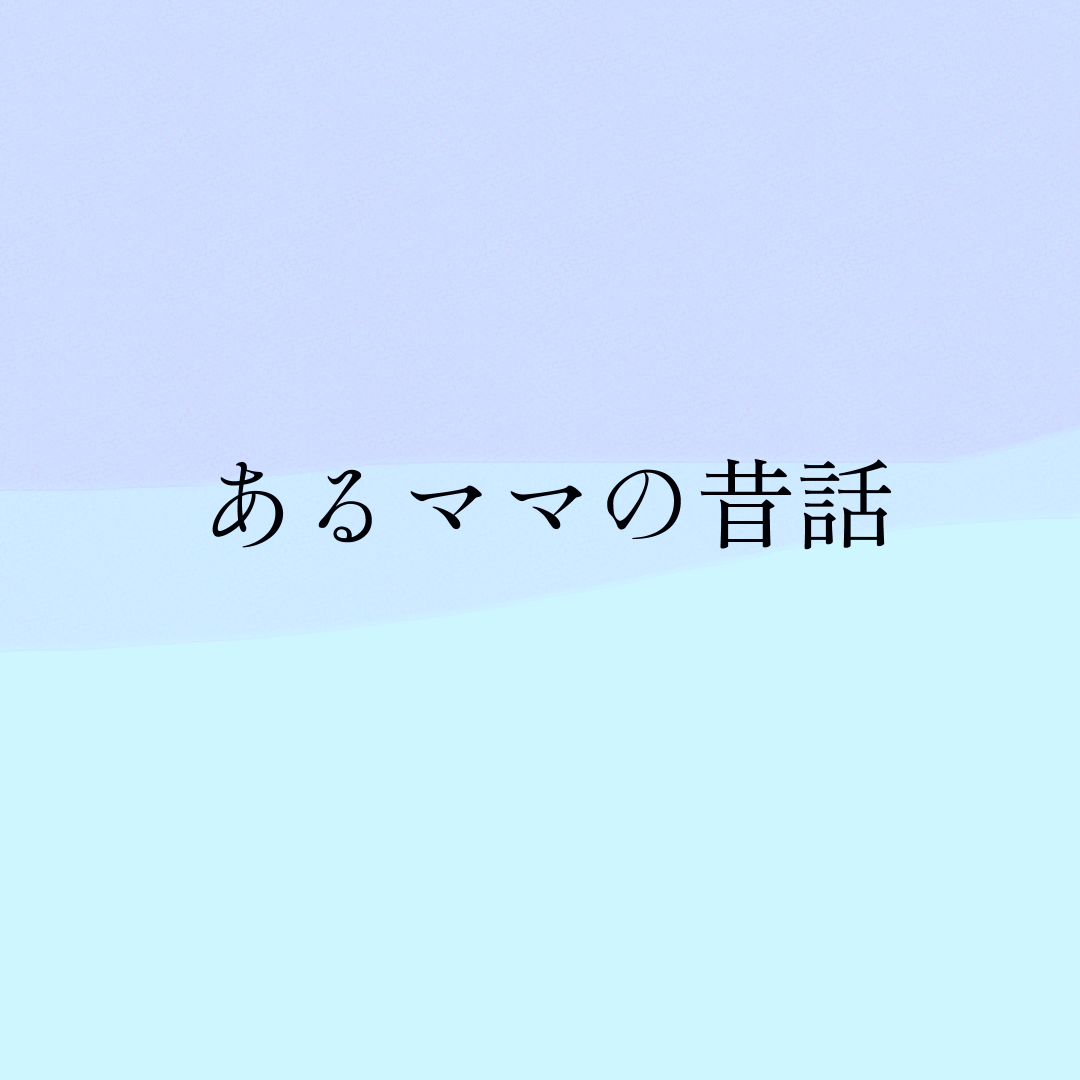
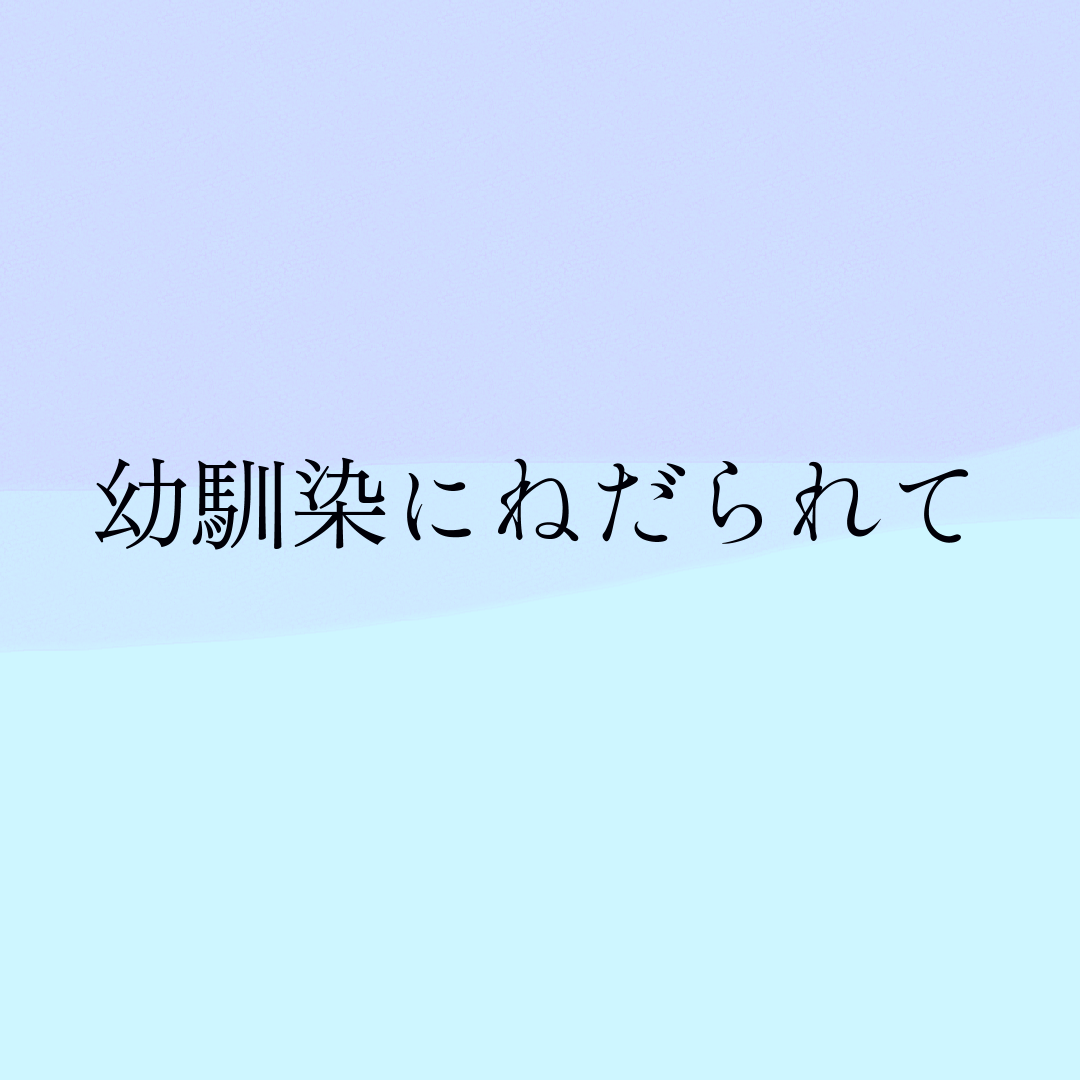
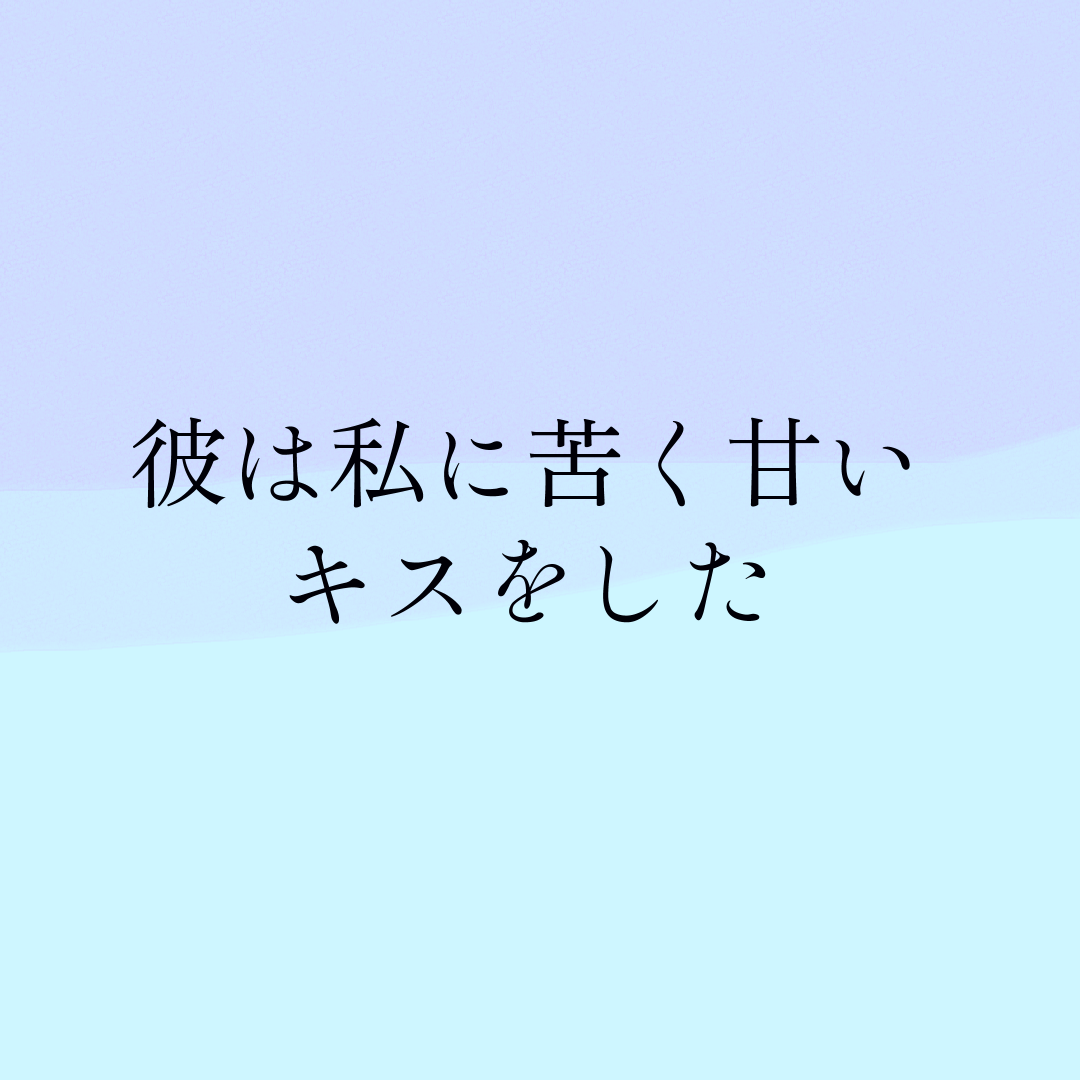
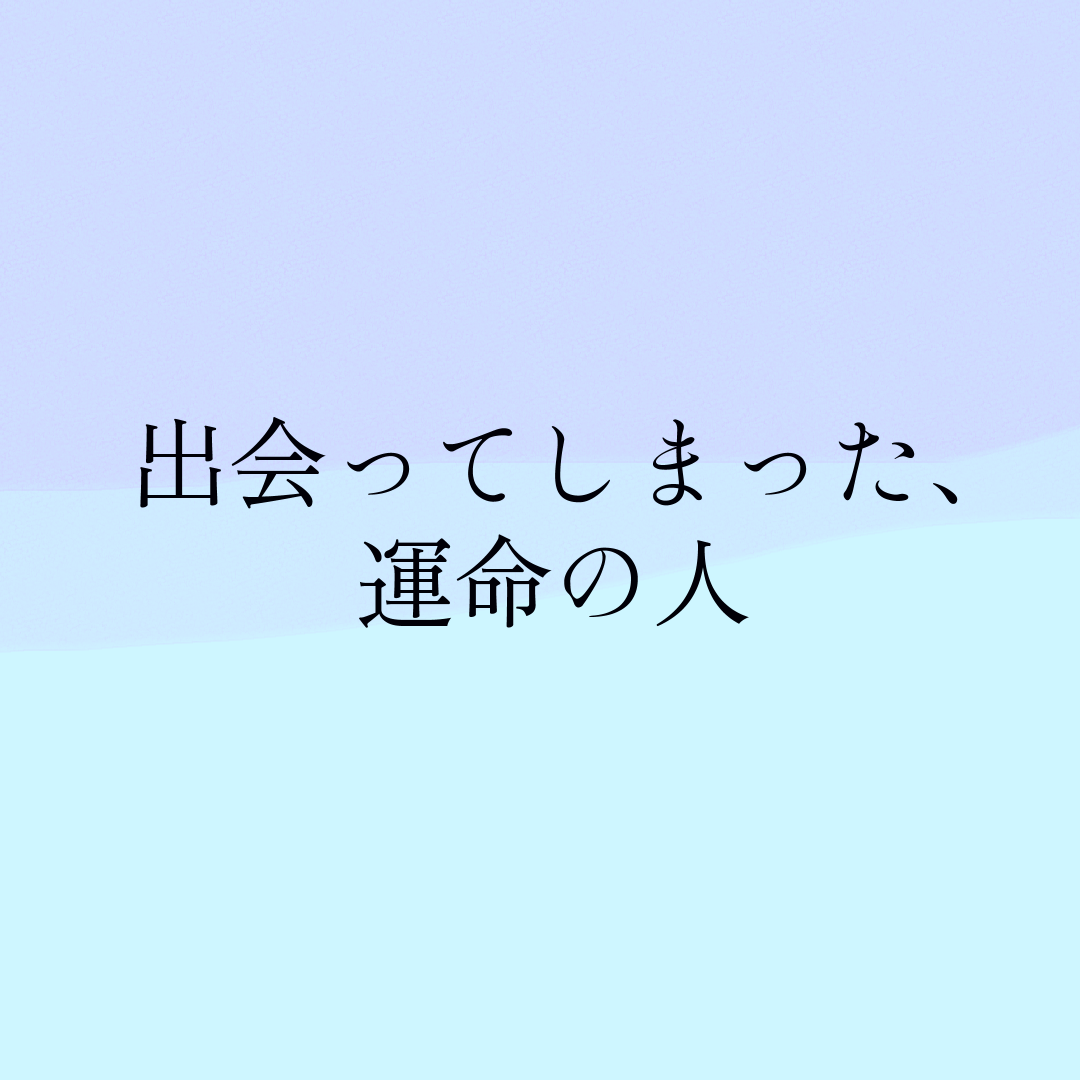
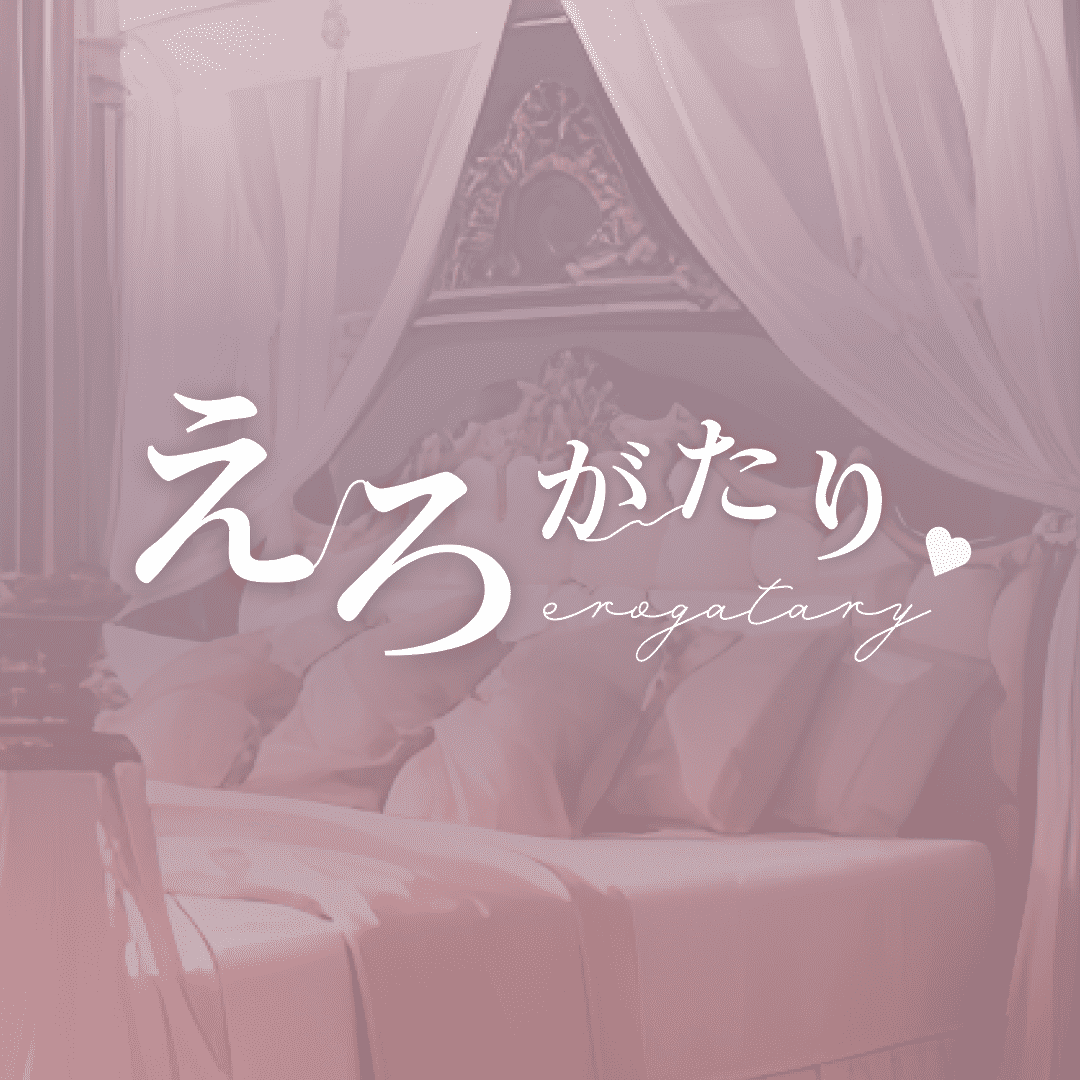
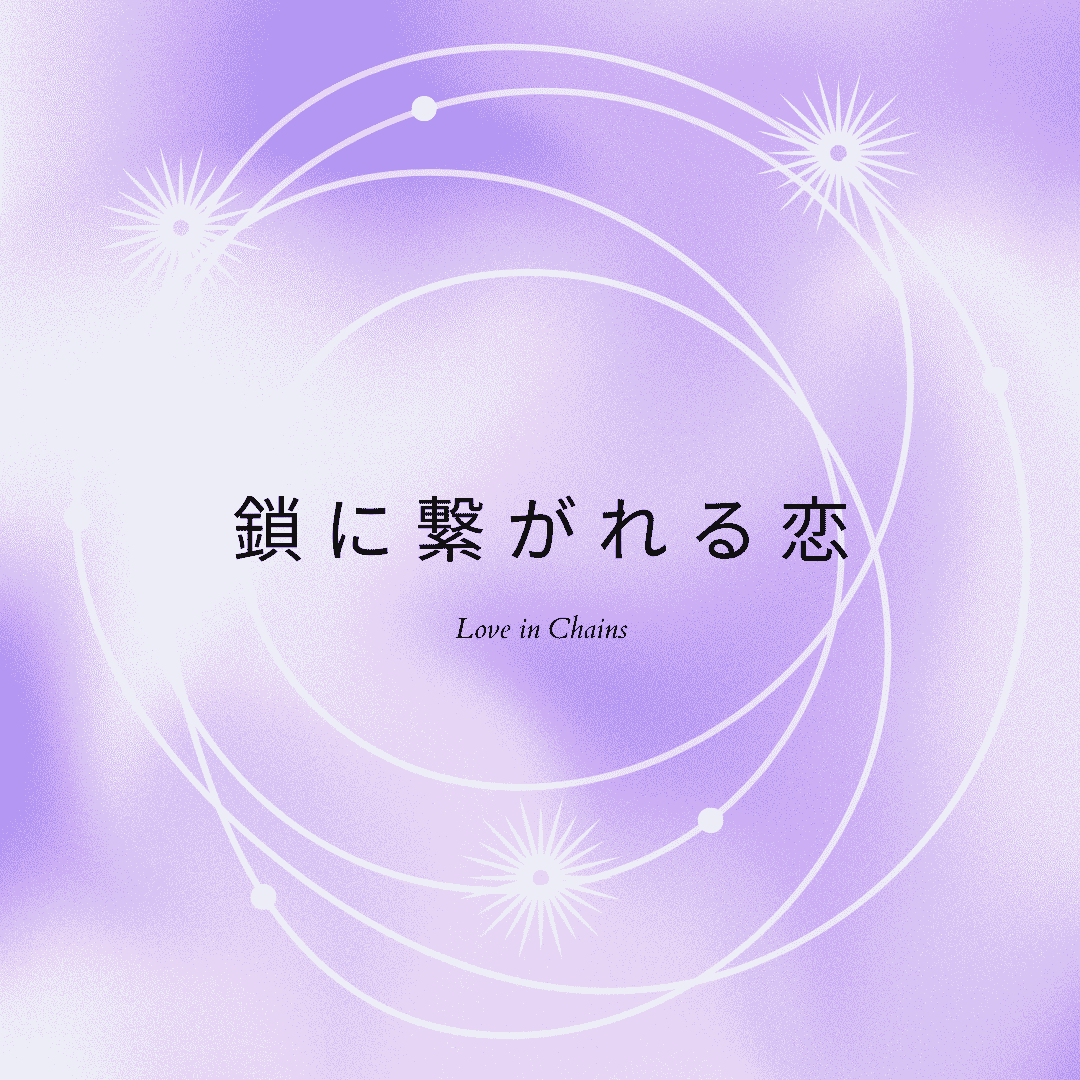



コメント