
0
幼馴染にぎゅっとされる
リクが持ってきてくれたクッキーは大きめだけど、シンプルな味わいでさくさくしていて、何枚でも食べられそう。既に2枚食べ終え、3枚目に手を伸ばした俺を見て、リクが口を抑えくすくすと笑う。
「アキ、昔からクッキー大好きだよね。」
「からかうなよぉ。」
「男で甘い物好きって、そんなに恥ずかしい?」
「いや、別に恥ずかしいとは思ってないけど。」
「じゃあどんどん食べて!」
リクと俺は幼稚園の頃からの仲だ。高校からは離れてしまったが、大学生になった今でも、こうして、お互いの家を行ったり来たりしている。
大学が始まって半年くらい経ち、一人暮らしにも慣れた頃、俺の新しい家が気になると言って、リクが遊びにきてくれたのだ。俺は普通の私大の文学部、リクは近くの有名な美大に通っている。リクは幼い頃から絵を描くのが上手で、美大に行くという夢をもっていた。それを叶えられたことを知った時は、自分のことのように喜んだ。
リクは出会った頃から変わらない中性的な雰囲気を纏っている。髪をホワイトにしてからというもの、その美しさにはさらに磨きがかかっていて、ぱっと見で俺と同じ性別かどうかわからなくなるくらいだ。
にこにこしながらクッキーを勧めてくれるリクを見ながら、もう1枚口に運ぶ。
「リク、大学どんな感じなの?」
「おもしろい人が多いよ! 美大だからかわかんないけど、話が面白くって、おしゃれな人も多いかな。」
「いいなー美大の学祭とか絶対行きたいんだけど。」
「予定でたら知らせるね!」
楽しみが増えるのはいいことだ。リクはペットボトルのミルクティーを一口飲み、また何か話し始めた。
「そういえばね、おれの男友達が彼氏と。」
「え、今なんて?」
「彼氏。おれの男友達が。」
「おお、彼氏、か……」
一瞬状況を飲み込むのに苦労した。どうやら言葉は間違えていないらしい。なるほど、俺の幼馴染の男友達に男の恋人が、ねぇ…。そういうのも、世の中だいぶオープンになってきたしな。珍しくもなんともないが、この綺麗な男に、何もかもを見透かされてそうで、少し身体が強張った。
「その子がね、すごく気持ちいいって。」
「気持ちいい?」
「うん。男同士のセックス、すごくいいんだって。」
そう呟き、長めの髪を耳にかけてみせた。昔から鈍感だと言われ続けていた俺でも、このリクの発言の意図くらいわかる。
「……試してみたいの?」
恐る恐る聞いてみると、リクはふわりと笑ってみせた。
「よくわかったね、アキ。」
艶やかに微笑むリクを見て、俺の胸の奥深くに隠していた気持ちが、引き摺り出されてしまった。
「いっかいさ、ぎゅってしてもいい?」
リクの、加糖のミルクティーよりも甘い声が、耳にのめり込んでくる。この声が俺をどろどろに溶かしてしまったのかもしれない…。
リクの両腕は細いけれど、温かい。さらに強く抱きしめられると、心臓の音がダイレクトにどくどくと伝わってきて、これだけでひとつになった気分になる。人に抱きしめてもらえるって、こんなにも心地いいんだ。いや、ずっと昔から特別な目で見てきた相手にされているから、余計心地いいのかもしれない。
少しだけ顔を上げると、しっとり濡れたリクの目と、目があった。とんでもなく興奮している俺が、その目に映っていて、目を逸らしそうになる。その瞬間…
「アキ……当たってるよ。」
「え、まじ?」
言われてすぐに自分の下半身に手を伸ばす。そこは確かに、ズボンを押し上げるくらい硬くなっていた。
「舐めてあげよっか。男にされる方が気持ちいいらしいよ。」
「ああ、じゃあ……してもらおっかな。」
気持ちいい、という言葉に弱いのを見抜かれている。食欲と性欲が、人よりも強いだなんて、そんなの全部曝け出せるの、どこを探しても、きっと、こいつしかいない。
ベッドの端に腰掛けると、リクは俺のズボンを脱がせた。まだ何もしていないちんこが期待しているかのように、熱を持っている。細く白い手がそれを掴み、軽く上下に動かすと、そこは赤色から赤黒い色へと変化していく。まだ触られただけなのに、これが口に入ったら、すぐイってしまいそう。そんなことを考えながら、ふーふーと荒い息を漏らし、なんとか暴発しないように耐える。
「アキのちんぽ、おっきいね。」
血管が少しずつ浮き出てくるのを見ながら、リクがうっとりした声を出した。
「見比べたことないからわかんないけど、そうなのか。」
「おれの2倍くらいあるもん。舐めごたえありそう。」
「舐めごたえってお前……」
その発言から、リクが他の人ともこういう関係を結んだことが容易にわかってしまい、なぜか胸の奥が痛んだ。まあいい、今は気持ち良くしてもらうことだけ、それだけを考えてよう。
「ん……むっ」
先っぽをぺろっと舌で舐められ、そのままリクのあったかい口内に入っていく。しばらくぴちゃぴちゃと舐めまわされ、俺のちんこは完全に硬くなってしまった。
「これだけでも硬くなっちゃうんだあ、気持ちいい?」
「……ああ」
まともな言葉が出てこない俺を見て、リクがちんこを咥えたまま微笑んだ。さらに、喉の奥まで咥え込まれ、どろどろとしたリクの唾液と俺の先走りが混ざり、卑猥な音が一人暮らしの部屋に響いていく。
「ぅ……ぐっ」
声が抑えられない。舌も唇も喉も、全てを駆使された、あまりにも丁寧な愛撫。オナニーするときには絶対に味わえない快楽に、どんどんと引き摺り込まれていく。特にカリ首の部分に舌が当たると感じてしまうことがバレ、そこばかり重点的に責めてくるのだ。刺激されるたびにちんこが口の中で暴れ、リクの口の中を犯してるみたいになってしまっている。
「あっ、やば……っ」
口だけではなく手でも愛撫され、どんどんと硬さを増していく。いよいよ限界がきそうになった時、ちゅぱ、と音を立て口から離されてしまった。
「えっ」
「これだけでイったらもったいないでしょ?」
そう言ってリクは、ゆっくりと自分の服を脱ぎ始めた。昔プールに一緒に行った時に見た裸と、ほとんど変わらない。白くてひょろりとした守りたくなるような身体。
「次はね、動いてあげるから。」
リクがパンツを下ろした時、ぐちゅとお尻から何か垂れたのが見えた。
「それ……」
「ああ、これは潤滑ゼリー。ここにくる前に入れてきたの。」
「リク、もしかして最初から…」
パンツを足から抜き、一線纏わぬ姿になったリクは、どこかの国の絵画に描かれている天使のようだった。どこもかしこも真っ白で、足と足の間には小ぶりなピンク色のちんこがついている。
「ああ、綺麗……」
「綺麗? ありがとう。アキにそう言ってもらえるのが一番嬉しいな。」
そう言いながら、俺のシャツを脱がせてくる。
「おれね、ずっとアキのことそういう目で見てた。ずっとね、いつおれの気持ちに気が付いてくれるかなって」
シャツを軽くたたんでベッドの下に置くのが見える。こういう丁寧なところも、昔から何も変わってない。
「でもね、もう我慢できない。今日絶対言おうって決めてきた。」
「うん。」
「アキ、おれの恋人になってよ。無理ならセフレに。」
「無理なんかじゃない。俺もずっと、リクのことが好き。何回お前で抜いたかわからない。」
勢いに任せて全部ありのままに言ってしまった。ああ、まあいいや。両思いだってわかるエピソードにしては強烈かもしれないけど、一番わかりやすそう。
「そこまで言っちゃうんだ。」
リクはまたくすくすと笑い、俺に抱きついてきた。そのままベッドに倒れ、リクが俺の腰に跨り、腹に手をついてきた。
「あのね、騎乗位は初めてだから……下手くそだったらごめんね。」
そんなの、好きな人が上で頑張ってくれるなら、なんだっていい。その状況だけでいよいよ暴発しそうになる。
「いい、動いてくれるだけで嬉しい。」
「このちんこ、おれのなかに入れてもいい?」
涙で揺れるリクの目を見ながら、しっかりと頷く。俺のちんこを数回擦り、いつのまにか封を開けていたゴムを被せられ、ゆっくりとリクのなかに飲み込まれていく。
「うっ、わ……」
ゼリーのぬるぬるとした感触と、なかの締め付けの強さに声が漏れる。頭がぐらりと揺れ、思わずリクの手を握る。リクは驚くことなく、嬉しそうにそれを恋人繋ぎにし、ゆっくりと腰を揺らし始めた。
「ん……っ、アキの……っ、おっきい。」
「気持ちいい? リク。」
「きもちいい……っ、ずっと、こうしたかった、からあ……ッ」
ぱちゅんぱちゅんと肌と肌がぶつかる音がするたび、なかが搾り取るかのようにうねる。ちんこの先端から根元までバランスよく圧をかけられている。気持ちよすぎて意識が飛びそうになるのを、手を強く握って耐える。
「アキっ、すきっ、ぁああ……すきっ」
ずっと恋焦がれていた声が、俺に何度でも告白してくれているのだ。その事実となかのうねりが、たまらない。
「俺もだよ、俺も……っ、リクがすきだ。」
「あうぅ……ッ!」
次の瞬間、リクのなかが細かく震えた。太ももを揺らしはあはあと甘い息を漏らし、繋いだ手には力が入っている。どうやらドライで達してしまったらしい。
「リク、イっちゃった?」
「ん……も、うごけないかもっ」
「じゃあ、次は俺がする。」
繋がったまま押し倒し、体勢を逆転させる。目の前には顔を赤らめた天使がいる。そっと唇を重ねてから肩を掴み、腰を激しく動かしていく。
「ぁっ、あ、ああっ、イっ、たばっか、なのにい。」
「や、俺がイくまで……もう少しだけ。」
あへあへとした力の抜けた声で抵抗してくるのが、愛らしくて仕方なかった。射精したくて、何度も何度も、腰を強く打ち付ける。そのたびにリクのなかは震え、小さく達してしまっているのがわかる。
「あっ、あんっ、ああッ、あっ、きも、ちっ奥、いいッ」
「奥が好きなんだ。」
「奥うっ、おくっ、きてっ」
「じゃあ、奥に出すよ。」
ゴムをつけているけれど、なかで達することには変わりはない。奥にとんとんと当てるように腰を動かすと、またリクの白い太ももが震え始めた。
「あっ、またッ、ドライでイっちゃ……っ」
「俺も、出るッ」
なかがさっきよりも激しく収縮したと同時に、俺も薄いゴムの中に射精した。
「はあ、はあ……」
しばらく動けそうになくて、リクに抱きついたまま息を整えていく。
「まさか、アキもおれのこと好きだったなんて。」
「なかなか言うタイミングもなかったし……遅くなってごめん。」
「ううん。おれのところの学祭、手繋いでいこうね。」
なんて可愛い誘いだろう。嬉しそうに笑ってそう言ったリクに、俺はもう一度口付けた。





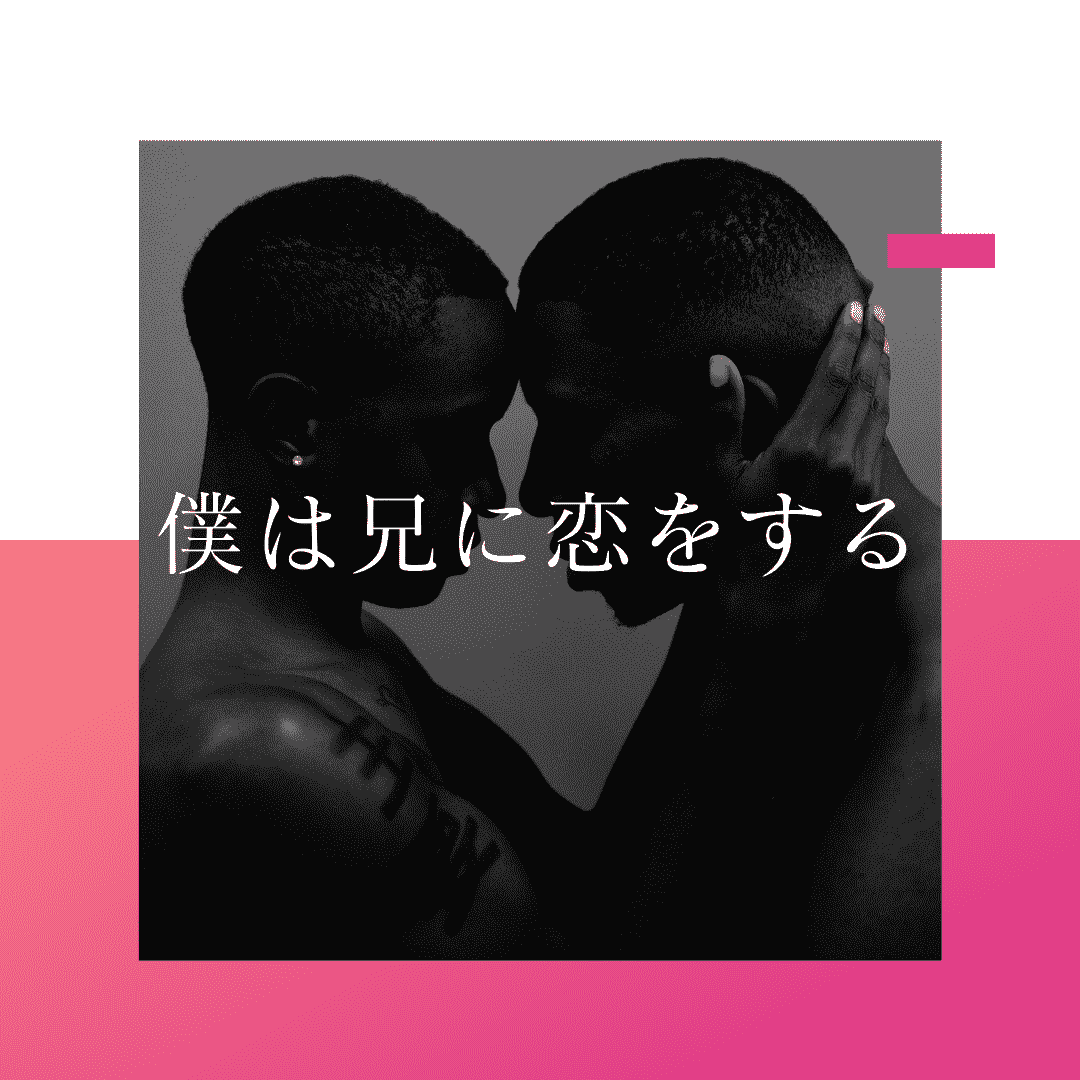



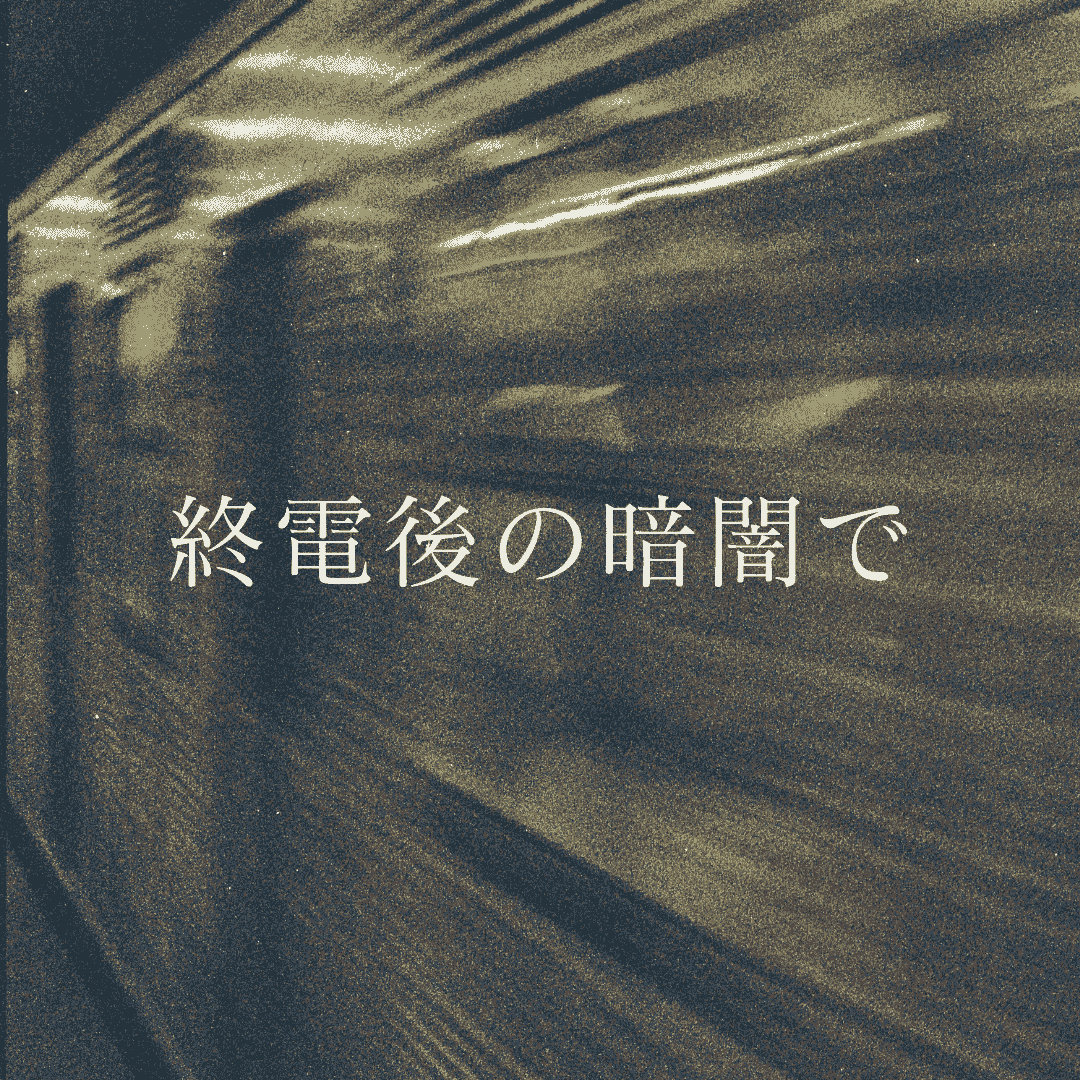
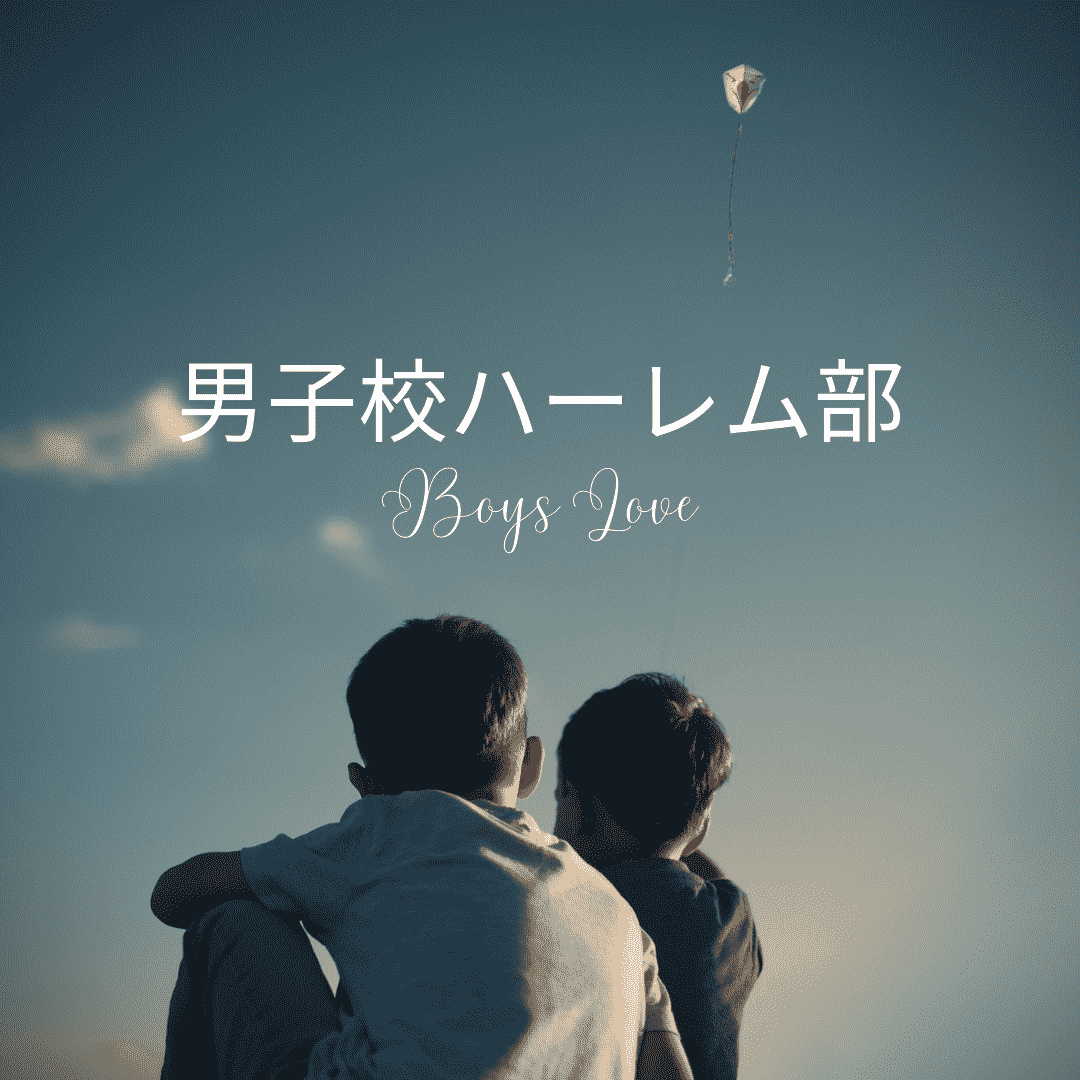
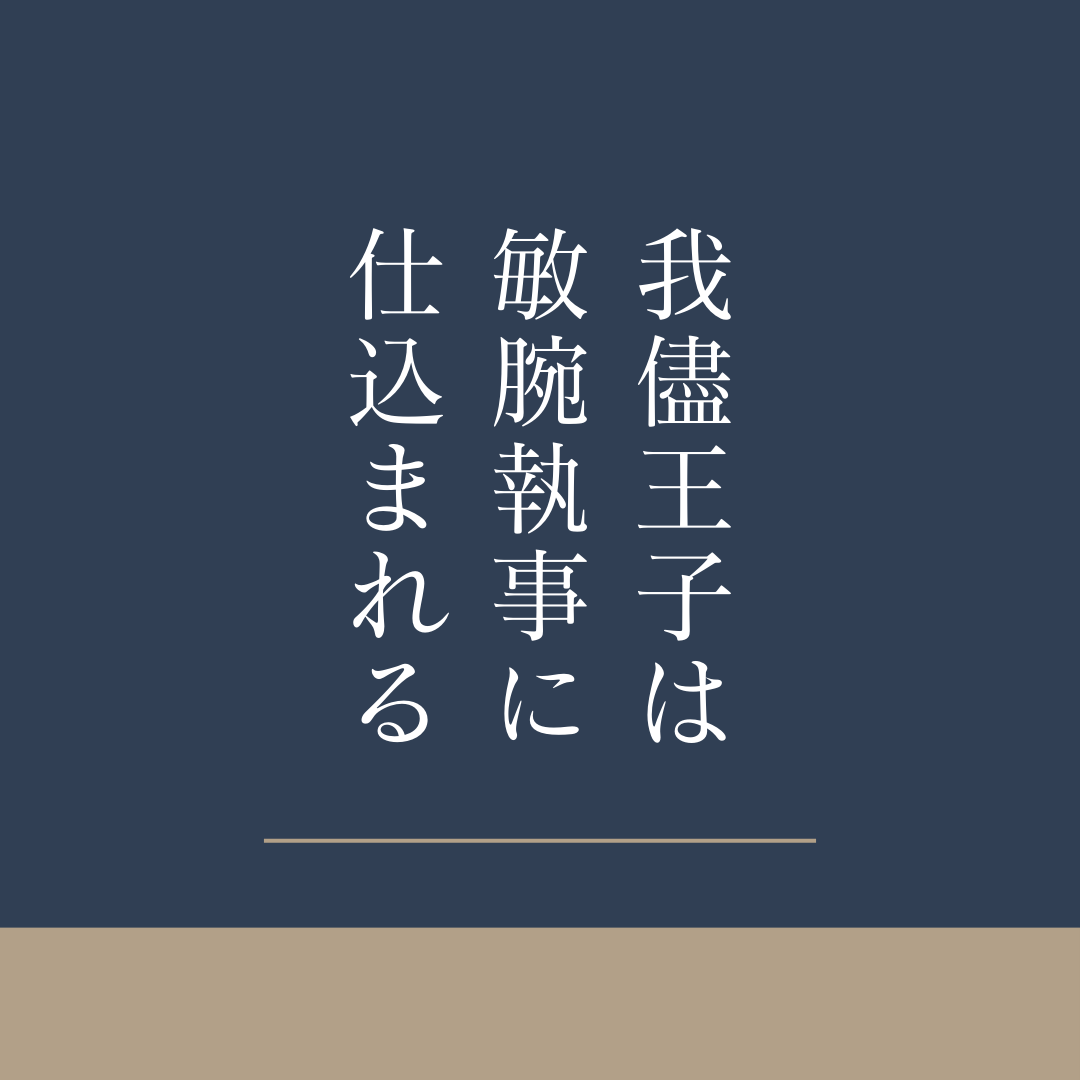

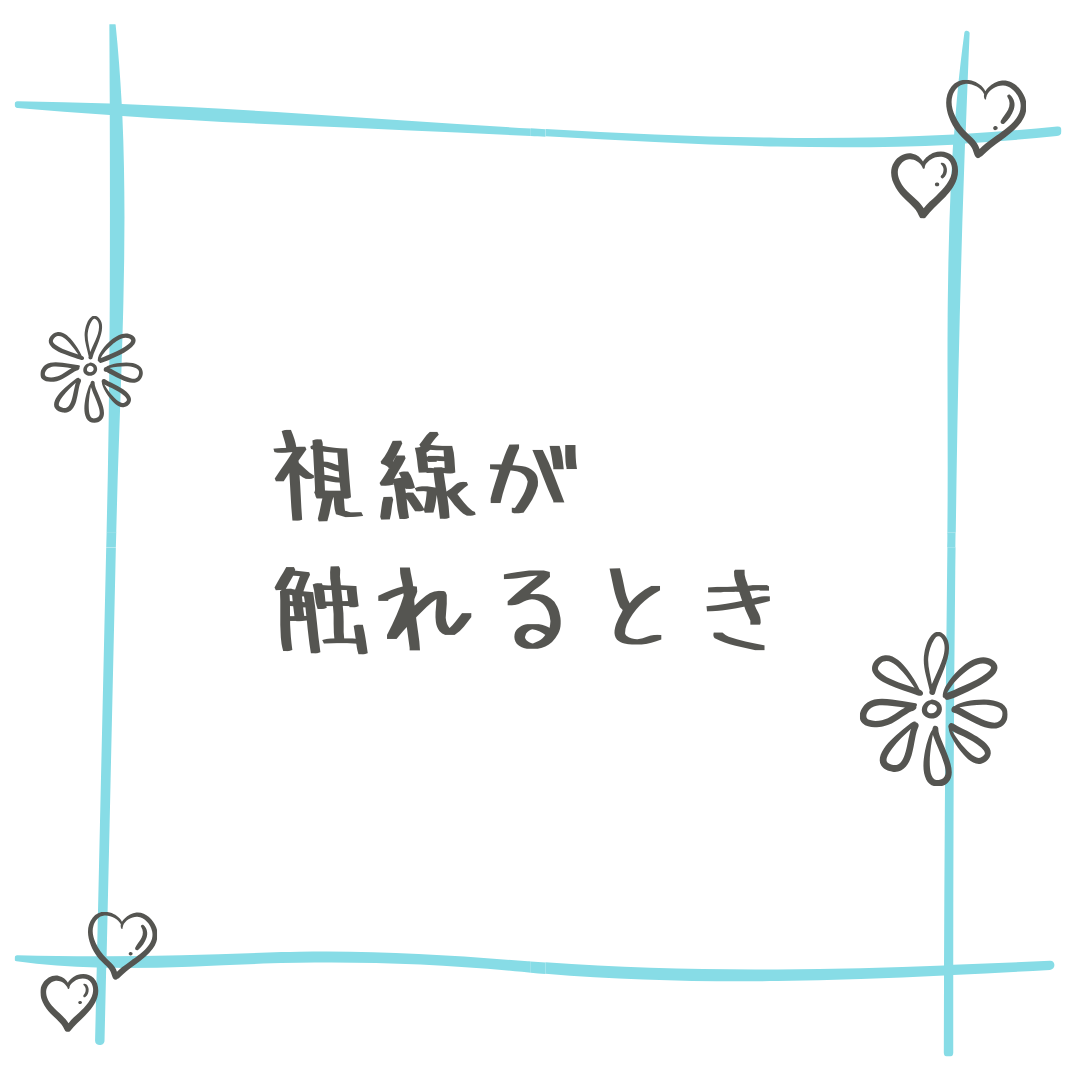


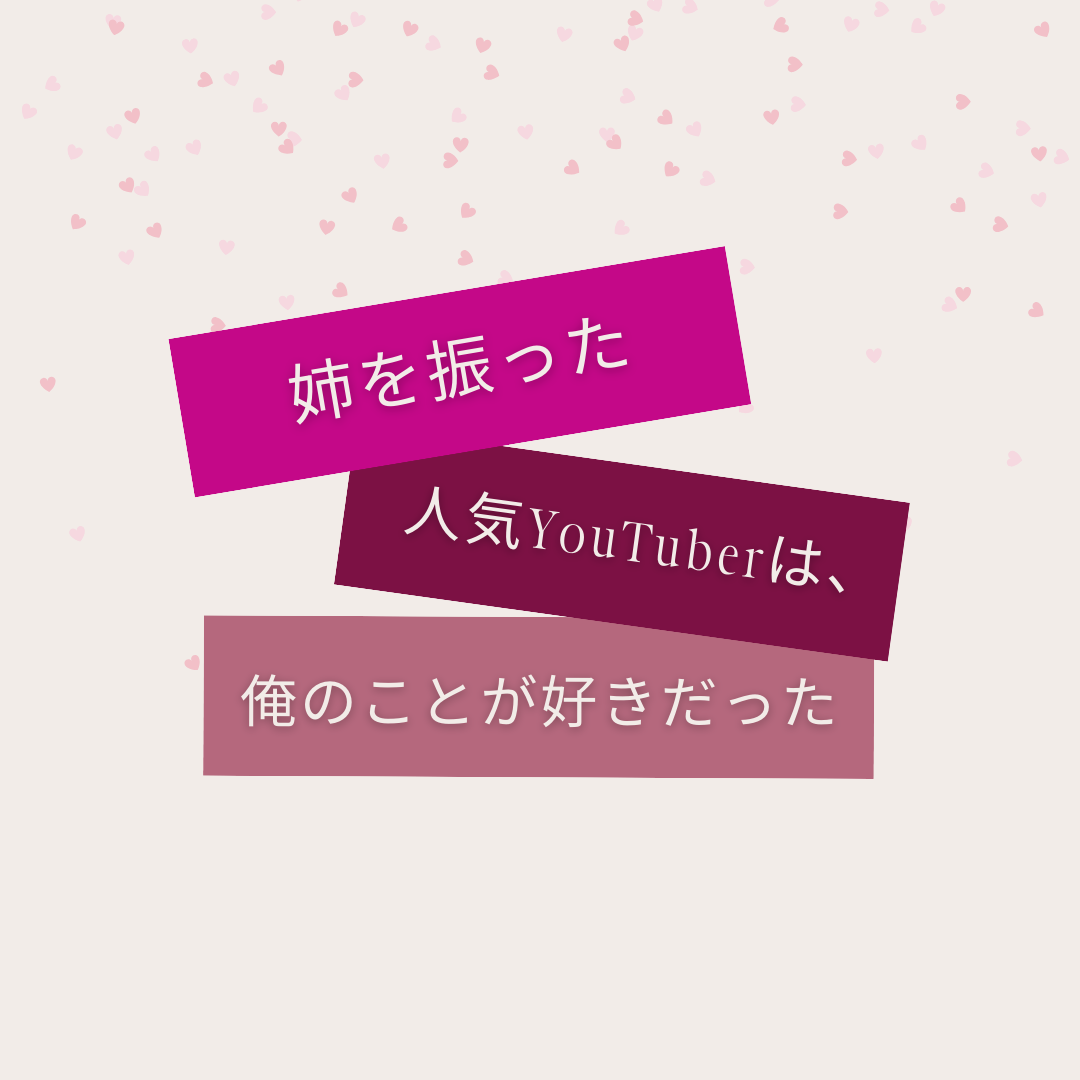









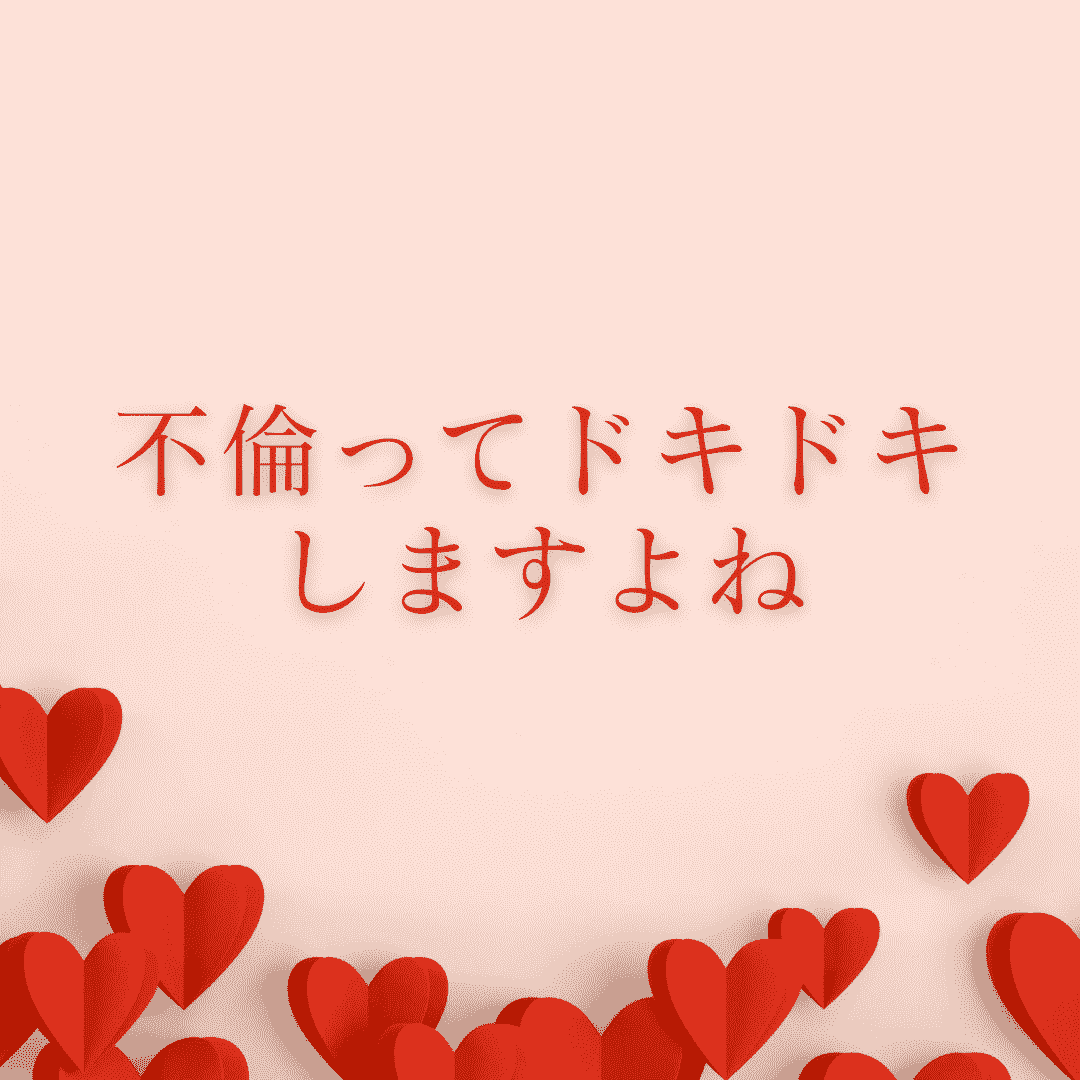




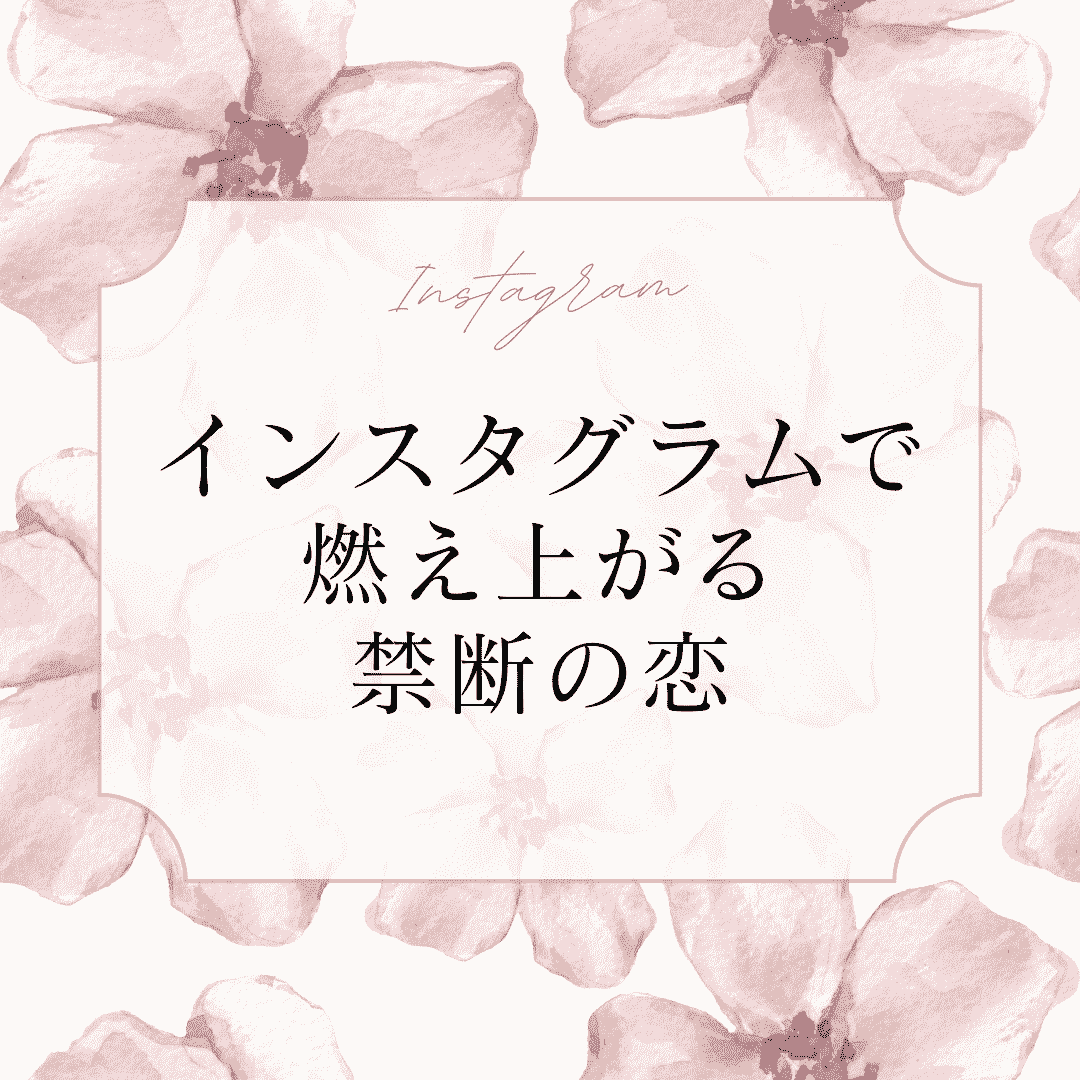






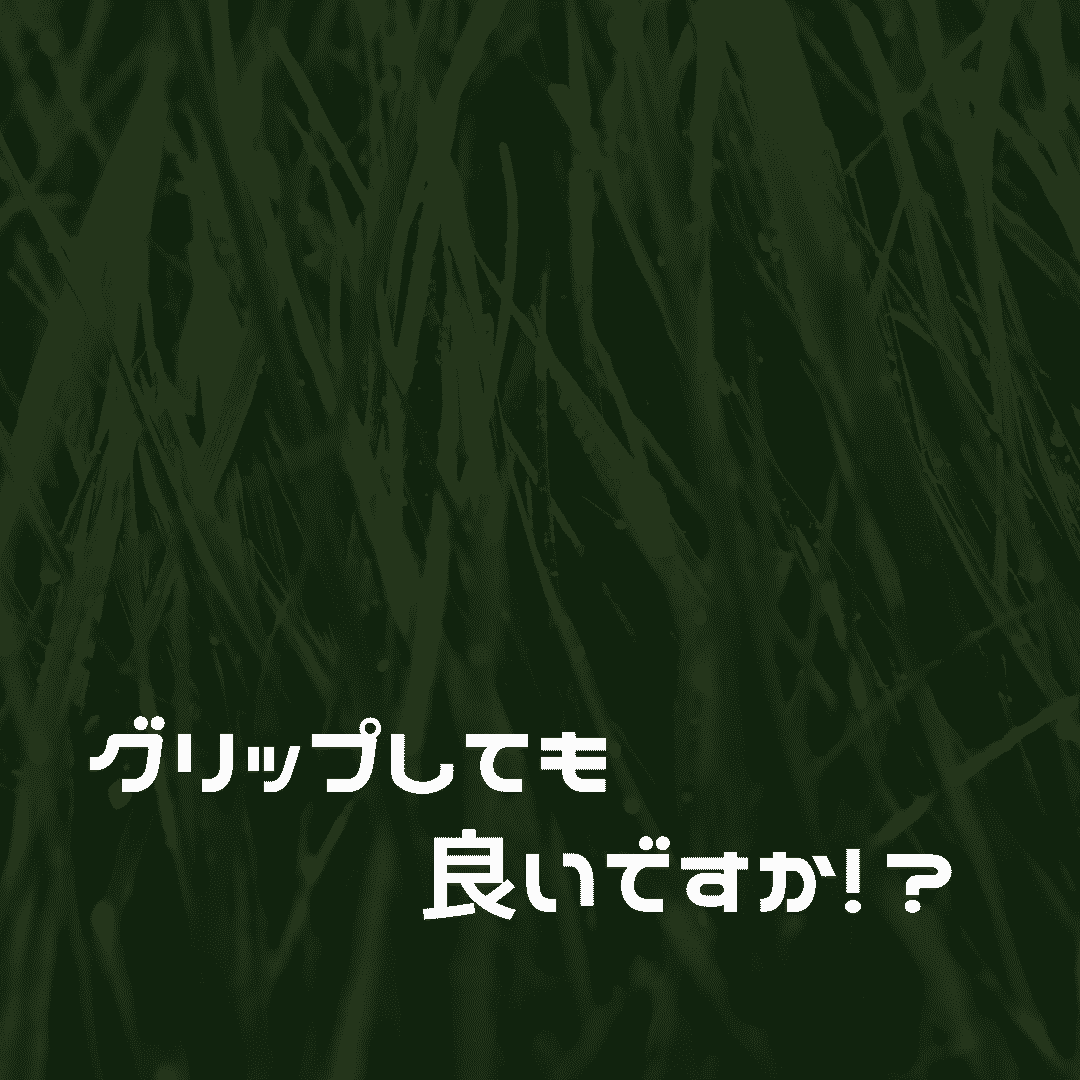

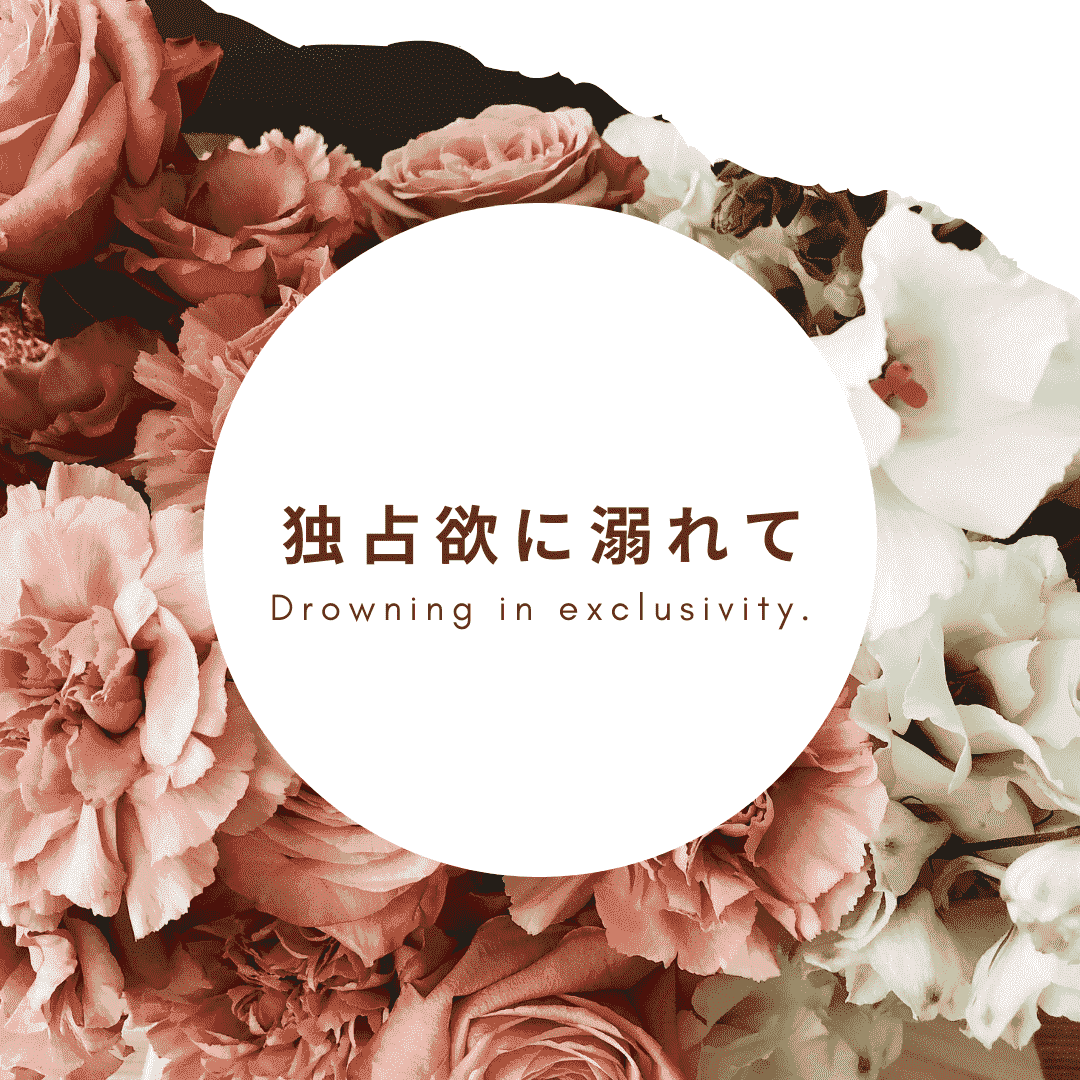
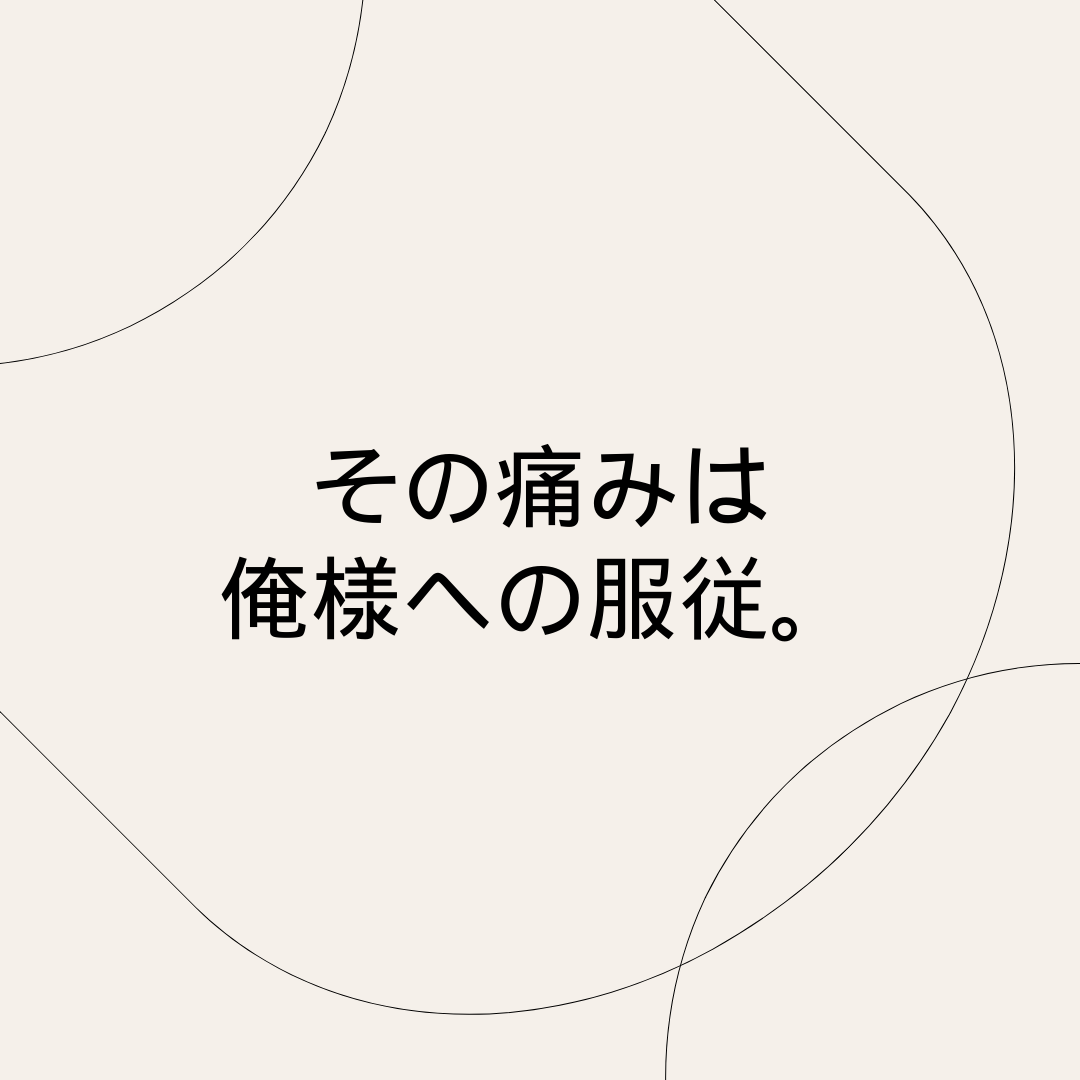
コメント