
0
男の子と男の子
「じゃあ行ってくる。」
「行ってきまーす!」
玄関で振り返る二人に、ミツキは笑顔で手を振った。
「いってらっしゃい。あ!楓太、水筒忘れてるよ!」
そう言いながら、廊下脇に放置されていた水筒を慌てて手渡す。
「やべ、みっちゃんありがとう!」
「ありがとな。よし、楓太いくぞ。」
「うん!パパ!」
仲睦まじく出かけていく二人が、玄関のドアの向こうへ消えるまで見送ると、短く息を吐いた。
残念だが、自分たち三人に血の繋がりはない。いや、正確に言えば、楓太とパートナーであるリョウの間には、遠縁というつながりはある。
今のご時世。結婚という形にこだわらなくてもいいと誓いあったのが5年前。それよりも前からリョウと楓太は共に暮らしていた。リョウのはとこにあたる人物の子供らしいが、詳しいことは聞いていない。自分が二人の世界に入った時には、既にどこからどうみてもリョウと楓太は親子に見えたし、リョウと同性である自分のこともなんの抵抗もなく受け入れてくれた楓太を、我が子のように思っているのもまた事実だ。しかし……
『ピピピピ』
そこまで思い返していると、自分のスマホのアラームが鳴った。やばい!と短く呟くとミツキは慌てて身支度を始めた。
今日は月に一度の楓太のサッカー教室のママ達とランチ会だ。最初は抵抗があったものの、こちらも意外にも好意的に受け入れられ、今ではミツキが来ないならと会が延期される程、固定メンバーとして歓迎してもらっている。
「今日はエリオットホテルのフレンチ……か。また凄い豪華なとこだな。」
ミツキは苦笑しながらリョウとの寝室に備え付けられているクローゼットを開けた。フォーマルすぎず、カジュアル過ぎない無難なラインを選んで身支度を整えていく。どれも全て、リョウが買い与えてくれたものだ。
フリーのプログラマーとして仕事に没頭し生活に全く無頓着だったミツキに、人間らしい生き方を取り戻してくれたのもリョウだった。そのことに感謝してもしきれない。
何一つ不自由のない暮らし。自分を受け入れ大切にしてくれる家族。誰がみても恵まれているというはずの生活をしているのに……
「……」
支度が終わり、鞄を持ちながらミツキはくるりとキングサイズのベッドを振り返る。このベッドのシーツが最後に乱れに乱れたのはいつだったか……
「はぁ……」
思い出せないくらい遠い過去に、ミツキは自嘲気味に笑うと、そのまま足取りを緩めることなく家を後にした。
***
「ミツキさん、今日どうかなさった?」
料理も終盤にさしかかり、それぞれのお喋りのピークも落ち着いてきた頃、隣に座った楓太の親友である太一のママ。リカが心配して声をかけてきた。
「えっ、あ、いえ。そんなことないですよ、今日も素敵な会で凄く楽しいです!」
「そう、それなら良いの。あぁそう。太一がね、この前楓太くんにリフティング負けたってとっても悔しがっていたのよ。ミツキさんが楓太くんに教えてらっしゃるんですってね。良かったら今度一緒に教えてくださらない?」
「あ、いえ僕はただ楓太の練習に付き合っただけで……でも、是非。楓太も太一くんと一緒に練習するって行ったら喜んでついてくると思います。」
ミツキの返事にリカは嬉しそうに微笑むと、少しだけミツキの方へ顔をよせ、囁くように問いかけた。
「ありがとう……そうだ、この後会がお開きになってからお時間あるかしら?」
「あ、はい……大丈夫です、けど」
普段からミステリアスで掴みどころのない人だという印象を受けていたが、近くで見るとその印象はより一層深くなる。
(うわっ、やっぱめっちゃ美人……てか、リカさんて一体いくつなんだ?)
「良かった。あなたは原石だから、是非紹介したかったの。」
「原石?」
「ううん、こっちの話よ。そしたらお開きになったら別々に帰ったと見せかけてラウンジで待ち合わせましょう。」
そう言いながら、リカは持っていたクラッチバッグからホテルのラウンジのカードを出すと、滑らせるようにミツキに手渡してきた。
「残念だけど、選ばれた人しか紹介できないの。」
「は、はぁ……」
変な勧誘とかだったらどうしよう。と一瞬不安がよぎるが、こんな高級ホテルでそんな怪しい勧誘はないだろうとミツキはそのカードを胸ポケットにしまった。
「お待たせ、ごめんなさいね。ちょっと別のママにつかまってしまって。」
その声に顔をあげると、リカが小走りにラウンジの入口から駆けてくるのが見えた。
「いえ、そんなことありません。大丈夫ですよ。」
頼んだラテはまだ半分ほど残っていたが、ミツキはそのまま立ち上がるとリカに続いた。
「支払いは部屋につけておくから気にしないで。」
「えっ!でも。」
「いいのよ。それも含めて向こうから頂いているから。」
「あ、はぁ……」
リカは慣れた手つきで近くにいたウェイターに声をかけ、そのままエレベーターホールへと向かった。
すぐにやってきたエレベーターに乗り込む。二人きりの空間に、ミツキはあちこち視線をめぐらせ、口を開くタイミングを狙うが、先にリカが口を開いた。
「私ね、美しさを保つために妥協したくないの。」
「え、あ、はぁ……そうなんですね、リカさん。すっごく綺麗ですもんね。年齢不詳っていうか、いつも自信があって……僕なんて。」
そこまでいうとリカがクルッと振り返り、ミツキの頬に手を添えた。
「もうおやめなさい。あなたは自分の魅力にもっと気づくべきよ。」
「えっ?」
「ごめんなさいね、ミツキさん。リョウさんとセックスしてないでしょ?」
「っ!!」
あけすけな言葉に、ミツキの頬がカッと熱くなった。
チン。と控え目なベルと共に、エレベーターの扉が開いた。
「わかるのよ。私もそうだったから」
リカはミツキの頬から手を離すとそのまま踵を返してエレベーターから降りる。
「あ、ちょ……」
ここで引き返しても良かったのではと思うが、それでもなぜか抗えない重力に引かれるように、リカの後を追った。
「私の場合は夫が高齢で不能になってしまったっていうのが大きな理由なんだけど。でもわかるでしょう?美しさって愛されて磨かれるのよ。」
わかる、わからないと言えば多分、わかる。と、ミツキは頭の中で返事をした。リョウとしなくなったのは別に冷めたとかではなく、お互いに忙しくてなんとなく……だったと思う。だが
『なんか、最近のミツキ。オカンみが増したよなぁー』
ソファに寝そべりながらケラケラと雑談の延長のような口ぶりで言われ、心の奥がチクリと傷んだ記憶がよみがえった。
「美しさを、磨く……」
「そう。だから、ミツキさん。今日はたっぷりと愛されて、リョウさんに貴方の魅力をまた見せつけてやるのよ。」
リカは廊下の最奥にある部屋の前で立ち止まり、ミツキを振り返ると艶っぽく笑うとカードキーを差し込み、静かにその扉を開いた。
「いらっしゃい。待ってたよ。」
部屋の中にはミドル世代のダンディな男性と大学生ぐらいだろうか?若い青年が立っていた。スイートルームなのだろうか。部屋は2つに仕切られているようで、奥にもう一つのドアが見えた。
「西園寺さん、手配ありがとうね。こちらが連れてくるって言ってた、ミツキさん。」
リカに軽く紹介されミツキは静かに頭を下げた。
「若いって聞いてたからウチで一番若いのを連れてきたよ、存分に楽しんでくれたまえ。じゃあリカと私は奥へ行こうか。」
「えぇ、じゃあね。ミツキさん。楽しんでちょうだい。」
「え、ちょ、リカさ……!」
状況を完全に飲み込めずリカの腕を取ろうとするが、それよりも早く、西園寺という男がリカの腰を抱いて、さっさと奥へと去ってしまった。
「あ……」
「緊張してますか?」
そう背中から声をかけられ、ミツキは驚いて振り返った。
「別に絶対ヤらなきゃいけないってルールもないし、良かったらのんびりしませんか?」
そう言いながら男はキングサイズのベッドのフチに腰掛けた。
「僕、テツって言います。ミツキさんて呼んでいいですか?」
「あ、はい……よ、よろしく?」
「よろしくお願いします。よかったらミツキさんも腰掛けませんか?」
テツの物腰柔らかな口調にミツキはおずおずと同じようにベッドに腰を下した。すると全く嫌じゃないタイミングで、静かにテツの腕がミツキの腰に回された。
「あっ……」
「楽にしていいですよ。」
首すじに唇を寄せられミツキの背筋が粟立つ。
「んっ……」
「綺麗ですね、ミツキさんの肌。」
「そ、そんなこと……なっ」
「もっと見てもいいですか?」
「あっ、あ……う、ん…」
ミツキが小さく頷くとテツはその反応を逃さず、ベッドに優しく押し倒してきた。
「あっ、あ……テ、テツくん。ちょ……」
チュクチュクとあちこち吸われ、ミツキはそのたびに腰のあたりに溜まる快楽に身を捩らせる。
「本当に、綺麗ですね。それに、凄く美味しい。」
「お、いしく……なっ、ああっ!!」
「ふふ、だんだん大きくなってきましたね。辛そう」
与えられる刺激にやんわりと勃起を始めたミツキのペニスを、テツはズボンの上から優しく撫で上げた。
「あっ、んっ!」
「脱がせていいですか?」
テツはそう尋ねると、ミツキが返事を返す前にスルッと器用に下着ごとはぎとった。
「ひぅっ!」
わずかに冷たい外気にミツキは足を閉じようとするが、テツにそれを拒まれガバッと大きく足を開かれる。
「やっ、はずかし……」
「どうしてですか?こんなに綺麗なのに。」
足のラインに沿って撫でるテツの手のひらの熱が、熱く心地よくミツキはまた身体を捩らせ淫らな声をあげてしまった。
「ひっ……あっ!」
幾度か足を撫でたあと、テツの手はやさしくミツキのペニスを握りこんだ。
「んあっ!!」
ひときわ大きな声をあげ、ミツキはその背を弓のようにしならせる。
「入口、ちょっと固いですね。でもすぐほぐれそうだ。」
優しくミツキのペニスを扱いながら、テツはその秘部にも指を這わせる。グッと押される圧力にミツキは一瞬顔をしかめると、その眉間のしわに優しくテツがキスを落とす。
「大丈夫。ゆっくりします。」
「あっ、う……ん、でも…ああっ!!」
「まずはミツキさん一回出した方が良さそうですね。可愛らしい液が……ほら、沢山」
そう言ってテツはわざとらしく音を立ててミツキのペニスに刺激を与え始めた。
「んあっ!そ、そんな……んっ、ああっ、あっ!」
いつの間にかテツの腕の中に迎え入れられ、あやすように背中を撫でられながら、ミツキは快楽を追いかけてしまう…。
「いいんですよ。今は全部忘れて気持ちよくなってください。」
「んぅ、あっ……んっ、テツく……きもち、いぃ…」
「うん、ミツキさん凄くいやらしい顔してるからわかりますよ。」
そう言いながら、テツは優しくまたミツキの額にキスを落とす。
「さ、一度出してみてください。とっても気持ちいいですよ。」
「あっ、うっ、うん……うん、あっ、あっイ…く、あっ……あああっ!!」
導かれるようにあっけなく吐精し、ミツキは荒く呼吸を繰り返した。
テツは再び優しくその背を撫でながらミツキの精を指先に集め、秘部に塗りたくる。
「ミツキさん、ゆっくり深呼吸しててくださいね。」
「うん……う………あああっ!!」
テツに言われコクコク頷きながら深く息を吸うと、そのタイミングで彼の指が自身のナカに侵入し、またミツキは大きな声をあげた。
「あぁ、やっぱり。ナカは柔らかくて……ふふ、僕の指に絡みついて離れないですよ。」
「やめっ、恥ずかし……」
「そんなことないです。本当に綺麗。さぁ、また気持ちよくなりましょうね。」
そう言いながらテツは優しくミツキの内壁を撫で上げるように指を出し入れし始めた。
「ふぐっ、うっ……んぁっ!……あっ、あっ!」
「すぐほぐれますね。気持ちいですか?」
「うんぁっ!……うん、あっ、きもち、いぃ……」
「いいですよ、そのまま…」
そう言いながらテツは身体の位置を変え、ミツキの上に覆いかぶさるとゆっくりと細かな抽挿を繰り返しながら指を抜き、即座に自身を秘部の入口にあてがった。
「いいですか?」
「あっ、……んあっ」
「あぁ、でもふふ……ミツキさん、僕の勝手に飲み込んでいく。」
言葉よりも早く、ミツキの身体がテツを迎え入れた。
「ああっ!」
「っ……あ、スゲ。」
「ひぅっ、あっ……」
「ふふ、ミツキさん。すご……もってかれそ」
「あっ、テツくん……」
ジュクジュクと広がる圧迫感とともに訪れる快楽に、ミツキは身体を捩らせながらそれを享受した。
「あと、すこし……押しますよ。」
グッと足を抱え上げられテツが腰をミツキに打ち付ける。
「ひあっ!!ああっ……」
最奥を抉られ、電流のように全身を快感が駆け抜けた。
「ゆっくり、動きますね。」
緩急をつけて繰り返されるテツの抽挿に、ミツキはギュッとシーツを握りしめながらまた淫らに声をあげた。
「んあっ、あっ……ひぐっ、んああっ!!きも……ちぃ…」
「えぇ、僕も凄く気持ちいいです。もっとよくなってくださいね。」
ぐちゅぐちゅと卑猥な水音がだんだんと大きくなっていく。
「ああっ、テ、てつく……僕、また…」
「うん、いいですよ。沢山イってください。」
ミツキの性感帯をあえて刺激するように、テツは角度を変えてミツキのナカを穿つ。
「あっ、そこ……ダメ、あっあっ!!」
「くっ……ミツキさんそんなに、しめたら俺も……」
やまない律動に揺さぶられミツキは快楽を全て受け止めようとテツの動きに合わせ腰を動かす。
「んあっ、も、でちゃ……」
「うん、いいですよ。さぁ出して、綺麗だよ、ミツキさん。」
そう言いながらテツは優しく頭を撫でる。その瞬間彼の下でミツキは一度大きく跳ね、全てをまた吐き出した。
「んあっ!!!あああっ!!」
「……っ!」
クタッと脱力するミツキのナカにわずかに遅れてテツも精を吐き出した。
***
「なぁ……今日、何かあった?」
その日の夕食後、洗い物を始めようとキッチンに向かったミツキの手首を掴んで、リョウは声をかける。
「えっ?別に。何も。いつも通り今日はランチ会だっただけだよ」
「太一のママにあった?」
会話に割って入る颯太の方を向き、ミツキは笑顔で彼の方を向く。
「うん、あったよ。今度一緒にリフティングの練習しようって話になったよ。」
「おっしゃー!楽しみ!!」
風呂行ってきまーす!と駆けていく楓太を見送り、リョウがまだ何か言いたそうにミツキを見つめるが、そのまま引き下がりリビングへと戻っていった。
「そっか。なら、いいんだけど。」
「うん。」
ブブッとズボンのポケットでミツキのスマホが震えた。シンクの影に隠しながらそれを開く。
『また、会いましょう。』
短いそのメッセージに、ミツキは小さく微笑んだ。





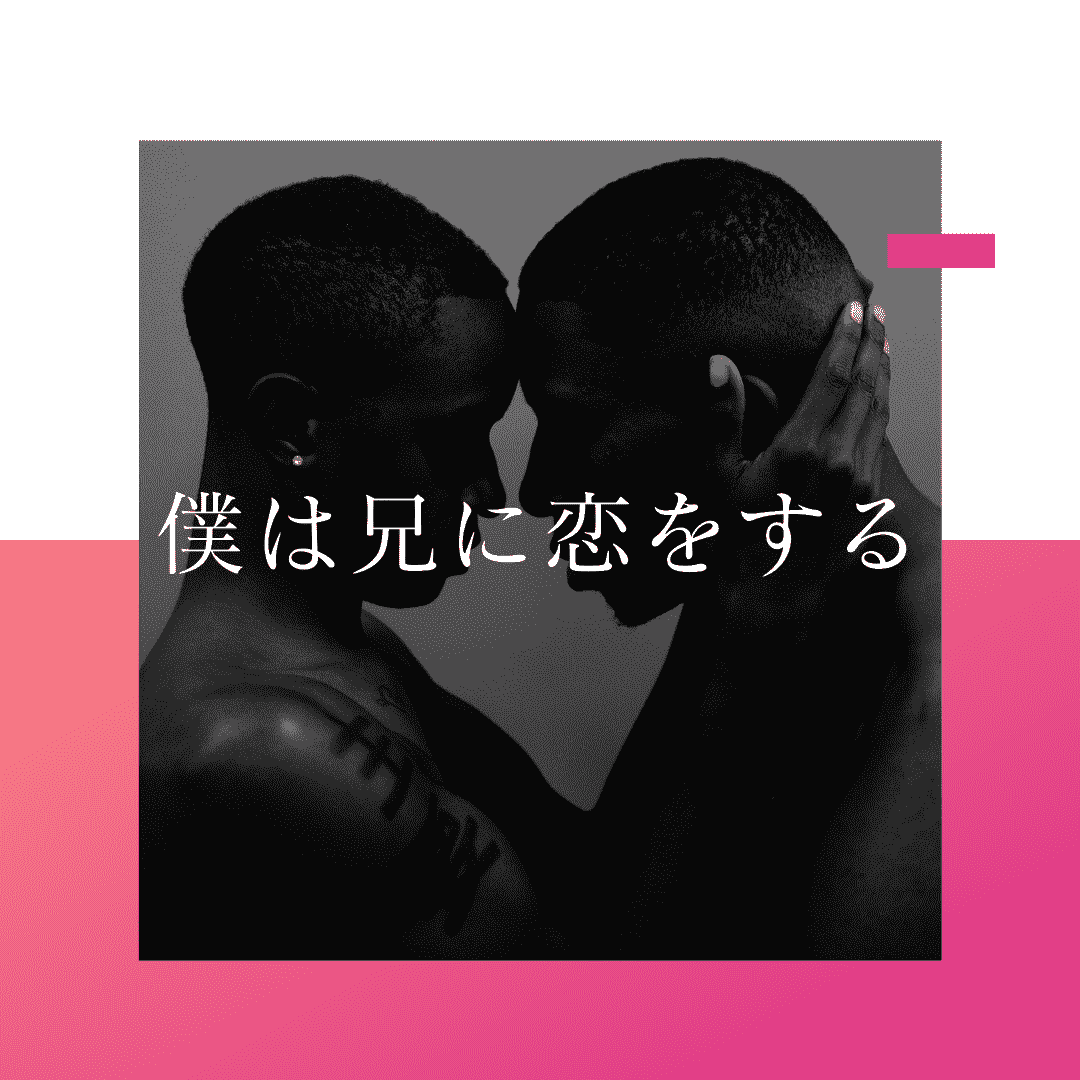



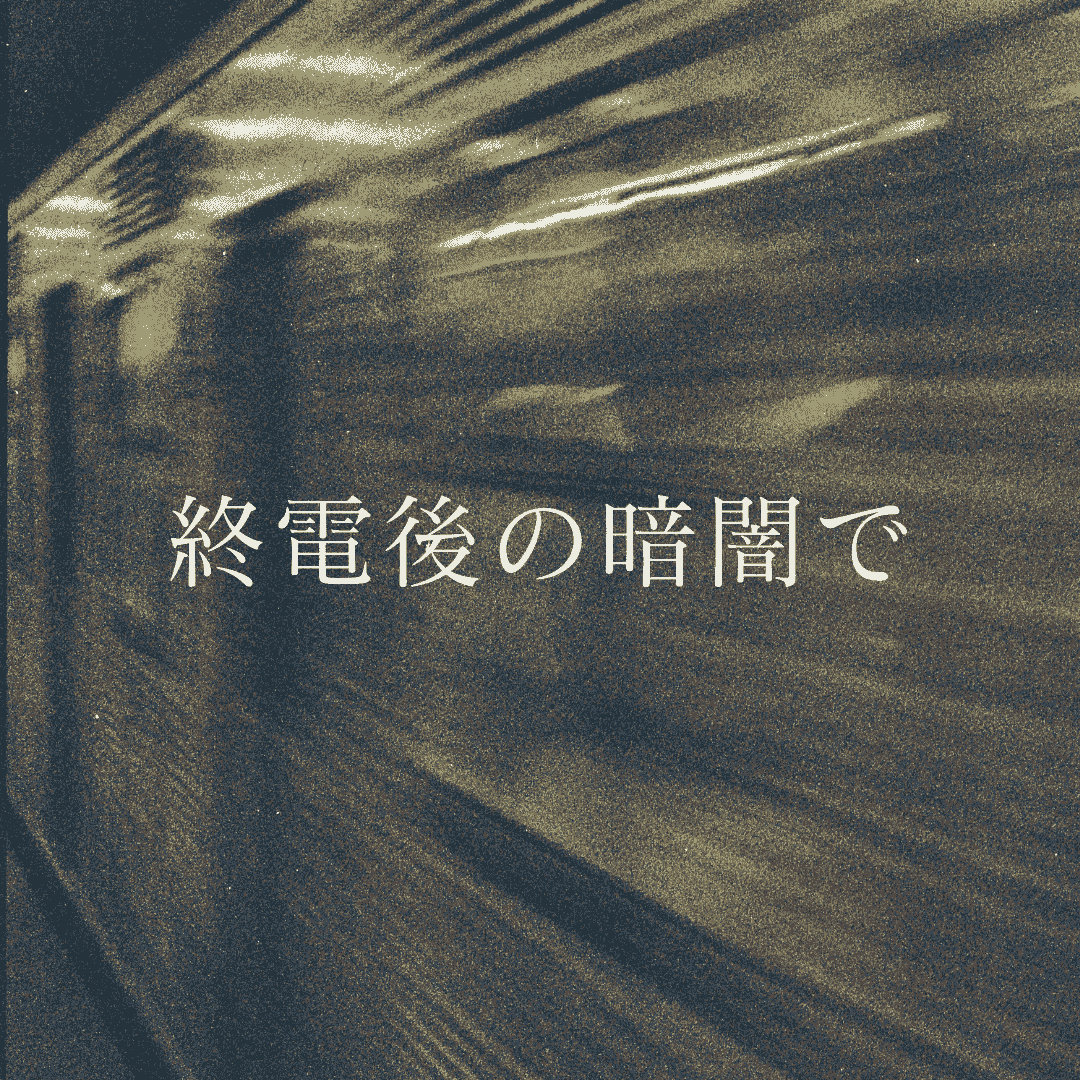
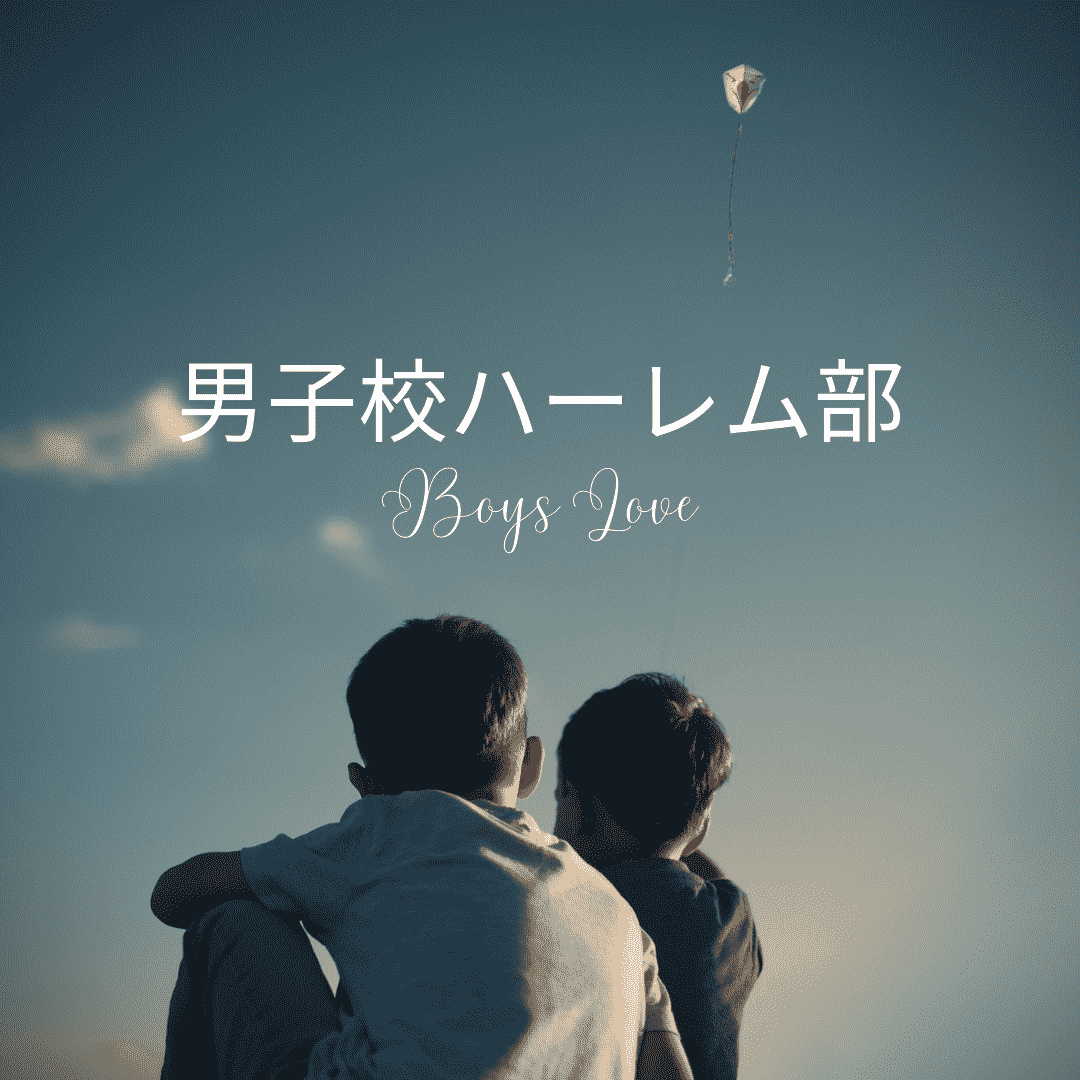
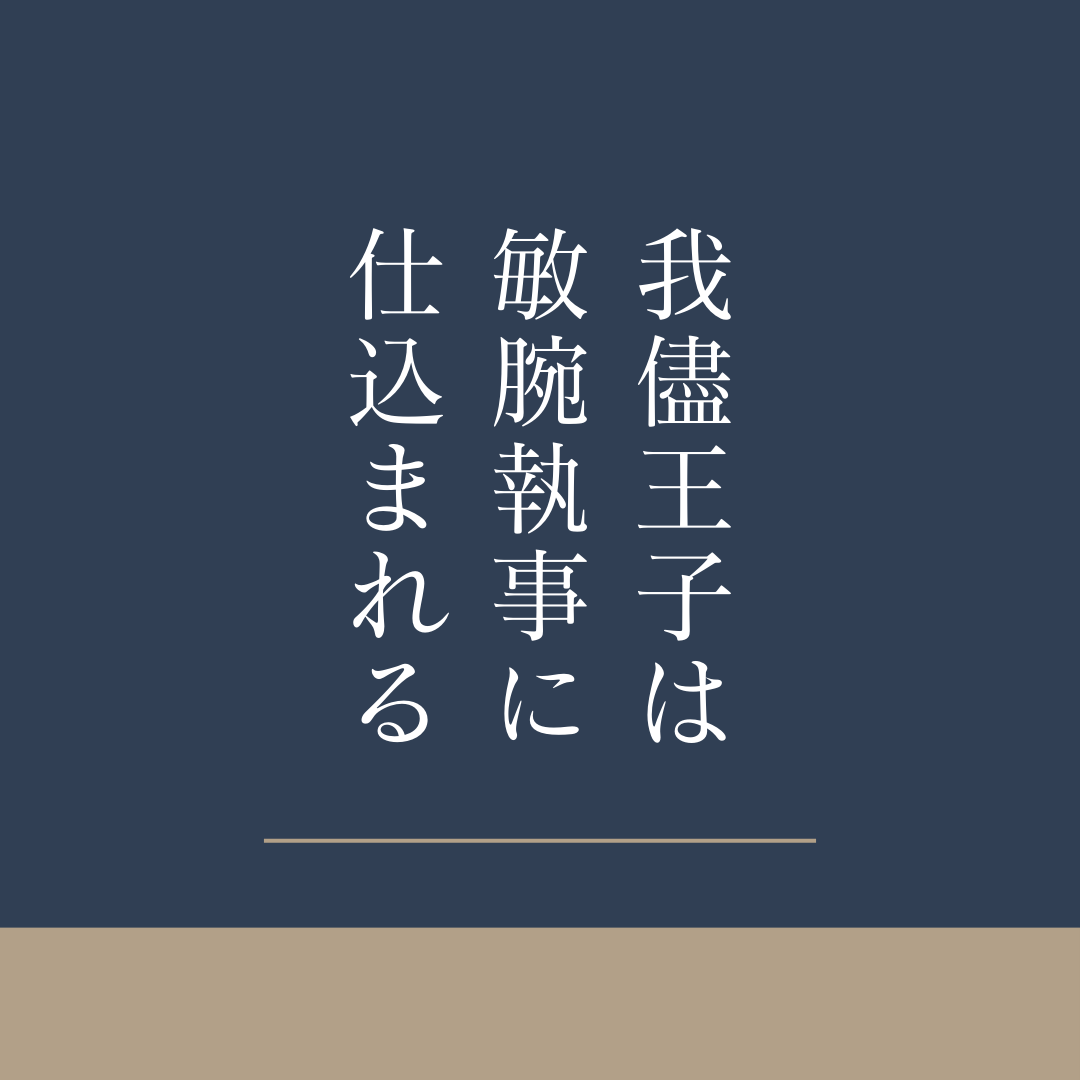

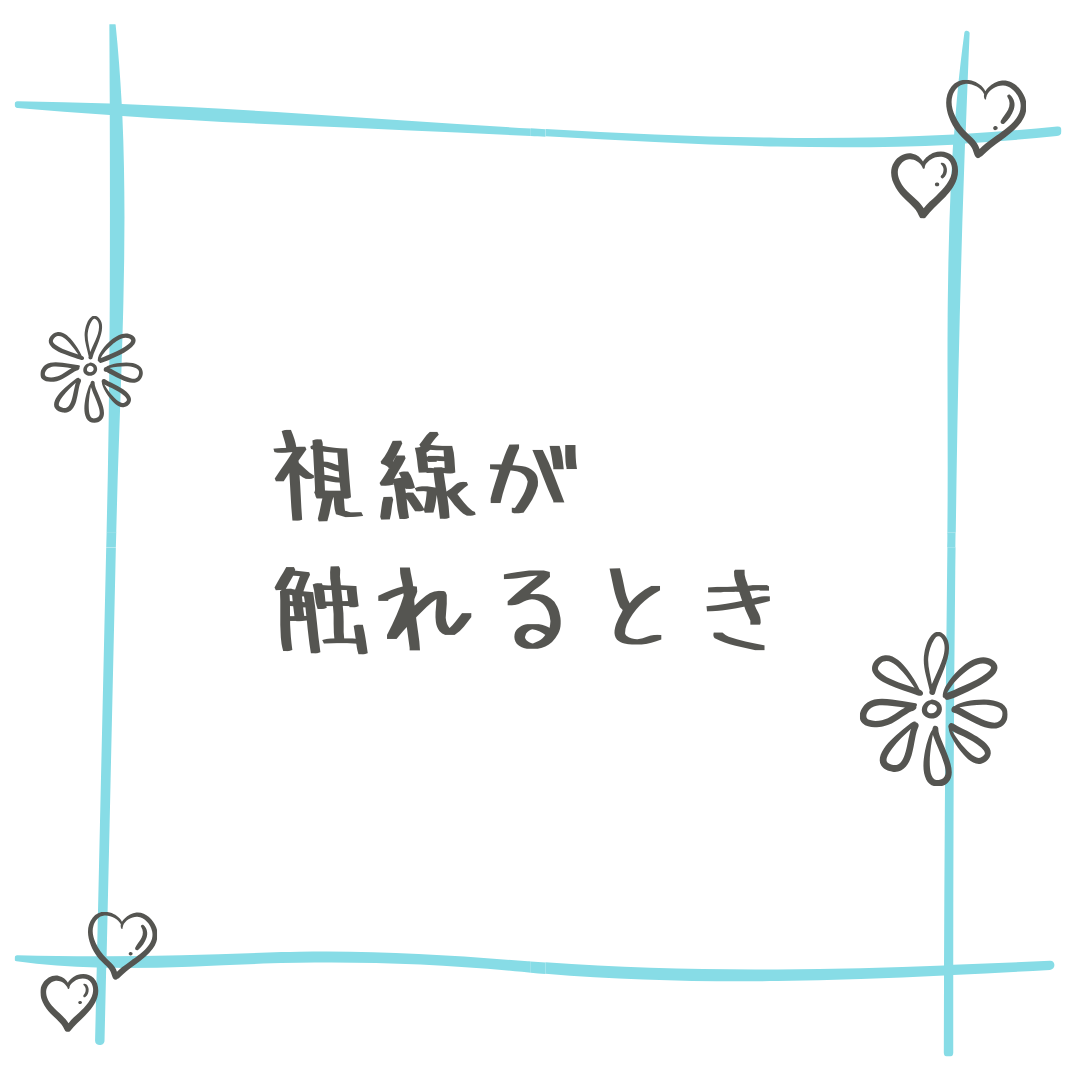



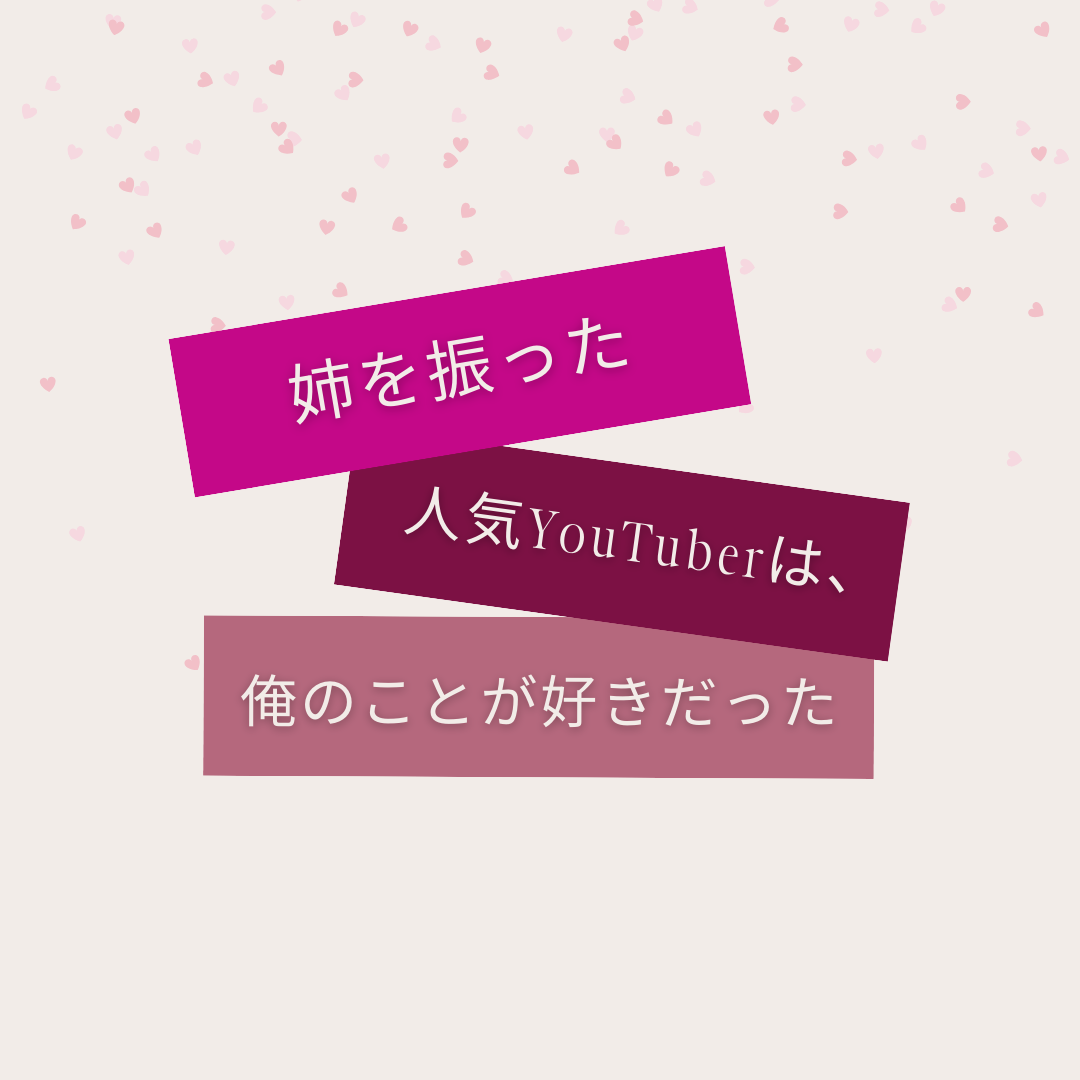








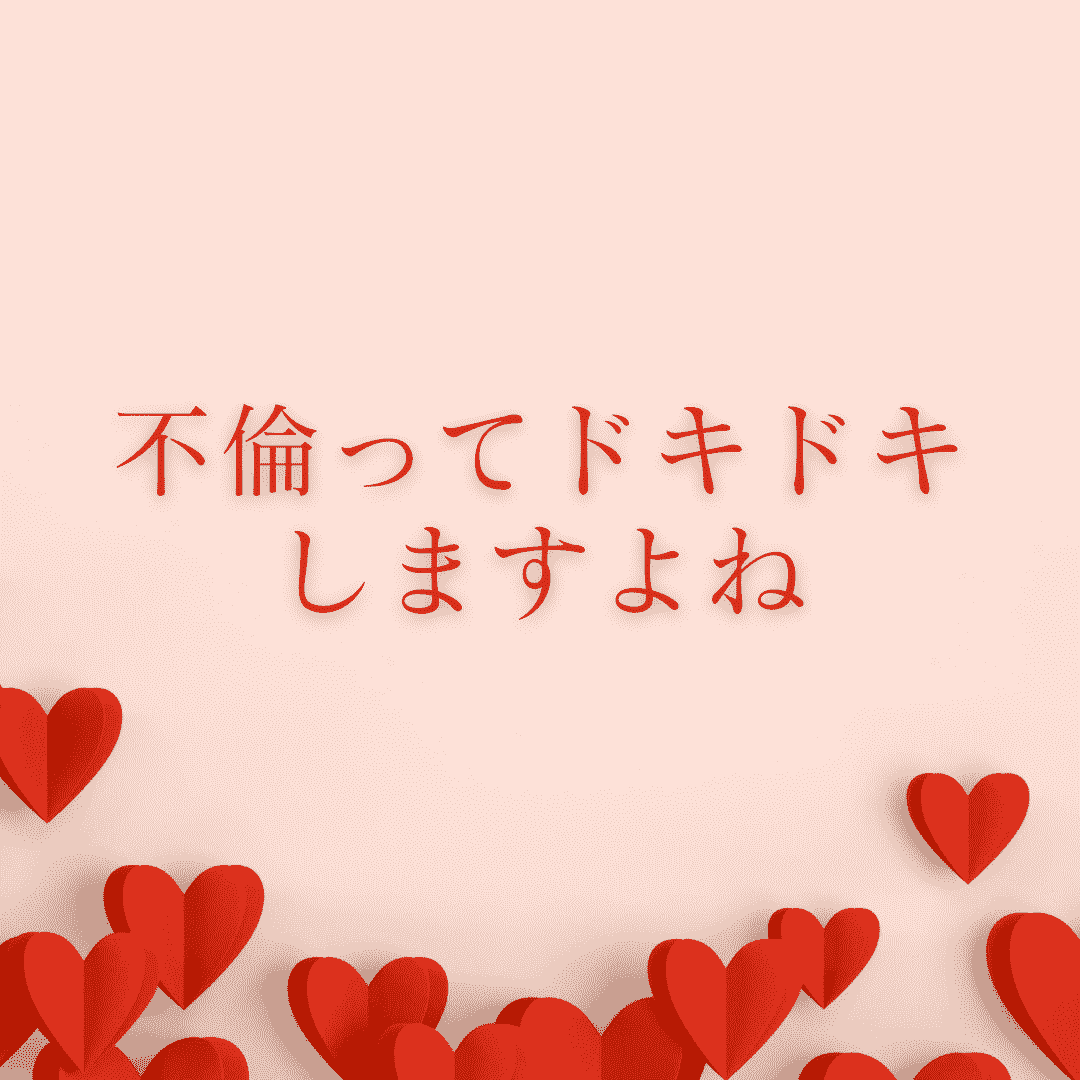




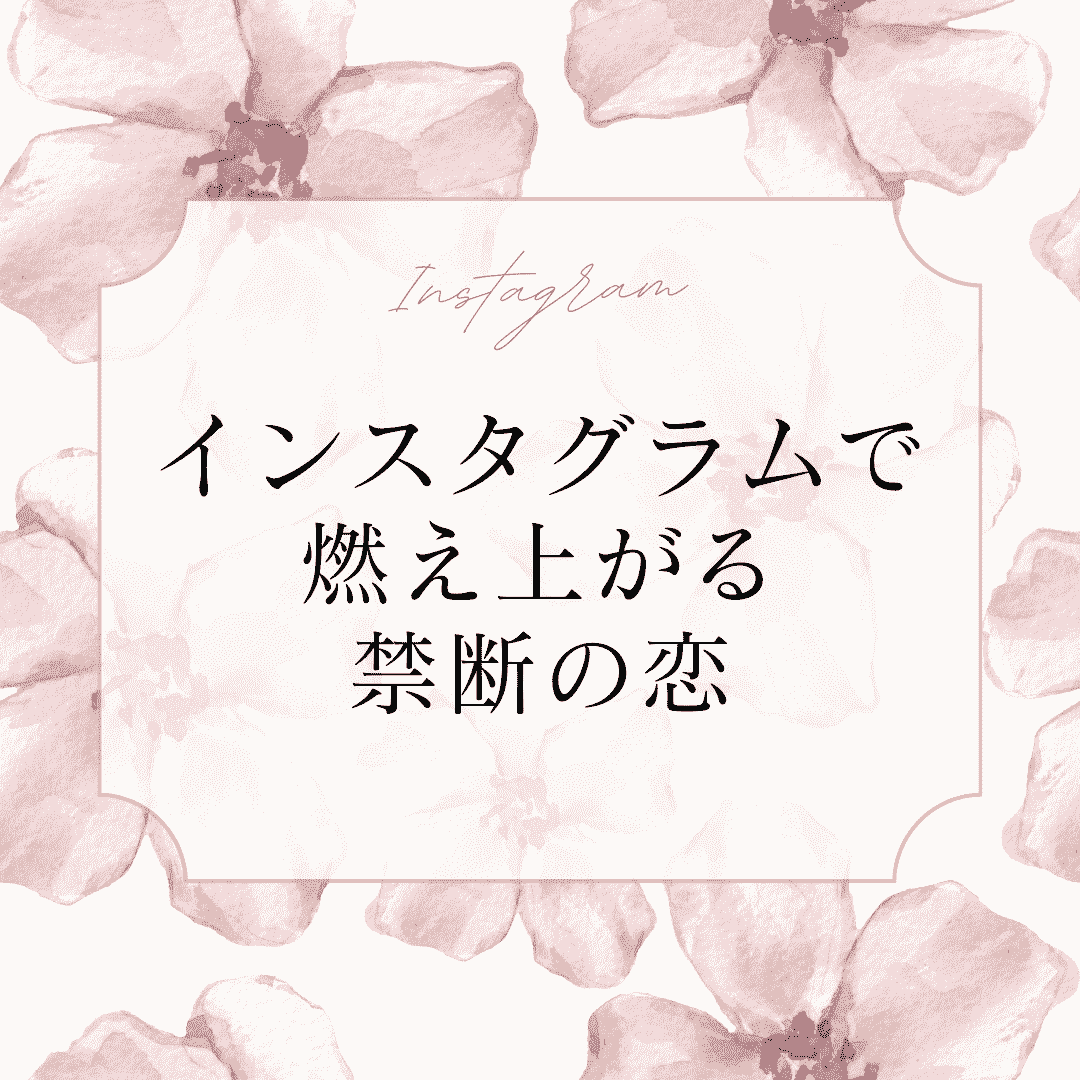






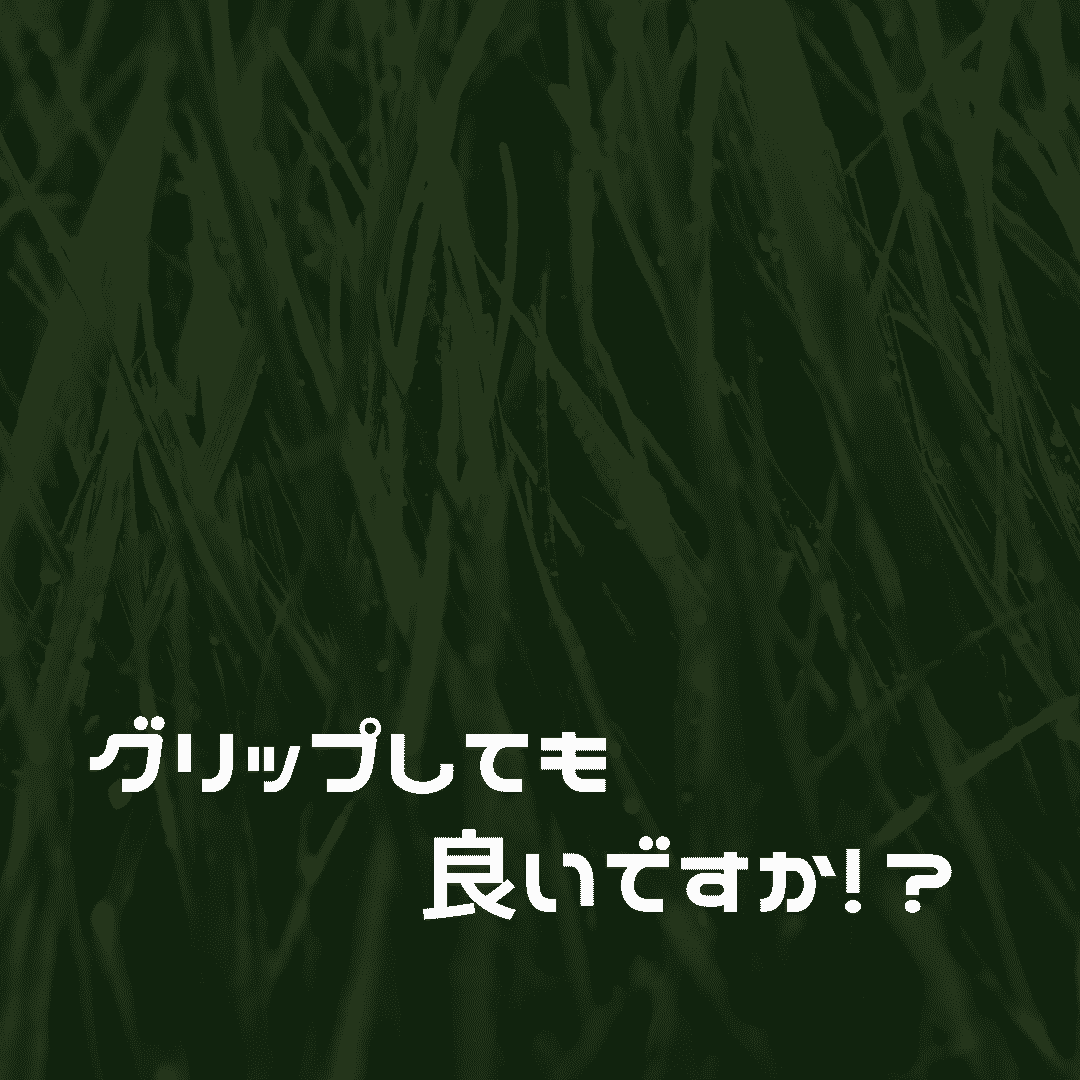

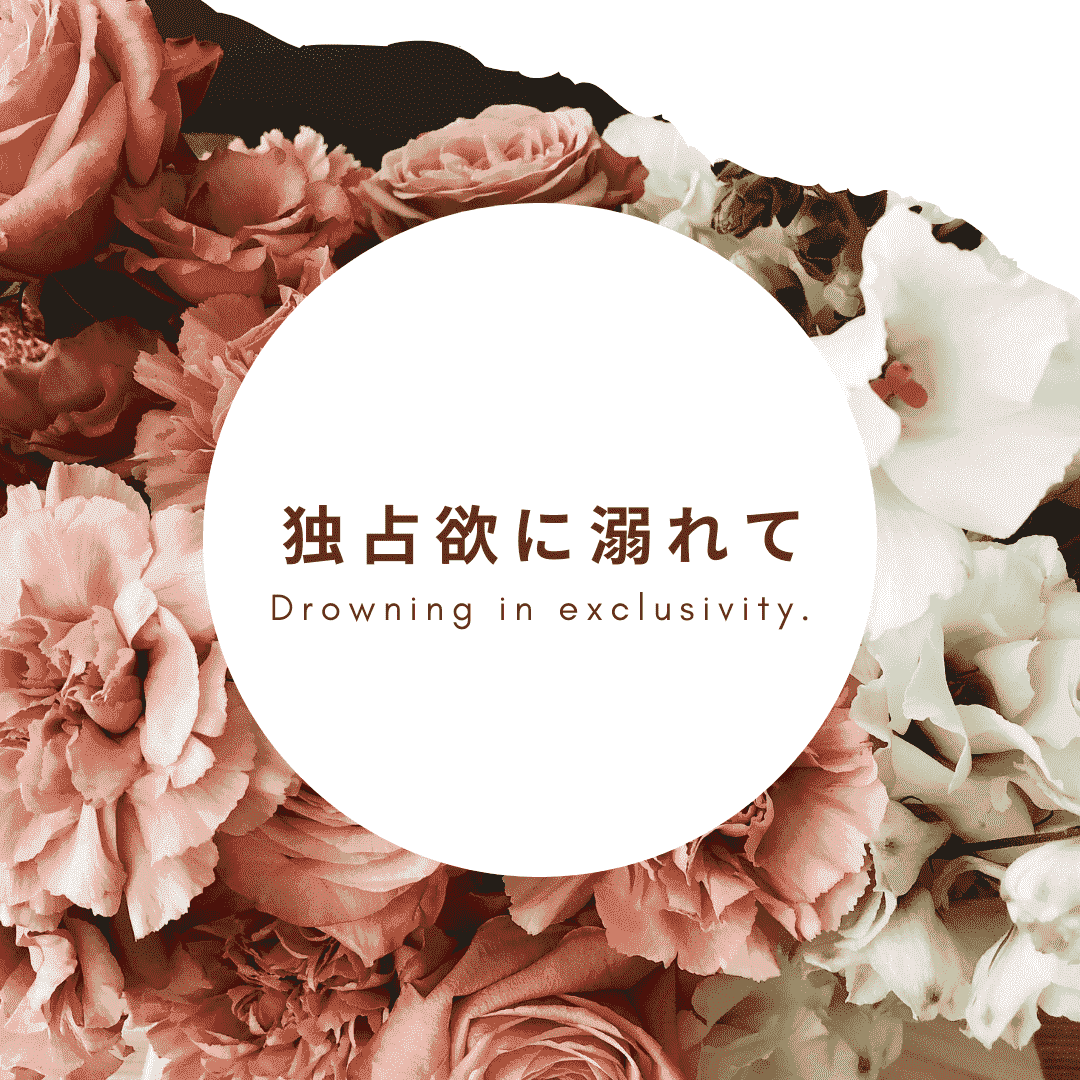
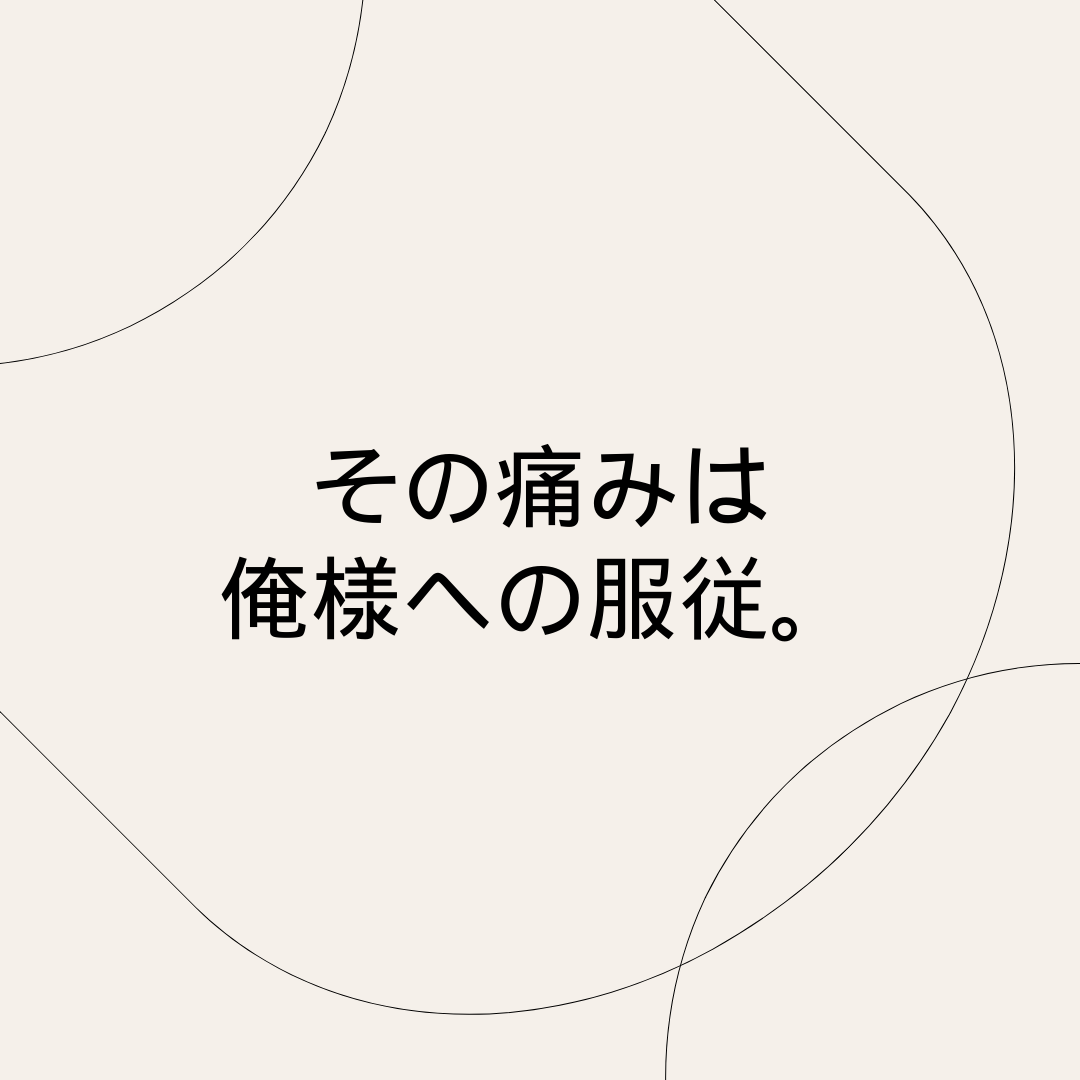
コメント