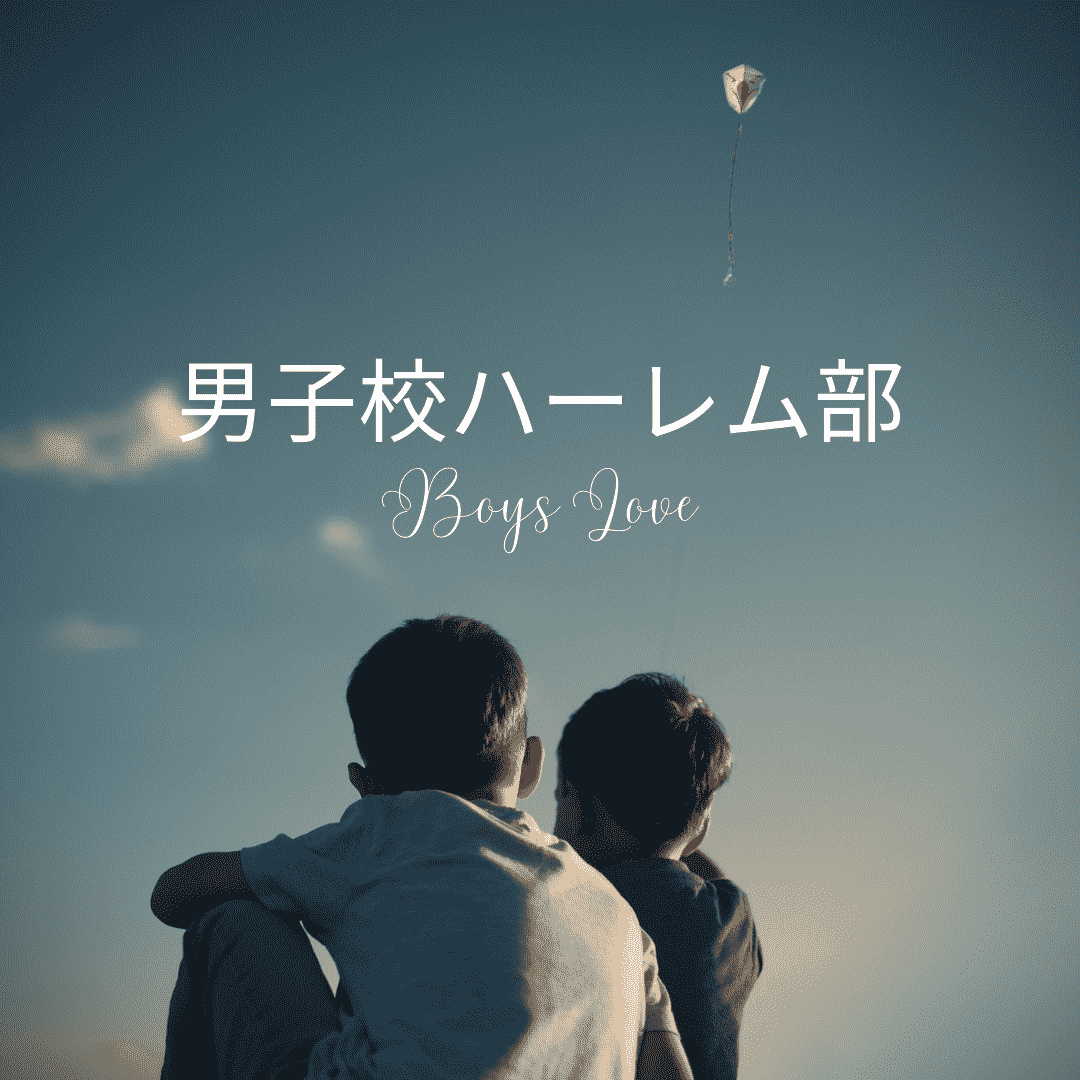
0
男子校ハーレム部
「ハーレム部?」
「そうだ。ここにくるのは初めてか?」
「初めてです……もう、何が何だか。」
180cmを超えている俺がおろおろとしている姿は、周りから見たら滑稽だろう。ハーレム部をまとめているという山畑と名乗る男が、愉快そうに笑った。山畑の周りには、女の子と見間違えるくらい華奢で可愛らしい顔をした男が3人、三角座りをしている。まるで異世界に迷い込んでしまったかのような感覚。ここが、新しく転入してきた高校の日常なのか?
俺は父親の転勤で、2週間前に、その市で最も頭がいい私立の男子高校に転入した。初めての引っ越しやら転入やらで、落ち着く暇はあまりなかったが、先生もクラスメイトもすごく優しくて、いい学校生活のスタートを切ることができた。
授業が全部終わった後、入部する部活を見学しようと校内をぶらぶら歩いていた時、気になる教室を見つけてしまったのだ。教室の扉に貼られている紙には「癒されたい人歓迎! 和気あいあいとした部活です」と書かれていた。癒し、といえば茶道部か華道部だろうか。確かに花や温かいお茶はリラックスできそうだ。そう思って扉を開いた途端、とんでもない光景が目に飛び込んできた。すけすけのベビードールを着た可愛らしい何人もの男の子が、ふわふわとした大きめのラグの上に座っているだなんて…。びっくりしないわけがない。
「お前まだ名前聞いてなかったな。なんて言うんだ?」
「江崎、です。」
山畑に聞かれてそう答えると、足元に男の子が1人寄ってきた。すりすりと俺のズボンに擦り寄り、ズボンの匂いを吸い込んでいる。
「あの、この子は……」
「そいつはアスカ。匂いフェチで、この教室入ってきたときから、ずっとお前に釘付けだったぞ。」
「アスカくん。」
「江崎くん、いい匂い……」
アスカと呼ばれた子は、吸い込まれそうなくらい、大きな瞳をしている。夢見がちな声で、俺の名前を呼んできて、思わず返事をしてしまった。
「あ、ありがとう。」
「江崎くん、舐めてもいい?」
「え?」
びっくりして思わず山畑の顔を見ると、山畑はなぜかにやにやと笑っていた。どういうことなんだこれは。状況がうまく把握できない。
「あの、舐めるって。」
「文字通りの意味。フェラしたいってこと。」
「ふ、ふぇら?」
「ハーレム部は、男の欲望を全部解放してくれる男子高校生が集まり、おもてなしする部活だ。癒されたい奴なら誰でも歓迎するぞ。」
「ハーレム部?」
「そうだ。思う存分楽しんでいけよ。」
「あ、あの、癒しってそんな……」
「江崎くん、あっち行こ。」
立ち上がったアスカくんに手を引かれ、さっそく教室の奥の方に置いてあるベッドに連れていかれた。そこの端に座るように言われ従うと、膝をついたアスカくんが、俺のズボンのベルトに手をかけた。かちゃかちゃと音を立て外され、一気に下ろされて下半身が寒くなる。
「ん……」
俺のまだふにゃふにゃしているものに鼻を近づけ、匂いを嗅いでいる。うっとりしていて、まるでいい香りのする花を嗅いでいるみたいな顔。実際に嗅いでいるのは、俺のふにゃチンなのに。
「これ、舐めていい?」
こんなに可愛い顔に上目遣いで聞かれて断る奴なんて、果たしているのだろうか。まあ少なくとも、恋人がいない歴イコール年齢の俺には、到底無理な話だ。
「じゃあ、お願いしようかな。」
そう言うと、すぐにちんこがあたたかいものに包まれた。そのまま先端をちろちろと舌で刺激され、思わず声が漏れる。
「うっ、やば。」
「ふほひい?」
「気持ちいってこと?」
ちんこを口に含んだまま喋るアスカくんに聞くと、こくこくとかわいい目をした小さな顔を縦に振った。
「ああ、すごくいい。」
するとアスカくんは、嬉しそうに目を細めて笑い、またぺろぺろと先端を舐め始める。小さな口の中で俺のちんこはむくむくと大きさを増していく。充分に大きくなったそれはアスカくんの喉に到達し、ぐぼぐぼと卑猥な音が鳴り始める。
「江崎くん、おれもなんかしたい~」
アスカくんの口と喉を堪能していると、お尻から何かが出ている男の子が近づいてきた。よく見るとそれは猫のしっぽのような形と色をしている。おそらくお尻に、挿しているのだろう。
「う……っ、き、君は?」
「おれはミイ。猫みたいでしょ?」
「たしかに、猫のミイ、っていそうだな……あああッ」
いきなりちんこを強く吸引され、恥ずかしい声が漏れてしまう。口しか使っていなかったはずのアスカくんが、いつのまにか右手も使いながら、俺のちんこを刺激し始めた。やばい、あっという間に出てしまいそう。すぐに出てしまわないよう、隣に座ってきたミイくんを見つめ、気持ちを紛らわせる。少しだけ吊り目なのが、猫っぽい気がする。手を伸ばして頭を撫でると、嬉しそうな顔をしてくれた。
「おれはなにしよっかなあ。」
「なんでも好きなことして。何かしてほしいことあればするし。」
自分でもびっくりするほどの言葉を発していた。そう言うと、遠くの椅子に座っている山畑がおかしそうに笑う声が聞こえてきた。我ながらこの場に馴染むのが早すぎる。
「じゃあ江崎くん、おれのここ、触って……」
そういって、ミイくんがシャツを脱ぎだした。尻尾以外何も纏っていない状態のミイくんは艶かしくて、同じものがついているとは思えないくらい、興奮する。俺の手を取り、ぷっくりしているピンク色の乳首に持っていった。
「ここ、触って……んあっ、きもち……っ」
試しに指の先でカリカリと触ると、ミイくんはすぐに甘い声を漏らした。少し触っただけでこうなるなんて、かなり敏感な体質なのだろう。それか誰かに開発されたか……そうであれば、ここでしっかり、ミイくんの乳首を開発してくれた誰かに、感謝したくなった。
俺が乳首をいじればいじるほど、ミイくんはとろとろの声を出し、小さなちんこが膨らんできている。そうこうしているうちに、ちゅぱ、と大きめの音とともにアスカくんの口から俺のちんこが抜き出された。
「んあ……っ、アスカ、くんっ、それっ……つかっていい?」
「いいよミイくん、もう出ちゃいそうなちんこ、入れてもらって。」
アスカくんがそう言うと、ミイくんは素早くベッドの上で、四つん這いになった。
「江崎くん、後ろの尻尾外して……なかにおっきいの、入れて。」
「お、俺、童貞なのに」
「いいから入れて。好き勝手、乱暴でもいいから。」
とろとろの声で話しながらミイくんがお尻をゆらゆらと揺らしている。もうたまんねえ、こんなの我慢するなって言う方が無理だ。アスカくんが渡してくれたゴムの袋を開け、震える手で初めてゴムをちんこに被せていく。
初めてだったのもあり、少しもたついてしまったが無事に被せ終え、ミイくんについている尻尾を軽く引っ張ると、それはにゅるんっと簡単に抜けた。ベッドの端っこにそれを置き、腰を掴みがちがちになったちんこを、さっきまで尻尾が生えていた場所にゆっくりと入れていく。
「ん……うぅっ……」
ミイくんの甘い喘ぎ声、まじでえろい。暴発してしまいそうになるのを堪えながら、根元まで入れ、それから言葉通り、好き勝手腰を振ってみた。
「あっ、あっ、ああああっこれっ、ほしかった、おっきいのぉッ!」
腰を振り、肌と肌がぶつかるたびに、ミイくんは大きな声で喘いでくれる。手で扱くときの何倍もの気持ちよさに持っていかれそうになりながらも、必死に腰を動かしていると、後ろから抱きしめられた。
「……っ、アスカ、くん?」
「僕はミドリ。ね、いっぱいキスしよ?」
ミドリと名乗った男の子は俺の隣に移動し、顔を近づけてきた。ミイくんの小さな穴にちんこを出し入れしながら、さくらんぼのように可愛らしい色をしたミドリくんの唇に、自分の唇を重ねる。
ちゅ、ちゅ、とまるでぷるぷるのゼリーに口付けているような感覚。一瞬俺の口が開いた隙に、ぬるりとミドリくんの舌が入ってきた。舌を絡ませ合うとぴちゃぴちゃと卑猥な音が鳴り始める。腰を打ち付ける音と舌が絡み合う水音が混ざり合い、ただの教室がどんどん淫靡な部屋に姿を変えていった。唇を離そうとしても舌を絡めてくるのをやめてくれず、舌を絡ませ続けていると、ミイくんの喘ぎ声が大きくなった。
「んあっあっ、も、おれイっちゃ……っ!」
ちんこを突っ込んでいるなかが細かく震えだした。唇を無理やり離し、腰を振ることに集中すると、すぐに強い締め付けがきた。
「ぁああんっ、あッ……ぁあッ!」
一際高い声を上げたミイくんは、四つん這いの姿勢を崩し、ぐったりとベッドに倒れ込んでしまった。
「ミイくん、大丈夫 ︎」
︎」
びっくりして声をかけると、後ろからとんとんと肩を叩かれた。振り向くとアスカくんが俺の後ろにべったりくっついていた。
「大丈夫。ミイくんいっぱい中イキしちゃっただけだから。」
「中イキ?」
「ちんぽじゃなくって、お尻のなかでイっちゃうこと。僕にもそれしてくれる?」
そう言ってアスカくんは寝転がり、自ら脚を開いて、既にぐちゅぐちゅになっている穴を見せつけてくれた。
「も、もちろん……」
次々とかわいい男の子が俺にセックスをせがんでくる。なんという楽園。ハーレム部という名前もぴったりだけど、楽園部とかに変えても良さそうだ。
アスカくんの太ももを掴み、まだ射精していないちんこを挿入していく。アスカくんのなかは、ミイくんのそれよりもふわふわとしていて、人によってこんなにも違うものなのか…と内心驚きながらも、ゆっくりと腰を動かしていく。
「ぁうっ、ん……んぅっ……」
アスカくんの喘ぎ声はミイくんよりも大人しく、控えめな声。お淑やかな喘ぎ声なのに、自ら脚を開いておねだりしてくれたというギャップがたまらず、思わずガツガツとなかを刺激してしまう。
「江崎くん、僕のちんぽもいっぱいよしよしして?」
さっきまでキスしていたミドリくんがアスカくんの薄い胸の上に跨り、俺と向かい合わせになる。ミドリくんのかわいらいい色をしたちんこに手を伸ばし、軽く擦ると、ぷるぷると震え出した。
「んっ、えさき、くっ、んああっ、気持ちいいッ!」
「あっ、あっ……なかっ、とろけちゃ……ふぁあッ!」
ミイくんとアスカくんの喘ぎ声が重なり、どんどん興奮が高まり、全身から汗が噴き出してくるのを感じる。
「ん……うっ、ちゅ、んむ……っ」
さっきまで絶頂しすぎて横たわってしまっていたミイくんが、俺の背中に抱きついてきて、首の後ろにちゅっちゅと愛らしい音を立ててキスしている。
「はあ、はあっ、あっ、僕もう出ちゃいそ……っ!」
ミドリくんがはあはあと息をし、限界が近いことを教えてくれる。
「んむっ、イ、イくときっ、ちゅー、してたいっ」
顔が近づいてきて、手を動かしながらもミドリくんと唇を重ねる。れろれろと舌を絡ませていると、手にぶちゅ、とミドリくんの精液がかかった。
「はあ……あっ、きれい、にっ……するからあっ」
アスカくんの胸の上から降り、ベッドの横に座ったミドリくんは、俺の手にかかった精液をちゅぶちゅぶと啜ってくれている。…とんでもない光景だ。
「えさき、くんっ、僕のも、さわ、って……!」
中を小刻みに震わせているアスカくんにお願いされ、ミドリくんが綺麗にしてくれた右手でもうすぐ破裂してしまいそうなくらい膨れたちんこを刺激し始める。
「あっ、あ……んっ、えさき、くっ、さいこおっ、だいしゅき……っあ、でるっ!」
びゅくびゅく、と中を強く締め付けながら、アスカくんが僕の手に射精した。それと同時に、なかの刺激で俺も薄いゴムに精液をはきだした。
「はあ……はあ……っ」
アスカくんが息を整えているうちに、ちんこを抜いた。そのままティッシュで拭こうとすると、後ろからミイくんが首に手を回してきた。
「最後はおれに綺麗にさせて?」
「ああ、ありがとう……」
ミイくんはベッドから降り床に膝をついて、射精したばかりの俺のちんこを、アイスキャンデイを食べる時のように舐め始めたのだ。
「あ……ミイくんそんな舐め方されたら、またっ」
「いいよ。この綺麗になったちんぽで、何回戦でもシよ?」
「おれまだ、なか挿れられてないもん。」
「まだイけるよね、江崎くん?」
後ろからも前からも横からも囁かれ、再びちんこが復活してしまう。俺の性欲が完全に満たされるまで、まだまだ時間がかかりそうだ。





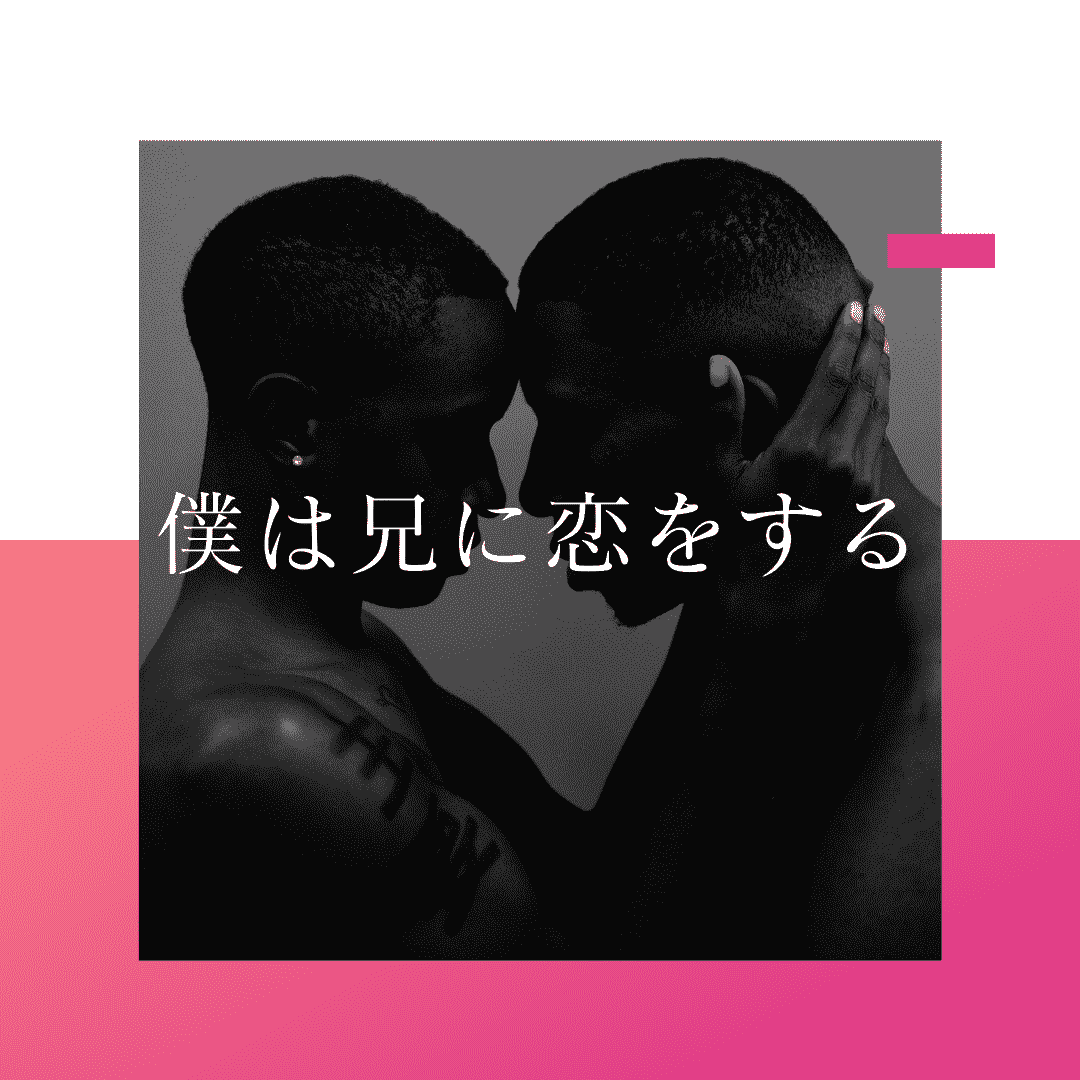



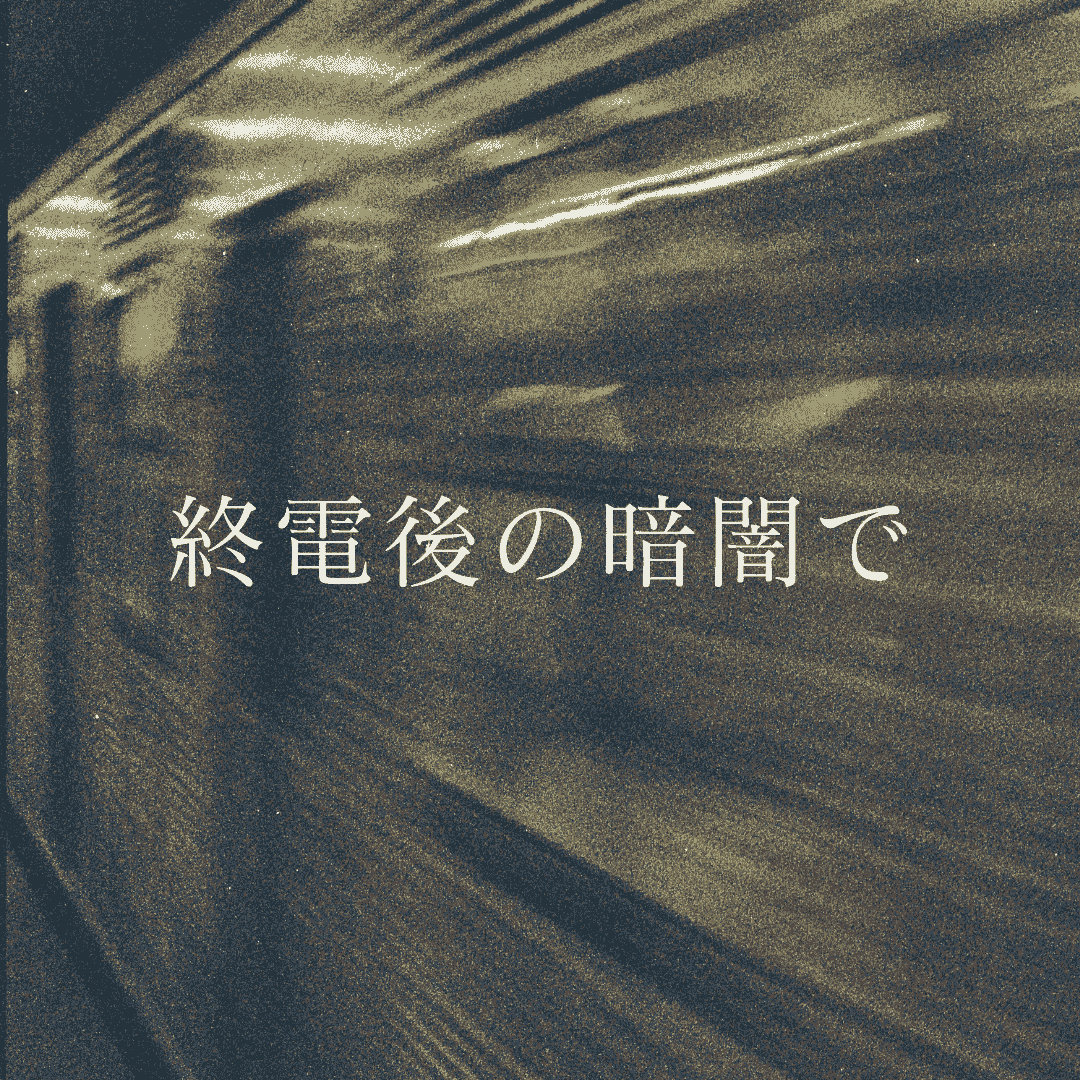
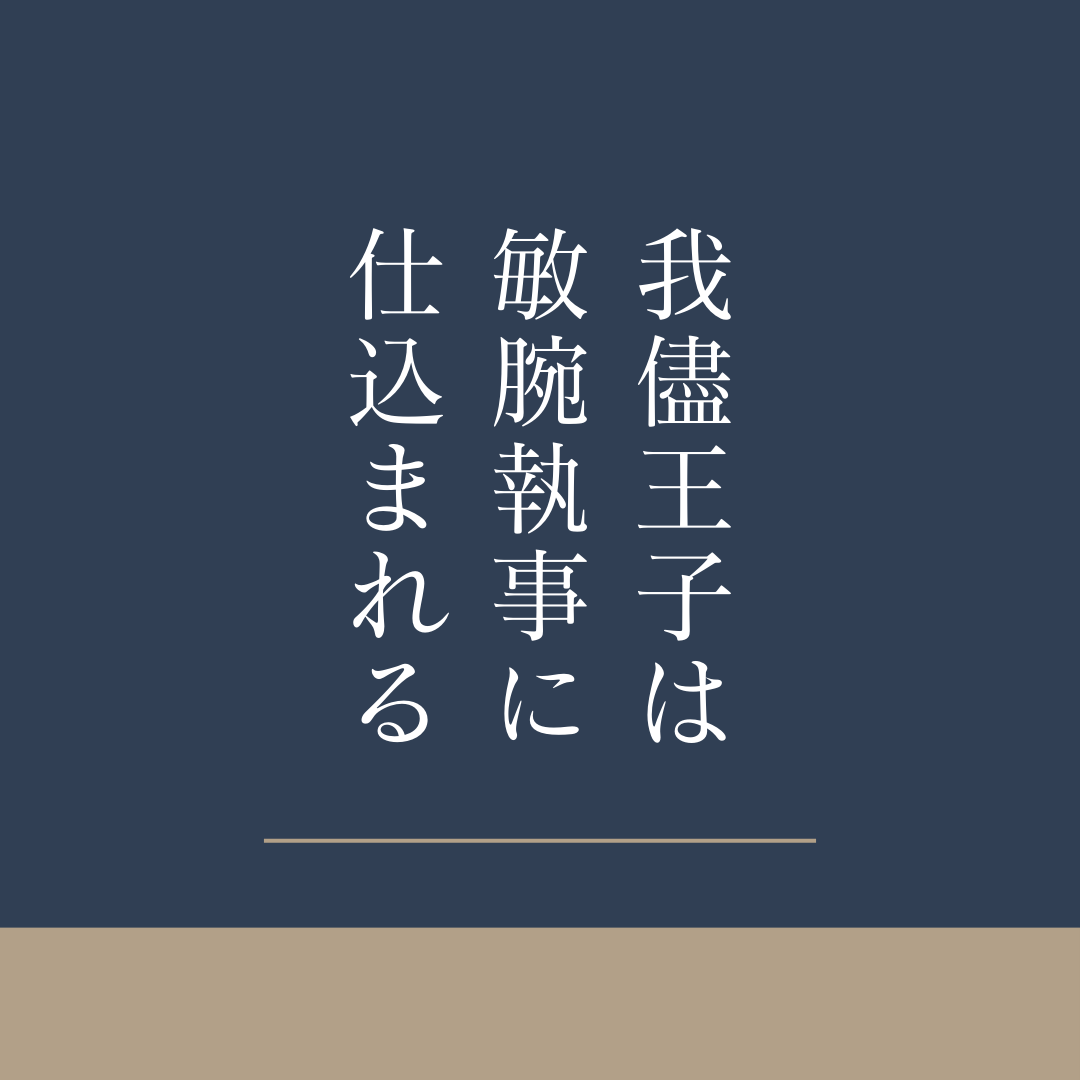

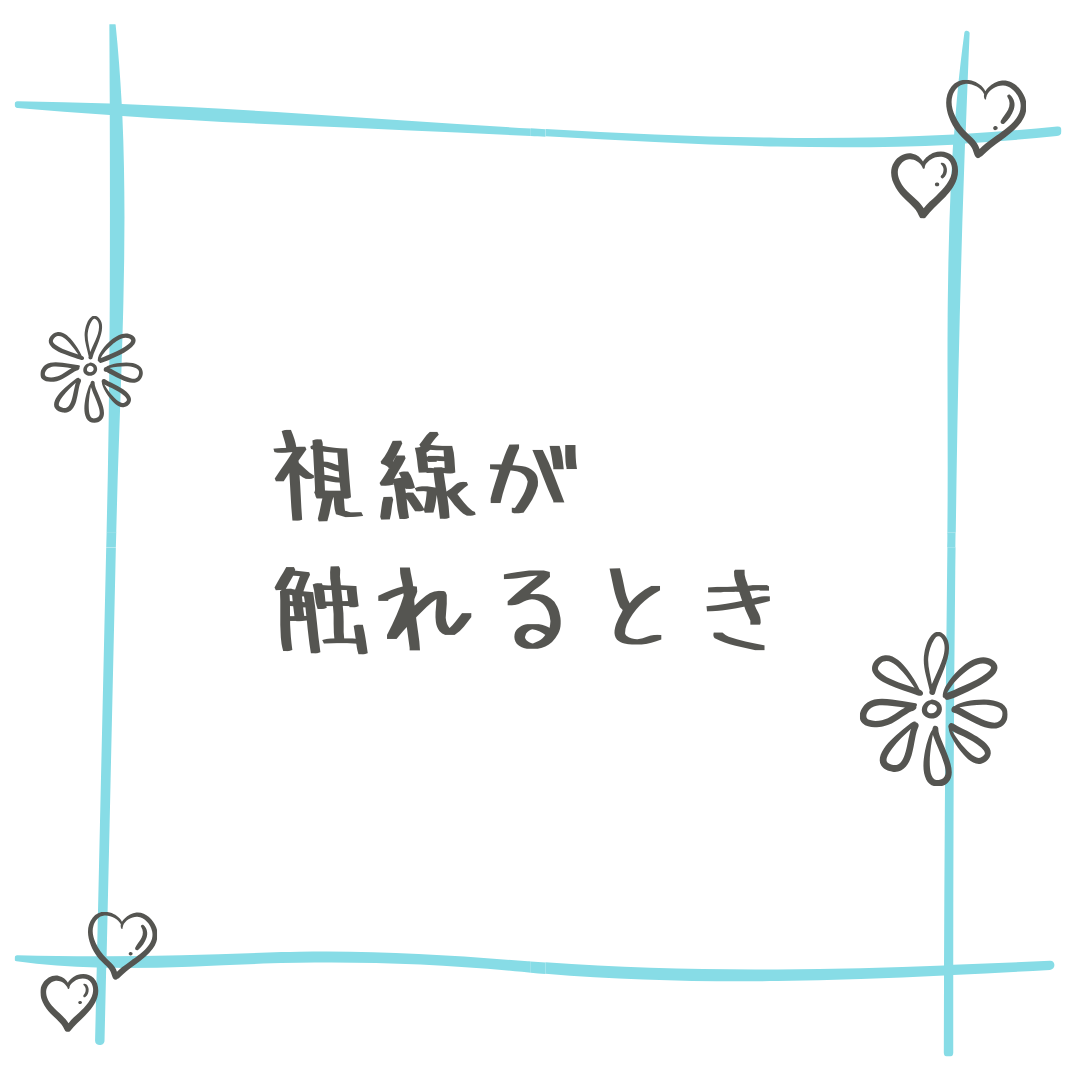



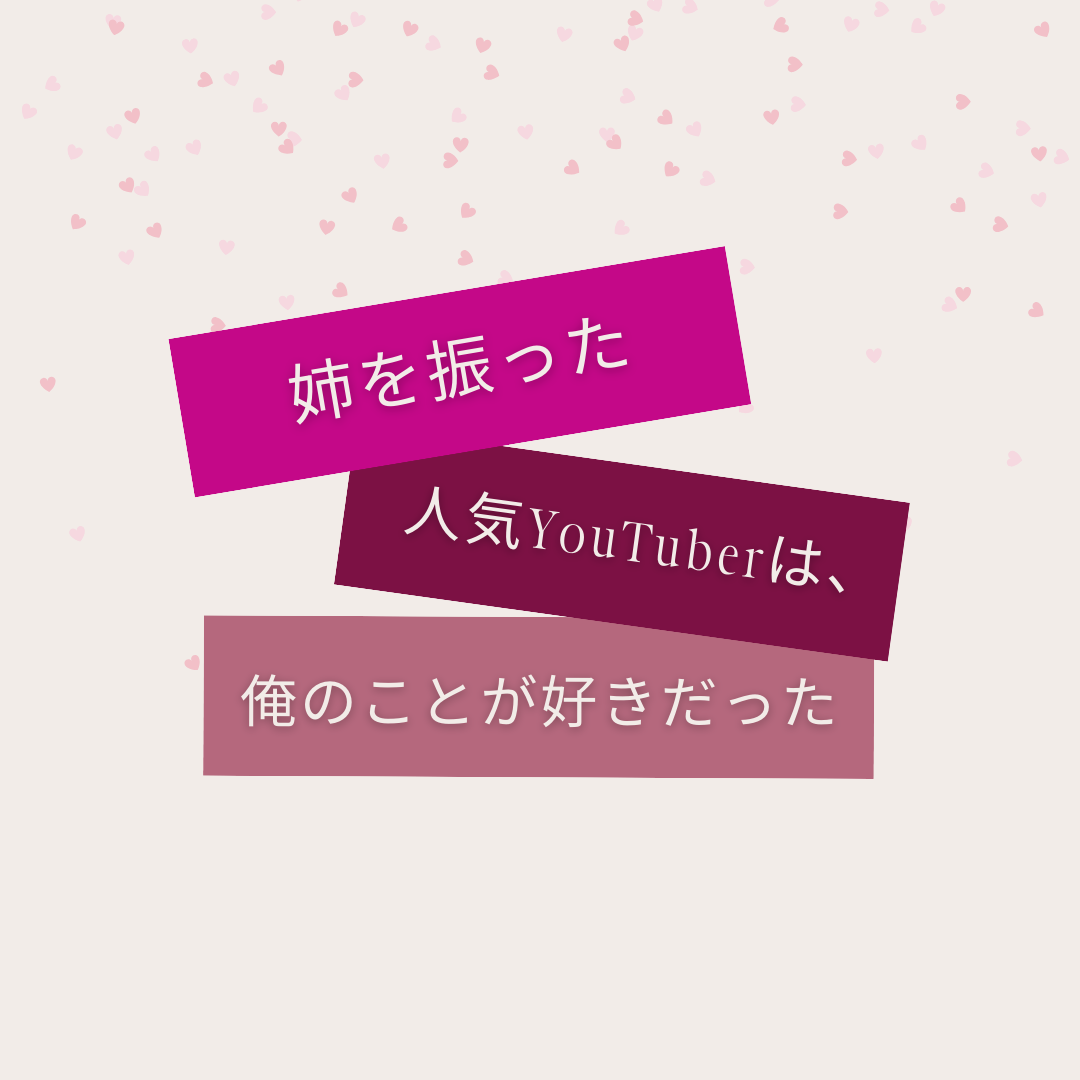









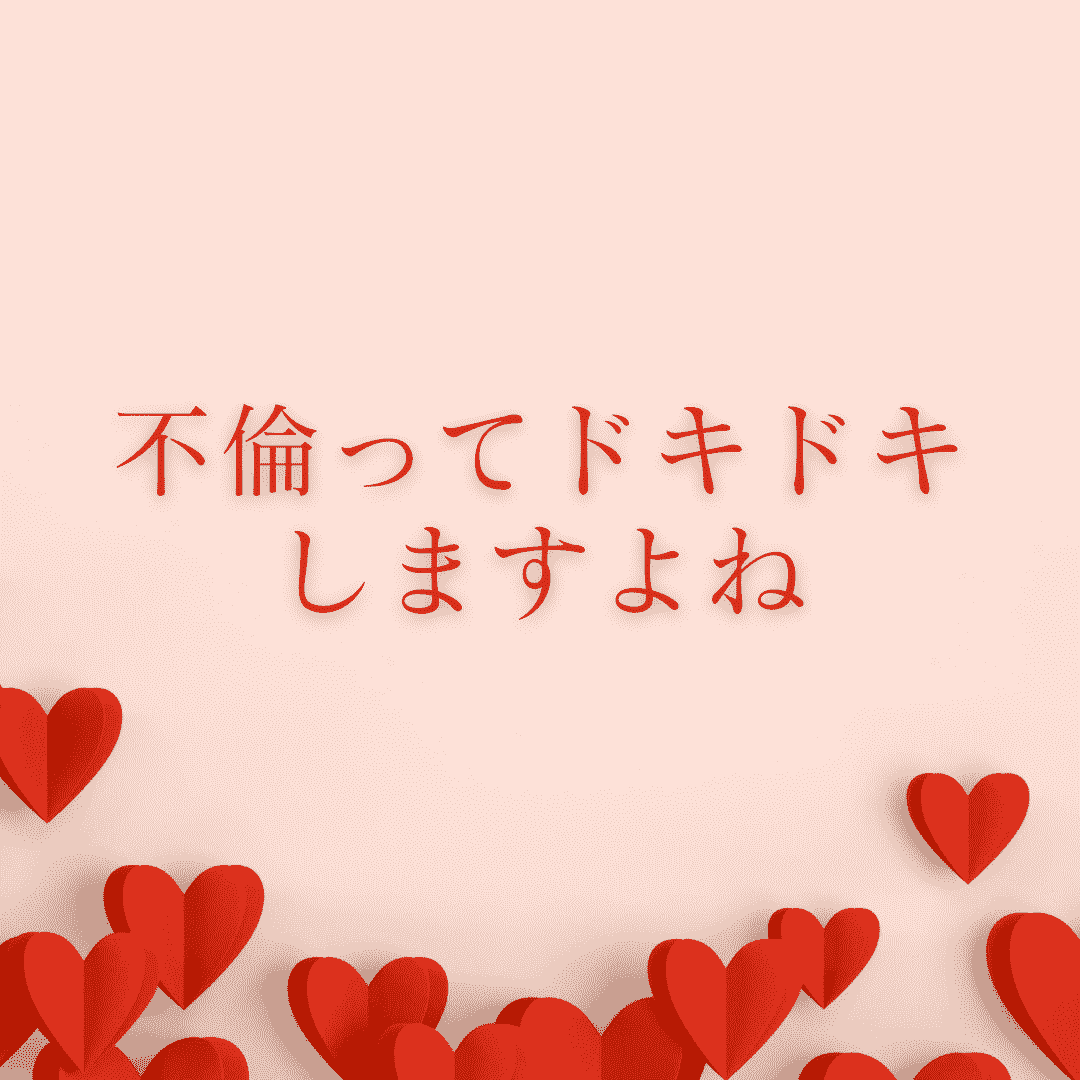




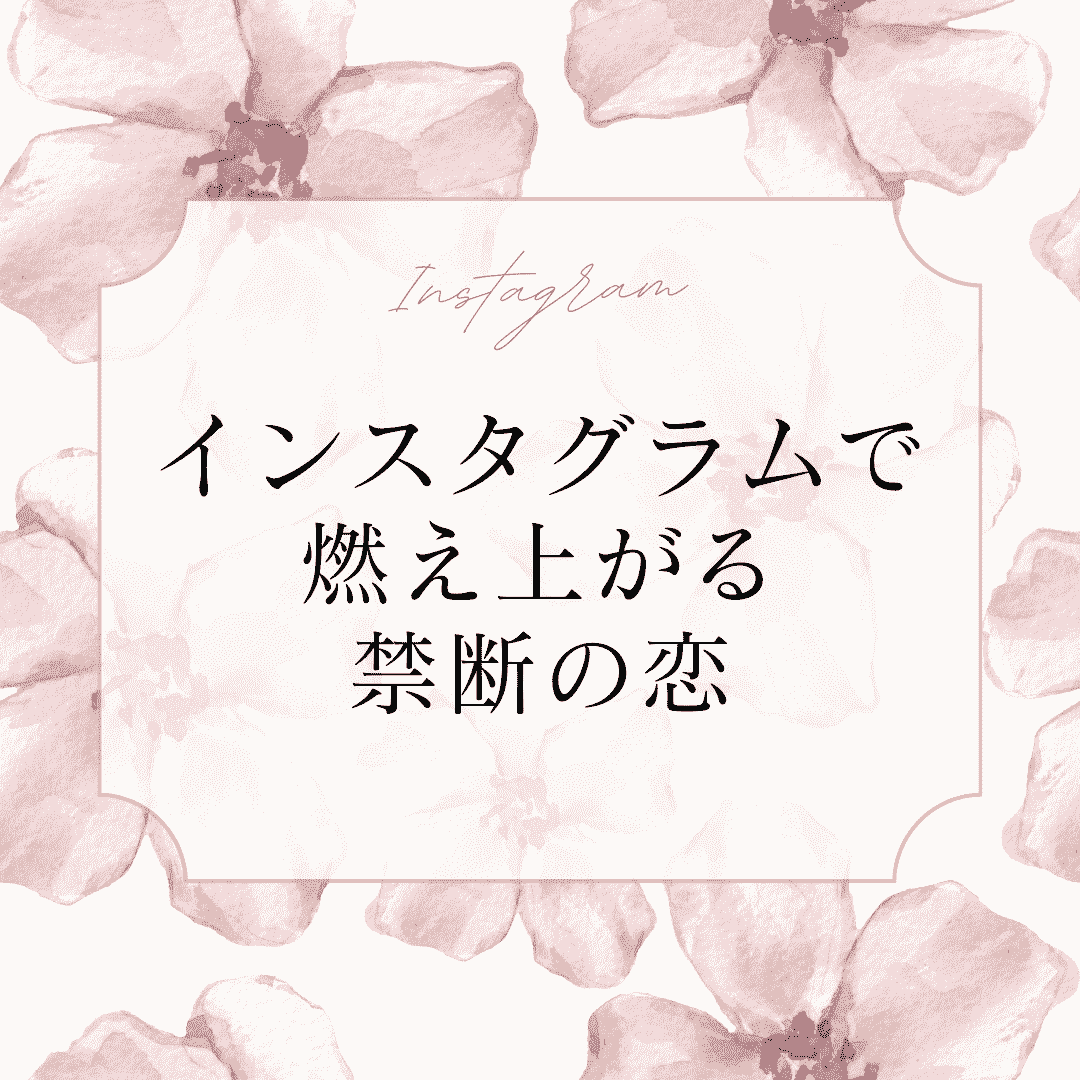

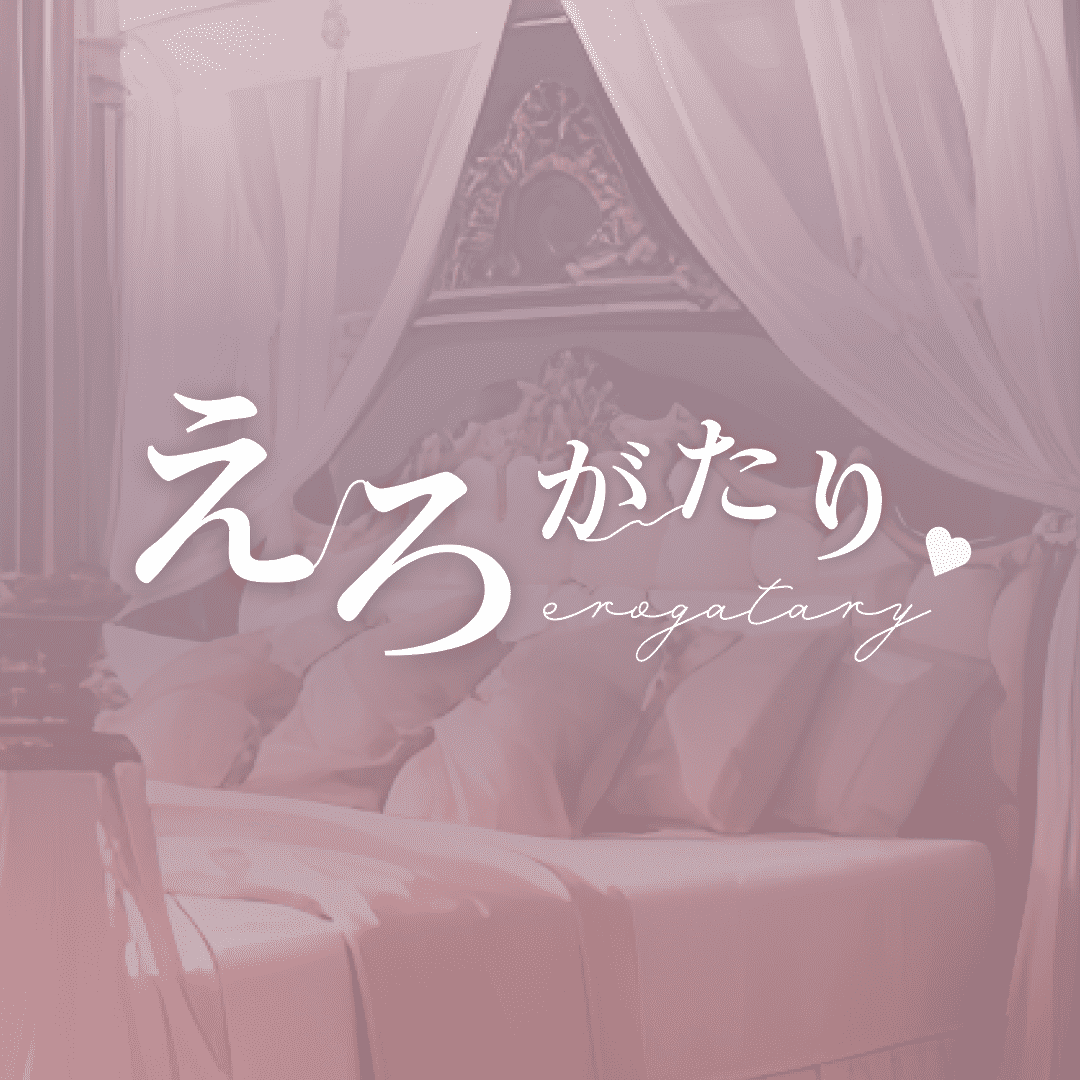





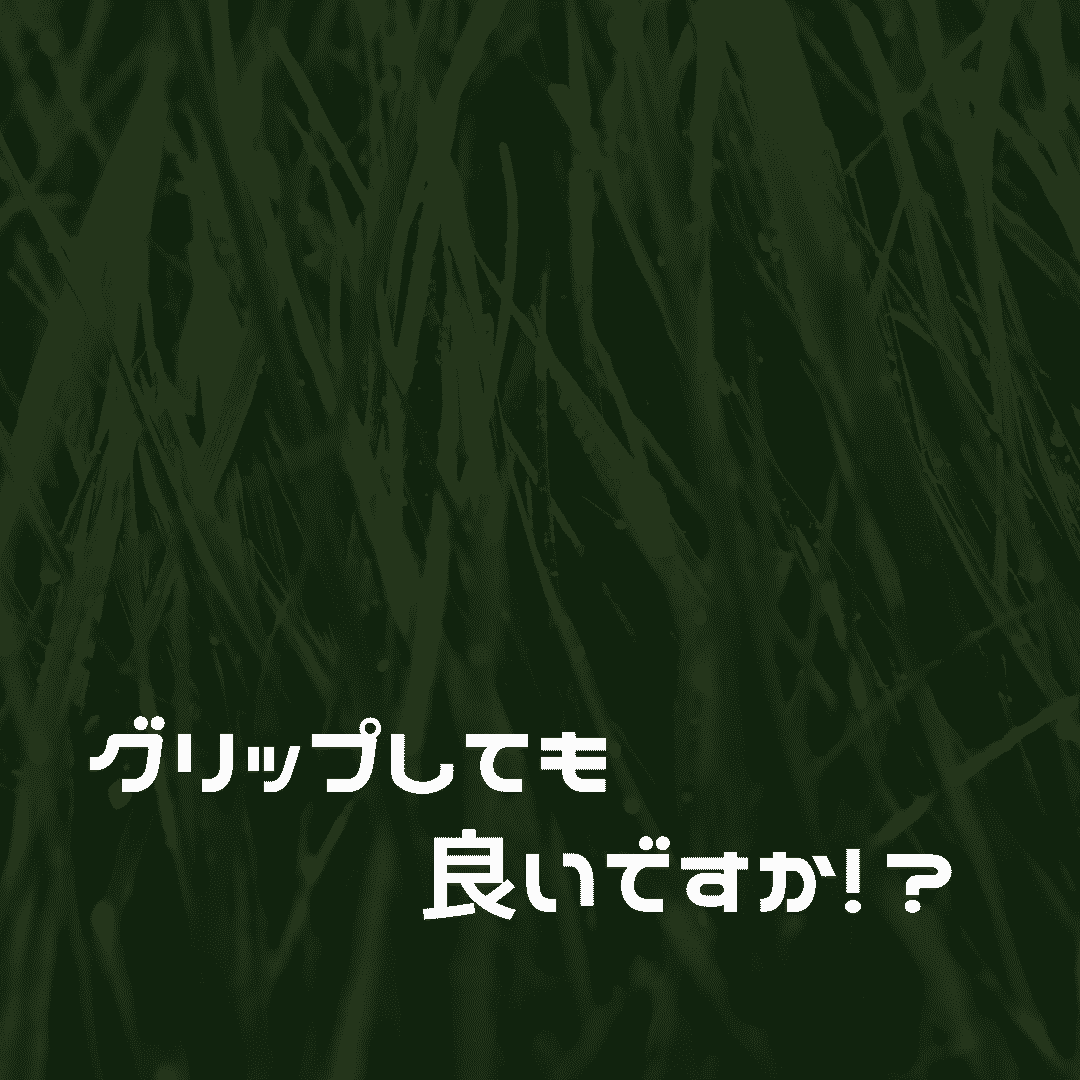
コメント