
0
真夜中のスイーツ・パティシエ
「じゃー今日もたっつんが夕飯担当な。」
「おっけー、カズキは?何時あがり?」
キッチンと洗面所にお互い立ち、それぞれ別の作業をしながらでも会話が成立するぐらい、狭いアパート。二人はいつものように、朝のルーチンに勤しむ。
「あー俺、今日17時なんだけど、そのあと厨房借りて練習してから帰るわ。」
「了解、そっちのコンテストはもうすぐだもんな。」
「そ、来週末だから。いよいよって感じ。」
カズキは身支度を終え簡単に洗面所を掃除し、たっつんこと、タツキのいるキッチンへと向かった。
「ほい、今日の昼飯。タコライスー。」
そして目の前に差し出された、タータンチェックのランチョンクロスに包まれた弁当箱を、両手で受け取る。
「うお!ラッキー!お前のタコライスだけは旨いんだよなぁー」
「だけは余計だっつーの」
背中にゆるい蹴りをくらいながら、カズキは弁当箱をそのままリュックにしまうと、玄関へ向かった。
いってきまーす!という声とともに、パタンと閉じる。その音を聞きながら、タツキはさっきまでカズキがいた洗面所へ向かい、洗濯機を開けた。そして、脱ぎ散らかされているカズキの洗濯物を次々と中へ放り込む。全ての洗濯物を入れ終えると、一番上に乗っていたカズキの下着を取り上げた。暫くそれを見つめたあと、無言で静かに抱きしめて、思い切り息を吸った。
「……はぁ、何やってんだ俺。」
邪念を追い出すように何度か頭を振ると、そのままボスッと下着を洗濯機に押し込み、スタートボタンを押した。
2人が製菓専門学校で出会ったのは4年前。数少ない男子の製菓希望ということもあり、仲良くなるのにそう時間はかからなかった。最初は友情の延長だったと思う。しかし、いつの頃からか……
偶然にも同じ製菓メーカーに就職した二人。それだけでも十分嬉しかったのだが、そこの伝統でもある『一人前になるまでは同期と共同生活』という時代錯誤のルールに則り、奇跡的にも同じ部屋に決まった時は、興奮して3日くらいまともに眠れなかった。
しかし、恐らくこの夢のような生活も、もうじき終わりを迎えてしまう。お互いいつかは一人前になるということは、頭では分かっているが…なかなか決心がつかないのも、また事実であった。
「さ、俺もぼちぼち出かけねーとな。」
気持ちを切り替えるように大きな声でそう言うと、タツキも、自分用に作った弁当を鞄につめこみ、部屋を後にした。
「迷っているねぇ、青年。」
中途半端に飾り付けられた数多のカップケーキに埋もれながら試行錯誤を繰り返していると、上から声が降ってきた。カズキがハッと顔を上げると、そこには腰に手を当てて、ニコニコと微笑む社長の顔があった。
「わっ、社長!すみませんお疲れさまです!」
「うんうん、いいよ。ごめんね、僕も集中を切らせるようなことをしちゃったね。」
そう言いながら社長は、カズキが中途半端に放ったカップケーキを取り上げ、ひとかじりした。
「……まだ少しコアントローがきついねぇ」
「そうなんす。スミレの色を鮮やかにしようとするとどうしても……」
「今回のテーマは?真実の愛だっけ?」
「えぇ、奇をてらってスミレを思いついたまではいいんですけど……なかなか。」
そう言って肩を落とすカズキに、社長は笑いながら背中を叩いてきた。
「君が真実の愛を見つけたら案外うまく行くかもねぇー」
「いや、俺が見つけても……」
なんて、苦笑しながら、カズキは小さく息を吐く。
「最後の鍵は案外そういうところにあるもんだよ、戸締りだけよろしくねー」
間延びした声を残したまま去っていく社長に、慌ててあたりを見回すと、時計の針は21時を回っていた。
「やべっ」
カズキは短くそう叫ぶと、慌てて後片付けを始める。とりあえず試作したケーキを片っ端からタッパに詰めると、そのままリュックに放って店を出た。
「真実の愛なんてなぁ……」
セキュリティをかけながら一人呟く。本音を言えば、そんなものはとうの昔に見つけていた。しかし、決して実らないその想いを、深く深く胸の底に封印して、うわべだけ取り繕った美しさを追及したところで、きっとハリボテのものしか出来ないのだろう。
「だけど、もし、今あいつがいなくなったら……」
初めて出会ったあの時から、ずっと近くで笑ってくれている顔が、ふと脳裏に浮かんだ。
「今、タツキを失ったら俺は多分なんもできんくなる。」
そう呟くと、カズキは帰路を急いだ。
「悪い、遅くなった!」
「お、お帰りー。お疲れさん。」
部屋に入るとカレーのスパイシーな匂いが鼻腔をくすぐった。
「手洗ったら手伝うよ。」
「さんきゅー」
二人で手早く支度を整え、遅めの夕食を取る。その日あったよしなしごとを報告しあう時間が、カズキにとって何よりの癒しになっていた。
「これ、試作?」
夕食を終え、順番に風呂に入っていたタツキが、タオルで髪の毛を拭きながら、ダイニングテーブルに並べられたカップケーキを見つけた。
「そう、ちょっと今日終わらなくてさ。続きやろうと思って持って帰ってきた。」
「大変だなぁー。にしても、相変わらず綺麗な出来だよなぁーこれスミレ?」
「そう、でもなかなか思うような色が出なくてさー。もうちょっとハッキリした色にしたいんだけど……」
デコレーションだけでも決めてしまおうと、バタークリームを絞り袋に入れながら、カズキは思い出したように慌てて口を開いた。
「あ!でもたっつんそれやめとけよ!酒めっちゃ入って……」
「ん?」
しかし、時すでに遅し。タツキは口いっぱいにカップケーキを頬張り、次の瞬間とろんとした目つきになり、突然笑い出したのだ。
「アハハハハ!!なんかカズキが目の前にいるんだけどウケる!」
腹を抱えて笑うタツキに、カズキは頭を抱えた。酒にめっぽう弱いショコラティエなんて、聞いたことがない。しかし、タツキは完全なる下戸だった。
「マジおもろい。最高。」
そう言いながらゲラゲラ笑って、次々にカップケーキに齧り付く。
「やめろって!明日残るぞ!」
慌てて残りのケーキを取り上げると、不服そうにタツキは唇を尖らせる。しかし、カズキの顔を見るや否や、パッと笑顔になった。
「あ!なんだクリームあるじゃん!」
「え?」
先ほどタツキからカップケーキを奪ったときに手に持っていたバタークリームが、頬についたらしい。タツキはカズキの首に飛びつくと、そのままペロンと頬を舐めた。
「んー。あまーい!」
「お、おい!」
突然のご褒美に、カズキは顔を真っ赤にしながらタツキをはがそうとするが、それよりも強い力でしがみつき、クリームがついていた箇所をペロペロと舐め始めた。
「んー終わっちゃった。じゃあ、次こっち。」
むぅ。とむくれたあと、タツキはあろうことか、そのまま流れるようにカズキの唇に噛みついた。
「んっぐ」
ビリビリと全身を電流が走り抜けたかのように、カズキの肌が粟立つ。
「んぅ……んっ、んー---!あまぁいねぇー」
ギュウギュウと唇を押し付けたあとプアッと音を立てて唇を離すと、タツキは艶めかしい眼差しでカズキを見つめ始めた。その視線に、カズキの頭の奥で、何かがブチッと切れた音がした。
「クソッ……」
タツキの腕を縛り上げ床に押し倒すと、そのまま深く口づける。
「んっ……ふぅ」
酷く甘いタツキの唇はバタークリームのせいか、それとも……
「んっ……あ、ぁ」
角度を変えながら深く唇を重ね、その隙に器用にタツキのパジャマのボタンを外していく。露わになった肌は風呂上りのせいか、暖かく強烈に良い香りがした。
「ひっぅ……ああっ」
ぷっくりとかわいらしくピンクに主張する胸の突起に吸いつけば、頭上で甘い声が響く。吸い上げる度に固くなるそこに、カズキは笑いながら唇を離した。
「気持ちいいの?」
「んっ……うぅ。ん…きもちぃ……そ、そこ。おいしいの?」
「あぁ、すっごい甘い」
「ふふっ……っ、ああっ、んっ……うぅ」
カズキの返事に、タツキは満足そうに笑う。そして、再び与えられる刺激に、身を捩らせた。酔っているせいなのか、素直に反応して見せるタツキに気をよくし、カズキは更に大胆に彼の身体をまさぐり始める。乳首を舌先で弄びながら更に手を下へと伸ばし、スエット地のゆるいウエストゴムから、右手を侵入させた。
「もう、勃ってんじゃん。」
すぐに主張を始めたタツキのペニスに指先が触れ、カズキは満足そうに微笑んだ。
「んっ……だって、きもち…ぃ」
恥じらうようにそう囁くタツキに、カズキは溜まらずもう一度深く口づけた。
「ね、もっと触っていい?」
「ん……」
タツキのペニスをゆっくりとしごき上げる。
「っ、あっ、あっ……んああっ!」
緩急をつけて撫で上げれば、タツキの先端からは愛液が次々とあふれ出し、下着を汚していくのだった。
「ビショビショになっちゃうから脱いでおこうな。」
「あっ、う……ぁ」
下着の中の籠った熱が解放され、温度差のある外の空気がまた刺激となり、タツキの身体が小さく跳ねる。グシュグシュと卑猥な音はいっそう大きくなる。カズキも自分自身が、下着の下で大きく主張を始めているのに気付いた。
「なぁ、俺もいいか?」
「へ?……ああっ!!!」
トロンとした顔のまま、カズキの言うことが理解できないとでもいうように、小首を傾げて見せる。ところが次の瞬間、感じたことのない快楽に、タツキは大きな嬌声を上げてしまった。
咄嗟に下を向けば、カズキが、見たこともないような大きさの彼のペニスと、自分のを合わせて、しごく様子が見えた。
「うあっ……あっ、んっ、んっ……き、きもちぃ……ああっ!!」
「っく……あぁ、俺も……いいよ、なぁ、たっつん。いいか?」
ペニスをしごく手をそのままに、カズキはタツキの秘部へと指を這わせ、その入口を少しだけ押し広げてくる。
「んっ…!」
感じたことのない妙な感覚にくぐもった声を出すが、カズキの切なそうな表情に溜まらず、タツキはコクリと一度頷いた。その仕草に、カズキは安心したように深く息を吐いた。
「ちゃんと、ほぐしてから、挿れるから。」
そういうとテーブルの上においてあったバタークリームをたっぷり指につけると、静かにタツキの秘部へと侵入を始めたのだ。
「ふあっ……あっ、あっ!」
「ゆっくり、息して」
「あっ……んっ、ふっ……うぅ…」
タツキの呼吸に合わせて、カズキの指がゆっくりと抜き差しされる。違和感しかなかったそこは、次第に熱を帯び始め、タツキの声に色が戻るまで、そう時間はかからなかった。
「あっ、あっ……んあっ!も、カ…ズキ、いれて…」
中途半端に強い刺激に、タツキは緩く頭を振ると、そのままカズキの首に腕を回し、口づけをした。
それまで大事にしていた秘部からカズキが指を引き抜くと、そのまま自身をあてがい、ひと思いに彼の中に侵入した。
「あああっ!!!」
弓なりに身体をしならせ、タツキはカズキの侵入を受け入れた。
「わりぃ、もう余裕ない。」
荒く呼吸を繰り返すタツキの腰をグッと掴むと、カズキはそのまま激しく自身の腰を打ち付け始める。
「んあっ、あっ、ああっ!!!んっ、き、きもちぃ…ああ、ダメいっちゃ……」
ジュグジュグと水音が大きくなるにつれ、タツキの中の快楽も、解放を求めて中心に集まる。
「んっ、うぅ……カ、ずき……きもち、ああっ、ああっ!!!ああ!でちゃ…でちゃうぅ…」
「あぁ、先に出させてやる。」
うわごとのようにそう繰り返すタツキの頭を優しく撫でると、そのままカズキはタツキのペニスを握りしめ、自身の律動に合わせてきつくしごいた。
「んあっ!ああっ、だめ……イく…いっちゃ……あああっ!!!」
ビュクッと音を立てて吐精すると、いっそうタツキの中がしまり、カズキ自身も引っ張られるように締めあげられたのだ。
「っく……あっ…うっ」
一瞬こらえようとするが、タツキの締め付けに負け、カズキもあっけなく達してしまった。
ハァハァと荒い呼吸を続けながら、二人は静かに見つめあう。どちらからともなく唇を重ねるとカズキは自分の下で、優しく微笑むタツキの頬を撫でた。
「好きだ。タツキ。ずっと前から。」
カズキの告白にタツキの瞳が大きく見開かれる。と、次の瞬間、花が綻ぶように満面の笑みを浮かべた。
「嬉しい。俺も大好き。」
その言葉にカズキもまた大きく笑うと、二人はまた深く口づけあった。
***
『若き天才パティシエ。フランスのコンクールで日本人初の優勝を勝ち取る!勝利のきっかけはテーマ通りの真実の愛!?』
ネットニュースのベタな見出しに、タツキは思わず吹き出してしまった。
「ただいまぁー」
間延びした大好きな声にスマホを放ると、そのまま玄関へと駆けていく。
「おかえり!」
さっきまでみていたネットの写真より、何倍もイケメンな本物にタツキは、笑いながらその首に飛びついた。





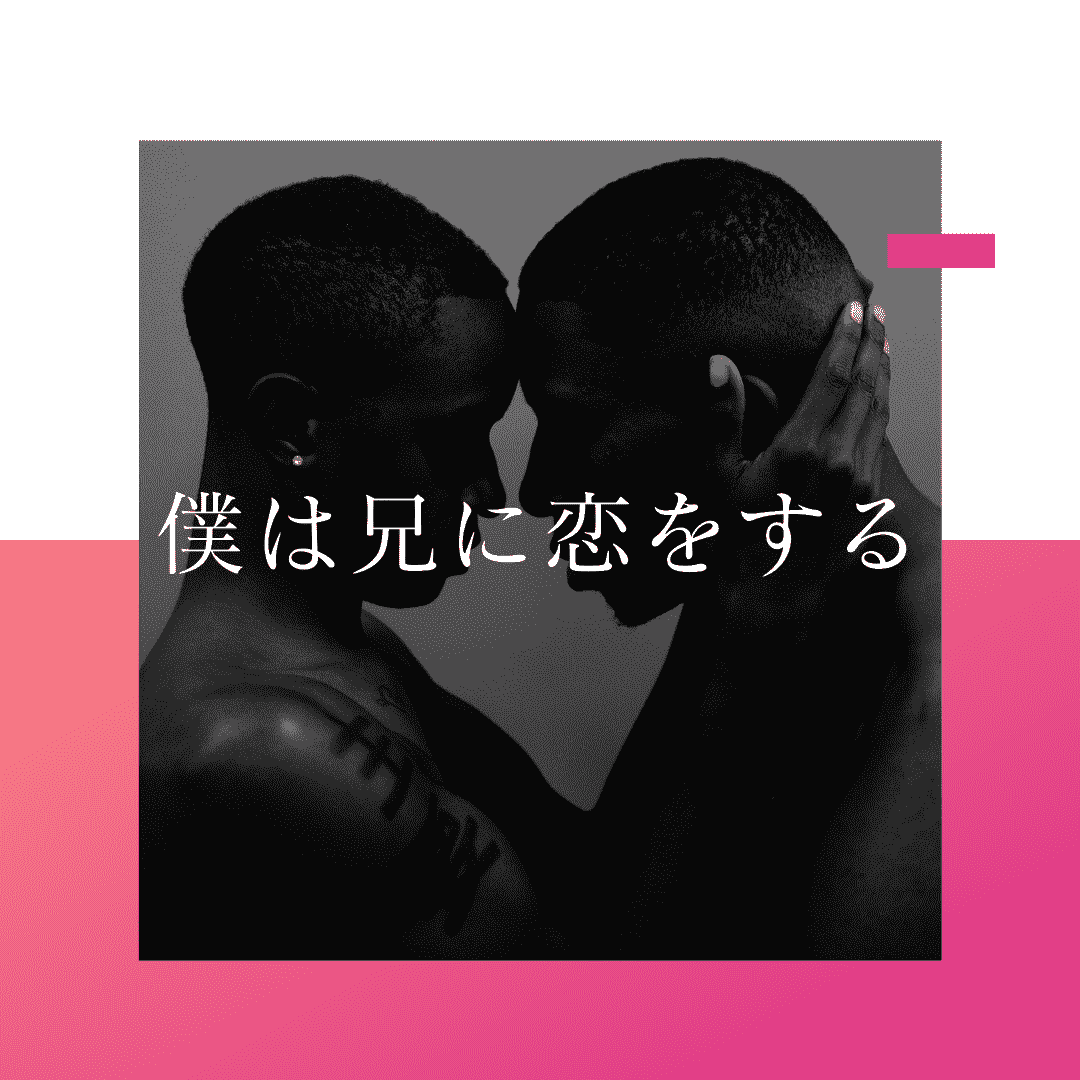



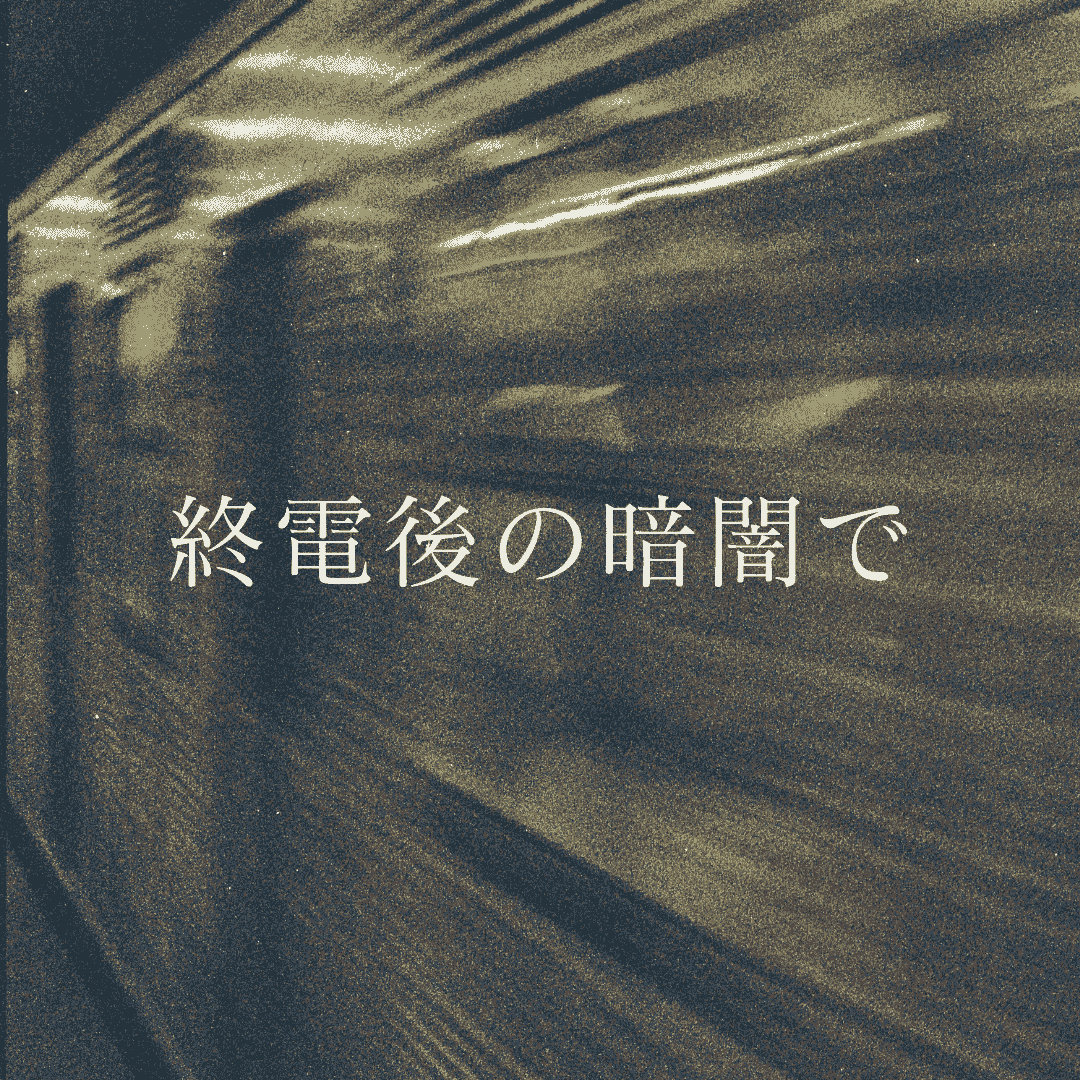
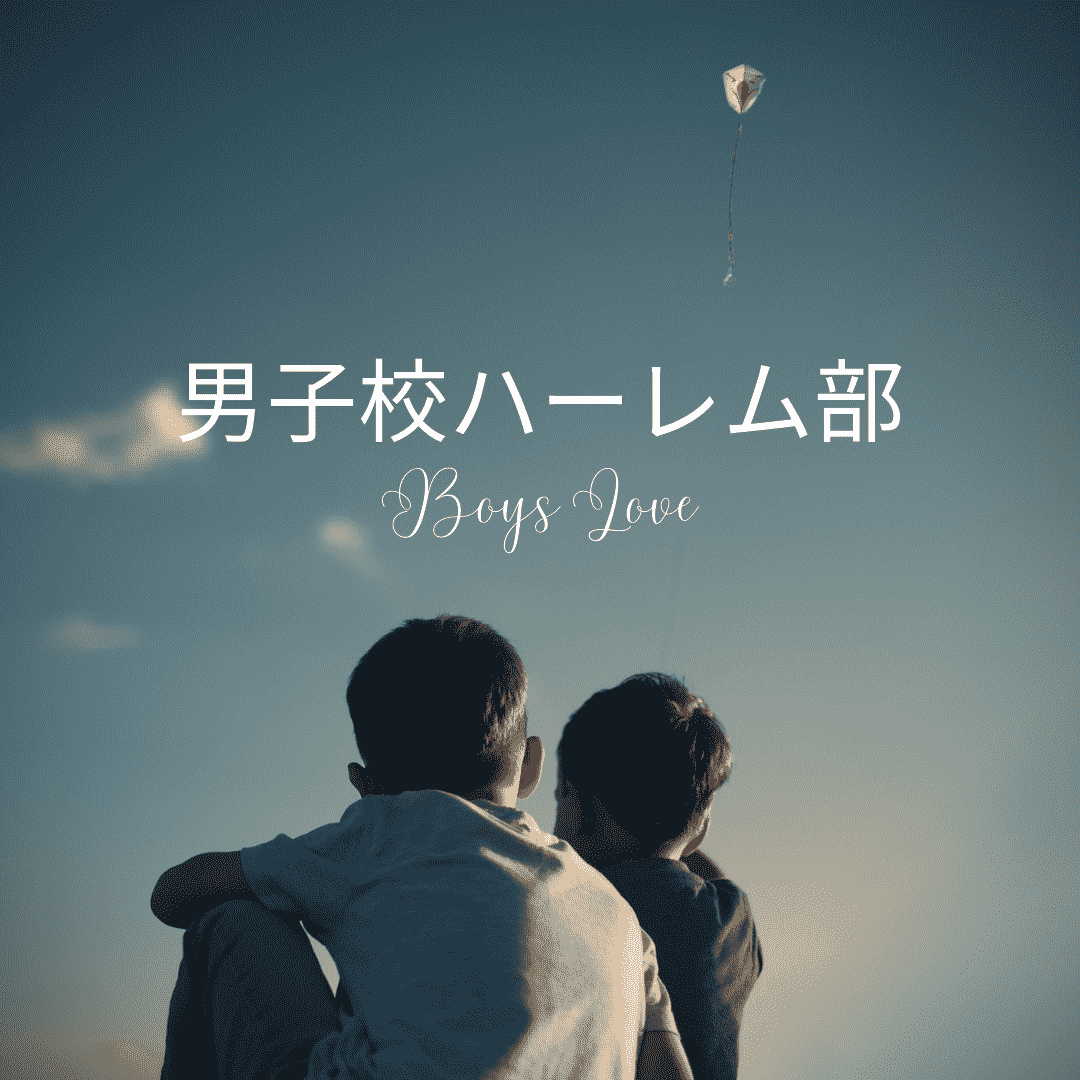
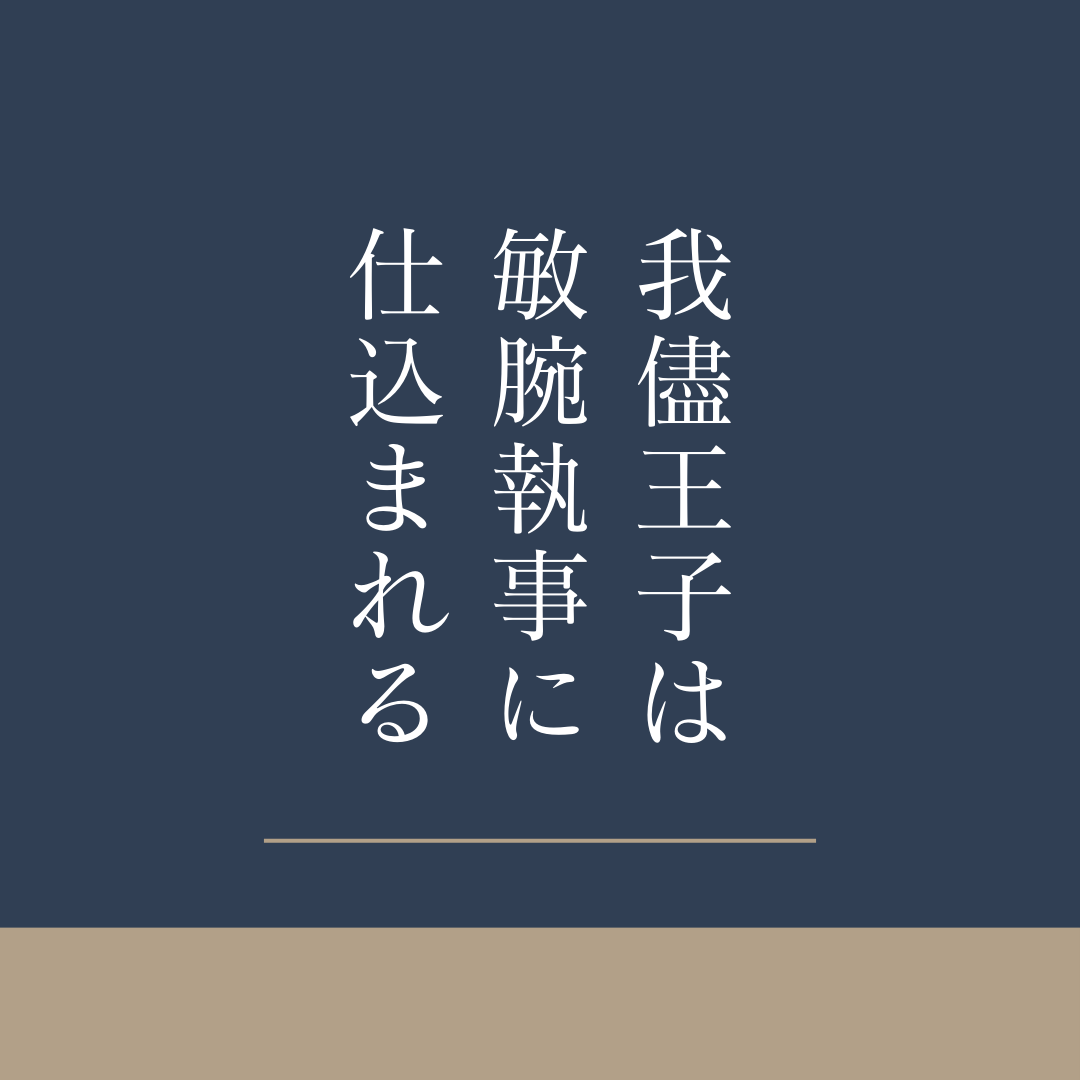

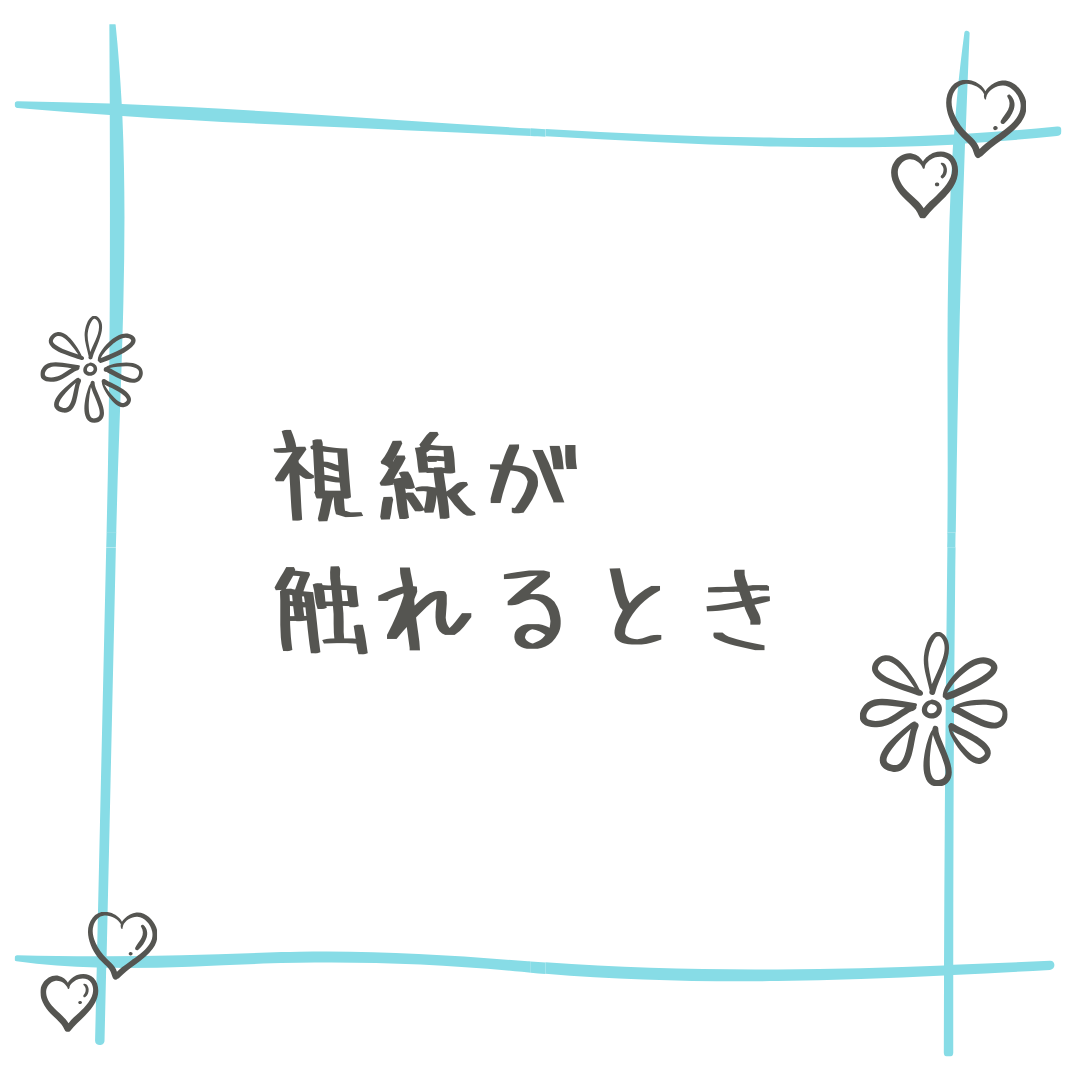


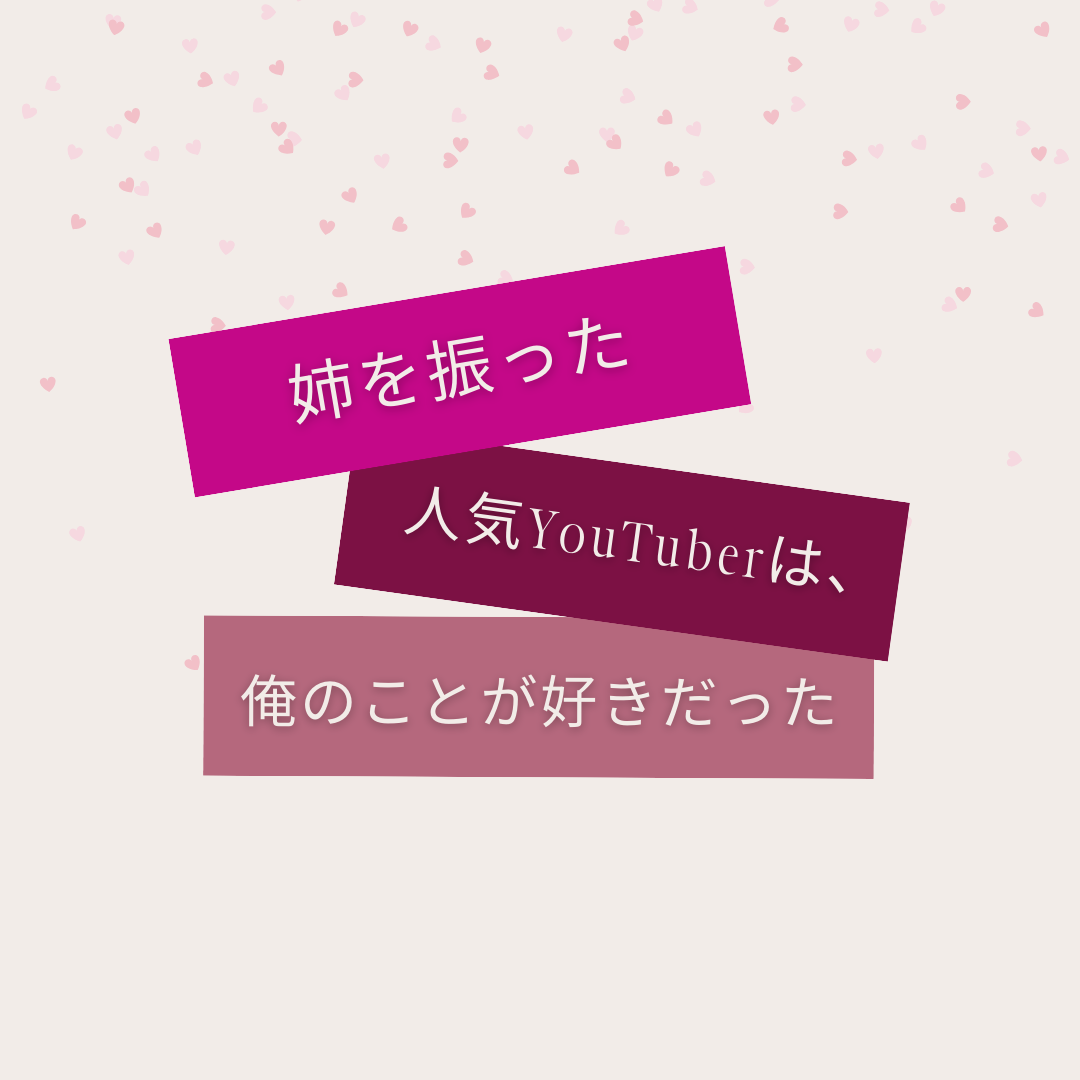









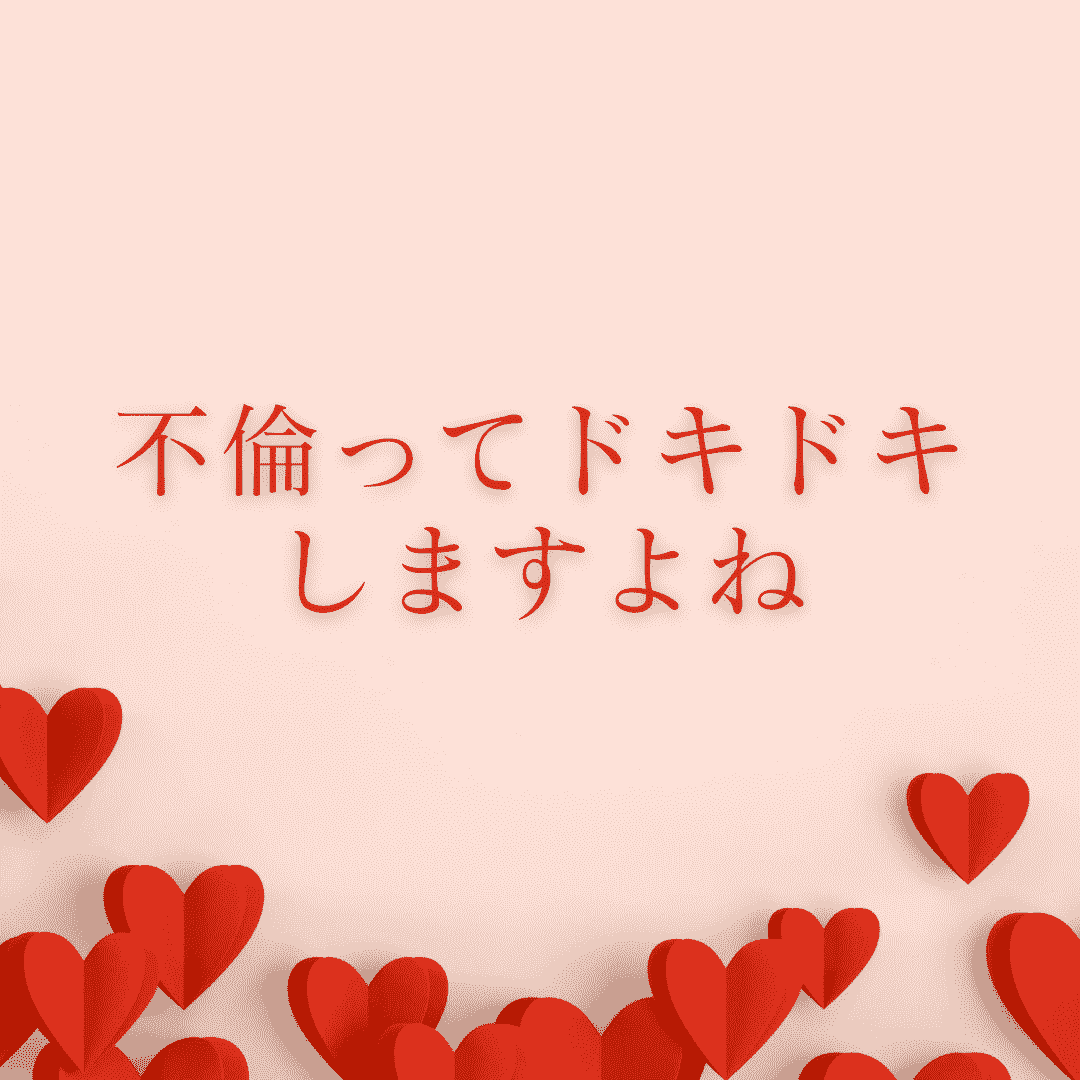




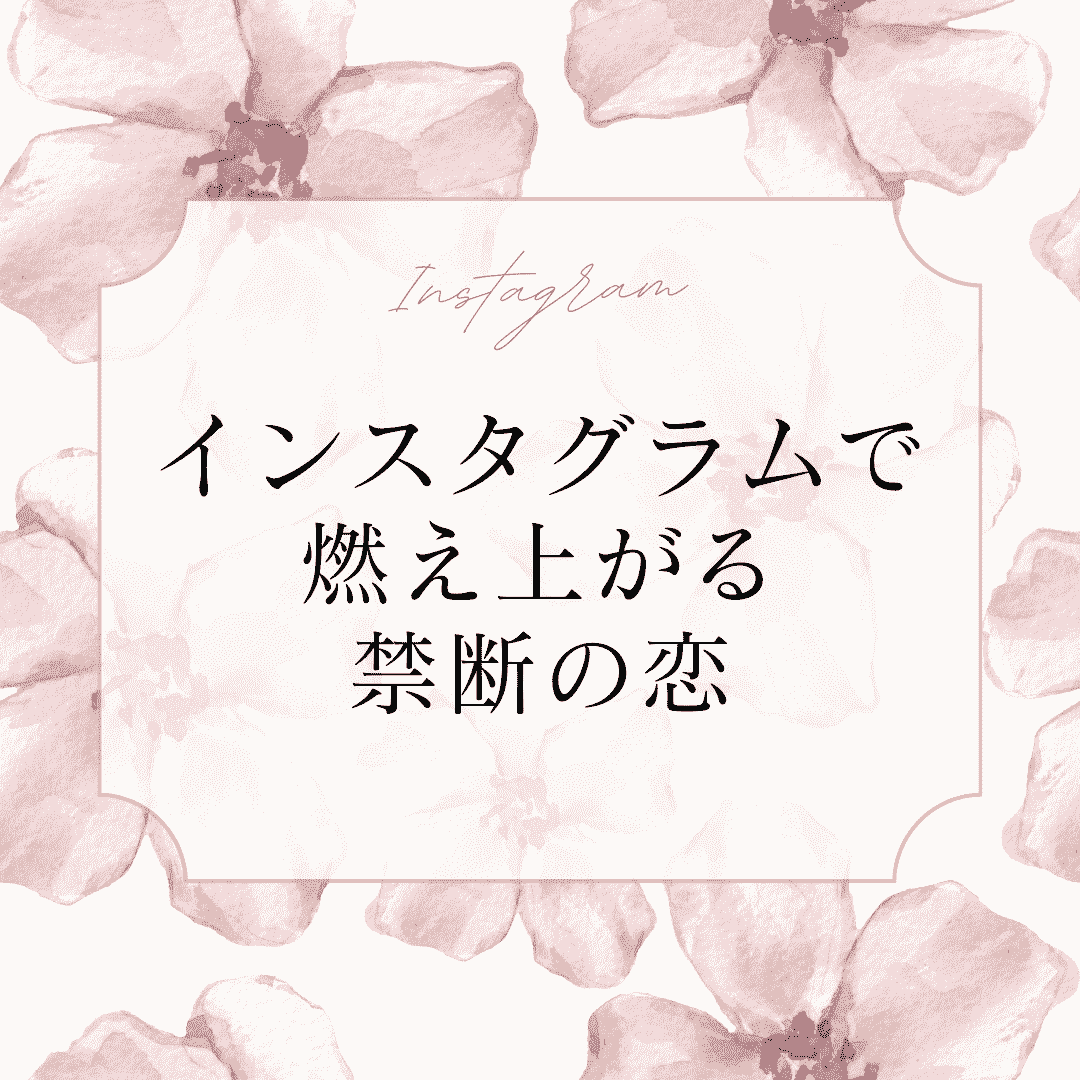

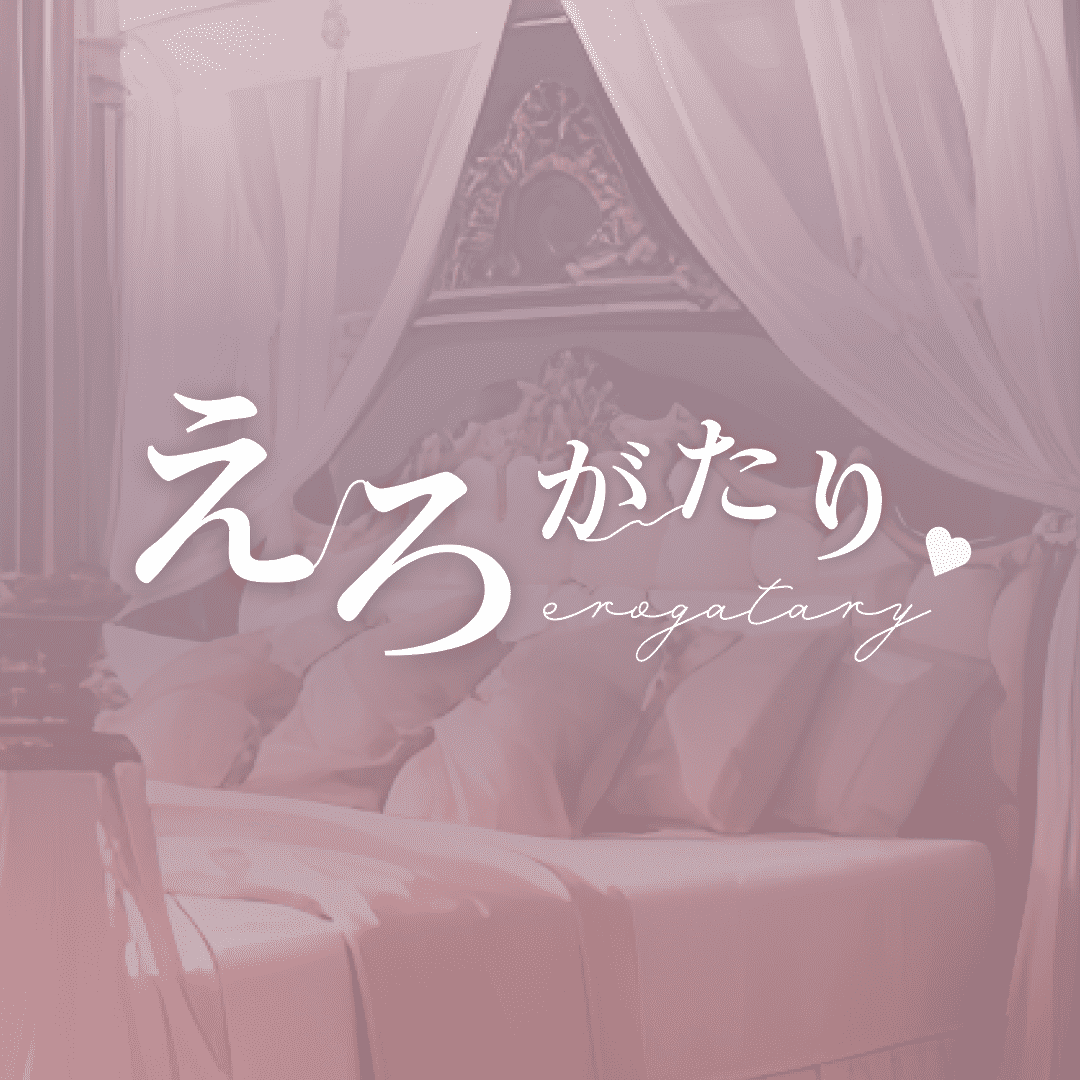





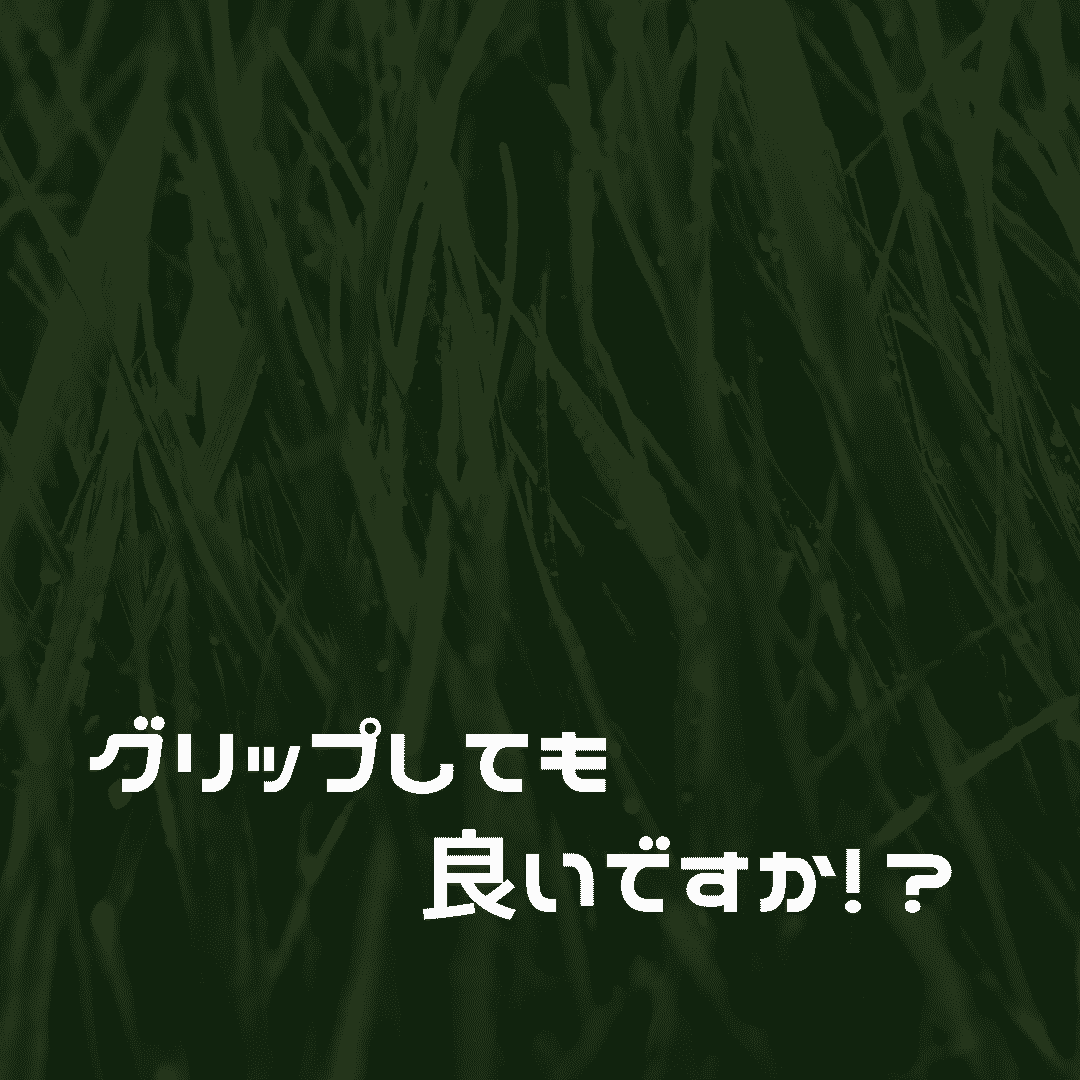
コメント