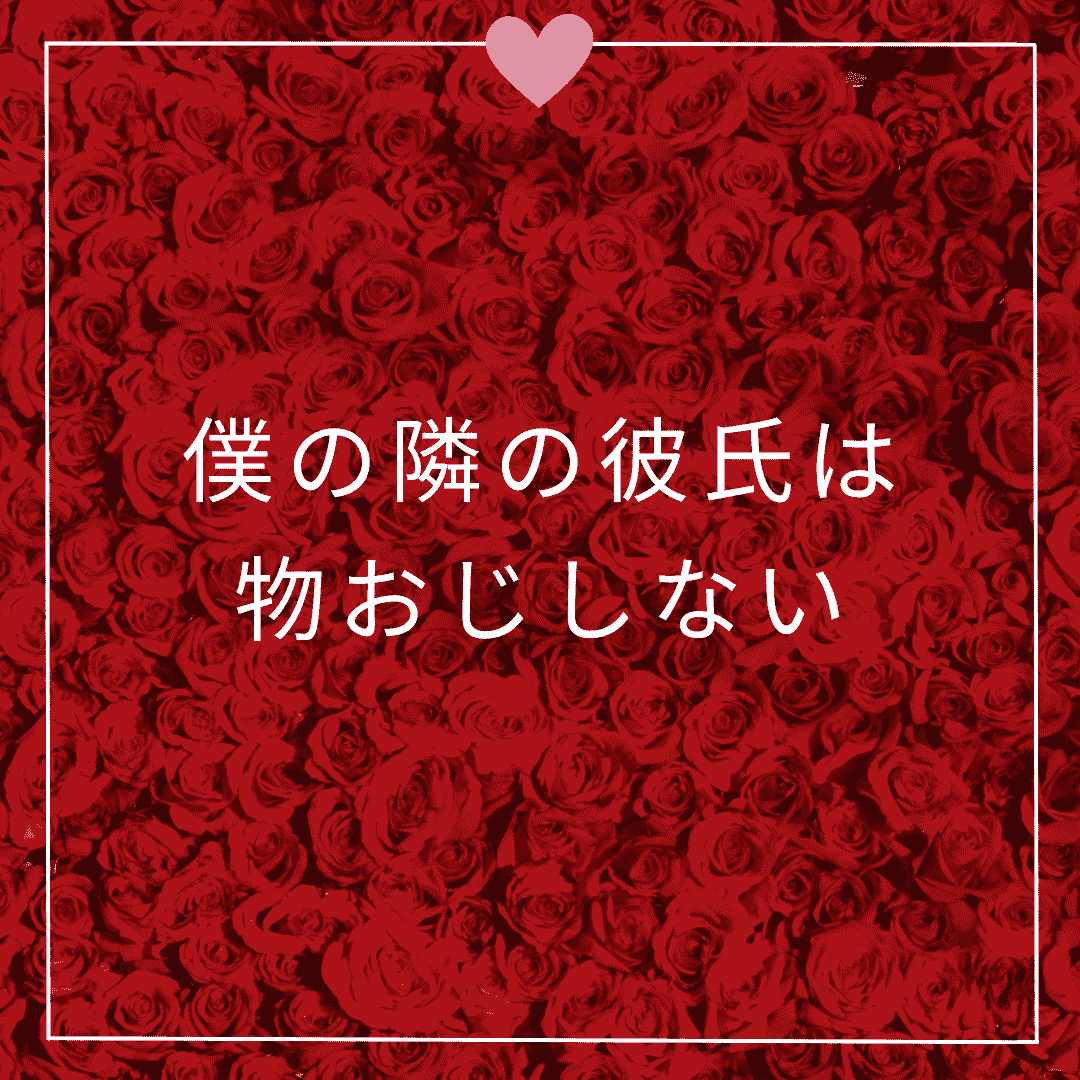
0
僕の隣の彼氏は物おじしない
「そう、いきなりなんだけどどうしてもやってみたくてさ。ユマもついてきてくれる?」
そう言って僕の手をぎゅっと握ってくる。そんなにまっすぐな瞳と声で言われたら反対なんてできない。最初から反対する気なんて全くないけども。
アパレル関連の職についているイトは5つ上である28歳、僕の自慢の彼氏だ。僕は細々とバーでバイトをしており、そこまで向上心やチャレンジ精神は持っていない。イトは僕とは真逆で、物おじしない性格だ。やりたいと決めたことはどれだけ困難なことでも一旦は試してみるのがモットーらしい。僕には真似できないけれど、それでも尊敬はしている。
イトは東京のとあるアパレルショップの店長をしていたが、来月から大阪の新店舗のオーナーにならないかと誘われたのだという。僕は働く場所にはこだわりがないため、ついてきてほしいと言われても断る理由はなかった。大阪でいい感じのバーを見つけて働くことにしよう。
引っ越し準備は順調に進んでいき、それから1ヶ月後には引っ越しすることができた。駅近のマンションの一室は広々としており、窓からの夜景も悪くない。少ないがいくつか愛用していた家具も全て届き、引っ越し祝いに共通の親友からもらった大きめのソファーに座る。
イトの腕にむぎゅとひっつくと、優しく頭を撫でてくれた。緩く巻かれている青みがかった髪がふわりと揺れる。引っ越し前までは金髪だったから、まだ慣れない。それでも住む場所が変わっても、この人がいればどこでだって生きていける気がする。こだわりのない僕が唯一手放したくないのが彼だ。
「ここで酒飲んだらおいしそー」
夜景を見ながら僕が口を開くと、また髪の毛をくしゃっとしてきた。この触り方、ペットにでもなった気分になるからちょっとおもしろい。
「ユマなんか作ってよ。俺つまみ作るし」
僕はカクテル作りが得意で、イトは料理が趣味だ。さっき見かけた近くのスーパーに行き、カクテルを作るための材料やおつまみになりそうな食材をカゴに入れていく。家に戻ると、イトはさっそくキッチンに立ってくれた。
「ユマ、俺が作ってる間にシャワーしてきなよ」
「ありがと」
ささっとシャワーを浴び終え部屋に戻ると、立派なおつまみが出来上がっていた。カマンベールチーズのベーコン巻き。僕がチーズ大好物なことを覚えていてくれている。野菜スティックは健康に気遣うイトらしいおつまみだ。
入れ替わりでイトもシャワーを浴びにいった。戻ってきて髪を乾かしているところに聞きにいく。
「イト何飲みたい?」
「ジントニック」
「言うと思ったー」
手早くジントニックを2杯作り、ソファーの前にあるローテーブルに置く。髪を乾かし終えたイトは前髪がぺたんって下がってて、この髪型を見ることができるのは僕だけなのだと思うと優越感に浸ることができる。ソファーに隣同士座り、かちりとグラスをぶつけて乾杯した。
「やっぱりジントニックが一番だわ」
「ほんっとジン大好きだよね」
「初めて店行った時に作ってくれたの、ジントニックだったから」
「……そうだったね」
こういう細かいこと、ほんっとよく覚えてる。僕は言われるまで思い出せなかったのに。
「あの時はこんなにも長く一緒にいるとか思いもしなかったけど」
すらっとした長い指が野菜スティックを摘み、口に運んでいる。ぽりぽりときゅうりが噛み砕かれていく心地よい音。細長いものを食べている様子って何でこんなにも官能的なんだろう。
「どうしたの?食べたい?」
僕の視線に気がついたイトが、細長いにんじんを手に持って見せてきた。そのまま自分の口に少し含み、ゆっくりと近づいてくる。そんなポッキーゲーム野菜版みたいな、みたいなっていうかそうか。にんじんを咥えたまま、こくこくと頷いている。僕も端っこを口で挟む。絶妙な塩加減。やっぱり僕はイトの作る料理の味付けが好きだ。
ふたりで両端からぽりぽりと食べていく。心地いい音。ぽりぽりの感触が突然消えて、ふにふにした大好きな人の唇が当たる。唇を軽く触れ合わせたまま咀嚼して、ごくっと飲み込む。お互い口に何もなくなったことを確認してから、本格的なキスが始まる。くちくちと舌を絡ませると、思っていたよりも早く唇を離されてしまった。物足りなくて口を尖らしてもイトは気がつかないふり。
「お酒、もっとほしい?」
「うん」
「じゃあもう1杯作ってくるね」
空になったグラスを持って、キッチンの方に向かう。どれだけ物足りなくても、もう1回キスしてって言えない。明日はイトの新店舗初出勤の日だから、緊張もするだろうしゆっくり寝かせてあげないと。
ー
面接に来たお店の重ための扉を開くと、煌びやかな装飾が目に飛び込んできた。クラブほどの音量ではないが最近流行りの音楽が流れている。ぐるりと見渡すと、ラフな格好をした男性が酒を作りながら、カウンター越しに女性客と話をしている。
引っ越ししてから数日後。イトは新店舗の準備で忙しく遅い時間にしか帰ってこないため、なかなか触れ合う時間もなかった。このまま働かず家にいるわけにもいかないから、家から近いバーをネットで調べて一番初めに出てきたところに面接に来た。どうやらただのバーではなさそうだ。
店長だというスーツを着た男の人に店内の奥の方の席に通され、業務の説明を淡々とされた。このお店はボーイズバーと呼ばれるお客さんとの会話がメインとなるらしい。バーテンをしていたときはうちの店の雰囲気がそうだったからか、話すことは少なく黙々と酒を作っていた。
「お話は得意?」
「んと、そこまで……でも頑張ってみます」
それからはイトと同じくらい忙しい毎日だった。たどたどしい会話もだんだんと上達していき、1ヶ月経った頃には指名制度はないものの自分目当てできてくれるお客さんが増えていった。
引っ越す前はなんとなくの気持ちで働いていたのに、今はこうしたらもっとよくなるだろうといったことを考えるのが楽しくてしかたない。気がついたらイトと触れ合うことなく数ヶ月が経っていた。
ー
イトが珍しく早めに帰ってきた日、僕はその日はお休みにし、簡単な料理を作って家で待っていた。
「ユマ、なんか変わったよな」
僕が作ったお酒をソファーでまったりと飲んでいるイトが話しかけてきた。
「どこが?」
「なんか、前よりも明るくなったし、それに物おじしなくなった」
「イトの方がそうじゃん」
「じゃあ俺に似てきたってことか」
ふふん、と鼻を鳴らしドヤ顔を見せてきた。確かに僕は、イトに言われた通り少し変わったのかもしれない。慣れない土地でできるだけたくさんの人と触れ合って、その時間をどれだけ楽しく過ごしてもらうかを第一に考えて頑張ってきた。ただのアルバイトから役職を上げようかなんて話も出てきている。
「良い方向に変わってるの、俺は誇らしいな」
「じゃあ今日は癒してくれる?」
「うん、しよっか、ユマ」
飲み干したグラスを机に置く音が響く。ゆっくりとベッドに移動して、お互い早急に服を脱がせあう。今日はゆっくりなんていていられなさそう。さっきトイレでなか慣らしてきてよかった。
その間にも舌を絡ませるキスをしていく。お互いセックスする体力が残らない日々を過ごしてきた。もう今はだいぶ慣れてきたから、これからはまた週2くらいでできそう。そう思うとますます興奮してきて、イトのちんこに手を伸ばす。
「まだ反応してないね」
「内心すげえどきどきしてるけどね。舐めてくれる?」
「もちろん」
イトの脚の間に顔を埋めると、大好きな匂いがする。手で強めに刺激しながら、触れた部分に舌を這わしていく。どくどくと血液が走っているのをダイレクトに感じられる。
「はあ……きもち、」
完全にちんこが上を向いたのを確認して、ぱくりと口で咥える。できるだけ唾液を出すことを意識しながら、喉奥まで咥え込む。
「んぐっ」
「ユマっ……そんな奥まで……無理するなよ」
「ん、んんっ」
イトが喜んでくれることならなんだってしたい。たとえ喜んでくれるかわからなくても、新しいことはどんどんやってあげたい。日頃気をつけていることは、ここでも活かすことができるみたい。
喉奥をごぽごぽとしめながら刺激すると、イトがさっきよりも気持ちよさそうな息を漏らし始めた。根元の方も唾液たっぷりの手で刺激していくと、それは苦しそうな息に変わる。
「ユマ……っ、で、出そうッ」
口から離そうとした瞬間、喉にねばねばとした濃いものが絡みついた。ちゅぶちゅぶと先端を吸い、何も残っていないことを確認して口から離す。
「ごめん……出ちゃった」
それでもまだちんこは萎えていない。そのままイトを押し倒し、ゆっくりと騎乗位の体勢で挿入していく。
「あ……んっ、ん……」
イトのちんこは、さっき射精したばかりだとは思えないくらいどくどくと脈打っている。どれだけ溜まっていたのだろう。さっきの精液も、今まで飲んだ中で一番濃かった気がする。
「なかっ、すごい締まってるな」
「ん、ひさしぶりっ、だから……」
「でもちゃんと準備してくれてたんだな」
「だって、ずっとしたかったもん」
もう我慢できなくて、先走りが垂れているちんこをぐちゅぐちゅ扱きながら腰を動かしていく。奥に当たるたびに太ももが震えて気持ちがいいことがばれてしまう。ぱんぱんと肌と肌が触れ合う音と2人の吐息だけが部屋に響いていて、その音にも興奮していくのがわかる。
「はあっ、ああっ……っ、なかっ……気持ちいいっ?」
「きもちいいよ……ユマっ、また出そうだ」
「いいよっ……いっぱい出して……っ!」
さっきよりも深く速く腰を上下に動かしていく。先に僕のちんこからびゅくびゅくと精液が飛び、イトのお腹にかかるのが見える。
「ひゃ、あああっ!」
そのままへたりそうになった僕の腰を掴み、下からがんがんと突き上げられていく。イったばっかりで揺さぶられるがままの状態になってしまっている。
「あっあん……っ、あっ……ぁッ!」
ごりゅ、と奥を突かれた瞬間、どくどくとなかに熱いものが広がっていくのを感じた。力を振り絞ってなかからちんこを抜き、そのままぺたんとイトのお腹に雪崩れ込む。
「よしよし、頑張ったな。大好きだよ」
「ん、ぼく、も……」
優しく頭を撫でられながら、僕は気がつかないうちにそのまま夢の中に落ちていった。






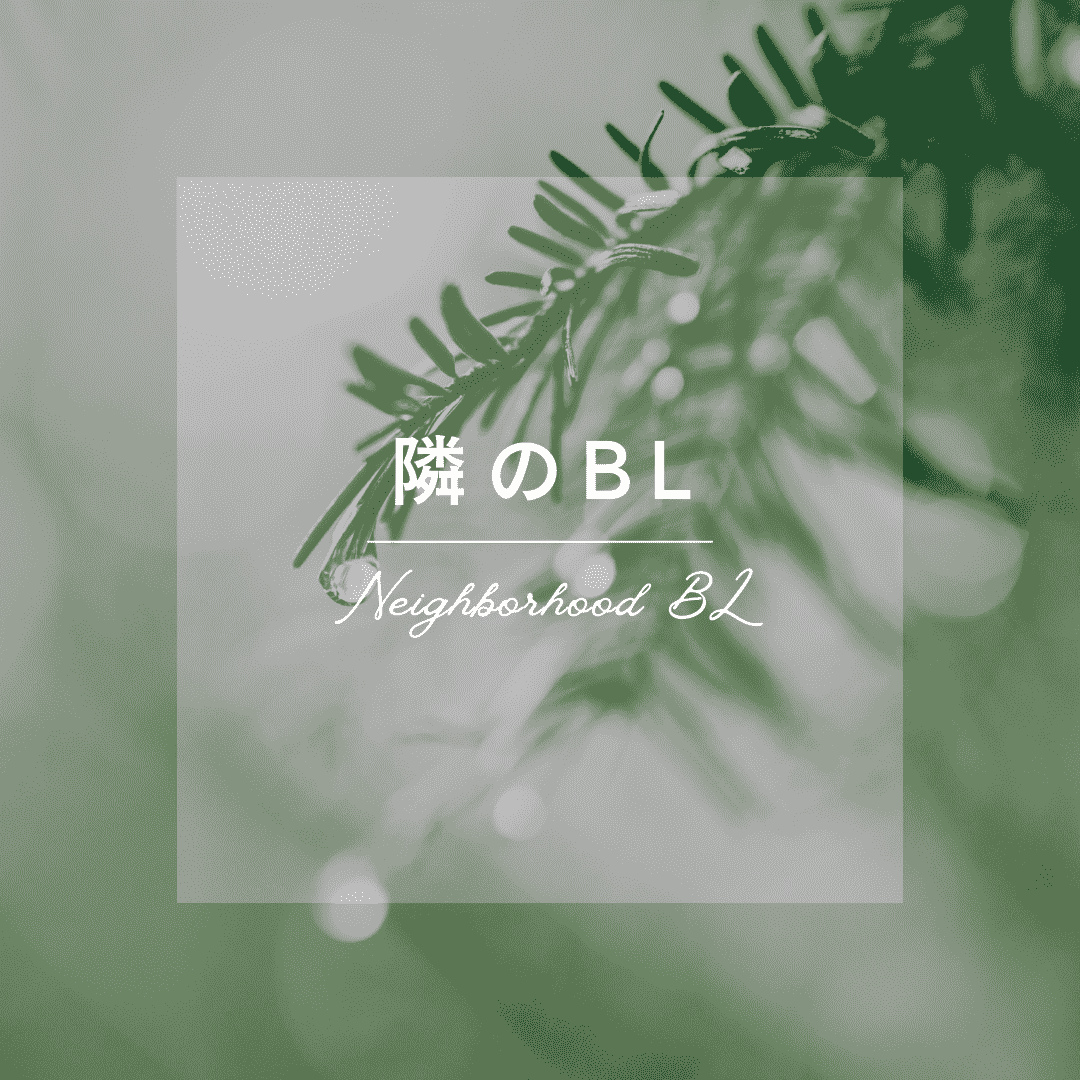
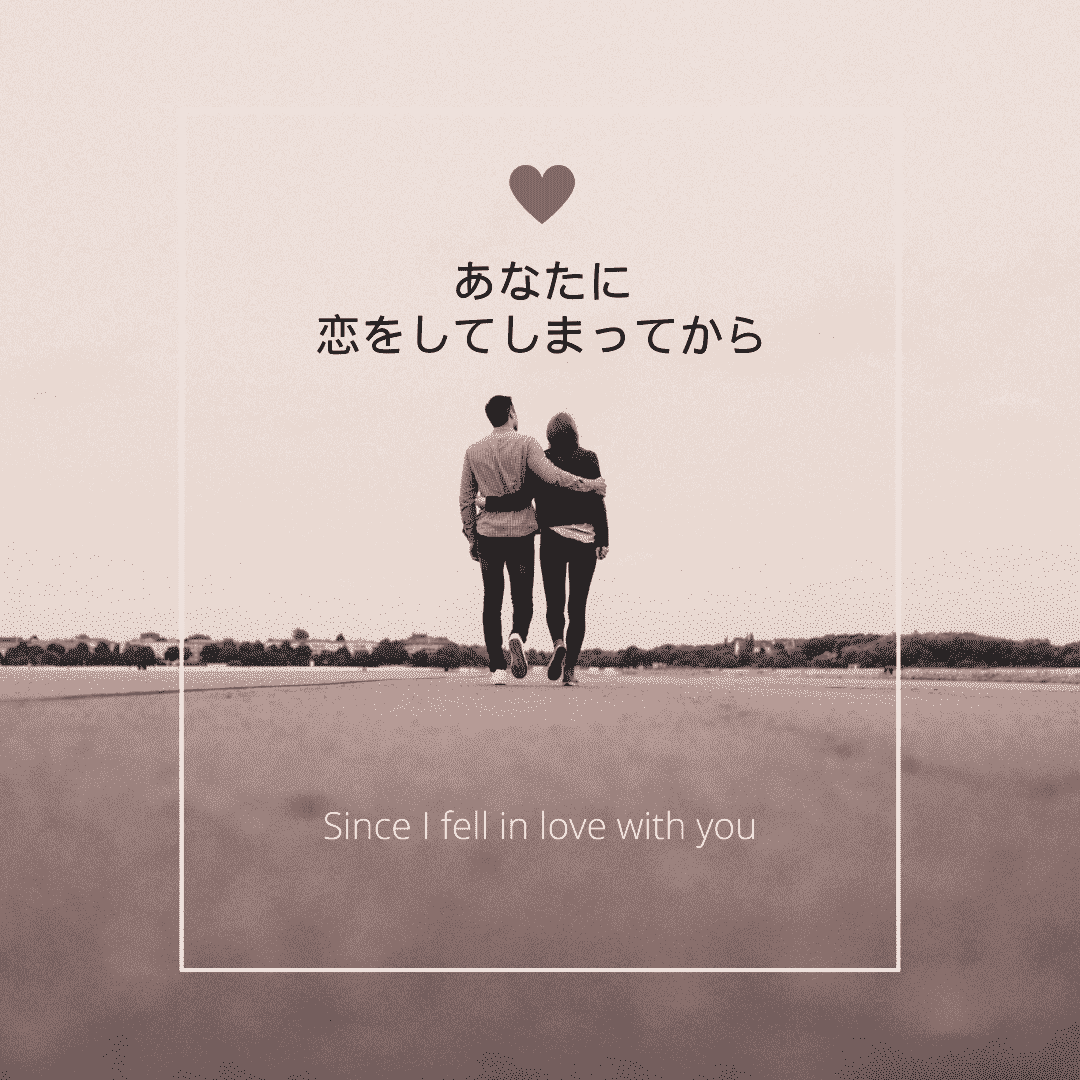

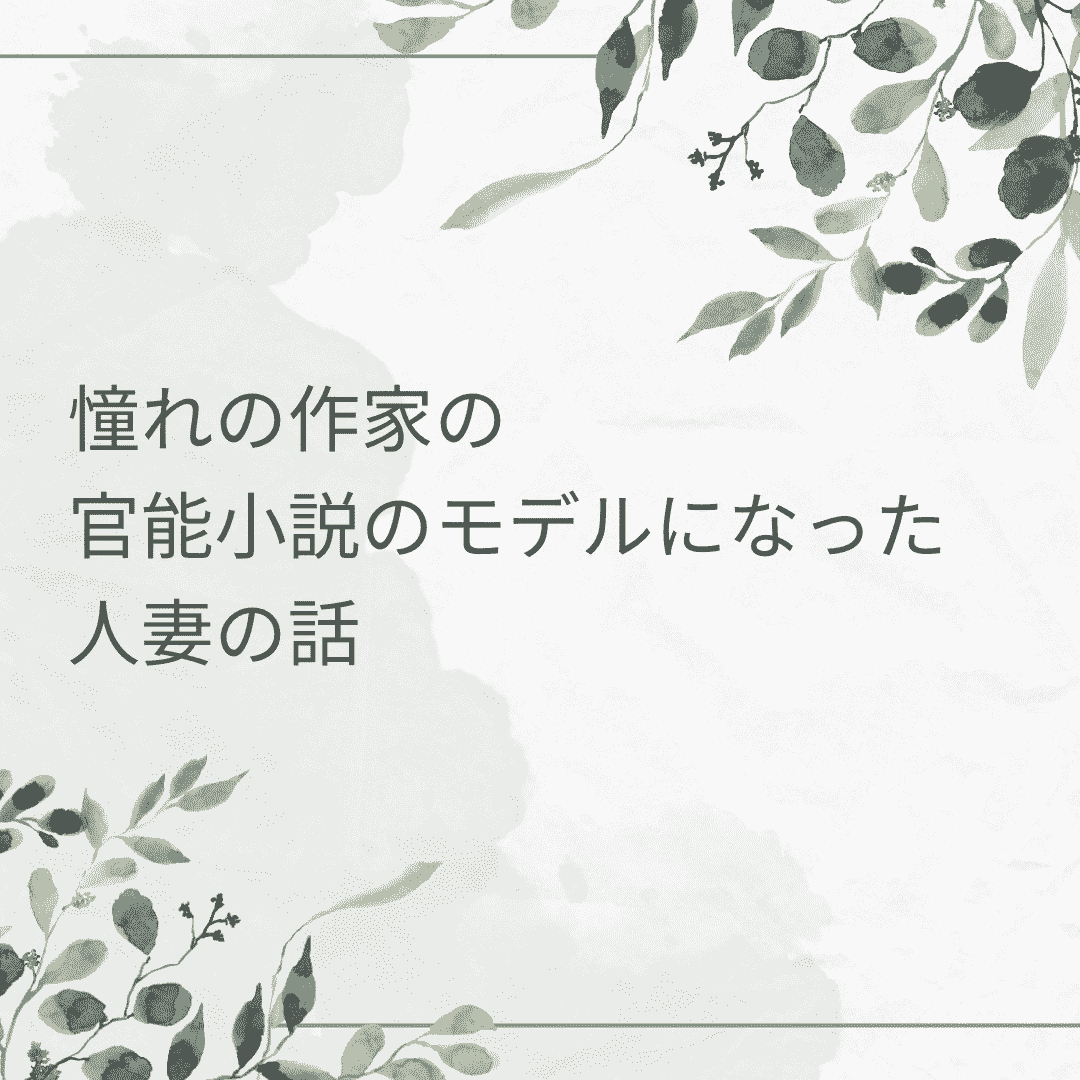


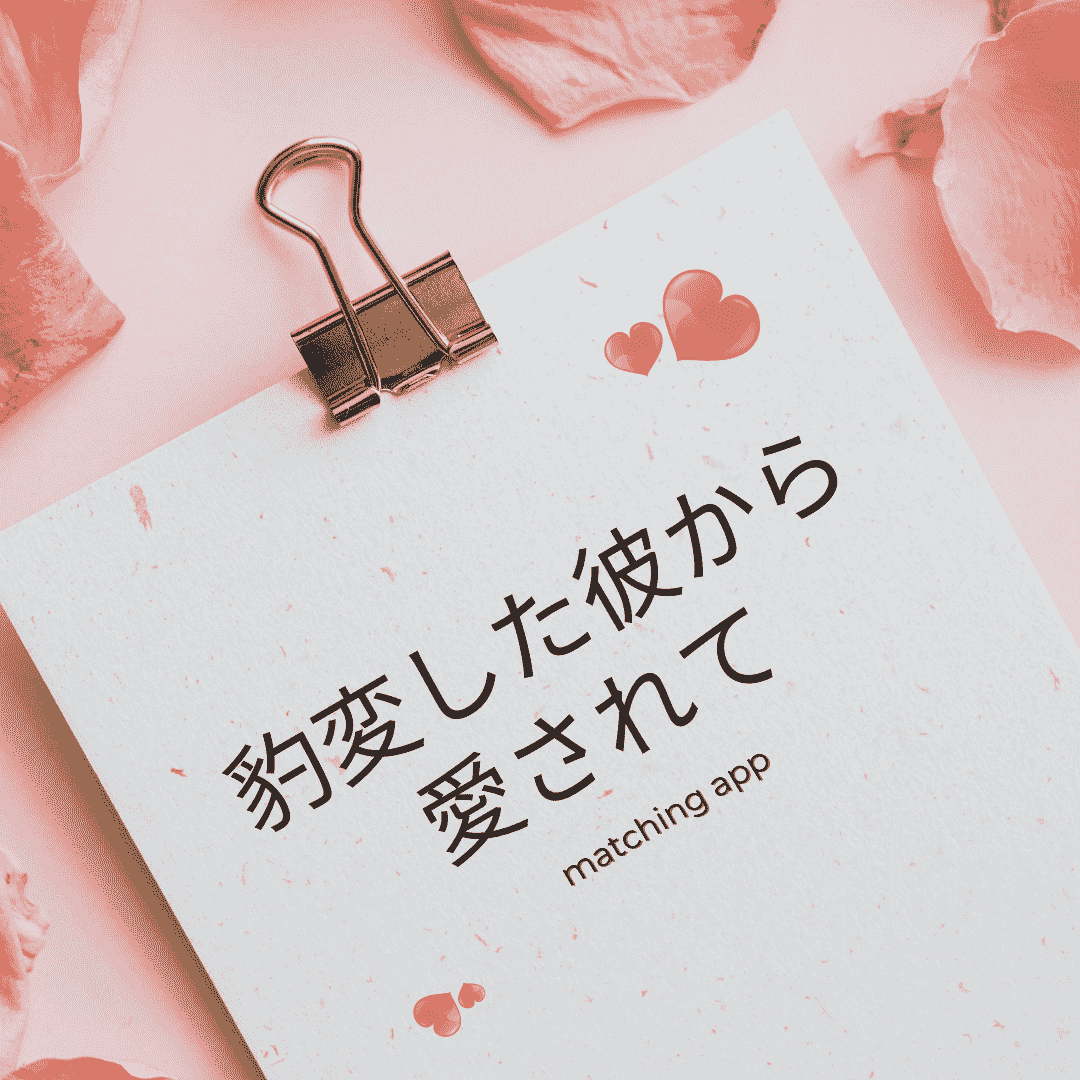

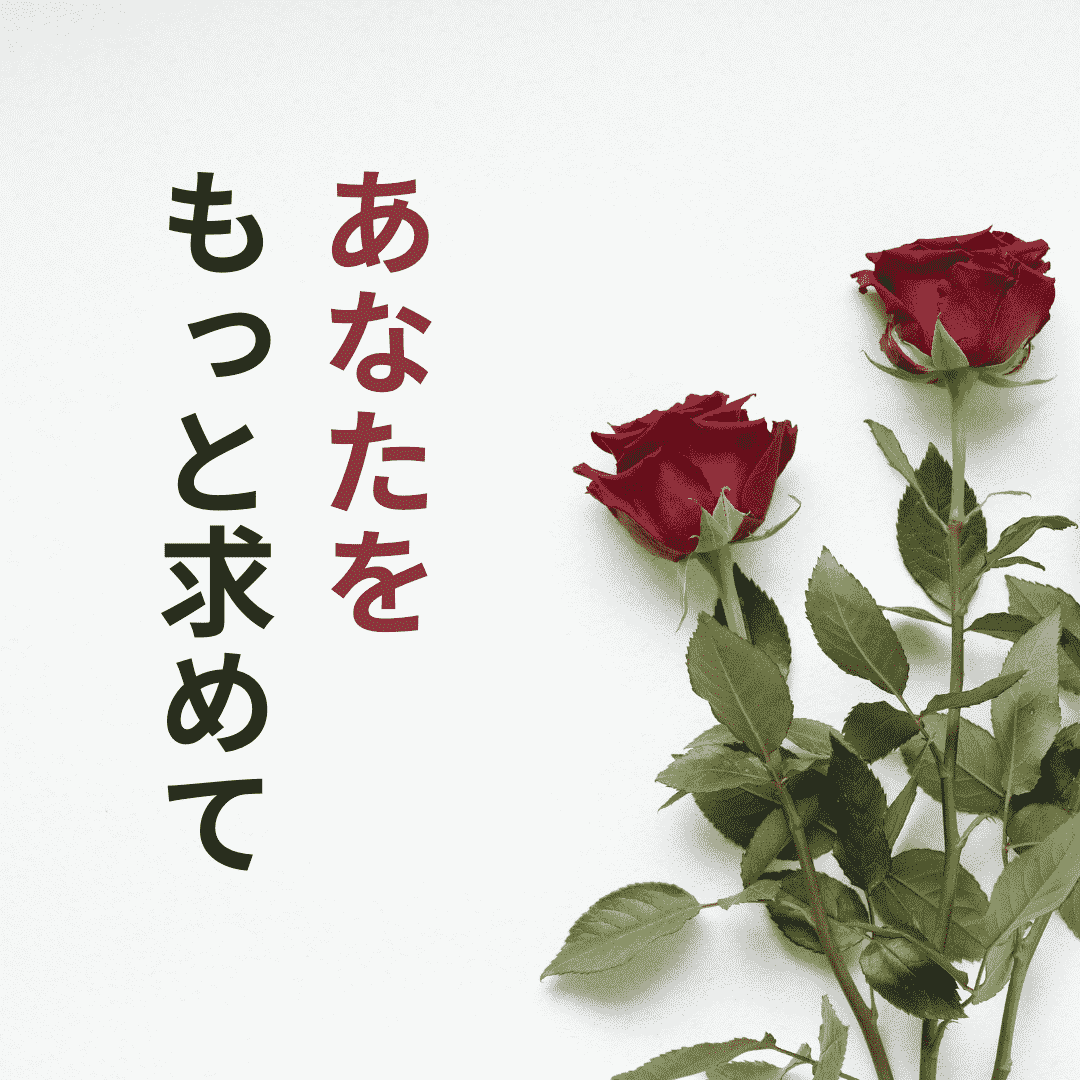





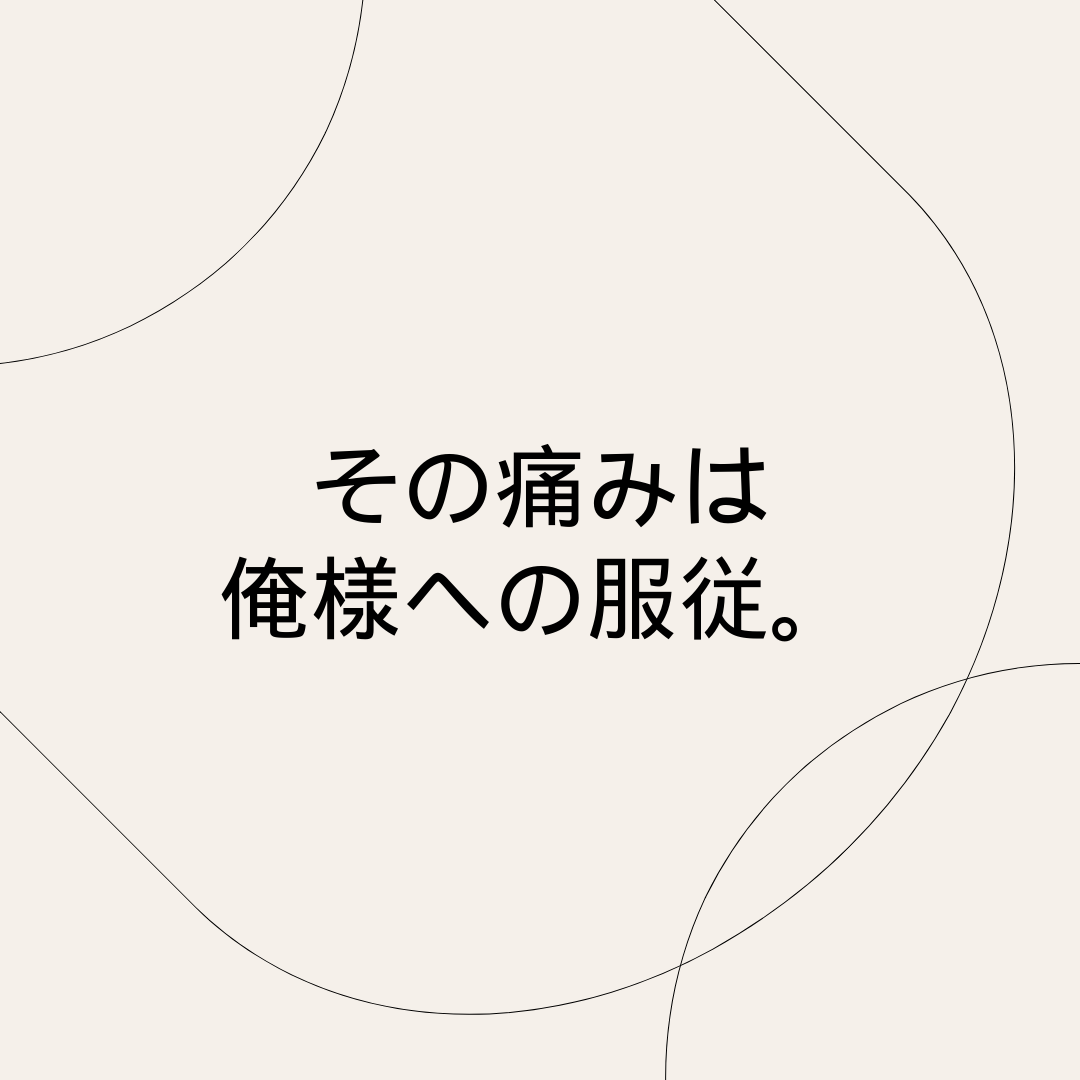

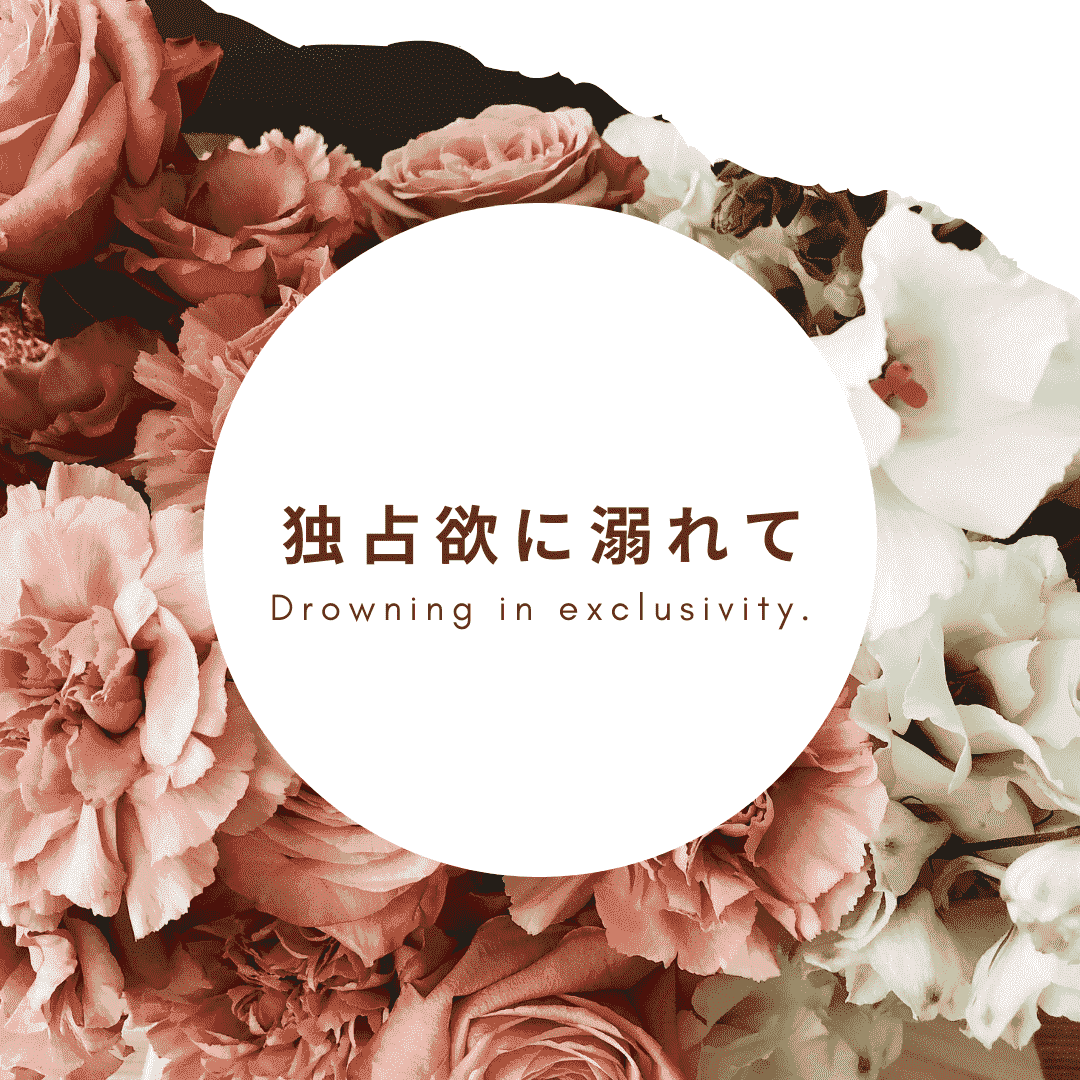
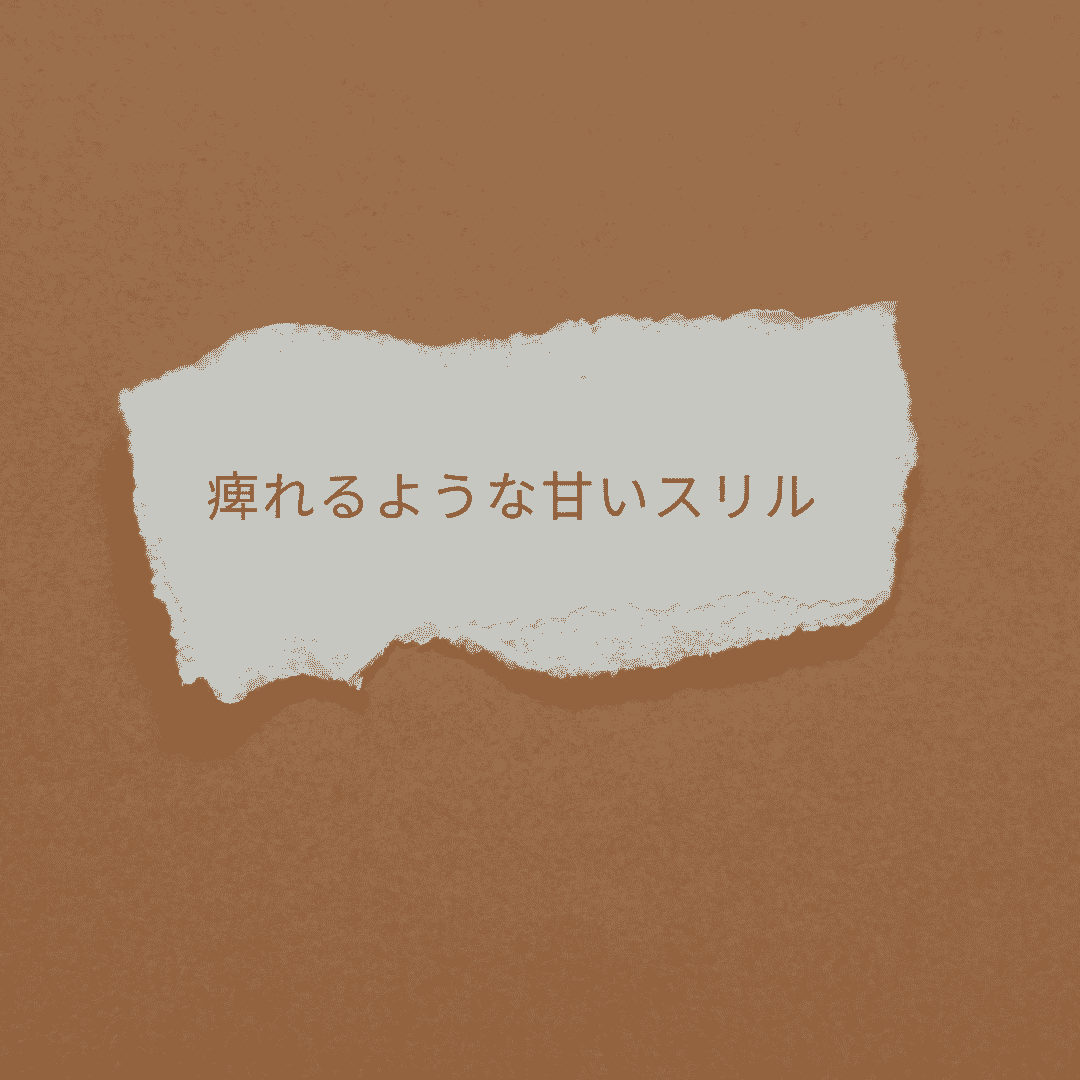


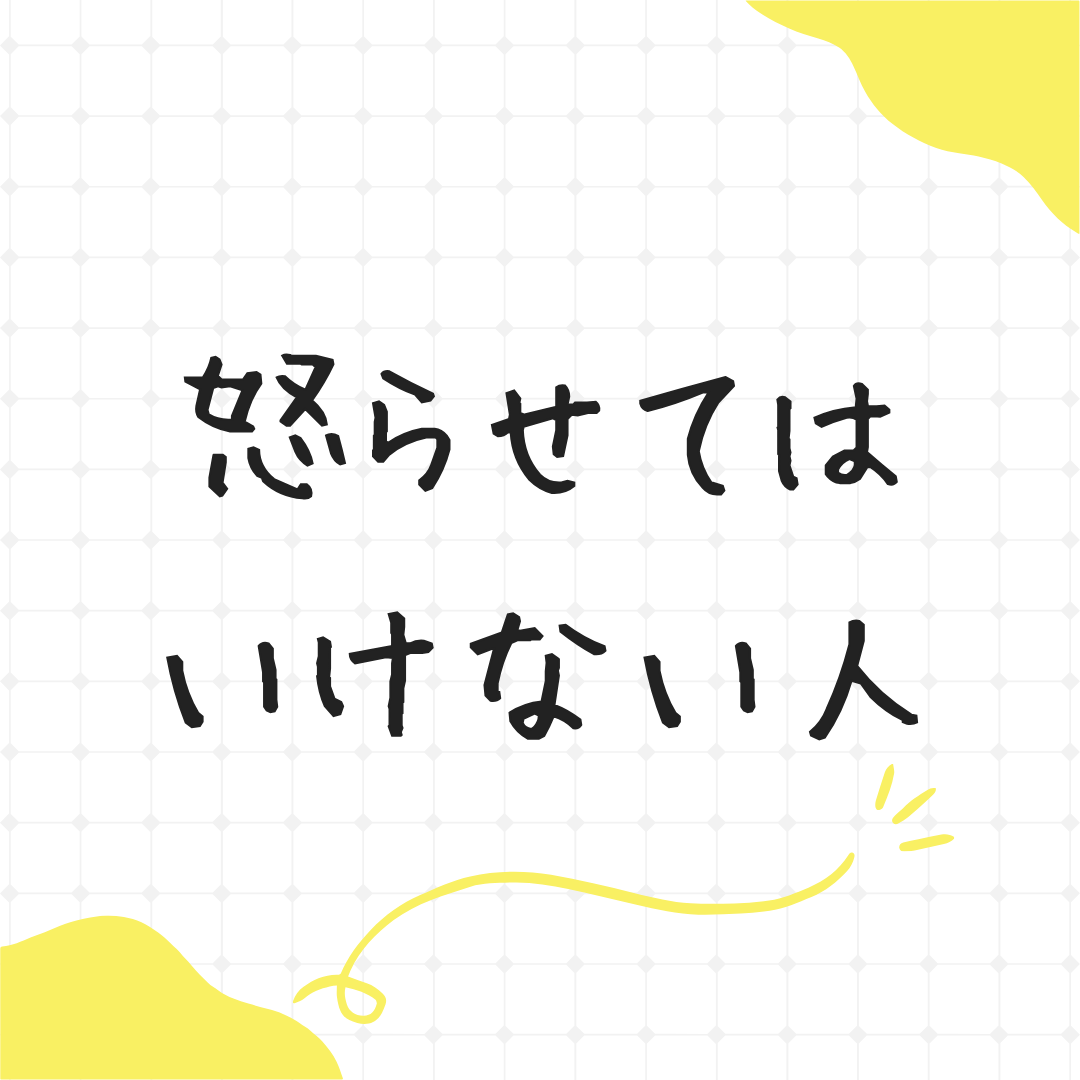

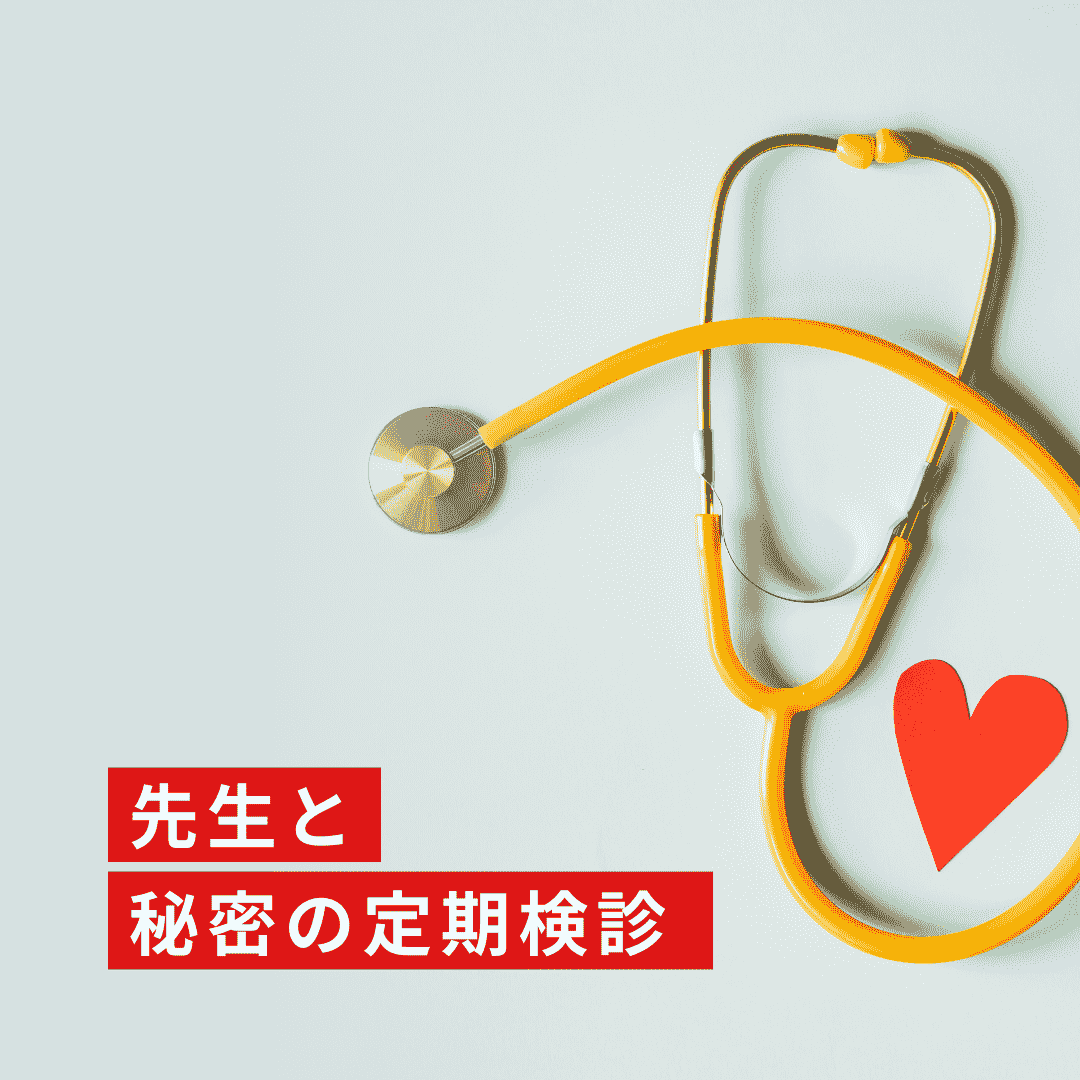
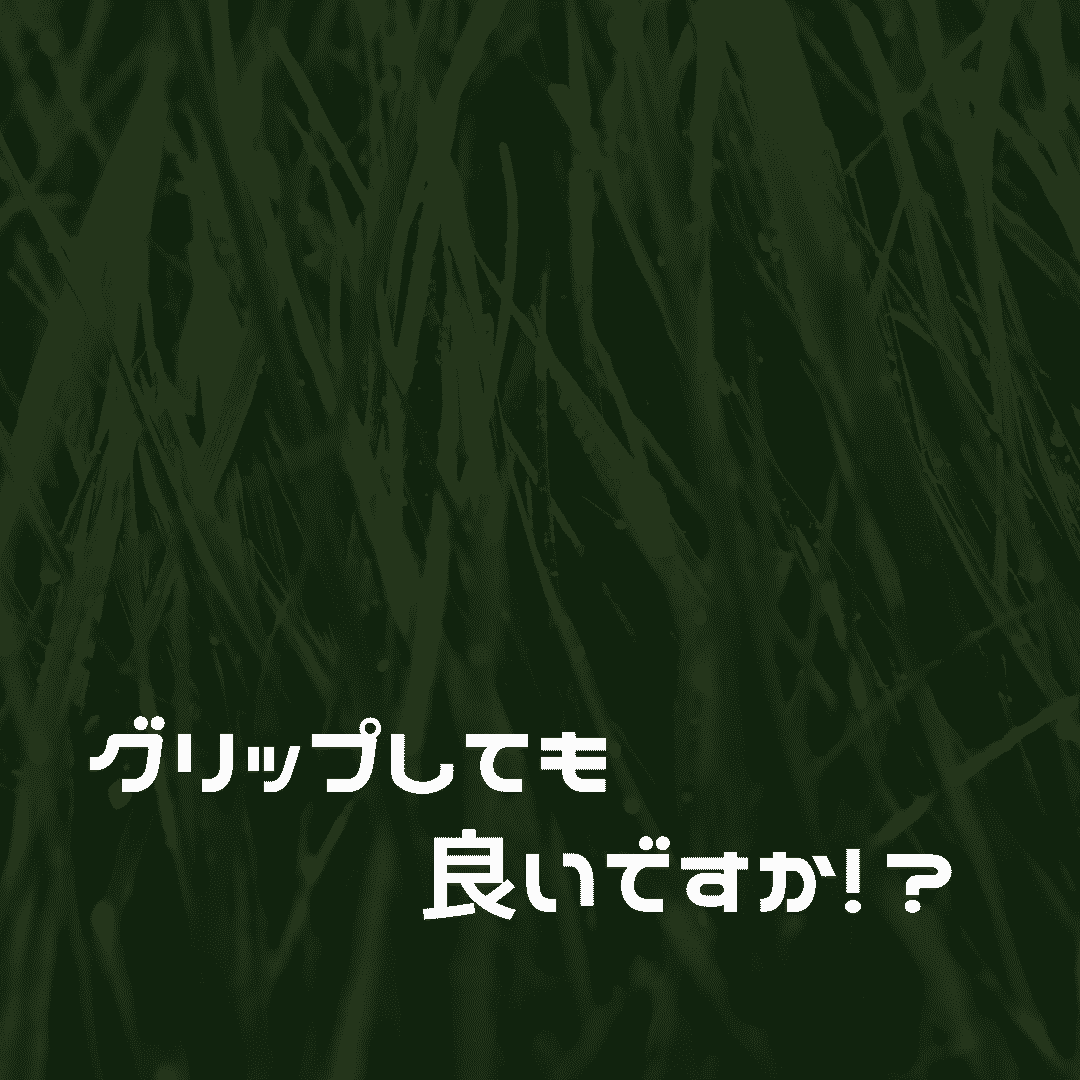
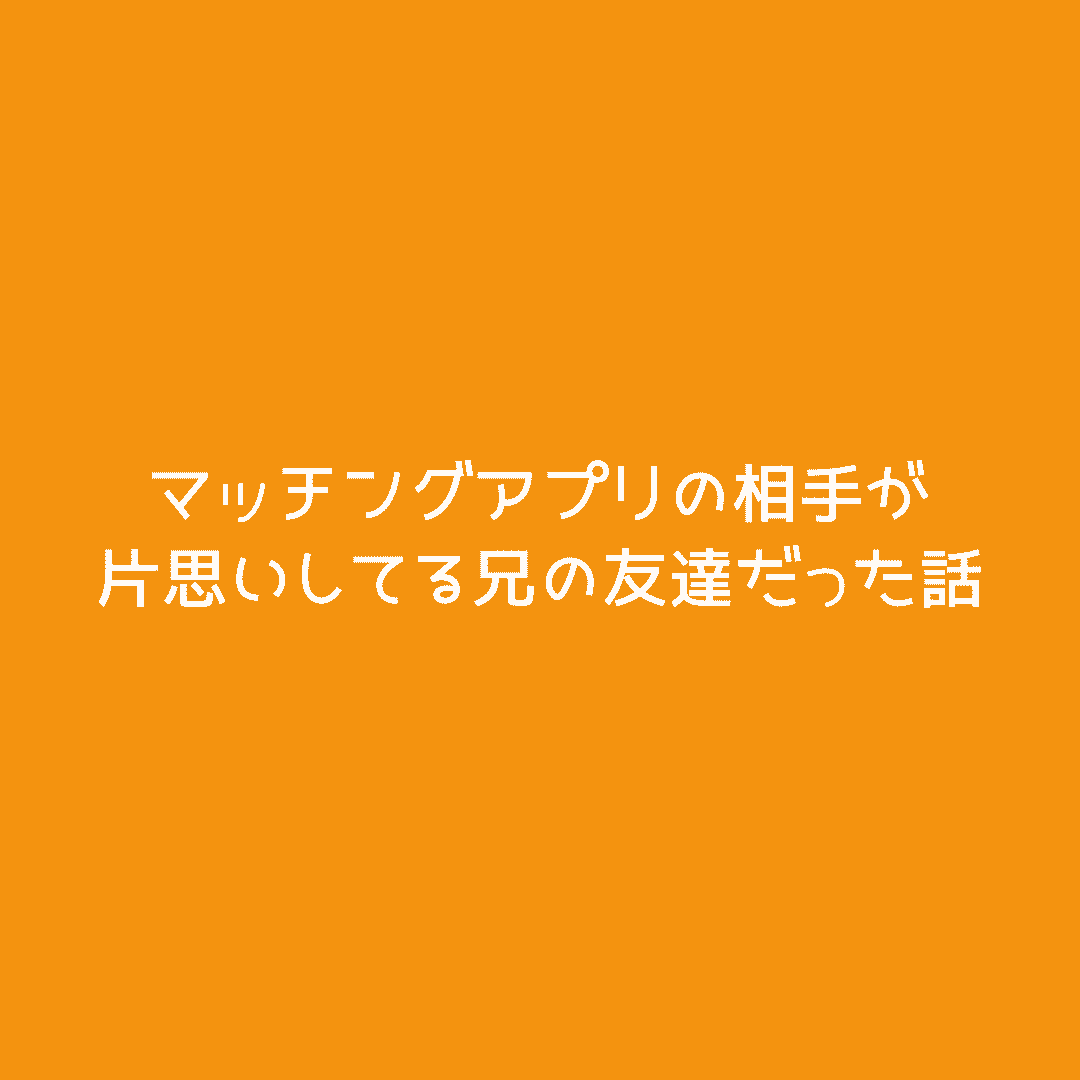
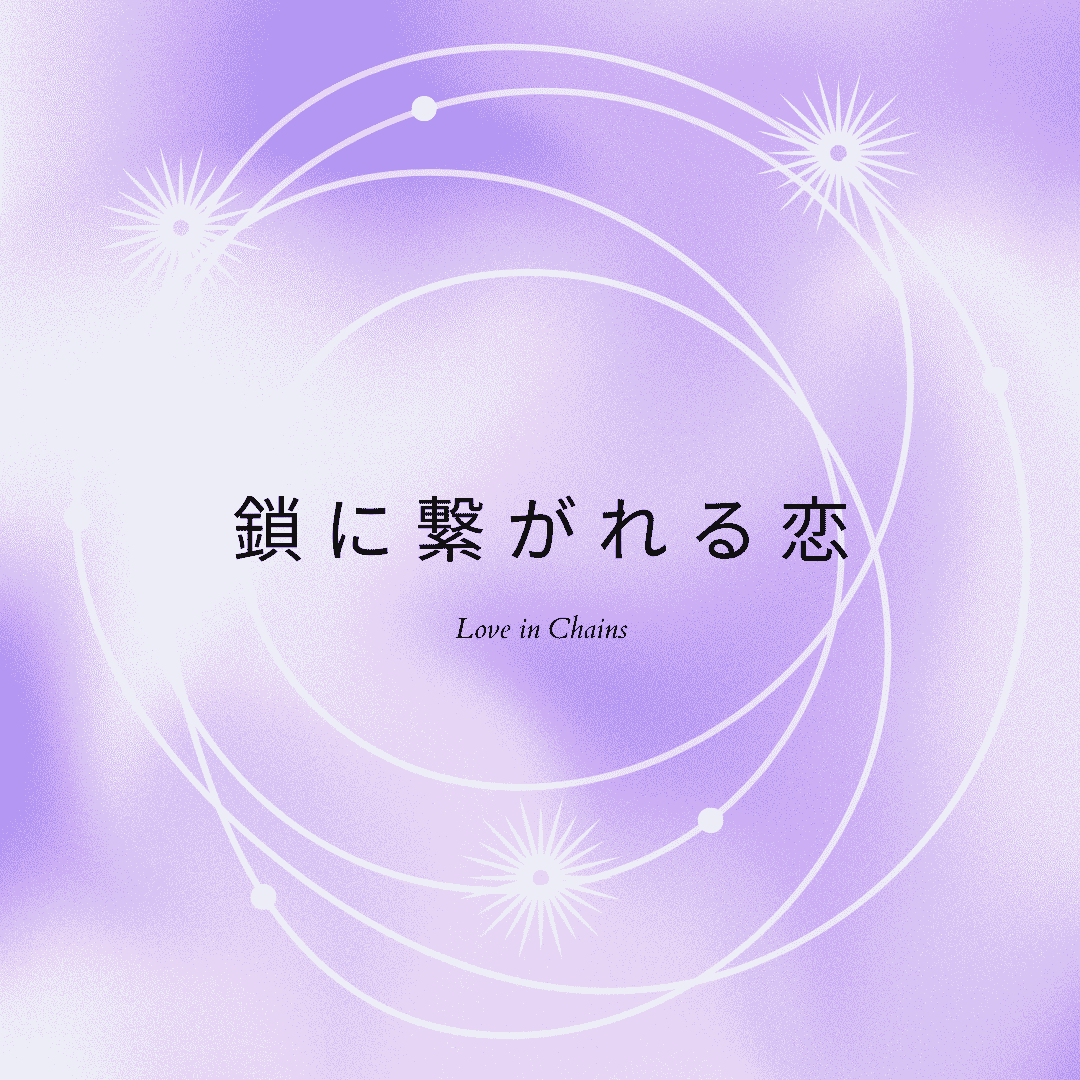


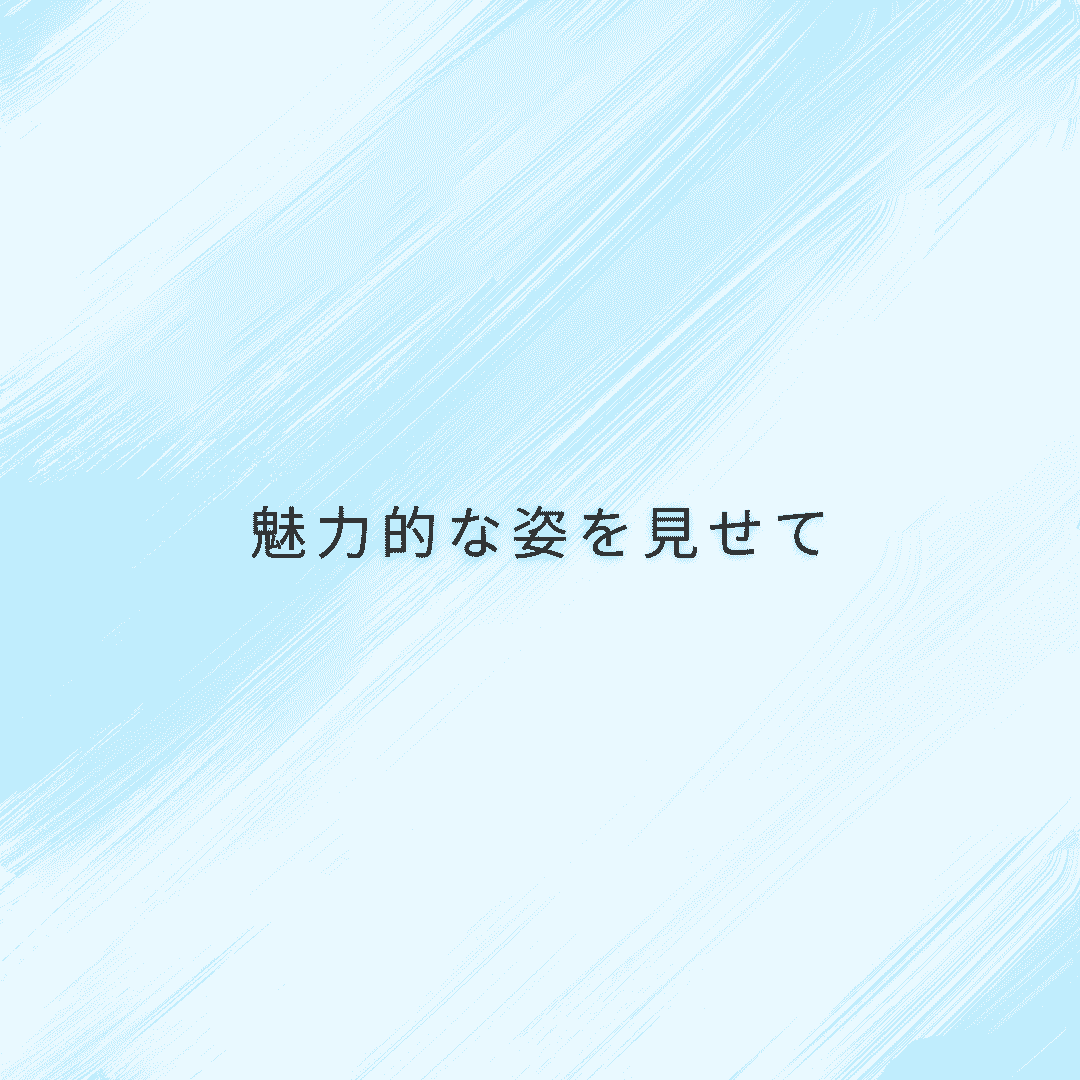
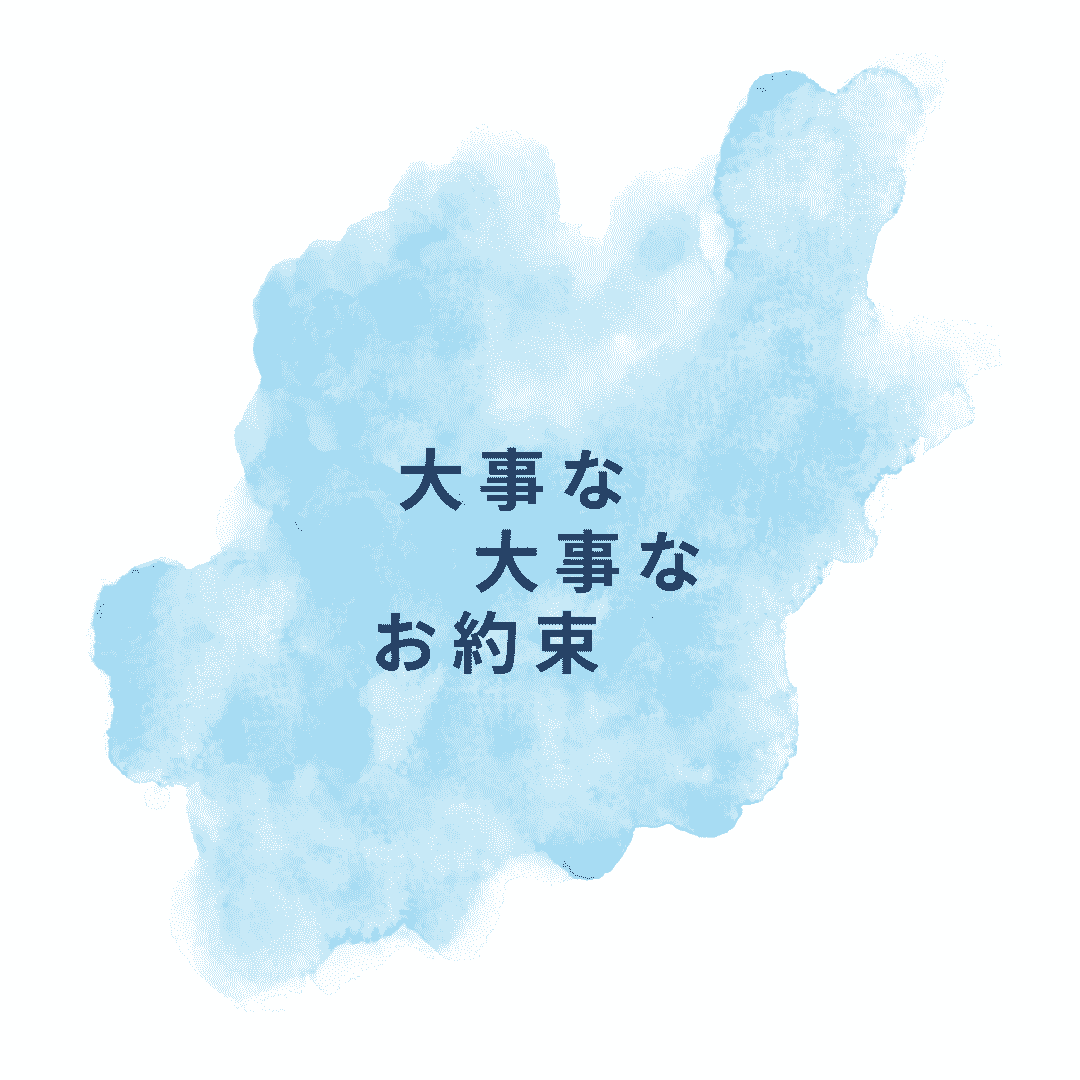


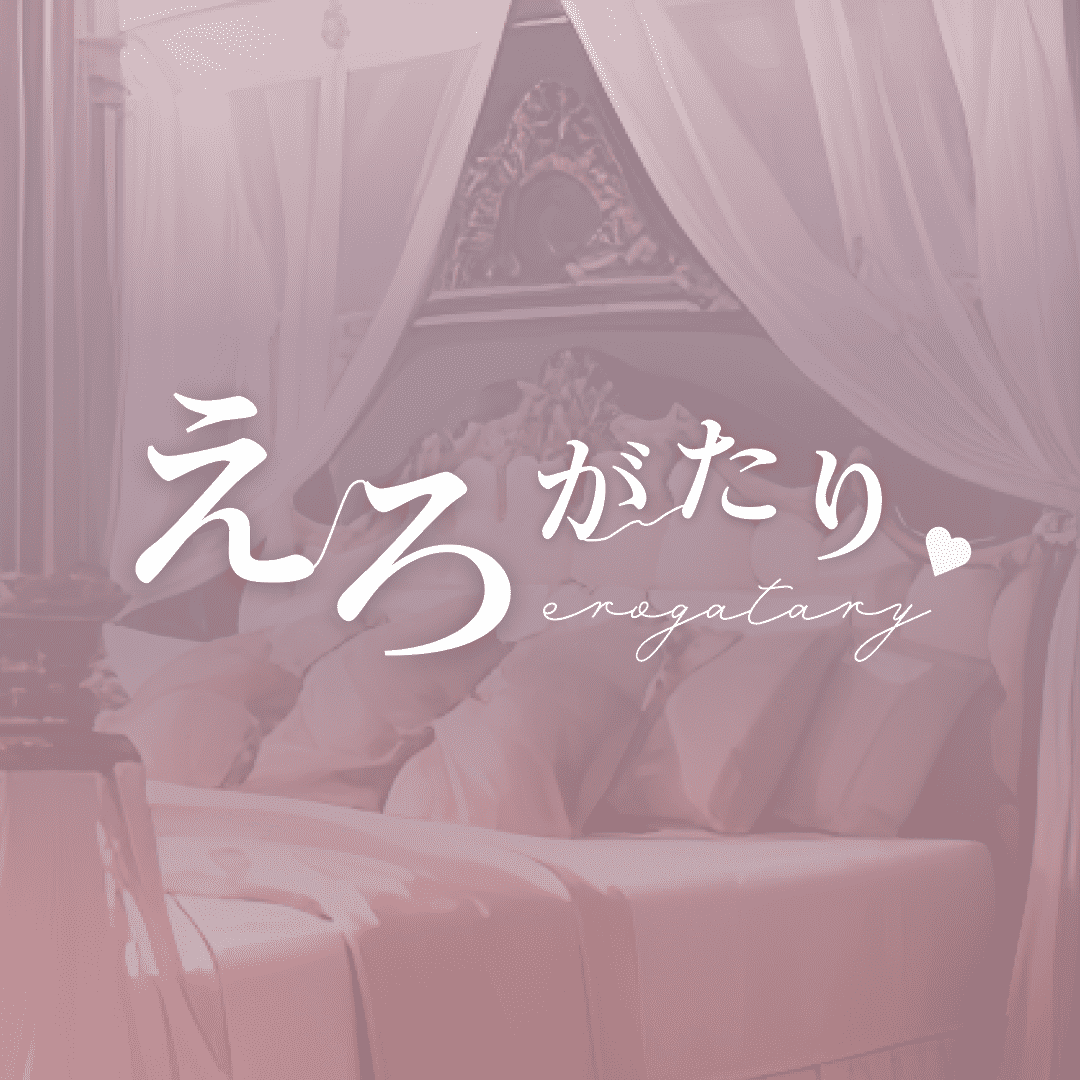



コメント