
0
俺は父と恋をする
愛する人ができた。7歳年上のその人は、僕ら兄弟が絶望の淵に立たされている時に突然現れた。父親の代わりではなく恋人になったのも運命だったのかもしれない。その人はモデルのような容姿をしていて、初めて出会った瞬間に胸がときめいたのは、さすがに自分の好みがはっきりしすぎているなと恥ずかしくなったのを覚えている。
「なんでこんなにかっこいいの……?」
「ミレはいつも俺のこと褒めてくれるな」
「そんな……そう思ってるから素直にそう言ってるだけなのに」
まっすぐな瞳に射抜かれそうになりながら、なんとかその顔を見つめながら言葉を紡ぐ。ズマの唇が近づいてきて、自然と触れ合う。唇を割って舌をさしこむと、さっき食べたばかりのフルーツゼリーの爽やかな味が広がった。果物を介してキスしているような、不思議な気分。くちゅくちゅと舌を絡ませていくと、頭の中がズマのことでいっぱいになっていく。
唇を離すと僕の頭を優しく撫でる。それから僕は、優しく服を脱がされていく。僕もズマの服を脱がせていくと、現役の刑事なのだとはっきりとわかるような、バランスよく鍛え上げられた肉体が見えてくる。柔道で全国大会レベルまでいったというのも頷ける。その鍛え上げられた硬い筋肉に、口づけをしていく。身体のパーツの何もかもが好きだと教え込むように、好きだと全部伝わるように。
見た目だけじゃない、俺たちのことを本気で支え、大切にしようというその優しさにも、僕は惚れてしまったのだ。父親の代わりでもあり、恋人でもある。この複雑な関係に、すんなり慣れることができたのも相性がいい証拠かもしれない。
こんな関係性になったのも、つい最近のことだ。僕とズマの出会いは3ヶ月前に遡る。
僕は持ち前の明るさでそこそこ友人も多い、どこにでもいる21歳の大学生だった。母が幼い頃に亡くなったが、刑事である父親が僕と僕の弟をまとめて面倒を見てくれていた。仕事が忙しく児童館に預けられることも多かったが、尊敬できる父親だった。憧れの父親のように強くなりたくて、幼い頃から剣道も続けていた。父親に関することがどれも過去形になってしまうのは、もうこの世にいないからだ。死に方にいいも悪いもないことはわかっているが、事故や病気ではなく、殉職だったところに父親らしさを今でも感じてしまう。
「俺たちどうすんだよ……」
葬式の日、弟が弱々しく発した言葉が頭にこびりついて離れない。講義も友達に会うのも楽しみだった大学も休みがちになった。とても勉強する気になどなれない。車の免許は持っていたから、高校生の弟を高校まで送っていくなどサポートできる部分はしていたが、だんだん限界に近づいていた。ご飯もそこまで食べていなかったから、どんどん痩せていった。大量に取りこぼした単位がある大学を辞めて就職しようかと考えていた時、その人がやってきた。
「ハヤテさんの息子さんだよね?」
「そう、ですけど……」
弟を高校に送り、家に帰ってきて一息ついていた時、手足が長くすらりとしたその男は家にきて、僕の父親の名前を口にした。
「あの、どなたですか?」
「カズマと言います。呼びづらいと思うのでズマとでも呼んでもらえれば」
「ズマ」
身分証代わりに警察手帳と保険証を見せられる。生年月日を見てささっと計算すると、俺より年上の28歳。顔が若いからか、あまり自分と年が離れているようにも思えない。マネキンのような体型に作り物のような美形で、目を見て話すのにどぎまぎしてしまう。
「君がミレくん?」
「そうです」
「弟くんは授業中か」
「夕方には迎えに行くつもりです」
そう言うとズマはペットボトルのお茶を飲み、ふうーと長くため息をついた。ズマは家に入ってきたばかりなのに、まるで昔から住んでいるかのようななじみ具合だ。
「単刀直入に言う。俺が2人の面倒を見る」
「えっ?」
ズマがそうはっきりと言い切った。あまりにも突然のことで受け入れるのに時間がかかるかと思いきや、僕はその言葉がきっかけでとある父親の話を思い出すことになった。
『お前たちふたりには、自分に何かあったら頼って欲しい人がいる。なかなか素質のあるやつだぞ』
ちょうど1年前くらいに、父親が僕たちに話してくれたことがある。そのときはそんな不謹慎なこと言うなよ、と少々いらつきながら返事をしたのをよく覚えている。その男がこの人だったのか。やっと出会うことができた。それにしても、父親も名前と顔くらい教えてくれていたらよかったのに。
「お葬式の時に挨拶しようかと思っていたけど、あまり時間がなくて」
「そうでしたか……」
「あと、全然タメ語で話してもらっていいから! 父親代わりって言っても全然年齢離れてないし」
「そっか、じゃあ……」
「緊張してる?」
どぎまぎしているのをすぐに見抜かれてしまった。どんだけわかりやすいんだよ僕は。かっこいい人を前にすると、うまく話せなくなるのだ。本当に昔からそう、わかりやすく面食いなのだ。
「すみません、顔が、好きで……」
「ミレくんおもしろいね」
「いや、そんな」
「もっと近づいたらどうなっちゃうかな?」
「もっ、もう!」
横に長いソファーに横並びで座っていたため、じりじりと距離を詰められると逃げられなくなってしまう。会ってすぐにイジられているのに、不思議と嫌な気分にはならなかった。
「まあ、お父さんの知り合いがちょっと世話しにきてる、って気持ちでいてよ。そんなに気負わずにさ」
「……じゃあ、お願いします」
「うん、こちらこそよろしくお願いします」
弟の高校が終わる時間にふたりで迎えに行き、車の中で自己紹介をした。弟も新しい兄がひとり増えたみたいで嬉しい、と言っており、すんなり3人暮らしが始まった。
「大学には行った方がいいぞ。将来何になるにしてもな」
ある休みの日、大学をやめるかどうか迷っているとズマに相談すると、そう答えてくれた。
「自分で自分の選択肢を狭める必要もないだろ。家のことは俺がやるし、明日から行ってこい」
その言葉で僕はまた大学に通えるようになった。大学に行って勉強するのも、3人で食卓を囲むのも、全部懐かしい。どれをしても父親との思い出を超えられないけれど、それでも楽しい毎日を過ごしてきた。
いつしか僕は、ズマのことを父親の代わりではなく、好きな人として見るようになっていた。見た目はもちろんのこと、僕たちのためになんでもしようと努力してくれている姿を見ていると、勝手に鼓動が速くなってしまうようになったのだ。そのことは、ズマが出勤の日、僕と弟だけで昼ごはんを食べていた時に指摘された。
「兄ちゃんさ、ズマのこと好きでしょ?」
「なんで?」
「見る目がさあ、明らかに好きな人見てる目、って感じする」
「まじか……」
身内にバレバレとか恥ずかしすぎる。弟いわく、僕はだいぶ見ててわかりやすい人間らしいけれど。
「どうすんの?なんにも言わずにこのまま過ごすのってキツくない?」
「まあたしかに、な」
このまま気持ちを押し殺したまま生活するのは確かにきつい。ズマとあんなことやこんなことをする妄想を繰り広げたのも一度や二度じゃないのだ。
「俺さ、今晩友達ん家行くから、言うなら今日だって」
弟にそう言われ、僕はその日の晩にズマに告白をした。返ってきた言葉は、想像もしていなかった言葉だった。
「俺もずっと最初から、ミレのことが好きだよ」
「なんで、」
「俺のこと見てる目があまりにも可愛かったから。父親代わりとしてこの家に来たけど、これからは恋人として、もっと深い関係になろうな」
その言葉を聞いて、堪えきれなかった涙が頬を伝っていった。その涙も丁寧に拭いてくれた。その日僕はズマと初めての経験をして、それから現在に至る。
ズマの鍛え上げられた身体に口付けていると、簡単に身体を持ち上げられてしまった。目を合わせたまま膝の上に乗るように言われ、その通りにする。
「これ、なんて言うか知ってる?」
「わかんない……」
「対面座位。今日はかわいいミレにたくさん上で動いてもらおっかなって」
「ん……」
さっきほぐしてきた秘部を、がちがちになっているズマのちんこにあてがう。ゆっくりと腰をおろそうとしても、なかが期待してるようにきゅんきゅんと締まってなかなかうまく動けない。
「ズマ、むりかも……なか、きゅんきゅん、って……」
「じゃあ手伝ってやらないとな」
「ぁああッ!」
肩を力強く押され、奥まで一気に入ってしまった。あまりの衝撃に、勝手に涙がぽろぽろと溢れてくる。涙を拭う間もなく、下からがんがんと突き上げられていく。
「んああっ、ぼく、がっ、動くって」
「なかが締まって動けないんだろ?俺が手助けしないと」
「やぁああっ、あっ、ああっ!」
下からごりゅごりゅと突かれるたびに、はしたない声が漏れてしまう。ちょうど前立腺に当たるような動きをされ、あっという間に触っていない自分のちんぽからとろとろと精液を漏らしてしまった。
「ところてんできるようになってすごいなあ、ミレ」
「ん……もう、気持ち良すぎて、苦し……っ」
「じゃあ俺もそろそろ出そうかな」
「あぁああっ、あっ、あああっ激、しいッ!」
なかに挿入されたまま押し倒され、腰を強く掴まれたまま強くピストンされる。はあはあと荒い息を漏らしているズマの綺麗な顔から、ぴちゅと汗が垂れてきた。もうなんだって嬉しい。ズマがくれるものならなんだって、僕の栄養になってくれる。
「ミレ……好きだよ、俺とこうなってくれて、ありがとう」
「ん……ぼく、も……っ!」
再び唇が重なる。舌を軽く歯で噛まれ、ぴりりとした痛みが広がる。いまはこの痛みだって愛おしい。好きな人からであれば、痛みでも快感に変わるというのはどうやら本当らしい。ズマに会って初めて知ったことがあまりにも多すぎて、知るたびにズマを好きになっていく。
「ミレ……出るっ」
なかに入っているズマのちんぽがもう一度膨らみ、それからびゅくびゅくと生暖かいものが僕のなかに広がっていく。ズマがこの家にきてくれたことも運命なのだとはっきりと言える。世間から見たら特殊な出会いだとは思う。だけどこの大切な人と助け合いながら、これからも幸せに生きていくつもりだ。






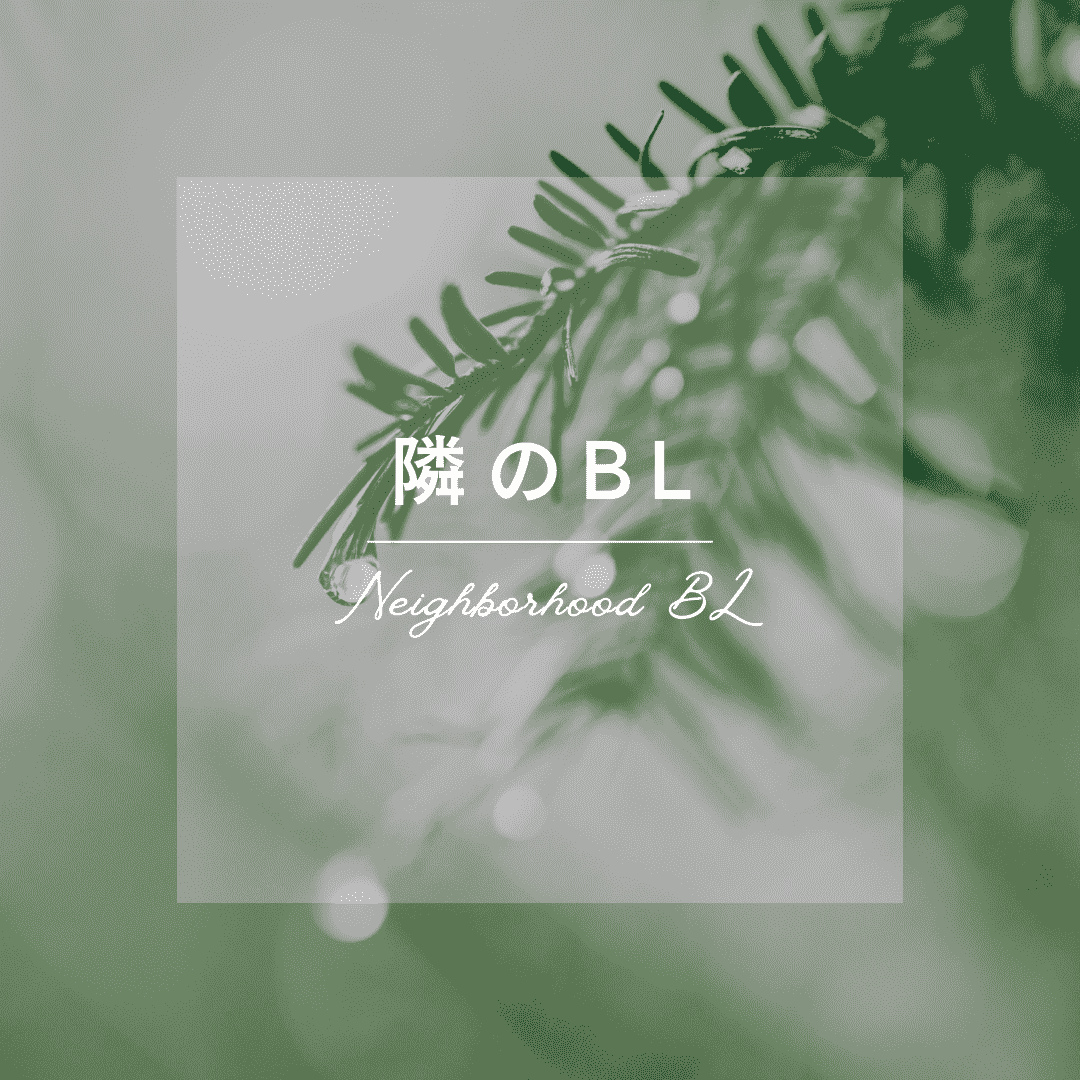
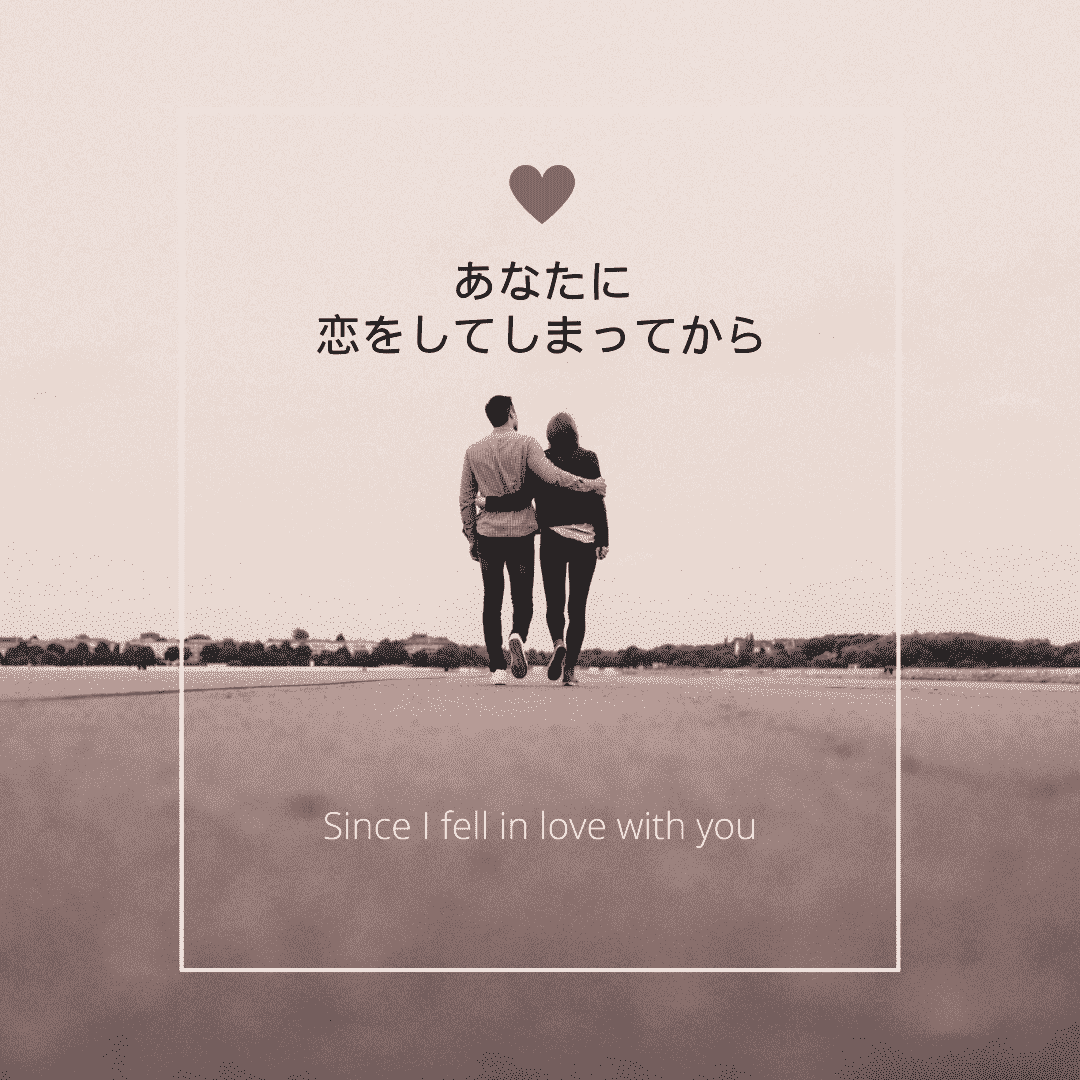

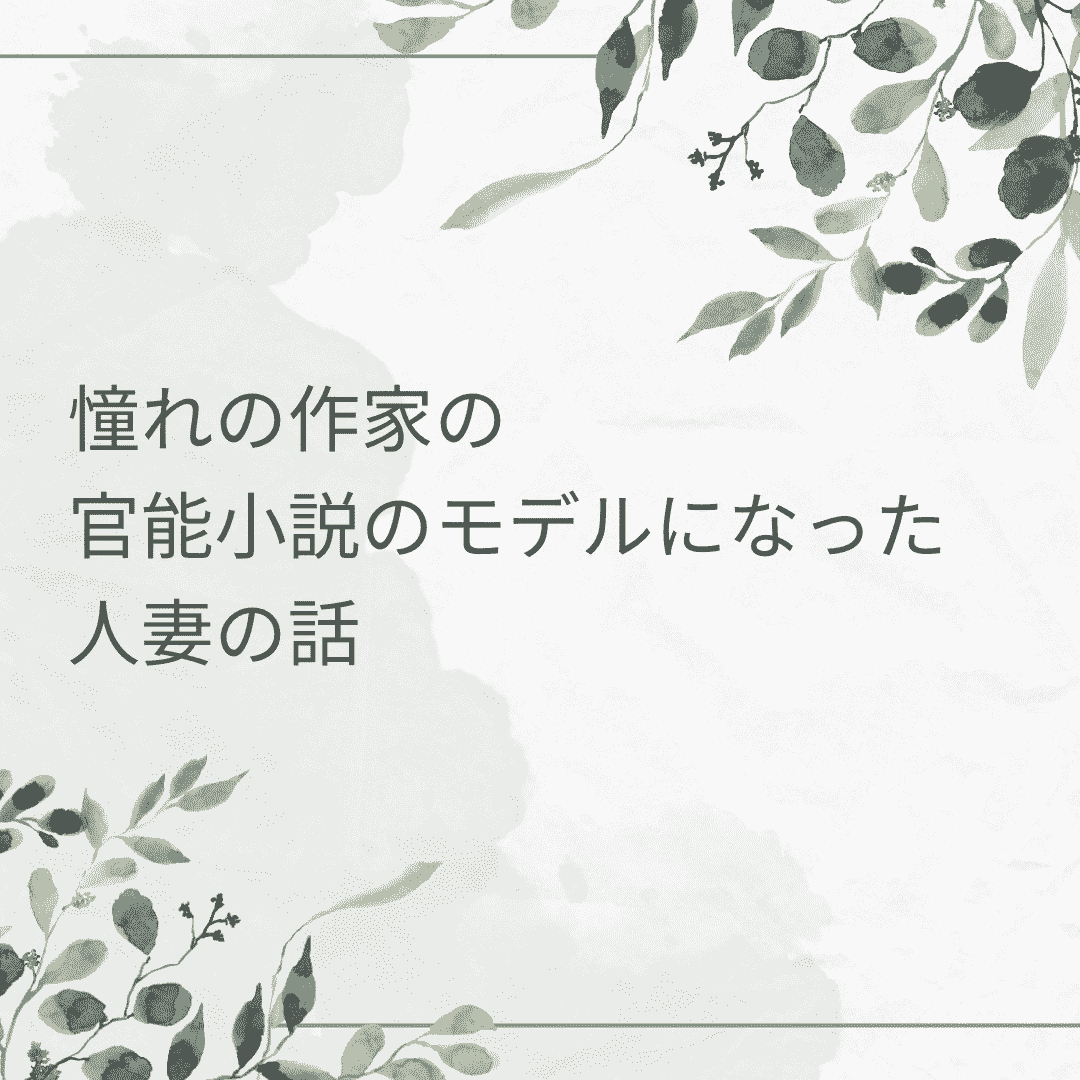


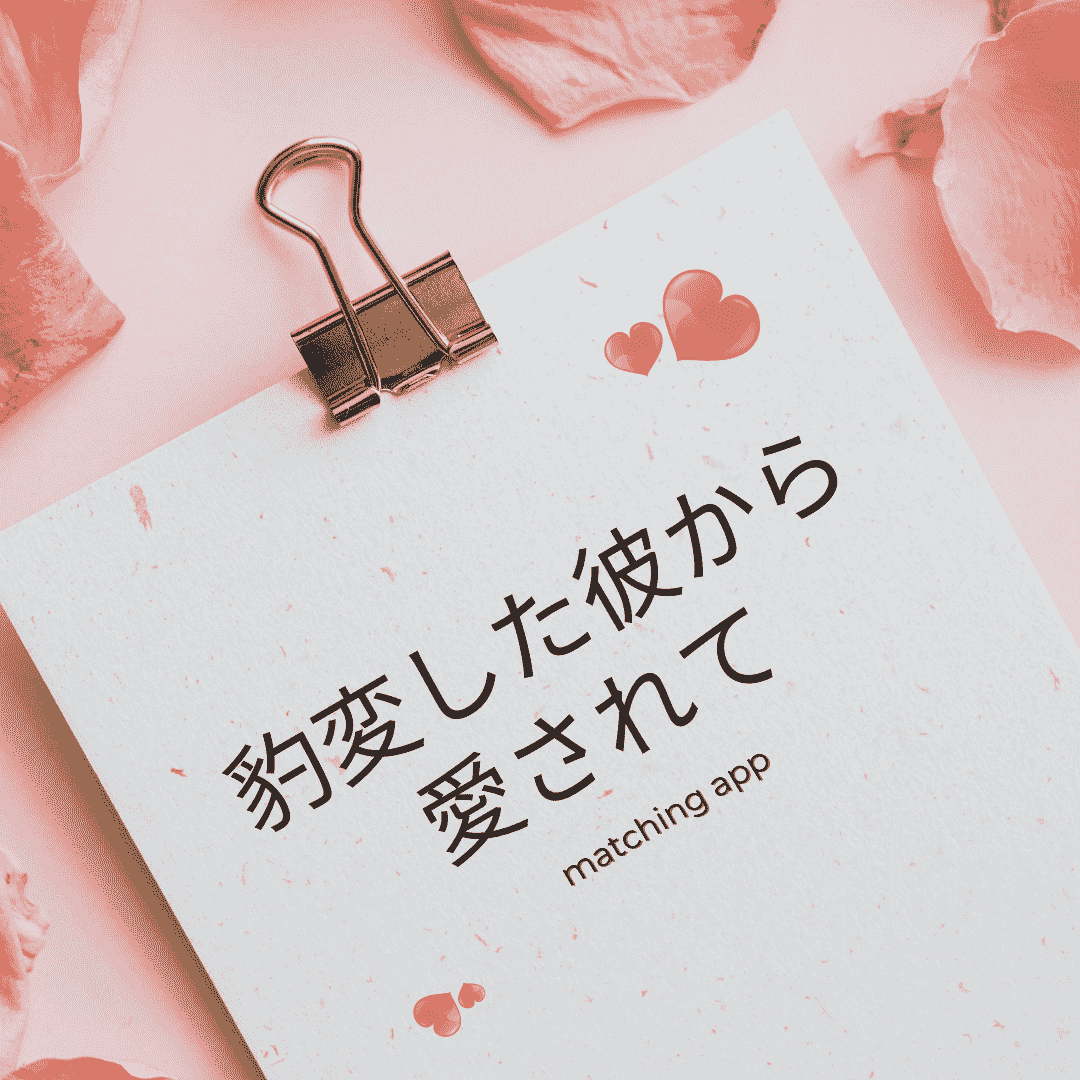

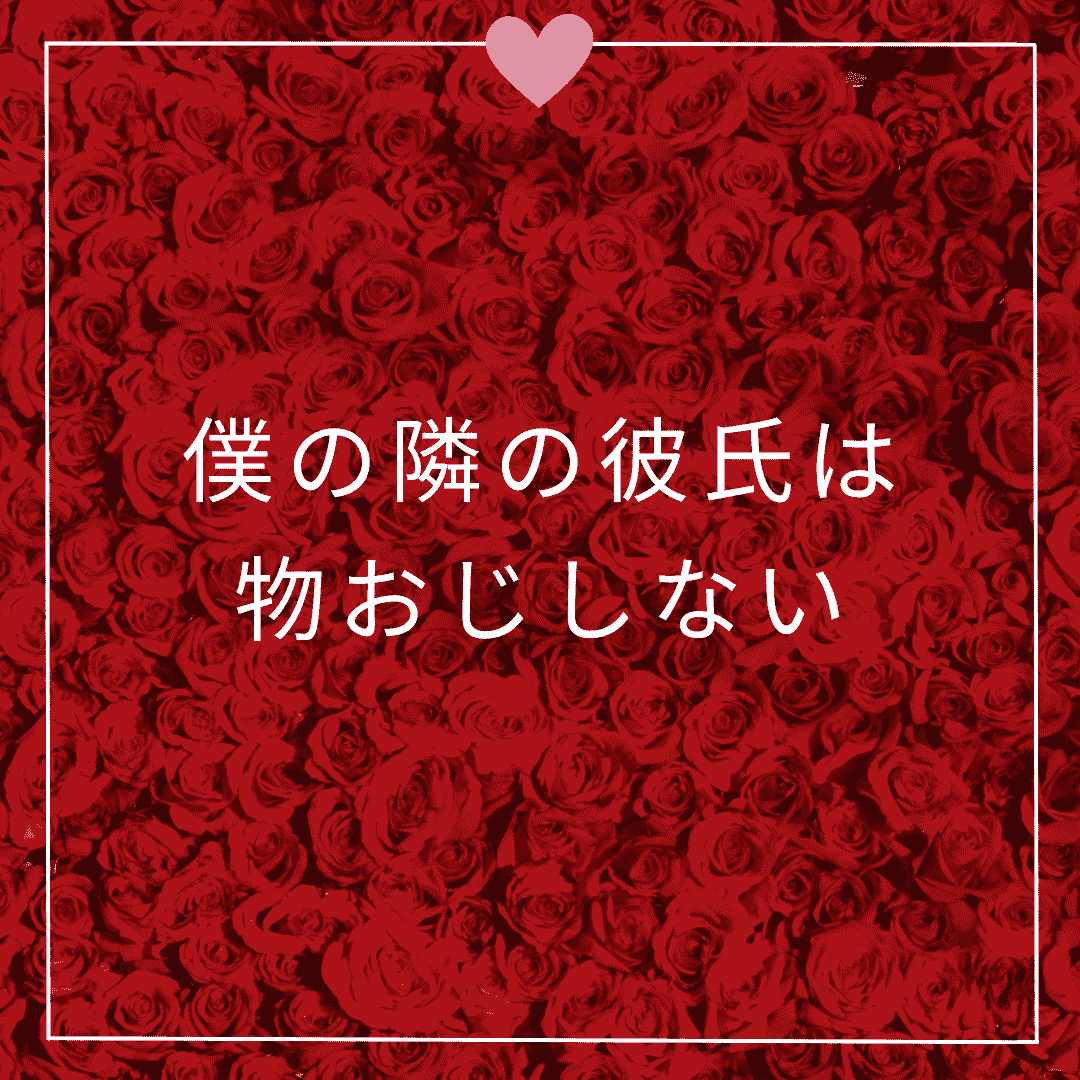
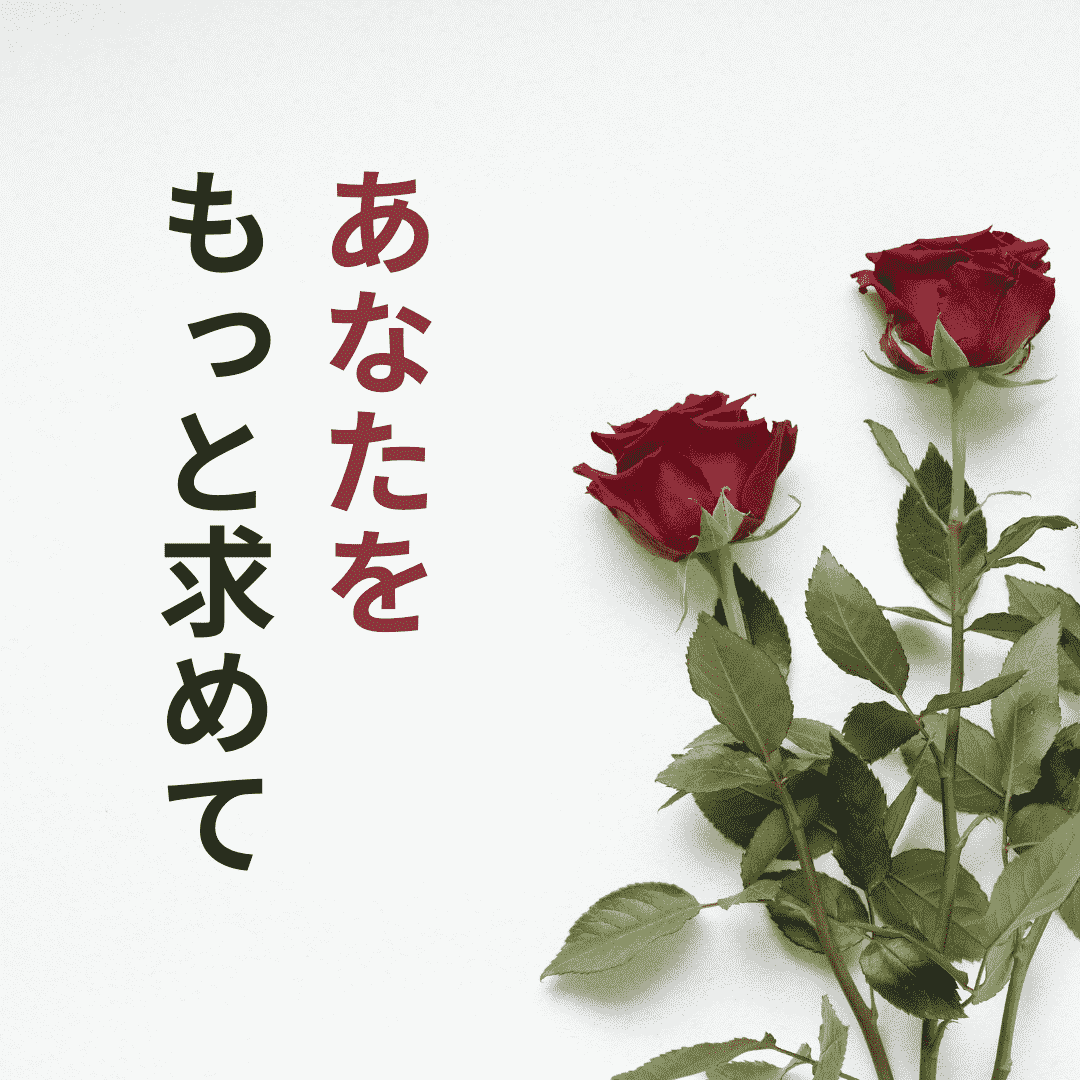





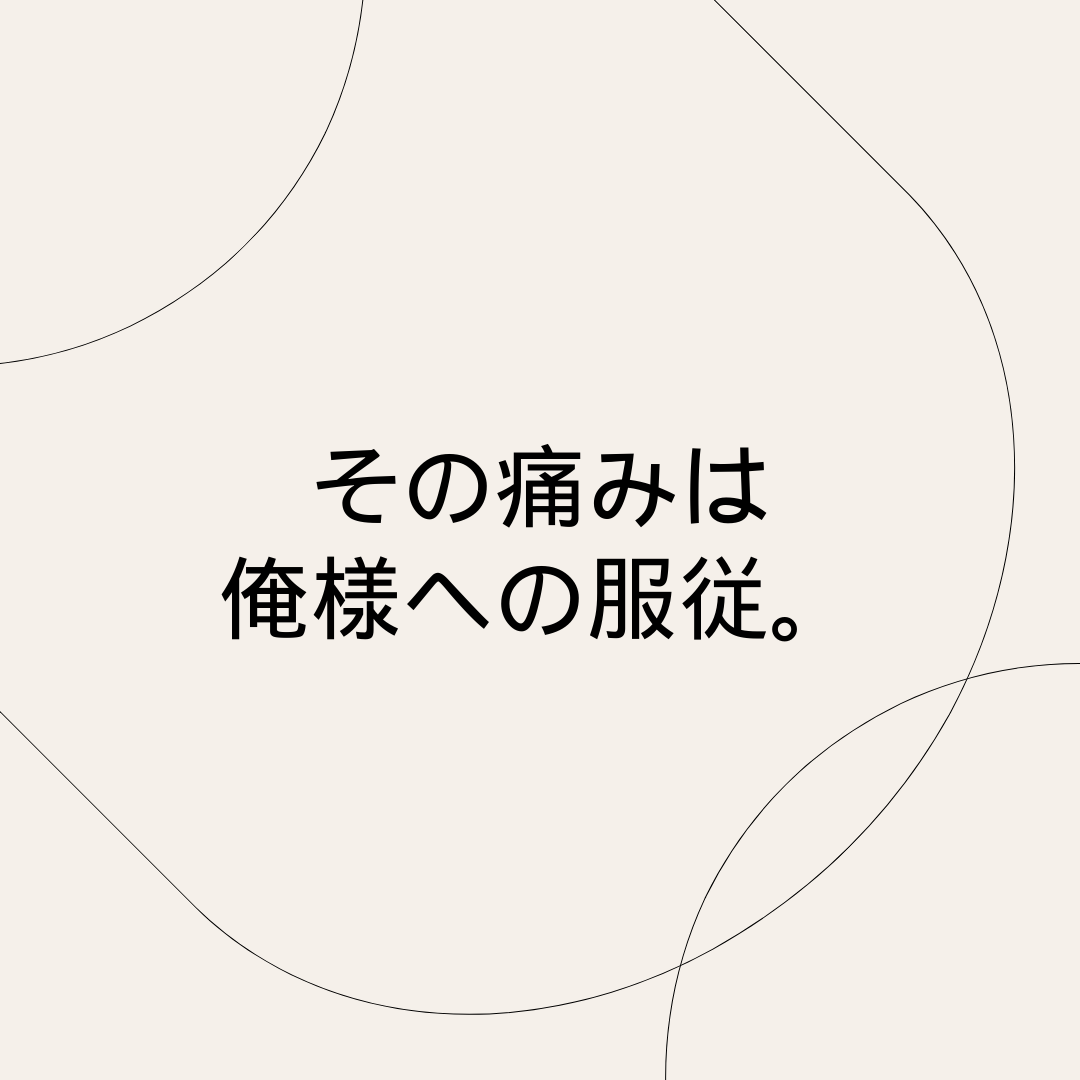

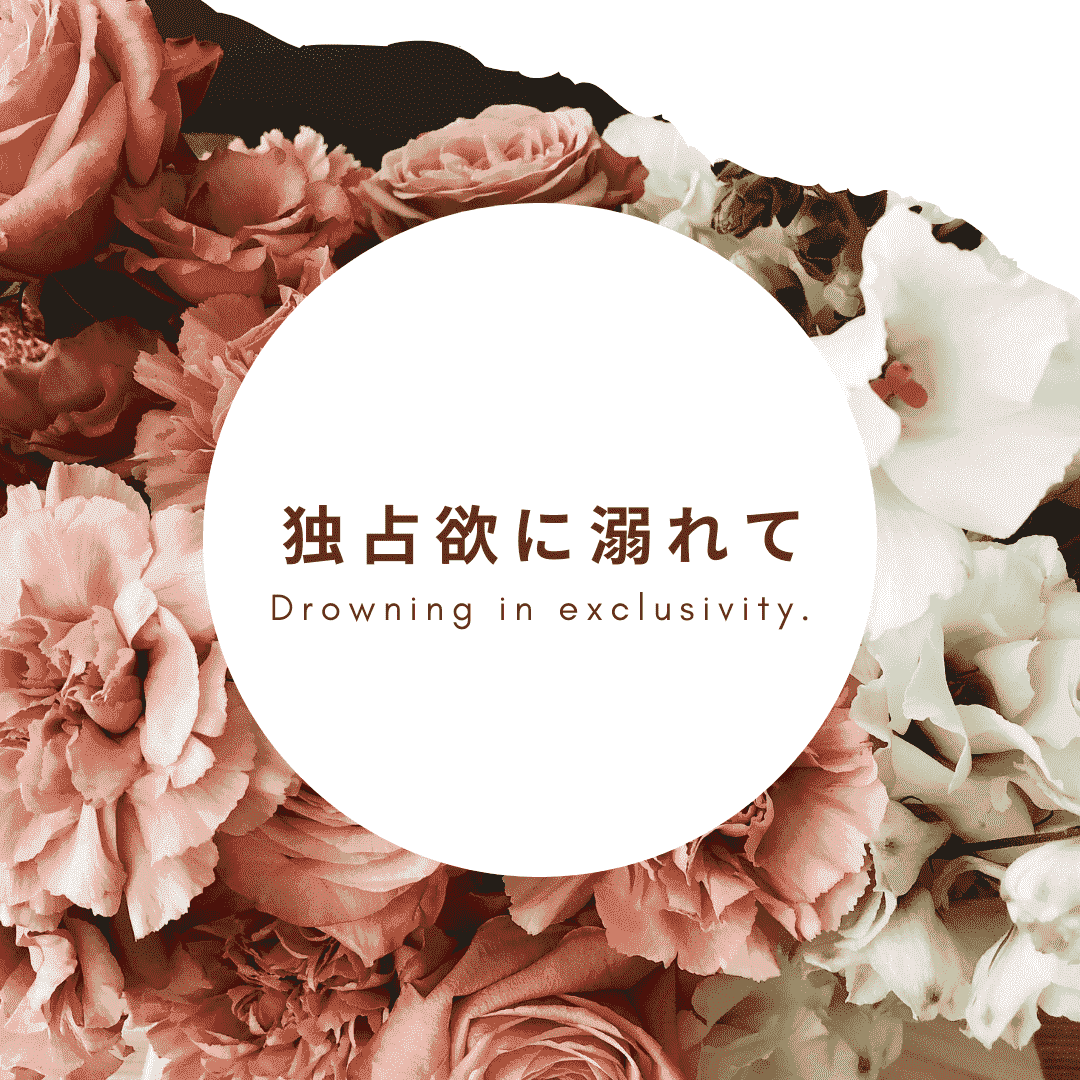
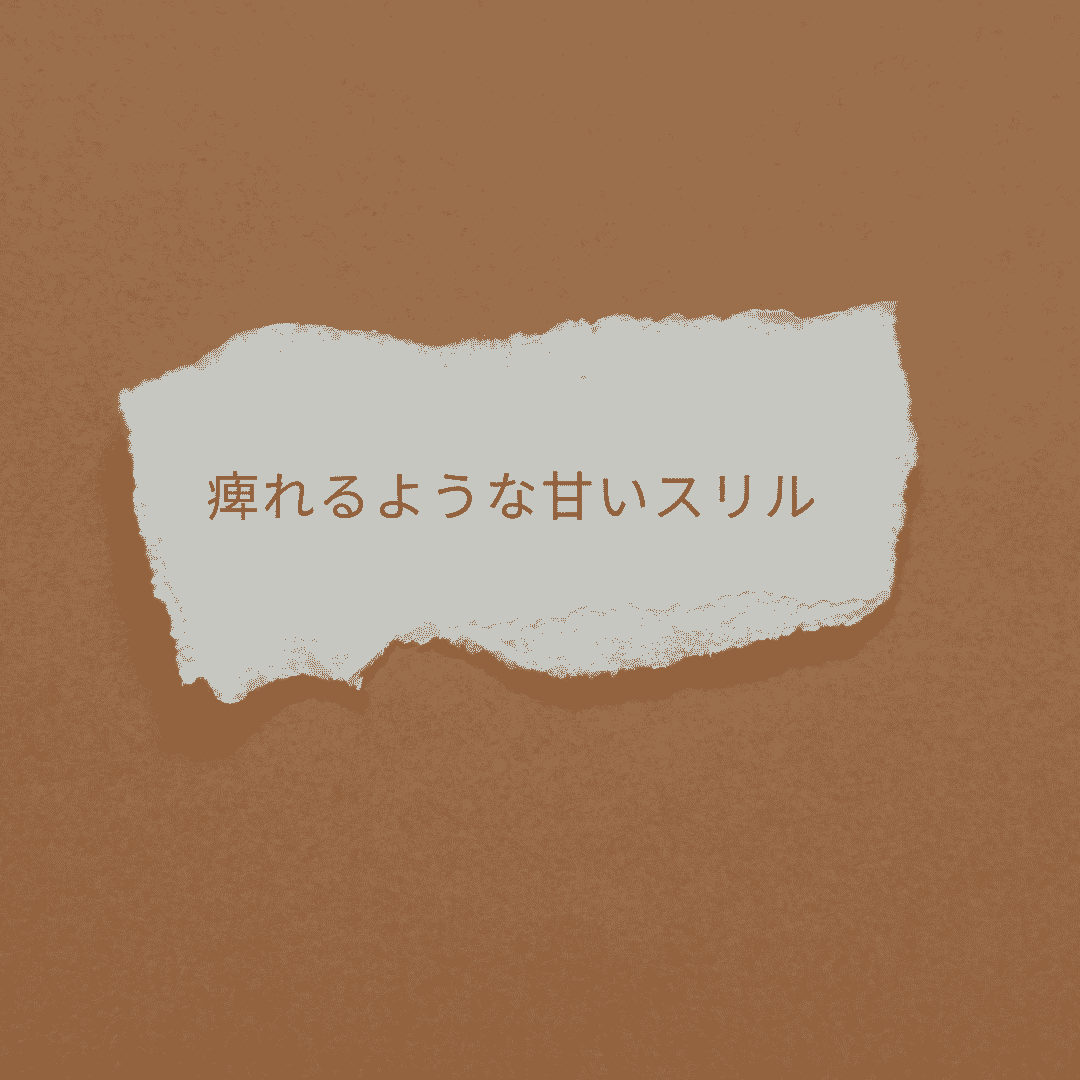


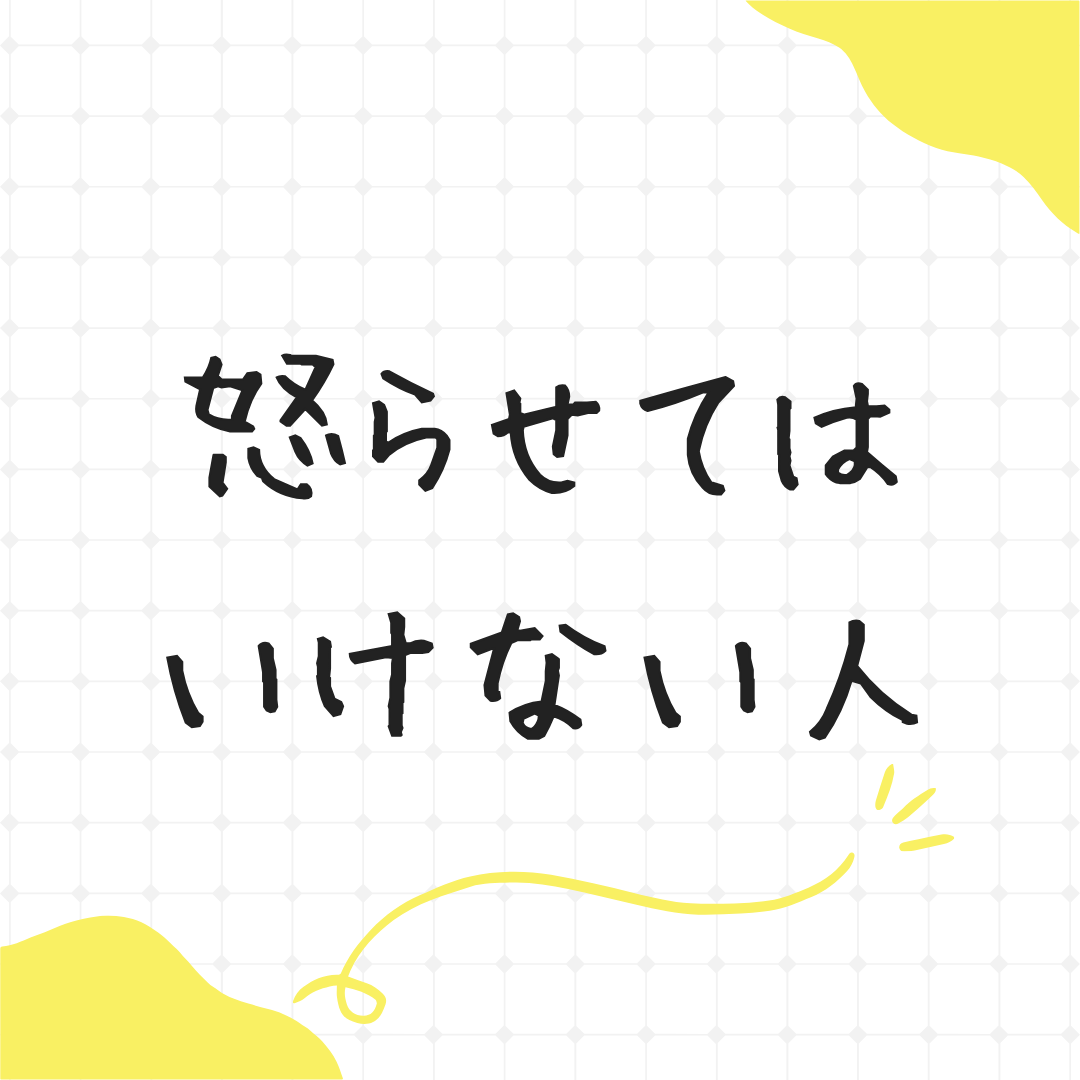

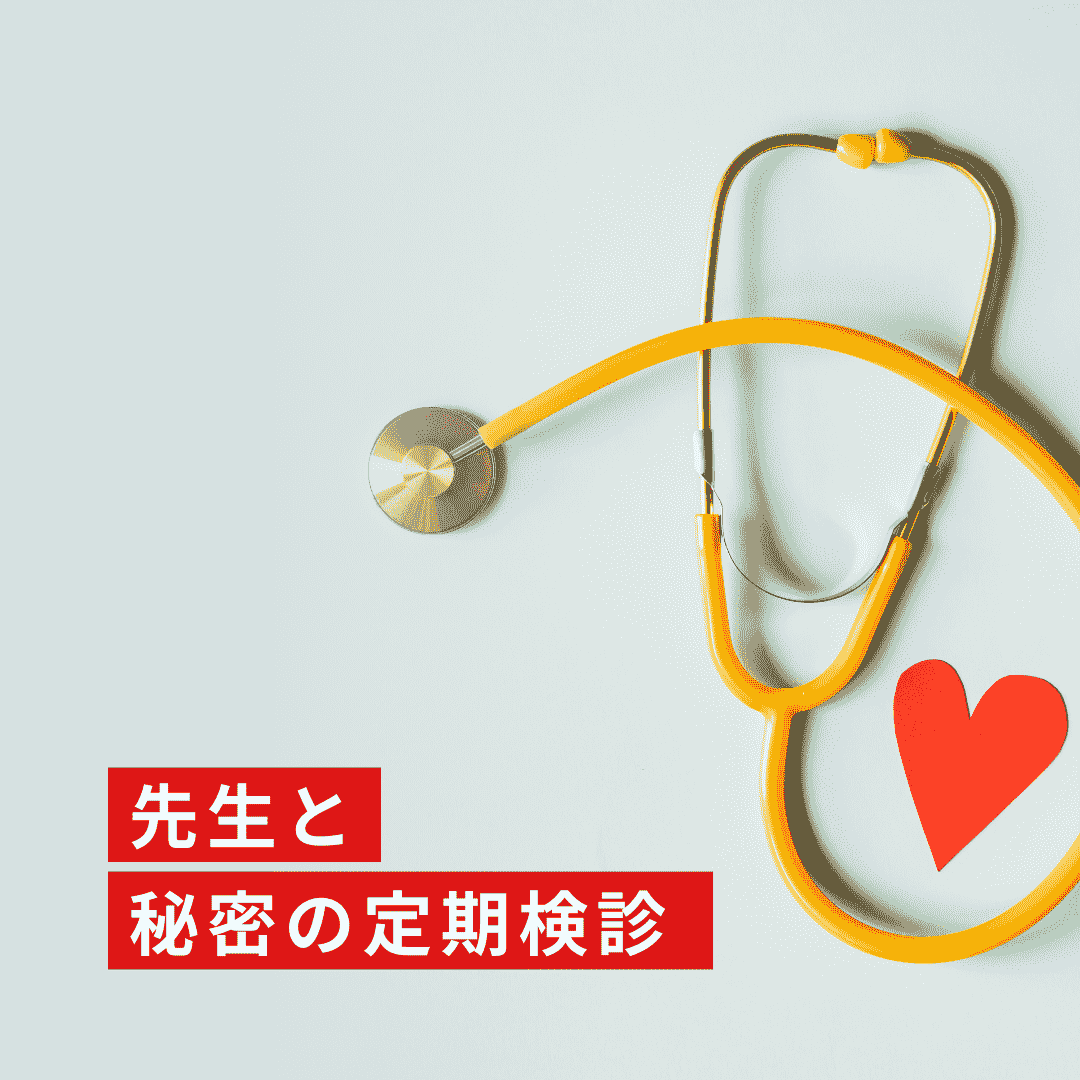
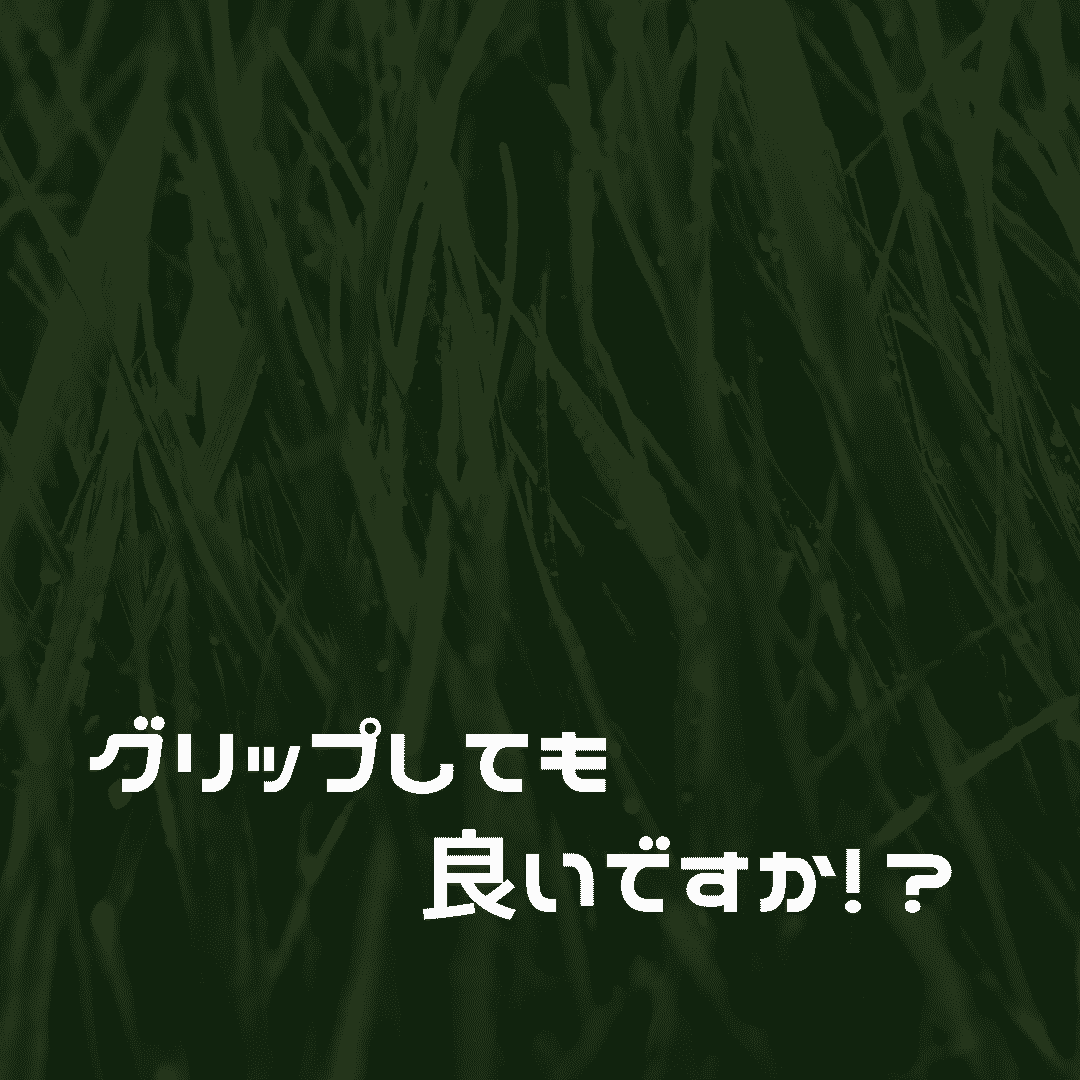
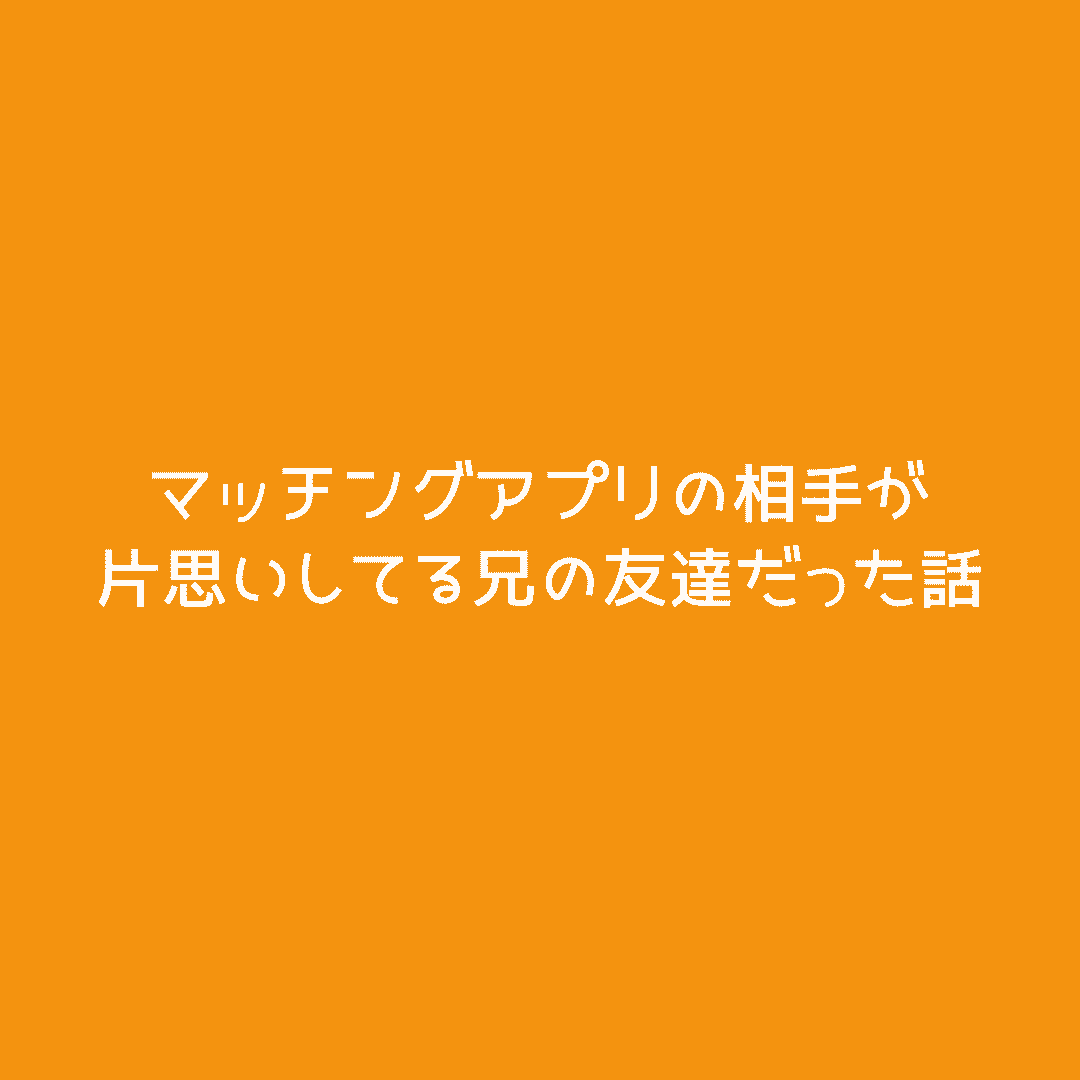
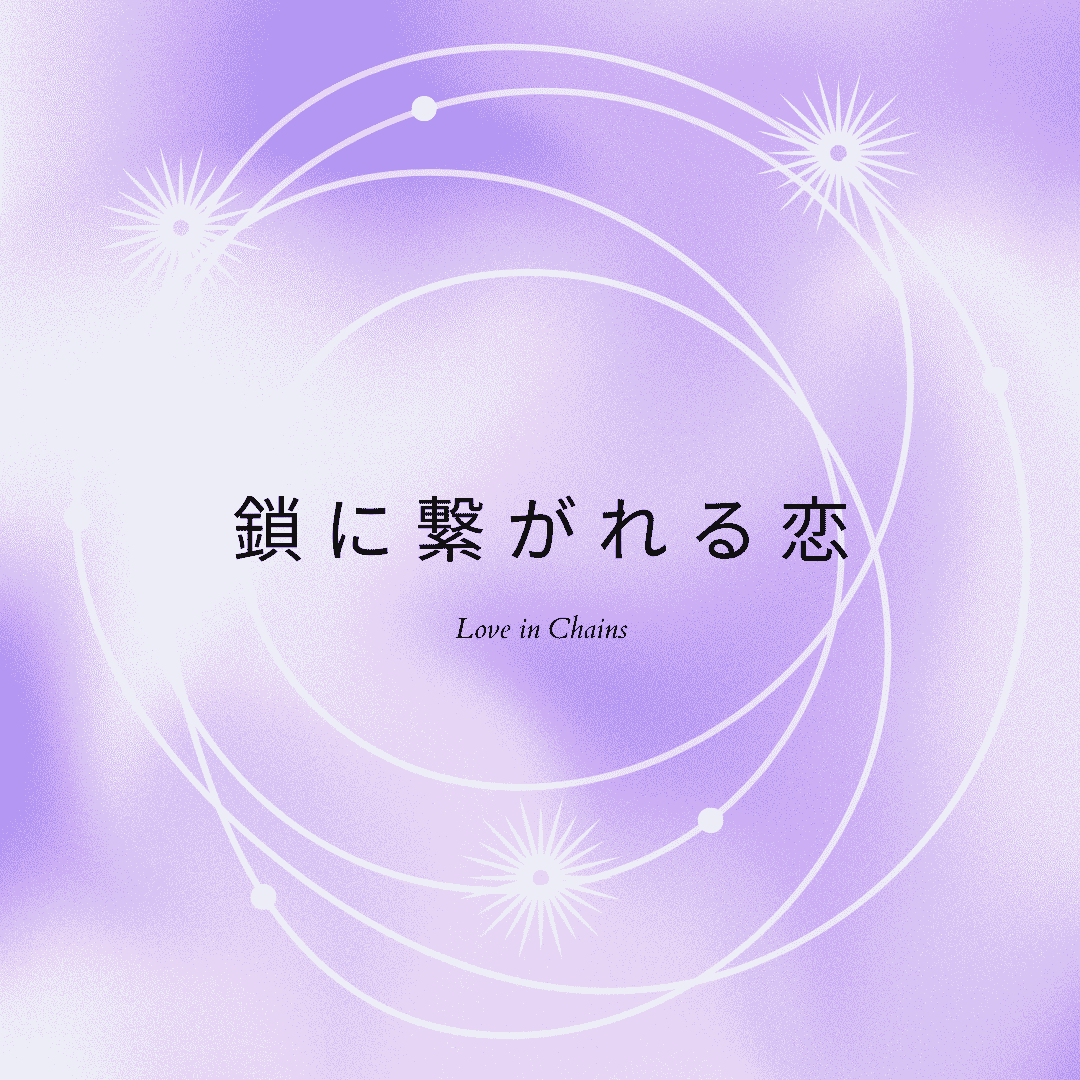


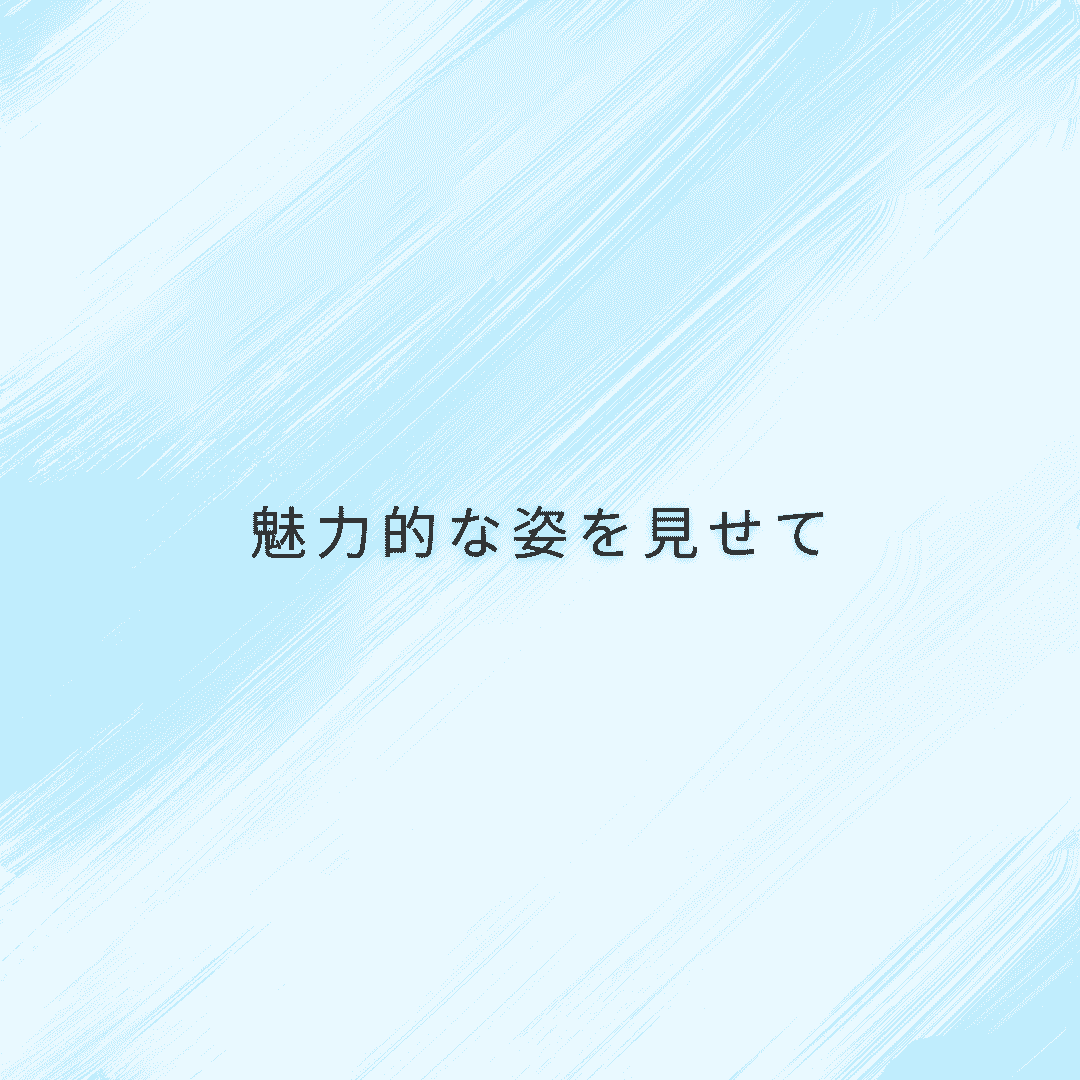
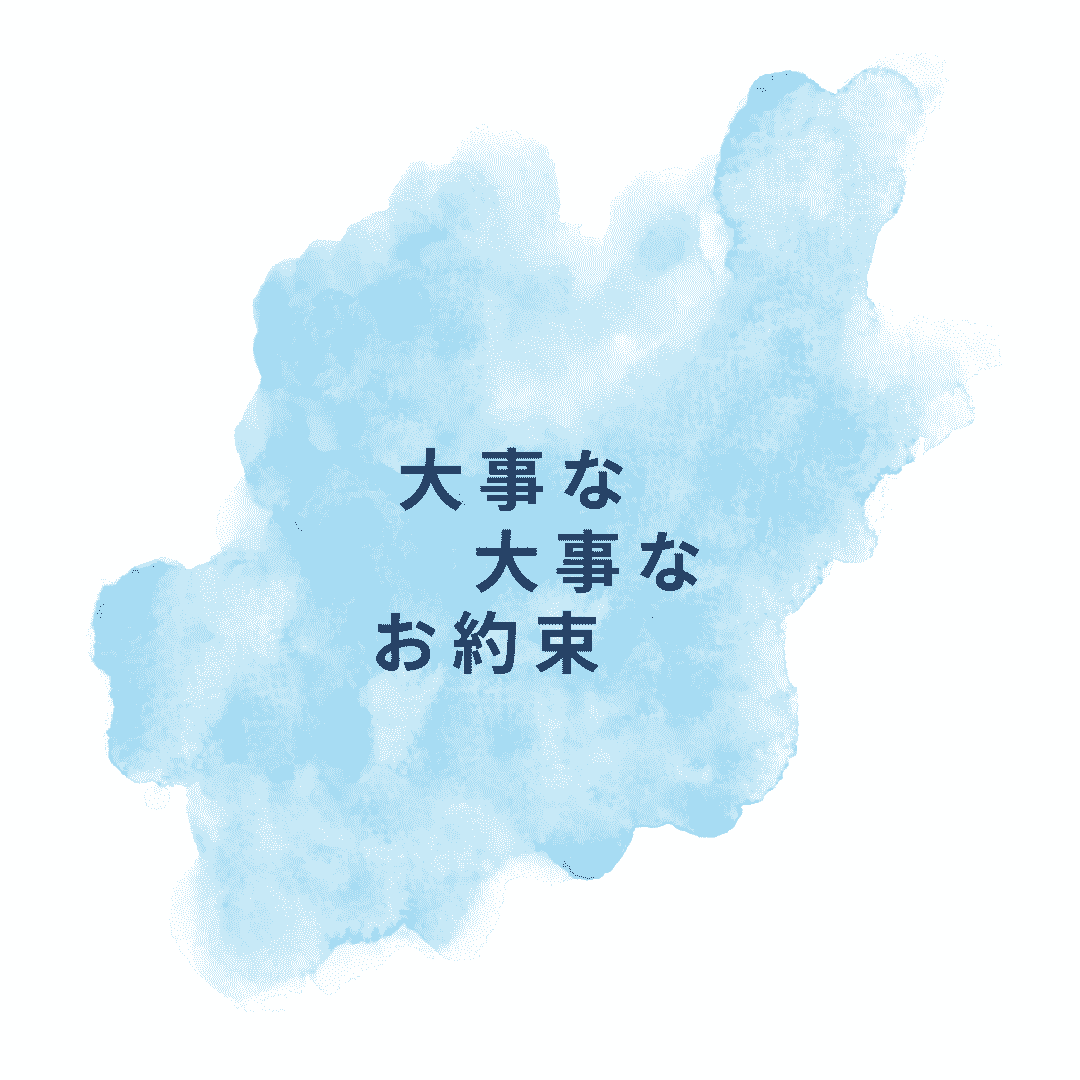

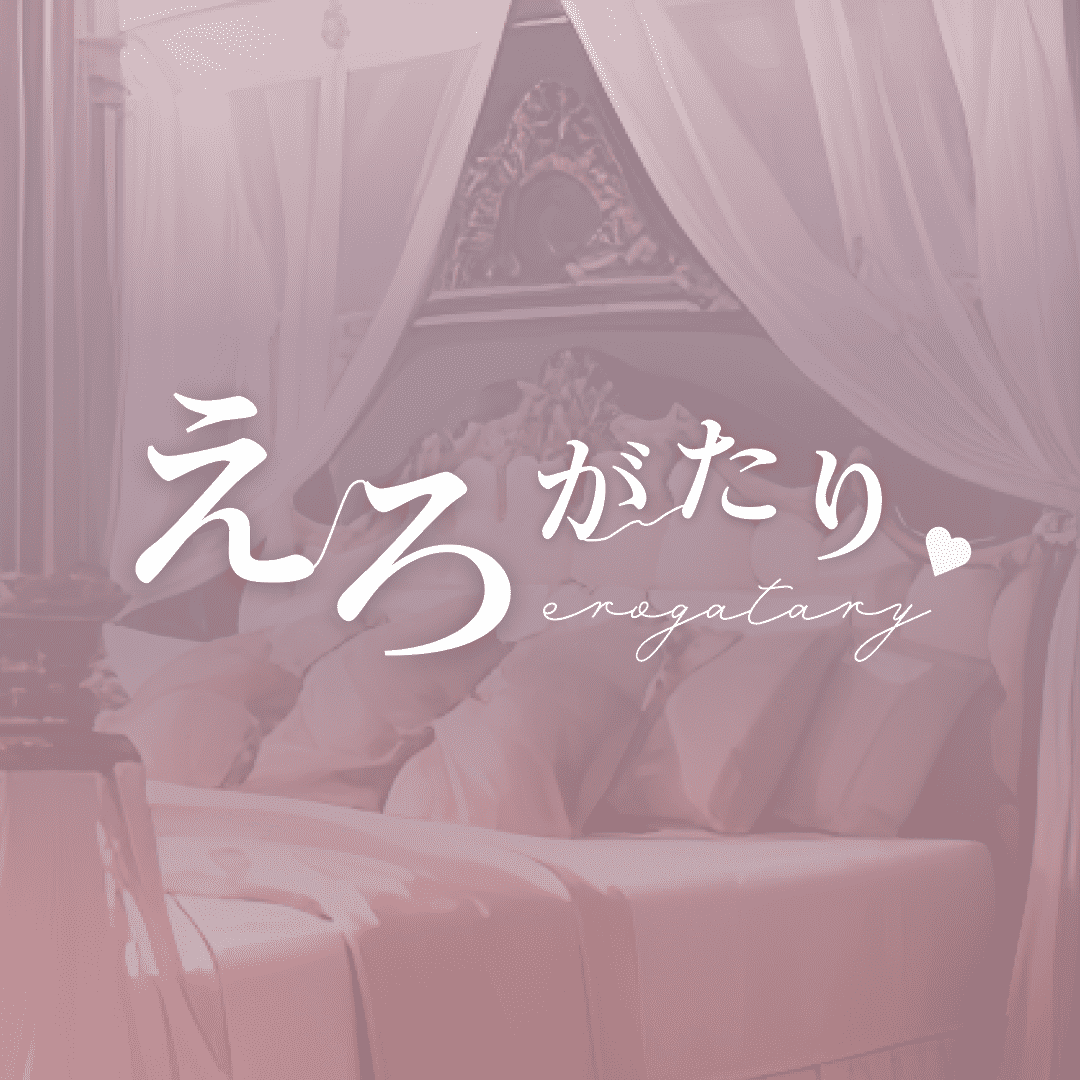



コメント