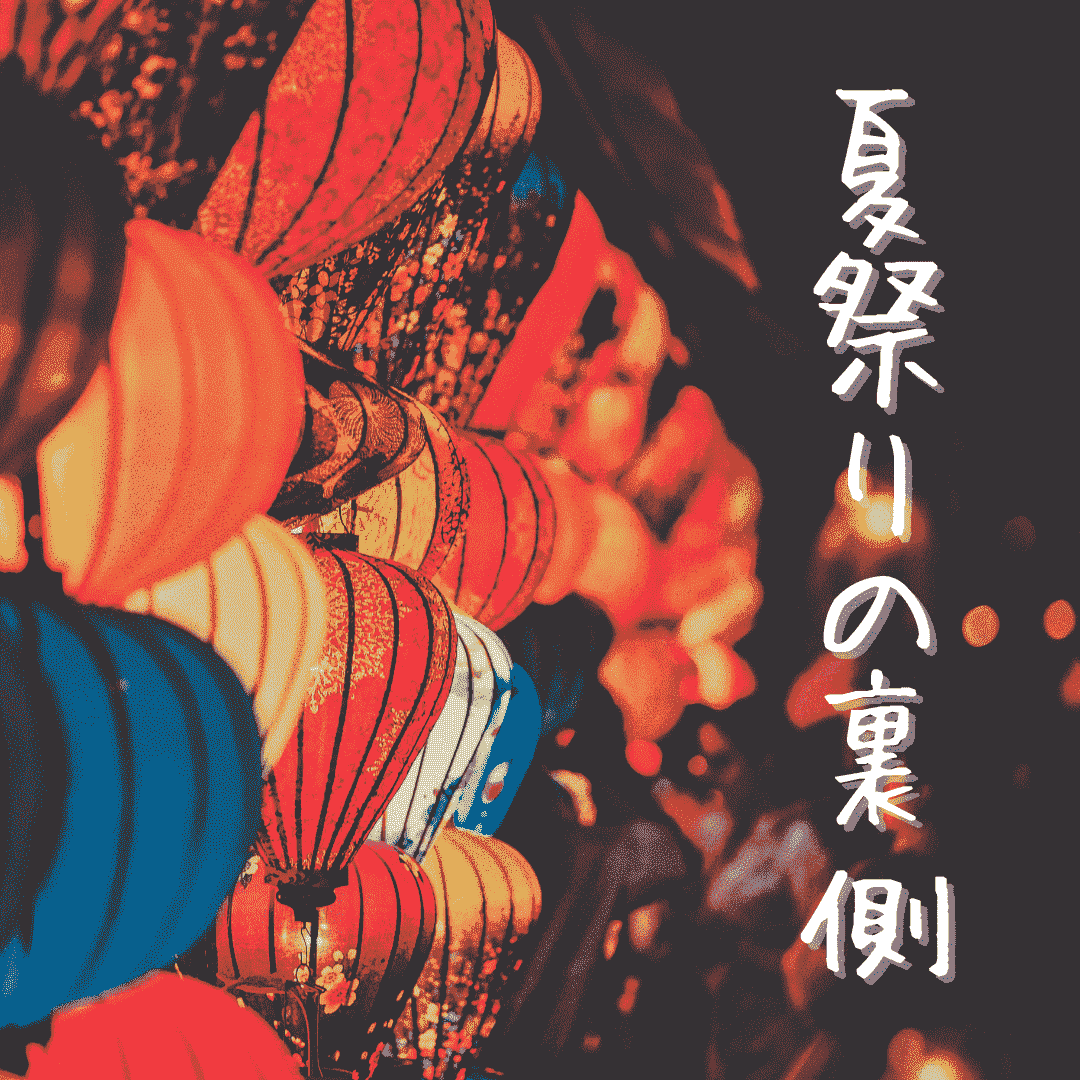
0
夏祭りの裏側
「シャン、シャン」と神楽鈴を鳴らしながら、千春は舞っている。
今日は神社の本祭で、見物に来ている客も、たいそう多い。
神社の一人娘の千春は、巫女の中でも一番舞が上手い。彼女目当ての見物客もいるくらいだ。左手に御幣(ごへい)を持ち、右手で神楽鈴を鳴らしながら舞い続けていた千春は、見物客の中に太一がいるのに気づいた。
「太一、約束どおり、見に来てくれたんだ!」と喜んだ千春の舞に、いっそう熱がこもった。
舞を終えた千春は、更衣室で千早(舞衣)を脱ぎ、胸に巻いていた木綿のサラシをほどいた。サラシで押さえつけられていた千春のふくらみが、大きく弾ける。
「ふううぅぅ〜」と千春は大きく安堵の息をもらした。
「千春ちゃんの胸、去年より一段と大きくなったのぉ。」
一緒に神楽を舞っていた先輩の巫女が、千春に声をかけてきた。
「太一さん、来とるんじゃろ?その胸なら、太一さんもメロメロやでぇ。」
「今日は本祭やし、花火もあるから、いっぱい可愛がってもうらうとええで。」
先輩たちから投げかけられるいやらしい会話に、千春は恥ずかしそうに頬を赤らめ、そそくさと浴衣に着替えた。
「頑張ってね〜」という皆の声に追い立てられながら、更衣室を後にした千春は、太一との待ち合わせ場所に急いで向かった。
赤い顔で、待ち合わせ場所に現れた千春。
「またオバちゃんたちに、からかわれたん?」
「ま、まあね。」
「神楽、去年よりずっと上手くなったね。」
太一は千春の神楽舞を褒めてくれた。
「えへへ…ありがとう。」と千春は照れながら笑う。
「苦しくなかった?」
千春の、豊満な胸を見つめながら聞く太一。
「もう、エッチ!仕方ないじゃない。」
そういいながら、千春は、以前太一に神楽舞の練習を見てもらったときのことを思い出す。Tシャツ、ノーブラで舞う千春のおっぱいは、姿勢を変えるたびに揺れて、太一を魅了し続けた。挙句の果てに、千春の舞が終わるまで太一は我慢できず、千春に襲いかかったのだ。
「み、みんなに襲いかかられちゃ、たまんないから…」
その時の太一の行動を思い出した千春は、太一の手を握り、赤くなった顔を見せないように、一歩先を歩き出す。
「神主になる修行は、どの辺まですすんだの?」
太一と千春は、許嫁の仲である。
「やっと半分ってとこかな? 祝詞(のりと)とか結構むずかしいぞ。」
「まだ一年もかかるのかあ、早く終わらないかな。」
「そう、せかすなよ。」
太一は都会で働きながら、神主になる修行をしていた。
「今年は出店が多いね、去年は寂しかったな。」
「コロナが一段落したからね。去年と同じじゃたまらないわ。」
「今年は去年の分の花火も一緒に打ち上げるらしいから、きっとすごいわよ。」
二人は参道の脇から、目的地の御神木がある林道に入った。ここから御神木の社までは、比較的緩やかな階段が続いている。
…林道に入って少しすると、脇の茂みから「あん、あん…」という喘ぎ声が聞こえてきた。
「…こ、今年は特にすごいね。」
周りの藪や茂みには、カップルが何組いるのかわからない。声だけならまだしも、「くちゅくちゅくちゅ…」「パンっパンっ」という行為の音も聞こえてくる。林道に街灯はついているが、脇の茂みまでは光が届かない。それでも千春は茂みから、むき出しの白いお尻や動く脚が見えたような気がしてしまう。
「まあ、この神社はこれで結構、有名だしな。」
野外プレイ目当てでくるカップルも、結構いると聞く。地元の警察も村おこしのためなのか、事件にでもならない限りは、黙認状態である。
周りから聞こえる喘ぎ声といやらしい音に、千春はいたたまれなくなる。そして、繋いでいた手を離すと、太一の腕にすがりついた。二の腕にあたる千春の柔らかいおっぱいの感触を楽しみながら、太一は「大丈夫だよ、さ、行こう。」と歩き出した。
林道を登り切ったところに御神木の社がある。ここまでくると、とても静かになり、誰の声も、いやらしい音も聞こえない。社の入口には鍵がかかっていて、神主である千春しか開けることはできなかった。
「やっぱり、ここは静かだな。」
「みんな、怖がって近づかないわよ。ここは神主しか入れないもの。昔、入ろうとした人が雷に打たれて
死んだっていう伝説、聞いたことあるでしょ?」
「太一だって、浮気したら天罰があたるわよ。」と、千春は悪戯っぽく太一を睨む。
「お、脅かすなよ。」
社の中は八畳位の板間で何もない。奥の格子戸越しに、月明かりに照らされた、御神木だけが見える。
ここは太一との思い出の場所だ。初めてキスされたのもここだったし、初めてのエッチもここだったな…と千春は思い出しながら、奥の格子戸を開けようと中に進んだ。
「千春っ」と、太一がいきなり抱きついてくる。
我慢できなくなった太一が、熱い欲情の吐息を首筋に吹きかけながら、激しく口づけしてくる。そのまま、舌をねっとりと絡ませてきたのだ。
「んっ……ん。」と千春も舌を絡ませて、それに答えた。
太一は浴衣の上から千春のお尻をわしづかみにした。千春は浴衣の下に、下着を何もつけていない。千春のお尻をつかんだまま、太一は跪き、浴衣の隙間から千春の股間に顔をうずめた。
「あっや、やめ…っ」
パンティを履いていない、生のアソコにいきなりキスされたのだから、たまらない。太一はすでに濡れそぼっている千春のアソコを、荒々しく吸い始めた。
「ん!んぁああっ…」と太一の頭をひきつけながら、喘ぐ千春。
愛液があとからあとから湧き出してきて、太一の顔をどんどん濡らしていった。気持ちよさのあまり、そのまま立ち続けていることができず、千春はその場にへたりこんだ。へたりこみながらも、両脚を広げ、太一の顔を股間におしつける。
「あ!おねが…もっと…もっ……」
叫ぶ千春に応えて、太一は千春の両脚を肩にかつぎ、上半身を起こした。
千春のアソコが太一の目の前で露わになった。
「え、ちょ、ちょっと太一…!」
大胆な行動におどろく千春には、目もくれず、太一は目の前であらわになった千春のクリトリスを、舌でなめ、吸いついた。
「んあ!ぁぁぁっ!ぁあああ~~~!」
半ば、失神したようなたまらない感覚で、頭の中が真っ白になる。
太一は立ち上がると、自分の浴衣の前をはだけ、パンツを脱ぎ始めた。そして、押さえつけられていた長大な肉棒が現れる…。
「僕のも、してくれる?」
といって、太一は巨大な肉棒を近づけてくる。千春は太一の前にしゃがみこむと、両手で肉棒を握りしめた。先端は先走りの液で濡れており、ビクンビクンと脈うっている。
千春はそれを口に含むが、大きすぎて亀頭の部分しか咥えることができない。口内に太一の味がひろがる。舌を鈴口につきたてながら、千春は夢中になって、太一のモノを吸い続けた。
「も、もう入れていいか?」と太一がいうので、口を離した千春は、静かに頷き、仰向けになった。
アソコを両手で広げて、太一を待ち構える。
「入れて?」
腰を持ち上げてねだる。いやらしいその光景に興奮した太一は、逸物を握りしめ、千春のアソコにあてがい、一気に腰をしずめた。
「まって、ま、…!んぁあああ!」と叫びながら、千春は両脚を太一の腰にからませ、腰を前後左右に動かす。
はだけた浴衣の隙間から、白いおっぱいが揺れているのが見える。その光景と動きに太一は耐えきれなくなり、天井を見上げながら千春の中に射精したのだった。
___
「気持ちよかった。、…一ヶ月ぶりだもの。」
太一の胸に抱かれながら、千春はそうつぶやいた。樹液を放出した後も、太一のモノは勢いを失うことなく、千春の中に収まったままだった。
「寂しかったの?」
「うん、早く一緒に暮らしたいな…」
「もう少しの辛抱だよ」とささやかれ、やさしく髪をなでられると、ますます愛おしさが募り、太一の胸に頬ずりする。
そのとき別の考えが、ふっと千春の頭に沸き起こり、いきなり我に返った。
「あ、花火!」
求め合うのに夢中で、ここに来た当初の目的は、二人の頭から完全に消えてしまっていた。
「まだ、始まってないみたいだから急ごう。」
そういいながら、中に入れたまま千春を抱いて立ち上がる。
「こんな格好、誰かに見られたら…」
「見られるって、誰に?」
(そりゃ、そうか)と安心した千春は、しっかりと太一にしがみつく。
格子戸を開け、御神木に向かおうとした太一は、社から降りる階段のところで、すこしよろめいた。
落っこちそうになる感覚に驚いた千春は、きつく太一にしがみつく。同時に千春のアソコ秘部も「きゅぅうう」と太一のモノを締め上げた。
「ちょ…下までしがみつかなくていいんだぞ。」
「ば、ばかぁ。」
耳まで熱くなって、太一の胸に顔を埋めた。
ようやく、御神木までたどり着くと、太一は千春を御神木の平らなところにおろした。
「御神木の前で、こんなことして大丈夫かな?」
「うちは子孫繁栄、五穀豊穣の神様よ。」
「その一人娘と将来の旦那様がシてるんだもの、怒るわけないわ。」
そう言いつつ、千春は太一の腰を両脚で挟んだまま、腰を再び動かし始めた。太一は千春の浴衣を脱がせると、おっぱいを揉みしだき始めた。白いたわわなおっぱいを、もっと見たいと思ったが、月明りだけでは良く見えない。
「ドン、パーン」
花火が始まった。月明りに加え、花火の灯りで千春の白いおっぱいがハッキリと見えた。そして、その光景は太一の劣情をかきたてたのだ。千春の中で逸物がより膨張する。
千春は「パーン」という音に驚き、アソコを「ギュ」と締めた。その動きに「うぅ……」と太一は呻く。
「花火、一緒に見よう。」
太一は千春を裏返し、背後から突き立てた。
「ドン」と花火が上がる音に合わせて、肉棒を突きあげる。
「パーン」という音と共に、千春のアソコが肉棒を締め上げてくる。
この動作の繰り返しが、満天の花火の中で続いた。
幻想的なこの光景の中で、千春は「んあっ、あっ、あぁあ~!」と絶叫し続けたが、花火の音にかき消され、太一の耳には届いていない。
花火も終盤に近づき、フィナーレのスターマイン(速射連発)が始まった。
「ドドドドドドドドド」という激しい破裂音に合わせて、肉棒を千春の中に叩き込む太一。
千春の左脚を持ち上げ、力の限り突き続ける。色とりどりの花火に染められた千春の白いおっぱいは、上下左右に激しく揺れながら動いている。
御神木にしがみつづけて悶えまくる千春の髪がほどけ、良い匂いとともに、長い髪が背中一杯に広がった。エロチックな光景を眺めながら、太一は長々と心地よい射精を、千春の中に迸らせたのだった。







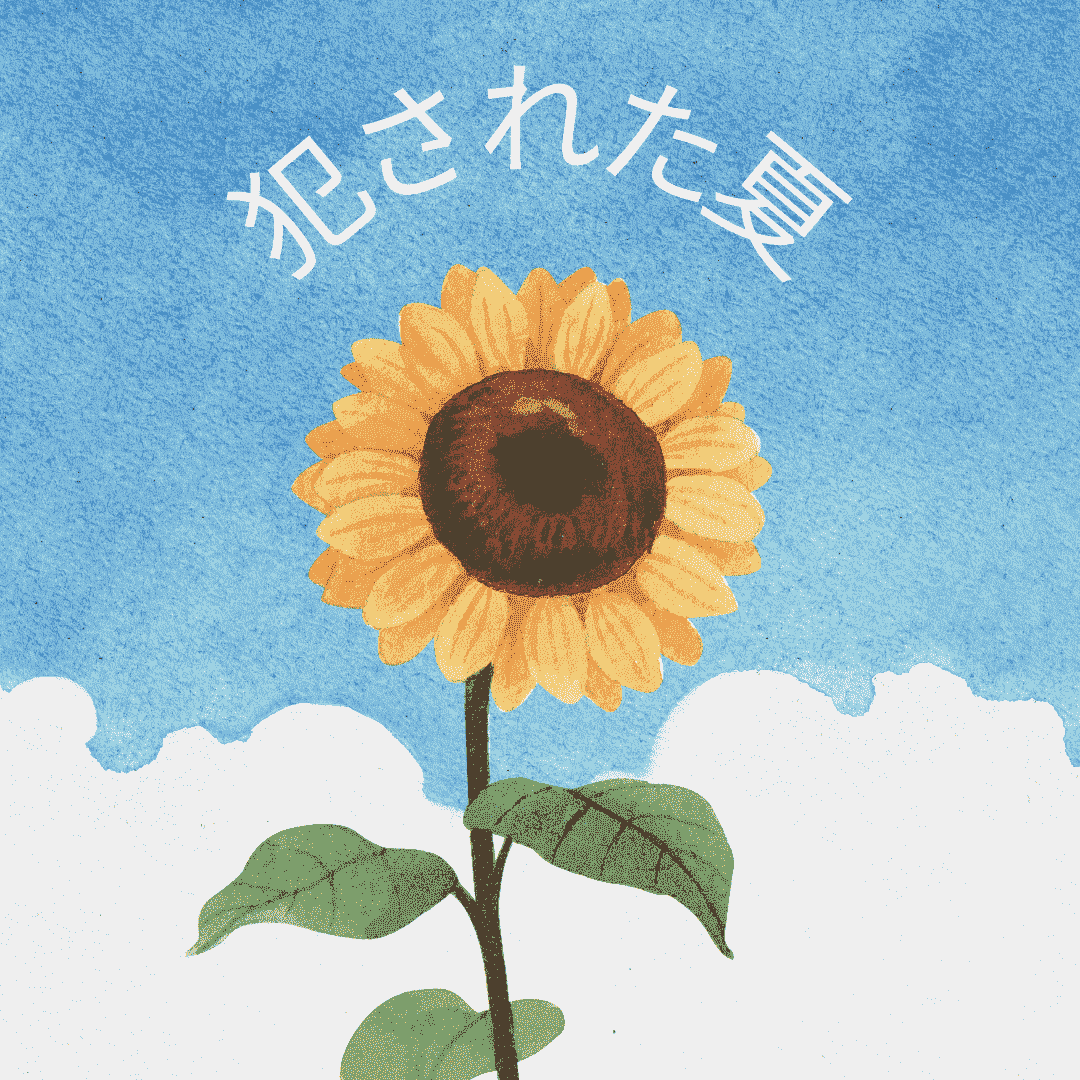


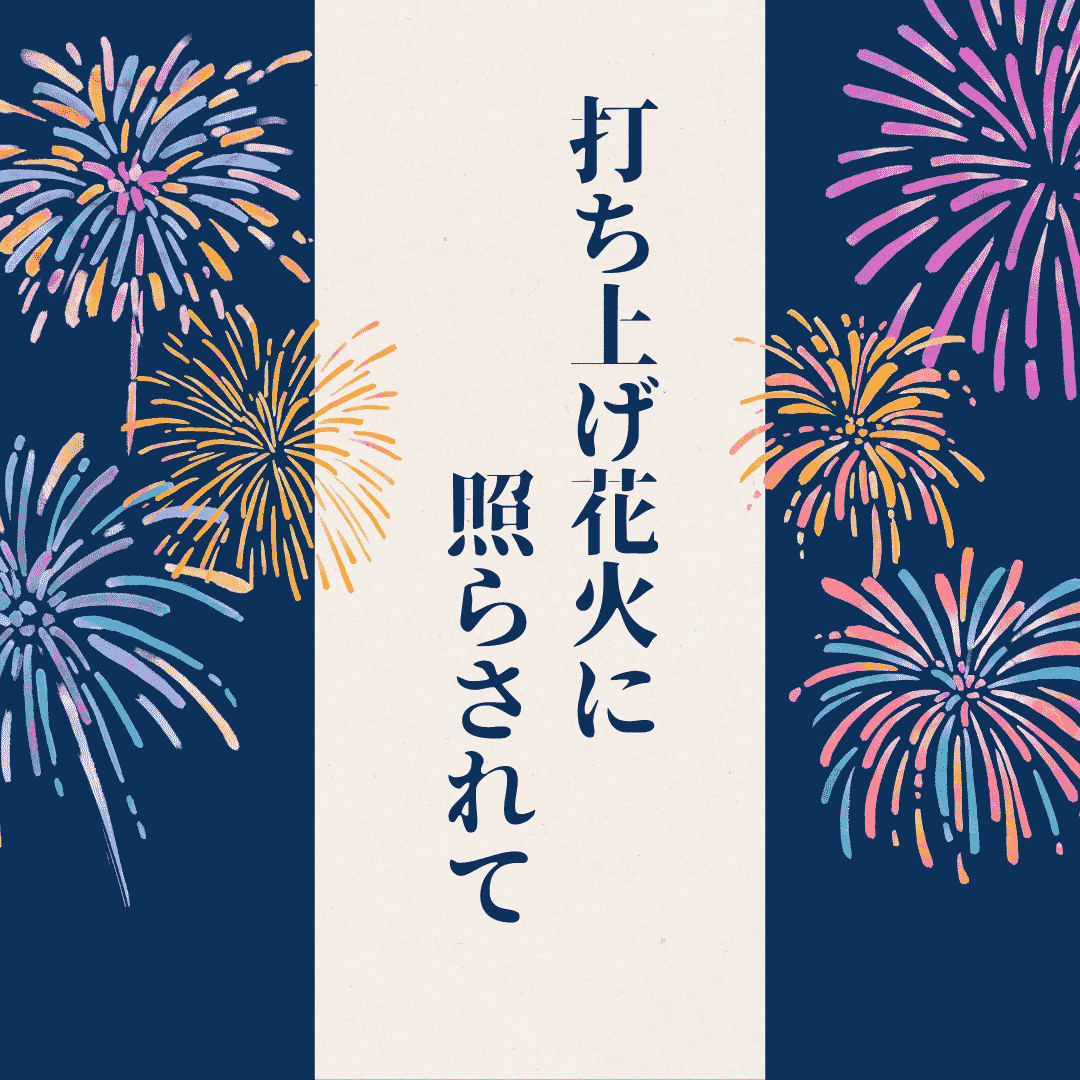

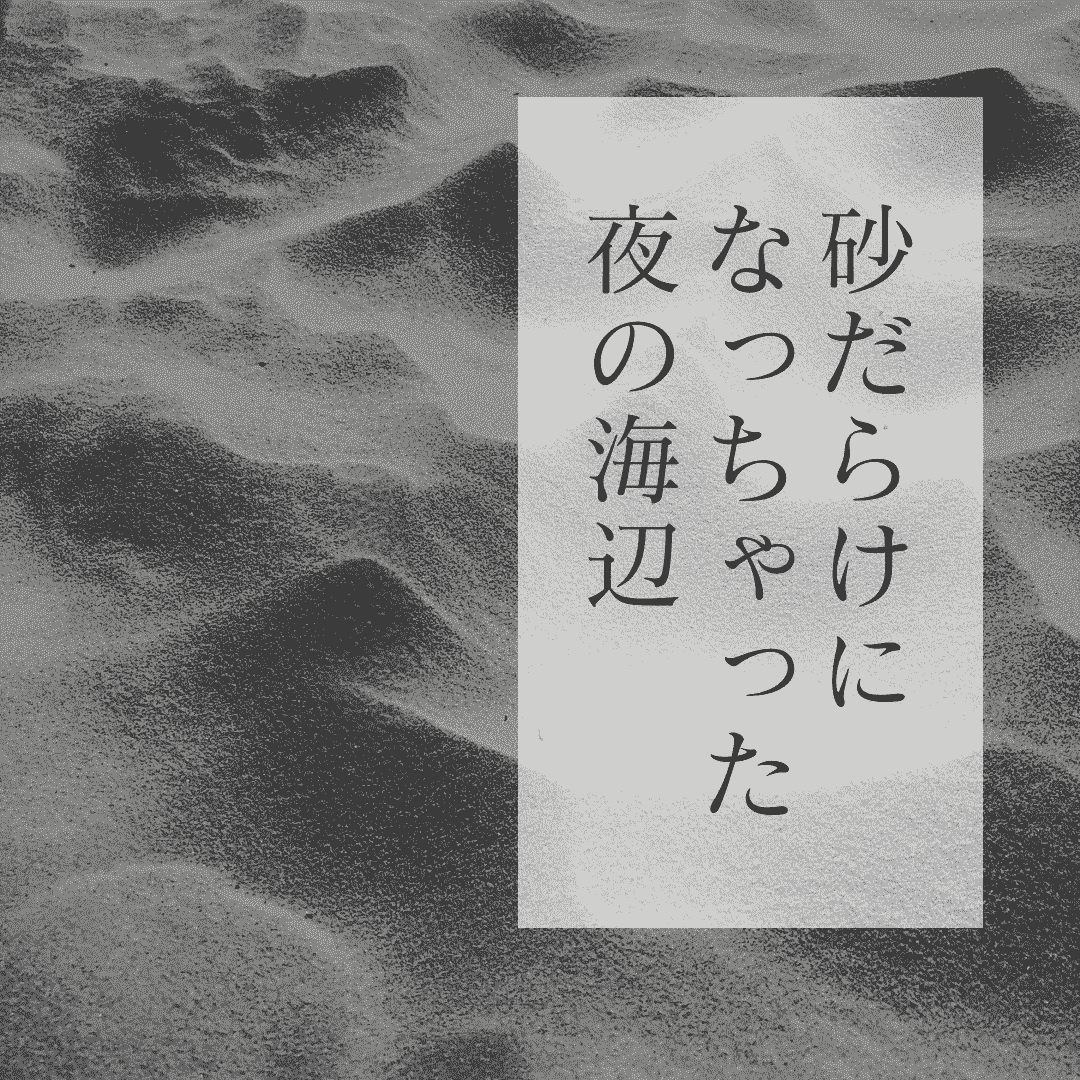

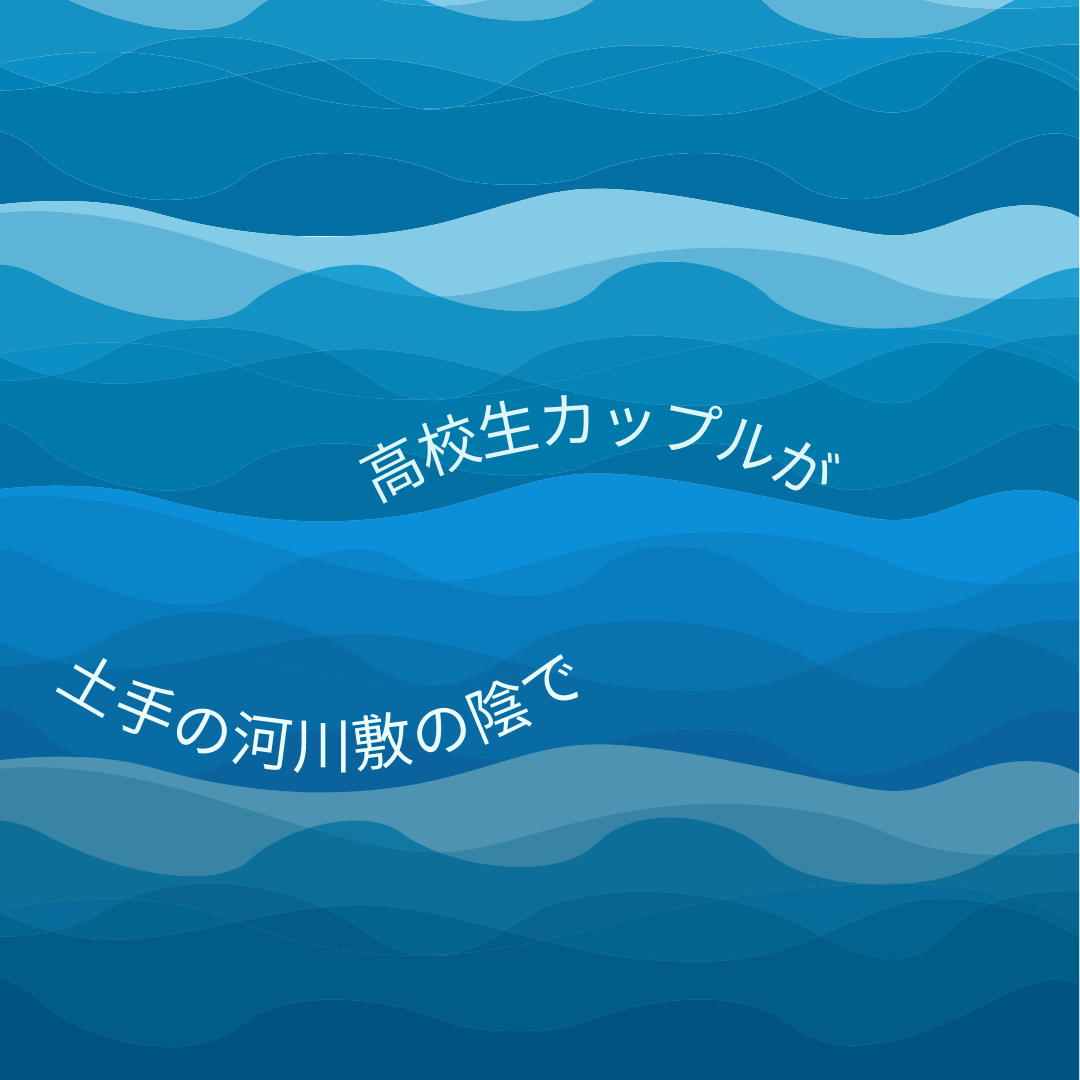


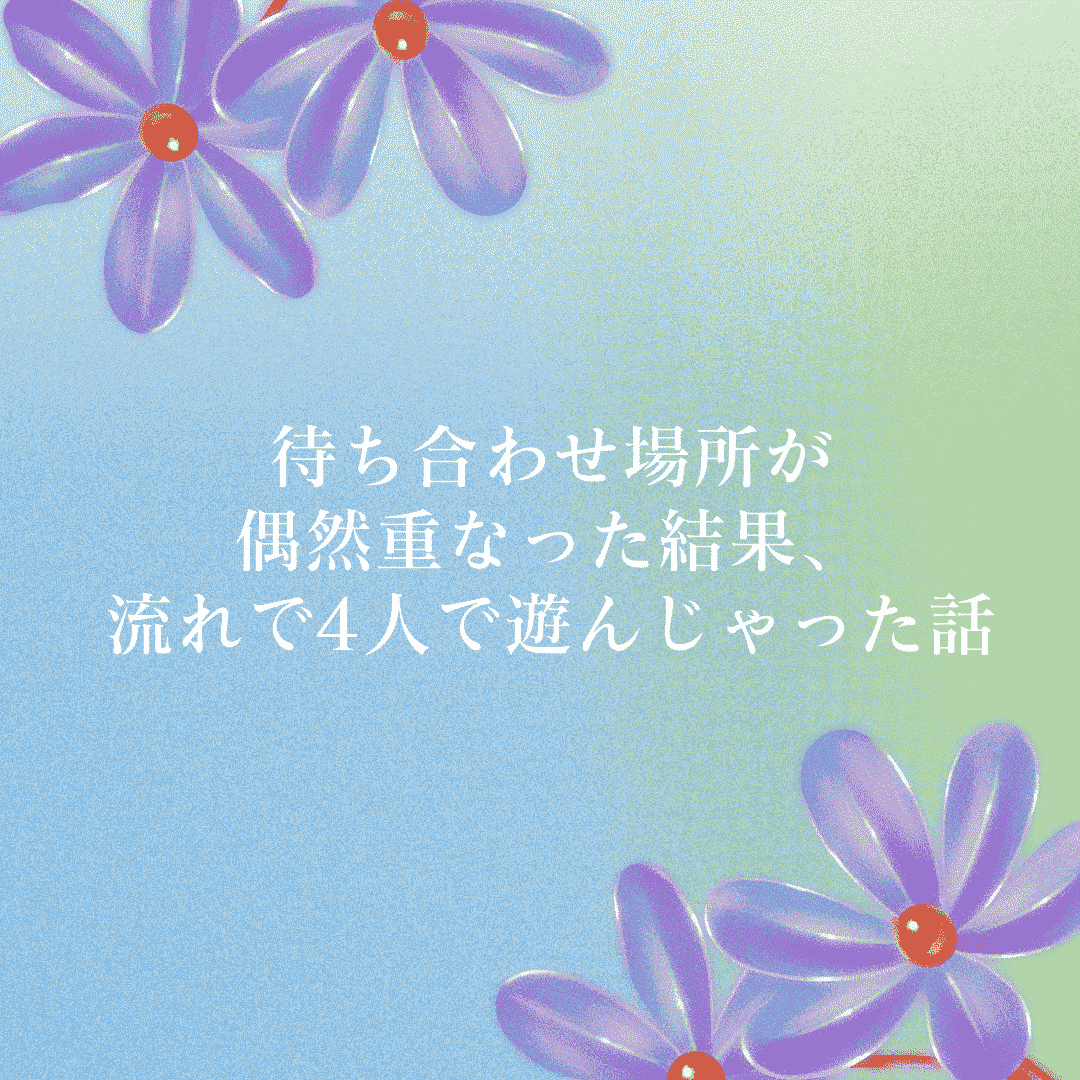




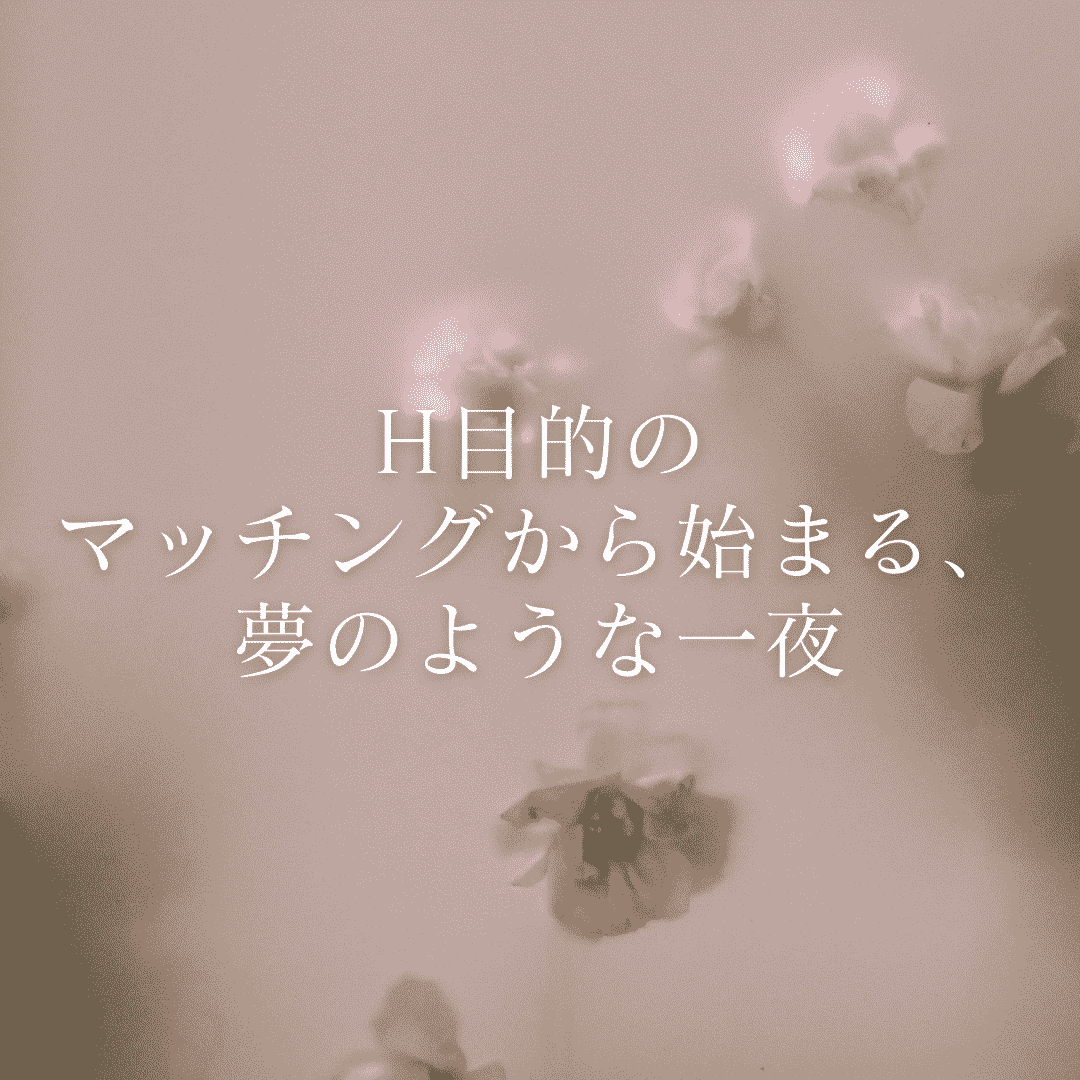

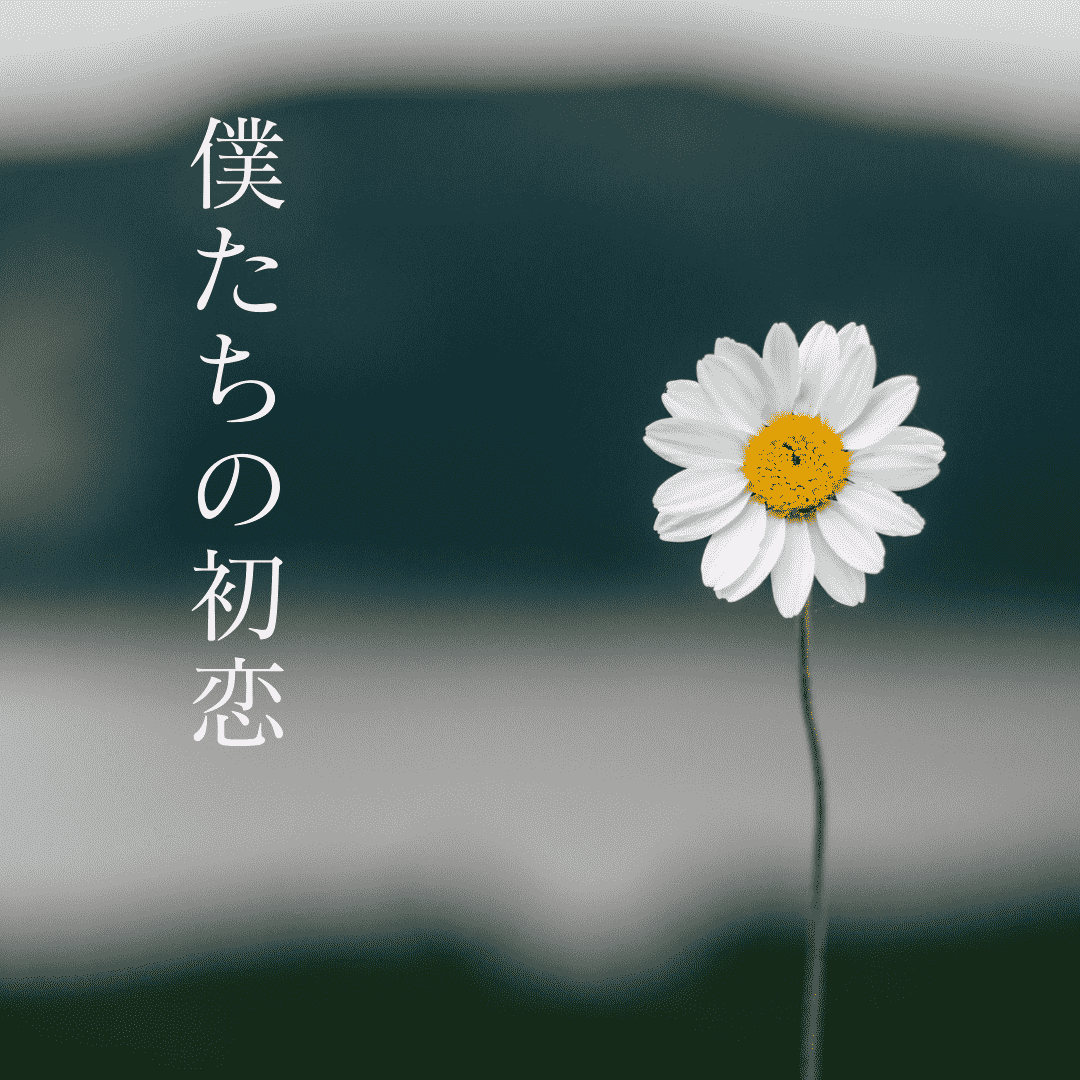


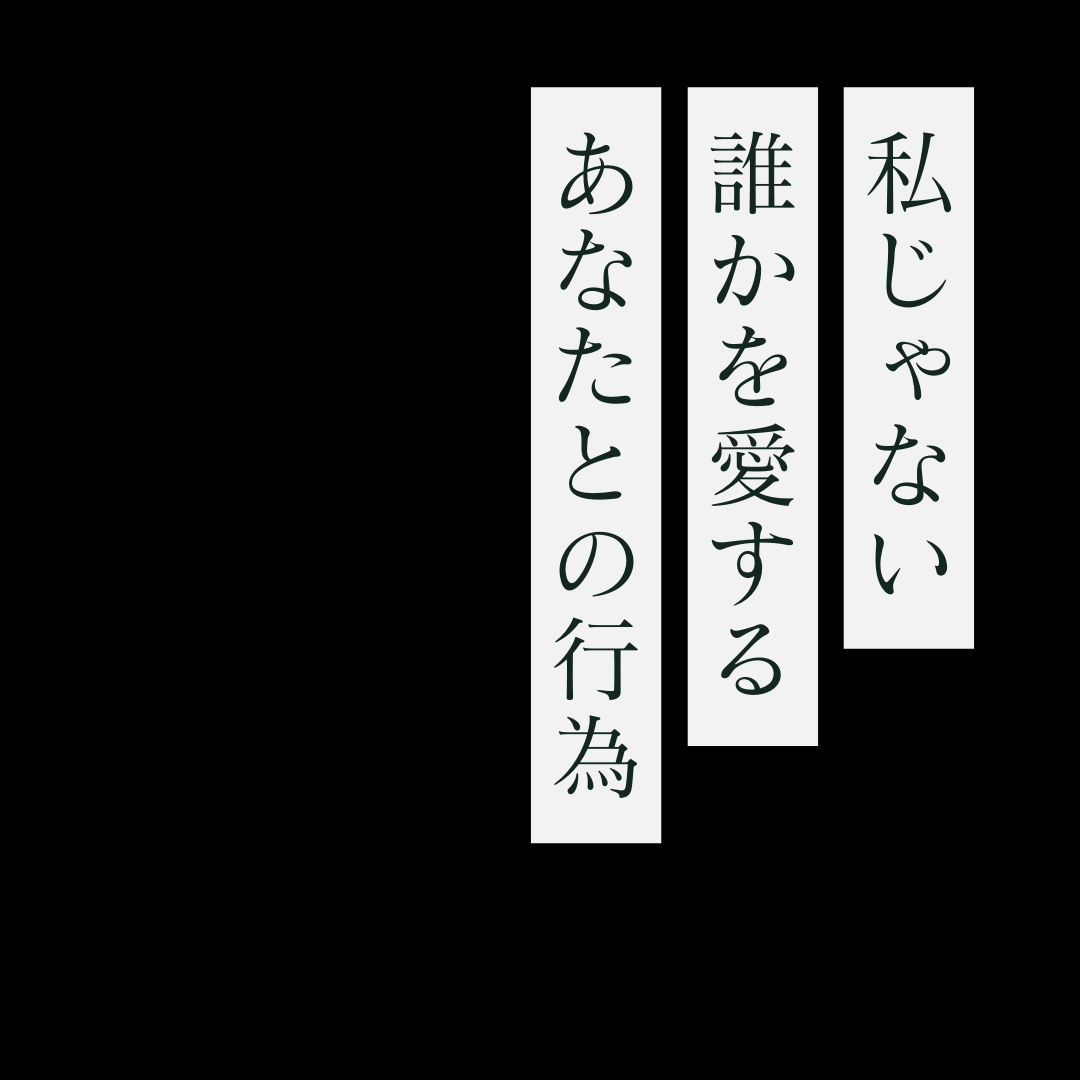

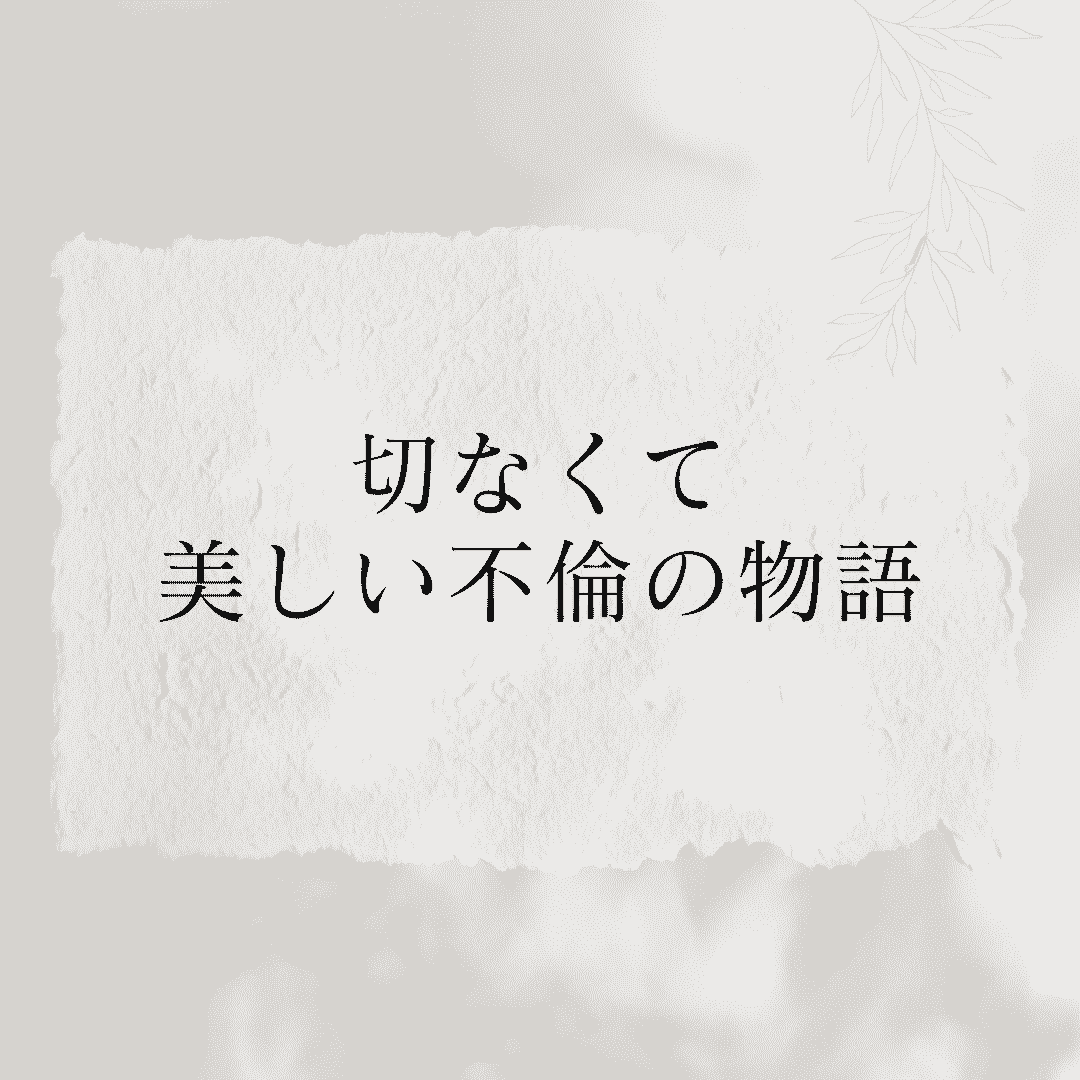
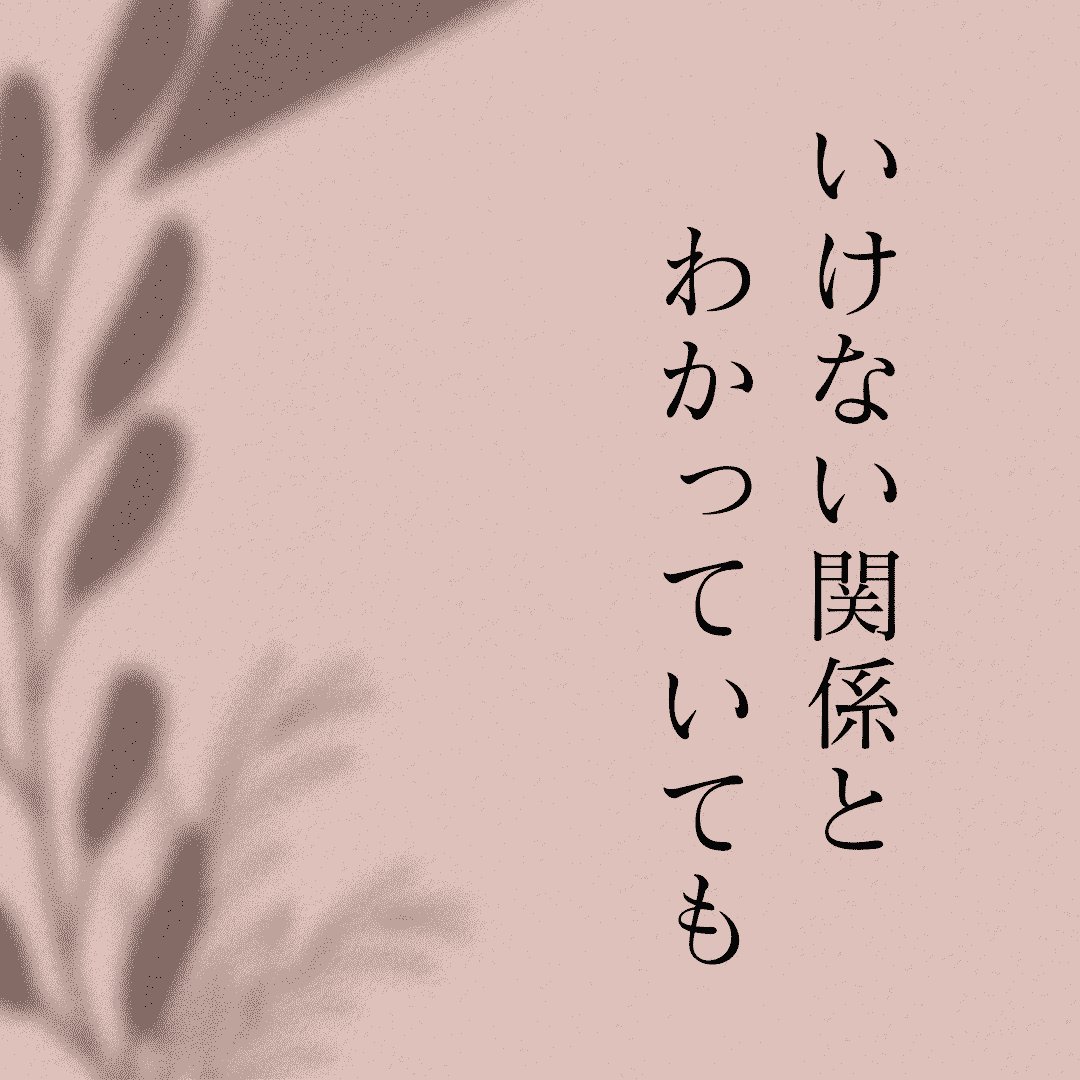









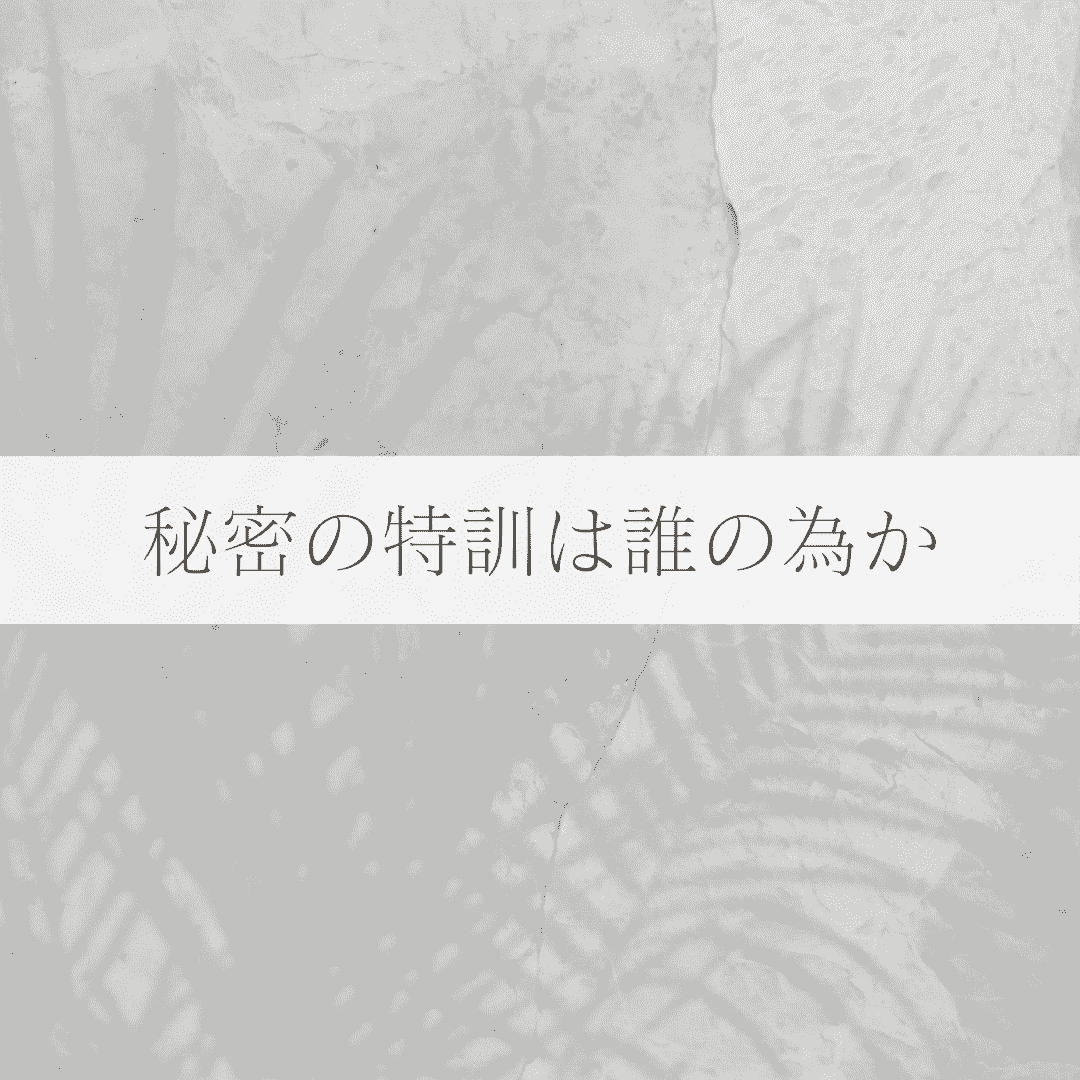
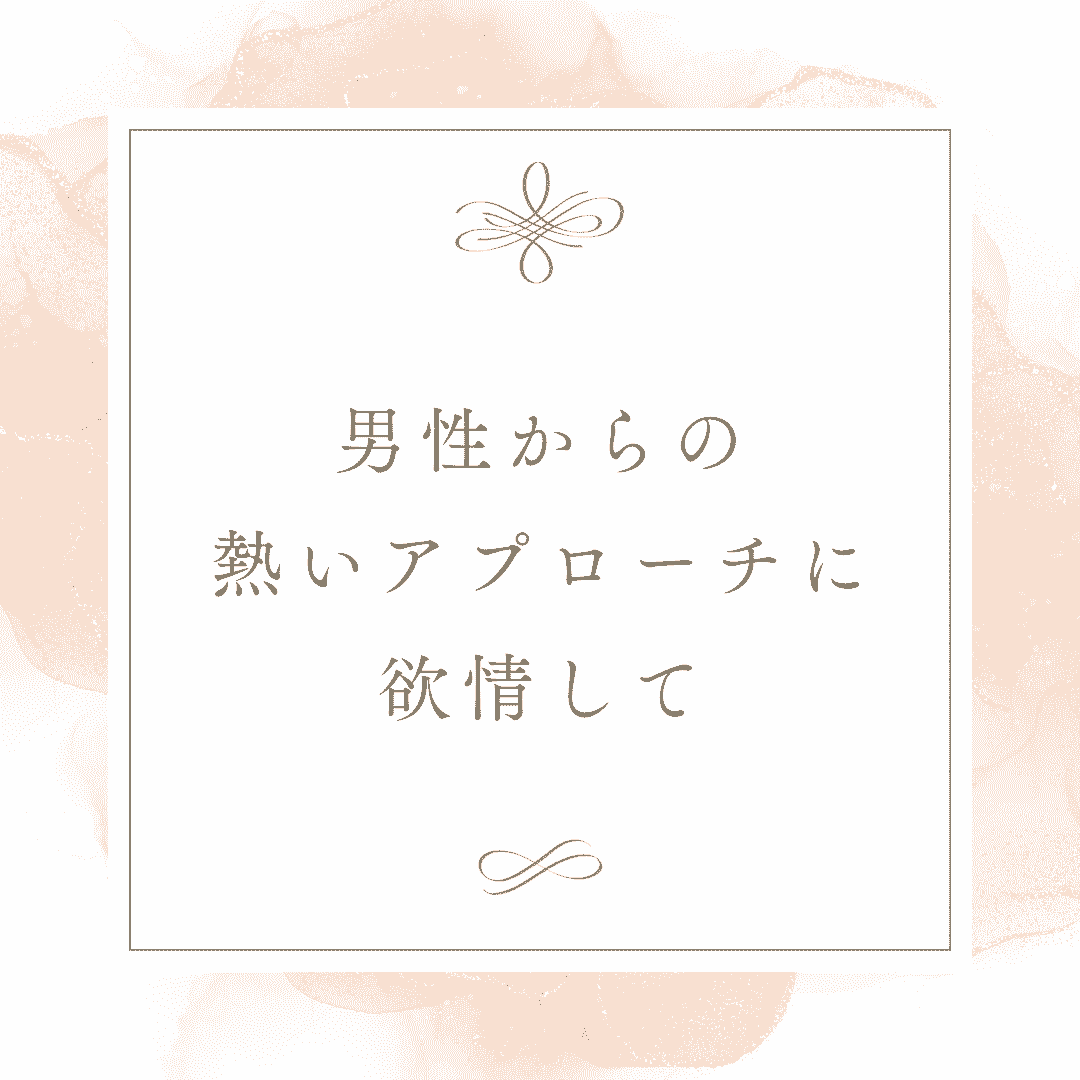


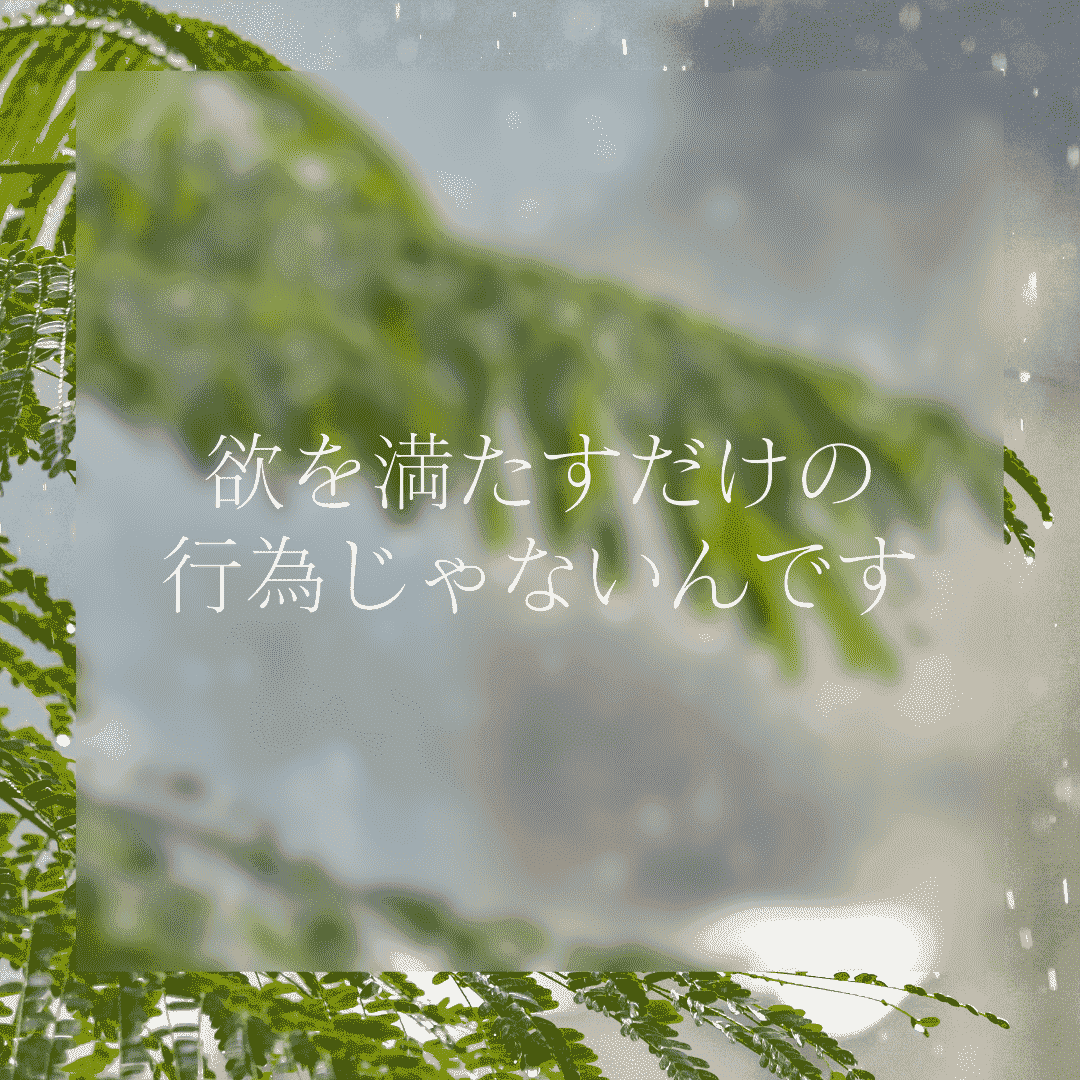

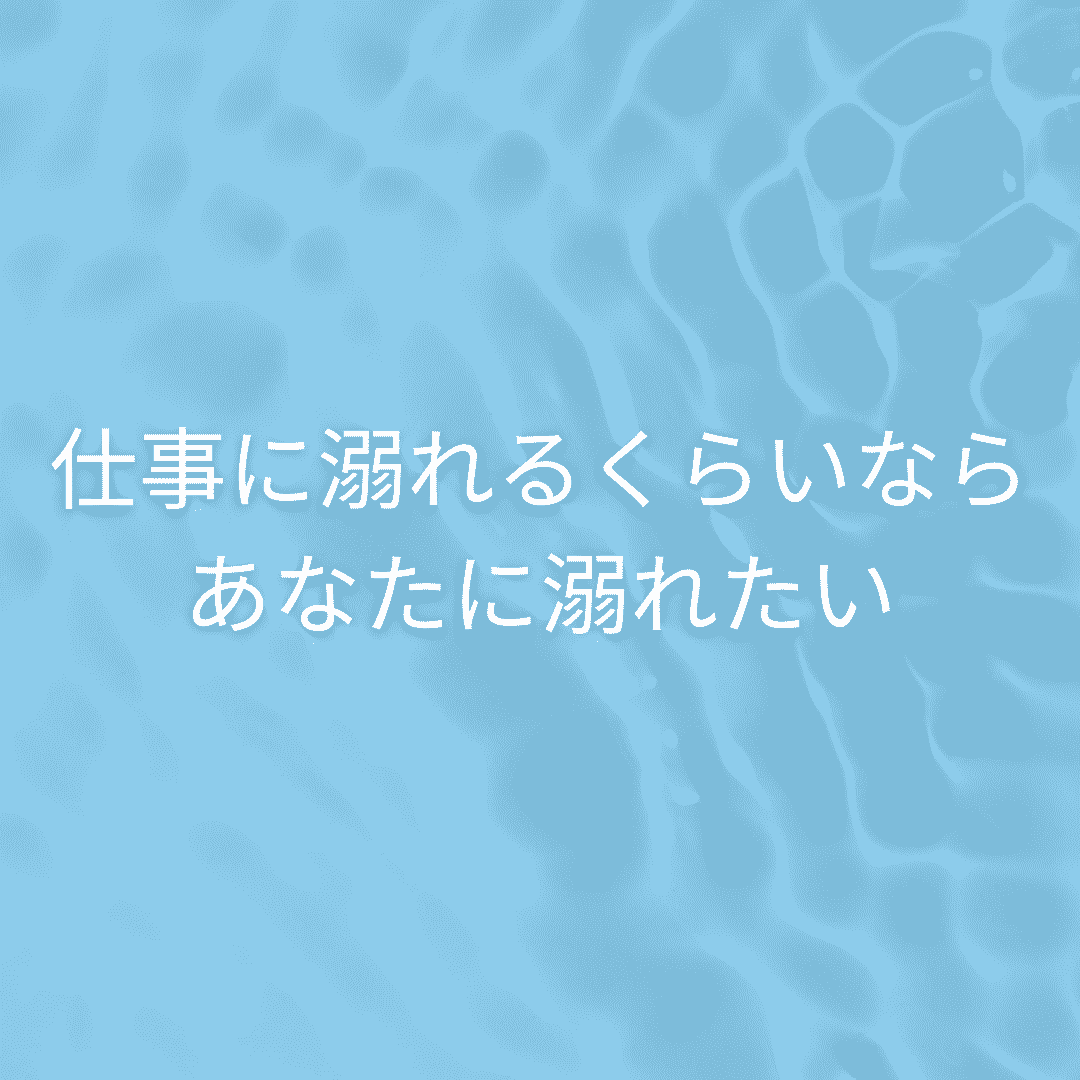


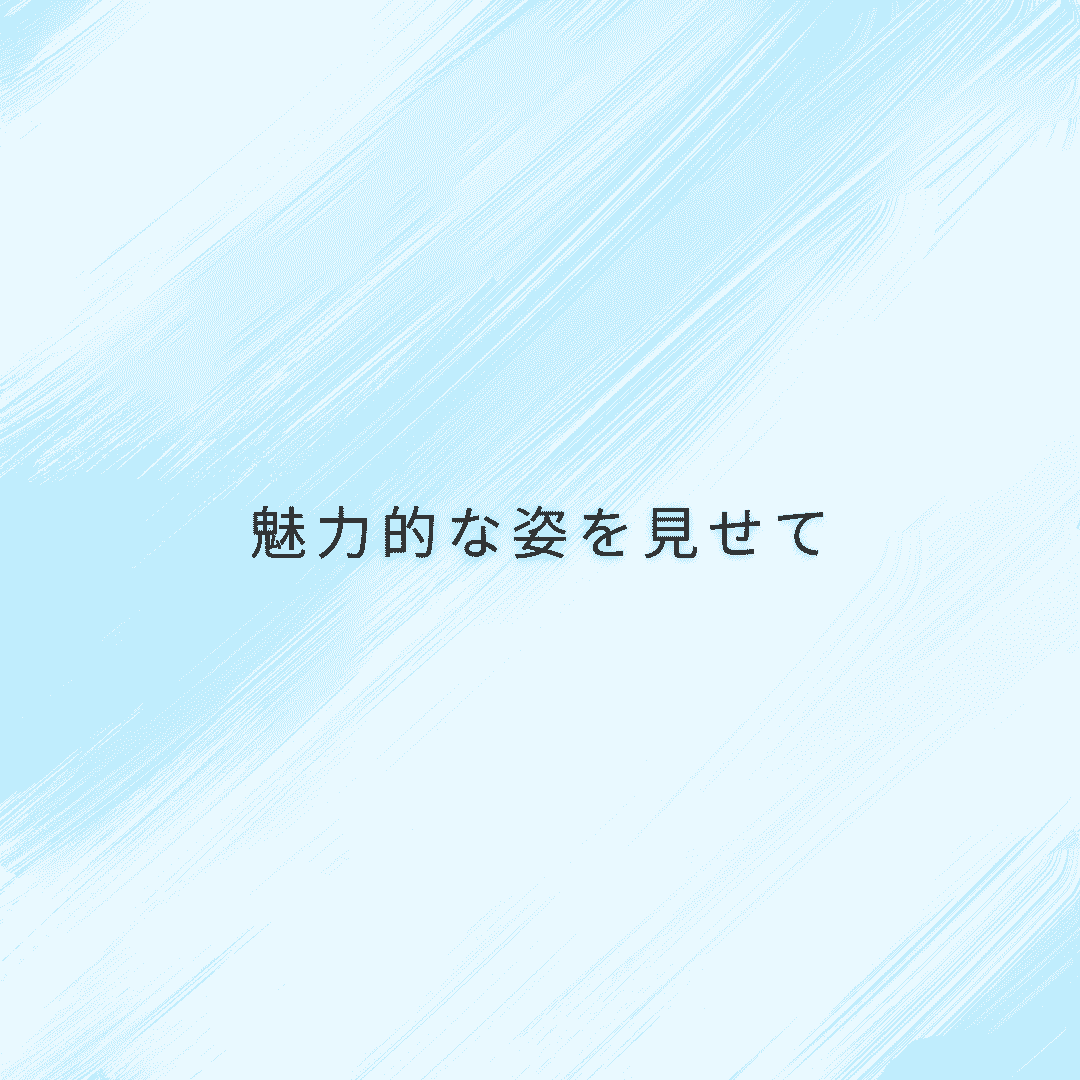
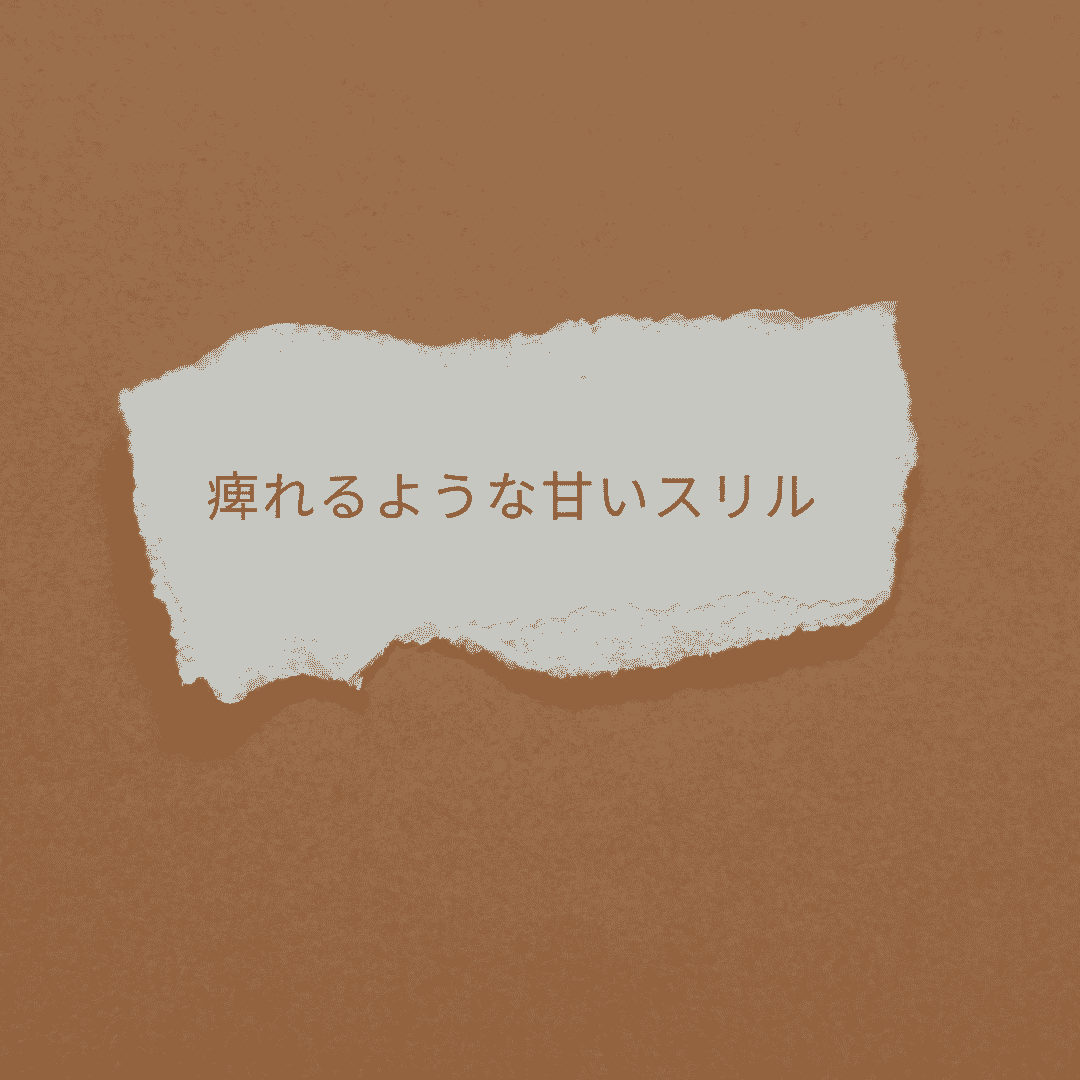

コメント