
0
夏の暑さに酔いしれる
「そこにいたら暑いよ。こっちへおいで」
そう言って私を手招きしてくれる彼。
父よりも年齢が上のその人は、落ち着いた声色なのに、仕草がどことなく子供っぽいように見えた。
ジリジリと身を焦がすような暑さが、まだ日も完全には昇っていないのに伝わってくる。
私は、布団の上で仰向けのまま、こちらを見つめてくる彼の方を見た。
「おはようございます。ようやく起きたのですね」
「君が隣にいないから起きたんだよ。いつもなら僕が起きるまで隣にいるのに…」
「暑さで目が覚めてしまって、縁側で涼んでいたんです」
ゆっくりと立ち上がり、私に手招きをする彼が重そうな腰を上げてこちらに近付いてきた。
夏仕様になった布団を見て、少し前の彼ならきっとそんなことはしないだろうと思った。
私と体を重ねるようになってから、彼の身の回りは、どこか私の好みのものが増えた気がした。
前までは年季の入った古書や分厚い参考書類、本などで溢れていた部屋も、今ではスッキリとした部屋に変わった。
古書もきちんと棚に収められて、書類が大量に乗っていた机の上には小さな向日葵の飾られた花瓶が置かれている。
埃っぽかった部屋も、毎日掃除をしているようで、埃も見当たらない程綺麗になり、私好みの香りまで漂っている。
「そろそろクーラーでも付けようかな。どう思う?和風の部屋にクーラーは変かな?」
「クーラーですか…扉が多いですから、風は入ってきますけれど…」
「僕が聞きたいのは、君が欲しいかだよ。暑いの苦手だろう?」
「…ふふ、それでは本当に私の部屋になってしまいますよ」
「いいんだよ、それで。ずっと僕の家にいればいいさ。あんな…浮気ばかりを繰り返す旦那より、僕の方がよっぽど君を愛してる」
少し怒ったような声色で、後ろから強く抱きすくめられた。
年齢なんて感じさせない程、体格の良い体は、線の細い私の体をすっぽりと収めてしまう。
浴衣から伝わるしっとりとした汗を帯びた肌の感触と、気温の高さを感じさせる熱を持った体。
項や首筋に甘いキスをされながら、ゆっくりと縁側に押し倒された。
「もう少しで陽が昇ってきますよ。ここは日当たりが良くなりますが…」
「…ごめんね、僕はそんなに辛抱強い方じゃないんだ」
真っ白になる前に、とついこの間染めたと困ったように笑い、話してくれた銀色の髪を掻き上げながら、私を見下ろす彼の目に息を飲む。
ここまで情熱的に求められるのは、とても心地良い気分だった。
横を見れば、乱れた布団が置いてあるというのに。
そんな近さですら我慢ならないと、浴衣の隙間から優しく太ももを撫でてきた。
指の腹で皮膚の弾力を楽しむように這わされ、太ももの付け根まで、指を滑らせながら何も身に付けていない膣の割れ目を撫でられる。
スリッと指の腹で、秘豆から膣の入口までをゆっくりと上下に優しく擦られ、もどかしさが募る。
甘い刺激だけでは物足りなくて、腰を捩って求めるように彼を見つめた。
「ん…?どうかしたのかな?」
私が今どんな気持ちなのかを知っている癖に、弱い刺激だけを与えてくる。
だが弱い刺激でさえも、先程まで行為をしていたせいもあってか、敏感に感じ取り、徐々にジワジワと痺れるような刺激が体に走るようになった。
膣の割れ目をゆったりとした動きで擦っていたのが突然、グニュッと膣内に挿入され、ひぐっと情けない声が漏れた。
「おっと。びっくりしたかな」
「ひ、ッ…うぅ…わか、ってるくせに…ッ…」
「うん、分かってる。君のことならなんでも知ってるよ。だからこそ別の顔も見たくなるんだよ」
目を細めて私を見つめてくるその目は、どことなく今にも悪戯をしそうな子供の表情と似ている。
じとっと拗ねるように見つめても、鼻を鳴らして嬉しそうに笑みを零すだけで、膣内に埋まった指を激しく動かしてはくれない。
それどころか、第二関節の所まで指を挿入して、クンクンッと上壁を擦りだしたのだ。
感じたことのない甘い痺れがつま先にまで走り、思わずピンと足先を尖らせる。
「ひ、やぁ、ぅぅッ!?」
「おやおや、ここは初めてだったかな?その反応は」
「んひッ、や、ぁッ!そ、こぉッ、へ、んぅッ…!」
「ああ、ここかい?そうだねえ、まだまだ序の口だよ。これからもっと強い刺激が待ってるんだから」
顔を覗き込むように、覆い被さってきたことによって、更に上壁をゴリッと擦り上げられ、感じたことのない敏感な箇所を掠めた。
ビクンと大きく背を仰け反らせて、腰をガクガクと震わせる。
尿意なんて感じていなかったはずなのに、突然何かが下腹部から湧き上がってくるような感覚を覚え、足を閉じようとした。
しかし彼の体が邪魔をして、閉じることも出来ずに尿意だけがジワジワと迫り上がってきていた。
「やッあぁ、ッ!いや、ぁッ!な、にかき、ちゃうぅッ…あ、ぁぁッ、やぁッ!」
「恥ずかしがらなくていいんだよ。ほら、我慢しないで出してごらん」
額に軽いキスをされ、甘い悪魔の囁きのように言われてしまえば、ビクンと体が震えて、今にも何かが溢れてしまいそうな感覚に膣がヒクヒクと収縮する。
彼の指の速度も上がり、上壁をゴリゴリと指の腹で激しく突き上げられた瞬間。
何かあらぬ敏感な箇所を突然、グンッと突き上げられて、ビクンと大きく背を仰け反らせて、ガクガクと痙攣する腰。
声にならない悲鳴に舌を突き出して彼の背中に腕を回した。
感じたことのない快感に恐怖心すら感じて、何度も首を激しく振り乱した。
それでも激しく突き上げてくる指は止まらず、ブチュブチュと聞こえてくるいやらしい水音に、鼓膜すら犯されている気になった。
「ひ、い、ッあぁぁ!や、ぁッ、いやぁッ!!そ、こぉ、いやぁ、ぁぁッ…!も、ぉ、でちゃ、ッやあぁ、ぁッ!!」
「出して。君の可愛い姿もっと見せて」
耳元で囁かれ、頬や首筋などに軽いキスをされ、グチュグチュと指先で中を突き上げる速度が上がる。
迫り上がる尿意に耐えられず、腰をガクガクと激しく痙攣させて、プシャァ、と勢いよく透明な体液が噴き出し、目の前にチカチカと火花が散った。
はひ、と過呼吸になりながら、必死に彼の背中にしがみついて、止めどなく噴き出る体液に、涙が溢れた。
漏らしてしまったという恥ずかしさと、彼の浴衣を濡らしてしまった申し訳なさで、ひぐっと嗚咽を漏らして涙が零れた。
それに気付いた彼は困ったように笑って、膣内から指をゆっくりと引き抜いて、口に含んだ。
その光景さえ、恥ずかしくて思わず彼の手首を掴んで「やめて」と涙声で叫んだ。
「恥ずかしくないよ。初めてだったのかな?大丈夫、君が思ってるような尿意じゃないんだから。ほらもう泣かないで」
恥ずかしくないと、言われてしまえば途端に安心感で溢れて、彼に抱き締められると余計に涙が溢れた。
感じたことのない快感に頭がついてこなくて、未だにガクガクと力の入らない腰が震え続けていた。
勢いはなくとも、まだまだ溢れ続ける体液に、ビクンと体が震えてしまう。
どこもかしこも敏感で、愛液と体液の溢れる膣をヌルヌルと指でなぞりながら、はだけた胸元や、腹部に何度も軽いキスをして、上体を起こす彼。
上気する頬と、耐えきれないと言わんばかりに舌なめずりをして私を見る彼の視線に、期待に胸が高鳴る。
三年前にこの縁側で寝ていた、どうしようもなくカッコいい彼に見惚れてしまった、新米の編集スタッフの私。
きっと終わっている頃だろうと編集長に言われ、原稿を取りに来たあの日に、私は彼に一目惚れをした。
旦那の浮気で揉めていたあの頃。
私の心の傷を癒してくれたのは、紛れもなく彼だった。
「そろそろ君が望むものを与えたいけれど…君が欲しいものはどれかな…?」
ピュルッと未だに噴き出てしまう膣に、浴衣の間から取り出された血管の浮き出る逞しい陰茎の先端を押し当てられて、楽しそうに笑みを浮かべた彼。
私の言葉を待つように、ただ押し当てるだけで、その先をくれない彼に、唇を噛み締めて精一杯にゆったりと腰を揺らして見せた。
息を飲んで彼の目をジッと見つめ、震える唇で彼を求めた。
「いじ、わる…ッ、しないで…ッ…なか、に…ほ、し…の…ッ」
ポロポロと溢れる涙に、恥ずかしさがとうに限界を迎えていて、これが精一杯の言葉だった。
すると彼の口端が楽しげに上がり、浴衣の前をはだけさせた。そそり立つ陰茎を見せつけるように数回擦り上げる。
「は…ッ…年を食っても君を見てると、元気になるんだ。この責任…取ってね」
私の足を更に左右に大きく開いて、フッと笑みを零して、そそり立つ陰茎を膣の中に挿入した。
先程まで指を受け入れていたこともあって、中はすっかり緩やかに解れて、すんなり彼を受け入れた。
年齢がふた回りも違うのに、浴衣の間から見える肉体は衰えてはおらず、寧ろしっかりと引き締まっているのが見えた。
旦那よりも綺麗な肉体を見て、自分はこんな素敵な人に抱かれているのだと想像するだけで、きゅうっと中を強く締め付けてしまう。
陰茎の太さまではっきりと分かってしまう程、中を締め付けてしまい、顔を顰めて熱い吐息を吐き出した彼が、意地悪そうに笑みを浮かべて私を見た。
「ぐ…ッ、…そんなに締め付けたら、駄目だよ…動けないでしょ?」
「う、ぅんッ…!ご、め、なさ…ッあ、ぁんッ!」
「本当に君って…僕のこと好きだよね」
今度は困ったように笑みを零して、愛おしげに顔を撫でてくれた。
彼の優しさと彼の温もりに、気が緩んだ瞬間。
ゴチュッと強い衝撃が最奥に響く。
「ひ、んッ、あぁぁッ!?」
根元までしっかりと収められた陰茎が、グリグリと最奥ばかりを突き上げて、先程の余韻が抜けないまま敏感になっている膣内は、嬉しそうに陰茎を強く締め付ける。
何度も最奥ばかりを的確に、突き上げられて透明な体液が、衝動と連動してプシッと噴き出てしまった。
それを嬉しそうに眺めて、激しく腰を振り乱す彼の指が、グリッと秘豆を押し潰した。
「やあぁ、ぁ、ッんあぁッ!!」
強すぎる衝撃と共に、中を強く締め付けて一回目の絶頂を迎えた。
しかし私が達しても尚、突き上げは速度を落とすことはなく、目眩がしそうな程強い快感が体を駆け抜けていく。
嫌々と首を振り乱しても、彼の衝動は止まるどころか、速度を上げていき、一気にカリ首まで引き抜かれたかと思えば、ゴンッと強く根元まで深々と突き刺される。
数時間前まで抱き合っていた余韻がぶり返すように、どこもかしこも快感が走り、ボロボロと涙が溢れ出てしまう。
嫌と言っても駄目と言われ、もう要らないと言っても、まだまだと言われる始末。
グズグズに解れた膣内は、すっかり彼の先走りと私の愛液が混ざり合った体液で溢れていた。
張り詰めた呼吸を吐き出すように、彼が強く私の腰を引き寄せて、歯を食いしばった。
「は、あ…ッ、も…でそう、だ…ッ、中、だすから…しっかり、うけとめ、て…ッ」
「うぅんッ、!きて、ぇ、おなか、いっぱい…ッ、してぇッ…!」
ゴンゴンと最奥を突き上げてくる陰茎が大きく脈打ち、ビクンと震えた瞬間。
ビュルルッと激しい勢いで、中に吐き出された。
火傷しそうな程、熱い精液がドプドプと先端から噴き出る度に、最奥に当たる感覚を感じて、背を仰け反らせて私も達してしまった。
体を丸めて、ビクビクと快感に酔い知れながら精液を中に吐き出し続ける彼に視線を向けた。
するとこちらの視線に気付くように、軽く唇にキスをされ、ゆっくりとまた腰を動かし始めた。
「締め切りも終わったし、君も今日は休みで僕の家にいる。これからやることなんて…一つだよね?」
そんなこと初めから分かってて、家に呼び出した癖に。
お見通しの彼の考えにふと笑みが零れる。
それ程までに自分に溺れてくれる彼が愛しくて堪らない。
そんな彼の要望に応えるべく、私もゆっくりと腰を揺らして、まだまだ長い彼との行為に期待を馳せるのだった。






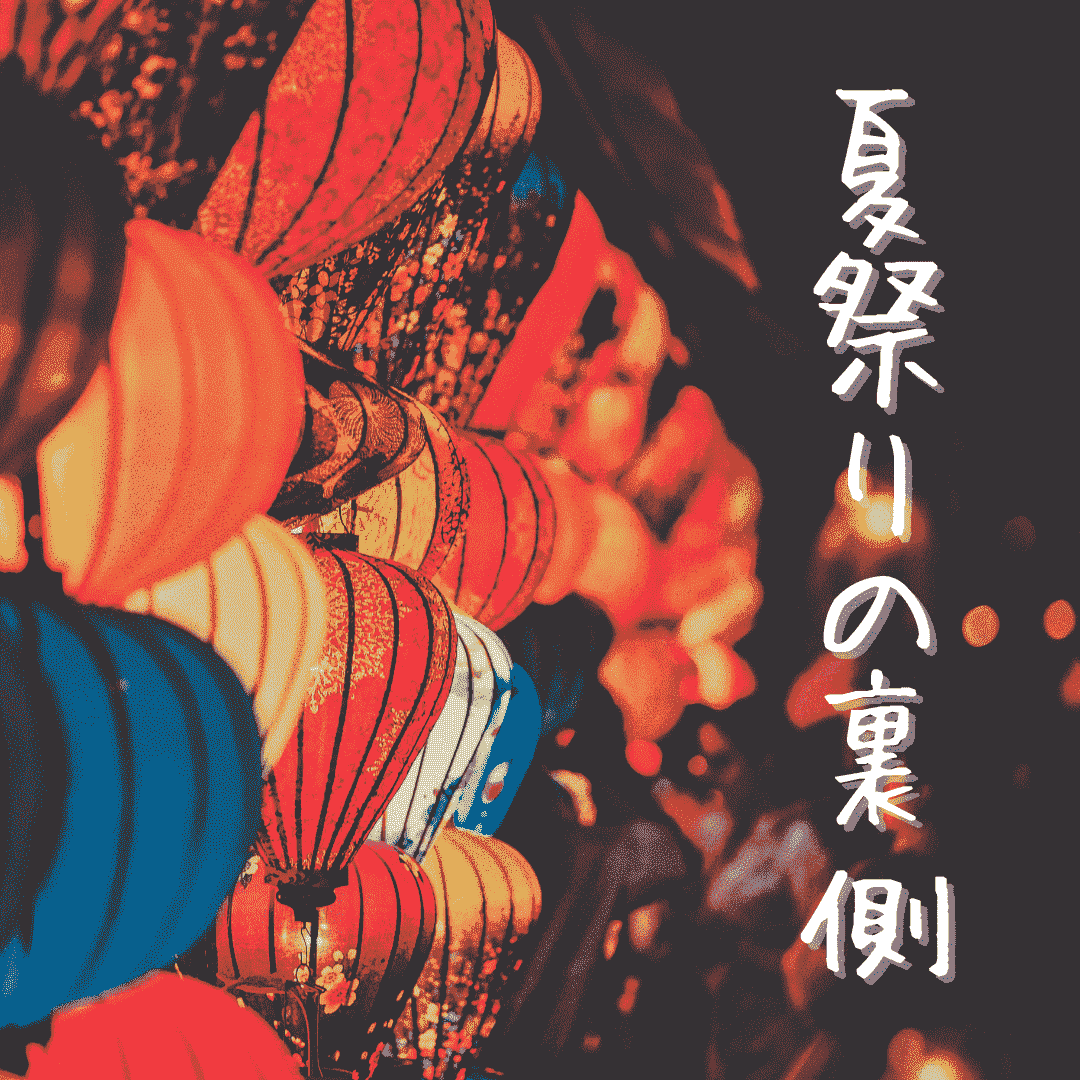

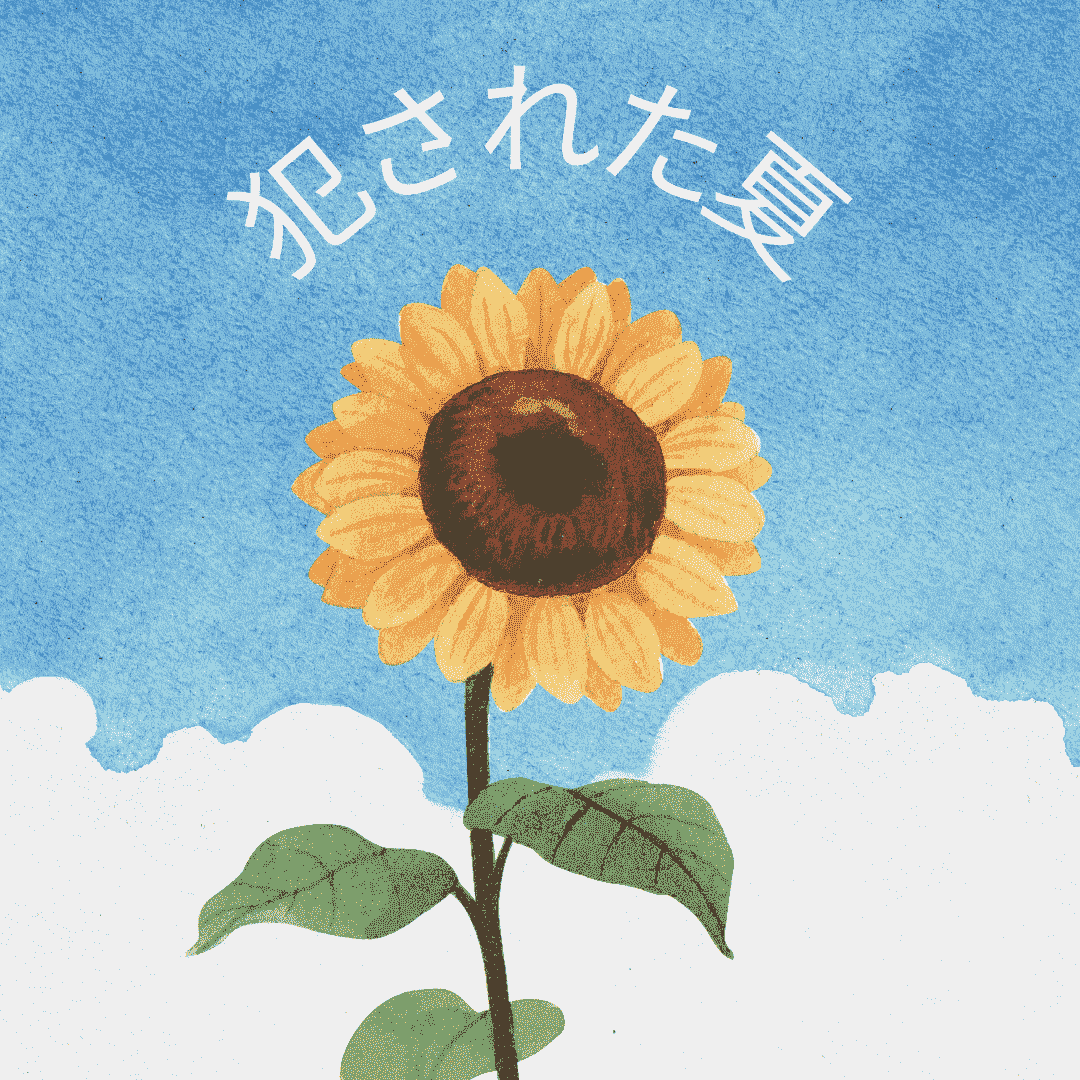


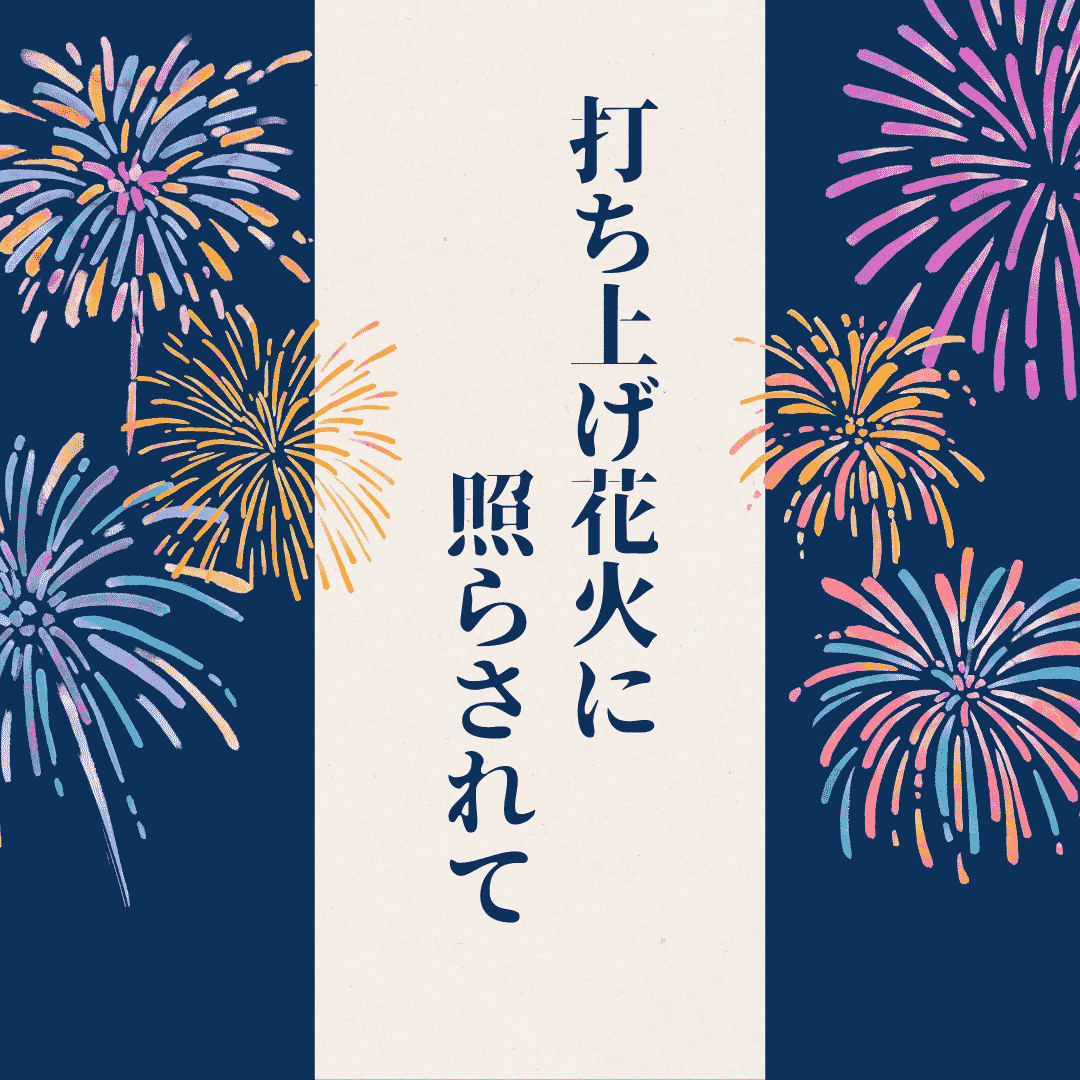

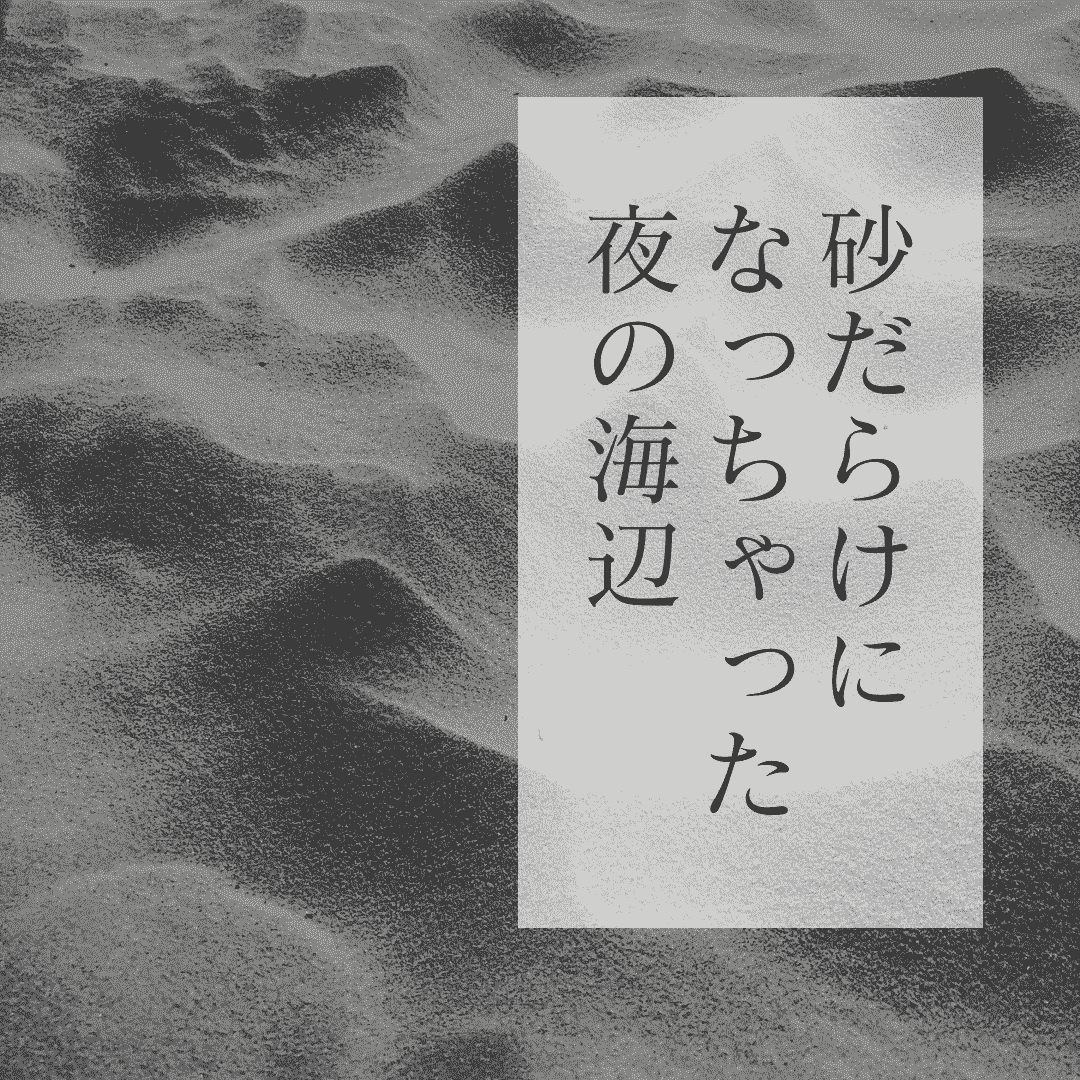

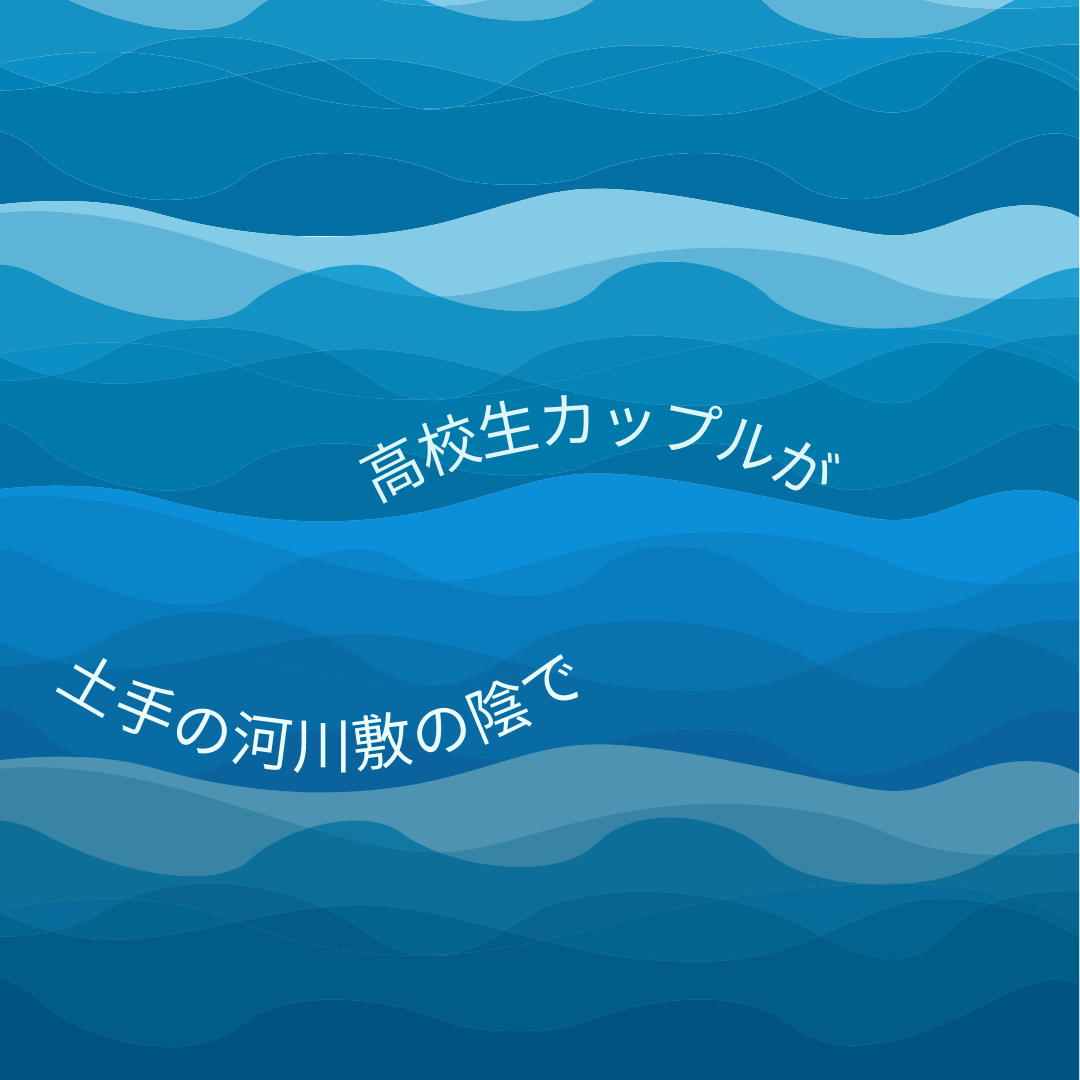


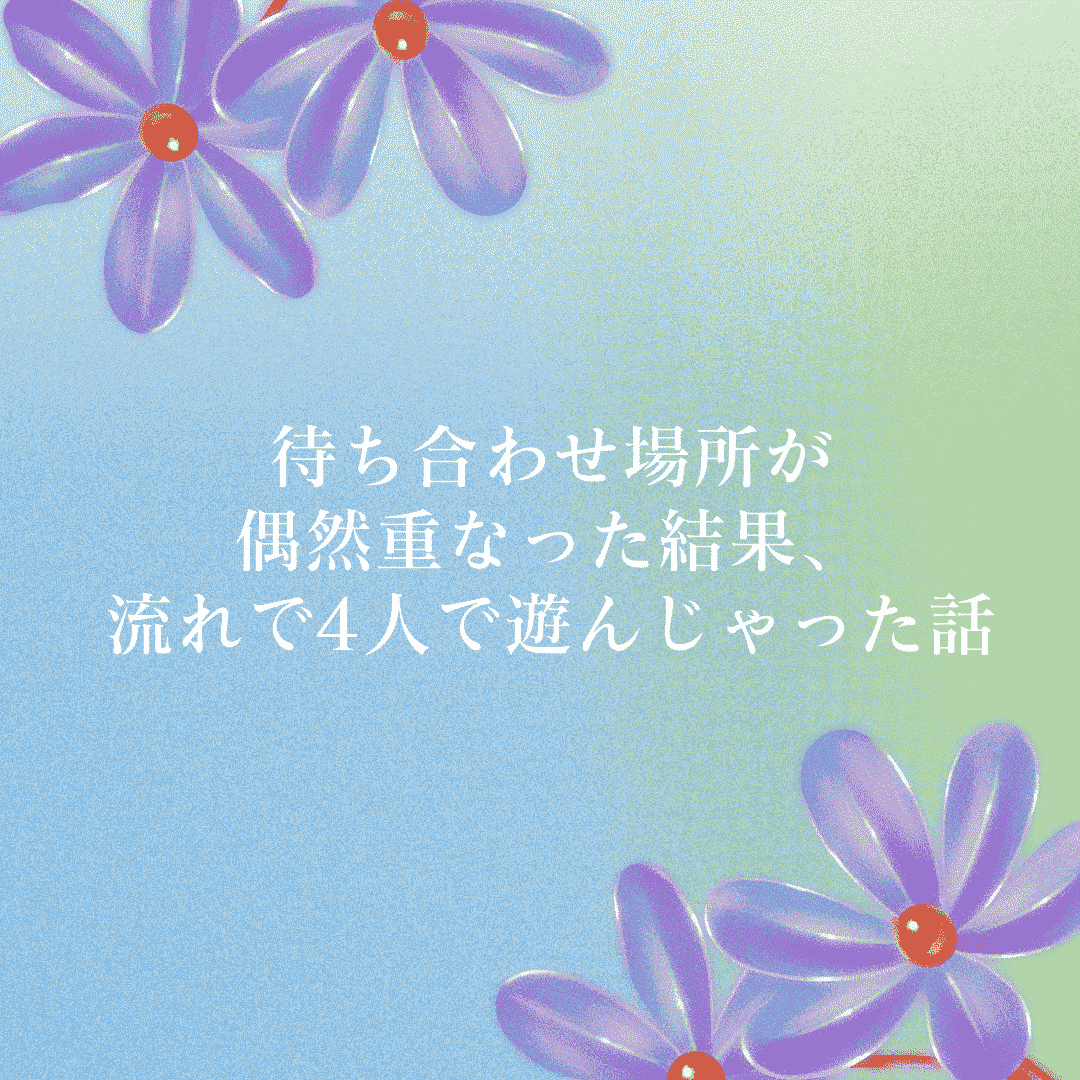




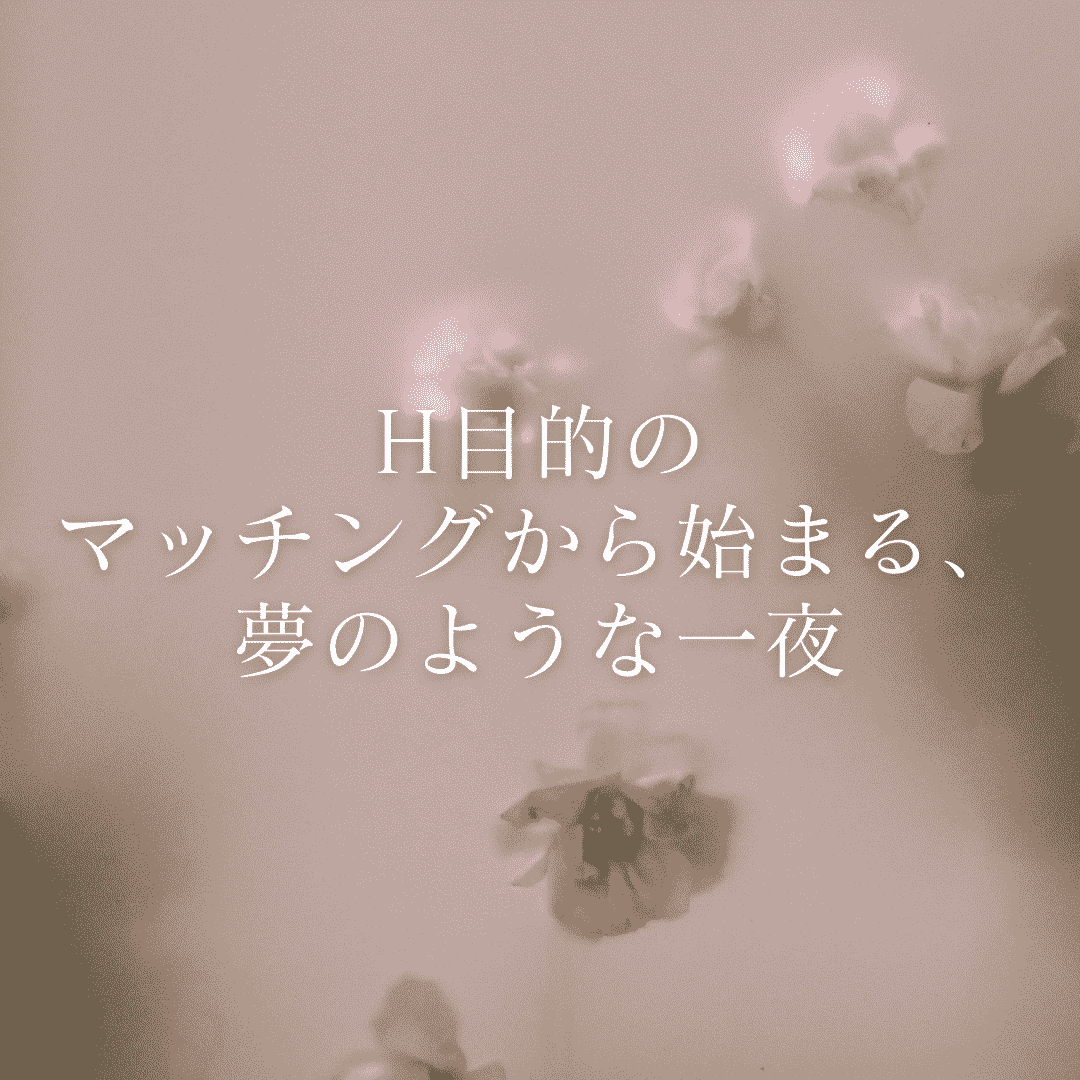

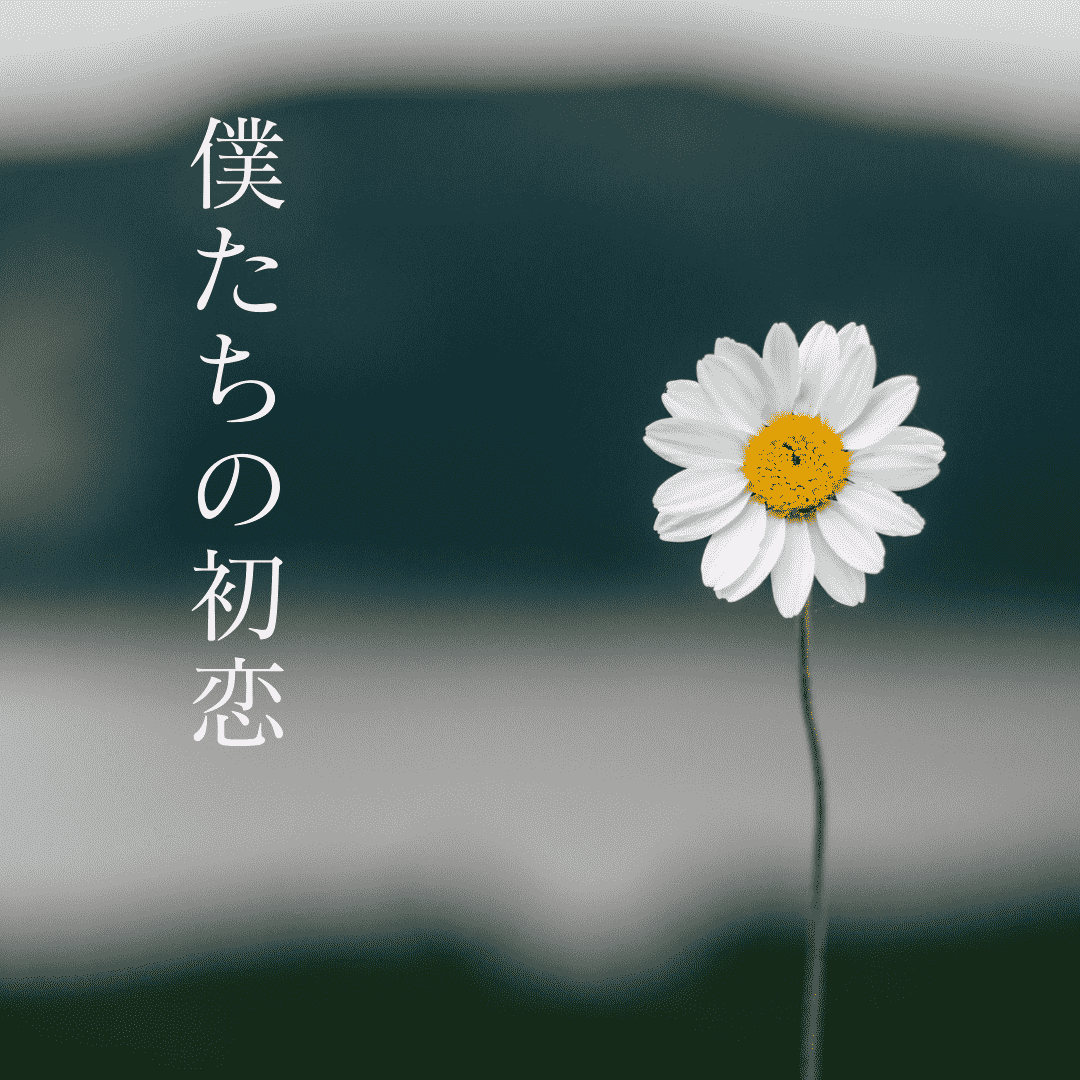


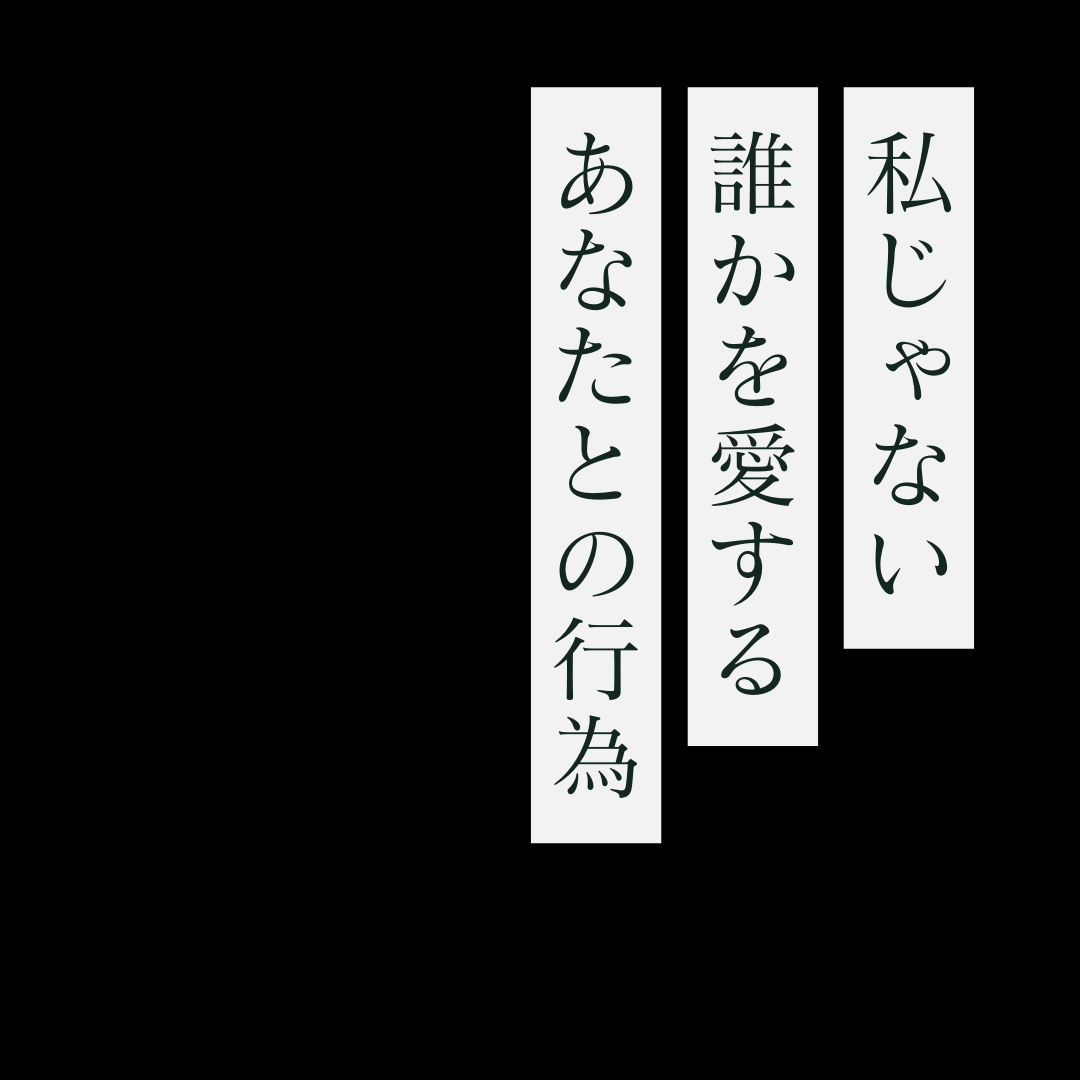

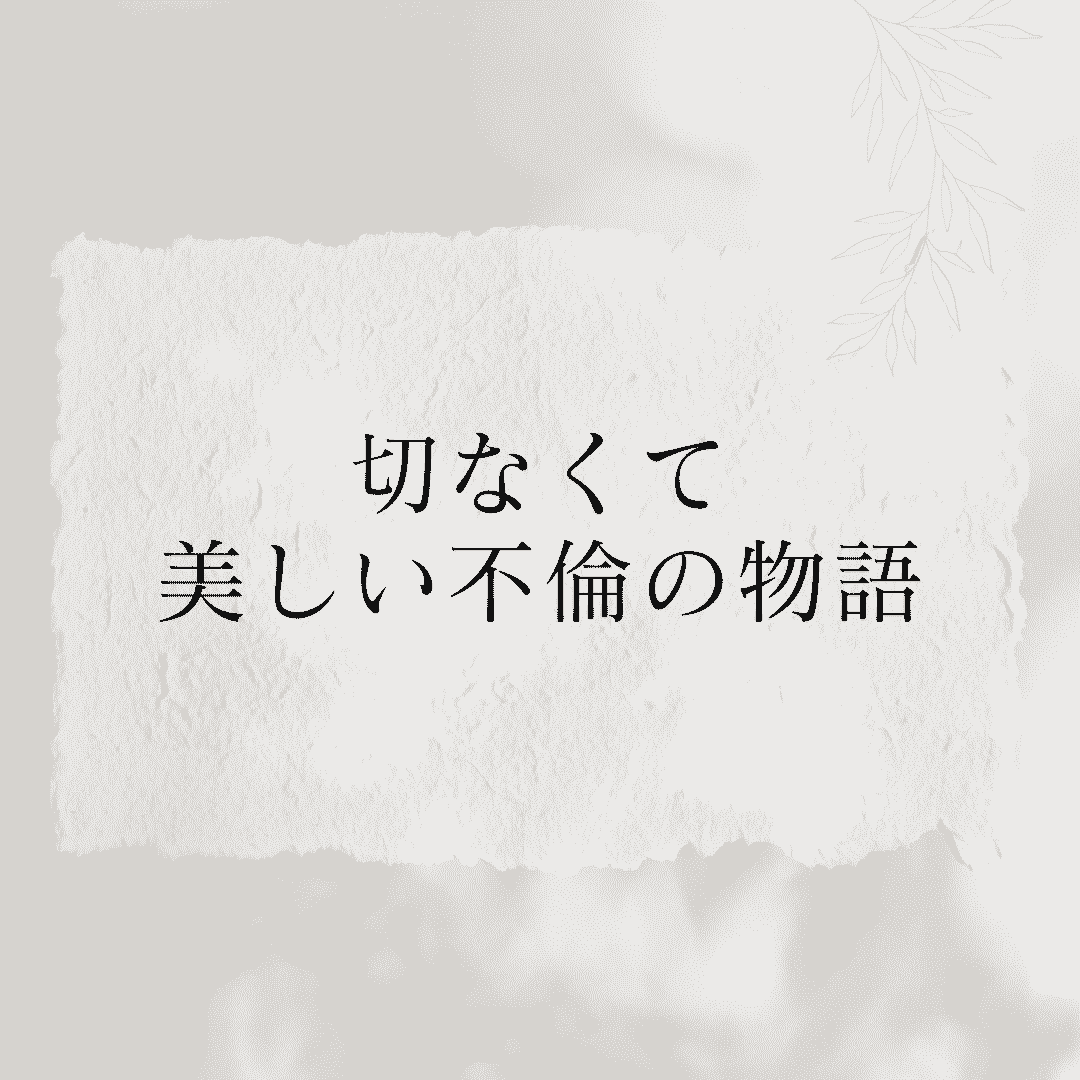
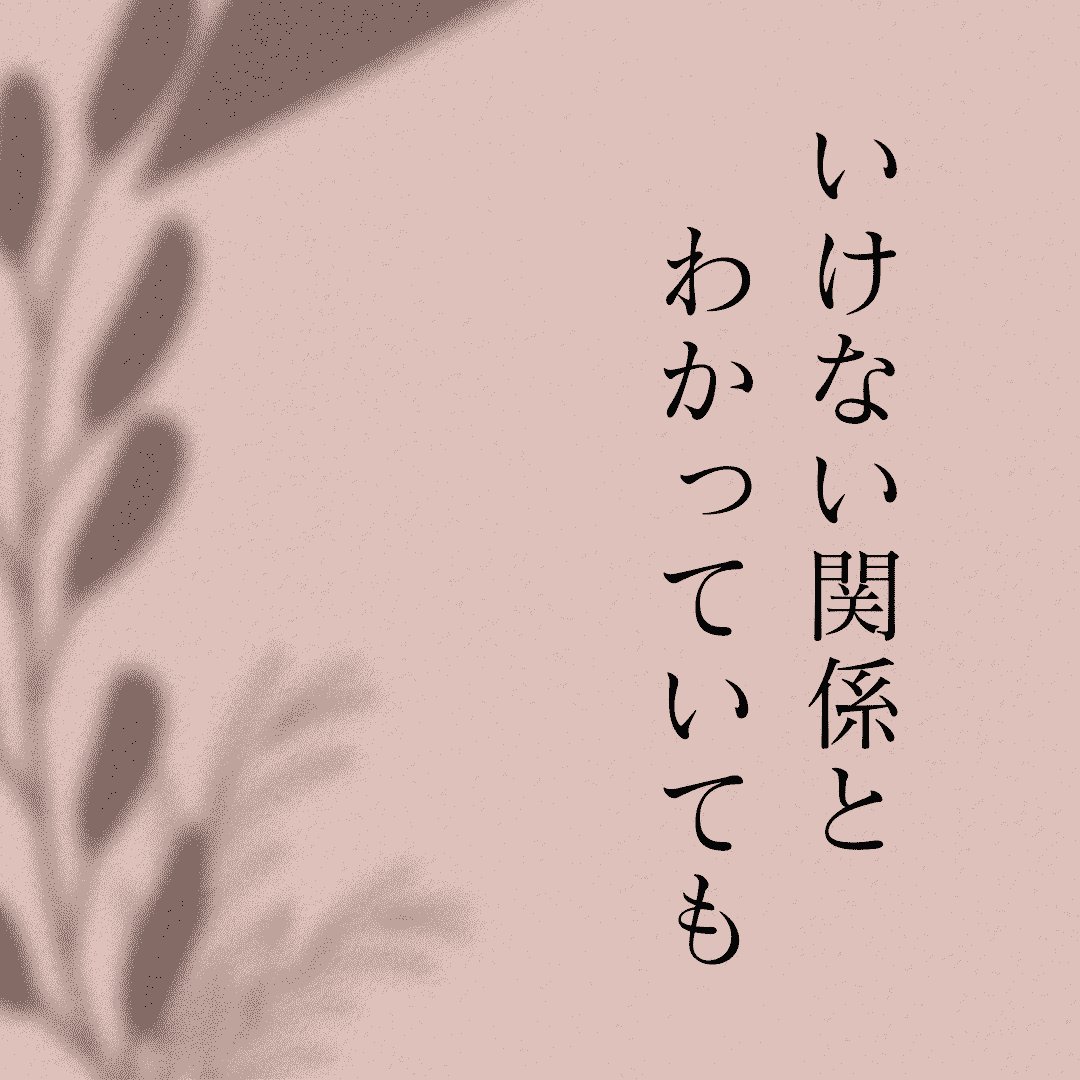








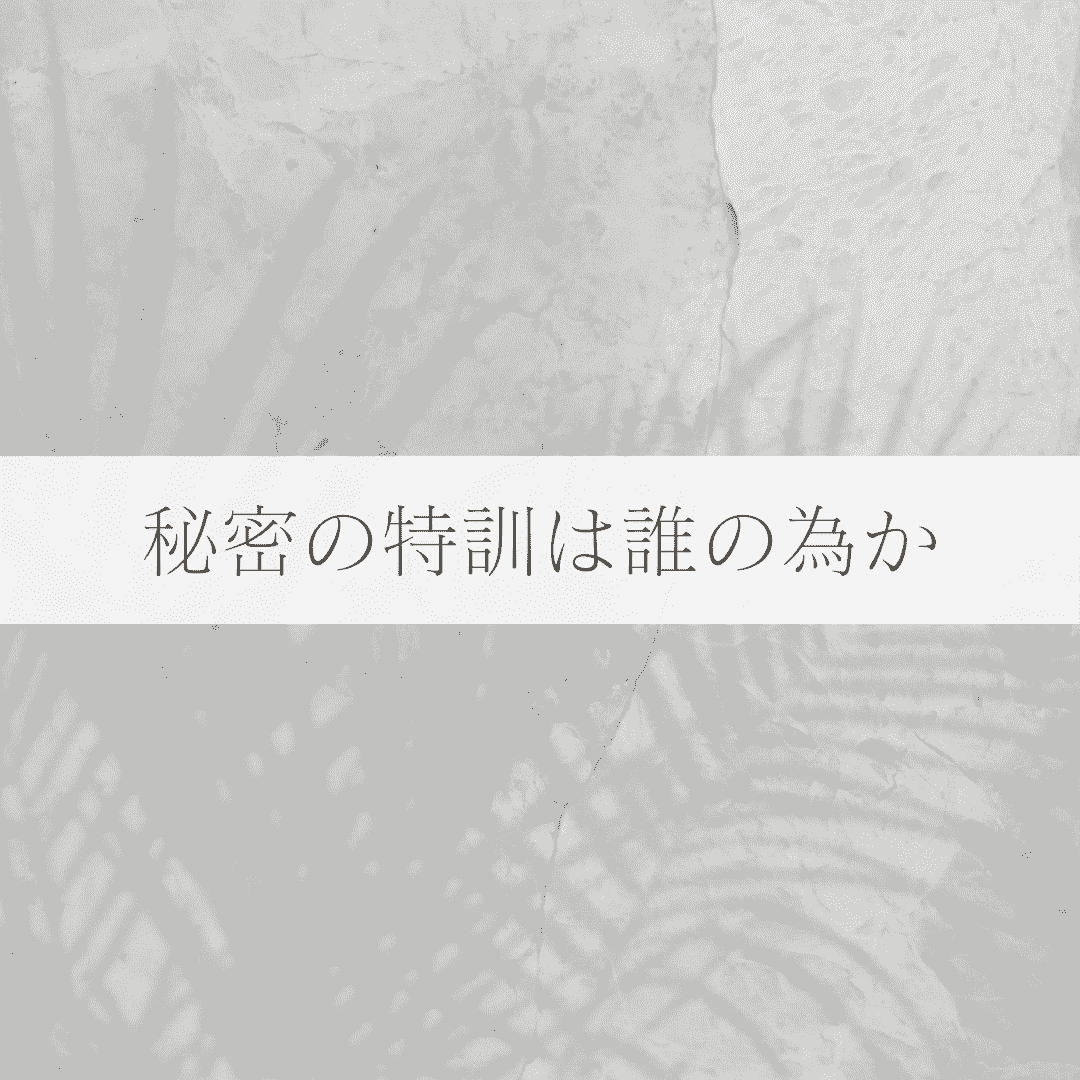
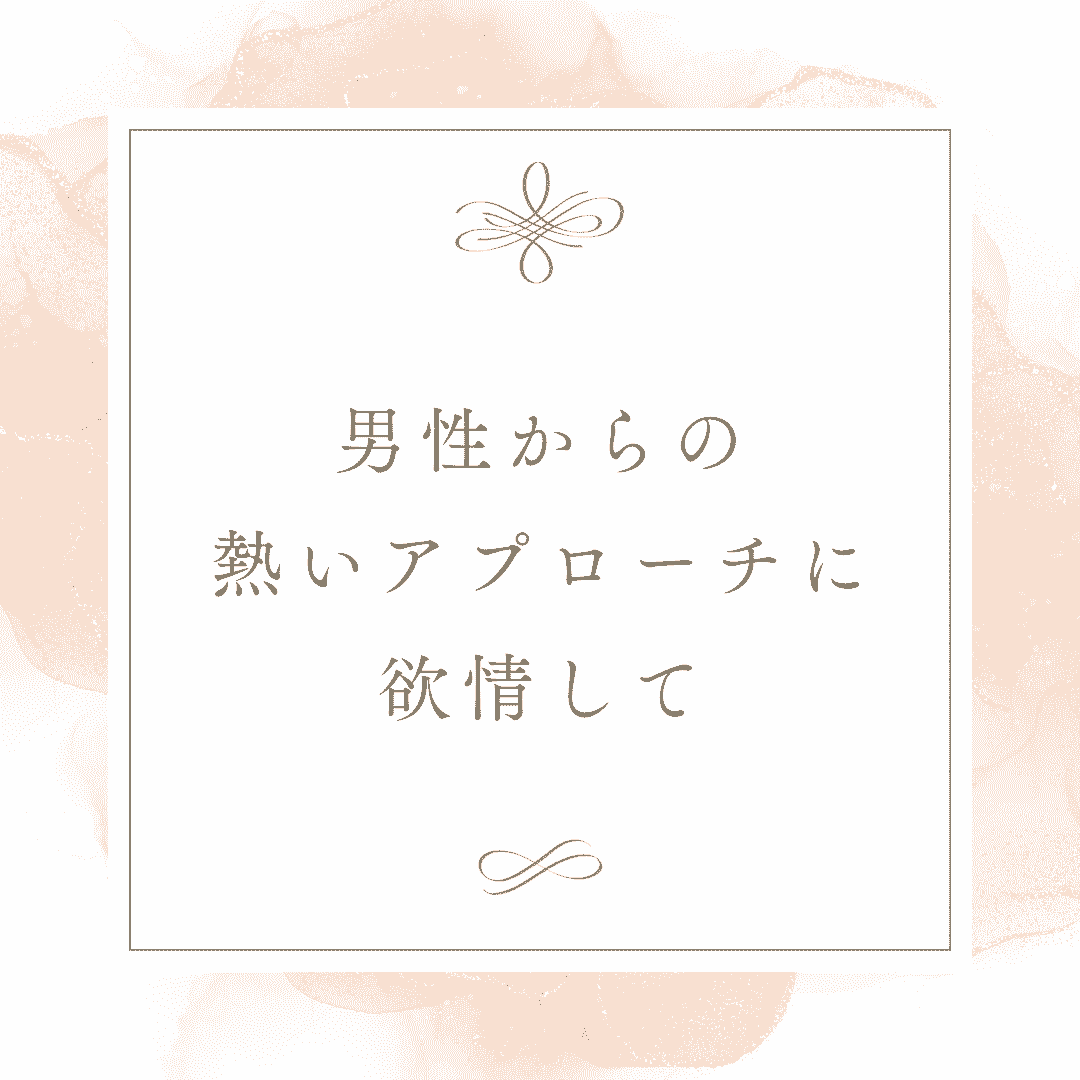


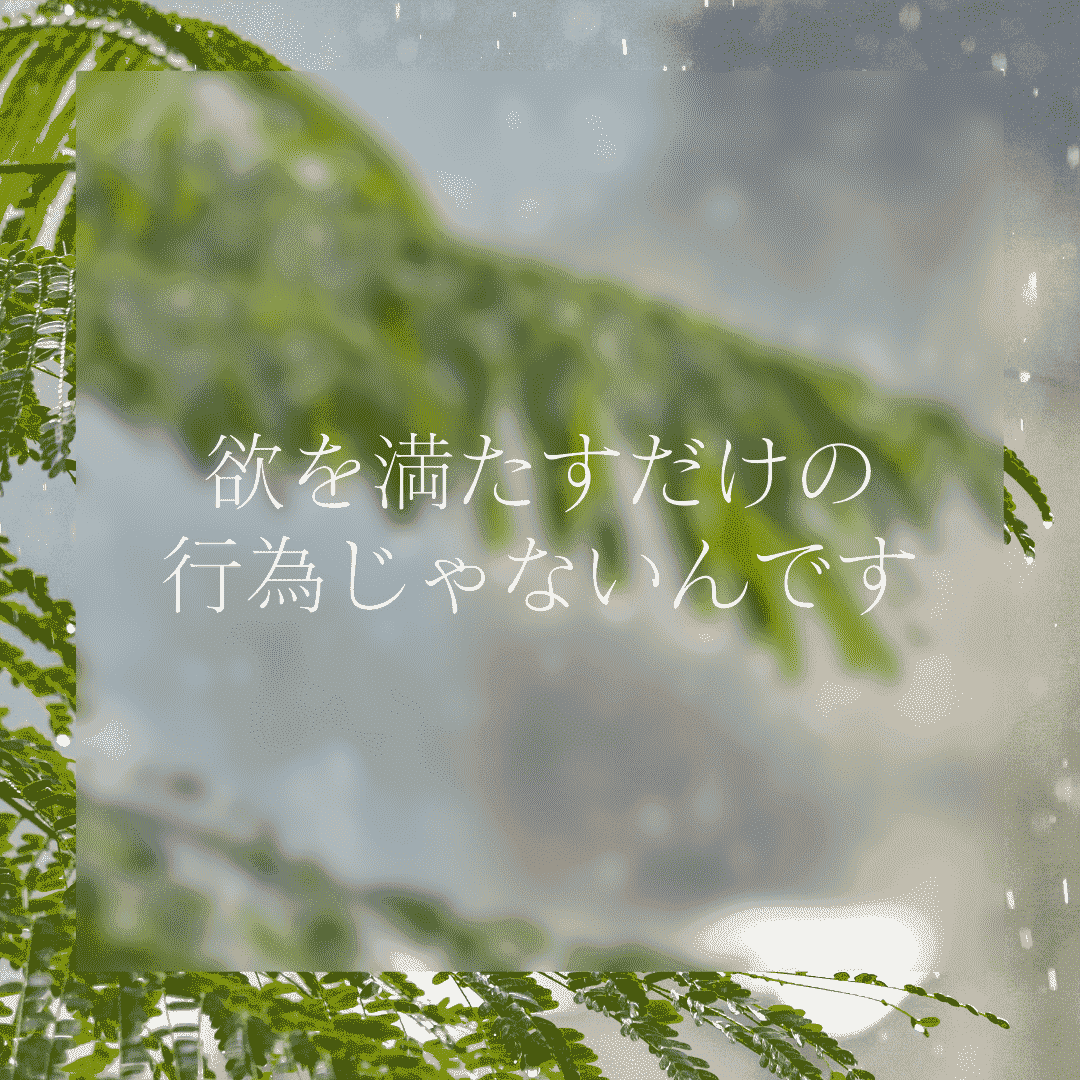

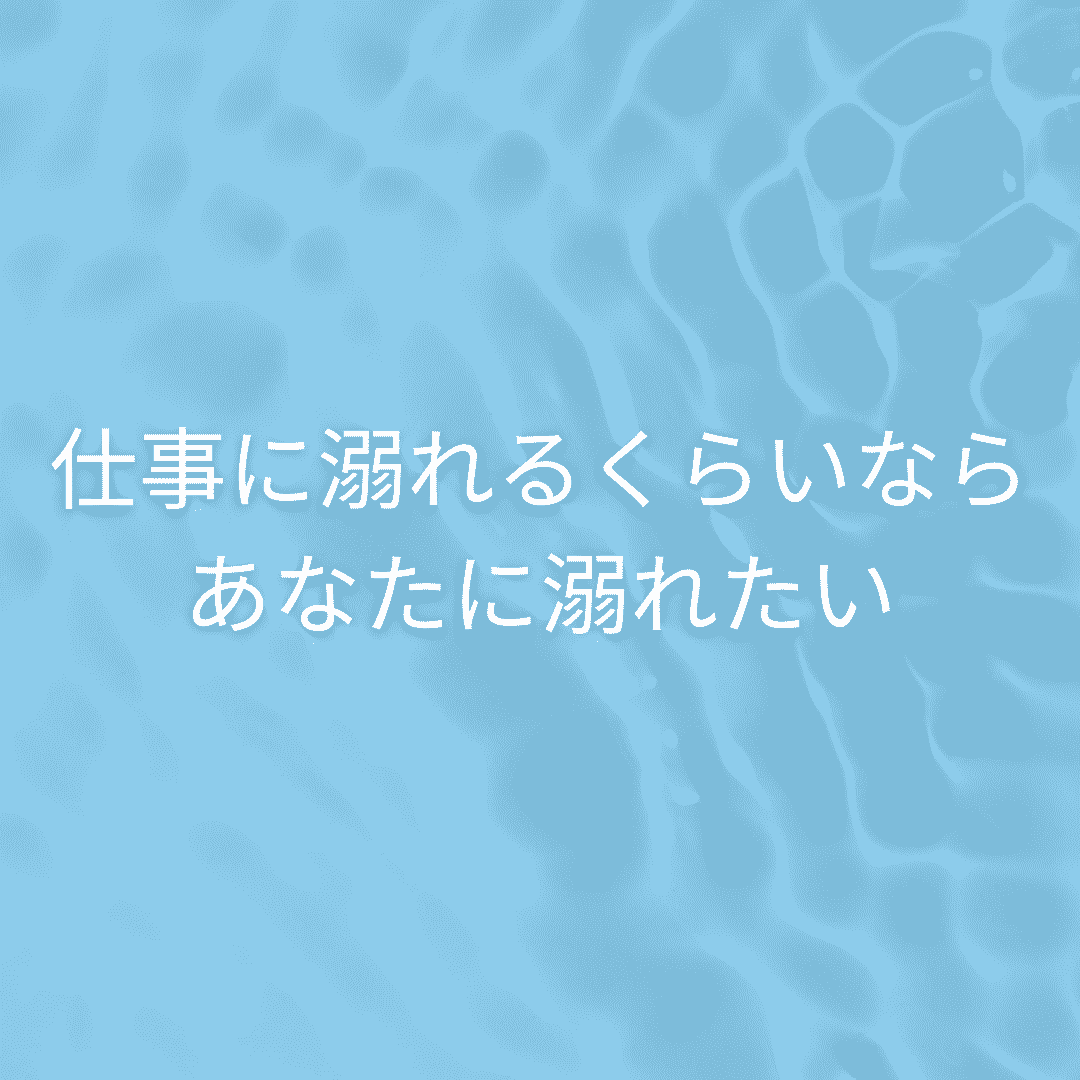


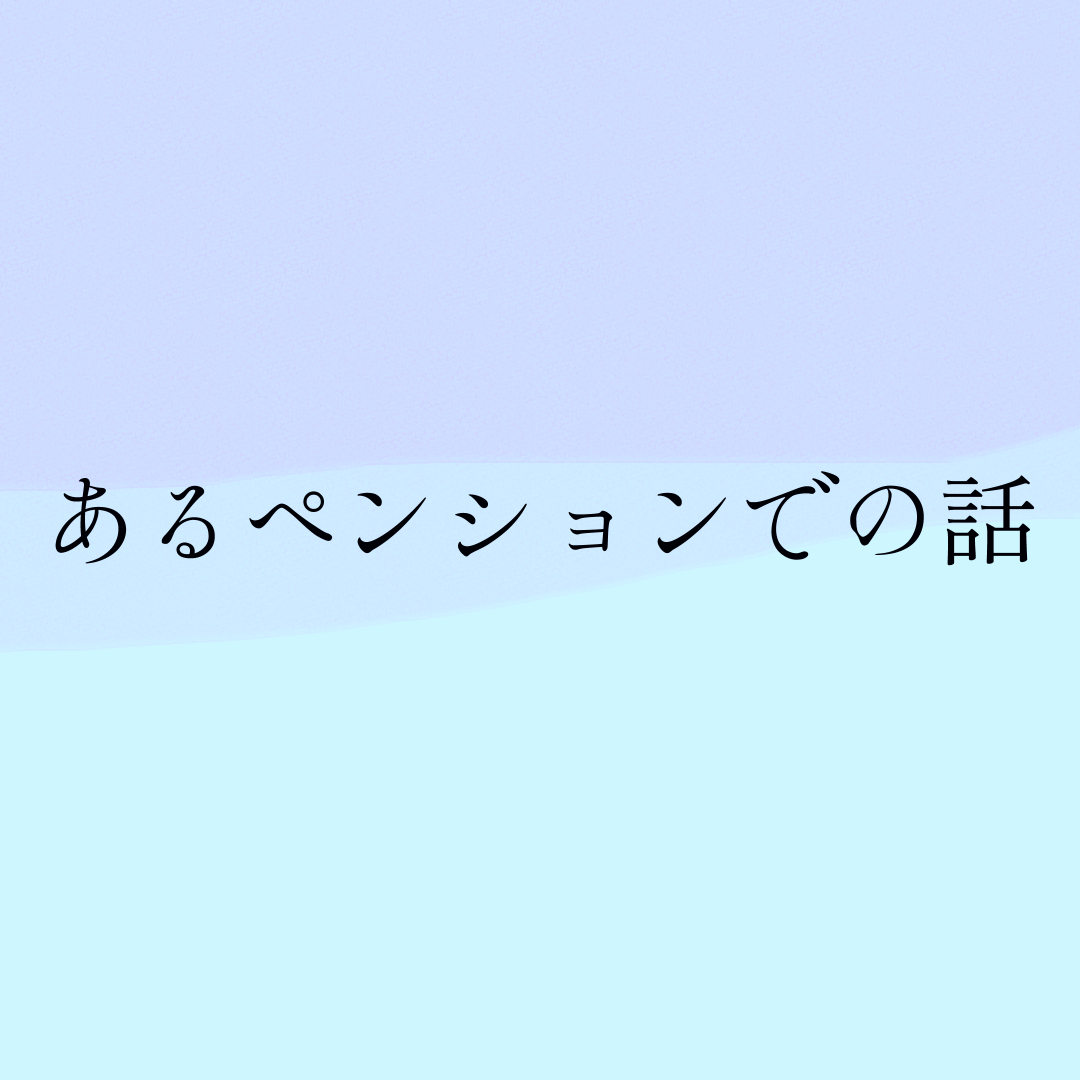
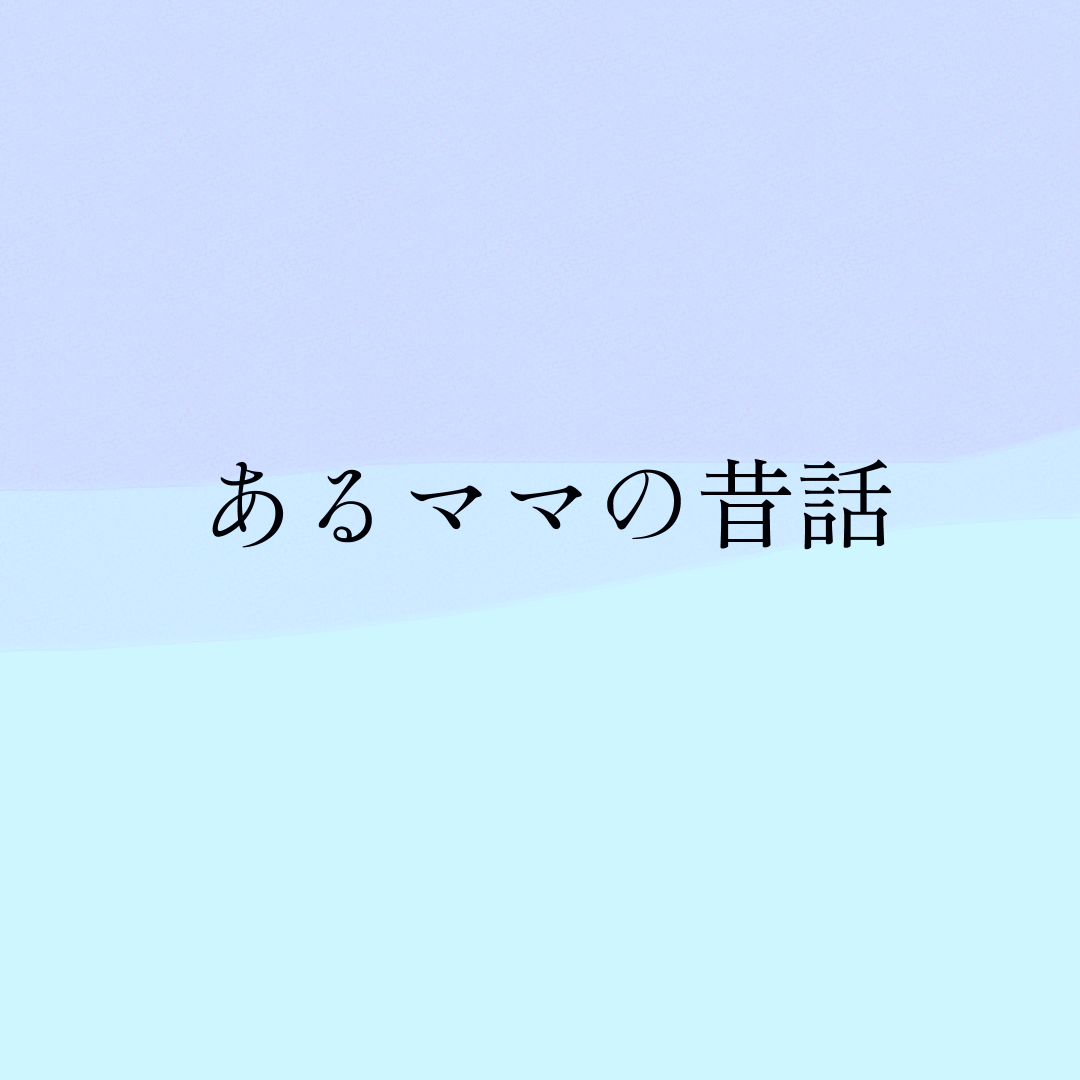
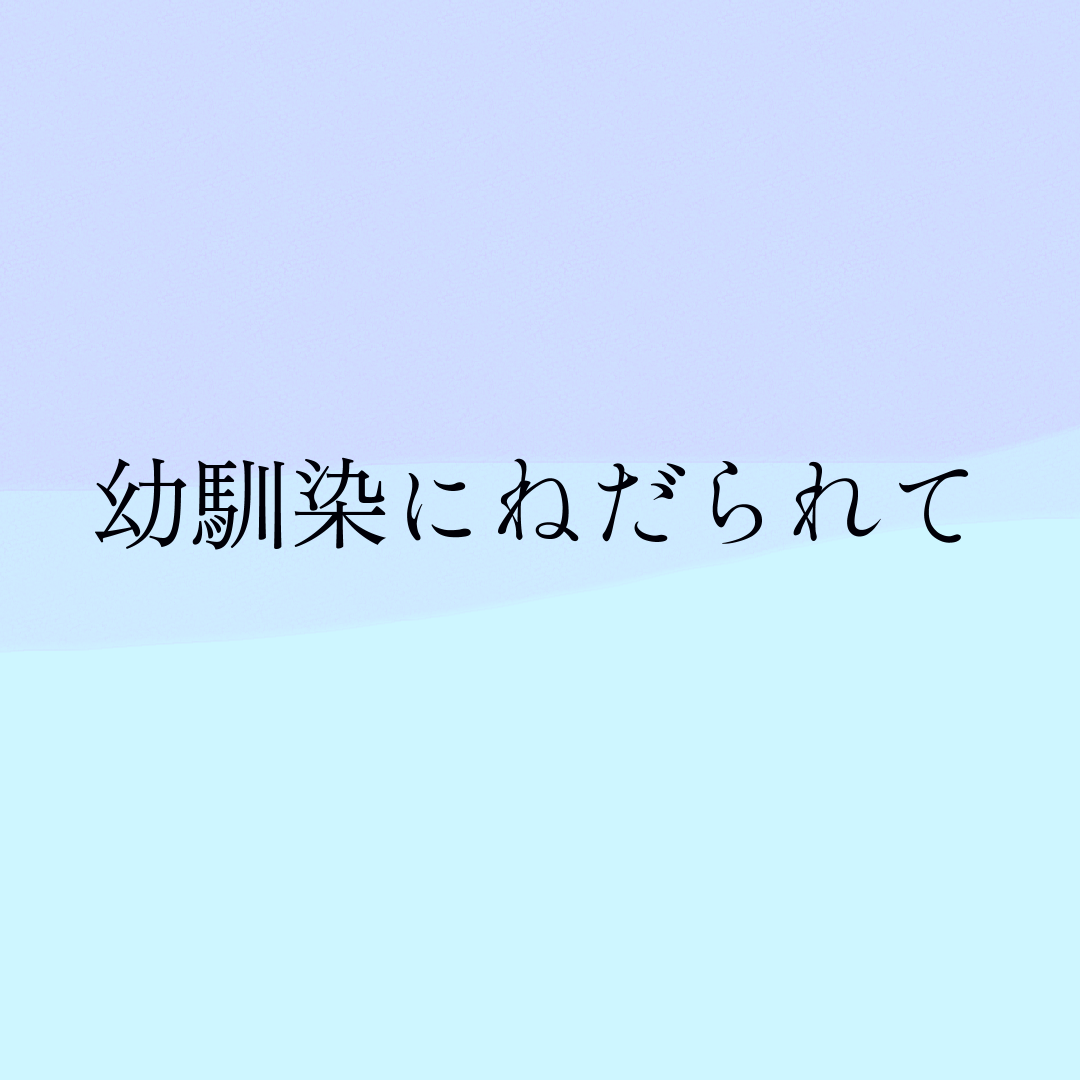
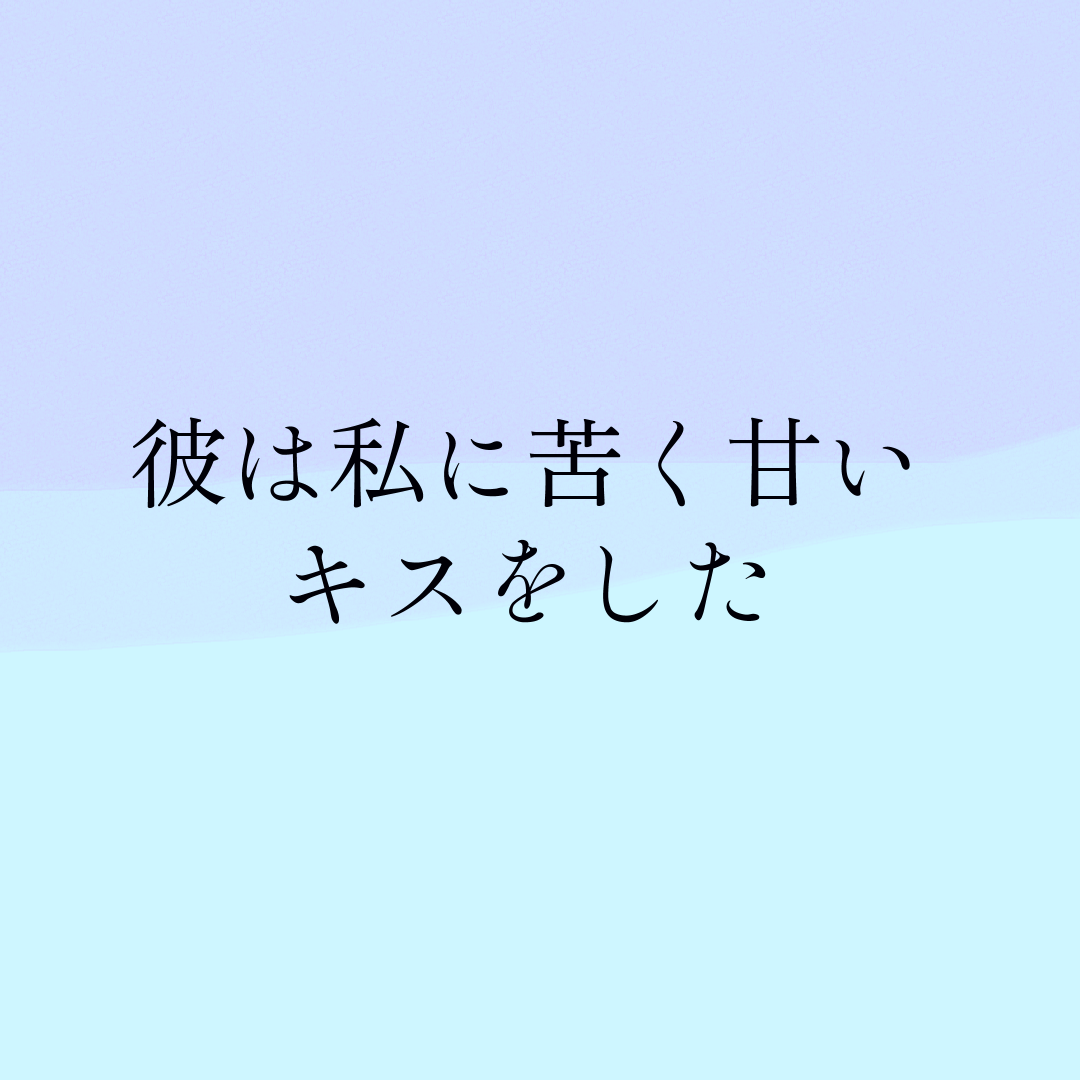
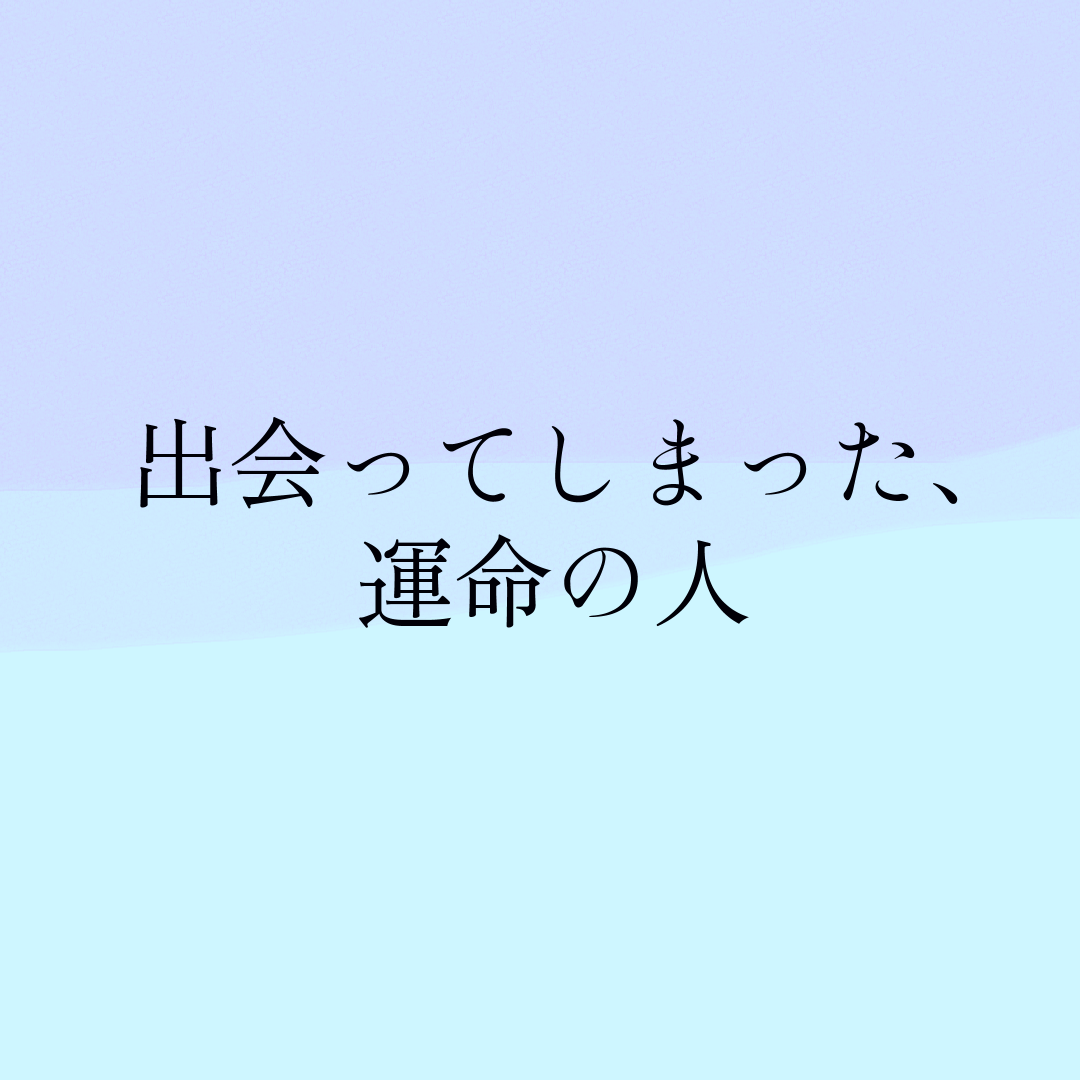
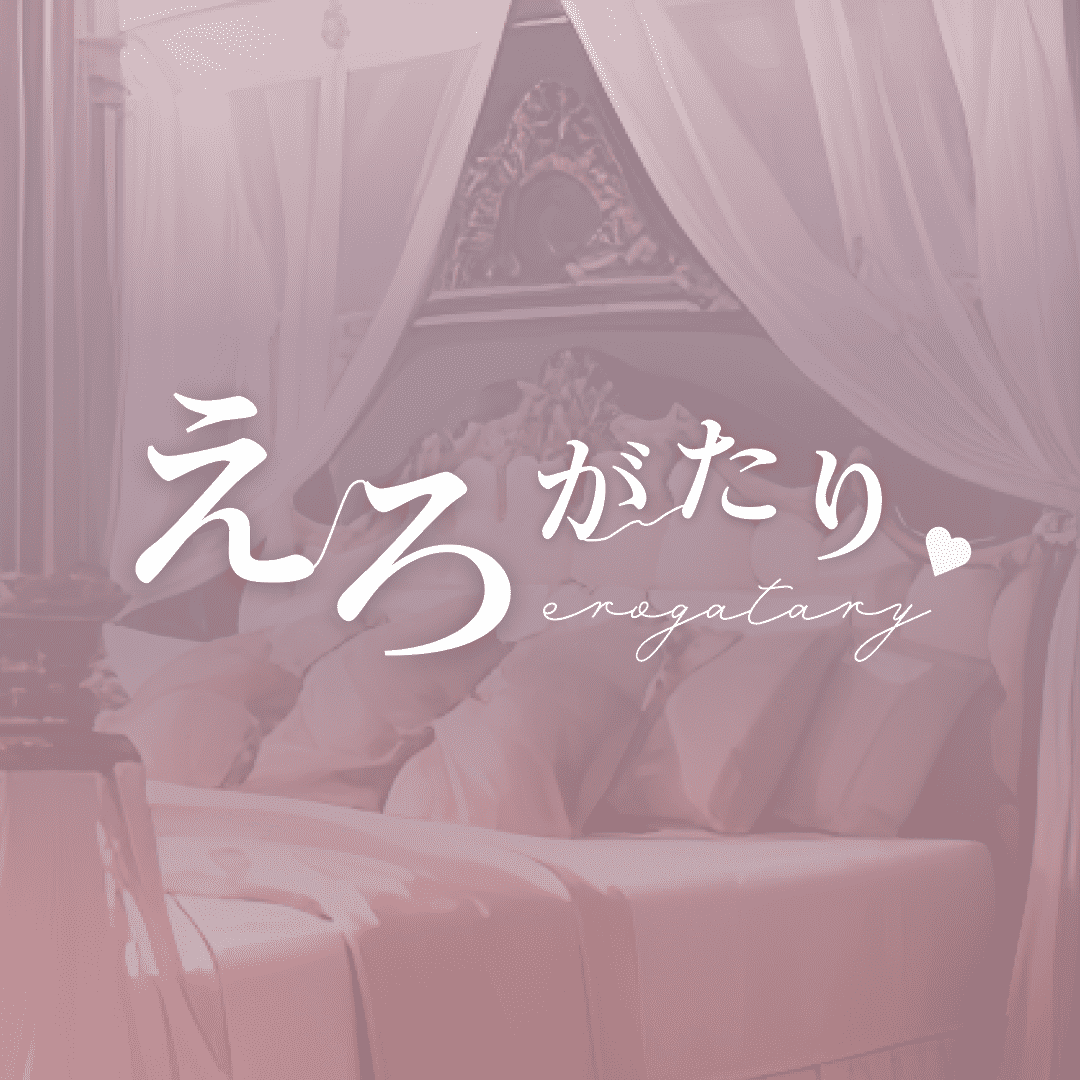
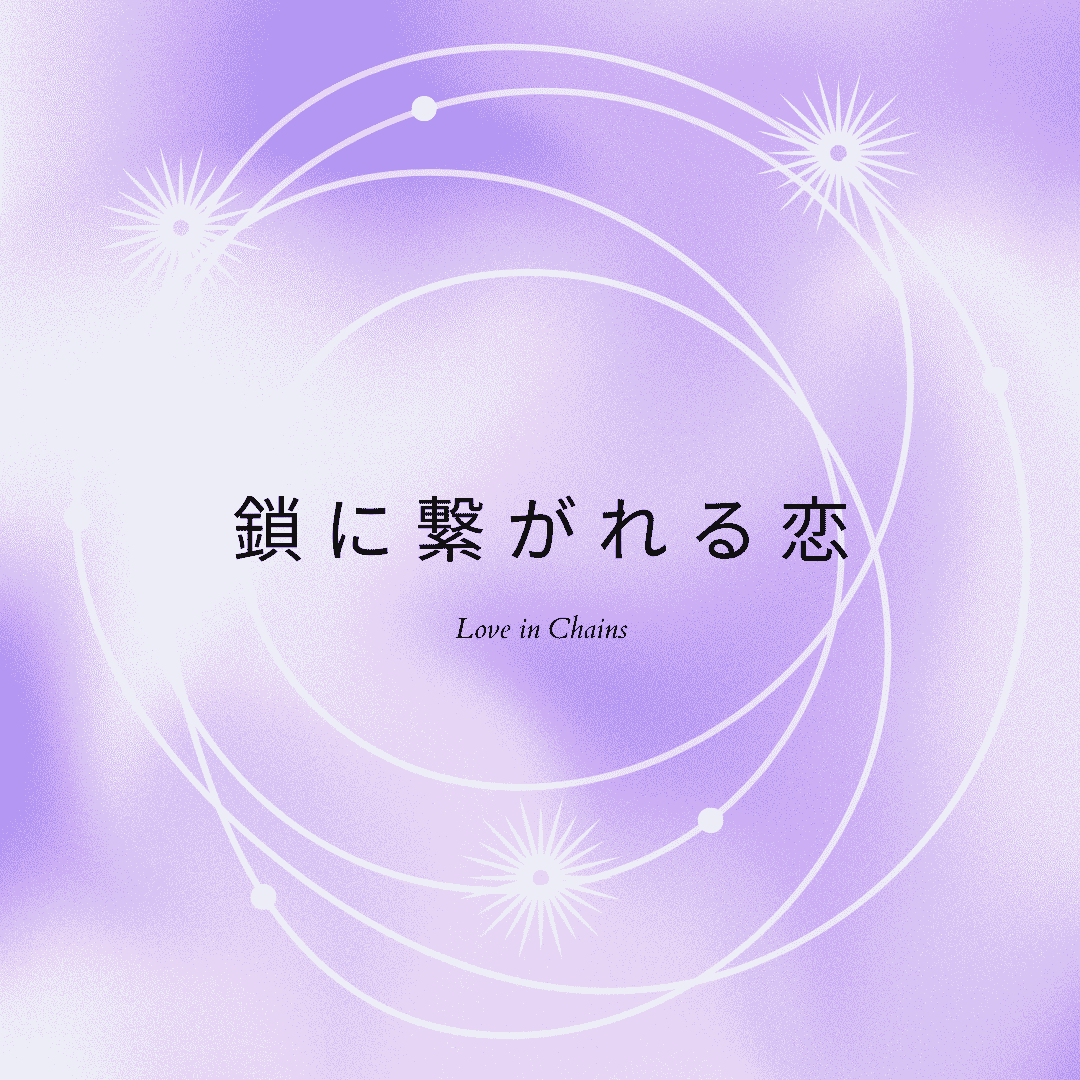



コメント