
0
マッチングアプリで出会った相手が生き別れた兄なんて何の冗談ですか?
「はぁ…あぁん」
マッチングアプリで出会った相手にすぐにこんなに熱い気持ちを感じるなんて、思わなかった。
7時間前に駅前で待ち合わせて食事をした。そして、私たちはそのままお互いを激しく求めあった。
私は中山もも。
25歳のOLだ。
結婚を意識しだしたけど、会社の中を見渡したらみんな既婚者。
少し年齢の上の社員が多い社内では、仕方ないこと。
さらに友達も、彼氏ができて、合コンの話もない。
『結婚を意識してるならマッチングアプリがいいんじゃない?』
そう言ってくれたのは、マッチングアプリで先月結婚相手を見つけた会社の先輩だった。
正直、夢見がちな私はそういう”お見合い”的な出会いより、恋愛結婚が理想だと思っている。
でも、その先輩に勧められて押し切られるように、ひとまずアプリを入れてみた。
休みの日にアプリをスクロールしていると、先輩が言うように、結婚を意識している人は多い印象…。
そのせいか、お付き合いをするには、申し分のない人ばかりだ。
「みんな出会いが少ないのかなぁ?」
そんなことを思いながらプロフィールを眺めていると、ふと目に留まる人がいた。
「茂木武蔵(もてきむさし)…。」
私は気になったその人と、何度かやり取りをした。
働いている会社、住んでいる場所、趣味のドライブ。
どれもこれも、条件は悪くない。
3歳年上の彼も私に興味を持ってくれたようで、実際に会ってみるまでに、それほど時間はかからなかった。
お互いプロフィール写真で顔を知っている。
服装も落ち着いていて、私の好みだった。
『この人ならこういう出会い方でもいいかも』
と思えるほど、私は茂木さんに一瞬で心奪われた。
「茂木武蔵さんですよね?」
「はい。中山ももさん?」
「はい。今日はよろしくお願いします。」
茂木さんはじっと私を見つめている。
「あ、あの何か…?」
「あぁ…中山さん、プロフの写真より実物はもっとかわいいなぁって。」
そんなふうに言われて、つい顔が熱くなる。
「あ、あのごめんなさい!いきなりこんなこと…。でもほんとに…。むちゃくちゃタイプです。」
茂木さんも恥ずかしそうに、そう言った。
「あ、ありがとうございます。」
お互いに照れてしまう。
「あ、じゃぁもうお昼ですし先に食事してからドライブしましょうか?」
「はい…」
茂木さんがエスコートしてくれたお店は、おしゃれなのにカジュアルなお店だった。
「パスタがおいしいです。」
そう言って勧めてくれたパスタは、ほんとにおいしかった。
でも私は、パスタが吸い込まれていく茂木さんの唇が気になって仕方ない。
なんだかつやっぽくて、セクシーなんだもん…。
食事の後はドリンクをテイクアウトして、茂木さんの車へと向かった。
車の趣味もいい。
エスコートも完璧。
何故この人に彼女がいないんだろう…不思議なくらいだ。
助手席に乗ってホルダーにドリンクを入れた。
隣を見ると、茂木さんはドリンクを口にしていた。
ほらまた—。
なんだろう。
この人の唇は、ほんとに私を惹きつけてくる。
「…?食事の時もですけど、俺のこと見てますよね?」
そう言われてハッとする。
「あ、あのごめんなさい。」
「ははは…。もしかして一口飲みたかったりします?」
そうやって、からかってくる茂木さん。
「い、いやその…」
「ももさんは食いしん坊なんですね。」
そう言ってニコッと笑った後、
「それとも俺に見惚れてます?」
なんて言われて、ドキッとしてしまう。
「なんてね。」
すぐにいたずらに笑って見せた。
その大人っぽさとのギャップに、さらに萌えてしまった。
『行きたいところがある』
と言って連れて来られたのは美術館。
「今やってる特別展示が見たくて。」
茂木さんは目を輝かせている。
私も美術館は好き。
特別展示は“美の中にある神秘”というものだった。
早速入館して見学をした。
茂木さんは驚くほど私と感性が似ていた。
何だか落ち着くなぁ。
そして特別展示のブース。
―え?
入って驚く。
だってほとんどの作品が、いわゆる男女の“絡み”だったから。
茂木さんを見ると、彼も気まずそうにしている。
それでも素敵な作品も多く、見て回る価値はあった。
けど―。
さり気なく私の腰に添えられた茂木さんの手に、気持ちが集中してしまう。
たぶんだけど、茂木さんも気持ちが高ぶっている気がする。
美術館を出た後も、ふたりの無言は続いた。
車のエンジンをかけて、茂木さんが前を見たまま口を開いた。
「いきなりだけど、二人きりでゆっくり話せる場所に行ってもいい?」
それって―。
「あの。」
「あ、嫌なら無理にじゃないんだ。」
茂木さんもテンパってるみたい。
私達は会ったばかりだけど、アプリである程度お互い知り合ってるし、もういい大人だ。
ましてやアプリで出会ってるし、お互い目指すところはきっと同じだろう。
もちろんヤリモクなんてことはないだろうけど、こうなってしまうことも可能性としては考えられる。
それに何より、私は茂木さんとならそういうことになっても構わない。
「いいですよ。」
笑顔でそう伝えた。
茂木さんもホッとしたような顔になって、車を走らせた。
郊外にあるお城のようなラブホへと入っていく。
無言だけど、私の手を引いて歩く彼の背中に、安心感を感じてしまう。
それと同時に、これから起こるであろうことに期待している自分もいた。
部屋に入ると天井までガラス張りで、やっぱり緊張した。
「シャワーする?」
そう聞かれてコクリと頷く。
服を脱いでいると、
「一緒にいい?」
と突然後ろから声をかけられて、
「キャ」
と小さく叫んでしまった。
「ごめん、でもお風呂ガラス張りだし、外から見られるより、一緒に入った方がマシかと思って…」
そう言われたらそうかも。
私はタオルで前を隠して、茂木さんを招き入れた。
彼は手際よく服を脱いで、一緒にシャワーを浴びる。
お風呂では、ほんとに一緒にシャワーをしただけで、ちょっとがっかりした。
でも茂木さんは、食い入るように私の背中を見つめていた。
シャワーのあとは、優しく髪を乾かしてくれた。
なんて心地良いんだろう。
茂木さんが、髪を整えてくれている。
なんかすごい安心感と幸福感。
ベッドに戻ると茂木さんはペットボトルを2本出して、1本渡してくれた。
「ありがとうございます。」
胸元から見える肌が、さっきの美術館での作品を思い出させて少し気分が高揚する。
座りなおすふりをして、少し距離を詰めた。
あぁこのまま抱かれるのかな?
不安を上回る期待に、胸躍ってしまう。
でも茂木さんの次の言葉で、地面から浮いていた足が着地させられるような気持ちになる…。
「ももちゃんのお父さんって、中山紀芳(きよし)だよね。」
思いもしない言葉に、驚いてしまった。
「ど、どうして…。」
「やっぱりそうだよね。」
茂木さんは少しうつむいた。
「実はその人、俺の父親なんだよね」
「え?」
「ももちゃんは覚えてないかもしれないけどさ、俺たち5年くらい一緒に暮らしてたんだ。兄妹として。」
え…いろいろと情報が追いつかない。
「最後に会ったのは俺が小5の時。」
私は何も言えないでいた。
「俺はももちゃんのお母さんと仲良くできなくてさ、俺の母親の家に引き取られたんだよ。」
そんな…。
「でも、ももちゃんは俺になついてくれててさ、“むーくんのお嫁さんになりたいって”言ってくれてたんだ。俺もまだ子供だったから、ももちゃんと結婚しようって本気で思ったりして。」
そう言って、自嘲気味に笑った。
「種違いだけど兄妹なのに、本気でそんなこと考えてたんだよね。」
むーくん…。その名前に私の記憶がうっすらと反応する。
「アプリでやり取りしてるときも、何となく思ってたんだよね。“ももちゃん”なんて可愛い名前あんまりないし、苗字も同じだし。それに背中のほくろ…」
あぁ、さっきお風呂で見られたんだ。
「共働きだったおやじとももちゃんのお母さんに替わって、俺がずっとももちゃんの世話してたから、お風呂だっていつも一緒だった。」
はぁ…。と短い息を吐いてから私を見る茂木さん。
「今日会って気づいちゃったよ。俺はあの時からずっと、ずっとももちゃんが好きなんだ。」
「茂木さん…」
「種違いの兄妹ってわかってる。それでも俺は、いけないってわかっても俺は—。どうしようもなくももちゃんに惹かれてしまう。」
茂木さんの目には、うっすらと雫が揺れている。
向き合って両手をつながれる。
そこから私も熱を帯びてしまう。
今まで感じていた安心感や懐かしさは私たちが共に過ごしていた時間や、父親からの遺伝的な本能なのかもしれない。
でも、今感じているこのドキドキは、そうじゃない。
私だって、兄妹以上の感情を持っていることは偽れない。
「む―くん。」
そう口に出してみると、とてもしっくりくる。
でもそれ以上に、下腹部が熱を持ってどうしようもなく彼を求めてしまう。
「ももちゃん…。いいかな?」
じっと見つめてくるむーくんに、私はこくりとうなずく。
知ってしまっても、なお抑えられない気持ち。
むーくんはそっと私の唇に自分のを合わせた。
唇から全身に甘いしびれが広がっていく。
もう一度視線が絡まったのを合図に、む―くんはガバッと私を押し倒した。
「もも…」
何度も私の名前を呼びながら、夢中で私の身体をまさぐっている。
ほほ、肩、脇腹、胸のふくらみ…。
まるで赤ん坊のようにむさぼってくるその刺激に、私は絶えず声をもらしてしまう。
「はぁ、あぁむ―くん。お兄ちゃん。」
彼の頭を抱えて、もっとしてほしいとおねだりした。
彼の舌が這い回る自分の身体を、恨めしく思う。
父親が一緒じゃなければ、こんな後ろ暗い気持ちにはならなかったのに…。
「あぁ、もも…こんなに体が成長して…。」
鷲掴みにした胸を見下ろしながら、彼はその形を堪能しているようだ。
太ももに熱い感触。
あぁ、これは…。
彼の股間に視線をやると、そそり立つ彼のペニスが見えた。
「あぁ、お兄ちゃんこんなになっちゃって…」
そう言って、そのたけりを手で包んだ。
「うっ!」
短くうめいて腰を折るむーくん。
「だって、だって。」
そう言いながら私の秘部に手を伸ばしてくる。
「ここに、」
む―くんの手が触れたその中心は”ぴちゃ”っと卑猥な音を出している。
「ここに入れたい。」
それは本当に切実な願い。
つながってしまっていいのか、どうか?
二人とも考えてしまう。
お互いがこんなに求めているのに…。
私はぎゅっと彼の身体を抱きしめた。
いや、抱きしめたのではなく、抱き着いた。
「怖いの?震えてる。」
優しく私を抱きしめ返してくれる。
しばらく熱い部分を感じながらも抱きしめ合った。
そしてむ―くんが、そっと耳元でささやいた。
「ももちゃんが怖いことや不安になることは避けたい。」
そして、そっと私の太ももの間に、彼のモノを滑り込ませた。
ゆっくりと私の蜜口をなぞるように動き始める。
「はぁ。」
む―くんの熱い吐息。
それは私の脳みそを、じわじわと溶かしていく。
「む―くん」
「ダメ、“武蔵”って呼んで」
「え?」
「ごめんももに“む―ちゃん”とか“お兄ちゃん”って呼ばれたら罪悪感半端ない。」
そうか。
“むーちゃん”って呼んだら、私自身も、小さかった頃を思い出してしまう。
それは確かにやばいかも…。
今はもう大人の私。
こういうこともできる“大人の女”なんだ。
「…むさし…。」
そう言った瞬間股の間でむさしのモノがドクンと波打った。
「あぁんん!」
快感に腰をそらしそうになるけど我慢した。
だって少しでも間違えば、彼のが私を貫いてしまう。
武蔵も我慢してくれてるのにそれはダメ…。
「あぁ、ももの蜜が俺のに絡みついてどうにかなりそう…。」
「私も…武蔵のが振れるたびにしびれちゃう。」
挿入(い)れてないのに今まで経験したエッチと比べ物にならないほどの快感。
“挿入(い)れてしまったらダメ”そう思う気持ちも相まってどんどん蜜があふれてくる。
「ずっとこうしていたい。」
「うん。」
「でも思いっきり出してしまいたい。」
「うん。」
解放されたいのに解放されたくない。
私たちの関係の間にあるジレンマのように、二人の密着がじれったかった。
後ろのアナにまで達する彼の先端を、全身で感じる。
あぁ、たかがマッチングアプリなのにこんなにマッチする相手と出会えた。
それなのに、私たちにはどうしようもできないしがらみに縛られてしまう。
それでも気持ちよくて、欲望には逆らえない。
胸をもみながら至福の表情を浮かべる武蔵が、最高に愛おしい。
もっとめちゃくちゃにしてほしい。
全部どうでもよくなるように…。
「はぁはぁ…」
荒くなった息遣いに武蔵の限界を感じる。
私だってもう…。
びちゃびちゃになった下半身を彼に押し付けた。
「いいの?もも、いけるの?」
コクコクとうなずくと彼は自分のモノを握った。
それを見て私は、
「ねぇそれは私が。」
とお願いする。
そう言って彼の股間に手を伸ばし、上下にこすり上げた。
「うっ!」
苦悶の表情を浮かべながらも、武蔵は彼の細く長い指を私の中に挿入(い)れてきた。
2本か3本か…ぐちゅぐちゅと私の中をかき混ぜる。
お互いの気持ちいいところを探りながら、どんどんと昇っていく。
「あっ!ももっ!」
そう言って彼は腰を逃し、私のおなかの上に白い液体を大量に放った。
そしてぐったりと、私の上に覆いかぶさる。
「…ごめん。」
彼の体液が私と彼の間で、熱くにじむのがわかる。
私たちはわかっている。
このままではいけないこと…。
それでももう、知ってしまっている。
これ以上の相手がいないこと。
それでもあがいてしまう。
これが冗談であればいいと…。






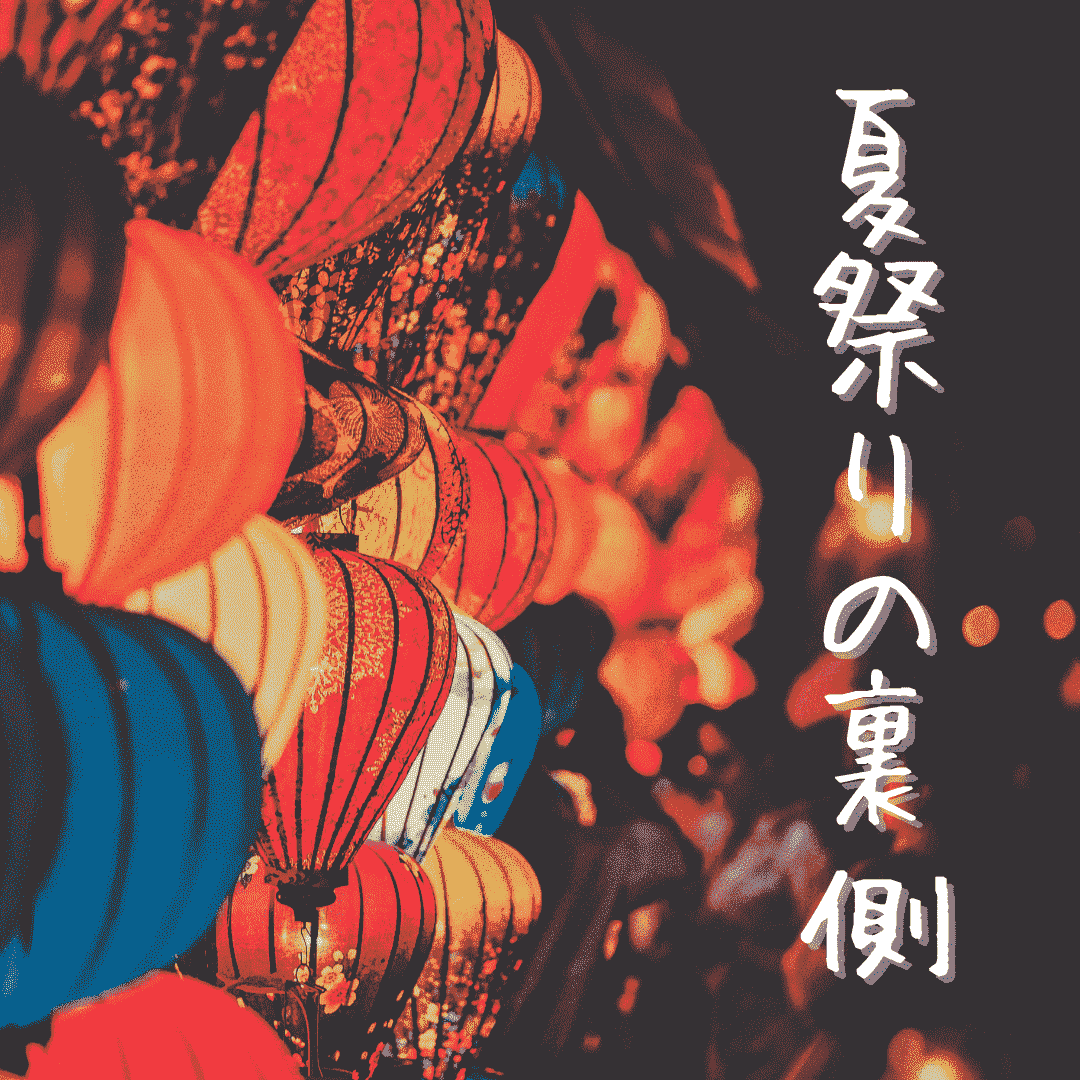

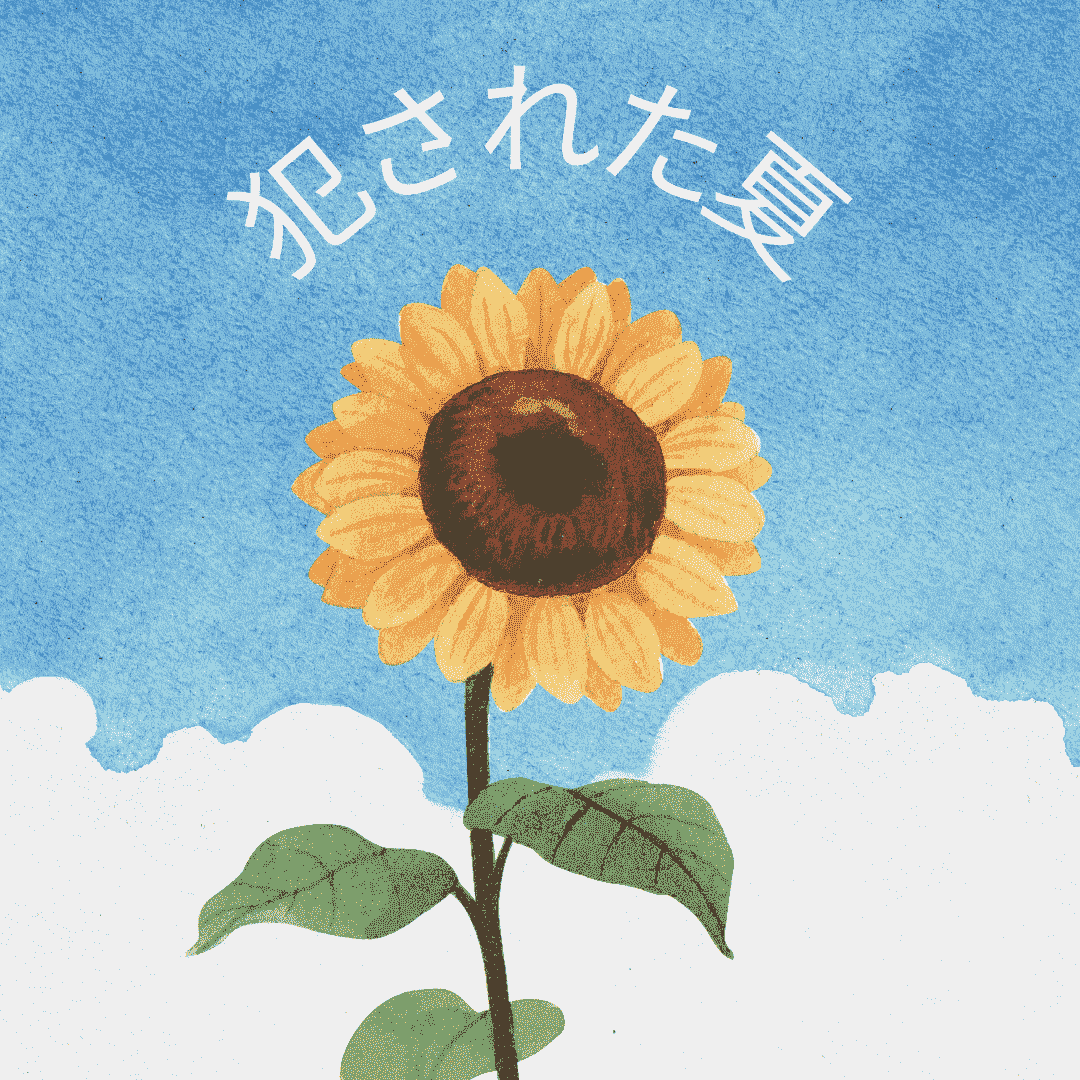


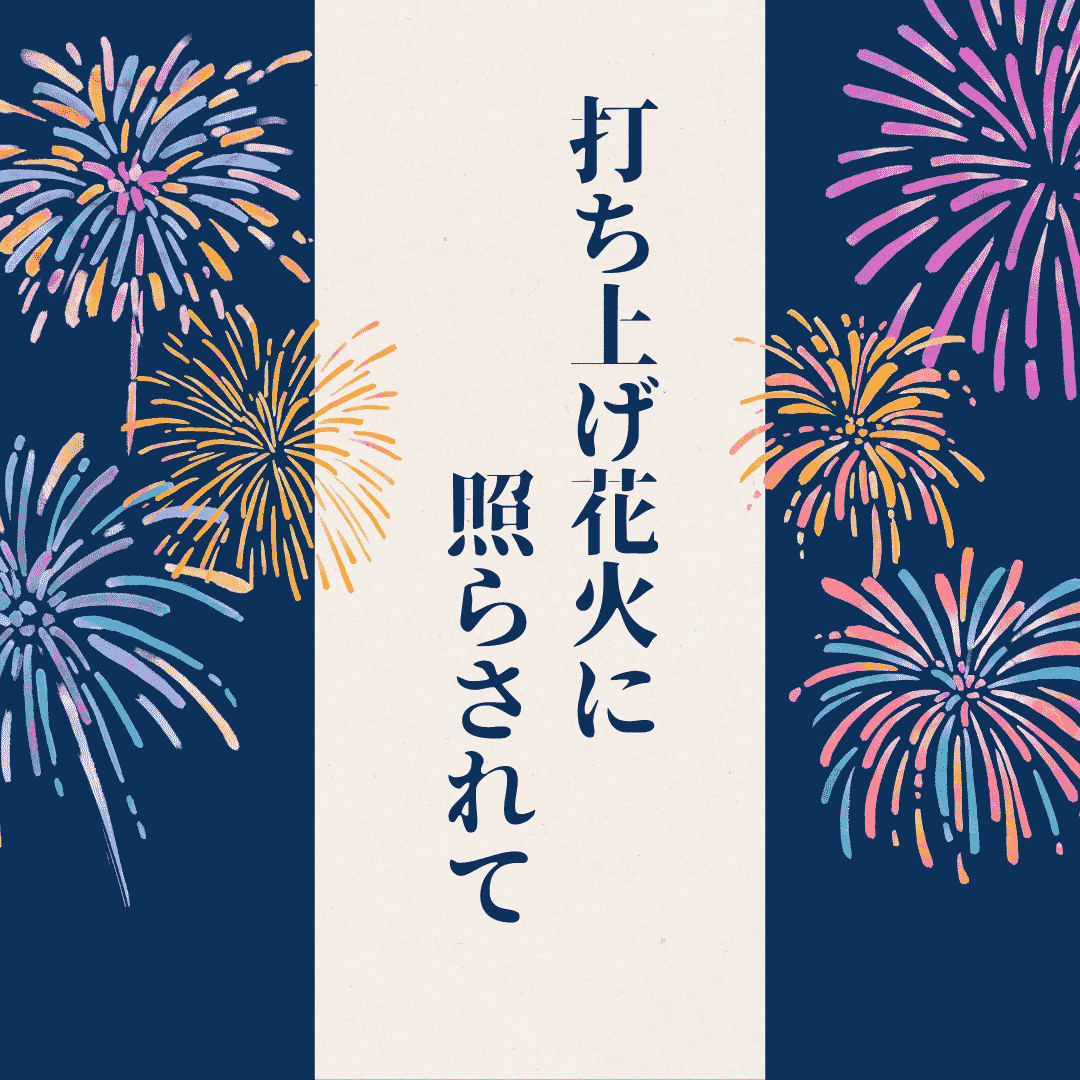

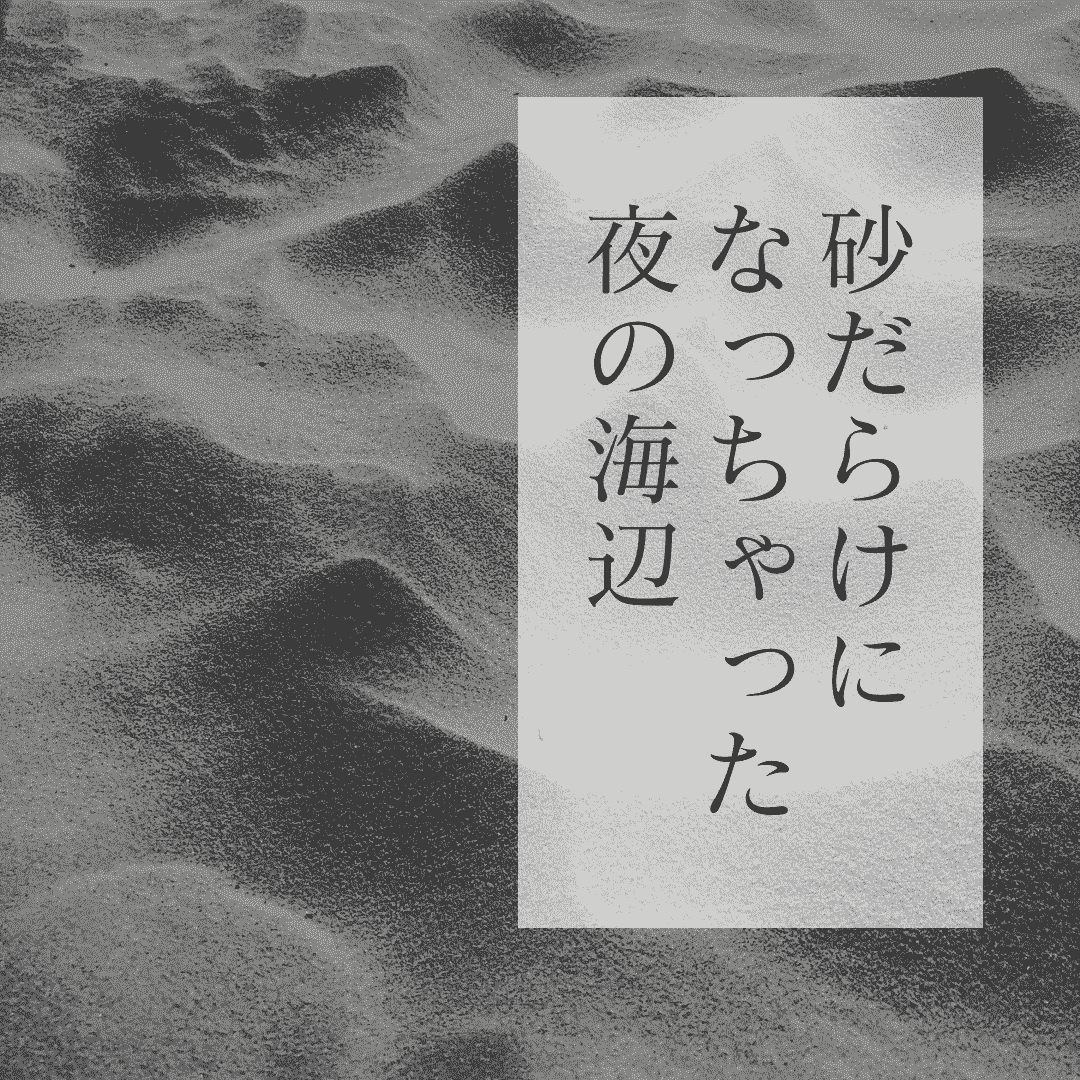

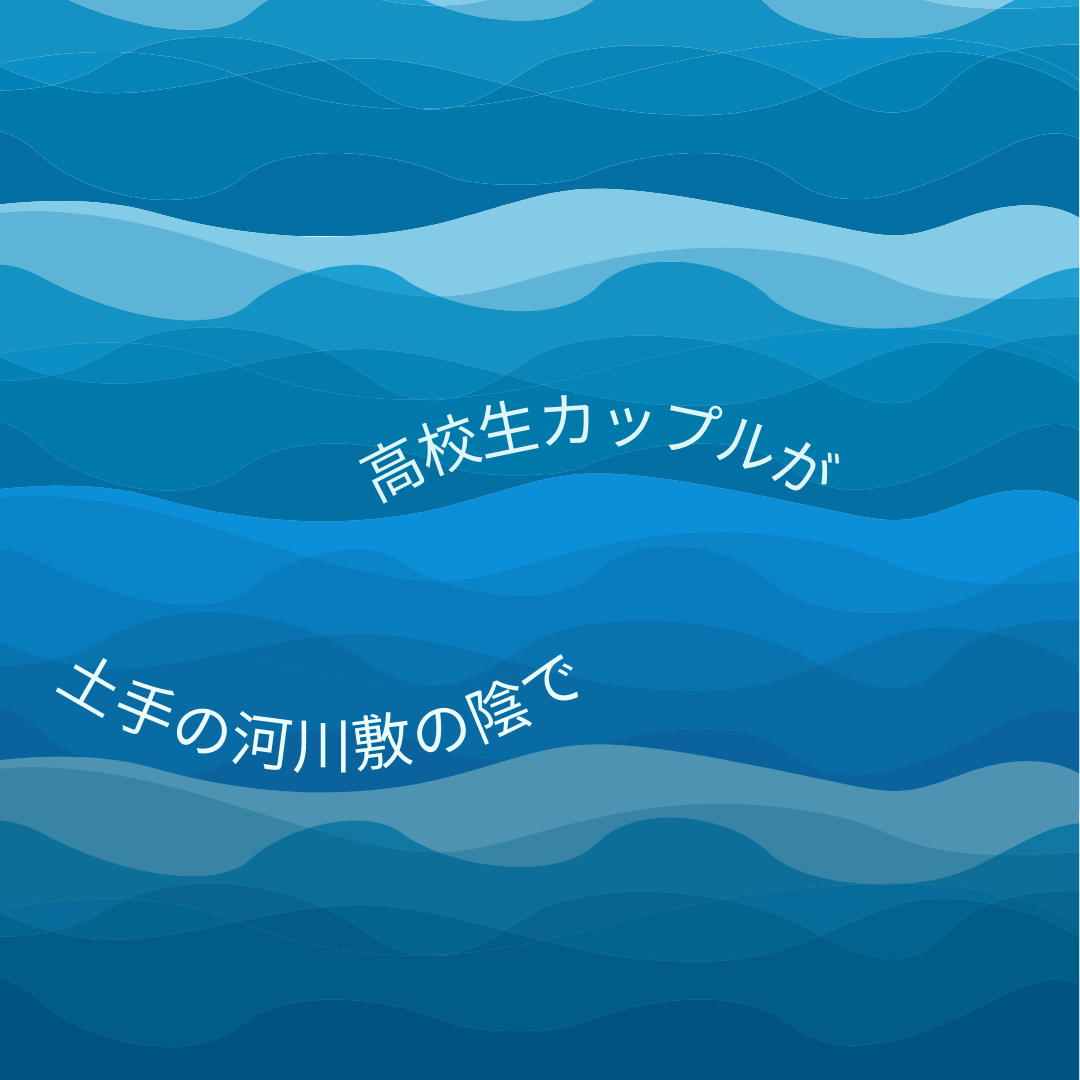


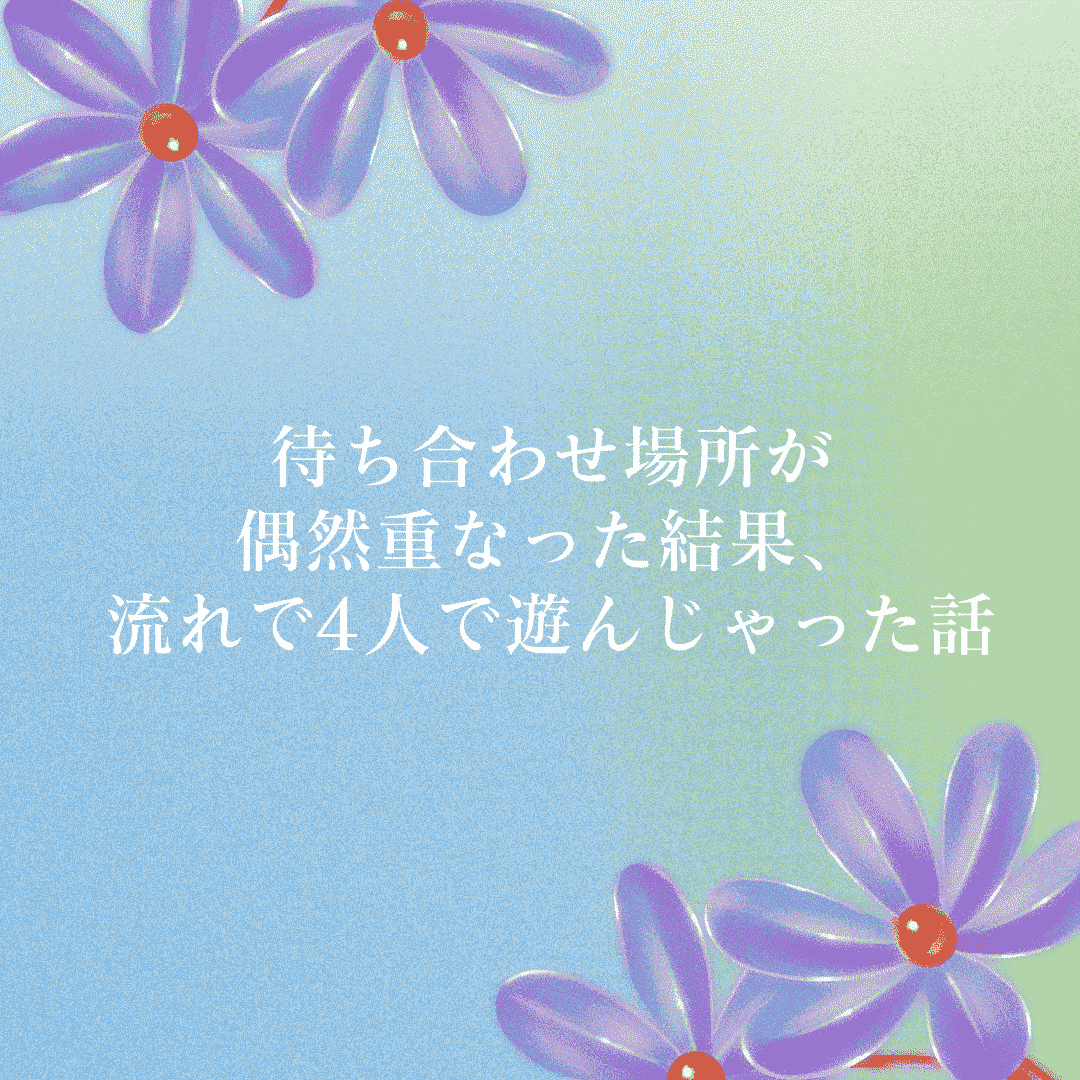




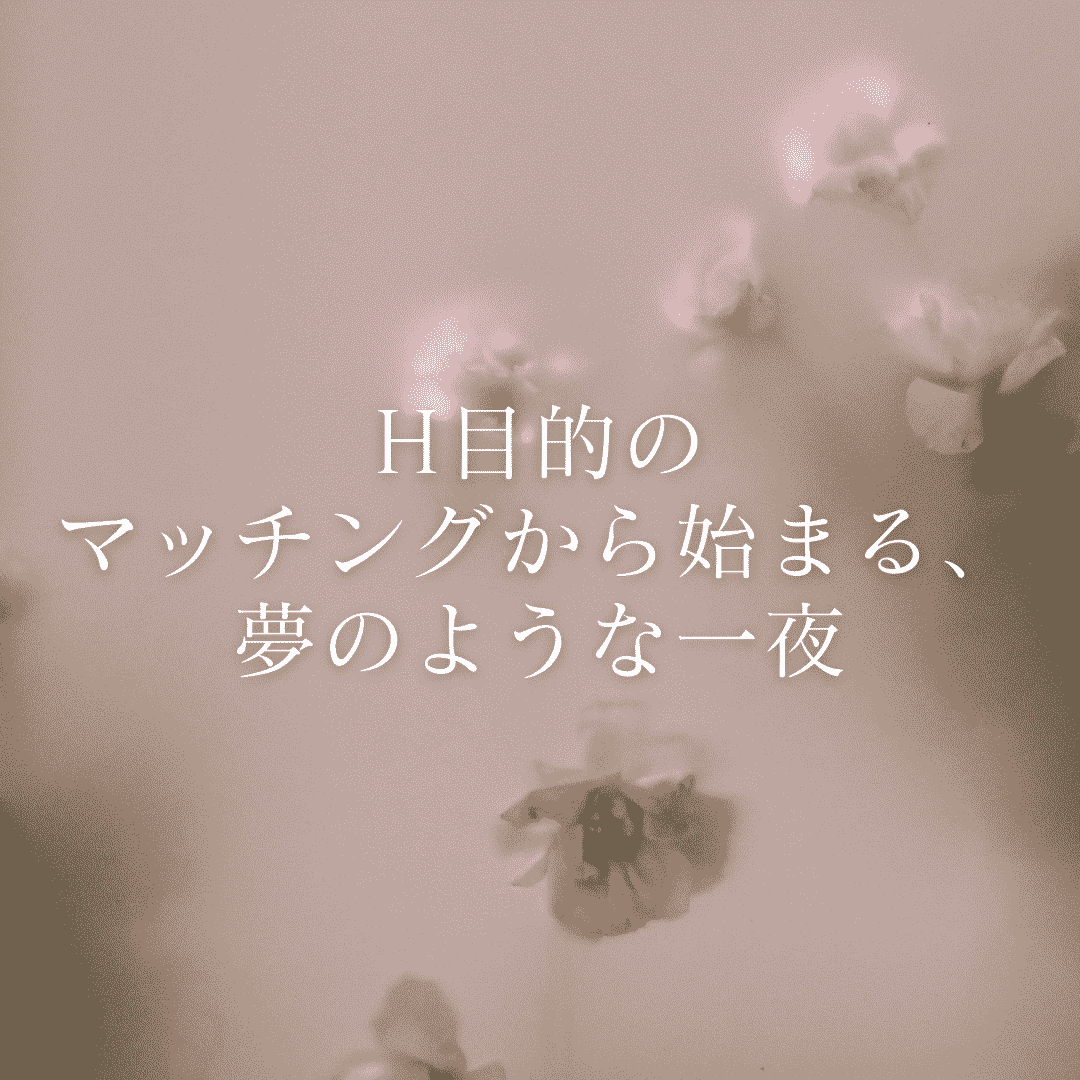

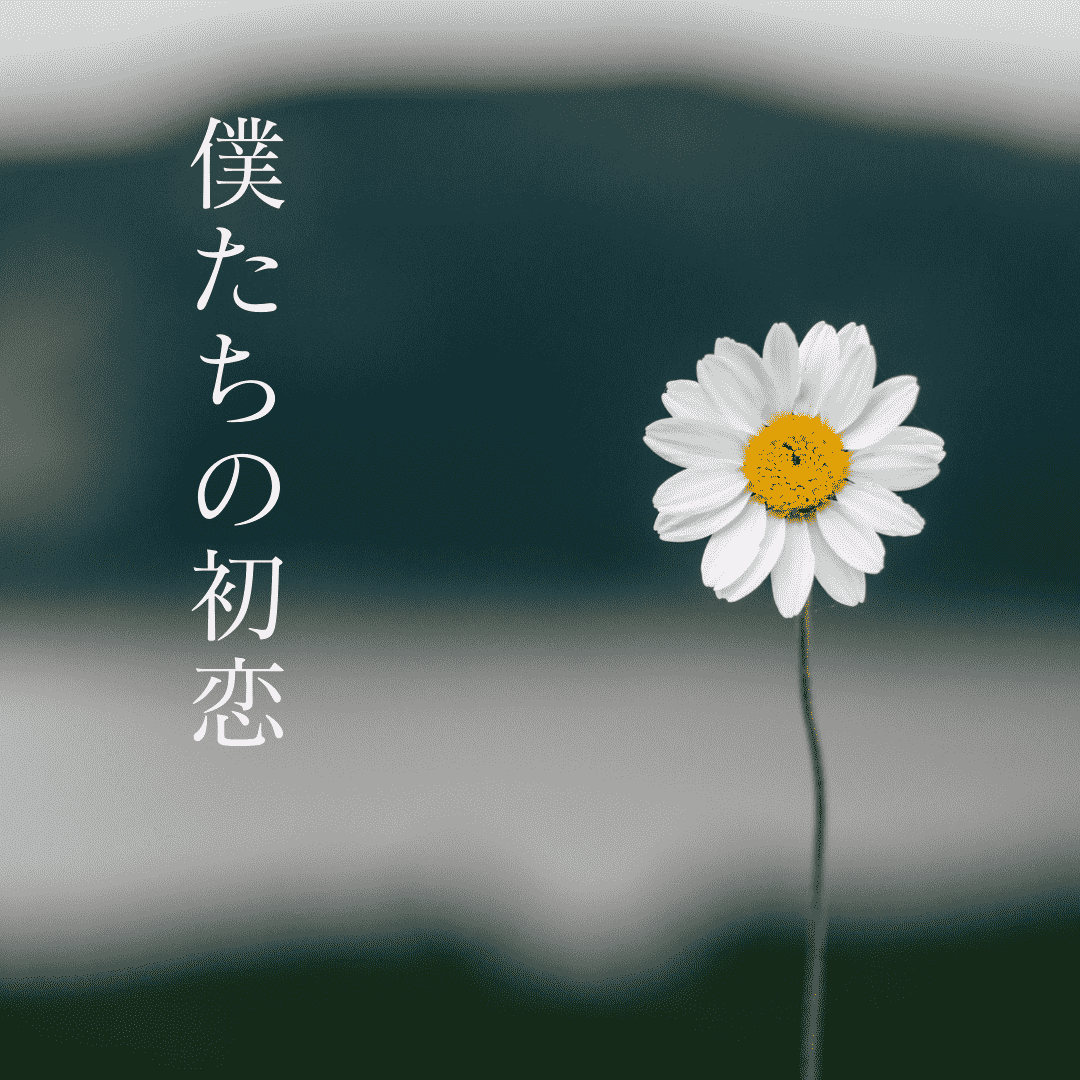


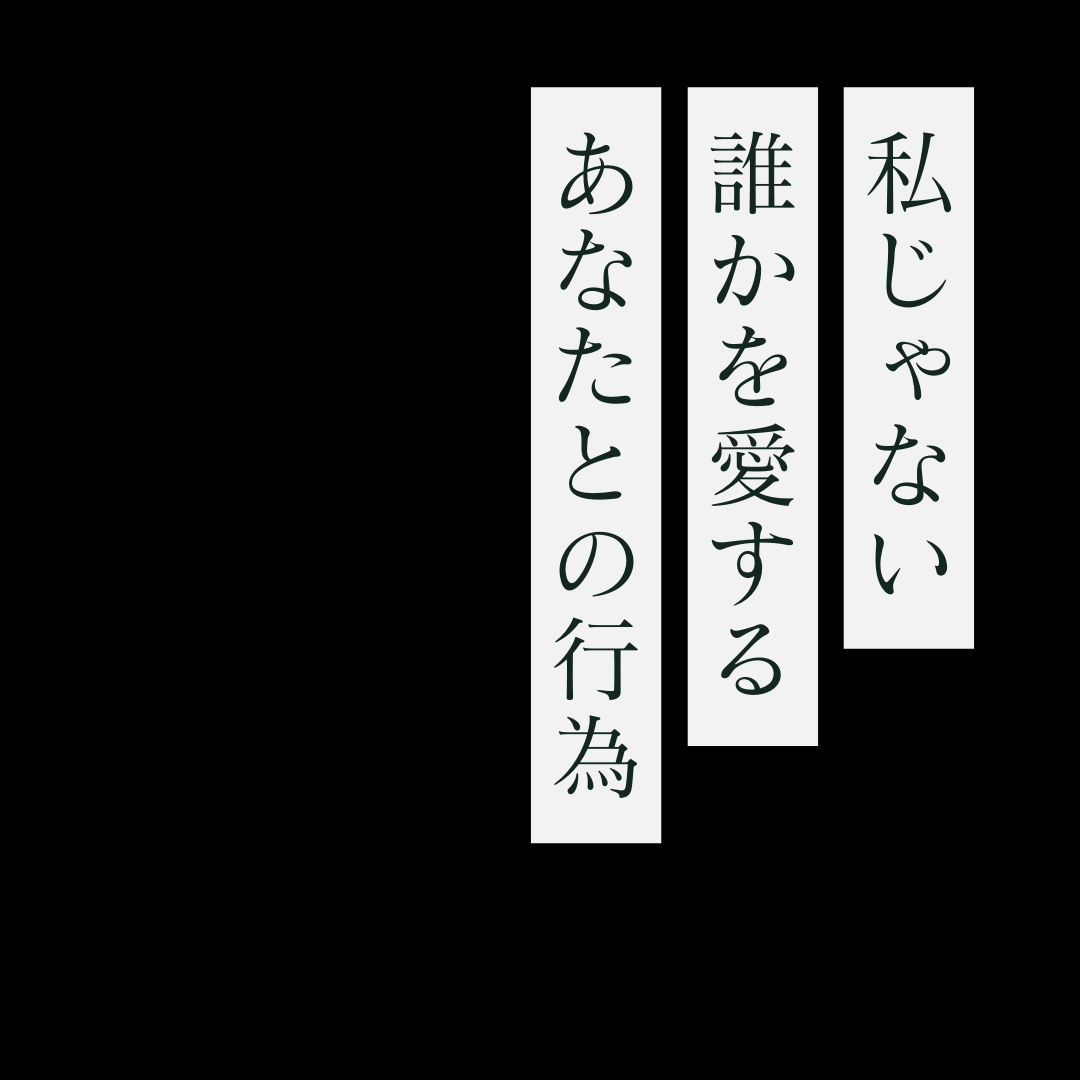

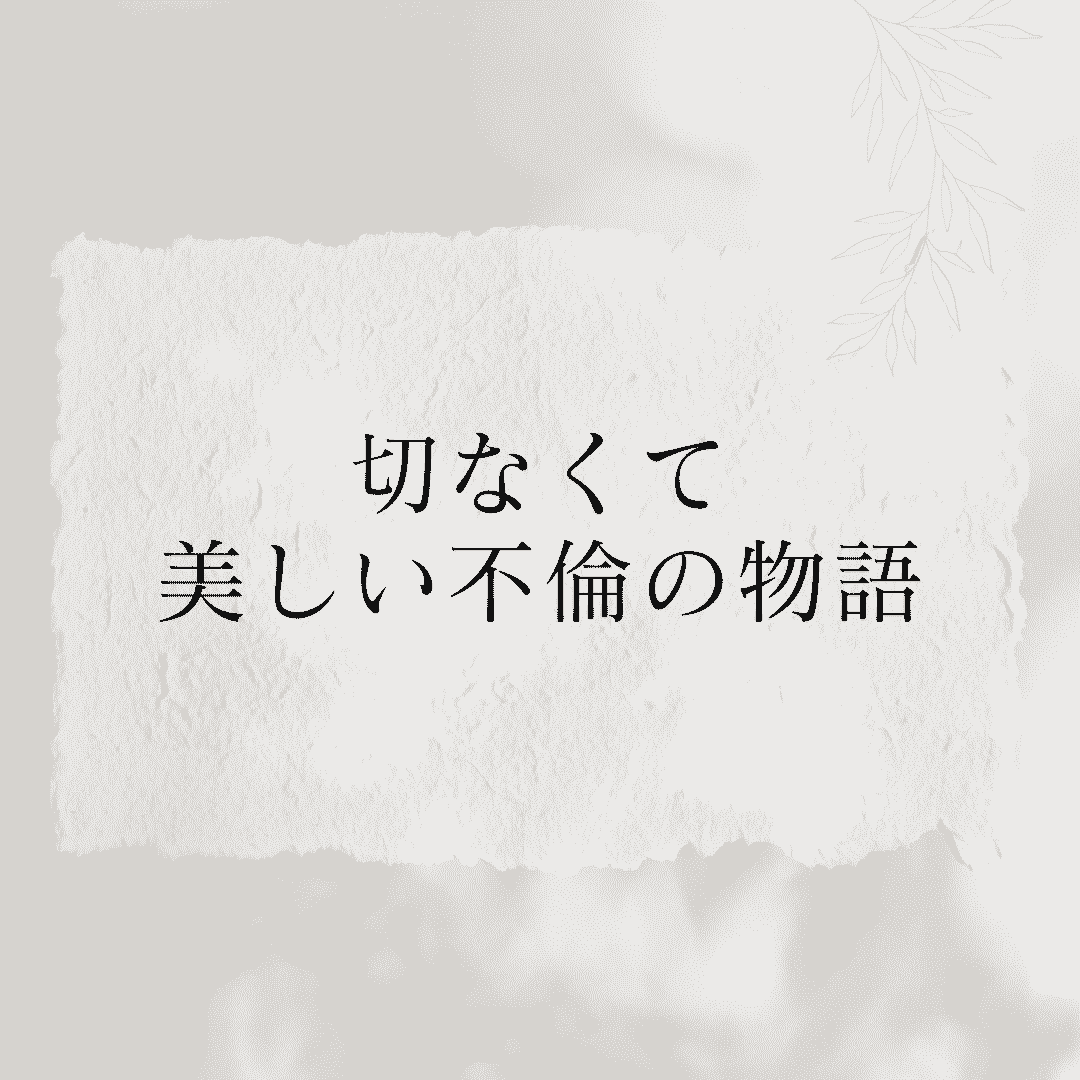
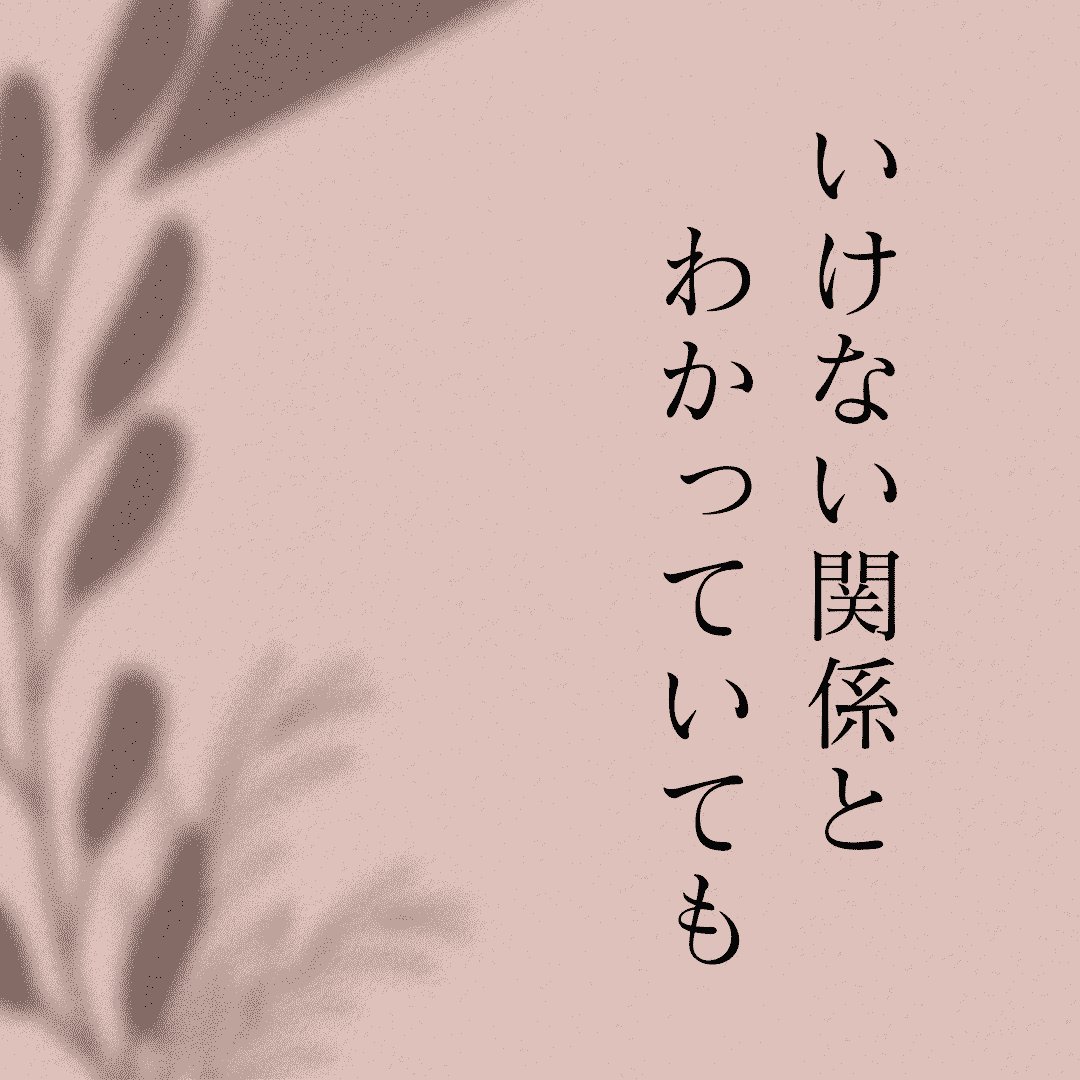








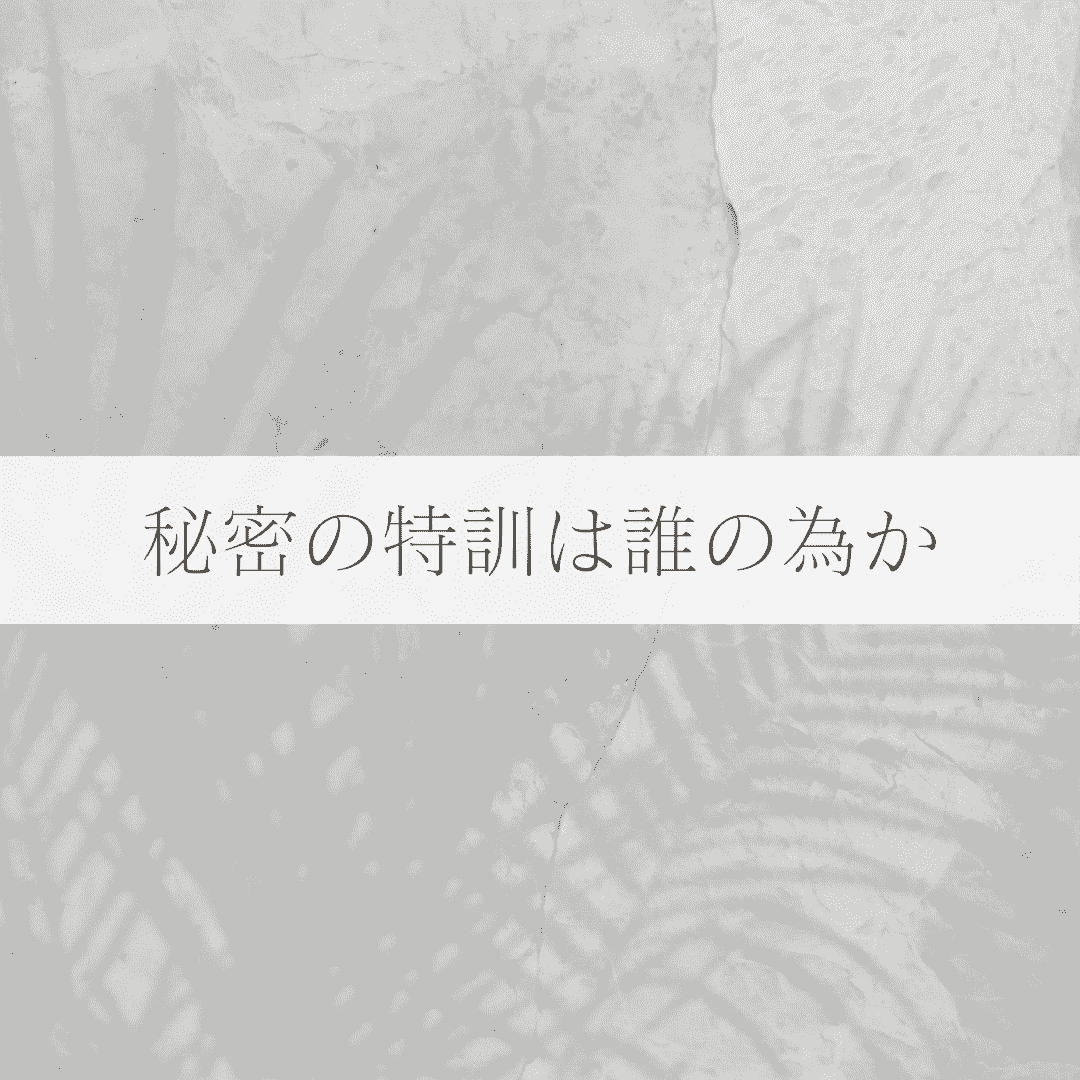
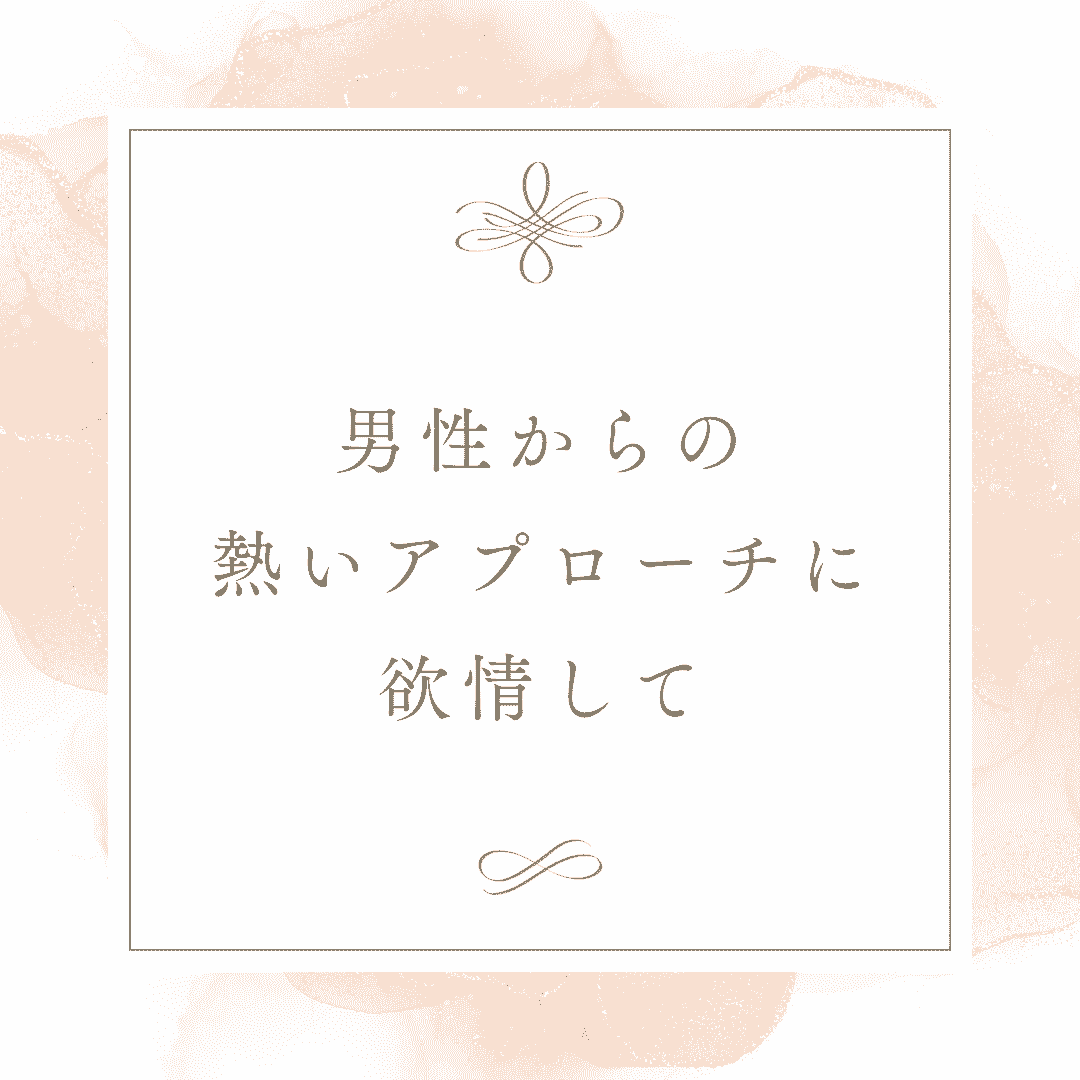


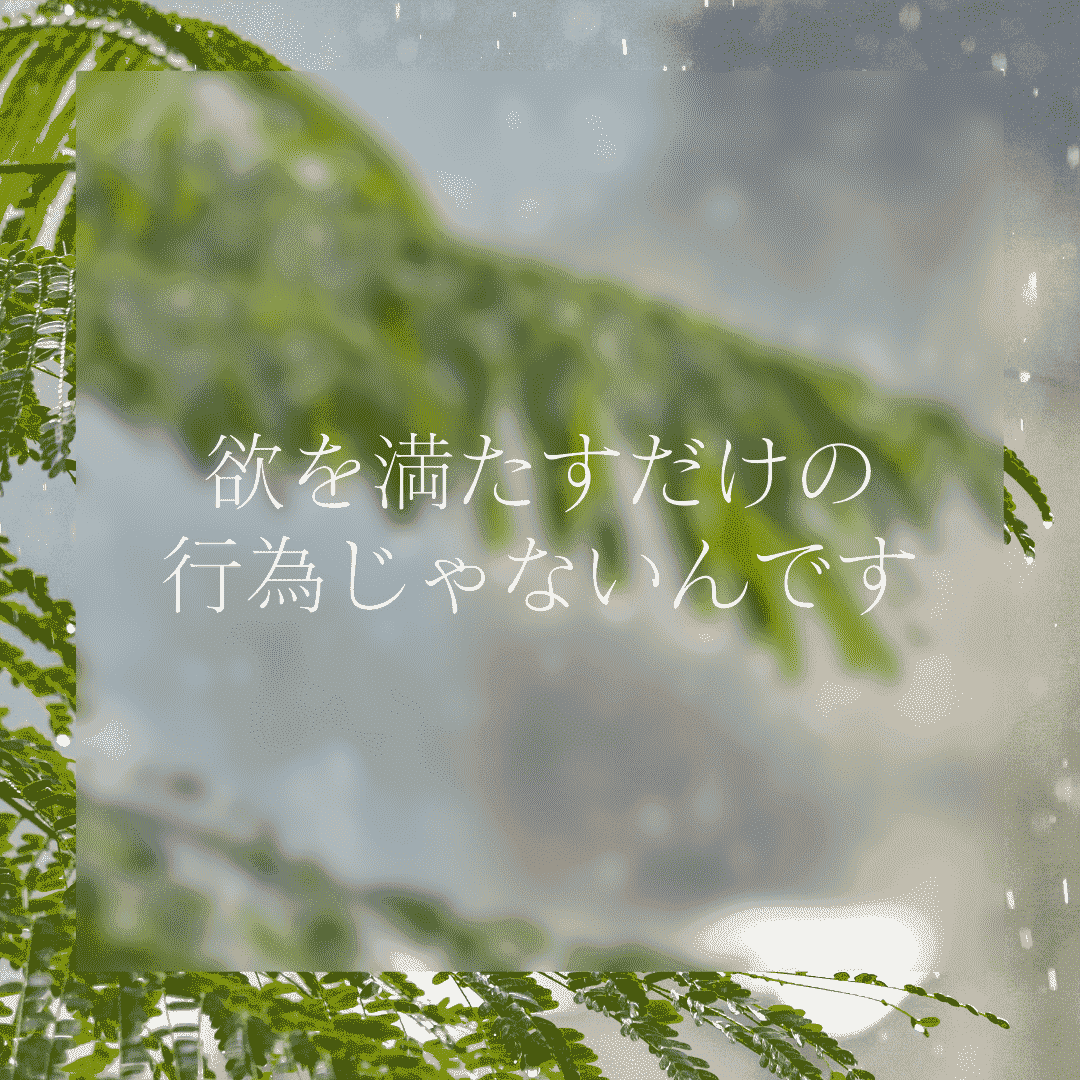

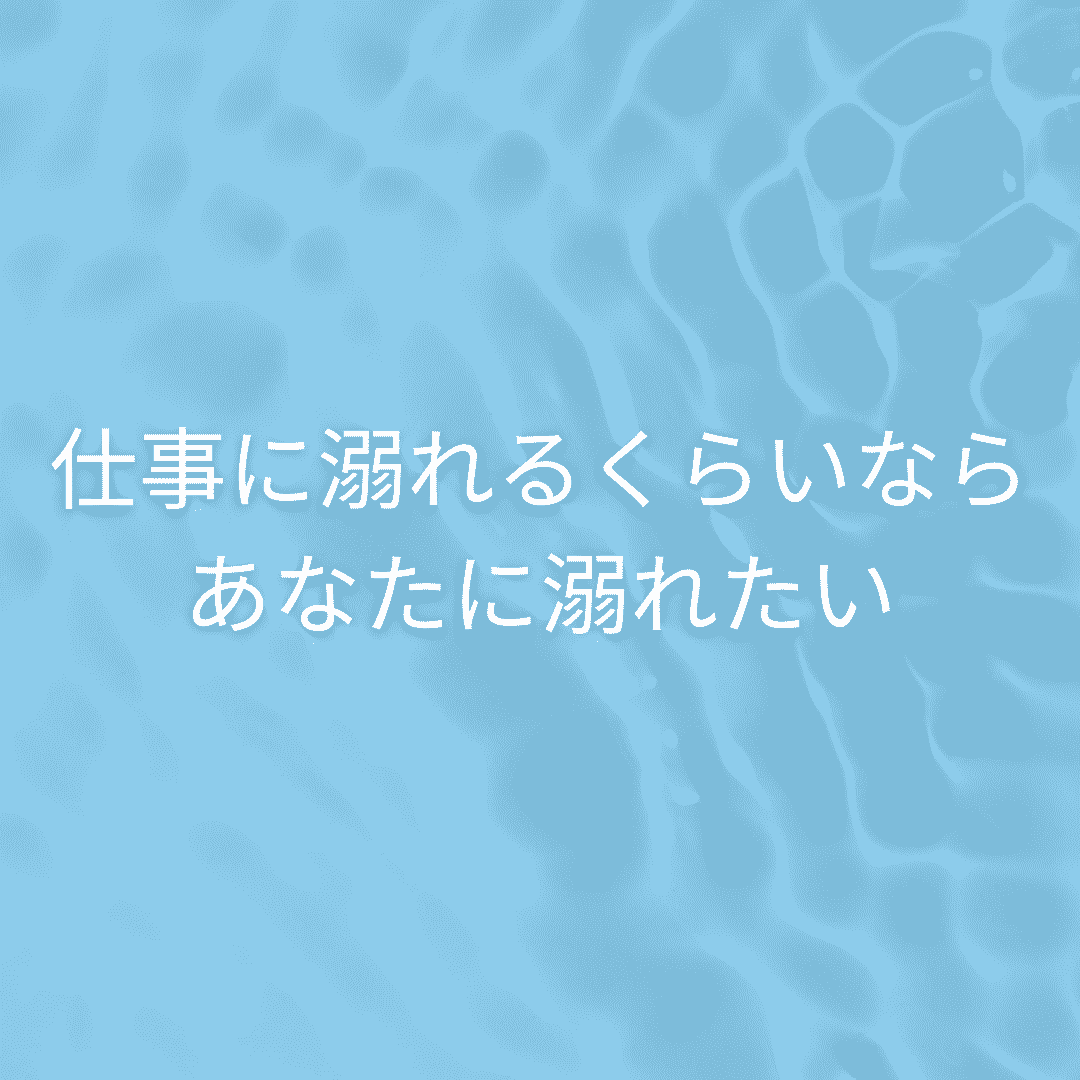




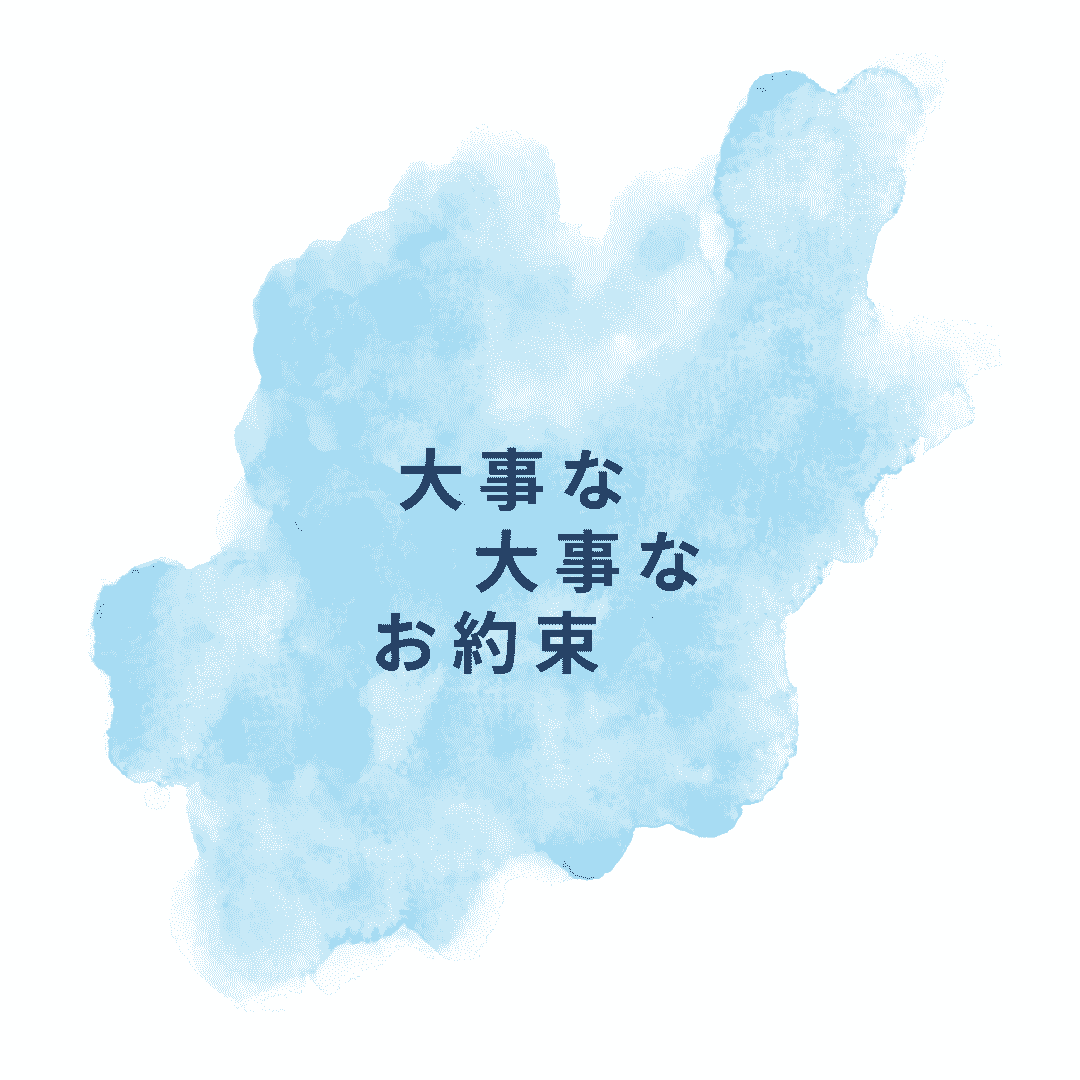

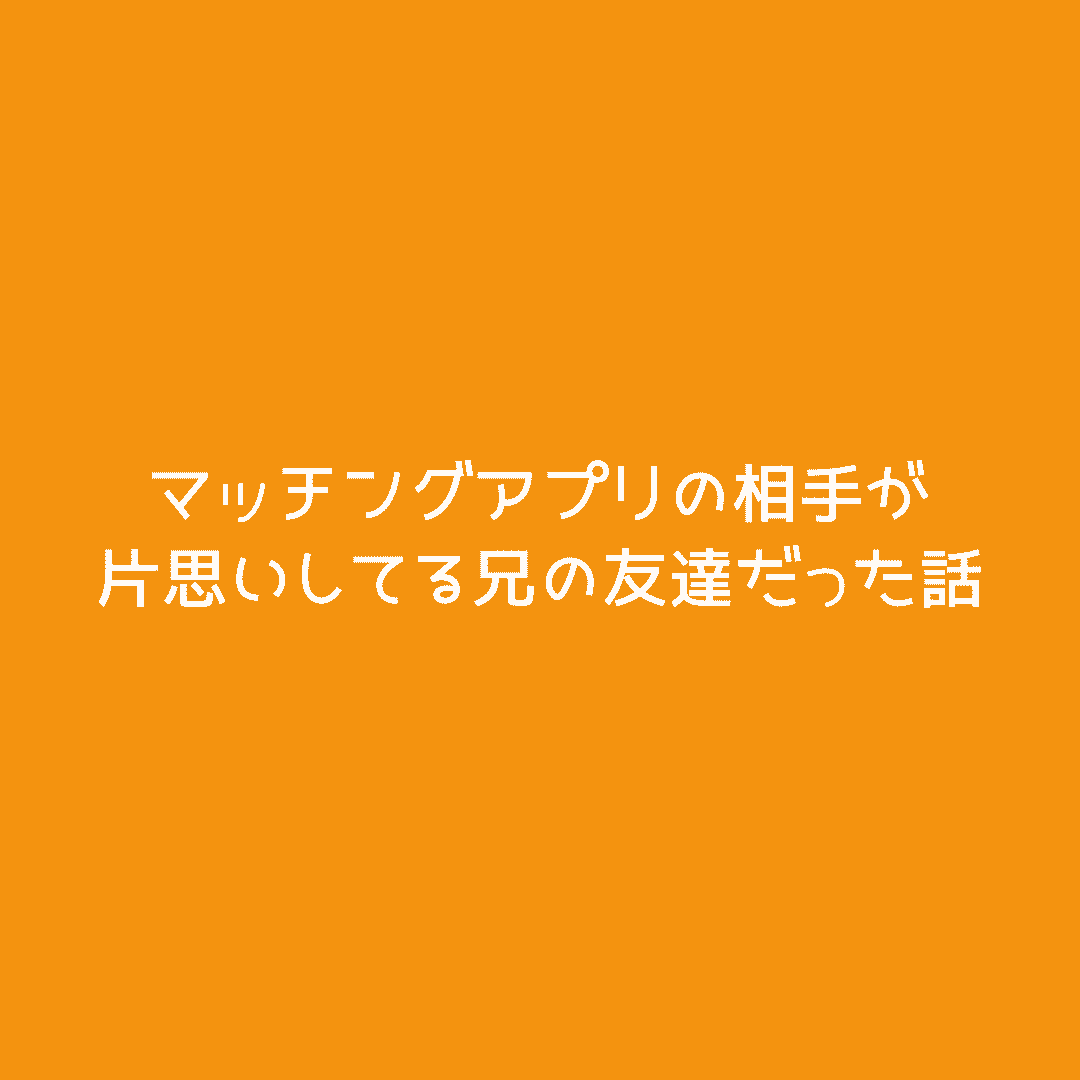
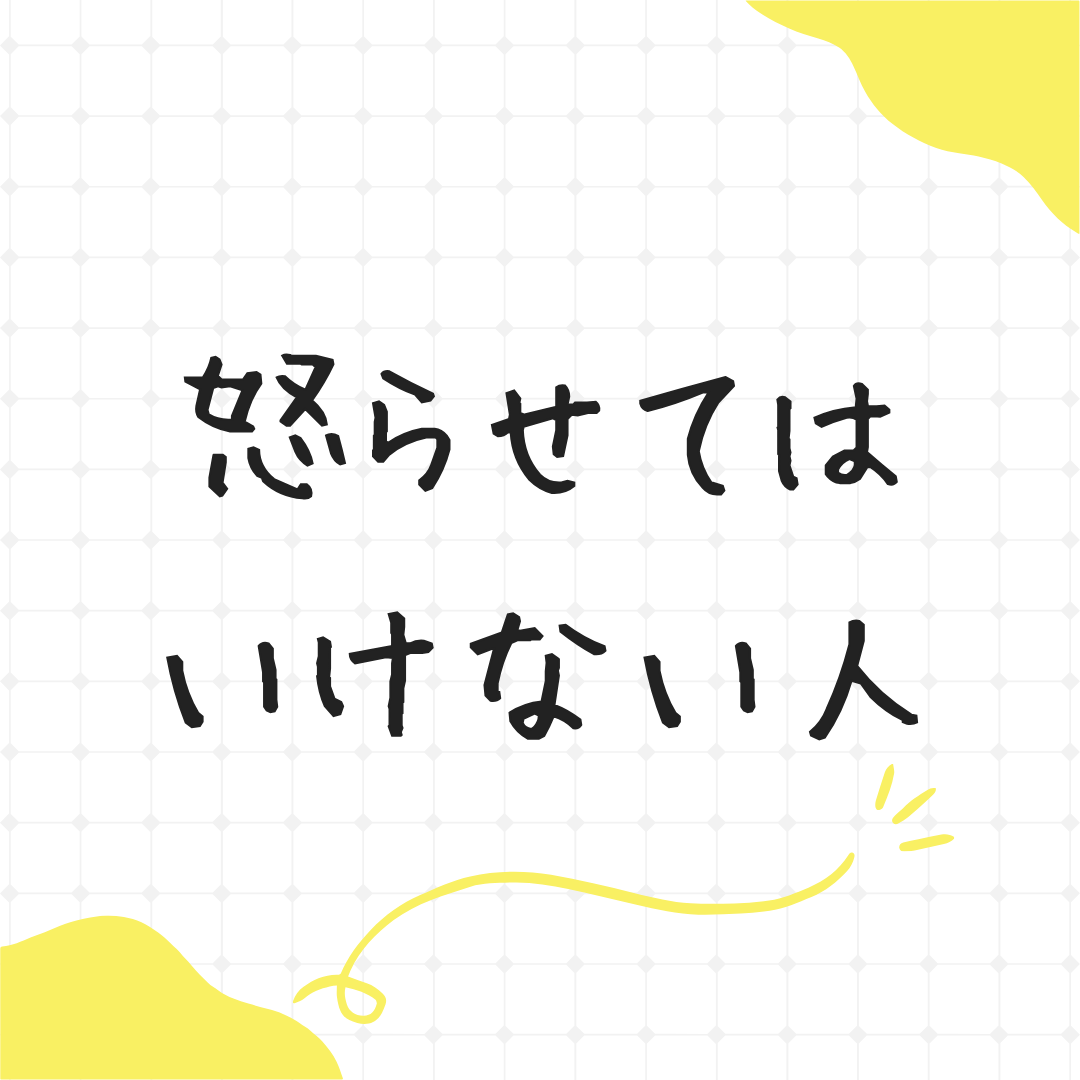

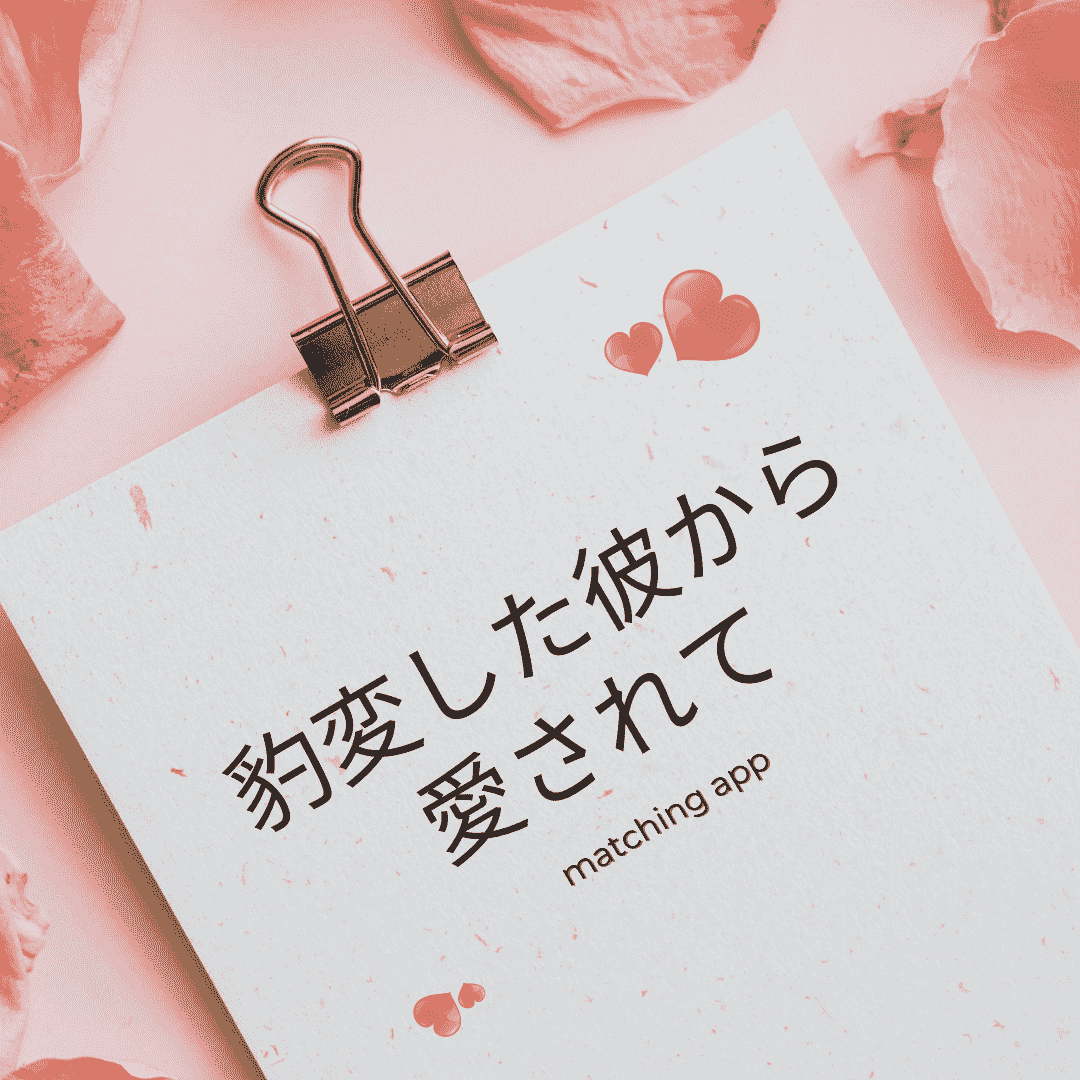


コメント