
0
フザケてキスすると逆にアイツから舌を入れてきた
「コウ、なんか頼んでもいい?お腹すいた」
「いいよ、頼めよ」
高校生の遊び場の代表ともいえるカラオケにこもってそろそろ5時間。
電子目次付タブレットを手にして渡すと、レンはぽちぽちと画面を押してフードメニューを見始めた。
さすがに5時間は長かったのか、他にもいた数名の友人たちは他の約束や用事があると俺とレンを残して帰ってしまった。
流行りの曲もだいぶ歌い終えてしまったし、仕方がないのかもしれない。
まあその分、レンとゆっくり話せるからいいか。
そんなことを考えているうちに小腹を満たすために頼んだポッキーやらポテチやらが盛られた皿が届いたので、もそもそとそれらを頬張りながらレンの声に耳を傾ける。
「ふーん、向こうからだったんだ」
「しかもいきなり言われたからさあ、まだ気持ちの整理ついてないし」
レンは習い事で出会い数週間前から付き合い始めた相手に昨日突然振られたそうだ。
理由は特になにも言われず、ただ『ごめん、別れよ』と言われただけでずっともやもやが止まらないらしい。
そこで俺も含めた何人かの友人達がそれぞれ誘い合って、急遽レンを慰める会を開催したわけだ。
さっきドリンクバーでなみなみと注いできたコーラを一口飲み、しゅわしゅわした感触を味わう。
ふとレンを見ると、細い指でポッキーを掴み口に運びしばらくもぞもぞと口を動かしてみせた。
「はぁぁ…何が悪かったのか……」
「ほんとに別れる理由とか言われなかった感じ?」
つぶやくレンに声をかけつつ、憂い顔をしみじみと眺める。
唇はきゅっと尖っていて、なにも塗っていないはずなのにピンク色でぷるぷるとしている。
肌も白くて綺麗だ。
もしレンが女の子なら思わず欲しくなるような蠱惑的な表情。
かっこいいというよりも可愛い雰囲気をしているから、その女の子と趣味や性格が合わなかっただけなのかもしれない。
「あ、思い出した」
「何?」
「理由。振られた時に言われたわけじゃないんだけど、付き合いたてくらいの時に言われた言葉」
「何言われたの?」
俺もポッキーを1本手に取る。
口につけたところで、まさかレンの爆弾発言が落ちるとは。
「キスが下手、って」
思わず固まってしまい、力が入って折れてしまったポッキーが机の下に落ちていく。
まずい、後で拾わないと。
「まじか」
「さらっと言われたからあんまり気にしてないと思ってたんだけど、やっぱりそれが原因だったのかも……」
寂しそうな声を出しながら顔を覆ってしまったレン。
キスが下手、って直接的すぎるだろ。
カップルって、そういうのを一緒に練習していくもんじゃないのか?まあ俺は真剣に誰かと付き合ったことないからわかんないけど。
そんなことを思いながら、ふと疑問に思ったことをレンに投げかけてみる。
「そんなにかあ」
「なに?」
「どんだけ下手だったんだろうなーって気になってきてさ」
「自分では全然、そんなことないって思ってたけど……でもそう言われたのは事実だし」
「…ちょっと試してみていい?」
語尾に笑がつきそうなくらい軽いテンションでその言葉を口にし、強引に近づく。
腕を掴んだが抵抗はされなかった。
そのままレンのほうへ顔を近づけてもその場にじっとしている。
ちょっとからかおうと思っただけなのに、こんなに大人しくされたらやっちまうぞ、マジで…。
レンの顔へさらに近づき、柔らかそうな唇にそっと俺の唇を押し当てる。
想像よりもずっとふにふにして気持ちがいい。
さすがに悪ふざけがすぎるだろうと唇を離そうとした時、シャツの裾を弱々しく掴まれた。
「ん……っ ︎」
︎」
そこから動けずにいると、口の中ににゅるりと温かいものが入ってきた。
慌ててそれを押し出そうと舌を動かすが、温かいレンの舌は俺の舌を追いかけるように絡んでくる。
離れようとしてるのに、離れなきゃいけないと思うのに、うまく身体が動かない。
「ふ……んぅ」
舌を絡ませながらもレンが甘ったるい声を漏らしてくる。
唾液がだんだんぬるぬるになっていって、その感触が気持ちが良くていつしか夢中で舌と舌を絡ませてしまう。
酸素が薄くなってきて頭がぼーっとしてきた頃、ようやくどちらともなく口が離れていった。
「ごめん……キス、止まんなくなっちゃった」
そう口にしたレンの顔が火照っている。
今まで見てきた人物の中で最もかわいく見えてしまい、気づいたらその細い身体を抱きしめてしまっていた。
「レン……キス、めちゃくちゃ上手いじゃん」
「ほんと?」
一瞬にしてレンの表情が太陽のようにぱあっと明るくなる。それからテーブルの上の皿から、ポッキーを1本掴んだ。
「じゃあ、これもしよ?」
そう言ってポッキーを口に咥え、ん、と俺のことを待っている。
待て。これじゃあまるで恋人同士みたいだ。
そんな思いが一瞬頭をよぎるがすぐに打ち消し、でもいいか、と自分に言い聞かせる。
ただのお遊びだ。ただキスの相性がいいだけの友達。それだっていい。
ポッキーのチョコがついている方を歯で挟み、目を瞑ってからもぐもぐと口を動かしていく。
ポッキーが小刻みに揺れて、レンも食べ始めたことを察する。
この状況にどきどきしているからだろうか、チョコの甘ったるさとクッキーのシンプルな味が、普段ポッキーを食べているときよりも強く感じられる。
突然クッキーの硬い部分がなくなり、柔らかい感触。
唇に到達し、気が付けばまたさっきと同じように舌を絡ませていく。
甘いお菓子を介したキスは新鮮で、どんどん鼓動が速くなってしまう。
唇を離すと、ふと目線を下げたレンが小悪魔のような顔で微笑んだ。
「コウ……勃ってる」
嬉しそうな声でそう言いながら、ぎゅっと服の上から俺のちんこを掴んできた。
「ご、ごめんな……友達にこんな反応されるとか、嫌だよな」
「嫌だったら舌、いれてないよ。それに俺、ずっとコウのこと気になってたし」
「え、付き合ってた女の子は」
「言ってなかったっけ、付き合ってたの男だよ?」
「まじ?」
突然の初出し情報に混乱しているうちに、レンが俺のズボンのベルトに手をかけてきた。
「おい、ちょっと……」
「舐めてもいい?」
「……っ、好きにしていいよ」
もう何が何だかわからなくなっていた。
俺はふざけてキスをしたつもりだったのに、レンは俺のことがずっと好きだったとか、付き合ってたのが男だったとか、もううまく整理できそうにない。
ただ一つだけわかることは、この状況に俺は全く嫌悪感を抱いていない、ということだけ。
「ちんぽ、やっぱりおっきい」
いつのまにか下着ごと下され、中途半端に勃っているちんこをまじまじと見られている。
「やっぱり、って」
「コウ身長高いから、大きいだろうなあって」
「どんな理由だよ」
「これ、もっとおっきくなるんだよね……んむっ」
さっきまで俺の舌を受け入れていた口が、なんの戸惑いもなくちんこを咥えている。
初めてのフェラにびっくりしすぎて、ただ力を抜いてソファーに座っていることしかできない。
先っぽのつるつるした部分を細かく舌で刺激される。
「ん……んぐっ……」
そのまま奥まで咥え込まれ柔らかくねっとりとした舌で刺激されながら、添えられていた手で竿の部分までやんわりと刺激されてゆく。
好きだとわかったのはいいが、まだ付き合うと決まったわけでもない。
しかもここはカラオケルーム、こんなことをしていい場所ではない。
そう思って『何とかレンを止めないと』と考えているはずなのに初めて味わう快感には勝てないのか、俺のちんこは俺の意思と裏腹にむくむくとレンの口の中で大きくなってしまうばかり。
「レン……やばい、出そうっ」
だから口から離してくれ、とまで言わないうちに、レンが強く吸引し始めた。
ちんこの先端から根元まで余すことなく刺激されているところに、さっきと比べ物にならないくらい強い刺激が俺のちんこを襲う。
もう限界だ。
「やばっ、おい……っ、うっ」
何度か大きく腰が揺れ、そのままレンの口の中に吐精した。
少なくない量のそれをごくりと飲み干すレン。
その表情を呆然と見ていると、俺を見上げてレンが問いかけてきた。
「気持ちよかった?」
「ああ……」
「今日、この後まだ時間あるよね?」
その有無を言わせない物言いに、俺は頷くことしかできなかった。
***
カラオケを出てまだ誰も帰ってきていないレンの家に向かい、お互いにシャワーを浴びて今はベッドの上。
あまりの急展開だけど、全く嫌じゃない。
ベッドに横たわるレンの脚に顔を近づけると、ボディソープの爽やかな匂いがした。
「脚ばっかり……もう、なかとろとろだからぁ」
強請るような声を無視し、つま先から順に舌を這わしていく。
びくびくと身体を震わせるのを見ながら感じている部分をゆっくりと、でも焦らすように唇と舌で堪能していく。
「ひぁっ……あしっ、そんなにすき?」
「レンのだから、かな」
手でもその滑らかな肌を堪能しながら、ぴちゃぴちゃと味わっていく。
丁寧に気持ちのいい肌を唇と指で慈しむように愛撫していき、とうとう太ももまで到達してしまった。
そのまま脚を開かせ、もうゼリーでとろとろになっていると教えてくれたソコに中指を入れていく。
「ん……ぅ……ッ」
まだ中指だけなのにとろんとした表情、これまでに何度もこういう経験があるのだろう。
それでもいい。俺とのこの行為はこれが初めてだから、そこに嫉妬心はない。
それよりも今から始まることへ期待する気持ちの方がよっぽど強い。
「ほんとにとろとろだ」
「さっき……自分でシャワーで……っ」
「ありがとう。えらかったな」
「……っ!」
何気なく発した言葉なのに、その言葉の後に中指がきゅっと締め付けられた。
顔を上げると、レンの目に涙が溜まっている。
それなりに長く一緒にいたはずなのに、レンがこんな風に泣くところを初めて見た。
「どうした?」
「そんなん……言ってもらえたこと、なかったから」
そのままずびずびと鼻を鳴らしながら泣き出してしまった。
落ち着かせようかと指を抜こうとしたが、いやいやと首を振られたのでそのままゆっくりと甘やかすように中を刺激し続けていく。
「ぁあッ、コウ……っ、好き……こんなに気持ちいいのも、優しいのも、初めてだから……っ」
ああ、生きてる中でこんな可愛らしく涙を流しながら告白される日がくるだなんて。
こんなこと言われて、断る理由なんてあるんだろうか?
喜びとかレンが可愛すぎるとか、なんかもういろんな感情が混ざりあう中、俺はレンの涙が残る目じりにキスをして言った。
「こんな俺でよければ、レン……これからもよろしくな」
「うん……ぁああッ」
人差し指も追加でゆっくりと入れていくと、泣きながらも甘い声を上げてくれた。
そのままばらばらと中を刺激していくと、たまに身体が大きく跳ねて気持ちがいいことを教えてくれる部分がわかってきた。
「ここ?」
「そこ……っ、ね、もう入れて、我慢できないから」
「っ!ゴム、つけるから」
「待って……俺がつける」
指を抜くと、レンが起き上がり近くに置いてあったゴムの封を開けてくれる。
レンが見せるとろけ切った表情や声でがちがちになった俺のちんこを愛おしそうにしながらかぶせてくれて、そのまま先端の部分に軽くキスまでしてくれた。
数分前にカラオケで出したばかりなのに、すぐこんなにがちがちになるだなんて。どれだけレンの身体に興奮してるかがよくわかる。
「入れるよ、レン」
「うん……きて」
もう一度脚を大きく開き、蕩けたレンのソコへ俺の欲望の塊を挿入していく。
気持ちいいところにあたるからかさっきよりも締まりが強くなっていて、痛いほど俺のちんこが締め付けられる。
無理に入れてレンを傷つけない様、慎重に腰を進めていくおかげで時間がかかってしまったが俺のちんこは根元まで入り切り、そのまま我慢できず強めに腰を動かしてしまった。
「ぁああッ!んぅ」
「ごめん、痛かった?」
「だいじょぶ……もっと激しくていいっ、いっぱい腰、動かしてッ」
その言葉に本格的に理性が飛んでしまい、狂ったように腰を打ち付けていく。
きゅんきゅんと中が小刻みに震えていて、俺のちんこを欲しがっているようにしか思えない。
上半身を倒してレンと身体を密着させながら、さらに深く抉る様に強めに腰を動かしていく。
「あんっあああッ、コウっ、きもち、いいッ」
「ここ?」
「そこぉッ、そこ、いいの……ッ!」
指で刺激して気持ちよさそうにしていたあたりを重点的に刺激すると、レンの声がさらに甘く高くなっていく。
エロ漫画のような展開だと頭の片隅でぼんやり思いながらも俺の腰の動きは早くなっていく。
それと同じくらいどんどん脈が速くなっていき、ちんこだけでなく全身が熱くなっていく。
「あっ、ああっん、きもちっ、すきっ、コウ、すきぃッ!」
言われた瞬間我慢ができず、思い切り腰を打ち付けたと同時にびゅくびゅくと薄いゴムの中に精をはきだしてしまった。
(あんなかわいい事言われたら…)こんなに早くイくだなんて、恥ずかしすぎる。
「ごめん、あっという間で」
ちんこを抜いて謝りながら隣に寝そべると、レンは嬉しそうにぎゅっと強い力で抱きついてきた。
「いいって。我慢できないくらい気持ちよかった?」
「うん、まあ」
「じゃあ復活したら、もう一回戦しよっか」
そう言ってレンがもぞもぞと腕の中で動き顔を近づけてきたから、愛おしくなって思わずまた唇を重ねてしまう。
おふざけから始まった恋だって、そりゃアリだよな。






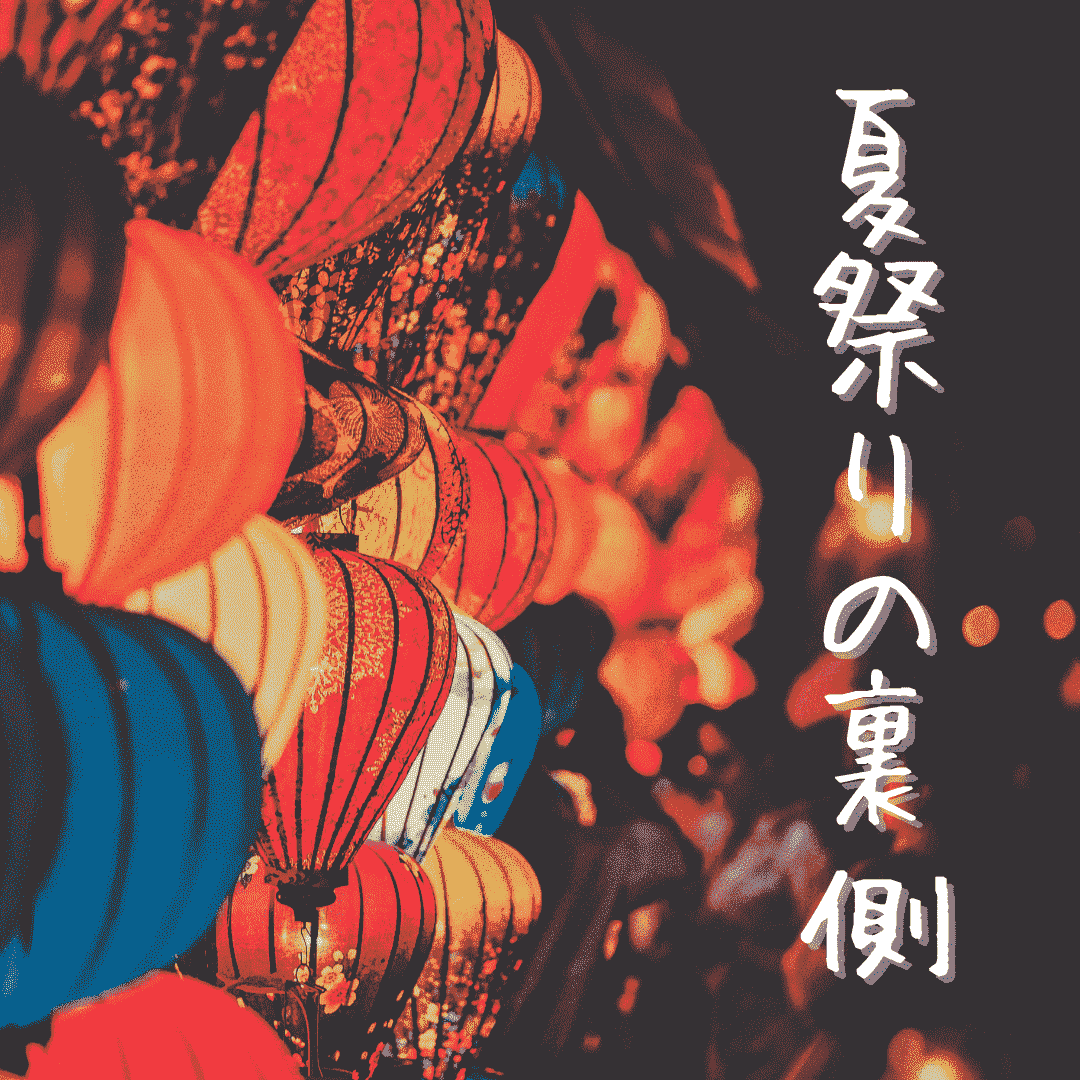

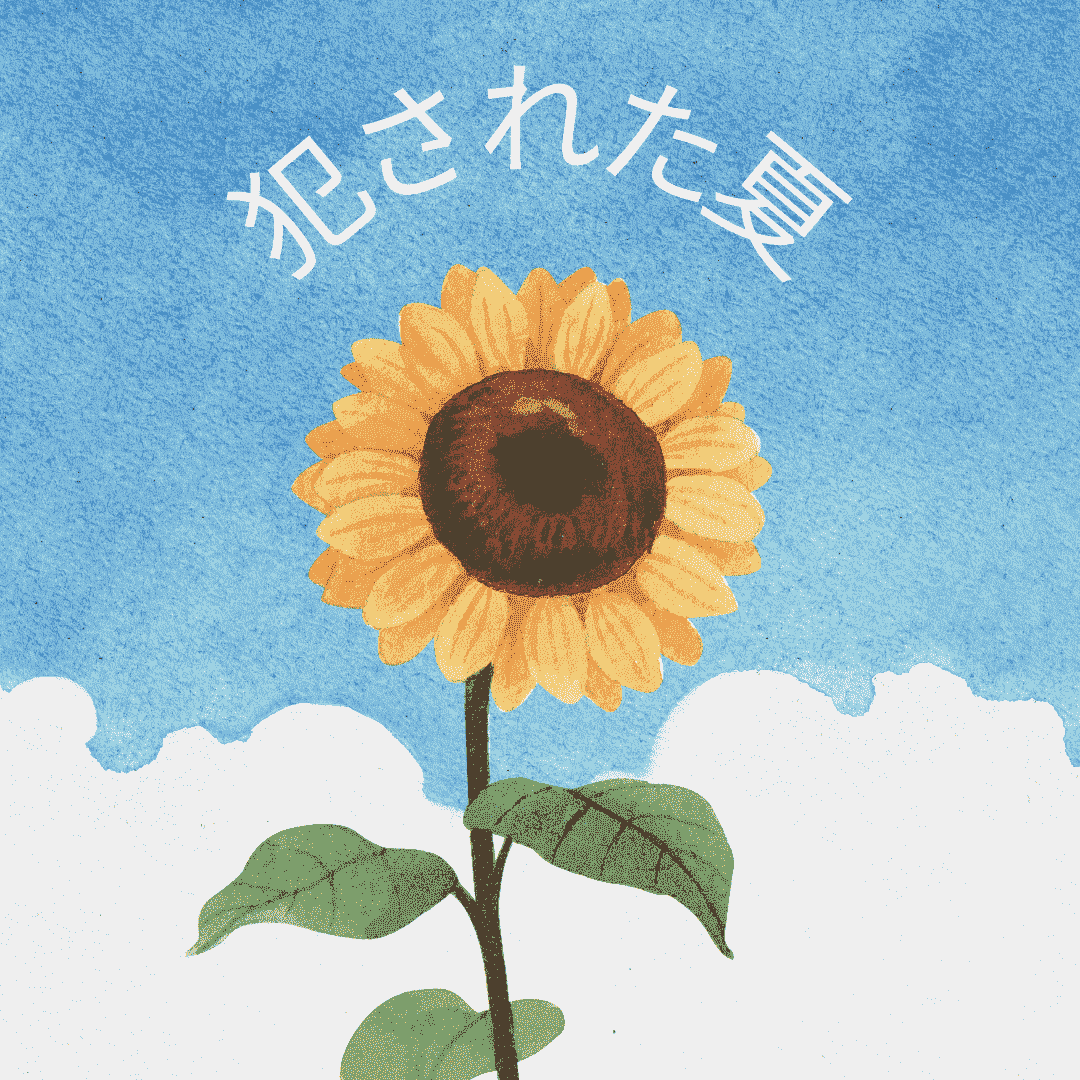


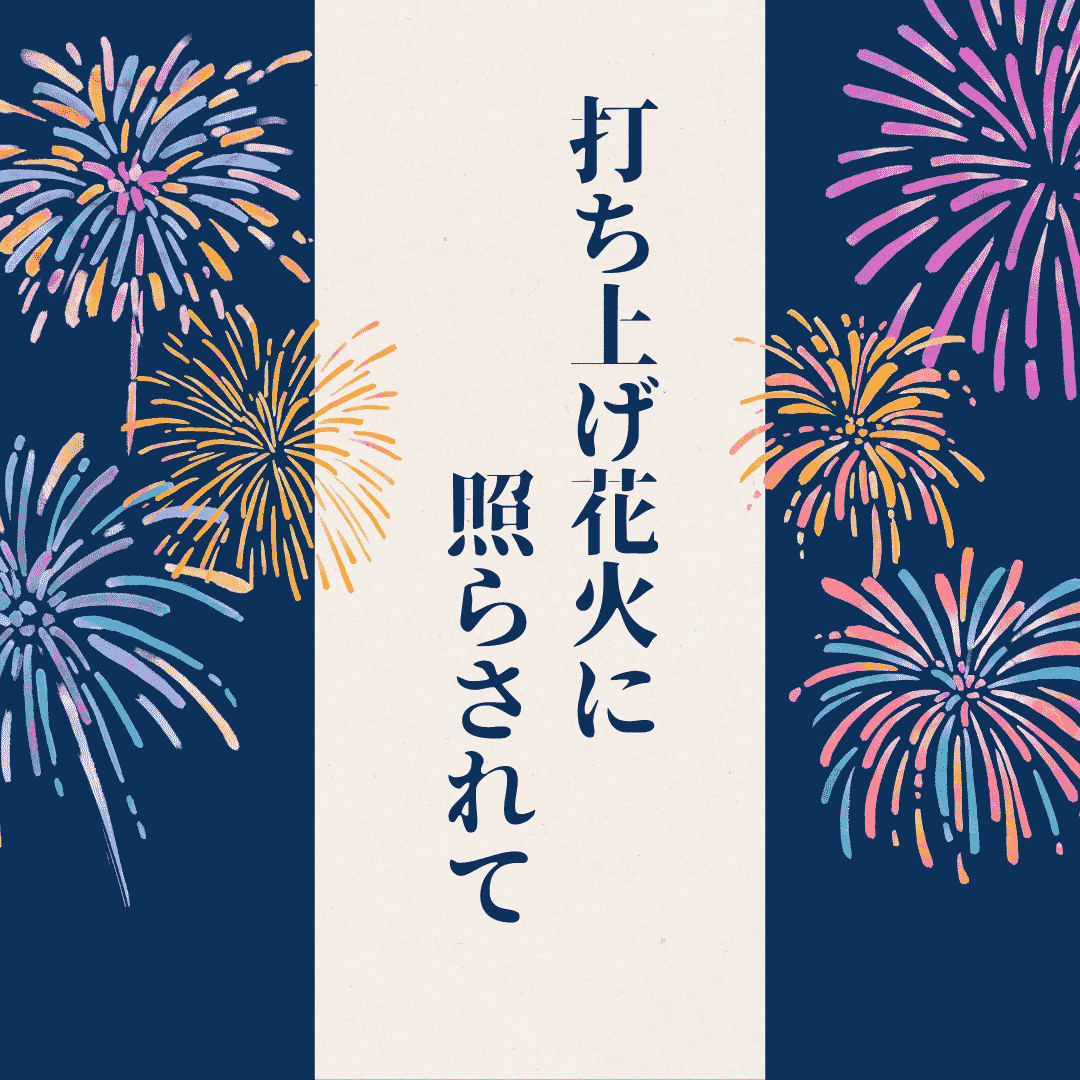

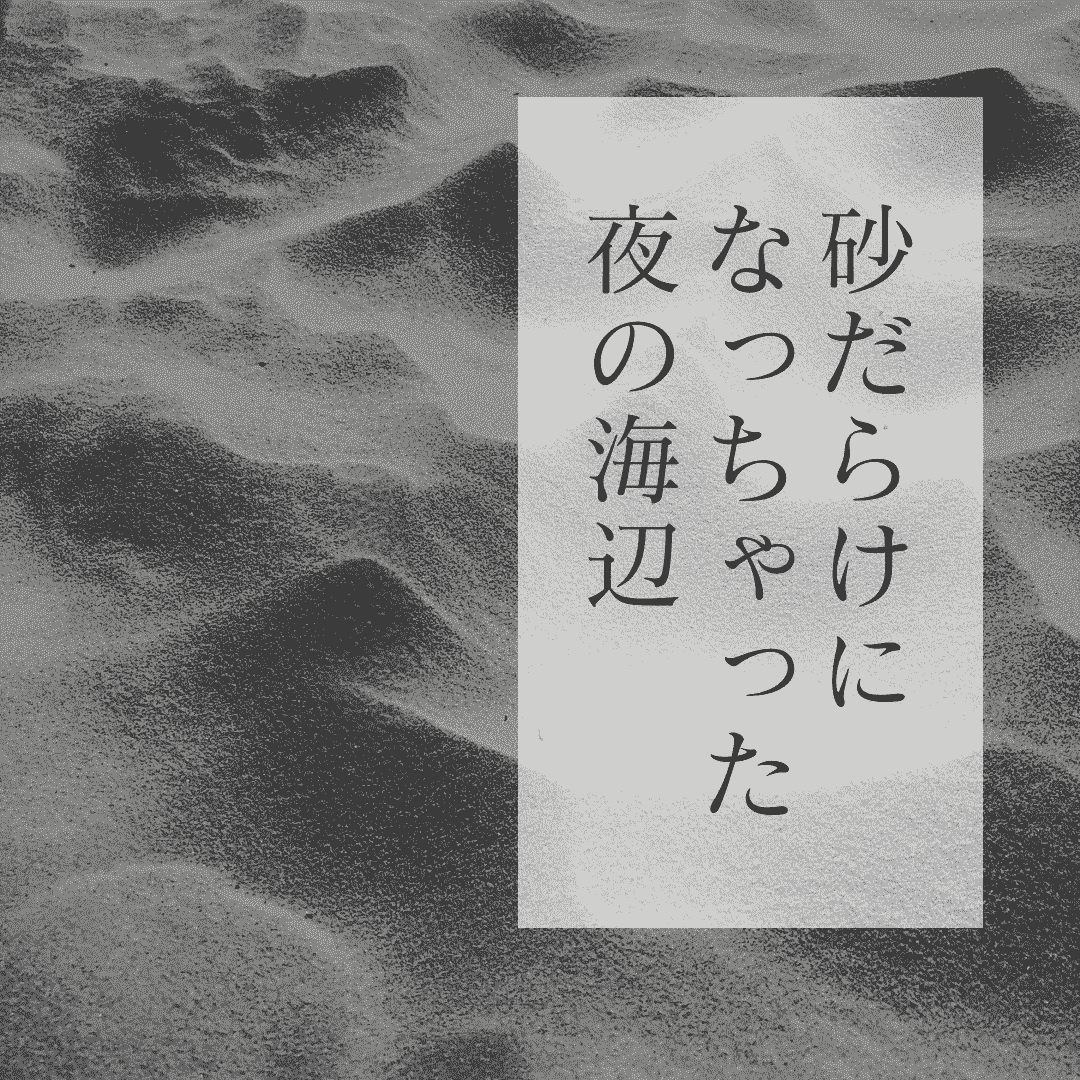

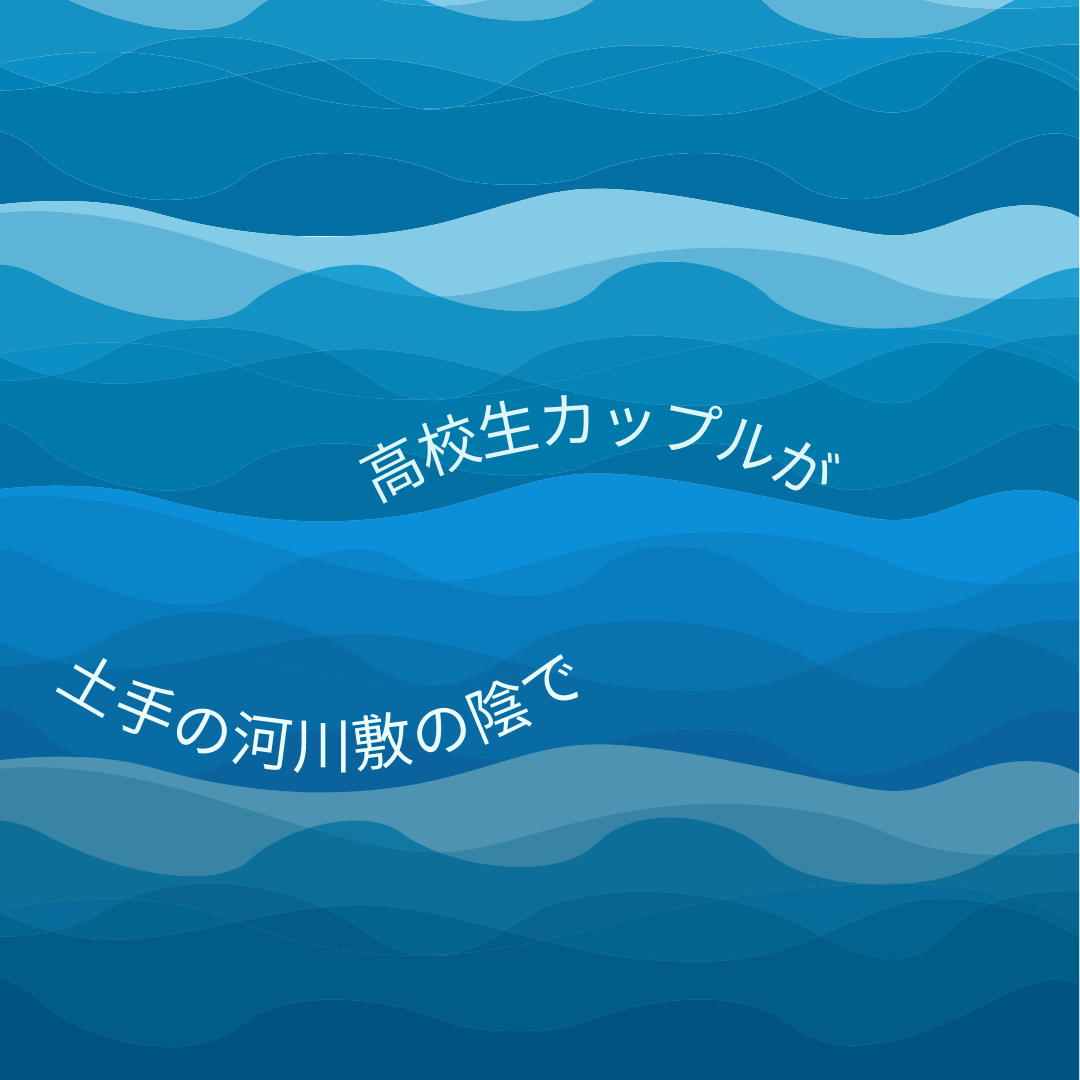


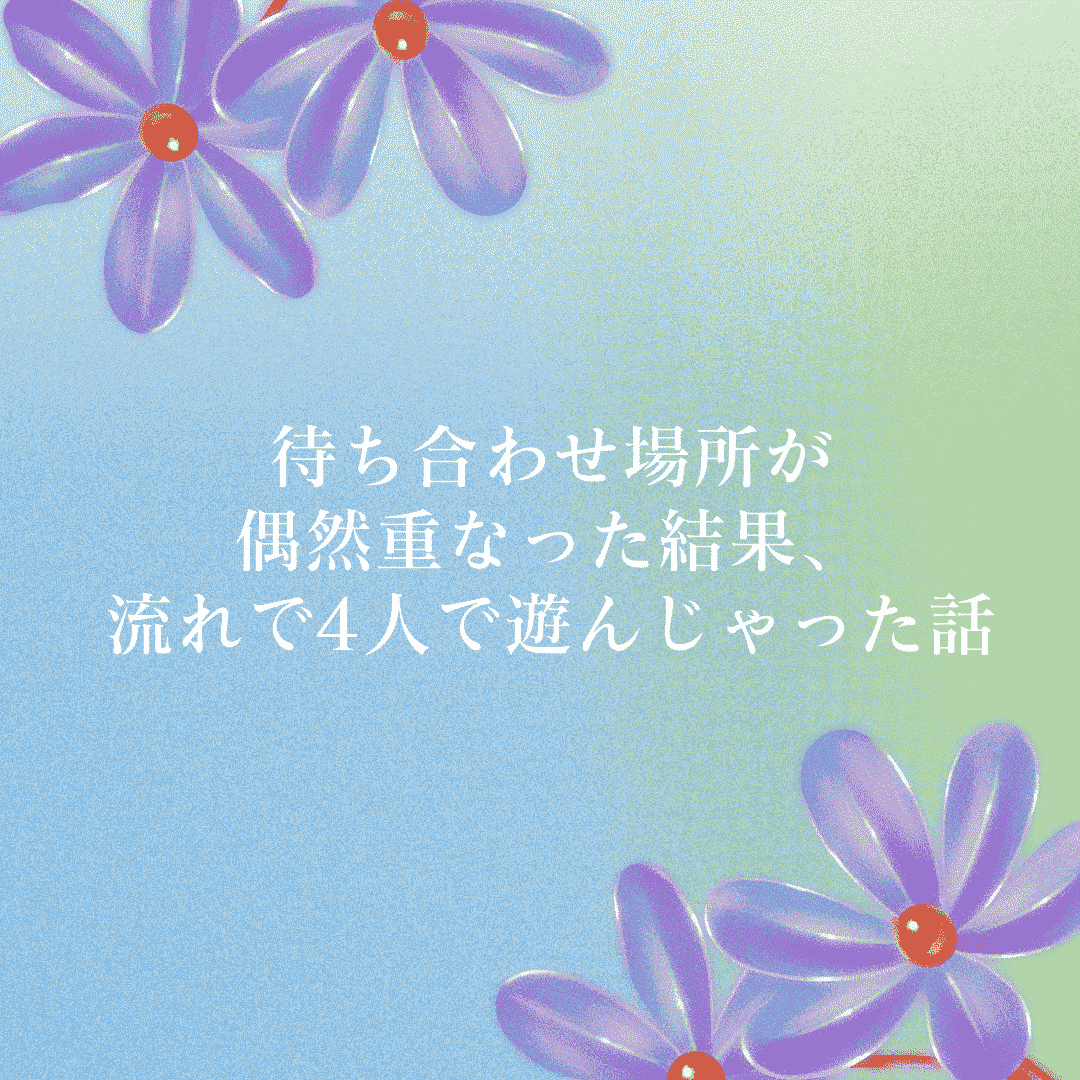




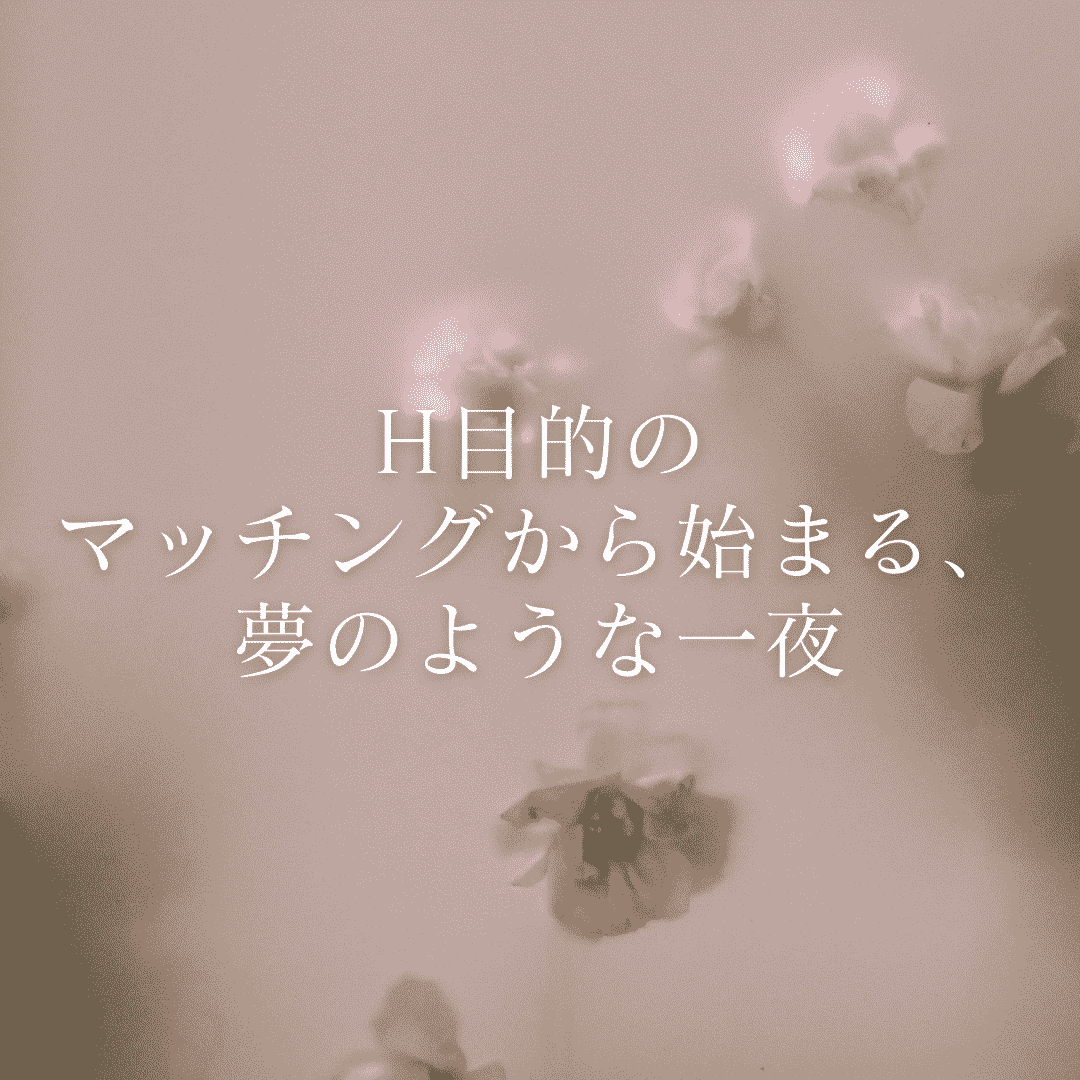

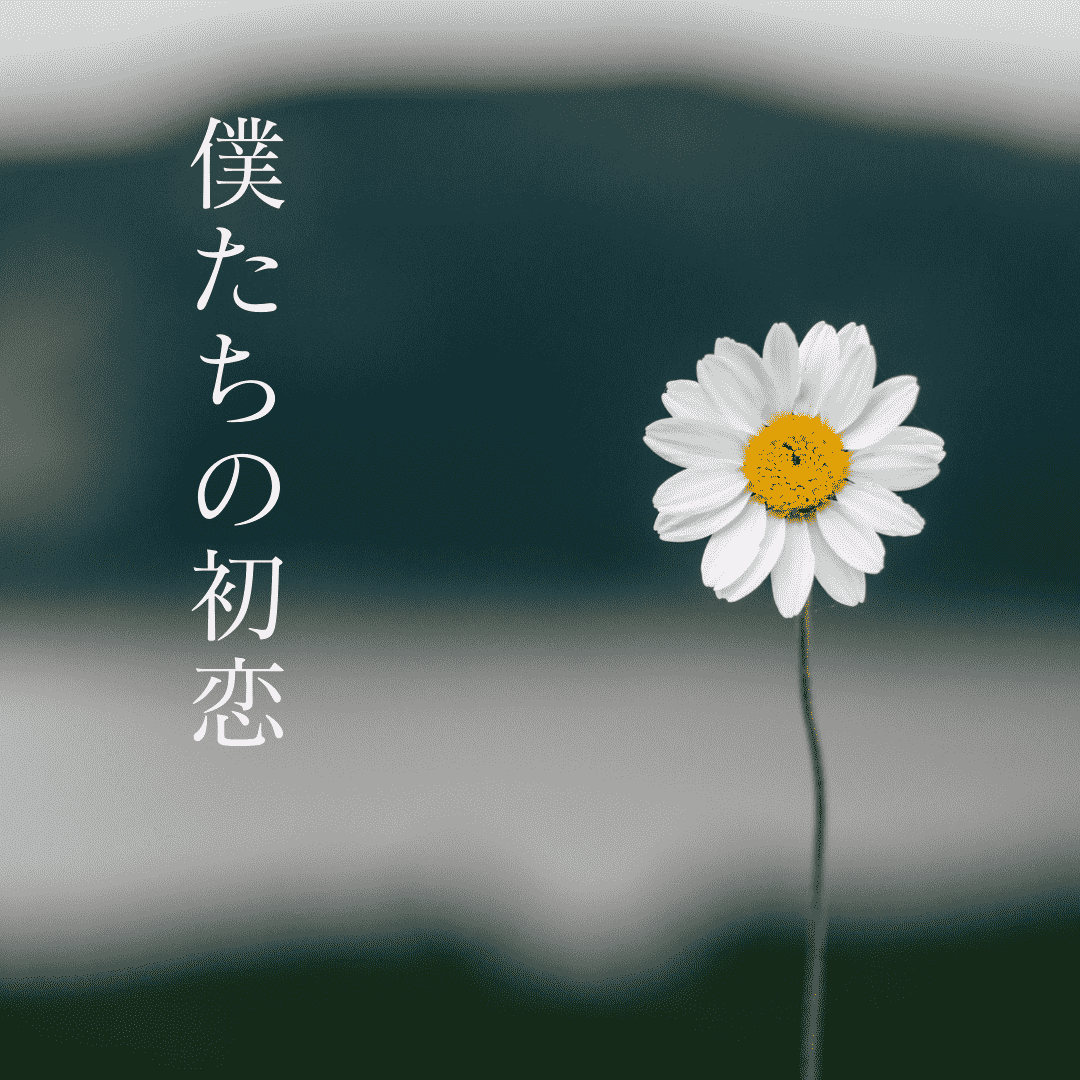


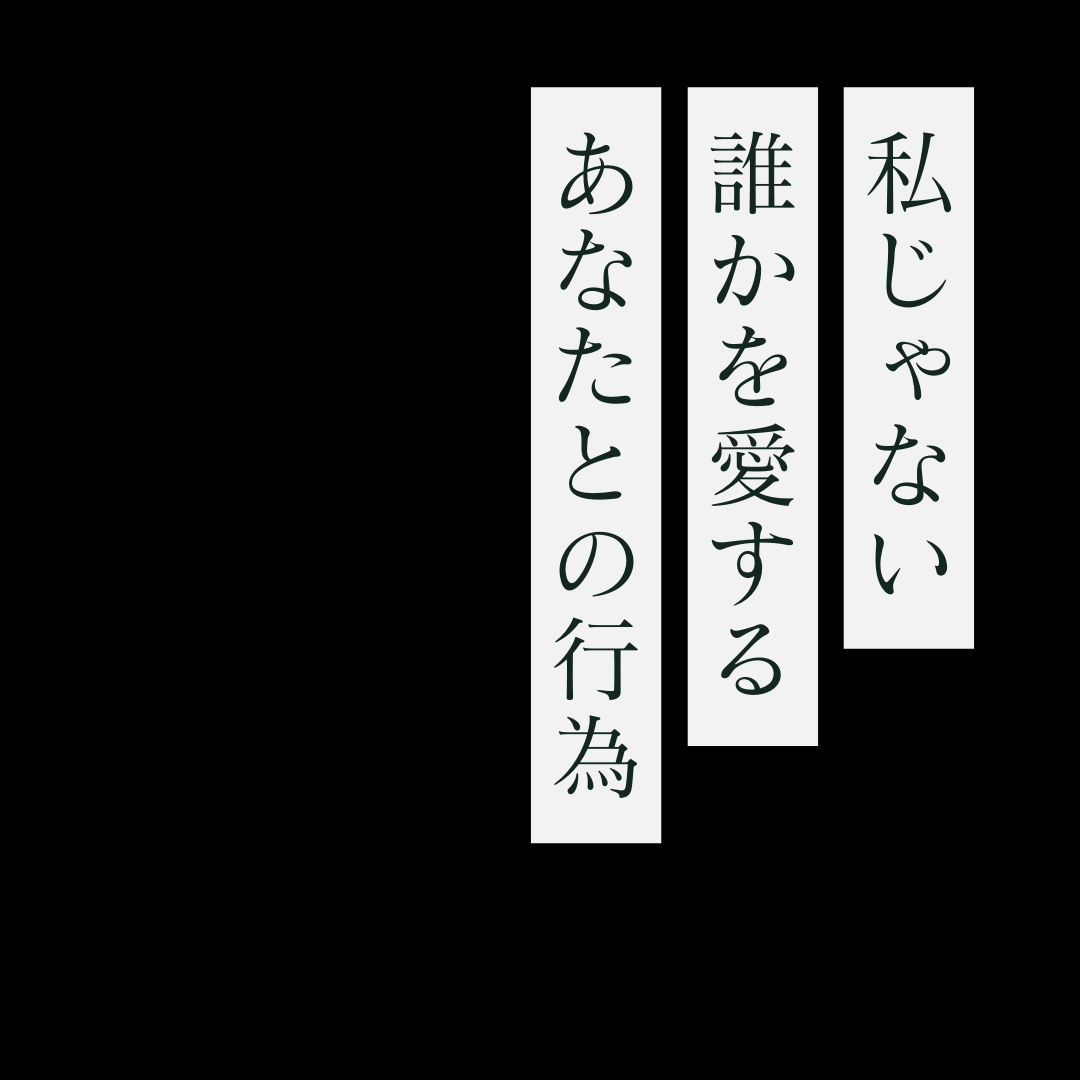

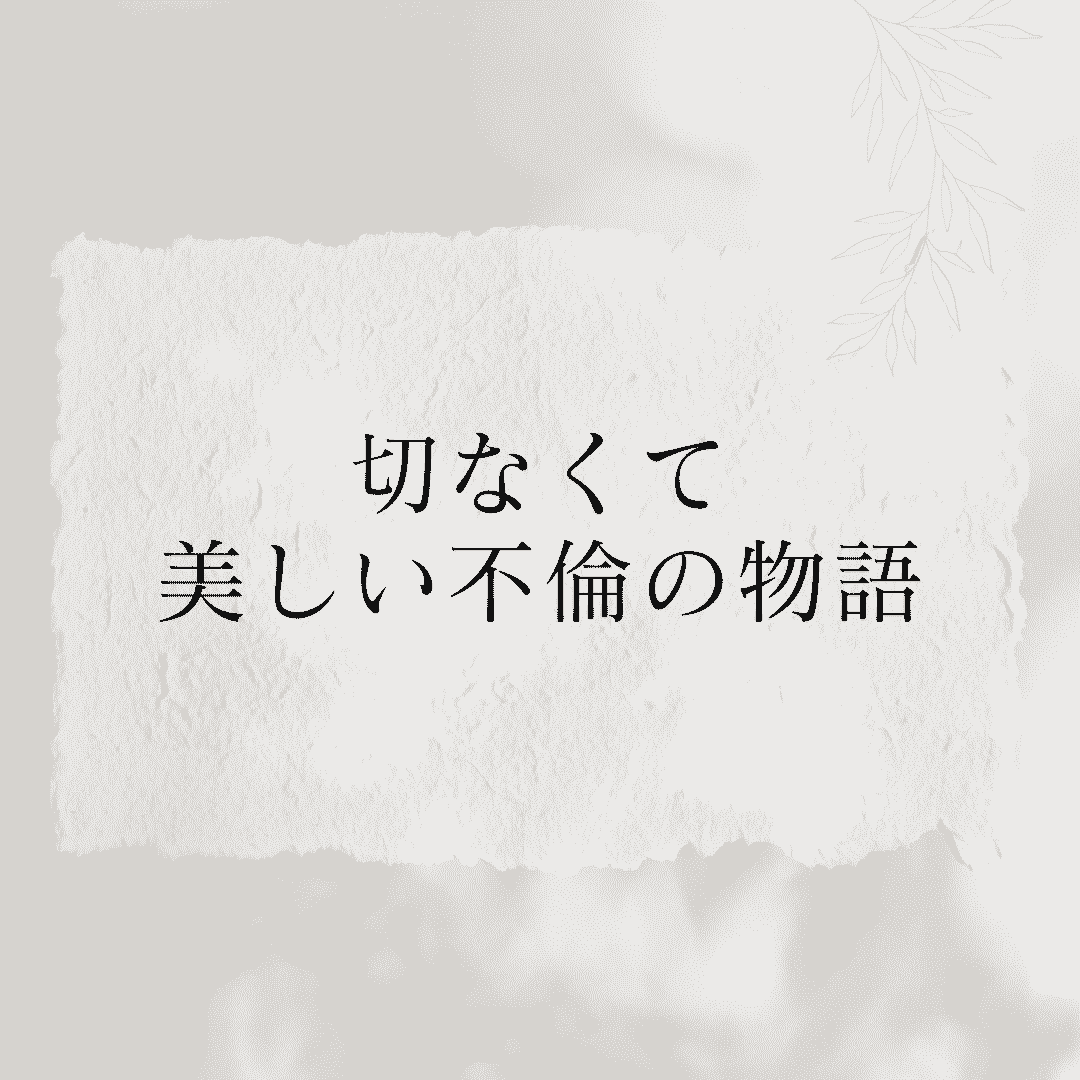
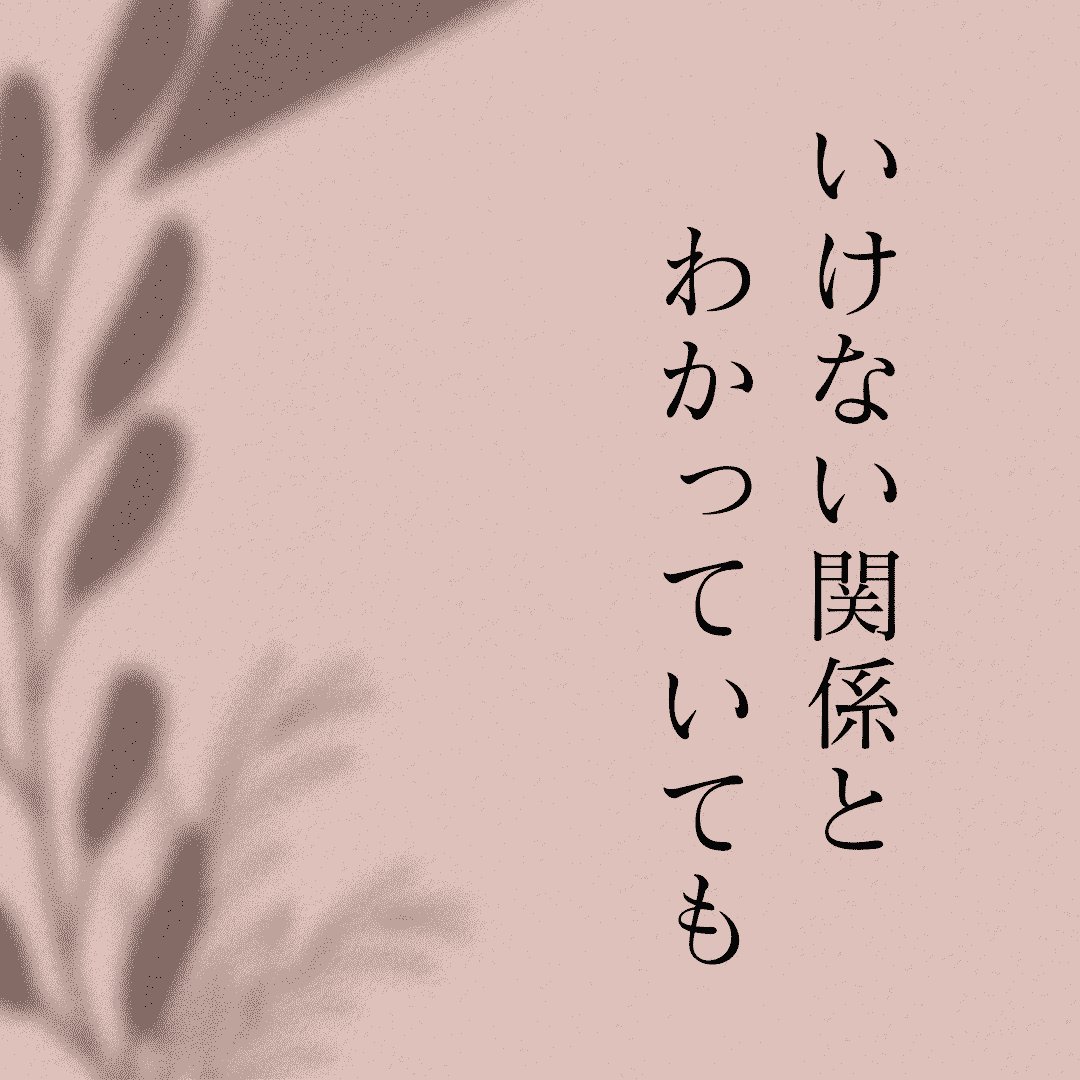








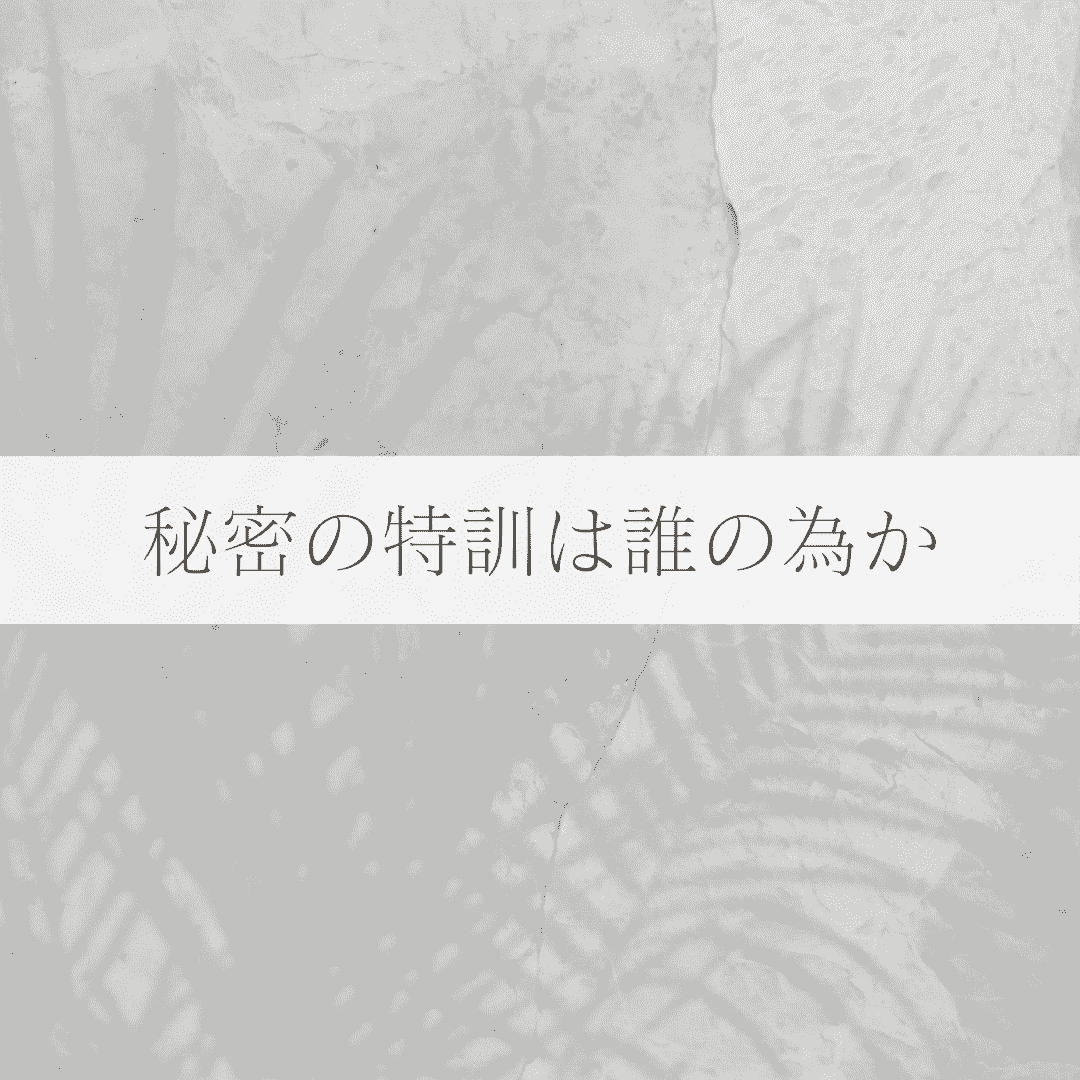
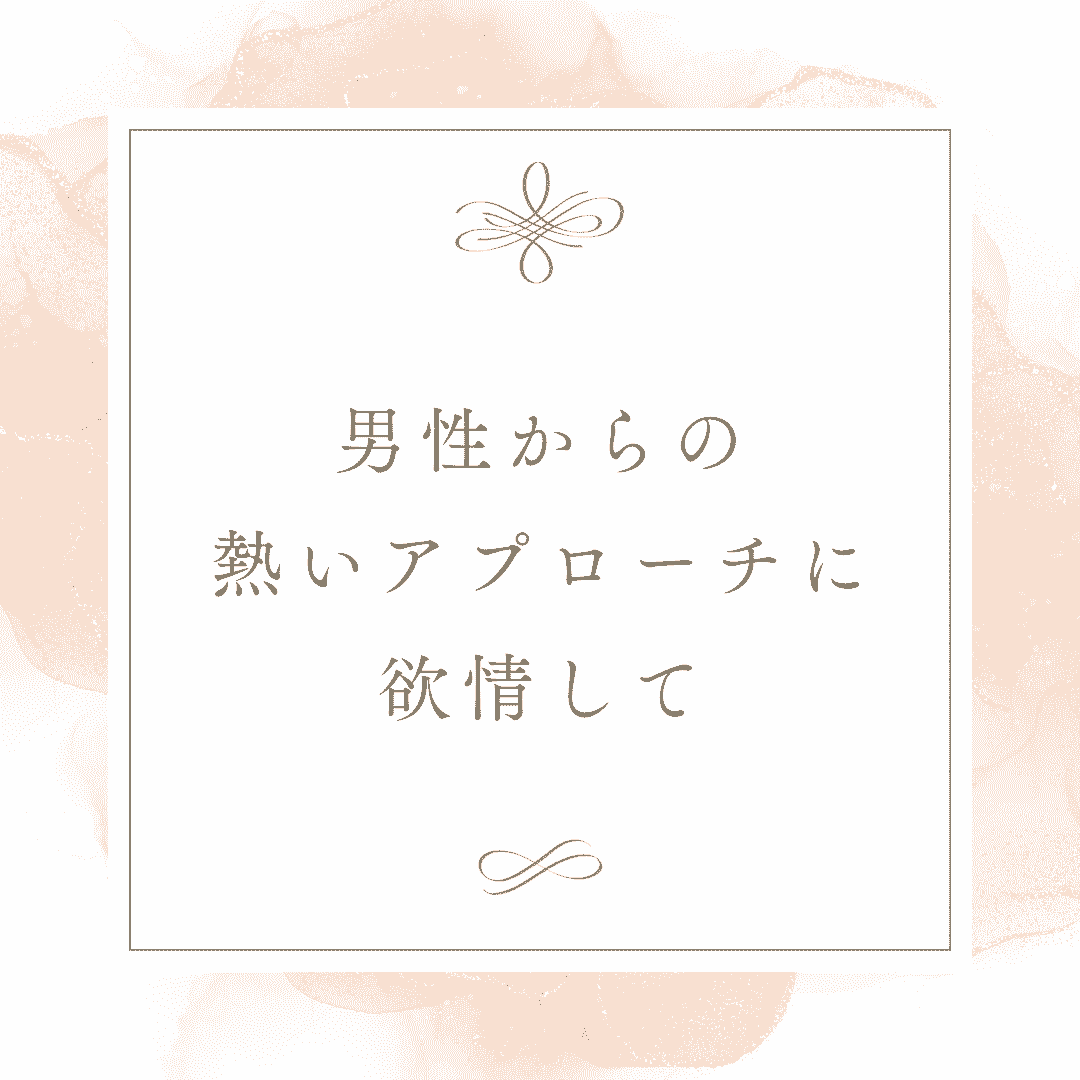


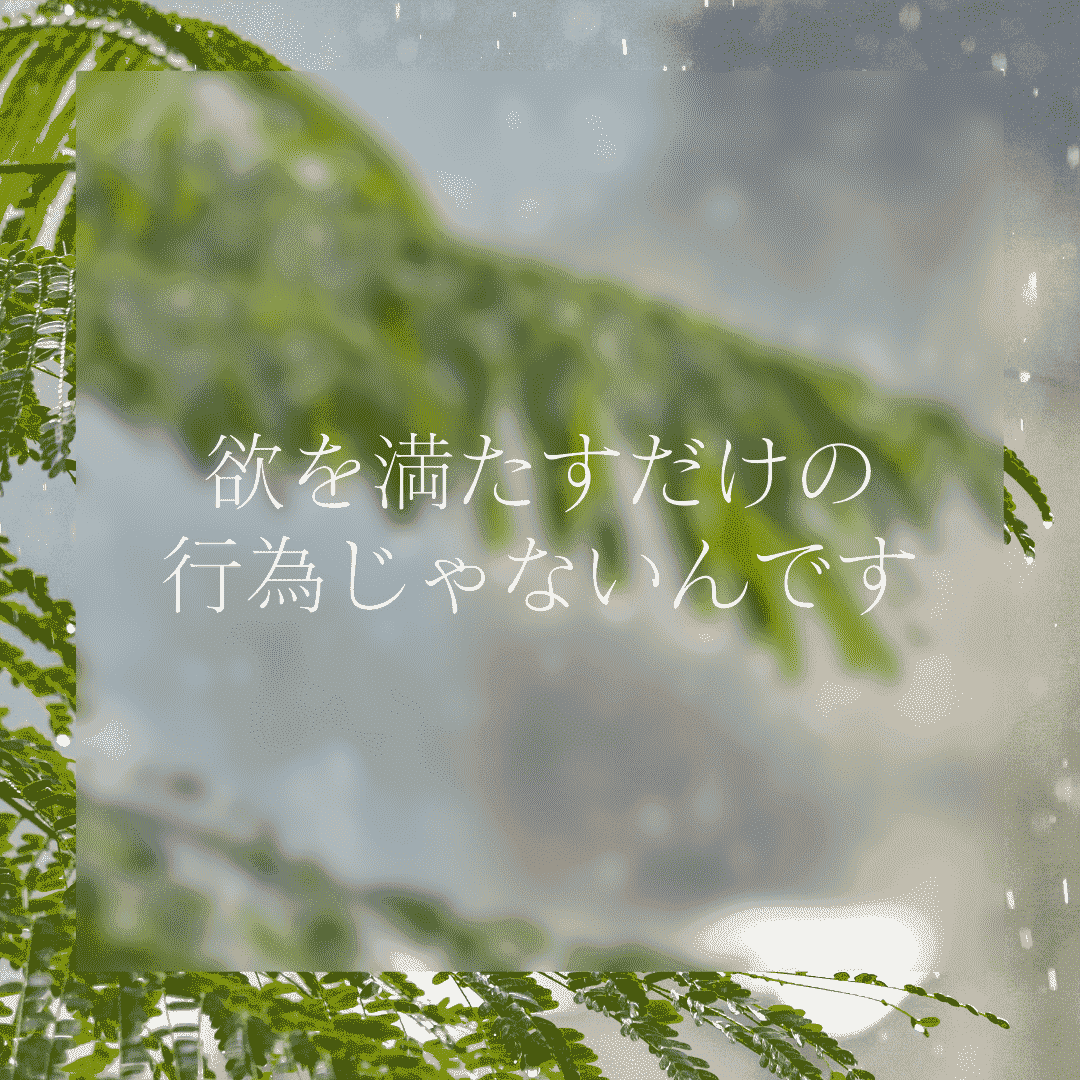

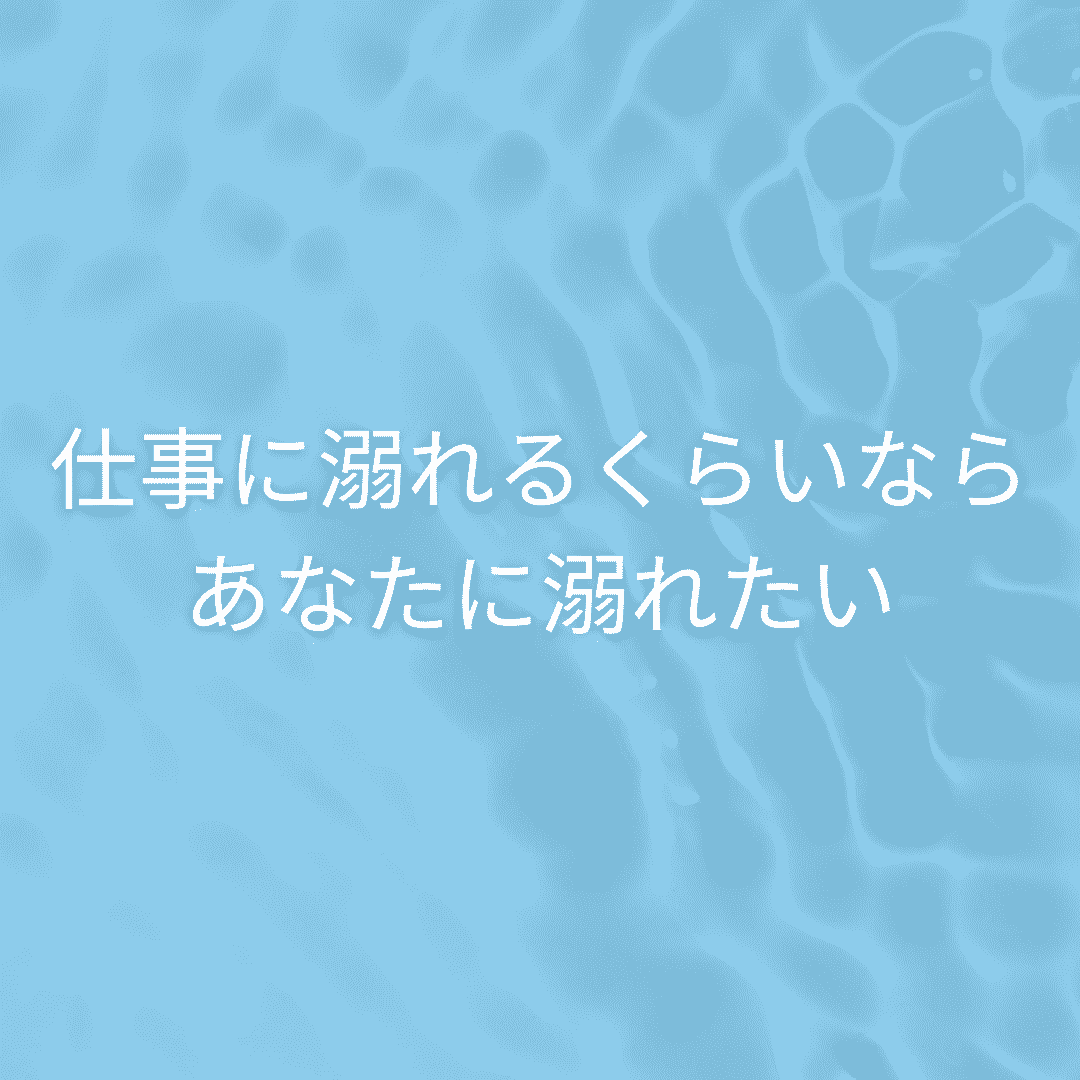








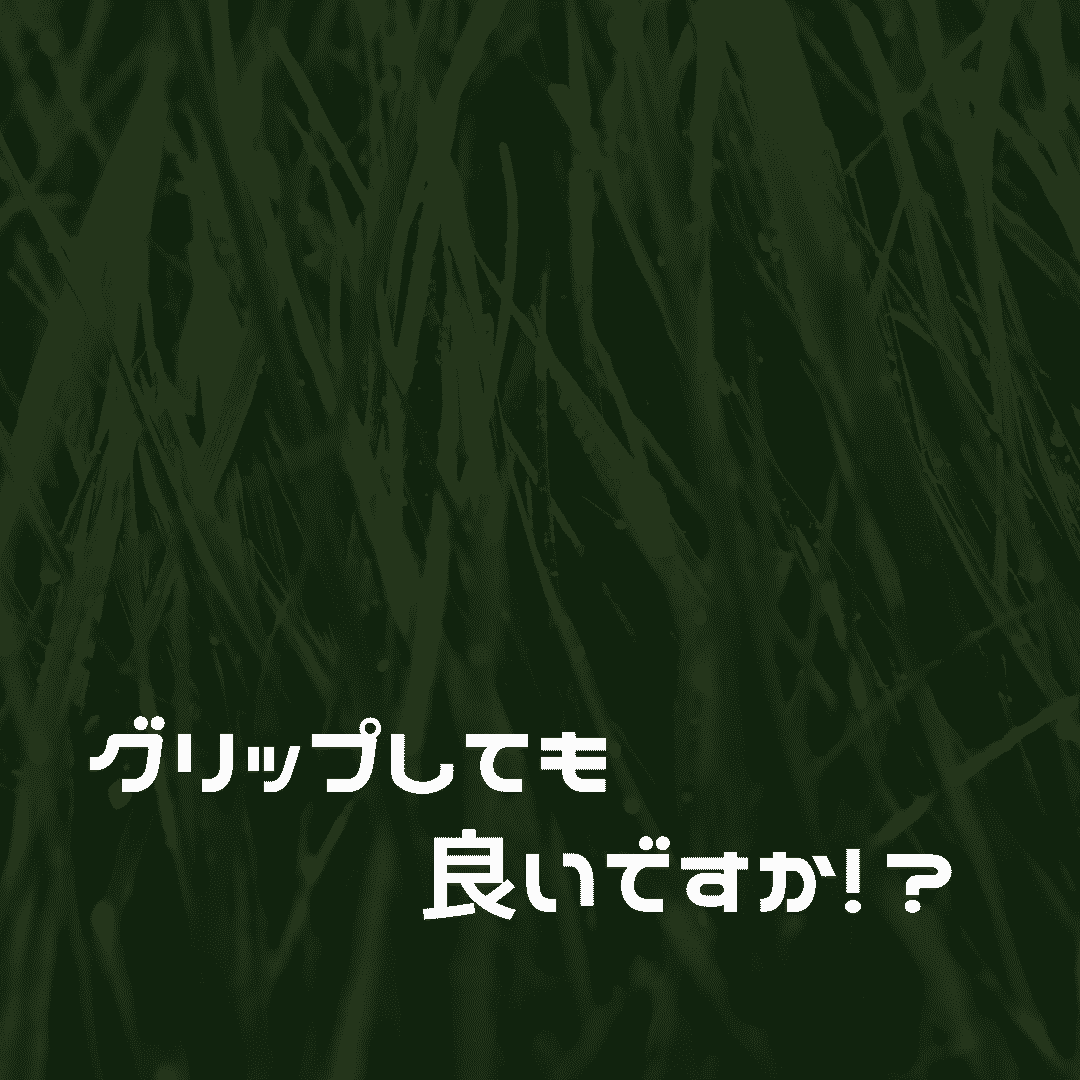

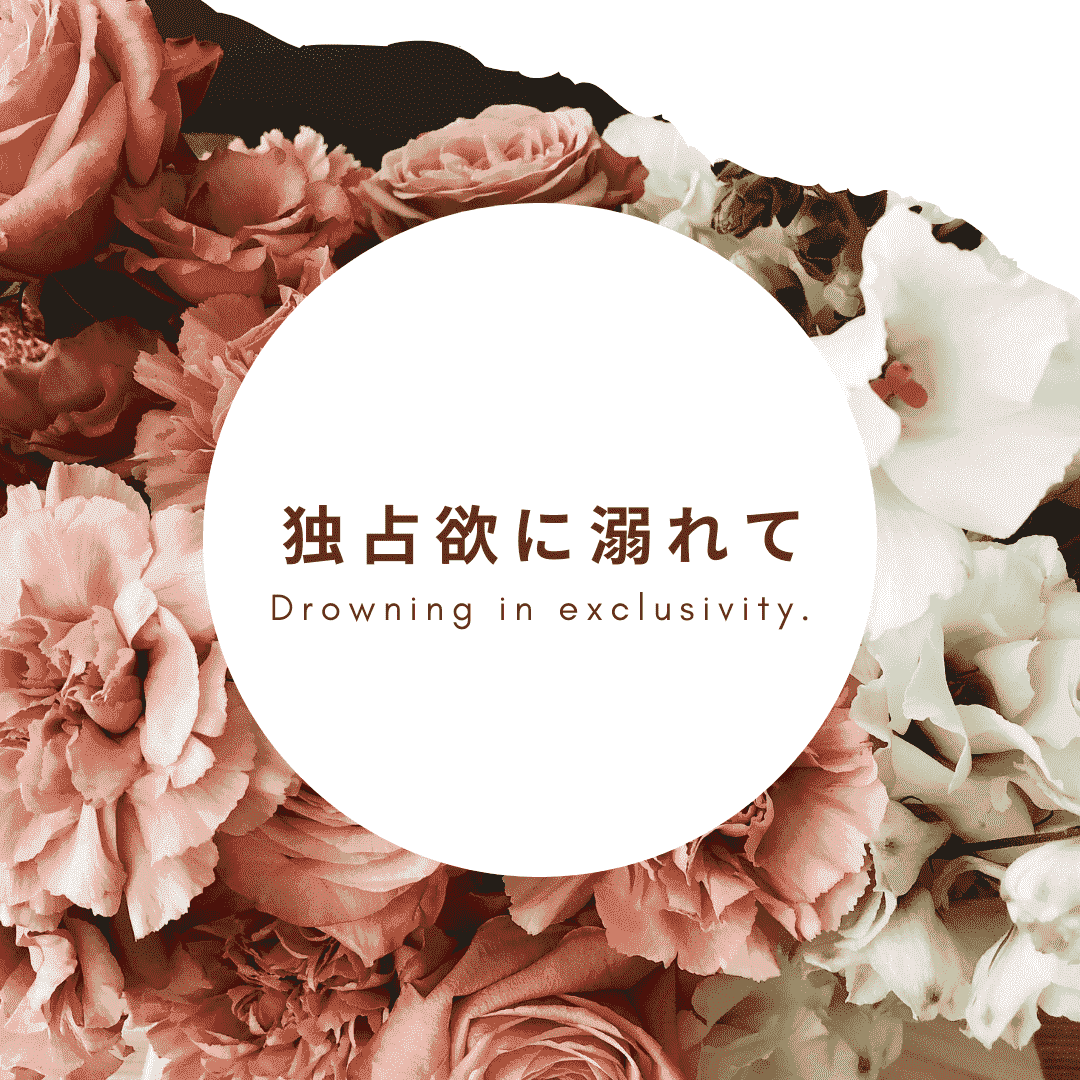
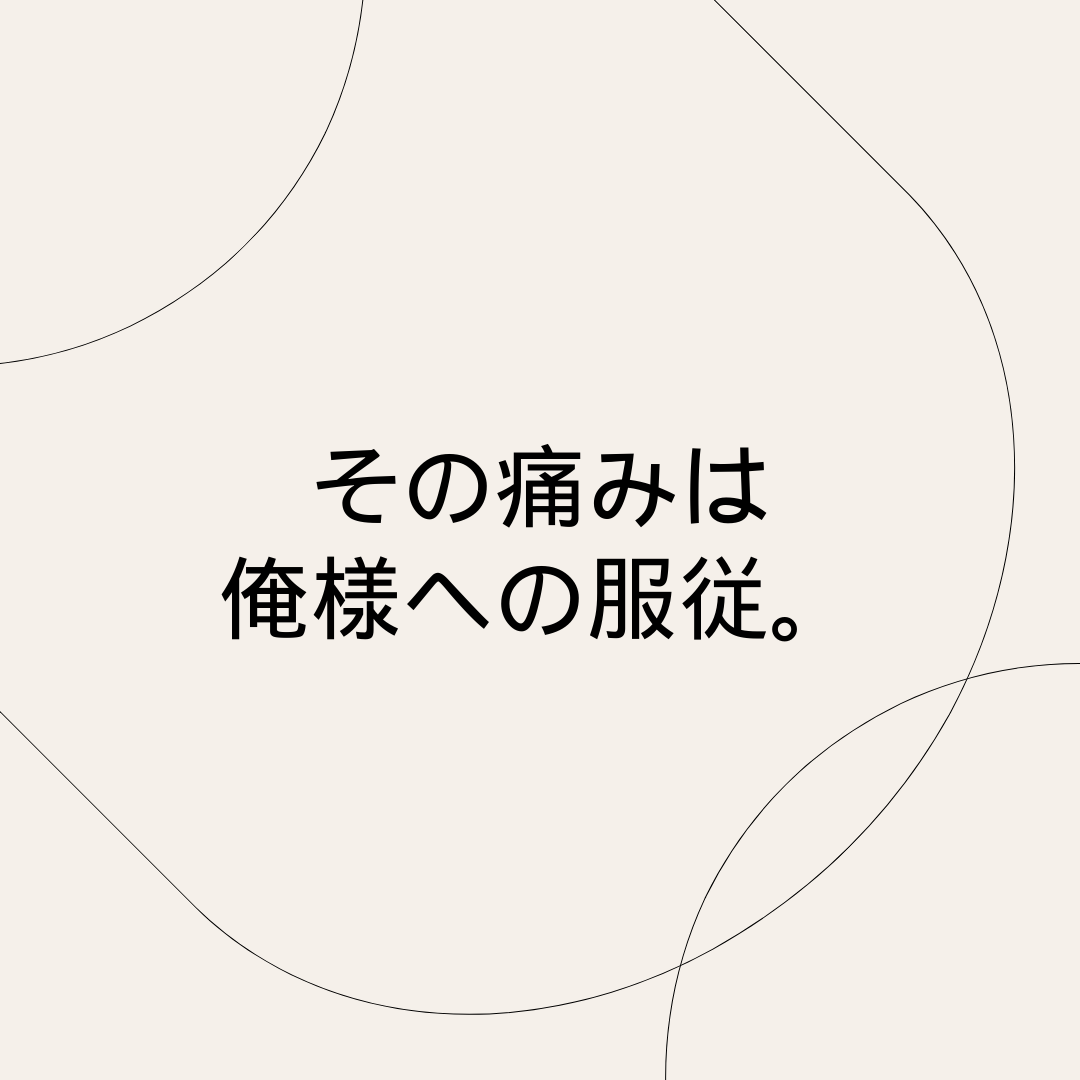
コメント