
0
心も、からだも濡れる不倫
私は渇いている…。
熱帯夜の中で喉の渇きを覚えて、ベッドから抜け出した。冷蔵庫を開けるとキンキンに冷えたビールが目に入ったが、明日も仕事だからと我慢をして麦茶を取り出した。使ってそのままだったグラスにとくとくと麦茶を注ぎ、喉の渇きを癒す。
どうしてだろう。それでも私の渇きはとどまることを知らない。本当は分かっている。
あの人。
あの、背が高くて脚が長いから、いつも私と目を合わせるのが大変そうだった人。
あの人だけが私の渇きを癒してくれたのだ。
無意識にあの人の腰のラインを思い出すかのように手を動かした。すると、持っていたグラスが滑り落ち、ガチャンと音を立てて床に叩きつけられて割れた。グラスは私たちの関係のような儚さと脆さを合わせたような、そんな偶像だ。
***
私がその人に出会ったのは、職場の近くにある喫茶店だった。
いつもはお弁当を持って仕事に向かうのに、とても寒い日に限って、作るのを忘れていた。派遣社員で、ただでさえ生活が苦しいのに外食なんて…とぶつぶつ文句を言いながら外に出たら、あまりの寒さに身がブルブルと震えるほどだった。
蕎麦屋までは徒歩で十分ほどかかるが、こんな極寒の中で十分も歩くのは、冷え性の私には地獄だった。近くに食べる場所がないかと見回すと、路地裏の入口に看板をみつけた。
【喫茶 テツ】
既に先が冷え切った足を動かして、必死に走り路地裏に入っていく。光のあまり届かない路地裏は、女性ひとりでは危険な場所に思えた。しかし、その日の私はそんなことより楽園を求めてそこを進んでいく…。
楽園はここか。
赤い重厚な扉を開くと、暖かな空間が広がっていた。
「いらっしゃいませ。」
バリトンボイスが店内に響く。
そこには背の高い、少年のような男性がいた。先ほどのバリトンはこの人なのだろうか? 少し見た目とのギャップを感じたのが、彼との出会いだった。
店内にはお客さんが全くいない。こんな寒空の下、わざわざコーヒーを飲みにやって来る人もいないか…と思いながら腰を下ろす。
バリトンの童顔店員さんがメニューを持ってきてくれた。そのときに、つっと指が当たった。普通なら不快感を覚えるものだけど、彼との触れ合いは決して悪いものじゃなかった。
そう考えると、彼との交流は最初から決まっていたのかもしれない。
***
なんて、割れたグラスのカケラを拾いながら考える。
派遣社員だった私には少しお高めのランチだったが、コーヒーは今まで飲んだ中で一番美味しく淹れられていた。
彼はコーヒーを淹れるのがとても上手かった。まあ、だから喫茶店を開いているのだけれど。
あの頃の私は凄く飢えていて、お金にも、仕事にも、恋人にも、食事にも、お酒にも…とにかく何にでも飢えていた。
だけど、あの人が淹れるコーヒーは私の心にすっと入ってくるような、そんな優しさが込められていた。ほっとする感じではなく、砂漠で彷徨う私に、そっと水を与えるような。
「何かコーヒーを淹れるコツがあるんですか?」
彼の店へ足を運び始めて半月が経った頃に、私は彼に聞いてみた。
「そうですね。温度管理をしっかり行なっています。」
真面目に答える童顔の彼が笑うと、本当に十代の少年に見える。
いつも店内には誰もいない。こんなに美味しいコーヒーを飲める店に皆が気づかないなんて。でも、オフィス街の路地裏にひっそりと佇むこの店は、確かに人目に付きにくい。お客さんがいないことをいいことに、私は彼との会話を楽しんだ。
「何故ここにお店を?」
「知り合いから譲り受けたんです。」
「コーヒーはずっと好きだったんですか?」
「昔は苦手でした。でも、大人になってから、コーヒーの美味しさに気がついたんです。」
「海外旅行はしたことある?」
「北欧の方にコーヒーの勉強をしに行きました。」
個人的なことを聞き出すまでに、時間は要しなかった。
今の給料では彼の元へ通うのはきつかったけど、それ以上に心が満たされている自分がいた。彼はどうなのだろう。聞くのが怖い。
「結婚してるの?」
ある日、ぽろっと聞いてしまった。
「してます。」
止める間もなく答えが返ってきて、私の盛り上がっていた気持ちが、がくんと下がった。
***
グラスの破片を全て拾い集めると、割れたグラスは彼からの贈り物だったな、ということを思い出した。何の飾りも付いていないシンプルなグラスなので、贈り物だということをつい忘れていた。
彼との交流が深くなった頃。それは春から夏へ移行しようと気温が上がっている頃で、昼は暑く、夜は寒かった。
私は初めてアイスコーヒーを注文した。急冷式でコーヒーを淹れていることを、彼自ら教えてくれた。グラスは彼が日頃からピカピカに磨いていたので、とても美しかったのを覚えている。
その日も私たちの他には誰もいなかった。
「ねえ、飲みに行かない?」
私ははっきりと下心を持って彼を誘った。渇くのだ、からだが。彼が欲しいと唸りをあげている。だから、もう私は自分の気持ちに嘘はつけなかった。
気付いたら彼のことが好きになっていた。大体、好きでなければ、生活に困るほどの値段がする喫茶店などに通わないだろう。たとえ、彼に奥さんがいるとしても。
「そうですね。」
彼は私の誘いに乗った。下心込みで。
自分から誘っておいて緊張をしながら、服を脱ぐ。下着姿になると、彼は「綺麗な下着ですね。」と言いながら、私の唇に自分のものを合わせてきた。
舌を差し出すと、彼は慣れたようにその舌を絡め取り、長い舌で深く私の口内をなぞり始める。私はびくびくと反応しながら、その刺激を受け取った。特に歯列の裏側を舐められるのが好きで、彼の舌が歯茎に触れると、私は腰をくねらせた。
彼の服は、私が脱がせてあげた。だって、彼は酔ってボタンを上手く外せなかったから。脱いだ彼のからだは意外と肩幅と胸板の厚さがあって、童顔とのギャップを感じる。
まるで声とからだだけ彼のもので、顔を取り替えたみたいな。それとも逆?
私がくすりと笑ったら、彼は挑まれたと思ったらしく私の下着を剥ぐ。じっと私の裸体を観察している。段々と恥ずかしくなって「貧相なからだでごめん。」なんておちゃらけてみても、彼は真面目に「ラインが美しい。」と私のからだを褒めてくれた。
胸を柔らかく揉む彼の手は繊細で、感度が上がっていくのを感じる。
「ぁ、、」
「そんな切ない声を出さないでください。」
彼はそう言い、私の固く立った頂を強く摩った。からだが素直に反応をして、思わず跳ねてしまう。彼は敏感になったラズベリーのような頂きを、こりこりと摘まんでは摩るを繰り返してきた。
「ここがいいんですか?」
そう優しく聴きながら、からだに触れてくる。いつも私が質問して、彼が答えるという流れがほとんどだった。だから、なんだか新鮮に思えて、改めてこの状況の異質さを感じた。
彼は私のことをきちんと好きで、セックスをしているのだろうか。不安になった。
「私のこと、好き?」
彼は私の質問には答えず、いきなり私の脚の間に顔を入れた。突然のことに驚いて、情けない声を出してしまう。
「ちょっと持って…!!」
そんな静止の声も届かず、彼は私の蜜壺をぺろりと舐め上げる。
「…ひっ」
腰が引けるが、彼が脚をガッチリと固定しているので、私はただ与えられる刺激に絶えるしかなかった。
じゅ、じゅる、ぴちゃ……。
そんな卑猥な音が私の部屋に響き渡る。自分の部屋なのに、この人がいるだけで違う空間に思えた。まるで2人だけの世界に切り離されたみたいな。
口で陰部を舐められ、吸い取られ、挿れられ、一回軽くイった後、彼は自分の男根を取り出した。
それは太く、形の良い、考え得る限りの中でとても理想的なものであった。今までみてきた陰茎の中では一番大きい。
「いきますよ。」
丁寧に私に断りを入れてから、私の蜜壺に挿入していく彼自身。圧倒的な物量に私は目を見張ったが、それでも私のからだはすんなりと彼を受け入れた。
潰れたマットレスの上で私たちはお互いに汗を飛び散らせながら交わった。彼はずしりと重いからだを私に打ちつけ、くっと歯を食いしばっている。気持ちが良くて、イってしまうのを必死に堪えているようだった。
私はうっとりと彼の腰のラインをなぞった。指を行ったりきたりさせて、彼のからだを確かめる。小さなくびれを見つけて私は嬉しくなった。
「ふっ、ふっ……」
「ぁっ、あ、……」
彼の息遣いと私の声が重なり調和していく。
からだの相性はばっちりで、私も彼も行為に夢中になった。
パンッパンッ!
彼が腰を動かす間に私の花芯をぐりぐりと押し込む。余裕のなくなった私のナカはもうトロトロになって蜜が溢れだしていた。
心も、からだも、完全に彼に溶かされている。その事実に、本当に現実なのだろうかと疑ってしまうほどだ。夢ならいいのに。だって、そうすれば私に都合の悪いことなんて、消去してしまえばいいのだ。でも、部屋に充満する匂いが私を現実に引き戻される。彼には妻がいて、これは不倫なのだと気付かされる。いや、不倫でも構わない。私はそれだけ彼を渇望していたのだから、それが満たされるだけで良かった。そのはずなのに。
「ねえ、私のこと好き?」
そんな問いをしてしまうのは、私が弱いからなのだろうか。弱いから、彼に確認しないと、この交渉が虚無な行いになってしまうと思ってしまっているのだ。
彼はふっと息をひとつ吐き、動きを止めた。
「僕が好きでもない人と関係を持つと思いますか?」
その言葉を聞いて、私は大変失礼なことを聞いてしまったと後悔した。そうだ。彼の性格を考えれば、考えなくインモラリティな行為なんてしないだろう。
謝ろうとして口を開くと、彼は私の口を塞ぐようにキスをしてきた。口内を蹂躙しながら、下もピストンを速めてくる。
「んっ、ふっ! んん!」
私たちは急激に襲ってきた頂点に同時に達した。
それから私たちは何度か交わり合い、本当の恋人のようになった。でも、彼が奥さんと別れるつもりはないことが分かっていた。だって、彼は苦しんでいたから。奥さんのことを愛していたし、私のことも本気だった。私はその彼の苦しみさえ、自分の心を満たす養分としていた。彼以外、満たすものがなかったから。
しかし、今はもう、その関係もない。
私は派遣先が変わり、あのオフィス街に全く用事がなくなってしまった。お弁当をせっせと作り、毎日ひとり寂しく食べる日々が続いている。
彼との交渉は派遣先が変わると共にぷっつりと途絶え、試しに店を訪ねてみたら閉まっていた。あんなに人が入らなかったら、潰れるに決まっているか。私の冷静な頭がそう考えた。
こうして、私と彼の関係は終わりを告げた。
さっき割ったグラスは彼との最後の繋がりだったのだ。それがなくなった今、私たちはもう何も関係のない赤の他人になってしまったということ。また私の冷静な部分が、私の感情にそう言い聞かせている。
私はグラスのカケラを袋に詰めぎゅっと口を縛り、ゴミ回収所に投げ捨てた。






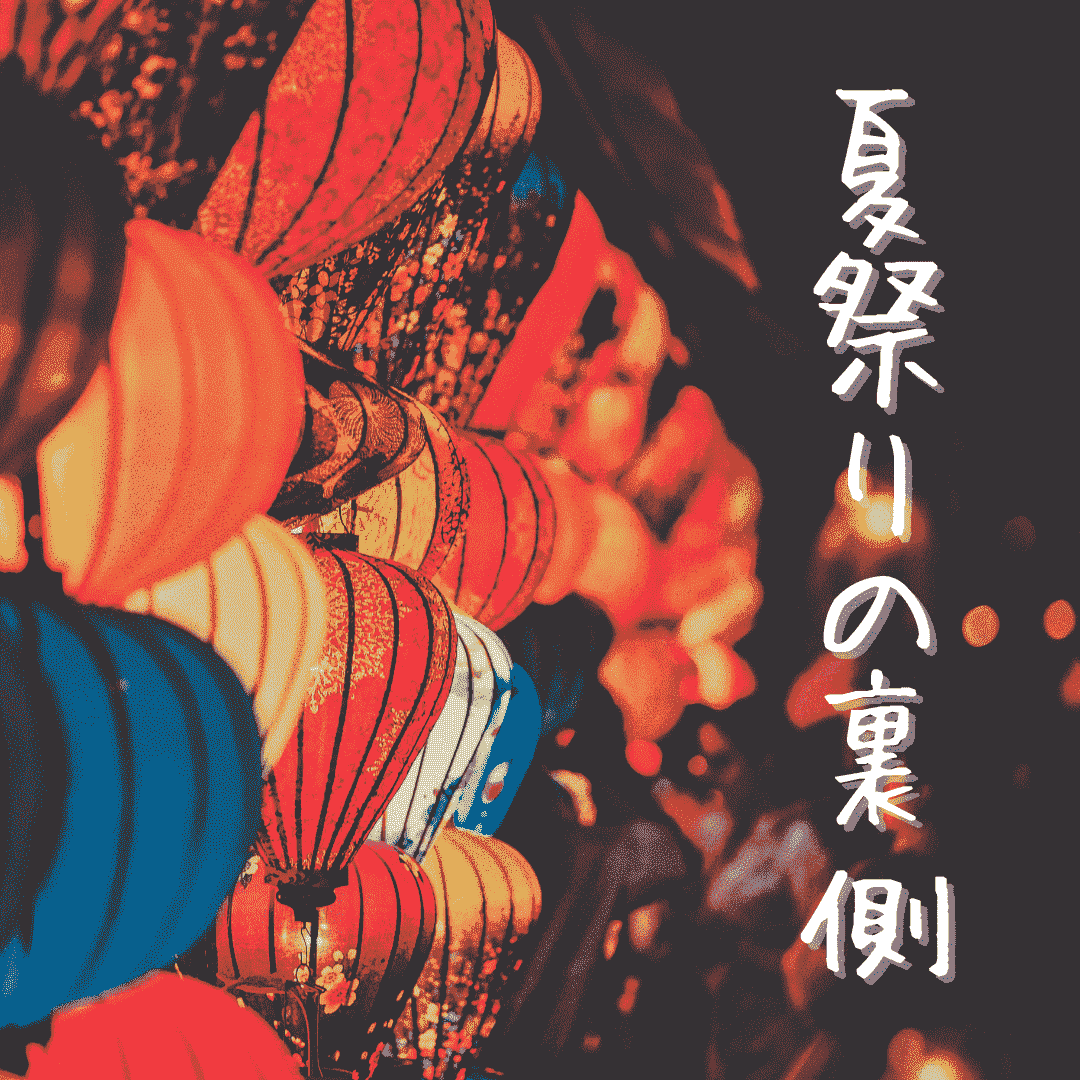

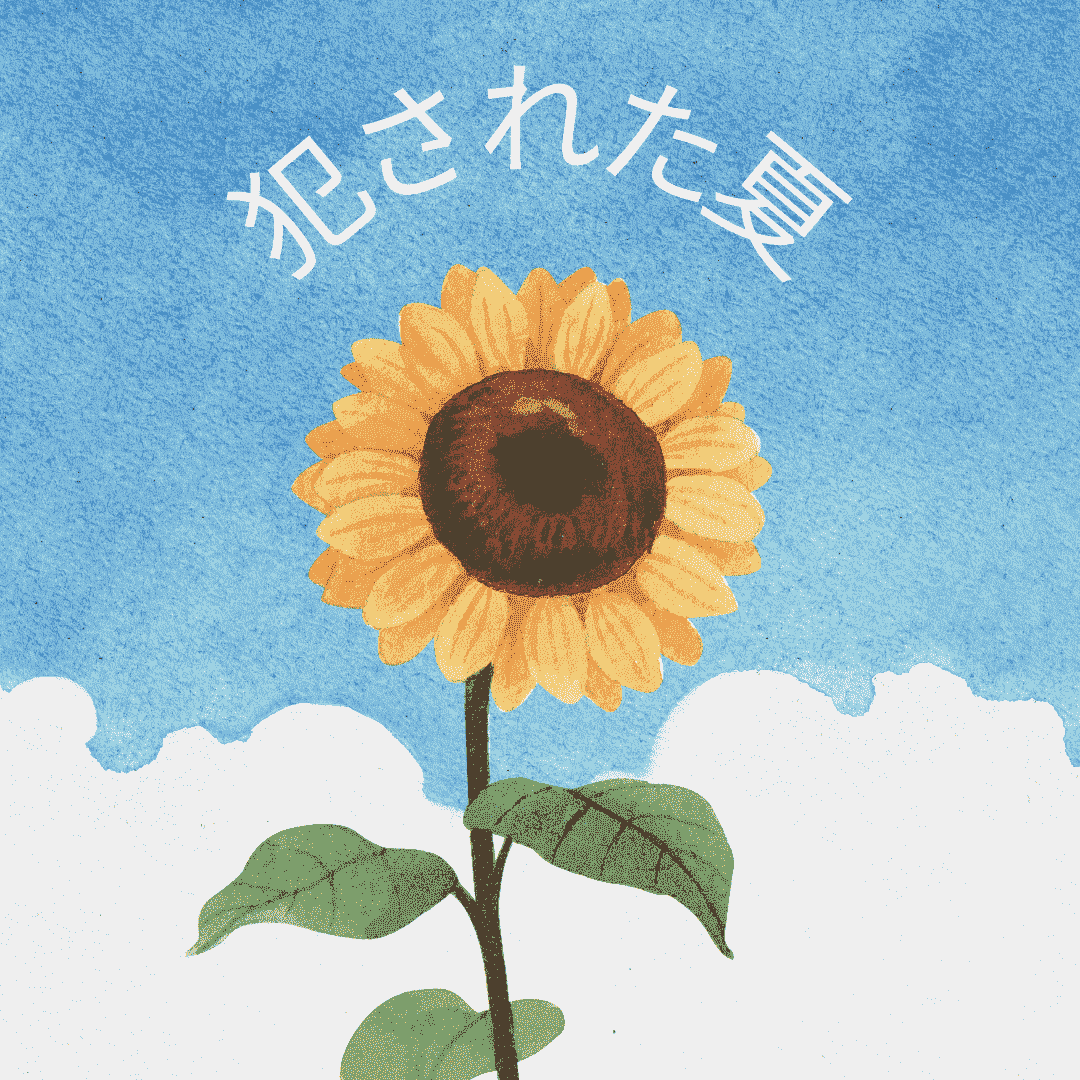


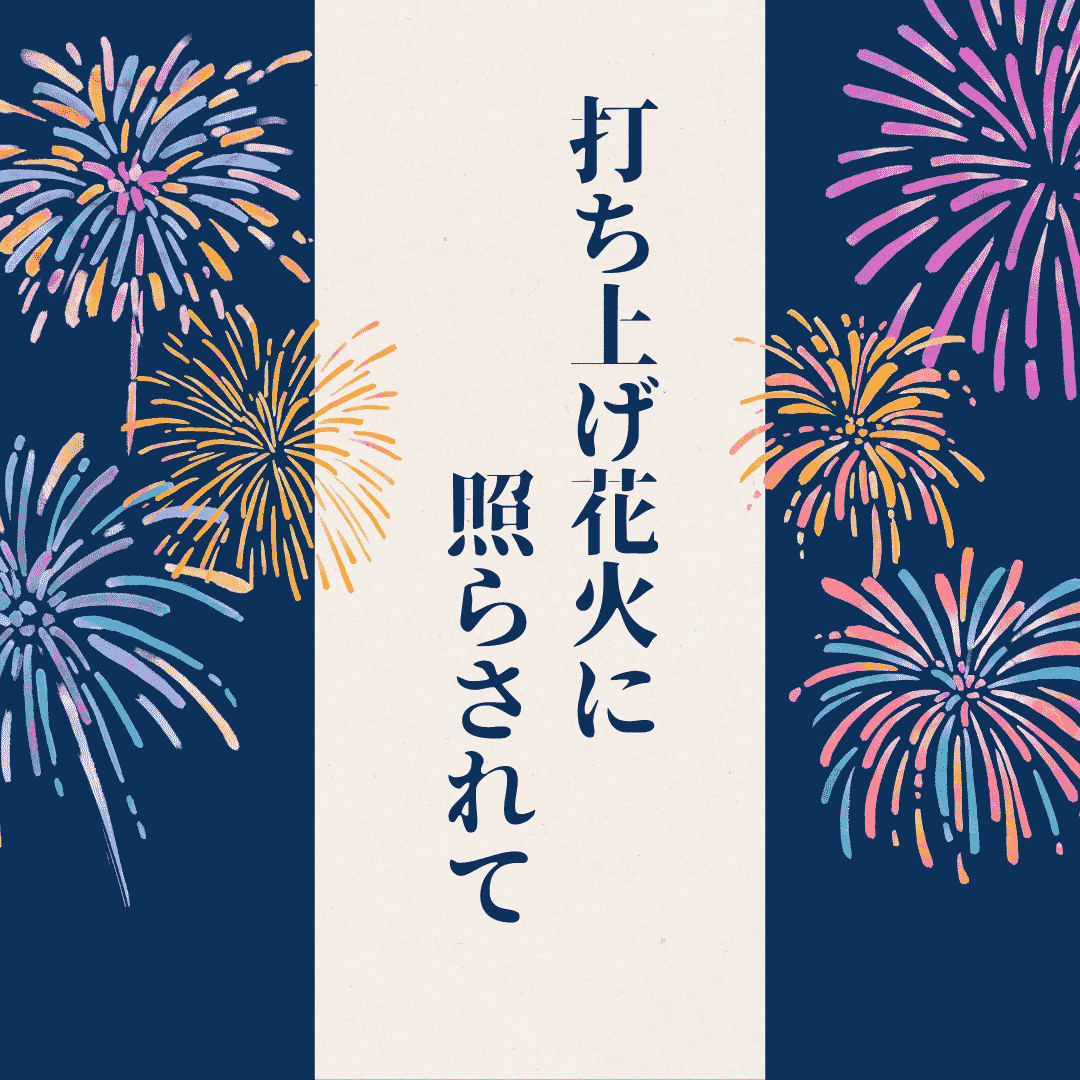

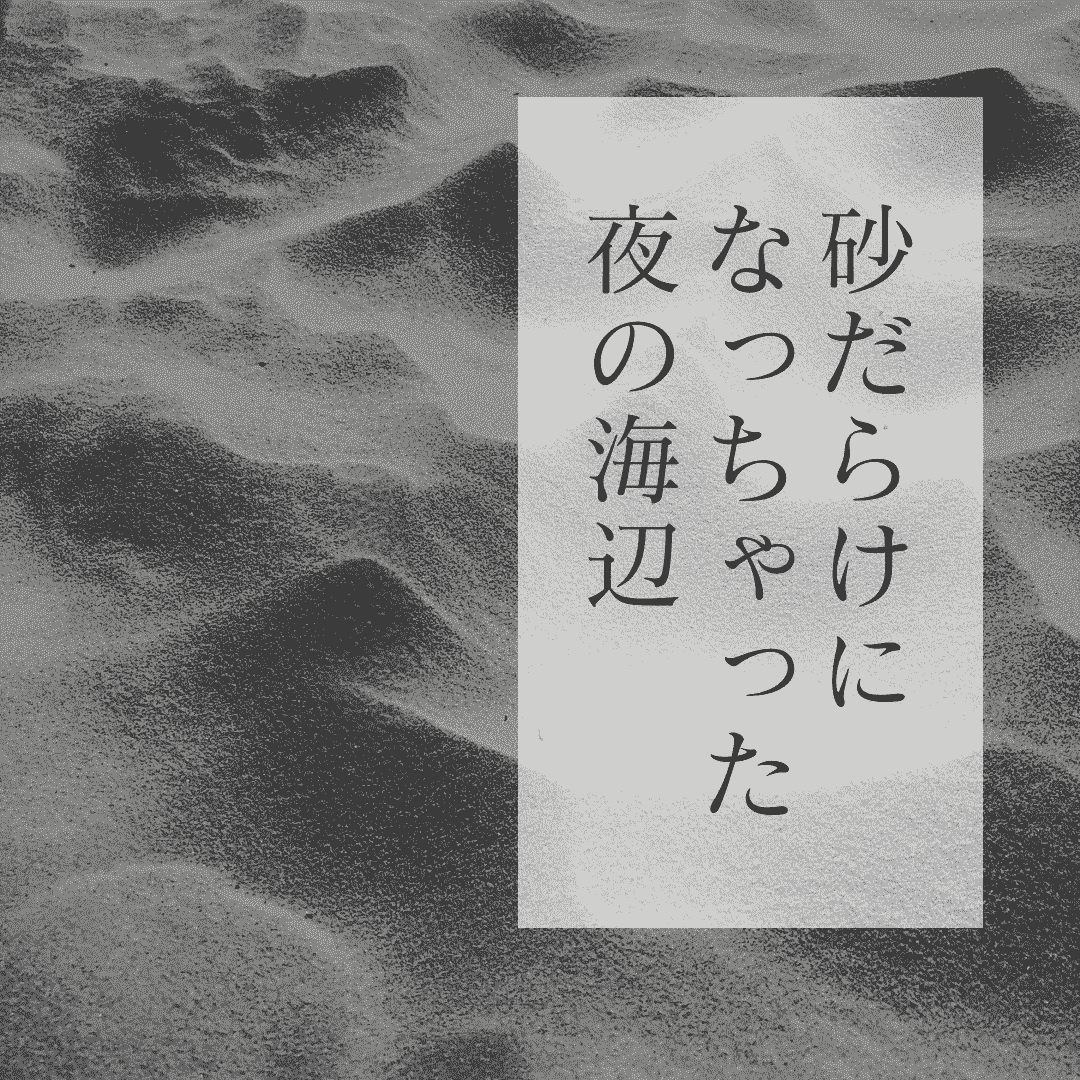

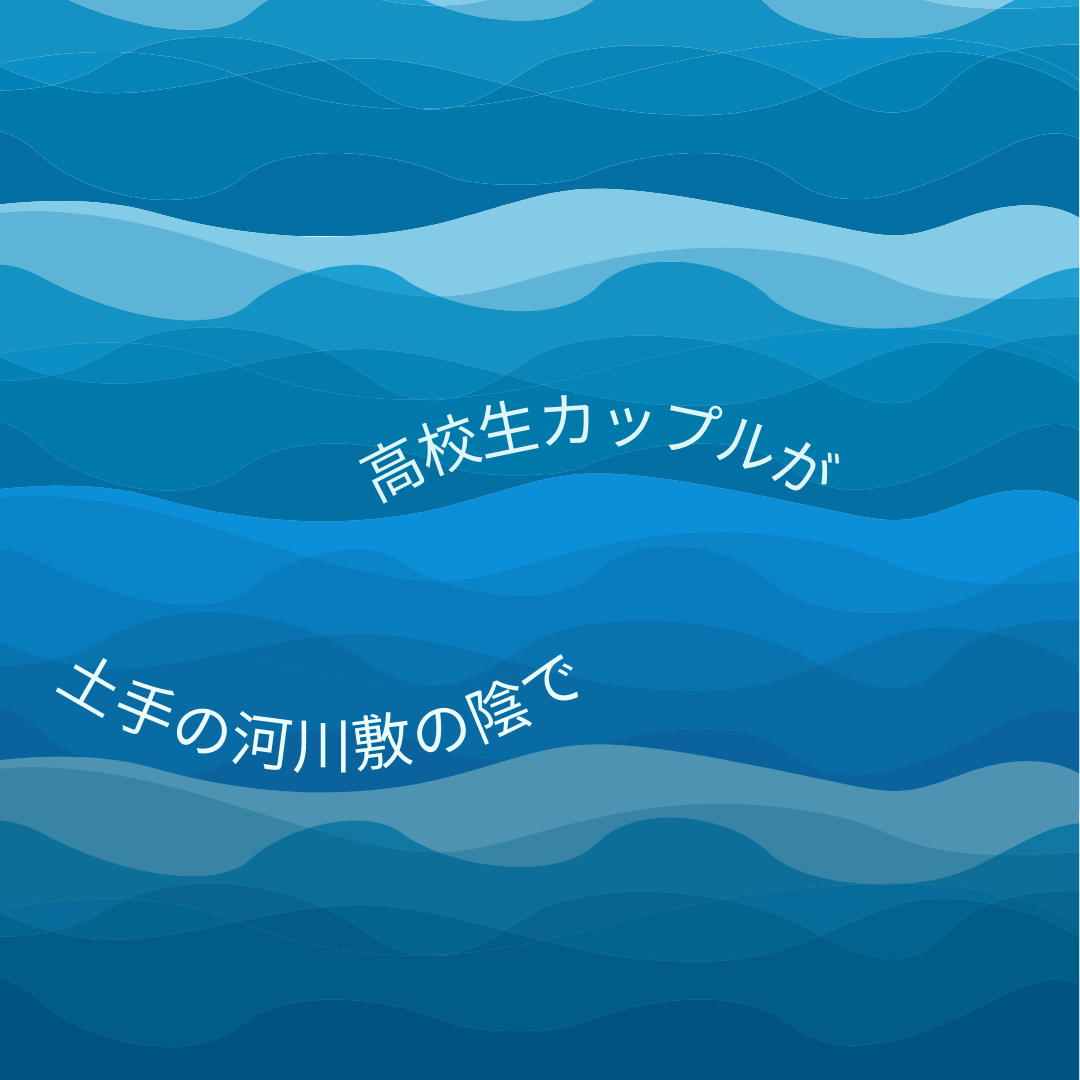


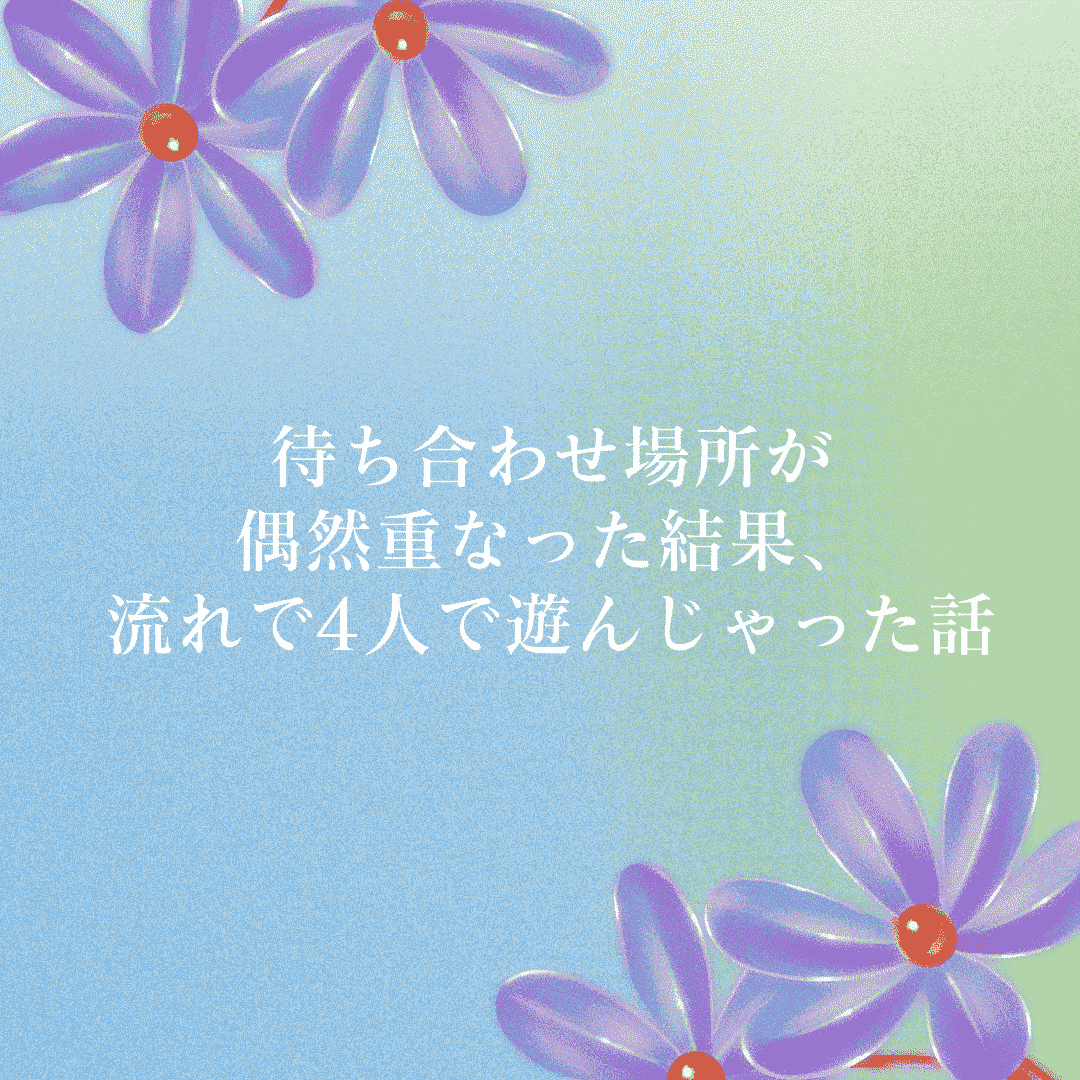



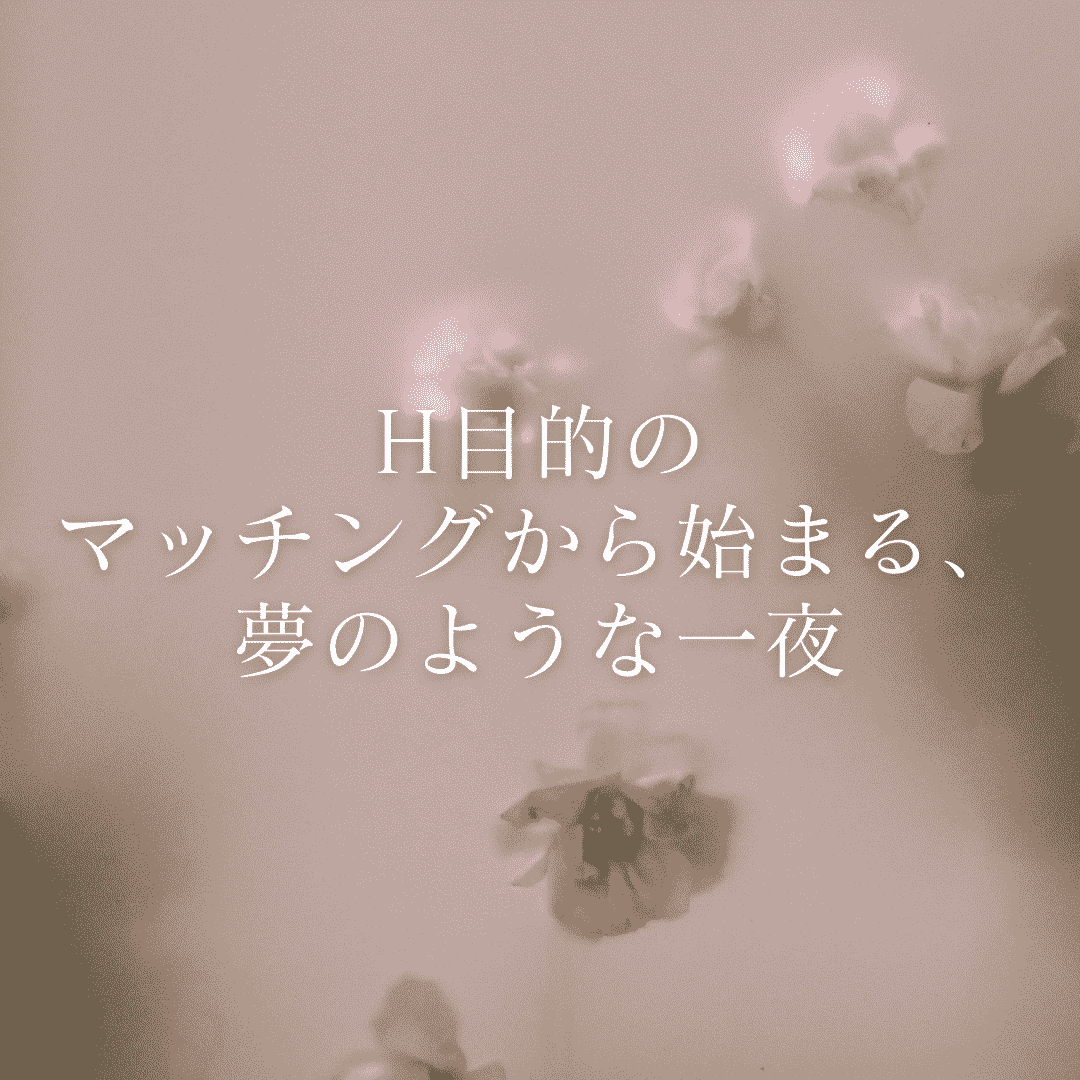

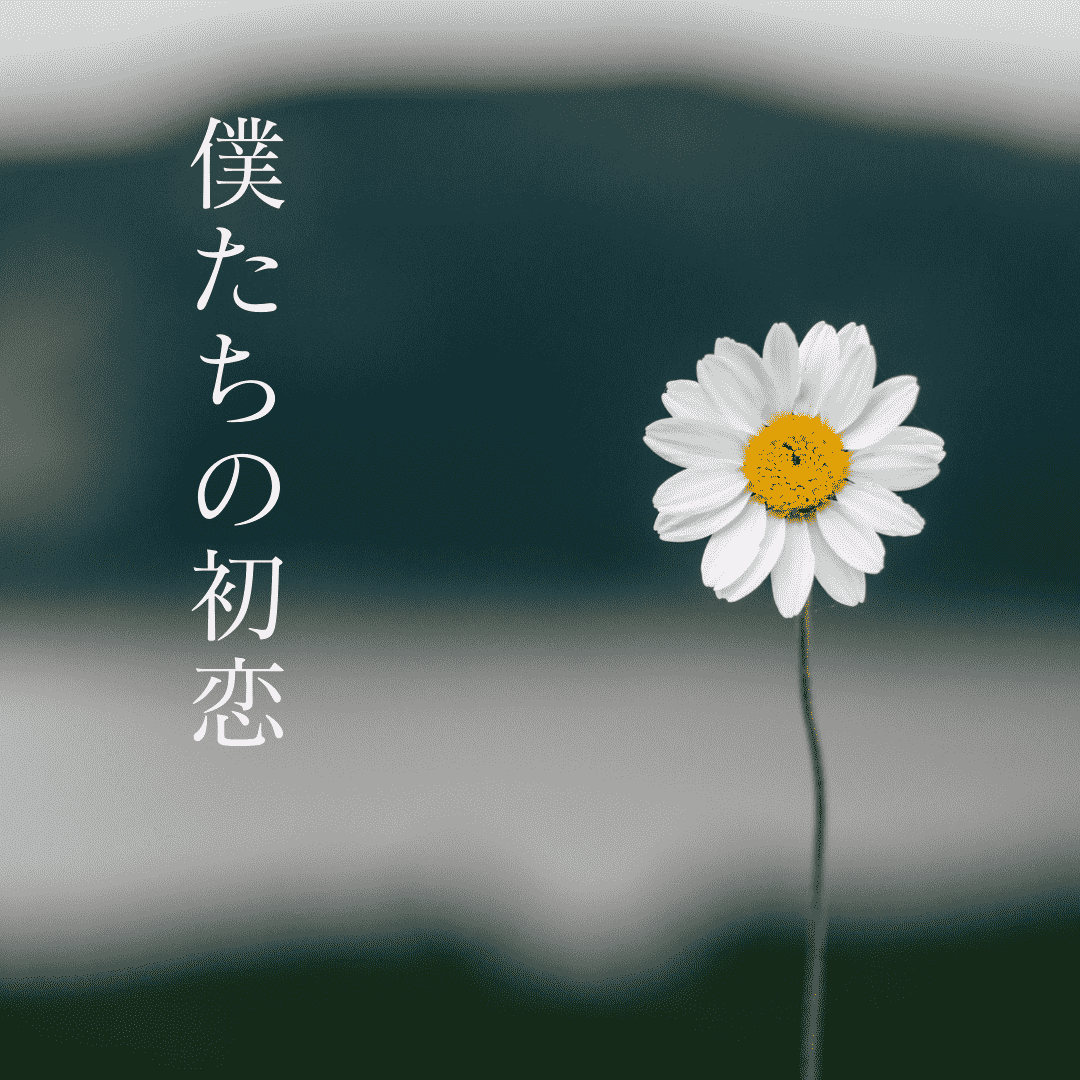


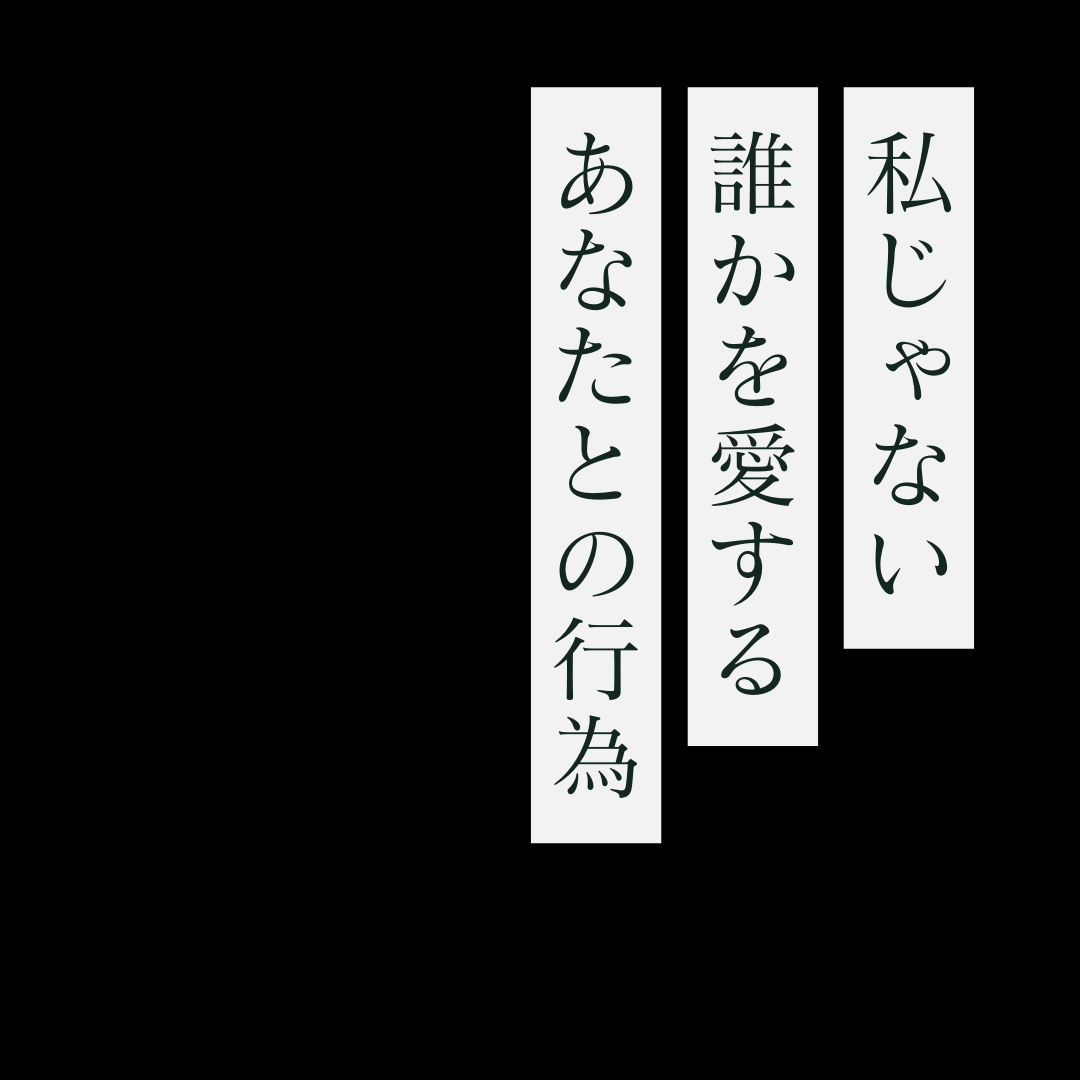

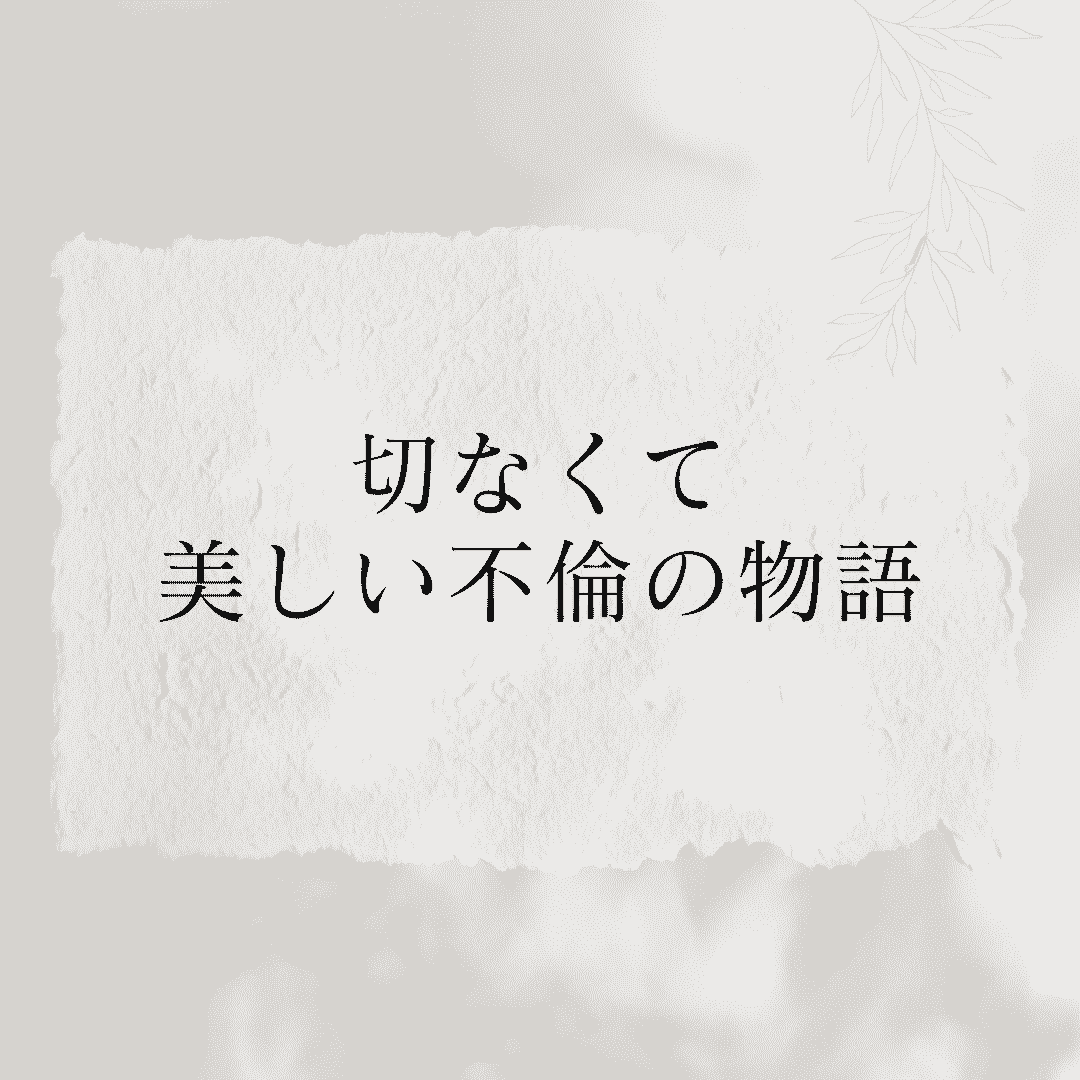
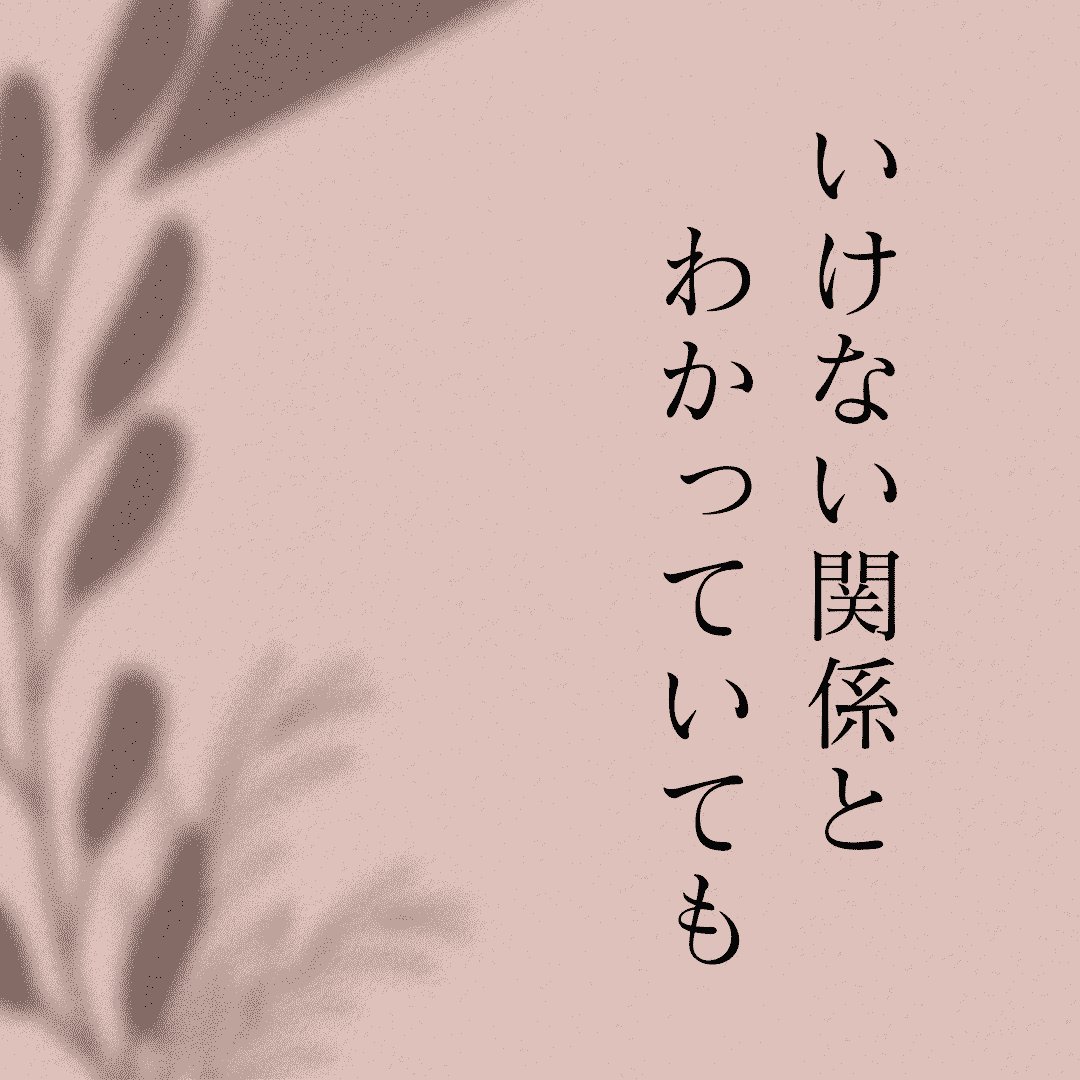









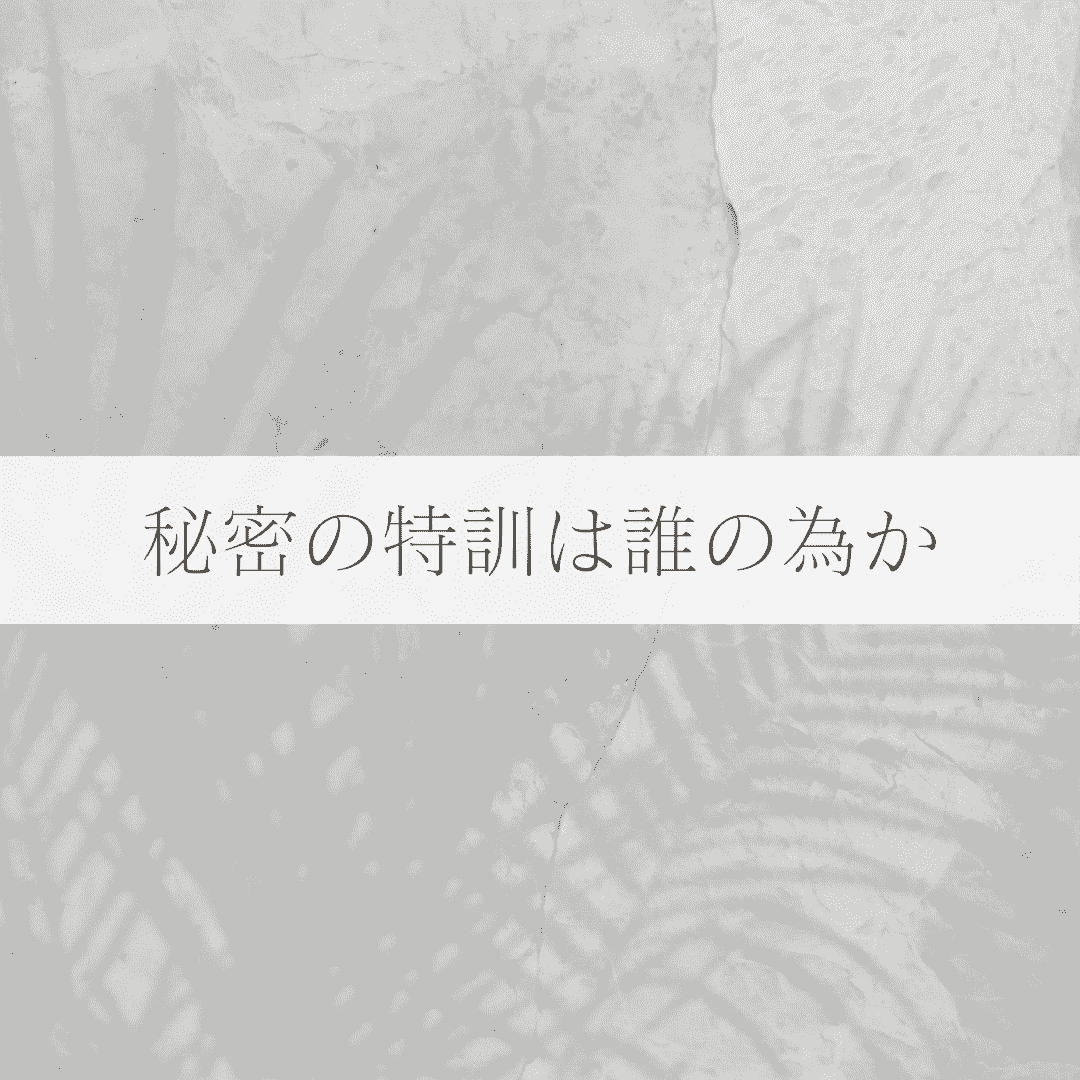
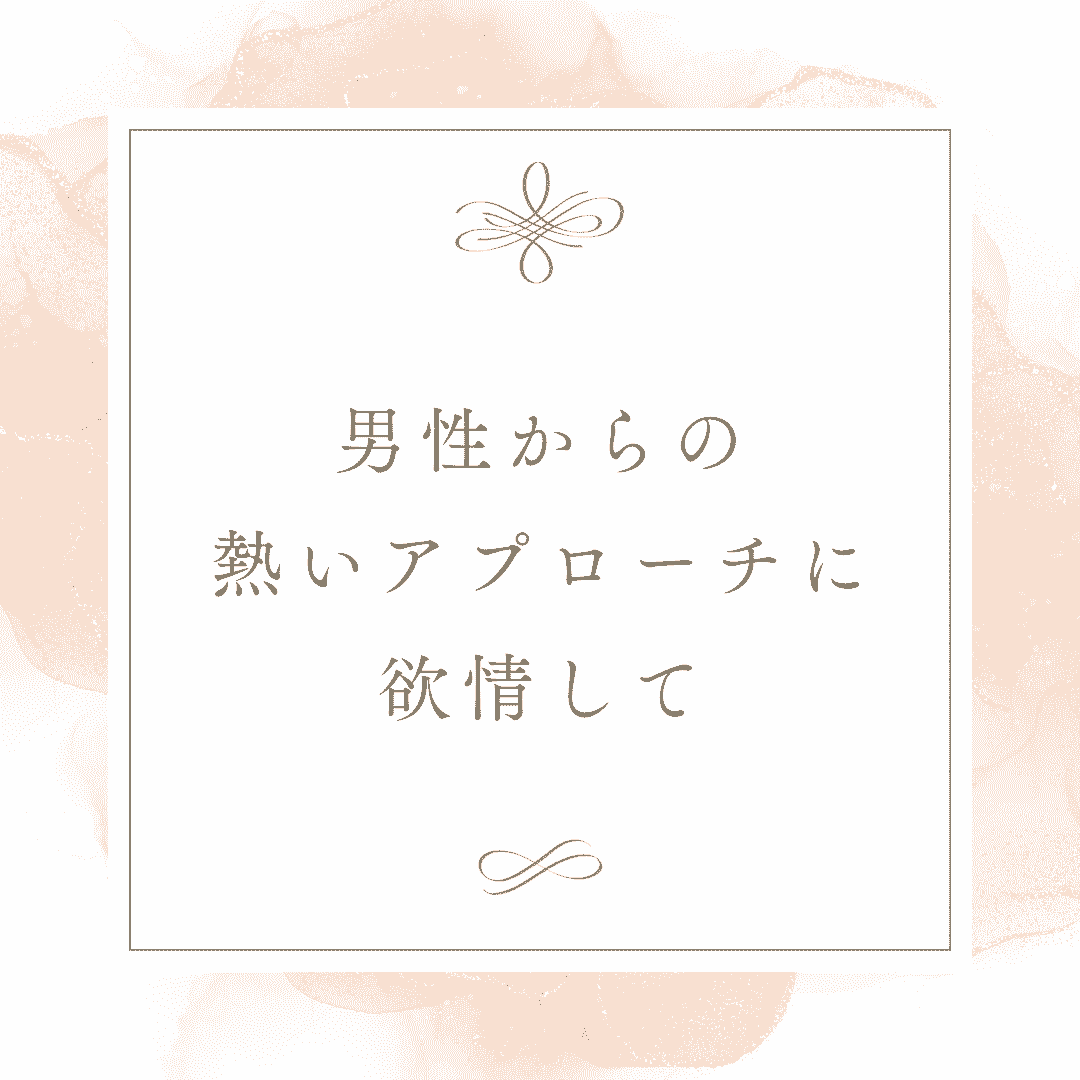


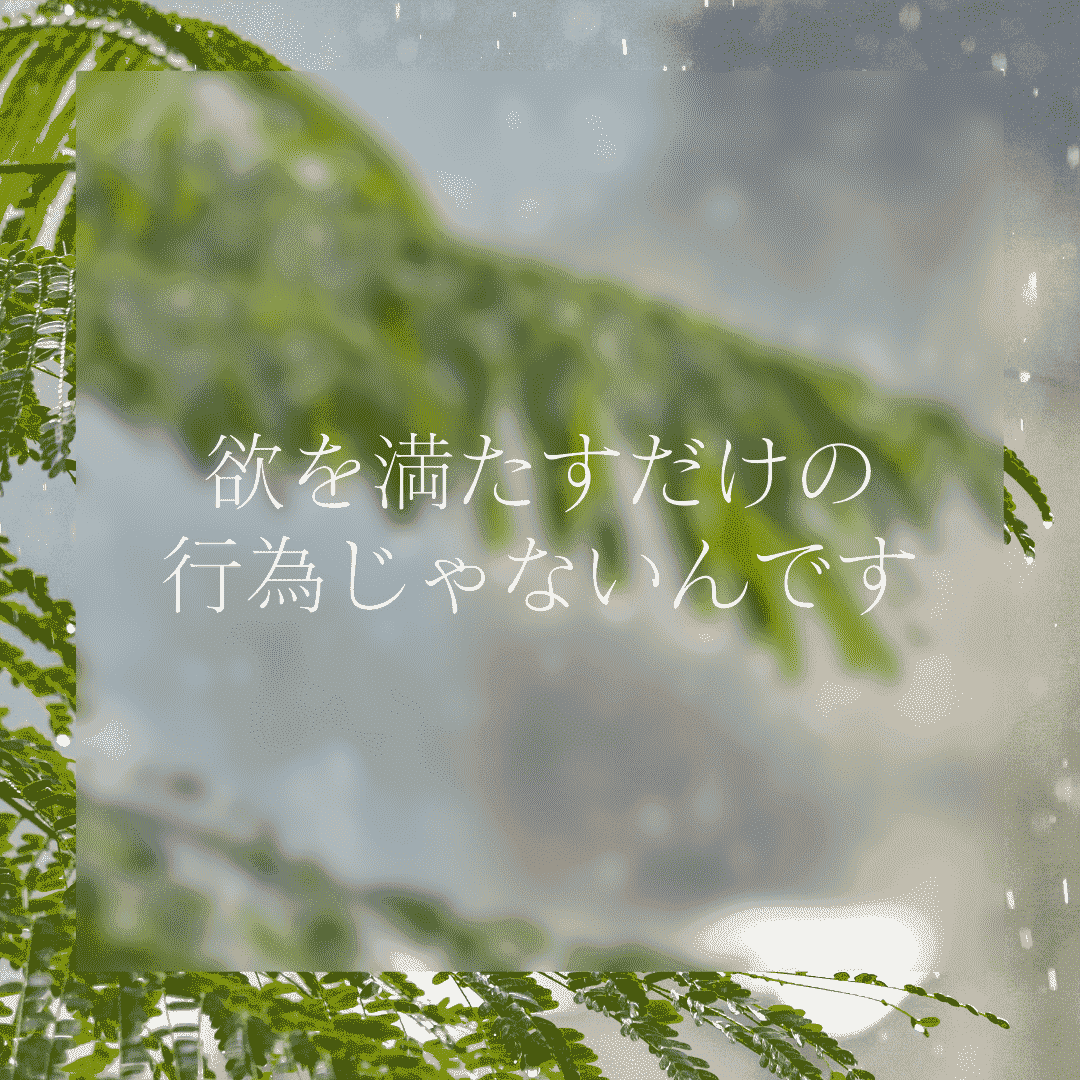

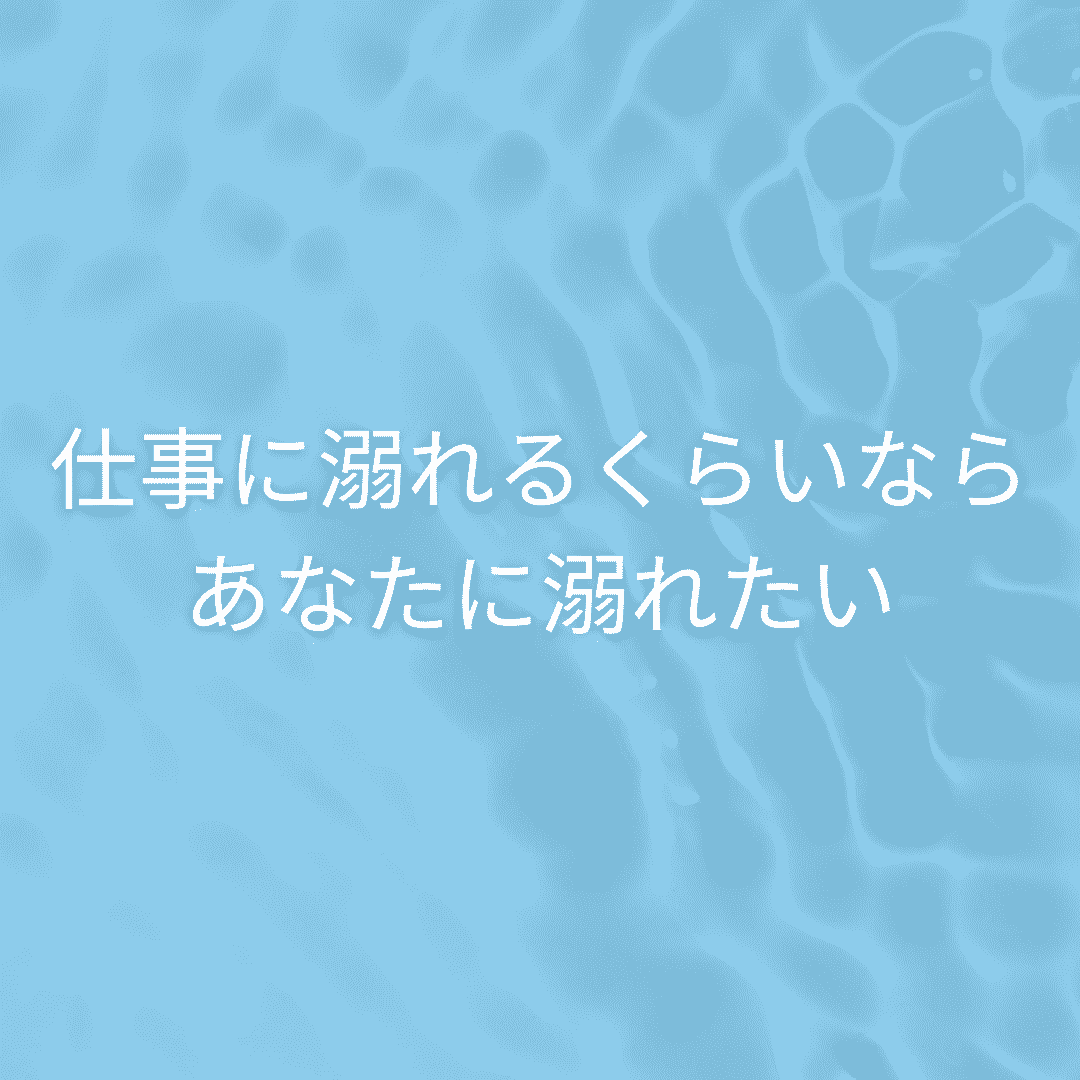


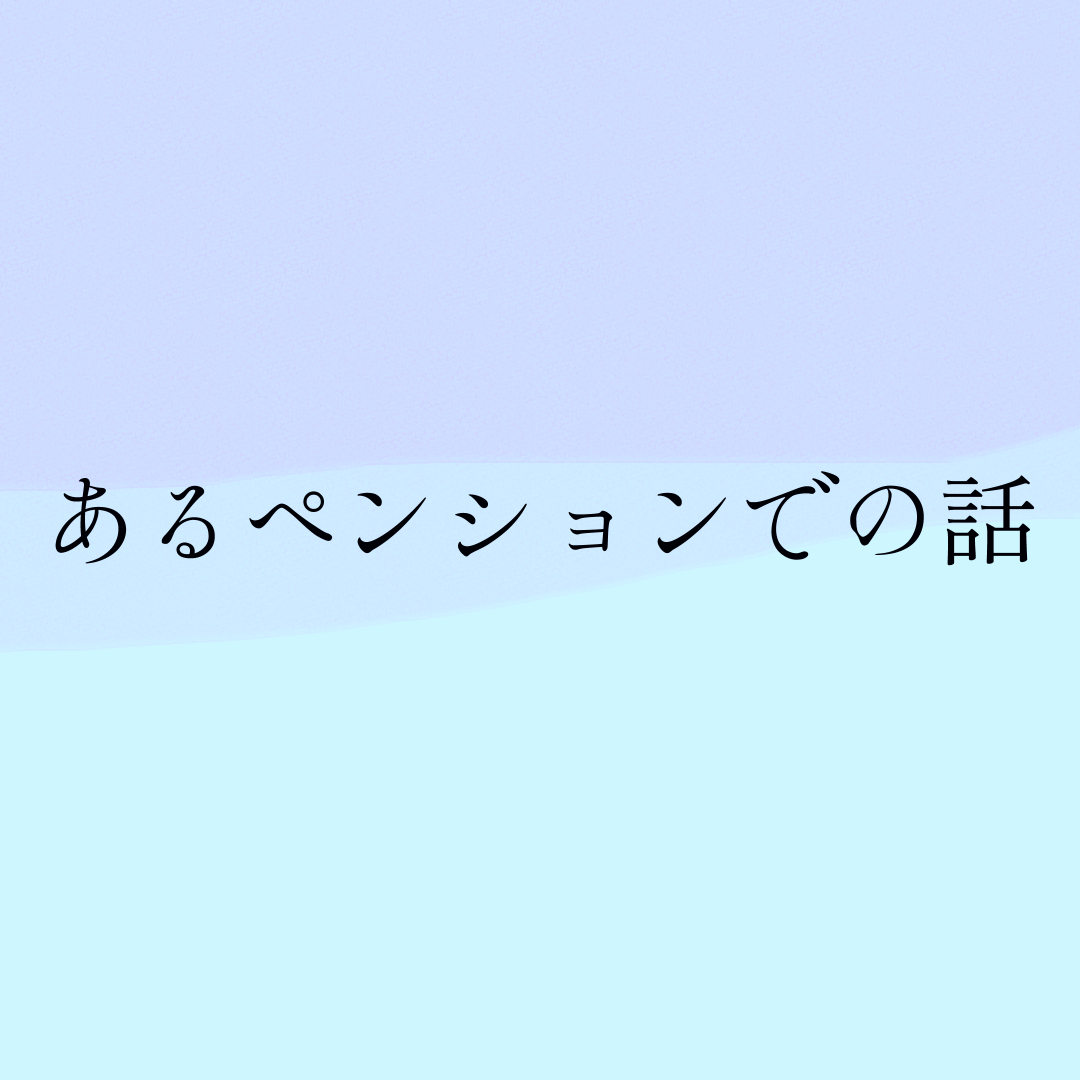
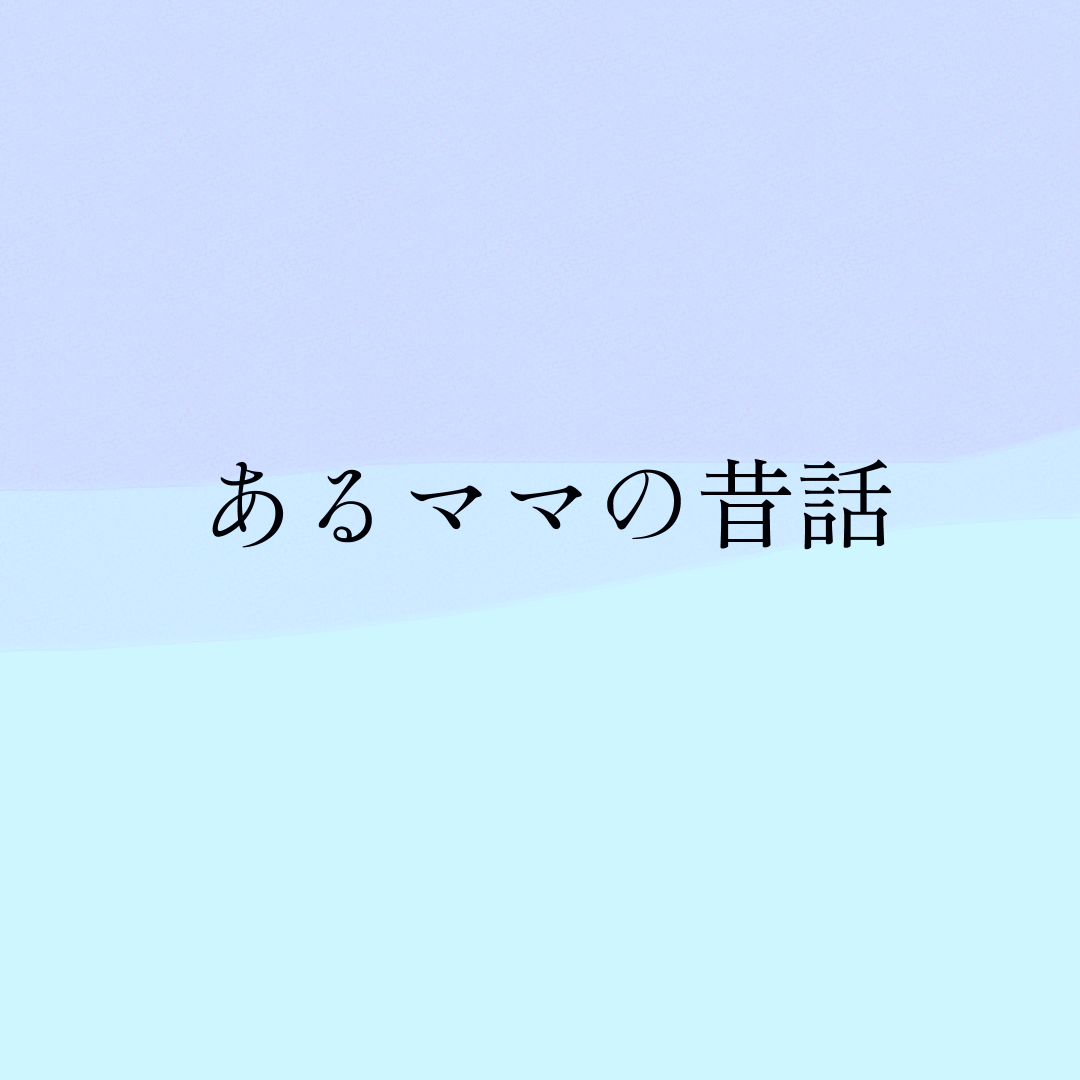
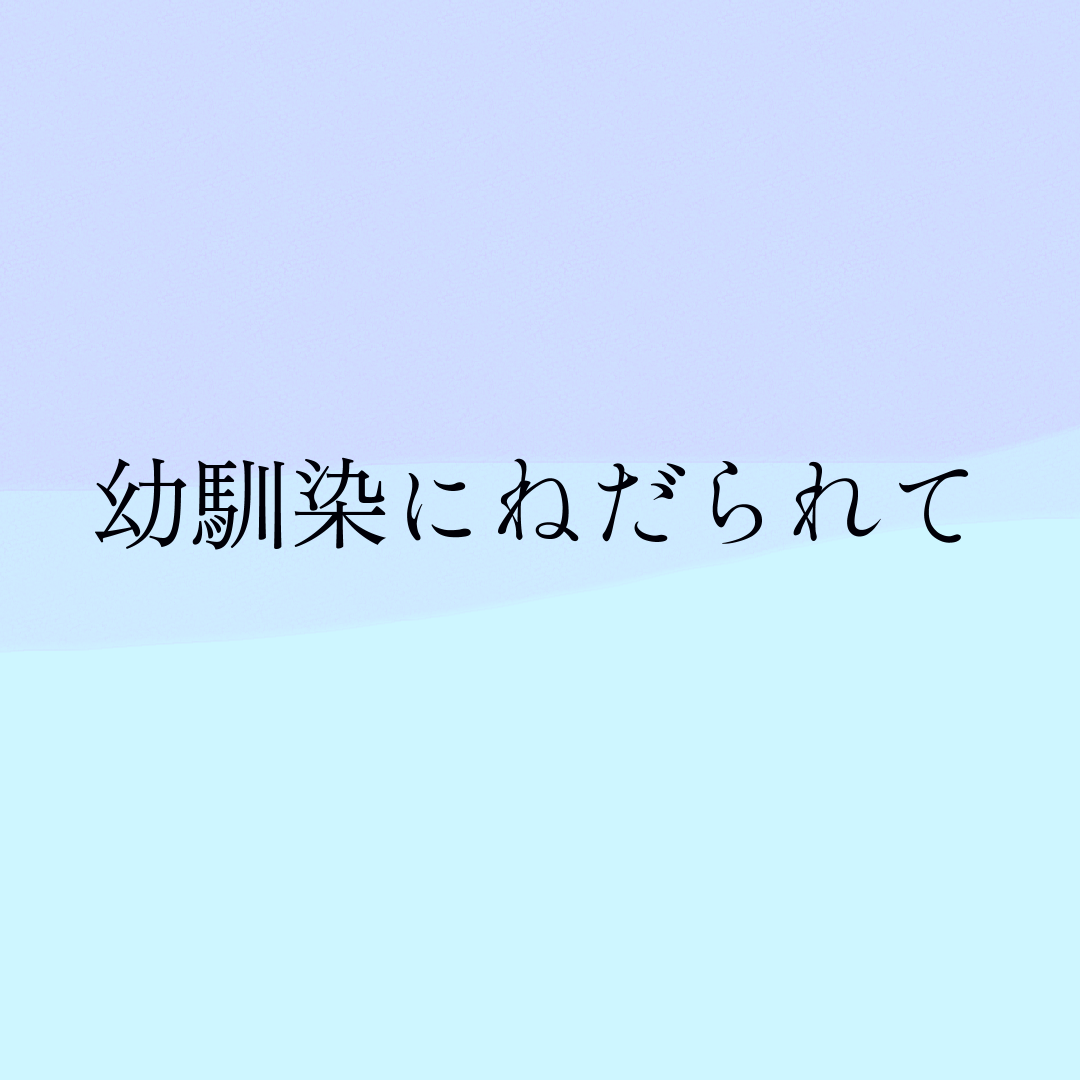
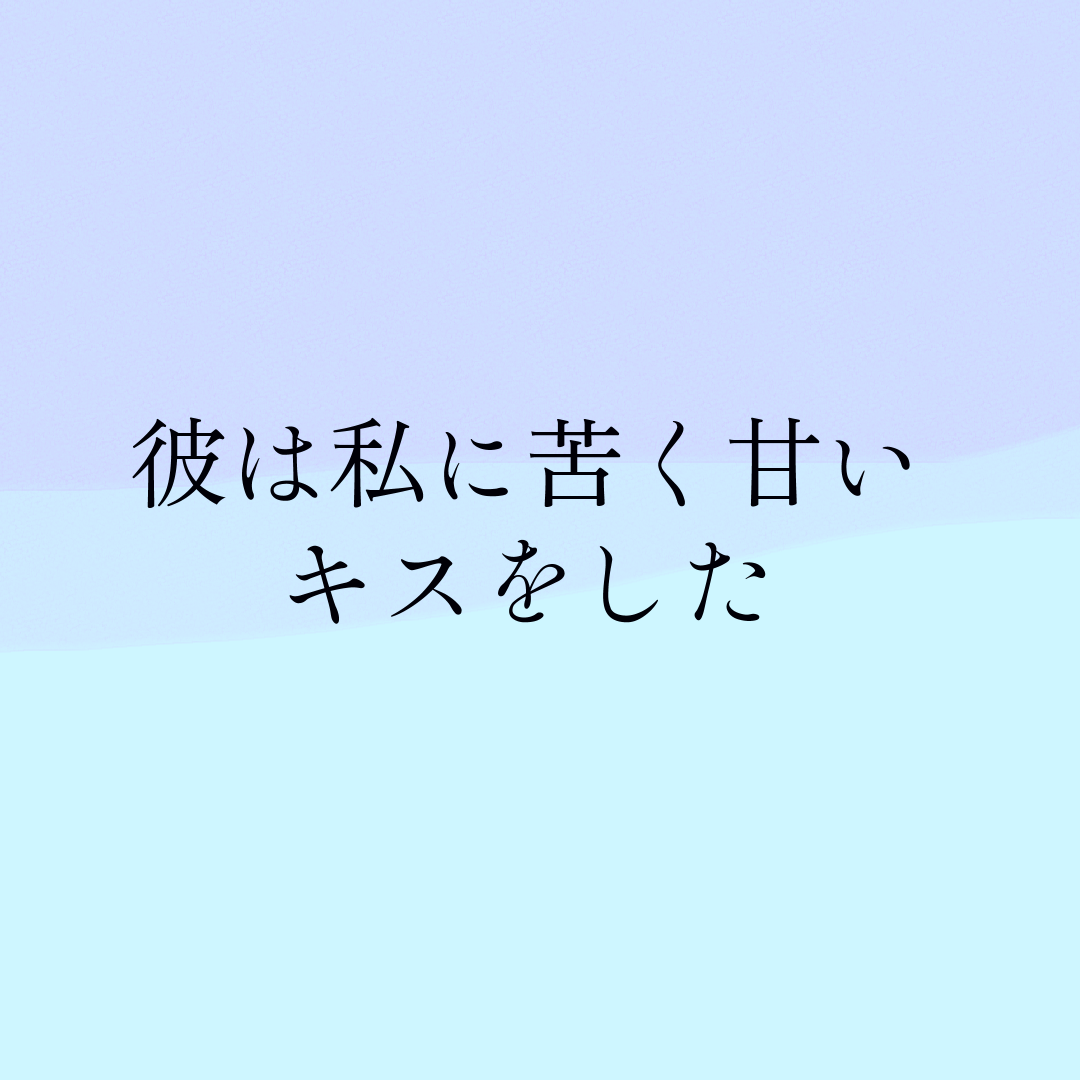
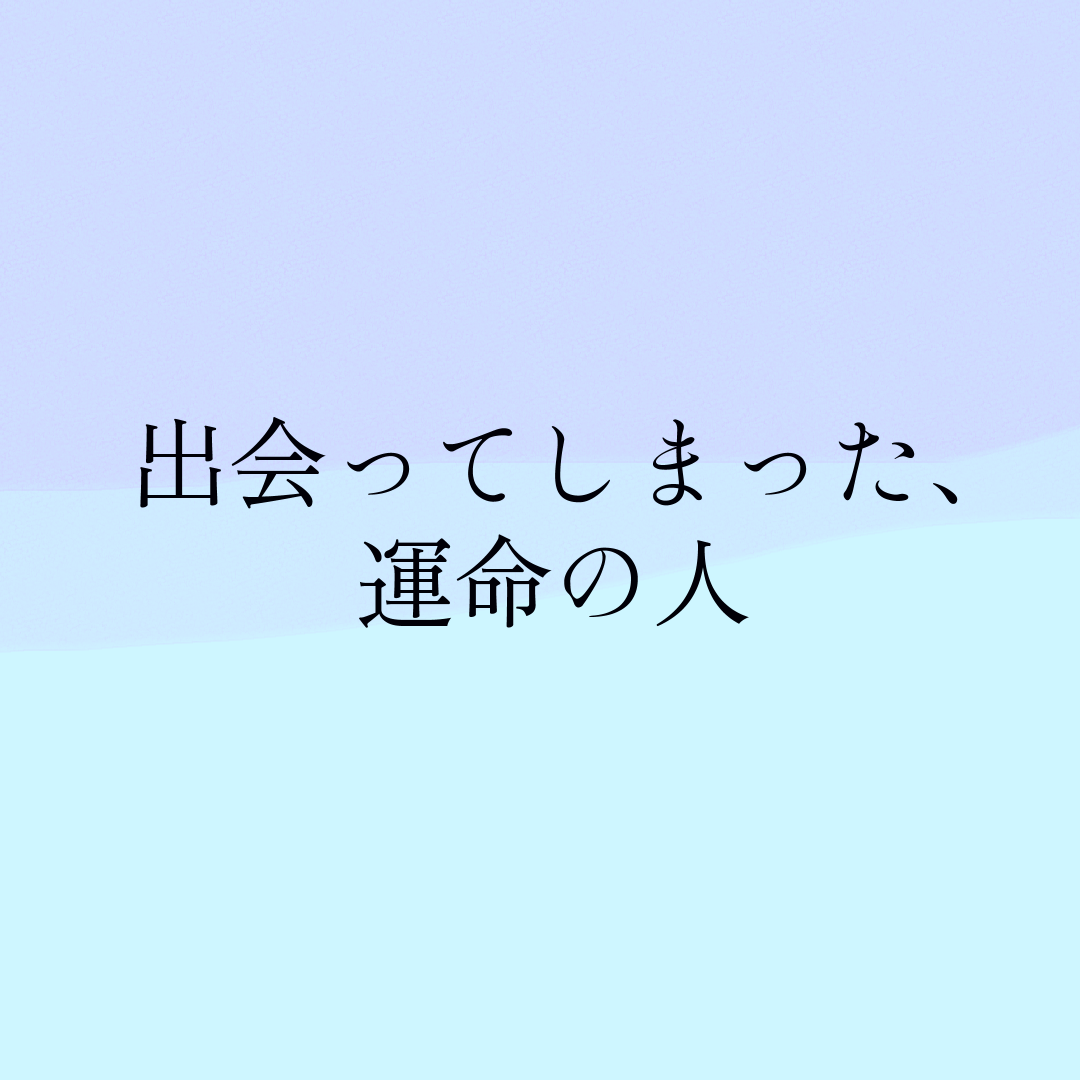
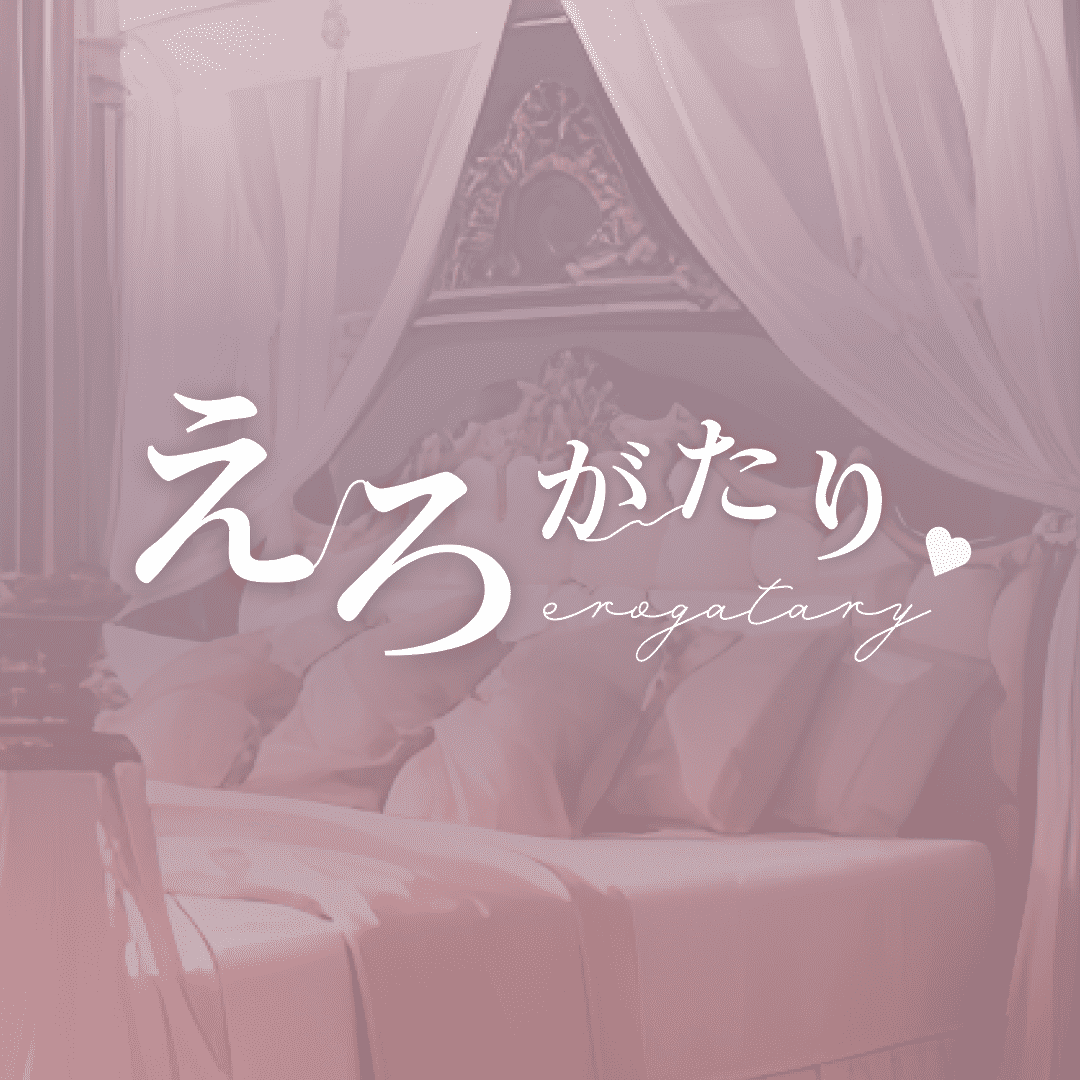
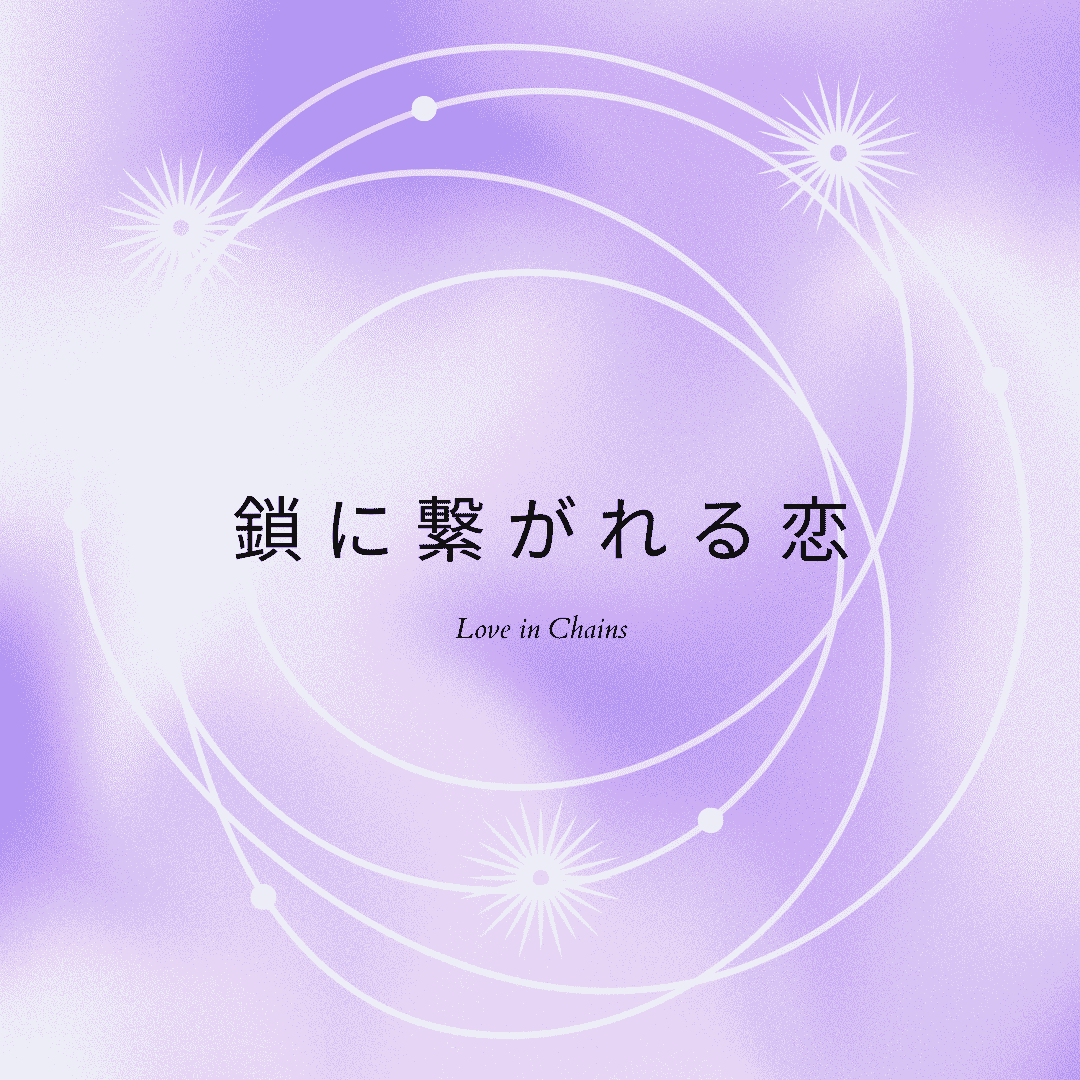



コメント