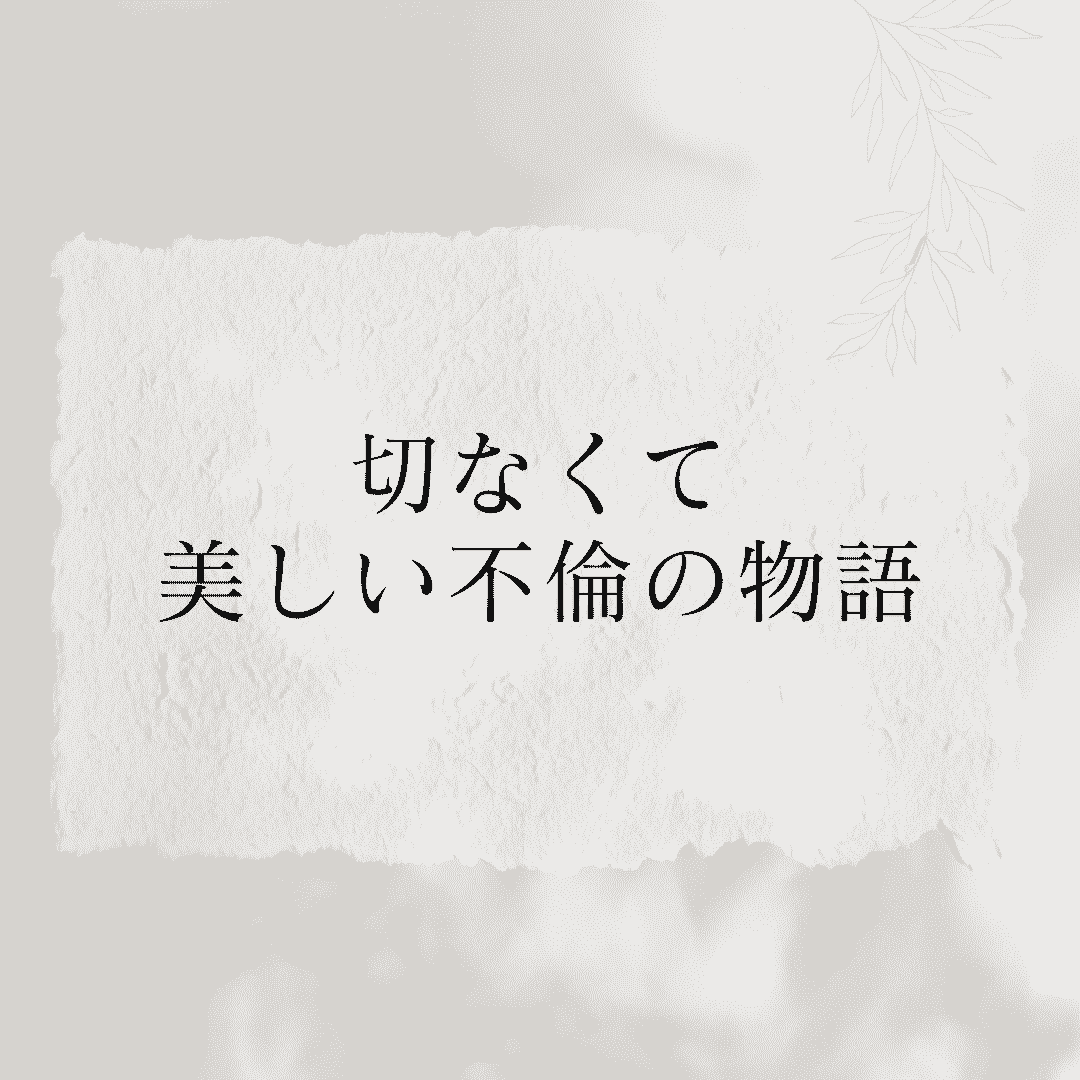
0
切なくて美しい不倫の物語
「あ、おはようございます。」
いつも声を掛けてくれる男性だ。
花に水をやっていると、必ず彼は、声を掛けてくれる。
人懐っこそうな笑みを見せて、瑞々しい花達が咲いている花壇を眺めている。
趣味で始めたガーデニングで育った、愛らしい花達に興味を持ってくれているのが嬉しかった。
彼は花壇の前にしゃがみ込んで、花を眺めては目を輝かせていた。
その横顔はとても爽やかで、まるで太陽のように眩しい。
スポーツマンのような短く黒い髪に、程よく付いた筋肉質な体。
ゆうに180センチは超えていそうな程、高い身長と長い手足。
目鼻立ちもくっきりしていて、まるでその横顔は、彫刻のようにはっきりとしている。美しい横顔だ。
そう思いながら、彼の横顔を眺めていると、ふとぱっちりとした二重の目と視線が交わった。
「今日は、旦那さんいらっしゃらないんですか?」
「え?え、ええ。今日も夜遅くに帰って来るみたい。」
どうしてそんなこと思ったのか、と彼に問い掛けると、ふと困ったように笑みを零した。
「悩みがある時に花壇をぼんやり眺めてしまうって言ってたでしょ?旦那さん、最近帰りが遅いって言ってたから…何かあったのかなって思いまして。」
「…きっと、捨てられると思うの。私は…アラフォーのオバサンだから…彼女より魅力がないのよ…」
こんなこと言ったって、仕方ないことだって分かってる。
けれど、今まで旦那も、私のことを愛してくれていると思っていたのに。
若い女の方へと走って行ってしまったのだ。
欲に溺れて、金に溺れて、女に溺れ続ける旦那は、もう二度と私の元には戻って来ない。
「お前みたいな女よりも、俺は若い女の身体の方が良いんだよ。」
そう告げられてから、突き付けられた離婚届。
私のことを愛してると言っていってくれていた旦那は、あっさりと私を捨てたのだ。
そう考えるだけで胸が苦しくて、視界が滲み、頬に熱い涙が流れ落ちた。
「…ごめんなさい、こんな所で…あなたに話すことでもないのにね…」
こんなみっともない顔を、彼に見られたくなくて、その場から逃げるように立ち上がった。
けれど、グンッと強く腕を掴まれ、そのまま家の中に押し込まれた。
ギュッと強く抱き締められる身体に、更に涙が溢れる。
きっと情けない姿を、見ていられなくなったのだろう。
それでも、彼の優しい温もりに期待をしてしまうのだ。
若い女に溺れて、私を見てくれない旦那からの愛の言葉も、優しい温もりでさえも、もう二度と感じられないのだから。
「…俺はそんなこと思いません。こんなに、魅力に溢れている人に、惚れてしまった奴がいるのだから…」
弱気になっていた心を埋めるように、彼の温もりが嬉しくて涙が溢れる。
すっぽりと彼の腕に収まる私の身体に、思わず彼の背中に手を回した。
自分を必要としてくれる人がいる。
そう思うだけで胸が高鳴って、縋るように彼に強く抱き着いた。
「好きなんです。あなたが落ち込んでいた俺に優しく話し掛けてくれた時から…結婚していようと、ずっと俺はあなただけを見てきたんです。」
ジッと強い眼差しで、私を見つめてくれる彼の視線と交わり、ゆっくりと唇が重なった。
少し乾いた唇と一瞬重なり、もう一度、もう一度と何度も繰り返し軽いキスをする。
啄むように何度もされるキスは徐々に深いものに代わり、上唇をジュルッと吸い付かれ、今度は下唇を軽く甘噛みされた。
そして、薄らと開いた唇の隙間を割り開いて、彼の肉厚な舌が逃げる舌を追い詰める。
久しぶりの感触に、ビリリッと電気のような快感が背筋を走り、思わず彼の背中に回していた腕に力が籠る。
ねっとりとお互いの唾液が交わるように、いやらしい水音が響き出した。
「は、ふッ、ぅ…ん、ぁッ…は、ぁ…ッ」
「やっぱりあなたは可愛い。ちょっとキスしただけなのに、こんなに蕩けちゃうなんて…」
大きな手が私の頬を撫でて、うっとりと目を細めている。
旦那とさえ、キスしたのなんていつか覚えていない程していないのに。
久しぶりの強い快感を拾った身体は、既に力も抜けていて、彼に縋り付くことしか出来なかった。
彼の背後から鍵の締められる音が聞こえて、ゆっくりと廊下に押し倒された。
目を細めて私を見下ろす彼の目は、いつもの穏やかさなんてなくて、今にも食われてしまいそうな程に鋭いものだった。
こんなに自分に情欲を向けてくれる彼に、期待が高鳴り、乾いた喉を潤すように息を飲んだ。
早朝だったこともあって、軽い化粧だけをしただけで、綺麗な衣服も身に付けていない。ただのラフなロングワンピース。
自分の格好を意識してしまうと、ふと恥ずかしさが込み上がり、頬に熱が集中する。
「もう、我慢出来ないんです…あなたが欲しい…」
「…こんなオバサンで良いの?魅力なんてないし…旦那に捨てられるような…こんな女なんて…」
「オバサンなんて…そんなこと言わないで。あなたはあなただ。何もかもが綺麗で、俺はあなたの優しい所に惹かれたんだ。」
強い信念が籠っているような目で言われ、一気に顔に熱が集中してしまう。
真っ赤になった顔を抑えて、彼から顔を逸らすとチュッと軽いリップ音と共に、頬から首筋、鎖骨に掛けてキスをされる。
決して痕を残してはくれないけれど、彼は何度も首筋に甘く吸い付いて、何度もキスをしてくれた。
甘い痺れが背中に走って思わず、足をゆっくりと動かしてしまった。
それに気付いた様子で、はだけたワンピースの中に手を入れて、太ももに指を這わせて、ショーツの方までワンピースを捲り上げられた。
顕になる下着と、若い頃よりも張りのない体を想像してしまい、途端に恥ずかしくなる。
「ん、ぅッ…や、やっぱり…やめましょ…こんなみすぼらしい体なんて…ッ」
「…そんなに悲観的になるなら、俺があなたの魅力を引き出してあげますよ。」
彼は小さくため息を吐いて、熱を孕んだ目でジッと見つめて、少し乱暴にショーツを剥ぎ取ってきた。
突然のことに驚いて、大きな悲鳴をあげてしまった。
そして彼は、いとも容易く私の両足を大きく左右に割り開いて、ねっとりと愛液の滲む膣を凝視する。
「や、ぁッ!?ちょ、っと、まってッ…!そん、なところ…ッ!いや、ぁッ…!」
彼は悲鳴をあげる私のことを無視して、そのまま大きく口を開いて、舌を突き出して見せた。
一瞬、ジッとこちらに視線を寄越して、私の反応を楽しむような素振りを見せて、すぐに膣に吸い付いたのだ。
「ひ、うぅぅッ…!?」
感じたことのない火傷しそうな程の熱さと、ねっとりとした体液に包まれる膣に、大きく腰が震えた。
ぴったりと唇を膣に吸い付いて、突き出していた舌で、クリクリと膣の入口をつつき始める。
ビクンビクンと激しく痙攣する腰を振り乱し、強すぎる快感に目眩すら覚える。
「や、だッ!やだやだッ、ぁぁ!そ、ん…やめッ…ッ!きたなッ…からぁぁ、ッひうぅ!!」
「汚い所なんてないんですよ。あなたはこんなに綺麗なのに、どうしてそんなに悲観的になるの?なら俺が分からせてあげますね。あなたが綺麗だということを。」
さも楽しげな声色で熱すぎる吐息を吐いてすぐ、彼の舌がグリッと膣の中に入ってくる。
突然の異物感と、感じたことのない感触にガクガクと腰が震えて、顔を隠すように両手で顔を覆った。
恥ずかしくて堪らなかった。
旦那にすらそんなことされたことなんてないし、自分ですら、そこまでふしだらなことはしたことないのに。
それなのに、彼は汚いなんて気にもしないで、ジュルジュルッと秘豆を吸い上げながら、舌でグニグニと中を虐めてくる。
あまりの強い快感に背を仰け反らせて、悲鳴をあげながらガクガクと腰を震わせてしまう。
腰を引きたくてもがっしりとおっぴろげられた両足は、身動き一つできなかった。
「ひ、ぃぃぃッ、あぁッ、やだやだッあぁ!やめ、てぇッ、なか、ぁぁッグリ、グリぃ、しないでぇッ…!!」
「んぶ…ッ…それは出来ないお願いかな。これからもっと凄いことするんだから…」
ドロっと唇から愛液か、唾液かも分からない体液を滴らせて、うっとりと目を細めて笑みを見せた。
何とも男らしい表情に思わず喉が鳴って期待に胸が弾む。
浅い呼吸を繰り返し、彼は身体を起こして左右に開いた足の間に割り込んだ。
まだ膣内に彼の舌の感触が残っている気がして、ヒクヒクと膣内が収縮して、彼を誘っているような気がした。
ぷっくりと膨らんだ秘豆をクリっと軽く弄られて、腰が大きく揺れた瞬間だった。
ズルンッと首をもたげた、今まで見たことない程、太くて逞しい陰茎が姿を見せたのだ。
舌なめずりをして、私を見つめる彼に反応するように、更に上へ上へと硬度の増していく陰茎に、恐ろしさすら感じてしまった。
旦那のよりも二倍もありそうな太い陰茎は、赤黒く、くっきりと血管も浮き出て、ヒクヒクと尿道を収縮させている。
「そ、それ…挿れる、の…?」
「そうですよ…これがあなたのここまでクるんです。ずっぽりとね。」
昔よりたるんでしまった下腹部をスリッと撫でて、ここまで来るのだと指でなぞられる。
思わず、ひくっと喉が震える。
そんな太いのが、そんな所まで来てしまったら…。
そう想像してしまうだけで、恐怖でガチガチと歯が唇が震えた。
怖い。
怖いという思いの方が、何よりも強かった。
けれど、それに反して、ビクンビクンと揺らめく陰茎を見るだけで、膣内からは止めどなく愛液が溢れてきていた。
頬を伝う涙を彼が優しく拭ってくれて、笑みを見せたのに気を取られた直後。
ゴリゴリッと肉壁を割り開きながら、今まで感じたことのない強い圧迫感を膣内に感じた。
「んッ、あぁぁッ!?ひ、ぎぃ、あ、ぁぁッ、こわ、いぃッ…!」
「うんうん、そうだね。怖いね。だけど、俺もう我慢できないんです。こんなに乱れるあなたを見てたら…」
ググッと更に奥へ奥へと押し込もうとしてくる陰茎の感触に、堪えきれない喘ぎ声が漏れ出す。
唇を噛み締めても耐えきれない声が、ひっきりなしに口から漏れてしまう。最初はゆったりと動いていた腰が、何かを探るように速度をあげて、ゴリゴリと激しく突き上げてきたのだ。
「ひ、うぅッ!!んあ、んんぁぁッ!やだ、ぁぁッ、そ、こぉ、ぉッ!や、ぁぁッ!」
両手を強く押さえ付けられて、足を強く伸ばしてゴリゴリと最奥だけを突き上げ続ける彼に、等々耐えきれずに達してしまった。
ビクビクと痙攣する膣内などお構い無しに、更に質量の増した陰茎で子宮口だけを突き上げられて、背を大きく仰け反らせて喘ぐ。
止めどなく溢れ出す愛液は、徐々に量も増していき、バチュバチュと大きな水音を立てている。
臀部に伝い落ちるのは、愛液かそれとも彼の先走りか。
どちらか分からないまま、止めどなく溢れ出すヌル付く体液が、フローリングを濡らしていった。
ゴンゴンと子宮の入口を突き上げられて、ひぐっと大きな悲鳴を漏らした瞬間、陰茎が大きく脈打つのを感じた。
「ああ…出そう…出る…で、るッ…!」
「ひ、ぃぃ、ッ、ひぐッぅ、やだやだッ、だめぇッ…そと、だし、てッえぇ…!なか、だけ、はぁ、んあぁッ!?」
バチュンっとより一層激しく突き上げられて、深々と根元まで埋まった陰茎を外に出す仕草など一切見せずに、私の願いも虚しく、ドプンッと感じたことのない精液の量が膣内に吐き出されたのを感じた。
ビクビクと大きく脈打ち、ドプドプと吐き出され続ける精液は、しっかりと子宮口の前に吐き出されて、下腹部からコプコプと、まるで飲み込んでいるような音が聴こえてくる。
痙攣する膣内と、吐き出される快感の波に身体の痙攣が止まらなかった。
ヒクヒクと震える身体と、まだまだ吐き出される精液の量に自然と涙が溢れて、弱々しく彼の身体に縋り付いた。
「ひ、ぃ…ッぅぅ…ま、だ、でて…る…ッぅ…」
「すみません…俺量が多いんです…でも俺は、あなたが妊娠してくれたら、嬉しいですけどね。」
「ば、かッ、いわな、いでぇ…ッひ、ぃ、ひんッぅ…」
やっと出し終えた陰茎が萎えて、膨大な質量が膣内から抜けていく。
ぽっかりと陰茎の太さに馴染んでしまった膣内からは、大量に精液が逆流し、コプコプと溢れ出てくる。
勿体ないと思う反面、もし本当に彼との子供が出来たら、と想像するだけで嬉しくなる自分がいた。
ゆっくりと近づく彼が、私に優しくキスをして柔らかい笑みを見せてくる。
「俺と結婚して、温かい家庭を築きましょうね。」
そう言ってくれる彼の言葉に、どうしようもない嬉しさが込み上がり、今までの旦那からの冷たい態度のことなんて、すっかり頭から消えていた。
私だけを愛してくれる彼の情欲に、私はただただ、身を預けて溺れるのだった。






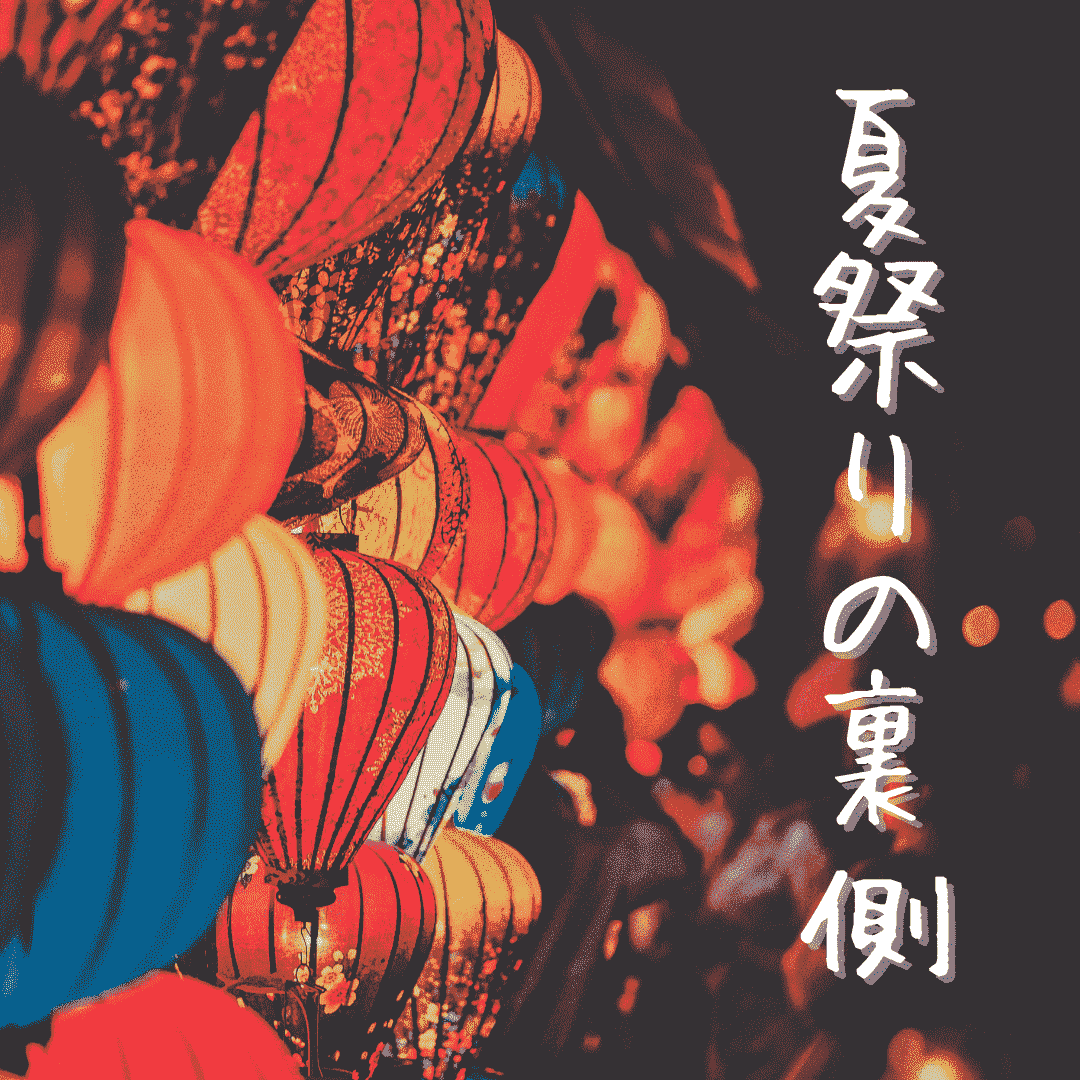

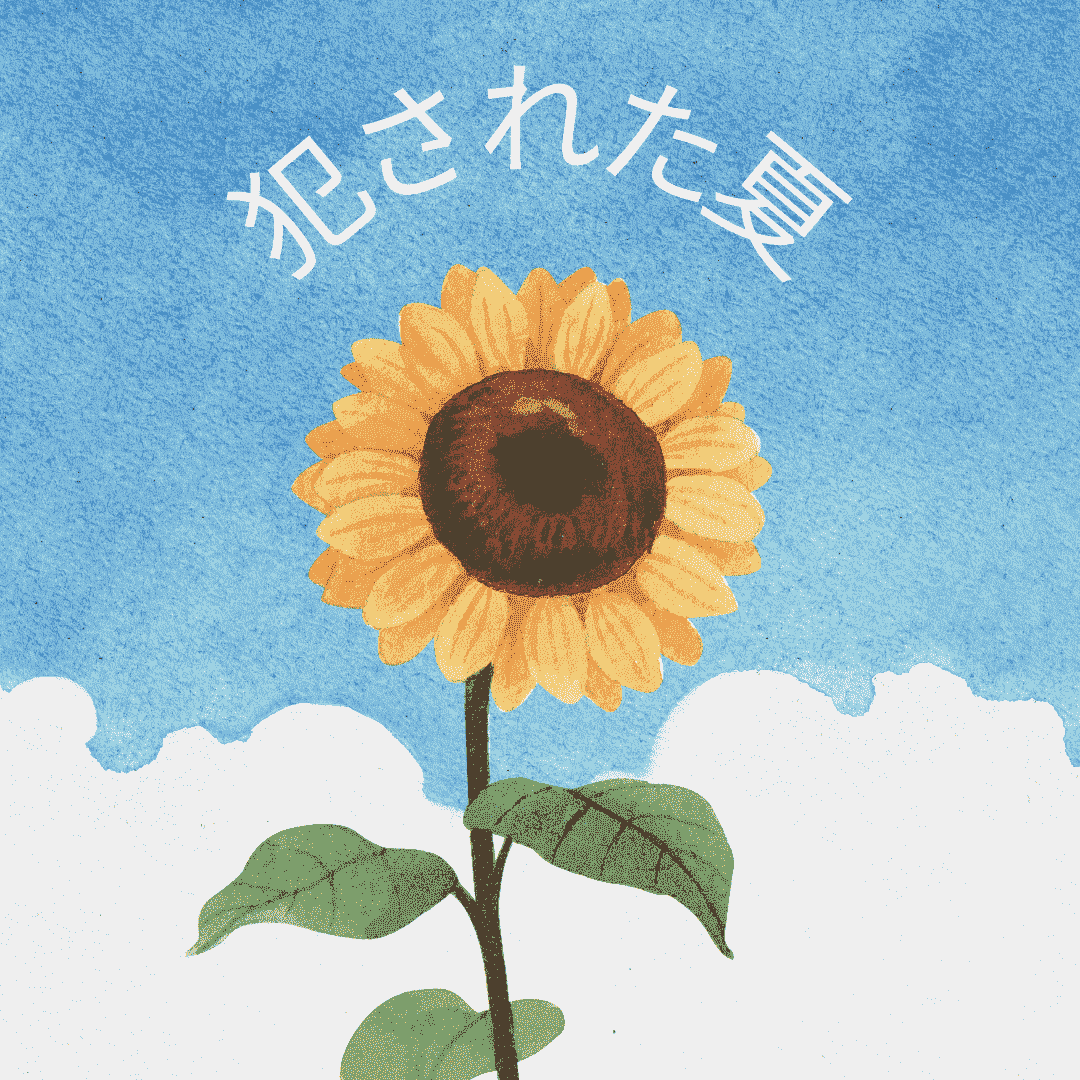


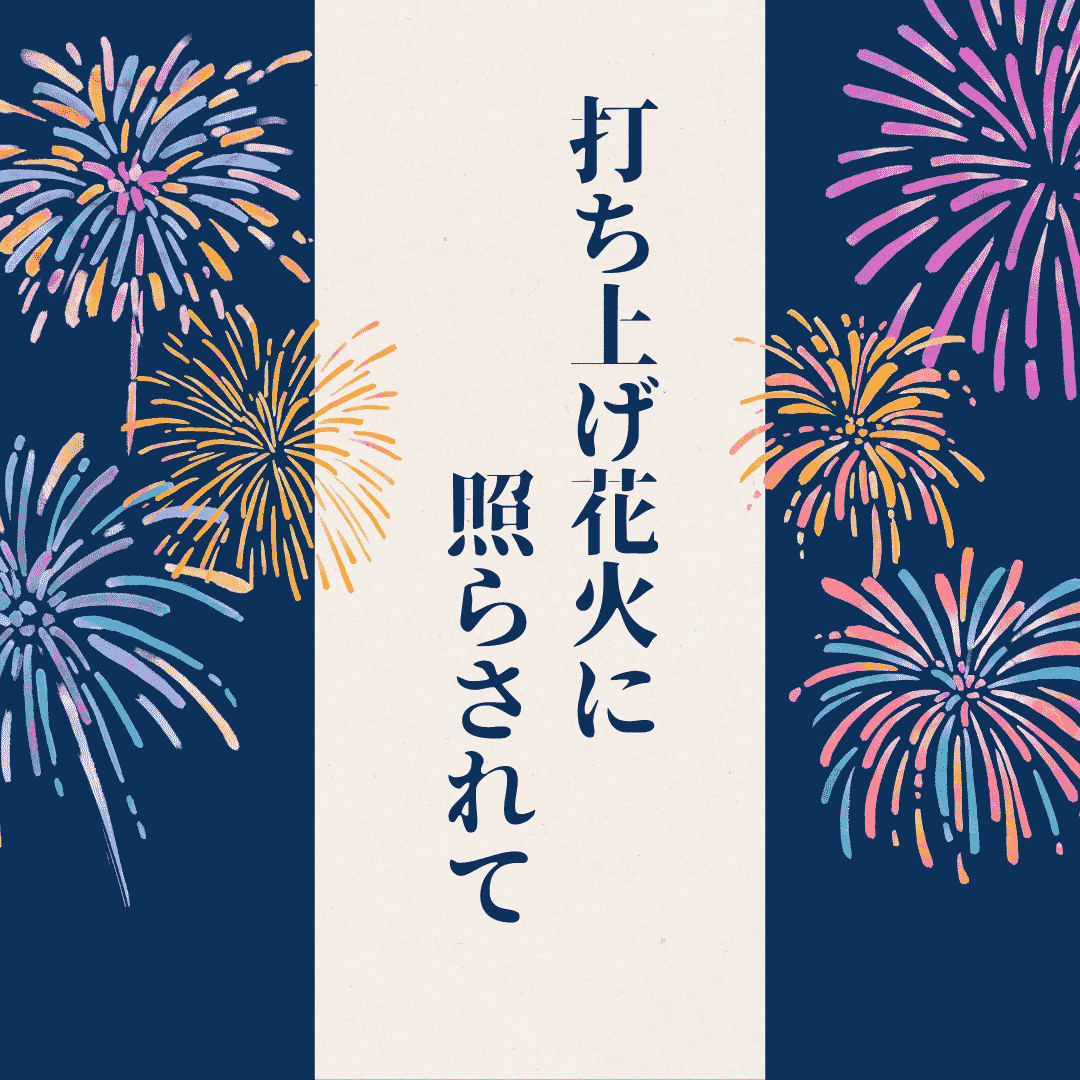

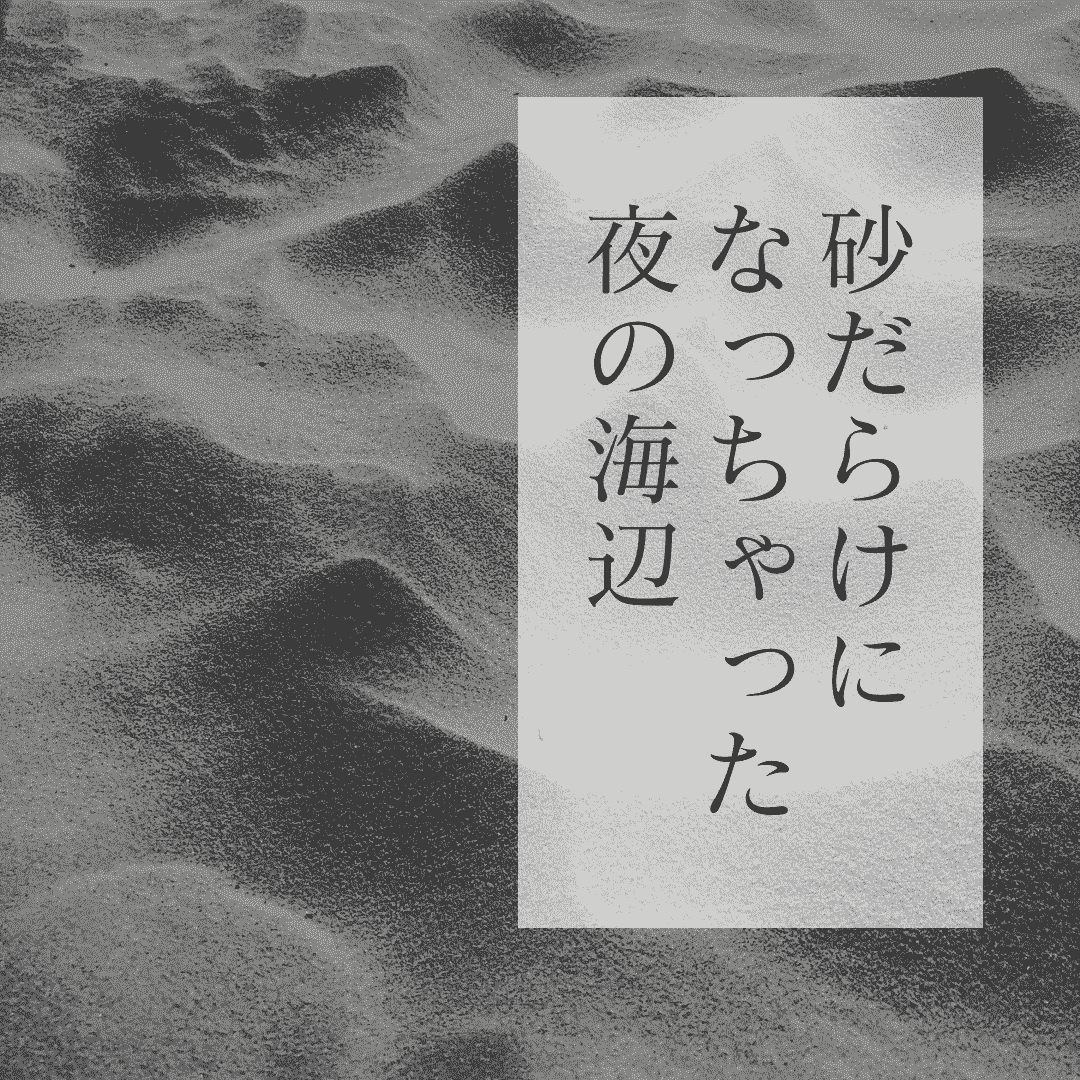

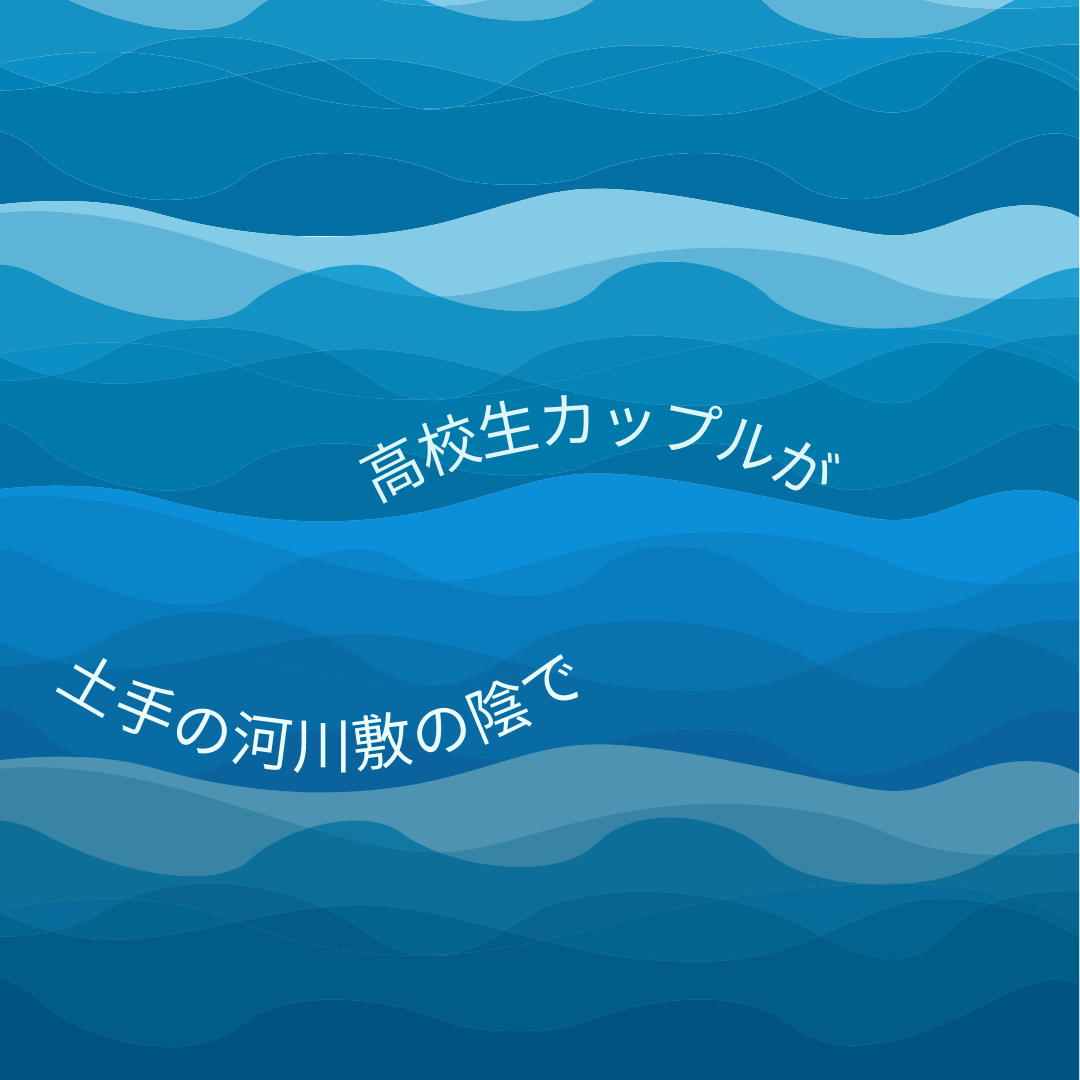


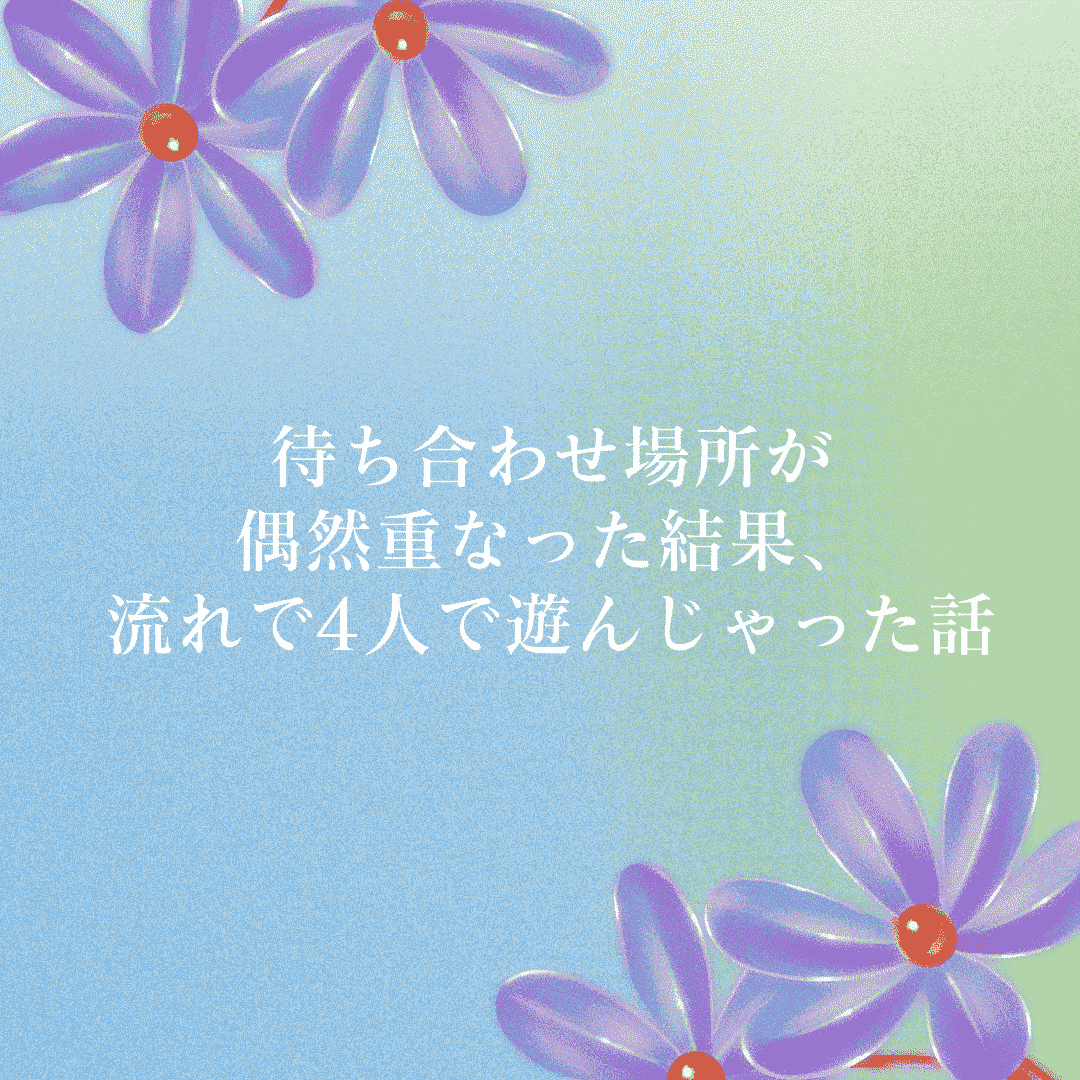




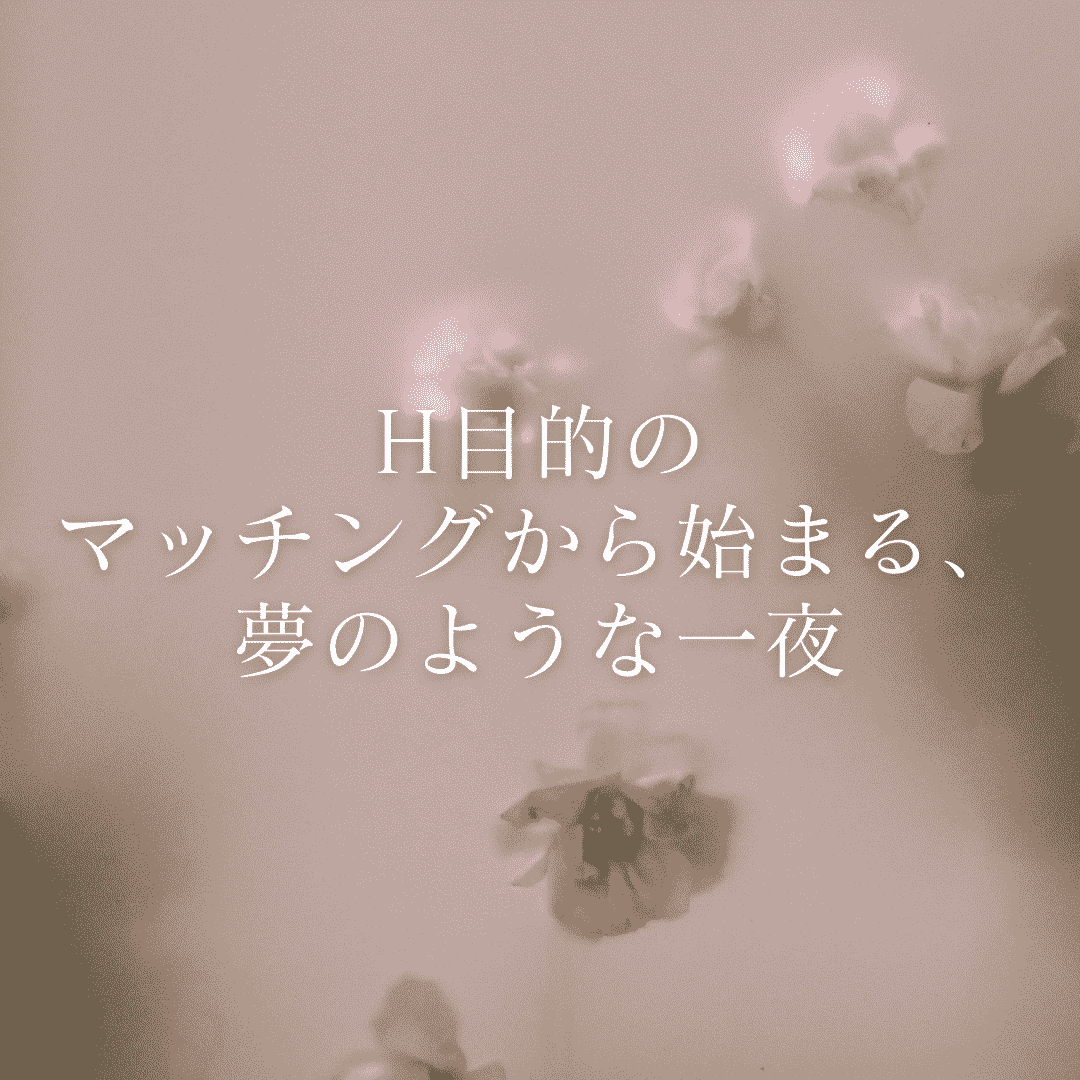

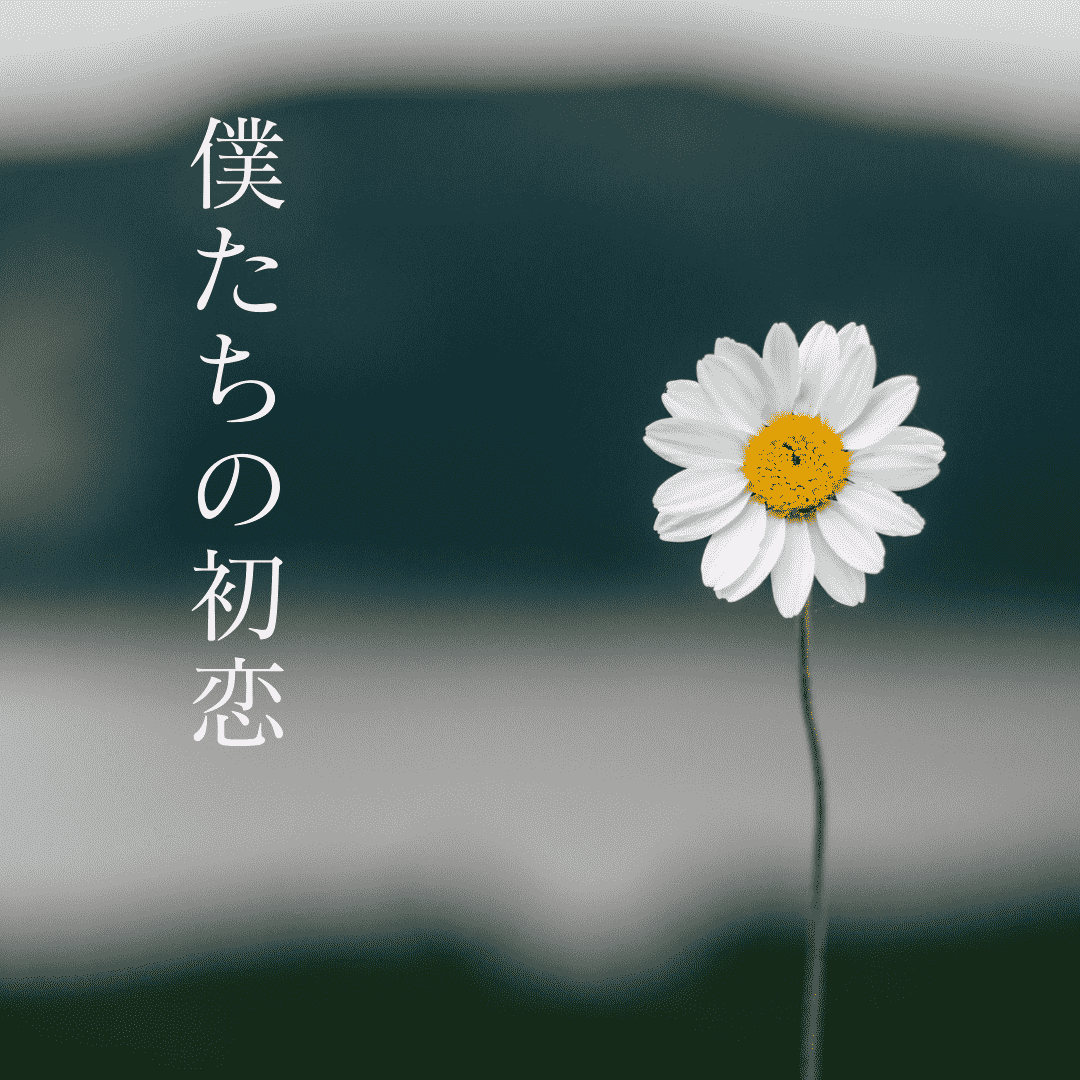


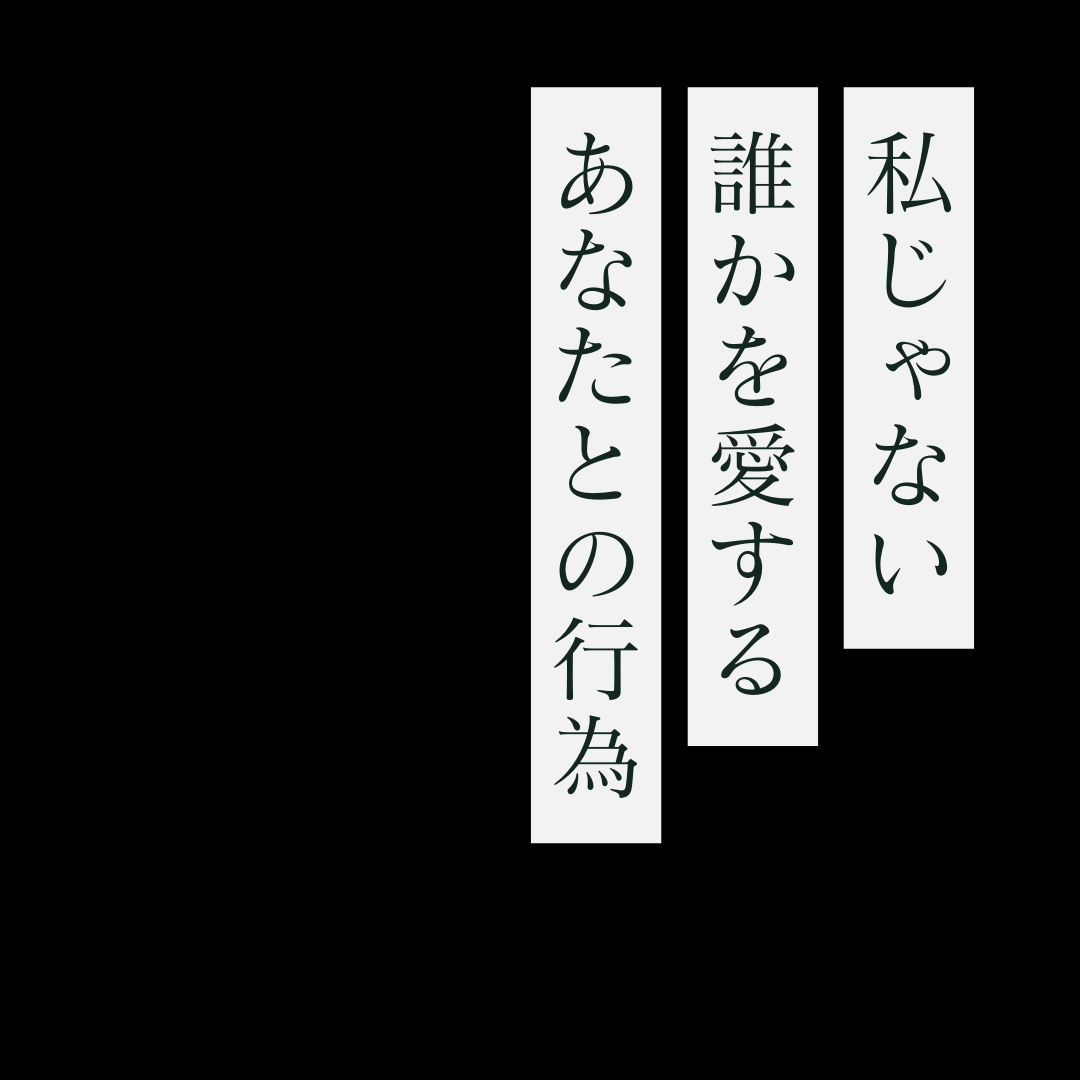

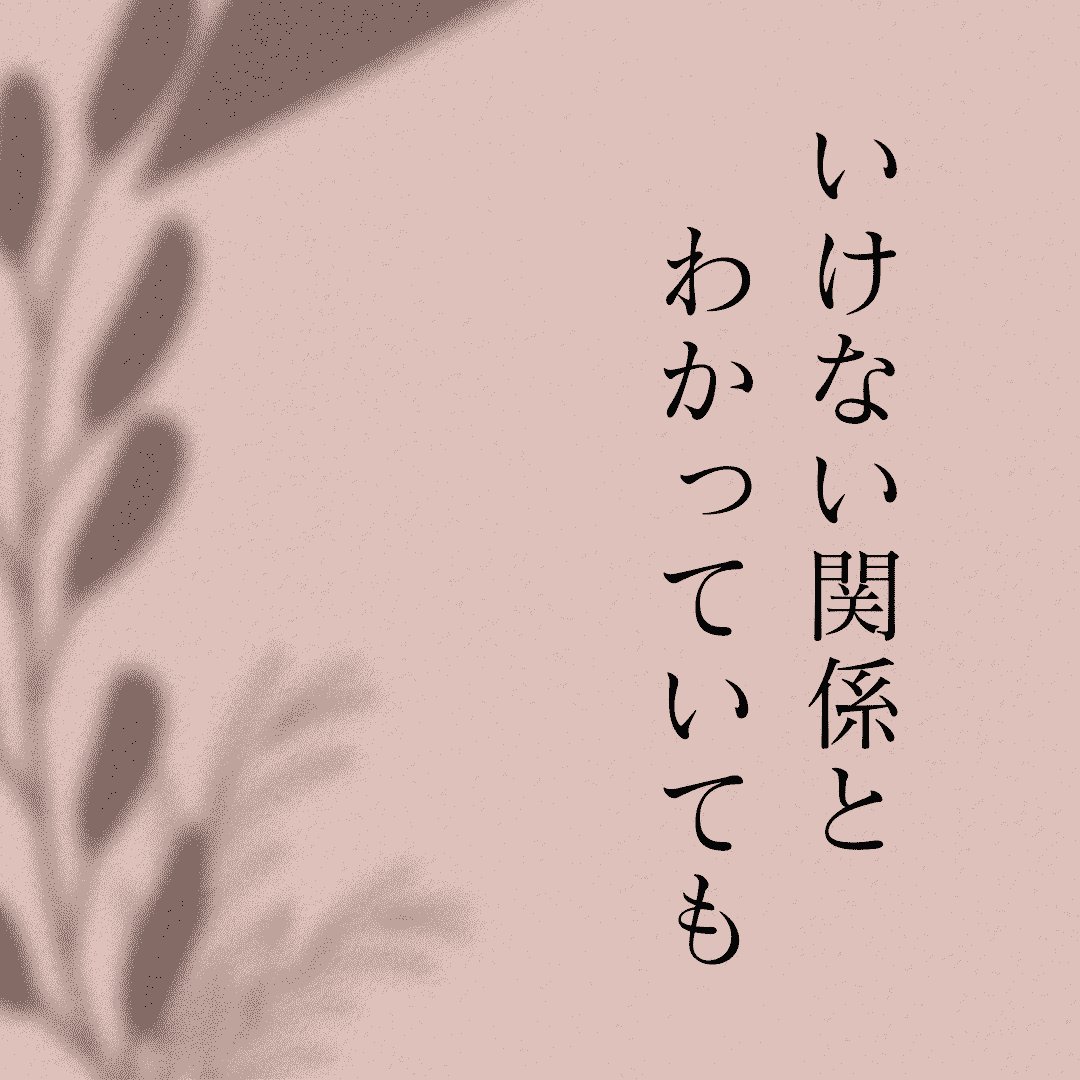









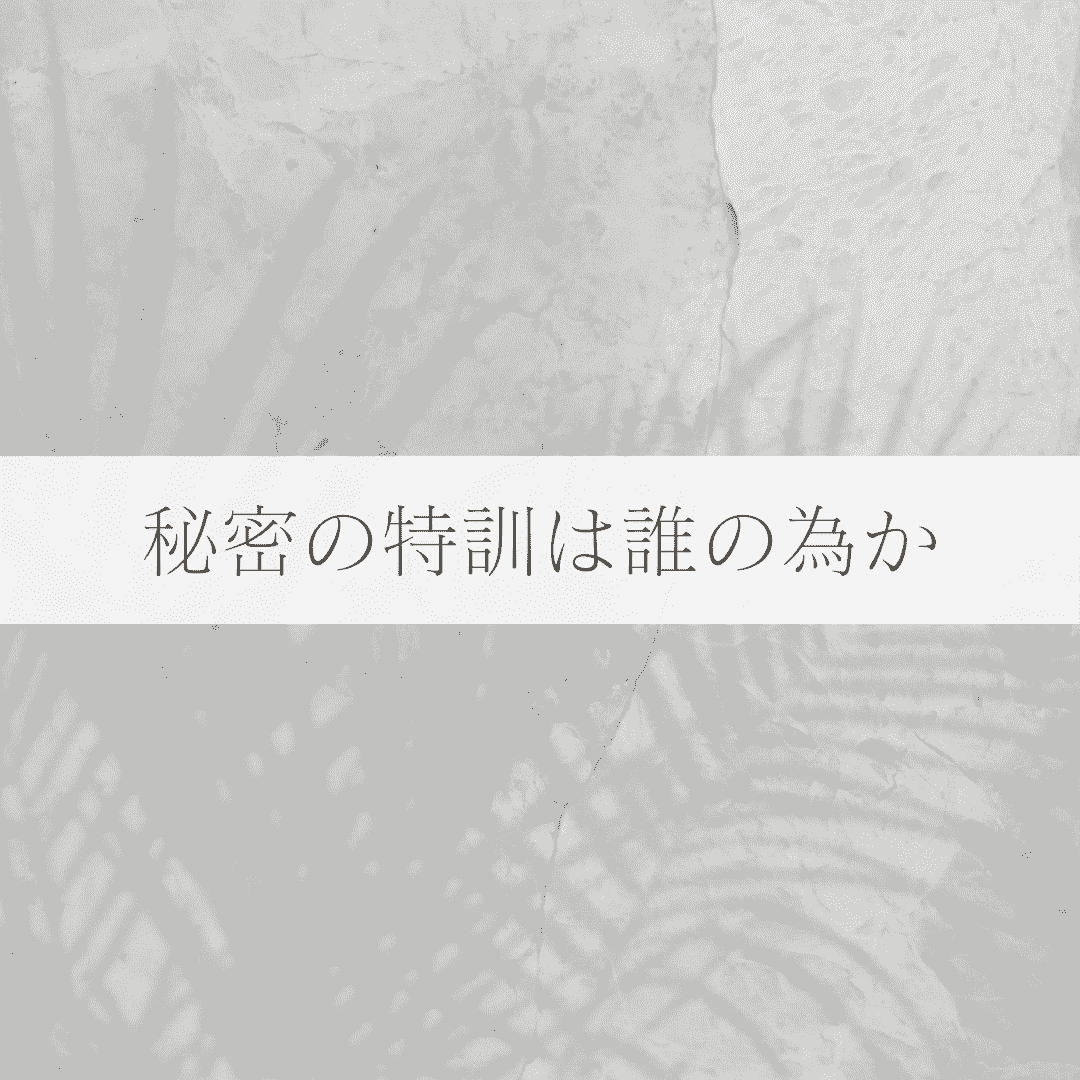
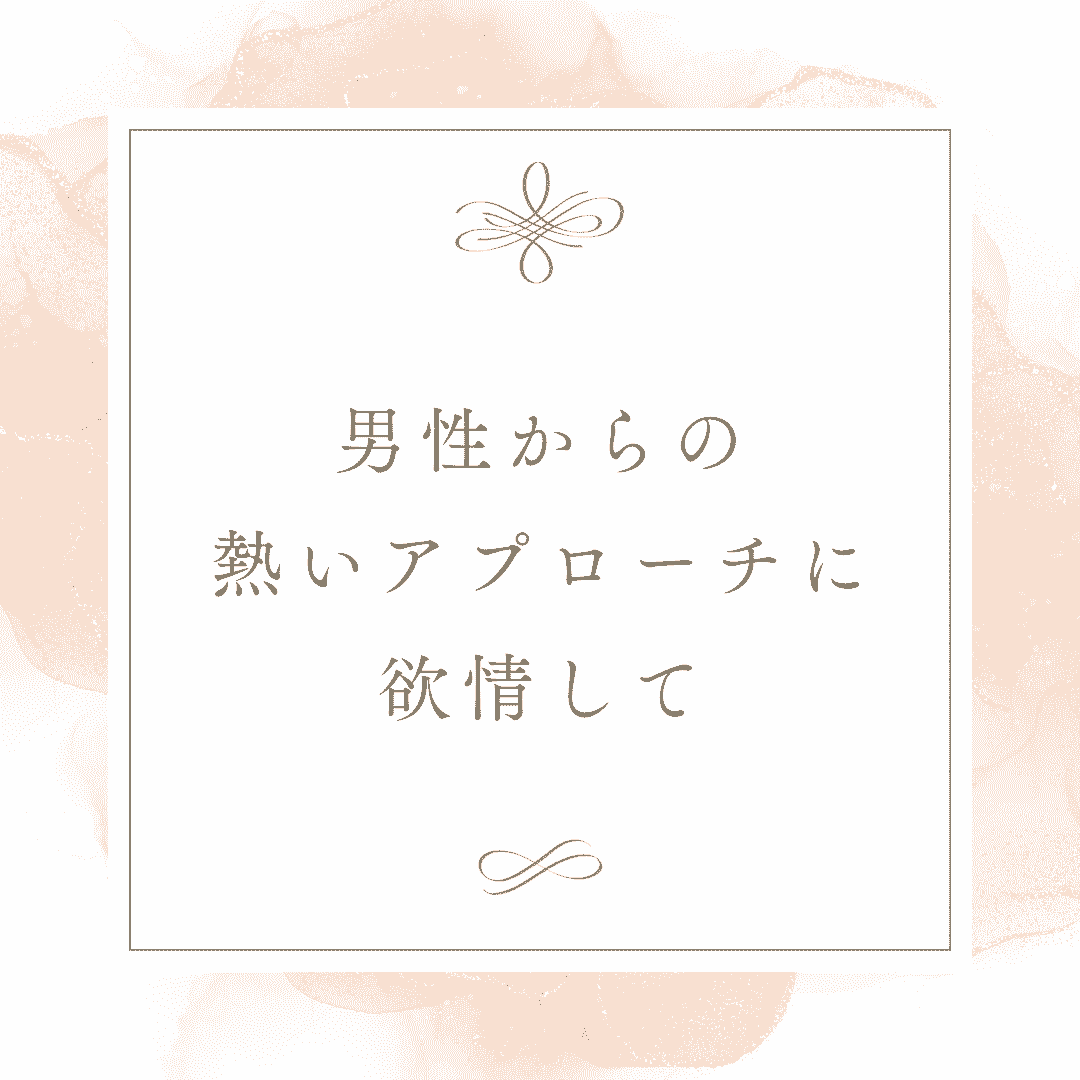


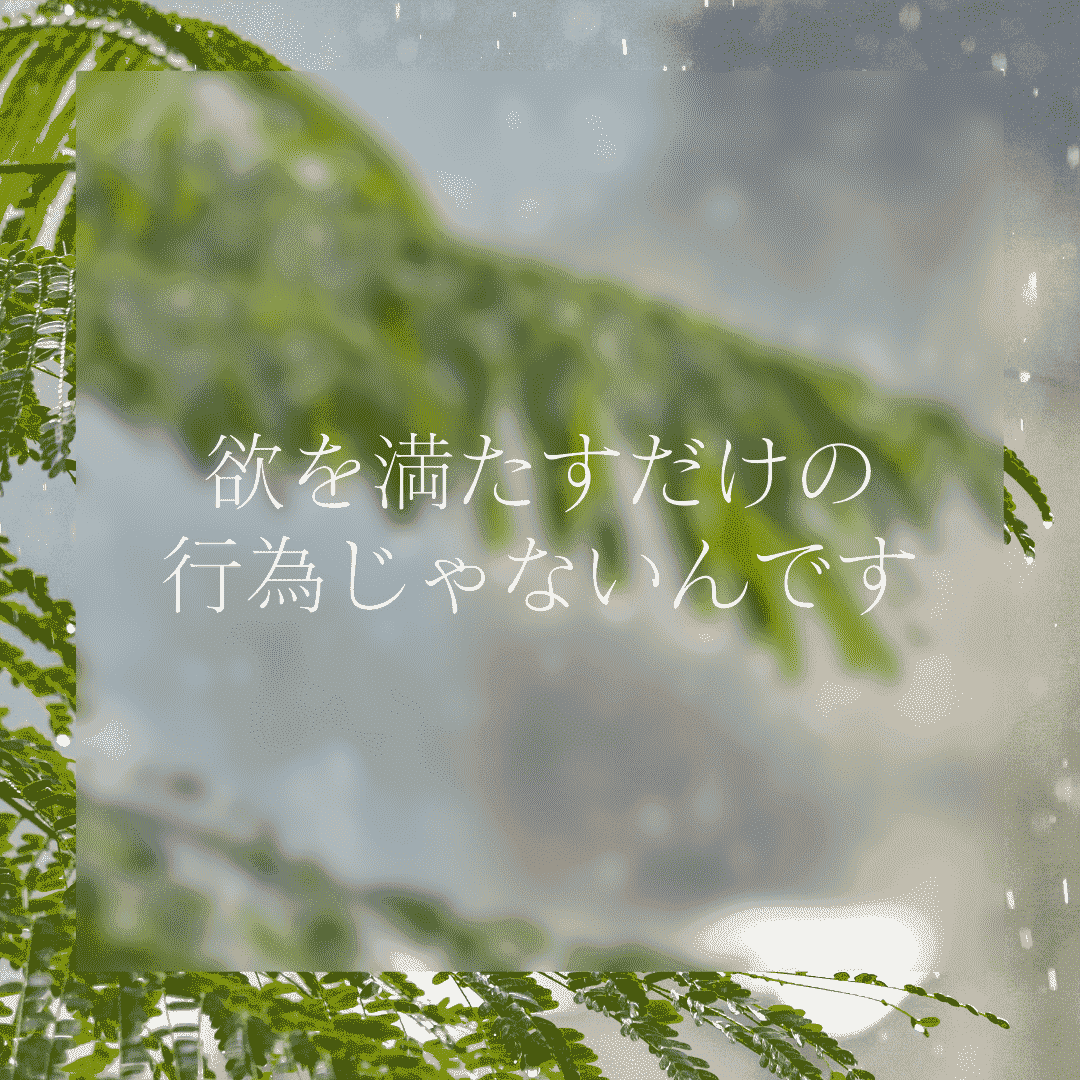

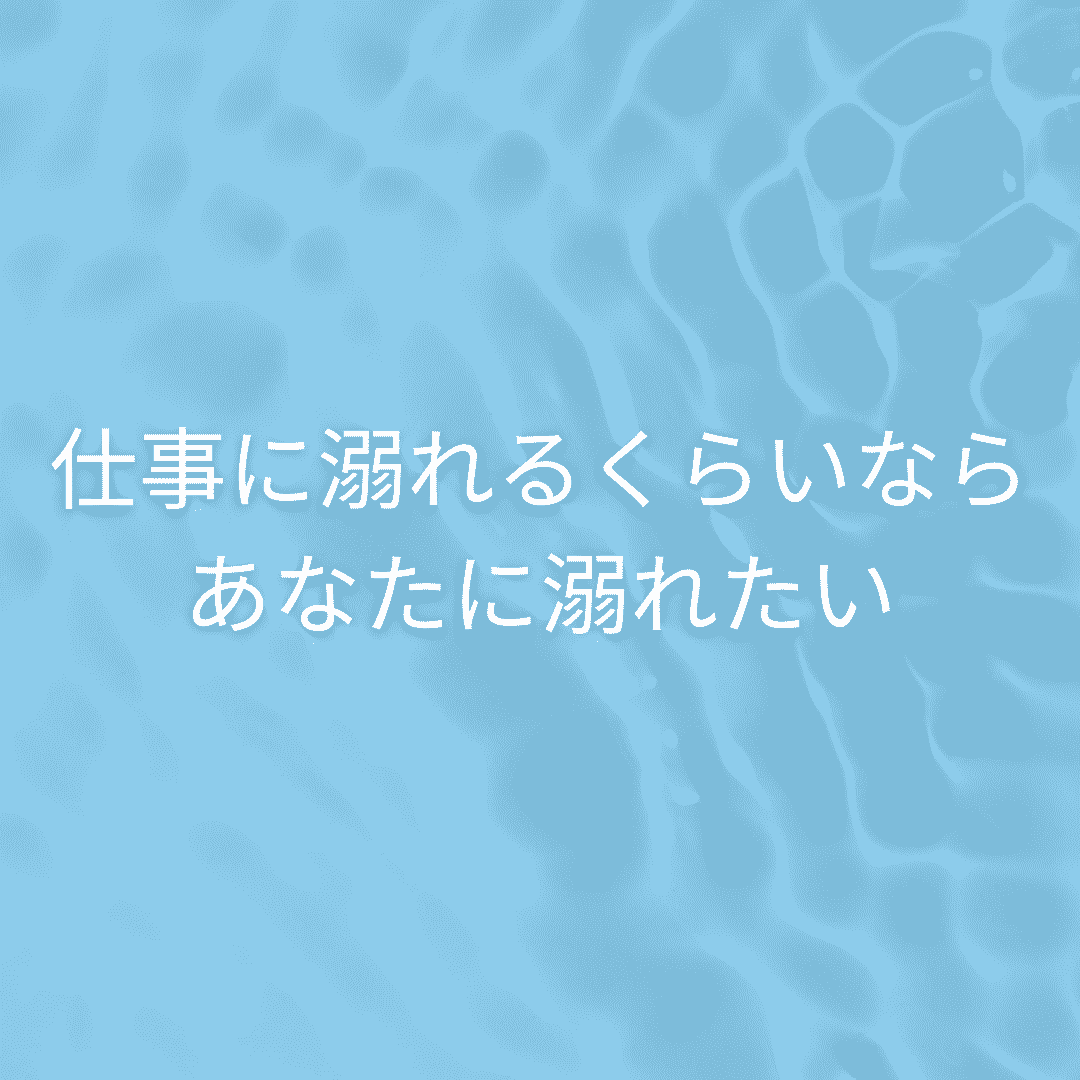


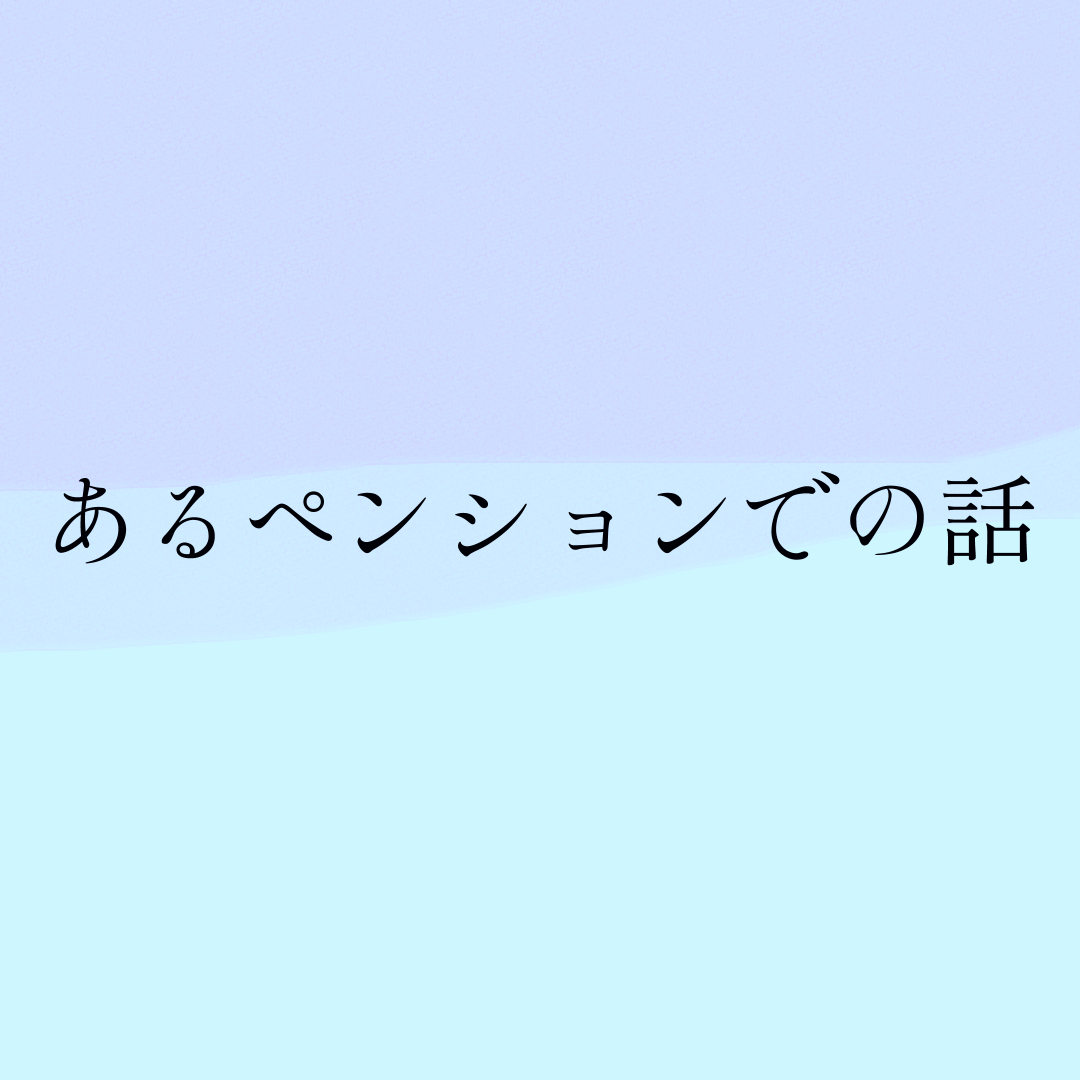
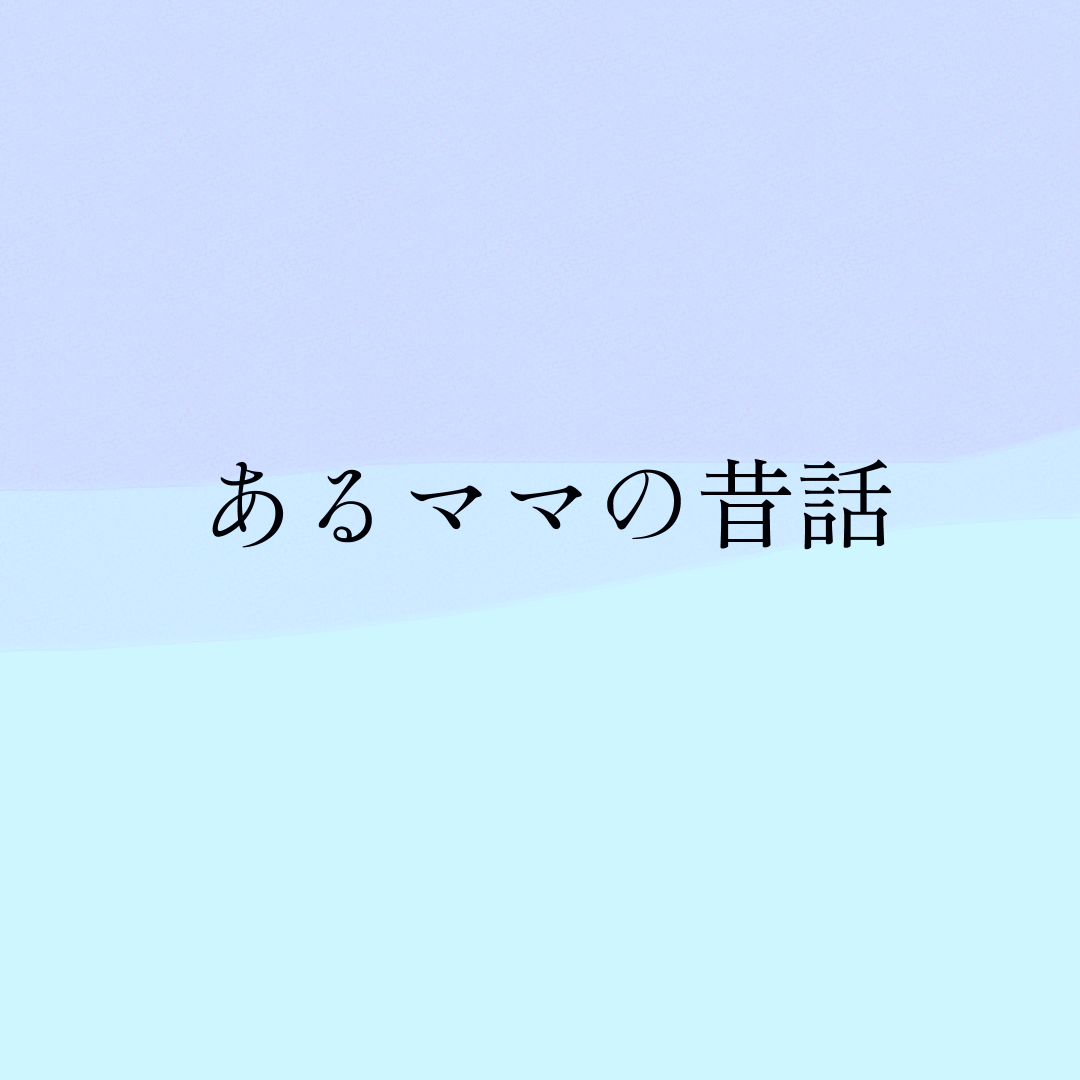
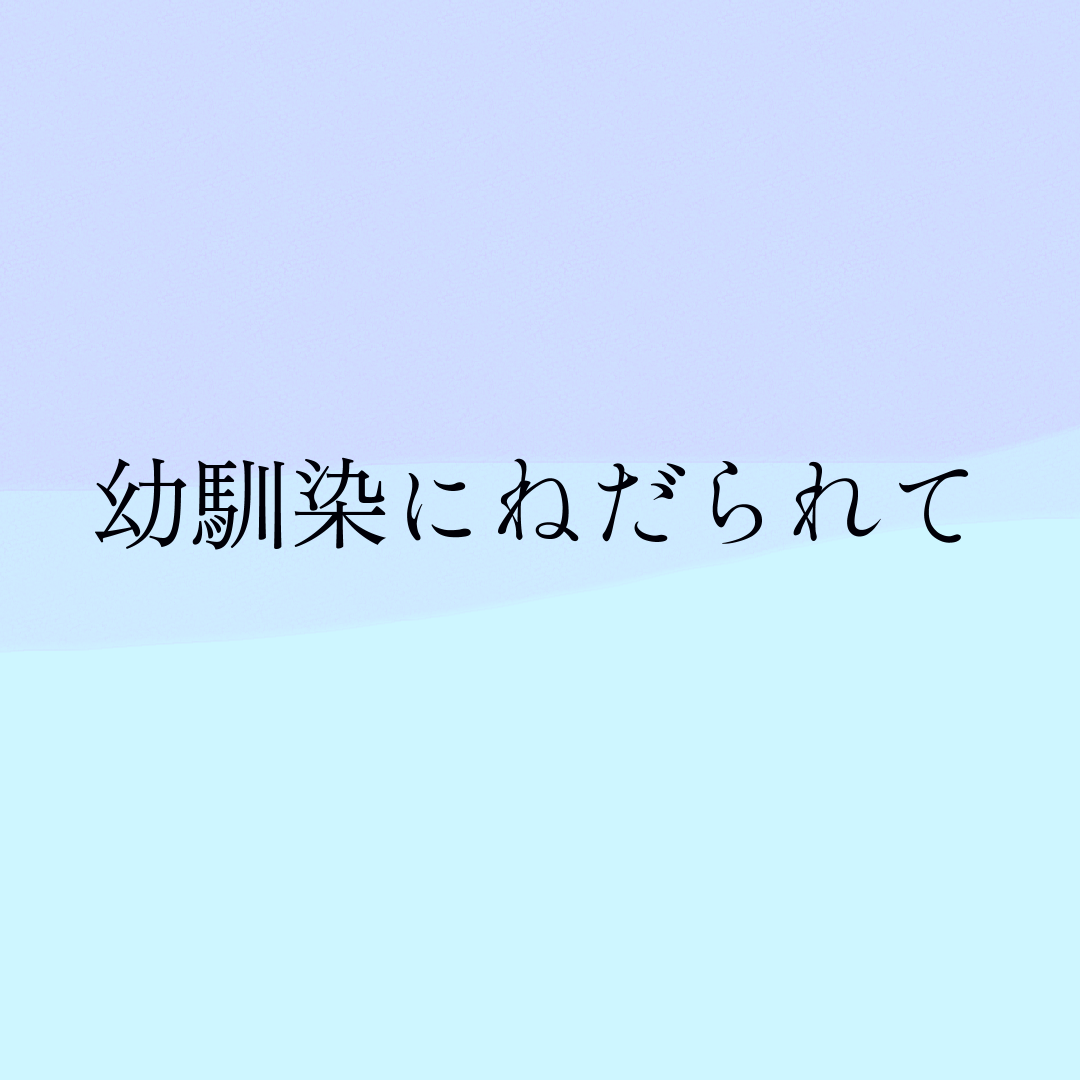
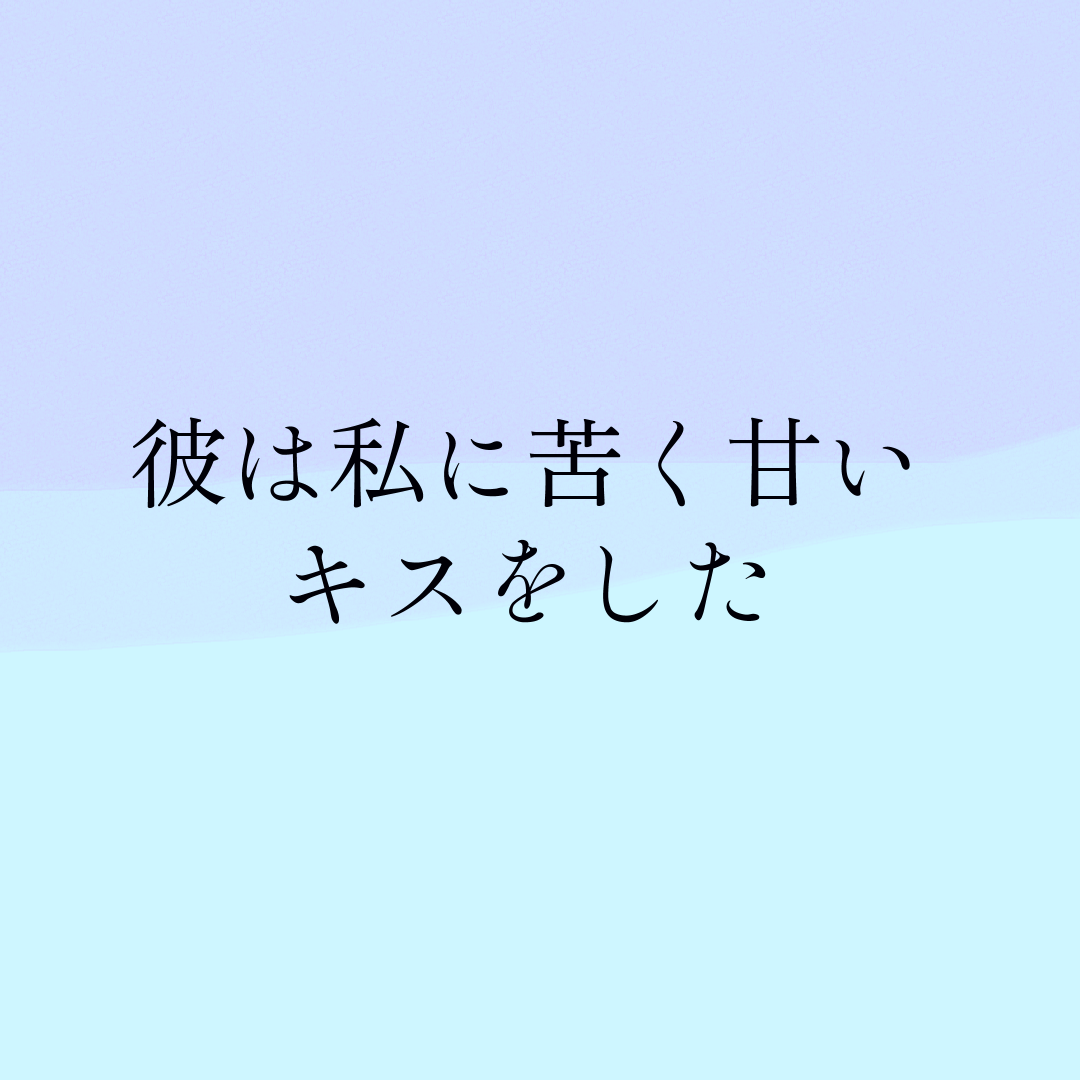
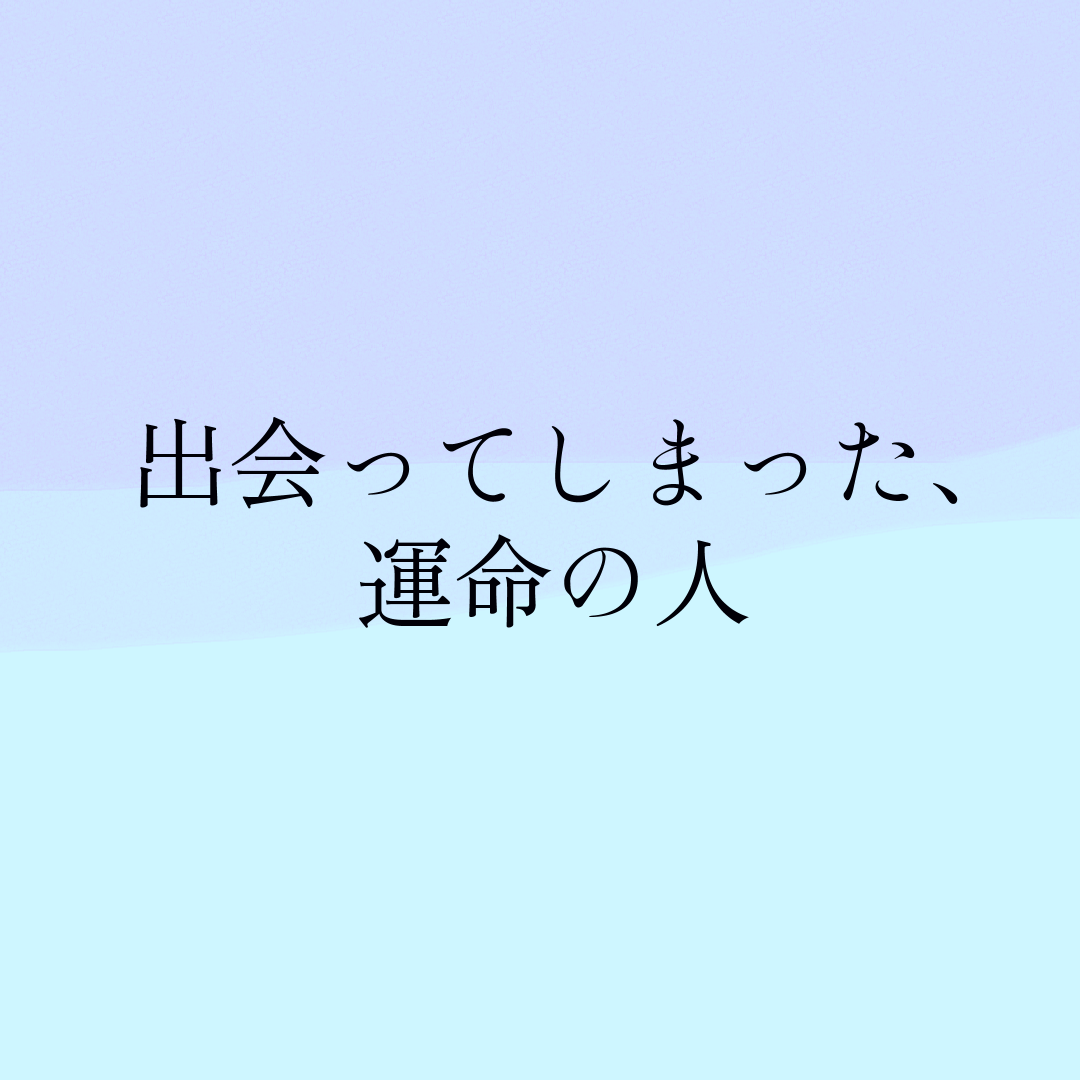
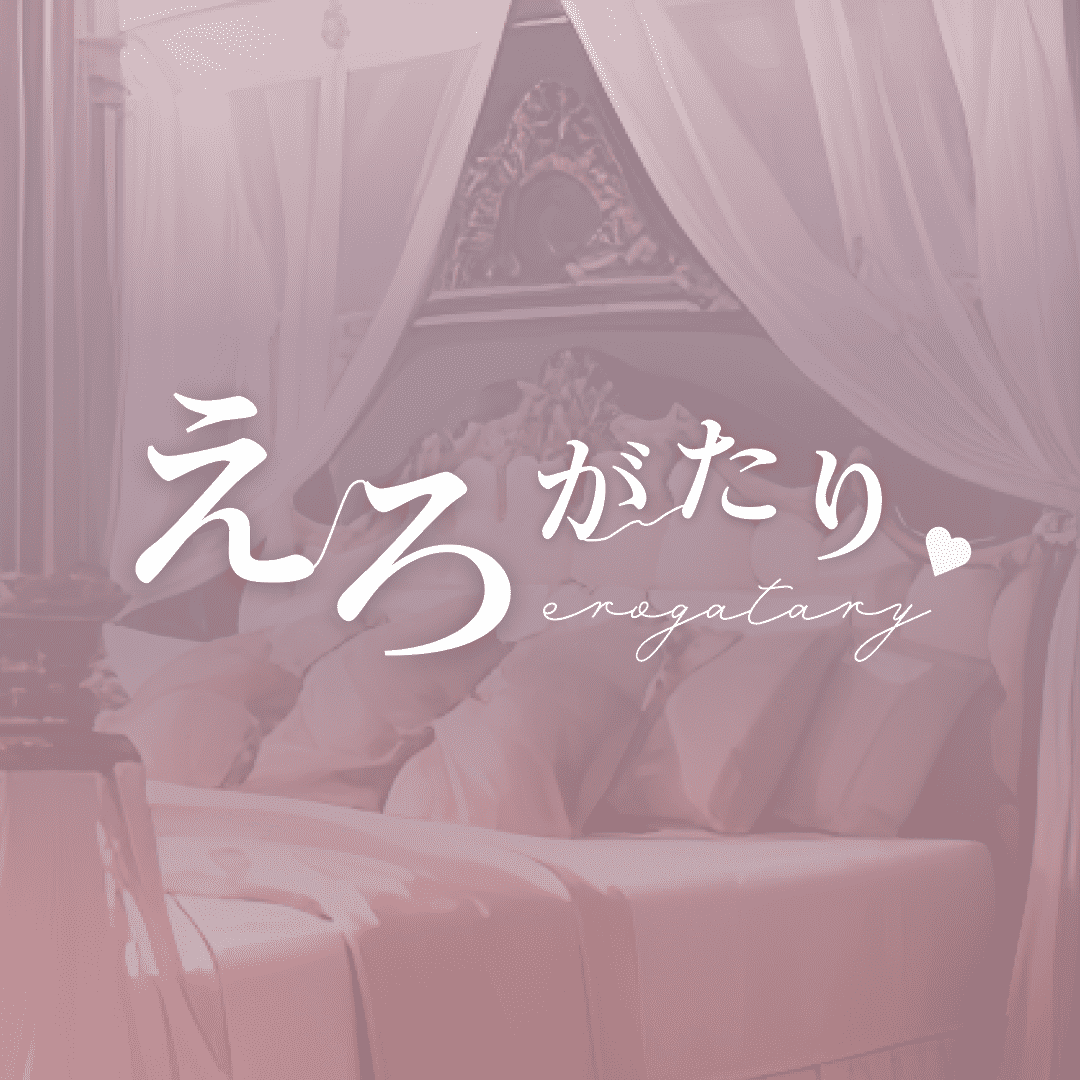
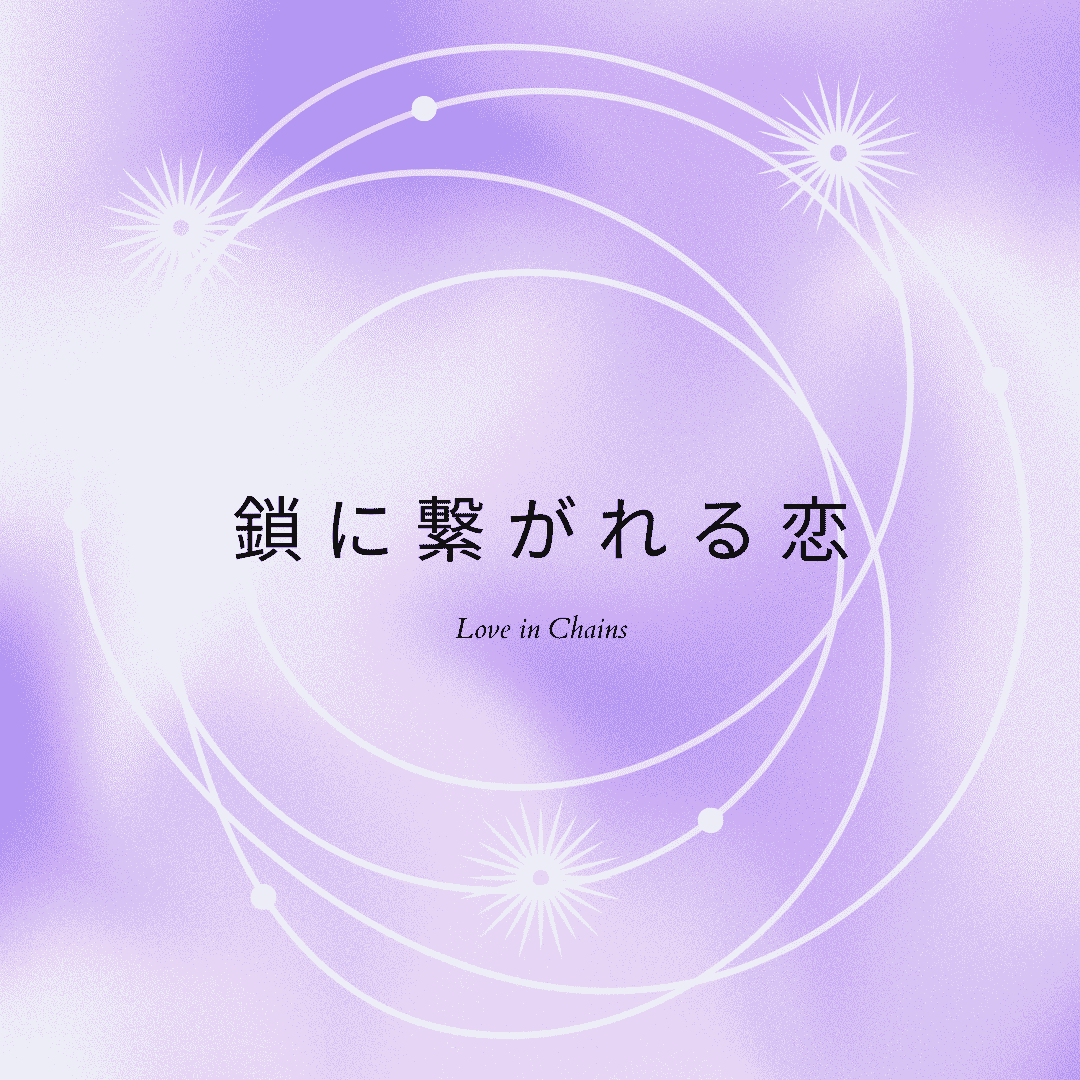



コメント