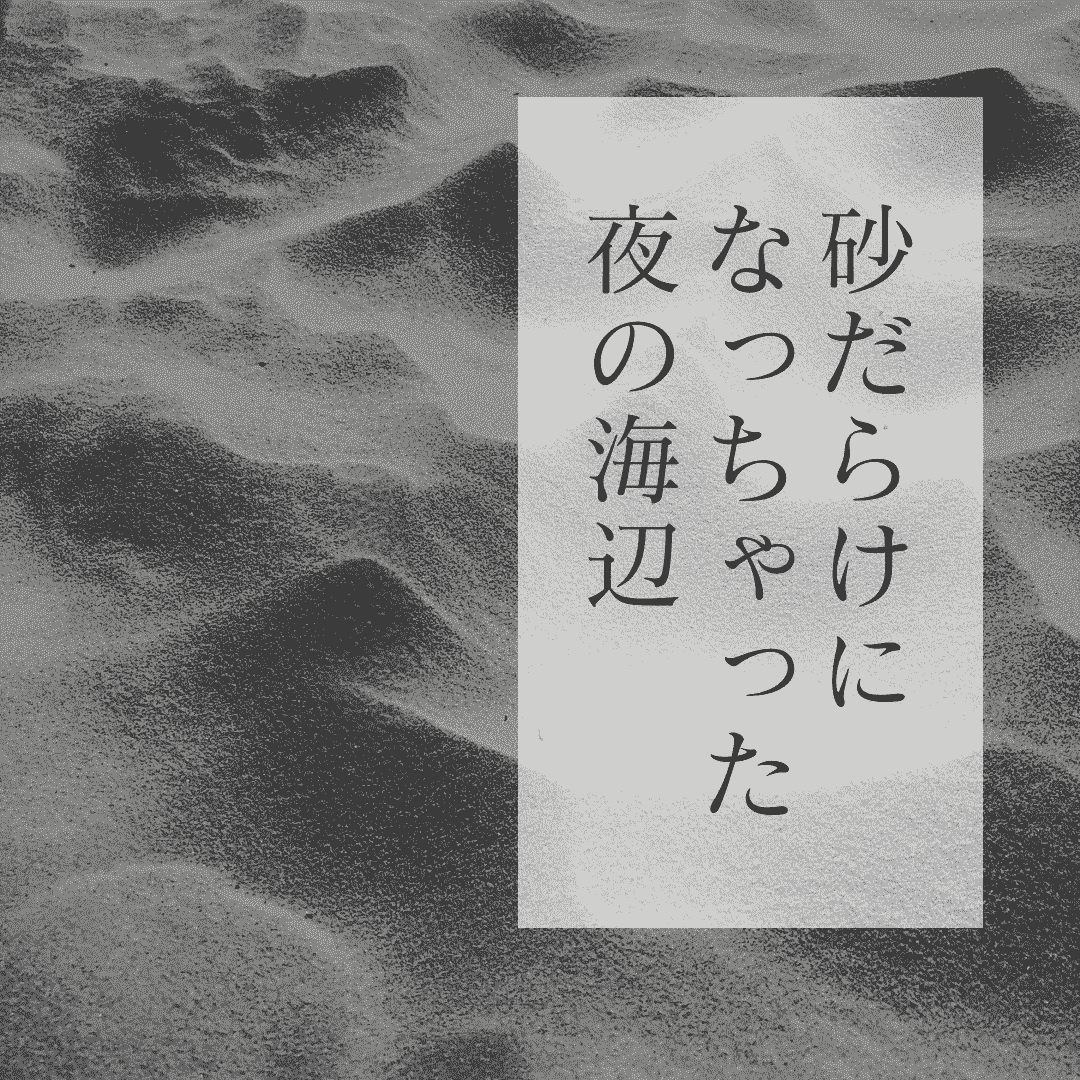
0
砂だらけになっちゃった夜の海辺
「ただいまぁ。」
「あら、お帰り。早かったね」
「うん、バス一本早いのに乗れたから。」
私は持田 栞(もちだ しおり)。
生まれた町を離れて就職して2回目の夏。
長期休暇を利用して帰省してきたのだ。
実家は小さな海辺の町。
観光客はほとんど来ないけど、一応小さな海水浴場があって、海の家もある。
いわゆる”穴場”だ。
子供のころは夏休みになると、ほぼ1日中海で過ごした。
今の職場の近くには、大きな川はあるけど、海は全く見えない。
だから夏になると、海があるふるさとが恋しくなってしまう。
まぁ、海だけじゃないんだけど…。
「栞、帰ってきたばかりで悪いんだけど、倉持さんとこ行ってくれる?」
お母さんが紙袋を見せながら聞いてくる。
「朔(さく)のうち?」
「そう。」
「何か届けるの?」
紙袋を見て、そう聞いてみる。
「いやね、昨日倉持さんとうちのお父さん一緒に飲んだんだけど、ジャケット間違えちゃったらしくて…。」
まったく…。と、お母さんは眉間にしわを寄せている。
「いいよ。」
「悪いわね。」
「どのみち顔出すつもりだったし。」
「よかったわ。じゃ、お願いね。」
お母さんは紙袋を置くと、いそいそと台所へと消えていった。
私は扇風機にあたりながら、食べかけていたアイスを一気にほおばって、立ち上がった。
倉持 朔(くらもち さく)とは同級生で、高校までずっと一緒だった。
彼の家はこの浜唯一の“海の家”的なものを営んでいる家だ。
海で遊んでいた時はみんなして、その海の家に上がり込み、駄菓子やかき氷を食べたり、昼寝したりして過ごしていた。
1年ぶりだなぁ。
朔、元気かなぁ。
「こんにちわぁ!」
「あ、栞ちゃん。いらっしゃい。いつ帰ってきたの?」
「さっき(笑)」
海の家から少し離れた、倉持家の住まいの玄関。
顔を出したのは朔のお母さんだった。
「これ、うちのお母さんが…」
といいながら紙袋を渡す。
「あぁ、さっき栞ちゃんのお母さんから連絡が来たよ。悪かったわね。」
おばさんに紙袋を渡した。
「朔は海の家にいるよ。他の友達も来てるみたいよ。」
朔とそっくりな笑顔で、おばさんはにっこり笑った。
「わぁ、じゃ私も行ってみるね。」
「はいはい、ありがとね。」
おばさんに見送られて海に向かう。
「あぁぁぁ!栞!」
海の家が見えると同時に、懐かしい友達の声が聞こえてきた。
手を振りながら、小走りに近づいた。
「いつ帰ってきたの?」
「久しぶり、みつは。」
そこには幼馴染の、みつは、和沙(かずさ)、成也(なるや)がいた。
「さっき帰ってきたんだ。」
「ヤダぁ、真っ先に会えてうれしい。」
和沙が抱き着いてくる。
相変わらず甘えん坊だな。
「栞、栞、俺も俺も。」
と成也が手を広げて近づいてくる。
「あんたは、ダメ!」
みつはにとめられて『ブー』ってなる成也。
あぁ、この感じ。懐かしい。
地元に帰ってきたって感じでなんかほっとする。
するとそこへ—
「はいはい、いつまでくっついてんの。」
「見てて暑苦しいよ。」
と言いながら、海の家の奥から朔が現れた。
片手で和沙を追い払うしぐさをしている。
「いいじゃーん、久しぶりなんだし。」
そう言って和沙は、私の胸をすりすりしている。
「ちっ!」
朔が小さく舌打ちした。
和沙は“してやったり”という顔をしている。
そんな和沙から私に視線を移して、
「お帰り、栞。」
と朔は言った。
「ただいま。」
よく日に焼けた肌。
潮と日差しで少しこげ茶の髪の毛。
着慣れたTシャツに半パン。
足元にはこなれたサンダル。
1年ぶりに会う朔は、年々たくましく男らしくなっていく。
それでも、いつも変わらない安心感をくれるのだ。
「栞も冷たいの飲む?」
「うん。じゃ、アイスコーヒー。」
「やっぱ都会にいるとおしゃれになるな。」
なんて、成也にからかわれる。
「もう!!フツーじゃん。」
と返すと、
「こないだまで、“オレンジ”とか、“パイナップル”とか言ってたじゃん。」
と言われてしまった。
まぁ確かに。
大人の女を意識してないと言えば、嘘になるだろう。
実は、彼にふられたばかりだ。
少し年上の彼とは、いわゆる“合コン”で出会った。
スーツが決まっていて、デートもワンランク上のプランをいつも立ててくれた。
告白してきたのは彼のほうだった。
なのに…。
あっけなく振られてしまったのだ。
『やっぱ、もっと洗練された大人の女のほうが俺には合ってる。』
そんなことを言われた。
1年も付き合ってなかったし、まだ傷は浅い。
そう思ったけど、やっぱりちょっときついなって思うときもある。
だから、この地元と地元の友達の感じは、ほんとに癒される。
※※※
夕方になるとみんな帰っていく。
みんなを見送って私も帰ろうとすると、
「お前いつまでこっちいるの?」
と朔から声をかけられた。
「5日間だよ。」
「へぇ、結構長くいられるね。」
「うん。」
少しの沈黙がはしる。
「また遊ぼうぜ。」
唐突に、朔がそういった。
「うん、楽しみ。」
「じゃ、気を付けて帰れよ。」
「あ、うん、またね。」
その夜、私は不思議な夢を見た。
『あんな男のこと忘れろよ。』
そう言って抱きしめる朔の腕は、たくましくて声も低く、鼓膜を揺さぶられるようだった。
はっと目を覚ましてもドキドキしている。
夢なのにその感触が、体にも耳にもしっかりと焼き付いている。なんでだろう…。
確かに私は、高校生のころから、朔のことがちょっと気になってはいた。
でもこんな夢を見るなんて…。
振られてから、ちょっとメンタルが弱ってたのかな?
※※※
実家にいる間、地元に残った子や帰省した子と遊んだり、飲みに行ったりして過ごした。
ただ、何をしていても、どうしても朔のことを意識してしまうのだ。
あんな夢を見たせいだ。
ある飲み会の席。
朔が隣に座ってくる。
狭い居酒屋だから、距離も自然と近くなる。
今まで感じたことなかったけど、朔って筋肉すごいな…。
朔が少し動くたびに、潮の香りが私の鼻をかすめてくる。
当たり前のように思ってたけど、ずっと変わらない朔の香り。
「ちょっとごめん。」
そう言って私の斜め前にあるビール瓶をとろうとして、朔の体が私に触れた。
「あっ…」
反射的によけてしまう。
「え?そんなよける?」
「あ、ううん、ごめん」
。
そう言ったけど成也がそれを見て、
「あれぇ?さっくん、栞になんかした?」
「してねーよ。」
「ほんとぉ?」
「あほ!マジでなんもしてねーし。」
な?と、私に確認するように聞いてくる朔。
「う、うん、ちょっとボーとしてて、びっくりしただけ。」
咄嗟に私も笑顔を作って、そう答える。
でもちょっと不自然になってしまう。
「いつまでもなんもしないから、こんな距離とられてるんじゃない?」
みつはがそう小さくつぶやいていたのは、私たちには聞こえなかった。
※※※
その帰り道—。
みつはと、朔と、私は3人で歩く。
「はぁ、楽しかった。」
「ほんと?」
「うん。楽しかったよ。」
「でも都会ならもっとおしゃれでおいしいものだしてくれるお店あるんじゃない?」
「うーん。まぁ、あるかもね。」
「もっとおしゃれしてさ、エスコートしてくれるようなスーツの似合う男(ひと)とかさ。何か憧
れちゃう。」
「はは…。そういうお付き合いもあるかもね。でもさ、社会人としてはさ、いろいろあるよ。」
私のワンピースの裾を海風が揺らす。
きもちいいな…。
「でも、私はここの雰囲気も大好き。」
「そっか、なんか安心するよね。」
みつはの言葉に、なんで?という顔を向ける。
「だって、前にくれたスーツの写メ。なんかかっこよくてさ。栞は変わっちゃうんじゃないかってちょっと不安になっちゃって。」
「そんなわけないじゃん。」
私はみつはの手を握った。
「そっか。」
そう言って笑顔になった後、
「彼氏とかってできないの?」
と聞いてきた。
思わず朔のことを横目で気にしてしまう自分がいた。
朔は黙って、私たちの横を歩いてる。
「大きな会社だしいい人いないの?」
「あ、それは、…」
ちょっとしどろもどろになる。
すると今まで黙っていた朔が、
「あんま変なこと聞くな。栞困ってんろ?」
と言い始める。
「えぇ?全然変なことじゃなくない?」
「もう、二人とも。私に言い寄ってくる人なんてそうそういないよ。」
と、慌てて曖昧に濁した。
「えぇ、栞かわいいのに。」
「はは、ありがと。」
みつはは少し酔っているようで、
「でも、いい人がいたらちゃんと気持ちは伝えなきゃだめだよ。」
なんて言っていた。
しばらく歩いてみつはは別の道に分かれる。
「じゃぁ、またねぇ。」
そう言ってご機嫌に手を振るみつは。
「うん、気を付けてね。」
「栞も気を付けてよぉ。」
「大丈夫だよ、朔いるし。」
「…、それが心配なんじゃない。」
みつははイジワルそうににやっと笑った。
「バーカ、何もしねーよ。」
朔はそう言ったけど、私は夢のことを思い出して、思わず顔が熱くなってしまった。
「まぁ、ほんと気を付けてね。」
そう言って、今度こそみつはは、私たちに背中を向け歩き出した。
二人きりになった私たちは、海沿いを静かに歩く。
波の音と朔のサンダルの音。
海からの風が、私のワンピースと朔のぱさぱさの髪を揺らす。
「あぁ、風が気持ちいいね。」
「だな。今日は涼しい方だな。」
「なんか海のにおいがして、“地元帰ってきたぁー”って感じ。」
「ちょっと浜のほう歩いてみる?」
「うん。」
堤防から砂浜に降りる。
夜の海はちょっと暗くて怖かった。
「危ないからちょっと手つないでいい?」
暗くて朔がどんな顔をしているのか、よく見えない。
「いや?」
「…いやじゃないけど…」
「はぁ。」
朔が小さくため息をつく。
「あのさ、やっぱ俺避けられてるよね?」
あ、勘違いをさせてしまった。
「そんな、そんなことないよ。」
あわてて否定する。
「もしかしてさ、さっきはあぁいってたけど…彼氏、いたりする?」
朔が力なく腕を下ろした。
「それで俺のこと警戒してるなら、なんかごめん。」
朔はそのまま砂浜に腰を下ろした。
腰につけてたタオルを砂浜にしいて、
「座る?」
と聞いてきたので“こくり”とうなずいて隣に腰を下ろす。
「…実はさ、フラれたんだ。」
「え?」
波の音に耳を傾けながら、私は吐き出すように彼とのことを朔に話し始めた。
朔は黙って聞いてくれた。
「はは…。背伸びしすぎちゃったのかな。」
悲しさはあるけど、涙は出ない。
朔がいてくれるという安心感。
そのほうが、私の中では大きくなっていた。
「背伸びかどうかはわからないけど、栞はきれいになったよ。」
「え?」
「俺、高校の時から、……栞のこと、好きなんだ。」
思いもよらない告白に、心臓が跳ねる。
「多分、みつはには気づかれてるけど、ずっと気持ち隠してた。」
「…」
「今でも、好きだから、すげー心臓バクバクしてる。」
「朔…」
「俺にも、チャンスある?」
そう言って振り向いた朔。
その瞬間、海から強い風が吹き上げてきた。
それは、私のワンピースを太ももの上までまくり上げた。
「あ、」
そう思った次の瞬間。
朔の視線が、私の足の付け根にくぎ付けになっているのに気付く。
急いでスカートを元に戻そうとする。
でも—
がばっ!
突然、朔が私に覆いかぶさってきた。
「ちょ、さ、朔…。」
力強い腕に押さえつけられ、朔のキスが降ってくる。
ちゅ、ちゅ、と音を立てて、何度も何度も私の顔に口づける。
「ごめん栞、欲しいんだよ…」
ごめんっていうけど、全然やめる気はなさそうだった。
いつも大人っぽくてみんなのまとめ役で冷静な朔は、今ここにはいない。
動物みたいに本能と欲望で私を求めてくる朔。
ちょっと乱暴で怖いはずなのに、その乱暴さに体がぞくぞくしてしまう。
ワンピースの裾から乱暴に手を入れて、急かすようにブラのホックをまさぐる。
プチン。
ブラが外れて朔のごつい手が、何の色気もムードもなく私の胸を揉みしだく。
AVでももっとムードがあるのに…。
とか、そんなことを考える余裕が、この時の栞には、まだあった。
「栞のおっぱい、柔らかい。」
そう言いながら口を近づけて、ちゅぱちゅぱと音を立てて吸い付く。
「あぁん、あぁ。」
ムードだなんだ言いながら、私も体は素直に反応して、ついからだをのけぞらせてしまう。
先端を舌で転がされて腰が無意識に動く…。
「あぁ、ヤバイ。むっちゃ勃起(た)ってる。」
そう言った朔の声に思わず下を見ると、半パンの中で、朔のが立派なテントを張っている。
それを見ただけで興奮して、あそこが“じゅわ”っと熱くなるのがわかった。
「栞も感じてる?」
そういうと私の下半身から下着を抜き取って、あそこに指をこすりつける。
ぬちゃ。
その水音を確認すると、朔のきれいな顔がにやりとゆがんだ。
しばらく楽しむように、私の中に指を抜き差ししながら胸を揉み続けた。
「あぁ、あぁぁん、さく……」
私はただただ、あえぐしかなかった。
「ねぇ、いい?」
半パンから引っ張り出された“モノ”を自分でさすりながら、朔が聞いてくる。
そんなのを見せられて、我慢できるはずがない。
「うん、うん。」
と何回もうなずく。
すると彼のペニスが私の入り口に押し当てられて、
「これで、ほかの男の子のことなんか、全部忘れて!」
と言ってきた。
そして朔のたくましい腰とともに、ぐっと、ペニスが私の中に押し込められてくる。
「あぁっ!」
快感でいっぱいになる。
「あぁ、ぁん朔、好き…、あん…いい…h
朔にしがみついて、一心不乱に腰をふった。
「やばいよ、栞、そんな乱れないで、俺、俺、イッちゃうよ…。」
「あん、だってもっと奥に、ほしい…」
「あげるよ、もう…、栞こんなエッチだったんだ。」
興奮のあまり、朔の言葉も、曖昧にしか聞こえない。
でもその瞬間—。
堤防の上をヘッドライトが照らした。
ドキッとして胸を手で押さえる。
でも、車はそのまま通りすぎる。
「大丈夫、こんなとこ、誰も気づかない。」
朔にそう言われてほっとする。
「でもドキドキしたね。栞の中、きゅってしまった。こういうスリルあるの、いいの?」
そう言われて、今更恥ずかしくなる。
「もう少し、俺も気持ちよくさせて。」
そして律動が再開される。
「栞、上になって。」
少しして、朔からお願いされた。
つながったまま私たちは入れ替わる。
二人から流れる汗で、もう髪も背中も砂まみれだ。
腰を上下すると、つながっているところが良く見えてくる。
何故だか幸せな気分…。
「ん…はぁ…栞とこんなにつながれるなんて、幸せ…」
あぁ、朔も同じ気持ちなんだ。
しばらくすると、朔が私の腰をぐっとつかんだ。
「ごめん、…」
そう言ってまた私を組み敷く。
「もう、…いく。」
「う、うん。」
一瞬固く抱きしめあって、深くキスをした。
ザアァア……
波の音にかき消されながらも、おかしくなりそうなほど、朔のが私の奥底まで犯しつくす。
「いくよ!」
切なくかすれた声。
「あ、う、うん。」
「あぁぁぁ!」
「あぁぁぁん!」
※※※
真っ暗な砂浜。
波の音を聞きながら、朔の横に横たわる。
「ごめんね、かわいいワンピースがもう…髪の毛も砂だらけ」
けもののように猛ったのが嘘のように、優しいいつもの朔。
「ふふ…。今そこ謝る?」
「確かに…。もっといろいろ、謝んなきゃだけど。」
そう言ってから、そっと私の髪をかき上げる。
「後悔はしてない。」
「朔。」
そういいながら、ピタッと朔にくっつく。
「私も…,私も朔のこと…好き…」
そう告げると、今日一…
…いや、
過去一優しい朔の優しいキスが、私の唇をそっと包み込んだ。






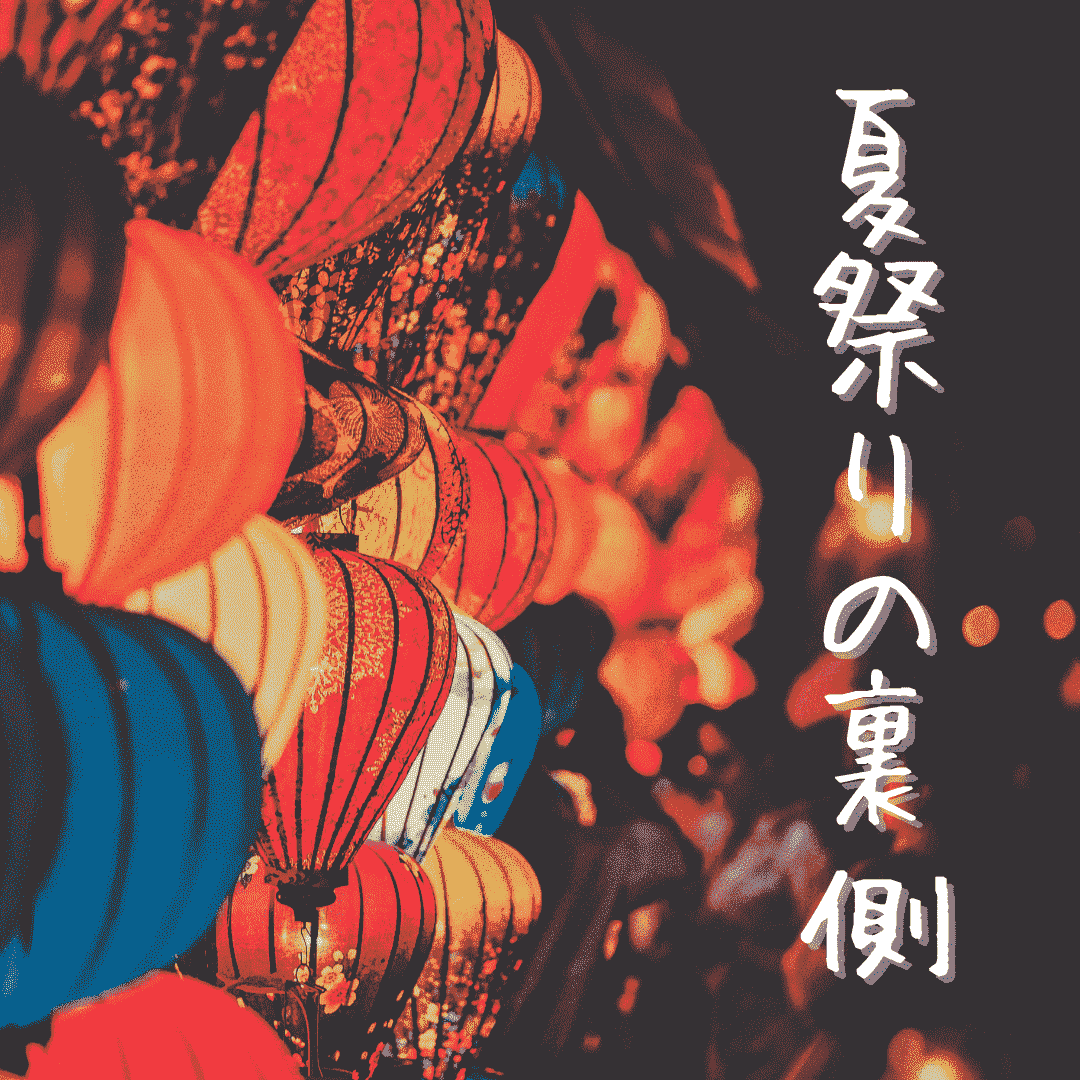

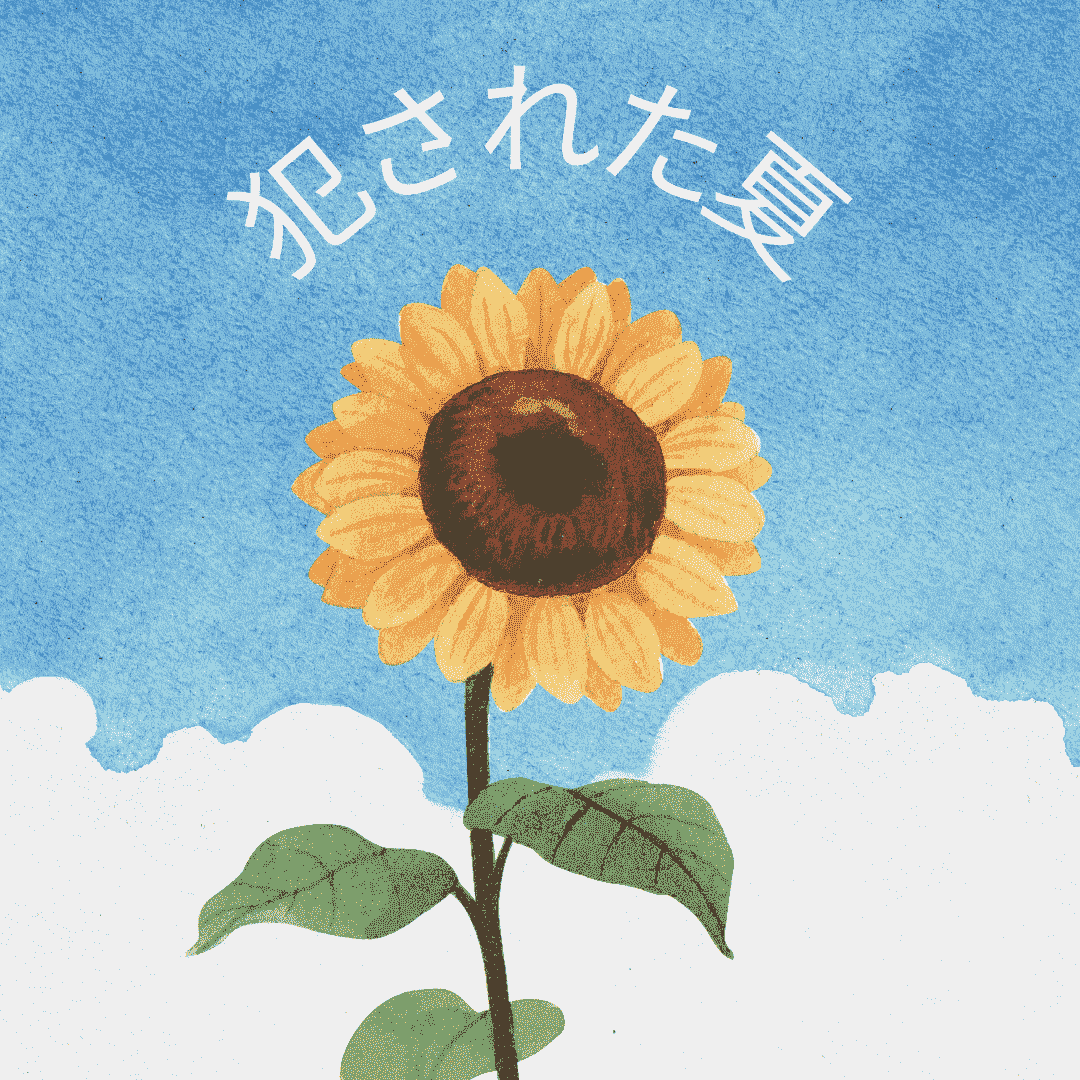


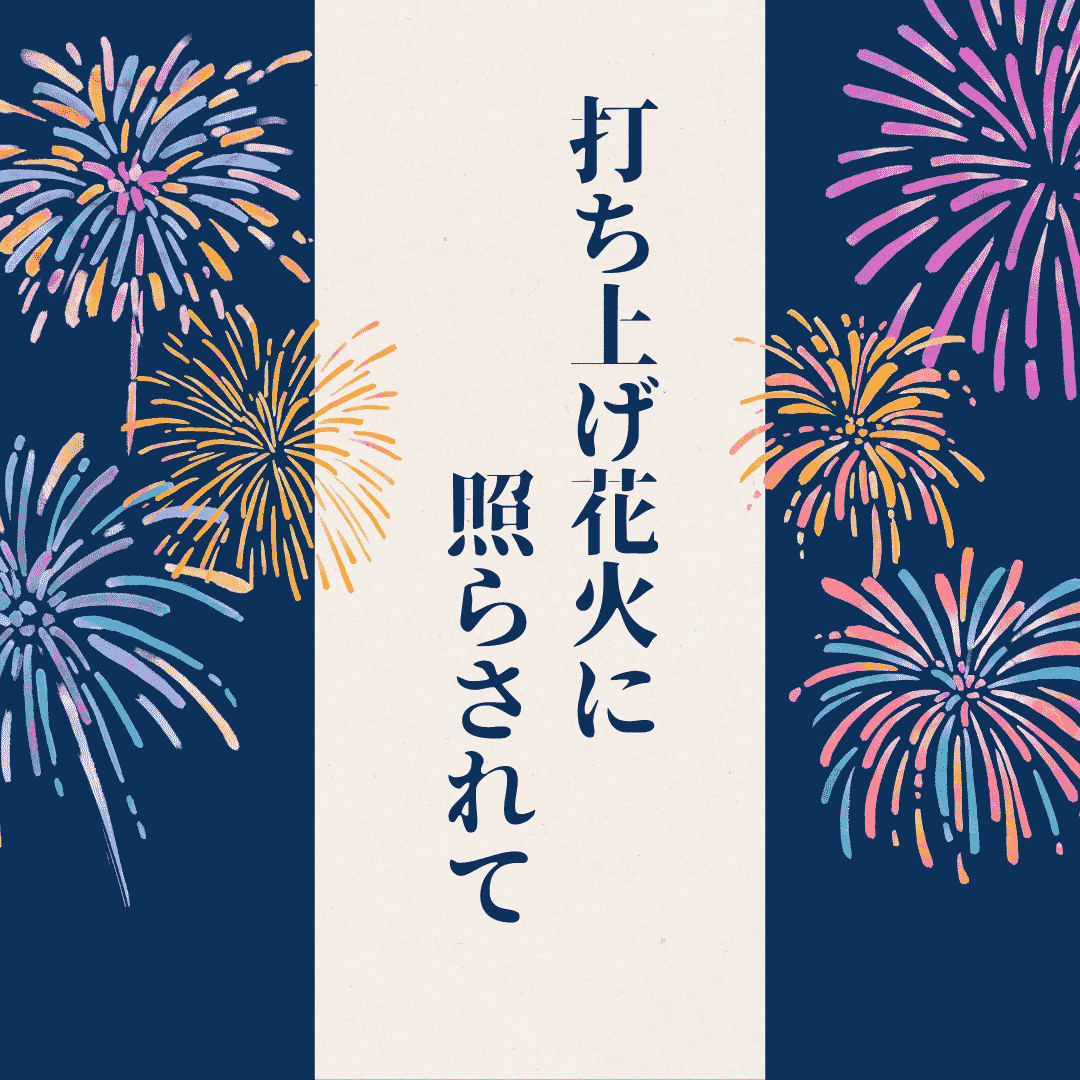


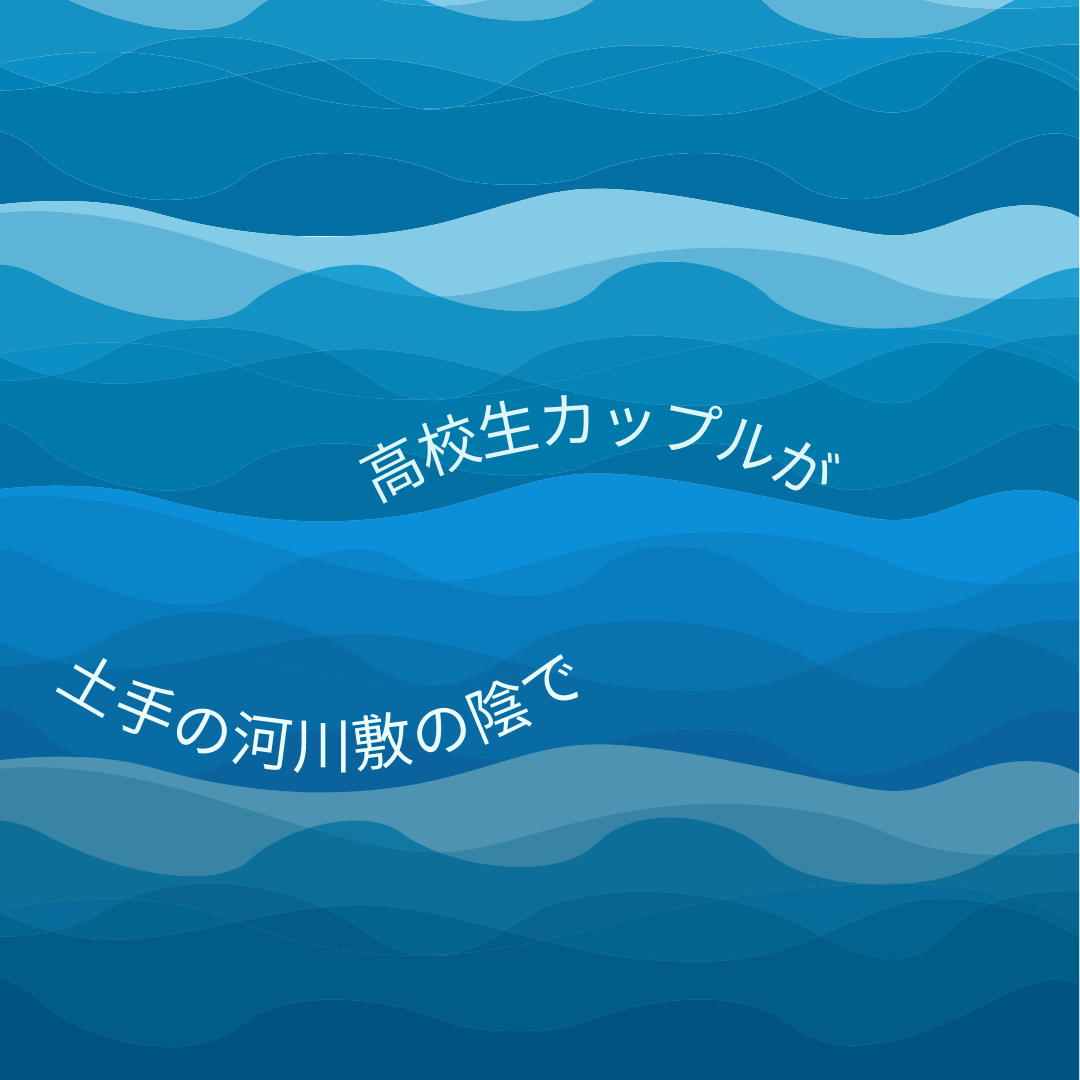


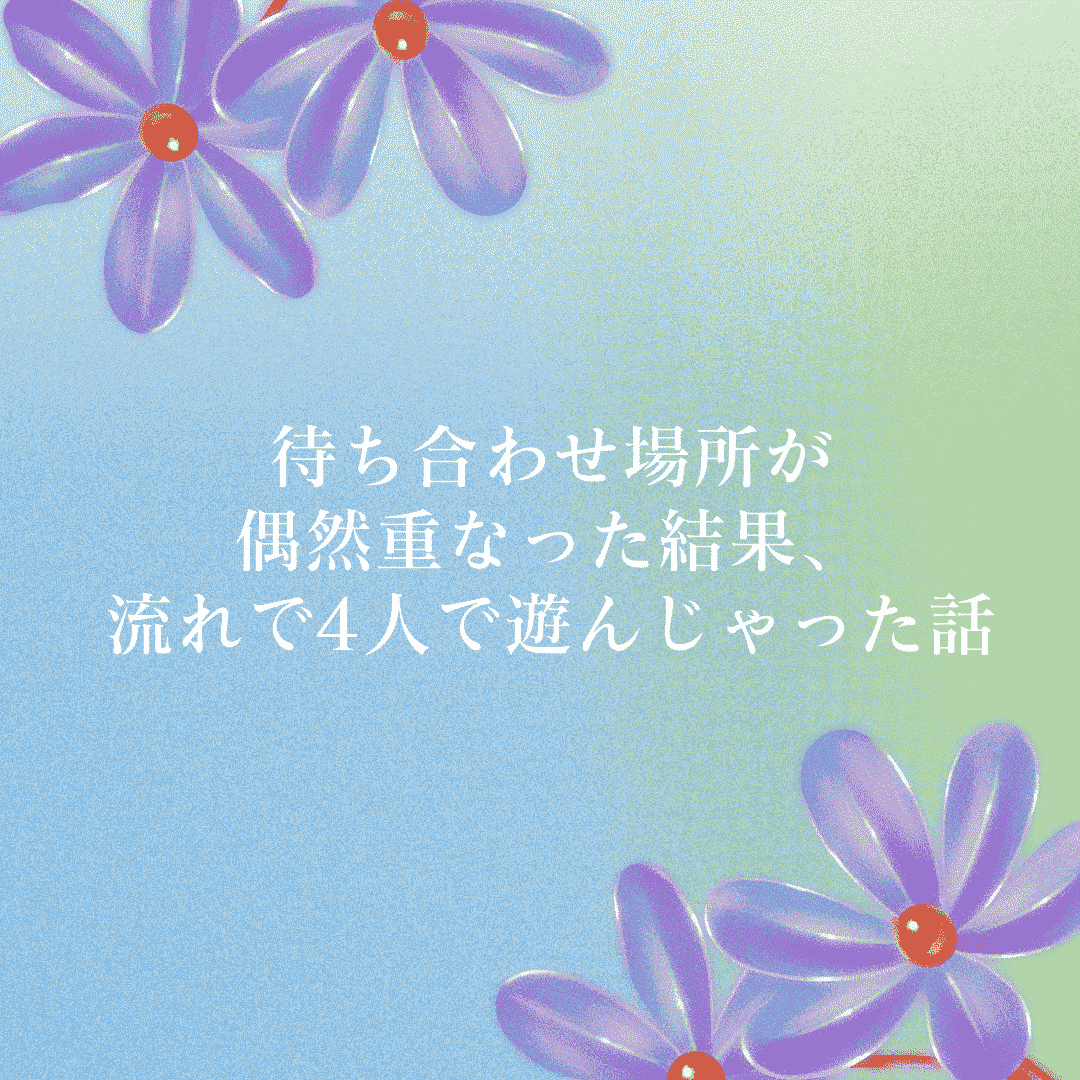




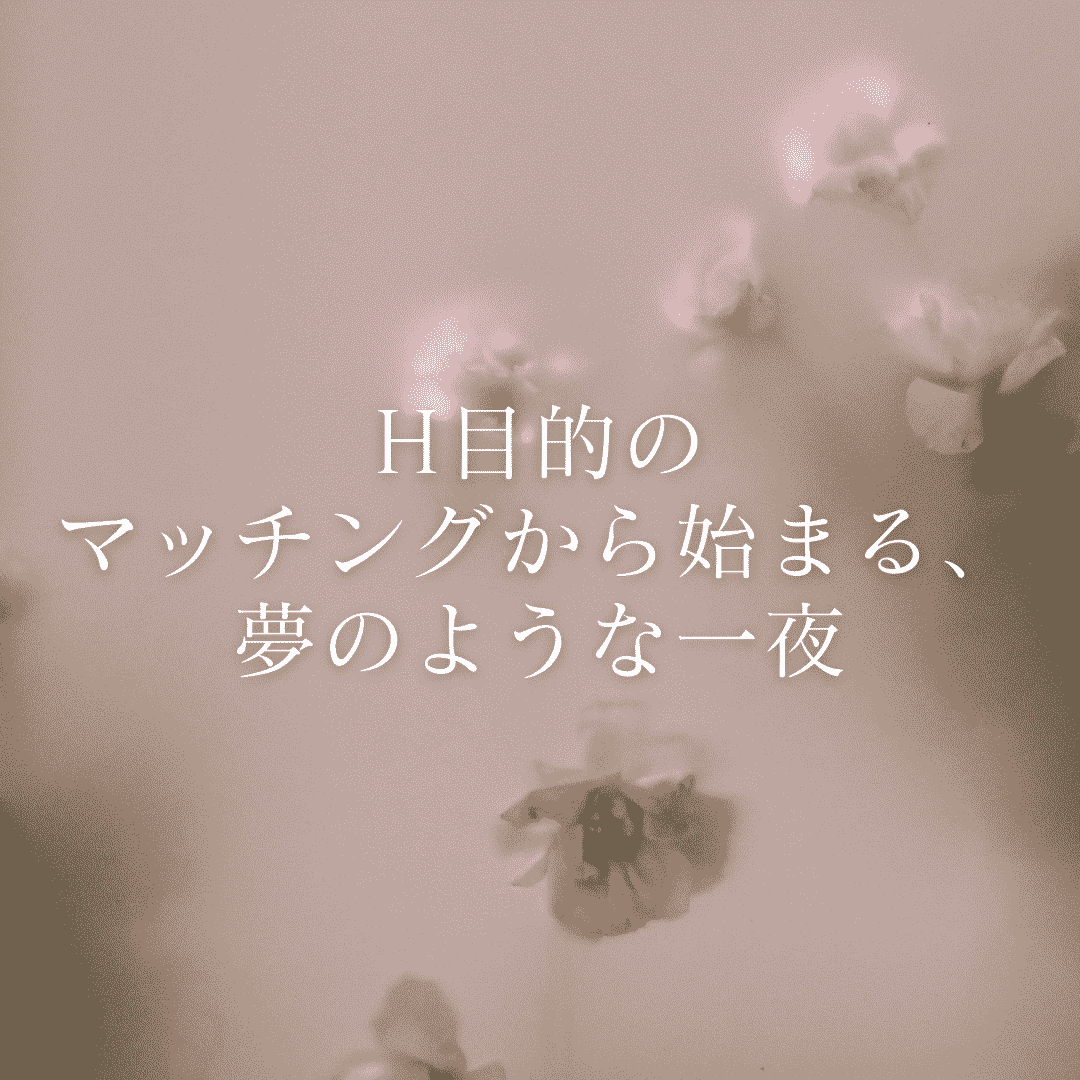

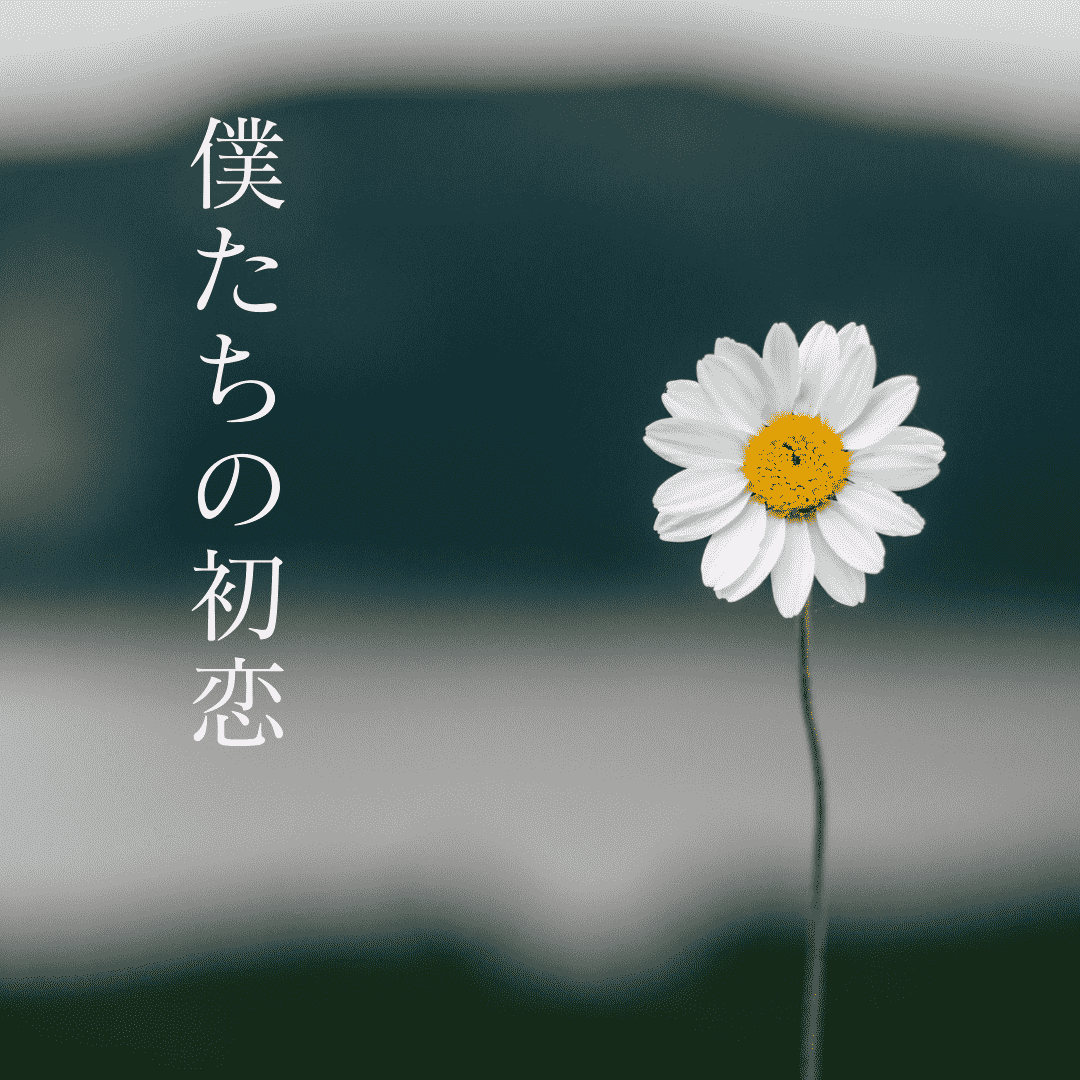


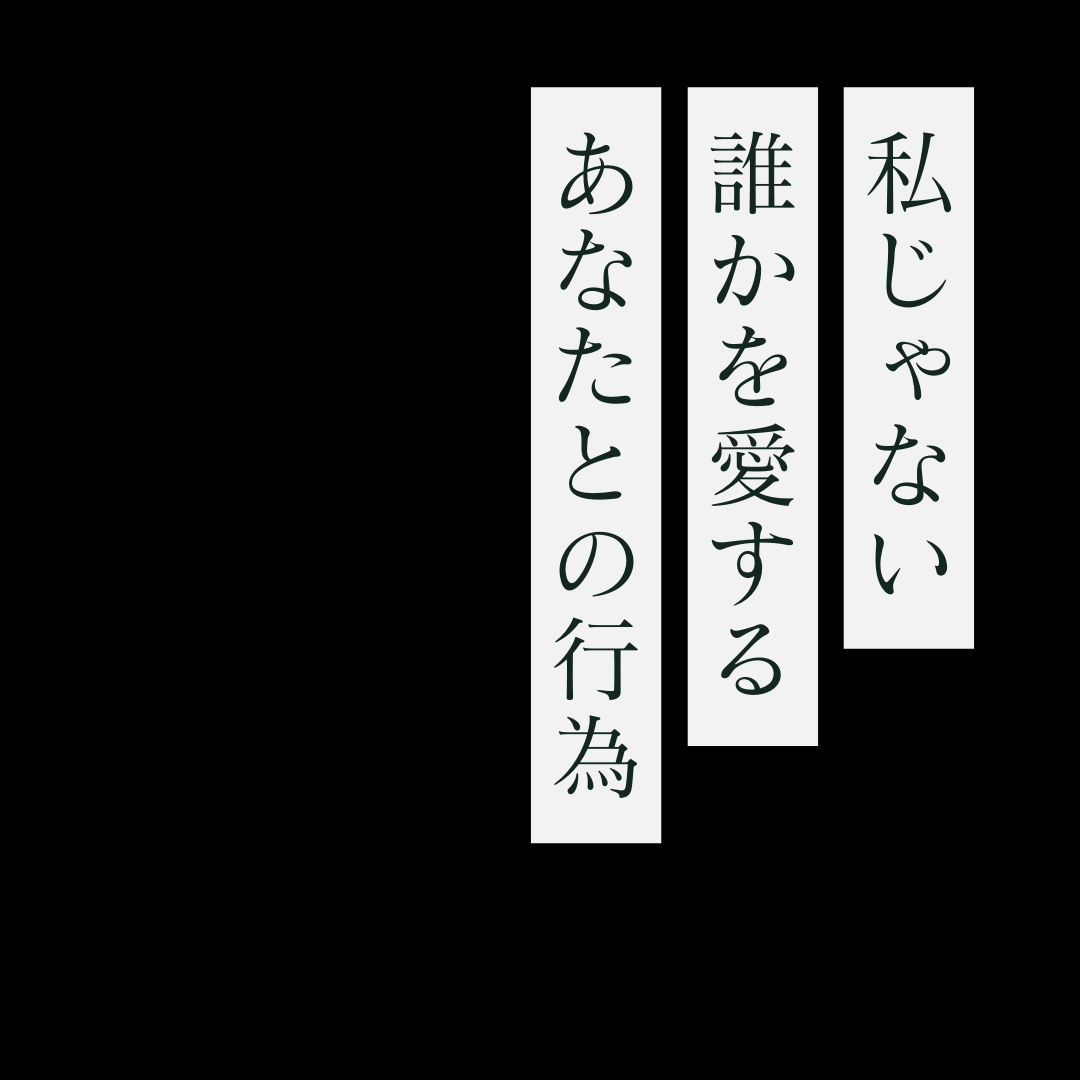

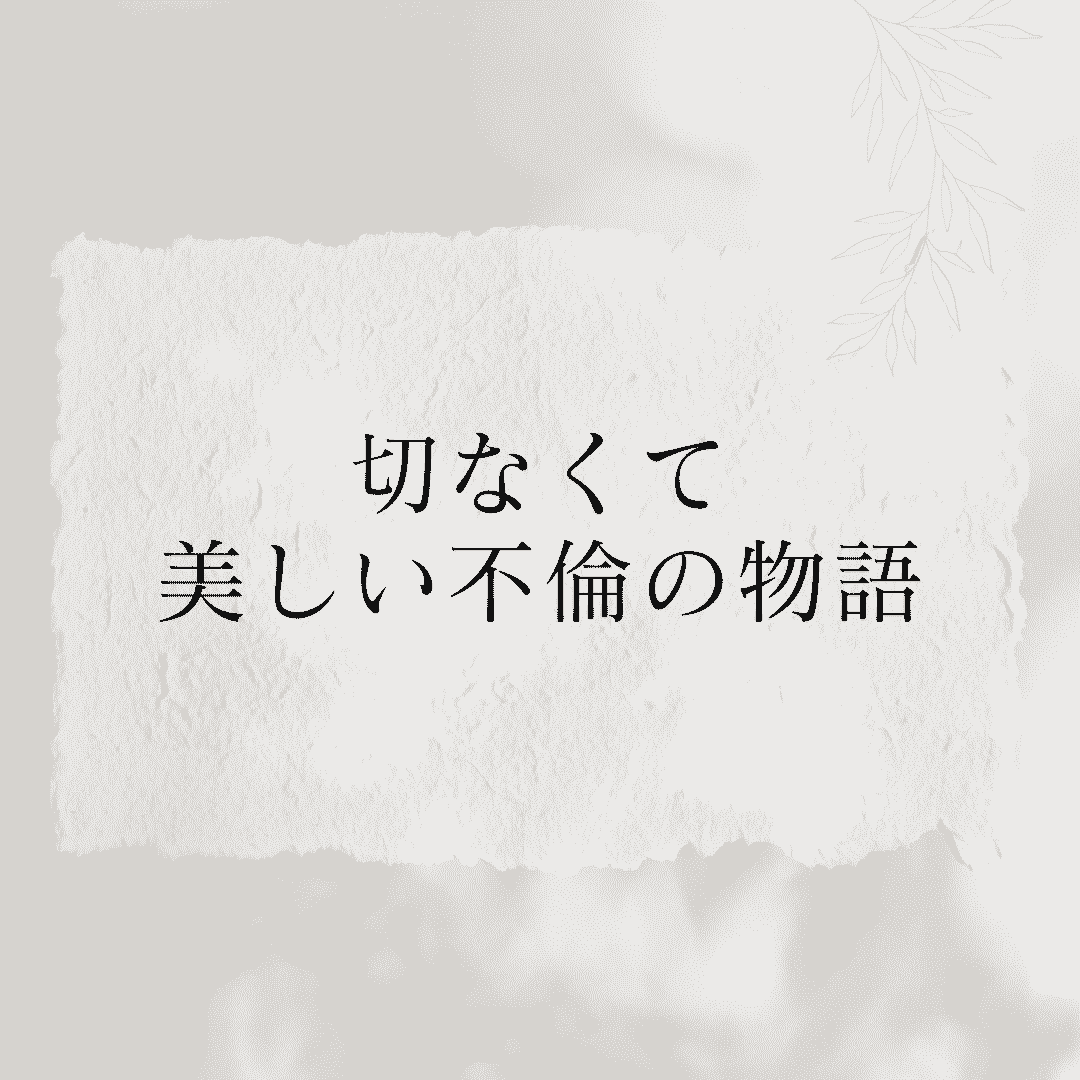
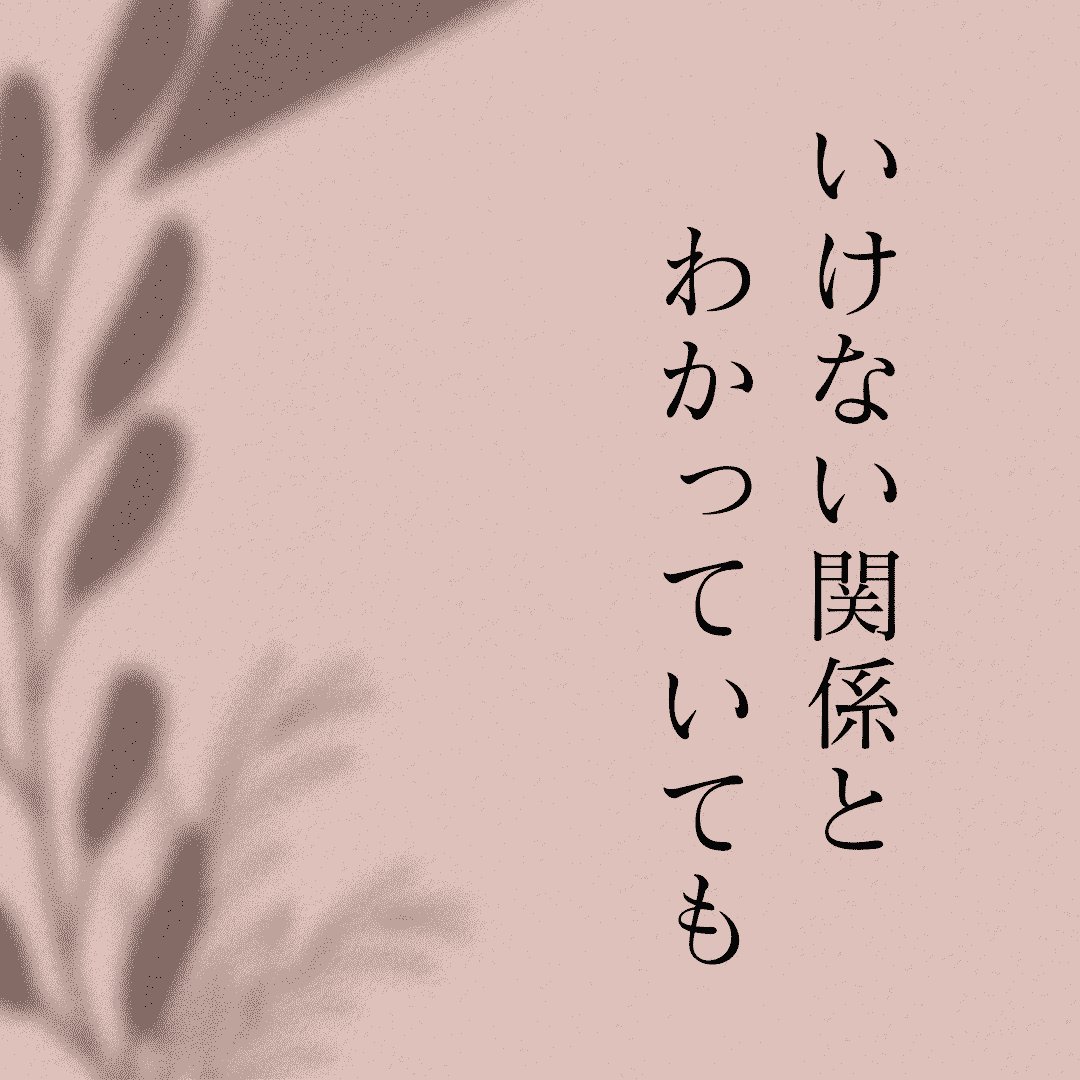









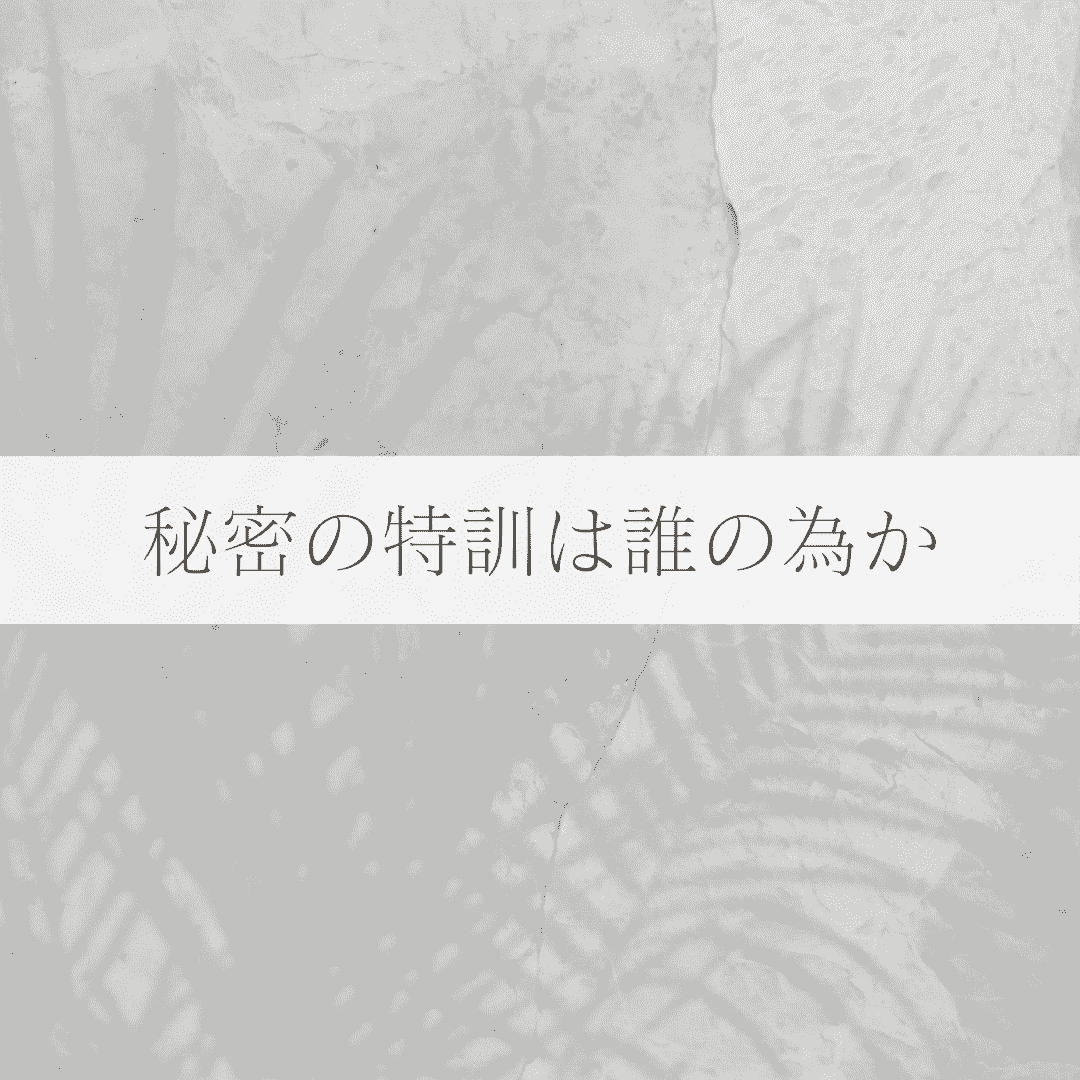
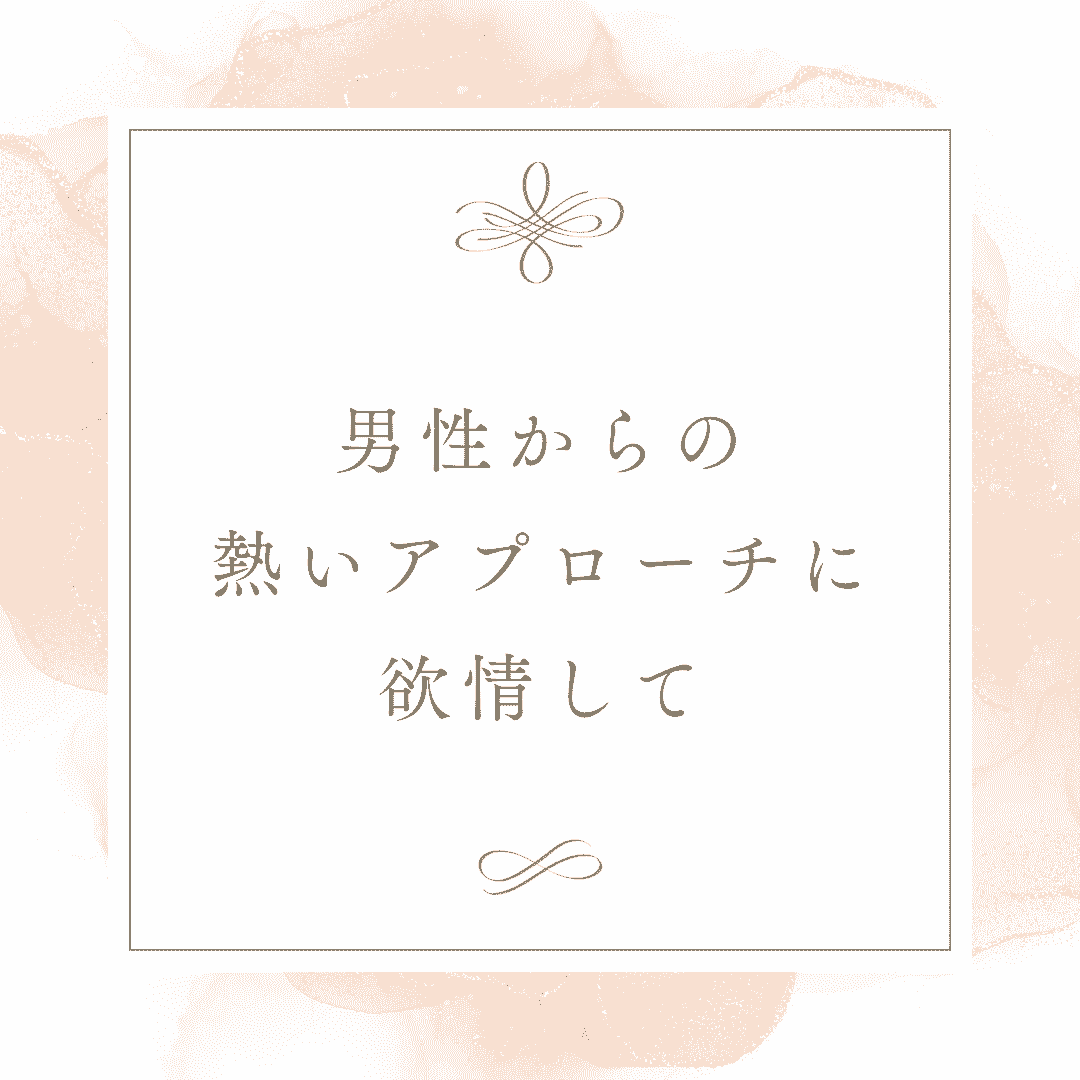


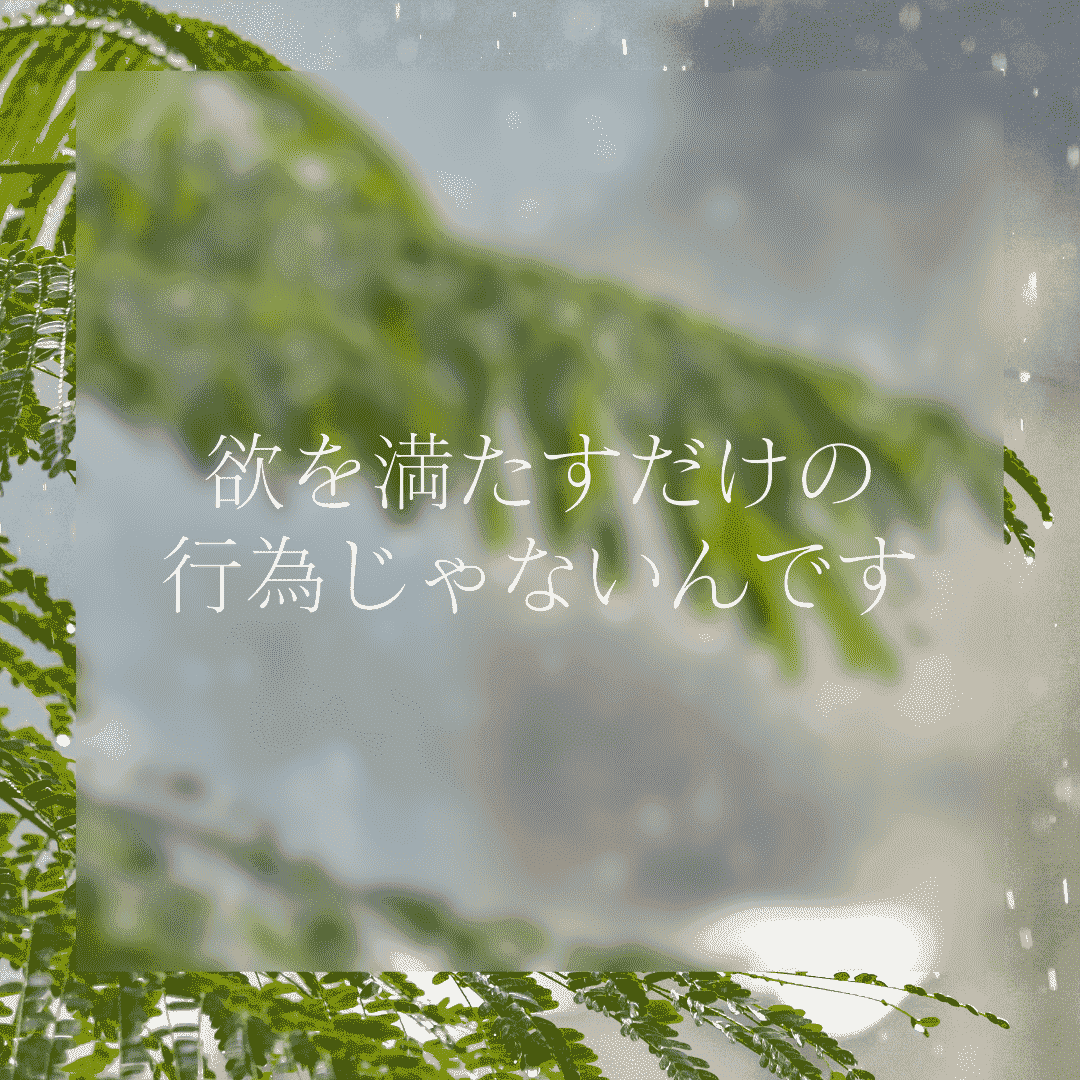

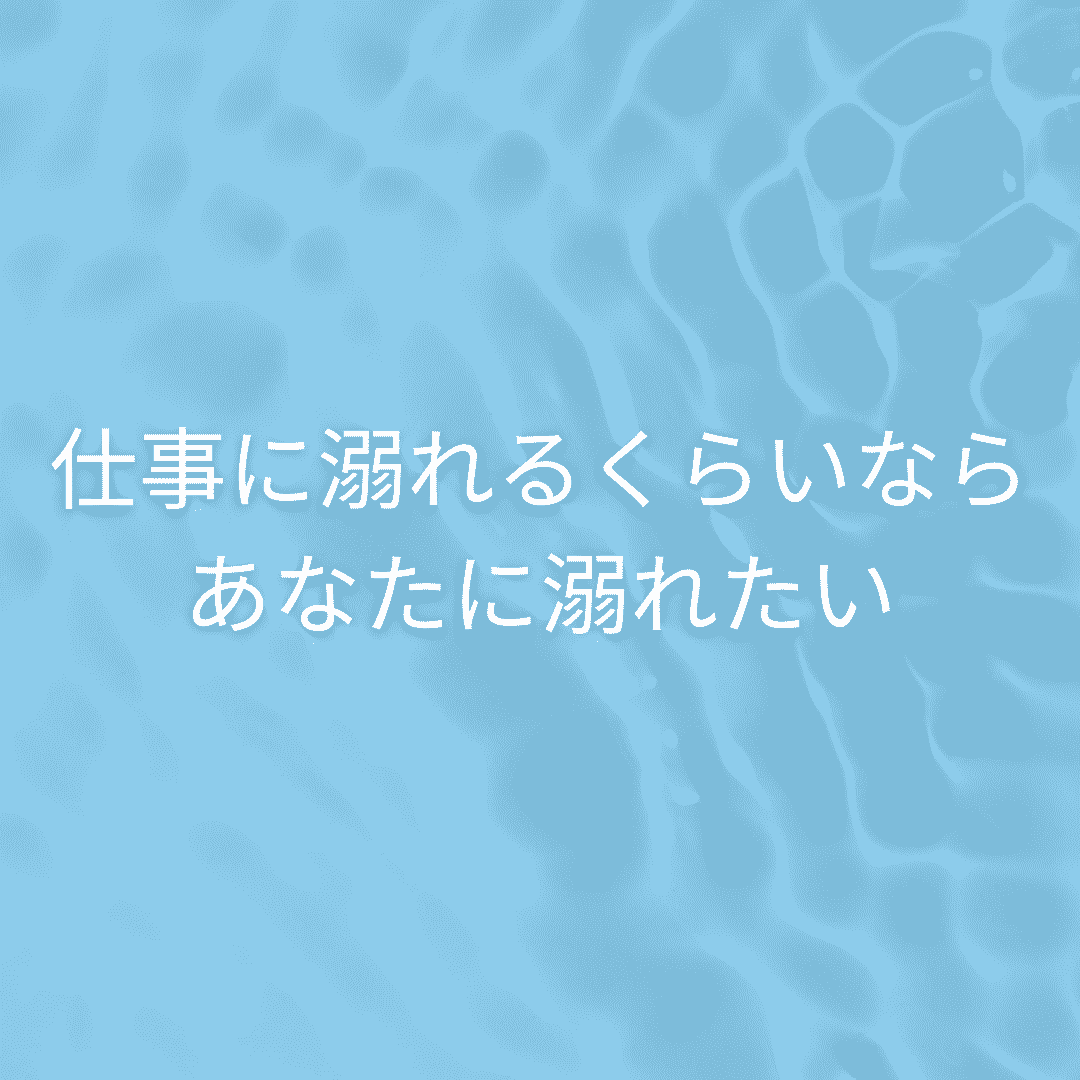


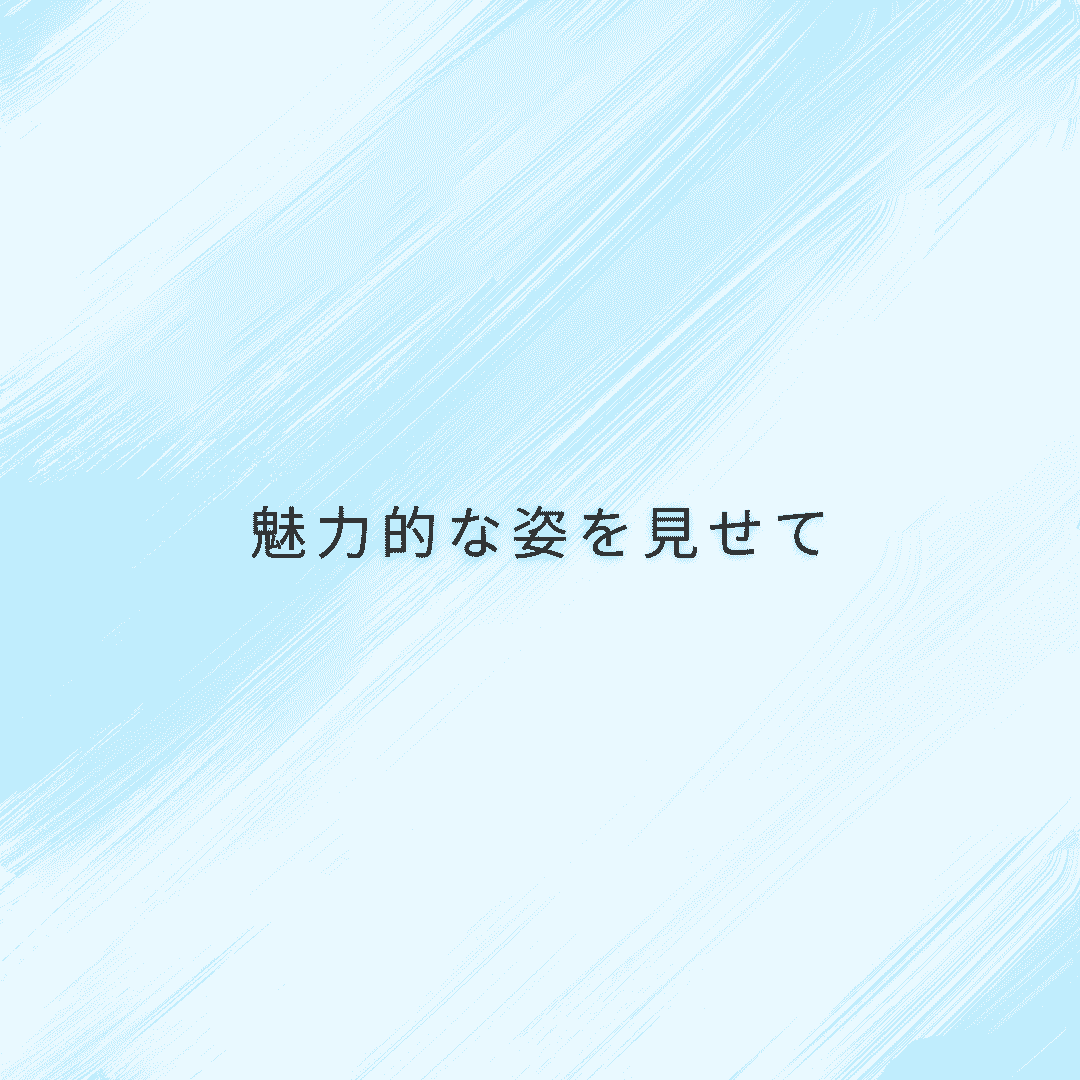
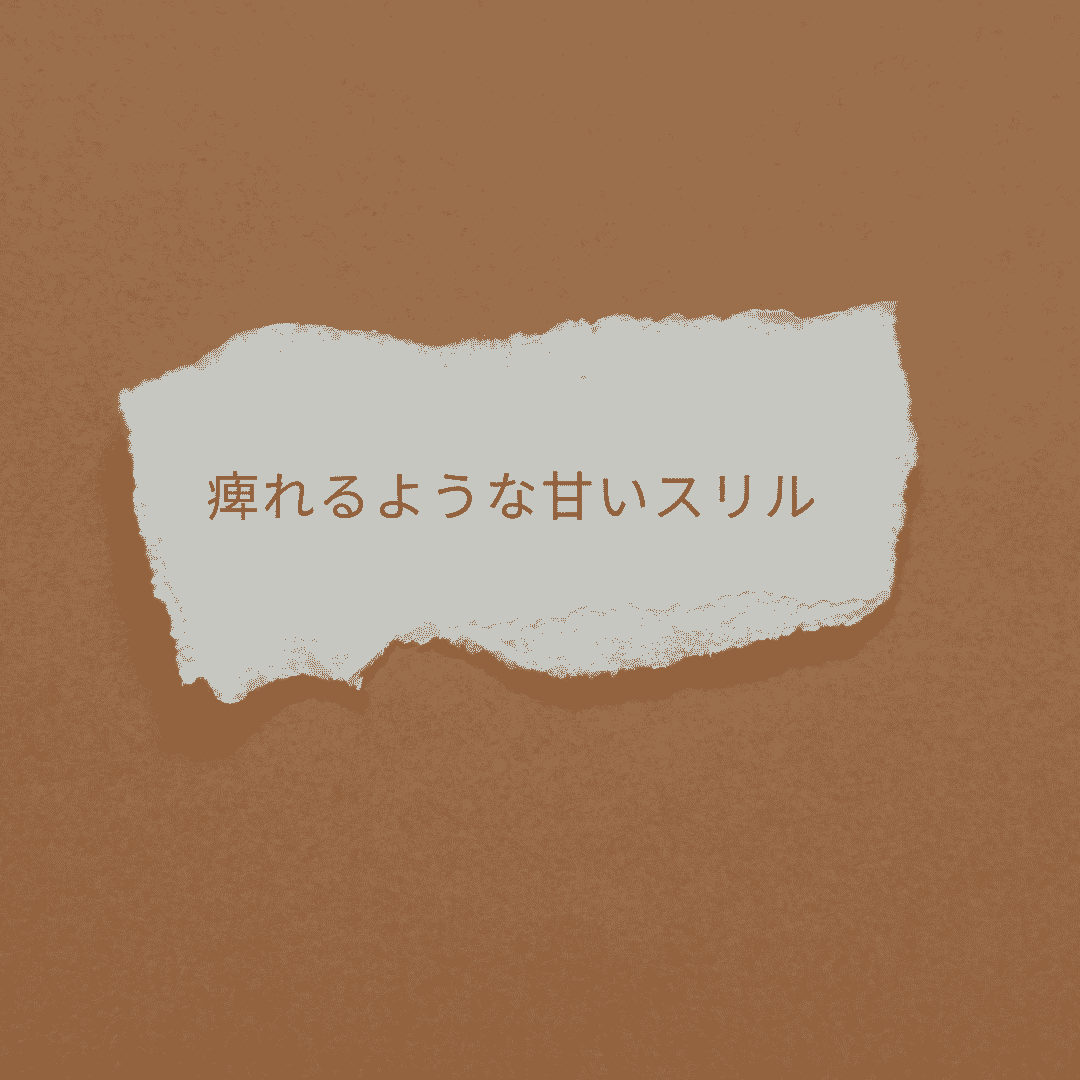

コメント