
0
アイドルPの野外Hレッスン
「はぁ…あん…」
誰もいない野外ステージに、私の嬌声が響く。
「ほら、もっと自分をアピールしないと。喘いでるだけじゃ何も伝わらないぞ。」
「あ、…。もっと…見て…」
「どこ見てほしいんだ?何してほしいんだ?」
「まゆのエッチなとこもっと…見て。はっぁん!もっといっぱい触ってぇ」
***
「お疲れ様ぁ。」
「お疲れ様。」
「ほんとに先に行ってていいの?」
「うん。もう一回だけ、振り確認してから追いかける。」
「ほんと勉強熱心だね、まゆは。」
「はは…」
「じゃ、先に行くけどちゃんとタクシー呼んでね。一応アイドルなんだし。」
「はーい。」
私は、まゆ。
グループでアイドルをやっている。
配信や路上ライブなどでそこそこの知名度がある私たちは、今日野外ライブの初日を終えた。
大きなステージではないけれど、満員の客席とファンの掛け声には、テンションが上がる。
グループ5人の中で断トツどんくさい私は、歌唱力はそこそこだけどダンスがかなりの苦手。
3日後にまたライブを控えているため、忘れないうちに復習しておこうと思って、残って練習することにした。
スタッフさんにはお世話になってるし、打ち上げには参加したいから、少し練習して合流しよう…
そう思っていた。
ステージは23時まで使っていいってスタッフさんに言われていた。
『帰りには管理事務所に声をかけてね。公園の入り口にあるから。』
そう言って、スタッフさんも先に打ち上げ会場へと向かった。
ステージに向かうと、裏の機材室の明かりがついていた。
あれ?まだ誰か残ってるのかな?
声かけたほうがいいかな?
でも、『少しだけだしいいかな』と思い直し、月明りだけに照らされるステージに立った。
1,2,3,4…
心の中でカウントをとりながら、気になっていた振りを一人で繰り返す。
ガタン。
しばらく一人で踊っていると、ステージ裏から音が聞こえた。
あ、もしかして機材室にいた人が帰るのかな?
そしたら、私もそろそろ引き上げようかな。
タオルで汗を拭いて、ステージの袖に向かう。
「まゆ、まだいたのか?」
「箱崎P、お疲れ様です。」
ステージの裏から現れたのは、箱崎亨(はこざきとおる)。
うちのアイドルグループのプロデューサーだ。
「まだ残ってらっしゃったんですね。」
「おう、ちょっとな。お前も打ち上げいかなかったのか?」
「あ、あのちょっと今日の振りがうまくいかなかったとこあって…」
「あぁ、4曲目か5曲目のやつだろ?」
さすが、わかってる。
「はい、次回に向けてみんなの足引っ張らないように少し練習してから打ち上げいこうと思って。」
「そうか。」
「はい。感覚残ってるうちに復習したかったんで。」
「じゃぁ。ちょっと見せてみ?」
「え?あ、はい。」
箱崎さんは、ステージの客席側に座って、私に踊るよう促した。
一通り踊ってみると
「まぁ、反省点はいかせてるんじゃない?」
と言ってくれた。
「ありがとうございます!」
「まゆさぁ、かわいいし歌もいいんだけどなぁ。」
「はぁ。」
やっぱりダンスがダメなのかなぁ?
そう思っていると、箱崎さんが立ち上がって近づいてきた。
「なんか足りないんだよね?」
「え?」
「わかる?」
「…いや、スイマセンちょっと…」
「ちょっと自己アピールが足りないんだよね。」
「自己…アピール?」
「5人で頑張ってるって思ってるっしょ?」
「…はい。」
「確かにそうなんだけどさ、ほかの子見てみ?」
ほかのメンバーの顔が思い浮かべる。
みんなかわいいし、歌だってダンスだって、ほんとに努力して頑張ってる。
ライブや握手会だけじゃなくて、SNSも上手に使いこなしている。
「確かにさ、みんなで売れるのは大事だけどさ、やっぱあいつらは”自分を一番売り込む”
っていうこともやってるんだよね。」
目の前まで来た箱崎さんを、じっと見つめる。
「仲間だけどライバルっていうかさ。でもまゆはちょっと控えめだよね。みんなが前に出るために自分を裏方にしちゃってるっていうかさ。」
「はぁ。」
「お前も同じ表舞台に立ってるんだよ?裏方じゃないんだから。」
「…」
「お前を見に来てるファンはさ、お前を見たいんだよ。彼らがお金出して見に来てるのはさ、自分の推しがキラキラ輝いててほしいからってこと。」
そっか…。
「だからもっと自分を売り込めよ。」
「はい。」
さすがプロデューサー。
思わず憧れの視線で見てしまう。
箱崎さんも、そんな私の視線に気づいて、私のほうを見てきた。
「なぁ。」
しばらく見つめあった後、箱崎さんが一歩私に近づいた。
「どうしたら自分をアピールできるか知りたい?」
「は、はい。」
どちらかというと、アイドルとしては個性も弱いし自己主張の仕方もうまくない。
そういう自覚はあるのだ。
アイドルになれてうれしかったけど、周りの子を見ていたらついつい『私なんか…』って思ってしまうこともあった。
こんなチャンスめったにない。
プロデューサー直々の指導なんて。
「そっか、じゃ特別にレッスンしてやるよ。」
そう言って、箱崎さんは私の後ろに回る。
腰を抱かれてそのままステージの真ん中までエスコートされた。
「今日ここに座ってた観客は全部がお前推しじゃない。」
客席に目をやったまま箱崎さんが言う。
「でもお前のパートの時は、大多数がお前を見てる。わかるよな?まゆ。」
「はい。」
「だからまずは堂々と立て。」
そう言って箱崎さんは私の腰に両手を添えて、足で私の足を肩幅に開かせる。
「アイドルになったからには見られてなんぼだ。存在感もカリスマ性も大切。」
「はい。」
「ここに立ったらほかの誰でもなく“私を見て”という気持ちを持て。」
箱崎さんが私を覗き込んできた。
自信にあふれた力強いまなざしが、月明りでもわかる。
「…私を見て…」
箱崎さんの言葉を繰り返す。
「お前を見せつけてやればいい。」
「はい。」
誰もいない客席に今日のライブの興奮がよみがえる。
私を見せつける…。
そうだ、みんなお金払って私たちを…私を見に来てくれてる。
自信をもって“アイドル Mayu”を見せなきゃいけない。
そう思っていると—
つ———。
「箱崎さん?!」
箱崎さんの手が腰からわき腹をなぞって、上に上がってくる。
「気にしないで、あぁあの歌うたってホラお前のソロ。」
「そう、言われても…」
「バカ、どんな状況でもすぐ笑顔つくれよ。」
あっ!そういうこと?
私メンタルを試されてるの?
ちょっと違和感を感じつつも、名プロデューサーの指示に従ってしまう。
「んあっ!」
歌い始めても私の身体を這う箱崎さんの手はとまらない。
首筋に鼻をうずめて深く息を吸っている。
これってホントにメンタル試してるだけ?
「ぁ!」
からだを這っていた箱崎さんの手が、わずかにバストをかすめた。
ライブ終わりにシャワーして、ブラはしていない。
カップ付きのキャミソールにしていた。
ライブの高揚感も冷めていなかったので、ちょっとした刺激に敏感になってしまう。
「あ、悪い。ほら続けて。」
箱崎さんの態度から悪気はなさそう。
これも特別レッスン。
そう思っているのに、再び…いや今度は確実に箱崎さんの手が胸に触れる。
「…!」
顔だけ後ろに向いて、箱崎さんを見る。
にやっと笑うその顔に“ぞくぞく”っとしてしまった。
「思ったよりでかいな。やわらかいし。」
そう言われて、顔が熱くなる。
「ほら、笑顔笑顔。もっと堂々としてろよ。」
箱崎さんは変わらずに、私に“アイドル”を求める。
歌おうとしてるのに、今度は首筋に柔らかい感触。
すぐにぬるっとした感触も続く。
あぁ、やだ首なめてるの?
こんなの…。抵抗していいのかな?
むに…。
「はぁ…!」
箱崎さんが私の胸を鷲づかみにする。
支えのない私のふくらみは、箱崎さんの手の平によって自由に形を変えていく。
ライブ後の興奮と久しぶりの感覚に、身体は欲望をのぞかせてしまう。
その手つきはとてもいやらしくて、耳にかかる吐息も淫靡に感じてしまったのだ。
箱崎さんほどの人になると、経験豊富なのだろうか?
気持ちいい…。そう感じてしまう自分が怖い。
密着している身体が熱を帯びてくるのが分かる。
私の身体の変化に気付いたのか、箱崎さんがぐっと腰をくっつけてくる。
…!これってもしかして…。
腰のあたりに固く熱いものが、押し付けられた。
すぐに、箱崎さんのペニスだと気付いた…。
これは特訓じゃない。
そう分かっているのに、もう身体は快感を求めてしまっている。
「まゆ感度いいね。もう感じてるんだ。」
「ち、ちが…」
「ふっ…。ほらここステージだよ。恥ずかしくないの?しっかり歌わなきゃ。」
そう言われて、仕方なく歌を続ける。
「へたくそだな。アイドルだろ。しっかりしないと罰与えるぞ。」
そう言って私のスウェットをずるっとおろす。
「あっ!いや。」
下着はつけているものの、むき出しになった私のおしりに“ぺちん”っと箱崎さんの平手が当たる。
「いたい!」
「いたいって言ったくせに乳首たったのはなんでだ?」
なんて、笑い交じりに言われる。
「ちゃんと歌わないからだよ。ほら笑顔も忘れんな。」
「は、はい…。ごめんなさい。」
「よし。」
そういうと、今度は箱崎さんの手が私の服の中に入ってきた。
「あ、箱崎さん…」
「とおるって呼べよ。」
「え?」
ぺちん!
「あん!」
「ほら、」
「とおるさん…」
そう呼ぶと、満足げにほほ笑む。
そして私の服をはぎ取って、首筋から背中までを箱崎さん…とおるさんの舌に舐めまわされた。
胸のとがりも強くつままれ、痛さと快感でどうにかなってしまいそう。
足に力が入らなくて、倒れて四つん這いになってしまう。
「立ってられないのか?根性ないな。」
とおるさんに見降ろされている。
「まぁ、ちょうどいいや。」
そういうととおるさんは自分のズボンをおろした。
目の前にいきり立つとおるさんの“ソレ”が差し出される。
「口の運動。ほらちゃんと持ってしゃぶって。」
私がおそるおそる手を添えると、とおるさんは頭を押さえつけて、私の口の中にそれを入れてきた。
「んん…」
口の中いっぱいのそれは、喉の奥まで突き立てられ、よだれと嗚咽が漏れてしまった。
それでも容赦なく腰を動かされ、私の口の中を彼の肉棒が何度も犯していく。
「んん!と…と、お…る、さ…。」
「ほらもう少し頑張れよ」
涙とよだれでぐちゃぐちゃだけど、夢中でそれに吸い付いた。
しばらくすると、とおるさんの腰が引かれた。
そのまま四つん這いでいると、とおるさんは私のおしりのほうに移動した。
そして私の下着に手をかける。
「いや…」
抵抗すると、とおるさんはにやりと笑った。
「いや?そんなわけないだろ。」
そう言って下着を素早く剥がすと、私の目の前に持ってくる。
「まゆ、下着ぐっしょりだけど?」
見せられて、恥ずかしくなる。
「男のちんこくわえて、自分のアソコびしょびしょにしてるとか…。アイドルとは思えないくらいはしたないなぁ。」
「あ、あ…、ごめんなさい。」
「はしたないけどさぁ、これじゃかわいそうだから…。」
そう言いながらとおるさんは、私の割れ目をなぞってくる。
「ひやぁ!」
からだの底から、ぞくぞくした。
「俺のでイカせてあげようか?」
イジワルに指を上下させられて、我慢できなくなる。
「は、はい…」
そう小さく言うと、
「ちゃんとお願いして。」
そう返された。
わずかに残る羞恥心と湧き上がる欲望が、せめぎあう。
「ほら、言わないと指でイクことになるよ。」
正直、それでもよかった。
でも根っからのMである私は、”恥ずかしいことを言わされる”ことに興奮してしまうのだ。
「あ…、とおるさんので、イカせて下さい。」
「え?俺のなに?」
「とおるさんの…、チンポでイカセテ…」
「いいね。自分の欲しいものはしっかり言わないとね。」
とおるさんは『よし』と言いながら頭をなでてくれた。
ポケットからゴムを出して私の背後からおしりをつかみ、ためらいなく私の割れ目を貫いた。
「あぁぁぁぁ!」
ご褒美として与えられたそれは、私を脳までしびれさせた。
「まゆ、顔上げて。」
私を後ろから揺さぶりながら、とおるさんが命令してくる。
「想像して、今日満員だった客席。」
「…あぁ、はい…」
「見てほしいんでしょ?みんなにまゆを。」
今はだれもいなくて静かで、月明かりしかない。
でも、ここにいっぱいのファンがいたら…?
私こんな恥ずかしい姿を見られちゃうの?
「まゆやらしいね。みんなに見られたら興奮するの?まゆの中きゅって俺を締め付けたよ。」
「はい…。みんなに見られたら、興奮します…」
「そっか、じゃぁもっとまゆのやらしいと見てもらおうよ。」
とおるさんは私の腰をしっかりと抱いて立ち上がり、つながったまま客席に向かって、私の足を開かせた。
「ほら、客先からまゆのが良く見えるね。」
「はぁ…あぁ。」
からだも頭もどんどん興奮してしてくる。
割れ目からは、だらだらとよだれが垂れている…。
「うわ…。むっちゃ濡れてきてすべる。」
「あぁん…いや。」
「“いや”じゃないじゃん…クク…」
と、とおるさんが笑っている。
「はぁ…あん…」
静かなステージに、私の嬌声が響く。
「ほら、もっと自分をアピールしないと。喘いでるだけじゃ何も伝わらないぞ。」
「あ…。もっと…見て…。」
「どこを見てほしいんだ?何をしてほしいんだ?」
「まゆのエッチなとこもっと…見て。はぁん!もっといっぱい触ってぇ。」
「もっとちゃんと脚広げないとちゃんと見えないよ。」
とおるさんに揺さぶられながら、自分でも胸やアソコを触る。
もっと激しくもっといっぱい。
「あぁん…とおるさん…。出ちゃう!出ちゃう!」
「いいぞ!」
とおるさんはつながったまま私を四つん這いにして、後ろから何度も激しく突いた。
「あぁぁぁぁっぁぁん!」
目の前がちかちかして、私は達した。
そして、ぬるっと箱崎さんのモノが抜かれる。
「すげえな、まだあふれてる。」
太ももに熱い液体が流れている。
私はそっとそこを指で広げて、中からあふれる液体に触れた。
「みんなに見えたかなぁ…?」
うつろにそう呟く。
「ふっ…とんだ淫乱(おおもの)だな。」
箱崎さんは鼻で笑って、ズボンをあげて立ち上がった。
「レッスンは終わりだ。今タオル持ってきてやるから。」
そう言ってステージのわきを降りて行った。
まだステージで横たわっていると、月が雲に隠れて満天の星が現れた。






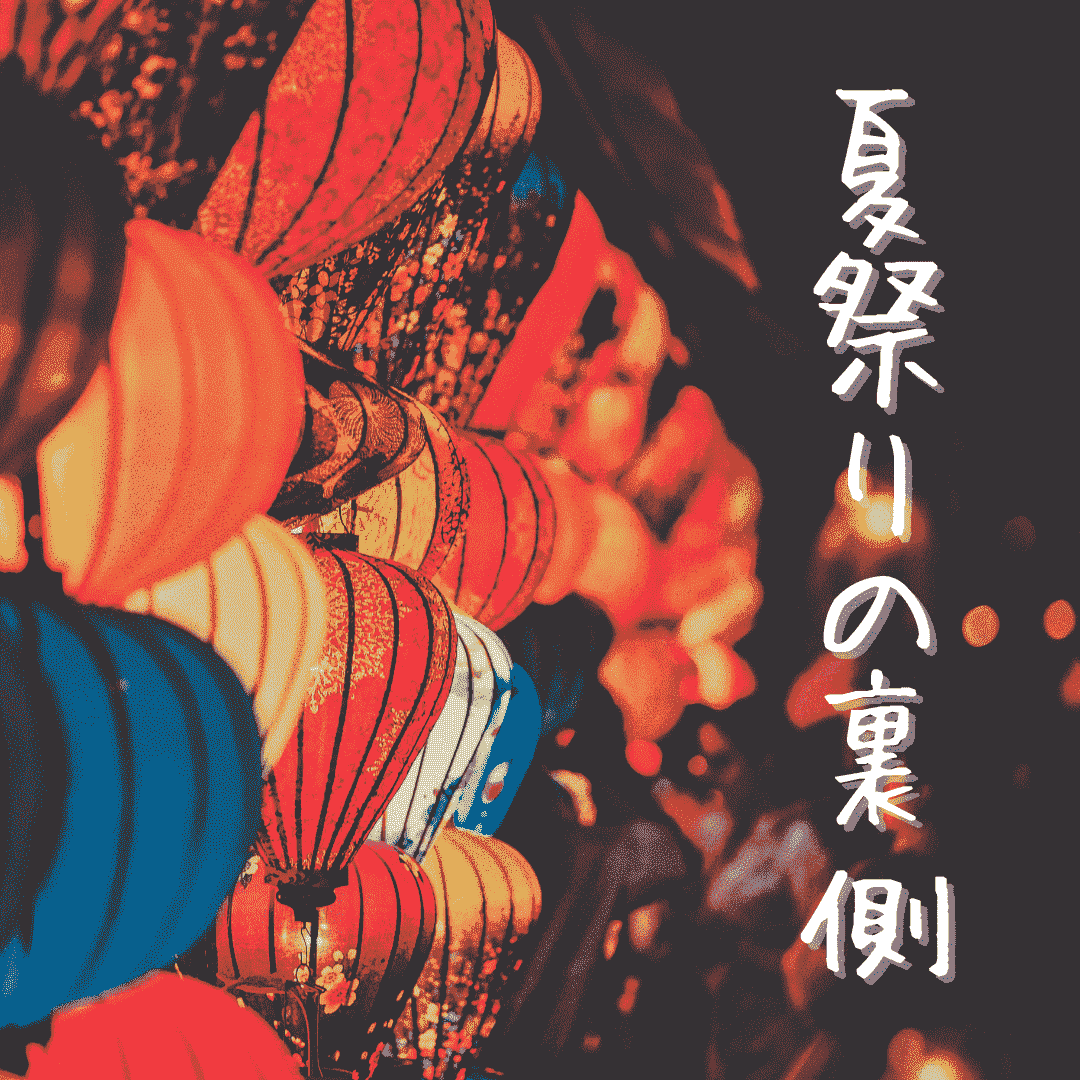

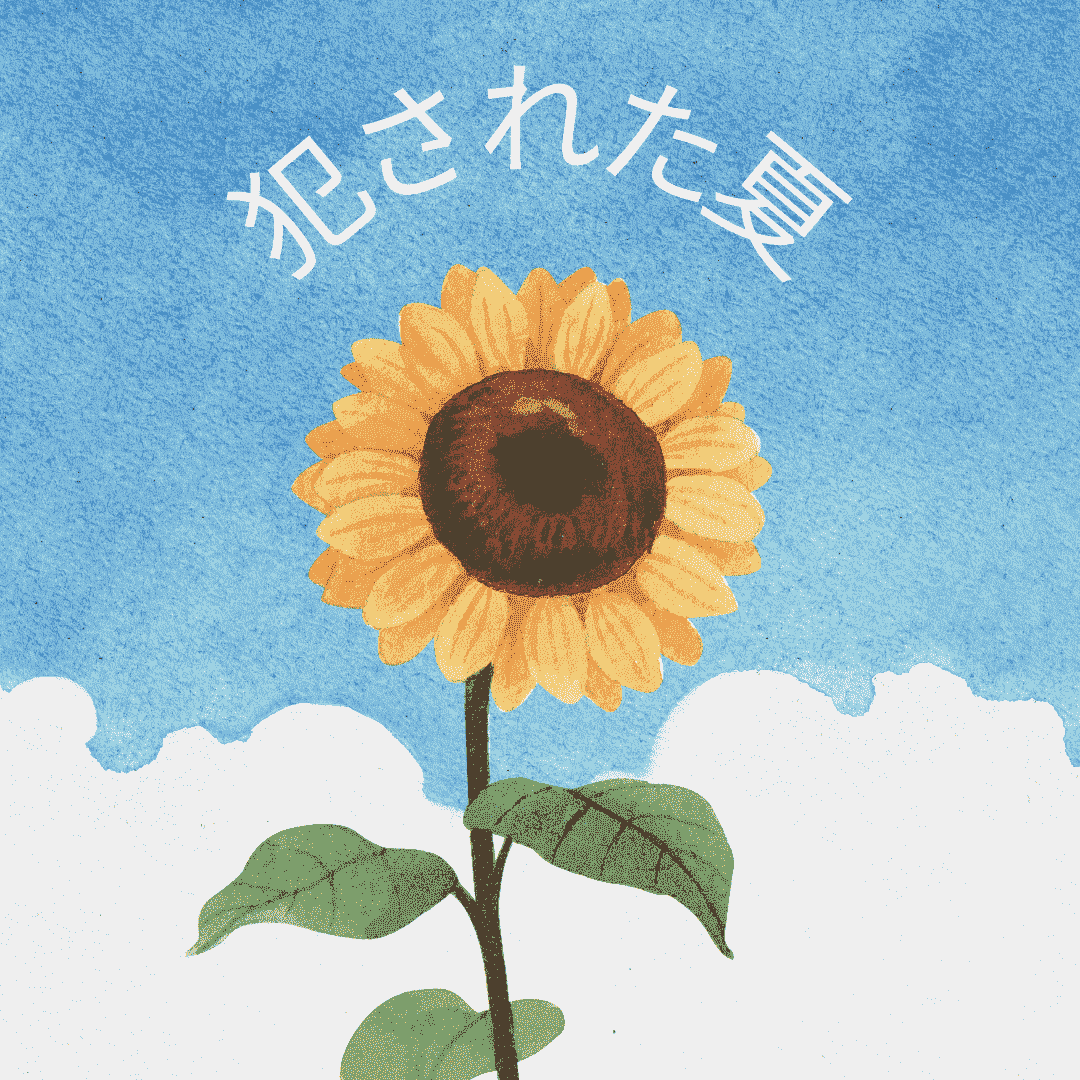


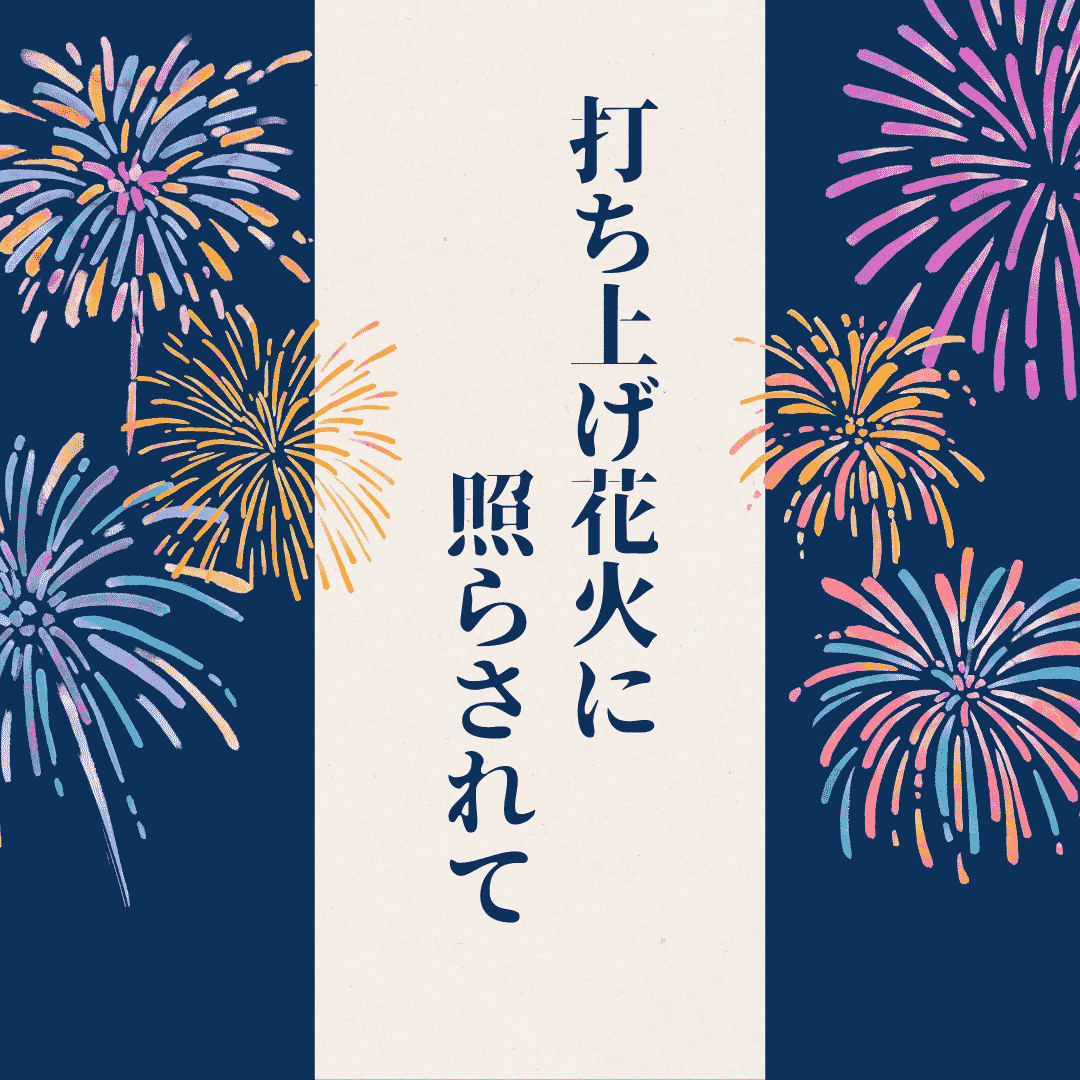

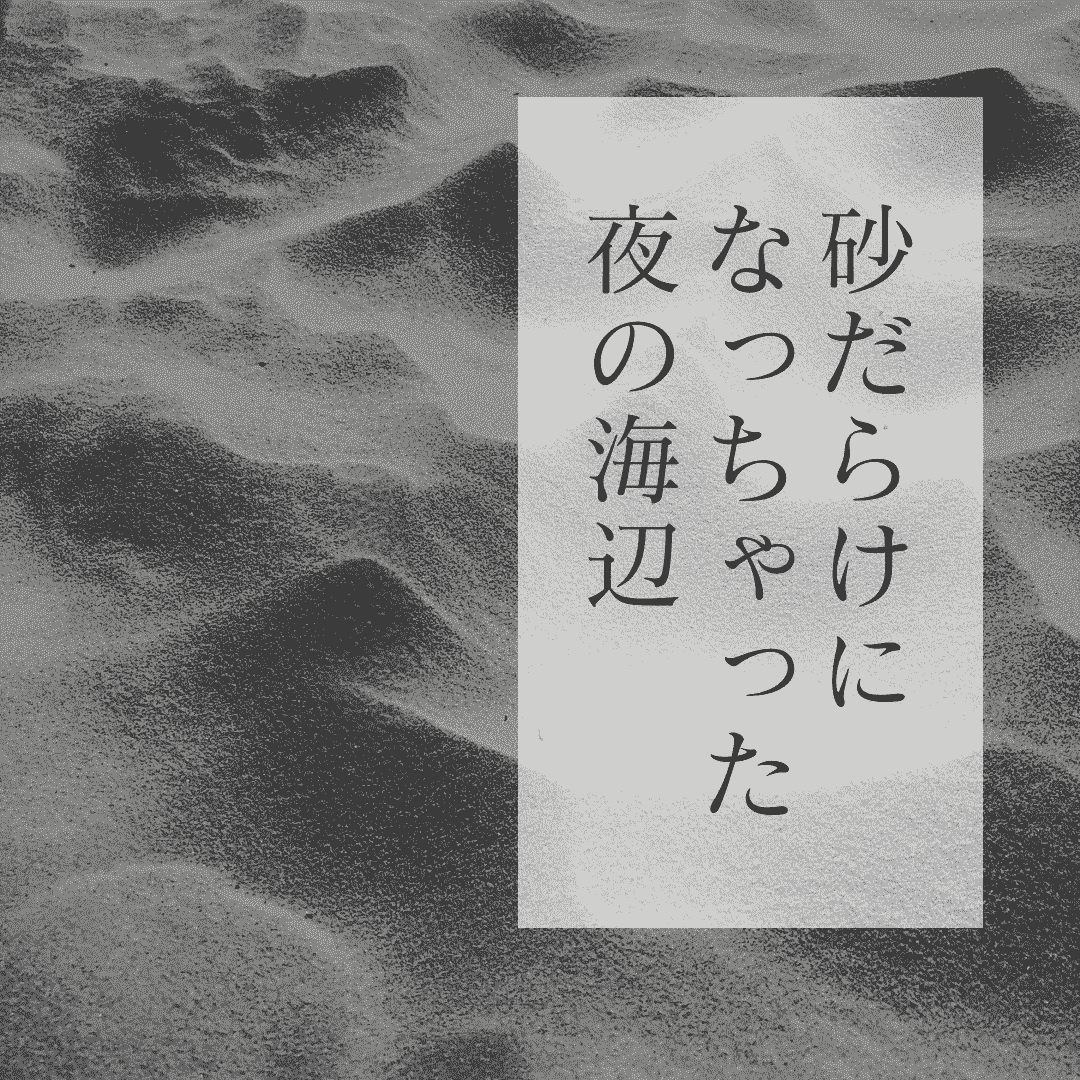

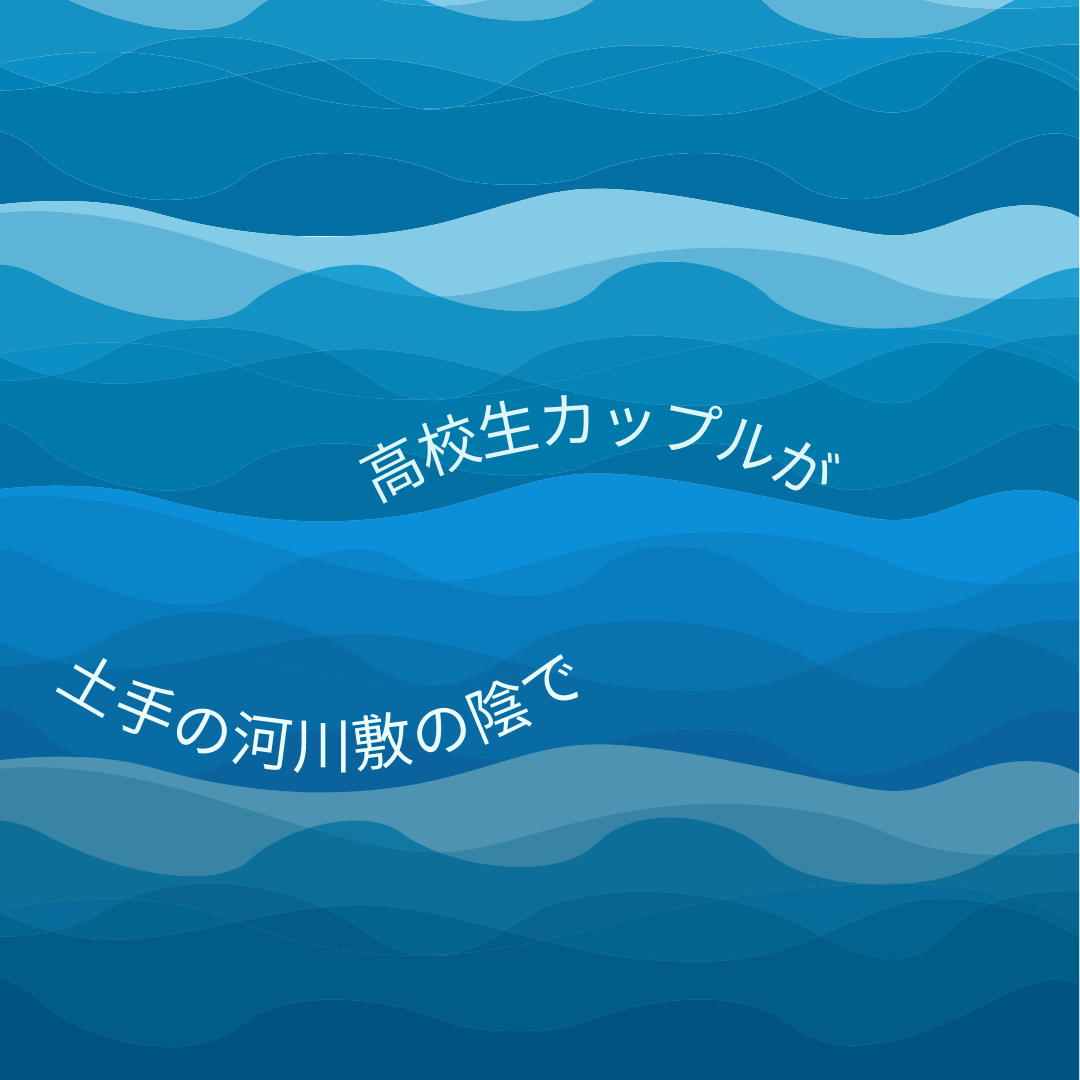

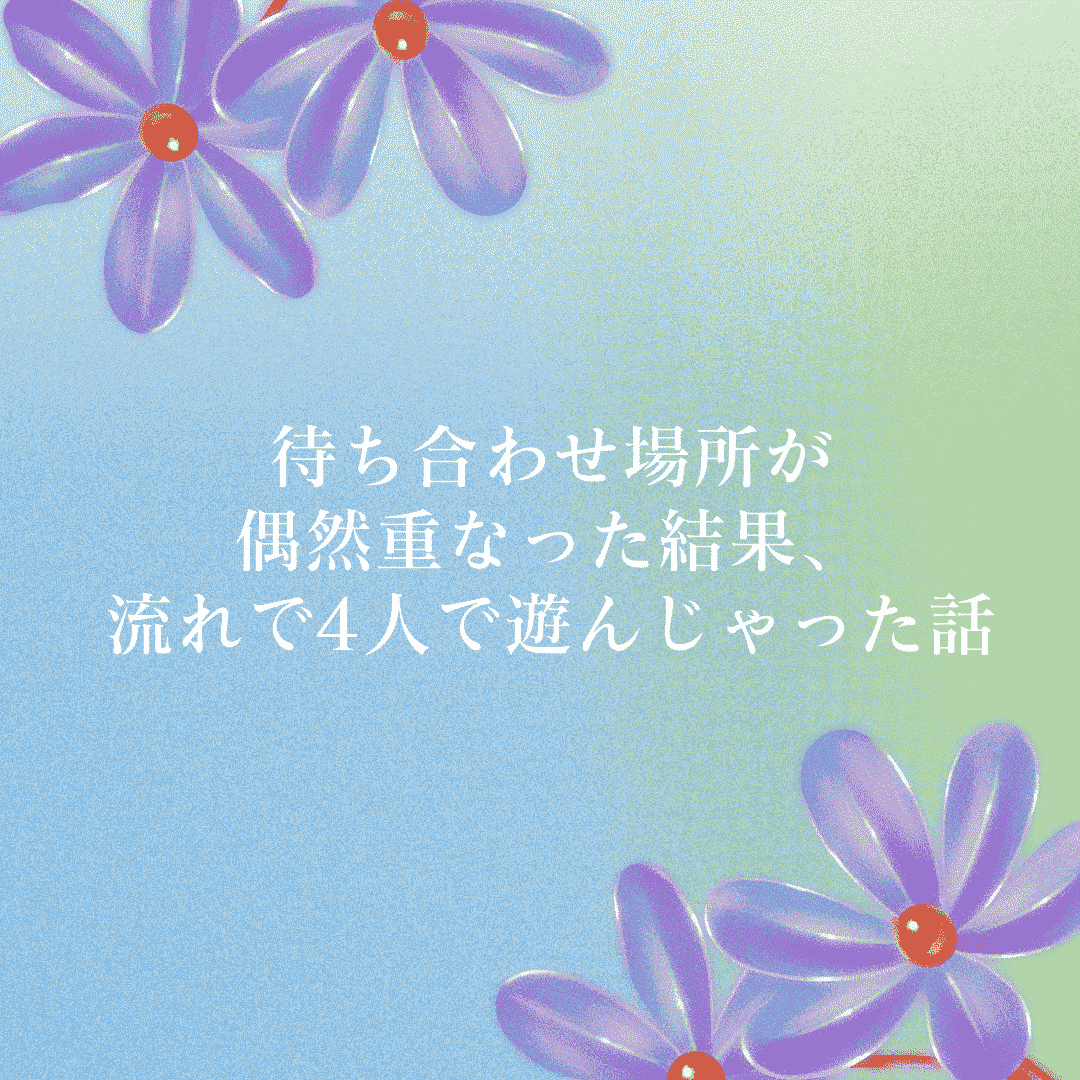




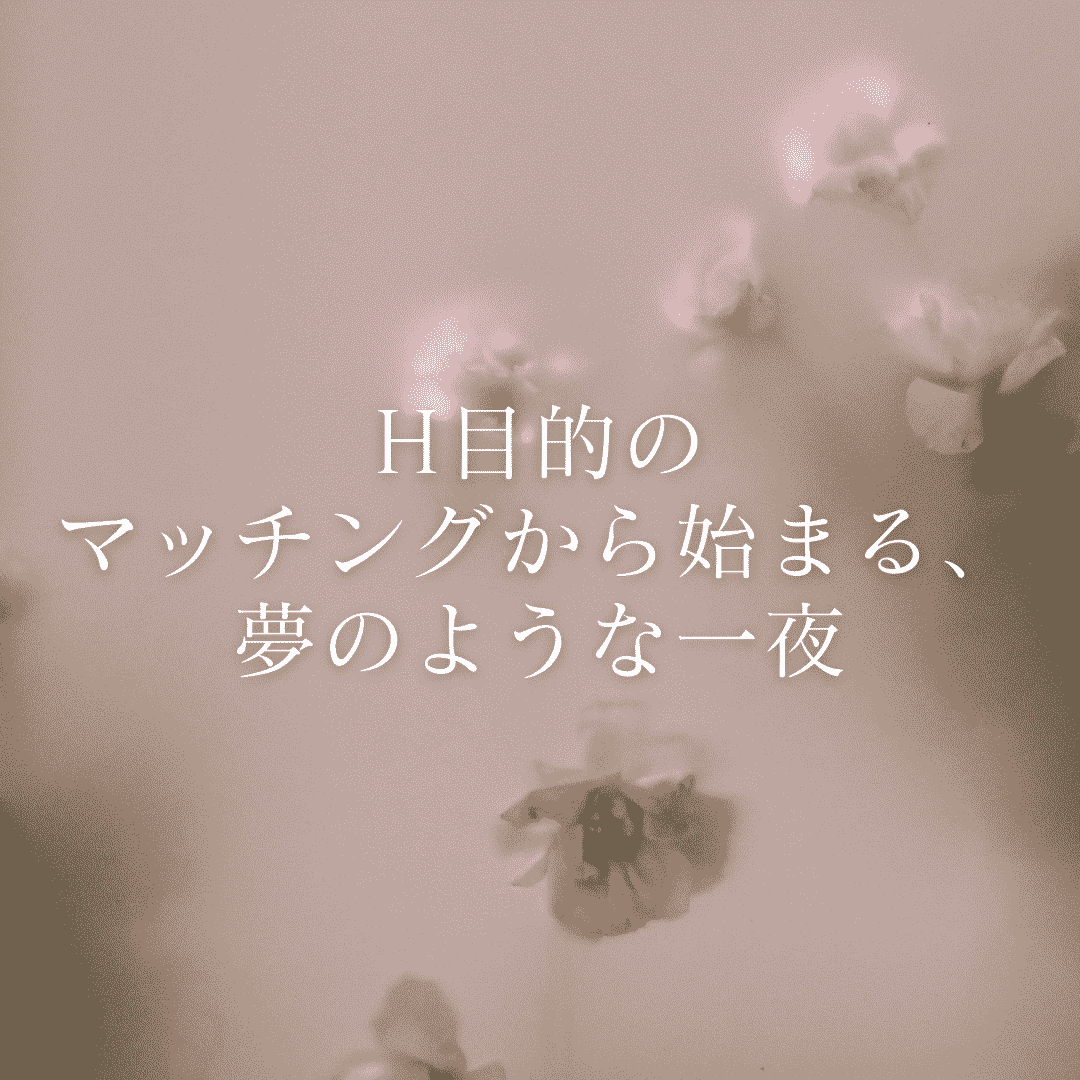

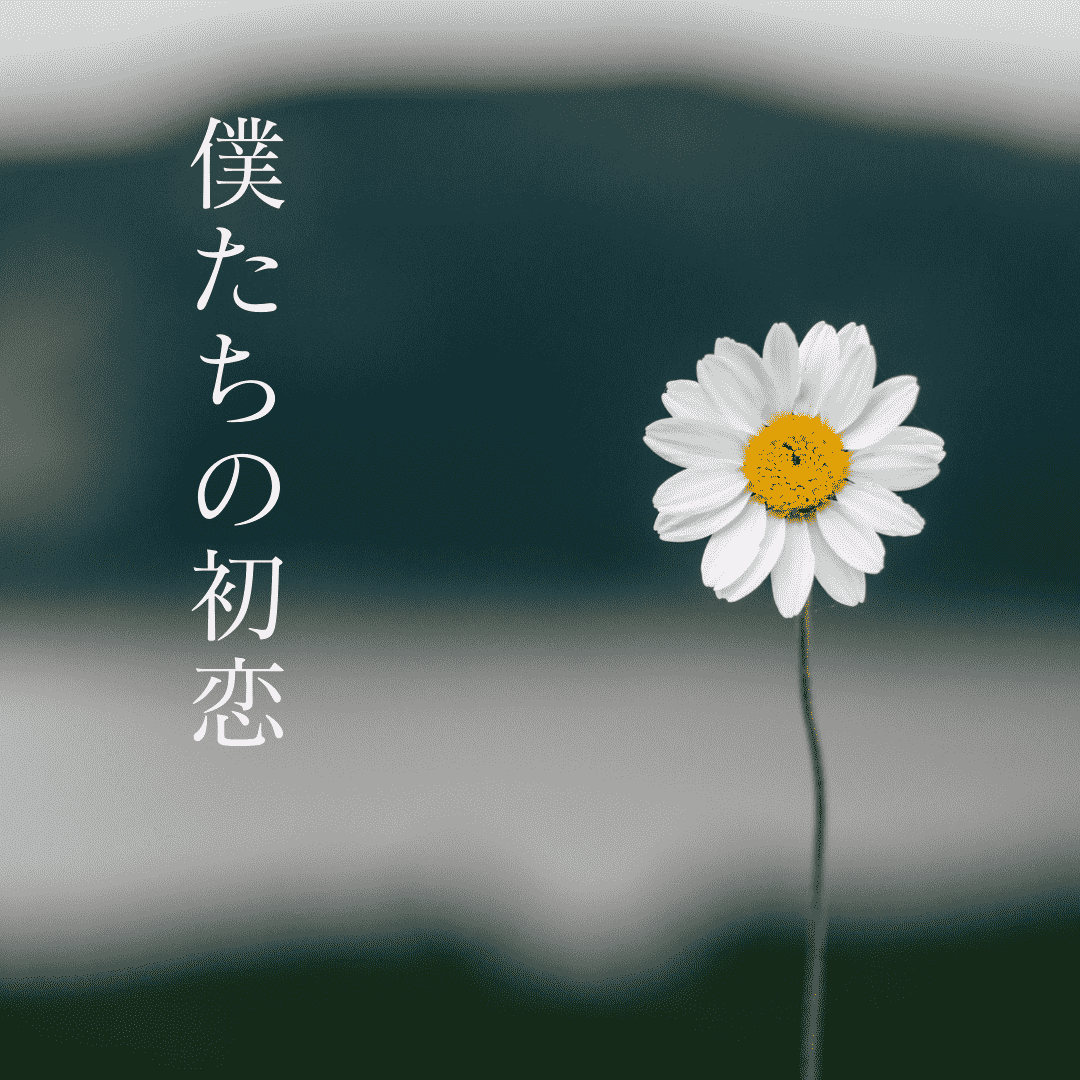


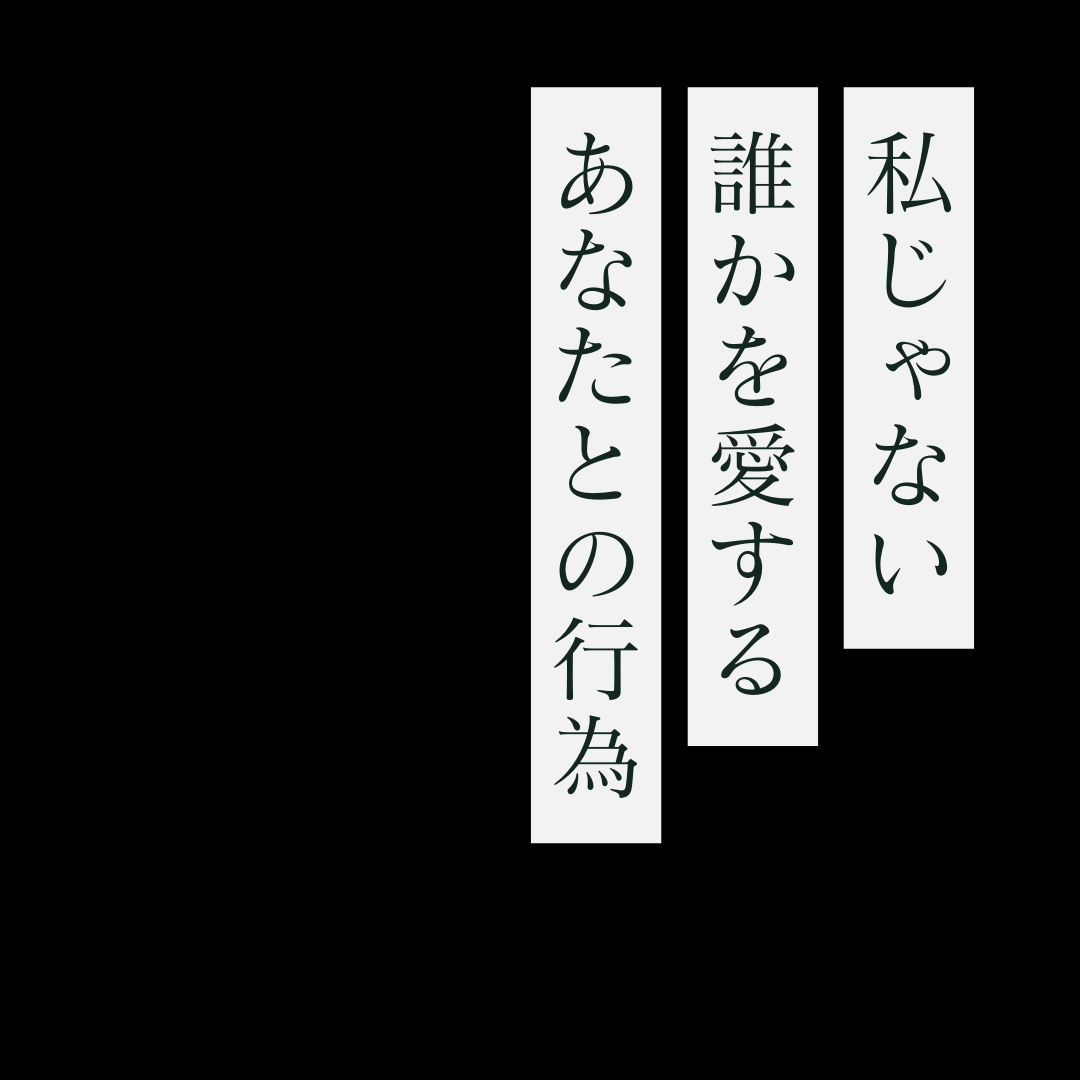

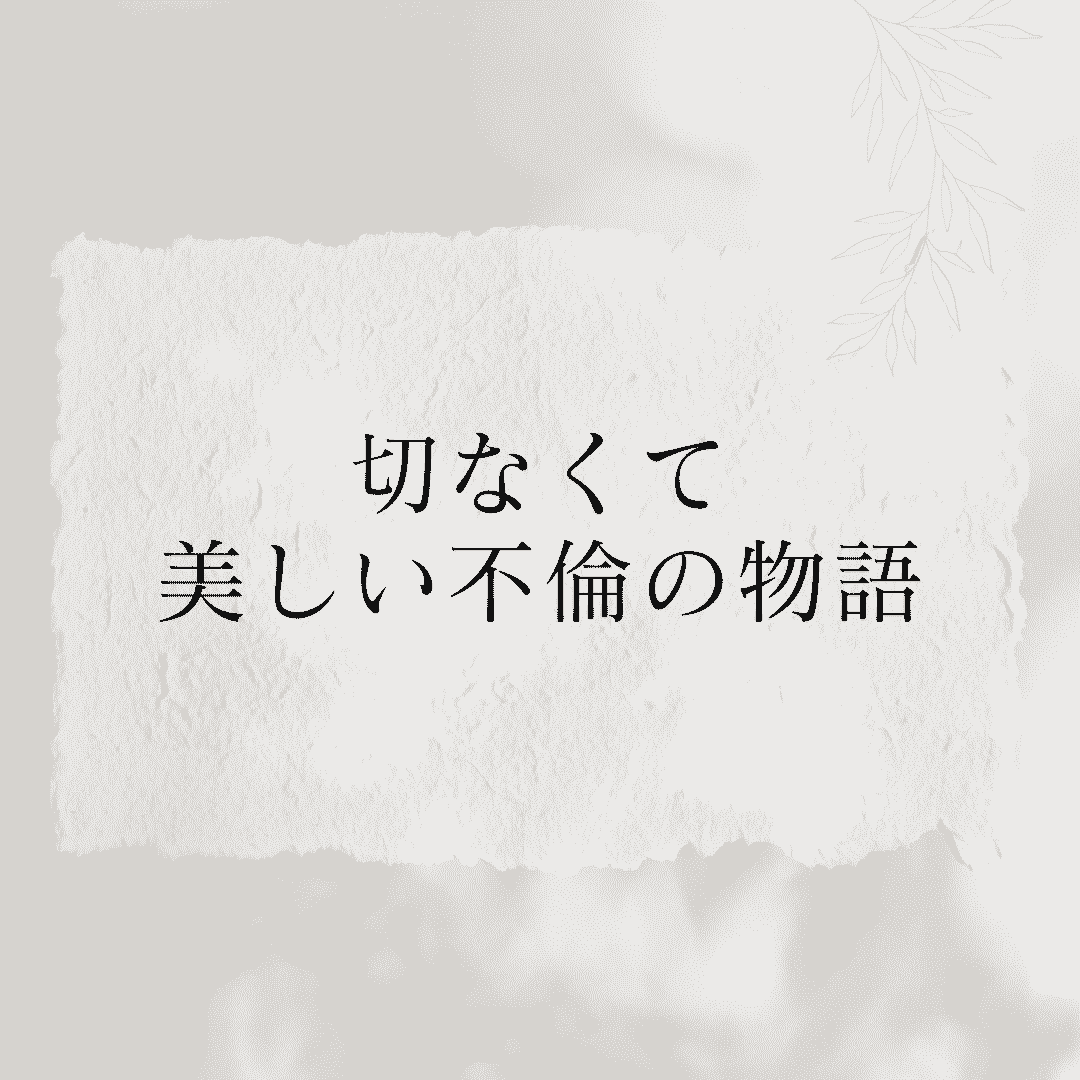
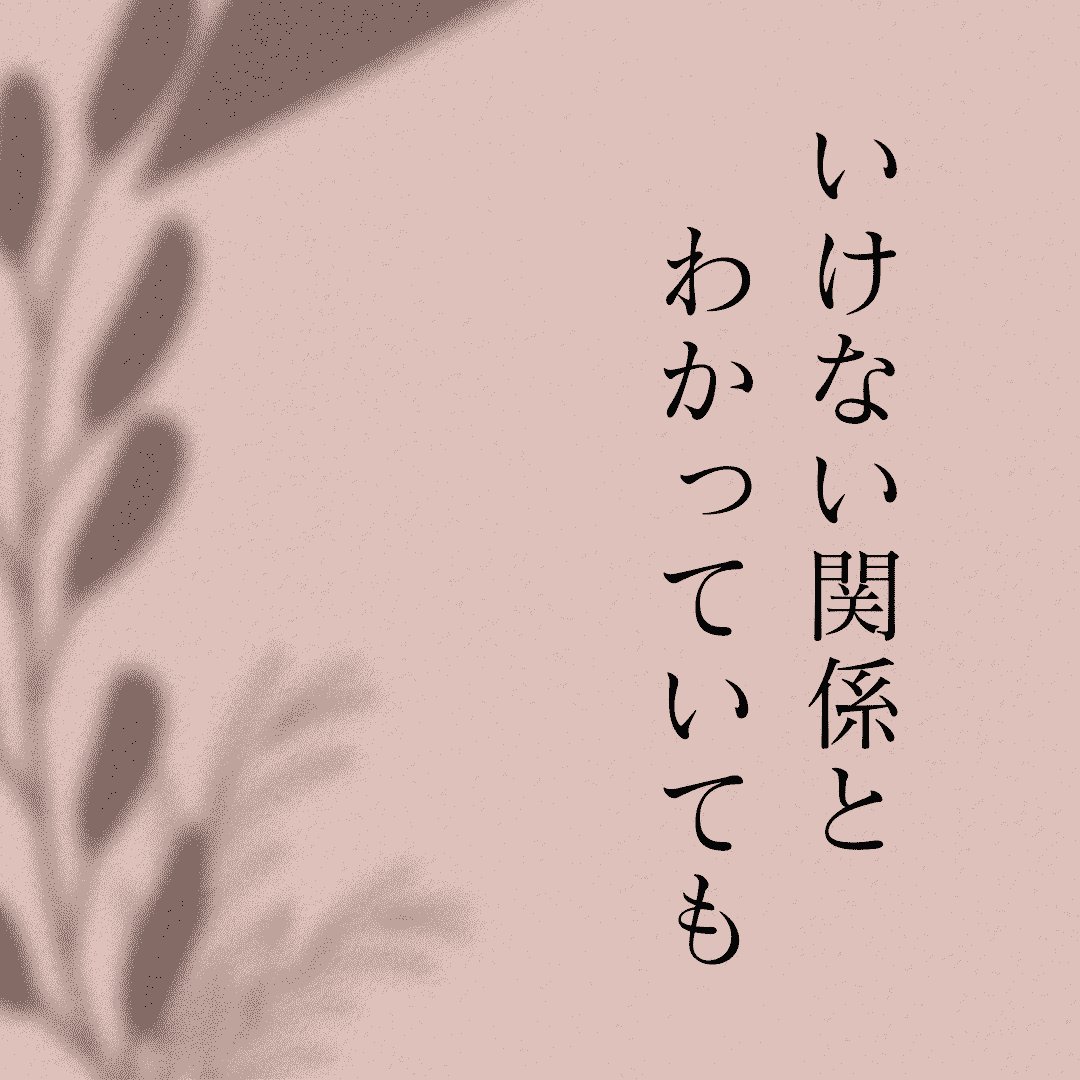









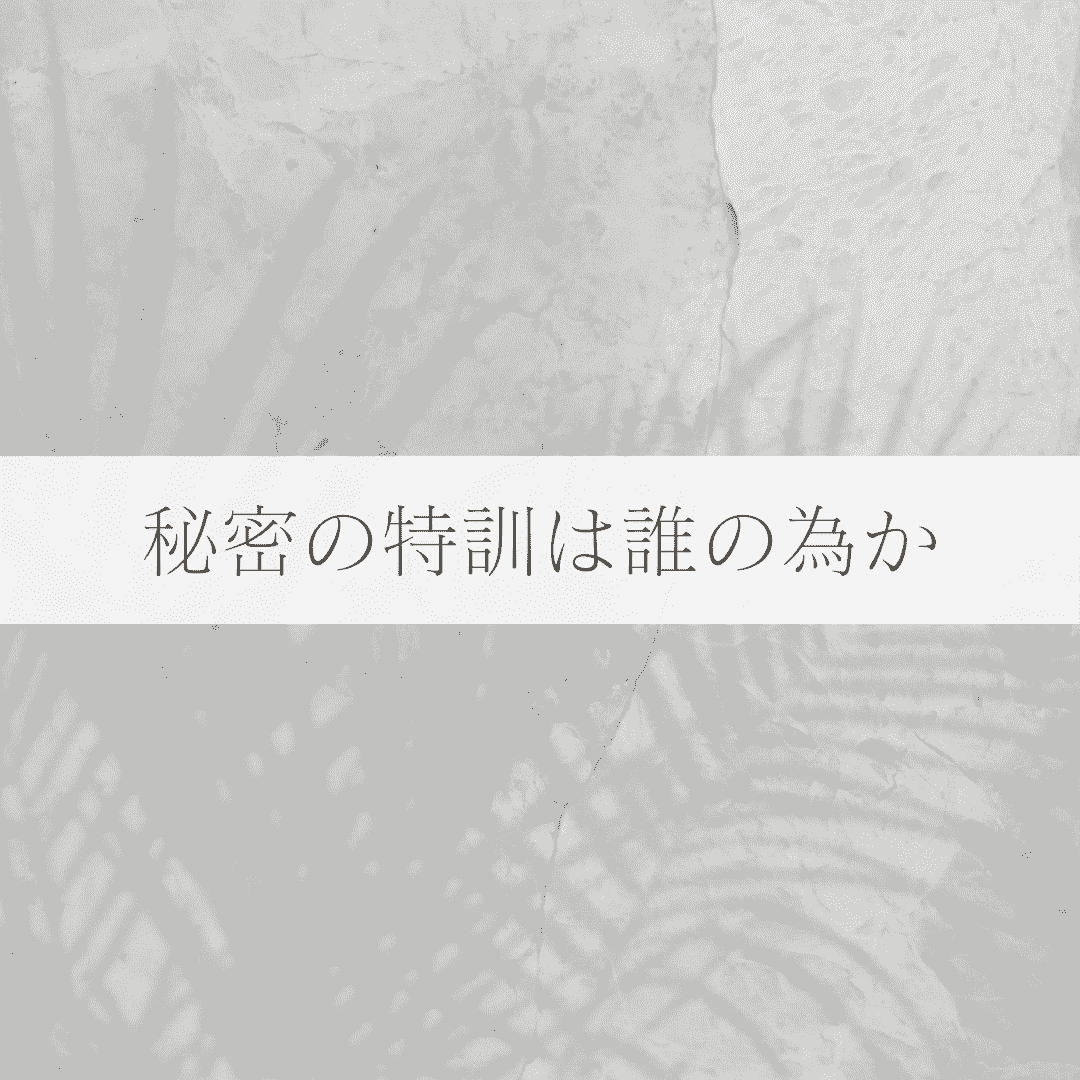
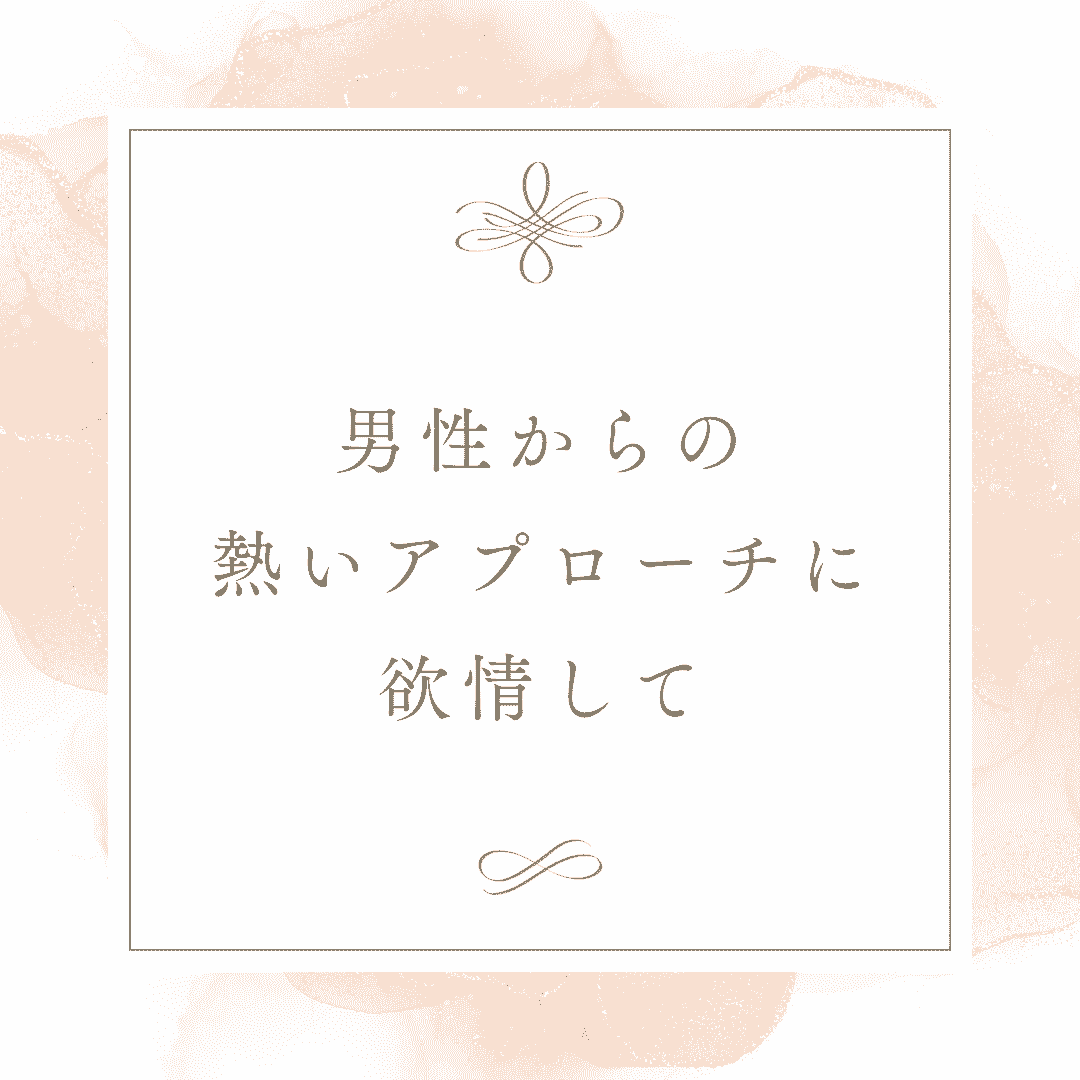


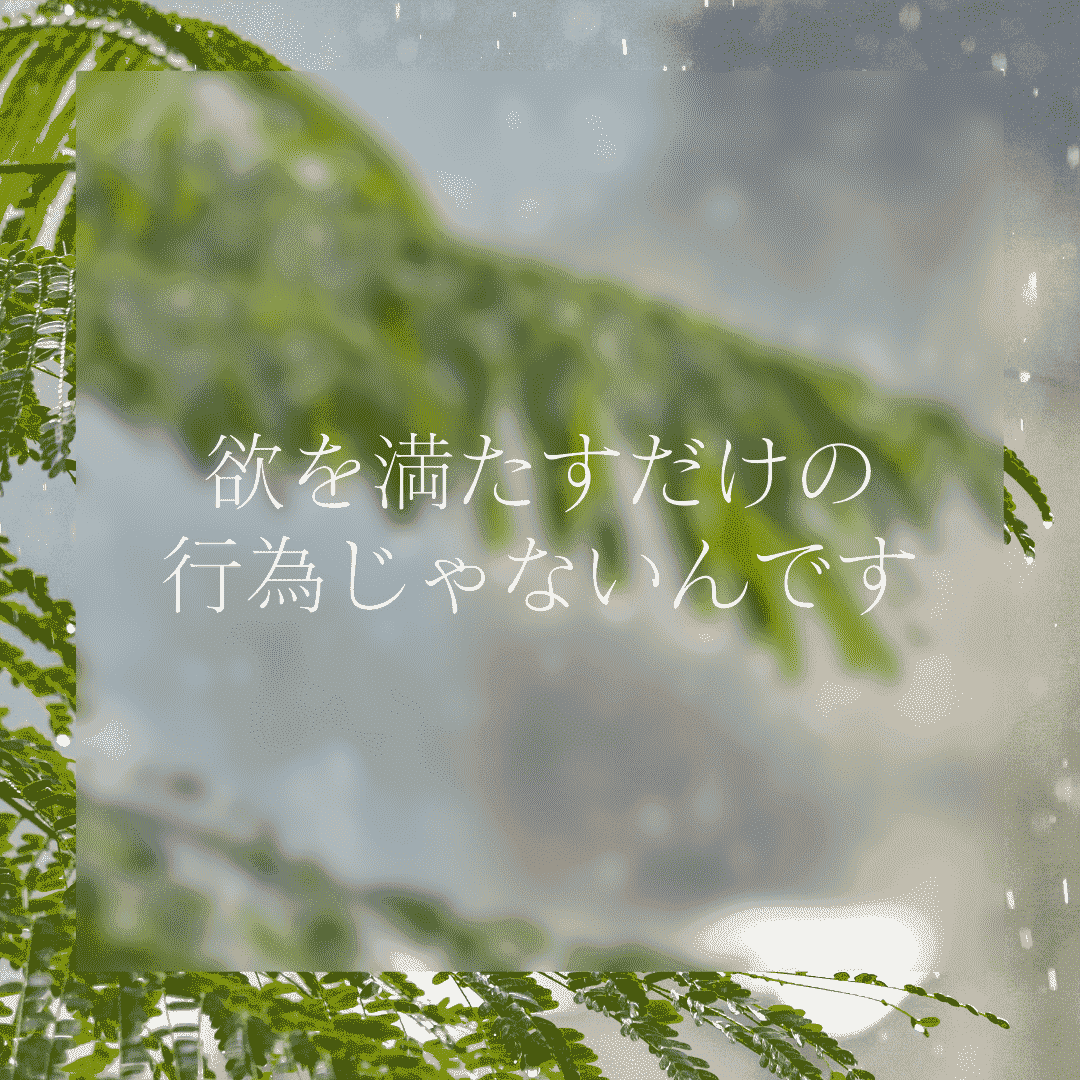

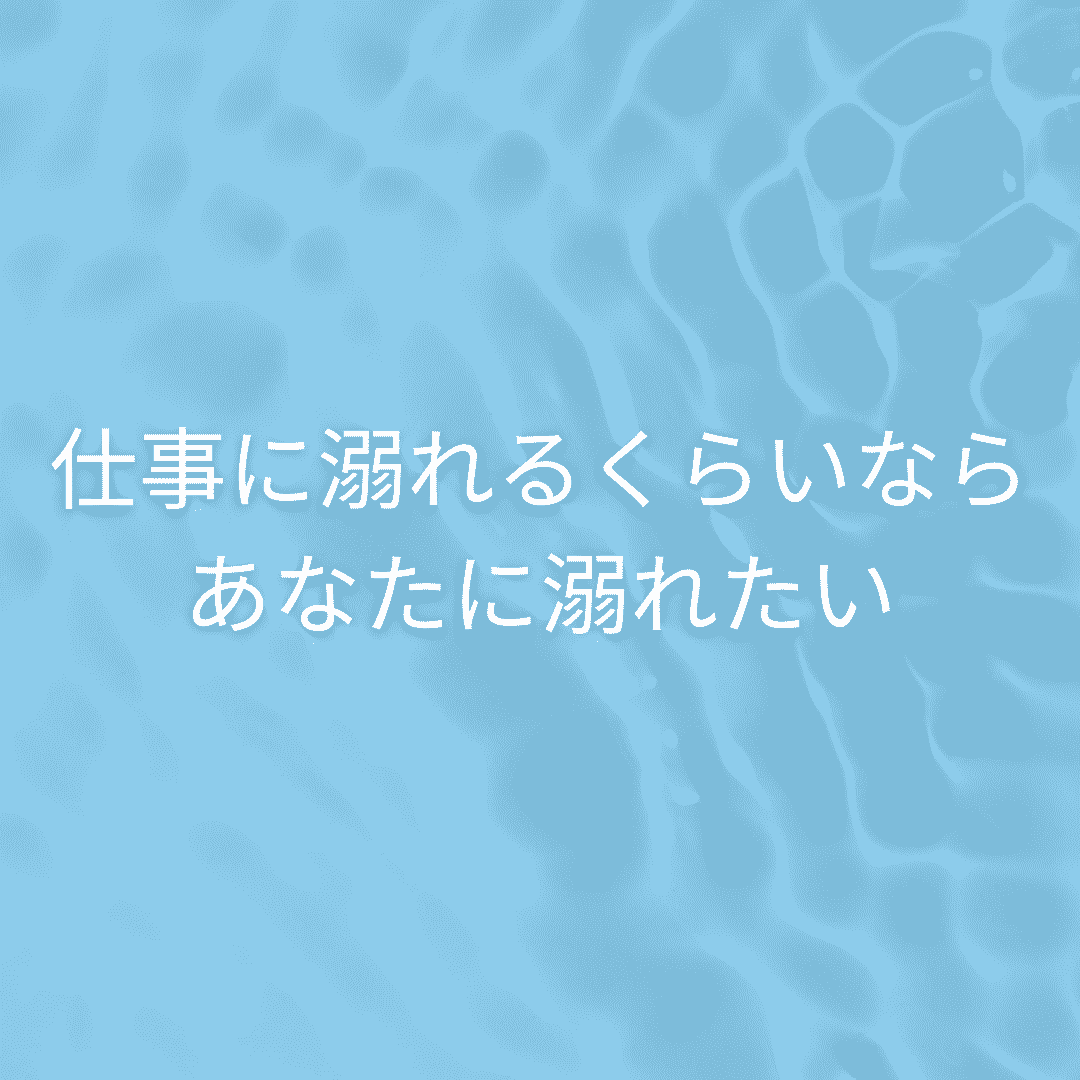


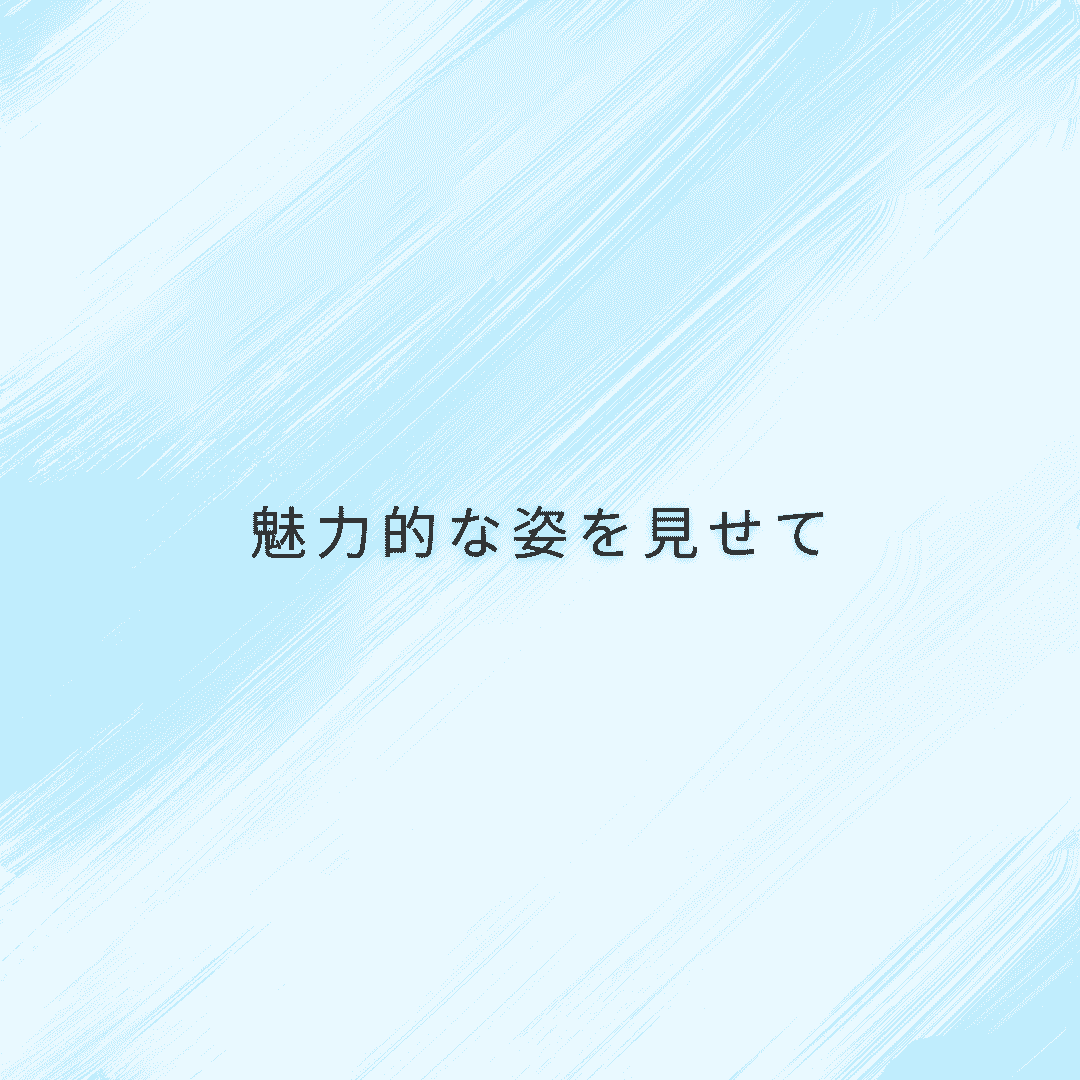
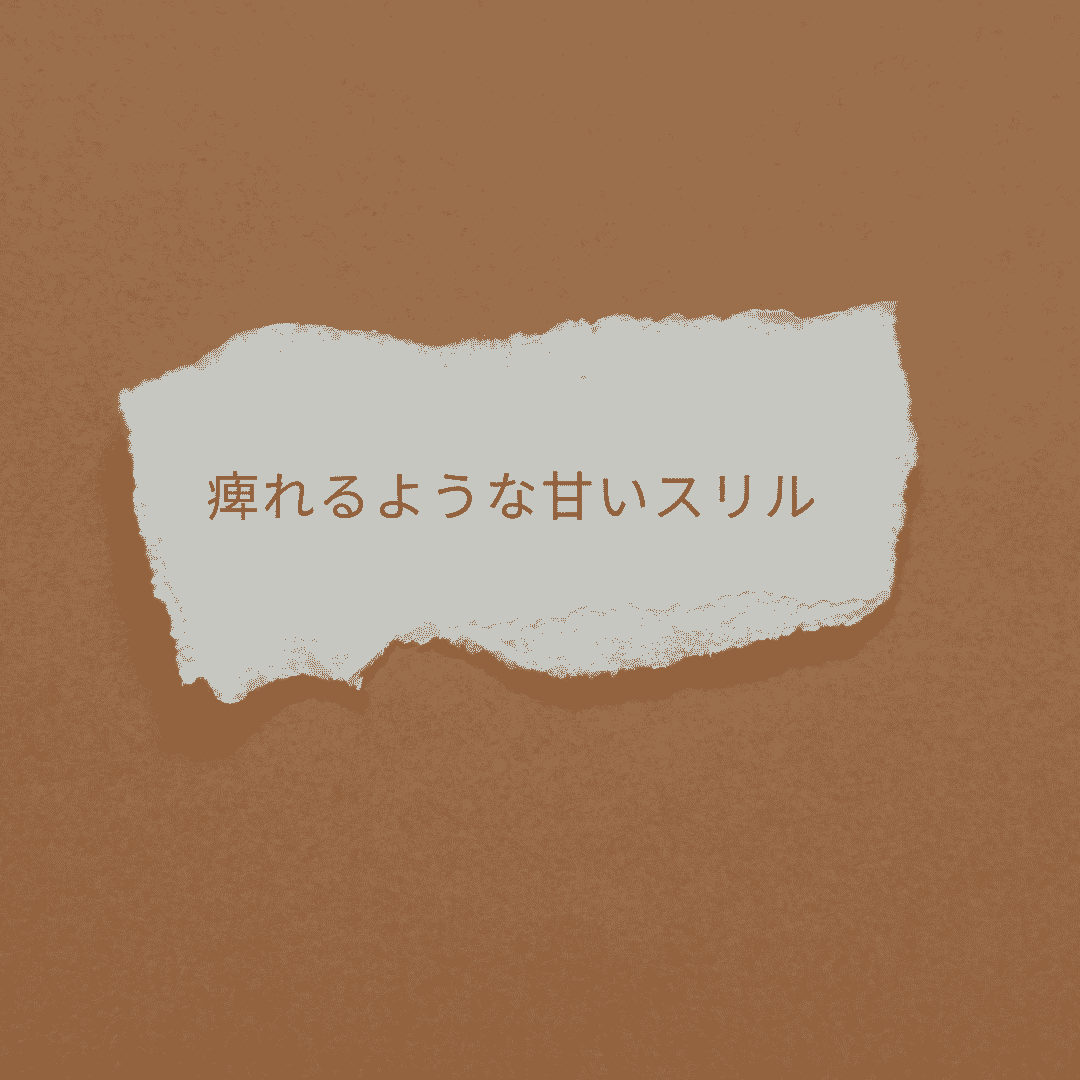

コメント