
0
忍び寄る指先〜もう抜け出すことはできない
熱い。タクミの長い指に触れられた太ももが、じわりと熱を持った。
そんなはずないのに、太ももが熱でピンク色に染まってしまった気がして、それを確認するために上半身を起こそうとした。なのにタクミに肩を押され、簡単にベッドに押し付けられてしまう。
どうやったってこの人には勝てない。
「サキ、何か気になるか?」
私が上半身を起こそうとしたのが気になったのか、太ももを触りながら聞いてきた。もう素直に答えるしかなさそう。
「そうやって触られると、すぐ熱くなっちゃう。」
「サキ、俺が触るとすぐ興奮しちゃうもんな。」
「あ……っ!」
太ももを撫でていた手がゆったりと移動し、タクミの中指が、既に濡れているまんこにゆっくりと侵入してきた。
「んぅ……っ」
「まだ動かしてないじゃん、指1本入れただけで気持ちいいの?」
「ちがっ、まだ、気持ちよくな…」
「じゃあいっぱい動かしてやるよ。」
柔らかく暖かい指が、中を傷つけてしまわないように、優しくぐちゅぐちゅと動き出す。
「あっ、あぁ……んっ」
声を抑えようと手で塞いでも、タクミにすぐに退かされてしまう。サキは諦めてそのまま声を出し、その大好きな指の感触を中で味わった。
大学の友人の付き添いで行った、合コンで知り合ったタクミは、穏やかで無害そうな見た目とは裏腹に、かなり性欲が強い。合コンのあと、そのまま勢いでラブホに向い、初対面で汗だくのまま3回戦し、身体の相性がいいからまた近々会おうよ、簡単な口約束と連絡先を交換し、その日は解散した。
その5日後、タクミから連絡がきたのだ。合コンの日に入ったところと同じラブホに集まり、あの夜と同じくらいの回数交わって、終わったら速攻で帰宅した。
そんな関係を始めてもうすぐ3ヶ月。どちらからも付き合おうと言うことはなく、ただ週に1回セックスをするだけという、わかりやすいセフレの関係。
初めのうちはそれでよかった。なのに、最近なんかおかしい…。
タクミに触れられた部分が、じんじんと熱を持ってしまい、まるで、身体全体が支配されているかのような気持ちでいっぱいになる。
最初のうちは気のせいかと思っていたが、回数を重ねるごとに、そのじんじんとした熱は、ただの熱ではなく、何か違うもののように思えてきた。
「もっと触ってほしい?」
腰をびくびくと揺らす私の反応をおもしろがって、わざと指の動きを止めたタクミに、意地悪く聞かれる。
出会って3ヶ月になる今日、私はタクミにちゃんと言わないと。タクミに触られるたびにじんじんするのは、タクミのことが好きだから、熱をもってしまうのだと。
「触って……中、もっとぐちゅぐちゅにして。好きだから。」
「好き?」
「好き……タクミのこと、好き。」
勇気を振り絞ってそう言った。なのにタクミは何も答えず、ただ口角を少し上げて笑ってみせた。そして、さっきより激しくまんこを弄り始めた。
「あっ、あぅ……っ、はげし、いッ」
いつの間にか人差し指も入っていて、2本の指がぐちゅぐちゅと愛液を泡立たせている。はあはあと半開きになっている私の唇の近くに、タクミの唇が触れた。またそこもじんっ、と熱を持ち始める。好きだ、好き、指で触れられても、唇で触れられても。全部、全部心地いい…。
「も……っ、入れて。」
中をかき混ぜる音を聞きながら懇願すると、タクミはあっさりとまんこからその指を抜き、素早くちんこにゴムを被せた。
あれが私の中に入るの、もう何回目だろう。会うたび最低でも2回戦はしているから、もう大体……数えようとした次の瞬間、硬いものが、奥を抉るような勢いで、まんこに入ってくるのを感じた。
「ぁあああっ!」
「よそごと考えないの。」
「なんっ、で…」
「目の動きでわかる。バレないと思った?」
ほわほわとした見た目でいかにも天然そうなのに、タクミはときどきすごく鋭い時がある。その鋭さを持つ人間が、私の好きな温かい指の持ち主と同一人物なことを、今でもたまに疑うことがある。
「あっ、あっあんっ、あっ!」
連続で奥ばかり押され、そのたびに耳を塞ぎたくなるような、甘ったるい声が漏れてしまう。タクミは、私が喘げば喘ぐほどピストンを早くするのだ。それがわかりやすくて、おもしろい。タクミの指に興奮する私と、私の喘ぎ声に興奮するタクミ。
私たちの未来はきっと明るい。
血管が張り詰めているちんこが出入りするたび、全身の血がとんでもない勢いで駆け巡り、頭が真っ白になる。
この行為をご褒美に、私は大学の講義を休まず受け、バイトに勤しんでいる。これがなくなったら、私は人間を保てるだろうか。そんなことを考えてしまうようになっていた。
限界が近いのか、タクミの腰の動きがさらに速くなっていく。私はそのピストンの衝撃と、強すぎる快楽に耐えるため、タクミの手を取り、大好きな暖かい指に触れた。指と指を絡ませ恋人繋ぎのようにすると、頭が沸騰しそうなくらい熱くなり、新たに分泌されたサラサラの愛液が、とろりといやらしく、まんこから垂れた。
タクミの腰の動きが遅くなり、薄いゴムのなかに射精したことを察する。絡ませていた指を離し、ゴムを外し、その口を結ぶのを、サキはぼーっとしたまま見ていた。
あ、さっきの返事聞かなきゃ。
「タクミ、さっき言ったことなんだけど。」
「ごめん。俺付き合ってる人いるから。」
行為後の多幸感でぼーっとしていた頭にがつん、と重たい石を投げつけられたような感覚。そのまま石が埋め込まれたように頭が重くなり、サキはしばらくベッドから動けそうになかった。
「それに、俺たち最初からそんなんじゃなかっただろ。」
「そう、だね…」
そのまま泣きそうになるのを堪え、タクミの顔も指も、できるだけ見ないようにしながら私はシャワールームへと駆け込んだ。
私は忘れることにした。
タクミという男など知らない、と思い込んで生きていくことにしたのだ。
あの日以来連絡も取っておらず、何をしているかすらも知らない。
そして、サキは大学を卒業し、同じ職場で知り合った男と付き合い始めた。明け方で薄暗い彼の部屋にあるベッドの上は落ち着くし、今気遣いのできる優しい男だ。触れ合っていても、私はあの日のようには濡れることはない。タクミの声ですら上手く思い出せないのに、私に優しく触れるあの指の感触だけは、頭から離れてくれやしなかった。私は何を求め、どんな人生を歩みたいのだろう。そうやって、時々自問自答することがある。
「サキ、どうしたの?」
ぼーっとしているところを、後ろから抱きしめられる。温かい、だけど、温かい以外何もない。
「……ごめん、今はひとりにして。」
「ごめん。わかった。」
その次の週末、私は1ヶ月住んでいた彼の家を出た。タクミが今どこで何をしているかの情報が、たまたま友人から送られてきたのだ。もう忘れたと思っていたのに、情報を知ってしまったら、身体が勝手に動き始め、家の中の荷物をまとめ始めていた。
夜22時、送られてきたバーの前に立っている。重たい扉を押し、ゆっくりと中に入っていく。店内には他の客は誰もいなかった。
「いらっしゃいませ。」
落ち着いた声。忘れていたはずの声なのに、その声を聞いた瞬間に、ちゃんと思い出すことができたのだ。昔よりも長くなった前髪の間から見える、切長の目。
「タクミ……」
カウンターの向こうにいるタクミは目を見開き、持っていたグラスを机に置いた。
「サキ、どうして。」
「たまたま通りかかったの。お酒、飲みたい気分だったから。」
そんなの嘘だ、でも、嘘だっていい。
ジントニックを1杯だけ飲み、その日は早めに店を閉めてくれた。タクミの家はバーの近くにあり、玄関で靴を脱ぐと、何も言わず優しく抱きしめられた。この指だ…。毎日シェイカーを振っていても、昔と何も変わらない。私の服に手を入れられ、それからゆっくりとおっぱいを揉みしだかれる。
「あ……んッ」
ひさしぶりの感覚。私がずっと、追い求めていた感覚。もうこの指の動きからは逃れられない。
「もう、店にいる時からヤりたくてしかたなかった。」
耳元でそう囁いたタクミは、乱暴に私のスカートと下着を脱がせ、廊下の壁に手をつくように言う。後ろからぐちゅぐちゅとまんこを弄られ、今までで一番濡れているのを感じた。
「あん……もうっ、ほし、いっ…」
そう強請ると、タクミはかちゃかちゃとベルトを外し、鞄から取り出したゴムをちんこにかぶせる。そして、私の腰を掴み、後ろから一気に入れてきた。
「ぁあああッ!」
腰を掴む指が、ひどく優しい。何度もタクミと交わってきたが、こんなに優しいのは初めて。挿入してから少し馴染ませ、それからとんでもない勢いで、腰を打ち付けてきた。
「あっ、あっ、あっっぁああッ!」
突かれるたびに、口からだらだらとよだれが垂れ、後ろを振り向くと、タクミがそれを器用に啜ってくれる。そのまま唇を重ね、ぐちゅぐちゅと水音を立て、舌を絡ませあった。腰の動きが速くなり、それにつられるように、私もくねくねと腰を揺らす。立ったままだからか、脚もガクガクしてきて、すぐにでも座り込んでしまいそう。それをぐっと堪え、後ろからの快楽をただただ享受していく。
「んあっ、あっ、タクミっ、タクミ、好きっ。」
「サキ……っ、俺も、好きだよ。」
「……っ! 今、なん、て……っ」
「好きだ、サキ……っ!」
そう言ってタクミは全身の力を込めて、私の奥を抉るように突いてくる。好き、好き。タクミからずっと聞きたかった言葉。私にやっと好意を向けてくれたんだ。それだけでこんなにも胸が苦しくなって、涙が溢れてくる。
「あ……っタクミ、好き……ぁああッ」
まんこがぎゅっと締まり、タクミの射精を促すような動きをしてしまう。腰を掴む指があたたかくて、そこに集中すると余計になかが濡れ、とろとろと愛液が床に溢れていく。次第に肌と肌がぶつかり合う音がゆっくりになり、タクミが私の中からちんこを抜いたのがわかった。
「こんな、廊下でするの初めじゃない?」
「たしかに……どれだけ溜まってたんだよーってな。」
タクミは笑いながらそう返してくれて、ホッとした。溜まってたのは私だけじゃなかったみたい。
一緒にシャワーを浴び、ベッドに横になる。タクミは、「今誰とも付き合っていない、だからよかったら付き合ってくれ」と真剣な顔でサキに言った。
「もう、曖昧な関係はやだよ」
そう囁いてタクミに抱きつくと、大好きな手が私の頭を撫でてくれた。
私はもう、抜け出すことはできない。
どこにも行かないし、行けない。
この指の温もりだけが、私を興奮させてくれるから。






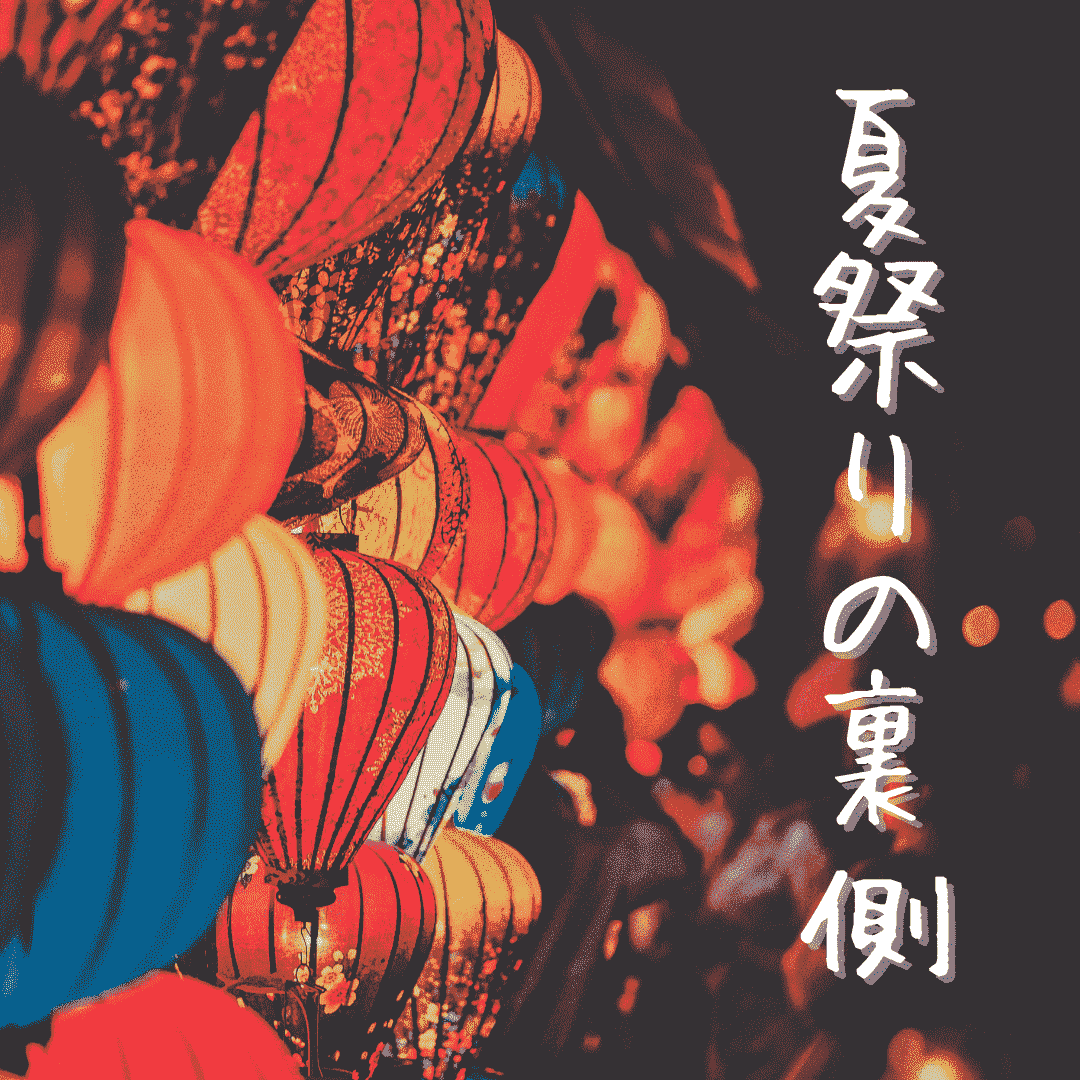
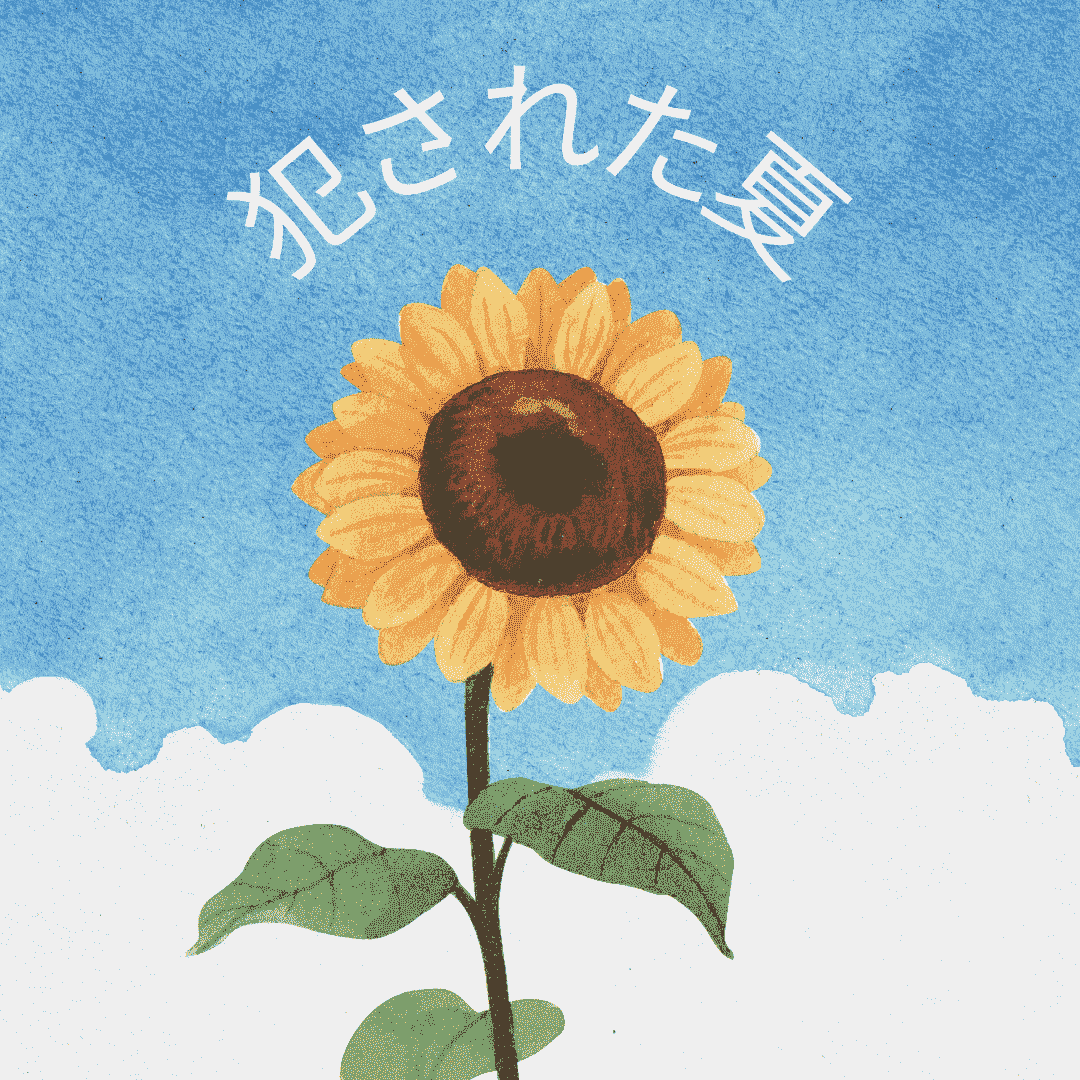


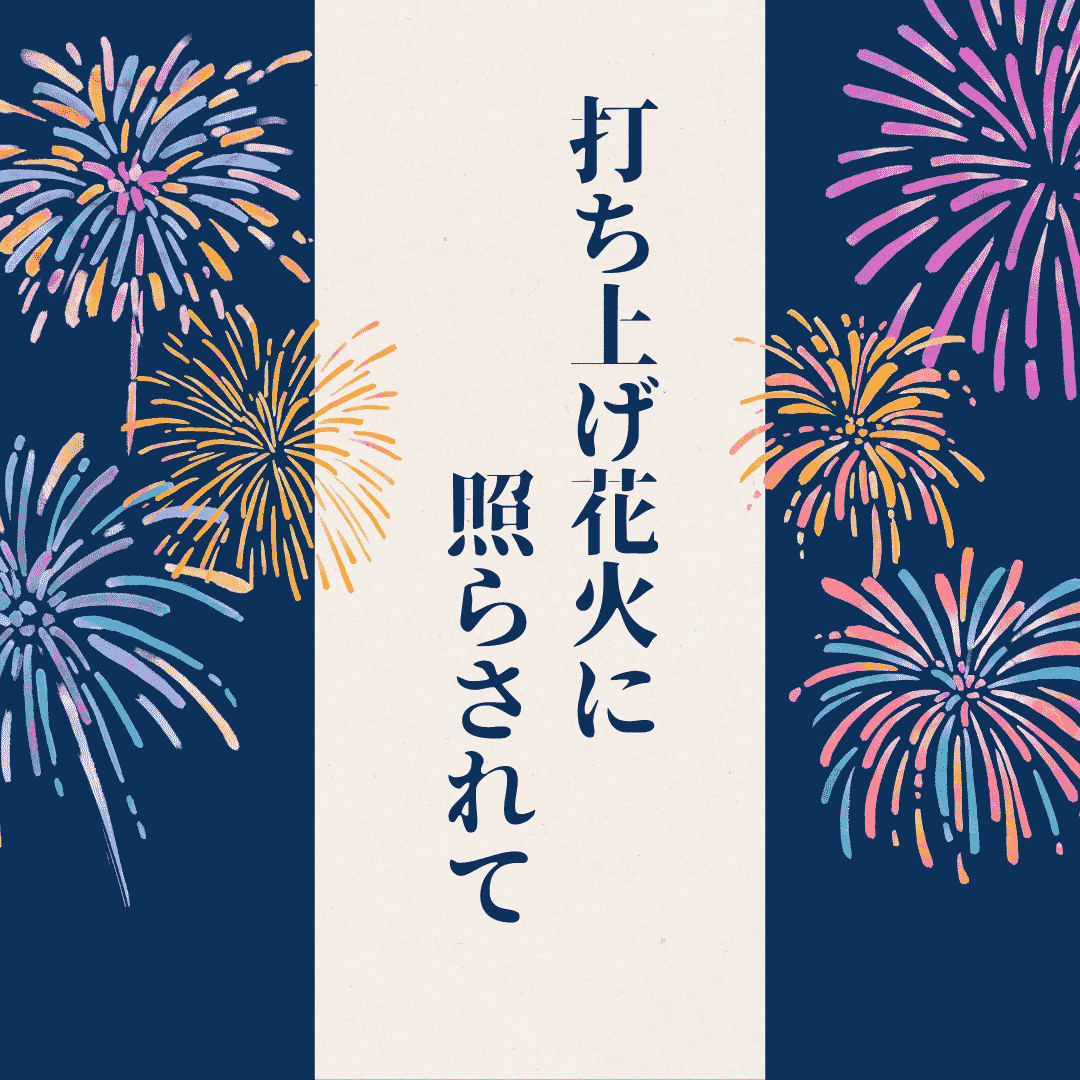

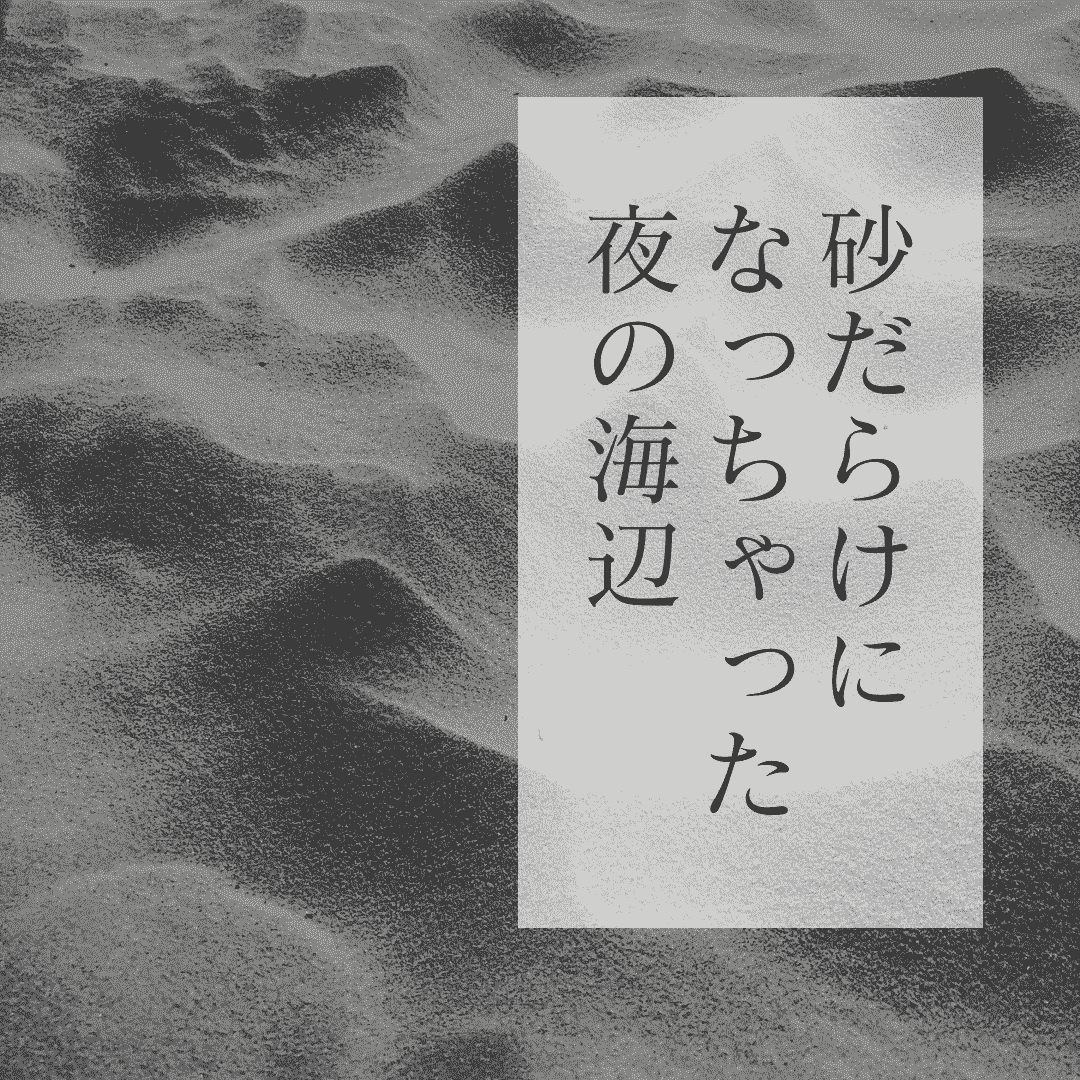

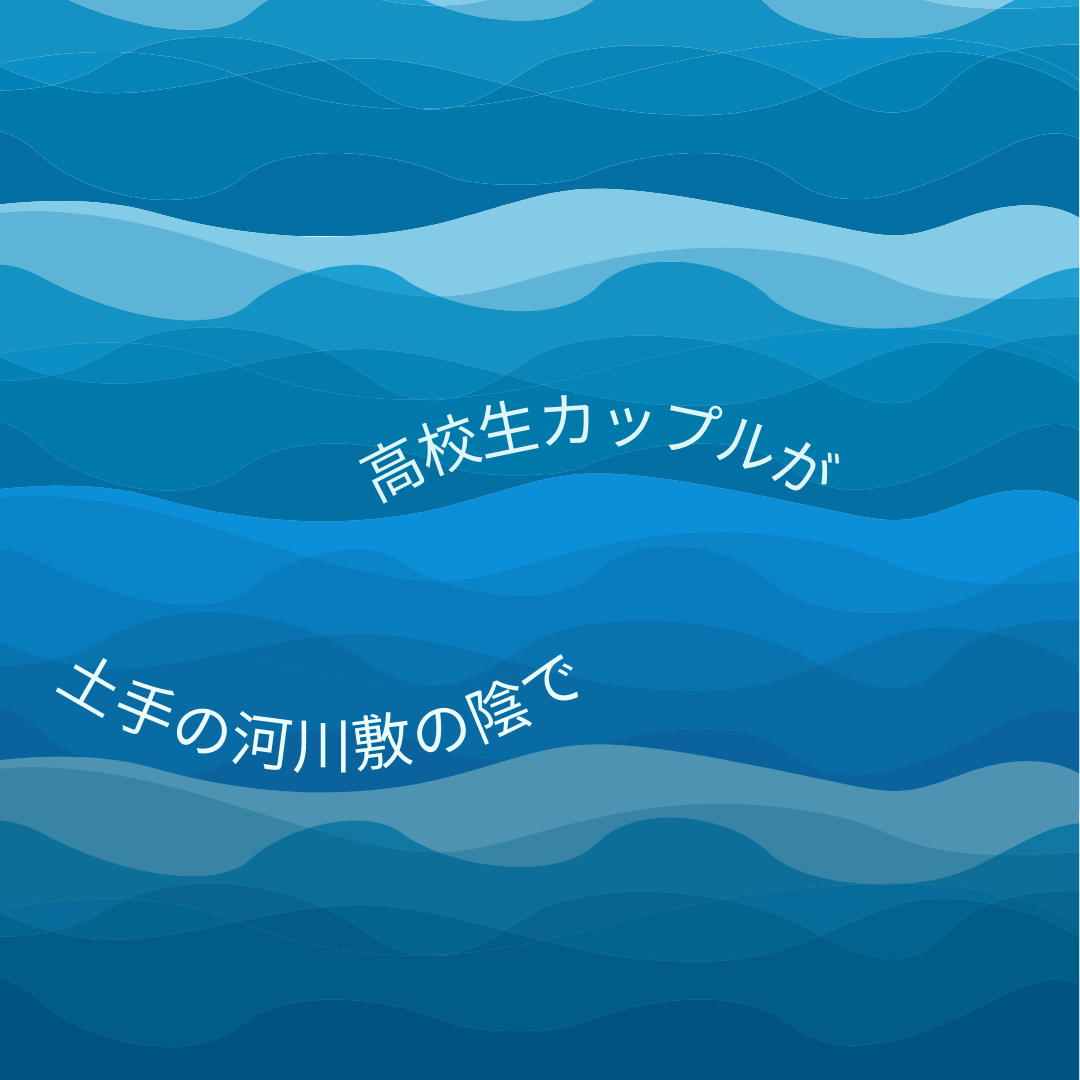


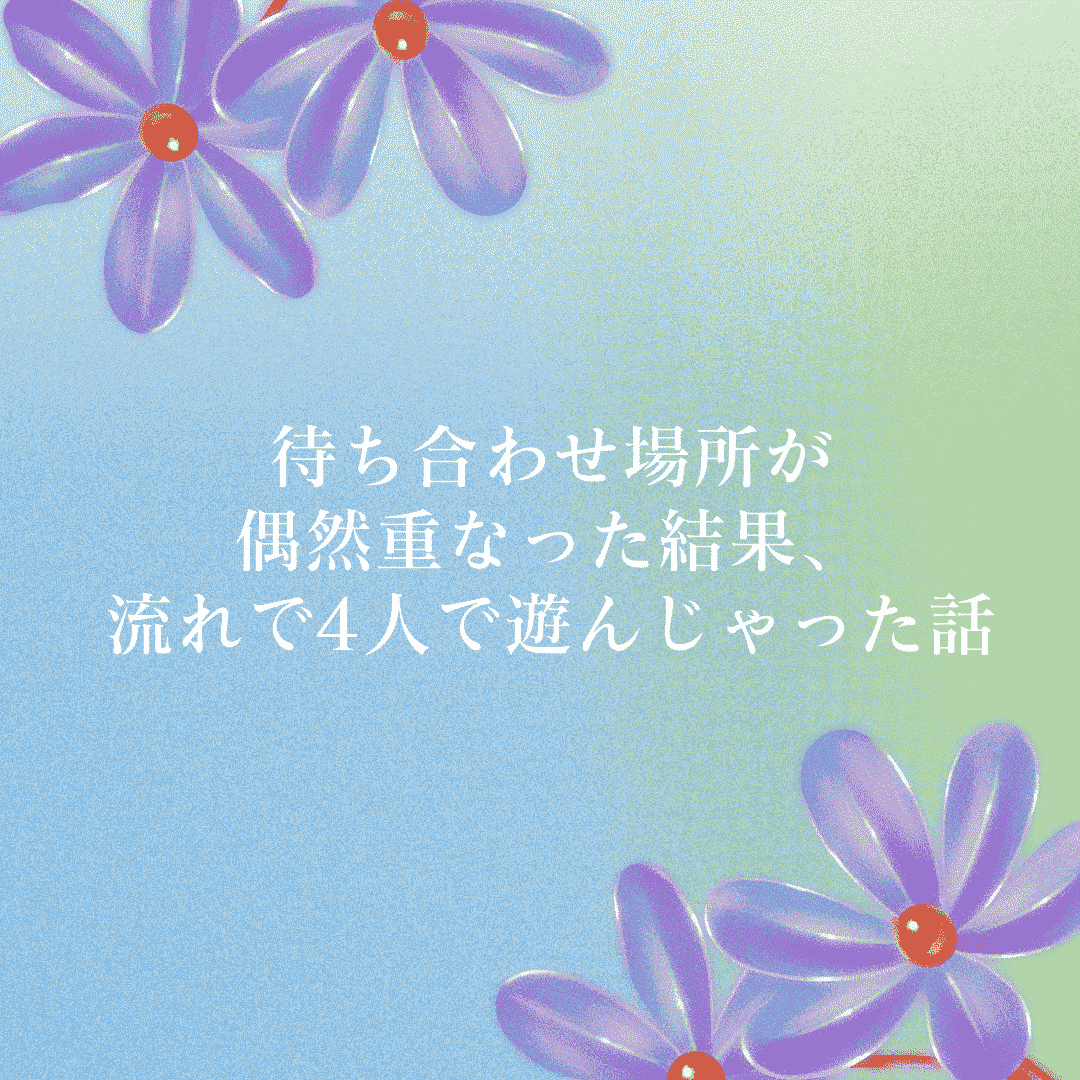




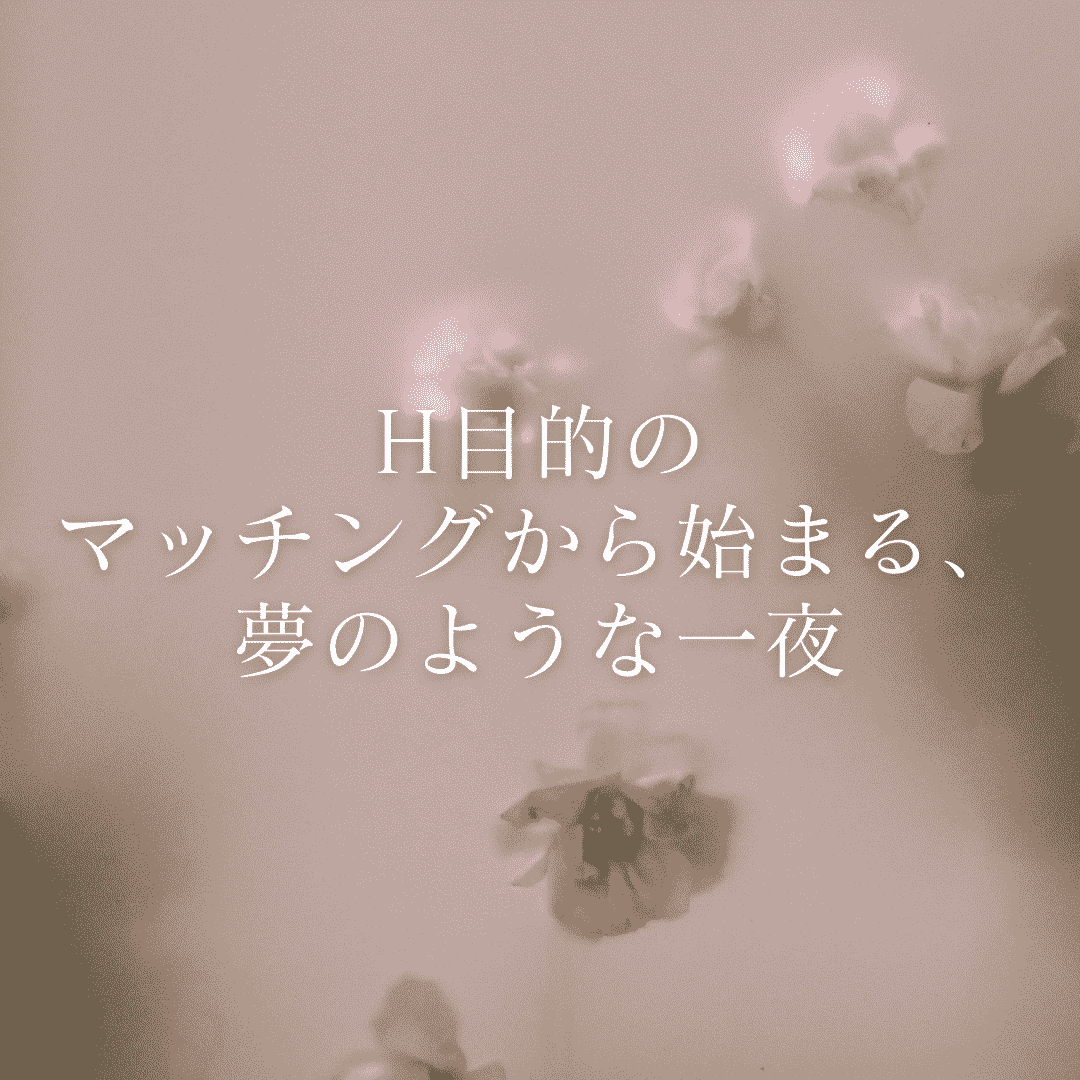

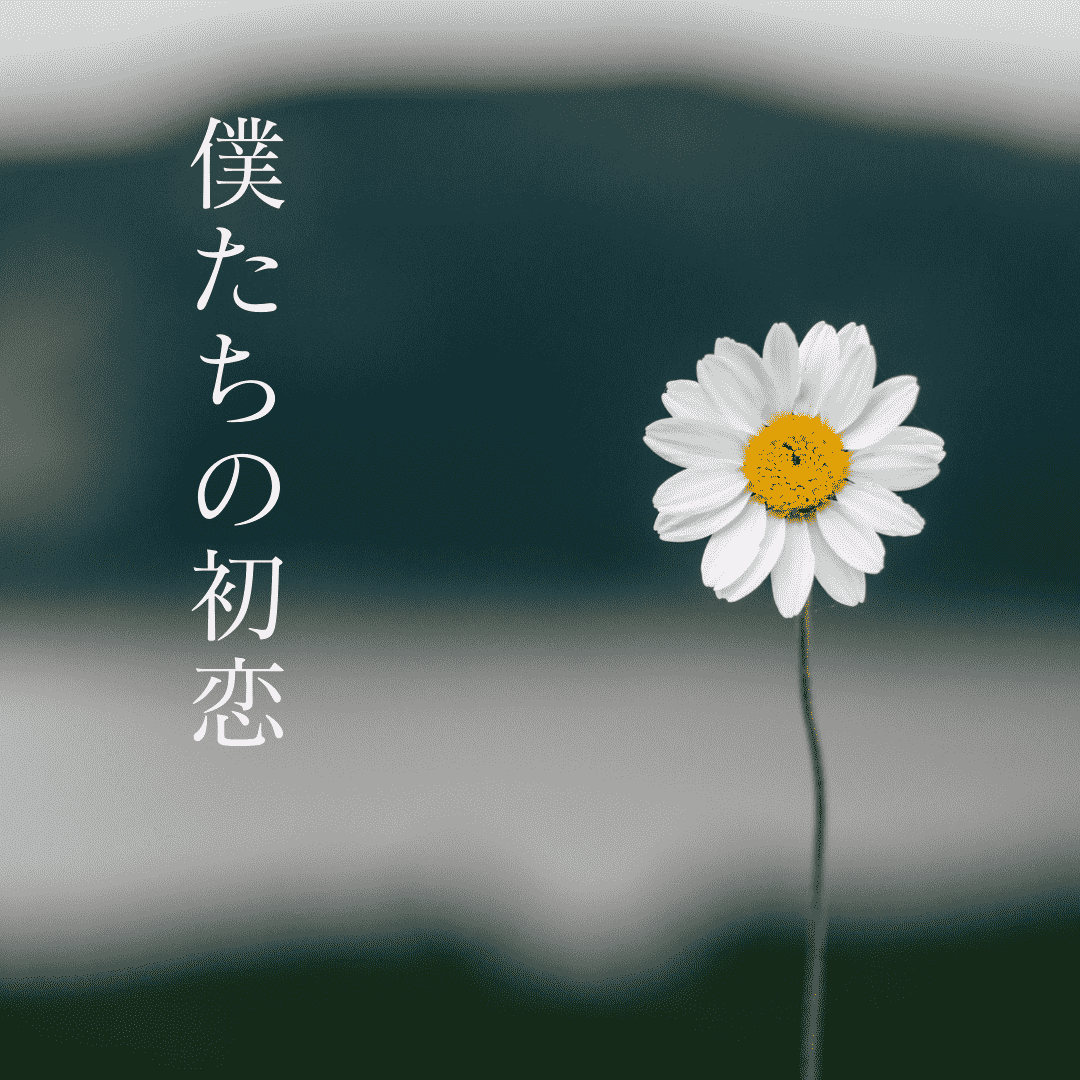


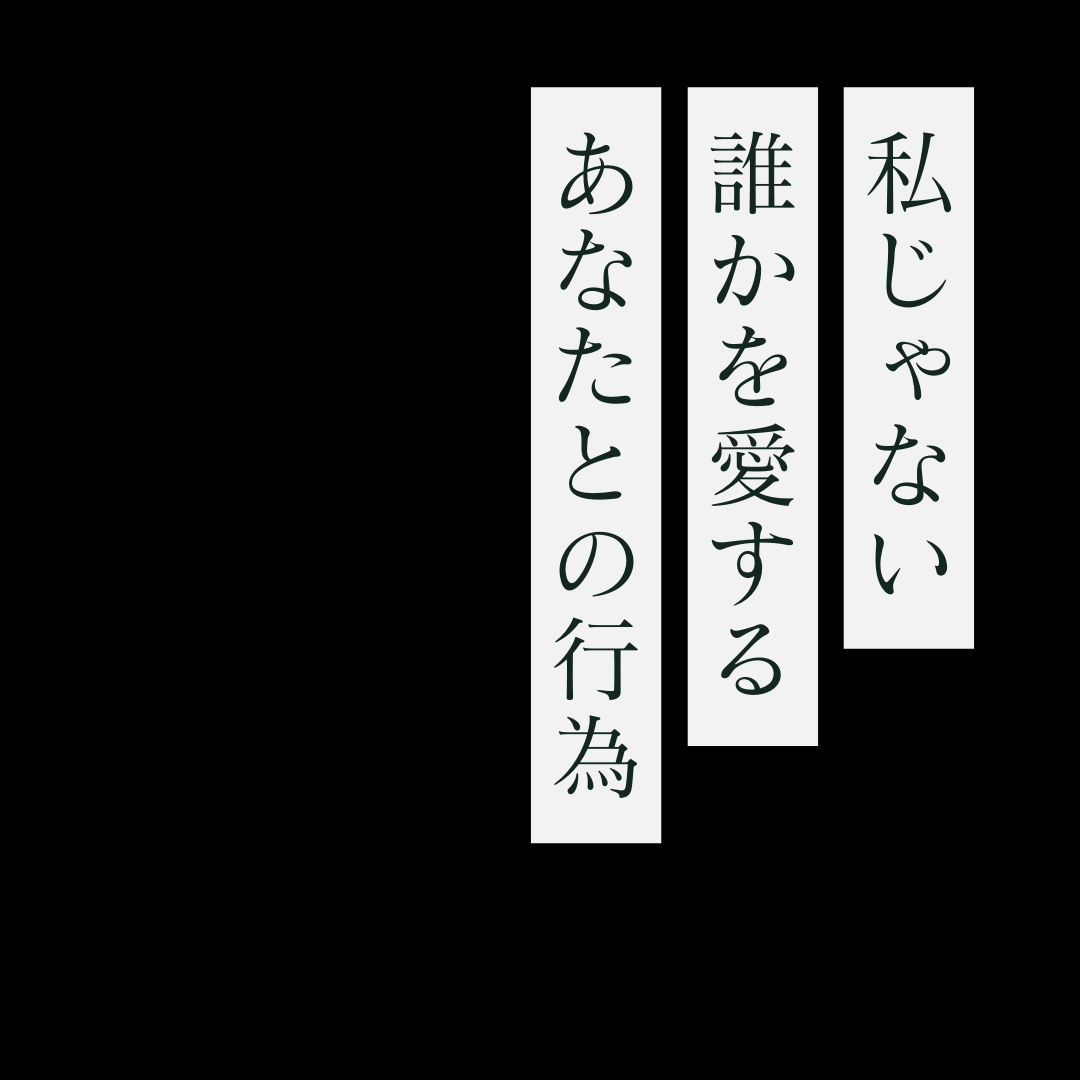

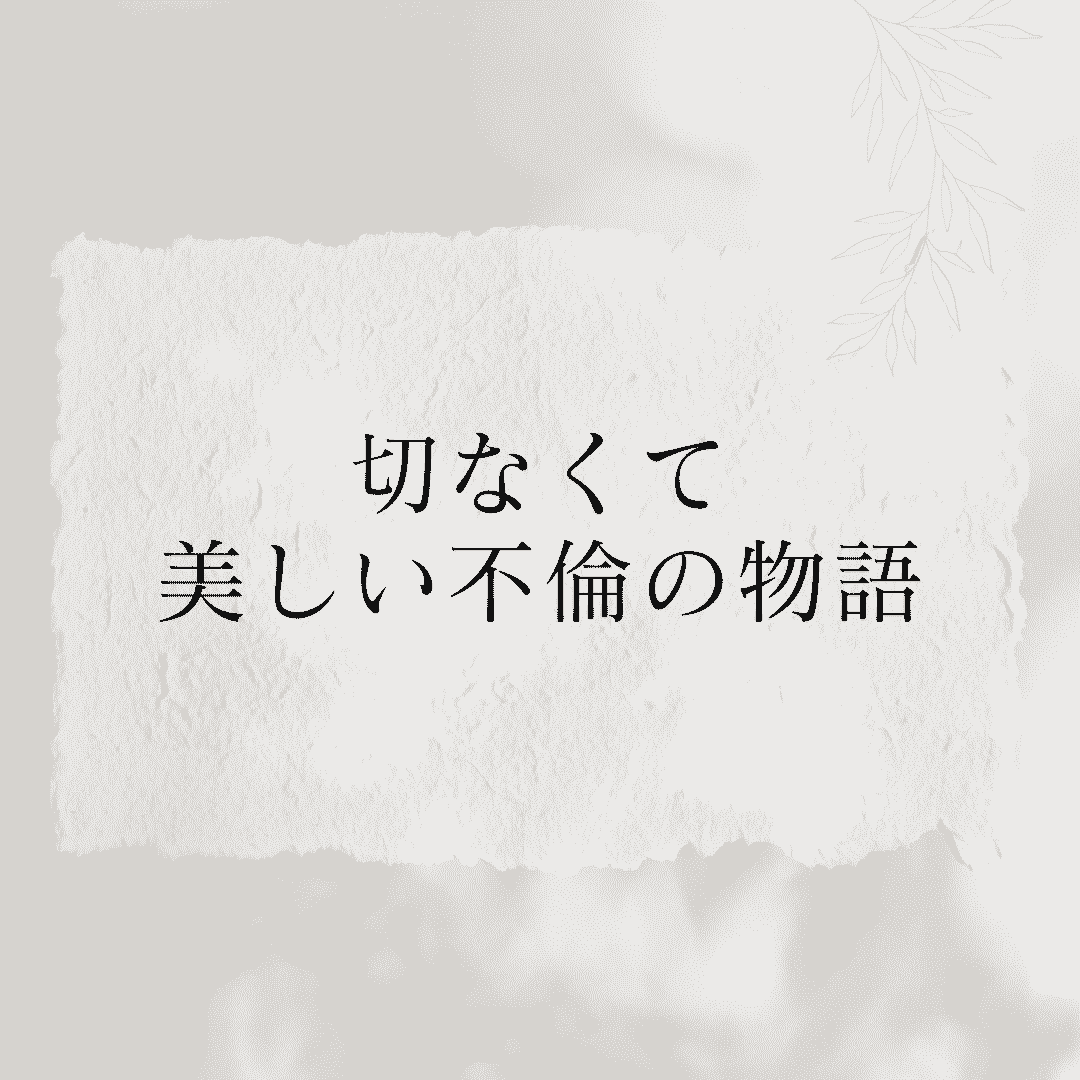
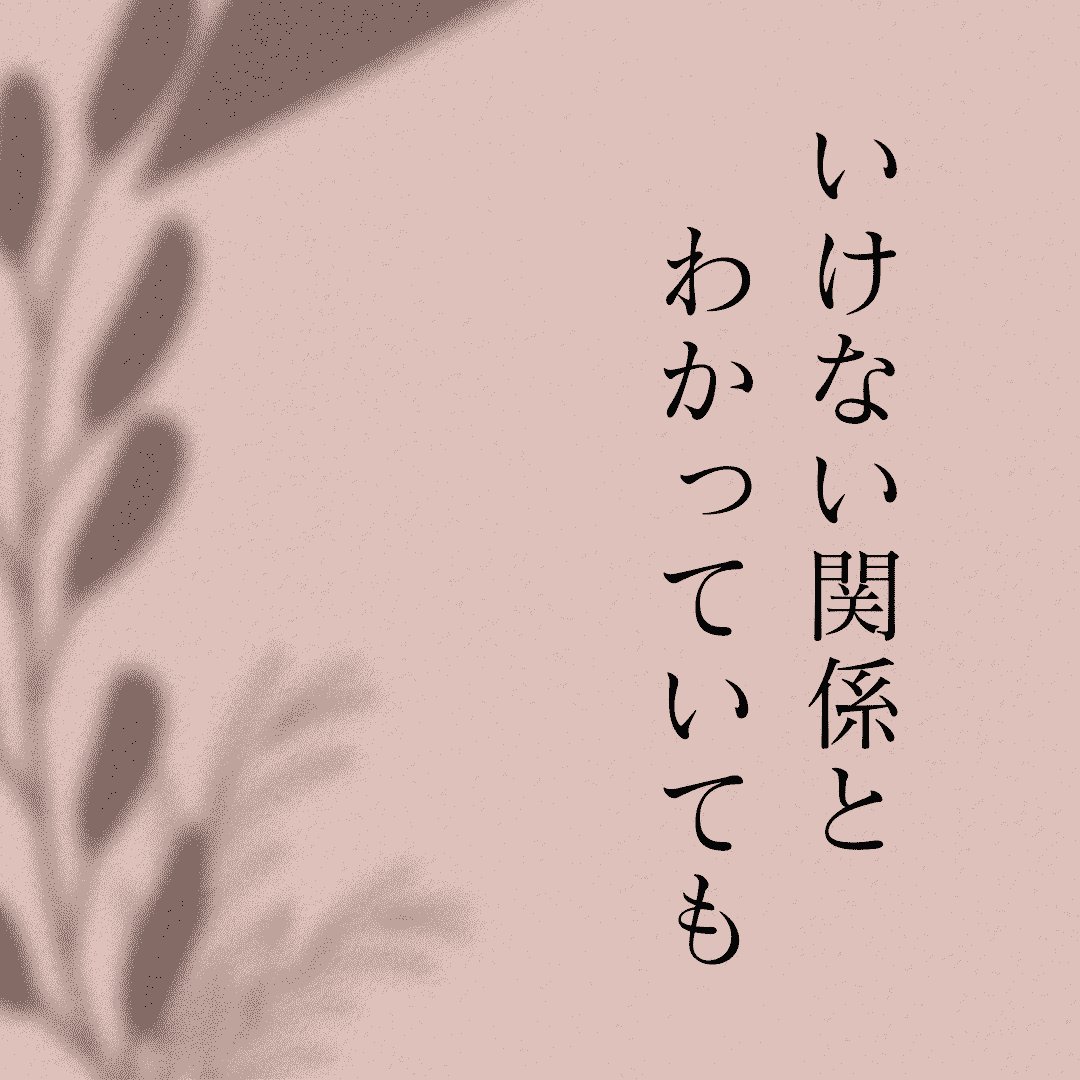









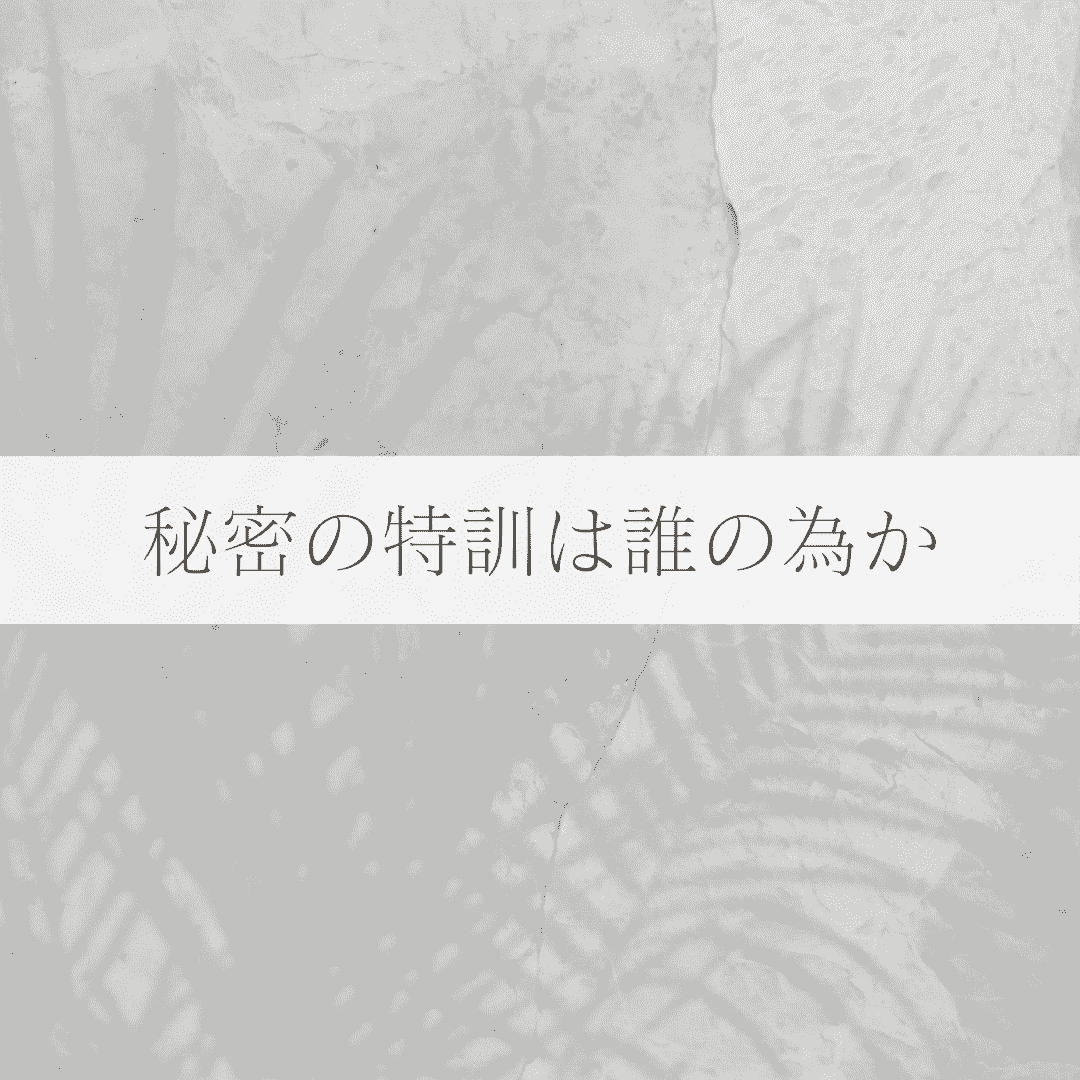
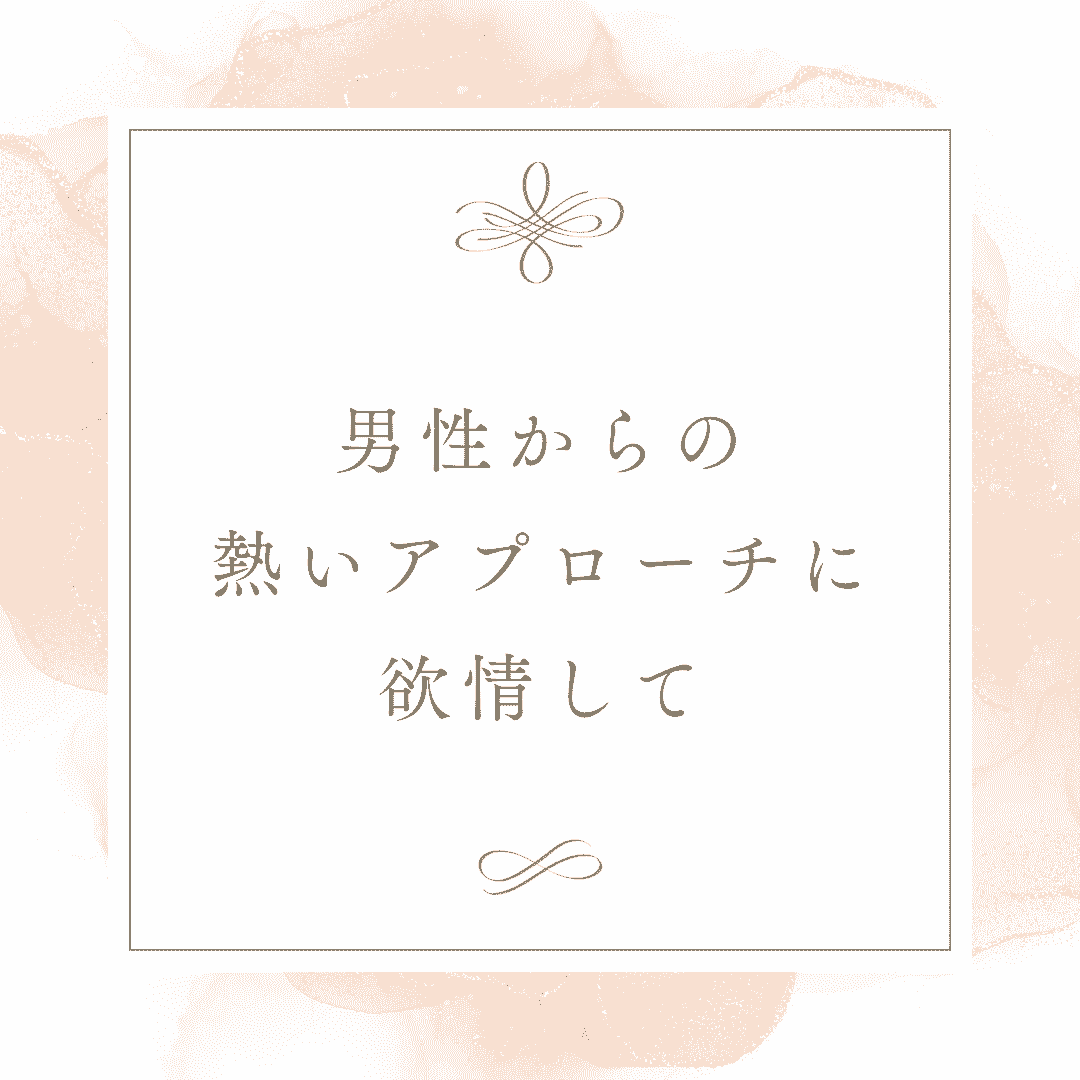


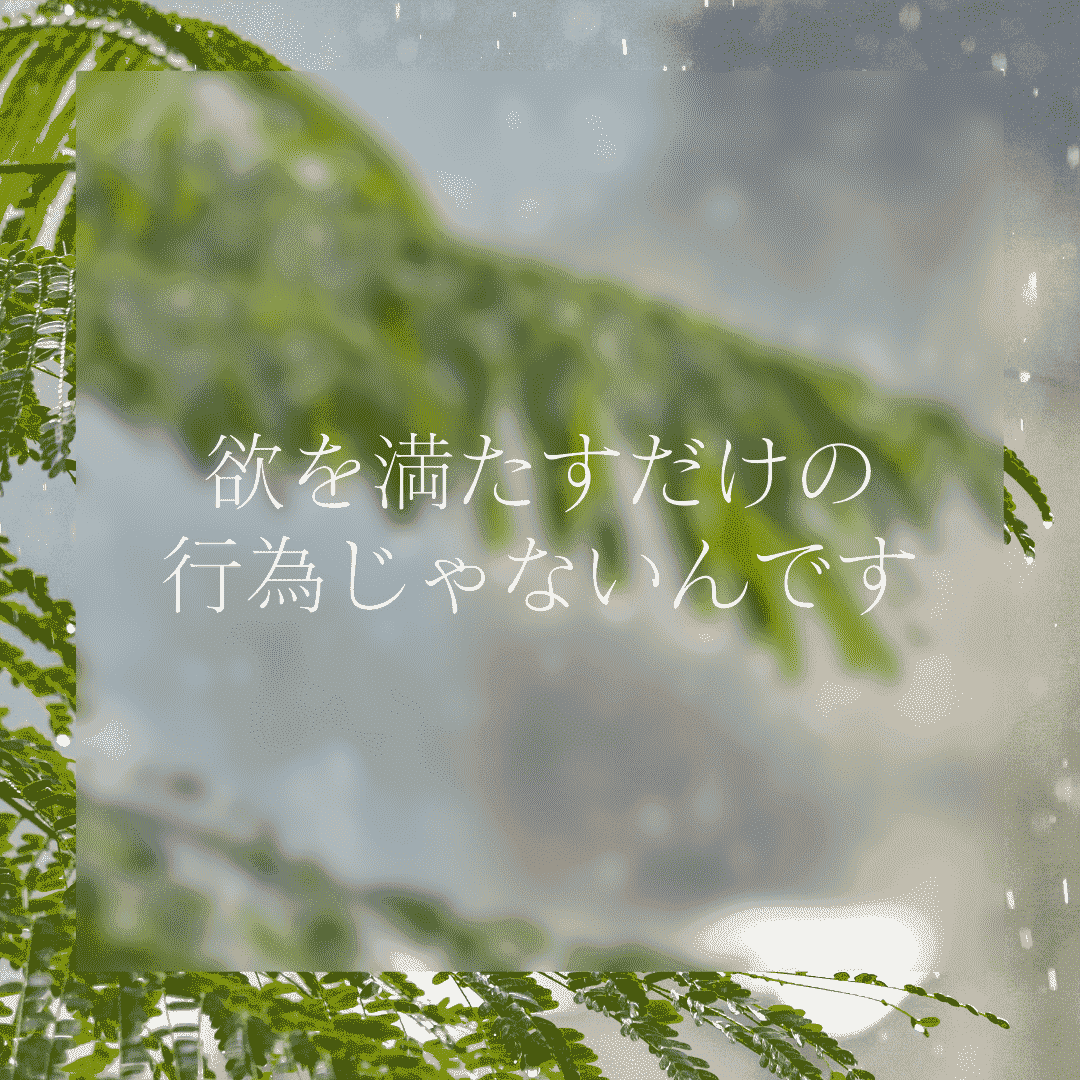

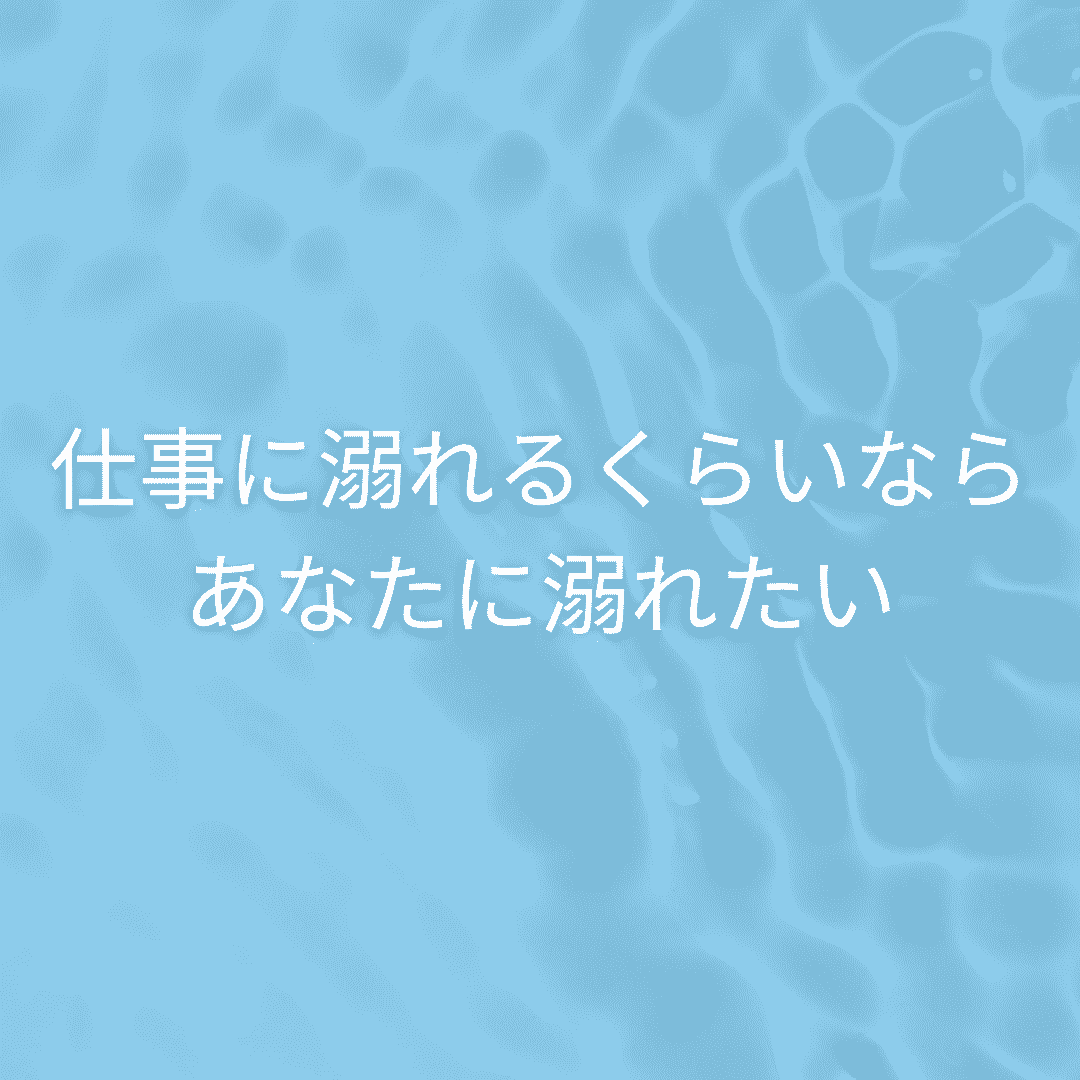



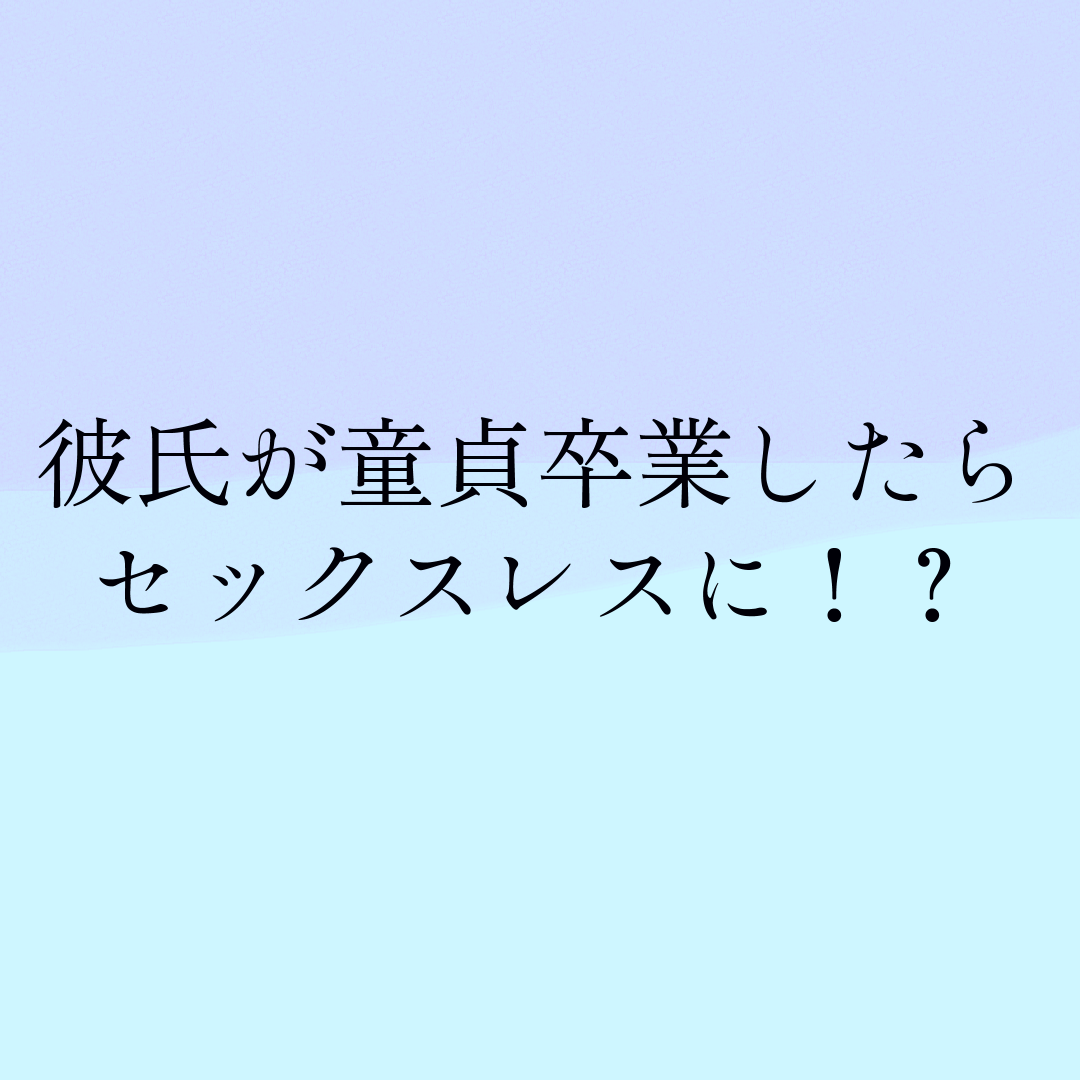








コメント