
0
あそこの神社をホテル代わりに
「それじゃ頼んだよ。」
「はーい。」
顔では笑顔を作るけど、内心はブスッとしてしまう。
私は橋田依里子(はしだよりこ)。
勤めていた会社が突然倒産した。
同居していた彼氏にも、無職になった途端に振られてしまったのだ。
「ニートを養う気はないから。」
そのたった一言で、追い出されてしまった。
再就職先も中々みつからず、マンスリーの家賃もバイトだけでは正直厳しい。
仕方なく実家に帰ってきて、自営のお店の店番をして過ごしている。
住んでいたときには何も感じなかったけど、都会から戻ってくると、痛切にかんじる。
― 何もない。
悪くはない。
空気はいいし、のんびりとした田舎の生活。
今流行の“移住”や“田舎暮らし”に憧れを持つなら、ぜひおすすめしたいくらいだ。
でも…でもさぁ。
コンビニもない、呑み屋もない、唯一の食堂は19時で閉店なんて…。
そして今。
私はさらなる憂鬱に、悩まされている。
村にある神社の春の大祭。
今年はうちが当番で、準備のお手伝いをしなければならない。
それを両親があっさり私に押し付けて来たのだ。
「仕事もないし、ただ飯で住ませてやってるんだからこのくらいやりなさい。」
なんて言われたら、やるしかないよね。
まぁ、大したことはしないしどうせ夜は暇だし…。
なんて安請け合いしたら、集まった長老たちに、がっつり力仕事から掃除から、飾り付けの手芸まで頼まれてしまった。
はぁ、こんなに一人でできるかなぁ…
なんて、ちょっとへこんでいたところ、
「今日はいなかったけど、神社の管理してる世話人さんが手伝ってくださるから、社務所の鍵やらなんやらはその人に聞いてな。」
と言われた。
へぇ、この神社の世話人なんていたんだ。
そういえば私が子供の頃掃除とかしてるおじさんいたなぁ。
私が小さいときに“おじさん”ってことは、今は“おじいちゃん”かな?
あんまり期待できないかも…。
次の日の夕方―
お店の閉店したあと、早速世話人さんの家へと向かった。
何はともあれまずは社務所の掃除だな。
「こんばんわぁ。」
チャイムもないのでおそるおそる引き戸を開ける。
勝手にドアを開けるのは“田舎あるある”だ。
「はーい。」
あれ…?
予想と反して若い男の人の声がする。
「…!」
座敷から土間に顔を出した青年を見て、ドキッとした。
「こ、こんばんは…。」
驚くほどのイケメン!
こんな田舎にこんないい男(オアシス)が!!!
「あぁ、大祭のお手伝いの人?」
これまた爽やかな笑顔で聞いてくる。
しかも…いい声。
「あ、はっはい。」
あぁ、なんでジャージで来ちゃったんだろう。
私のバカ。
「ちょっと待っててくださいね。」
イケメンはそう言うと、上がり端にかけられた社務所の鍵を手に取った。
「はい。これお願いします。」
渡された鍵を受け取った。
「あの…」
できれば一緒に行きたい。
「社務所は神社の右の裏っかわにありますよ。」
「あ、は、はい。」
なんだ、残念。今日は一緒に来てくれないのか…。
なんてちょっとがっかりしていると、
「私もちょっとしたらすぐいいくので、鍵開けて待っててください。」
そう言われて、つい心が躍ってしまった。
「はい。」
私は一足先に神社へと向かった。
社務所の鍵を開けて中に入る。
へぇ、意外ときれいかも。
とりあえず窓を開けてそこにあった掃除機をかける。
最新式のスティック掃除機なのでちょっと驚いた。
「ふぅ。」
と一息ついたところで、
「遅くなりました。」
と彼が現れた。
「あ、俺 中瀬三晴(なかぜみはる)と言います。」
「あ、私 橋田依里子です。」
急に自己紹介をされ、私も慌てて返した。
「もしかして橋田商店の…」
「あ、はい。」
狭い村だ。みんな知ってるのは当たり前か。
「橋田さんちにこんなきれいな方がいたとは、驚きです。」
そんなことをさらっと言ってくるので、つい照れてしまう。
でもよく考えたら、この村には若い人は珍しいから、ただのお世辞ってことも考えられる。
「私も、世話人さんがこんなに若くて素敵な方とは知らなかったです。」
そうにっこりと返した。
すると彼は赤くなってうつむいてしまった。
やだ…。かわいい反応。
「あ、そ、掃除機かけてくださったんですね。」
「はい。」
話を逸らされた。
「じゃ、そろってるものの確認しましょうか?」
そう言って社務所の物置のような場所に掛けられた布をめくる。
私も急いでそばへと駆け寄った。
一通り確認して、必要な物をリスト化できた。
「少し休みましょうか。」
「そうですね。」
そういうと三晴さんは、社務所にある冷蔵庫を開けた。
「昼の間に買っておいたんです。コーヒーとお茶どっちがいいですか?」
なんて気が利くんだろう。、
「じゃ、お茶を。」
「はい、どうぞ。」
冷たいお茶をいただいた。
二人でお茶をしながら、世間話をする。
「中瀬さんてどちらの出身ですか?」
同級生だけではなくて、学校全員の名前がわかるほど、小さなコミュニティーだ。
中瀬さんは私の記憶にないから、きっとここの出身じゃないだろう。
「あぁ、俺は○○市の出身なんですけど、おじの跡を継ぐ人がいなくて俺がそれを申し出たんです。」
へぇ、じゃぁ私が小さい時に見たあのおじさんは、中瀬さんの叔父さんなんだ。
「よそ者なのに、みんなよくしてくれてありがたいです。」
「いやいや、こんな田舎に来てくれるなんてみんな喜んでますよ。」
少しの沈黙が走る。
「橋田さんも…橋田さんもうれしいですか?」
「はい?」
突然、まっすぐ私の方を見て聞いてくる中瀬さんに、驚いた。
でも、私を見つめるその子犬のような瞳に、思わずうなずいてしまう。
「は、はい。頼りにしてます。」
そういうと彼の顔は、雲から現れた太陽のようにぱぁっと明るくなった。
そして、足りないものを買い足しに行くため、三日後に待ち合わせることとした。
私は車がないので、中瀬さんに出してもらう。
今日はばっちりおしゃれした。
中瀬さんの反応も悪くない。
なんやかんやと帰ってきたのは夕日が沈む頃だった。
「夕飯奢ります。」
中瀬さんの提案をありがたく受け取り、村唯一の呑み屋へ。
知った顔ばかりで冷やかされるが、和気あいあいといった雰囲気に、お酒が進んでしまう。
「俺飲んでないから送ります。」
中瀬さんがそう言ってくれたので、素直に甘えた。
車に乗ると、ペットボトルのお水をくれた。
なんて気が利くんだろう。
発車してすぐにフタを開ける。
その拍子に―
ガタンッ
車が大きく揺れて水が少し溢れてしまう。
「あっ」
私の声に中瀬さんがちらっとこちらを見たあと、すぐに路肩に車を止めた。
「ごめんなさい。」
「これ使ってない綺麗なやつだから使って。」
そう言って手渡されたタオルで、口元と胸元を拭いた。
そして、すぐに彼の視線に気づく。
中瀬さんが、じっと私を見ている。
そして少しずつ近づいてくる。
「いい匂い。」
そう言って私の髪を掬う。
なんだろう。
髪を触られただけなのに…気持ちいい。
そっと私の髪に口づけてから、私の肩に優しく手を添えてきた。
「中瀬さん…」
「橋田さん…いや依里子さん。俺初めてあったときからその…一目惚れっていうか。」
薄暗い車内でも、中瀬さんの顔が赤いのがわかる。
「好きなんです。」
小さな声でいう。
そのドキドキが私にも伝わってくる。
「あ、あの…」
「…」
そのまま私の答えも聞かずに、中瀬さんは私の唇に自分の唇を押し付けてきた。
「あっ、中瀬さ‥ん」
「あぁ 柔らかい。」
とても興奮している様子の中瀬さんに、少し焦った。
だって、こんなところで欲情されたら困っちゃう。
誰が通るかわからないし。
だからといって、中瀬さんも私もいわゆる“実家住み”。
ラブホなんてものは、この地域にないし…。
「依里子さん、だめですか?」
すでに彼のズボンの中心は張り詰めていた。
「あ、あのここではちょっと、できればホテルというか‥なんかそういうところは…」
「そんな…ホテルまで30分はかかるのに…」
そう、切なそうに訴えてくる。
そりゃそうだよね。
30分もたてば、熱は冷めてしまう。
「あっホテルはないけど。」
そう言うと運転席に体を戻す。
「あの神社なら。」
「へ?」
「あそこなら誰も来ないしホテルの代わりになります。」
喜々とした声でそう言うと、中瀬さんは再び車を走らせる。
2分もしないうちに神社についた。
中瀬さんは車を降りて助手席のドアを開けてくれた。
社務所まで待てないのか、神社の脇の大祭の世話人の待機所のような狭いスペースに連れ込まれた。
畳2畳の狭いスペースに彼のジャンバーが敷かれて、私はそこに投げ出される。
まだ知り合って間もないけど、彼のイメージが音を立てて崩れていく。
あんなに穏やかで優しい人だったのに、今目の前にいる男は盛の付いた動物のように欲に忠実だ。
カチャカチャと自分のベルトを外して、ズボンを下ろしている。
「ひゃっ…!」と思わず声が出てしまうほど膨張して血管の浮いているアレが目の前に現れた。
「気持ちよくさせますから。」
そう言うと、私に覆いかぶさって激しく唇を奪ってきた。
荒々しく早急な感じのキス。
でもそれが、身体や脳を痺れさせる。
こんなに激しく求められたのは初めてで、私の本能も呼び覚まされてしまう。
呼吸も忘れるほどに、私を貪る彼の唇や舌の動きに応えて行く。
どちらとも分からない唾液が、2人の口の端からこぼれる。
神社の外の街頭からわずかに入ってくる光が、中瀬さんの端正な顔を映しだした。
シャツの前ボタンが外されて、影が濃く刻まれる筋肉。
それに見とれていると、突然胸の膨らみを鷲掴みにされる。
「はっ!」
短く息をはいた。
でも先のことを考える間もなく、今度は突起を甘噛された。
「ひゃぁ、あん中瀬さん!」
歯を立てられるたびに私の下半身はぴくっと反応して、あそこからじゅわっと何かが溢れ出す。
触られたら、恥ずかしい。
そう思って、無意識に足を擦り合わせた。
「依里子さん、気持ちいいですか?」
そんな私の行動に興奮気味に聞いてくる中瀬さん。
「気持ちよくないですか?」
無反応の私を、心配そうに気にしてくれている。
「ねぇ、どこが依里子さんを気持ちよくさせられますか?」
そう聞きながらも、唇から首、肩、胸、突起、腰と、どんどん指を滑らしていく。
そしていよいよ太ももの付け根に指が移動して、パンツの端をなぞって中心へと向かう。
でも途中で指は止まる。
「あれ?依里子さんこれって…」
彼の指に私の蜜が絡みついた。
あぁ、神社という神聖な場所なのに、こんなに簡単に乱れて淫靡な汁を垂れ流している。
そんな心配をよそに、中瀬さんは私の中心を攻め始めた。
「あぁ依里子さんすごいよ。」
嬉しそうに私の蜜を掬っては指を舐めている。
「いや、言わないで…」
恥ずかしさのあまり、両手で顔を隠す。
「いいんですよ。声もコレも、我慢しないでどんどん出して。」
下着の隙間から中瀬さんの指が入ってくる。
「あっ」
ぬちゅ。
びちょびちょになったあそこは、中瀬さんの指をすんなり迎え入れた。
「俺が触ったからこうなったんだね。」
そう嬉しそうに微笑むと、優しい声とは裏腹に、荒々しく私の下着を剥ぎ取った。
「あぁもったいない。」
そう言って私の股に顔をつけて、ジュルルっとその蜜を吸う。
彼の整った鼻が恥骨を刺激してくる。
腰がヒクヒクと浮いてしまう。
「依里子さん…ほしいんだね。」
そうつぶやいて、私の膝の裏に手を添えて、持ち上げる。
「依里子さんのアソコ、ひくひくしてビンクになってかわいい。」
愛おしそうに私のソコを見つめると、
「じゃ、挿入(い)れるよ。」
その言葉とともに、彼の肉棒の先端が私の割れ目にあてがわれた。
「ん、んん…」
期待と快感で体が震えてしまう…。
「んっ!」
中瀬さんの顔が少し歪んで、私の中に彼の質量が押し込まれてきた。
「あっ、あぁぁぁぁぁぁぁぁっ!」
挿入(い)れられただけで、軽くイッてしまったのだ。
「あれ?イッちゃった。」
恥ずかしい。
「うれしい。少し楽になった?」
そんな優しい言葉に、私はコクリと頷いた。
「じゃあとはゆっくり…」
彼が何か言おうとした瞬間、私の中が彼をキューッと締め付けたのが、自分でもわかった。
「ごめん、優しくゆっくりなんてできそうにない。」
そう言うとぎりぎりまで腰を引いて
「ふっ!」
と力いっぱい、腰をうちつけてきた。
「ハァッ!」
その後も驚くほどのスピードで、何度も浅いところから最奥までをピストンし続けた。
「あぁあぁんいいいい。」
ここが神社だということもすっかり忘れ、私も腰を動かし続けた。
終わりたくない。
でも、イきたい。
そんなジレンマで果てそうな彼の腰を、足でホールドして腰を振った。
彼も小刻みに、最後を耐えている。
「あぁぁぁごめん…、もう出そう!」
「あぁん、私もぉ みはるさん…!!」
静かな山に激しくぶつかり合う音を響かせて、私達は絶頂を迎えた。
「依里子さん。」
行為の終わった気だるさの中で、彼が私を呼ぶ。
「また 愛し合ってくれますか?ホテルはないから、また神社(ここ)で。」
まだアソコに彼の残像を感じながら、私は頷いた。






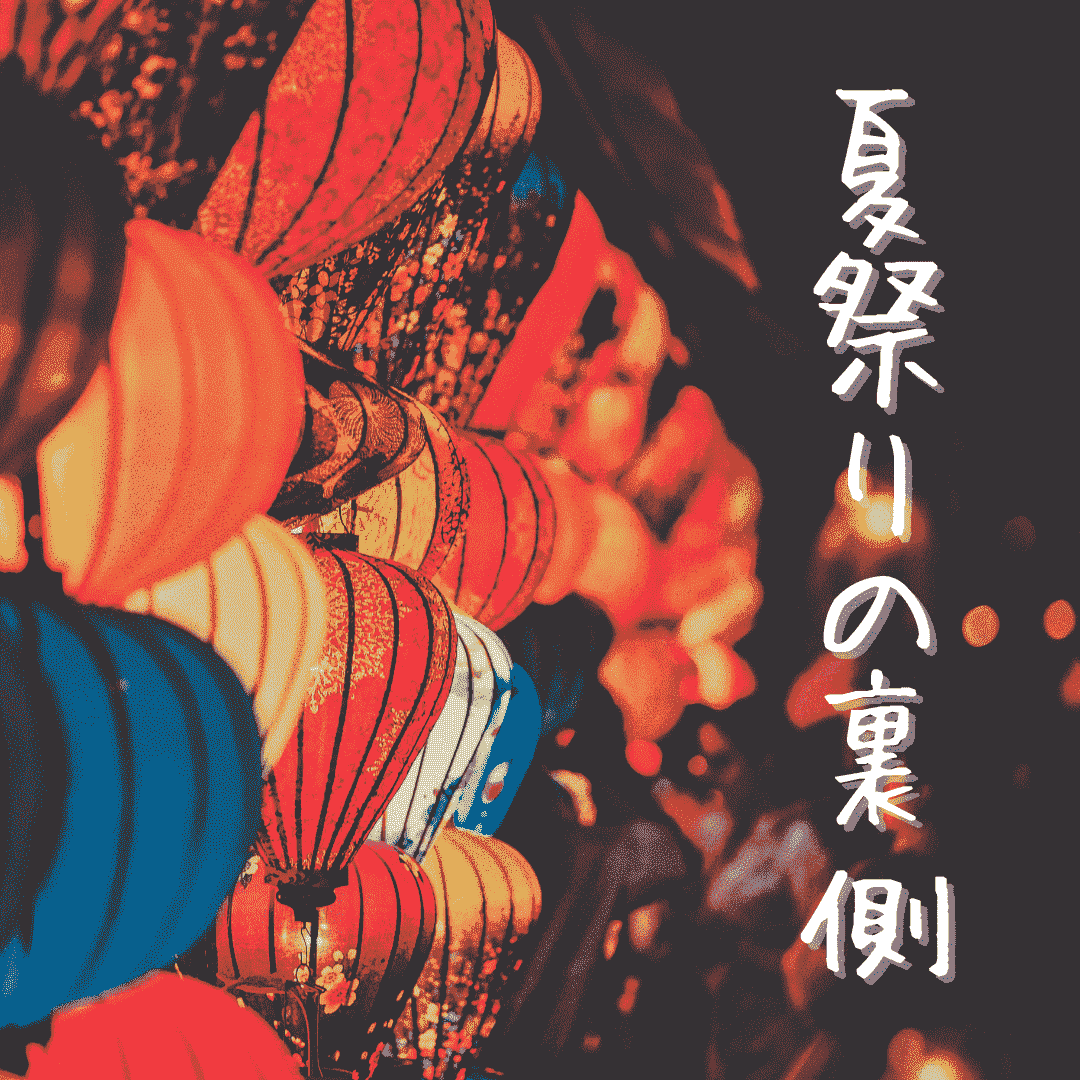

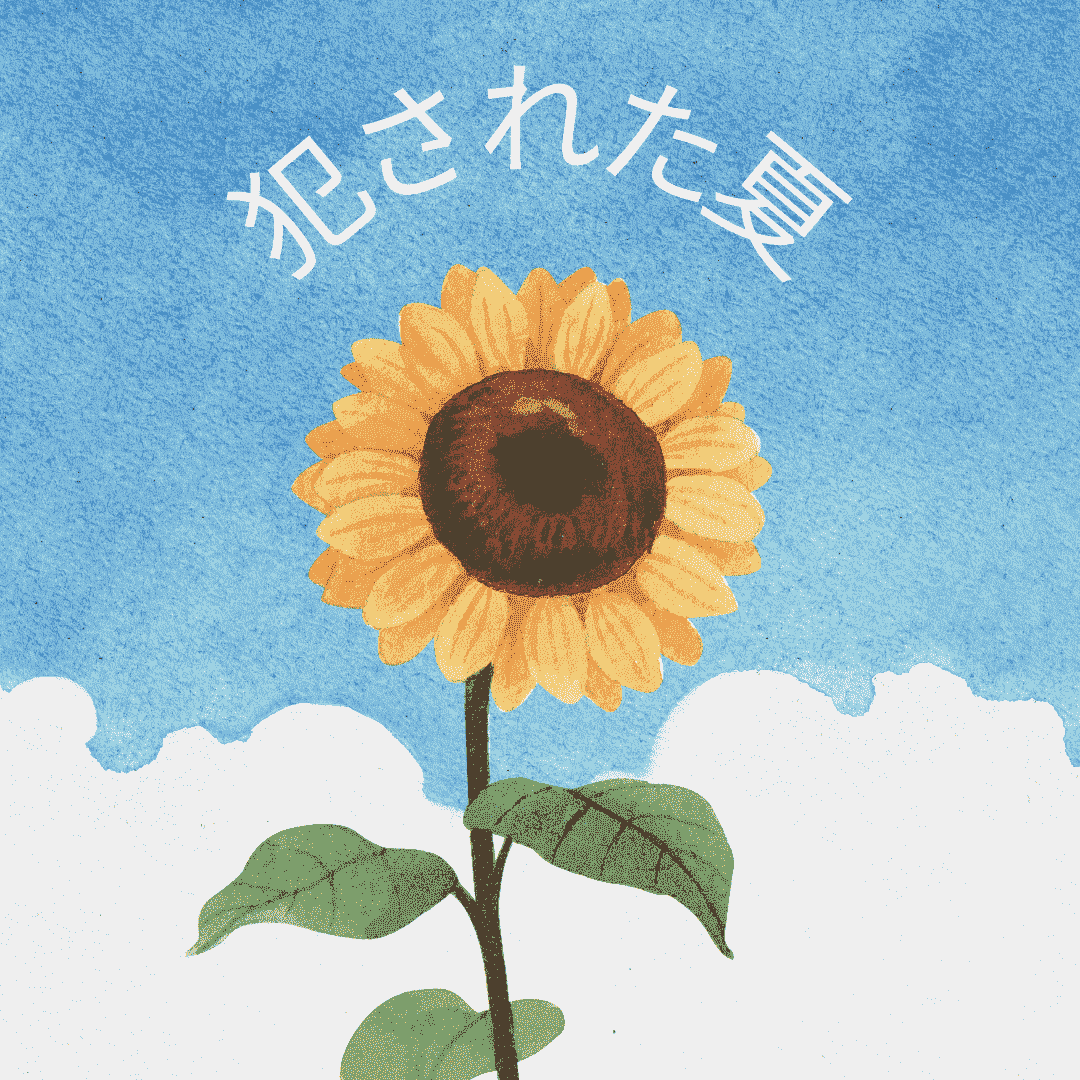


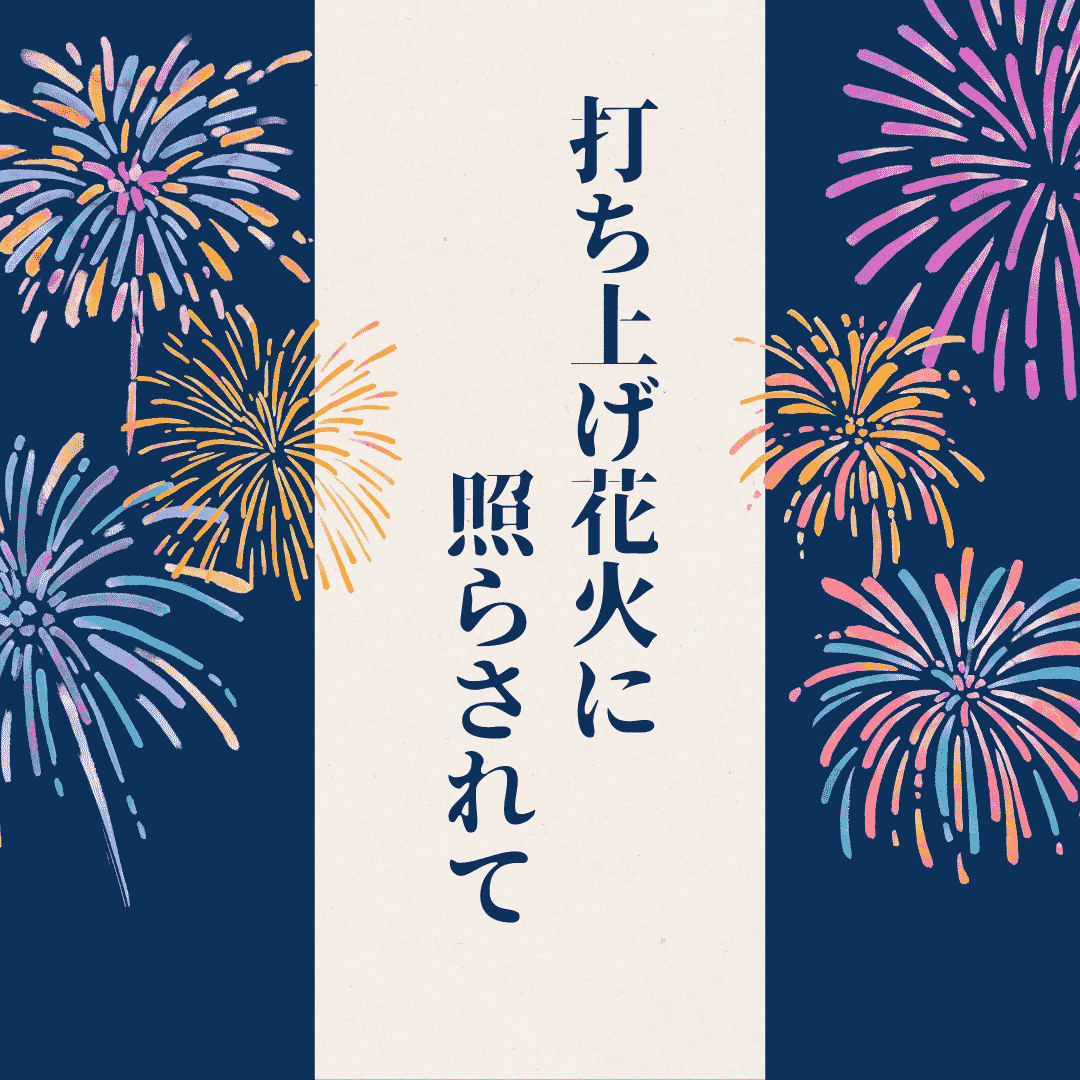

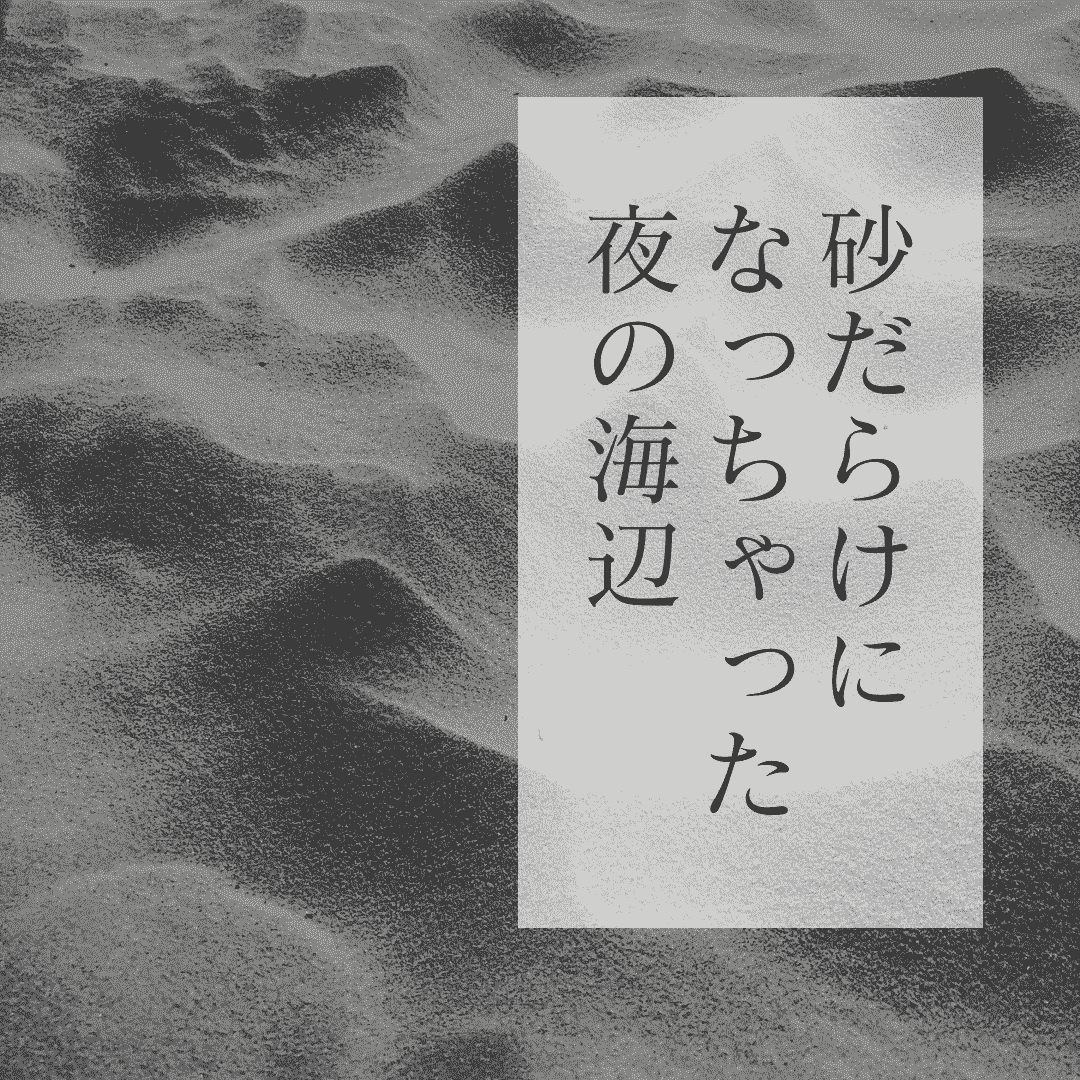

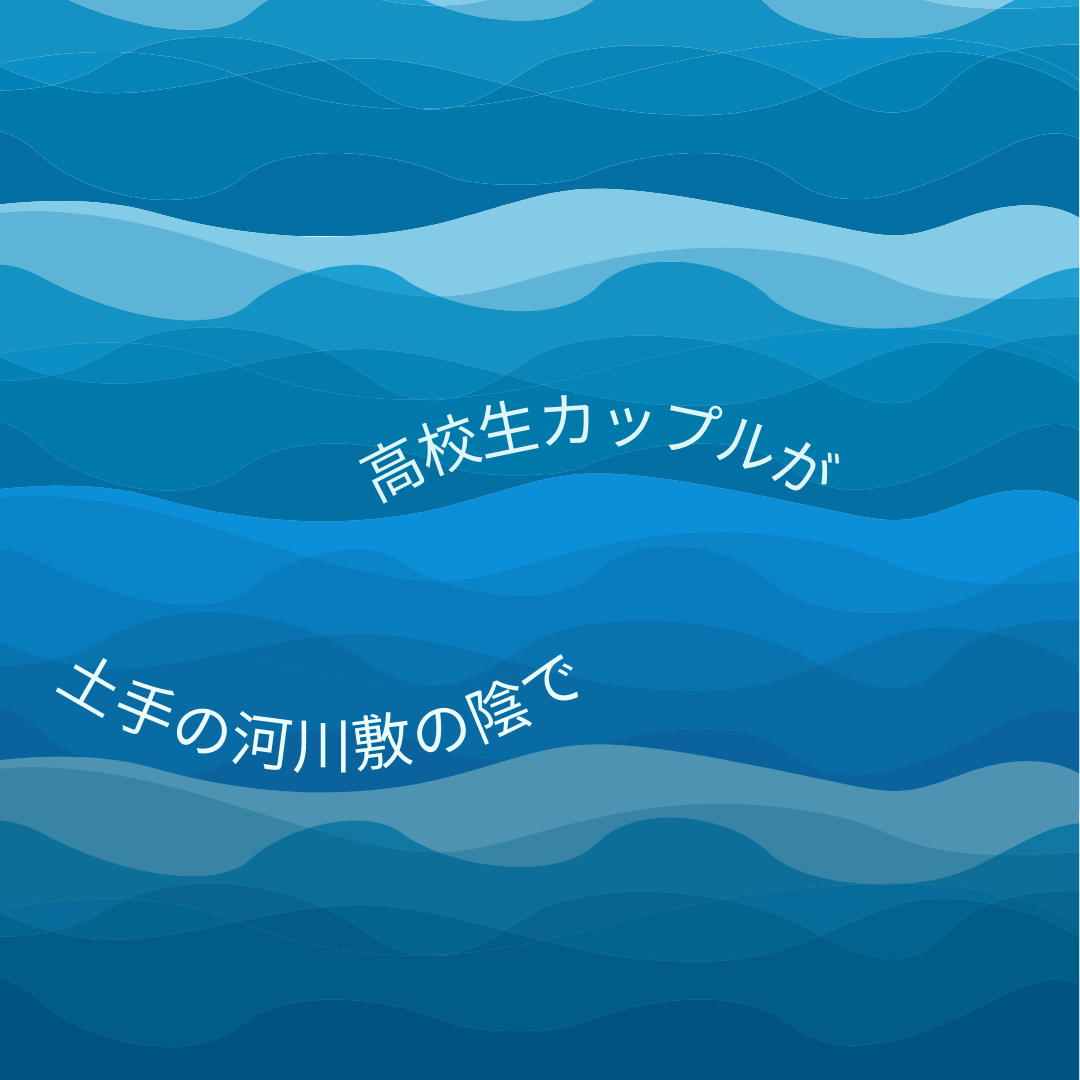


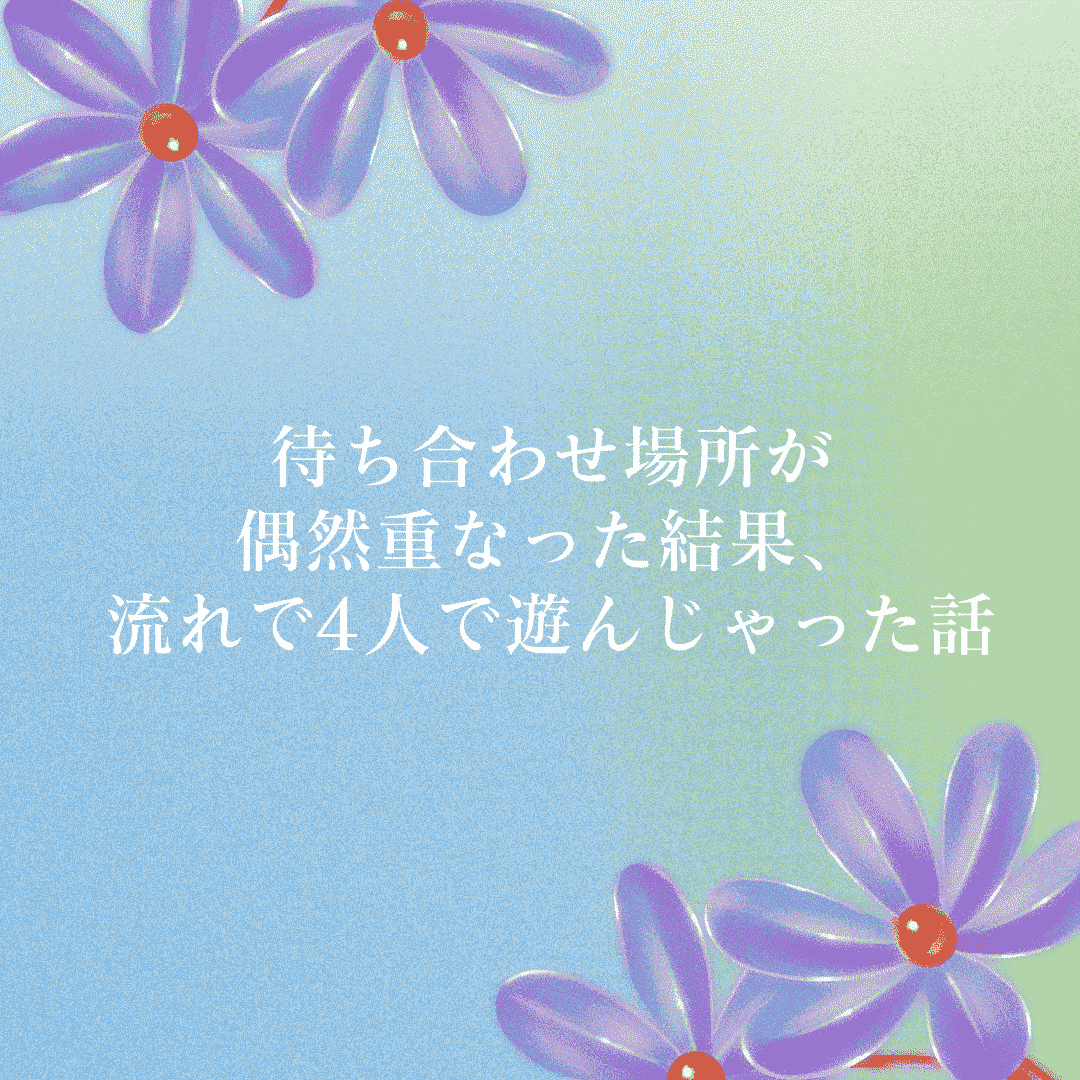




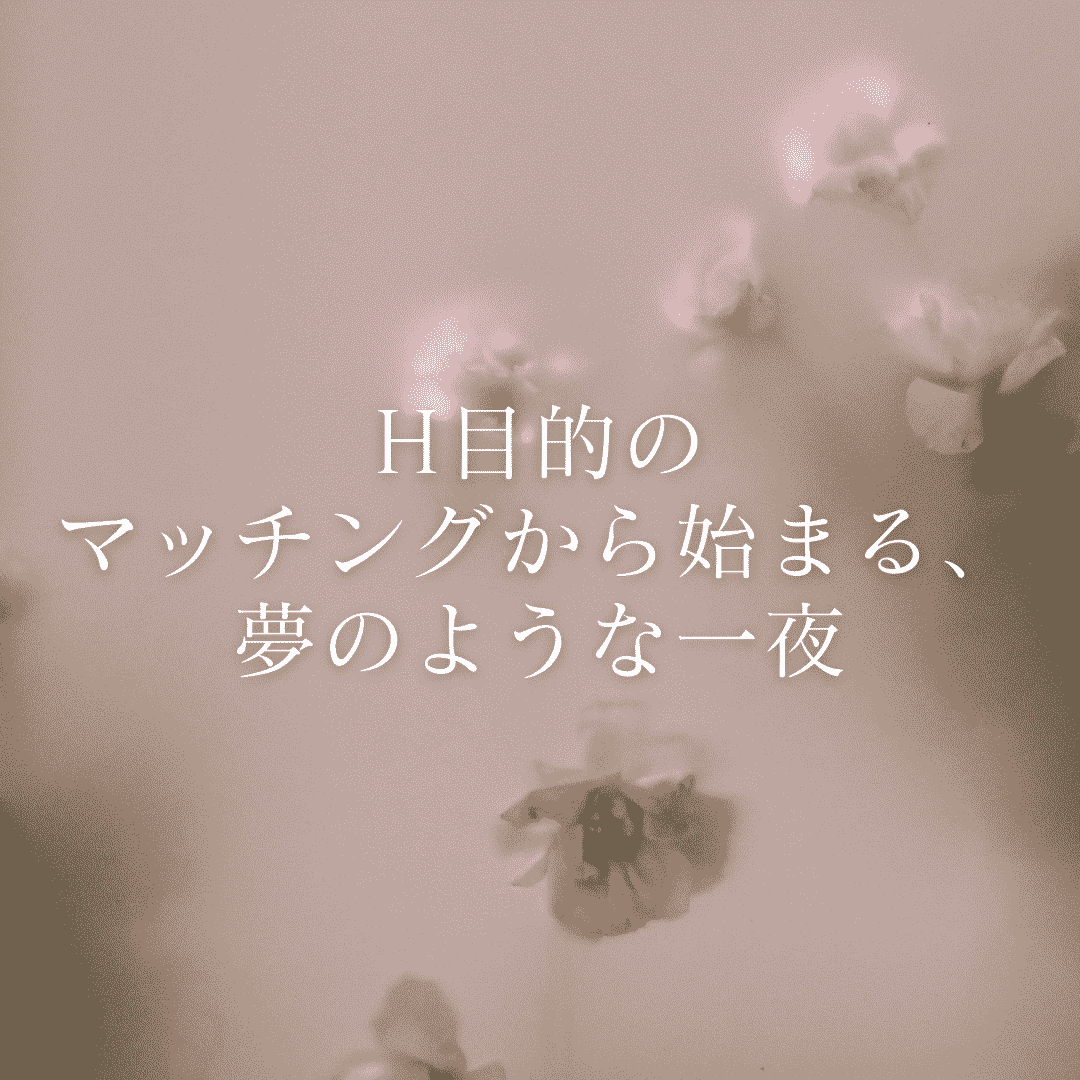
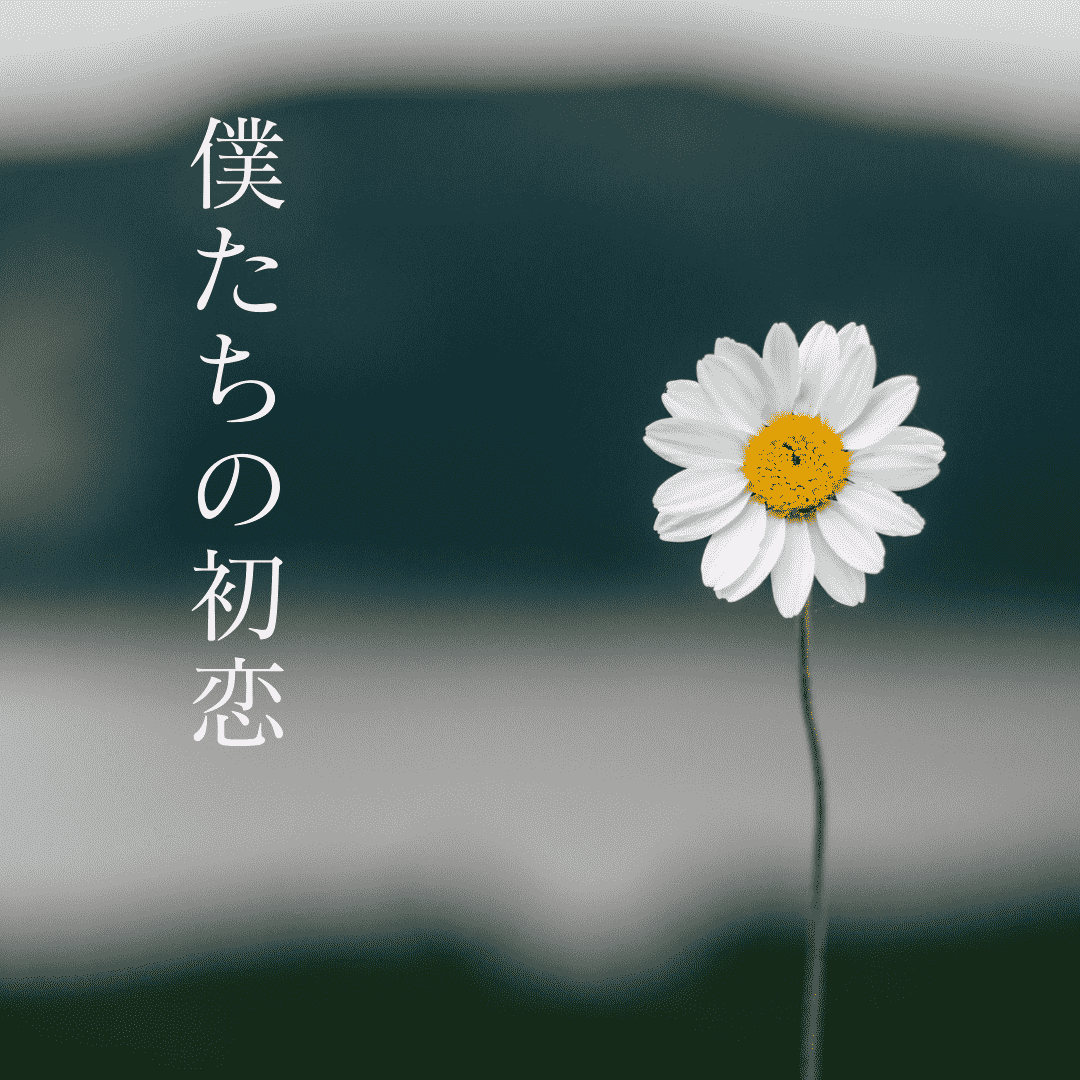


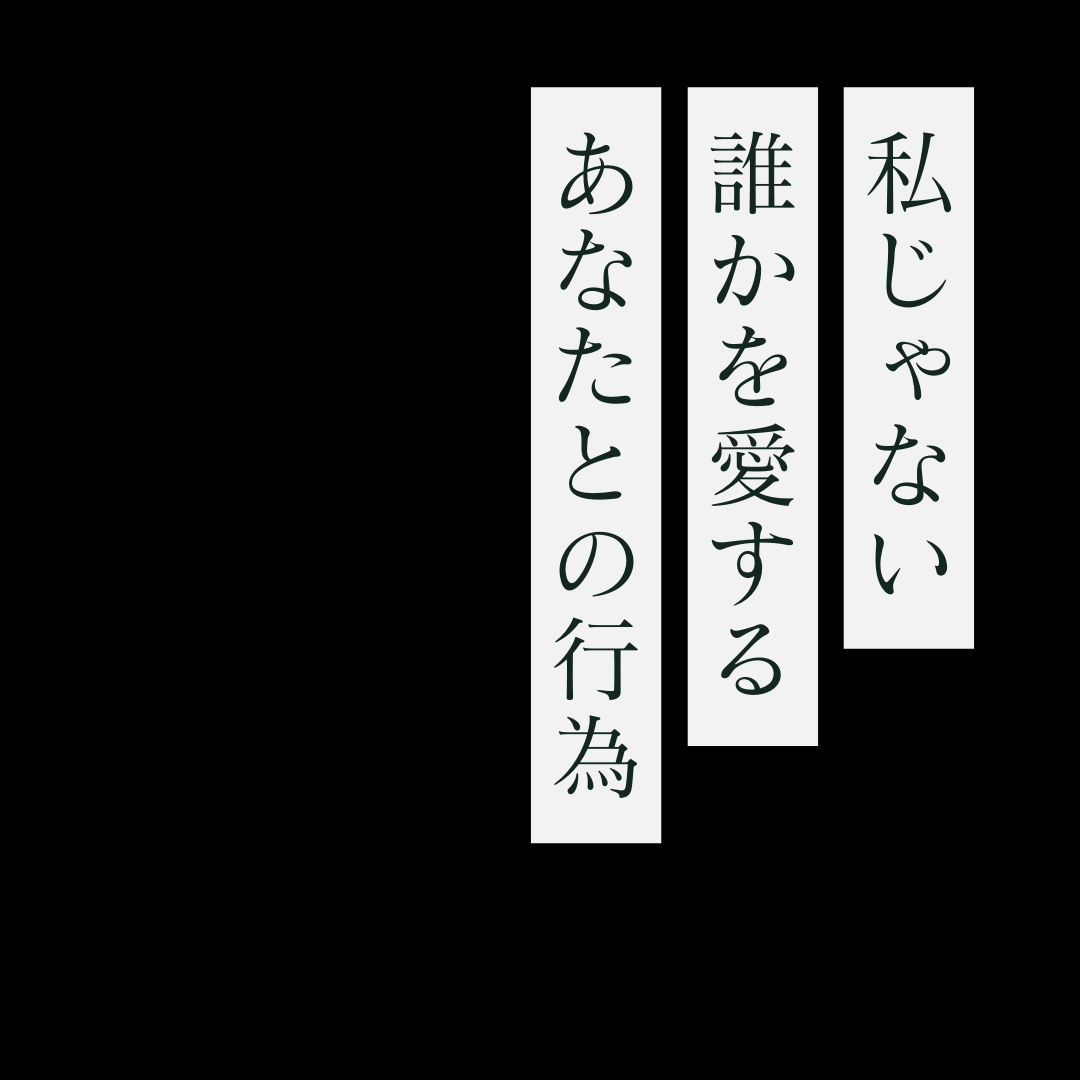

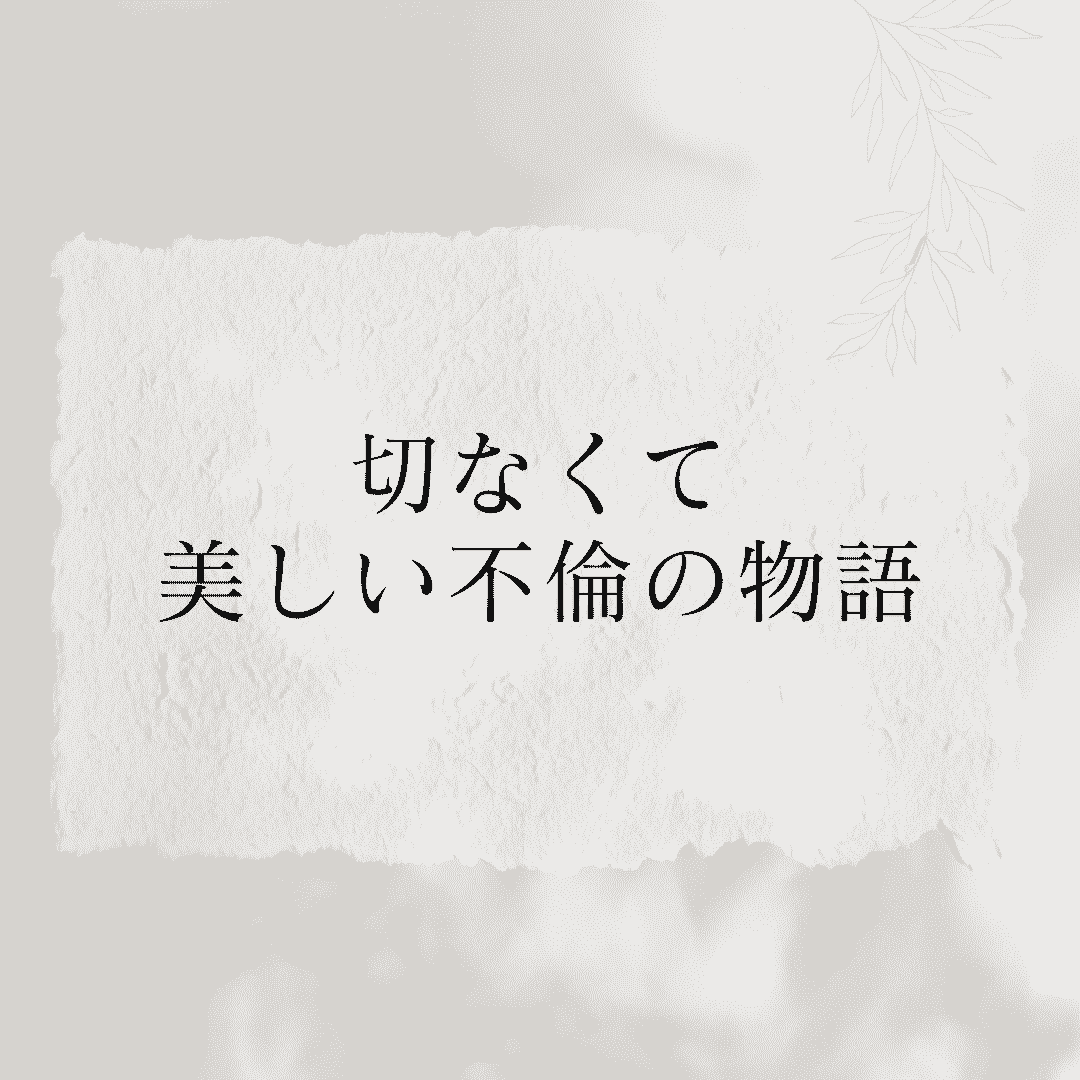
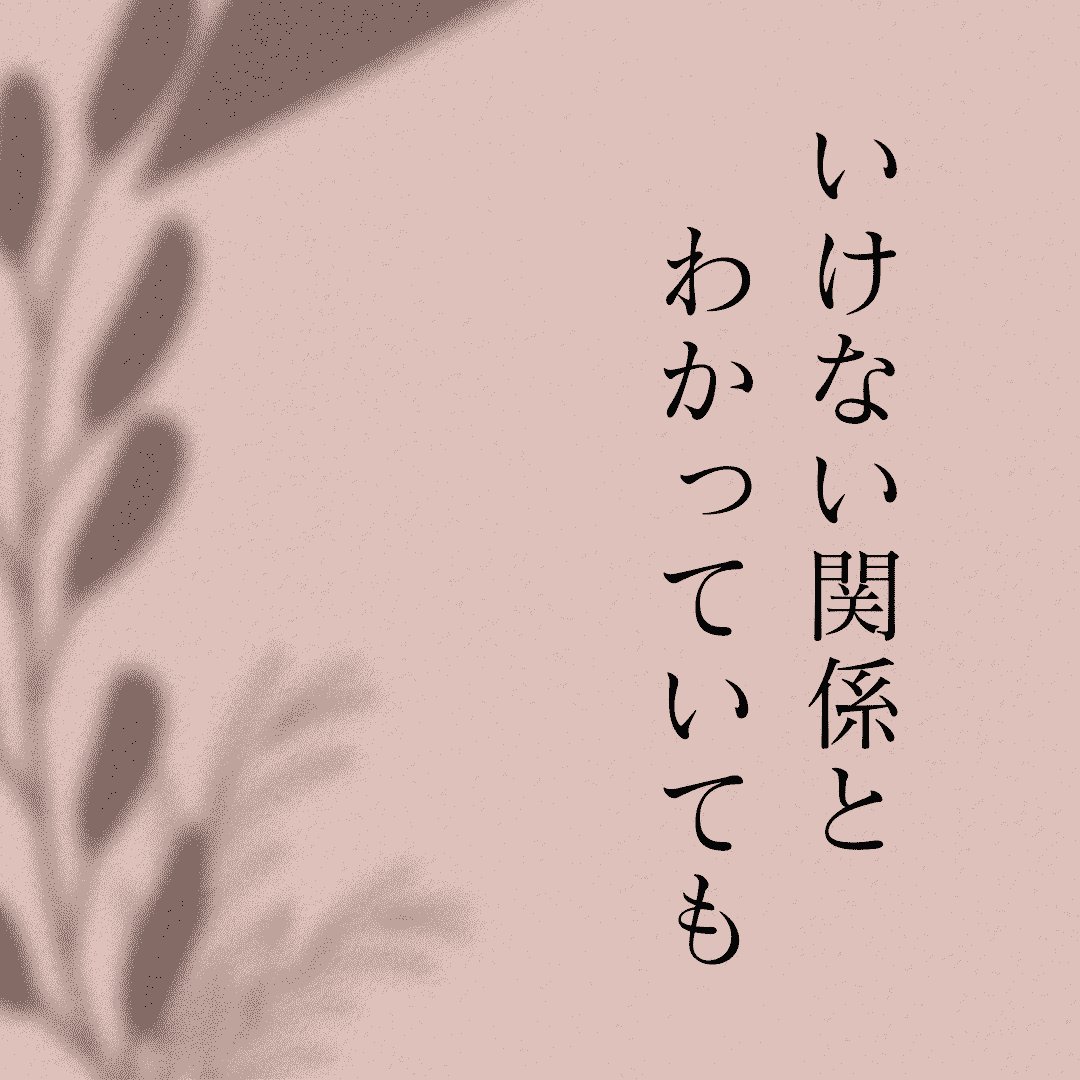









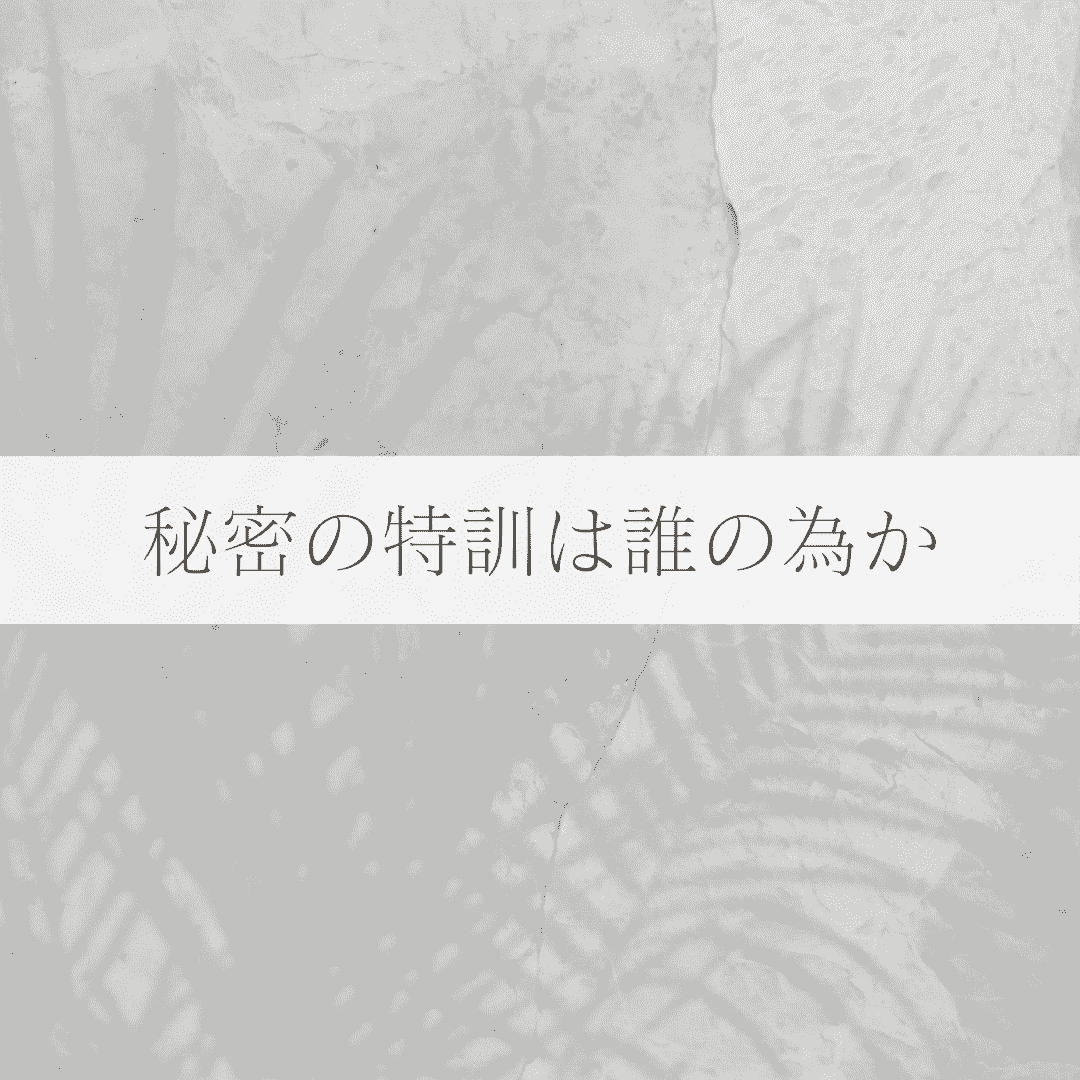
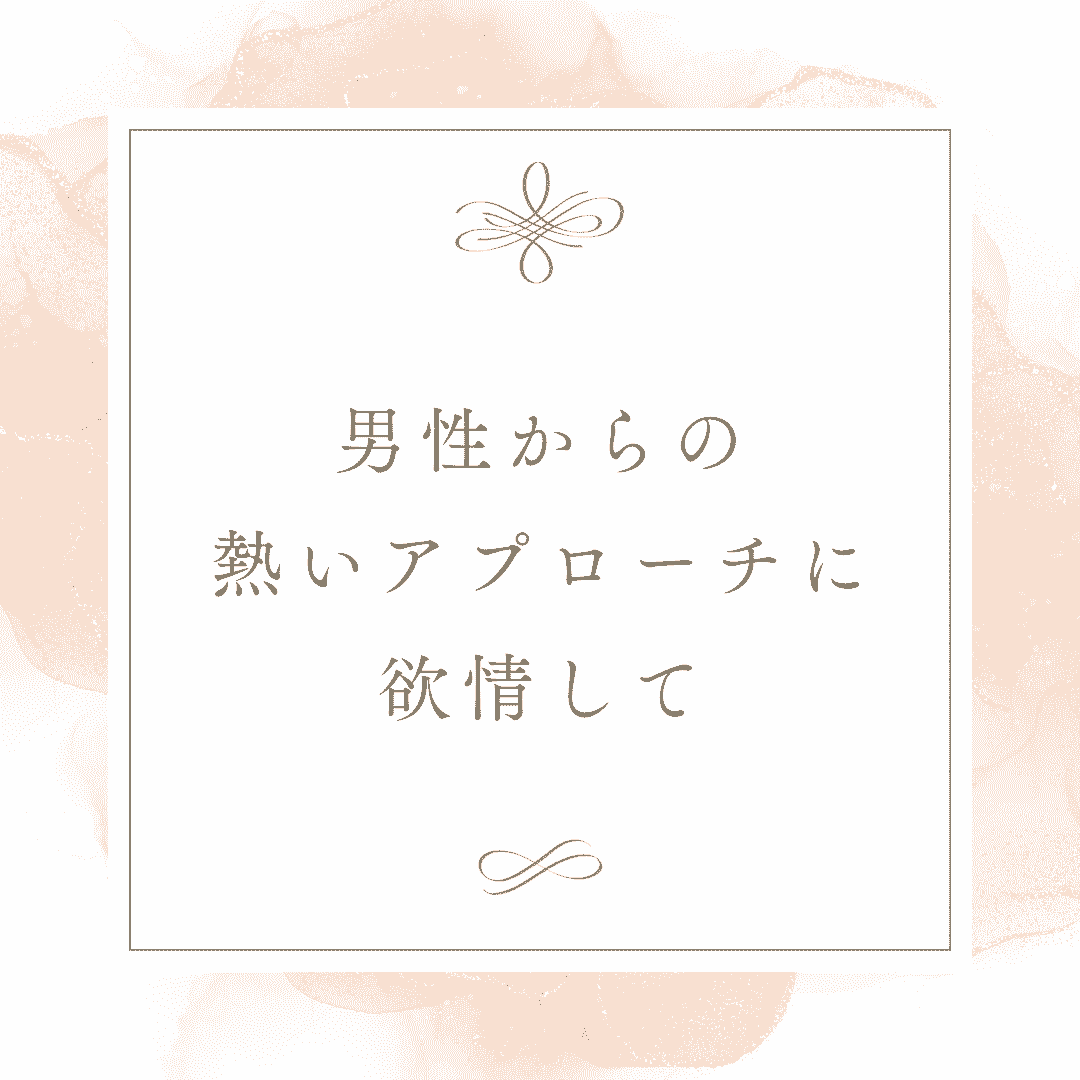


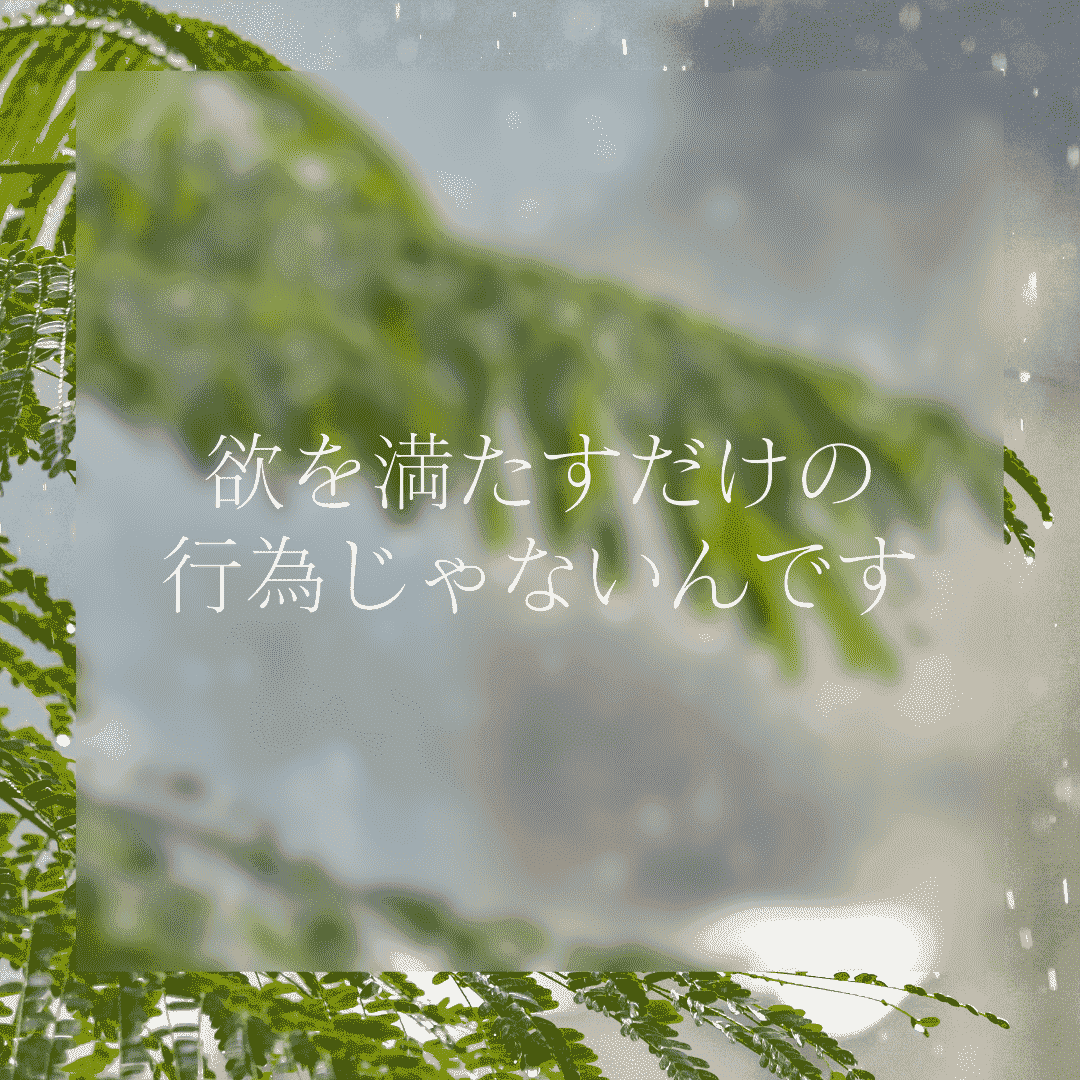

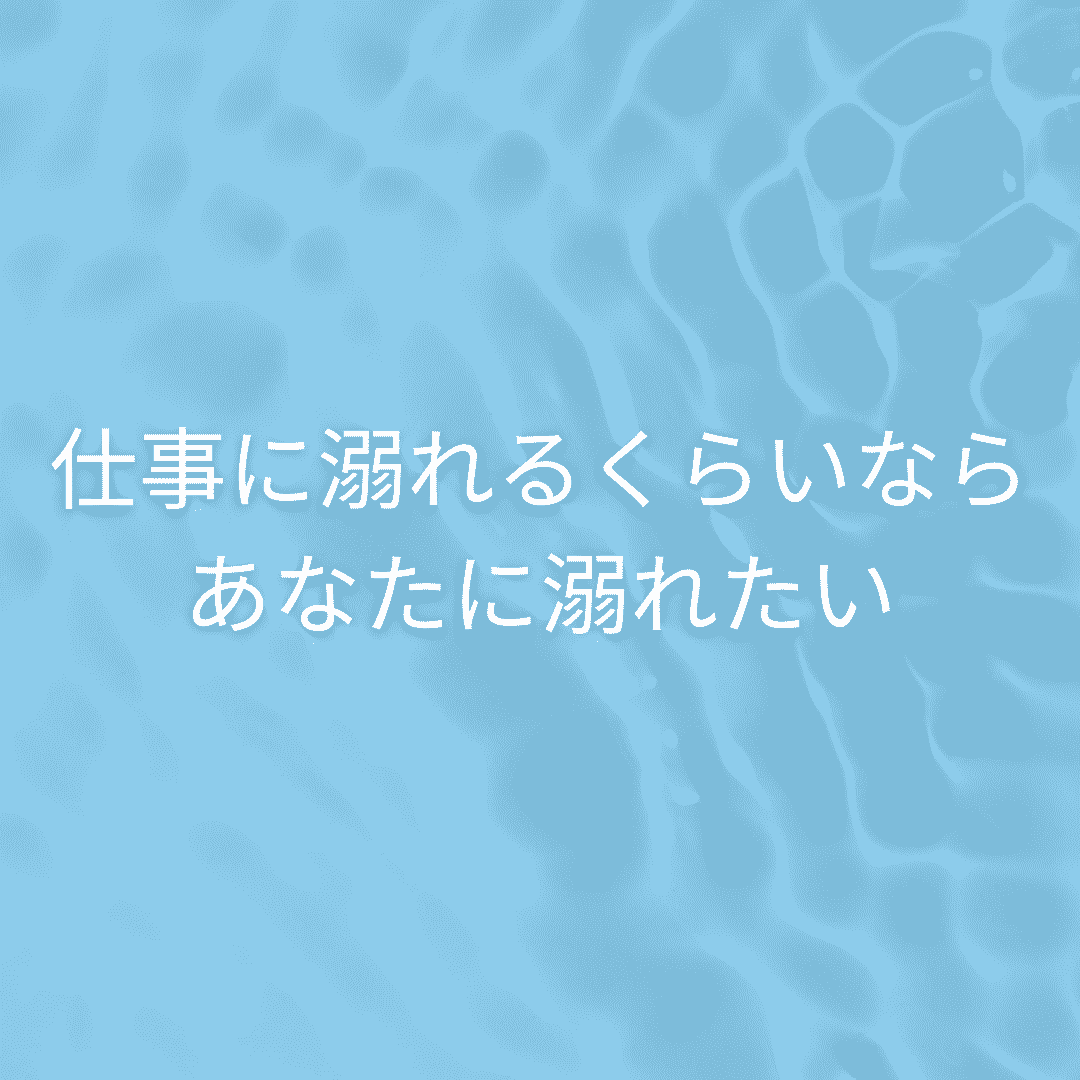


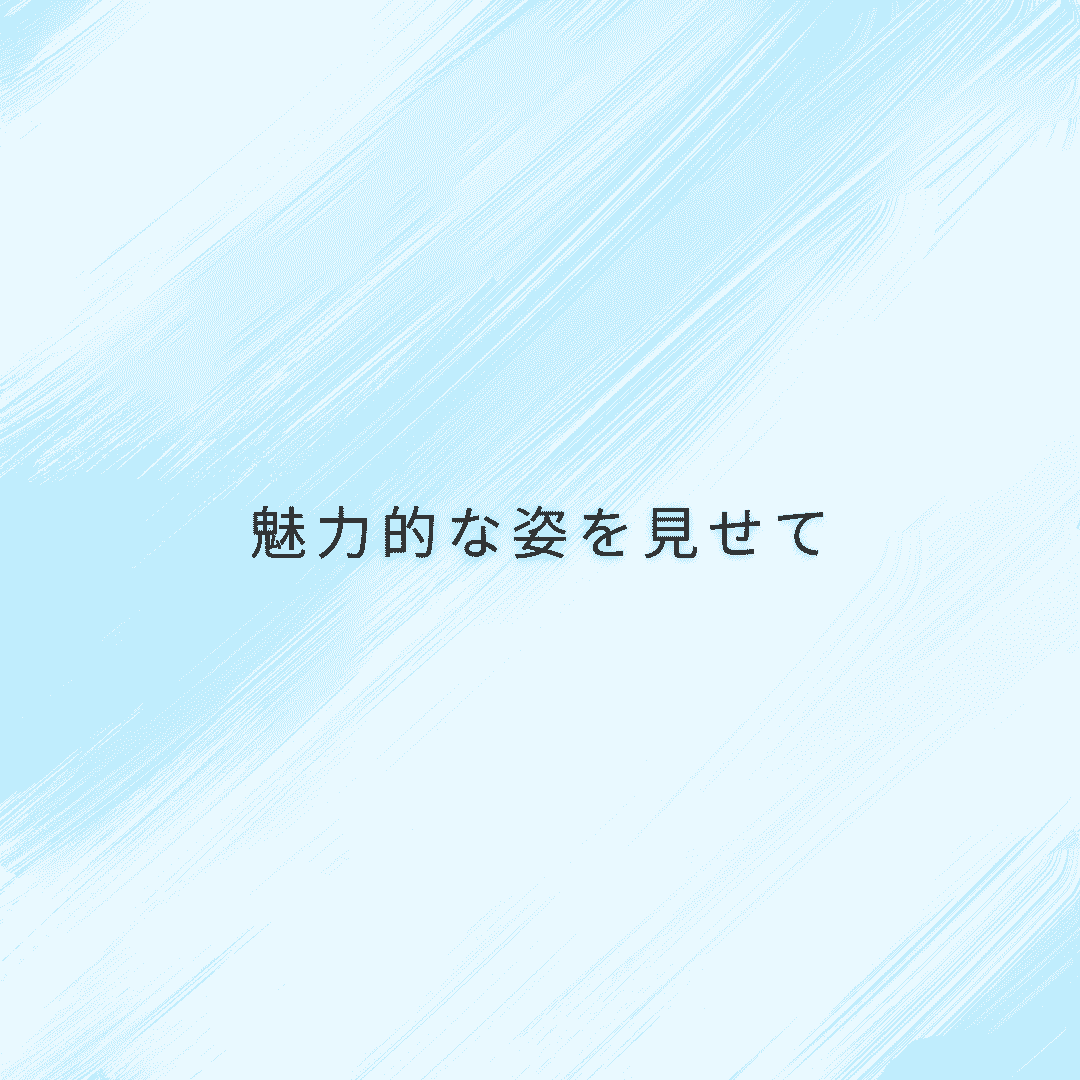
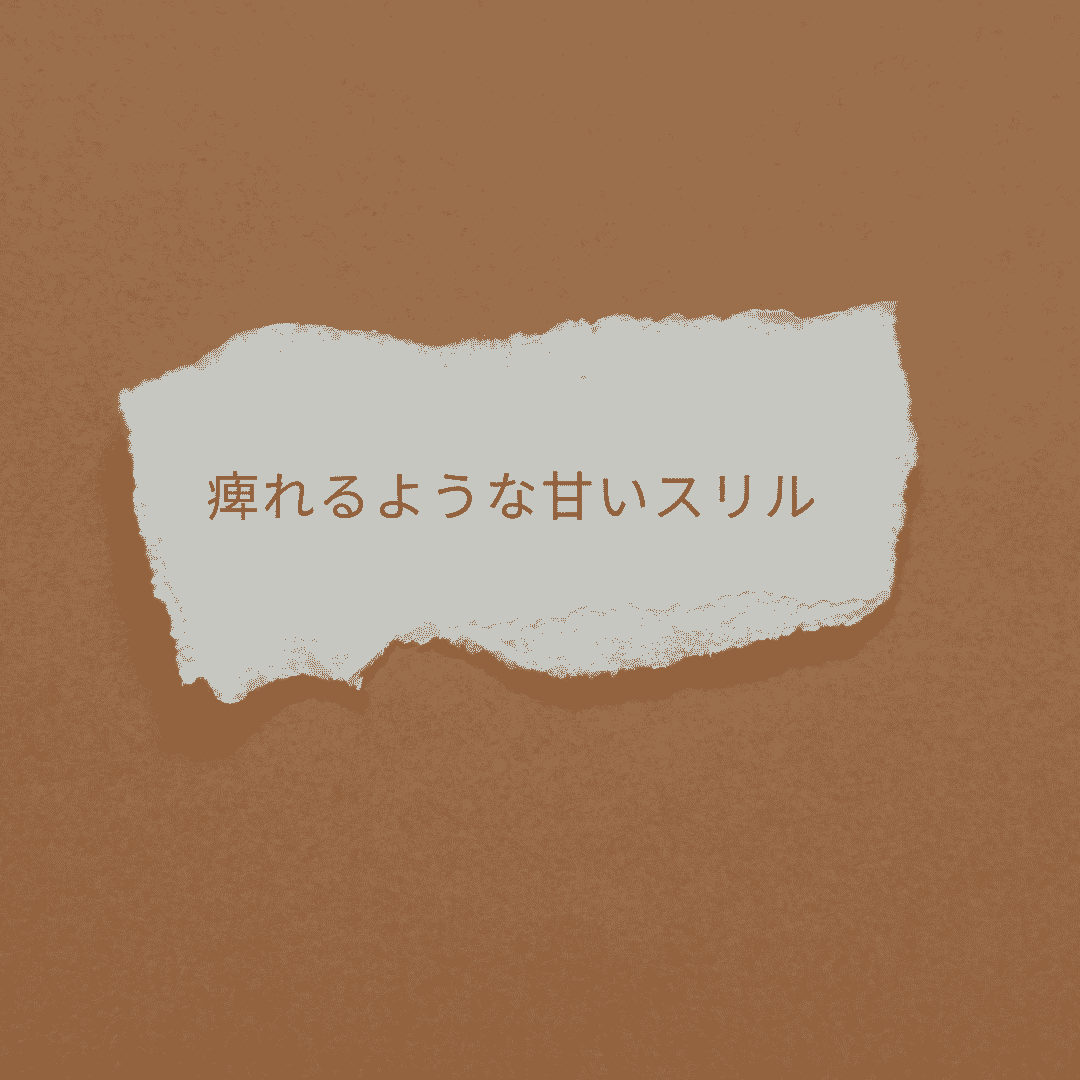

コメント