
0
深夜のインスタライブ:禁断のBL秘話
「あの……もしかしてアオくんですか?」
よく晴れた水曜日の昼。これから若者の間で流行りそうな、おしゃれカフェに足を運ぶ。そして、いつものように自撮りをしようとした時、あの人を見つけてしまった。
俺の向かい側の席に座り、同行者に写真を撮ってもらっている男性。すらっとした手足に明るめの茶色い髪を、ウルフカットにしている。間違いない、最近インスタフォロワー数50万人を突破した人気インスタグラマーのアオくんだ。
撮影が終わると、アオくんはカメラを持った同行者を先に帰らせていた。運ばれてきたシフォンケーキを前に目を輝かせているところに、そっと声をかけた。すると、嬉しそうな顔をしながら答えてくれた。
「いつも投稿見てくれてるの?」
「ほ、ほんものだ……ずっと見てます!」
「ありがとう。すごい顔がいいけど、もしかしてモデルとかしてる?」
かっこいい人にそんなことを言ってもらえるだなんて……頭がどうかなりそう。顔がにやけてしまうのをなんとか抑えながら、スマホを取り出した。
「実は俺もインスタグラマーしてて……こんな感じのなんですけど。」
恐る恐る画面を見せた。
「1万人もいるの!すごいね。ふーん大学生なんだ。ルトくんって呼べばいい?」
「うあああそんなそんな……まだまだです……ルトくんって呼んでもらえるんですか?」
「俺さ、こうやってカフェとか街中で声かけられたの初めてなんだよね。」
「え、意外だ……」
こんなにかっこいい人が歩いてきたら、二度見も三度見もして、すぐにインスタグラマーだってバレるだろう。それなのにまだ、街中でバレてないだなんて。
「みんな街中で人のことあんまり見てないっぽいよ。ルトくんはよく見てる。俺のことそんなに好き?」
「す、好きです!」
勢いよくその言葉を口にすると、なんだかおもしろくなっちゃって、声を出して笑ってしまった。つられてアオくんもへにょっと笑ってくれた。いつもクールな写真が多いから、こんなに可愛い笑い方をするのを初めて知った。
インスタアカウントをフォローし合い、何枚か一緒に自撮りをしたあと、アオくんはとんでもないことを口にした。
「ルトくんさ、よかったらこのあと家に来ない?」
「ええっ?いいんですか?」
「いいよいいよ。インスタグラマーの知り合いって初めてでうきうきしちゃって……って、めっちゃ口開いてるね?」
憧れの人からのまさかのお誘いに、口が開いたままになってしまっていたらしい。慌てて口を閉じて頭を縦にこくこく動かすと、アオくんはまたさっきのへにょんとした笑顔で頷いてくれた。
***
「はぁっ……あっ、あっ……」
甘ったるい声が止められない。ソファーに座らされたまま、憧れていた綺麗な顔の男の人にちんこを喉奥まで咥えられ、ぐぼぐぼと音を立てて刺激されている。ちんこの先っぽから根元まで、手も使ってまんべんなく気持ち良くしてくれていて、声が抑えられない。すぐに達してしまわないように、一生懸命お腹に力を入れていても、あまりの気持ちよさに意識が飛びそうになる。
ーーー
アオくんの家は白と黒のもので統一されており、ところどころに観葉植物が置いてある。整理整頓好きな成人男性のひとり暮らしの部屋ってこんな感じなのか、と部屋をぐるぐると見渡していると、いきなり後ろから抱きしめられた。
「わっ、急になんですか?」
「撮影するためのカフェに入った時からさー、可愛い子いるなーって思ってたんだよねえ。」
「えっ、っと……俺のことですか?」
なんだか様子がおかしい。俺の耳元にあるアオくんの口からは、はあはあと荒い息が漏れている。腰のあたりに押し付けられているものは、明らかに勃起したちんこだと、服の上からでも感触でわかる。
「しかもさっき好きだ、とか言ってくれたし。」
「好きって、そりゃもちろん好きですけど……」
「俺のこと本当に好きか、試してみよっか。」
そうして俺はあっという間に下着ごと服を脱がされ、ソファーに座らされた。抵抗する間もなく、まだ何の反応も示していないちんこが温かい口腔に含まれた。それはぬるぬるした唾液を纏った舌で少し刺激されただけで簡単に硬くなり、喉奥で刺激されるまでに時間はかからなかったと思う。限界まで膨らんだと思っていたちんこが、声を漏らすたびに育っていく。先走りと唾液が混ざってさらに音が大きくなっていって、耳からも犯されている気分になる。
「ん……も、もっ、出ちゃ……アオくんっ、出るうッ!」
自分のものと思えないくらい高い声をあげ、ぶるりと腰が震えた。さっきよりも強めに吸引された次の瞬間、アオくんの口の中にねばねばした精液を流し込んでしまった。
「はあ……はあっ、アオくん、ごめっ」
近くに見えたティッシュを取ろうと腕を伸ばそうとした時、下からごくりと喉の音がした。もしかしてと思いながらアオくんの顔を見ると、口を開けて見せてくれている。
「飲んじゃった。かわいい子の精液って甘いねえ。」
「そんなに俺、可愛いですかね……」
「かわいいよ。自分でわかってなかったなんてもったいない。さっきの嫌じゃなかった?」
「嫌、じゃなかった。好き。」
「よかった。俺も好きだよ、ルトくん。」
さらりと告白され、唇に軽くキスされた。
「じゃあ、さっきの続きしよっか。」
アオくんはすごく細く見えたのに、ソファーに座っている俺を、軽々と横抱きにして、ベッドまで運んでいった。時間をかけてなかをほぐされた俺は、その日何度も何度も絶頂させられることになった。
***
アオくんと付き合い始めてから3週間が経った。俺は実家暮らしだが週の半分以上はアオくんの家に泊まりにいっている。そのまま大学へ行くこともよくあり、その日は丸一日セックスのことが頭から離れなくて大変だけれど、どの講義も機嫌良く受けられるしまあいっか、なんて思っていた。
講義が終わりアオくんの家へと帰り、一緒にご飯を作って食べる。共通の話題で盛り上がったり、一緒にお風呂に入ったりしているうちに、あっという間に24時を過ぎている。
「あ、やべ。」
「どうしました?」
ベッドの中で抱きしめ合い、今にもやらしいことが始まりそうな雰囲気だったのに、アオくんが焦った声を上げて飛び起きた。ベッドサイドテーブルに置いてあったスマホを握り、なにやら操作している。
「インスタライブやるって予告してたんだったわ。」
「明日にしたらいいんじゃないですか?」
「いや……ライブしたい……でもルトくんも食べたい……」
「強欲すぎますって。」
「じゃあどっちもやるか。」
「え?」
聞き返したものの、俺の言葉も聞かずに、アオくんは本当にインスタライブを始めてしまった。慌てて画面を覗き込むと、画像モードになっている。よかった、映ってはいない。
「みんな遅くなってごめんね~まだ起きてる?」
ベッドサイドチェストにスマホを置き、画面に向かって話しながら、俺のパジャマを脱がしにかかってきた。抵抗する間も無く素っ裸にされ、ベッドの下にある引き出しからゴムと潤滑ゼリーを取り出している。
「うん、うん……そう、なんかぼーっとお風呂入ってたら忘れてたんだよね。ごめんって。」
コメントを読みながらも器用に潤滑ゼリーを中指に垂らし、俺の足を開かせ中指をつっこんできた。
「ん……ッ」
指が入ってきた衝撃で声が漏れてしまい、慌てて口を抑える。できるだけ音を立てないためかいつもよりもゆっくり動かしていて、新鮮な動きになかがきゅんきゅんと締まってしまう。
「みんなこの時間までなにしてたの?……動画見てた?いいなー、俺も見ようかな。」
アオくんは、そう話しながらも、俺への刺激は止めない。人差し指も入ってきて、2本の指をなかでばらばらに動かされた。
「んっんっ……」
頑張って口を抑えていても、気持ちよ過ぎて声が小さく漏れてしまう。もう動かさなくていいと目で訴えると、やっと抜いてくれた。
「実況ねー俺もよく見るわ。睡眠導入剤として聴きながら寝ることもある。いやマジだって!おすすめの実況者いたら教えてほしいな。」
ゴムの風を口を使って開け、硬そうなちんこにつけていくのが見える。すごく冷静に、時には笑いも交えながら、なのに手元は、すごくいやらしいことをしている。
ゴムをつけ終え、もう一度大きく俺の脚を開かせてくる。音を立てずにキスをされ、そのままゴムがついたちんこがゆったりとなかに入ってきた。
「ぁあッ!」
急いで手の甲を噛む。やばい、聞こえてるかも。
「今なんか音した?音?深夜に飛ぶ鳥じゃない?」
「んっ、んんっ」
「そんな鳥いないって?いるかもしれないじゃん。」
静かに軽快な話をしながらも、なかの動きは凶暴だ。器用なアオくんは短期間のうちに理解した俺の好きなところを的確に攻めてくる。荒い息を堪えられず手が唾液でべとべとになっている。ぱんぱんと肌と肌がぶつからないようにぬるぬると動いている。焦らされているような感覚になってしまい、なかを締めて必死に快感を得ようとしてしまう。今までは突っ込む側だったのに、アオくんによってこんなにもえっちな身体の動きするように作り替えられてしまった。もう戻れなさそうだ…。
「あーそろそろ切ろっかな。また夕方とかに配信しよっかな、じゃあねー」
「んぅ……!」
奥をぐりぐりと抉るように動き声が漏れそうになった瞬間、アオくんがスマホを掴み画面を操作して、画面が真っ暗になったのが見えた。ベッドの脇にそれを置き、俺に抱きついてさっきの倍以上激しく腰を打ち付けてきた。
「あっ、あああんッ、やばっ」
「もう我慢できないから切っちゃった。」
「ん、こえっ、おさえれなかっ、た……っ」
「いいって。我慢させてごめんな。」
優しい言葉を言われながらも、腰の動きは止まらない。さっきはできるだけ控えていた肌と肌のぶつかる音も部屋中に響いていて、今いやらしいことをしていると身体のなかだけでなく音でも体感できて、鼓動がありえないくらい速まっていく。
「やべっ、ルトくん、出る……っ」
俺のちんこをぐちゃぐちゃいじりながら、吐息まみれの声で耳元で囁いてきた。この余裕のない声、さっきの配信中の冷静な声とのギャップがたまらなかった。
「んんっ、おれも……イくっ、ぁああ!」
出る直前に手を離され、勢いよく精子がアオくんのお腹に飛ぶ。少し経ってからアオくんもイったらしく、ちんこを抜いてすぐ、これでもかというくらい、優しい力で抱きしめられた。
声を我慢しながらのセックスにちょっと興奮した。なんてアオくんに言ったらまたやられちゃうから言わないでおこっと。次はノーマルなプレイがやれるといいな、と思いながら、俺は大好きな人の腕の中で眠りに落ちていった。






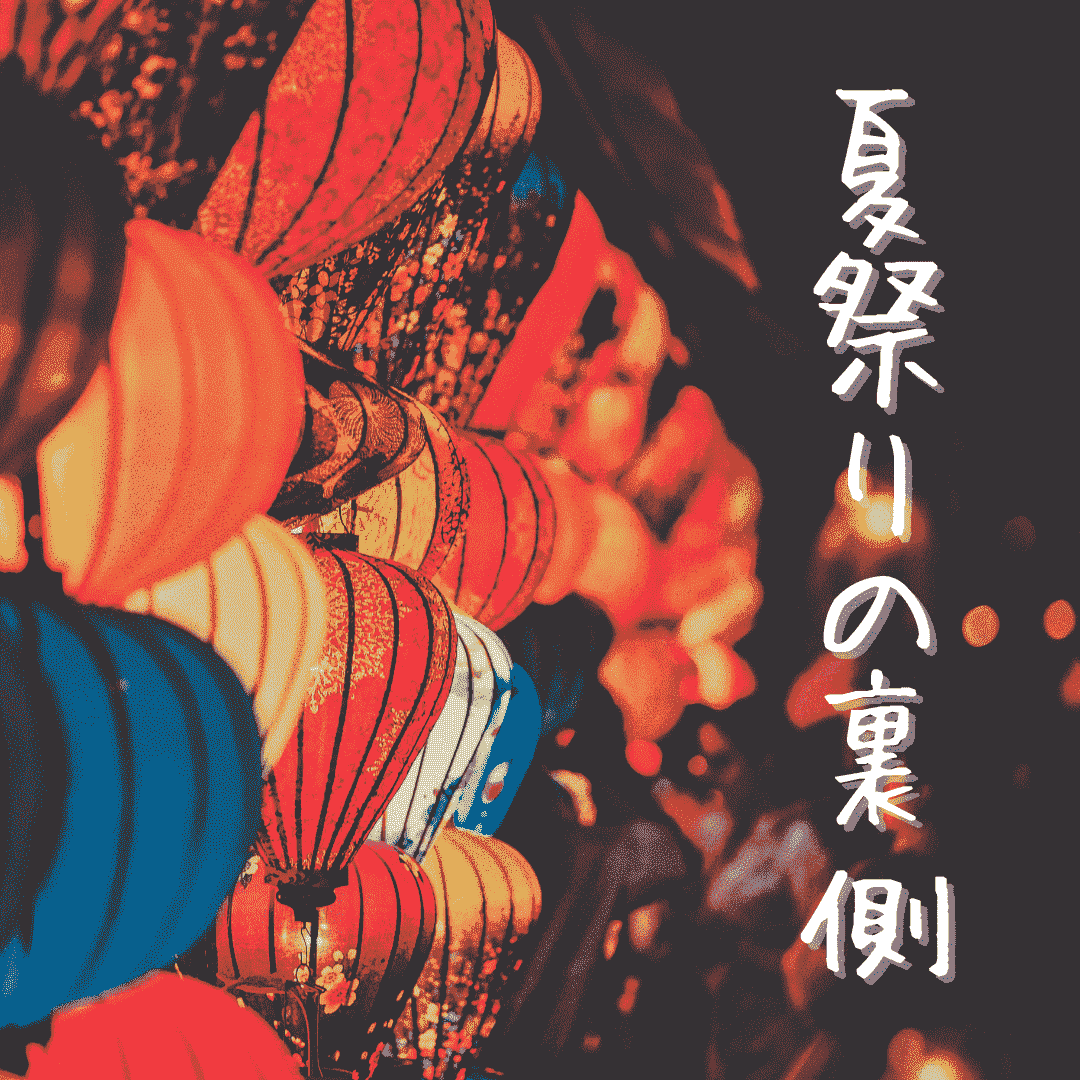

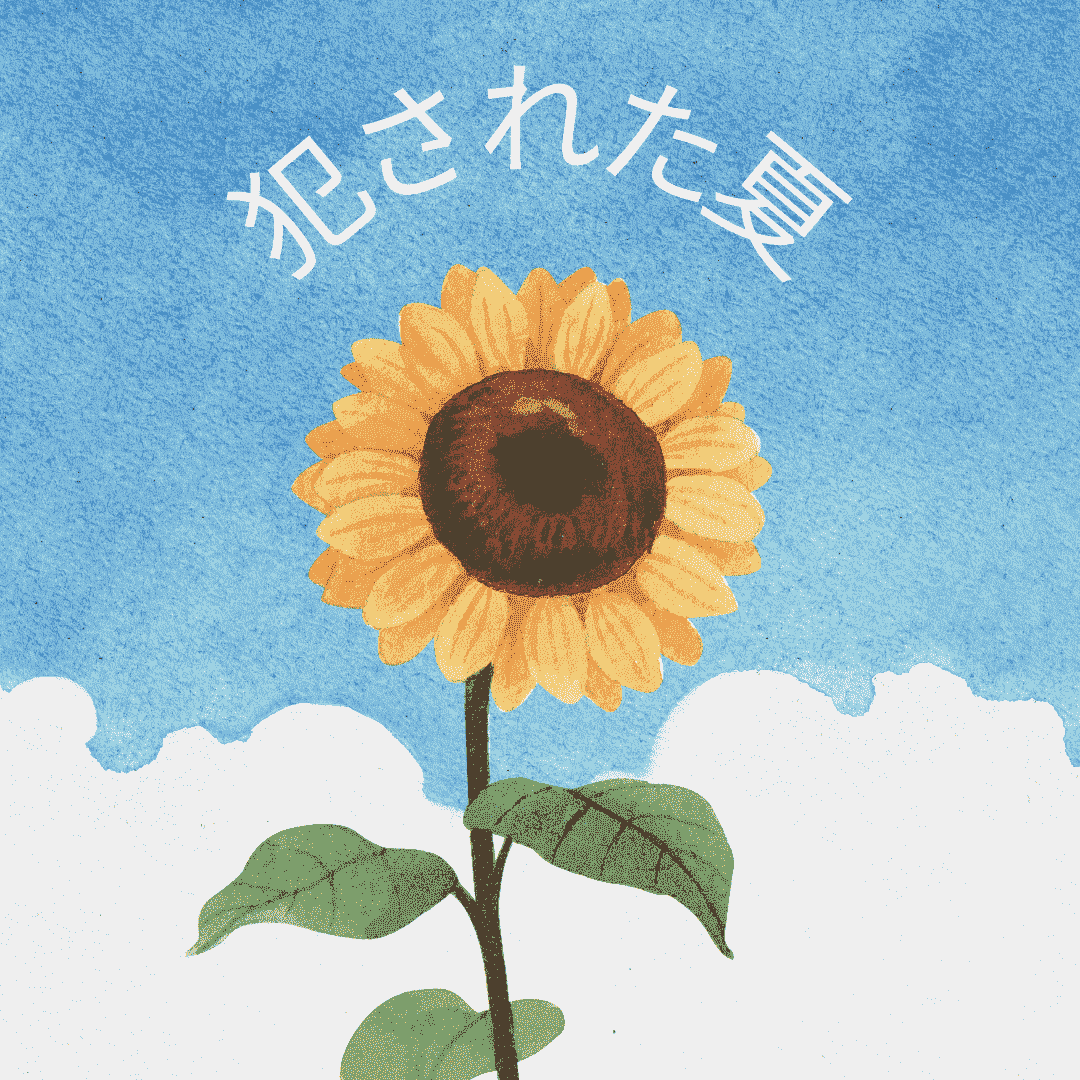


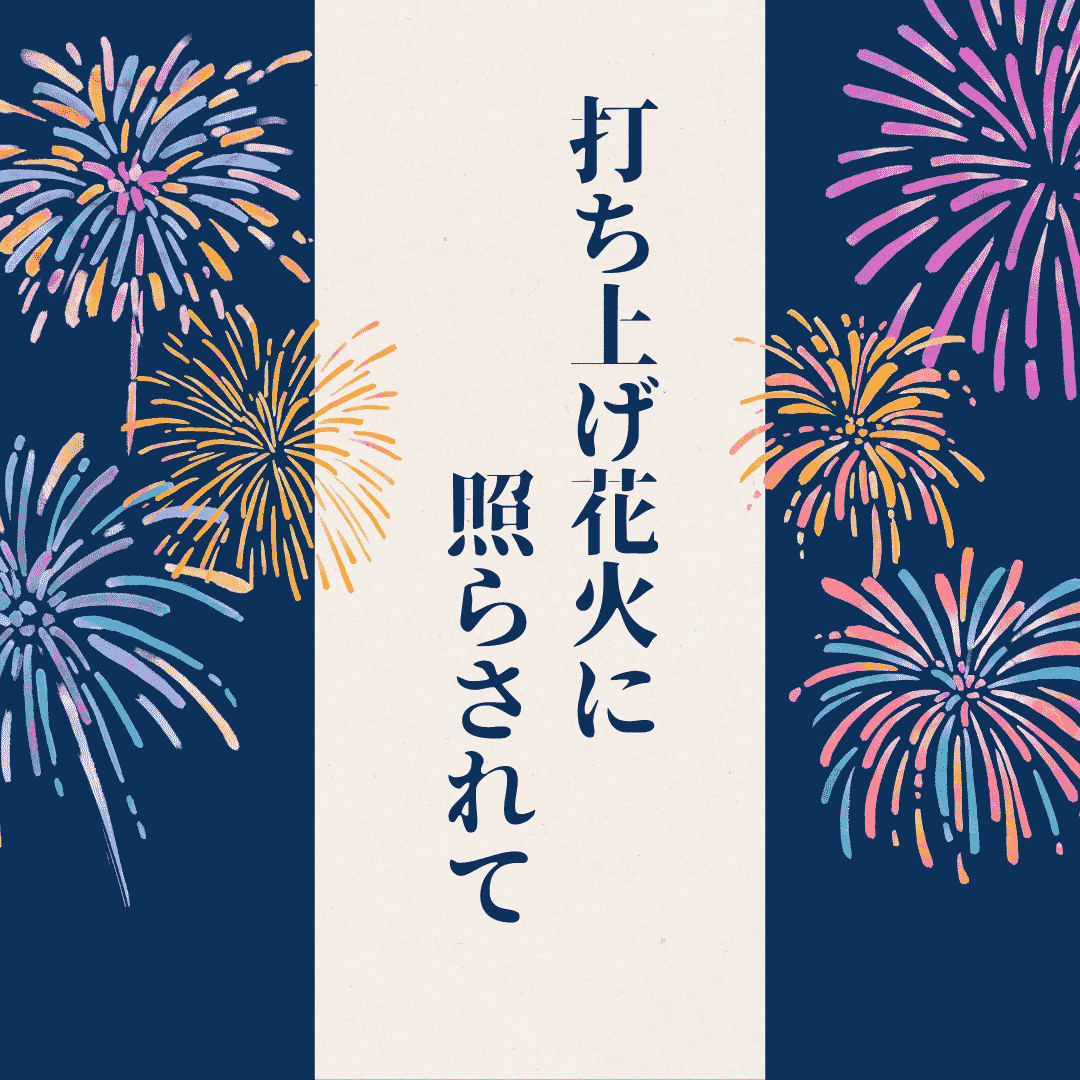

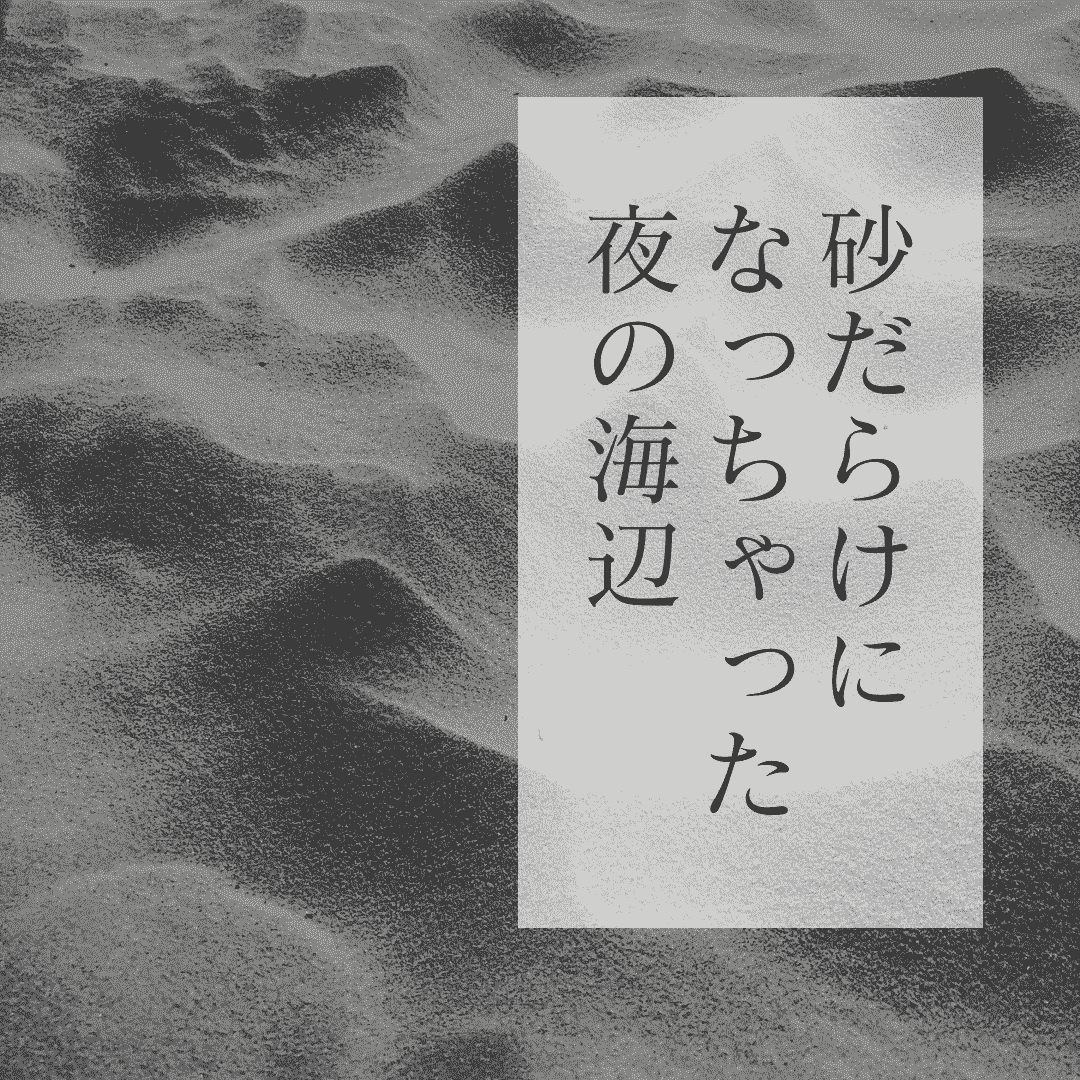

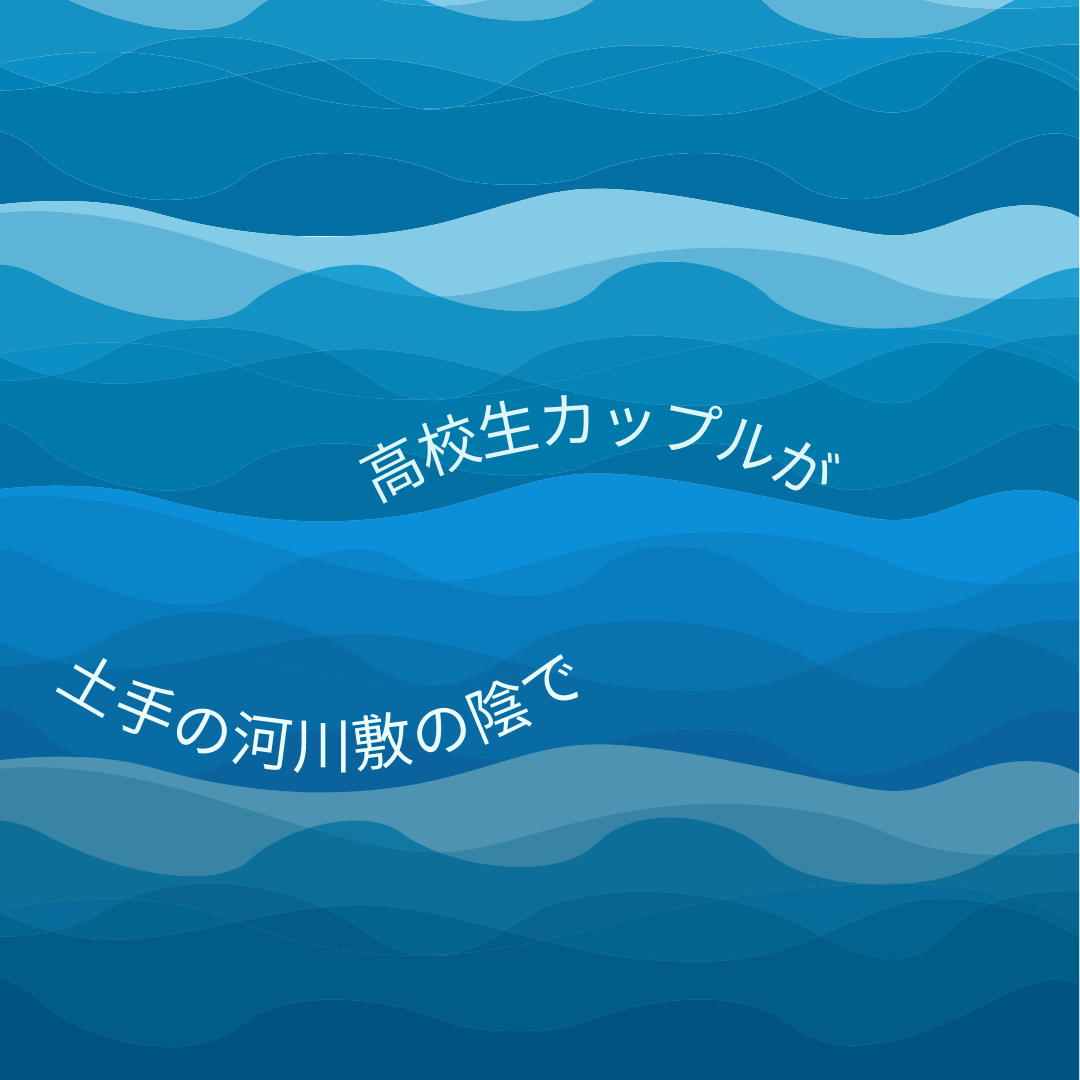


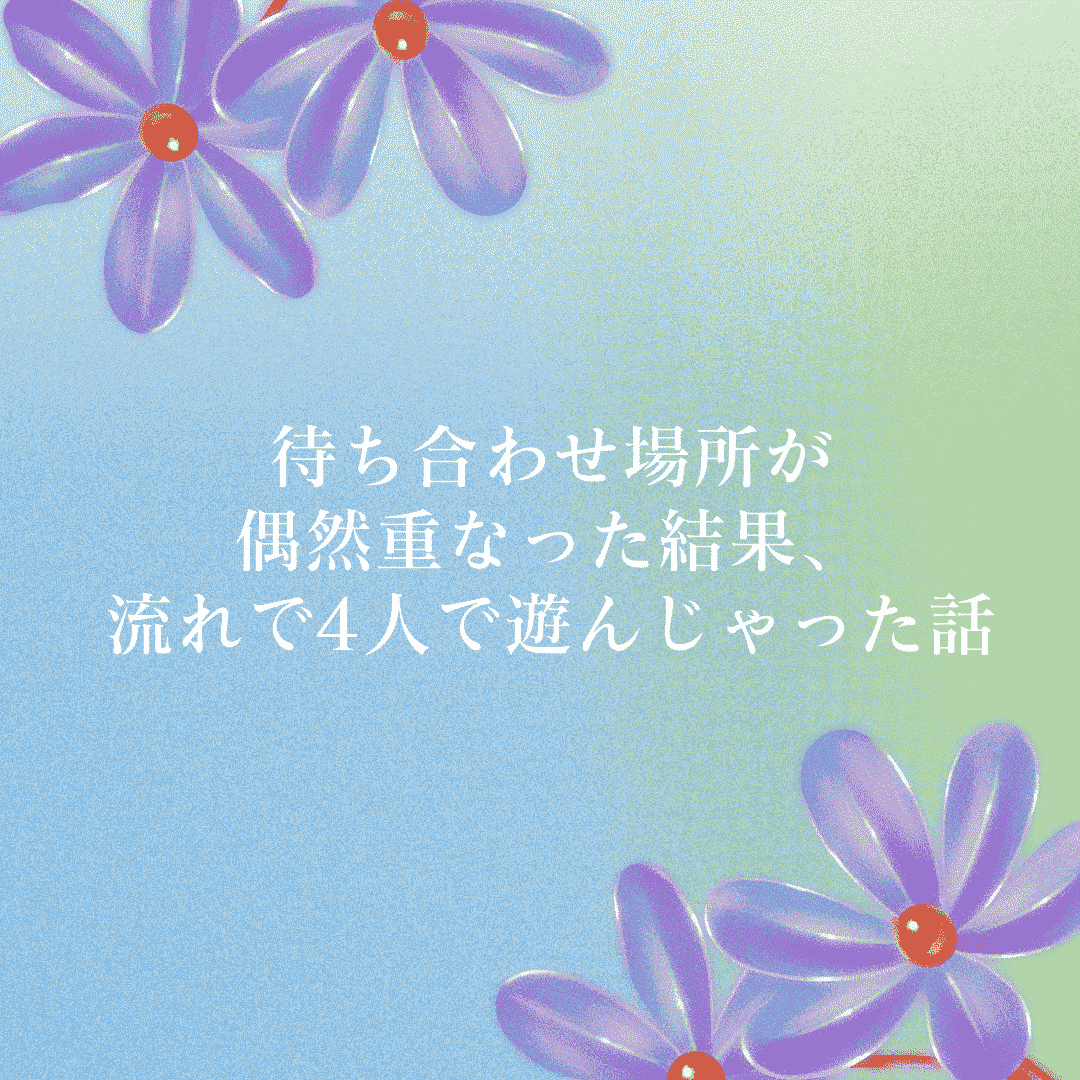




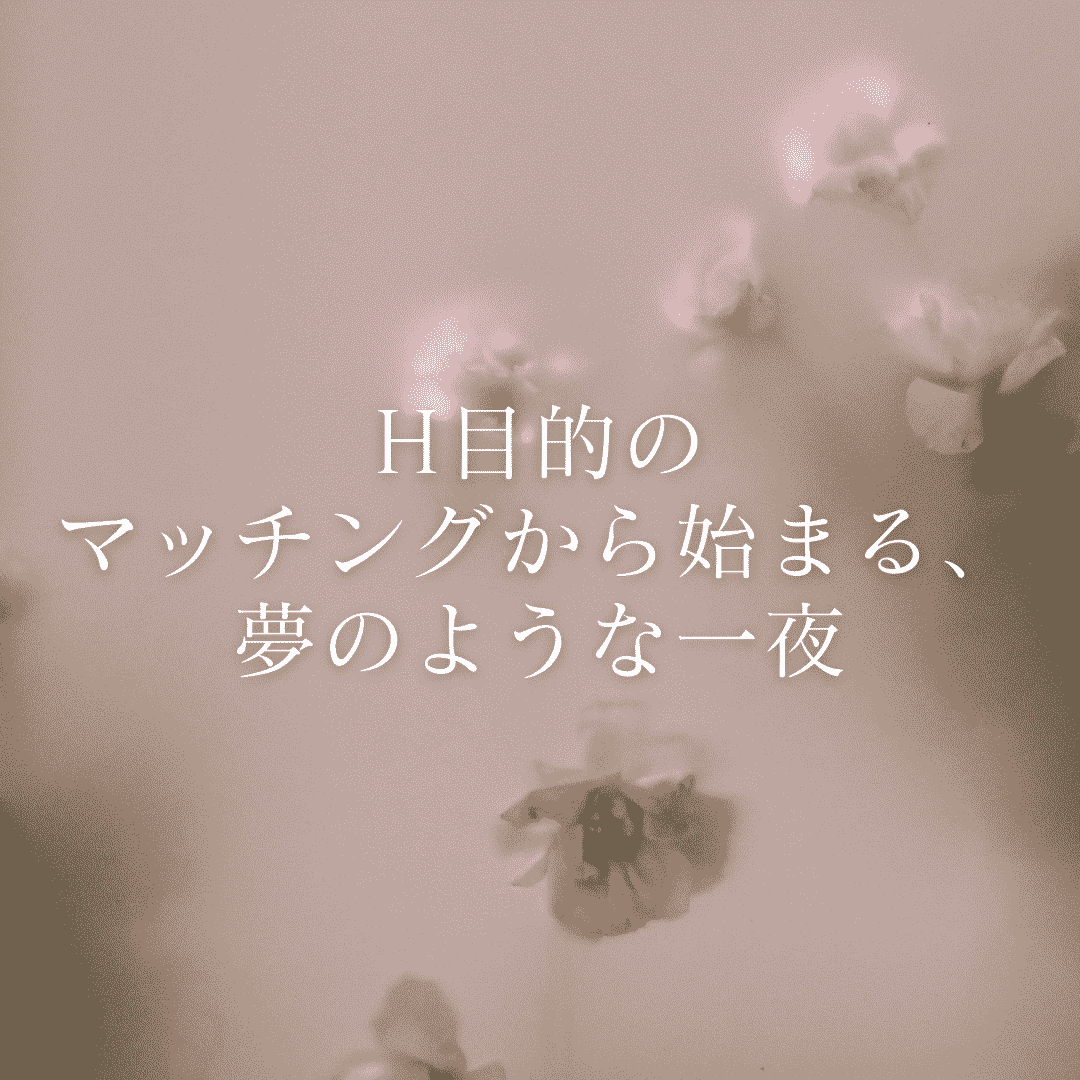

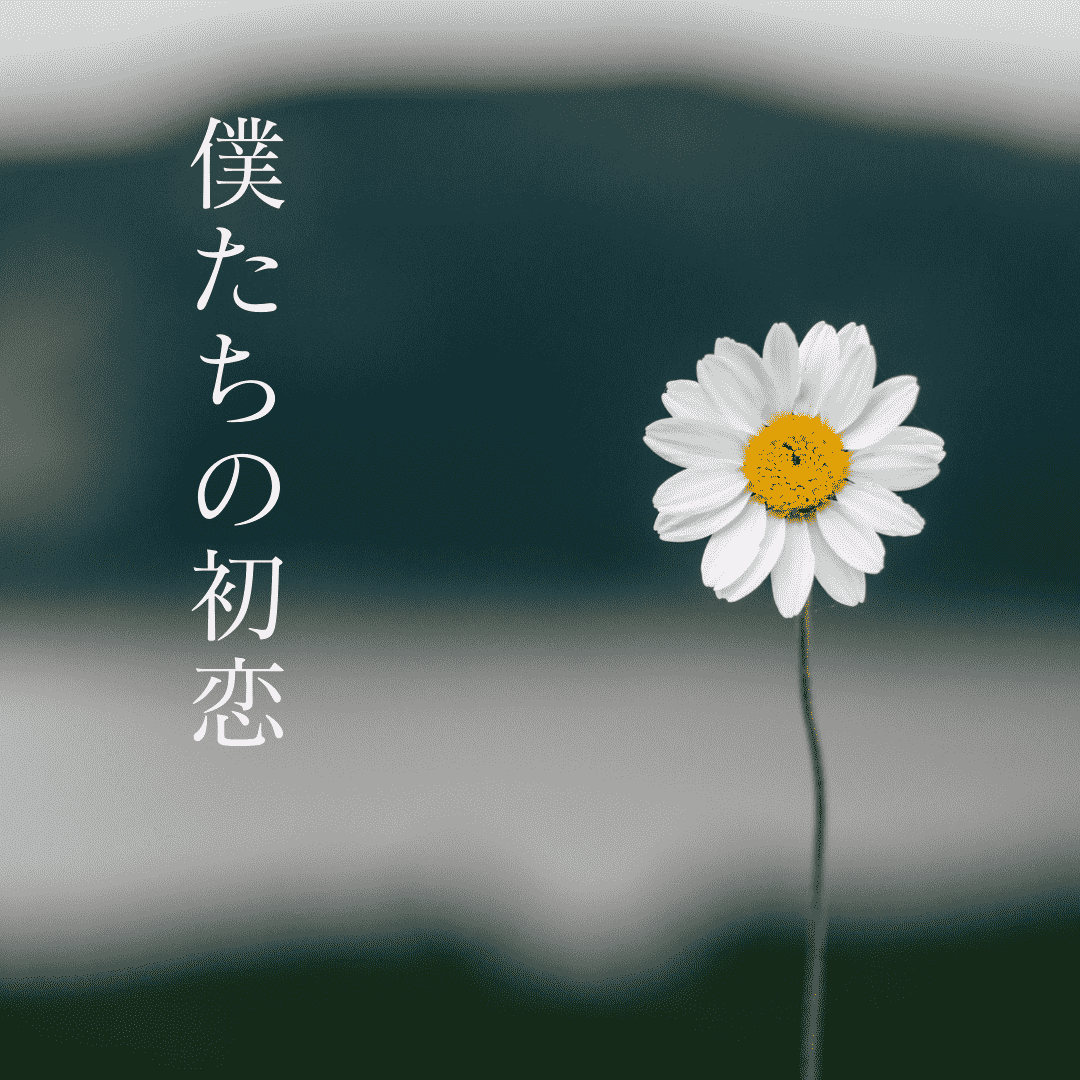


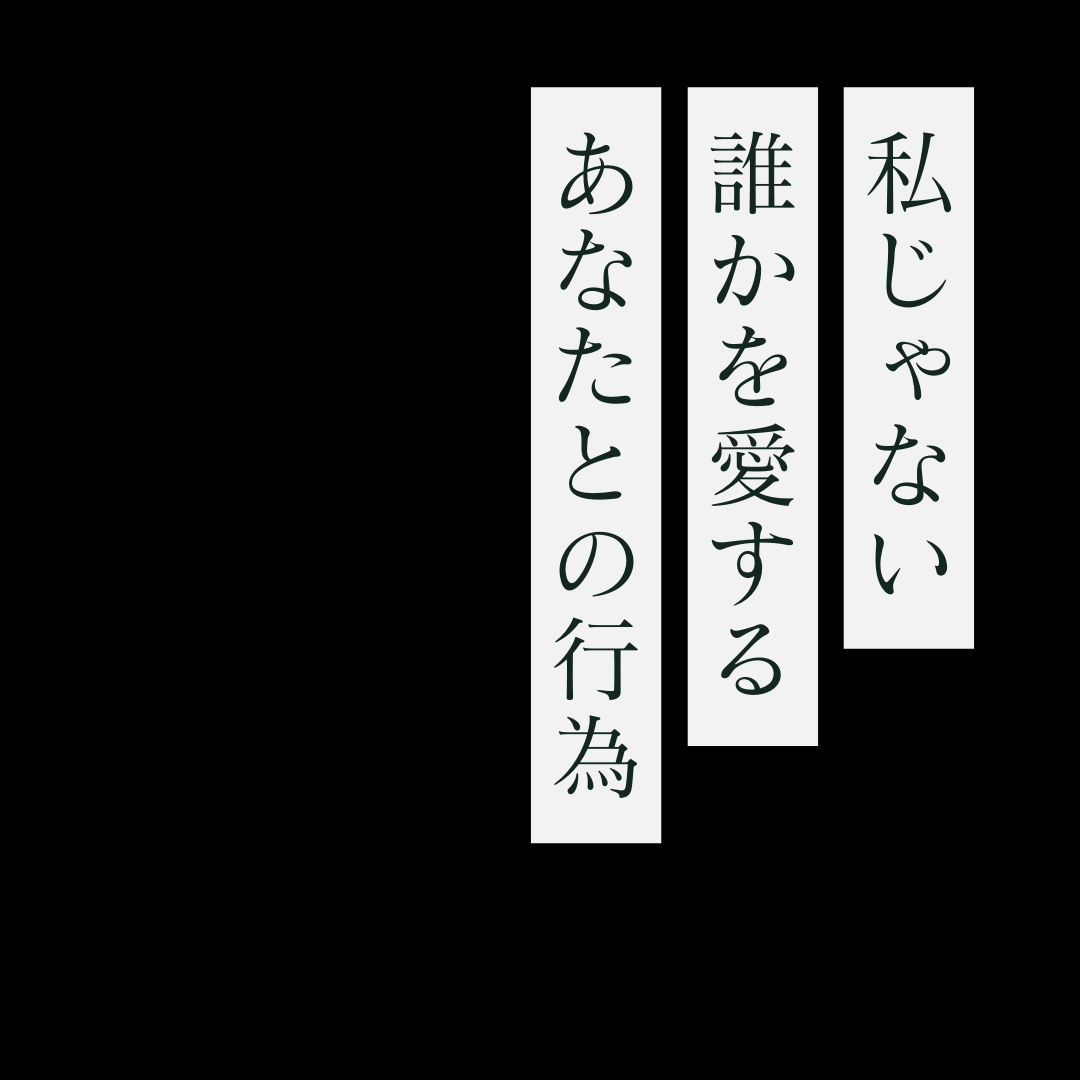
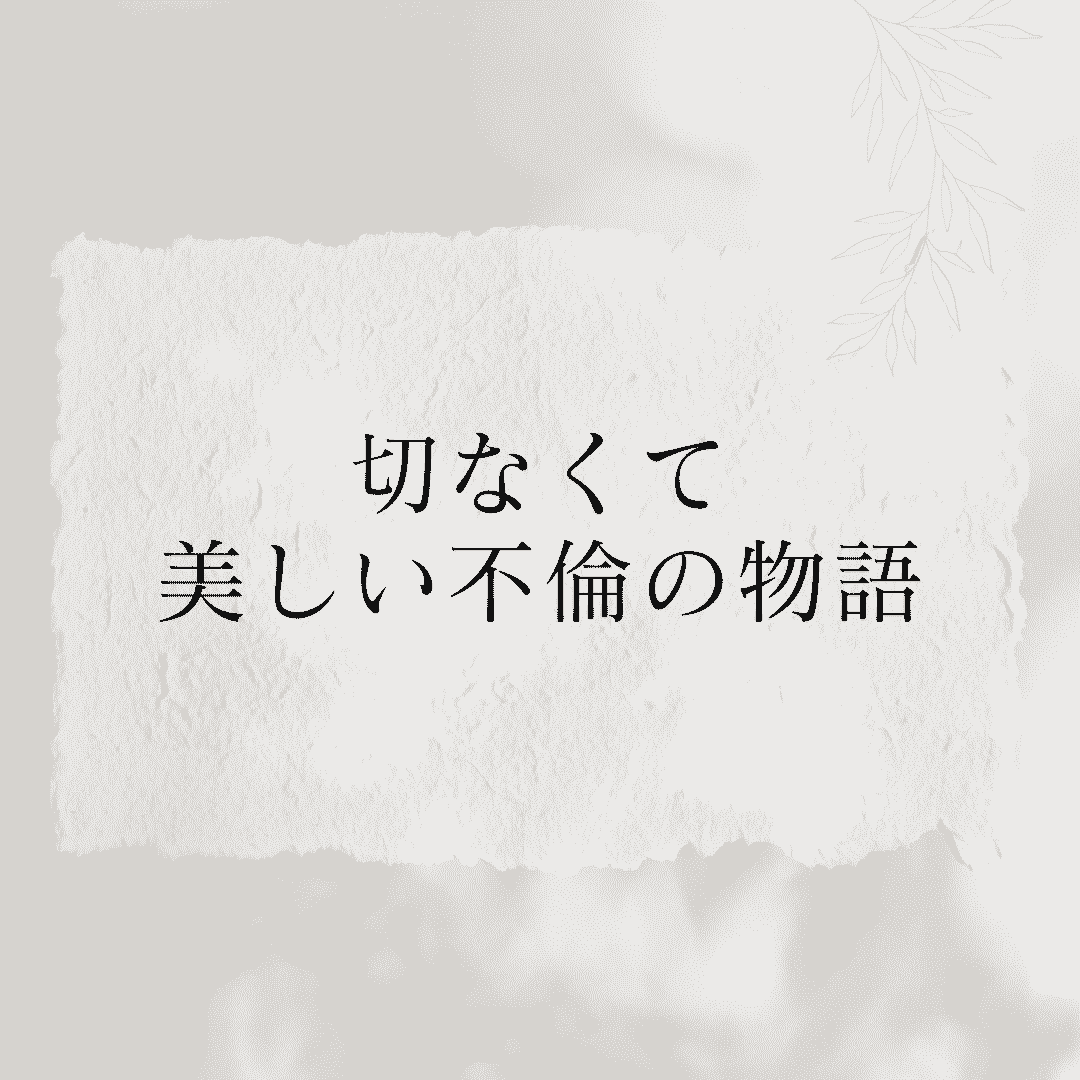
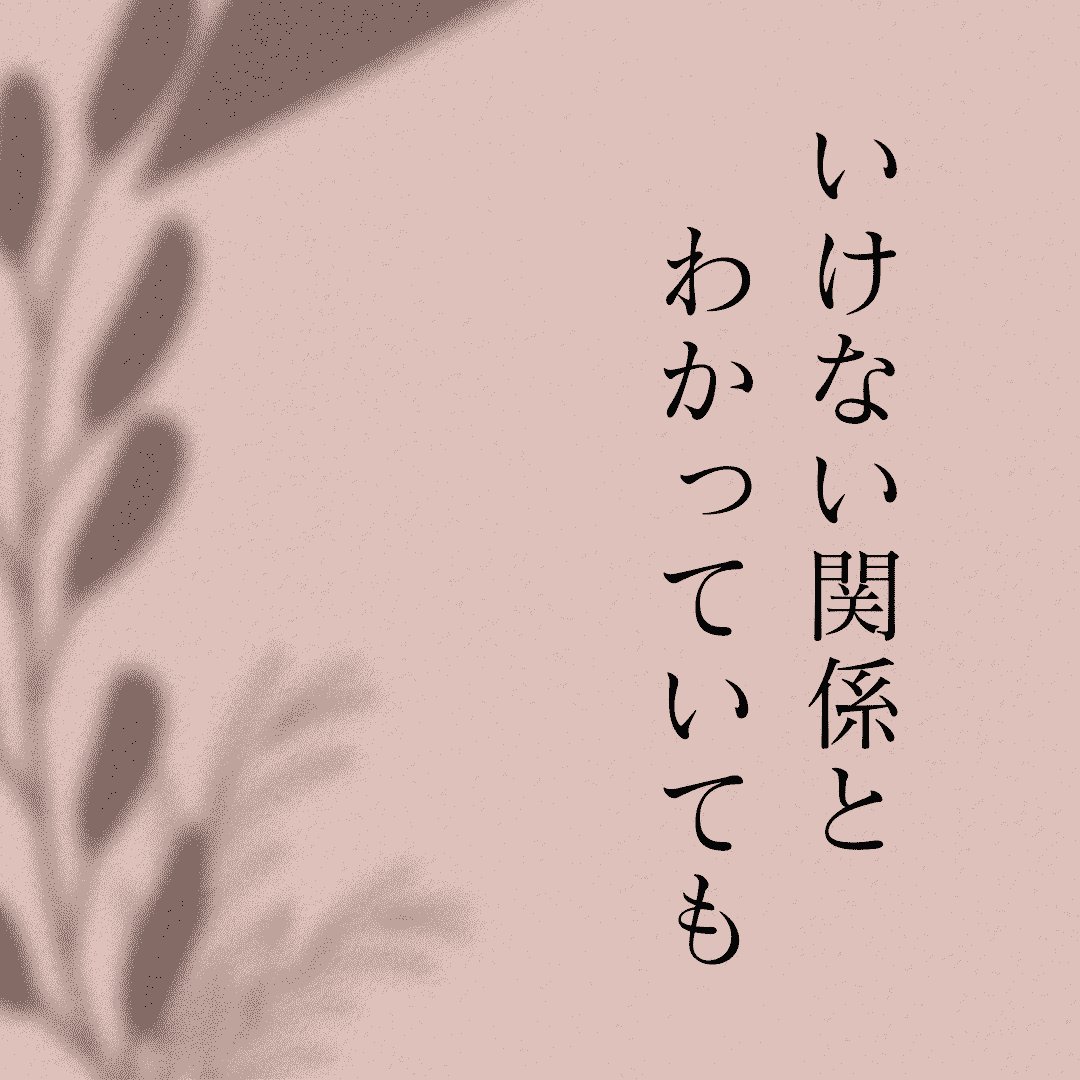









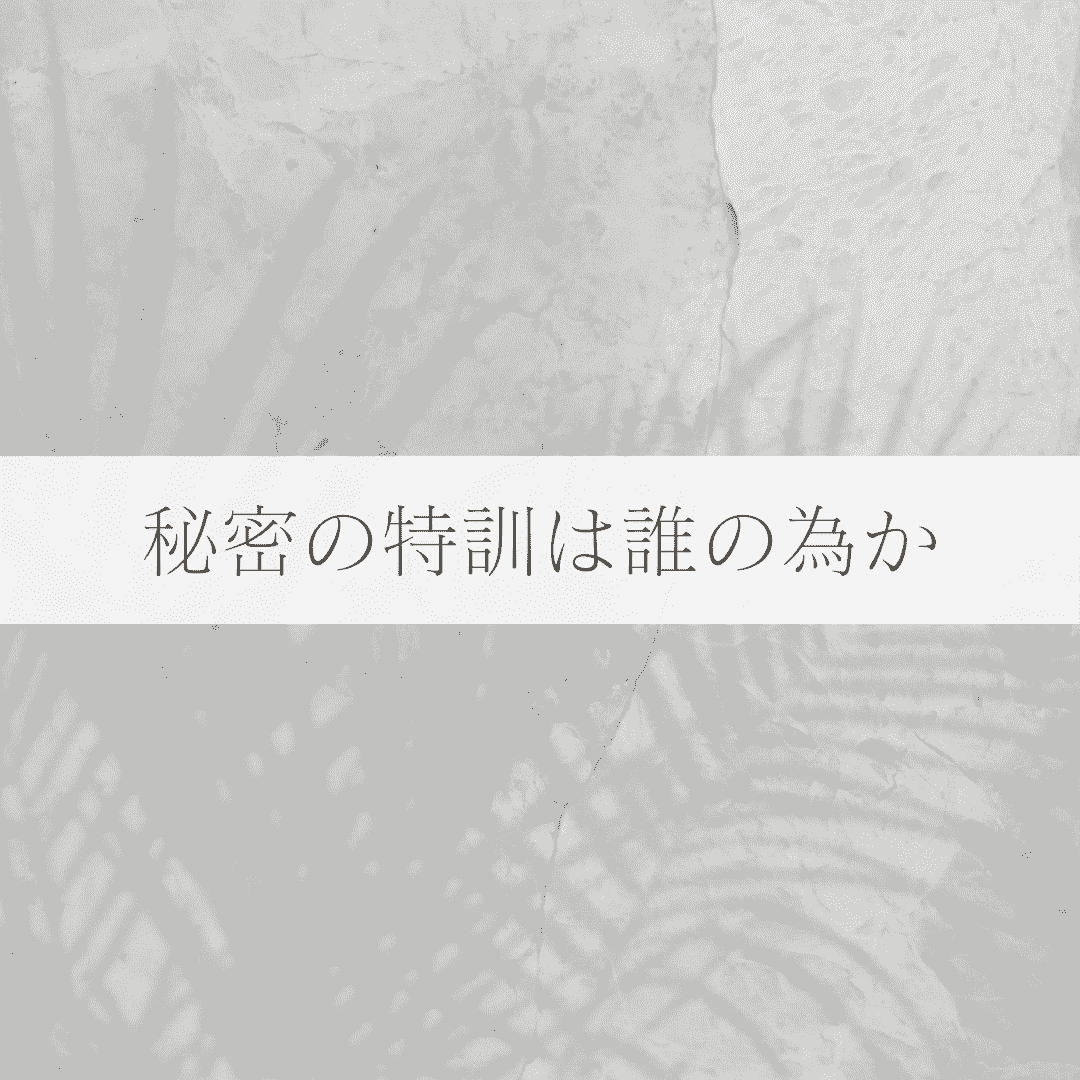
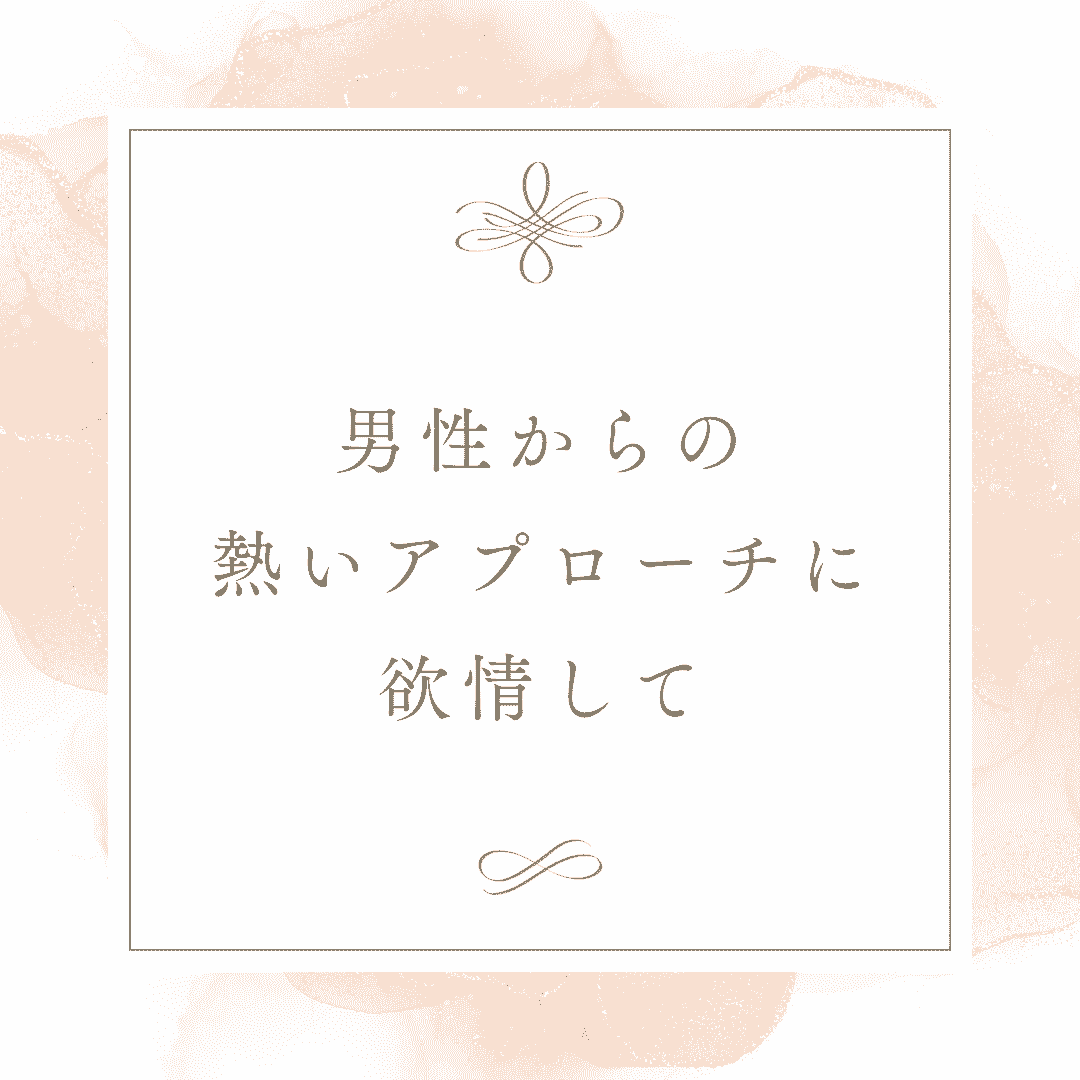


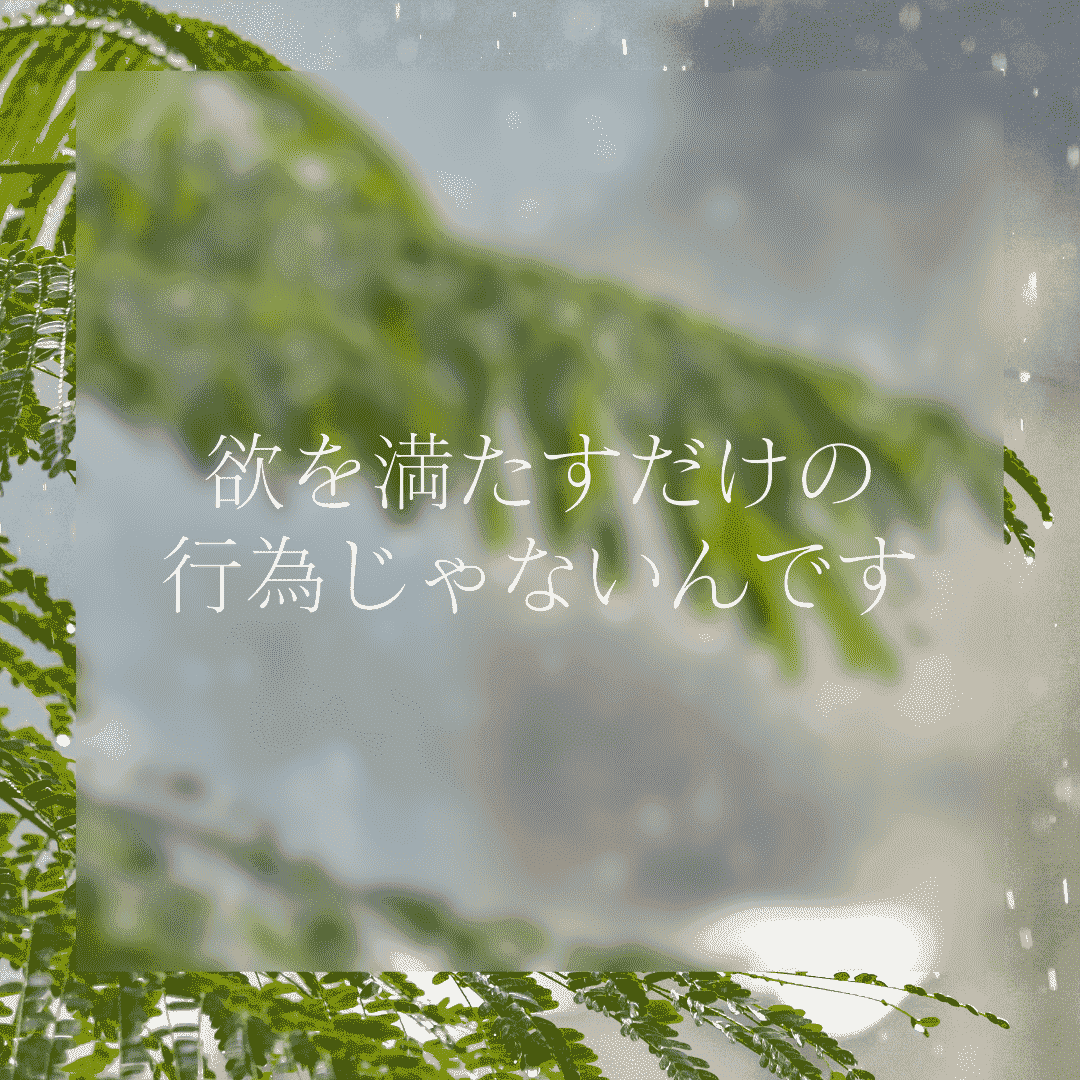

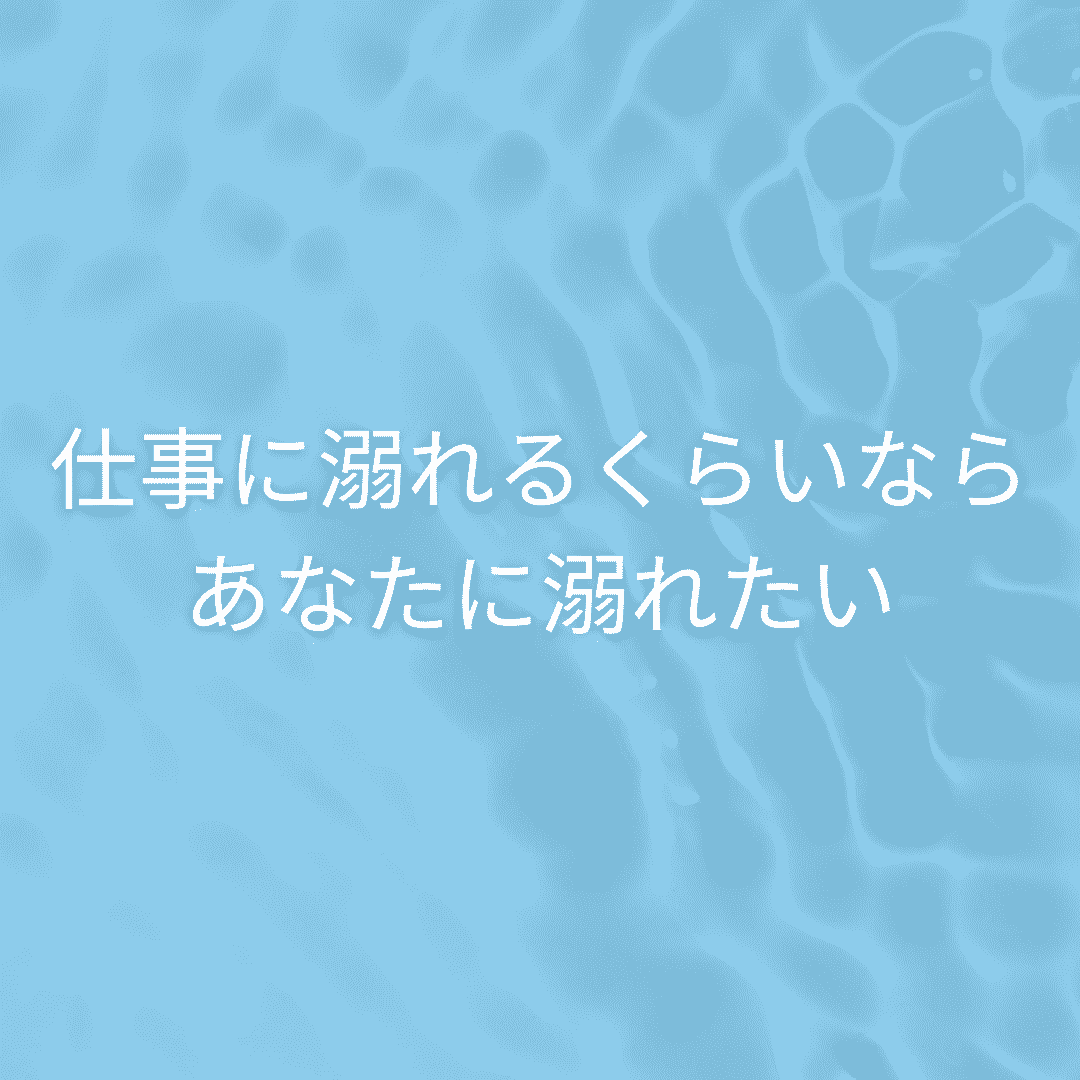



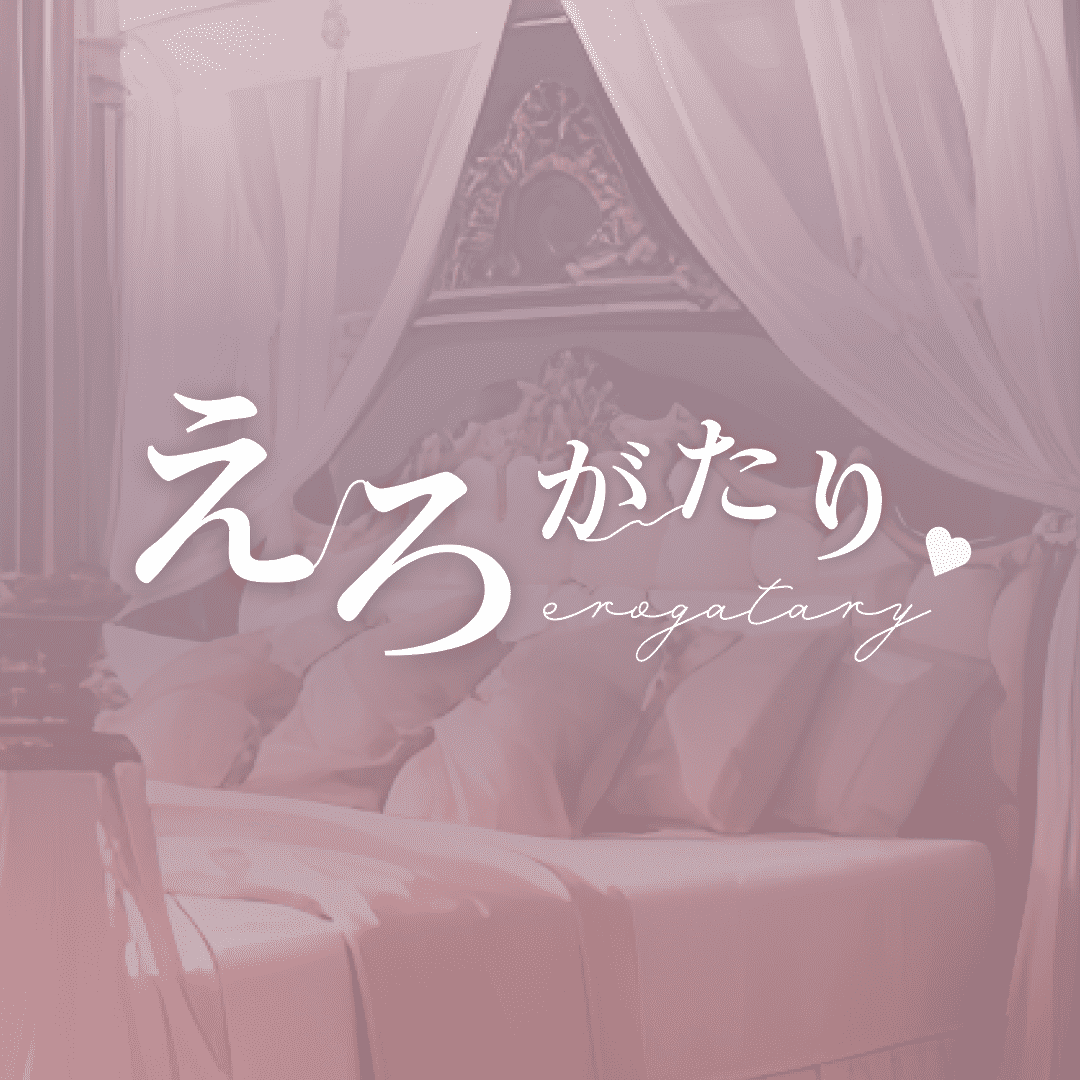





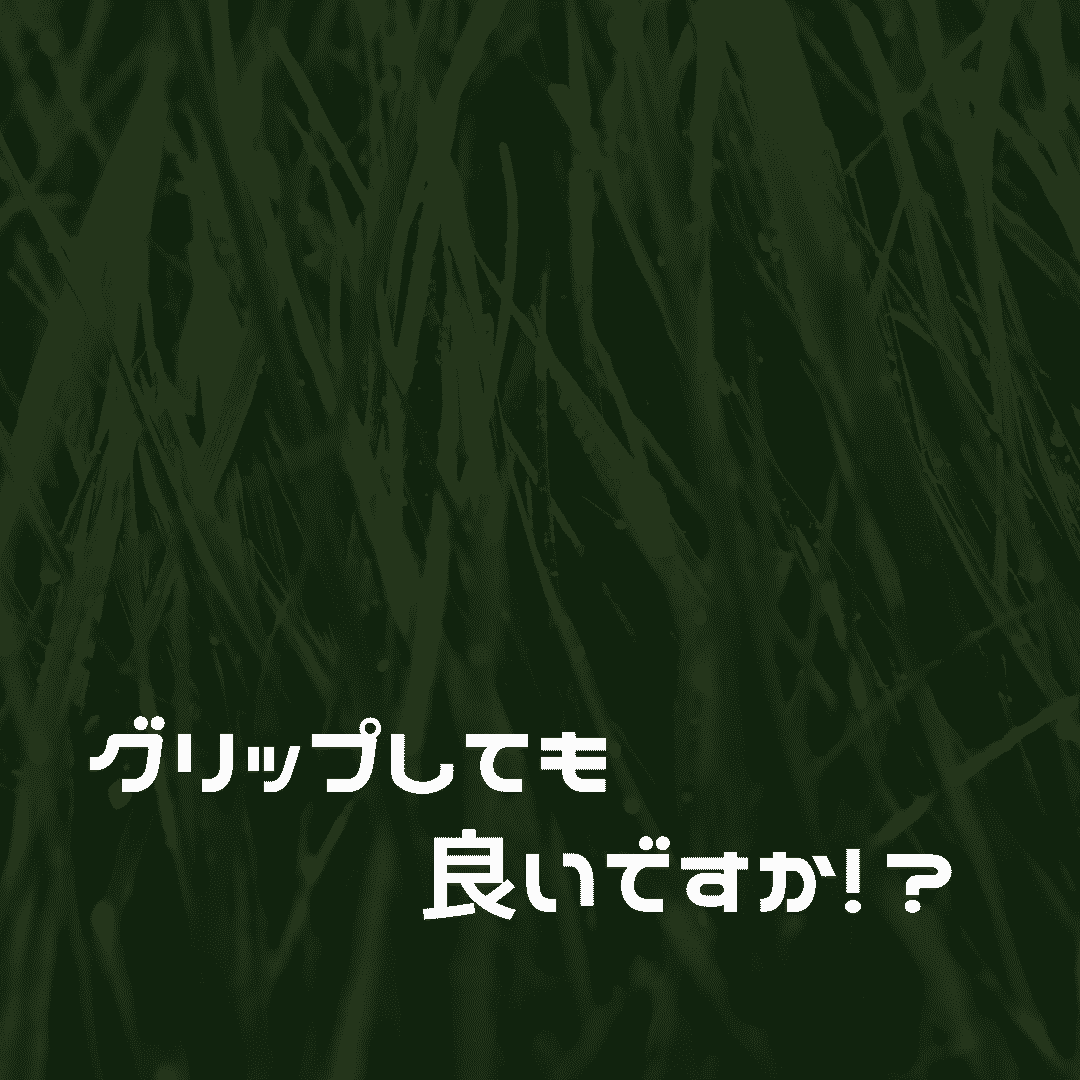
コメント